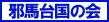 |
TOP > 著書一覧 >吉野ヶ里は邪馬台国なのか | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
|
| 吉野ヶ里は邪馬台国なのか | ||||
 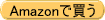 |
吉野ヶ里は古代史へのロマンをかきたてた。
環濠集落、無数の土器片、美麗な管玉、頭部を失い、あるいは幾本もの鏃を射込まれた人骨たち、そして朱塗りの甕棺に有柄銅剣を抱いて眠る「王」。 さらに楼観・城柵跡が発掘されるにつれ、古代史ファンの想いは「魏志・倭人伝」と邪馬台国へと飛んだ。 吉野ヶ里は卑弥呼の生きた地か? 様々の立場の論者が、最新のデータと科学的検証で古代史に迫る、吉野ヶ里決定版。 |
|
本書「はじめに」より 1 |
この文庫の編集部の方から、 「吉野ヶ里遺跡について発表された多くの論考から、これは、と思うものをえらび、文庫の 形で、まとめてほしい。題は、『吉野ヶ里は邪馬台国か』にしたい。」 とのお話があった。 私は、編集部から提案された『吉野ヶ里は邪馬台国か』という題名には、やや抵抗があった。 新聞、テレビなどから得られる吉野ヶ里の像は、巨大である。しかし、新聞やテレビは、ジャーナリズムそのものである。新聞やテレビとしては、吉野ヶ里と邪馬台国とを結びつけて報じたほうが、一般の人の関心をひきやすい。そのため、とかく、吉野ヶ里と邪馬台国とを結びつけて報道しがちである。 だからといって、その報道の熱気にあてられて、吉野ヶ里イコール邪馬台国とするのには、そう とうな問題がある。 すでに、何人かの学者は、過剰とも思える反応に、抗議の声をあげている。 この本にもおさめさせていただいた論考のなかで、明治大学の、大塚初重教授(考古学)は のべる。
「私は吉野ヶ里遺跡が邪馬台国とは思わない。私の知るかぎり吉野ヶ里遺跡を邪馬台国と決
めつけた考古学者はひとりもいない。」
「この遺跡(吉野ヶ里遺跡)が直接に邪馬台国に関係するようなものではないことは、述べ てきたところを斟酌(しんしゃく)していただければ、歴然としている。邪馬台国ブームに浮かれ、吉野ヶ里の正当な評価を怠ることは、この遺跡から予想をはるかに越える成果を導き出した調査 員諸氏の学問的良心と熱意に対して、何よりも非礼であろう。」(「弥生時代のクニとオウ」 『季刊邪馬台国』39号) さらに、北九州市立考古博物館の副館長の武末純一氏(考古学)も、つぎのようにのべてい る。「吉野ヶ里は素晴らしい遺跡である。弥生時代に関するいろいろな新しい情報を提供してく れるし『ああそうだったのか』とはじめて納得のいく場面も少なくない。しかしながら、吉 野ヶ里遺跡を絶対化したり、『弥生時代像が大きく変わった』とか、短絡的に『邪馬台国は ここだ』とする一部の論調には、筆者は与(くみ)しない。」(「北九州吉野ヶ里の同時代史」『歴史 読本』1989年9月号) 吉野ヶ里イコール邪馬台国とするのは、専門の考古学者の多くからは、問題にならないよう に見られている。これに対し、『吉野ヶ里は邪馬台国か』という題名は、吉野ヶ里が邪馬台国であることを、 なかばみとめたような題名である。あるいは、その可能性を、そうとう認めたニュアンスの題 名のように思える。 編集部から話があった日、 「題名については、また、あらためて、検討させていただきましょう。」 といって別れた。 ところが、家にかえって、愚妻に、 「今日、徳間書店から、吉野ヶ里についての論考をまとめて、編集してほしいとの、話があ ったけれども、題名がきまらないんだ。なんという題名がいいかなあ。」 というと、 愚妻が、 「『吉野ヶ里は、邪馬台国か』というのが、いいんじゃない?」 という。まるで、編集部の話を、聞いていたかのようである。 ああ、やはり、一般の読者の興味は、そこにあるのだ。 最近、佐賀新聞社から、タブロイド判の号外誌『倭人伝のクニ吉野ヶ里王国を見た』が出 た。そこでも、「卑弥呼の邪馬台国はここなのか」のキャプションがはいっている。 編集部と、その後、何度か話しあったすえ、題名は、『吉野ヶ里は邪馬台国なのか』とする ことにした、 |
2 |
テレビ、新聞などが、一過性の「ウケ」をねらって、ジャーナリスティックであることはや
むをえないのかもしれない。しかし、そこから、実像とははなれた虚像が、つくられて行く。
テレビ、新聞その他の報道のままに、自説を変化させていった学者もいた。
とくに、私が、ちょっとひどいなと思ったのは、これまでも、私とたびたび論争をしてきた 古田武彦氏である。 古田氏は、大変な、文学的文章力をもった方である。 古田氏の臨場感にあふれ、感動をそのままつたえようとする文章は、とくに、邪馬台国問題 に、それほどくわしくない人の心をうつことが多いようである。ジャーナリスティツクな文章 であるために、ジャーナリズム関係者のファンも、多い。 しかし、「感動」は、文学の本質にはなりえても、それがそのまま科学や学問の本質となる とはかぎらない。 古田氏には、「感動」は、すべての真実の根源であって、文学的真実であるとともに、科学 的真実でもあり、学問的真実でもあるという、思いこみがあるようである。 感動が、科学的真実や、学問的真実となるためには、それなりの「検証」が必要である。そ のとき、そのときの、テレビ報道や新聞報道のままに、「感動」し、その「感動」を真理であ るとして、直下に文章に記せば、ジャーナリズムは歓迎するであろうし、多くの読者の心に、 うったえうるかもしれない。 しかし、論理的には、まったく一貫性のないものになる。 そして、学問的、科学的でないものに転化してしまう。 |
3 |
古田氏の見解は、大マスコミでかなりしばしば報道されたので、一応、その軌跡を追ってお
こう。
吉野ヶ里遺跡が発掘される以前、古田氏は、つぎのようにのべていた。 「卑弥呼の都は、志賀島の地、博多湾頭にあった。」(『古代は輝いていたⅠ』朝日新聞社) その他の本でも、「邪馬一(壱)国(古田氏は、邪馬台国ではなく、邪馬一国であると主張 する)は、博多湾岸である。」と、くりかえし、強く主張してきた。そして、それに反対する 他説を批判してきた。 そして、吉野ヶ里遺跡が、発掘された。 3月17日号の、『週刊朝日』で、古田武彦氏は記している。 「歴史の女神はようやくその横顔を見せはじめた----吉野ヶ里遺跡を巡り終えたとき、私の 脳裏を横切ったもの、それはこの感慨だった。」 博多湾頭と、吉野ヶ里遺跡とでは、距離的にもはなれている。歴史の女神が、その横顔をみ せはじめたとすれば、その横顔は、これまでの古田氏の、「卑弥呼の都=博多湾頭説」に、否 定のサインを送っていることになるはずである。そこは、どうなるのか。古田氏は記す。 「この墓(墳丘墓)はズバリ言って、卑弥呼と同等の倭王ないし副王クラスの王墓だ。私は 夕闇の中に、空恐ろしい思いで立ちつくした。」 このような、文学的ともいえる感動にみちびかれて、古田氏は、さらに記す。「ここ佐賀平野の東域は、少なくとも倭国の重要な副中心である。それどころか、邪馬一 (壱)国が『戸数七万戸』(倭人伝)の広域である点からすれば、中心の一翼にあり、とも見 なしえよう。」 こうして、博多湾岸から、範囲をひろげ、吉野ヶ里あたりも、邪馬一国にふくめようとする。 しかし、そうすると、それまで、古田氏がくりかえし、奥野正男氏や私などの、「邪馬台国 =筑後川北岸説」を批判してきたことと、矛盾してしまうのである。 |
4 |
そして、さらに、一月ほどあとの、『週刊文春』4月13日号に、「吉野ヶ里遺跡は邪馬台国
だ」という文を記す。
古田氏はいう。 「『ああ、やっぱりあったか。そうでしょう、そうでなきゃおかしい。』 そういう『ついに出たか』という驚きだったのです。」 「やっぱりあったか。」「そうでなきゃおかしい。」などの文章は、かねがね、邪馬台国は吉野 ヶ里付近にあったと主張してきた奥野正男氏などが、のべるべきことばである。奥野氏の筑後 川北岸説を、熱心に攻撃して、博多湾岸説をのべつづけてきた人が、いうべきことばではない。文学的感動だけを追っていると、自説に、一貫性がなくなることの端的な例証である。 古田氏は、さらに記す。
「吉野ヶ里もその首都圏の一端に当っていると言っていいでしょう。」 マスコミの熱狂が、そのまま、古田氏の「感動」にリンクするので、このようなことになる。 |
5 |
そして、『歴史と旅』の6月号でも、「吉野ヶ里は邪馬壱国の中心地」という文を発表してい
たのが、マスコミの報道が、おちつきはじめた段階で、古田氏は、もとの自説に回帰しはじめ
る。
『正論』の6月号に、古田氏が発表された「吉野ヶ里のしめした道標」では、「吉野ヶ里は、 倭国の中心領域(首都圏)の一端に当っている。いわば副心臓部だ。」ということになり、「主 心臓部」は、「糸島・博多湾岸こそ中心の地だ。」という。 そして、『歴史と旅』の特別増刊7月5日号には、「吉野ヶ里は倭国の副心臓部」という文を 発表し、さらに、6月の末に、光文社のカッパ・ブックスの一冊として、『吉野ヶ里の秘密』 を刊行する。 古田氏はいう。 「(倭人伝の世界の)最中枢部は、どこか。それも、この本を読み終えたなら、もう、疑う 人はいまい。」 そして、「邪馬壱国の中枢は春日市だ」という。 『吉野ヶ里の秘密』の巻末に、古田氏は記している。 「わたしのインタビュー記事の題として、『吉野ヶ里は邪馬台国だ』〈週刊文春四月二二日 号〉とあったのは、編集部のワーク。それを"うけて"わたしの説が『吉野ヶ里"邪馬台 国』説であるかのように紹介したものもあった。〈月刊ASAHI創刊号、佐原真氏〉」 めまぐるしいことである。信奉者として、ていねいにつきあったならば、読者も、大変であ る。『週刊文春』の、「吉野ヶ里は邪馬台国だ」という題名は、編集部のワークであるという。で は、その内容も、編集部のワークだったのであろうか。その内容を読めば、題名を、「吉野ヶ 里は邪馬台国だ」としても、ふしぎではない内容である。 古田氏は、『吉野ヶ里の秘密』のなかで記している。
「わたしの胸はおどった。こわかった。
(墳丘墓中央の巨大甕棺から、)金印とまでいわずとも、せめて銀印くらいは、出土するか
もしれぬ。ぜひ、なにか、『文字』が出土してほしい。そう願った。
「『盗掘』はなかったのだろうか。夜が明けるのを待ちかねて、電話した。」 そして、現場責任者の、七田忠昭さんから、「盗掘はなかったようです。」との答えをうる。 古田氏は、あきらかに、マスコミの熱気をうけて、巨大墳丘墓から、金印あるいは銀印がで てくるかもしれないと思っていたのだ。『週刊文春』に、「(巨大墳丘墓の)中心に眠っている 人物が倭王であっても全く不思議ではない。」「(銀印は)金印にくらべると数多くもらってい るらしい。副王クラスなら、この銀印が出てくるかもしれません。」とのべているのは、『週刊 文春』編集部のワークではない。 要するに、吉野ヶ里の巨大墳丘墓から、『魏志倭人伝』に記されている金印か銀印がでてく るかも知れないと思っていたのに、それがでてこなかったので、しだいに熱がさめ、もとの自 説にもどったということであろう。 そもそも、発掘にあたった佐賀県の文化課では、当初から、墳丘墓は、弥生中期のものであ ると発表しているのである。 マスコミの熱気にあてられずに、冷静に判断すれば、弥生中期の墳丘墓から、弥生時代後半 以後の、邪馬台国時代の、金印や銀印が、でてくるはずがない。 そのことは、吉野ヶ里発掘の総リーダーの、佐賀県教育委員会文化課の高島忠平氏が、この 本にもおさめた論文のなかで、つぎのようにのべているとおりである。 「吉野ヶ里の墳丘墓は紀元前一世紀前半から(紀元後)一世紀初頭にかけて造られたもので、 およそ80年間にわたって続いたものと言えます。一方、卑弥呼の亡くなったのは三世紀の ごろ 半ば、248年頃と推定されますので、時代的にもまったく合いません。」(『Days Japan』 1989年6月号) |
6 |
吉野ヶ里の巨大墳丘墓のことにかぎらず、初歩的、基礎的な事実をきちんとおさえずに、個
人的「感動」や、「思いこみ」を、そのまま、「真理」と考え、そこから議論を発展させ、他説
を批判する傾向が、古田氏の論考では、いちじるしい。
古田氏は、『正論』にのせた論文でのべる。 「倭人伝にいう『倭国』とは、墓制からいえば、『甕棺国家』だったのである。」 『吉野ヶ里の秘密』のなかでも、「倭国は、甕棺国家だった。」とのべる。 ここから、巨大墳丘墓の特別に大きな甕棺から、金印や銀印がでてくるかもしれない、とい う発想が、生じるのである。 しかし、「倭人伝にいう『倭国』」は、墓制からいえば、「甕棺国家」ではなかった。「甕棺国 家」とするのは、誤りである。 そのことは、多くの考古学者が、のべているとおりである。 九州歴史資料館の、高倉洋彰氏はのべる。 「甕棺墓葬の伝統が(弥生)後期前半を境に急速に消滅し、箱式石棺・石蓋土壙墓と交替し ていく」(『考古学雑誌』第58巻、第3号。1972年) 福岡市埋蔵文化財センターの、浜石哲也氏は、「甕棺墓社会の発展と終焉」という文のなか でのべる。
「甕棺墓地の形成時に比べ、その終焉はきわめて唐突な感がある。
吉野ヶ里遺跡と同じく神埼郡内にあり、ひろく、吉野ヶ里遺跡とともに、「吉野ヶ里王国」 をなしていたのではないかとみられる遺跡に、二塚山遺跡がある。 この二塚山遺跡の文化財調査報告書『二塚山』が、1979年3月に、佐賀県教育庁文化課 から出されている。500ページをこえる大著である。 そのなかで、吉野ヶ里遺跡の発掘の総リーダーでもある高島忠平氏は、記している。
「北部九州弥生時代の埋葬形式は三津式の段階で、甕棺墓が衰退し、土堰墓・石棺墓にとっ
て変るのは地域的に若干の時期差はあっても、一般的に認められる傾向である。」
|
7 |
突然の、しかも、私の名前での編集という、たいへんあつかましいお願いであるにもかかわ
らず、諸先生からは、こころよく、転載の許可をいただいた。まことにありがたいことである。
冒頭の高島忠平氏の、「邪馬台国は吉野ヶ里の楼観から見えた」は、吉野ヶ里遺跡について の、全体的な見通しを、きわめて簡潔に、要領よくまとめたものである。 全体像をつかむのに適していると思う。 第二論考の、大塚初重氏の「『吉野ヶ里』の真相」、および、第三論考の、高倉洋彰氏の「弥 生時代のクニとオウ」は、「吉野ヶ里イコール邪馬台国説」のなりたちえない根拠をのべたも のである。この二つの論考には、軽佻浮薄な傾向をいましめる趣旨がくみとれる。 第四論考の、江宮隆之氏の「吉野ヶ里遺跡"邪馬台国"説を追う」と、第五論考の、奥野正 男氏の「吉野ヶ里こそ邪馬台国だ」とは、「吉野ヶ里は邪馬台国である」とする立場にかたむ く論考である。 江宮隆之氏の文章は、作家の筆になるので、まず、読みやすさに、特徴がある。邪馬台国論 争のおもな問題点が紹介整理してある。一般の人が、なにが問題なのかを知るのに役立つ。た だ、吉野ヶ里遺跡に、卑弥呼の墓があるのではないかとする考察は、考古学の専門家からは、 異論があるであろう。 また、奥野正男氏は、吉野ヶ里遺跡の発見される以前から、邪馬台国の所在地を、吉野ヶ里 遺跡をふくむ筑後川北岸地域と主張してきた方であった。 吉野ヶ里という狭い地域を、イコール邪馬台国とするのではなく、佐賀県の東半分の神埼郡、 三養基郡、鳥栖市から、福岡県の筑紫野市、小郡市、甘木市、朝倉郡、三井郡にいたる広い地 域を、邪馬台国の位置にあてる。この地域の平野部には、奈良盆地が、二つ、すっぽりおさまる、という。 吉野ヶ里遺跡のすぐ近くの、三津永田遺跡、横田遺跡、二塚山遺跡などからは、すでに、か なりな数の鏡、鉄剣、鉄刀、鉄矛、きわめて多くの玉類などが出土している。 神埼郡を中心とする地域は、邪馬台国時代の遺物に、ほぼあたるかとみられる後漢式鏡や、 小形の  製鏡(中国の鏡をまねてつくった小形の国産鏡)の出土密度が高いこともたしかで
ある。鉄剣などの出土密度も高い。 製鏡(中国の鏡をまねてつくった小形の国産鏡)の出土密度が高いこともたしかで
ある。鉄剣などの出土密度も高い。
甕棺の数から推定されるある一時期の推定人口は、千人ていどとみられているとはいえ、吉 野ヶ里遺跡以上に、甕棺の密集している地域は、九州でも、きわめてすくないといってよい。 人口は、やはり、相対的には、大きかったといえる。 マスコミによる熱気にあてられることなく、神埼郡を中心とするひろい地域は、やはり、邪 馬台国の候補地の一つとして、今後も、探究される必要がある。(私自身は、筑後川の今すこ し川上の、福岡県の甘木・朝倉地域が、邪馬台国の中心地であろうと考えているが。) 以上のように、「吉野ヶ里は邪馬台国の地である」とするのに、批判的な論考二編と、むし ろ、賛同にかたむく論考二編とを、やや、対立的な形でおさめた。 さらに、「雑魚の魚まじり(ざこのととまじり)」であるが、吉野ヶ里に関する私の論考を、すこしおさめさせていただいた。 そして、佐賀県の教育庁文化課からでている雑誌『新郷土』にのせられていた発掘ドキュメ ントを転載させていただいた。 最後に、11月末日までに刊行された吉野ヶ里についての、おもな、単行本、雑誌特集、雑 誌論文の一覧表をそえた。 この本がきっかけとなって、吉野ヶ里遺跡、邪馬台国、さらには、日本古代史についての論 議が、いっそう活発になり、探究が深化されることを願ってやまない。 |
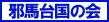 |
TOP > 著書一覧 >吉野ヶ里は邪馬台国なのか | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |