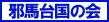 |
TOP > 著書一覧 >日本人と日本語の起源 | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |
| 日本人と日本語の起源 | 毎日新聞社 |
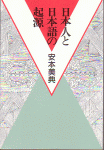 |
日本人の起源をめぐる議論は、邪馬台国問題などと異なり、学問的に進化され、「素人」では、なかなか、手のとどかないものとなりつつある。
しかし、基本的データや事実と、パラダイムとを整理しておくことは、学者たちの見解を理解するのに、役立つところがあるであろう。 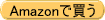 |
プロローグ 私の「新説」の内容と特徴 ■ 私の「新説」のポイント |
はじめに、「日本人と日本語の起源」についての、私の「新説」のおもなポイントを紹介して
おこう。ポイントは、つぎのようになる。
|
■ この本の特徴 |
この本は、二つの特徴をもっている。 まず、第一の特徴についてのべよう。 最近、大都市の電車内や街なかなどで、つぎのような光景に、よく出あう。
つまり、私たちが、「日本人」なるものを考えるとき、おもに、「ことば」という文化的側面 と、「からだ」という遺伝的側面との二つを考えていることが多い。「言語」と「人種」の二つと いってもよい。 このうち、人種のほうは、皮膚の色、頭髪・身長・頭の形・血液型などの生物学的特徴を考え る。 これまでの日本人起源論は、ことばか、からだの、どちらかを主にしているものが、ほとんど であった。 しかし、日本人の起源を考えるばあいは、ことばに関する諸事実も、からだに関する諸事実 も、ともにうまく説明できる仮説を考えなければならない。ことばに関する諸事実とからだに関 する諸事実とを、総合的に考えようとしたこと、それが本書の第一の特徴である。 たとえば、「からだ」なら「からだ」だけを考えた議論には、一定の限界がある。日本列島以 外の地にも、日本人と同じ身体的特徴をもった人たちは、たくさん住んでいるからである。 私じしんが、固有にもっている方法とデータとは、おもに、言語学的、文献学的なものであ る。 言語学的、文献学的な知識は、ここ五千年以内というような、比較的現代に近い時代のことに ついては、かなり確実な情報を与えてくれる。 日本人の起源を探究する学問には、自然人類学、文化人類学、考古学、言語学、民俗学、民族 学、文献史学、神話学などがある。 言語学的、文献学的な知識と、他の分野の成果とを、どのように統一的に理解すべきかが、こ の本の大きなテーマでもある。 この本の第二の特徴として、日本人の起源についての諸説や諸事実を、整理し、把握するさい の、切り口の新しさを、あげさせていただいてもよいであろう。 従来は、日本人の起源論を把握するさいの代表的な切り口として、「混血説」と「変形説」に わけて考えるという方法がとられてきた。 1988年夏に、東京上野の国立科学博物館で開かれた「国立科学博物館百十周年記念日本 人の起源展」も、日本人の起源論を大きく混血説と変形説とにわけるという立場から企画されて いた。(国立科学博物館編集『日本人の起源展』読売新聞社刊参照。)  「混血説」は、清野謙次、金関丈夫などが主張した。
日本の石器時代人と、現代人とでは、骨などの身体的特徴が、かなりちがう。このちがいを、
「混血説」では、大陸などから人がわたってきたことによる「混血」にもとづくと考える。
「混血説」は、清野謙次、金関丈夫などが主張した。
日本の石器時代人と、現代人とでは、骨などの身体的特徴が、かなりちがう。このちがいを、
「混血説」では、大陸などから人がわたってきたことによる「混血」にもとづくと考える。
清野謙次によれば、日本の石器時代人は、アイヌでも、日本人でもない、「原日本人」であっ たという。この原日本人が、アジア大陸から朝鮮経由で日本に渡来してきた人々や、南方の人種 との混血によって、徐々に、現代日本人が形成されたという。 そして、原日本人が、もっと北方地域の人々と混血してできたのが、現代アイヌである、と考 える。 いっぽう、「変形説」は、長谷部言人、鈴木尚などが主張した。 「変形説」では、石器時代人と現代人との、骨などの身体的特徴のちがいは、おもに、日本列島 内部での、進化にもとづく「変形」によるとする。身体的な形質の変化は、環境の要因、とく に、文化あるいは生活様式(食物や労働など)の変化によってもたらされたと考える。 しかし、混血説と変形説とにわけて考えるという切り口は、現在では、あきらかに、時代遅れ のものとなっている。 今日では、日本人の形成にあたって、「混血」のあったことは、多くの学者が、ほぼ共通して みとめるところとなっている。ただ、その「混血」の度合いが、大きかったか、それほど大きく なかったかについては、議論がわかれている。 また、生活様式により、身体的形質がかなり「変形」しうることも、多くの学者の、みとめる ところとなっている。 そして、今日では、「混血説」か「変形説」かよりも、むしろ、つぎの二説の対立のほうが、 表面にでてきている。
その対立を止揚しようとしたのが、私の「新説」である |
■ 日本語祖語の大膨張 |
日本人という大河の源は、けっしてひとつではない。源を異にするいくつかの支流が合流し
て、この大河となっている。
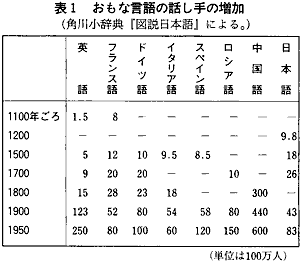 世界には、およそ、三千種の言語があるといわれている。そして、日本語は、現在、中国語、
英語、ロシア語、ヒンディー語、スペイン語につぎ、世界で、第六番目に使用人口の多い言語で
ある。
世界には、およそ、三千種の言語があるといわれている。そして、日本語は、現在、中国語、
英語、ロシア語、ヒンディー語、スペイン語につぎ、世界で、第六番目に使用人口の多い言語で
ある。
現在、英語の使用人口は、約二億五千万人。これに対し、日本語の使用人口は、約一億二千万 人。約半分である。 しかし、つい五百年まえの西暦1500年ごろには、英語の使用人口は、約五百万、日本語の 使用人口は、約千八百万人と推定されている(図2、表1参照。角川小辞典『図説日本語』によ る)。日本語の使用人口は、英語の使用人口の三倍強であった。英語は、ここ五百年ほどのあい だに、使用人口が、50倍になった。英語の使用人口は、とくに、19世紀以後に爆発的に大き くなった。 ロシア語も、スペイン語も、五百年ほどまえには、日本語よりも使用人口がすくなかった。五 百年ほどのあいだに、ロシア語は、15倍以上、スペイン語は、14倍以上に使用人口が膨張し た。日本人は決して少数民族ではなく、大河と呼ぶにふさわしい。 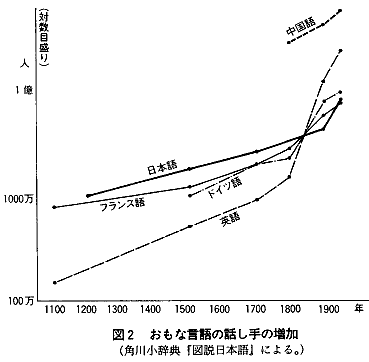 英語やロシア語、スペイン語が、ここ五百年ほどのあいだに、急激に膨張したのは、政治的な
事情による。
英語やロシア語、スペイン語が、ここ五百年ほどのあいだに、急激に膨張したのは、政治的な
事情による。
日本語も、その初源においては、縄文時代のすえ、あるいは、弥生時代のはじめに、北九州お よび南朝鮮において、「北方語基層-南方語上層」という形で成立した。比較的少数の人たちの 言語であったであろう。 その意味では、日本語祖語の成立時期は二千数百年まえといえる。 その言語をつかう人々が、北九州に成立した邪馬台国の母体となった。 邪馬台国の後継勢力が東遷して、大和朝廷となり、大和朝廷の政治的発展により、日本語は、 大膨張をとげることとなる。 四世紀ころからはじまる大和朝廷の政治的な発展にともなって、日本語を使用する人口が、急 激に増大していった。 約二千年まえの弥生時代、北九州に存在した日本語祖語は、おそらく、数万ないし数十万てい どの人々が用いている言語にすぎなかったのであろう。 それが、大和朝廷の政治的発展によって、日本列島全体にひろがっていった。7世紀の奈良時 代の日本の人口は、六百万人〜七百万人といわれる。これは、西暦1500年ころの英語の使用 人口よりも多い。 奈良時代には、『古事記』、『日本書紀』、『万葉集』なども成立し、「日本人」という意識もそう とう明確になっていたとみられる。そして日本語はついには、現在みられるように、一億をこえ る人々によって用いられる大言語になった。 これが、私の考える、「新北方人基層説」である。 |
■ アイデンティティ欲求に科学性を |
日本は、経済的に豊かになってきた。それとともに、日本人が日本人であることの意味を知り
たいという願望が、しだいに強くなってきているように思える。一種のアイデンティティ(自己
確認)欲求といえようか。
これまで、日本人や日本語の起源に関するはなばなしい論争が、何度かくりかえされてきた。 また、日本古代史関係の本が、さかんに刊行されつづけている。このようなことは、日本人の、 アイデンティティ欲求と結びついているといえよう。 私たちは、なにごとによらず、ものごとの起源を知りたいと願う。私たちが古代の日本のすが たを明らかにしたいと強く願うのは、ふるさとを遠くはなれた人が、ふるさとをなつかしがる気 持ちにも似ている。 私は、旧満州(現在の中華人民共和国の東北地方)に生まれて、育った。第二次世界大戦後に、 日本に引きあげて来た。 そのため、新聞で、中国残留孤児の記事をみるたびに、胸が痛む。運命が少し幸いしなかった ならば、私も、残留孤児になっていた可能性があったと思うからである。 戦乱の中で、親と子は、はなればなれになった。しかし、生活がおちつくと、自分の出自を知 りたいと、痛切に願う。その痛切さは、父母のもとで、しあわせに育った人々の想像をこえる。 人間は、生活に、いくらかでもゆとりができると、自分が自分であることの意味を知りたいと 願う。 しかし、注意しなければならないことがある。強い願望は、しばしば錯覚を生む。 中国残留孤児の場合でも、ときおり、とうてい本当の親もととは思われないところに、引きと られている例があるという。 身もとを確認するためには、血液型の検査など、科学的な方法にうったえる必要がある。 日本人の起源のばあいも、同じである。 日本人の起源の問題は、ロマンあふれる問題であるが、まだまだ解けていない問題も多い。 この本がきっかけになって、一人でも多くの若い人たちが、日本人の起源の問題に、興味をも っていただければ幸いである。 |
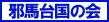 |
TOP > 著書一覧 >日本人と日本語の起源 | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |
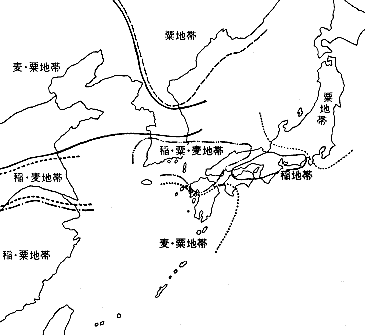 甲元真之・山崎純男氏共著の『弥生時代の知識』(東京美術刊)に、「東アジアの初
期農耕類型」を示す地図がのっている(右図参照)。
甲元真之・山崎純男氏共著の『弥生時代の知識』(東京美術刊)に、「東アジアの初
期農耕類型」を示す地図がのっている(右図参照)。
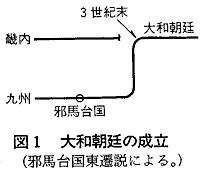
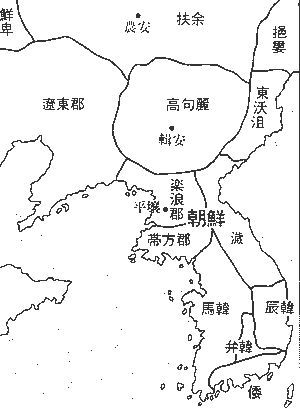 西暦400年前後には、朝鮮側の資料「広開土王の碑文」にうかがえるような、大和朝廷
によるかなり大規模な朝鮮半島出兵があった。
西暦400年前後には、朝鮮側の資料「広開土王の碑文」にうかがえるような、大和朝廷
によるかなり大規模な朝鮮半島出兵があった。