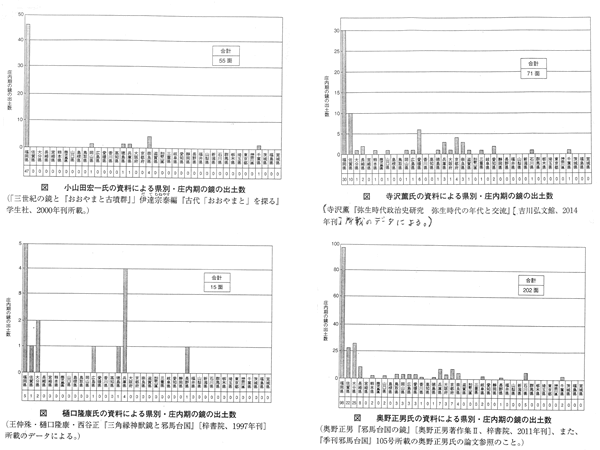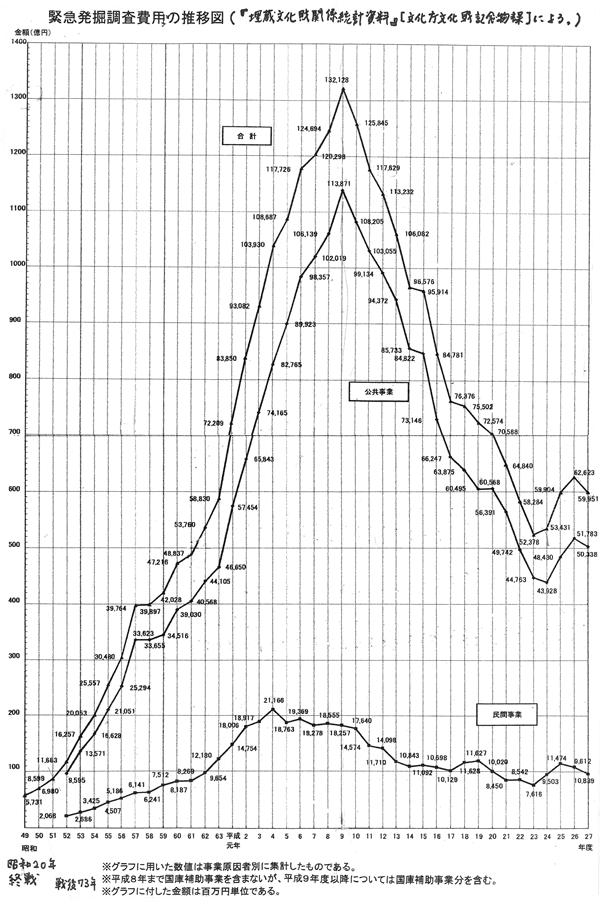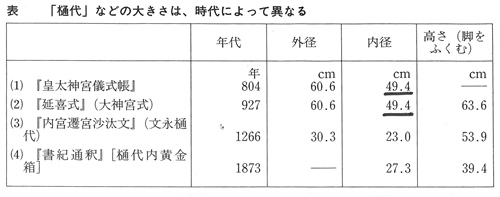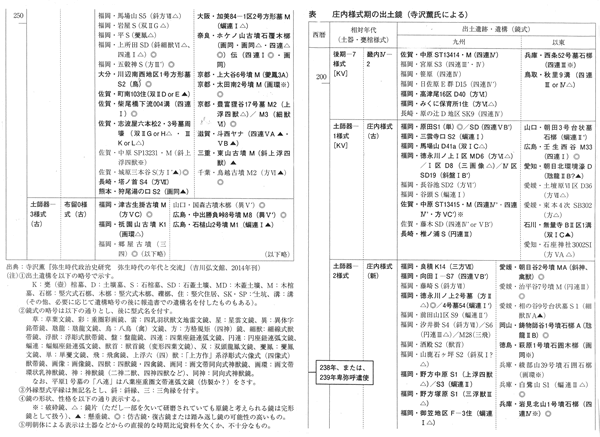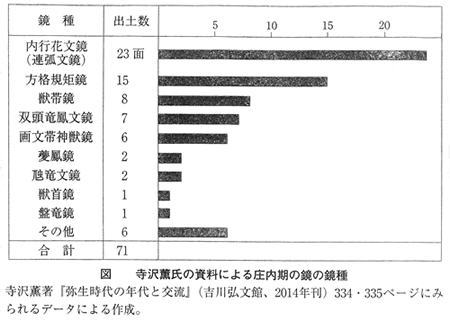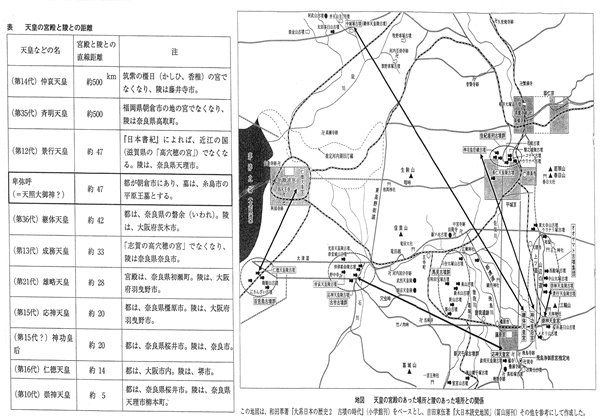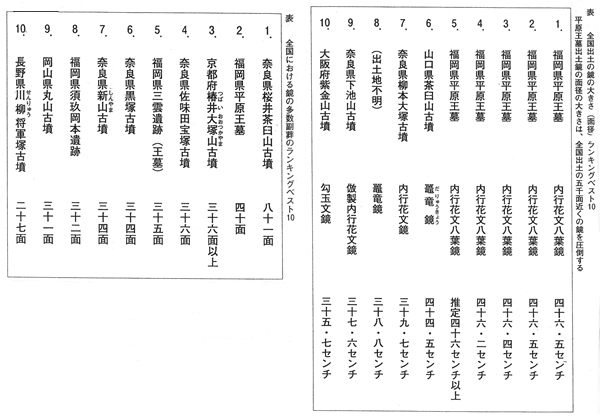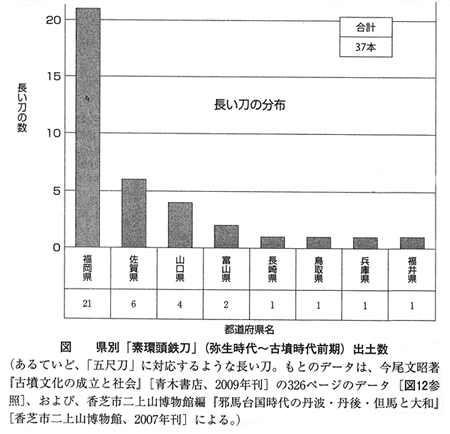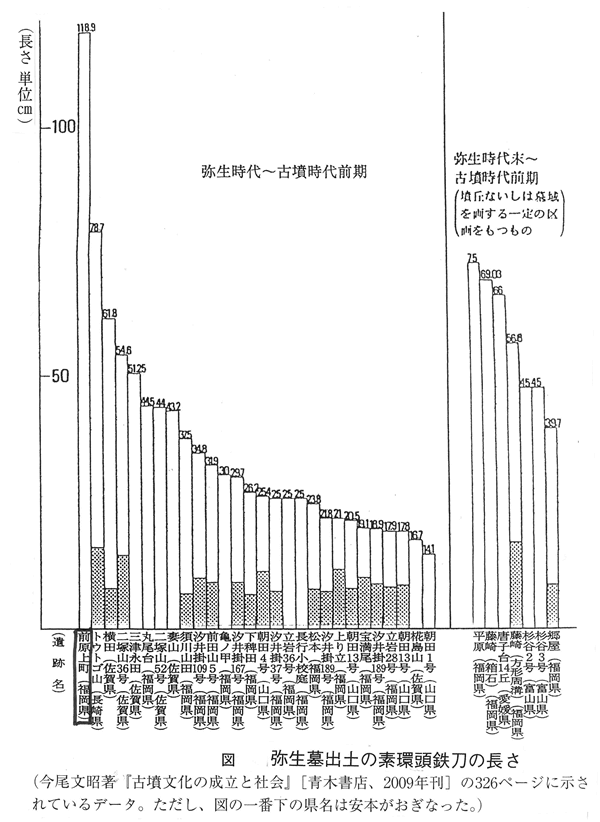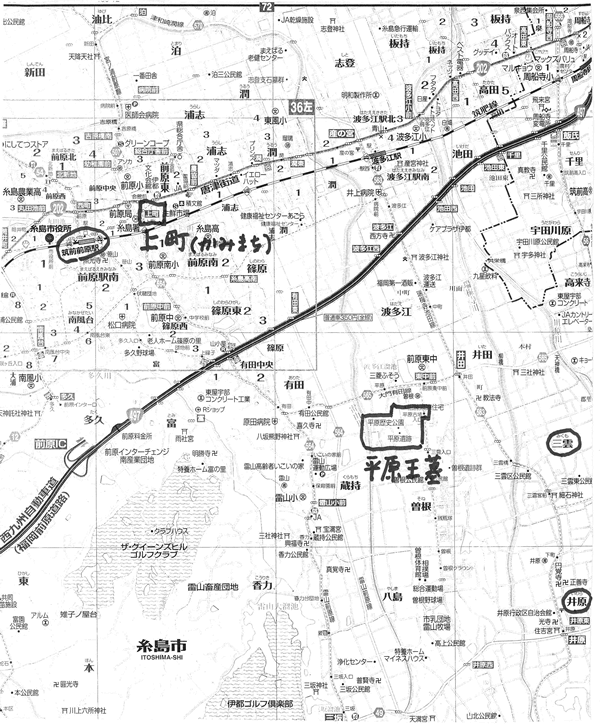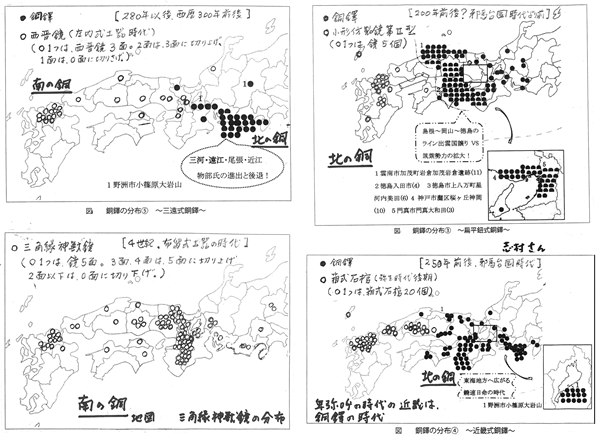■石野博信氏との討論
2006年5月13日(日)「邪馬台国の会」に石野博信氏(当時、徳島文理大学教授、兵庫県立考古博物館館長など)をお呼びして、「再現性」「検証性」について、討論した。
(下図はクリックすると大きくなります)
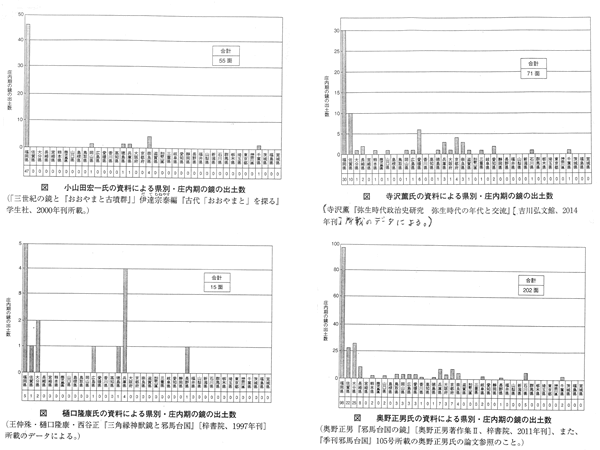
これらのグラフから、
①いずれの図においても、福岡県からの鏡の出土数がもっとも多い。
②福岡県と奈良県とを比較してみる。いずれのデータによっても、奈良県からのこの時期の鏡の出土数は、福岡県の1/10以下である。
石野博信氏の反論
『再現性』などということばの意味がよくわからない。同じものをみても、意見の違うことのあるのは、ふつうのことではないか。意見が違ったばあいは、なぜ意見が異なったのか、その理由を明確にして行くべきである。そのようなプロセスを通じて、邪馬台国も、しだいにあきらかになって行くとみられる。
このような意見もあるが、どうなのであろうか?
科学について、下記の意見が一般ではないか。
科学についてのポピュラーな入門書
森博嗣著『科学的とはどういう意味か』(幻冬社、新書2011年刊)
「では、科学と非科学の境界はどこにあるのだろう?
実は、ここが科学の一番大事な部分、まさにキモといえるところなのである。
答をごく簡単にいえば、科学とは『誰にでも再現ができるもの』である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが『科学的』という意味だ。
ある現象が観察されたとしよう。最初にそれを観察した人間が、それをみんなに報告する。そして、ほかの人たちにもその現象を観察してもらうのである。その結果、同じ現象をみんなが確かめられたとき、はじめてその現象が科学的に『確からしいもの』だと見なされる。どんなに偉い科学者であっても、一人で主張しているうちは『正しい』わけではない。逆に、名もない素人が見つけたものでも、それを他者が認めれば科学的に注目され、もっと多数が確認すれば、科学的に正しいものとなる。
このように、科学というのは民主主義に類似した仕組みで成り立っている。この成り立ちだけを広義に『科学』と呼んでも良いくらいだ。なにも、数学や物理などのいわゆる理系の対象には限らない。たとえば、人間科学、社会科学といった分野も現にある。
そこでは、人間や社会を対象として、『他者による再現性』を基に、科学的な考察がなされているのである。」
「まず、科学というのは『方法』である。そして、その方法とは、『他者によって再現できる』ことを条件として、組み上げていく、システ厶のことだ。他者に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また、再現の一つの方法として実験がある。」
また、生物学者 池田清彦(早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授)著『科学とオカルト』(講談社、学術文庫2007年刊)で下記のように述べている。
「19世紀までは、現在のような制度化された科学はなかった。そればかりか、今日、科学の重要な特徴と考えられている客観性や再現可能性を有した学問それ自体もなかったのである。」
そして、池田清彦氏は、「『再現可能性』という公準」という見出しの節をもうけて、例をあげて、「再現可能性」「同じやり方に従って行なえば、だれがやっても同じ結果がでること」こそが、「科学」においては、重要であることをのべている。
更に、社会科学者、上野千鶴子(東京大学名誉教授)『情報生産者になる』(筑摩書房新書2018年刊)も下記のように述べている。
「社会科学は経験科学です。信念や信条にもとづいて、主張を唱えるのではなく、検証可能な事実にもとづいて、根拠のある発見をしなければなりません。わたしはゼミで学生にしょっちゅう『あんたの信念は聞いてない』と言ってきました。『それは何を根拠に言うの?』とも、しつこいぐらいに聞きました。根拠のない信念はただの思い込み。『偏見』ともいいます。」
化学や物理学や医学・薬学など、実験可能な分野における「実験」にあたるものが、天文学における「観測」や、社会科学や人文科学における「統計的調査」である。
「実験」や、「観測」や、「統計的調査」は、いずれも、外部世界、客観世界にたずねかけ、「再現できる」かどうか、をたずねる「方法」である。森博嗣氏のいうように、科学というのは、「方法」なのである。
そして、STAP(スタップ)細胞事件における「再現性」が問題にされた。
考古学には、巨額の費用がそそぎこまれている。
文化庁文化財主任調査官であった岡村道雄氏はのべている。
「開発に伴って最低限遺跡の発掘記録をとるために使われている予算は平成11年度で約1100億円です。」(岡村道雄、山田晃弘ヽ赤坂憲雄(司会)「事件が問いかけるもの-前・中期旧石器考古学の現在」[『東北学Vol4、2001年刊]
・日本列島改造論をとなえた田中角栄がなくなったのは1993年
・「緊急発掘調査費」以外に、博物館・資料館・研究所などの設立・運営費・大学の研究者の人件費や助成金。
・自然科学分野をふくむ科学研究費助成金(科研費)
2017年度
a.「緊急発掘調査費」約600憶円
b.「科学研究費助成金総額」 2,284億円
2017年から過去30年間にわたる「緊急発掘調査費総額」2兆5,645億円
2017年から過去40年間にわたる「緊急発掘調査費総額」2兆8,462億円
戦後50年では、ゆうに3兆円を超すとみられる。
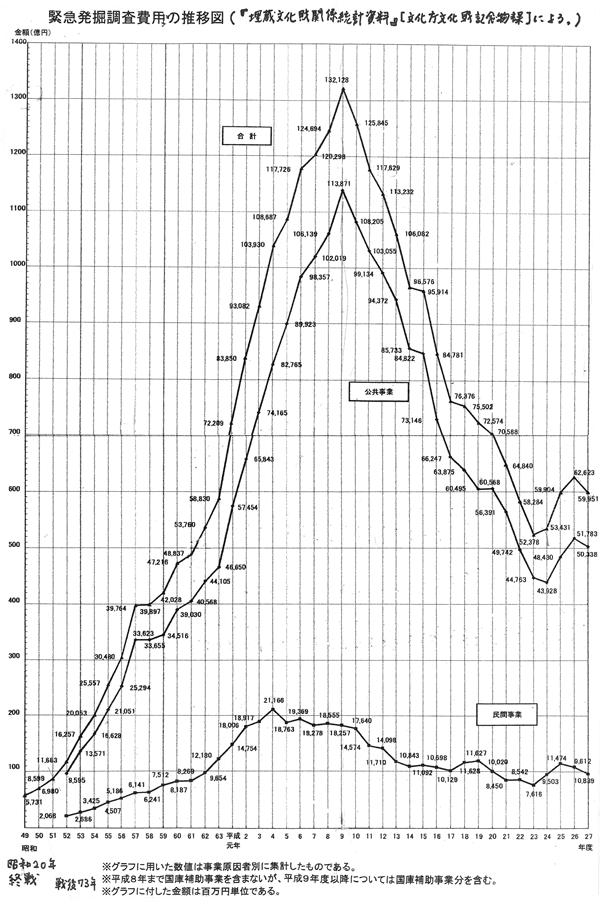
穴沢咊光(あなざわわこう)氏の批判
「資料の激増によって、梅原(安本注:京都大学教授の梅原末治のこと)のやったように自分の頭脳をデータベース化していたのでは追いつかなくなり、碩学の頭脳と資料のファイルに代わってコンピューターが登場し、『考古資料に関する情報ネットワークの開発によって、学界共通のデータベースには夥しい資料が登録され、そこから引き出される情報がただちに研究資料となる』という情報革命の時代が必ず到来するであろう。そういう時代に、考古学の最新課題となるのは、いろいろの情報をいかに総合して過去を復原するかという考古資料の解釈理論であり、『考古学は報告書や図録を出版するだけが能じゃない』といわれるようになるだろう。こういう時代になって、日本考古学が梅原のやったように『資料の語ることがおのずから結論となる』という厳格経験主義に拘泥し続けるならば、国際学界からは『事実を積み上げるばかりで、その説明を試みない』と『峻列な非難を浴びせられる』であろう。いや、現実に欧米の学界からすでにそのような非難が聞こえてきているのである。
筆者の知人のある外国人の考古学者はいう。日本考古学はデータで窒息しつつある。」
「現在まで、日本考古学主流のやってきたことは、さながら梅原的研究戦略の踏襲であり、これに無反省であれば、ついには晩年の梅原のように八幡の藪知らずのようなデータの森の中で迷子になるだけであろう。
我々日本の考古学研究者は、無意識の中に、梅原末治が作り出した大伝統の中に生き、良い意味でも悪い意味でも彼の遺産にドップリと浸っている。梅原はすでに亡いが、我々日本の考古学研究者一人一人のアタマの中には無数の小さな梅原が生きている。
梅原の考古学は日本考古学の成長過程の一つの段階であった。いまや、日本考古学の新たなる発展のために、梅原の模範に倣って日夜勤勉精励にモノを究める一方で、彼の学問を厳しく拘束しついにはその頽落に導いた厳格経験主義を脱皮するべき時期が到来しているのではあるまいか?」
「厳格経験主義に徹した記述の学者だった梅原にとっては、データ(資料)がすべてであった。彼の学問とはデータをどこからか仕入れてきて発表する以外にはタネもシカケもなく、それ以外に特別な方法も方向もなかったのだ。
「彼が我々日本の考古学者に残した偉大な遺産を最後に指摘することにしよう。
それは、梅原が残した膨大かつ良質な資料の記載や京大の伝統となった『青銅の考古学』と共に、『遺物を嘗めるように周到に観察し、正確に記載し、できるだけ速やかに上質の印刷の報告書にまとめて出版し、学界の共有財産とする』という習慣を、日本考古学の大伝統として学界に定着させたことである。」(以上、穴沢咊光「梅原末治論」[角田文衛編『考古学京都学派』雄山閣出版、1997年刊所収]による。)
考古学者、細谷葵(ほそやあおい)氏の批判
細谷葵氏(女性)は現在お茶の水女子大学特任准教授。
1996年当時、ケンブリッジ大学留学中に、「理論なき考古学-日本考古学を理解するために」という報告文を発表。イギリスのリバプール大学で、1996年12月に開催された「理論考古学グループ(Theoretical Archaeology Group)」の学会で。
この報告文は1997年に、岡山大学の考古学者の新路泉(にいろいずみ)氏らがインターネットで紹介されており、容易に見ることができる。
細谷葵氏は、この報告文において、「日本考古学における『理論』の欠如」を指摘し、「提示されているものは、説明も議論も伴わないバラバラのデータの山積み」で、これは、「日本考古学の独特のあり方」であり、欧米と日本とが、「根本的に異なる原理において進められているということ」を、まず指摘する。
遺跡、遺物は、年代を古くもって行くなど、また、邪馬台国や卑弥呼と呼びつけるほど、マスコミにとりあげられやすい。
かくて、塔の高さは、どんどん高くなり、年代は、どんどんふるくなる。
「再現性があるかないか」などのチェックを経ず、研究者の「意見」の方を尊重しすぎると、「話題性が高く魅力のあるもの」のほうに、ずれこんでいってしまう。
考古学者の森浩一氏はのべている。
「最近は、年代が、特に近畿の学者たちの年代が古い方へ向かって一人歩きしている傾向がある。」(『季刊邪馬合国』53号。梓書院、1994年刊)
年代くりあげ論は、客観的な事実や根拠を、提出しているわけではない。年代を古くしたならば、どのような「解釈」ができるかという「思考実験」をしているにすぎない。
古代の年代が古いほうへ、古いほうへと、ひとり歩きして行くのは、つぎのような事情によるとみられる。
とくに畿内のばあい、年代のキメテとなるものが出土することは、まずない。
西暦年数に換算しうるような、年代を記した土器などが出土しているわけではない。
ある考古学者A氏が、みずからの発掘にもとづいて、ある遺跡について、考えられる年代を発表する。そのさい、当然のことであるが、みずからの発掘についてのそれなりの無意識の愛着が生ずる。
考えられる年代のうち、もっとも古い年代を発表しがちになる。それは、
①古い年代ほど、マスコミがとりあげやすい。記者も、みずから執筆した記事が紙面を大きく飾ることを、期待するところがある。記事を、センセーショナルにするためには、年代は古いほどよい。
②マスコミを大きく飾ったほうが、発掘継続や、保存のための費用を、獲得しやすくなる。(旧石器程造事件など、まさにそうであった。)
③考古学者B氏は、考古学者A氏が、年代をあそこまで古くみているのなら、ということで、みずから発掘した遺跡について、さらに、考えうるもっとも古い年代を発表する。
④大阪府立弥生文化博物館館長の考古学者、金関恕(かなせきひろし)氏は、その編著の『古代の鏡と東アジア』(学生社、2011年刊)のなかでのべている。
「考古学の議論はいきなりパンチを喰らわすのではなく(笑)、だいぶ断りをいれながら(爆笑)……。」
このような傾向があるため、他の考古学者が、かなり無理な年代くりあげを行なっていても、それはその考古学者の考え、ということで、異論がはさまれることは、よほどのばあいをのぞいては、まずない。
客観的キメテがなく、かなりは、解釈にゆだねられているから、このくりかえしによって年代は、古いほうへ、古いほうへと、ひとり歩きして行く。
しかし、事実からは、かけはなれがちになる。矛盾が生じがちになる。それを、また、解釈でおぎなう。
かくて、考古学は、具体的事物をとりあつかう学問でありながら、「解釈」が、氾濫する状態となる。かりに、X氏が、年代を定めるキメテとなるような「事実」を提出しても、それは、X氏の「意見」と考えられがちとなる。
このような状態では、「邪馬台国問題」の解決は、むずかしいことは、おわかりいただけるであろう。なにが示されても、それは、X氏の「見解」となり、「事実」として定着しないのである。
科学や学問は、どんな科学や学問でも、それだけで孤立してしまうと、みずからの科学性を喪失してくるものである。
旧石器捏造事件のさい、『ネイチャー』誌は、「捏造された出土物は、批判の欠如をさし示す(Fake finds reveal critical deficiency)」という文章をのせ、「井の中の蛙(かわず)、大海を知らず」という『荘子』にもとづく日本のことわざの英訳"A frog in a well that is unaware of the ocean"を引用して、この事件を痛烈に批判している(Cyranoski. D,Nature、Vol.408.280ページ、2000年、11月号)。
そこには、つぎのような文章がみえる。
「この(旧石器捏造事件の)話は、藤村新一が捏造作業をつづけるのを許した科学文化についての疑問をひきおこした。」
東京大学医科学研究所の教授などであった黒木登志夫氏はその著書『研究不正』(中公新書、中央公論社、2016年刊)のなかでで記している。
「SF(藤村新一)のねつ造を許したのは、学界の長老と官僚の権威でもあった。その権威のもとに、相互批判もなく、閉鎖的で透明性に欠けたコミュニティが形成された。」
旧石器捏造の発覚以前から疑問を提示していた考古学者の竹岡俊樹氏は、その著『考古学崩壊』(勉誠出版、2014年刊)のなかで、のべている。
「私たちがさらに情けないと思うのは、発覚の後の対応である。自らの行ってきた学問に対する反省はまったく行われなかった。藤村というアマチュアや、文化庁(岡村)に責任を押し付け、その上、批判する者を排除しつづけた。検証は名誉職が好きな『権威者』たちによるパフォーマンスにすぎず、生産的なことは何も行われなかった。」
「この十数年間待っていたが何も変わらなかった。」
人類学者で、国立科学博物館人類研究部長(東京大学大学院理学系生物科学専攻教授併任)の馬場悠男(ばばひさお)氏がのべている、
「私たち理系のサイエンスをやっている者は、確率統計学などに基づいて『蓋然性が高い』というふうな判断をするわけです。偉い先生がこう言ったから『ああ、そうでございますか』ということではないのです。ある事実が、いろいろな証拠に基づいて100%ありそうか、50%か、60%かという判断を必ずします。どうも考古学の方はそういう判断に慣れていらっしやらないので、たとえば一人の人が同じことを何回かやっても、それでいいのだろうと思ってしまいます。今回も、最初は変だと思ったけれども何度も同じような石器が出てくるので信用してしまったというようなことがありました。これは私たち理系のサイエンスをやっている者からすると、まったく言語道断だということになります。」
旧石器捏造事件などがあっても、おなじようなことが繰り返されている。
中国の洛陽で「三角縁神獣鏡」が発見されたという記事が新聞にのったことがあった。マスコミに持ち込んだのは、大阪府の行政の考古学者であった。
中国全土では三千面以上の鏡が発掘によって出土している。そのなかには「三角縁神獣鏡」は一面も存在しない。
しかるに、中国の王趁意氏なる人物が十数面の「三角縁神獣鏡」を、つぎつぎと、とりだしてみせる。これは手品である。そのようなことができる王趁意氏は「神の手」の持ち主である。しかるに、行政の考古学者が、いたって簡単に信じこんでしまう。そして「私が実物を見たのだから確かです。」などと強く主張する。
「言語同断」というか、データサイエンスの基本的な学識に欠けている。
構造が、旧石器捏造事件と、ほとんど同じである。
ストップ詐欺被害!
考古学者たちの目は、フシ穴なのか。
読売新聞の記者であったジャーナリストの矢沢高太郎氏は、つぎのようにのべる。
「新聞やテレビで大きく報道されることによって社会的な関心が高まり、遣跡の生命が守られたケ-スは多い。しかし、同時に弊害もまたさまざまな形で発生した。学者にとっては、地味な論文を発表する以前にマスコミで大々的に取り上げられるほうが知名度も高まり、学界内部での地位も保証される傾向が強まった。一部の学者や行政の発掘担当者はそれに気づき、狡知にたけたマスミ誘導を行なってくるケースが多々見られるようになってきた。その傾向は、藤村(新一)氏以外には、考古学の。本場である奈良県を中心とする関西地方に極端に多い。そして、発表という形をとられると、新聞各社の内部にも何をおいても書かざるをえないような自縄自縛(じじょうじばく)の状況が、いつの間にか出来上がってしまった。そんなマスコミの泣き所を突く誇大、過大な発表は、関西一帯では日常化してしまっている。藤村(新一)氏は『事実の捏造』だったが、私はそれを『解釈の捏造』と呼びたい。」(旧石器発掘捏造”共犯者”の責任を問う)[『中央公論』2002年12月号」
平成10年度(1998)においては、科学費の総額1,179億円よりも。緊急発掘調査費1,256憶円のほうが多い。
これほど莫大なお金を費消しつづけながら、日本の古代を知るための、正確で有効な情報をもたらさない。むしろ、根拠のない誤った情報を現代も、やたらマスコミ発信しつづけているようにみえる。考古学とはいったい何なのか。
納税者の一人として、強く抗議をしてよい段階にあるようにみえる。
「公的教育費の対GDP(国内総生産)比率国際比較」という総計がある。これによると。日本は、一番最近の2017年度の数字で、3.47%である。これは、154カ国地域のなかの114位である。
小学校・中学校の教師たちは、加重な仕事量にあえいでいる。そのため、教師を希望する人たちが、しだいにへってきているという。(大きなお金が動く→組織ができる→お金を差配する人が生じる→権限を生じる→既得権となる)
「既得権となっているのだからしかたがない」ということで、過去にばかり金を投じ、未来への投資が困難になっているようでは困る。(現役世代が減り、高齢者の貧困はすでに深刻になりつつある)
「緊急発掘的なものの調査費用などの国際比較」も行なってみるなど外部からみたワクグミや基準も検討してみてはどうか。
大阪府知事であった橋下徹(はしもととおる)氏は、2008年に、府立博物館などの補助金を大幅に削減しようとした。「博物館の廃止もあるでしょうね。」とのべた。それは、「文化の切り捨て」として、マスコミにたたかれた。文化をなんとこころえるのかと。
文化は必要である。しかしかぎられた予算の配分にはバランスが必要である。
森浩一氏は述べている。
「今日の政府のかかえる借金は、国立の研究所などに所属するすごい数の官僚学者の経費も原囚となっているだろう。」
「ぼくはこれからも本当の学問は町人学者が生みだすだろうとみている。官僚学者からは本当の学問は生まれそうもない。」(以上、季刊『邪馬台国』102号、梓書院、2009年刊)
「僕の理想では、学問研究は民間(町)人にまかせておけばよい。国家が各種の研究所などを作って、税金で雇った大勢の人を集めておくことは無駄である。そういう所に勤めていると、つい権威におぼれ、研究がおろそかになる。」(『森浩一の考古交際録』[朝日新聞社出版、2013年刊])
考古学は、厖大なお金を費消しながら、社会への見返りが、あまりにもすくない。
むしろ誤った方法と認識とにもとづき、迷路にはいりこみ、大本営発表をくりかえすようになってきている。社会をミスリードするものである。
これだけの金額をつぎこめば、たとえ付随的にでも、これだけはたしかにいえるということがあってもよさそうである。それがあまりもすくない。
考古学界(会)は、緊急発掘調査費は、当然与えられるものという一種の既得権にもとづいて、過去に行ってきたことをくりかえすのではなく、外部の有識者などの意見もとりいれ、AIなどをいかして、主要な情報記録の自動化や、有効な情報抽出の効率化などに取り組み、思い切った経費削減をはかって欲しい。
報告書などは、一定の様式というか、パターンがあるので、あるていどの自動化は可能なはずである。人員の削減なども、検討してみてほしい。
21世紀のAIやデータサイエンスの時代に、19世紀以前の感覚や方法でとりくんでいるようにみえる。現状では、既得権益の上に安住しているとみられてもしかたないところがある。
[目録作成主義考古学批判]
1960~1970年代にかけて、アメリカの考古学者ルイス・ビンフォード(Lewis Roberts Binford 1931~2011)は「新考古学(ニュー・アーケオロジー new archaeology)」をといた。
ビンフォードがいう。
「従来の考古学は資料を提供するだけで、科学的な学問とはいいがたい。考古学者は埋蔵品の目録を作成するよりも、埋蔵品をもとに、古代文化を明らかにすることに、力をそそぐべきである。」
どこから、何が出土したかを、正確・詳細に記述し、目録を作成して行けば、おのずから過去が復元できる、ということにはならない。
古代を復元するためには、古代を復元するという明確な目標と、そのための「方法」とを、もたなければならない。
そうでないと、目録を作成しても、その目録によって、みずからが、あらかじめもっている「仮説」をうらづける事実だけを抽出して行くということになってしまう。何兆円もの金をかけて発掘が行われても、おそろしく主観的な古代史像ができあがってしまう。
古代史像を「客観的に」復元するためには、それなりの「方法」が必要である。
戦後50年以上、三兆円以上かけて掘ったが、その結果わかったことがある。
それはつぎのようなことである。
「掘って、遺跡・遺物を観察し、正確に記録をとることを重ねるだけでは、三兆円かけても、七万余戸とされる邪馬台国の場所さえ。きめることができない。データはもう気の遠くなるほど存在している。探究の方法を誤っているのではないか。ボーと生きてんじゃネーよ!」
もはや、データを記録するよりも、集めたデータを整理し、正確な推定をすべきである。19世紀的な素朴な探究法にしたがうのではなく、ビッグデータ分析法、データアナリシスの方法、AIなどを利用し、科学的な推定の軌道にのせるべきである。このような分析法によるとき、考古学的データを用いたばあいの結論は、昨年くわしく述べたように、すでに出している。
精密な発掘、精密な観察記録だけでは、「科学」というよりは、「技術」と呼ぶべきであろう。
小畑峰太郎著『STAP細胞に群がった悪いヤッら』(新潮社、2014年刊)という本がある。
この本のなかに、北海道大学名誉教授の武田靖氏の、鋭くも的確な見解が、紹介されている。
武田靖氏は、STAP細胞騒動を、「科学系と技術系という本質的に相容れない二つの集団」「基本的に知識体系の異なる集団」の対抗の観点からみる。
武田靖氏と小畑峰太郎氏はのべる。
「【武田】そこ(化学工学)では、科学に最も重用な『なぜ?』という内なる問いかけに、答えを見出すことが、ほとんど困難なのだ。その結果、『なぜ?』という問いかけすらしなくなり、ただひたすら実験を繰り返すことになる。(安本註。これと、ひたすら掘って、出てきたものを、正確に記録することを繰り返すことを基本とする考古学とを重ねてみよう。)
おそらく小保方は、そのように学んできたのだろう。つまり、『なぜ?』という問いかけをすることの重要性を学んでいない。
彼女の言い分を聞いていると、そうとしか思えない。実験を繰り返して、200回も実現できるようになっていれば、どういうパラメーター(媒介変数)の範囲でそれが実現されるかを考えるものだ。科学的な姿勢と発想を持っていれば、『なぜ』そうなのかを、当然考えてしかるべきなのである。
なぜそうなるかを考えていれば、もっと自信を持って説明できるはずなのだ。何も全てを分かる必要はなく、分かることと分からないことが、はっきりしていれば良いのである。」
「【武田】小保方を擁護するとすれば、『技術者』ならば、それでも良いということだ。『なぜ』かが分からないとしても、確実に物が作れれば良いのであるから。(安本註。考古学では、とにかく掘って結果を出せばよい。)」
「【小畑】今、日本の科学の世界では、そうした風潮が蔓延しているように思える。産業に結びつくための技術に偏した科学、あたかも結果を即座に出せるかのような。そこに利権と予算と拙速主義が集中して同居すると、必然的に今回のような捏造事件が起きてしまうのではないか。」
「【武田】科学と技術は、別の文化で、だから科学者と技術者は異なる人種なのだ。」
「【小畑】科学という学問、そして研究は、従事する者に対して、情け容赦ない苛烈な献身を要求する。『それでも地球は回る』と言ったガリレオの時代から、己が身を焼き尽すような科学への憧憬と献身、自己犠牲が、科学者の栄光を保証し、彼らの名をその歴史に刻んできたのである。時代の変遷の中、科学を忘れた科学者がメインーストリームに立つようなことも、たとえ一時はあるにせよ、まかり間違っても、技術者が科学者に成り代わるような世は決して来ないのではないか。それを科学は許さないだろう。
技術者が自らの法(のり)を超えて、『科学者』として、科学の世界に一歩でも足を踏み込んだが最後、僭称者には手酷い復讐が待ち受けている。
考古学は、基本的に、「技術」であり、邪馬台国の探求は、「科学」の問題なのではないか。