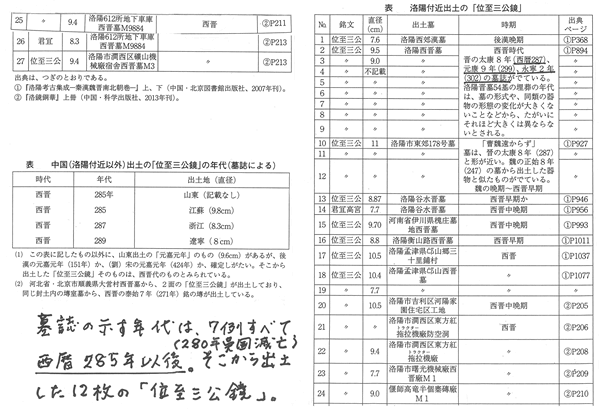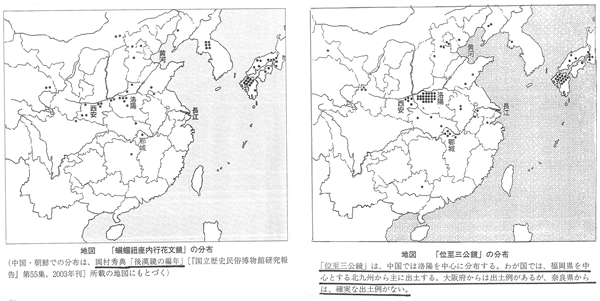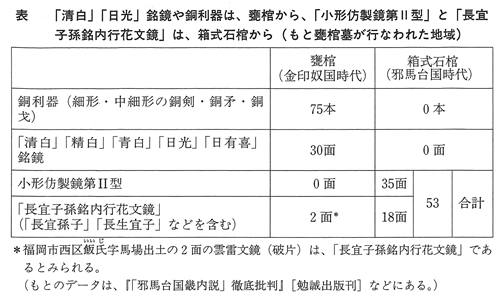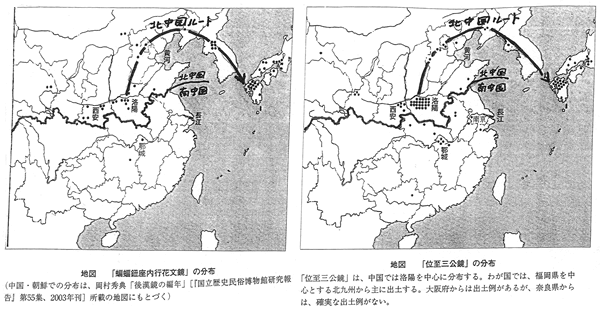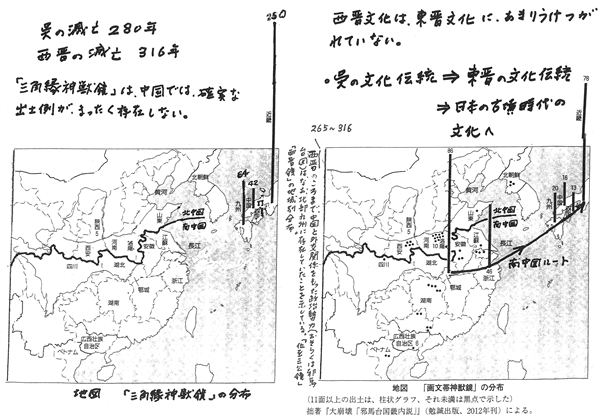日本最大の考古学関係の学会・日本考古学協会は、どこへ行くのか。
■失敗を重ねる考古学エスタブリッシュメント(既得権益派)
ものごとに成功したり、上達したりする近道であり、かつ正道といえる方法がある。それは、すでに成功している人、上達している人のまねから始めることである。「学(まな)ぶ」ということばは、「まねぶ(まねをする)」から来ている。
邪馬台国問題は「証明」を必要とする問題である。
とすれば、偽物(にせもの)や詐欺師にだまされて、同じような失敗をくりかえしている考古学エスタブリッシュメント(既得権益派)についていってはいけない。
「証明」の分野においてたえざる進展とめざましい成果をあげているデータサイエンス数理科学数学などにこそ、ついて行くべきである。
最近のデータサイエンスの進歩は、めざましい。とくに、世間の耳目を集めたのは、碁、将棋、チェス、オセロ、五目ならべなどのゲームにおいては、いまや、いかなる名人、上手といえども、コンピュータに勝てなくなってしまったことである。
たとえば、碁では、2017年5月に、グーグル傘下のディープマインド社の「アルファ碁」が、世界ランキング第1位の中国の柯潔氏を、3勝無敗で圧倒している。
将棋でも、同じ年の同じ月に、山本一成(いっせい)氏ら開発の「ポナンザ」が、佐藤天彦(あまひこ)名人に、2連勝し、電王戦を制している。
チェスでは、すでに、1997年に、IBMのスーパーコンピュータ「ディープブルー」が、ロシアのチェス世界チャンピオン、ガルリ・カスパロフを破っている。
これらのゲームでは、一手一手について、最終「勝率(勝つ確率)」を、コンピュータが示すことができる。さらに、コンピュータ同士を戦わせて、より勝率の高いソフトウェアを開発することができる。あるいは、自分自身との対局を、数千万回くりかえして、能力を強化することができる。文字どおり、機械(メカニカル)的に打つ手が定められて行くのである。
確率計算の結果のほうが、名人の手を読む力を上まわっているのである。
ここで、注意、注目すべき事は、AI将棋などにしても、ベイズ統計にしても、統計学的検定理論にしても、「確率」を求めることが、基礎をなしていることである。AI将棋などは「勝率」という形での「確率」を求める。ベイズ統計学では、「邪馬台国が福岡県にあった確率」「奈良県にあった確率」などの形で確率を求める。統計学的検定論では、種々の仮説のうち、一定の確率(ふつうは、1%、または、5%)以下の確率でしか成立しない仮説は捨てる(棄却)する約束をもうけることによって話を進める。そうしないと、「どんな小さな確率でも成立しないとは言えない」というような議論を強固に主張する人が出てきて、議論に決着がつかなくなるからである。つまり、仮設の取捨を客観的に行う装置として、「確率」を求める。鍵は「確率」にある。このことは、重要である。
毎週木曜日にイギリスで発行される国際的な科学ジャーナル『ネイチャー(Nature)』は『毎日新聞』で旧石器捏造事件についてのスクープのあった2000年の11月5日(日)の10日後の11月16日(木)に、早速この事件をとりあげて論じている。
「この(旧石器捏造事件の)話は、藤村新一が捏造作業をつづけるのを許した科学文化についての疑問を引き起こした。」
「日本では、人を直接批判することは難しい。とくに、エスタブリッシュメント(既得権益派、支配階級、社会的に確立した体制がわにある人々)の地位にある人々を直接批判することはむずかしい(In Japan, it is hard to criticize people directly, especially those in established positions)。」
「日本では人々を直接批判することは、むずかしい。なぜなら、批判は、個人攻撃とうけとられるからである。」
「直感が、ときおり、事実をこえて評価される。」
また、東京大学名誉教授の医学者、黒木登志夫氏は、その著『研究不正』(中公新書、中央公論新社、2016年刊)で、2012年に発覚した、ある麻酔医のおこした一連の論文捏造事件について、つぎのように記す。
「学会とジャーナルは積極的に自浄能力を発揮した。特に、日本麻酔科学会の報告書は、今後のお手本になるだろう。」
そして、旧石器捏造事件については、つぎのように記す。
「日本考古学協会は、検証委員会を立ち上げたが、ねつ造を指摘した竹岡(俊樹)と角張(かくばり)[淳一(じゅんいち)]は検証委員会に呼ばれなかった。ねつ造発見の10日前に発行された岡村道雄の『縄文の生活誌』は、激しい批判にさらされ回収された。しかし、岡村は、責任をとることなく、奈良文化財研究所を経て2008年退官した。」
「SF(藤村新一)のねつ造を許したのは、学界の長老と官僚の権威であった。その権威のもとに、相互批判もなく、閉鎖的で透明性に欠けたコミュニティが形成された。」
宮崎公立大学の教授であった考古学者の奥野正男氏も、毎日出版文化賞を受賞されたその著書『神々の汚れた手』(2004年、梓書院刊)の中で述べている。
「この事件(旧石器捏造事件)の本質とは何か。宮城県の地下には、数十万年前の旧石器が埋まっているという。まだ発掘で証明されていない。岡村(道雄)の予言が藤村という石器蒐集マニアによって、何十万年も前の地層から、予言通りの『前期旧石器』が次々に発見された。岡村の予言が学問的真実として立証されたという話が事件の本質である。これはものの道理を超えたオカルト話にほかならない。この物語が醸し出すうさん臭さは、考古学協会の検証部会や再調査の場で協会幹部がよってたかって藤村関与の遺跡のシロかクロかだけを論議した点にもよく現れていた。協会幹部は大会で『検証に参加すれば説明責任を果たしたと認めてよいと公言し、宮城・埼玉県など藤村の作為を黙認した行政研究者(地方公務員)の免責も約束した』。藤村一人を犯人にまつりあげ断罪する協会幹部の指導は、関係学者の『藤村に騙された』という大合唱となり、その後の検証でも関係学者の責任を誰も口にしようとしない、学会・研究団体の論理的退廃を生みだした。このような学会の実態は国民の考古学不審を大きくするばかりである。」
■じつは、旧石器捏造事件に類した事件は、日本の考古学の世界ではすでに何度も起きている。
[永仁の壺事件]
1957年に、「永仁の壺事件」が起きている。
「永仁の壺」は、愛知県志段味村(しだみむら)[現、名古屋市守山区]の「出土品」として紹介された。考古学の専門誌の『考古学雑誌』の1943年7月号にも紹介された。
「永仁の壺」は鎌倉時代の「永仁二年」(1294)に作られた古瀬戸の傑作として、重要文化財にもなった。
しかし、これは、結局、重要無形文化財(人間国宝)であった加藤唐九郎(とうくろう)氏のおこした贋作事件であったことで落着する。
この壺の、重要文化財への指定には、陶芸家・美術史家の、小山富士夫(こやまふじお)氏の強力な推薦があった。小山富士夫氏は、文部技官で、文化財専門審議会委員であった。当時、陶磁研究の第一人者とされていた。
小山富士夫は、加藤唐九郎氏の技に心酔する。ひたすら唐九郎氏を信じこむ。
文化財専門審議会は、この分野の権威者によって構成されている。その委員である小山富士夫氏が、判断を誤っていた。贋作であることを指摘したのは、滝本知二氏と菊田清年氏、小野田五風(ごふう)氏などの地元の古陶器家たちであった。滝本知二氏は、元瀬戸市史編纂委員、菊田清年氏は、瀬戸市の古陶器研究家、小野田五風氏は古陶器研究家で陶磁器修理業の人であった。
[勾玉事件]
また、梅原末治氏の「勾玉事件」がある。
梅原末治氏は、大正から昭和時代にかけての大考古学者であった。京都帝国大学の教授であった。
梅原末治氏は、多くの発掘出土品の精密な記録を残した人であった。
梅原末治が、伝橿原市出土、大和鳥屋千塚(とりやせんづか)[橿原市]出土などのように記して、古代の勾玉として紹介したものの八割以上が、現代技法によって作られたものであるとして、ガラス工芸の専門家の由水常雄(よしみずつねお)氏から、徹底的な批判をあびた(『芸術新潮』1972年1月号、『週刊新潮』1972年1月23日号、由水常雄著『火の贈り物』[せりか書房、1977年刊])。鉛ガラスでなく、ソーダガラスであること、ビール瓶を溶かして作られた独特の色をしているもののあることなどが指摘された。
この場合も考古学会の権威者が、判断を誤り、その誤りを指摘したのは、ガラス工芸の専門家であった。
旧石器捏造事件に関係した。岡村道雄氏は、文化庁文化財調査官、永仁の壺事件に関係した小山富士夫氏は、文部技官、勾玉事件に関係した梅原末治氏は、京都帝国大学教授。いずれも、国費によって生計をたて、研究を行ってきた人たちである。エスタブリッシュメントの地位にある人々であった。この種の事件は、あげて行けばきりがないほどで、ゆうに一冊の本が書ける。
考古学のエスタブリッシュメント(既得権益派)の人々は、ほとんど同じような失敗を、みんなでくりかえしている。失敗から学ぶことをしていない。そのような「学問」についていってはいけない。
ある仮説が、定説・通説となるためにはいくつもの関所を通り、チェックを受けなければならない。
その関守(せきもり)の役目をはたすのが、管轄官庁である文化庁であり、学会(学界)であり、ばあいによってはマスコミである。
旧石器ねつ造者の藤村新一氏が、発見したり、発掘に参加した関与遺跡は186ヵ所におよび、そのうち藤村新一氏が本格的に発掘調査に参加した遺跡は33ヵ所であったという。
期間は、1976年の宮城県の座散乱木(ざさらぎ)遺跡の発掘にはじまり、2000年11月に『毎日新聞』のスクープによって発覚するまで足かけ25年間におよぶ。
岡村道雄氏は、文化庁の文化財部記念物課の埋蔵文化財部門の文化財調査官の主任であった。埋蔵文化部門は、文化財保護法にもとづいて、各地の遺跡の保護や発掘調査状況の監督を行なうセクションである。
岡村道雄氏は、その著『縄文の生活誌』(講談社、2000年刊)の中で記す。
「1980年4月、座散乱木の切り通しの前に、藤村新一氏や私たちは横一線に並び、地層断面を一生懸命に削った。私の移植ゴテにも石器が当たった『カチッ』という手ごたえがあった。まちがいなく卒業論文以来、長年夢にまで見た『旧人』の石器だ。日本にも四万年前にさかのぼる中期旧石器時代に、確実に人類が生活していたのだ。その瞬間、あまりの感激に、体の中を電気が走り、あたりが暗くなるような眩暈(めまい)を私は覚えた。」
考古学研究者は、人がらのよい、だまされやすい人が多いのであろうか。
ほとんど同じような話がある。
「ナウマン像の脂肪酸」事件である。
宮城県古川市の馬場壇A遺跡の14万年~11万年前ともいわれる当時の地表の、石器と石器の見つかった地点の土には、動物の脂肪酸が残っていて、それが北海道広尾郡忠類(ちゅうるい)村[現、十勝(とかち)支庁中川(なかがわ)郡幕別町(まくべつちょう)南部、「忠類」はアイヌ語の「チュウルイトプイ(流れの激しい川)による]から出土したナウマンゾウのものと一致した、という話である。
国立歴史民族博物館の副館長(のち館長)であった考古学者の佐原真氏は、その著『日本人の誕生』(「大系日本の歴史1」小学館、1992年刊)において、つぎのように記す。
「私たちが宮戸島の『晩餐(ばんさん)』で現生動物ではイノシシにいちばん近いと聞いた動物の正体が脂肪酸組成で忠類のナウマンゾウと一致することを電話で知らせる中野氏(安本注。中野益男氏。文部省の科学分析担当者)も、奈良でそれを受ける私も感激でふるえんばかりであった。」
ナウマンゾウの脂肪酸が検出されたのであれば、馬場壇A遺跡は間違いなく旧石器時代のものとなる。
ところがのちに、馬場壇A遺跡の石器はすべて藤村新一氏の捏造したものであったことが判明する。
では「ナウマン像の脂肪酸」とはなんであったのか。現在では発掘担当者の、手のアブラであったのではないか、などといわれている。ほとんど笑い話のような話である。
なお、「脂肪酸」事件を検討したものに、つぎのものがある。
・灘波紘二・岡安光彦・角張淳一「考古学的脂肪酸分析の問題点・・・日本考古学協会第六七回総会(2001年度)研究発表要旨。」
日本考古学の世界はみずからがあらかじめ持っている説にとって都合のよいものが、つぎつぎに出土・出現するようになる世界であるらしい。
すこし、というかかなり注意したほうがよい。
岡村道雄氏の「あまりの感激に、体の中を電気が走り、あたりが暗くなるような眩暈(めまい)を覚えた。」と、佐原真氏の「感激でふるえんばかりであった。」とは表現がかなりよく似ている。
ここでは感激によって、どれだけ「信じこむことができるか」が判断の基準になっているようにみえる。
「仮説」はいくつかの関所を通り抜けることによって、「定説」になって行く。
その関所の関守(せきもり)の役目をはたすのが、文化庁の担当官であり、国立歴史民族博物館などや研究所であり、学会(学界)などのはずである。ところがそれらの人たちが、関守の役目をはたしていない。
藤村新一氏は関所破りをしたのではない。「神の手」の持ち主とあがめられて、二十数年間、ゆうゆうと何度も関所を表門から通り抜けているのである。
おそろしく間の抜けた話なのである。
日本の他の学問分野では、あまり例がない。世界的にもかなりめずらしい事件である。
関守たちはいう。
「こんなひどいインチキをする奴がいるんだ。」
だました奴が悪いというが、本来チェック役でだまされてはいけない人たちがだまされているのである。お墨付きを与えているのである。
犯人を批判してすむ話ではない。
関守たちは、二十数年間なにをしていたのか。なんのために、お上から、税金にもとづく食い扶持を与えられていたのか。このような事態がおきるのをふせぐためではなかったのか。関守たちはだまされることによって、結果的に人をだます立場に立ってしまっているのである。公費の浪費にもつながることになる。
「旧石器の年代は、古くさかのぼれるはずだ。」
「邪馬台国は畿内にあったはずだ。」
先入観でものを見るから不都合な事実やデータが目にうつらなくなる。あやしげな話に簡単にひっかかるようになる。
そこにはみずからの立場を守ったほうが、研究費かせぎ、調査費かせぎ、生活費かせぎに都合がよい、というおもわくもほのかにみえる。そのおもわくが判断を誤らせる。
重ねていう。失敗をくりかえしている考古学エスタブリッシュメントのとっている方法についていってはいけない。成功している方法にこそついて行くべきである。
日本の考古学の世界では、その世界の中で出世し発言力を持っているということを正しい論証力、判断力をもっているということとのあいだに、しばしば大きなへだたりがある。
出世力のほうは、その世界の大勢や伝統的な考え方にしたがうほうが出世しやすい。しかし、その世界の伝統的な考え方じたいが誤った方向に進んでいるばあいは、「出世力」は「客観的事実」などと、しばしばあわなくなる。昔の陸軍の失敗を思い浮べよ。
確率論によって支えられた現代統計学・数理統計学は、医学・薬学をふくむ自然科学はもちろんのこと、心理学・社会学などをはじめとする人文科学においても、社会科学においても、研究を進める武器として用いられ、客観性をそなえた「科学」の基礎をなしている。
ただ考古学の分野では、確率・統計などの基礎教育を行なう伝統が築かれていない。ここに大きな問題がある。他の分野の研究者は、考古学研究者と話しても、しばしば外国人と話をしているように、話が通じない。
「データがもたらす事実そのもの」よりも、考古学の分野では「社会的に偉い人」の判断や発言が重んじられ、それが基準となる。属人主義の傾向が根づよい。率直にいえば学問や科学の体(てい)をなしていないことがすくなくない。
考古学の分野では社会的に地位のある人でも、しばしば「どれだけ感激できるか」「電気が走ったような感覚がえられるか」が、真実性を裏づける基準として、用いられるようにみえる。
マスコミで騒がれたところに予算がつくという傾向から、考古学の分野に厖大な公費が流れこんでいるが、失敗をくりかえしている考古学にそれほど公費をそそぎこむことが妥当かどうか、検討をしてみる必要がある。
「邪馬台国北部九州説」と「邪馬台国畿内説」との間、「邪馬台国福岡県存在説」と「邪馬台国奈良県存在説」とのあいだには、その「成立しうる確率」において、圧倒的な差がある。
ほぼ「100%対0%」である。しかもそれは「考古学的データ」によって計算してもそうなる。
「邪馬台国畿内説」「邪馬台国奈良県存在説」をとる人々は、この事実に関して、「明確な反証」を示さなければならない。
しかし、今またこれまでと同じような事件が起き、進行しつつある。強い警告を発せざるを得ない。日本考古学協会は、日本最大の考古学関係の学会である。
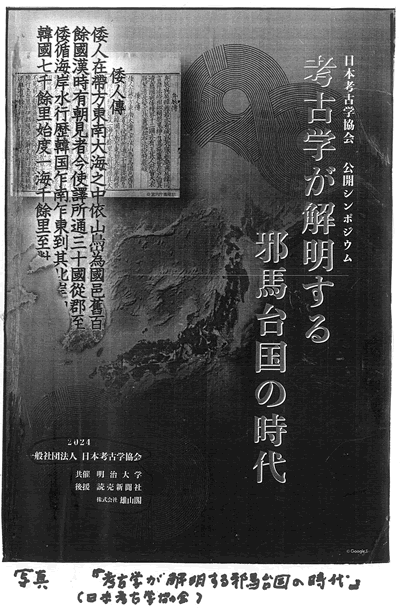 会員数は三千名から四千名を推移している。会員のおよそ7割程度は行政関係の発掘担当者(緊急調査などの発掘にあたる)であるといわれる。
会員数は三千名から四千名を推移している。会員のおよそ7割程度は行政関係の発掘担当者(緊急調査などの発掘にあたる)であるといわれる。
日本考古学協会、あるいは協会幹部のあり方について、東京大学の黒木登志夫氏や宮崎公立大学の奥野正男氏などから批判の行われていることは、さきにみてきた。
『ネイチャー誌』に見られる批判や、旧石器捏造事件についての告発者竹岡俊樹氏の行われている批判の多くも、日本考古学協会、あるいはその幹部のあり方にあてはまると言えよう。
現在の日本考古学協会の会長は、明治大学の教授・石川日出志氏である。石川日出志氏は、日本考古学協会の名において、寺沢薫氏、岡村秀典氏、福永伸哉氏など「邪馬台国畿内説」の人ばかりを集めて「考古学が解明する邪馬台国の時代」と題する公開シンポジウムを開き、その内容をまとめた冊子を日本考古学協会の名において出版社雄山閣から刊行している(2024年9月刊)。
これはどういうことなのであろう。
日本考古学協会の会員には、吉野ヶ里遺跡の発掘で著名な高島忠平氏、三重大学教授の小沢毅氏、関西外国大学教授の佐古和枝氏、奈良県立橿原考古学研究所の所員であった関川尚功(せきがわひさよし)氏など邪馬台国九州説の立場に立つ人や、邪馬台国畿内説に異論を表明している人なども決してすくなくない。
私(安本)もまた、日本考古学協会の会員である。
『考古学が解明する邪馬台国の時代』(以下、『シンポジウム報告書』と略記する)を読めば、会長の石川日出志氏は「日本考古学協会としては、邪馬台国畿内説でいきます」と号令をかけておられるようにみえる。ずいぶん無神経で、独断的な話である。
シンポジウム登場者のうち、寺沢薫氏の諸説については、寺沢氏の支持または指示する説および鉄などのデータが、寺沢薫氏の述べている邪馬台国が畿内にあったとする結論を否定している(成立の確率が九州説の千分の一以下)。そこに「自己矛盾」が見られる(「自己矛盾」は、寺沢氏が、他説批判の際に、しばしば使用される言葉。ただし、寺沢氏の用いる「自己矛盾」は、確率計算などの客観的基準に基づくものではない。寺沢氏の主観的な判断にもとづいている)。
寺沢氏の見解については、すでにややくわしく検討してきた。
そこで、次に岡村秀典氏の見解を取り上げよう。
京都大学名誉教授岡村秀典氏の「卑弥呼の鏡=三角縁神獣鏡」説批判。
■邪馬台国畿内説論者における邪馬台国問題をめぐっての重要な相違点
岡村秀典氏は、九州大学助教授、京都大学教授をへて、現在、京都大学名誉教授、文学博士。立派な経歴の持ち主である。
まず、とりあげなければならない事は『シンポジウムの報告書』には表(おもて)だってあらわれていないが、シンポジウム登場者のあいだに、同じ邪馬台国畿内説論者であるとはいえ、邪馬台国問題をめぐって、その立場、見解において、かなり大きな、かつ重要な相違点が見られることである。
寺沢薫氏と岡村秀典氏とのあいだの、見解の大きな相違点の例をみてみよう。
(1)岡村秀典氏は、卑弥呼に魏の皇帝から与えられた「銅鏡百枚」を「三角縁神獣鏡」であると考えておられる。これは京都大学考古学研究室の伝統的な考え方にしたがうものである。(小林行雄氏、樋口隆康氏)
岡村秀典氏は、その著『三角縁神獣鏡の時代』(1999年、吉川弘文館刊)147ページに、つぎのように記しておられる。
「倭王卑弥呼に下賜された『銅鏡百枚』は三角縁神獣鏡であると考えている。」
(2)寺沢薫氏は「三角縁神獣鏡」は日本で製作された鏡であろうと、考えておられる。
寺沢薫氏はその著『卑弥呼とヤマト王権』(2023年、中央公論新社刊)において述べられる。
「中国に出土例がなく、国内で500面を超えるといわれる三角縁神獣鏡は、画文帯神獣鏡や斜縁神獣鏡群を範型として日本で製作されたとみるほうが合理的だと私は考えている。」(329ページ)
岡村秀典氏は『シンポジウム報告書』において、銅に含まれている鉛同位体比についてのデータなどを示しておられるが、寺澤薫氏は『卑弥呼とヤマト王権』の中で、鉛同位体比についてのデータにもとづいての、「銅鏡百枚」に「三角縁神獣鏡」がふくまれるとする説批判などもかなりくわしく紹介しておられる。岡村秀典氏は、寺澤薫氏の著書に、目を通しておられないのであろうか。
「邪馬台国=畿内説」の考古学者、石野博信氏[関西学院(かんせいがくいん)大学・大学院]も、98年の『歴史と旅』4月号所載の「"卑弥呼の鏡"ではない」の中で、次のように述べている。
「(三角縁神獣鏡は)ヤマト政権が弥生以来の祭式を廃止し、中国鏡をモデルとして、四世紀にヤマトで創作した鏡なのである。」
「平成十年と年が改まって早々の一月九、十日は、橿原考古学研究所と天理市教育委員会によって調査された黒塚古墳出土の三十二面の鏡の報道でもりあがった。その後、一月二十三日に"鏡の取り上げは終了した"と報道されるまでの十三日間は、十七、十八日の現地説明会をはさんでマスコミ各社とも黒塚報道が続いた。ある調査員の。"これは(文化現象ではなく)社会現象だ"というつぶやきは、まさにその通りだと思う。
なぜそうなったのか。三角縁神獣鏡は、倭国の女王卑弥呼が西暦二三九年に魏の皇帝から貰った鏡だ、という学説をマスコミがそのまま信じたからだ。確かに『魏志倭人条』には、他の品々と共に『銅鏡百枚』を賜う、と書いてあるけれども、いま考古学界で三角縁神獣鏡とよんでいる鏡が、これに相当するかどうかはまだ結論が出ていない。
それなのに。"邪馬台国の鏡""卑弥呼の鏡"として、連日大見出しで報道した全マスコミの罪は大きい。たとえ本文で、非中国鏡説があると書いていても、読者は見出しの大きさに圧倒されてしまうし、圧倒しようという意図がまる見えである。
私は、現地で三角縁神獣鏡が二十面をこえたと聞いたときに、これは中国からの輸入鏡ではないと、感じた。なぜか。」
「大和(おおやまと)古墳集団には、二十七基の前期前方後円(方)墳がある。そのうち黒塚古墳と同等以上の全長120メートルをこえる古墳が十八基ある。十八基の古墳がすべて三十面の三角縁神獣鏡をもっているとすれば、この地域だけで五百四十面が埋もれていることになる。(「魏志倭人伝」で卑弥呼が賜ったとする)「銅鏡百枚」をはるかにこえてしまう。全長200メートルをこえる四基の大王墓が、一基で百面をこえる三角縁神獣鏡をもっていたとすればどうなるのか。
このような単純計算に対して、中国鏡論者は、黒塚古墳や三角縁神獣鏡三十二面が出土した京都府山城町の椿井大塚山(つばいおおつかやま)古墳の被葬者は、鏡配布にかかわる職務を担当していたから多量に保持していたが、他の職務の人はそうとは限らないという。
たまたま調査した二つの古墳被葬者が鏡の配布担当者というのも都合がよすぎる考えだし、両者で六十面以上の『中国鏡』を保持するのは、どう考えても持ちすぎ、隠匿のしすぎである。三角縁神獣鏡は、大王から配布を命ぜられた公器だというのだから。
以上のように、今回の黒塚古墳調査の大きな成果の一つは、三角縁神獣鏡が邪馬台国とはなんら関係ないことが判明した点である。」
石野博信氏は共著『邪馬台国研究 新たな視点』(朝日新聞社、1996年)の中で、次にまとめられるような見解も述べておられる。
(1)京都の椿井大塚山古墳は、土器からすると、どうみても4世紀の中ごろから4世紀後半ぐらいのものではないかと思われる。(埋納年代:鋳造年代)
(2)椿井大塚山古墳から、三角縁神獣鏡が三十数面出土している。
(3)3世紀の三角縁神獣鏡が、だれでも認める形ででてこない。3世紀だと考えた三角縁神獣鏡をもつ古墳は、かなり努力して古くしている方のものである。
(4)椿井古墳の三角縁神獣鏡と同じ型で作った鏡を、いくつかの古墳で分有するようになるのは、4世紀中葉以降であると考えられる。それは、前方後円墳が、東北から九州まで全国的に広まった段階と一致するのではないか。
『邪馬台国研究 新たな視点』の中で、石野博信氏は述べる。
「あれ(三角縁神獣鏡)を勉強しなくても卑弥呼のことがわかる。後のことなのだからあれは無視していいと考えればいいのではないかと思っている。」
33枚の三角縁神獣鏡が出土した奈良県の黒塚古墳の発掘の計画者であり、直接の指揮者である奈良県立橿原考古学研究所調査研究部長の河上邦彦氏[関西大学(かんさいだいがく)]も「三角縁神獣鏡が『卑弥呼の鏡』などということはありえない」「ヤマト政権が作り出した鏡に違いない」と、『産経新聞』1998年1月16日付朝刊の記事のなかで、明言している。
三角縁神獣鏡は、「葬式に使った葬具」で、「ヤマト政権が、配下の豪族の死にあたって葬具として分け与えたのだろう」と、河上氏はいう。
河上邦彦氏は、『東アジアの古代文化』の1998年春・95号の、「黒塚古墳発掘の意味」という鼎談(ていだん)の中で述べている。
「ここでしっかりと書いておいて欲しい。新聞に書かれた各説がウソばかりだと(笑)。」
そして河上邦彦氏は、冗談のような感じで、三角縁神獣鏡問題を考えるうえで、きわめて重要な意味をもつとみられる発言をしている。
「京大には椿井大塚山古墳の鏡が保管され、その関係者はその鏡を十分見ることができた。三角縁神獣鏡は、重く、大きく、文様がすばらしい。これは舶載鏡だと信じ切ったら、もうそのままで来ている。京大の関係の人たちでどうも舶載鏡説が高いのはそのへんに原因するのではないか。」
京都大学は、近畿にある。かつての王城の地である。近畿を発掘すれば、当然、多くのものが出土する。地の利が与えられている。発言の機会も与えられやすい。
「何年も研究したエライ肩書の専門家が、あれだけ断定的にのべるのだからそうとうな根拠があるのだろう」と、マスコミも、ふつうの人も思ってしまうだろう。しかし、マスコミを通してのPRばかりがあって、その実体がない。
京都大学を卒業した人でも、京大考古学のエスタブリッシュメント(既成勢力)の見解に、したがわない人たちがいる。
そのような考古学者の一人、原口正三(はらぐちしょうぞう)氏は、高槻市教育委員会編『邪馬台国と安満宮山(あまみややま)古墳』(吉川弘文館、1999年)におさめられた「基調報告 三角縁神獣鏡から邪馬台国を解く」の中で述べている。
「要は、三角縁神獣鏡は中国にも朝鮮にも一枚もない。これは皆さん、ひとつ肝に銘じておいていただきたい。」
「卑弥呼がもらった鏡は20センチを超えるようなものではなくて、直径十数センチまでの小さいものだった。三角縁神獣鏡は、その後、それをモデルにして大量生産をした。
そうでなければ、同じ地域で十回も順番をつけて同じ鋳型からつくるという追いかけ鋳型は、製作地でないと出てきません。」
「梅原末治先生は、富岡謙蔵(とみおかけんぞう)さんの後を受けて鏡の研究をされた方ですが、先生の書かれた本を読むと、大正時代から昭和15年ぐらいまで、全国の鏡の集成をやったり枚数をそろえたりされています。そのころから、ほかの鏡に比べて三角縁神獣鏡はとびきり枚数が多いわけです。現在、朝から晩まで全国で各自治体にいる職員が血眼になって調査をしていますから、ますます鏡の枚数は増えるだろうと思います。それを、あくまであれは魏でつくったのだと言い張っているのは、もう信仰にも近い考え方だろうと思います。」
■中国の考古学者、王仲殊の見解
2015年になくなった中国を代表する考古学者、王仲殊氏(中国の社会科学院の考古研究所の所長などであった)は、「三角縁神獣鏡」などは、中国で作られたものではなく、中国の工人が、日本に渡ってきて、日本で作ったものである、とする説をかねて述べてこられた方であった。
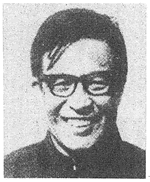 王仲殊氏は、かつて、私に、次のようなお手紙をくださったことがある。
王仲殊氏は、かつて、私に、次のようなお手紙をくださったことがある。
「安本美典先生(中国語の「先生」は、日本語の「様」に近いニュアンス)
您好(ニンハォ)[您好(ニーハォ)〔今日は〕の丁重表現]!
(2013年の)8月21日にお手紙いただきました。
三角縁神獣鏡=魏鏡説破滅をテーマとする大著を恵贈していただき、ありがとうございます。
二〇世紀の初期に富岡謙蔵が提出した魏鏡説は、これはこれで理解できるものです。
ただし、二〇世紀の80年代以降になると、中国本土および朝鮮半島の地域内に、三角縁神獣鏡の出土例が完全に存在しないことが、確認されたのち、魏鏡説は、成立がむずかしくなりました。とくに、1986年10月に、二面の景初四年銘の三角縁盤龍鏡が発見され、いわゆる『特鋳説』もまた、立足の余地を完全に失いました。これは鉄のように固い事実です。
何人(なんびと)も、否認することができないことです。
森浩一先生か逝去され、悲しい思いにたえません。なつかしく思うことです。
二〇一三年十一月十日 王仲殊 拝」
(下図はクリックすると大きくなります)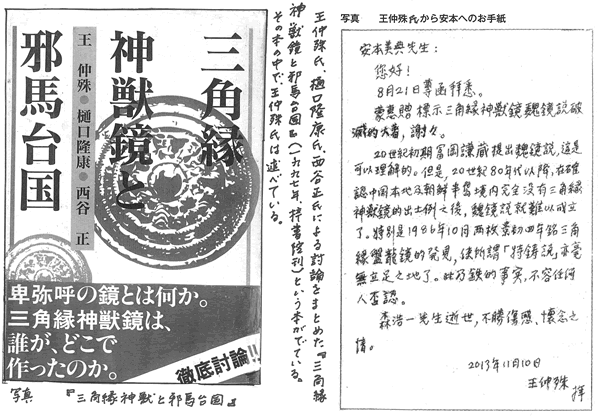
王仲殊氏、樋口隆康氏、西谷正氏による討論をまとめた『三角縁神獣鏡と邪馬台国』(1997年、梓書院刊)という本がでている。その本の中で、王仲殊氏は述べている。(本の表紙は上の図参照)
「1920年代ごろから、日本の学者は、日本出土のいわゆる『舶載』の三角縁神獣鏡を三世紀中国の三国時代の魏鏡であると考え、これこそが魏の皇帝の下賜した『卑弥呼の鏡』であると主張して来ました。これはつまり、三角縁神獣鏡の『魏鏡説』であり、日本の学界で七十年あまりにわたって主導的な位置を占めつづけていて、現在に至っています。
しかしながら、中日両国において考古学の発掘調査が進展して来たことによって、じっくりと考えてみなければならない新たな事実に、我々は直面することになりました。日本において、いわゆる『卑弥呼の鏡』である三角縁神獣鏡が古墳から次々と出土し、その数は既に四百数十面の多きに達し、『魏志』『倭人伝』に記されたり『銅鏡百枚』を大幅に超過するありさまとなっています。それに対して中国では、魏王朝の都の所在地洛陽はもとより、北方や南方の各地において、大量の銅鏡が発掘されたにもかかわらず、三角縁神獣鏡らしきものはただの一面も出土していない。さらに、当時の中国は朝鮮半島に楽浪郡と帯方郡を設置していたため、各種の中国銅鏡が朝鮮と韓国の古墳から出土しているが、そめ中にも三角縁神獣鏡が含まれていません。これらの事実は明らかに、三角縁神獣鏡が中国で作られたものではなく、日本で製作されたものでなければならないことを物語っているのであります。
『魏鏡説』を主張する研究者は、以上述べた動かし得ない事実に対して、一種の『特鋳説』と称する学説を提出し、三角縁神獣鏡は魏王朝が女王卑弥呼に下賜するため、景初三年から正始元年までに特別に鋳造したものであると唱えて、自説を堅持しようとします。
 しかし中国の魏王朝は、果たして銅鏡を外国のために特鋳する必要でもあったのでしょうか。また魏王朝は、他の外国の君主のために銅鏡を特鋳していないのに、なぜ倭の女王のためだけに特鋳したのでしょうか。かりに特鋳が行なわれたとしても、その際、見本がなくてはどうしようもないではありますまいか。中国の職人たちは、これまで中国において三角縁神獣鏡を鋳造したことがなかったのに、どうして邪馬台国の女王のためにこのような未曾有の銅鏡を特鋳することが出来ましょうか。つまり、特鋳説は不合理で、どうしても成立しない。わけても京都府大田南5号墳の青龍三年銘方格規矩四神鏡の出土は、魏王朝の賜わった『卑弥呼の鏡』が景初三年よりも前に製作されたことを証明したので、三角縁神獣鏡の特鋳説があくまで否定されてしまいます。」(青龍三年銘方格規矩四神鏡は上図参照)
しかし中国の魏王朝は、果たして銅鏡を外国のために特鋳する必要でもあったのでしょうか。また魏王朝は、他の外国の君主のために銅鏡を特鋳していないのに、なぜ倭の女王のためだけに特鋳したのでしょうか。かりに特鋳が行なわれたとしても、その際、見本がなくてはどうしようもないではありますまいか。中国の職人たちは、これまで中国において三角縁神獣鏡を鋳造したことがなかったのに、どうして邪馬台国の女王のためにこのような未曾有の銅鏡を特鋳することが出来ましょうか。つまり、特鋳説は不合理で、どうしても成立しない。わけても京都府大田南5号墳の青龍三年銘方格規矩四神鏡の出土は、魏王朝の賜わった『卑弥呼の鏡』が景初三年よりも前に製作されたことを証明したので、三角縁神獣鏡の特鋳説があくまで否定されてしまいます。」(青龍三年銘方格規矩四神鏡は上図参照)
ベイズの統計学の考え方にしたがえば、つぎのようにモデル化できよう。「日本と書かれた箱に、赤い玉が500個はいっている。中国と書かれた箱に、赤い玉は0個はいっている。
今、このどちらかの箱から、玉を1個とりだしたところ、赤い玉であった。この玉が中国と書かれた箱からとりだされた確率は、いくらか。とりだされる確率は、それぞれの箱に入っている玉の量に比例するものとする。」
中国と書かれた箱から取り出された確率は、当然0(ゼロ)である。無い袖(そで)を振ることはできない。
三角縁神獣鏡は中国(魏)からもらったものであるとする学説は、客観的な基準をあらかじめ定めず、言葉だけの解釈にたよれば、どんな説でも成立とするという見本のような学説である。
しかし、この説をとなえる人たちにとっては、先生や先輩の説にしたがい、それを補強することによって、京大の教授などの権威の座が与えられるという個人的な成功をもたらした学説である。手ばなすことはできない。
かくて、一種の、学術的カルトが成立する。
■「三角縁神獣鏡」の、「古墳築造時鋳造説」
「三角縁神獣鏡」は、わが国で古墳築造時に、その古墳の比較的近くで鋳造されたとする見解は、私の知るところ。三つである。
(1)鈴木勉氏の見解(「邪馬台国の会第372回講演(2018年9月23日)資料参照)
(2)新井宏氏の見解(「邪馬台国の会第268回講演(2008年4月20日)資料参照)
(3)私(安本美典)の見解(「邪馬台国の会第268回講演(2008年4月20日)資料参照)
まず、(1)の鈴木勉氏の見解は、鏡の鋳造技術面から見た発言である。
奈良県立橿原考古学研究所共同研究員で、工芸文化研究所所長の鈴木勉氏は、その著『三角縁神獣鏡・同範(型)鏡論の向こうに』(雄山閣、2016年)の中で、次のように述べている。
「三角縁神獣鏡の仕上げ加工痕が、出土古墳によって異なる、つまり、仕上げ加工技術が出土古墳ごとにまとまりを見せる。このことは鏡作りの工人らが出土古墳近くの各地に定住していたか、あるいは移動型の工人集団が各地の政権からの依頼を受けて各地へ赴いて製作にあたったか、を考えることになる。」
「椿井大塚山古墳の『研削』鏡16面は、どれも同じ目の砥石を使って仕上げ加工されたことが分かる。湯迫車塚(ゆばくるまづか)古墳の3面の『研削』鏡には同じ細かい目の砥石が使われたことがわかり、佐昧田宝塚古墳の3面の『研削』鏡にも同レベルの細かい目の砥石が使われたことが分かる。」
「仕上げ加工の方法は、同范(型)鏡群よりも、出土古墳によって規定されている。」
三角縁神獣鏡製作の仕上げのさいの加工の技術が、出土古墳ごとにまとまりを見せる、というのである。
つまり、仕上げ加工の方法は、同位(型)鏡(工場でつくられた製品のように、同じ文様、同じ型式の鏡)でも、出土古墳が異なっていれば違いがあり、同じ古墳から出土した鏡は、異種の鏡でも、同じであるというのである。
また、数理考古学者の新井宏氏は、鏡の原料の銅にふくまれる鉛の同位体比について調べ、鈴木勉氏とまったく違う方法・根拠により、鈴木勉氏とほぼ近い結論を述べておられる(新井宏氏の見解は、『古代の鏡と東アジア』[学生社、2011年]に収められた論文「鉛同位体比から見た三角縁神獣鏡」に述べられている)。
そして、(3)の私(安本美典)の見解はコピー鐃を作るさいの面径の変化に着目
私も鈴木勉氏や新井宏氏と、ほぼ同じ結論に到っている。ただ、そのような結論を導き出す方法、根拠は両氏とは、また異なる。
私の方法は、鏡のコピー鏡(同笵鏡、同型鏡、踏み返し鏡などといわれるもの)を鋳造するさいに、収縮や、拡大現象がおき、もとの鏡(原鏡、原型など)にくらべ、条件により、コピー鏡の面径が、大きくなったり、小さくなったりすることがあることに着目するものである。
「三角縁神獣鏡」には、コピー鏡が多いが、そして、同一古墳から、コピー鏡が数面出土することがあるが、ある鏡の、同一古墳から出土したコピー鏡では、面径が一致する傾向がみられ、異なる古墳から出土したコピー鏡のあいだでは、古墳ごとに面径が異なる傾向がみられる。このことに着目した議論である。
このような議論については、拙著『「邪馬台国畿内説」を撃破する!』(宝島社新書、宝島社、2001年)や、『大炎上「三角縁神獣鏡=魏鏡説」』(勉誠出版、2013年)において、データを示し、ややくわしく論じた 。
 また、このような拙論に対し、京都大学の考古学者のある先生からの批判がみられるが、そのような批判に対する反批判も、『大炎上「三角縁神獣鏡=魏鏡説」』の中で述べた。
また、このような拙論に対し、京都大学の考古学者のある先生からの批判がみられるが、そのような批判に対する反批判も、『大炎上「三角縁神獣鏡=魏鏡説」』の中で述べた。
要するに、その京大の先生の批判は、「鏡の面径の単なる測定値の違い(差)」と、「統計学の検定理論における有意差」との区別がわからないまま議論しているもので、統計学のごく初歩的な知識を欠いた議論で、話にならない。
率直に言って、京都大学の考古学でこの程度か」と思えるのである。
以上、シンポジウム登場者で、同じ畿内説の立場の人でも、寺沢薫氏、岡村秀典氏とでは、かなり重要な問題点について見解が異なっている事例を示した。
つぎに、岡村秀典氏の著作物の中にみられる記述間における「自己矛盾」の例を取り上げよう。これもかなり重要な論点の一つである。
■岡村氏の著作物に見られる記述間の「自己矛盾」
岡村氏は、考古学的遺物の「埋没年代」(埋納された年代)ではなく、「制作年代」(鏡の鋳造された年代)をもとにして年代を考えられる。
岡村秀典氏は、その著『三角縁神獣鏡の時代』(1999年、吉川弘文館刊)において、つぎのような図を示しておられる(上の図参照)
この図によれば、「漢鏡6期」の「制作年代」は、およそ西暦100年~160年ごろとなる。
そして、岡村秀典氏は『三角縁神獣鏡の時代』において、次のように記す。
「漢鏡6期は、簡略化した方格規矩(ほうかくきく)四神鏡・蝙蝠鈕座内行花文鏡(こうもりちゅうざないこうかもんきょう)、盤竜鏡(ばんりゅうきょう)、双頭竜文鏡(そうとうりゅうもんきょう)など径10センチ前後の小型鏡が流行した時期である。」
ここにあげられている「双頭竜文鏡」(「双頭竜鳳文鏡」ともいう)系の鏡に、「位至三公鏡」もまた、「漢鏡6期」の鏡とみなされることは、つぎのようなことからわかる
。
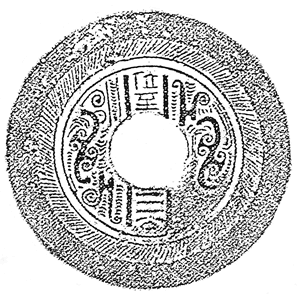 (1)『倭人と鏡』(第2分冊。1994年刊。埋蔵文化財研究会編集・発行)という本がでている。
(1)『倭人と鏡』(第2分冊。1994年刊。埋蔵文化財研究会編集・発行)という本がでている。
そこに、福岡県前原市大字井原の正恵(しょうえ)古墳群から出土したとされる「漢鏡6期」の「双頭竜文鏡」とされる鏡の写真(右図参照)をみればこれは、明確に「位至三公鏡」である。
(2)『倭人と鏡』では、香川県是行谷(これゆきだに)古墳群出土の「位至三公鏡」なども、「漢鏡6期」と記されている。
(3)銅に含まれている鉛の同位体比の分析によれば、「位至三公鏡」は、「双頭竜文鏡」(双頭竜鳳文鏡)や、「蝙蝠(こうもり)鈕座内行花文鏡(蝙蝠鈕座『長宜子孫』銘系内行花文鏡)」とほぼ同じ分布域の値を示している(下の図参照)。
なお、これらのくわしい測定値などは、拙著『邪馬台国は銅鐸王国へ東遷した』(2016年、勉誠出版刊)に示されている。
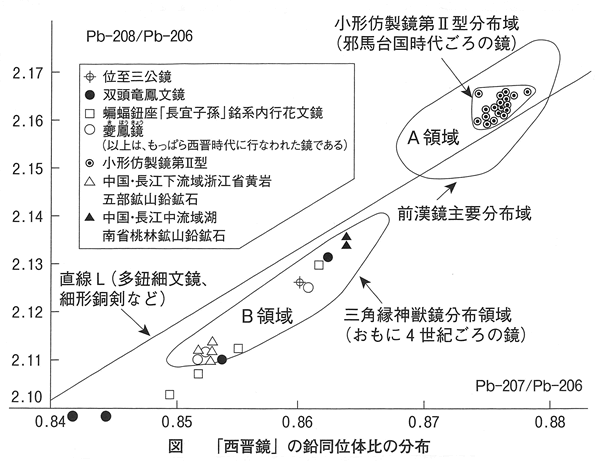
いっぽう、中国の洛陽付近出土の青銅鏡についての図録集に、中国で出版された『洛鏡銅華』(霍宏偉主編『洛鏡銅華』(2013年、中国・科学出版社刊)がある。
この図録集は、ほかならぬ岡村秀典氏の監訳で、『洛陽銅鏡』(2016年、科学出版社東京刊)と、題名をややかえ変更して日本語訳が出版されている。
『洛鏡銅華』には、「双頭竜文鏡」系の鏡が、すべてで13面紹介されている。その内わけは、次のとおりである。
(1)「位至三公鏡」 11面 「西晋」時代鏡
(2)「君宣」銘鏡 1面 「西晋」時代鏡
(3)「宜官」銘、双頭竜文系鏡 1面 「北朝」時代鏡
すべて「西晋」時代以後の鏡とされている。
「西晋」の国は。265年~316年のあいだ存在した国である。
岡村秀典説にしたがえば、これらの鏡は、西暦100年~160年ごろ「制作」され、西暦265年~316年ごろ埋没したことになる。その間100年以上のへだたりがある。岡村説は正しいのであろうか。
 『洛陽銅鏡』は、翻訳書で、原本が存在しているから、原本の記す年代、岡村氏も変更することができなかった。
『洛陽銅鏡』は、翻訳書で、原本が存在しているから、原本の記す年代、岡村氏も変更することができなかった。
そこから岡村秀典氏の関係する著作物の記す年代の間の「矛盾」が顔をのぞかせている。
・「洛陽晋墓」出土鏡
「洛陽晋墓の発掘(原題 洛陽晋墓的発掘)」[『考古学報』1957年第Ⅰ期(『洛陽考古集成』下巻、中国・北京図書館出版社、2007年刊、所収)]という報告書がある。
洛陽の晋代の墓、54基の発掘の結果をまとめたものである。
これらの墓からは、晋の太康八年(西暦287年)、元康九年(299年)、永寧二年(302年)の墓誌などが出土しているから確実に西晋時代に築造されたものである。
「洛陽西晋墓」から出土した鏡をまとめると上の表のようになる。
「位至三公鏡」は、8枚出土しており、最も多い。
この表を見れば、たしかに、漢代の鏡も出土している。
おのおのの家で持ち伝えられたものであろう。
岡村秀典氏、の学説に従えば、「位至三公鏡」8枚もまた、後漢代の西暦100年~160年に「制作」され百年以上伝世されて西晋代の265年~316年に「埋没」したことになる。
しかし、そのようなに考えると、西晋時代に築造された墓に、西晋代に「制作」された鏡が、ほとんど埋納されていなかったことになる。少し不自然ではないだろうか。
「位至三公鏡」は晋代に「制作」された可能性が大きいように見える。
さらに洛陽付近から出土した「位至三公鏡」について、すべてをまとめると下の表のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
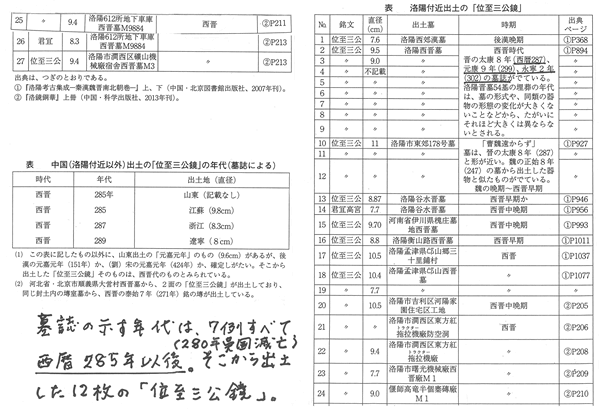
この表を見ると、後漢晩期(魏の時代にきわめて近い)出土のものが1枚ある。しかし、大部分は西晋時代に築造された墓から出土している。
そして、墓誌によって築造年代のわかる7例のすべてが西暦285年以後302年までの、西晋時代の築造年代であることを示している。
これも「位至三公鏡」が、墓の築造年代に近い時期に制作・鋳造されたものが多いことを示しているように見える。
さらに次のような事実がある。
上の方にある「西晋鏡」の鉛同位体比の分布の図をよくご覧になられよ。
わが国で出土した「位至三公鏡」「双頭竜文鏡」「蝙蝠(こうもり)鈕座内行花文鏡」「夔鳳鏡(きほうきょう)」などの鏡に、「三角縁神獣鏡」などに近い、長江(揚子江)中・下流域の「華中系」の銅が用いられている。
なぜ、洛陽など、黄河中・下流域の「華北」からおもに出土する「位至三公鏡」「蝙蝠鈕座内行花文鏡」系の鏡に、「華中系」の銅が用いられているのであろうか(下の図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)
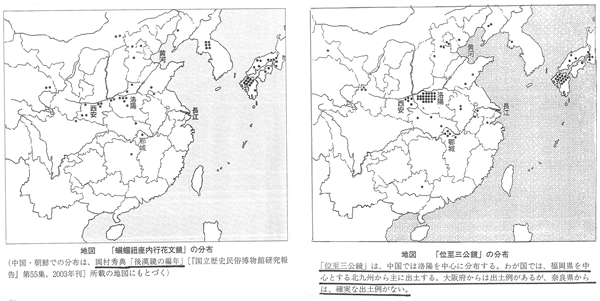
その理由としては以下のようなことが考えられる。
・魏や晋の時代、中国の北方では、銅材が不足していた。
このことについて、中国の考古学者、徐苹芳氏は、「三国・両晋・南北朝の銅鏡」(王仲殊他著『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年刊所収)という文章のなかで、つぎのようにのべている。
「漢代以降、中国の主な銅鉱はすべて南方の長江流域にありました。三国時代、中国は南北に分裂していたので、魏の領域内では銅材が不足し、銅鏡の鋳造はその影響を受けざるを得ませんでした。魏の銅鏡鋳造があまり振るわなかったことによって、新たに鉄鏡の鋳造がうながされたのです。数多くの出土例から見ますと、鉄鏡は、後漢の後期に初めて出現し、後漢末から魏の時代にかけてさらに流行しました。ただしそれは、地域的には北方に限られておりました。これらの鉄鏡はすべて夔鳳鏡(きほうきょう)に属し、金や銀で文様を象嵌(ぞうがん)しているものもあり、極めて華麗なものでした。『太平御覧』〔巻七一七〕所引の『魏武帝の雑物を上(のぼ)すの疏(そ)』[安本註。ここは「上(たてまつ)る疏(そ)」と訳すべきか]によると、曹操が後漢の献帝に贈った品物の中に。”金銀を象嵌した鉄鏡”が見えています。西晋時代にも鉄鏡は引き続き流行しました。洛陽の西晋墓出土の鉄鏡のその出土数は、位至三公鏡と内行花文鏡に次いで、三番目に位置しております。北京市順義、遼寧省の瀋陽、甘粛省の嘉峪関などの魏晋墓にも、すべて鉄鏡が副葬されていました。銅材の欠乏によって、鉄鏡が西晋時代の一時期に北方に極めて流行したということは、きわめて注目に値する事実です。」
西暦280年に、華北の洛陽に都する西晋の国は、華中・華南の長江流域に存在した呉の国を滅ぼす。
呉の都は、建業(南京)にあった。
その結果、華中・華南の銅が、華北に流れこみ、華北で、華中、華南の銅原料を用い、華北の文様をもつ青銅鏡がつくられるようになったとみられる。
西晋時代の「位至三公鏡」で、墓誌により年代の推定できるもの12面が、すべて、西暦285年以後に埋納されたものであることは、すでに、上の方にある”洛陽付近出土の「位至三公鏡」”や”中国(洛陽付近伊賀)出土の「位至三公鏡」の年代(墓誌による)”の表でみたところである。
つまり、文様が、北方系、銅原料が華中・華南系であることは、「西晋鏡」の大きな特徴である。
「西晋鏡」は、おもに西暦280年以後に鋳造された可能性が大きい。それが、わが国に流れこんでいる。
つまり、「位至三公鏡」などの鏡は、岡村秀典氏ののべるように、おもに後漢時代の西暦100年~160年ごろに「制作」鋳造されたものではなく、西暦280年以後の西晋時代に「制作」鋳造されたと見るべきである。
中国社会科学院考古研究所の所長をされた考古学者、徐苹芳氏はのべる。
「考古学的には、魏および西晋の時代、中国の北方で流行した銅鏡は明らかに、方格規矩鏡・内行花文鏡・獣首鏡・夔鳳(きほう)鏡・盤竜鏡・双頭竜鳳文鏡・位至三公(いしさんこう)鏡・鳥文鏡などです。
従って、邪馬台国が魏と西晋から獲得した銅鏡は、いま挙げた一連の銅鏡の範囲を越えるものではなかったと言えます。とりわけ方格規矩鏡・内行花文鏡・夔鳳鏡・獣首鏡・位至三公鏡、以下の五種類のものである可能性が強いのです。位至三公鏡は、魏の時代(220~265)に北方地域で新しく起こったものでして、西晋時代(265~316)に大層流行しましたが、呉と西晋時代の南方においては、さほど流行してはいなかったのです。日本で出土する位至三公鏡は、その型式と文様からして、魏と西晋時代に北方で流行した位至三公鏡と同じですから、これは魏と西晋の時代に中国の北方からしか輸出できなかったものと考えられます。」(『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年刊)
「魏の時代にはいわゆる『位至三公鏡』が新たに出現しております。これは後漢の双頭竜鳳文鏡から変化してできたもので、西晋時代になって特に流行しました。ちなみに、洛陽の西晋時代の墓から出土した沢山の銅鏡のうち、三分の一がこの位至三公鏡でして、数量ではベストワンです。西晋の墓からは、そのほか様々な銅鏡が出土していますが、例えば内行花文鏡・変形獣首鏡・夔鳳(きほう)鏡・方格規矩鏡・盤竜鏡などは、魏の時代の銅鏡と何ら違いはありません。また洛陽を中心としてその周辺の地点、例えば河南省の陝(せん)県・鄭州市・安陽市・焦作(しょうさく)市・また陜西省の西安などで行なわれた調査発掘の成果によりますと、後漢の末期から魏晋時代にかけての墓から出土します銅鏡は、洛陽出土のものと何ら変わるところがありません。」(以上、『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年刊)
「曹魏(三国の魏)の時代になって尚方工官は回復し、『右尚方』が銅鏡の製作を担当した。鋳造された銅鏡の様式は、すべて後漢以来の旧式鏡で、方格規矩鏡・内行花文鏡・獣首鏡・夔鳳鏡・盤竜鏡・双頭竜鳳文鏡などである。曹魏の時に新しく登場した『位至三公』鏡の花紋は、後漢の双頭竜鳳文鏡を踏襲したものである。西晋の時、この『位至三公』鏡は特に流行した。」(「三国、両晋、南北朝の銅鏡」『三角縁神獣鏡の謎』全日空、1984年刊)
さきの「洛陽晋墓」から発掘された鏡については、大阪府教育委員会の西川寿勝氏は、『三角縁神獣鏡と卑弥呼の鏡』(学生社、2000年刊)のなかで、つぎのようにのべている。「中国では蝙蝠鈕座連弧文(こうもりちゅうざれんこもん)鏡や通称『位至三公(いしさんこう)』鏡とよばれる双頭竜文鏡(そうとうりゅうもん)鏡の小型鏡が三国時代以降も引き続いて製作され広く分布している。『位至三公』鏡は、魏晋(ぎしん)代に都があった洛陽(らくよう)市で発掘された洛陽晋墓五十四基中、主流となる鏡式である。」
岡村秀典氏は「三角縁神獣鏡」を、3世紀の魏の時代、卑弥呼の時代の鏡としたため、「三角縁神獣鏡」よりも古い土器年代の地層から出土している「位至三公鏡」などのを、魏の時代よりもまえの後漢時代の2世紀(西暦100年~160年)に「制作」鋳造されたものとすることになった。
しかし、じっさいは、「位至三公鏡」などは、おもに、西晋時代(西暦265年~316年)に「制作」鋳造したものと考えられる。
そう考えなければ、なぜ「位至三公鏡」などの銅原料として、長江流域の銅が用いられているのか説明できない。
このように考えることを裏づけるさらに別のデータが存在する。
上の方にある「西晋鏡」の鉛同位体比の分布の図をご覧いただきたい。
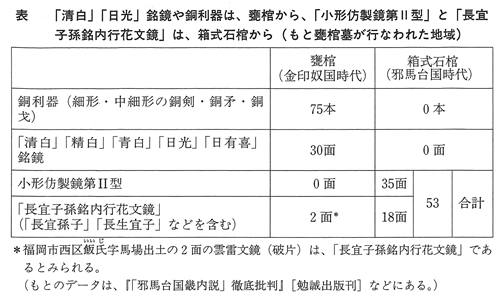
また、小型の仿製鏡について、考古学者森浩一氏はつぎのようにのべる。
「『長宜子孫』(長く子孫によろし)という銘を書きました内行花文鏡が後漢の後半の代表的な鏡ですが、それが北九州での三世紀ごろと推定される墓から点々と出ております。しかし、中国鏡だけではとても、すでに広がりつつあった鏡に対する愛好の風習はまかないきれないとみえまして、北九州の社会では、(中略)邪馬台国がどこかにあった時代に、直径が8センチ前後の小型の銅鏡を多量に鋳造しています」
上図の"「清白」「日光」銘鏡や銅利器は、甕棺から、「小型仿製鏡第Ⅱ型」と「長宜子銘内行花文鏡」は、箱式石棺から(もと甕棺が行われた地域)"を参照すると、小形仿製鏡第Ⅱ型がこの鏡に相当する。
そして、小形仿製鏡第Ⅱ型は甕棺からは出土せず、箱式石棺から出土する。
箱式石棺は邪馬台国時代と考えられるので、小形仿製鏡第Ⅱ型は邪馬台国時代の鏡であると考えられる。
これは、上の方にある「西晋鏡」の鉛同位体比の分布の図から、小形仿製鏡第Ⅱ型は前漢鏡の分布の領域であり、三角縁神獣鏡や位至三公鏡や夔鳳鏡や蝙蝠鈕座内行花文鏡などは別領域である。
三角縁神獣鏡が邪馬台国時代のものならば、銅材料として小形仿製鏡と混じりそうだが、そのような結果になっていない。この点からも三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡説が成り立たない。
・鏡が、わが国へ到達した2つのルート
蝙蝠鈕座内行花文鏡や位至三公鏡などは北中国ルート(下図参照)であった。
(下図はクリックすると大きくなります)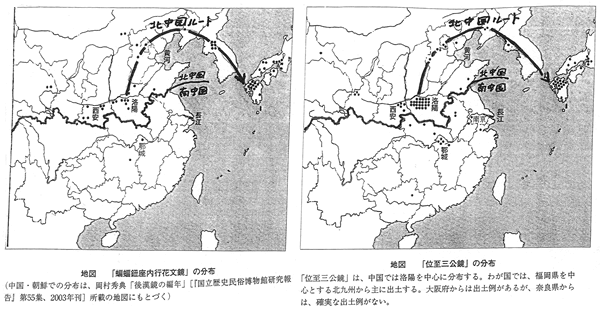
そして、青銅鏡の県別分布の中心が、北部九州の福岡県から近畿の奈良県へとうつる。
東晋の時代には南中国ルート(下図参照)になる。
(下図はクリックすると大きくなります)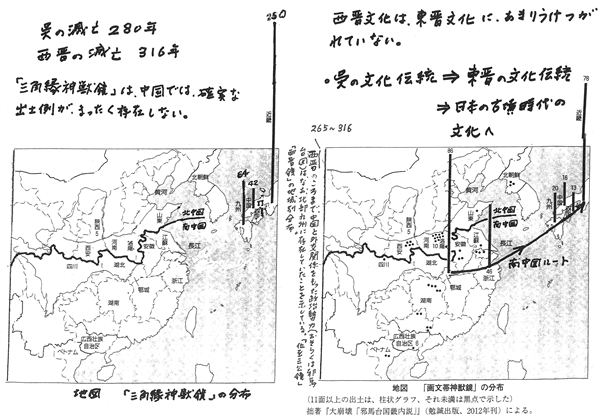
日本と国交をもった西晋の国のころまでの鏡などが、すべて福岡県を中心に分布することは、西晋の国のまえの魏の時代の邪馬台国が北部九州にあったことを強くさし示す。
そして西晋の国の存続期間は、西暦265年~316年である。
したがって、わが国において、鏡の世界での地殻大変動がおきたのは西晋の国の後の320~350年ごろとみられる。
■京都大学の伝統
京都大学においては、梅原末治、小林行雄、樋口隆康などの諸氏による鏡の研究についての伝統がある。
しかし、その伝統には、次のような問題点があると、私は思う。
(1)[目録作成主義の問題点]
1960~1970年代にかけて、アメリカの考古学者、ルイス・ビンフォード(Lewis Roberts Binford 1931~2011)は、「新考古学(ニュー・アーケオロジー new archaeology)」をといた。
ビンフォードはいう。
「従来の考古学は、資料を提供するだけで、科学的な学問とはいいがたい。考古学者は、埋蔵品の目録を作成するよりも、埋蔵品をもとに、古代文化を明らかにすることに、力をそそぐべきである。」(植木武氏ら訳『過去を探求する』雄山閣、2021年)
どこから、何が出土したかを、正確・詳細に記述し、目録を作成して行けば、おのずから過去が復元できる、ということにはならない。
古代を復元するためには、古代を復元するという明確な目標と、そのための「方法」とを、もたなければならない。
そうでないと、記録することじたいが目的になってしまう。
あるいは目録を作成しても、その目録によって、みずからが、あらかじめもっている「仮説」を裏づける事実だけを抽出して行くということになってしまう。
多額の費用をかけて発掘し、記録しても、おそろしく主観的な古代史像ができあがってしまう。古代史像を、「客観的に」復元するためには、それなりの「方法」が必要である。
以上のように、確率・統計学の立場からは、成立する余地がないとみられる議論が、考古学の分野では、大手をふって濶歩している。
論理や論証がなく、科学や学問の体(てい)をなしているとはいえない。
毎日新聞のスクープがなければ、偽旧石器が、今でも、教科書にのっているはずである。




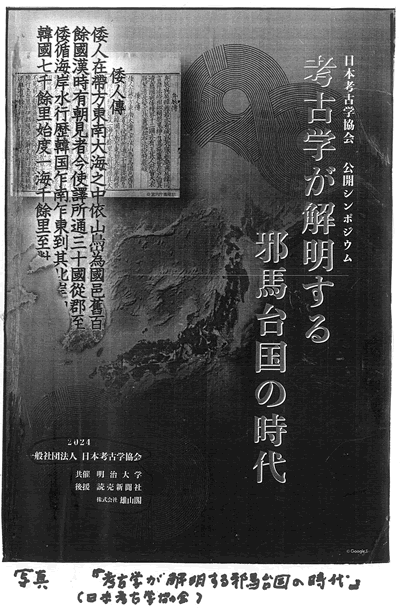 会員数は三千名から四千名を推移している。会員のおよそ7割程度は行政関係の発掘担当者(緊急調査などの発掘にあたる)であるといわれる。
会員数は三千名から四千名を推移している。会員のおよそ7割程度は行政関係の発掘担当者(緊急調査などの発掘にあたる)であるといわれる。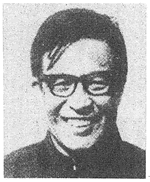 王仲殊氏は、かつて、私に、次のようなお手紙をくださったことがある。
王仲殊氏は、かつて、私に、次のようなお手紙をくださったことがある。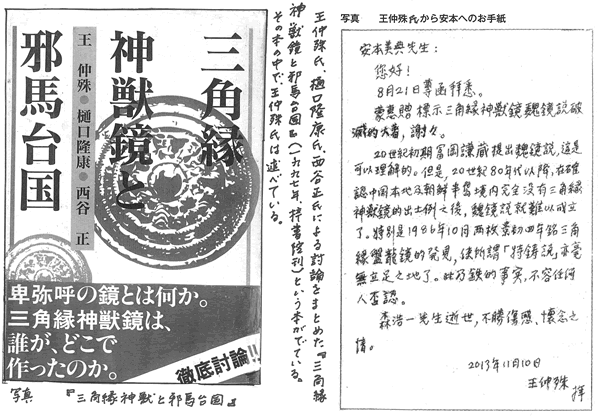
 しかし中国の魏王朝は、果たして銅鏡を外国のために特鋳する必要でもあったのでしょうか。また魏王朝は、他の外国の君主のために銅鏡を特鋳していないのに、なぜ倭の女王のためだけに特鋳したのでしょうか。かりに特鋳が行なわれたとしても、その際、見本がなくてはどうしようもないではありますまいか。中国の職人たちは、これまで中国において三角縁神獣鏡を鋳造したことがなかったのに、どうして邪馬台国の女王のためにこのような未曾有の銅鏡を特鋳することが出来ましょうか。つまり、特鋳説は不合理で、どうしても成立しない。わけても京都府大田南5号墳の青龍三年銘方格規矩四神鏡の出土は、魏王朝の賜わった『卑弥呼の鏡』が景初三年よりも前に製作されたことを証明したので、三角縁神獣鏡の特鋳説があくまで否定されてしまいます。」(青龍三年銘方格規矩四神鏡は上図参照)
しかし中国の魏王朝は、果たして銅鏡を外国のために特鋳する必要でもあったのでしょうか。また魏王朝は、他の外国の君主のために銅鏡を特鋳していないのに、なぜ倭の女王のためだけに特鋳したのでしょうか。かりに特鋳が行なわれたとしても、その際、見本がなくてはどうしようもないではありますまいか。中国の職人たちは、これまで中国において三角縁神獣鏡を鋳造したことがなかったのに、どうして邪馬台国の女王のためにこのような未曾有の銅鏡を特鋳することが出来ましょうか。つまり、特鋳説は不合理で、どうしても成立しない。わけても京都府大田南5号墳の青龍三年銘方格規矩四神鏡の出土は、魏王朝の賜わった『卑弥呼の鏡』が景初三年よりも前に製作されたことを証明したので、三角縁神獣鏡の特鋳説があくまで否定されてしまいます。」(青龍三年銘方格規矩四神鏡は上図参照) また、このような拙論に対し、京都大学の考古学者のある先生からの批判がみられるが、そのような批判に対する反批判も、『大炎上「三角縁神獣鏡=魏鏡説」』の中で述べた。
また、このような拙論に対し、京都大学の考古学者のある先生からの批判がみられるが、そのような批判に対する反批判も、『大炎上「三角縁神獣鏡=魏鏡説」』の中で述べた。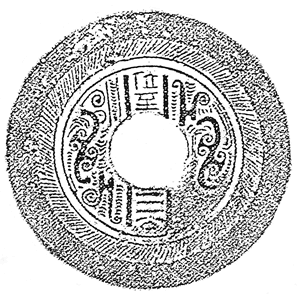 (1)『倭人と鏡』(第2分冊。1994年刊。埋蔵文化財研究会編集・発行)という本がでている。
(1)『倭人と鏡』(第2分冊。1994年刊。埋蔵文化財研究会編集・発行)という本がでている。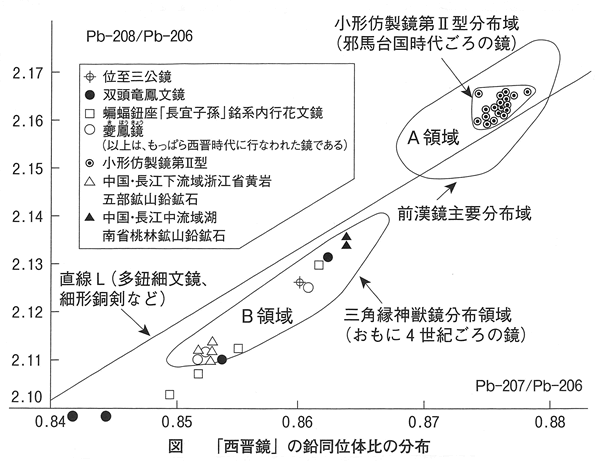
 『洛陽銅鏡』は、翻訳書で、原本が存在しているから、原本の記す年代、岡村氏も変更することができなかった。
『洛陽銅鏡』は、翻訳書で、原本が存在しているから、原本の記す年代、岡村氏も変更することができなかった。