この本は、誤読・誤訳・勝手読みのオンパレードである。
2018年度のノーベル賞受賞者の、本庶佑(ほんじょたすく)氏はのべた。「教科書に書いてあることも、疑え。」と。邪馬台国問題においては、とくに、社会的権威のある人の書いた本や、社会的権威のある出版社から出た本なども、疑いながら読んだほうがよい。
この回では、そのようなトレーニングをしてみよう。
『鏡が語る古代史』という本がある。この本は、京都大学教授(現名誉教授)の書いた本である。岩波書店から新書版で刊行されている。おもに、青銅鏡にみえる「銘文」を読んだものである。しかし、その内容は、誤読、誤訳、勝手読みのオンパレードである。そして、明確なデータの「改ざん」例さえみられる。文部科学省の示す「研究不正」についてのガイドラインに、「捏造」「盗用」「改ざん」の三つがあげられている。つまり、この本は、「研究不正」の域に達している。
京都大学と、岩波書店の名が泣く。
なぜ、こんなことになるのか。
「三角縁神獣鏡=魏鏡説」に、こだわりすぎるから、このようなことになるのである。
[1]「盖(がい)」は、「蓋(きぬがさ)(衣笠)」であって、「金属」ではない
「青祥(せいしょう)」は、「吉祥なる金属」なのか?
『鏡が語る古代史』の奥付(おくづけ)の、著者の紹介に、つぎのように記されている。
「岡村秀典(おかむらひでのり)
1957年生、京都大学文学部卒業、文学博士。京都大学助手、九州大学助教授を経て、
現在:京都大学人文(じんぶん)科学研究所教授、東アジア人文情報学研究センター長
専攻:中国考古学
著書:『三角縁神獣鏡の時代』(吉川弘文館、1999)
『夏王朝』(講談社、2003)
『中国古代王権と祭祀』(学生社、2005)
『中国文明』(京都大学学術出版会、2008)
『雲岡石窟の考古学』(臨川書店、2017)ほか」
岡村秀典氏は、北京大学への留学もされた方である。京都大学で、文学博士の学位もとっておられる。
立派な経歴である。
そして、この本『鏡が語る古代史』は、学術出版社の代表格ともいえる岩波書店から、新書の形で出されている。
にもかかわらず、この本は、誤読、誤訳、勝手読みの氾濫といってよい。これは、どうしたことか。
さっそく、例をあげることからはじめよう。
この本では、非常に多くの鏡の銘文の訳が示されている。
この本の79~80ページに、つぎのような文かある。(傍線を引いたのは安本。)
「岐阜県城塚(しろづか)古墳の出土と伝える『尚方作』獣帯鏡(五島美術館蔵)が制作された。径20センチ、「永平七年」鏡と同じように四神を含む七体の瑞獣が内区にあらわされている。その銘文は整った七言八句で、次のようにいう。
尚方作竟大毋傷。 尚方(しょうほう)鏡(かがみ)を作(つく)るに、大(おお)いに傷(きず)なし。
巧工刻之成文章。 巧(たくみ)なる工(こう)は之(こ)れを刻(きざ)み、文章(ぶんしょう)を成(な)す。
左龍右乕辟不羊。 左龍(さりゅう)と右虎(うこ)は不祥(ふしょう)を辟(しりぞ)く。
朱鳥玄武順陰陽。 朱鳥(しゅちょう)と玄武(げんぶ)は陰陽(いんよう)を順(ととの)う。
子孫備具居中央。 子孫(しそん)備具(びぐ)し、中央(ちゅうおう)に居(お)らん。
長保二親樂富昌。 長(なが)く二親(にしん)を保(たも)ち、楽(たの)しみ富(と)み昌(さか)えん。
壽敝金石如矦王。 寿(いのち)は金石(きんせき)とともに敝(つ)き 侯王(こうおう)の如(ごと)くあらん。
青盖爲志何巨央。 青盖(せいしょう)の志(こころざし)を為(な)すや、何(なん)ぞ央(つ)きん。」
「カールグレンが考証したように、その『盖』[安本注。「青盖(せいしょう)」の「盖」]は『羊』に「皿」を加えた字で、『祥(しょう)』の仮借(かしゃ)であり、『青祥』は緑色の吉祥なる金属をいう。有志鏡工たちは『青盖』を雅号とするグループを 『尚方』工房の中に立ちあげ、「尚方作」の本鏡を試作したのである。」
この『青盖(せいしょう)』の読みと意昧とは正しいのか?
岡村秀典氏は、「青盖」は「青祥」で、「青祥」は「緑色の吉祥なる金属」と記す。
ところが、辞書を引いてみると、「青祥」という語には、「吉祥」的な意味がのっていないのである。「災禍を予兆するもの」「わざわい」というような意味しかのっていない。
現在、世界最大の漢字の辞書は、韓国で出されている『漢韓大辞典』(檀国大学校付設東洋学研究所編、檀国大学校出版部刊)である。それにつぐ世界最大級の漢字の辞書としては、中国で出されている『漢語大詞典』(漢語大詞典出版会刊)や、わが国で出されている『大漢和辞典』(諸橋轍次著、大修館書店刊)などがある。
これらの辞書には、「青祥(青祥)」という成句がのっている。
意味は、『漢韓大辞典』『漢語大詞典』は、「青眚(せいせい)」のことであるとする。『大漢和辞典』は、[木神のわざわい]と記す。
「青眚」をさらに引いてみる。すると、「青色の物によって生みだされる(もので、)災禍をよく予兆する(あらかじめ知らせる)怪異現象をさす。」などとある。
『漢韓大辞典』は、「青祥」の項で、『隋書』の「五行志上」の、つぎの文を紹介している。
「陳の国の禎明(ていめい)二年(588)四月群(むれ)なす鼠(ねずみ)が無数であった。蔡州(さいしゅう)[現在の河南省]の岸から石頭(地名)の淮水(わいすい)[川の名]に入る。青塘(せいとう)[青々と草の生えた堤(つつみ)の意味か]の両岸にいたる。数日にして死ぬ。流れにしたがって江に出た。青祥にあてはまる。」
また、『漢韓大辞典』は、「青眚」の項で、『新唐書』の『五行志一』の、つぎの文を紹介している。
「篋中(きょうちゅう)[はこの中]の薬が、化して、蠅(はえ)数万となり、飛び去った。化して蠅となるは、敗北の象(しるし)である。青眚にあてはまる。」
このようなものが、「吉祥」であったり、グループの「雅号」などになりうるであろうか。
『大漢和辞典』には、つぎのようにある。
「眚(せい)」については、「災(わざわ)い」「ふいに生じる災い」「疫病の流行など」とある。
「青眚(せいせい)」については、「貌(ぼう)[外にあらわれる姿]を恭(うやうや)しくしないためにおこるわざわい。」とある。
いずれも、良(よ)い意味はない。
どこで、岡村氏は、誤りをおかしているのであろうか。ここには、何重もの誤りが重なっているのである。
(1)岡村氏は、「祥」をかならず、「吉(よ)いきざし」の意味をさすものとしてしまっている。しかし、「祥」は、「吉(よ)いきざし」のみをさすとはかぎらない。「悪いきざし」もさす。たとえば、藤堂明保編「学研 漢和大辞典」では、『春秋左氏伝(しゅんじゅうさしでん)』の「これなんの祥(きざし)ぞや、吉凶いづくに在(あ)りや」の文を引き、「祥」を、「吉凶にかかわらず、神の意向や、今後の運勢があらわれたもの。」と説明している。「吉祥」もあれば、「凶祥」もあるわけである。
(2)岡村秀典氏は、さきの文章で、「盖」は、「祥」の「仮借」であるとのべる。
しかし、「盖」は、「祥」の「仮借」であろうか。「仮借」とは、漢字を、その成り立ちによって分類したものの一つである。
辞書類は、「仮借」を、つぎのように説明する。
「ある意味を表わす漢字がない場合、意味は違うが同じ発音の既成の漢字を借用する方法。
たとえば、供物を盛る祭器を意味する『豆』という文字を、同音の植物を表わす文字に借用するようなもの。」(『日本国語大辞典』[小学館刊])
「ぎざぎざの刃のついた戈(ほこ)を描いた我(が)という字を、一人称の代名詞の『ガ』に当てるように同音の当て字のことである。」(『学研漢和大辞典』「学習研究社刊」)
このように、「仮借」とは、「同音」の他の字を借用することである。
ところが、「盖」と「祥」とは、そもそも同音ではない。
『学研漢和大辞典』によるとき、「盖」は、「蓋」の異体字である。その中国音は、つぎの二種のようになっている。
(a)kab(上古音)-kai(中古音)
(b)ɧap(上古音)-ɧap(中古音)
ただし、「ɧa」は「ガ」に近い音である。
「祥(祥)」の字の音は、つぎのようになっている。
giaŋ(上古音)-(yiaŋ)-ziaŋ(中古音)
わが国の漢字音の漢音(唐代の長安音にもとづく)でも、「蓋(盖)」は、「カイ、コウ(カフ)」の音、「祥(?)」は、「ショウ(シャウ)」で、音が異なる。(「蓋」「盖」を、[ガイ]と読むのは、慣用音による読み。)「盖」と「祥」とは、そもそも、同音ではない。したがって、「仮借」とはいえない。
たんに、「盖」も「祥」も、省略した字として、「羊」の字に書かれることがあるという関係にある。
(3)[盖]は、たしかに「羊」に略されることがある。「祥」も、たしかに、「羊」に略されることがある。
だからといって、「盖」が直接「祥」になったり、「祥」が「盖」になったりするわけではない。「盖」と「祥」とは、別の字である。「盖」と「祥」とが直接通じるというのなら、せめて、そのように使用されている事例をあげなければならない。「盖」は、「漢語大詞典」は、①に、「蓋」と同じ、と記し、②に、「蓋」の字の簡化字(簡体字)である、としている。「蓋」は、ふつう「ガイ」と読み、「ふた」や「かさ」をさす。さらには、「きぬがさ(貴人にさしかざすかさ)」や「天蓋」などをさす。
「岡村秀典」氏を、「典ちゃん」と略す人がいるかもしれない。「安本美典」のことも、「典ちゃん」と略す人がいるかもしれない。しかし、だからといって「安本美典」が、 「岡本秀典」氏をさすことになるわけではない。
たとえば、藤原鶴来編「書源」(二玄社、1970刊)で、「蓋」の字を引けば、下図のようになっている。
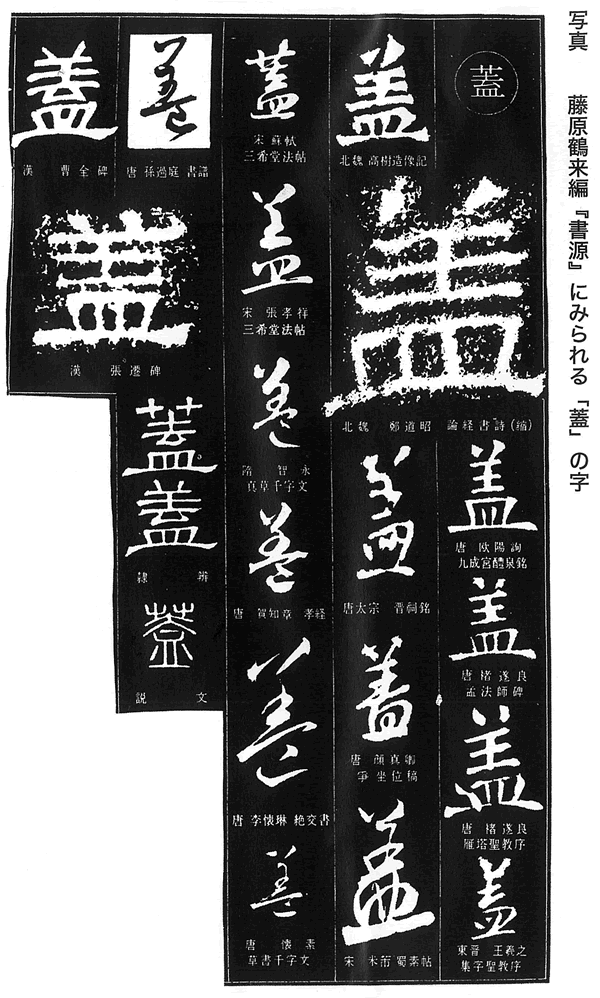
そこには、各時代の「蓋(盖)」の字がみられるが、ここには、「祥」の字はない。
(4)辞書には、「青蓋(せいがい)」という熟語が、「青祥(せいしょう)」とは、別にのっている。「青盖(せいがい)」は、「青蓋(せいがい)」の意味にとるべきである。「青祥」の意味にとるべきではない。
諸橋轍次の『大漢和辞典』で、「青蓋」を引くと、「漢制(漢の制度で)、王の車に用いる青色のおおい。青蓋車を見よ。」とある。
「青蓋車」を引くと、「青色のおおいのある車。古く、皇太子・皇子または王の乗用としたもの。」とある。
「漢語大詞典」で、「青蓋」を引くと、「青色の車蓋。漢の制度で、皇太子や皇子の乗る車。」とある。また、「かりに、帝王を指す。」とも記されている。
貴人に、「蓋(きぬがさ)」をさしかける制度は、古く中国にはじまり、朝鮮半島、そしてわが国を蓋(おお)った風俗文化であった。
『漢韓大辞典』の「青蓋」の項には、『後漢書』の「輿服志(よふくし)[乗りものと冠服の制度などを記す]」、『晋書』の「輿服志」、『文選』などをはじめとする中国の諸文献にみられる「青蓋」の語の使用例が、数多く示されている。
そして、『漢韓大辞典』には、下図にみられるような、「青蓋」の図ものっている。
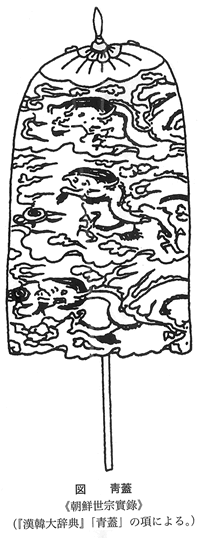 「青蓋車」ということばは、わが国の『日本書紀』のなかにも、二回でてくる。
「青蓋車」ということばは、わが国の『日本書紀』のなかにも、二回でてくる。
一つは、「清寧天皇紀」にでてくるものである。いま一つは、「顕宗天皇紀」にでてくるものである。
いずれも、のちの顕宗天皇と仁賢天皇とが、皇子時代に、「青蓋車」で、宮中にむかえいれられたという記事である。
この『日本書紀』の「青蓋車」を、小学館刊の「日本古典文学全集」本は、「青蓋車(あおききぬがさのみくるま)」と読み、岩波書店刊の「日本古典文学大系」本は、「青蓋車(みくるま)」と読んでいる。
そして、いずれも、『後漢書』の「霊帝紀」のなかにみえる「青蓋車」の使用例を示す。
そして、岩波書店刊の「日本古典大系」本は、「青色のおおいのある車。中国で皇子の乗る車をいう。」という説明をつけている。
『万葉集』の4204番の歌にも、「青盖(あおきぬがさ)」という語がでてくる。
「大伴家持(おおとものやかもち)の君が高くかかげておられるホオガシワの枝は、青い蓋(きぬがさ)に似ていますね」、という意味の歌である。皇子のように見えますよ、という歌である。
(5)また、「冠蓋」ということばがある。
「冠蓋」は、「きぬがさ」を用いることを許された高い地位、とくに、位階を示す。
『続日本紀(しょくにほんぎ)』の「文武天皇(もんむてんのう)紀」の慶雲(けいうん)三年(706)二月十六日の天皇の詔(みことのり)のなかに、つぎのことばがある。
「四位は飛蓋(ひがい)の貴(たふと)きあり、五位は冠蓋(かんがい)の重きなし。」
「飛蓋」「冠蓋」は、いずれも、「蓋(きぬがさ)」をさす。文武天皇の勅は、有蓋の四位と、無蓋の五位とに、処遇の違いをもうけるべきことをのべている。これは、『律令』の「儀制令」15には、一位から四位までの「蓋(きぬがさ)」についての規定があるが、五位については、「蓋」の規定がないことにもとづくものである。
そして、中国の山東省から出土した後漢時代の西暦133年にあたる年(陽嘉二年)に刻された石碑「陽嘉残碑」に、「冠盖」の文字がみえる(下図の、最末行の頭)。この「冠盖」の「盖」の字が、「蓋」ではなく、「盖」になっていることに注意。これは、もちろん、「冠盖(かんしょう)」などとは読めない。
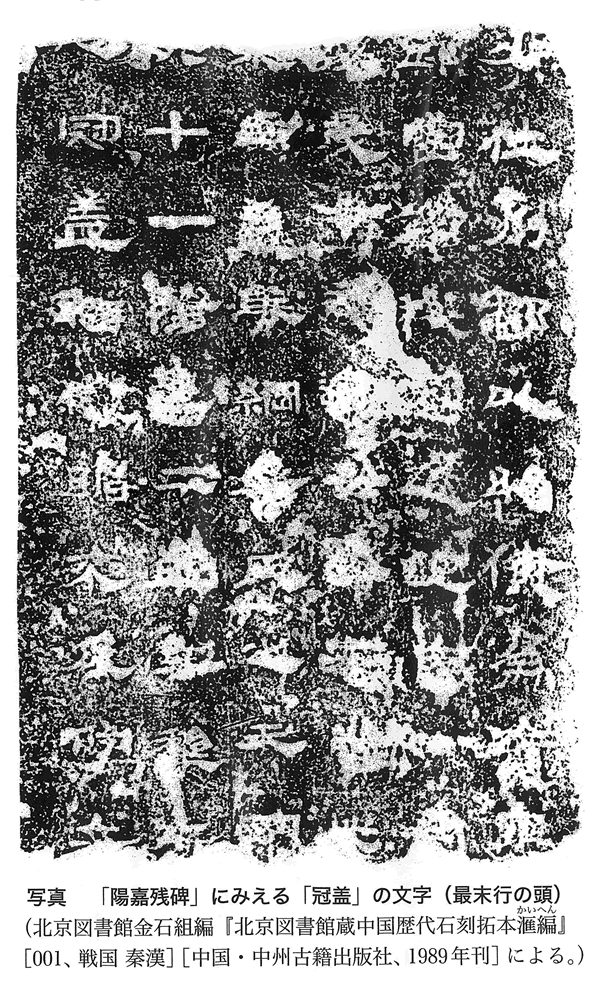
『万葉集』の240番の柿本人麻呂の歌に、「我(わ)が大君(おおきみ)は盖(きぬがさ)にせり」という表現がでてくる。
この歌の「盖」の字は、テキスト(写本)によって異同があるが、「蓋」よりも「盖」の字にしているテキストが多い。
岡村秀典氏の、「青盖」は、「青祥」で、「緑色の吉祥なる金属」などというのは、まったく初歩的な誤りとみられる。
(6)駒沢大学の教授であった三木太郎氏は、「青羊作」という鏡の銘に関連し、つぎのようにのべる。(傍線は、安本。)
「『青羊』の『羊』が『蓋』の省画体であることは、各種『青蓋』鏡と『青羊』鏡を比較すれば、瞭然である。」
「では、『青羊』が『青蓋』と同一だとして、どういう意味になるのであろう。『古鏡拓影』解説は、『青蓋』を『まさに人の姓名であろう』と推測し、根拠として「鄭樵の『通志』では青氏は名をもって氏となしたもので(注では古の天子名とある)、あるいは青陽氏の後という。晋の趙襄子の参乗の青荓(せいけん)が予譲の友であると『呂氏春秋』にみえている」と記す。しかし、『青盖陳尹(ちんいん)作竟(=鏡)(青蓋の陳尹が作る鏡)』『青羊畢少郎作(青蓋の畢少郎が作る)』などの事例は、人名説と相入れない。とすれば『青蓋』が、皇太子や皇子の乗る車に用いる青色のおおいを意味し、転じて『故に王を青蓋車と曰(い)う』(『後漢書』志第二十九『輿服(よふく)』上)とあることから推せば、王の機関のことか、との推量を可能にする。・・・・・(下略)」(『古鏡銘文集成』新人物往来社、1998年刊)
また、宮崎公立大学の教授であった奥野正男氏は、つぎのようにのべる。
「『青蓋』とは漢代天子の車にかける青色の覆いである。転じて天子の意とされるから、意味としては『尚方作』と同じであろう。」(『邪馬台国の鏡』梓書院2011年刊。205ページ)
(7)岡山県都窪郡山手村宿の寺山古墳から出土した盤竜鏡では、「黄羊作竟」の銘がある。「黄羊」についても、三木太郎氏は、「王室の一機関と推定できる。」とする。
「黄蓋」という熟語も、辞書類にのっている。
『漢語大詞典』には、つぎのようにある。
「黄色の傘(かさ)、あるいは、黄色の車蓋。つねに、皇帝の車駕をさすのに用いる。」「大漢和辞典」にも、「黄色のかさ」とある。
(8)さらに、「三羊作鏡」という銘のある鏡もある。「三蓋」という熟語も、辞書にのっている。
諸橋轍次氏の「大漢和辞典」では、「三蓋」の項に、「三つのおおい。三蓋車を見よ。」とある。「三蓋車」の項では、「漢代の車の名。三蓋(三層の傘)があるので名づける。天子親耕のとき{天子が、親(した)しく[あるいは、みずから]、農耕にたずさわるとき[天子が、民に農業をすすめる儀式のとき]}これに乗る。」とある。
天子が、農業の奨励のために、みずから農耕をする儀礼は、中国では、古くから行なわれた。
『礼記(らいき)』に、「みずからい帝籍(せき)[藉は、藉田(せきでん)のこと。藉田は、天子が、祖廟の祭りに用いる米を作る田のこと)を耕(たがやす)す」(「月令篇」)、「天子、藉をなすこと千畝(せんぽう)、みずから耒(らい)[すき]をとる」(祭義編)、「天子みずから南郊に耕す」(祭統篇)などとある。
『漢書』の「文帝紀」二年(紀元前179年)の条に「勧農の詔(みことのり)」がのっている。
そこに、つぎのようにある。
「藉田を開け。朕みずから、率先して耕す。」
「いま、ここに群臣を率い、みずから農(たがや)すことによって、勧(すす)める。」
三蓋車は、そのときにのる車である。
後漢の学者、蔡邕(さいよう)が、朝廷の制度について書いた『独断』という本がある。そこに、「古天子、諸侯、藉田のとき、三蓋車に乗る。」とある。
沈約(しんやく)の『宋書』の「礼志五」にも、「新耕藉田、三蓋車に乗る。」とある。
そして、『晋書』の「列伝第二十五」の「潘岳(はんがく)」(247~300)の伝や、梁の昭明太子の編集した文学書『文選(もんぜん)』に、潘岳の作った「藉田(せきでん)の賦(ふ)」がのっている(「賦」は、リズミカルな美文)。
「藉田の賦」は、晋の武帝(司馬炎)が、泰始四年(268)に、藉田の儀礼を行なったさいに、潘岳が、晋の国の徳をたたえて作ったものである。
そこでは、天子の車について記したところに、つぎのようにある。
「天子すなわち玉輦(ぎょくれん)に御(ぎょ)し、華蓋(かがい)に陰(かく)る[天子は、玉飾りのある車に乗られ、華(はな)もようのある蓋(かさ)にかくれられている]。」
「三蓋車」の「蓋(かさ)」は、華もようのあったことが、うかがえる。
なお、「藉田の賦」は、づぎのような文ではじまる。
「晋(しん)の時代の四年[泰始四年(268)正月丁亥(ていがい)の日(十九日。現在のグレゴリオ暦の二月十九日)、皇帝陛下は、みずから、公卿(こうけい)百官をひきい、洛陽郊外にある千畝(せんぼう)の田をたがやされた。これは、いにしえの礼にしたがうものである。」
(9)「青蓋」などを金属とする説は、スウェーデンの中国語学者のカールグレンが、いまから八十年以上まえの、1934年に発表した論文で、説いた説である。(Bernhard Karlgren, "Early Chinese Mirror Inscriptions", Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, No.6, 1934.)
岡村秀典氏の説は、それによっている。
いっぽう、中国の考古学者、王仲殊は、カールグレンの説を批判し、その説が、「いっそう人をして、まよいわからなくさせてしまった。」とのべる。
そして、王仲殊は、「青羊」は、鏡職人(鏡工、鏡師)であるとする。[王仲殊著『三角縁神獣鏡』(学生社、1992年刊)168ページ、「『青羊』とは」参照。]
考古学者の近藤喬一(たかいち)氏は、カールグレンや王仲殊の見解を検討したうえで、「青盖を名のる工匠名家」と記す。[近藤喬一「西晋の鏡」(『国立歴史民俗博物館研究報告第55集』、国立歴史民俗博物館、1993年刊、所収)]
近藤喬一氏は、つぎのようにのべる。(傍線をひいたのは、安本。)
「後漢代、尚方工官と同じく、青盖も青蓋車が皇太子及び皇子の乗る母衣(ほろ)(車につけるおおい)青く輪の朱色の車といわれるように特殊な意味をもつことを重視するなら、本来は彼等に奉仕する工人グループから出たもので、河南洛陽・陝西(せんせい)長安の首都や副都に置かれた。」
岡村秀典氏は、八十年以上まえに提出されたカールグレンの説による。すでに、その説にはいくつも異論がでていても、無頓着で、ひとつひとつの言葉や、説について、みずからきちんと辞書、文献にあたって、調べ、チェックしてみようとしていない。カールグレン以後、良質の辞書類も刊行され、種々の情報検索機能も、とくに最近では、格段にアップしているのに。
カールグレンの説は、思いつき的な説で、広く文献・資料にあたってたてた説とはいえない。
「青蓋」「青羊」「黄羊」「三羊」などは、王室の機関名に由来するとみられる。
「呂氏」「張氏」「田氏」などのような「氏」がついていないことは、「青蓋」などが職人の個人名ではないことを思わせる。
「青蓋」「黄蓋」「三蓋」は、いずれも、たがいに関連する意味をもつ。熟語として、いずれも、辞書にのっている。
以上から、「青蓋」「黄蓋」「三蓋」は、およそ、つぎのような意味内容をもつものと判断される。
「天子の御物(ぎょぶつ)[もちもの]を作ることをつかさどった役所に、『尚方(しょうほう)』があった。
『青蓋(せいがい)』『黄蓋(こうがい)』『三蓋(さんがい)』は、本来、『尚方』のなかの、つぎのような鏡工(鏡職人、鏡作り師)などの、グループ名に由来するとみられる。
(1)[青蓋(せいがい)]おもに、皇太子や王族のもちものの製作を担当したグル-プ。
(2)[黄蓋(こうがい)]おもに、皇帝のもちものの製作を担当したグループ。
(3)[三蓋(さんがい)]おもに、天子が、親しく農耕にでかけるときのもちものの製作を担当したグル-プ。」
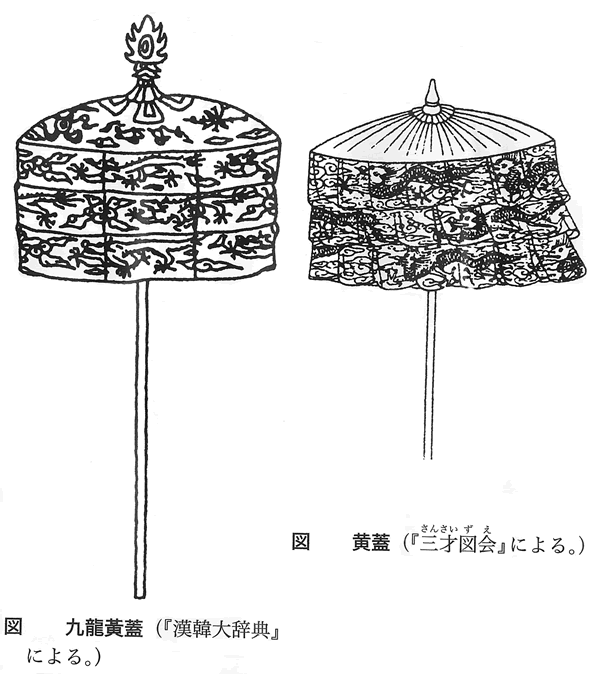
『時代別国語大辞典 上代編』(三省堂刊)にのせられている「きぬがさ(蓋)」の説明を、つぎに示しておく。この説明文のなかに、「身分によって色を変える」とあることに注意。
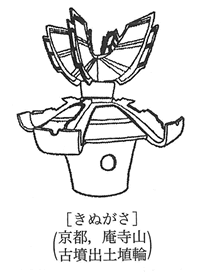 「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」
「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」
じじつ、わが国の『律令(りつりょう)』の「儀制令(ぎせいりょう)」では、「蓋(きぬがさ)」の色などについて、つぎのように定めている。
「凡(およ)そ蓋(きぬがさ)は、皇太子は、紫(むらさき)の表(うへ)、蘇方(すは)[赤紫色]の裏(うら)、頂(いただき)及び四角(しかく)[四隅(よすみ)]に、錦(にしき)を覆(おほ)ひて総垂(ふさた)れよ。親王は紫の大(おほ)き纈(ゆはた)[くくりぞめ。しぼりぞめ]。一位は深(ふか)き緑(みどり)。三位以上は紺(こむ)。四位は縹(はなだ)[うすい藍色]。四品以上及び一位は、頂(いただき)・角(すみ)に錦を覆ひて総(ふさ)垂れよ。二位以下は錦を覆へ。唯(ただ)し大納言以上は総(ふさ)垂れよ。並に朱(あか)き裹。総(ふさ)には同色(どうじき)用ゐよ。」

■岡村秀典氏の解釈
以上のような理解に対し、岡村秀典氏はのべる。
「六〇年代に有志の鏡工たちが立ちあげた『青盖』工房は、しばらく獣帯鏡や盤龍鏡の制作をリードしていた。しかし『池氏』や『杜氏』ら個人工房の作品と比べると、マンネリ化は否めなかったためか、七〇~八〇年代に『青盖』は『青羊(せいしょう)』『黄盖(こうしょう)』『三羊(さんしよう』などの小工房に分裂した。
「盖(しょう)」は「羊(よう)[=祥(しょう)]」の仮借(かしゃ)で『青』と『黄』は銅を象徴し、『三』は鏡の原料となる三種の金属をいうから、いずれも同系の吉祥語である。」
「蓋(きぬがさ)」と解すべきものを、「銅や金属をさす吉祥語」であるという。ほとんど話にならない誤訳というべきである。中国やわが国の古文献に、したしんでいない人の解釈としか思えない。
この解釈がよくないのは、つぎのようなことからいえる。
(1)「青祥」や「黄祥」という熟語があるが、いずれも、「吉祥句」とはいえない。「青祥」については、すでにみてきた。
「黄祥」という熟語については、『漢語大詞典』に、「災祥(わざわいのきざし)を、予示する黄色の物象。」「土の色の黄、黄眚(こうせい)、黄祥あり。」と記されている。「黄眚(こうせい)」の項に、「災異を予示する黄色の物象。」とある。
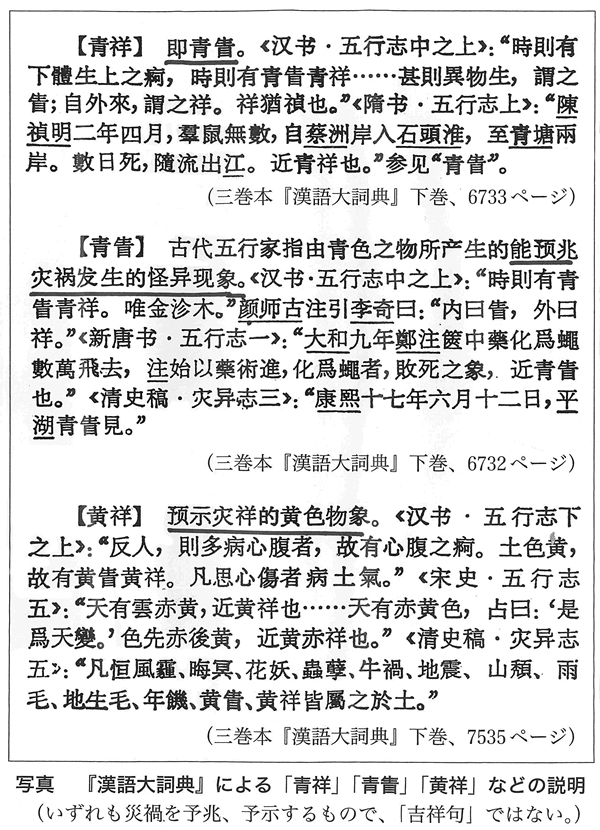
(2)「青蓋(せいがい)」「黄蓋(こうがい)」「三蓋(さんがい)」は、たがいに関連した意味をもつ熟語として、辞書にのっている。しかし、「青祥(せいしょう)」や「黄祥(こうしょう)」「三祥(さんしょう)」のほうは、「青祥」「黄祥」は、「わざわいのきざし」として辞書にのっているが、「三祥」という熟語は、辞書にのっていない。岡村氏の「三祥」の「三」は、「鏡の原料となる三種の金属をいう。」などは、岡村氏の想像的解釈というべきである。
総じて、岡村氏の訳読については、つぎのようなことがいえる。
(1)きちんと。一語一語辞書類をしらべることを行なっていない。
(2)中国や日本の古典での使用例にあたっていない。
(3)三木太郎や奥野正男氏、王仲殊、近藤喬一氏などの先人の説をきちんと参照していない。
以上のようにみてくると、岡村秀典氏の、つぎのような訳読や説明は、いずれも誤りとみられる。(傍線は安本。)
(1)「三羊宋氏作竟善有意。 三羊宋氏(さんしょうそうし)鏡を作るに、善(よ)き意(おもい)有(あ)り。
良時日家大富。 時日(じじつ)良(よ)ければ、家(いえ)は大(おお)いに富(と)まん。
宦至三公中常侍。
仕(つか)うれば三公(さんこう)・中常侍(ちゅうじょうじ)に至(いた)らん。
長宜(ママ)。 長(なが)く宜(よろ)し。」
「『宋氏』はつづいて『青羊』と合作し、「青羊宋氏作」画像鏡を制作する。その銘文はやや特殊だが、図像文様には『宋氏』の個性があらわれ、作鏡者は『宋氏』であったのだろう。『青盖』の分解に端を発する工房間の再編成は、『青盖陳氏』や『三羊宋氏』『青羊宋氏』のように作鏡者名から追跡できる合作のほかに、銘文としてはのこらない鏡工や工房の吸収合併も少なくなかったと思われる。」(以上、岡村氏の著書の、108ページ。)
ここにみられる「三羊(さんしょう)」「青羊」などは、「三蓋(さんがい)」「青蓋(せいがい)」などと読むべきものとみられる。
(2)「黄盖作竟甚有畏、 黄盖(こうしょう)鏡(かがみ)を作(つく)るに、甚(まこと)に威(おごそか)なり。
國壽無亟、下利二親。
国寿(こくじゅ)は極(きわ)まり無(な)く、下(しも)は二親(にしん)に利(よろ)し。
尭(ママ)賜女爲帝君。
尭(ぎょう)は女(むすめ)を賜(たま)い、帝君(ていくん)と為(な)す。
一母婦坐子九人。
一母婦坐(いちぼふざ)し、子(こ)は九人(くにん)
翠盖覆貴敬坐盧、 翠蓋(すいがい)は貴(き)を覆(おお)い、敬(つつし)みて盧(ろ)に坐(ざ)す。
東王父西王母哀萬民兮。
東王父(とうおうふ)・西王母(せいおうぼ)は万民(ばんみん)を哀(いつく)しむ。
作鏡者の『黄盖』は『黄祥(こうしょう)』の仮借であろう。淮派の『青盖』は一世紀末に『青羊』『黄羊』『三羊』など「盖(祥)』字の雅号を共有する小工房に分解したがその一部は四川に移って広漢派の周辺で盤龍鏡などを制作していた。『黄盖』や建寧(けんねい)二年(169)獣首鏡を制作した「三羊」は、その流れを引く小工房であろう。その鏡には広漢派と共通する文様が多ものの、『広漢西蜀』が四言の銘文を主に用いたのに対して、それらの鏡は七言を主とする銘文を用いたところに淮派の影響がのこっている。」(以上、岡村氏の著書の、157・158ページ。)
しかし、「黄盖」は、文字どおり、「黄盖(こうがい)」と読むべきであろう。
「黄盖(こうしょう)=黄祥(こうしょう)」と読んだのでは、すでにみたように、「災祥を予示する物象」(『漢語大詞典』)になってしまう。
そもそも同じ銘文のなかに「黄盖(こうしょう)」のほかに「翠盖(すいがい)」ということばが、銘文のなかで、あきらかに、「貴(とうとい人)を覆(おお)い」という形ででてくる。それなのに、「黄盖」のほうは、「こうがい」と読まずに、「こうしょう」と読むのは、不自然である。また、「青盖(せいがい)」「黄盖(こうがい)」「翠盖(すいがい)」のように、色を意味する「青(せい)」「黄(こう)」「翠(すい)」と、「かさ」を意味する「盖(蓋)」とが結びついているのである。したがって、これらは、いずれも、本来、貴人にさしかける「蓋(かさ、おおい)」であると、なぜ、統一的に理解しないのであろうか。
岡村秀典氏の本では、「青蓋」「黄蓋」「三蓋」の例にみられるように、小さな誤りが、たえまなくあり、全体的な結論も大きく誤っている。
[2]原文の改竄(かいざん)
『全唐文』の「銅鏡鉗文」について
別の例をあげよう。
岡村秀典氏は、『鏡が語る古代史』のなかで、『全唐文』という文献の一部を引用し、つぎのようにのべる(岡村氏の本の224ページ。つぎの引用文に傍線を引いたのは、安本)
「それから六〇〇年ほど経った唐の文宗(ぶんそう)(在位八二七~八四〇)のとき、朝廷では卑弥呼への下賜品が話題になった。相次ぐ戦乱によって唐王朝はいちじるしく衰退していたところに、チベットの吐蕃(とばん)国が馬を要求してきたのである。その対応をめぐって朝廷では激論が戦わされ、数多くの軍功をあげていた王茂元(おうもげん)「安木注。これは「王茂元(おうぼうげん)」とカナをふるべきである。なぜなら①「元」を、漢音の「ゲン」で読んでいる。「茂」の漢音は、「ボウ」である。②漢音は唐代の長安音を写したもの[『広辞苑』」である。)は次のように上奏した。
むかし魏は倭国に酬(むく)いるに銅鏡・紺文(こんぶん)に止(とど)め、漢は単于(ぜんう)に遺(おく)るに犀毘(せいび)・綺袷(きごう)に過ぎず、ともに一介の使もて将に万里の恩とす。(「奏吐蕃交馬事宜状」)
この原文は『魏』と『漢』、『倭国』と『単于』、『銅鏡』と『犀毘』、『紺文』と『綺袷』が対句になっている。魏が倭国に贈った『銅鏡』は『魏志』倭人伝にみえる『銅鏡百枚』、『紺文』は『紺地句文錦』ほか各種の絹織物を二字に省略したものであり、漢が匈奴に贈った『犀毘』は『史記』匈奴伝などにみえる黄金の帯金具、『綺袷』は『服繍(ふくしゅう)袷綺衣・長襦(ちょうじゅ)・錦袍(きんぽう)」など各種の絹織物を二字に縮約したものである。要するに、魏は倭王に対して銅鏡と絹織物を与え、漢は匈奴単子に対して帯金具と絹織物を贈ったが、万里のかなたにある蛮夷に対して、それ以上の厚遇は前例がない、と王茂元は論じたのである。」
これは『全唐文』684巻にのっている文章である。
ここに岡村氏が引用している「全唐文」の文章は、魏から卑弥呼に与えられた鏡に関連して、以前問題になったことがある。2011年7月に刊行された『季刊邪馬台国』110号でも、とりあげられている。そのことについては、あとでのべよう。
問題は、つぎのような点にある。岡村秀典氏が「全唐文」のなかの、「奏吐蕃交馬事宜状」として引用した文のなかにみえる「紺文(こんぶん)に止(とど)め」の「紺文(こんぶん)」が、『全唐文』の原文では、下の写真にみられるように、「紺文(こんぶん)」ではなく、「鉗文(けんぶん)」になっている。原文では、「金へん」の「鉗」になっているものを、岡村氏は、なんのことわりもなく、「糸へん」の「紺」に晝きかえている。その上で「魏志倭人伝」の「紺地句文錦」と結びつけているのである。勝手な書きあらためというべきである。岡村氏の本には、原文の写真などは示されていない。岡村氏の本だけを読む人には、そのように岡村氏によって書きかえが行なわれていることはわからない。
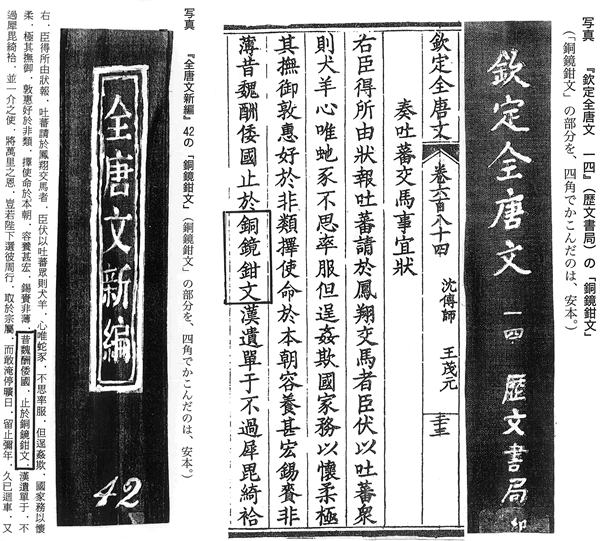
これって、データの改竄に近い。いや、データの改竄そのものではないだろうか。みずからの解釈に都合がよくなるように、原文そのものを、ことわりもなく書きかえているのであるから。
岡村秀典氏の本は、2017年の5月に刊行されている。同じ年の8月には、東大の分子細胞生物学研究所の教授らの論文に、改竄などのあったことが報じられている。その教授らが、アメリカの雑誌『サイエンス』にのせた論文は、撤回されることになり、教授の処分が行なわれた。
また、2019年の5月11日前後の新聞には、東洋英和女学院(東京)の院長が、岩波書店から出した本や、雑誌に掲載した論考で、実在しない神学者の論文を捏造して引用したことなどから、懲戒解雇されたことが、報じられている。
権威のある書店から、出された本や、権威ある大学の先生の発言などでも、うっかり信用してはならない。できるだけ、チェックをしながら読むべきである。
もちろん、この私の文章についても、そうである。
考古学の分野では、「事実」と「解釈」との、区別のついてない議論や発表が、あまりにも多い。
岡村秀典氏の「銅鑼紺文」なども、その類かも知れないが、ルーズを通りこして、「研究不正」の域に達している。このようなことが、邪馬台国論争などを、大きく混乱させている。
文字を、原文の「鉗(けん)」から「紺(こん)」へ書きあらためたのなら、そのように書きかえたことや、その理由を一言(ひとこと)のべるべきであろう。
たんに、原文の「鉗文(けんぶん)」は「紺文(こんぶん)」の誤字であると判断されたのか。それとも「鉗」は「甘」と省略されうるだろう、「紺」も「甘」と省略されうるだろう、よって、「鉗」は「紺」に等しいという論法によられているのか。(この論法は、すでに紹介した「盖」は「羊」に省略される、「祥」も「羊」に省略される、よって、「盖=祥」が成立する、という論法とほぼ同じである。さらには、「岡村秀典=安本美典説」も成立しそうな論法である。)
・「鉗」と「紺」とは、音が違う
「鉗」と「紺」とは、中国音が異なっている。「仮借(かしゃく)」も成立しそうにない。
「鉗」の中国音は、つぎのとおり(中国音は、藤堂明保編『学研漢和大字典』による。)
gɪam(上古音)-gɪεm(中古音)
「紺」の中国音は、つぎのとおり。
kәm(上古音)- kәm(中古音)
上の写真の右側にみえる「欽定」は、「君主の命による選定」(『広辞苑』)の意味である。「欽定」であるから、そうとう、ていねいに校正されているはずである。
また、上の写真の左側にみられるように、『全唐文』の他のテキストでも、この部分は、「鉗文」となっている。「紺文」の誤植の可能性は、低いようにみえる。
・「銅鏡鉗文」の意味は?
では、原文の「鉗文」が正しいとして、「銅鏡鉗文」は、どういう意味なのであろうか。
『全唐文』のこの部分の記事が最初に問題になったのは、2011年のことである。聖徳(せいとく)大学(千葉県)の山口博教授が、「三角縁神獣鏡=特注説」(「三角縁神獣鏡」は、魏が倭に贈るために、特別に注文してつくった鏡であるとする説)をとなえ、その根拠として、『全唐文』のこの記事をとりあげた。そして、その見解が『週刊新潮』の2011年の6月16日号に紹介された。
岡村秀典氏は、この山口博教授の見解に、ほぼしたがっているのである。
『季刊邪馬台国』の110号(2011年7月刊)において、この「鉗文」の意味について、私は、およそ、つぎのように論じている(今回、多少、加筆、訂正している)。
「『全唐文』のなかの『問題の記述』はつぎのようなものである。
〈昔、魏ハ倭国ニ酬(はなむけ)スルニ、銅鏡ハ鉗文(けんぶん)ニ止(とど)メ 漢ハ單干ニ遺(おく)ルニ犀毘綺袷(さいびきごう)ヲ過ゴサズ 並ビニ一介ノ使、将(まさ)ニ万里ノ恩トス〉
この文で、ややわかりにくいのは『鉗文(けんぶん)』ということばと、『犀毘綺袷(さいびきごう)』ということばである。
とくに重要なのは、『鉗文』の解釈である。これが、問題の核心である。(「犀毘綺袷」については、「コラムⅠ」参照。)『鉗文』について、山口博氏は、『これは倭国にとって禍々(まがまが)しい模様や銘文を刻むのをやめて、彼らの好むような銅鏡を作ってあげたと読める。いわば特注品を贈ったとあるわけです。』という。
----------------------------------------------------------------------------------------------
 コラムⅠ 「犀毘(さいび)」[帯鉤(たいこう)]と「綺袷(きごう)」
コラムⅠ 「犀毘(さいび)」[帯鉤(たいこう)]と「綺袷(きごう)」
犀毘(さいび)は、北方民族の、革帯(かわおび)の留め具である。犀の角でつくる。左の写真Aのボタン(左につきでたところ)を、裏(からだがわ)にして、革帯に固定させる。表(おもて)[ボタンと反対がわ]の、湾曲した鉤(かぎ)に、革帯の、もう一方の端についている写真Bのような、金属の鐶(かん)[輪]をはめる。[「犀毘(さいび)」の読みは、『大漢和辞典』による。岡村秀典氏の読みは、「犀毘(せいび)」。)
毘(び)は本来、「ヘソ」の意味である。
帯鉤は、中国では、戦国時代から用いられていた。
「綺袷(きごう)」の「綺」は、「いろいろの模様を織りだした絹織物、あやぎぬ」のことである。
「袷」は、「裏のついたきもり、あわせ」のことである。
--------------------------------------------------------------------------------------
ウーム。この解釈は正しいのであろうか。山口氏の独自の解釈というか、『特注説』を前提とした、いわば勝手な解釈のようにみえる。
『鉗(けん)』は『くびかせ、くびかせをつける、くつわをはめる』の意味である。
山口氏は、『くびかせ』は『禍々しい』ことなので、『鉗文』は『禍々しい模様や銘文』と解釈されたようである。しかし、これは『超訳』というか、連想訳というべきである。というよりも、ほとんど誤読といってよい。その理由を、すこしくわしくお話しよう。
『鉗』には『禍々しい』などという意味はない。原義どおりにとるべきで、『鉗文(けんぶん)ニ止(とど)メ』は『文(ぶん)を鉗(けん)するに止(とど)め』で『文様(もんよう)』や『銘文』にくびかせをつける、つまり、あるていどの制限、制約をつけるにとどめるほどの意味とみられる。
つまり、多少粗悪な鏡も、特に立派でない鏡も、大きな鏡も、小さな鏡も、とくべつに制約条件はつけず、あるものを(かき)集めて与えた、というほどの意味のようにうけとれる。
ちなみに、中国のばあい、日本と異なり、鏡が、一つの墓のなかから、まとまって出土することは、かなりまれである。死者生前の使用物をうずめたからである。
『洛陽焼溝漢墓(らくようしょうこうかんぼ)』のばあい、総数95基の墓から、118面の銅鏡が出土している。一つの墓からの出土は、1、2面ていどである。
「洛陽晋墓」のばあいは、総数54基の墓から、24面の銅鏡が出土している。
一度に100面の鏡を集めるのは、なかなか大変であったことを思わせる。
『全唐文』の文のなかには、酬(はなむけ)したこと、酬(むく)いたこと、つまり、贈ったとは書いてあっても、『作ってあげた』『特注品を贈った』ことなどは、書いてないのである。『特注説』という前提をもっていないかぎり、山口氏のようには読めない。
たとえば、江戸時代の本居宣長が、藤貞幹(とうていかん)[藤原貞幹]の論文『衝口発(しょうこうはつ)[口を衝(つ)いて発す』を批判した著名な論文に、『鉗狂人(けんきょうじん)』がある。『鉗狂人』という文献名は、『広辞苑』にも一項目としてのっている。これは、藤貞幹が『口を衝いて発す』といっているから、本居宣長は『自由に言葉を発することができないように、くつわ(口輪の意味)をはめる、制約する』といっているのである。「鉗口令(かんこうれい)」[このばあいの「鉗口(かんこう)」は「鉗口(けんこう)」の慣用読み]といえば、あることがらについて、他人(ひと)に話すことを禁ずる命令のことである。
『鉗狂人』を『禍々しい狂人』などと訳しては、たんに藤貞幹を罵倒していることになり、本居宣長の真意は伝わらない。
藤堂明保(とうどうあきやす)の『学研漢和大辞典』(学習研究社刊)をみても、『鉗』には、『くびかせ』『くつわ』のような名詞の意味や、『くびかせをかける』『くつわをはめる』のような動詞の意味はのっていても、『禍々しい』のような形容詞の意味はのっていない。
『鉗狂人』の『鉗』も『くつわをはめる』の、動詞の意味で用いられていることに注意。」
ここまでの議論で、うかがえるように、岡村秀典氏は、みずからが、文献や資料にあたってしらべて説を立てているわけではない。基本的には、カールグレンや山口博氏などの説の、うけうりなのである。八十年以上まえに提出された説や、週刊誌で騒がれた説のうけうりなのである。
カールグレンや山口博氏の説に対する批判などには、無頓着である。批判に対する再批判などは行なわれていない。
要するに、立証責任を、なにも果していない。
岡村氏のこのたびの本は、自説の宣伝のための本になっていても、自説の証明のための本にはなっていない。最近の京都大学は、このように安直に本を作っていれば、博士になり、教授がつとまるようになったのか。東洋史学者の内藤湖南や、中国文学者の吉川幸次郎が活躍していたころにくらべ、教授の質の、いちじるしい劣化がある。
・「出土」と「採集」
岡村秀典氏が、原文をことわりなく書きあらためている例を、いま一つあげておこう。
岡村秀典氏は、『鏡が語る古代史』の214ページで、つぎのようにのべる。(傍線を引いたのは安本。)
「三角縁神獣鏡の成立
日本の古墳から大量に出土する三角縁神獣鏡にも、二三九~二四〇年の魏の年号をもつ鏡がある。それも青龍二年鏡と同じように後漢鏡の模倣によって成立した。
そのうち景初(けいしょ)三年(二三九)『陳是(ちんし)[氏]作』に三角縁神獣鏡のモデルになったのは、一九〇年ごろの画文帯同向式神獣鏡である。洛陽市吉利(きつり)区の出土例は、径一五センチ、鈕の右に西王母、左に東王公があり、外区の画文帯は時計回りにめぐっている。」
この文章の傍線部で、岡村秀典氏は、「出土例」と記す。
ところが、中国で出されている『洛鏡銅華上』(中国・科学出版社、2013年刊)の188ページをみると、この洛陽市吉利区の鏡は、「采集(採集)」と記されている(右下の写真参照)。
 「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」
「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」
つまり、この鏡は、「出土品」ではない。「採集品」なのである。
このような、微妙なことばのおきかえがある。「採集」品のばあい、贋造鏡がまじる可能性がある。中国では、贋造鏡がきわめて多い。そのことについては、拙著『邪馬台国大戦争』(勉誠出版、2017年刊)のなかで。かなりくわしく、多くの例をあげてのべた。
しかも、この中国で刊行された『洛鏡銅華』の本は、ほかならぬ岡村秀典氏の監訳で、わが国でも、『洛陽銅鏡』(科学出版社東京、2016年刊)と題して、出版されている。
そこでは、ちゃんと、「採集」と訳されている(翻訳本の、194ページ)。「出土」とは記されていない。
翻訳本のほうは、原文があるから、「出土」と書きかえるわこには行かなかったのであろう。
岡村氏の、この種の大ざっぱさは、かなり気になるところである。
[3]「景初四年鏡」と「位至三公鏡」
「景初四年鏡」も、洛陽で作られた?
岡村秀典氏は、その著『鏡が語る古代史』の216ページで、つぎのようにのべる。(傍線を引いたのは安本。)
「このように『陳氏』は、二三九年に画文帯同向式神獣鏡を忠実に模倣した和泉黄金塚鏡をまず試作し、その年のうちに画像鏡の要素を取り込んだ三角縁神獣鏡を創作したのである。
翌年に『陳氏』は、『景初四年、陳是作』盤龍鏡と『正始元年、陳是作』三角縁同向式神獣鏡をつくっている。正始元年(二四〇)鏡は、径二三センチ、全体として『景初三年』三角縁神獣鏡を継承しつつ、文様をややていねいに表現し、外区の厚みを増している。景初四年(二四〇)鏡は淮(わい)派の盤龍鏡を模倣したもので、径一七センチと小さく、龍と虎が一対ずつ対峙し、外区は斜縁状をなしている。これは図44に示した一連の同向式神獣鏡とはモデルが異なるため、モデル鏡にはない乳を四方に加えたことをのぞけば、文様上の共通性はみられない。しかし、銘文のパターンと筆跡からみると、いずれも『陳氏』による一連の作品と考えられる。
『魏志』倭人伝によれば、景初三年六月、倭王卑弥呼の派遣した大夫難升米(なしめ)が魏の帯方郡に到着し、同年一二月に都洛陽で魏帝より『銅鏡百枚』を賜与されたという。いまみたように、ちょうどその年に『陳氏』が後漢鏡をモデルに三角縁神獣鏡を創作したプロセスが明らかになり、モデル鏡の有力な候補が洛陽で発見された(安本注。すでにのべた採集鏡のこと)ことから、『銅鏡百枚』が三角縁神獣鏡であり、その工房が洛陽にあった可能性がきわめて高くなった。」
この岡村秀典氏の文章によれば、岡村氏は、「景初四年」銘鏡も、洛陽の、「陳氏」の工房で作られた、と考えておられるようである。
しかし、「景初四年」という年は、存在していない。「景初年間」は、「景初三年」までである。
そのため、中国では一面も出現しないのに、わが国で、二面も「景初四年」銘鏡が出現したことは、一時、大きな問題となった。
2015年になくなった中国を代表する考古学者、王仲殊(中国の社会科学院の考古研究所の所長などであった)は、のべている。(傍線を引いたのは、安本。)
「鏡の銘文において『景初四年』という紀年が出てくるはずは無いのである。」[王仲殊「日本出土の景初四年銘の三角縁盤龍鏡について」(『三角縁神獣鏡』学生社、1992年刊、205ページ)]
「もはや言わずもがなであるが、広峯一五号墳で出土し、あと一つ辰馬考古資料館の所蔵になる景初四年銘の三角縁盤龍鏡もまた、陳是(陳氏)が日本でつくったものなのである。まさに陳是本人は海東の『絶域』にあったので、魏がすでに『正始』の年号に改めていたことを製作の時点では知らなかった。そこで、さきに三角縁神獣鏡をつくった際に銘文の中で使った『景初三年』という紀年の後を受けて、三角縁盤龍鏡では『景初四年』の紀年を記してしまった。---こう考えれば、全てが理解できるのである。」[王仲殊「日本出土の景初四年銘の三角縁盤龍鏡について」(『三角縁神獣鏡』学生社、1992年刊、206ページ)]
王仲殊は、かつて、私に、つぎのようなお手紙をくださった。(傍線は安本。)
「安本美典先生(中国語の「先生」は、日本語の「様」に近いニュアンス)
恷好(ニンハオ)[袮好(今日は)の丁重表現]!
(2013年の)8月21日にお手紙いただきました。三角縁神獣鏡=魏鏡説破滅をテーマとする大著を恵贈していただき、ありがとうございます。
二〇世紀の初期に富岡謙蔵が提出した魏鏡説は、これはこれで理解できるものです。
ただし、二〇世紀の八〇年代以降になると、中国本土および朝鮮半島の地域内に、三角縁神獣鏡の出土例が完全に存在しないことが、確認されたのち、魏鏡説は、成立がむずかしくなりました。とくに、1986年10月に、二面の景初四年銘の三角縁盤竜鏡が発見され、いわゆる『特鋳説』もまた、立足の余地を完全に失いました。これは鉄のように固い事実です。
何人も、否認することができないことです。
森浩一先生か逝去され、悲しい思いにたえません。なつかしく思うことです。
2013年11月10日 王仲殊 拝」
「景初四年鏡」問題は、かなり重要な論点のはずである。それなのに、岡村秀典氏は、その本のなかで、なんのディスカッションも示さず、「景初四年鏡」も、洛陽にあった陳氏の工房で作られたものであるかのように記す。
以下は次回の第435回の講演会に続く




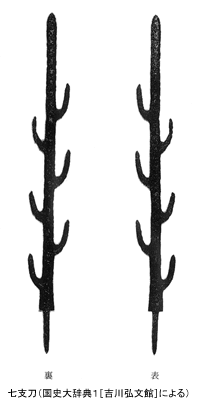 現在、奈良県の天理市にある石上神宮(いそのかみじんぐう)には、国宝の「七支刀(しちしとう)」が存在する。
現在、奈良県の天理市にある石上神宮(いそのかみじんぐう)には、国宝の「七支刀(しちしとう)」が存在する。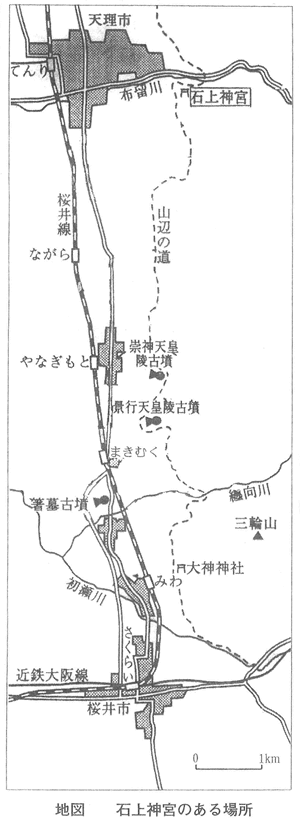
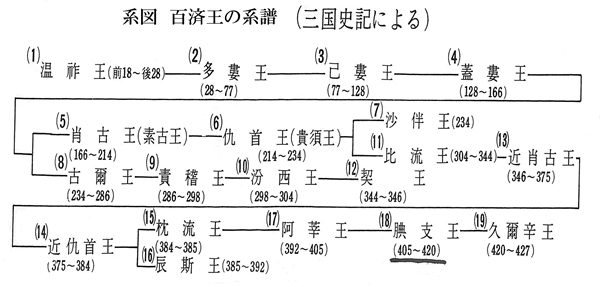
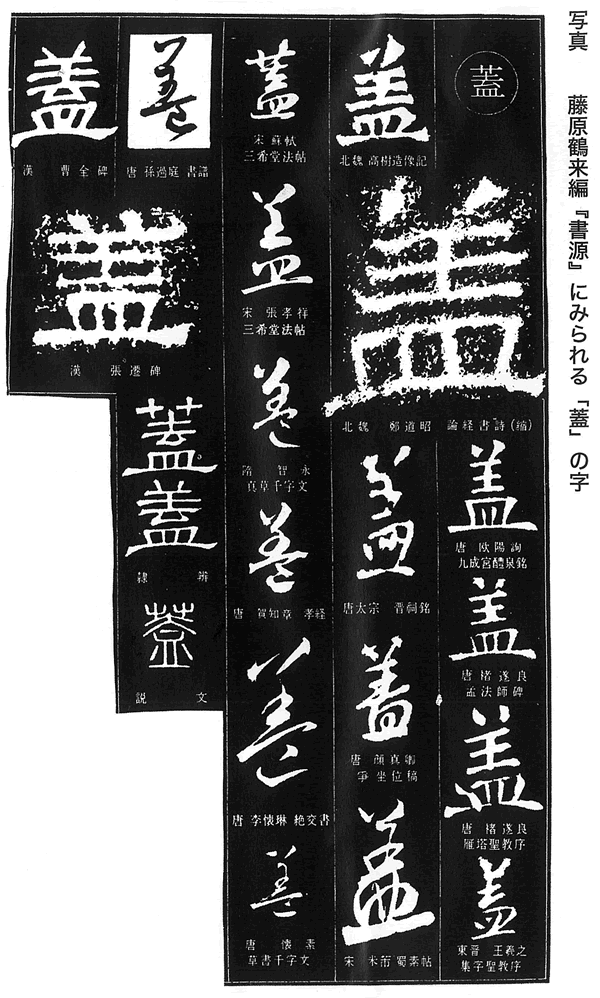
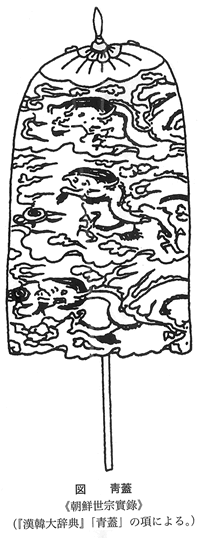 「青蓋車」ということばは、わが国の『日本書紀』のなかにも、二回でてくる。
「青蓋車」ということばは、わが国の『日本書紀』のなかにも、二回でてくる。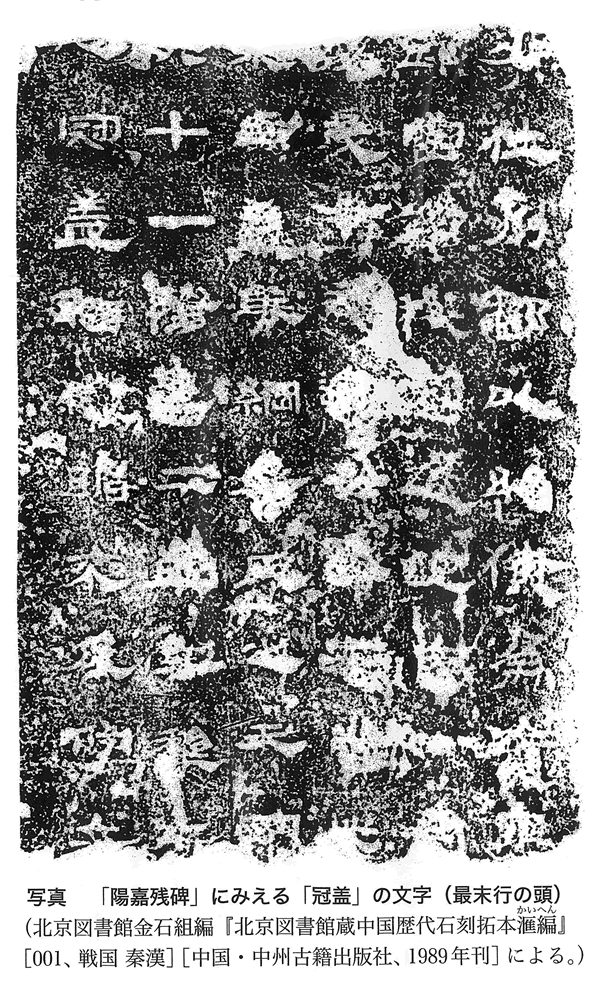
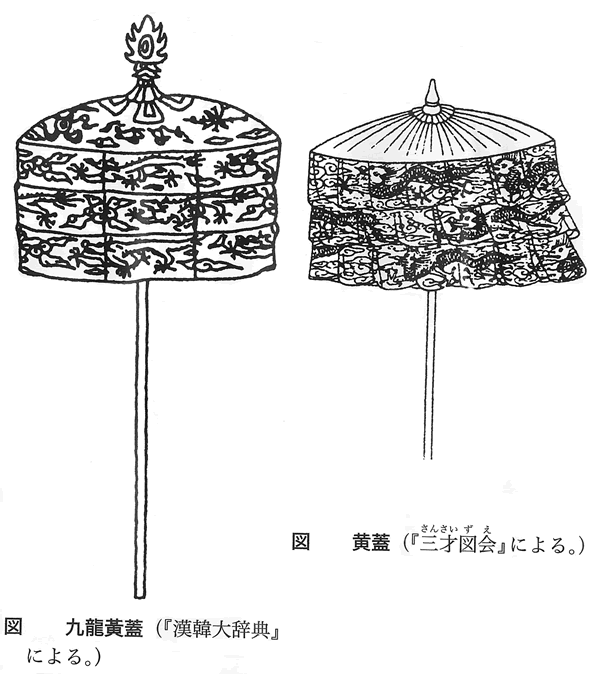
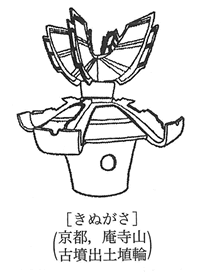 「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」
「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」
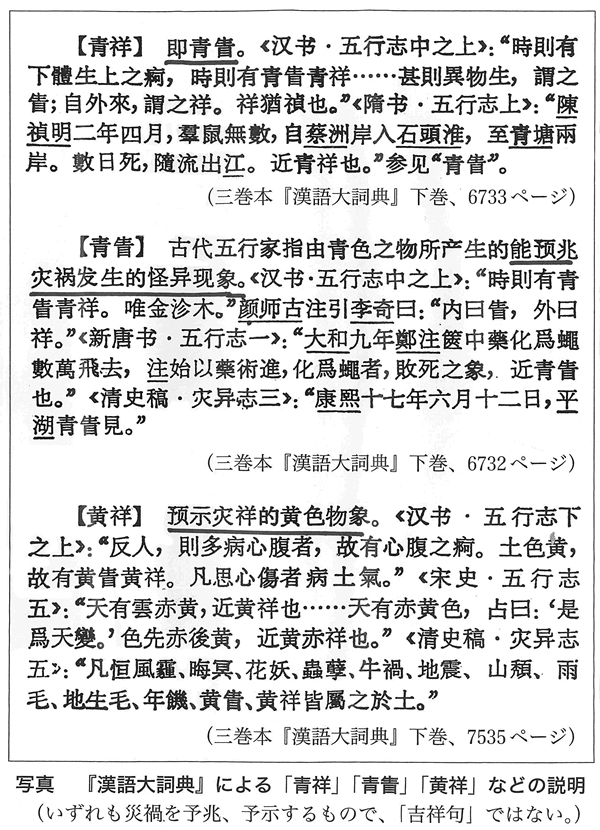
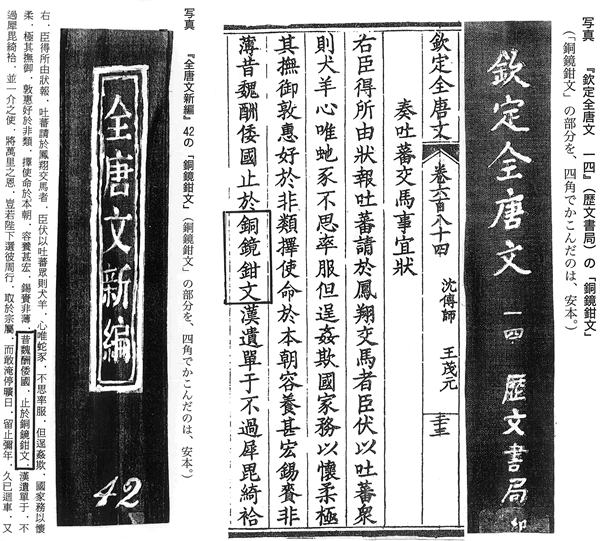
 コラムⅠ 「犀毘(さいび)」[帯鉤(たいこう)]と「綺袷(きごう)」
コラムⅠ 「犀毘(さいび)」[帯鉤(たいこう)]と「綺袷(きごう)」 「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」
「きぬがさ[蓋](名) 絹または織物で張った長い柄のかさ。神体・仏像の渡御や天皇・貴人の行列の際、後からさしかけ、左右に綱を引張って支える。儀制令によれば、貴人に用いる場合には、身分によって、色や四隅(よすみ)の錦・ふさなどを変えた。」