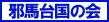 |
TOP > プロフィール > 私と邪馬台国 | 戻る |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
安本美典 |
| 私と邪馬台国 | ||||
| 第一章 序 |
|---|
私は、どうして、古代史の森にふみこんだのだろう。
私の大学での専攻は、心理学であった。しかし、これまでに書いた本の数は、心理学関係の 本よりも、古代史関係の本の数の方が多いほどである。しかも、一冊あたりの本の発行部数と いうことになると、ほとんど問題にならない。古代史関係の本の発行部数が、心理学関係の本 の発行部数をはるかに圧倒する。 心理学関係の本も、古代史関係の本も、私としては、同じように力をそそぎ、同じように努 力しているつもりである。しかし、読者の層の厚みが、まるで違っているようである。 私は、大学における数年の専攻で、その後一生の専攻が決定されるとは思わない。 また、いろいろなことに、興味をもちつづけたいと思う。 まして現在は、学際的な研究が、強く求められている時代である。 さまざまな分野の研究者が協カして、問題の解決にあたることが多くなっている。 日本古代史の問題は、多くの研究者が、協力して探究するのにふさわしい 性質をもっている。自分の専攻に、それほどこだわる必要はないと思う。 それにしても、私じしんは、私じしんの興味のあり方や、研究の対象を、それほどしばしば 変えているようには思わないのである。自分の専攻は、ある意味で、一貫していたように思う のである。 はじめに、そのことについて述べておこう。 |
| 上へ |
| 第二章 統計学へのめざめ |
|---|
もう、あれから、何年になるだろう。そのころ、私たちの一家は、父の郷里の、岡山の草深
いいなかにすごしていた。祖父が、まだ、健在だったから、高等学校の、二年生のころだった
とおもう。
夏休みの日々の多くを、私は、家の土蔵の、二階ですごした。そこは、ひんやりと冷たく、 祖父や、叔父や、父たちが、若い日々に読みふるした書物が、うずたかくつまれていた。ほこ りをかぶったこれらの書物は、私にとって、フロンティアであった。 私は、かいこが桑の葉を食むように、それらの本を読みふけった。 波多野完治氏(現お茶の水女子大学名誉教授、元同女子大学学長)の、『文章心理学入門』(三省堂刊)も、これらの本の名に埋っていた。そのころ、私は、波多野完治氏が、どのような人であるかさえ、知らなかった。それにもかかわらず、このB6判の、うすい書物は、どんなに新鮮なおどろきを、私に、与えたことだろう。 それは、自然科学と、もっとも縁遠いと思えた文学の領域に、科学の光を、与えようとするも のであった。それは、学校で、まだ一度も習ったことのない、未知の科学であった。しかも、 それは、難解ではなかった。 私は、『文章心理学入門』を読み終えたとき、土蔵のまえで、大きないちじくの葉が、ざわ ざわと揺れるのをながめながら、なにか、ひとつの秘密を知ったときのような、こわいような 楽しさにひたったことを、いまでも忘れはしない。 文学や言語の鍵を、科学の方法でさぐること、………。将来、どのような方向に進むにしろ、 このような研究をしてみたい、というのが、そのとき以後の、ひそかな、私の願いとなった。 そのころ、私は、岡山県高梁市の高梁高校に通っていた。汽車通学であった。高等学校の三 年生になって、私たちは、統計学と確率論の、初歩をならった。 当時、統計学や確率論は、大学の入学試験の範囲外であった。そのため、そのころの多くの 高等学校においては、統計や確率は、まま子あつかいであった。 しかし、幸いなことに、高等学校の数学の先生が、仮谷太一先生であった。仮谷先生は、 統計学者で、現在は、川崎医大の教授をしておられる。仮谷先生は、統計学の新しい 動向なども語られた。 そのころ、統計学の分野では、増山元三郎氏や、北川敏男氏が、さかんに活躍され ている時期であった。推計学(推測統計学)ということばが、新鮮なひぴきをもっているころ であった。 高等学校の先生が、ひとつのしっかりとした専攻をもつ学者で、その分野で活躍しておられ る方であるということは、ひとつの刺激であった。 この刺激は、第二の転機をもたらした。入試の勉強に追われながら、私は、むさぼるような 気持で、推計学(推測統計学)の本を読んだ。 完全には、理解できなかったにしろ、当時の推計学の書物の多くがもっていた、若々しい革 命的な雰囲気が、私の心をとらえた。 |
| 上へ |
| 第三章 没入 |
|---|
大学にはいって、私は、受験勉強から、解放された。それは、緑の日々であった。ありあま
る自由な時間と、自分のカの限界をまだ確かめていない「青春」とを、私は、手に握っていた。
私は、内部から、エネルギーが、あふれでる感じを。もった、青春期独特の昂揚感であろう。 私は、「文章心理学」の研究にとりくんだ。波多野完治氏の『文章心理学』は、文学作品の文 体の分析に、統計学を用いている。 たとえば、谷崎潤一郎の文章と、志賀直哉の文章とを比較 するために、そのセンテンスの長さの平均値や、名詞と動詞の使用度をしらべている。 しかし、そこで用いられている統計学は、現在では、「記述統計学」とよばれるものである。それは 第二次大戦前に行なわれ研究であるから、当然のことであった。 「記述統計学」の軌囲で処理してさえ、このように興味のある結果でてくるのであるから、新しい 統計学「推計学」を用いたならば、もっとさまざまな結果が、得られるのではなかろうか。それが、私の着目点であった。 若い時というものは、みずからの限界を知らないがゆえに、しばしば一種の天才願望をもつものである。それは、ロマンティシズムともむすびつくものであろう。 クレッチマーの、『天才の心理学』が、いつの時代でも、多くの青年によって読まれるのは、 そのゆえによるのであろう。 もしかしたら、新しい研究分野をきりひらくことができるかもしれない。そのことが、当時の私をかり たて、没入させるおおきな誘因であった。 |
| 上へ |
| 第四章 計量国語学会 |
|---|
私が、大学(京大)の学生のころ、昭和31年に、国立国語研究所の水谷静夫氏(現東京
女子大学教授)、京都府立大学の樺島忠夫氏、新潟大学のの渡辺修氏などの若い国語学者の呼びかけ
により、「計量国語学会」が発足している。
その機関誌『計量国語学』創刊号巻頭の、「計量国語学会結成趣意」には、 つぎのようなことばが述べられている。 「われわれ発起人一同は、数理的(特に統計的)方法による国語研究の進歩、ならびにその 方法、成果の普及を願い、言語に関する諸種の科学、技術、言語教育の発展に資するととも に、隣接諸科学および外国の同じ分野の科学者との連絡を緊密にするにする目的で、広く言語関係 の研究者に呼びかけて、ここに計量国語学会を結成する」 私は、計量国語学会が発足するという話を京大の国文の遠藤嘉基教授からうかがった。早速、 「結成趣意書」をとりよせた。学生でも入会可能であったし、投稿可能であった。私は、入会 し、創刊号へ投稿した。その原稿は、文章の、マルからマルまで、つまりセンテンスの長さの度 数分布が、対数正規分布といわれる型の分布にしたがうことを論じたものであつた。 この論文は、『計量国語学』の創刊号にのった。 ただし、私は、それ以前に『解釈』(解釈学会編)という雑誌に数編の論文をのせていたし、 また、三省堂からでている『文学・語学』(全国大学国語国文学会編)に、一編の論文をのせて いた。しかし、これらの雑誌は、国語国文学関係の雑誌であったため、統計的な理論を、十分 に展開することができなかった。 その点、「計量国語学会」は、私の希望の条件を、かなり満たしていた。私は、ほとんど、 毎号のように投稿した。これは、いまにして思えば、編集者の水谷静夫氏などにとって、いさ さか迷惑な面もあったであろう。いやしくも、「計量国語学」は、学会の機関誌である。 学生仲間が出している同人雑誌ではない。そこへ、学生からの投稿原稿を、毎号のせるというわけ にも行かなかったであろう。 掲載をことわられたこもあり、それに対して不満をこぼしたりしたこともあった。 |
| 上へ |
| 第五章 著書出版 |
|---|
学生のころには『源氏物語』54帖のうち、いわゆる「宇治十帖」の作者が、他の44帖と同じく、
紫式部といえるかどうかを、文体の、統計的分析の結果からさぐろう、という研究に、
かなりなエネルギーをそそいだ。
「宇治十帖」と他の44帖との間に、文体上偶然以上の(有意の)違いがみとめられるかどうかをしらべた。文体を統計的にしらぺ有意差検定を行なって行くという方法を用いた。 この研究は、大学卒業の翌年に、『文章心理学の新領域』と題して、東京創元社から、刊行された。 私のこの研究は、考えのいたらぬところが、たくさんあった。しかし、幸いにして、学界 では、あるていどの評価を、うけることができた。とくに、波多野完治氏、小林英夫氏(言語学者、 元東京工大教授)からいただいたお手紙は、私に勇気を与えた。 昭和34年に、心理学を専攻として、大学を卒業した。卒業論文は、現代作家百氏の文章 の文体を、統計的にしらべ、その結果を因子分析し、百人の作家の文章を、八つのグループに わけ、さらに、作家の性格とその文体との関係を考えるというものであった。 この研究は、のちに、『文章心理学入門』という題で、誠信書房から刊行された。 統計学は、記述統計学から推計学(推測統計学)へ、そしてさらに、因子分析法などを含む 多変量解析の方向へと、発展をみせつつあった。 私の文学作品などの統計的分析も、だいたいこの発展の方向にしたがう形で進んだ。 |
| 上へ |
| 第六章 海外の研究の状況 |
|---|
さて、私は、大学にはいってからのち、外国では、文章や文体、あるいは、人間の言語や古
文献などを、統計的に研究したものとしては、どのようなものがあるのであろうと思って、
関連文献を、かなり、こまめに集めて読んだ。そして、日本では、それまでに、波多野完治氏の研
究以外は、ほとんどないのに対し、外国では、その種の研究が、かなりたくさんあることを知
つた。
作者推定論(作者未詳の古典の作者を、文体の統計的分析によつて推定したもの)、執 筆時期推定論(ある作品が、その作者の青年期に書かれたものか老年期に書かれたものか、用 語などの統計的分析によって推定したもの)、文体と作者の性格との関係を論じたもの、統計 的語彙論(語彙の量的性質をしらべたもの)、………。 私は、はじめ、その外国文献の量に圧倒された。しかし、このような研究は、外国でも、当時は、なお、黎明期にあったのであろう。 主要な文献にひととおり目を通すことが、不可能というほどではなかった。 この分野の研究に、すでに、推計学を用いている研究のあることを知った。また、のちには、 言語や文章の研究に、因子分析法などを用いた研究のあることも知った。 外国文献を読むことは、私には、三つぐらいの効果があったように思う。 第一は、自分の研究の方向が、この分野の研究の全体的な発展の方向から、それほどはずれ ていないらしいという安心感をもたらしたことである。 第二は、当時の外国のこの分野の研究の水準が、量はともかく、質的には、 それほどまでに高いとは思えず、十分競争になるような 感じがしたことである。すなわち、競争心を刺激されたことである。マラソンでも、みんなが あまり速すぎれば、競争心がおこらず落後してしまうであろう。それと同じで、当時の外国 のこの分野の研究の水準が、現在ほどには高くなかったことは、幸いな、ことであった。 第三には、外国研究は、やはり、研究上のさまざまなヒントをもたらした。 |
| 上へ |
| 第七章 邪馬台国と統計的情報学 |
|---|
『三国志』のいわゆる「魏志倭人伝」に最初に興味をもったのは、大学生のころであった。
神田の古本屋で、たまたま島谷良吉氏の、『国訳魏志倭人伝』(タイプ印刷、昭和31年刊)
を入手し、邪馬台国の位置を、地図上で、あれこれと考えてみた記憶がある。
私が大学を出てから数年後の昭和40年に、中央公論社から、井上光貞氏の『日本の歴史1 神話から歴史へ』が刊行された。この本には、日本古代史のそれまでの諸学説が、穏健な姿勢 によって、適切に整理し、紹介されている。問題の所在を示し、多くの人々に、古代史への興 味をかきたてる触発的な好著である。私は、この本から、強い刺激をうけた。 私は考えた。 邪馬台国や日本古代史の問題は、文献を、統計的に分析するという方法によって、探究する ことはできないであろうか。 ことぱ、文章、文献、これらは、すべて、人間から人間へ、情報を伝えるものである。そして、現在の情報科学において、統計学や確率論が、探求のための基本的な武器となっている。統計学や確率論は、雑多な情報の中から、本質的なものをとりだすのに適している。現代の進歩した統計学は、日本古代史という対象に対して必ず、鋭利な武器となる可能性が多分にある。 私の専攻は、統計的情報学であるともいいうる。 日本古代史の諸問題の中には、統計的情報学の中に包摂しうる問題が、かなりあるのではなかろうか。また、邪馬台国問題などは、かなりポピュラーである。統計的情報学が、この問題に有効さを示しうるならば、私が専攻とするような学問分野もあるということを、多くの人々に知っていただくよいきっかけとなるであろう。 このように考えた私は、邪馬台国問題に、本腰をいれてとりくむこととした。私は、30代 のはじめにあった。 「日本のあけぼのを推理する」(『科学朝日』昭和40年11月号)、「卑弥呼考-推計学の立場から-」(京都大学国文学会編『国語国文』昭和41年6月号)、「邪馬台国の位置について」(計量国語学会編『計量国語学』39号、昭和41年12月)などが、比較的初期の論文である。 『計量国語学』にのせた「邪馬台国の位置について」は、昭和41年の10月1日に立教大学 で開かれた計量国語学会で、口頭発表したものを、まとめたものである。 この立教大学での大会には、現在、国立国語研究所の所長をしておられる野元菊雄氏がみえ ておられた。野元氏は、当時、筑摩書房から出ている雑誌『言語生活』の編集にタッチしてお られた。野元氏は、私の口頭発表に興味をいだかれ、筑摩書房の編集者に、単行本として出し たらどうかという話をして下さった。 私の日本古代史関係の最初の本『邪馬台国への道』は、昭和42年に、刊行された。 昭和42年1月に、講談社から、宮崎康平氏の、『まぼろしの邪馬台国』が刊行され、 大きな反響を呼んだあとであった。私の本も、あるていどの反響を呼ぶことができた。 |
| 上へ |
| 第八章 古典にたいする姿勢 |
|---|
なお、私は、『源氏物語』の研究からはじめて、『古事記』『日本書紀』の研究に進んだ。こ
の点、本居宣長が歩いた道と、ほんのちょっと似たところがある(ここに、本居宣長をもって
くるなど、まったく気のひける話であるが)。本居宣長は、賀茂真淵からすすめられ、時代の
下る作品から研究をはじめ、順次上代へと進み、『古事記』の研究に至った。
私は、先学の多くの研究成果のお蔭で、『源氏物語』から『万葉集』、『万葉集』から『古 事記』『日本書紀』へと、大いそぎで通りすぎることができた。 このような道を歩んだことは、自分の説が、どのようなものであるかを考えるさい、あるい は、重要なことかも知れない。 今日、『三国志』『漢書』『後漢書』などの中国文献を重視する方は、しばしば、日本側の文 献、とくに『古事記』を、あまり重視されない傾向がみられる。これは、恐らく、中国文献の 発想法と、『古事記』などの発想法とが、異なるところにも、一つの原因があると思われる。 『三国志』『漢書』『後漢書』は、「怪、力、乱、神を語らず。」的な色彩が強い。陳寿の『三国志』は、『魏略』とくらべても、荒誕の説を載せるところがすくない。 この眼で『古事記』を見れば、どこかに違和感を感じられるのではないだろうか。多少とも、 荒誕の書的に見えるのではないだろうか。 ところが、『源氏物語』から『万葉集』へ、『万葉集』から『古事記]へ、と進むと、『古事 記』の発想法が、なんとなく自然に理解できるところがあるのである。あきらかに『古事記』 は、『源氏物語』と『万葉集』とを結ぶ線の古代への延長上にある。 本居宣長は、『古事記』を尊重して、外国文献を排斥した。もちろん、私は、外国文献を排 斥するつもりはないし、それはそれとして、尊重するつもりである。しかし、すくなくとも 、外国文献を重視し、『古事記』など国内文献は軽視するという姿勢は、とらないつもりであ る。 このようなことを、わざわざ記したのは、人がある説を立てるときに、その人がそれまで に歩んできた道において、見たり、聞いたり、考えたりしてきたことがらの影響が、ほとんど 無意識のうちに強く働いていることをいいたいからである。 人が歩んできた道は、みな異なる。そのため、Aの人にとっては、説明なしで、きわめて自 然にみえることが、Bの人にとって、まったく不自然にみえるのである。 説のわかれるゆえんである。 |
| 上へ |
| 第九章 興味の対象 |
|---|
私が大学をでる年の春に、父が病没した。私は、たまたま力だめしのつもりでうけた国家公
務員上級試験(心理職)が、なんのはずみか、全国第一位という成績だったので、生活の資を
得るために、労働省にはいった。その後、一橋大学の社会心理学者、南博氏の力で設立された、市場調査の会社「日本リサーチセンター」にうつり、データの統計的解析の仕事にたずさわったりもした。
しかし、私の興味、関心は、一貫して、ことば、文章、文献など「人間の生みだした情報の 統計的解析にあった。 最近、私は、日本語の起源の問題にとりくんでいる。それは、確率論や統計学の助けにより、 言語と言語とのあいだの近さの度合を、数字ではかる方法によっている。日本語と朝鮮語、日 本語とアイヌ語、日本語とインドネシア語………など、日本語と日本の四周の言語との距離を数字ではかり、それによって、日本語の起源をたずねようとしている(講談社現代新書、『日本語の成立』、大修館書店刊『日本語の誕生』など)。 これもまた、人間集団がもつ、言語という情報組織の、統計的解析である。 私の内部においては、私の興味、関心のあり方、あるいは、専攻は、一貫しているのである が、たまたま、その専攻は、既存の学問分類にあてはまらず、これまでの学問分野のさまざまな領域と関係する。そのため、「あなたの御専攻は?」などと時おりたずねられることとなる。 しかし、このようなことは、これからは、他の領域ても、しばしば起こるであろう。 たとえぱ、コンピュータの普及発展にともない、コンピュータ科学が生まれた。コンピュータ科学などは、既存の学問分野のさまざまな領域と関係する。 |
| 上へ |
| 第十章 新しい分野に挑戦 |
|---|
人間的な情報についての統計的解析の学、それは、わが国の学界において、なお明確な位置
を占めていない。
しかし、時代の流れとともに、起きる学もあれば、滅ぴる学もある。かって、修辞学などは、 西欧において、重要な学であったが、現在では、昔日のおもかげはない。わが国の儒学なども、またそうである。 私は、自分の選んだ道に、時には孤独を感ずることはあるにしても、後悔はしていない。そ れ以外に、道はなかったように思うし、また、自分の適性もそこにあるように思うからである。 人間的な情報についての統計的な解析の学は、人間の精神の活動の結果である、言語、文学、 文化、歴史などの、人文科学の諸領域に、数理的な、あるいは、自然科学的な方法を導入する ことを意図する。 それは、数理人文学と名づけてもよい内容をもつ。そして、私は、その数理人文学を発展させることが私に与えられた仕事と思っている。人間は、だれしも、自分の存在の意味を知りたいと願い、存在のあかしを得たいと願うものである。現在は、たとえ、名のない学であろうとも、自分自身がそこにフロンティァを感じ、生命の充実感をおぽえるならば、そこにかけるべきなのであろう。 若いときというものは、新しい方法などに対する適応性が大ぎいものである。 そして、新しい分野に興味をもってとびこむときには、案外、ちょっとしたことがきっかけ になっているのではなかろうか。 ひんやりとした土蔵の中に眠っていた波多野完治氏の『文章心理学入門』は、とうとう私を、 ここまで、つれてきてしまった。はじめ、文章研究という小川にそって歩いていて、 いつか、広い海原をながめているような気がする。 この本を書きはじめるにあたり、まず、胸にうかんだのは、少年の日の、あの日のことであ る。緑濃い、いちじくの葉に、風がわたる夏の日のことである。 もう、あの日から、数十年の歳月がとぴ去っている。思いかえして、感慨なきを得 ない。 本を書くさいの願いは一つ。私の書いた本が、読者のだれかにとって、かっての波多野完治 氏の本が私にとってそうであったように、触発的でありうることである。 虚偽より真実へ 闇より光へ 死より永遠の生命へ導きたまえ タゴール |
| 上へ |
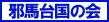 |
TOP > プロフィール> 私と邪馬台国 | 戻る |