| TOP>活動記録>講演会>第268回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第268回 特別講演会(2008.4.20 開催)
| ||||
1.三角縁神獣鏡は魏鏡か 新井宏先生
|
 ■ 三角縁神獣鏡と同笵鏡論の現状
■ 三角縁神獣鏡と同笵鏡論の現状10年ほど前までの研究の状況
もし、三角縁神獣鏡が「卑弥呼の鏡」から自由になれば、三角縁神獣鏡をもって古墳 時代の年代を定めてきた旧来の学説も、三角縁神獣鏡をもって古代国家像を描いてきた 旧来の学説も、大きな変質を余儀なくされるであろう。 いわば中国鏡か国産鏡かの議論の重要さも、意味が薄れてしまうのである。 更に、三角縁神獣鏡に特徴的な「線キズ」が、中国鏡に認められない(?)ことから、鋳造技術面からも、国産鏡説への流れがあるように見受ける。 ■ 鉛同位体比による判定 ウランやトリウムが崩壊した後の落ち着き先は全て鉛。その鉛は質量の異なる4種類 (204,206,207,208)の同位体で成り立っている。 この4種類の比率が地域や鉱山で微妙に異なっているので、指紋やDNA鑑定のように 青銅器の区分にも使える。 ■ 三角縁神獣鏡と斜縁二神二獣鏡の比較 卑弥呼の三角縁神獣鏡神獣鏡と中国鏡の鉛同位体の比較をしてみる。 ところが、中国は夏とか殷のように古い時代に研究に熱心であり、漢、魏の頃のものの研究は後回しに なっている。そのため中国で発見された魏時代の鏡で鉛同位体比分析されたものがない。 そこで、福永伸哉氏が魏鏡としている斜縁二神二獣鏡と、三角縁神獣鏡の様式の中でも、卑弥呼の鏡とされる初期段階のものの鉛同位体を比較した。 その結果、この二つの鏡は異なるデータを示し、三角縁神獣鏡は、斜縁二神二獣鏡よりも庄内・古墳早期の  製鏡に近い数値となった。 製鏡に近い数値となった。
■ 自給されていた鉛原料
 製鏡 製鏡
大部分の三角縁神獣鏡は国産である。しかしオリジナル鏡など魏鏡の存在を排除する ものではない。 |
2.三角縁神獣鏡は誰が作ったのか 安本美典先生
|
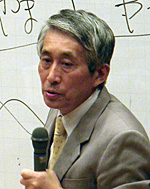 ■ 「同デザイン同型鏡」と「同デザイン踏み返し鏡」とは区別すべき
■ 「同デザイン同型鏡」と「同デザイン踏み返し鏡」とは区別すべき
三角縁神獣鏡には、同じ形式、同じ文様の鏡がかなり多い。これを「同デザイン鏡」と呼ぶことにする。 かつて、京都大学の梅原末治は「同デザイン鏡」は同一の鋳型で作った鏡と考えた(同笵鏡説)。しかし、青銅は冷えて固まる時に縮んで鋳型を壊してしまうので、同じ鋳型で二面以上の鏡を作らない。 現在は、「同デザイン鏡」のなかには、「同デザイン同型鏡」と「同デザイン踏み返し鏡」があると考えられている。 「同デザイン同型鏡」とは、一つの原型となる鏡をもとにして、型押しによりいくつもの鋳型を同時に作り、これによって製作した同じ型の同デザイン鏡である。 ところが、原鏡となる鏡をもとにして作った鏡、つまり、コピー鏡、あるいは、母鏡をもとにして作った子供の鏡を、新たな原鏡として、もとの母鏡の孫コピー鏡を作ることができる。このようにして作った「同デザイン鏡」を「同デザイン踏み返し鏡」と呼ぶ。 「同デザイン鏡」でも、「同デザイン同型鏡」と「同デザイン踏み返し鏡」とは、区別して考えなければならない。「同デザイン同型鏡」は、同時期に作られた兄弟鏡である。しかし、「同デザイン踏み返し鏡」の母子関係にある鏡は、製作時期が異なると考えられるからである。 樋口隆康氏、岡村秀典氏、福永伸哉氏などの議論では、「同デザイン鏡」はすべて「同デザイン同型鏡」で、製作時期は同じとして、三角縁神獣鏡の製作年代、編年を考えている。ここに、最も大きな、根本的な誤りがある。 三角縁神獣鏡では、子コピー鏡、孫コピー鏡、曾孫コピー鏡が作られている。従って、兄弟関係いとこ関係、おじ・おい関係などになる鏡が多数存在している。三角縁神獣鏡の編年はこのような事実をもとにして考えるべきである。 ■ 異なる古墳から出土した三角縁神獣鏡は異なる時期に鋳造されている。 以下の例のように、「同じ古墳から出土した同デザイン鏡は面径が一致する。」という強い法則性がある。 表1. 奈良県佐味田古墳などから出土している「天王日月」銘唐草文帯四神四獣鏡
表2. 福岡県原口古墳などから出土している「天王日月」銘獣帯三神三獣鏡
表3. 大阪府紫金山古墳などから出土している獣文帯三神三獣鏡
これまで出土した三角縁神獣鏡のデータ(『倭人と鏡 その2』(埋蔵文化財研究所関西世話人会編)巻末データ+黒塚古墳出土鏡)をもとに、一つの古墳から二面以上出土しているケースを全て取り出して調べると、
踏み返しによって同デザイン鏡を製作すると、銅の収縮によって、新しい鏡は元の鏡よりも面径が1.2%ほど小さくなる。この現象を考慮すると、上記データは、次のようなことを示していると考えられる。
岡村秀典氏は三角縁神獣鏡の伝世を説くが、岡村氏の言うように、中国大陸で製作されて日本に運ばれ、時間を経てから各地に埋納されたものであれば、伝世の過程でバラバラになるので、上記のような高い確率で同デザイン同型鏡が同じ古墳から出土することは考えにくい。 ■ 三角縁神獣鏡の年代 岡村秀典氏は『三角縁神獣鏡の時代』のなかで、三角縁神獣鏡をはじめから「三世紀の中国鏡」と決めてかかり、三角縁神獣鏡がどのような年代の古墳あるいは遺跡から出土したかは、ほとんど無視して話を進める。 しかし、三角縁神獣鏡は前方後円墳から多量に出土していて、三角縁神獣鏡と土器との「確実な 共伴関係」は多い。 そこで明らかなのは布留式以降の土師(はじ)器と共伴することが多く、これまでのところ確実な庄内式土器との共伴がみられないという事実がある。 たとえば、徳島文理大学の石野博信氏は著書の中で次のように述べる。 墓から出てくる三角縁神獣鏡について土器で年代がわかる例を見ると、四世紀の「布留式土器」と近畿で呼んでいる土器と出てくる例はありますが、その前の、三世紀の土器といっしょに出てくる例は一つもない。それは埋葬年代を示すのであって、製作年代は示さないということはあるんでしょうが、それにしても、ひとつもないのはおかしい。新しいんだろう。 学者によって多少意見が異なるが、邪馬台国時代は、庄内式土器の時代あるいはそれよりも前の時代とされている。庄内式土器よりも一時代あとの布留式土器と共伴する三角縁神獣鏡は、三世紀の邪馬台国の時代の鏡ではないことは明らかである。 方格規矩鏡や内行花文鏡をはじめとする中国北方系の鏡こそ、庄内式土器や庄内式以前とみられる土器とこれまでしばしば共伴関係が見られるものである。 ■ 三角縁神獣鏡の製作者 三角縁神獣鏡が国産鏡とすると、この鏡は誰が作ったのであろうか。 『古語拾遺』神武天皇の段に次のような記述がある。 「また、天(あま)の富の命(高皇産霊の命の子で、忌部氏の祖神)をして、もろもろの齊部(いんべ)氏をひきいて、種々の神宝、鏡、玉、矛、盾、木綿(ゆう)、麻(お)などを作らせた。」 また、崇神天皇の段には、「崇神天皇の時代にいたって、宮中にまつられていた天璽(あまつしるし)の鏡と剣とから天皇は威圧を感ずるようになられ、同じ宮殿に住むことに不安をおぼえられた。そこで、齊部氏をして、石凝姥(いしこりどめ)の神の子孫と、天の目一箇(まひとつ)の神の子孫との二神をひきいて、さらに鏡を鋳造し、剣を作らせて(レプリカを作らせて)、天皇の護身用のものとした。これがいま践祚する日にたてまつる神璽の鏡と剣である。」と記される。 これでみると、宮廷の祭祀をつかさどる氏族である忌部氏が、石凝姥の神の子孫(鏡作り氏)などをひきいて鏡を鋳造したという。鏡作り氏は職業集団をひきいる伝統のあるリーダー氏族である。 鏡作り氏は各地の部民を指揮して鏡を作り、それを大和朝廷に貢納していたとみられる。大和の国、伊豆の国田方郡にある鏡作り郷に加えて、各地にある香美(土佐)、各務(美濃)などの郡名や、覚美(摂津)、香美(美作、安芸、阿波)各務(美濃)などの郷名が部民の存在を示している。 鏡作り氏の首長は鏡作造(かがみつくりのみやつこ)であり、天武天皇の時代に連(むらじ)姓になっている。 鏡作り氏を中央で掌握していたのは、忌部氏であった可能性が高い。忌部氏は祭祀具の製造に従事した氏族で、持統天皇の即位式では神璽の剣と鏡を奉った記録がある。 その後、忌部氏が中臣氏におされて衰えるにつれ、鏡作り氏も衰えたものであろう。 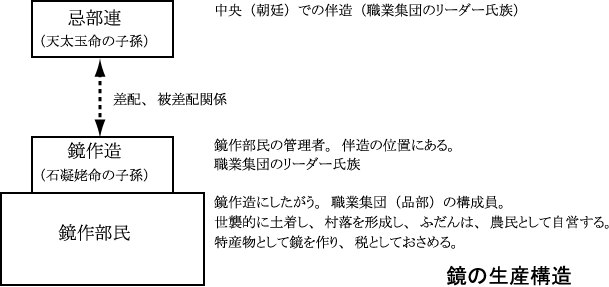
■ 鏡作り氏の役目 大化前代の4世紀を中心とする時代において、各地にいた鏡作り氏の役目は、およそ次のような物であったと考えられる。
各地の鏡作り氏に属する部民は、平生は、農民としての生活をし、製作した鏡の貢上、 または労働の負担をするかわりに、租税の一部が免除されたとみられる。 |
| TOP>活動記録>講演会>第268回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |