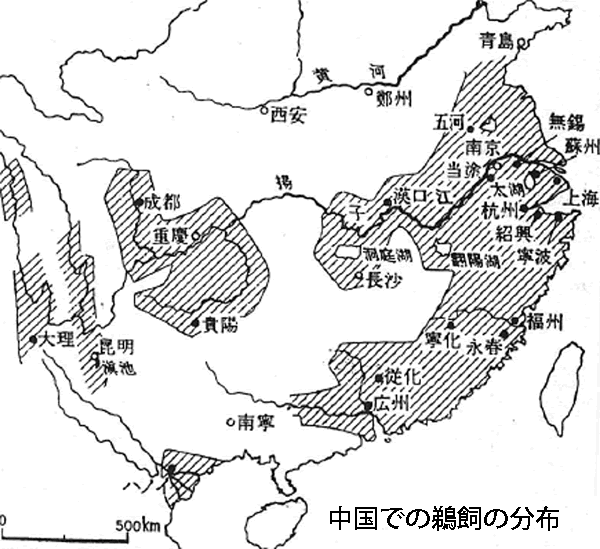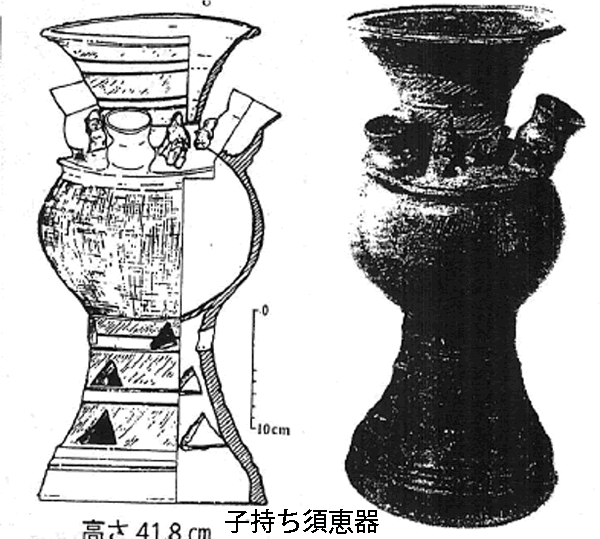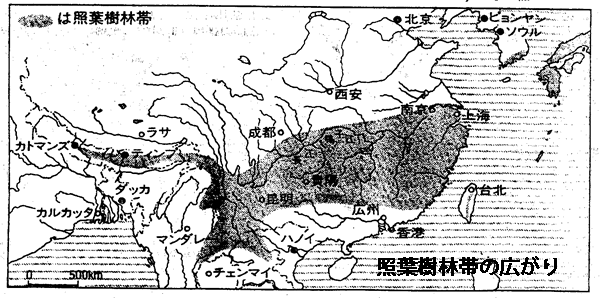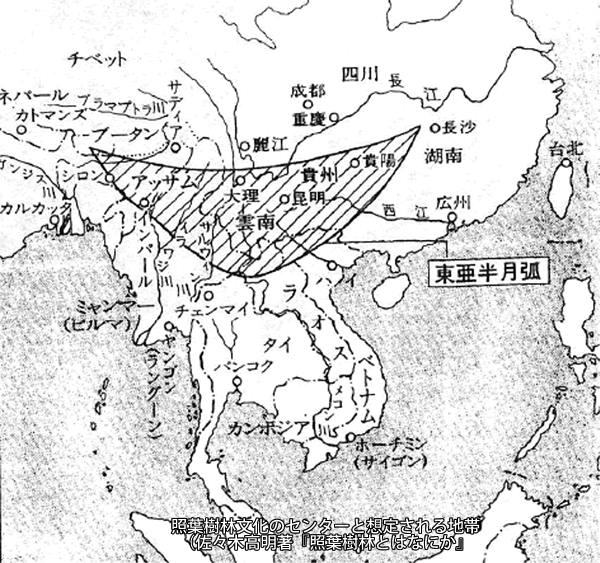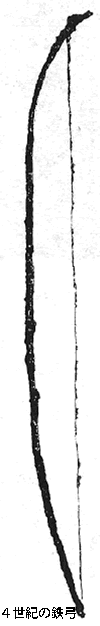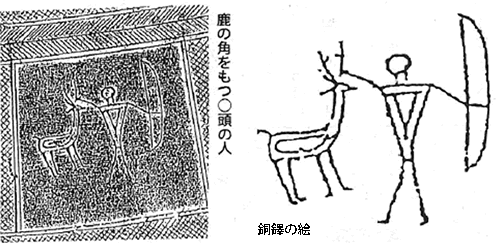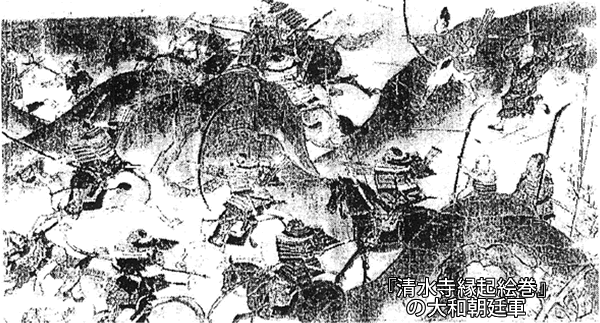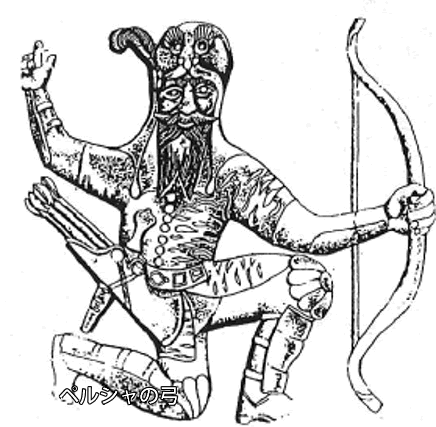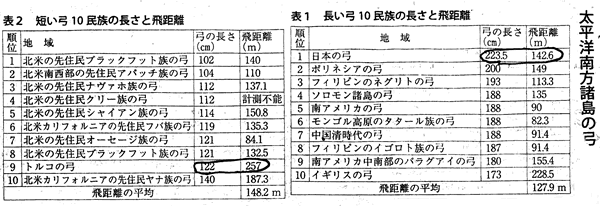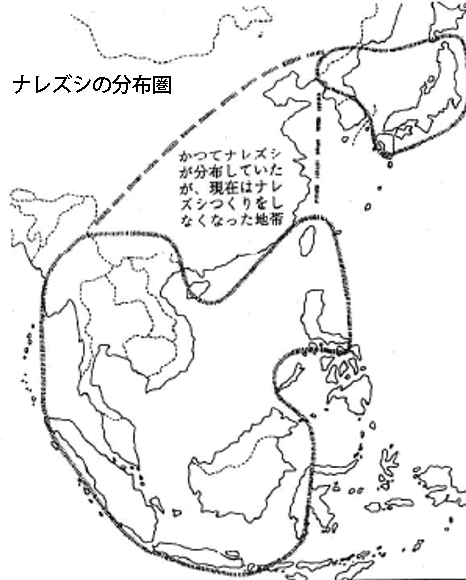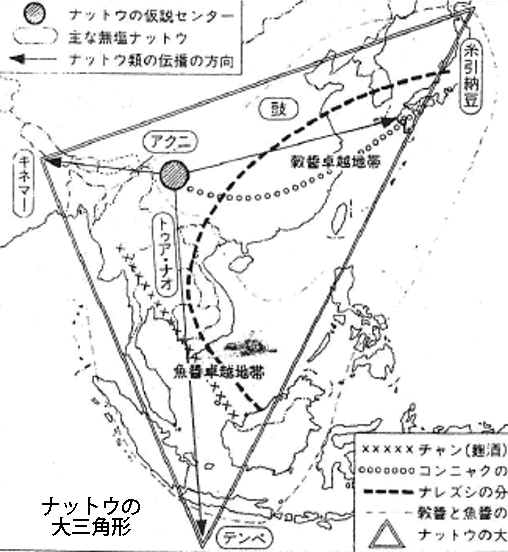| TOP>活動記録>講演会>第307回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第307回 邪馬台国の会(2012.3.25 開催)
| ||||
1.日本民族の起源
|
■倭人の鵜飼 鵜飼は中国の揚子江流域で古くから行われており、その範囲は戦国時代からの楚の国の領域に重なる。遠く雲南の地域にまで広がっている。
一方日本では、土井ヶ浜遺跡の弥生人に川鵜を抱いている女性が出土している。これは鵜を食べるためではなく、飼っていたと考えられる。 ・照葉樹林文化 このように照葉樹林帯に共通文化が広がるのは、『周圏論』で説明できる。
|
■倭人の弓 日本の弓は世界的に見ると非常に特徴がある。
平安時代に、東北の胆沢の蝦夷のアテルイが大和朝廷軍を破った。このアテルイの反乱を鎮静したのが坂上田村麻呂である。坂上田村麻呂が造ったお寺の清水寺に清水寺縁起絵巻があって、大和朝廷軍と蝦夷軍との合戦図がある。その弓の図をみると、両軍の弓は明らかに違い、大和朝廷軍は長弓で、蝦夷軍は短弓である。
世界の各国の弓を調べると、朝鮮の高句麗の弓も短いし、中国の弓も短い、モンゴルの匈奴の弓も短い。どうみても馬に乗って弓を射るには短いアーチェリー型の方が扱いやすい。 匈奴は古くは「ふんぬ」と読み、漢の武帝によって中国の周辺から追い出され、その後西に移動して、ヨーロッパへ向かった「フン族」の移動としてヨーロッパの民族大移動を誘発させたと言われている。 ペルシャ(現在のイラン)の弓、ブータンの弓、タイの弓も短い。また、日本に来た蒙古も『蒙古襲来絵巻』から、短弓であることが分かる。
アメリカのカリフォルニア大学教授のサクストン・ポープ(Saxton Pope)は弓の研究から、世界各地の34民族の弓について、長さ、飛距離、材質などを調べた。
・「ナレズシ」 大宰府に残る『翰苑』という古い文献がある。この『翰苑』には「(倭人は、)文身鯨面して、なお太伯の苗(びょう)と称す。」と書かれている。また『魏略』を引用して、「その俗、男子は皆文身鯨面す。その旧語を聞くに、みずから太伯の後という。」とある。 これらは、「日本語の起源」の講演でも話したいと思う。
|
2.「山片蟠桃と津田左右吉」(前回講演の続き)
|
梅花短期大学の宮内徳雄教授は、「山片蟠桃から津田左右吉へ」という論文で、およそ、つぎのように述べている。 おもな例を三つほどあげてみよう。 ③中国においても、かつて、十九世紀的な文献批判学がさかんで、学者、政治家として著名な康有為(こうゆうい)(1858~1927)が、『孔子改制考』をあらわし、夏・殷・周の盛世は、孔子が、古(いにしえ)にことよせて説きだした理想の世界にすぎないと述べた。殷王統は、星体神話にすぎないともいわれた。
|
3.本居宣長
|
本居宣長の著述で、後世にとくに大きな影響を与えたものとしては、つぎの三つをあげることができる。 ①皇国史観 ②「古事記」の注釈 ③偽僣説 そして、宣長の考え方の根本をなしているのは、①の「皇国史観」である。他の二つは、ここからみちびきだされたものである。 宣長は、つぎのようにいう。 「現在ありえないことであるからといって、古代にもありえなかったと考えるのは、あて推量である。 人間の知恵には限界があり、太古においてどのようなふしぎがあったかは、はかり知れない。したがって、古代のことは、『古事記』『日本書紀』などをもとにして知るべきである。『古事記』『日本書紀』に記されていることは、現代人の目からみてどのように不合理にみえようと、さかしら心(小賢しい心)によって判断せずに、そのままうけとるべきである。」  本居宣長は、また、述べている。 本居宣長の考えは、江戸時代の当時においてすら、「雨月物語」を書いた大才、上田秋成(1734~1809年)から鋭い批判をあびている。 |
4.『魏志倭人伝』のテキスト
|
紹興本と紹煕本 (b)慶元本[けいげんぼん](いわゆる紹煕本)南宋の、紹煕年間(1190~1194)に刊行されたと、しばしばいわれているテキスト。わが国の宮内庁書陵部に存在するもので、清朝から中華民国時代にかけての学者、張元済(ちょうげんさい)の編集した百衲(ひゃくのう)本二十四史の『三国志』のなかの『魏志倭人伝』は、宮内庁書陵部のものを、影印(写真印刷)したものである(このテキストは、「季刊邪馬台国」18号などで、その写真版をみることができる)。しかし、慶応大学の、この時代の書誌学の第一人者、尾崎康氏によれば、「紹興本」が、官刻であるのに対し、この「いわゆる紹煕本」は、南宋中期の建安(けんあん)で印刷された坊刻(ぼうこく)本(民間で刊行された本)で、「紹煕本」と呼ぶのは、まったく不適当であり、テキストとしては、あまりよいものではないという(『季刊邪馬台国』18号)。いわゆる「紹煕本」が紹煕年間に刊刻されたという根拠は、まったく存在せず、慶元年間(1195~1200)の刊本が存在しているだけである。したがって、慶元本と呼ぶのが妥当である。慶元本は、坊刻本であるためか、「俗字」や「略字」の使用がめだつ。たとえば、真(眞)、青(靑)など。 また、現在、『三国志』全体の原文にあたるばあいの手にはいりやすい代表的なテキストとしては、たとえばつぎのようなものを、あげることができる。 ②百衲本『三国志』(台湾商務印書館刊)清朝から中華民国時代にかけての学者、張元済が、いくつかの版本を集め、写真にとってまとめたもの。 ③『三国志集解』(『二十五史7』芸文印書館刊) 清の考証家、盧弼(ろひつ)の撰になる。諸本の異同を、ややくわしく記している点に特徴がある。 ④『和刻本正史 三国志』(汲古書院刊) 日本の出版社から出されており、ふつうの書店に注文すれば、容易に手にいれることができる。句読点、返り点、送り仮名がつけられている。 |
| TOP>活動記録>講演会>第307回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |