■「位至三公鏡」 
「位至三公鏡」とよばれる形式の鏡がある。
昨年の2017年11月の講演で紹介した『洛陽銅華』(岡村秀典氏監訳の日本語版では、『洛陽銅鏡』)には、「位至三公鏡」の類といえるものが、十二面紹介されている。いずれも「西晋」時代の鏡とされている。
『洛鏡銅華』上巻による位至三公鏡の一例
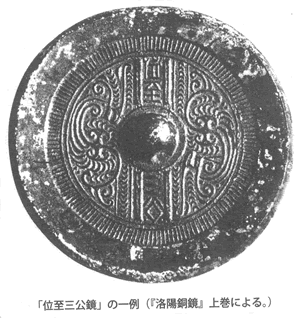 西晋中後期
西晋中後期
直径9.7cm、厚さ0.4cm
円形、円鈕、円鈕座、鈕座の上下にある双線の間に、それぞれ縦書きの「位至」、「三公」の4字の銘文がある。左右両側に変形鳳紋がある。
外に2条の弦紋と櫛歯紋がめぐる。
幅広い無紋の平縁。2003年4~7月、伊川県槐荘墓地6号西晋中後期墓出土。
河南省文物考古研究院蔵〔河南省文物考古研究所・伊川県文物管理委員会2005〕。
(霍宏偉)
西晋王朝は、「西暦265年~316年」のあいだつづいた。すなわち、卑弥呼の時代のあとの、三世紀末から、四世紀はじめごろに存在した王朝である。
注:岡村さんの主張は「漢鏡6期」(後漢前期)、「漢鏡7期」(後漢後期)として、、西晋時代としていない。
■中国出土の「位至三公鏡」の年代
中国の秦・漢時代から南北朝時代までの(洛陽ふきんでの考古学的発掘の、報告書類を集大成したものとして、『洛陽考古集成-秦漢魏晋南北朝巻-』(上・下二巻、中国・北京図書館出版社、2007年刊)が刊行されている。
また、洛陽ふきんから出土した鏡をまとめた図録に、すでに紹介した『洛鏡銅華』(上・下二冊、中国・科学出版社、2013年刊)がある。
『洛陽考古集成』『洛鏡銅華』にのせられている「位至三公鏡」のうち、出土地と出土年のはっきりしているものすべてを、表の形にまとめれば、下表のようになる。
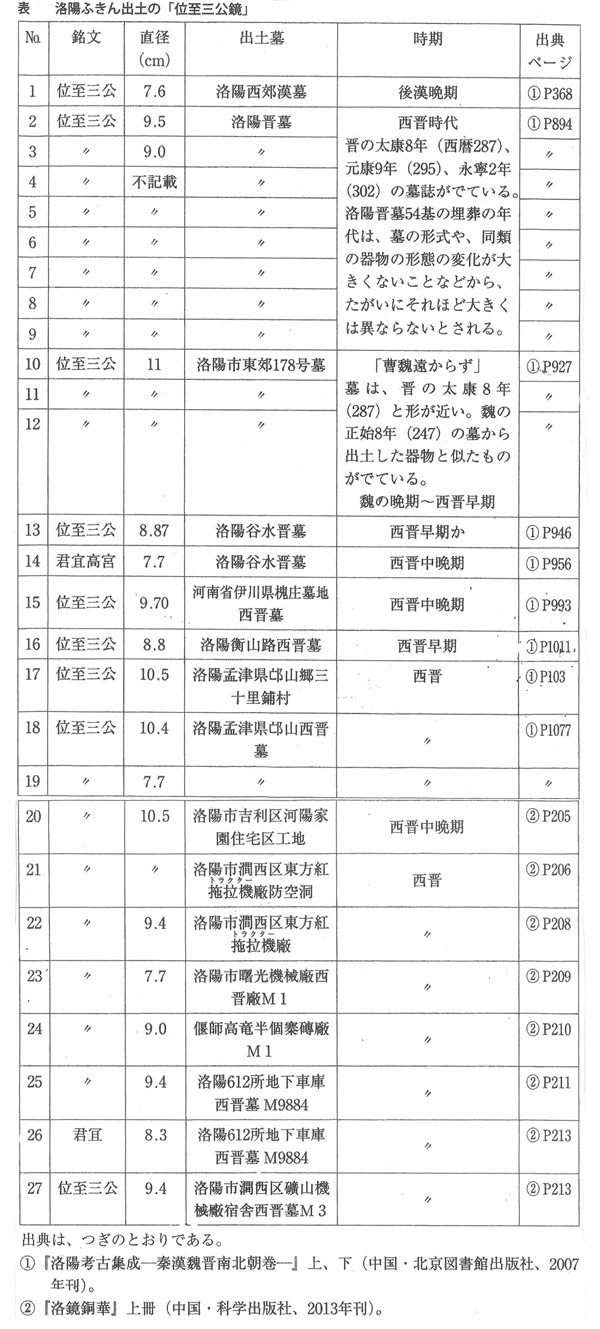
これらはすべて、魏や西晋の都であった洛陽ふきんから出土しているものである。
この表をみると、つぎのようなことが読みとれる。
(1)「位至三公鏡」は、後漢晩期に出現している。
(2)表の全部で二十七面の鏡のうち、後漢時代のものは、一面のみで、魏や西晋期のものが二十六面である。圧倒的に、魏や西晋(265年~316年)の時代のものが多い。No.2~9に記すように、「洛陽晋墓」のばあい、二十四面の出土鏡のうち、八面は、「位至三公鏡」である。表の「洛陽晋墓」のばあい、西暦287年(太康八)、295年(元康九)、302年(永寧二)の、三つの墓誌がでていることが注目される。いずれも、西晋時代のもので、西暦300年前後である。
(3)西晋よりもあとの、南北朝時代のものとしては、双頭竜鳳文鏡系の「宜官」銘翼虎文鏡が一面、北朝(386~581)の鏡として、洛陽市郊区岳家村から出土している。ただし、これは、出土年がしるされていない(この鏡のことは、『洛鏡銅華』および、『洛陽出土銅鏡』に記されている。)
「位至三公鏡」が、主として西晋時代のものであることは洛陽ふきん以外から出土した「位至三公鏡」についてもあてはまる。
いま、近藤喬一(たかいち)氏の論文「西晋の鏡」(『国立歴史民俗博物館研究報告』55集、2003年刊)にのっている「紀年墓聚成」の表にもとづくとき、年代の確定できる中国出土の「位至三公鏡」は、下表のとおりである。
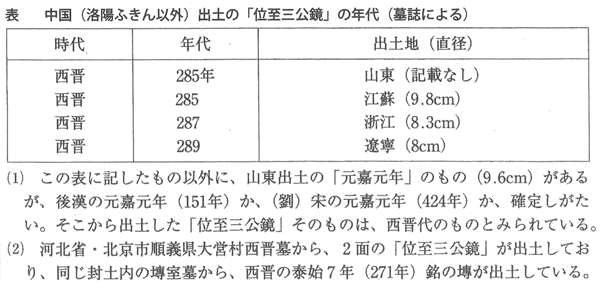
この表のものに、さきにのべた「洛陽晋墓」出土の八面の「位至三公鏡」を加えれば、年代のほぼ確定できる十二面の「位至三公鏡」のすべてが、西暦285年以後に埋納されたものといえる。すべて、西晋時代のものである。
注:280年に呉が滅ぶ。
表に示されている鏡の年代からみて、わが国から出土する「位至三公鏡」も、そのほとんどは、西暦285年以後ごろ、埋納されたもので、中国と日本との地域差、年代差を考えれば、西暦300年ごろ以後に埋納されたとみるのが穏当である。
そして、その「位至三公鏡」が、わが国においては、北九州を中心に分布している。
■わが国出土の「位至三公鏡」
「位至三公鏡」は、「三角縁神獣鏡」などと異なり、中国からも出土するが、わが国から出土する「位至三公鏡」については、つぎのようなことがいえる。
(1)中国で、おもに西晋時代に行なわれた「位至三公鏡」は、わが国では、福岡県・佐賀県を中心とする北九州から出土している。奈良県からは、確実な出土例がない。
(下表参照)
下表はクリックすると大きくなります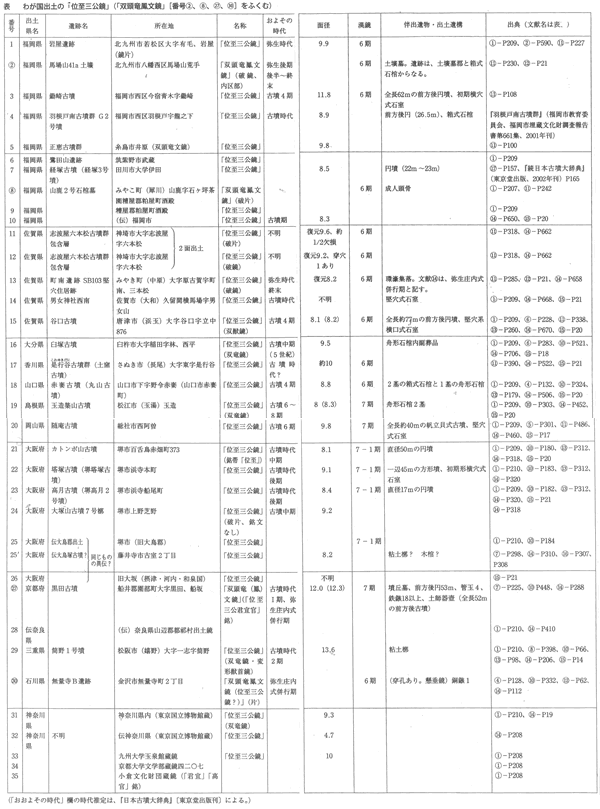
ただし、この表は「位至三公鏡」の祖型である「双頭竜鳳文鏡」をふくむ。
(2)「位至三公鏡」よりも、形式的にまえの時代の鏡(「長宜子孫」銘内行花文鏡など。そのなかに、魏代の鏡がふくまれているとみられる)も、北九州を中心に分布する。
(3)九州出土の「位至三公鏡」は、弥生時代の遺跡から出土しているものがあるが、九州以外の遺跡から出土した「位至三公鏡」は、まず、古墳時代の遺跡から出土している。九州以外の地の「位至三公鏡」は、九州方面からもたらされた伝世鏡か、あるいは、踏みかえし鏡であるにしても、九州よりもややのちの時代に埋納された傾向がみてとれる。
(4)これらのことから、魏のあとをうけつぐ西晋の西暦300年ごろまで、鏡の出土分布の中心は一貫して北九州にあったといえる。
(5)「位至三公鏡」よりも、形式的にも、出土状況も、あとの時代の「三角縁神獣鏡」などは、畿内、とくに奈良県を中心に分布する。(「位至三公鏡」は、おもに、庄内式土器の時代の遺物として出土し、「三角縁神獣鏡」は、おもに、そのあとの布留式土器の時代の遺物として出土する。)
(6)「三角縁神獣鏡」は、確実に三世紀の遺跡から出土例がない。四世紀の遺跡からの出土例がある。
(7)倭国は、西晋王朝と、外交関係があった。『日本書紀』の「神功皇后紀」に引用されているところによれば、西晋の『起居注』(西晋の皇帝の言行などの記録)に、西暦266年に倭の女王が晋に使をだしたことが記されている(この倭の女王は、卑弥呼のあとをついだ台与であろうといわれている)。『晋書』にも、この年、倭人が来て入貢したことが記されている。
倭の使が、外交関係のあった西晋の国から鏡をもたらしたとすれば、その鏡のなかには、「位至三公鏡」がふくまれていた可能性が大きい。
「位至三公鏡」などのこのような傾向からみれば、西暦300年近くまで、中国と外交交渉をもった倭は、九州に存在していたようにみえる。
■「位至三公鏡」の年代
さて、問題は、ここからである。
岡村秀典氏は、その著『三角縁神獣鏡の時代』(吉川弘文館、1999年刊)のなかで、つぎのようにのべる。
「漢代400年間の鏡は、文様と銘文の流行の推移をもとに、およそ50年前後の目盛りでつぎのように大きく七期に区分する。
漢鏡1期(前二世紀前半、前漢前期)
漢鏡2期(前二世紀後半、前漢中期前半)
漢鏡3期(前一世紀前半から中ごろ、前漢中期後半から後期前半)
漢鏡4期(前一世紀後葉から一世紀はじめ、前漢末から王莽代)
漢鏡5期(一世紀中ごろから後半、後漢前期)
漢鏡6期(二世紀前半、後漢中期)
漢鏡7期(二世紀後半から三世紀はじめ、後漢後期)
これに三世紀の三角縁神獣鏡をはじめとする魏鏡を加え、都合、漢・三国代の中国鏡を八期に大別することにする。」
ここで、さきに、「わが国出土の『位至三公鏡』」をまとめた前の表を、今一度ご覧いただきたい。
この前の表(わが国出土「位至三公鏡」)には、「漢鏡」の欄がある。そこに、「6期」とか「7期」とか、記されている。これは、右の岡村氏の規準により、七期の区分の、どれにあたるかを示したものである。
これによれば、わが国出土の「位至三公鏡」の年代は岡村氏の区分によるとき、つぎのようになっている。
「漢鏡6期」に属するもの………………………11例
「漢鏡7期」に属するもの…………………………7例
(うち、「7期」とのみあるもの3例。「7-1期」とあるもの4例)
これは、岡村氏のさきの区分の年代では、「後漢中期」から「後漢後期」までのものとなる。実年代で、「二世紀前半~三世紀はじめ」のものとなる。つまり、「卑弥呼遣使前」の年代となる。
ところが、これは、岡村秀典氏監訳の『洛陽銅鏡』に示されている十二面の「位至三公鏡」が、いずれも、「西晋」代のものとされているのと、あきらかに矛盾する。「西晋」代は、すでにのべたように、「西暦265~316年」であって、「卑弥呼没後」の年代であるからである。
なぜ、そんなことになるのか。
それは、岡村秀典氏が「景初四年鏡」をふくめ、「三角縁神獣鏡」の年代を、卑弥呼の時代のものと、きめてかかるからである。
わが国において、(位至三公鏡)の年代は、その出土遺跡や、その遺跡から出土する土器の形式からみて、(岡村氏の鏡の編年によっても、)「三角縁神獣鏡」の年代よりも、古く位置づけなければならない。
「三角縁神獣鏡」を、卑弥呼の時代のものと設定すれば、「位至三公鏡」を、それ以前の「後漢中期」から「後漢後期」のものと設定せざるをえないのである。
しかし、「事実」は、「位至三公鏡」は、おもに、西晋時代(265~316)のものである。「三角縁神獣鏡」は、そのあとの、主として、四世紀の、前方後円墳時代、布留式土器の時代のものなのである。
岡村秀典氏の鏡の年代論は、みずからの著書で示す年代と、監訳本のなかで示されている年代とのあいだで、矛盾している。監訳本のほうは、中国に原文がある。岡村氏も、大幅に内容を変更することができないのである。そのために、矛盾が生じている。
岡村秀典氏の著書の『三角縁神獣鏡の時代』のなかで示されている年代は、いろいろな異論があるなかでの、岡村氏の「推定値」「設定値」である。「西晋」時代のものとする監訳本のほうが、信頼度は高いとみられる。
■鉛同位体比の測定値
「位至三公鏡」(とくに、わが国出土の位至三公鏡)が、西晋時代以後のものとする考えをサポートする別のデータがある。「位至三公鏡」などの鉛同位体比の測定値である。
銅のなかにふくまれる鉛の同位体比によって、銅の生産地や、鏡の製作年代を、あるていどまで知ることができる。
鉛には、質量(乱暴にいえば地球上ではかったばあいの重さ)の異なるものがある。鉛は、四つの、質量の違う原子の混合物である。その混合比率(同位体比)が産出地によって異なる。鉛には、質量数が、204、206、207、208のものがある。つまり、四つの同位体(同じ元素に属する原子で、質量の違うもの)がある。鉱床の生成の時期によって、鉛の同位体の混合比率が異なる。いわば、黒、白、赤、青の四種の球があって、その混合比率が産出地によって異なるようなものである。
鉛同位体比研究の重要な意味は、青銅器に含まれる鉛の混合率の分析によって、青銅器の製作年代を、あるていど推定する手がかりが与えられることである。
とくに、質量数207の鉛と206の鉛との比(Pb-207/Pb-206 Pbは鉛の元素記号をあらわす)を横軸にとり、質量数208の鉛との比(Pb-208/Pb-206)を縦軸にとって、平面上にプロットすると、多くの青銅器がかなり整然と分類される。
それによって、青銀器の製作年代など考えることができる。
すなわち、古代の青銅器は、大きくはつぎの三つに分類される(下図参照)。
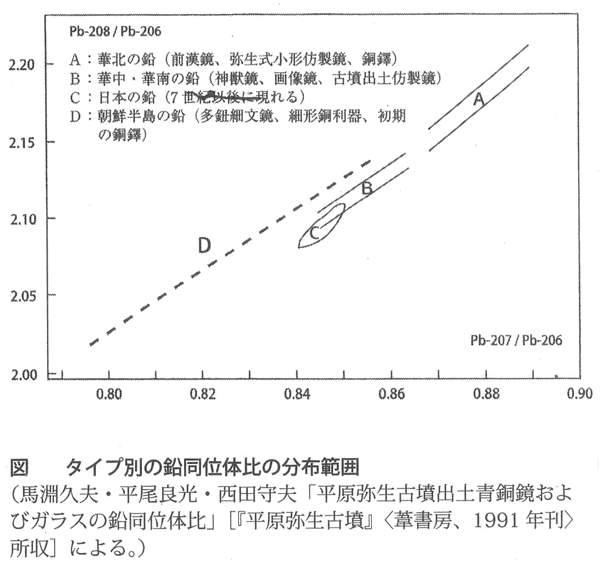
(1)「直線D」の上にほぼのるもの
もっとも古い時期のわが国出土の青銅器のデータはこの直線の上にほぼのる。「直線D」の上にのる青銅器またはその原料は、雲南省銅あるいは中国古代青銅器の銅が、燕の国を通じて、わが国に来た可能性がある。細形銅剣、細形銅矛、細形銅戈、多鈕細文鏡、菱環式銅鐸などは、「直線D」の上にのるグループに属する。
「直線D」の上にのる鉛を含む青銅器を、数多くの鉛同位対比の測定値を示した馬淵久夫氏(東京国立文化財研究所名誉研究員、岡山県くらしき作陽大学教授)らは、朝鮮半島の銅とするが、数理考古学者の新井宏氏は、くわしい根拠をあげて、雲南省銅あるいは中国古代青銅器銅とする(新井宏著『理系の視点からみた「考古学」の論争点』[大和書房、2007年刊]参照)。
(2)「領域A」に分布するもの
甕棺から出土する前漢・後漢式鏡、箱式石棺から出土する雲雷文「長宜子孫」銘内行花文鏡、小形仿製鏡第Ⅱ型、そして、広形銅矛、広形銅戈、近畿式、三遠式銅鐸などは、「領域A」に分布する。弥生時代の国産青銅器の多くも、この領域にはいる。
(3)「領域B」に分布するもの
三角縁神獣鏡をはじめ、古墳から出土する青銅鏡の大部分は「領域B」にはいる。
ほぼ、西暦300年ごろから400年ごろに築造されたとみられる前方後円墳から出土する鏡の多くは、この領域にはいる。
ところで、わが国で出土している「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「蝙蝠鉦座内行花文鏡」「夔鳳鏡(きほうきょう)」など、私が、「いわゆる西晋時代鏡」とよぶものの鉛同位体比は、つぎのような重要な持徴をもつ。
--------
★「いわゆる西晋時代鏡」にみられる鉛同位体比の特徴------------
(1)「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「蝙蝠鈕座内行花文鏡」「夔鳳鏡(きほうきょう)」などは、北九州を中心に分布する。
(2)これらの鏡は、中国では、おもに華北に分布する。洛陽を中心とする形で分布する。
(3)それにもかかわらず、わが国出土のこれらの鏡の鉛同位体比は、双頭竜鳳文鏡をふくめ、つぎの古墳時代に出土する「三角縁神獣鏡」や「画文帯神獣鏡」などに近い。図の「B領域」の付近に分布する。華中・華南産の銅が用いられている。華北の銅原料ではない。
つまりこれらの鏡は、それら以前の時期の中国北方系の特徴をもつ鏡と、それ以後の南方的特徴をもつ鏡との中間的・橋わたし的な特徴をもつ。文様は北方的で、原料は南方的である。
-------------------------------------------------------------
魏や晋の時代、中国の北方では、銅材が不足していた。
このことについて、中国の考古学者、徐苹芳氏は、「三国・両晋・南北朝の銅鏡」(王仲殊他著『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年刊所収)という文章のなかで、つぎのようにのべている。
「漢代以降、中国の主な銅鉱はすべて南方の長江流域にありました。三国時代、中国は南北に分裂していたので、魏の領域内では銅材が不足し、銅鏡の鋳造はその影響を受けざるを得ませんでした。魏の銅鏡鋳造があまり振るわなかったことによって、新たに鉄鏡の鋳造がうながされたのです。数多くの出土例から見ますと、鉄鏡は、後漢の後期に初めて出現し、後漢末から魏の時代にかけてさらに流行しました。ただしそれは、地域的には北方に限られておりました。これらの鉄鏡はすべて夔鳳鏡(きほうきょう)に属し、金や銀で文様を象嵌(ぞうがん)しているものもあり、極めて華麗なものでした。『太平御覧』〔巻七一七〕所引の『魏武帝の雑物を上(のぼす)すの疏(そ)』(安本註。ここは『上(たてまつ)る疏(そ)』と訳すべきか)によると、曹操が後漢の献帝に贈った品物の中に”金銀を象嵌した鉄鏡”が見えています。西晋時代にも鉄鏡は引き続き流行しました。洛陽の西晋墓出土の鉄鏡のその出土数は、位至三公鏡と内行花文鏡に次いで、三番目に位置しております。北京市順義、遼寧省の瀋陽、甘粛省の嘉峪関などの魏晋墓にも、すべて鉄鏡が副葬されていました。
銅材の欠乏によって、鉄鏡が西晋時代の一時期に北方に極めて流行したということは、きわめて注目に値する事実です。」
西暦280年に、華北の洛陽に都する西晋の国は、華中・華南の長江流域に存在した呉の国を、滅ぼす。呉の都は建業(南京)にあった。
その結果、華中・華南の銅が、華北に流れこみ、華北で、華中・華南の銅原料を用い、華北の文様をもつ青銅鏡がつくられるようになったとみられる。
西晋時代の「位至三公鏡」で、墓誌により年代の推定できるもの十二面が、すべて、西暦285年以後に埋納されたものであることは、すでに、前の表などでみたところである。
つまり、文様が、北方系、銅原料が華中・華南系であることは「西晋鏡」の大きな特徴である。「西晋鏡」は、おもに西暦280年以降に鋳造された可能性が大きい。それが、わが国に流れこんでいる。
■「西晋鏡」の鉛同位体比
つぎに、「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「蝙蝠鈕座長宜子孫銘内行花文鏡」「夔鳳鏡」など、おもに西晋時代に行なわれたとみられる鏡の、鉛同位体比について考える。
これらについては、もとのデータも、かかげておく(下の表参照)
下のグラフをみれば、いわゆる西晋鏡の鉛同位体比は、あきらかに、それ以前のものと違っている。
(下図はクリックすると大きくなります)
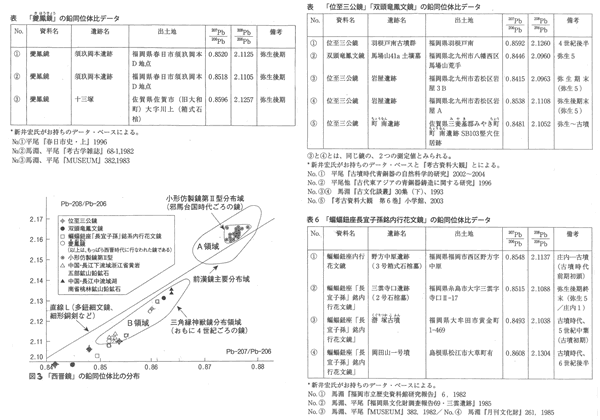
これらの鏡は、おもに、北部九州に分布しているにもかかわらず、つぎの時代に主流となる、「三角縁神獣鏡」の鉛同位体比の分布領域と、そうとうていど重なりあう。「三角縁神獣鏡」は、近畿を中心に分布する。
これらの鏡には、中国南方、長江(揚子江流域)などの「南中国」系の銅が用いられていると判断される。
上図から、つぎのようなことがいえよう。
「『位至三公鏡』は、『双頭竜鳳文鏡』の子孫的な鏡ではある。しかし、上図をみれば、わが国出土の『位至三公鏡』と『双頭竜鳳文鏡』とで、鉛同位体比の分布に、それほど差はない。」
以上のようにみてくると、岡村秀典氏の、「位至三公鏡」などを、卑弥呼遣使以前の、後漢の時代のものとする説は、自己矛盾をきたし、ほとんど完全に崩壊しているようにみえる。
国学院大学の教授であった考古学者、柳田康雄氏ものべている。
「近畿地方中央部(大阪・奈良県)では、いまだに弥生終末までに漢鏡の破片すら出土していない。岡村秀典(1999)の漢鏡の分布図では、漢鏡4期以後近畿に分布するようになっているが、これらは伝世して早期古墳以後に副葬されるのであり、弥生時代から当該地に分布するものではなく、東漸した北部九州人が持ち込んだものである。」(『邪馬台国新聞』第5号、2017年5月22日号。【全国邪馬台国連絡協議会事務局発行。】)
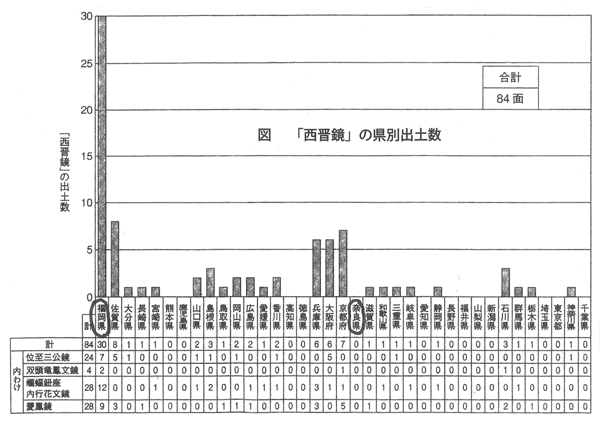
■銅の産地
鏡の銅原料問題について、いますこし議論しておこう。
岡村秀典氏は、『鏡が語る古代史』の218ページで、つぎのようにのべる。
「徐州は曹操の地盤である沛国譙(しょう)県[安徽省亳州(はくしゅう)市]に隣接し、三国代には魏の領域に属している。つとに富岡謙蔵が指摘しているように、三角縁神獣鏡には『銅は徐州に出で、師は洛陽に出づ』というめずらしい銘文があり、三角縁神獣鏡の制作をめぐっては、徐州と洛陽が焦点とりなっている。そこで、次にその銘文を検討してみよう。」
この岡村秀典氏の「徐州は、三国代には魏の領域に属している」という発言は、そのままみとめてよいのであろうか。後漢時代の「徐州剌史部」の全域が、三国時代の魏の領域になっているわけではない。
三国時代の、魏の領域になっている徐州に、銅を産出する地域は、ふくまれていたのか。西晋時代、東晋時代の徐州は、どの範囲をさすのか。
すでに、1992年に、中国の考古学者、王仲殊氏は、参考文献を示し、かなりくわしく論じている。
王仲殊氏はいう。(傍線を、引いたのは、安本。)
『銅出徐州』の銘文にある徐州とは、どの地を指しているのであるか、研究しなければならない。思うに徐州とは漢の武帝が置いた十三の刺史部〔州内の国政を視察・報告させるために中央から派遣した官の刺史が監督する地域〕の一つで、管轄地区はいまの江蘇省の長江以北および山東省の東南部の地区であった。後漢時代の徐州の治所〔郡役所のおかれこころ〕は剡(せん)(いまの山東省剡)にあり、魏時代に彭城(ぼうじょう)(いまの江蘇省徐州)にうつした。しかし、指摘しなければならないことは、いまの徐州一帯では、古代より銅を産出しない。『漢書』地理志、『続漢書』郡国志には、彭城およびその付近の地区には、漢代に鉄鉱があり、かつて鉄官〔鉄の産地で鋳造を担当した官〕がおかれたが、しかし銅鉱はない。『新唐書』地理志、『宋書』地理志などにも、徐州には鉄を産するといっているが、銅を産出するとはいっていない。
ただ、明・清時代の関係ある書籍になってようやく徐州付近に銅山があり、『旧く、かつて銅を産す』といっているが、実は根拠のないことである。清時代の雍正年間〔1723~1735年〕に徐州府に銅山県がおかれたが、しかし銅山といっても有名無実である。近代の実地踏査によれば、徐州利国駅〔山東省との境にある地〕でとれるおもな鉱石は赤鉄鉱であり、銅山島の南端にある鉄峰の赤鉄鉱の中に黄銅鉱がまざっていて、風雨によって緑色になっている。銅山の名のおこりはこのことからおこったのであろうが、しかし、採鉱のできるような銅鉱山ではない。要するに、上にのべたように、三国時代には、彭城およびその付近では決して銅を産することはなかった。しかし、もし『銅出徐州』の銘文中の徐州が、いまの江蘇省の長江以北と山東省東南部の広大な地区をさしているならば、いまの揚州市付近の江都、儀徴一帯には、古く銅鉱があり、漢代の初めに呉王の劉濞が鋳銭したところと伝えられている〔呉王劉濞は漢高祖劉邦の兄の子で、呉地方に封建され、王国内の予章郡で銅山を開発して、銅銭を鋳造した。後、呉楚七国の乱の中心になった人物でもある〕。当然、この地は長江に近く、鏡銘中の『徐州』にあたるかどうかについてはなお肯定しがたい。要するに、『銅出徐州』の銘文は比較的複雑な問題であり、さらにすすんだ研究がまたれる。少なくとも、鏡は『銅出徐州』の銘文があっても、必ずしも鋳鏡の銅が徐州にでたと説明するには十分でないし、また銅をとることのできない彭城およびその付近に銅がでたとは説明できない。」(王仲殊著『三角縁神獣鏡』「学生社。
1992年刊」)
つまり、こういうことである。
下の地図を、ご覧いただきたい。 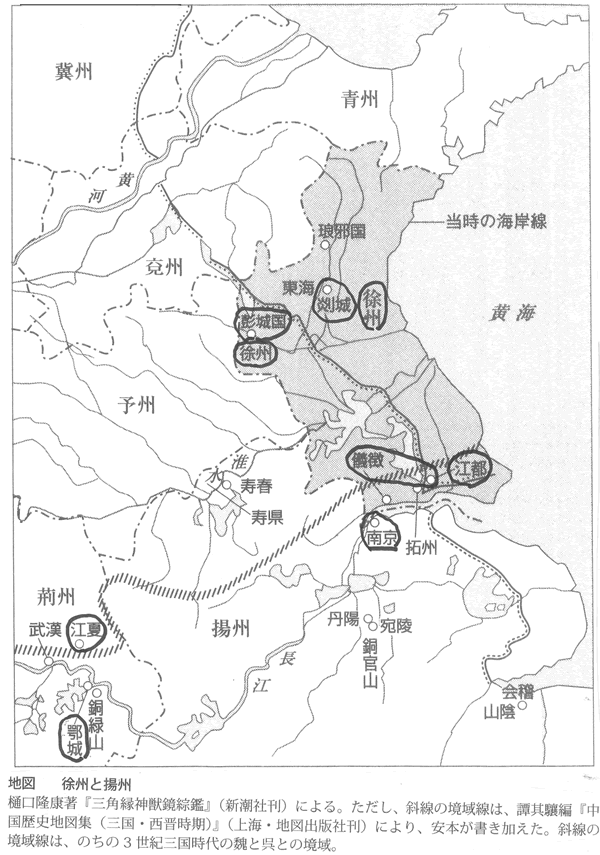
王仲殊氏の文章中にみえる「江都」「儀徴」などは、後漢の時代、「徐州剌史部」の監督する地域内にはいっていた。
この江都、儀徴には、古く銅鉱があった。
三国時代には、「江都」「儀徴」などの地域は、呉の領域内にあった。
西暦280年に、その呉を滅ぼした西晋の時代には、この地域は、とうぜん、西晋の領域内にあった。
したがって、この地域の銅は、北の洛陽にもってくることができた。「位至三公鏡」などの、いわゆる「西晋鏡」を、製造することができた。
そして、前のグラフ(「西晋鏡」の鉛同位体比の分布)、をみれば、いわゆる「西晋鏡」の銅原料は、中国の長江下流域の浙江省の黄岩五部鉱山の鉛鉱石のものに近いことがわかる。五部鉱山の鉛の測定値を中心とするような形で、「西晋鏡」の鉛同位体比の測定値が分布している。
ところが、「三角縁神獣鏡」になると、長江の長江中流域の、鄂州市に近い、湖南省桃林鉱山の鉛鉱石の測定値に近づくものが多くなっている(下図参照)。
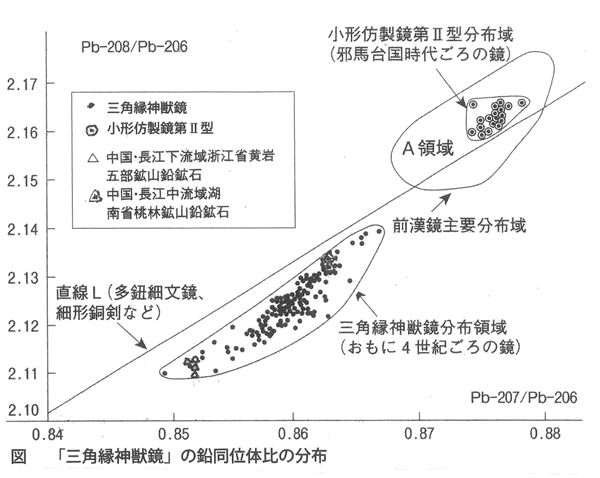
この鄂州市(鄂城)ふきんのことについては王仲殊氏は、つぎのように記す。
「江夏郡の武昌県は今の湖北省鄂城(地図参照)にあった。黄初二年(221年)に孫権が公安より都を鄂にうつして、武昌と改名し、同時に江夏、豫章、盧陵三郡の地をもって武昌郡とし、武昌県をその郡治としたが、まもなく、武昌郡を江夏郡と改称し、武昌県をやはり郡治としていた。黄龍元年(229年)、孫権はまた建業[南京]を都としたが、江夏郡の武昌を長江中流域の重要地として、上大将軍陸遜が太子孫登を輔けて武昌留守の事をつかさどったことは、この武昌の地の重要なことを示している。甘露元年(265年)、呉王孫皓はまた建業より都を武昌にうつしたが、臣民が反対したので、宝鼎元年(267年)にまたまた建業に帰らざるを得なかった。
(下図はクリックすると大きくなります)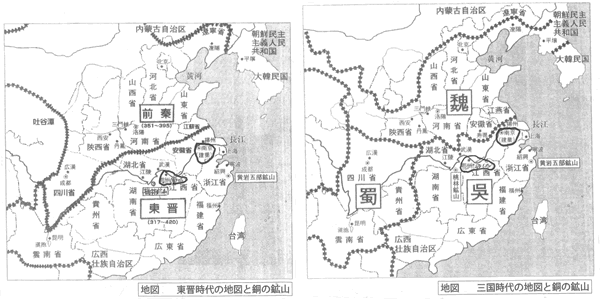
解放以来、鄂城及びその付近で、大量の三国時代の呉墓が発見され、多くの銅鏡が出土した。このことによって、人々は武昌がまた呉の銅鏡鋳造業の中心の一つであることを確信した。」(『三角縁神獣鏡』[学生社刊])
わが国で、「三角縁神獣鏡」が盛行したのは、おもに四世紀である。中国の王朝でいえば、東晋(317~420)の王朝にあたるころとみられる。
そのころ、中国の長江中流域の鄂州市ふきんの銅がわが国にもたらされている。
かつての呉や西晋、さらに東晋の人々が、大量の銅をもつて、わが国に渡ってきたものとみられる。
岡村秀典氏の議論の方法は、かつてだれかによって提出された説などを、すでに、その説には、さまざまな批判や反証が示されているにもかかわらず、そのような批判や反証のほとんどにふれず、答えないまま、自説の論拠として再提出し、強調しまとめるという方法がめだつ。
大和書房の社長で、古代史研究家であり、かつ、雑誌『東アジアの古代文化』を編集された大和岩雄は、「『卑弥呼の墓』と『卑弥呼の鏡』」(『東アジアの古代文化』96号、1998年夏号)という文章のなかで、三角縁神獣鏡についての、いわゆる「特鋳説」を説く岡村秀典氏の文章をつぎのように批判し、あきれておられる。
「三角縁神獣鏡が中国本土から一面も出土していないことと、『魏志』倭人伝に『銅鏡百枚』が卑弥呼の『好物』と書かれていることから、卑弥呼が特別に注文した特注(鋳)品、つまり三角縁神獣鏡は『卑弥呼の鏡』という(岡村秀典氏らの)説がある。」
「魏の朝廷では、激論の末、海のかなたからはるばる朝貢してきた卑弥呼にさまざまな引き出物を与えることを決定し、『急ぎ』特注品を『数ヶ月』で調製し、景初三年に魏の都に来た倭使に渡し、さらに正始元年には三角縁神獣鏡は『厳重に箱詰めされ、まとまって倭にもたらされた』と(岡村秀典氏は)書く。岡村の小説風文章は問題である。魏の朝廷の激論や、特注品の数ケ月での製作、箱詰めにしての発送などは、文献史料上の根拠はまったくない想像である。」
ふつうの人が、おかしい、と思う感覚を、専門家が、おかしいとは、思わなくなってしまっているのである。
政治家ではない京都大学の教授が、トランプ大統領なみに、「ファクトチェック(事実確認)」を大幅に必要とするような文章を書いてどうするのか。
『鏡が語る古代史』の「あとがき」に京都大学人文科学研究所の「中国古鏡の研究」の共同研究班で、鏡の銘文を読んだことが記されている。
ふしぎに思う。共同研究班の人々のなかに、たとえば、「青祥」や「黄祥」の意味について、きちんと辞書を引いて。たしかめる人は、いなかったのであろうか。「位至三公鏡」などは、中国で後漢代よりも、むしろ、西晋代に流行した鏡である。それを、岡村氏のいう「漢鏡」(後漢時代の鏡)の範囲で考えることに、疑問をもつ人は、いなかったのであろうか。病気は重い。
中国社会科学院考古学研究所の所長をされた考古学者、徐苹芳氏はのべる。
「考古学的には、魏および西晋の時代、中国の北方で流行した銅鏡は明らかに、方格規矩鏡・内行花文鏡・獣首鏡、夔鳳鏡(きほうきょう)・盤竜鏡・双頭竜鳳文鏡・位至三公鏡・鳥文鏡などです。
従って、邪馬台国が魏と西晋から獲得した銅鏡は、いま挙げた一連の銅鏡の範囲を越えるものではなかったと言えます。とりわけ方格規矩鏡・内行花文鏡・夔鳳鏡・獣首鏡・至位三公鏡、以上の五種類のものである可能性が強いのです。位至三公鏡は、魏の時代(220~265)に北方地域で新しく起こったものでして、西晋時代(365~316)に大層流行しましたが、呉と西晋時代の南方においては、さほど流行してはいなかったのです。日本で出土する位至三公鏡は、その型式と文様からして、魏と西晋時代に北方で流行した位至三公鏡と同じですから、これは魏と西晋の時代に中国の北方からしか輸入できなかったものと考えられます。」(『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年刊。傍線は安本。以下も同じ)
------------
双頭竜鳳文鏡と位至三公鏡-------------
①双頭竜鳳文鏡
一つの体躯の両端に竜または鳳凰の頭がついている。これを一単位の文様とするとき、二単位(二体躯分)が、左右に描かれている。
一単位の二つの頭がともに竜頭のこともあれば、一方が竜頭、一方が鳳頭のこともある。「双頭・竜鳳・文鏡」と区切るべきである。
文様の基本は、S字形または逆S字形で、点対称。
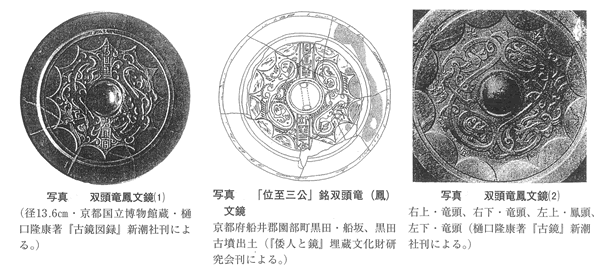
中国で、時代があとの南北朝時代(439~589)の双頭竜鳳文鏡系の鏡も出土している。 
②位至三公鏡
位至三公鏡は、「位は三公(最高の位の三つの官職)に至る」という銘のある鏡である。鈕をはさんで、上下に「位至」と「三公」の銘文をいれ、内区を二分する。
左と右とに、双頭の獣の文様を配する。獣の文様は、ほとんど獣にみえないことがある。小形の鏡である。中国では、後漢末にあらわれるが、おもに西晋時代に盛行した。
双頭竜鳳文鏡の系統の鏡である。双頭竜鳳文鏡にくらべ、獣の文様がくずれている。
また、双頭竜鳳文鏡では、主文様の外がわに連弧文があるが、位至三公鏡では、連弧文がないのがふつうである。
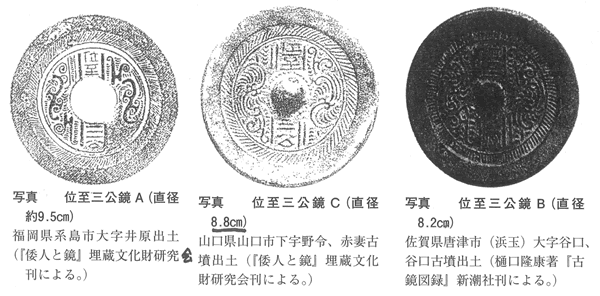
---------------------------------------
中国、洛陽の西晋(265~316)時代の墓(洛陽晋墓)から出土した「位至三公鏡」。
この墓からは、285年の墓誌が出ている。西暦300年前後、卑弥呼よりも、あとの時代である。そして「三角縁神獣鏡」は「位至三公鏡」よりも、あとの時代の鏡である。
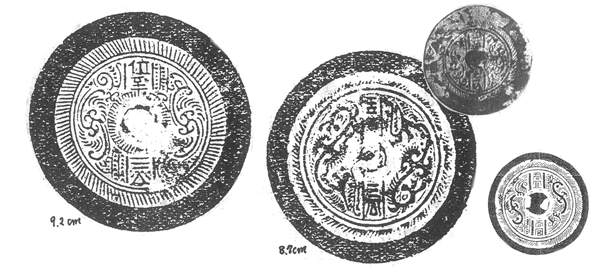
わが国出土の「位至三公鏡」は中国の後漢時代の「位至三公鏡」よりも、西晋時代の「位至三公鏡」に近い。とくに鉛同位体比の測定結果は、わが国出土の「位至三公鏡」が、西晋時代鏡であることを、かなり決定的に示しているといえよう。
岡村秀典氏は「三角縁神獣鏡=特鋳説」をとる。
『毎日新聞』2018年1月18日(木)夕刊(伊藤和史氏)
今どきの歴史「三角縁神獣鏡製作地論争 画期的『国産説』の登場」鈴木勉・工芸文化研究所所長の説の紹介。
魏志倭人伝によれば、3世紀、卑弥呼は魏に使書を送り、贈り物をもらった。そのリストに「銅鏡百枚」とあり、魏の年号入りの品も含むこの鏡を指すと考えるのだ。
近畿地方が分布の中心なので邪馬台国畿内説の論拠にもなるが、重大な弱点がある。100枚どころか500枚以上も見つかっている上、肝心の中国から出てこないのだ。「倭の好む鏡を魏が特別につくって贈った。だから中国にない」とする「特鋳説」があるが、考古学の常道にないアクロバット的学説だろう。」







