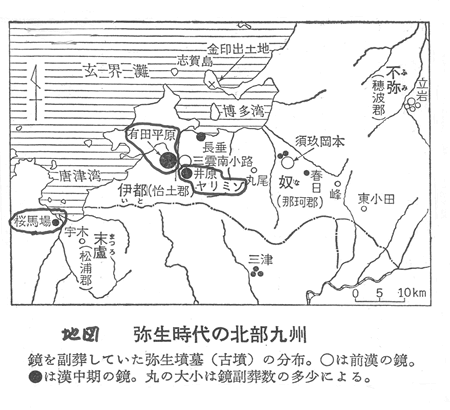■倭国の大乱の年代を記した文献
『魏志倭人伝』に、つぎのような文章がある。
「(倭)国は、もと男子をもって王としていた。ところが、七、八十年まえに倭は乱れ、国々は長年のあいだ攻撃しあった。そこで、(国々は、相談の結果、)ともに一人の女子をたてて王とした。(彼女は、)名を卑弥呼という。鬼道につかえ、よく人心を惑わしていた。すでに成年に達していたが、夫をもたなかった。(彼女には、)弟がいて、政治を補佐している。」
また、『後漢書』の「倭伝」は、つぎのように記している。
「(後漢末の)桓帝(かんてい)、霊帝(れいてい)の治世(146~189)に、倭国は大いに乱れ、たがいに攻めあい、何年ものあいだ主のいない状態であった。(ときに、)一人の女子がいた。その名を卑弥呼という。すでに成年に達していたが、未婚で、鬼道につかえて、よく人々を惑わしていた。そこでともに(倭国の人々は、卑弥呼を)立てて王とした。」
さらに、『梁書(りょうしょ)』にも、つぎのようにある。
「漢の霊帝の光和(178~183)年中に、倭国は乱れて、たがいに攻めあって、年を歴(へ)た。そして、卑弥呼という一人の女子をともに立てて王とした。」
なお、『梁書』は、唐の太宗の勅を奉じて姚思廉(ようしれん)と魏徴(ぎちょう)が撰したものである。636年に成立している。
『魏志倭人伝』の文章と、『後漢書』の「倭伝」や『梁書』の文章とをみくらべるならば、ここの部分の文章が、大略同じ内容を伝えていることがわかる。
ただ、『魏志倭人伝』で「七、八十年まえに」となっているところが、『後漢書』の「倭伝」では「桓帝・霊帝の治世に」とおきかわっている。『梁書』では「光和年中」におきかわっている。
これはなぜであろうか。
『後漢書』や『梁書』は、『魏志倭人伝』の筆者がもっていない情報をもっていて、このように書いたのであろうか。
じつは、かならずしもそうとはいえない。
後漢は、魏・呉・蜀の三国時代よりも、まえの時代の王朝である(下図参照)。
しかし、史書の成立の時期は、逆である。『三国志』のほうが先に成立して、『後漢書』のほうが、あとで成立している。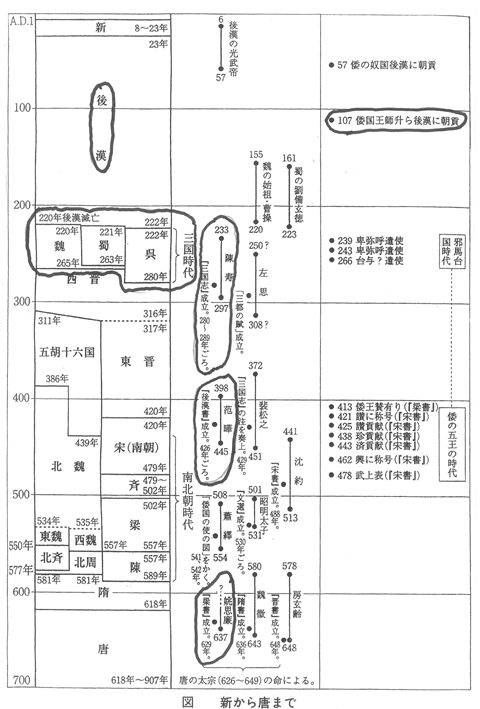
『三国志』の成立は、284年前後とみられる。『後漢書』のほうは、426年ごろの成立とみられている。さらに、『梁書』は、636年の成立である。
『後漢書』のほうが、『三国志』よりも、百年以上、あとで成立している。『梁書』は、『三国志』よりも、三百年以上あとに成立している。
したがって、『後漢書』の筆者の范曄(はんよう)は、陳寿の書いた『三国志』の文章を参考にして書いた可能性がある。
■「住七八十年」の意味
ところで、『魏志倭人伝』のさきの文章の、「七、八十年まえに」と現代日本文に訳したところは、原文では、つぎのようになっている。
「住七八十年」
じつは、この「住」の字の理解には、つぎの二とおりの説がある。
(1)諸橋轍次著『大漢和辞典』(大修館書店刊)に、「(住は、)往に通ず」とあるように、「住(ゆくこと)」と読み、「七、八十年さかのぼると」「七、八十年まえに」の意味であるとする。東京大学の教授であった日本史家、井上光貞は、『日本の歴史1 神話から歴史へ』(中央公論社刊、1965年)のなかで、この部分を、「七、八十年まえ」と訳す。さらに、つぎのように記している。
「『いまから七、八十年まえ』というのは倭人伝の筆者が、ある時点を起点としてかぞえた年数で、いつを起点にしたかははっきりしないが、かりに卑弥呼の死んだ240年代の末を起点に逆算してみると二世紀の160、170年代ということになる。」
東洋史家の榎一雄・植村清二らの見解も、井上光貞の見解とほぼ同じである。ただ、榎一雄・植村清二は、「住」の字は、「往」の字の誤りとする。
(2)東京大学の教授であった中国語学者、藤堂明保は、『倭国伝』(学習研究社、1965年刊)のなかで「住七八十年」の部分を、つぎのように読んでいる。
「住(とど)まること七、八十年」
「もとは、男を王となっていたのは七、八十年間であったが国は乱れて、攻め合いが何年も続いた。」
宮崎公立大学の教授であった奥野正男氏は、この藤堂の読み方を支持しておられる。
■「桓帝(かんてい)・霊帝(れいてい)の治世に」は、机上の計算か
『魏志倭人伝』のなかの「今」は、張政が、倭国に滞在したころの、あるいは報告書を提出したころの、西暦250年前後を指すことが考えられる。
そこから、七、八十年さかのぼると、倭国の大乱があったのは、西暦170年~180年ごろのこととなる。
ところが、『後漢書』や『梁書』は、『魏志倭人伝』よりも、だいぶのちの時代に成立している。『後漢書』の筆者、范曄(はんよう)は、原文にあるように、七、八十年まえ、と書くわけにはいかない。
そこで、范曄は、机上で計算して、桓帝・霊帝の治世(146~189)にと、書きあらためたのではないか。
『梁書』の編者、姚思廉(ようしれん)らは、それを、さらに、霊帝の光和中(178~183)にしぼったのではないか。
幕末~明治時代の歴史家、菅政友(かんまさとも)なども、私の考えに近い考えをのべている。
もちろん、『後漢書』や、『梁書』の筆者が、別に、『魏志倭人伝』以外の情報をもっていた可能性も、完全には、否定できないが。
■長大---長大(ひととなる)
『魏志倭人伝』につぎの文がある。
卑弥呼の年齢について述べた個所である。
「年、已(すで)に長大なれども、夫壻(ふせい)無し。」
この文のなかの「年已(すで)に長大なれども」とはどういう意味であろう。なんとなく「おばあさんであるが」という意味のような印象を受ける。「おばあさん」とはいかないまでも、「年をとっても」などと翻訳されていることが多い。
しかし、ここの「長大」はそのような意味ではない。「成人したけれども」あるいは「大人になったけれども」の意味である。それは、日本の古典の使用例からも、中国の文献の使用例からも、そう言える。
日本文献の例からあげよう。
わが国の文献で、「長大」ということばがはじめてみえるのは、『上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)』である。『上宮聖徳法王帝説』は、最古の聖徳太子伝である。そこには、つぎのようにある。
「上宮王(かみつみやのおほきみ)[聖徳太子]産生(あ)れます。王の命(おほきみのみこと)、幼(いときな)く少(わか)くして聡敏(さと)く智(さとり)有(あ)り。長大(ひととな)る時に至りて、一時(ひととき)に八人(やたり)の白(まを)す言(こと)を聞きて其の理(ことわり)を弁(さだ)む。」(岩波書店刊、日本思想大系2『聖徳太子集』による。原文は漢文。校注および訓(よ)みは、家永三郎・築島裕氏による。)
ここでは、「長大」は、「長大(ひととな)る」と読まれている。そして、「長大(ひととな)る」について、『聖徳太子集』の補注で、つぎのように説明されている。
「成実論[じょうじつろん](仏教書。一切皆空を説く)天長[てんちょう](824~834年)点(漢文を訓読するために原文に書き加えた文字・符号)に『長大』を『人トナラシメタテマツレリ』と訓じている。ヒトトナルは成人となるの意で、この名詞形はヒトトナリである。」
『上宮聖徳法王帝説』は、成立年代の異なる五つの部分からなる。「長大」をふくむ部分は、奈良時代の成立とみられる。『古事記』『日本書紀』と、ほぼ同じ時代の成立である。
「長大」は、「老人になる」というような意味ではなく、「成人となる」「成年に達する」意味で用いられている。
なお、『日本書紀』の「推古天皇紀」では、さきの『上宮聖徳法王帝説』の「一時(ひととき)に八人(やたり)の白(まを)す言(こと)を聞きて」のところを、「壮(をとこさかり)に及びて、一(ひとたび)に十人(とたり)の訴(うたへ)を聞(き)きたまひて」と記している。
「長大」を、「壮(男ざかり)」にあたるとしている。
「長大」という言葉がつぎに日本文献にあらわれるのは、奈良時代に成立した藤原氏の人物伝『藤氏家伝(とうしかでん)』である。『藤氏家伝』の「武智麻呂伝(むちまろでん)」に、「年長大(としひととな)るに及(いた)りて、小節(せうせつ)に繋(かか)らず」(年及長大、不繋小節)とある。
この「長大」も、「成人するにおよんで」の意味である。
最終的には、平安時代の810年~824年(弘仁年間)に成立したとみられる『日本霊異記(にほんりょういき)』に、つぎのような使用例がある。
「(産まれた児が、)長大(ひととな)り、年十有余(としとをあまり)の頃(ころほひ)に、」 (上巻、第三。この文では成人して、十有余のころに、とのべている。)
「(子牛が、)長大(ひととな)りて後に、」(上巻、第二十。これは、子牛が車を引くことができるていどに大きくなった、ことをのべているところにみえる。)
「長大(ひととな)るに随(したが)ひて、面容端正(かほかたちきらぎら)し。」(中巻、第三十一。)
「(子牛が、)長大(ひととな)り、寺の産業(なりはひ)に馳(は)せ使(つか)はれ、」(中巻、第三十二巻。)
「(女の子が、)八箇月(やつき)を経(へ)て俄(にはか)ならずして長大(ひととな)る。」(下巻、第十九。八ヵ月のあいだに、徐々に大人になってしまった怪異をのべる。)
西暦927年に撰進された律令の施行細則である『延喜式』にも、「長大」の使用例がある。『延喜式』の巻第五の「斎宮(いつきのみや)」に、つぎの文がある。
「几(およそ)斎王(いつきのみこ)の国に到(いた)るの日は、度会郡(わたらいのこほり)二見郷(ふたみのさと)の磯部氏(いそべうぢ)の童男(どうなん)を取り、卜(ぼく)して戸座(へざ)と爲(な)し、其の炬火(ひたき)には当郡(たうぐん)の童女(どうにょ)を取り、卜(ぼく)して用(もち)ひよ。但し喪(も)に遭(あ)ひ及(また)長大(ひととな)らば、すなはち替(か)へよ。」
吉川弘文館刊の『国史大系』では、この文の原文は、つぎのようになっている。
「几斎王到国之日。取度会郡二見郷磯部氏童男。卜爲戸座。其炬火取当郡童女卜用。但遭喪及長大即替之。」
ここの文の意味は、「童男童女が大人になる」という意味である。したがって『延喜式』の「長大」の訓読みの「ひととなる(大人になる)」はきわめて的確である。
このような訓(よ)みの伝統は、その後も引きつがれる。『今昔物語』巻第一の第三話の「太子、年已(すで)に長大に成給(なりたま)ひぬ」も同じ意味である。この文は、つぎのような文脈のなかで用いられている。
「今は昔、浄飯(じょうぼん)王の御子悉達(しつだ)太子は十七歳におなりになったので、父の王は大臣たちを集めてお話し合いになり、『太子はもうりっぱにおとなにおなりだ(太子、年已(すで)に長大に成給(なりたま)ひぬ)。そこで妃(きさき)を奉ろうと思うが、理想的な妃としては誰がいるだろうか。』」
つまり、「長大」は「妃をめとるほど大人になったこと」を意味している。
『平家物語』巻六のつぎの文の「長大」も同じ意味である。
「かひがひしう廿余年養育す。ようよう長大するままに、ちからも世にすぐれてつよく・・・。」
この文は二十余年の養育の結果、木曾義仲が大人になったことを言っている。
このような使い方は『三国志』のばあいも同じである。「東夷伝」のなかで拾ってみても、つぎのような例がある。
「今の高句麗王の曾祖(父)の、名は宮(きゅう)なり。生まれて能(よ)く目を開き視(み)る。其(そ)の国の人之(これ)を悪(にく)む。長大するに及び、果(は)たして凶虐にして、数数(しばしば)寇鈔(こうしょう)し、[そのために]国、残破せらる。」(「高句麗伝」)
この文の「長大」も「成長する」「大人になる」の意味である。
『三国志』の「東夷伝」の「高句麗伝」ではつぎのような例もある。
高句麗の習俗では、婚姻が成立すると、婿は娘の家の妻屋(つまや)に住み、子供が生まれてその子が「長大」になると、妻をつれて自分の家に帰る。
また、『三国志』の「呉志」の第七の「諸葛謹伝」に、つぎのような文がある。
「(曹)丕(ひ)の業をつぐに逮(およ)ぶ。年己(すで)に長大。」
曹操が西暦220年になくなる。長男の曹丕が、そのあとをつぎ、やがて魏の初代の皇帝に即位するのも220年のことであった。このとき、曹丕の年齢は34歳である。(曹丕は、226年に、40歳でなくなっている。)
以上内外の文献はいずれも「長大」の意味が「おじいさんやおばあさんになって」の意味や「年をとって」の意味ではないことを示している。単に「成長して」「成人して」「大人になって」の意味で用いられている。
もともと、「長」には、「長(ちょう)ず」「成長する」「大人になる」の意味がある。
『日本書紀』の「神武天皇紀」に、つぎのような文がある。
「長(ひととな)りたまひて日向国(ひむかのくに)の吾田邑(あたむら)の吾平津媛(あひらつひめ)を娶(ま)きて、妃(みめ)としたまふ。」
また、『日本書紀』の「神代上」につぎのような文がある。
「素戔鳴尊(すさのをのみこと)、年(とし)已(すで)に長(お)いたり。復(また)、八握鬚髯(やつかひげ)生(お)ひたり。しかれども、天下(あめのした)を治(しら)さず。」
この文の「年(とし)已(すで)に長(お)いたり。」も、「おじいさんになった。」の意味ではなく、「成人した。」の意味とみられる。
■後漢末、遼東には、公孫氏が蟠踞(ばんきょ)していた
後漢末から三国時代にかけての遼東の豪族に、公孫氏なるものがいた。遼東襄平(じょうへい)[遼寧省遼陽市]出身の公孫度(こうそんど)にはじまる。公孫度は、はじめ、玄菟郡(げんとぐん)の役人となり、のちに、遼東の太守(郡の長官)となった。
公孫度は、東は高句麗、西は鳥桓(うがん)、南は海を渡って山東の東萊(とうらい)の諸県を討って、大いに領土をひろげた(下図参照)。
190年、南満州に独立して、遼東侯、平州牧と称した。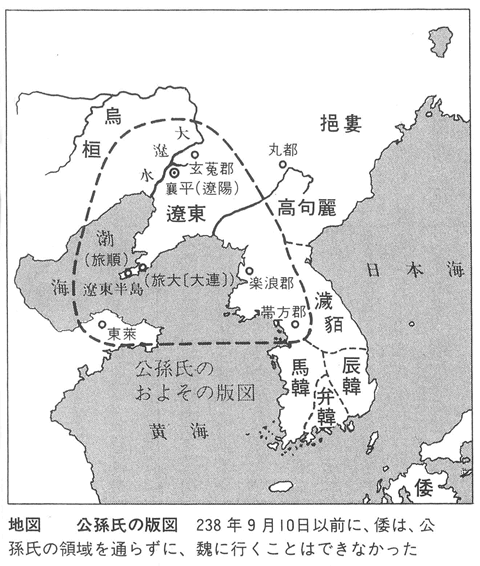
204年に、公孫度は病死し、子の公孫康(こうそんこう)があとをついだ。公孫康は、204年に、楽浪郡をにぎった。
公孫氏は、楽浪郡をわけ、慈悲嶺山脈をさかいとして、その北を楽浪郡、南を帯方郡とした。
207年、公孫康は、遼東に逃れてきた袁尚(えんしょう)・袁煕(えんき)[後漢末の群雄の一人である袁紹の子]を斬って、その首を、魏の曹操に献じ、襄平侯に封ぜられ、左将軍を拝した。
221年、公孫康が死ぬと、弟の公孫恭(こうそんきょう)が立ったが、康の子の公孫淵(在位228~328)が成長すると、恭を脅して、位をうばった。魏は淵に来朝を命じたが、淵は、これに応じなかった。自立して燕王を称し、百官を設け、年号をたてた。
そのころ、魏は、諸葛亮孔明が病死し、蜀からの脅威が除かれていた。
238年、春正月、魏の明帝は、詔勅をくだし、司馬懿仲達に命じて、遼東を攻撃させた。軍は、6月に遼東にいたり、9月10日、司馬懿仲達は、襄平において公孫淵を包囲し、大いにこれを撃ち破った。司馬懿仲達は、公孫淵父子の首を斬って、その首を、洛陽に送りとどけた。遼東の強力な地方政権は滅亡した。魏は、遼東郡、玄菟郡、楽浪郡、帯方郡の四郡をことごとく平定した。
238年12月8日、明帝は、病の床についた。
239年の正月1日に、司馬懿仲達が、遼東から帰還した。明帝は、司馬懿仲達を、寝室にいれ、後事をたくした後、死去した。時に三十六歳であった[宋の裴松之(はいしょうし)は、明帝はなくなったとき、三十四歳のはずであるという]。
現在の『三国志』の刊本の記すように、倭の使が魏に派遣されたのが、最初二年の6月であるとすれば、遼東の公孫淵と、魏の司馬懿仲達との戦いのまっ最中に派遣されたことになる。また、明帝は、12月の8日以後は病気であったから、おそらくは、病気のまっただ中であったころに、倭の女王に、詔書を下したことになる。これはやはり不自然である。
現在の『三国志』の刊本は、十二世紀以後に印刷されたものである。
現在、福岡県筑紫郡大宰府町の、大宰府天満宮に伝来する張楚金撰、雍公叡注の『翰苑』が存在する。平安初期九世紀に書写され、そのまま今日に伝来したものである。張楚金は、唐代の人で、高宗(在位649~683)につかえた人である。また、雍公叡の注は、唐の太和年間(827~835)以前の成立といわれている。
この『翰苑』は、『魏志』の文を引き、倭の女王が使を遣わしたのは、「景初三年」であったと、はっきり記している。すなわち、つぎのとおりである。
「魏志に曰く、景初三年に、倭の女王、大夫難升未利(なんしょうみり)等を遣わし、男の生口四人・女の生口六人・斑布二疋二尺を献ず。詔して以て親魏倭王と為し、金印紫綬(しじゅ)を仮す。」(読み下し文は、竹内理三による。)
さらに、『梁書』「倭伝」は、女王の使のあったのは、最初三年で、公孫淵が誅せられたあとであると記している。
「魏の景初三年に到り、公孫淵が誅(ちゅう)せられた後、卑弥呼ははじめて使を遣わして朝貢した。魏はもって親魏(倭)王となし、金印紫綬を仮した。」
『北史』も、『太平御覧』も、公孫氏が誅せられたあと、と記している。
以上のように見てくると、女王卑弥呼が、魏へ使をだしたのは、「景初三(239)年」が正しく、『三国志』の現行刊本の「景初二年」は、誤刻であるように思われる。
『三国志』の「魏書」の「公孫度・公孫康・公孫淵・公孫恭伝」につぎのような文がある。
「初平元年(190)、公孫度は、中原の騒乱を知ると、目にかけていた官史の柳毅(りゅうき)や陽義(ようぎ)らに向って、『漢(後漢)の命運は絶えんとしている。いまこそ、諸君らとともに、王の位を狙うべきだ。』と語った。」
「最初、公孫度が中平六年(189)に遼東を占拠して以来、公孫淵に至るまで三代を経過し、[景初二年(238)]まで、)あわせて五十年で、(公孫氏は、)滅亡したのであった。」
つまり、後漢末の中国や、倭国において、動乱がみられたころ、遼東において、公孫氏が、台頭・蟠踞(ばんきょ)していた。
その間の、倭国の状況は、中国王朝によく伝わらない状態であったとみられる。
『三国志』の『魏志』の「東夷伝」の序文のところで、陳寿は、つぎのようにも記している。
「(東方の地域については、)公孫淵(こうそんえん)は、父祖三代にわたって遼東の地を領有した。そのため、(中国の)天子はそのあたりを絶域(ぜついき)[中国と直接関係を持たない地域]とみなし、海のかなたのこととして放置した。その結果、東夷との接触は断たれ、中国の地へ使者のやってくることも不可能となった。」
公孫氏が、滅ぼされたので、倭の卑弥呼は、魏へ使をつかわしたのであった。
奴国が滅び、卑弥呼が、王になったのは、公孫氏が遼東に割拠した五十年間のうちにあったとみられるが、正確にいつであるかは、情報が不足していてわからないというべきである。
以上みてきたように、中国の後漢は、桓帝、霊帝のころから、ごたごたしはじめ、結局、西暦220年に、後漢は、滅亡している。そして、魏の国が成立する。
それと、軌をひとしくするように、倭国も、桓帝、霊帝の170年~180年ごろから乱れはじめている。
そして、西暦220年前後に、新しく女王卑弥呼が立ち、倭人の国をまとめたようにみえる。
金印奴国が滅亡したのが、いつであるかは、はっきりしない。しかし、170年~220年ごろの、四、五十年のあいだに滅亡したとみてほぼよいであろう。
このようにして、後漢のバックアップをうけた奴国の時代から、魏の国のバックアップをうけた邪馬台女王国の時代に推移したと考えられるのである。
■卑弥呼は、倭国大乱のときに王になったのか?
『後漢書』「倭伝」の記事を、もう一度みてみる。
「桓(かん)[帝]、霊(れい)[帝]の間、倭国大いに乱れ、こもごもあい攻伐すること歴年、主なし。一女子あり。名を卑弥呼(ひめこ)という。年長ずるも[長(ひととなる)]嫁(か)せず。鬼神の道に事(つか)えて、よく妖(よう)をもって衆(しゅう)をまどわす。ここにおいて、(倭国の人々は、卑弥呼を)ともに立てて王となす。」
この文章を、よくみてみよう。
大乱のあったときに、卑弥呼が、王になったとは、記されていない。
大乱と、卑弥呼が王になるまでのあいだに、「あい攻伐すること歴年」という文がはいっているのである。
(『魏志倭人伝』でも、「相攻伐歴年[あい攻伐すること歴年]」と、『後漢書』と同じ文を用いている)
ここで歴(へ)た年が、五、六年なのか、二、三十年なのか、四、五十年なのか、わからないのである。
もし、倭国大乱がはじまったころに、あるいは、それからそれほど年数を歴ないうちに、卑弥呼が王になったと理解すれば、卑弥呼の在位期間が長くなりすぎる。
■邪馬台国勃興の時期
私は、つぎの三つは、その時期が、大きくみれば、重なると考える。
(1)中国で、後漢王朝から魏王朝へと移り変わる時期
後漢が滅亡し、魏が建国したのは、西暦220年である。しかし、後漢の末の桓帝(在位146~167)、霊帝(168~189)のころは、すでに天下騒然として、後漢衰亡の兆があった。桓帝の時代は、外戚・宦官・党人の政争に終始した。学者や学生が、朋党をくみそしりあい、さらに、儒学徒と宦官とが、反目対立した。桓帝の末期の166年には、桓帝が宦官に加担して、党人の中心人物李膺(りよう)ら二百余人を獄に下した。「党錮(とうこ)の獄(ごく)」である。
つぎの霊帝の169年には、「第二の党錮(とうこ)の獄(ごく)」があり、184年には、黄巾(こうきん)の賊が、兵をあげた。
黄巾の賊が平定されてのちも、群盗蜂起し、それを討伐する諸将が割拠し、さらには、匈奴などの異民族が背反した。
(2)後漢によって金印を与えられた奴国中心の時代から、魏によって金印を与えられた邪馬台国中心の時代へ移り変わる時期
中国で、後漢帝国が、衰運の影を見せはじめたころ、わが国でも、後漢をバックアップ勢力としていた奴国も、権威を失なったのか、倭国は、「大いに乱れて」いる。
(3)わが国の北九州中心部における・葬制が、甕棺墓葬の時代から、箱式石棺葬などの時代への移り変わる時期
宮崎公立大学の教授であった考古学者の奥野正男氏はいう。
「いわゆる『倭国の大乱』の終結を二世紀末とする通説にしたがうと、九州北部では、この大乱を転換期として、墓制が甕棺から箱式石棺に移行している。
つまり、この箱式石棺墓(これに土壙墓、石蓋土壙墓などがともなう)を主流とする墓制こそ、邪馬台国がもし畿内にあったとしても、確実にその支配下にあったとみられる九州北部の国々の墓制である。」(『邪馬台国発掘』PHP研究所刊)
「前代の甕棺墓が衰微し、箱式石棺墓と土壙墓を中心に特定首長の墓が次第に墳丘墓へと移行していく・・・・・。」(『邪馬台国の鏡』梓書院、2011年刊)
畿内説の考古学者の白石太一郎氏(当時国立歴史民俗博物館。現、大阪府立近っ飛鳥博物館長)ものべる。
「二世紀後半から三世紀、すなわち弥生後期になると、支石墓はみられなくなり、北九州でもしだいに甕棺が姿を消し、かわって箱式石棺、土壙墓、石蓋土壙墓、木棺墓が普遍化する。ことに弥生前・中期には箱式石棺がほとんどみられなかった福岡、佐賀県の甕棺の盛行地域にも箱式石棺がみられるようになる。」
■邪馬台国勃興の地
金印奴国を中心とする時代から、金印邪馬台国の時代に移り変りの時期に、北九州の中心部の墓制が、甕棺墓葬の時代から、箱式石棺墓葬などの時代へと、移り変わったのは、なぜなのであろうか。
そもそも、甕棺墓葬が、おもにおこなわれたのは、下の二つの地図に示されている地域である。
とくに、下の右の地図で、考古学者の原田大六が、「中心地区」とした地域は、甕棺墓葬時代のつぎの邪馬台国時代に、末盧国、伊都国、奴国、邪馬台国などが存在した可能性が高いとみられる地域である。
この地域の甕棺墓葬が衰退したのは、なぜであろうか。
甕棺墓葬がもっぱら行なわれた金印奴国の時代も、原田大六の示す下の右の地図の「中心地区」の外周部では、箱式石棺などがかなり行なわれていた。
すなわち、下の右の地図にみられるように、対馬では、甕棺がほとんどみられず、箱式石棺が、もっぱら行なわれていた。
(下図はクリックすると大きくなります)
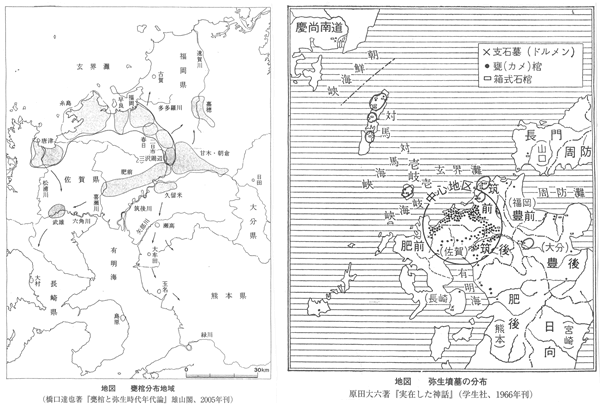
(下図はクリックすると大きくなります)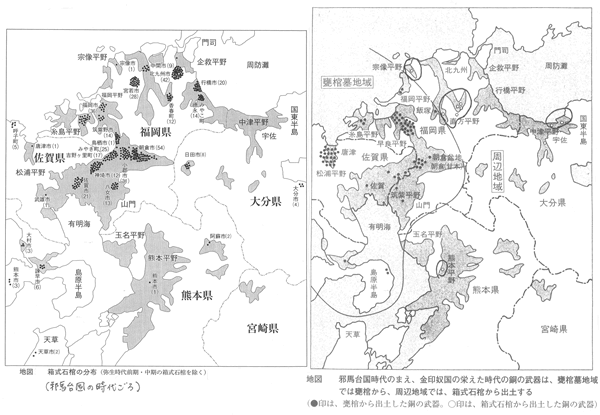
壱岐でも、箱式石棺が行なわれていた。
福岡県、筑前の東北部、遠賀川(おんががわ)の下流域、旧筑前の国の遠賀郡、鞍手郡、宗像郡の地域から、豊前・豊後にかけての地域にも、箱式石棺がみられる。
この地域は、つぎのような点で、注意を引く。
(1)のちに、神武天皇が、南九州の日向から出発し、北九州の遠賀川の河囗ふきんにいたっている。『古事記』によれば、神武天皇は、「筑紫の岡田(おかだ)の宮(みや)に一年滞在した」という。「岡田(おかだ)」の音は、むかしは、「をかだ(wokada)」である。「岡」は、のちに、「遠河」「遠賀」と表記されるようになった。
私は、神武天皇は、実在の可能性が、かなりあり、その活躍年代は、邪馬台国よりものちの西暦280年~290年ごろと考える(このシリーズの拙著『古代年代論が解く邪馬台国の謎』参照)。『古事記』『日本書紀』の記す伝承によれば、神武天皇は、この地にはいるさい、土着の勢力から、なんらの抵抗もうけていない。もちろん、戦いもなかった。『古事記』によれば、岡田の宮に一年滞在し、この地で、東征のための準備を、ととのえたようにさえみえる。
(2)神武天皇以前の時期とみられるが、北九州勢力の饒速日(にぎはやひ)の命(みこと)が、畿内に天下ったことになっている。
物部氏の祖先の饒速日の命の東遷伝承を、ややくわしく伝える『先代旧事本紀』によるとき、饒速日の命とともに天降った氏族の祖には、遠賀川下流ふきんに関係するとみられるものが、かなり多い。物部氏の祖先は、遠賀川河囗ふきんを、おもな根拠地にしていたのではないか。勉誠出版から出している(シリーズの拙著『古代物部氏と「先代旧事本紀」の謎』参照)。
(3)卑弥呼の死後、卑弥呼の宗女(一族の娘)台与(壱与)、年十三なるものが、あとをついで、女王となる。この台与(とよ)は、『古事記』『日本書紀』の伝える万幡豊秋津師姫(よろずはたとよあきづひめ)のことで、のちに、忍穂耳(おしほみみ)の命(みこと)と結婚し、邇邇芸(ににぎ)の命(みこと)をうみ、皇室の祖先となった人ではないかとみられるふしがある。
この台与(万幡豊秋津師姫)の時代に、それまで、卑弥呼の時代に、筑後川流域の甘木・朝倉(現朝倉市)地域にあった都を、東方の遠賀川下流ふきんから、豊前の国の京都(みやこ)郡あたりに、都を移した(あるいは、もとにもどした)可能性がある。
それは、より東方の出雲や畿内を経略する必要があったためである。
伝承上の、出雲の国譲り、出雲への天の穂日の命の派遣、畿内方面への饒速日の命の派遣、さらには、邇邇芸の命の南九州への天下り、なども、台与(万幡豊秋津師姫)や、天の忍穂耳の命の時代に行なわれた可能性が大きい。
のちの豊前(ぶぜん)、豊後(ぶんご)の国は、もとは、「豊の国」であった。万幡豊秋津師姫がおさめたので、「豊の国」という名称になったのか、あるいは、もともと、「豊の国」の出身者であったので、万幡豊秋津師姫の名のなかに、「豊」の語がはいっているのか、あきらかではない。しかし、「万幡豊秋津師姫」と「豊の国」とのあいだには、なんらかの関係があるのではないかと思われる。
ちなみに、のちの、『魏志倭人伝』の記すところによれば、対馬国、一大国(一支国の誤り)、奴国、不弥国などには、地方官を意味する「卑奴母離(ひなもり)[夷守(ひなもり)]」がおかれている(最終ページの「弥生時代の北部九州」の地図参照)。
「ひな」は、いなか、都から遠いところを意味する。
『万葉集』に、山上憶良(やまのうえのおくら)のつぎのような歌がある。
「天(あま)ざかる鄙に五年(いつとせ)住(すま)ひつつ都の風俗(てぶり)忘らえにけり」(880番の歌)
この歌は、「地方に五年も住みつづけ、都の流儀も、忘れてしまいました。」の意味である。山上憶良は、726年に、筑前の国の国守(こくしゅ)[国司の長官]となって、赴任している。
ところで、『魏志倭人伝』によれば、「一大率」(ひとりの身分の高い統率者。長官)をおいた伊都国や、投馬国(とうまこく)、さらには、邪馬台国には、「卑奴母離(ひなもり)」の官をおいていない。「伊都国」「投馬国」「邪馬台国」に共通して「卑奴母離(ひなもり)」の官がおかれていないのは、この三つの国は、「地方」とみられていなかったためではないか? 卑弥呼女王の、直轄地的な色彩が強かったのではないか?
邪馬台国時代には、「奴国」は、「地方」とみられるようになっていたようである。
奈良時代成立の『万葉集』や、平安時代成立の『延喜式(えんぎしき)』に、「夷守(ひなもり)の駅(うまや)」の名がみえる。
この駅は、筑前の国の糟屋郡(かすやぐん)の日守(ひなもり)八幡宮のあたりとみられ、現代の福岡市東区多多羅のあたりに比定されている。糟屋郡のあたりは、「奴国」の範囲にはいるともみられ、「不弥国」の範囲にはいるともみられる。
『魏志倭人伝』によれば、「奴国」にも、「不弥国」にも、「卑奴母離」の官がいた。




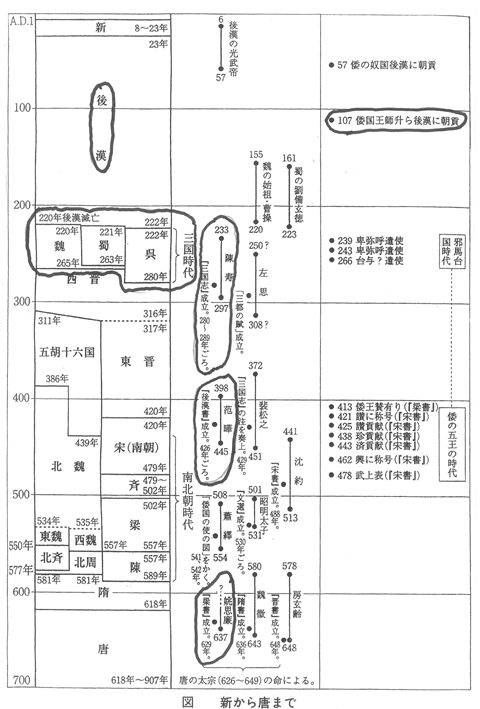
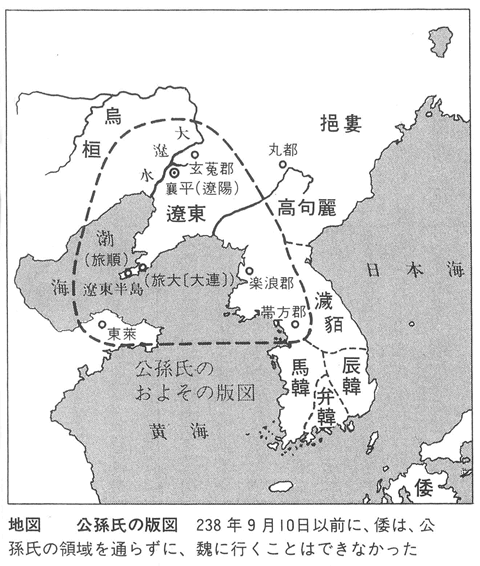
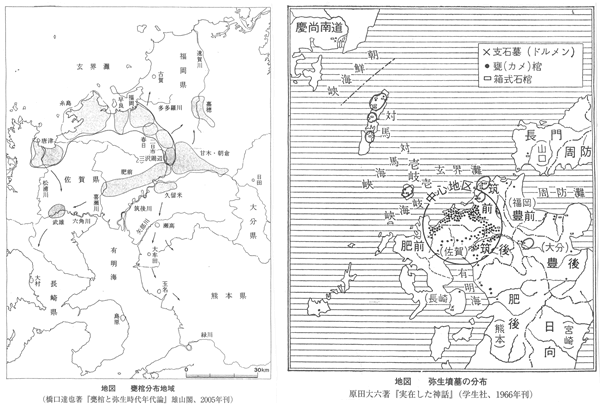
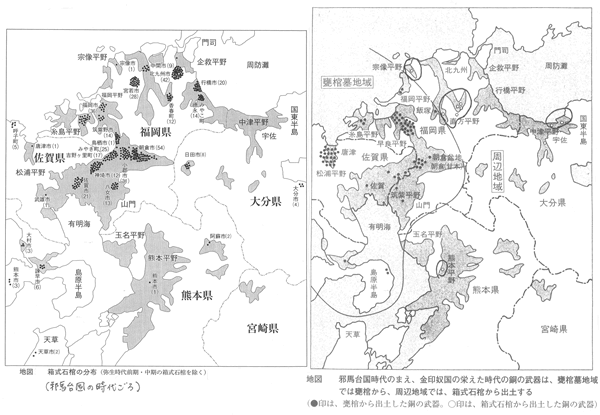
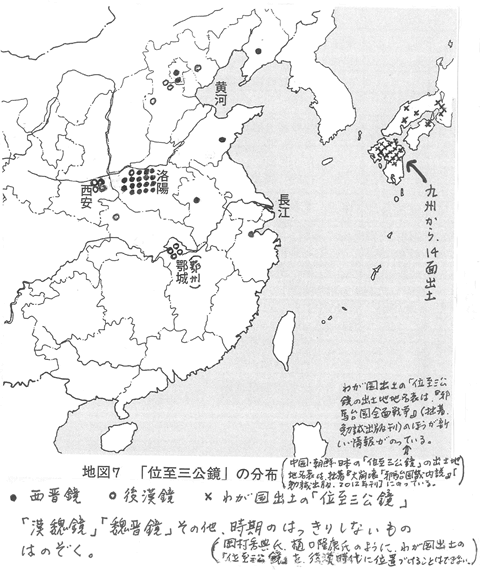
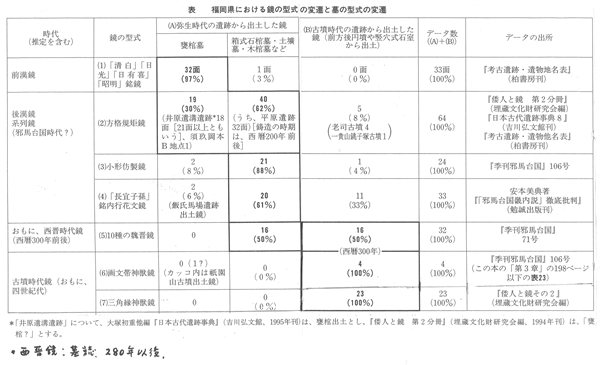
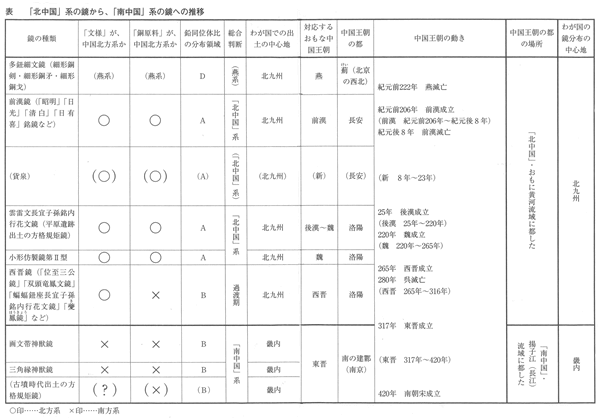
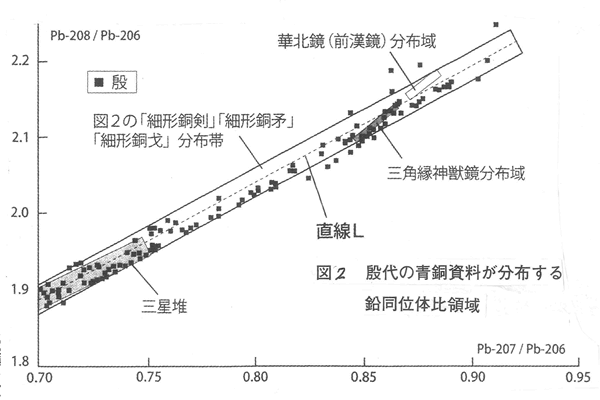
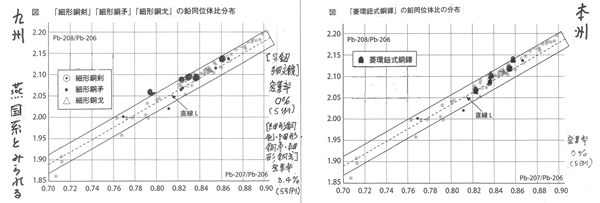
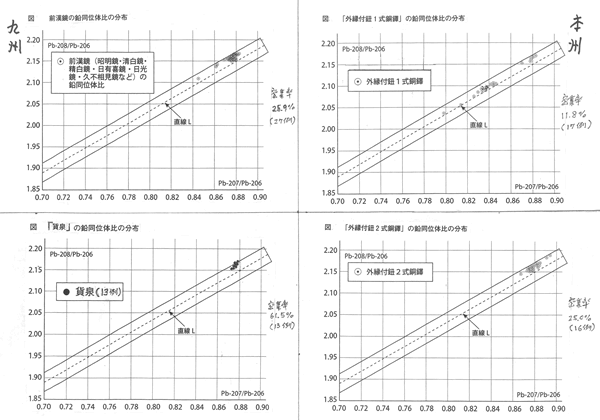
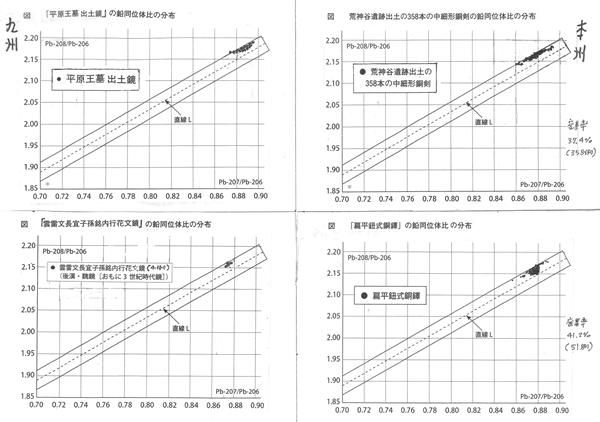
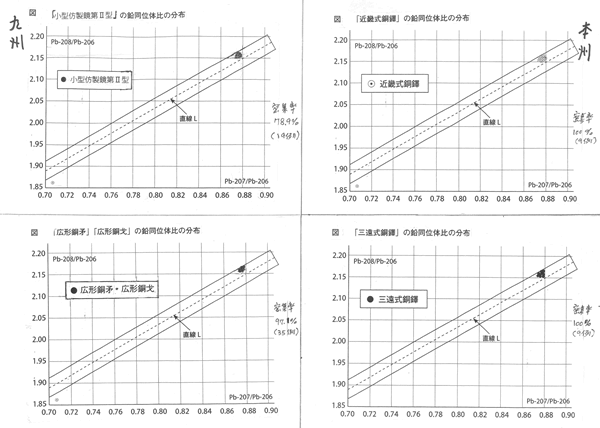
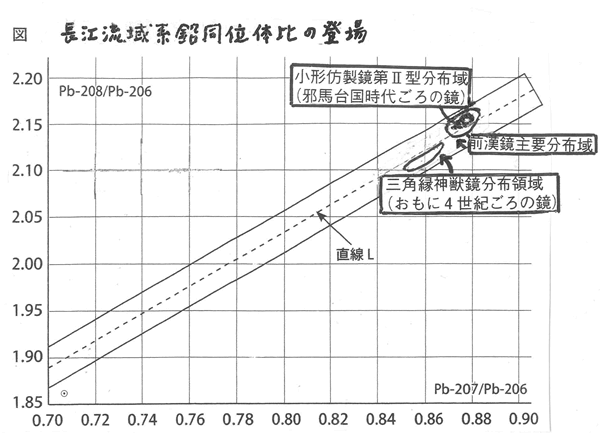
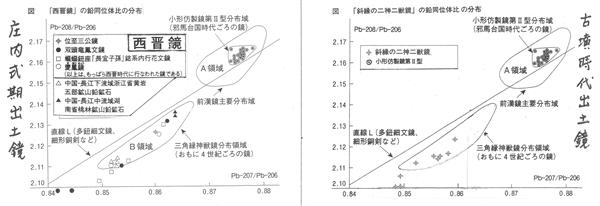

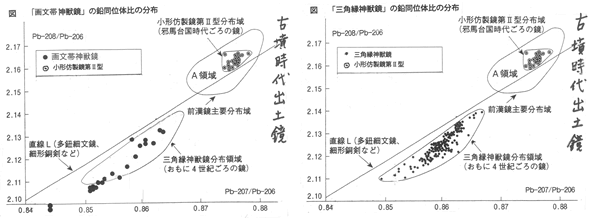
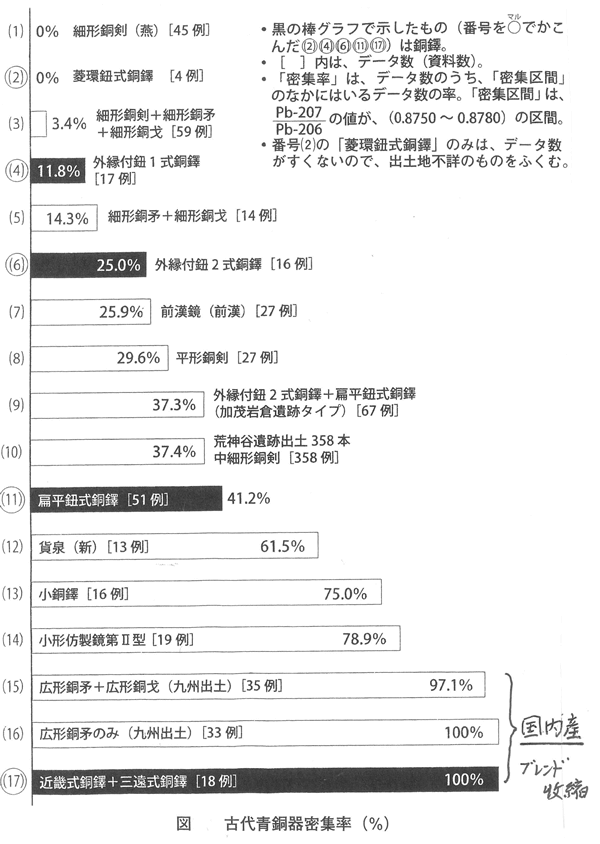
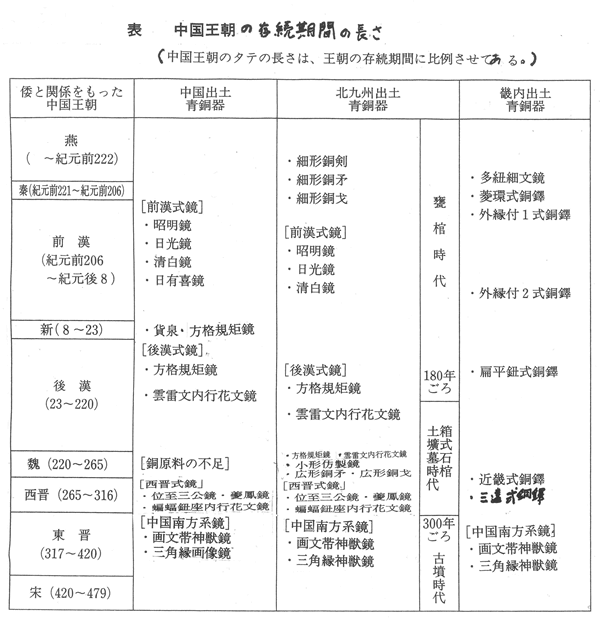
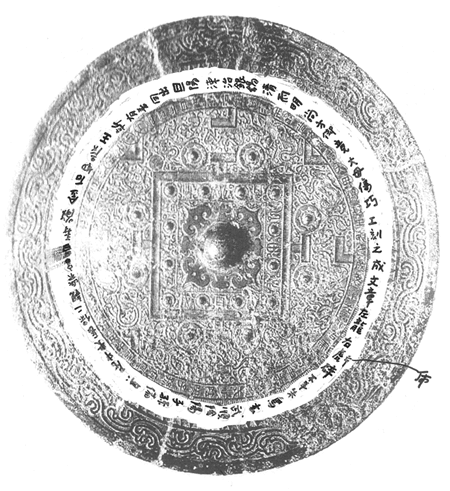 。これはほぼ後漢時代の鏡と思われる。
。これはほぼ後漢時代の鏡と思われる。