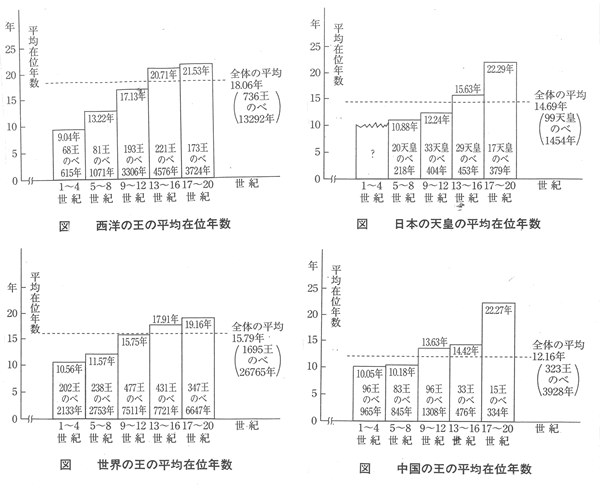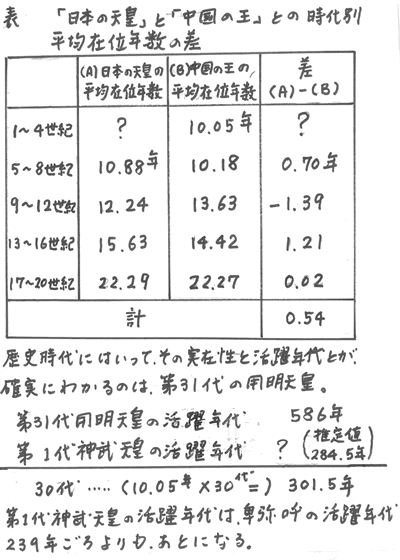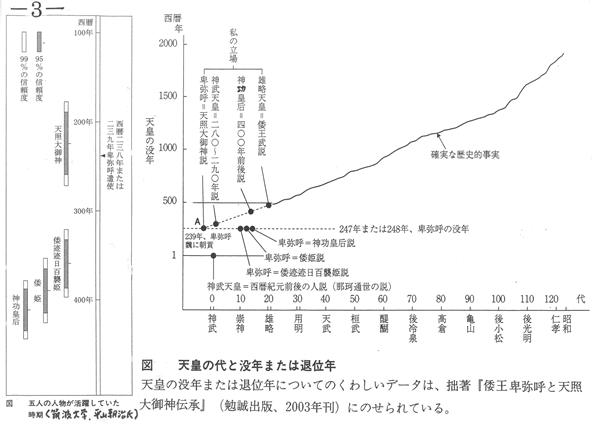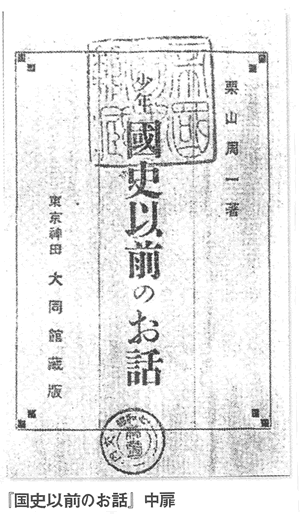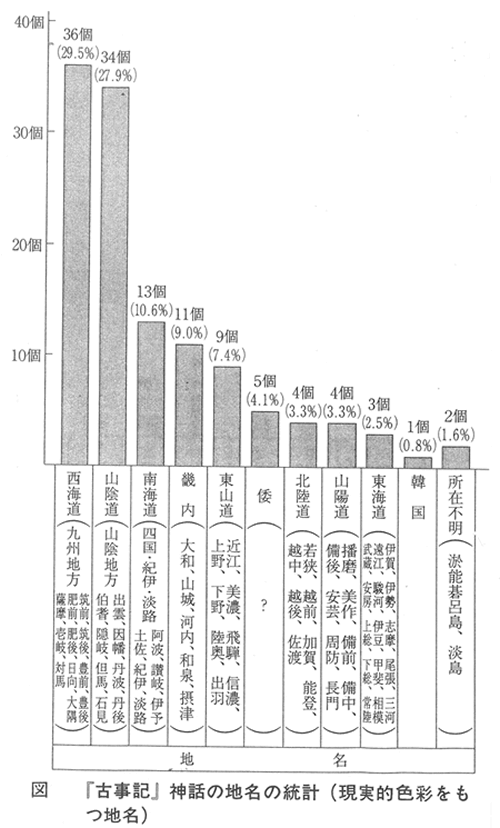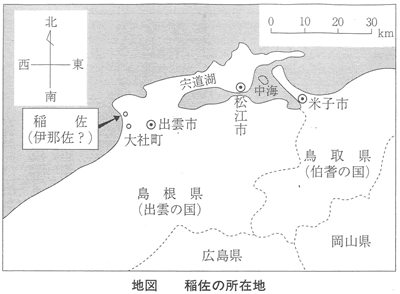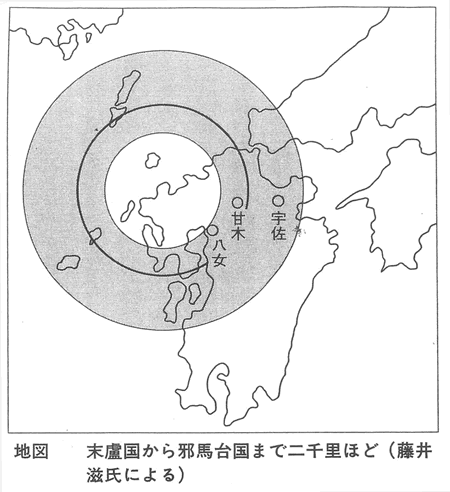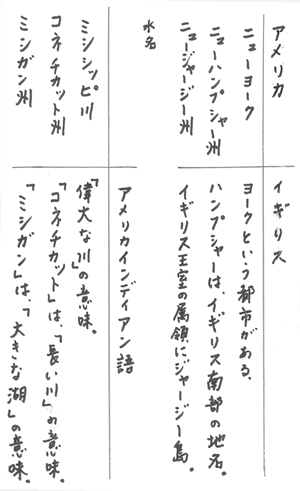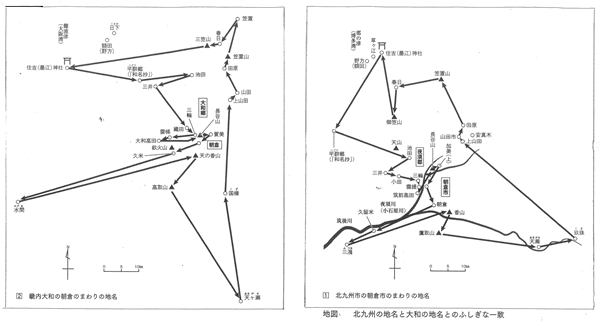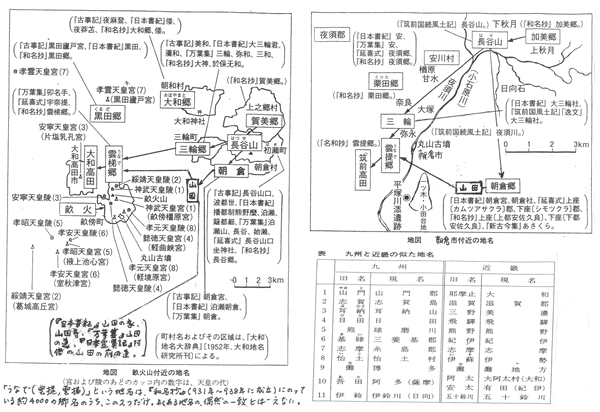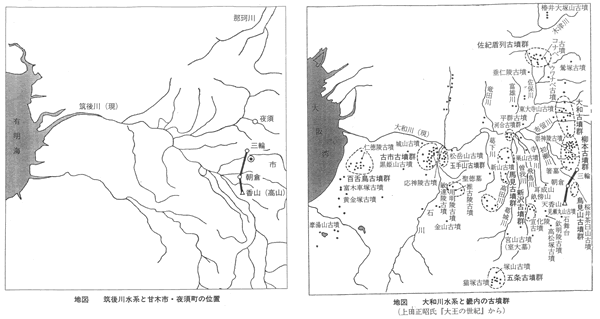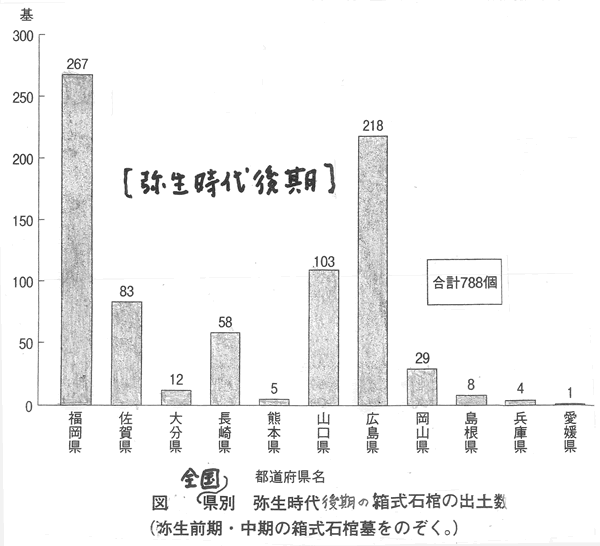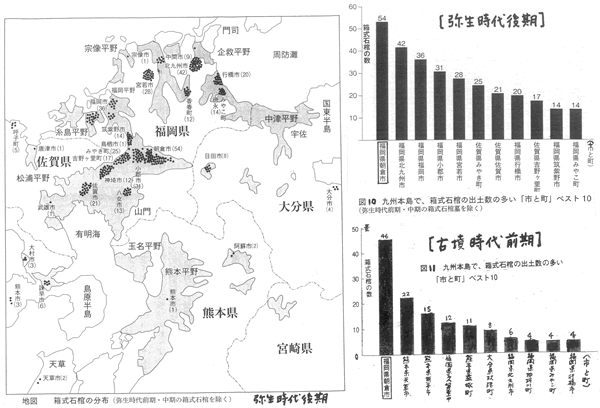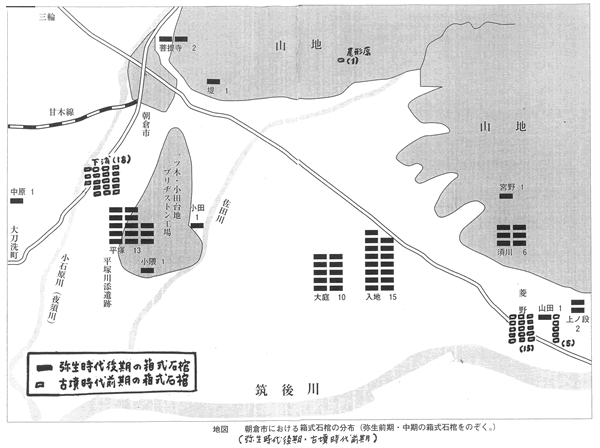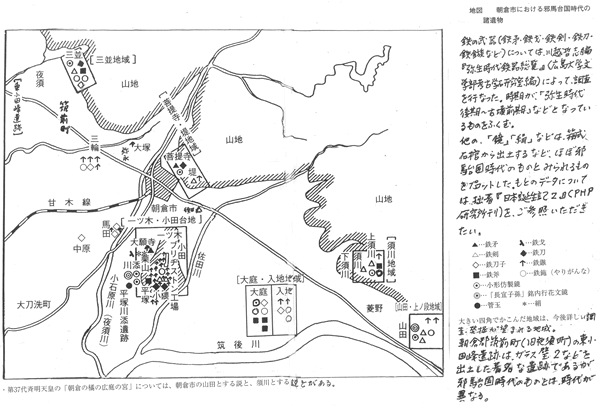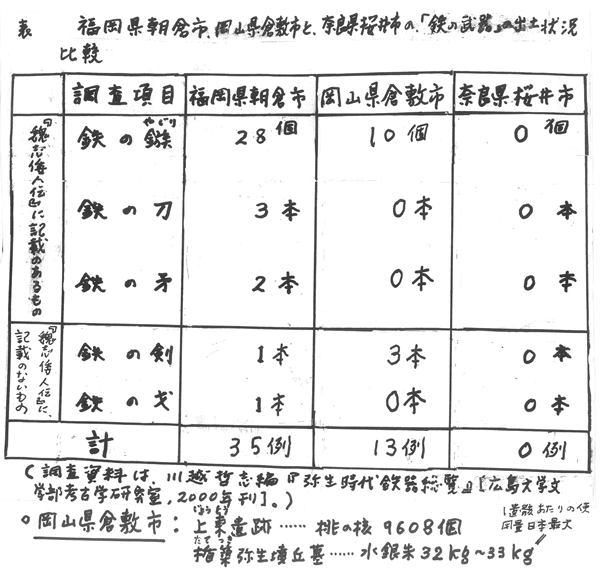| TOP>活動記録>講演会>第374回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
Rev.3 2019.4.5 |
第374回 邪馬台国の会(2018.11.25 開催)
| ||||
1.「卑弥呼=天照大御神」説と「邪馬台国東遷説」
|
卑弥呼の都は福岡県の朝倉市あたりにあったと思っているが、今回はその根拠を示したい。 たびたび紹介しているが、下図の右上のグラフは日本の天皇の平均在位年数を示したもので、400年ごとにまとめると、古い時代になるほど天皇の平均在位年数が短くなることが分かる。そして下の3つのグラフから、中国、西洋、更に世界の王の平均在位年数を示すと、日本の天皇の平均在位年数と同じような傾向があることが分かる。 まとめると右のようになる。
これに対する批判に、400年ごとにまとめているが、100年、50年ごとにまとめると、規則性がなくなるというものがある。しかし統計はある程度データをまとめないと規則性が出てこない。それを細かく区切って規則性がないからダメだというのは統計が分かっていない主張である。 確実に存在したという天皇は31代用明天皇である。在位期間は3年なので活躍した時代は西暦586年とすることができる。そこで天皇の在位年数が中国と同じ10.05年とすると、神武天皇が活躍していた年代は西暦284.5年となり、明らかに卑弥呼の時代より後になる。 しかし『古事記』『日本書紀』に神武天皇より5代前に天照大御神という女神の神話がある。5代約50年さかのぼると、西暦250年となり、卑弥呼の時代と合致する。 横軸に天皇の代をとり、縦軸に天皇の没年(西暦)をとると下記のグラフになる。 (下図はクリックすると大きくなります)
このように統計的な方法で卑弥呼=天照大御神とする前に、卑弥呼は天照大御神ではないかと唱えた学者は下記にように多い。
■白鳥庫吉の「卑弥呼=天照大御神」説 白鳥はまた、邪馬台国北九州説を説き、畿内大和説を主張する京都帝国大学(現在の京都大学)の内藤湖南(ないとうこなん)と白熱の論争を戦わせた。邪馬台国の位置をめぐる諸説は、それまでにも出されてはいた。しかし、現代まで長く尾を引く、いわゆる「邪馬台国論争」は、このときはじめて、激しい沸騰を見せたといってよい。 白鳥は、明治四十三年(1910)に発表した「倭女王卑弥呼考(わじょうおうひみここう)」のなかで、『魏志倭人伝』の「卑弥呼(ひみこ)」に関する記事内容と『古事記』『日本書紀』の「天照大御神」に関する記事内容とを比較している。そしてその二つの記事内容について、「その状態の酷似すること、何人(なんびと)もこれを否認するあたわざるべし」と述べている。 白鳥は、いまから百年以上前に『古事記』『日本書紀』の神話が伝える天照大御神は、『魏志倭人伝』の記す卑弥呼の反映なのではないか。天照大御神がいたと伝えられる「高天の原(たかまのはら)」は、邪馬台国の反映なのではないかとする考えを示している。
■和辻哲郎の「卑弥呼=天照大御神」説 和辻は観察眼の広さと明晰な思考によって知られる。和辻は、ドイツの哲学者ニーチェやデンマークの哲学者キュルケゴールの研究から、さらに、日本文化の研究に進み、『日本古代文化』『古寺巡礼』『風土』などの数々の名著を著した。 和辻哲郎の「卑弥呼=天照大御神説」は、『日本古代文化』(岩波書店、1920年)のなかにみえる。『日本古代文化』は、和辻がまだ二十六歳という若さで著した著作である。 和辻はその東遷説を展開する出発点として『古事記』『日本書紀』の神話と『魏志倭人伝』の記述との一致をやや詳しく指摘している。 「君主の性質については、記紀の伝説は、完全に『魏志倭人伝』の記述と一致する。たとえば、天照大御神は、高天の原において、みずから神に祈った。天上の君主が、神を祈る地位にあって、万神を統治するありさまは、あたかも、地上の倭女王が、神につかえる地位にあって人民を統治するありさまのごとくである。また天照大御神の岩戸隠れのさいには天地暗黒となり、万神の声さばえのごとく鳴りさやいだ。 和辻哲郎は、ついで、大和朝廷の国家統一が、どのように行われたと考えられるかについて述べる。大和朝廷は、邪馬台国の後継者であり、『古事記』『日本書紀』の伝える「神武東征(じんむとうせい)」の物語の 「国家を統一する力が九州から来た」という中核は、否定しがたい伝説に基づくものであろうとする。
■黒板勝美(くろいたかつみ)の『国史の研究』 『国史の研究』が刊行された当時、岩波書店は、この本を、「学界の権威として、洛陽の紙価を高からしめたる名著」とし、「最近まで各方面にわたりて学界に提出されし諸問題」を、「一一懇切詳密に提示論評し」、「その拠否を説明取捨し以て学界の指針たらしめ」「宛然(さながら)最近に於(お)ける国史学界進展の総決算たる観を呈して居る」、そして、「わが国史に就(つ)きての中正なる概念を教示する」もので、一般人士はもちろんのこと、「専門研究者も座右(ざゆう)に備ふるべき好伴侶(はんりょ)たるを失はない」とのべている。 黒板勝美は、『国史大系』などの編集者であり、他の説の批判や自説の主張においては、つねにその根拠を、くわしくのべている。岩波書店がのべていることは、当時にあっては、けっして誇大な宣伝ではなかったのである。その説は、学問的考究の上にたつ、穏健中正な見解とみられていたのである。
■国史の出発点は神代 黒板は、『国史の研究各説』上巻の冒頭で、およそつぎのようにのべて、「国史の出発点を所謂(いわゆる)神代まで、遡(さかのぼ)らしめ得る」と説く。
■天照大御神は「なかば神話の神、なかば実在の人」 「天照大御神は、最初から皇祖として仰がれた方であったからこそ、三種の神器の一つである八咫鏡(やたのかがみ)を霊代(たましろ)として、やがて伊勢に奉斎され、今日まで引きつづき皇室の太廟として、とくに厚く崇祀(すうし)されているのである。
■アカデミーの立場からの「高天の原=地上説」の評価 「天孫民族が大和や日向に入る以前、すなわち、いまだあい分れていない時の地が、いわゆる『高天の原』であるともいえよう。本居宣長が、これを天であると解釈しているのは、『古事記』のできたころ、わが国民が、そのように考えていたとする意味においては妥当であるが、もし、高天の原を、天孫民族の祖国と解すべきであるならば、地上のどこかにこれを擬すべきである。ところで、『旧事本紀』の天孫本紀が古伝であることは、学者の意見の一致しているものであるが、それには、天孫饒速日の命(にぎはやひのみこと)が、高天の原から大和に降臨したと記載されている。これは、のちに神武天皇が大和に入ったさいに、物部氏の祖饒速日の命が、天皇と同族である証拠を示したという『日本書紀』の記事とも一致するものである。このような大和降臨説話の存在は、すくなくとも高天の原をもって大和とする説にとって、大きな打撃であるといわなければならない。それで、高天の原を、海外に擬してもさしつかえないという説がでてきたのであるが、日本語がふきんの外国語とまったく系統を異にしている点から、天孫民族がわが国に移住してきたのは非常に太古であったろうといわれる白鳥博士の説をある点までみとめ、また、考古学的にもこの説を支持しうるならば、高天の原国内説は、よほど有力になってくるであろう。もっとも、本居宣長も、すでに『古事記伝』の大八州生成の条で、『すべて神代の故事は多く西になんありける』といっており、暗に九州の一部に高天の原を擬していたように思われる。『日本書紀』の景行天皇紀十二年、仲哀天皇八年の条に、九州の土豪が、三種の神器と同様の鏡、剣、玉の三種の神宝を船中の榊(さかき)の枝に取り掛けて、天皇を奉迎したことがある。神宝が主権者のしるしであり、三種の神器が天孫民族に特有なものであったとすれば、これらの土豪も、あるいは高天の原から分かれた天孫民族の一部であって、景行天皇や仲哀天皇の御代まで、なお九州の北部に存在していたものではあるまいか。」 さらに、黒板勝美は、『国史の研究総説』(1931年刊)で、「高天の原は、本島のなかの大和にはなかったとする説が有力であるように思われる。」とし、つぎのような点も指摘している。
■栗山周一のおよそ一千年延長説 栗山周一は、『少年国史以前のお話』(大同館書店、1933年刊)の第二章「日本列島に渡って来た民族」の冒頭で、「日本の年代」についてのべる。 「わが国の古伝説によれば、神武天皇即位元年より現今(1932年)まで、二千五百余年と称せられるが、この紀元年数には、大いなる錯誤がある。このことは、すでに、歴史の専門家が認めている。今、従来の学説(安本註。那珂通世説)により、六百六十年の誤差があるとすれば、日本の紀元は、約西暦紀元と一致することになる。しかし、支那、朝鮮の関係史料と比較すれば、日本の年代と支那、朝鮮の年代とは一致しない。よく調べてみると、朝鮮と支那とはほぼ一致するが、日本と支那、日本と朝鮮とが一致しない。いずれかの年代が誤っているということになる。大局よりみて、日本の紀元は、従来史家の、六、七百年ではなく、約一千年以上の錯誤のあることがわかる。
また、栗山周一は、『日本欠史時代の研究』(大同館書店、1933年刊)で、みずからの年代論の根拠について、ややくわしくのべている。 栗山周一は、自説の根拠として、天皇の一代平均在位年数にもとづく年代論を展開する。「国史の年代が、書紀において、約一千年以上ひきのばされていることは、古い時代の歴代天皇の在位年数を調査すればよくわかる。いま、これを、最初『古事記』の年数によってみると、次のようになる。 上掲1天皇平均14年と、『古事記』により算出の12年とを平均して、在位年数1天皇平均13と仮定すれば、今上天皇より神武天皇まで124代の年数は、1612年となる。日本紀元2600百年に足らざること約一千年であるから、この計算よりすれば、約一千年の誤差があらわれている。」
■神話伝説の中の史実 卑弥呼をヒミコいとよむべきか、ヒメコとよむべきかは明らかでないが、支那文字をもって日本の音を表したものである。天照大御神は、日の御子(ひのみこ)と伝え、『オホヒルメムチノミコト』という。ヒルメノミコトすなわち姫尊(ひめみこ)である。ヒメコ、ヒミコと音通ではないか。卑弥呼に、日の御子(ひのみこ)、姫御子(ひめみこ)[姫尊(ひめみこ)]、または日の巫女(ひのみこ)の意があるとすれば、正しく日本の神話にでてくる神々の名と思われる。 卑弥呼は、よく鬼道に通ずというが、未開時代においては、大衆をおさめ支配するに魔術が、ぜひ必要であった。現今でも、野蛮人においては、魔術師が、一番尊ばれるのである。そこで、鬼道とか巫道とか、またはふしぎな霊を祭るのである。神を祭り、神のお告げを聞くという原始的な宗教である。 文学博士内藤湖南先生は、卑弥呼をもって倭姫の命(やまとひめのみこと)とせられており、笠井新也先生は倭迹迹日百襲姫の尊(やまとととひももそひめのみこと)とせられているが、私は、いずれも首肯しがたい。女王卑弥呼は、倭姫の命や神功皇后初伝を生んだ根拠ではなく、天照大御神神話を生んだ根拠をなすものであることは、大体想像がつくのである。 『魏志』が日本の事実を誤り伝えたというよりも、『魏志』こそ事実であって、『古事記』『日本書紀』が、卑弥呼の口碑伝説などを、それとは知らずに誤り伝え、美化しているのではないかと私は思うのである。
■邪馬台国は北九州
■栗山周一の「邪馬台国東遷説」 「倭人の大和東遷は、卑弥呼の死後である。神武天皇の東征の神話のごとき、まさにこの方面の消息を伝えたものとみられる 卑弥呼の血族または関係の民族が、大挙して大和地方にうつり、九州の倭国の名をそのまま称して『大和』といった。奈良県の古名大和(倭)は、倭人が九州より移住東遷して、邪馬台の旧名を襲用して大和に永住したので、国名は改めなかったと解すべきである。『邪馬台』は、『大和』を誤り伝えたものではなく、『邪馬台』の倭人が、大挙東遷して、ここに『ヤマト』の名を称したものであろう。日本をヤマトと称するは、奈良県大和に出ずること申すまでもないが、奈良県大和の古名は、九州の邪馬台に出で、倭人も魏人も、これをヤマトと称したのである。なぜに旧地の国名を称したのか。当時支那大陸との交通上、その信用とか便利とか、国家統治の方策などから、依然として邪馬台と称したのであろう。大和政府の原始は、倭国に求めねばならぬ。彼等倭人は、さかんに支那文化を輸入し、大挙大和方面に渡渉移住し、一部は瀬戸内海方面に分布し、淀川平野より大和に侵入した倭人は、もっとも強力であった。」
■邪馬台国の風俗、習慣 「『魏志』と日本神話とを比較すれば、ここに、面白い一致点の多々あるを見出す。『魏志』にでているくわしい記事をみると、その風俗習慣や、社会の状態は、まったく日本の上古、すなわち、『古事記』神話にでているものと、なんら異ならない。 「これら風俗や習慣は、その文化は、『古事記』『日本書紀』初伝の原始をなすもので、日本太古の風俗習慣こそ、倭国倭人にその原始があると考えられるのである。もちろん、かかる太古の時代において、わが日本列島の事情が、すこしの誤謬もなく、支那の文書記録に伝えられているとは考えられない。それは、太古にあらざる現今においてすらも、外国の事情が、誤りなくわれらに伝えられているかというと、実は、日々の新聞紙の報道すら、ときにはほとんど信用のできぬことがある。かかる太古において、かくばかり多数の一致点を見出しうることこそ、じつにふしぎというべきである。」
■岩戸がくれは、天照大御神の死を意味する 和辻哲郎が、暗示的にのべていることを、栗山周一は、ずばり、「大神の崩御」とのべるのである。 「とにかく、倭国人は、九州北部に一国家を作った民族で、文化の程度も高かった。その民族が、人口の増加とともに、大挙して近畿地方に移り、ここに今日の日本を作ったものとすれば、国史の解決はつくのである。邪馬台国の延長としての大和政府を考えるならば、すべて解決がつくのである。神話のうちに現れているところをみると、日本神話は、南方から北方へ進んできている。すなわち、高千穂の宮とか日向とかいう名があらわれている。つまり、倭人は南方民族であって、のち瀬戸内海より東進して大和に入ったのであるから、神武天皇の東征の神話のごときも、この辺の消息をよく物語っているものであろう。」
■また、学習院大学の教授であった飯島忠夫はその著『日本上古史論』(中文館書店、1947年)のなかで、およそつぎのようなことを述べている。
■第二次大戦後も「邪馬台国東遷説」の立場をとった学者はけっしてすくなくない。 「(前略)端的に申しますと、私は卑弥呼の国が東征して、大和朝廷の基を開いたと思うのであります。もちろん、卑弥呼はとうに死んでおりますし、その子孫はありませんが、その勢力をついだものが東征したろうというのであります。(中略)神武天皇御東征の話がどれだけ歴史的事実を伝えたものか解りませんが、すくなくともその話の筋の中には北九州の勢力が大和へうち入った記憶だけは留めているのではないでしょうか。」
■東京大学の日本史家、井上光貞は、その著『日本の歴史1 神話から歴史』(中央公論社、1965年刊)のなかでのべる。 もちろん邪馬台国東遷説も、可能性のある一つの仮説にすぎないが、「北九州の弥生式文化と大和の古墳文化との連続性」、また「大和の弥生式文化を代表する銅鐸と古墳文化の非連続性」という中山氏や和辻氏の提起した問題は、依然として説得力をもつと考えられる。また、邪馬台国は、その女王壱与(いよ)が266年に晋(しん)に遣使した後、歴史の上から姿を消してしまった。いっぽう畿内の銅鐸も、二、三世紀の弥生後期にもっとも盛大となり、しかも突如としてその伝統を絶った そして三世紀末、おそくとも四世紀はじめごろから古墳文化が畿内に発達して全国をおおっていくのである。邪馬台国東遷説は、この時間的な関係からみても、きわめて有力であるといってよいであろう。」
■以上に紹介したもののほか、東洋大学の教授であった日本史家、市村其三郎(1902~1983)はその著『民族日本史』(刀江書院、1954年刊)のなかで、つぎのようにのべている。 「『古事記』『日本書紀』は、いずれも、日本国の主都が、九州から大和地方に移動したことを伝えています。いわゆる神武天皇の東征です。これは、かならずしも、根拠のない話ではなさそうです。ただ、これが事実であったとすると、すでに述べたように、ヒミコ女王の国の他には、正統日本国というものが考えられないのですから、神武天皇はどうみても、ヒミコ女王の何代目かの子孫ということになりましょう。『日本書紀』にのっている神武天皇の東征の詔(みことのり)というのをみると、神武天皇は、ヒルメノミコト女王の子孫だと明記してあるのです。ヒルメノミコト女王とはなんでありましょうか。九州地方にそのような名の女王があられたとしたら、それはまぎれもなくヒミコ女王のことでなければならないでしょう。ヒミコとヒルメノミコドとをくらべると、語音もまったく似ているでしょう。似ているというよりは、一致しているといってよいでしょう。」 「こればかりではありません。ヒミコ女王下の日本国も、神武天皇にはじまる日本国も、正式の国号は、ともに倭国であって、奈良時代になって初めて、倭国は日本という国号に改められています。神武天皇は、すくなくとも、ヒミコ女王の後継者であって、ヒミコ女王と無縁の方では、けっしてなかったろうと思われるのです。」
■以上のようにみてくると、「邪馬台国東遷説」はこれまで、おもに白鳥庫吉、和辻哲郎、黒板勝美、和田清、井上光貞(以上はいずれも東大教授)、飯島忠夫、市村其三郎など、東大系の学者たちにより、示唆され、主張され、発展させられ、支持されてきた、といえるであろう。
|
2.邪馬台国=福岡県朝倉市地域説
|
| TOP>活動記録>講演会>第374回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |