| TOP>見学会>壱岐旅行・古代史探訪『魏志倭人伝の旅』 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
邪馬台国の会事務局 |
壱岐旅行・古代史探訪『魏志倭人伝の旅』(2015.10.27-29) |
||||
1日目 |
| 安本先生は参加されませんでしたが、久しぶりに邪馬台国の会の見学旅行を企画しました。 羽田を出発し、福岡について、現地集合の方々も合流して、古代史探訪『魏志倭人伝の旅』に出発となりました。バスに2時間弱乗り、まずは唐津のマリンセンターおさかな村で昼食。さすが唐津で、海産物がおいしい。 菜畑遺跡-末蘆館 また少しバスに乗り、末蘆館・菜畑遺跡に到着、あいにく雨が降ってきた。最初の見学でもあり、雨にもめげない館長さんの熱心な説明に皆さん満足。菜畑遺跡といえば、縄文晩期の稲作で有名な遺跡です。更に、甕棺墓の初期が唐津付近と聞き、関心を持ちました。また、甕棺墓の後に箱式石棺墓となった。箱式石棺は長崎方面に多いなど、現地で得られる情報に感心しました。 |
 福岡空港到着  菜畑遺跡・末蘆館での説明 |
|
 内野会長挨拶 |
ビューホテル壱岐での懇親会 唐津港からフェリーに乗って、2時間ほどし壱岐の印通寺港に着く。いよいよ壱岐だ! ビューホテル壱岐の美人おかみをはじめとするホテルの方々の歓迎を受ける。 夕食の豪華な生うにや新鮮な刺身に舌つづみをうちながら歓談し、お酒も結構進みました。そして最後に行った河村先生の講演から地元ならではのいろいろなお話を聴くことができました。 |
|
 宴会風景 |
 河村先生・会長とおかみ |
 河村先生の講演 |
2日目
|
|
志々岐神社、白沙八幡社 朝から、志々岐神社や白沙八幡神社を廻り、志々岐神社の古い鳥居と白沙八幡神社の新しい鳥居が対照的であった。 原の辻遺跡-一支国博物館 壱岐旅行の目的の一つである一支国博物館で、またもや熱心な館長さんの説明を受け、更に原の辻遺跡では発掘もした年配のガイドさんの案内で最古の船着き場や復元された弥生時代の建物などを見学する。おおいに満足! |
 白沙八幡神社 |
|
 一支国博物館 |
 原の辻遺跡・船着き場跡模型 |
 原の辻遺跡 |
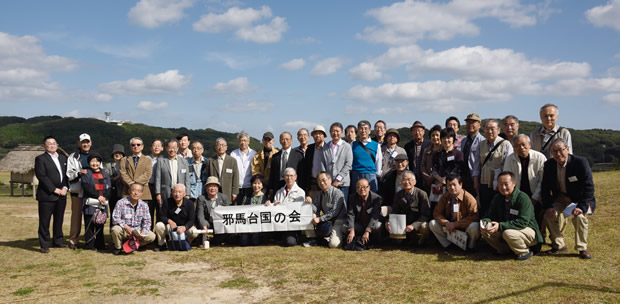 原の辻遺跡で全員写真(クリックすると拡大します) |
||
 岳ノ辻・展望台  天手長男神社  月読神社 |
「岳ノ辻」の展望台 天気が良いので、予定を変更して、壱岐で一番高い山の「岳ノ辻」の展望台へ行く。少し霞んでいたが対馬が見えた。 昼食は「あまごころ本舗」でうに丼である。さすがに壱岐特産のウニはうまい。 壱岐国一宮・天手長男神社(あまのたながおじんじゃ) 壱岐の国一の宮の天手長男神社へ行く。階段がきつい。階段を上がってみると、一宮にしては小さい神社である。階段を下りてから廻りを見回すと少し遠くの丘に鳥居が見えた。河村先生に聞くと、天手長比売神社といい天手長男神社と男女ペアの神社となるそうだ。今は天手長男神社に合祀されているため、鳥居の跡だけが残されている。さすがに一宮ということで、一宮めぐりの御朱印帳を出して、御朱印をもらう方がいた。 月読神社 続けて月読神社へ行く。ここもさほど大きい神社ではない。鳥居が古く、年代を感じさせる。 |
|
| 鬼の窟(おにのいわや)古墳・掛木(かけぎ)古墳 ここでみなさんの希望から、予定にない鬼の窟古墳と掛木古墳を見学する。掛木古墳では隣接する風土記の丘資料館のお姉いさんの誘いで、煎りどんぐりやアケビにつられ、資料館入ってしまった。予定にないところだったので、時間をとられてしまい、次の予定の猿岩が見られなくなった。壱岐に来て古墳を見ても観光名所の猿岩を見ないのはさすが「邪馬台国の会」だと、河島先生が感心する。 壱岐国の二宮・聖母宮(しょうもぐう) この日の最終は聖母宮(しょうもぐう)となる。神功皇后が壱岐に着き、順風を待たれたこのちを「風本(かざもと)」と名付けて三韓征伐に出発し、帰りにも立ち寄られ、勝利を祝って「勝本(かつもと)」と改めたと言い伝えられている。壱岐の二宮である。河島先生のおはからいもあり、予定にないお祓いを受け、大感激。 壱岐の島の郷ノ浦から帰りはジェットフォイルで博多港へ行く。さすがジェットフォイルは早い。 |
 掛木(かけぎ)古墳  聖母宮(しょうもぐう) |
|
3日目
|
|
住吉神社 11月8日からの大相撲九州場所を控えているためか、筑前の国一宮の住吉神社の境内に入ると、相撲の朝稽古をしていた。さすが大相撲の力士たちで迫力がある。その朝稽古を通り過ぎ、神社の前で、宮司さんの案内による神社の説明を受けた。更に今回は特別の配慮で、境内にある能楽堂を見学させて頂いた。能楽堂にかかっていた額は二・二六事件後の総理大臣で、戦後戦犯で死刑になった福岡市出身の広田弘毅の書である聞いて、歴史があると感じた。また能楽堂の舞台の下に甕があって、能の舞台を踏むと響くようにできていると聞いて、また感心した。 |
 住吉神社 |
|
 住吉神社宮司の説明 |
 住吉神社境内の相撲朝稽古風景 |
 能楽堂 |
 板付遺跡弥生館  板付遺跡 |
板付遺跡-板付遺跡弥生館 板付遺跡弥生博物館では館長さんから、長くにわたって詳細な説明を聞いた。板付遺跡も縄文晩期の早期水田で知られている。最近は縄文晩期と言わず弥生時代早期と言うらしい。夜臼式土器から板付式土器に変わっていったことに興味があり、縄文晩期の突帯文土器と朝鮮からの無紋土器から板付Ⅰ式土器ができたと考えていたが、館長さんの説明では、あくまで板付の夜臼式土器[刻目突帯文土器(きざみめとったいもんどき)ともいう]が発展して、板付Ⅰ式土器になったと言った。現地ではそのような認識なのだということを確認した。更に近くにある弥生時代の竪穴式住宅や復元された倉庫を見学した。 |
|
| 裂田溝(さくたのうなで) 昨年11月の河村先生の講演で話された、神功皇后が実在した証明となる裂田溝(さくたのうなで)を見学した。そこで那珂川町教育委員の説明を聴き、古代の人々が硬い花崗岩を削って水路を造った苦労が感じられた。更に近くにある神功皇后伝承ゆかりの裂田神社を見学した。 染井の井戸 この井戸は仲哀天皇がクマソ征伐に北九州に来て亡くなった時、将兵の指揮が落ちていた。そこで、神功皇后は近くの泉で、白生地(しろきじ)のヨロイを高くさし上げて、「我々は天皇の意志を継ぎ、遠く海を渡り、新羅の国へ進もうとしている。昨夜、不思議な神霊のお告げが出た。このヨロイは亡くなった仲哀天皇のまだ使っていないヨロイである。もしこの泉でヨロイが赤く染まったら、この戦いは必勝である。万一染まらないならば望みを捨てて、早々に引き返そう。」とお告げを伝えた。全軍が見るなかで、ヨロイを泉に沈め、二刻後に引き上げると、奇跡が起こり、白生地のヨロイが真紅色に染まっていたとのこと。この泉の井戸が染井の神水と語られていると立て看板に書かれていた。 細石神社(さざれいしじんじゃ) 細石神社の祭神は磐長姫(いわながひめ)と木花開邪姫(このはなさくやひめ)の二柱とのこと。近くに平原遺跡、三雲南小路(みくもみなみしょうじ)遺跡、井原鑓溝(いはらやりみぞ)遺跡がある。 |
 裂田溝(さくたのうなで)  染井の井戸  細石神社(さざれいしじんじゃ) |
|
 平原遺跡  鎮懐石八幡宮 |
平原遺跡-伊都国歴史博物館 原田大六氏が努力して発掘した平原遺跡を見学した。更に近くにある伊都国歴史博物館を見学した。邪馬台国の会で2002年に見学した時から比べ、非常に整備されて、きれいになったのにはびっくり。立て看板は「原田大六氏は直径45センチの大鏡は伊勢神宮ご神体の八咫の鏡と同型鏡であると考察し、この墓は天照大神の墓とした。そして、この遺跡発掘調査報告書は原田大六著『平原弥生古墳 大日孁貴(おおひるめのむち)の墓』として発行されている。」とのこと。そして、発掘調査報告書編集委員の井手氏が説明員として説明しており、近くでこの原田氏の本も販売していた。 鎮懐石八幡宮 見学の最後は、神功皇后と関係が深い鎮懐石八幡宮で宮司さんの丁寧な説明を聞いた。神功皇后は卵形の美しい二個の石を肌身に抱き、鎮懐として出産の延期を祈ったとのこと。また、鎮懐石万葉歌碑があり、江戸時代に建てられた九州最古の万葉歌碑であるとのこと。この鎮懐石八幡宮て今回旅行は終わりとなった。そして福岡空港へとバスは帰った。 |
|
| TOP>見学会>壱岐旅行・古代史探訪『魏志倭人伝の旅』 | 上へ | 戻る |