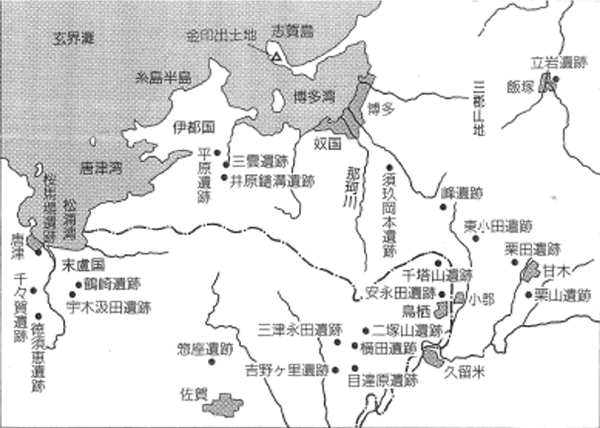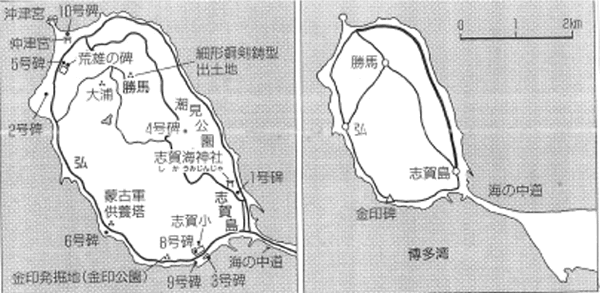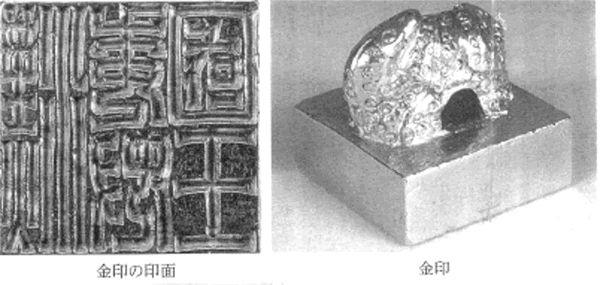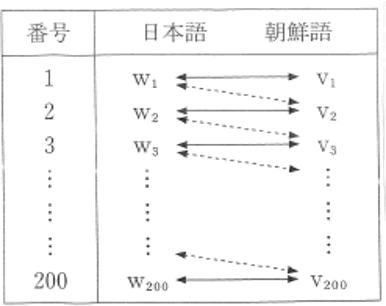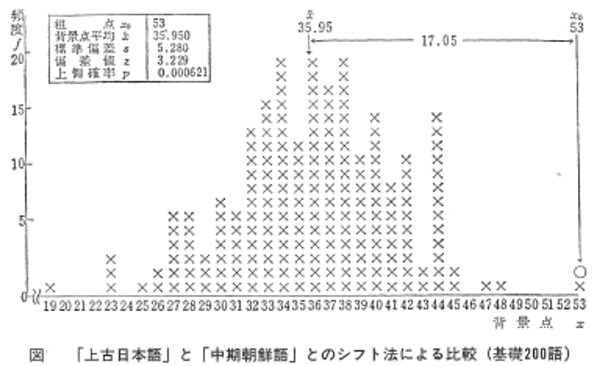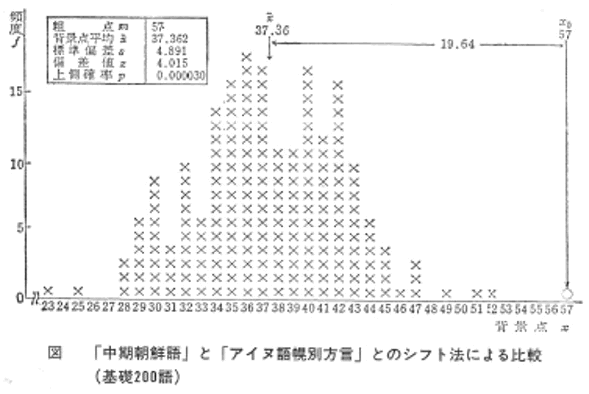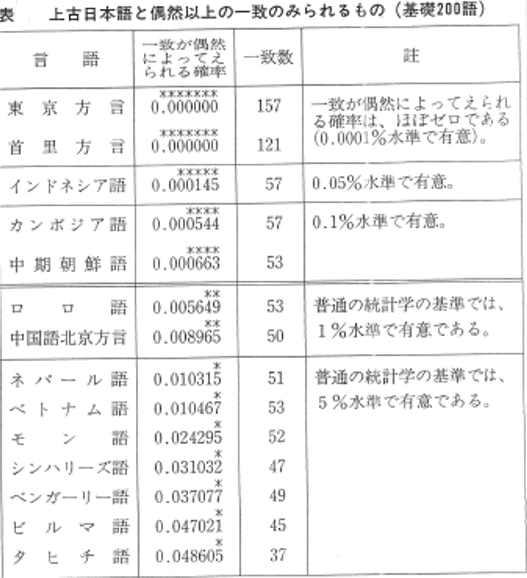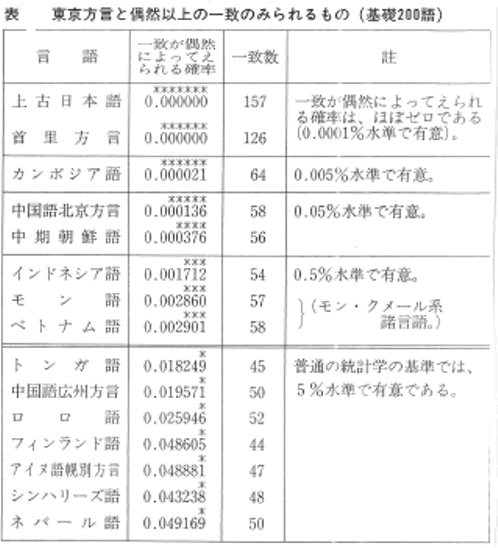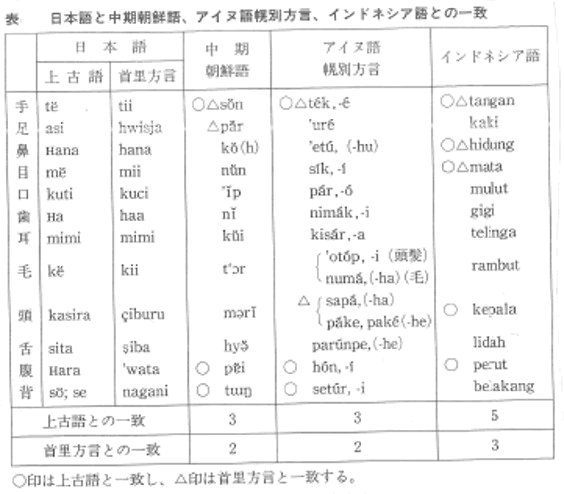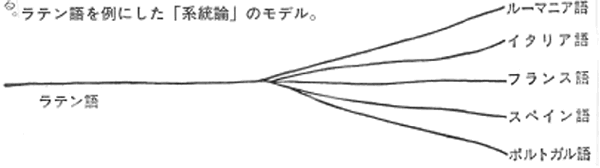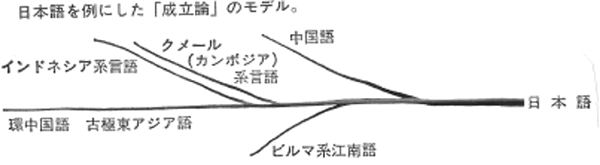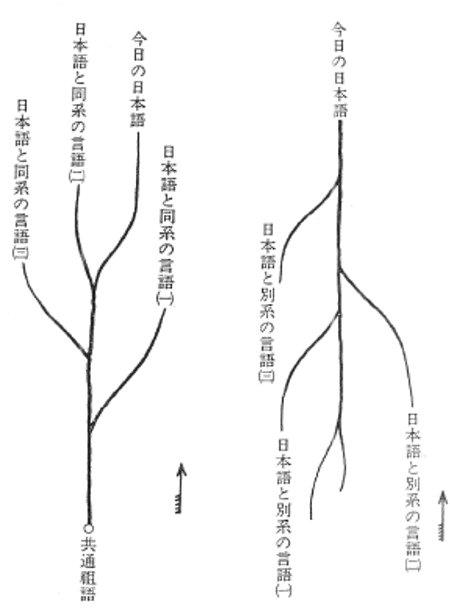| TOP>活動記録>講演会>第311回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第311回 邪馬台国の会(2012.7.22 開催)
| ||||
1.金印論争
|
金印(きんいん)は志賀島(しかのしま)(現、福岡県福岡市東区志賀島叶が崎)で江戸時代の1784年(天明4)に発見され、現在は金印公園となっている。 金印を偽造とする説 亀井南冥(1743-1814)について、人名事典では「江戸時代中期~後期の儒者。寛保3年8月25日生まれ。徂徠学派の僧大潮に儒学を、のち大坂で永富独嘯庵(どくしょうあん)に医学をまなぶ。筑前福岡藩儒医にとりたてられ、天明3年甘棠(かんとう)館の総受持(総裁)となった。朱子学派の東学問所[修猷(しゅうゆう)館]と対立し、寛政異学の禁の余波をうけ、寛政4年失脚。門下に広瀬淡窓ら。文化11年3月2日死去。72歳。著書に『論語語由』『肥後物語』などがある。」とある。 確かに、江戸時代は『風土記』の偽物が多く出回っていることなどから、信用できないとする風潮があるが、金印ははたしてどうであろうか? a.印面の文字 後漢の光武帝前後のものとみられる印にみられる「漢」の字は、つくりの下が「火」の字になっているものが多い。 これらが、漢の字体の違い影響があったと思われる。 これら印譜を見て、どれが後漢のものか分からない。後漢書から関係記事を探し出すのは、中国の学者が調べた先行文献がないと分からない。 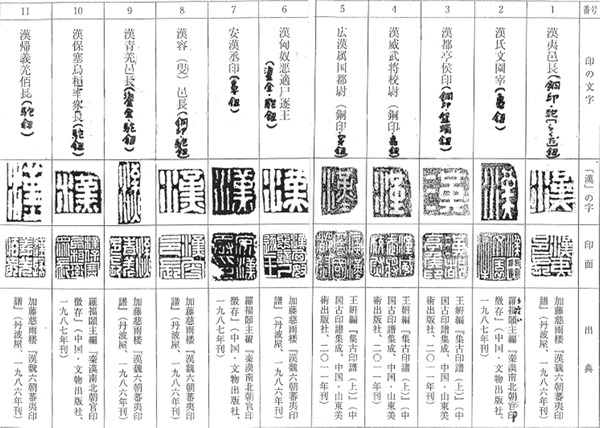 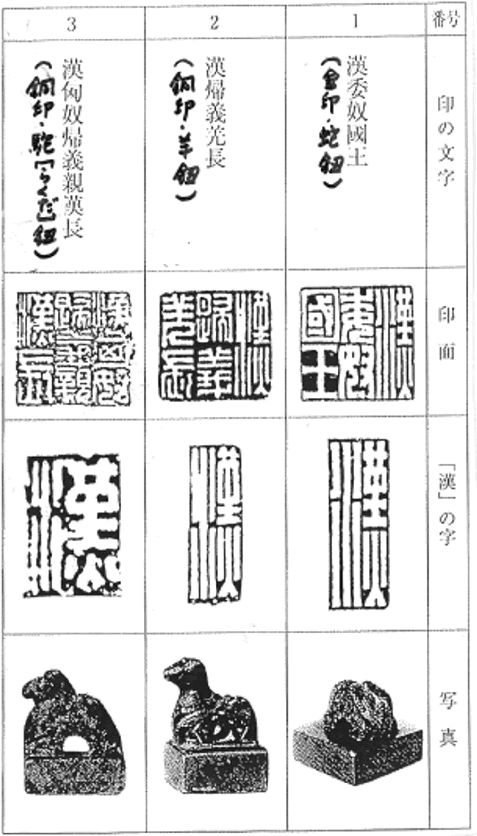 上記表において、 「2」と「3」は戦後に出土したものであるが、 これは、『後漢書』の「西羌伝」で、「漢委奴国王」の印と同じく、後漢の光武帝時代の印と考えられる。 三浦氏は印譜類を見れば、簡単に偽物が作れるとした。 b.金印の寸法 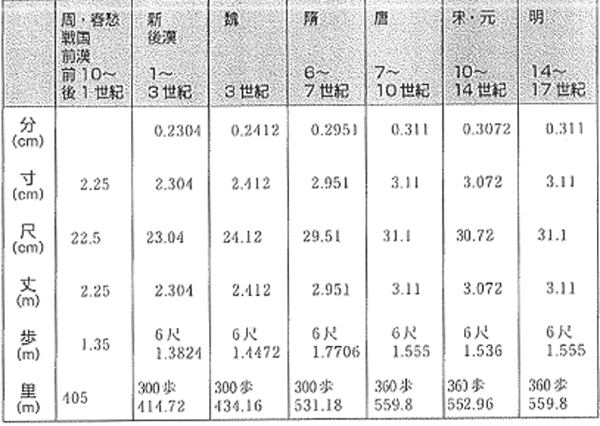 これいついて、三浦佑之氏は、『金印偽造事件』のなかで、つぎのようにのべている。 確かに、下記の表にある、顧従徳編の『集古印譜』の「蛮夷王印」の寸法を見ると志賀島金印と同じ寸法である。 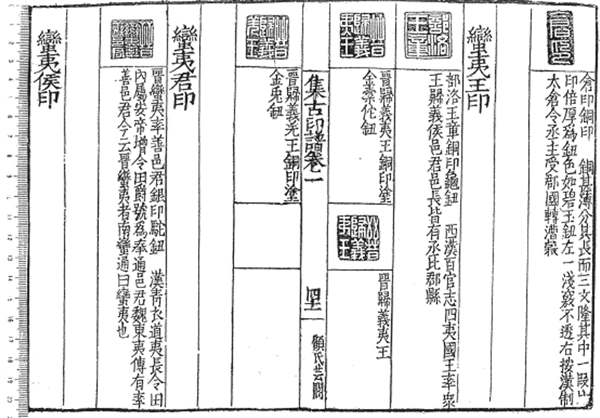
「滇王之印」が1957年に雲南省晋寧県石塞山の土壙墓から出土した。これは金印で蛇の鈕である。 c.金印のつくり しかし、この石塞山の金印は1957年の出土で江戸時代には知る由もない。後から出土した後漢の金印は志賀島の金印と共通点が多いのである。これは志賀島の金印が本物であるということではないか。 |
2.日本語の起源 |
■コンピュータを使って基礎語彙の一致を調べる ・基礎語彙 文化語は変化しやすいが、基礎語彙は変化しにくので、基礎語彙200の単語リストを作成する。そして、基礎語彙200単語を並べて比較し、一致の度合いを調べる。 日本語と朝鮮語とアイヌ語の単語リストの例を下記表に示す。 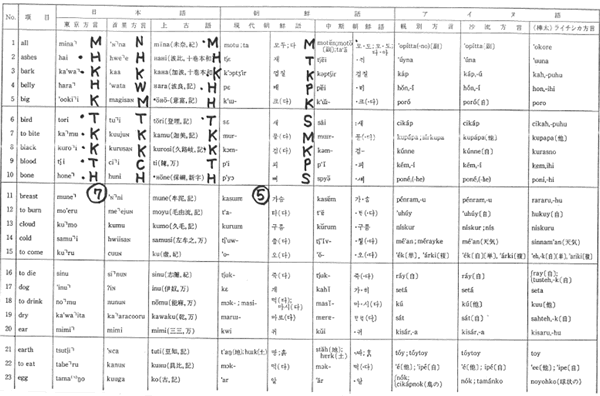 ・実際の手法例 ・シフト法(アメリカのオズワルドによる)
コンピュータで解析した結果は下記の表になる。○は意味が対応する場合の一致で、×は意味が対応しない場合の一致である。上古日本語と中期朝鮮語は○が53であり、シフトによる×平均値が35.95なので、偶然以上の一致と言える。中期朝鮮語とアイヌ語幌別保元も○が57であり、シフトによる×の平均値が37.36なので、偶然以上の一致と言える。
それに対し、日本語はそうではなく、いろんな言語が日本に流れ込んで出来てきた言語である。インドヨーロッパ言語のように強くない。
国語も、古い文化圏の言語の上に、新しい文化圏の言語が重ねられるということが繰りかされてきた。古来、国語の中に流れ入った外国語は、日本周辺の言語としては、アイヌ語、朝鮮語、南方語、そして、最も徹底的には、漢語であり、また、漢語を媒介とする印度の古語梵語である。近世以後においては、ヨーロッパ諸言語がある。 ・日本語の起源・形成のプロセス ・クレオール語(英creole)[またはクリオール言語]は、ピジン言語が母語化したものである。複数のピジンが言語接触を通じて単一のクレオールに収斂する場合もあれば、逆に、一つのピジン言語が歴史的・地域的に複数のクレオールに分化していく場合もある。いずれにせよ、クレオール言語の出現とは、ピジン(ないしその発展形態)を第一言語(first language) として習得し、常用する人々(典型的にはピジン使用者の子供たち)の出現を意味する。すべてのピジンが必ずクレオール化するわけではない。 カリブ海域のハイチ語、インド洋のセイシェル語、西アフリカのシエラーレオネのクりオ語などが特によく知られている |
3.日本古代史についての諸説 騎馬民族説
|
・騎馬民族征服説 邪馬台国は、北九州にあった。邪馬台国の勢力をうけつぐものが、古墳時代前期に畿内にう つり、神権的政権をたてた。そののち、古墳時代前期末(五世紀のころ)、南朝鮮から騎馬民族(夫余民族の一派)がはいり、九州をへて、大和に進出した。この騎馬民族は、大和の神権的政権の地方豪族と合作して、統一国家政権としての大和朝廷を創め、応神、仁徳などの大王の時代となった。 騎馬民族征服説は、東京大学の東洋史家、江上波夫がとなえた。 図で書けば、次の図のようになる。 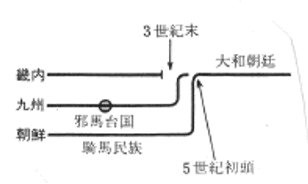 しかし、 ・高句麗の広開土王と戦った日本 まず、「広開土王の碑文」の記事を、とりあげてみよう。 あとを継いだ長寿王(ちようじゅおう)により、広開土王の死後二年(414)に、広開土王の功績を記した石碑が、鴨緑江岸の、通溝(中華人民共和国の吉林省集安県の地)東北方6キロメートルのところに立てられた。広開土王の陵を守護するためのもので、高さ6.3メートルの巨碑である。この碑文は1884年(明治17)に、わが国の学界に紹介された。 「獲るところの鎧鉀一万余領」 「広開土王の碑文」は記す。 ・西暦351~500年の東アジアの国際関係 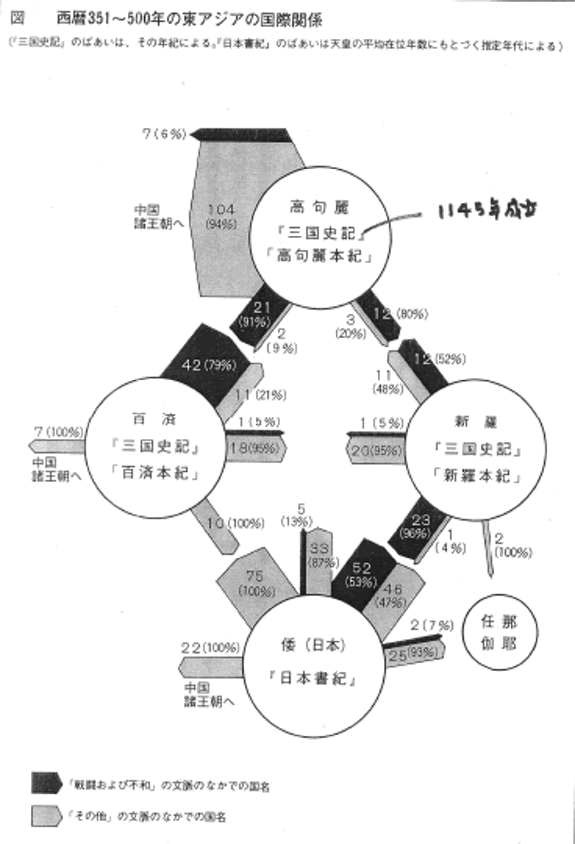 |
4.『魏志倭人伝』を徹底的に読む
|
■狗邪韓国(魏志倭人伝) 従郡至倭循海岸水行歴 ■狗邪韓国はどこか 狗邪韓国は、弁韓べんかん)・辰韓(しんかん)など十二ヵ国の一つである。『三国志』の「弁辰伝」に、弁辰の「狗邪国」とあるのは、狗邪韓国のことである。現在の慶尚南道の金海付近にあった。 (1)倭の一国とみる説 (2)倭の一国とはみない説 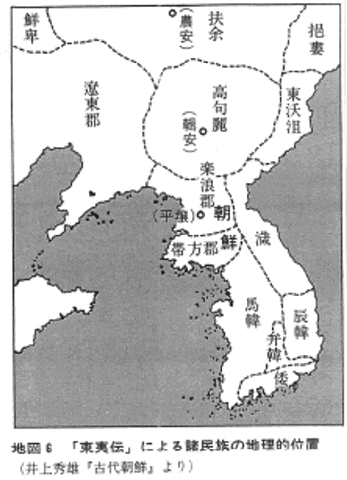 ■対馬国(魏志倭人伝) 七千餘里始度一海千餘 ■対馬国にいたる (2)対馬はもともと一つの島で、江戸時代以降の人工開削によって、北島と南島とがわかれた。すなわち、現在、対馬は大船越、万関瀬戸は昭和にはいってから開削された。したがって『魏志倭人伝』の対馬を、北島か南島かの、いずれか一方だけをさすとする見かたは正しくない(東洋史家の白鳥庫吉は、「方四百余里」の「方」は、周囲を意味すると考え、『魏志倭人伝』の「対馬国」が、対馬全島をさすとすれば、周囲が長すぎるとして、南島だけをさすと考えた)。ただし、「大船越」の名からうかがわれるように、この地を船をかついで越えたことは古代から行なわれた可能性がある。 (3)対馬の主要遺跡は、地図のとおりである。また、対馬からは、百本以上の銅鉾(どうほこ)が出土している(壱岐からは四本のみである)。 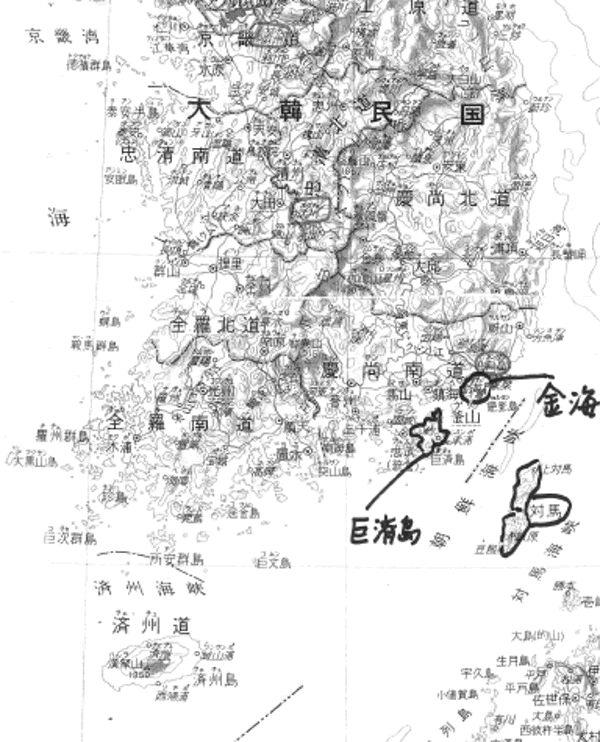 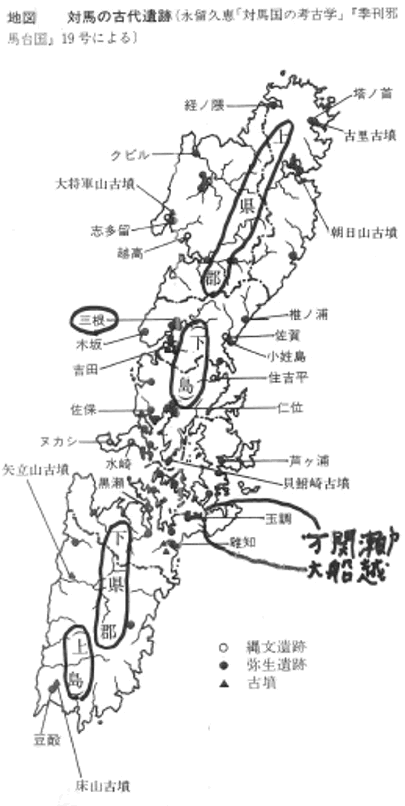 |
| TOP>活動記録>講演会>第311回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |