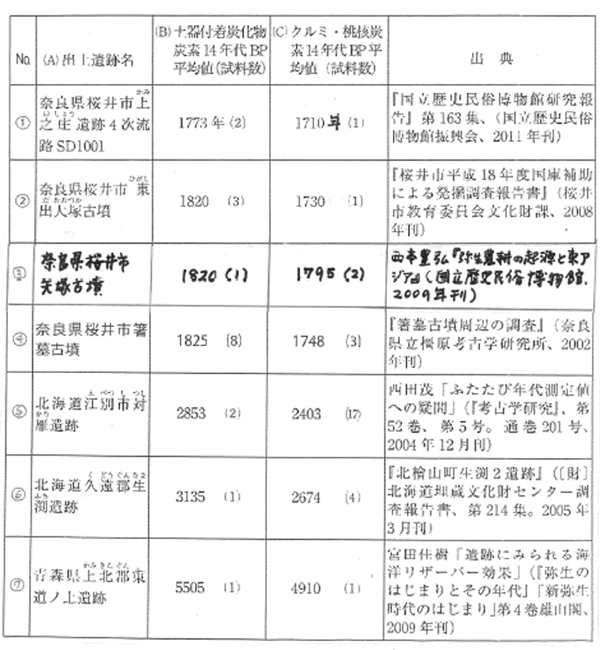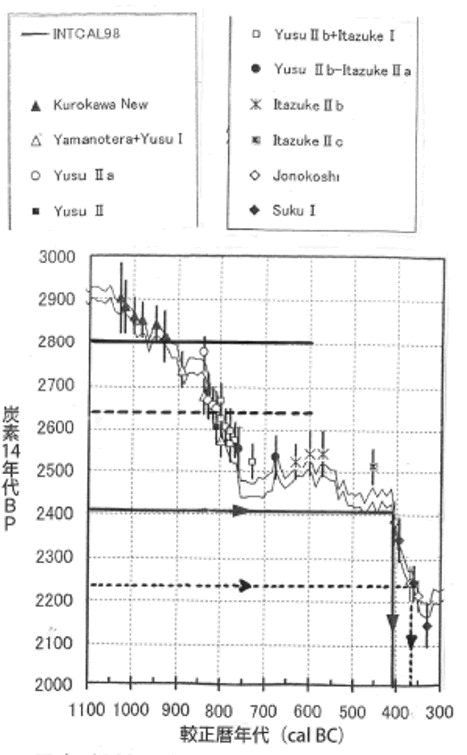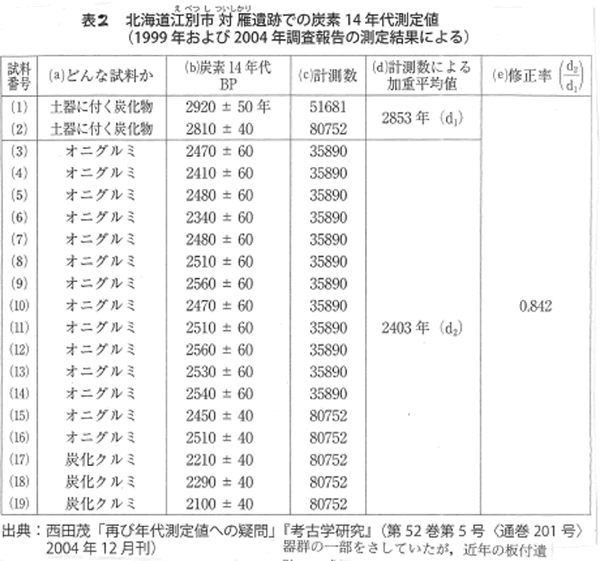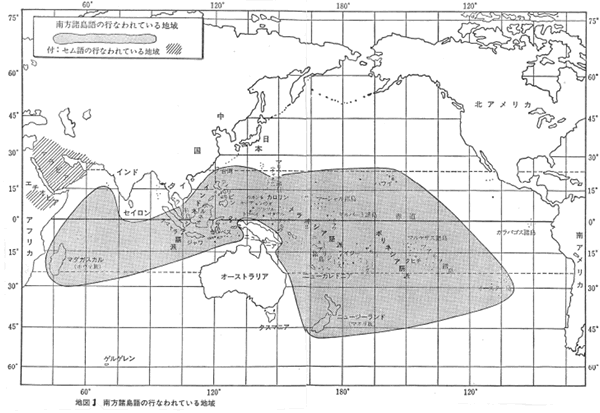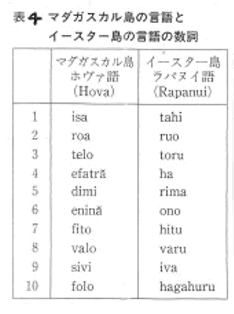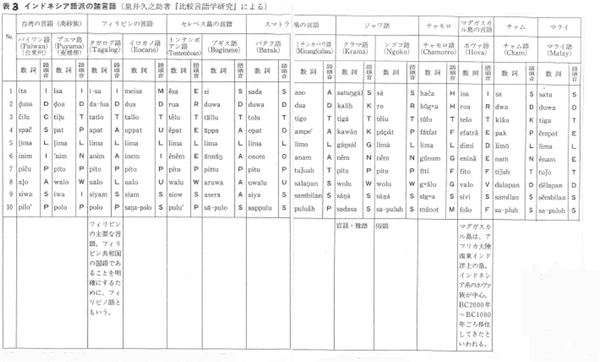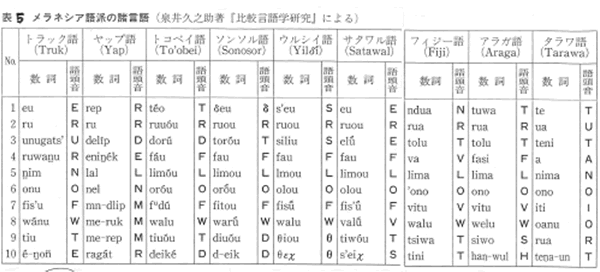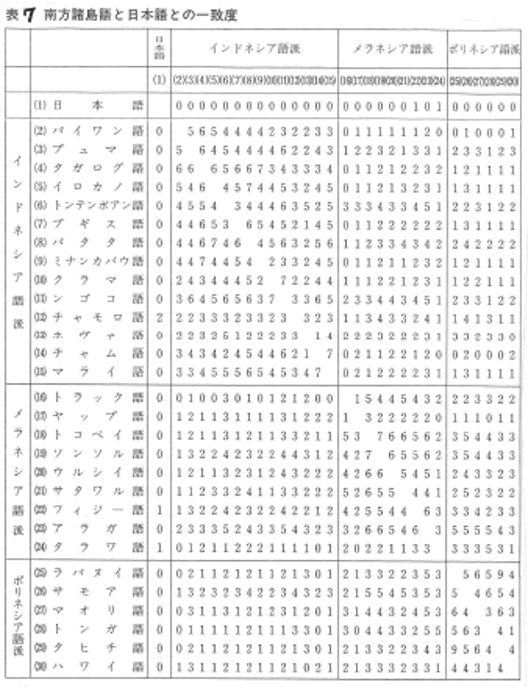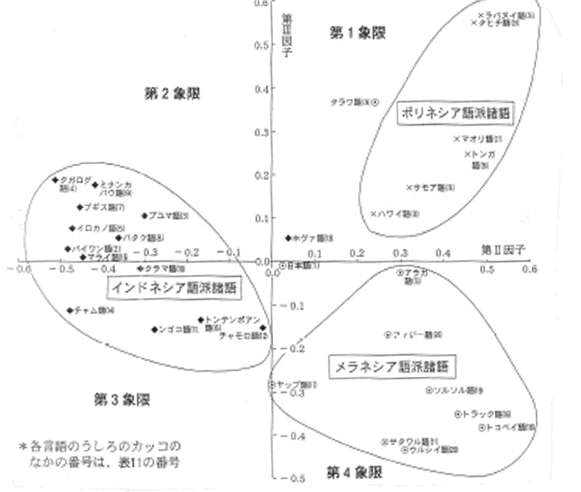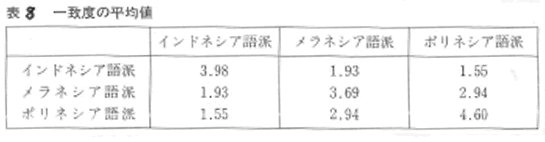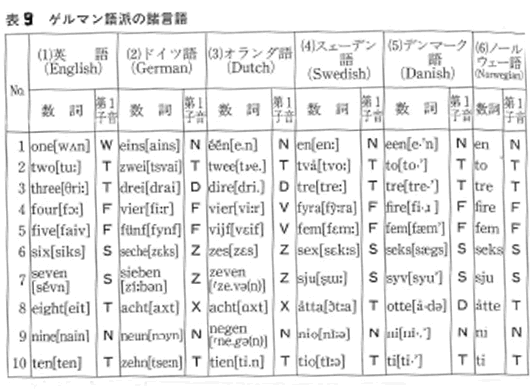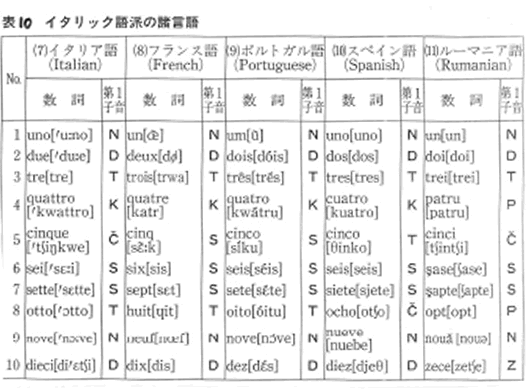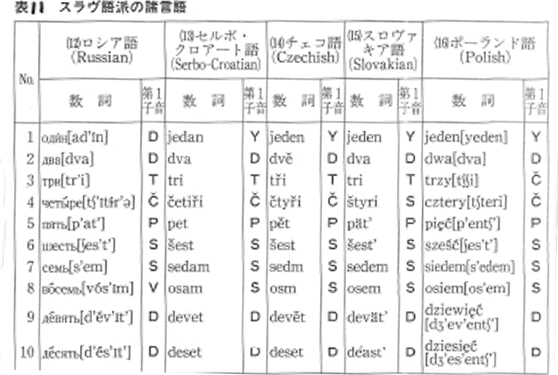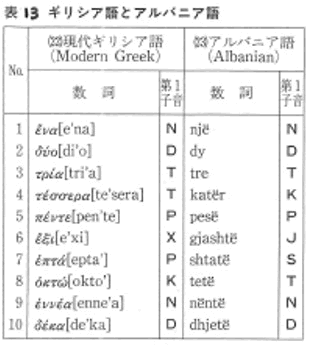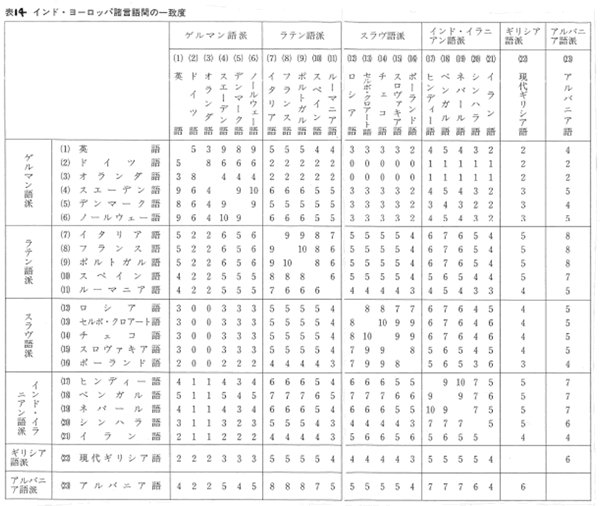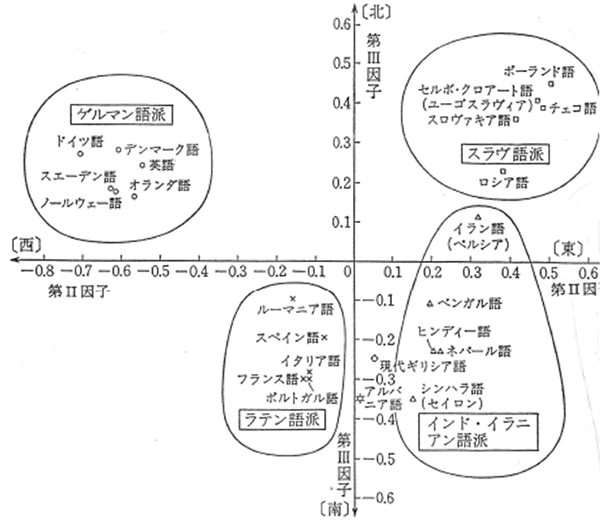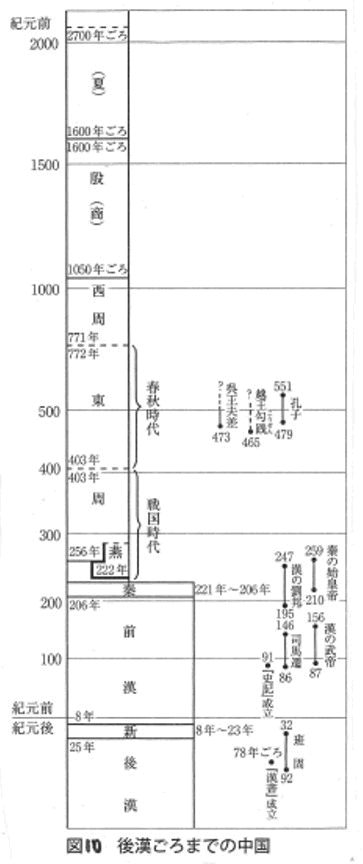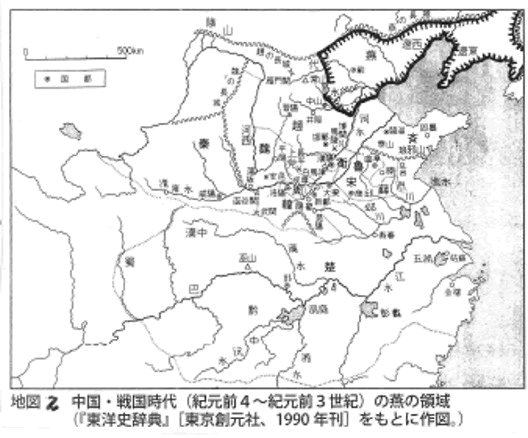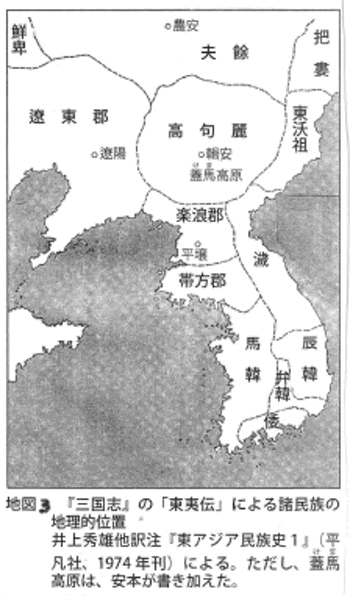| TOP>活動記録>講演会>第310回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第310回 邪馬台国の会(2012.6.24 開催)
| ||||
1.稲作弥生時代の起源
|
歴史民俗博物館は弥生時代のはじまりを古くした。従来、西暦紀元前300年から400年前ごろとしていたのに対し、歴博グループは縄文晩期から弥生前期までの種々の土器付着炭化物を炭素14年代法で分析したところ、弥生時代は紀元前1000年ごろから始まったとした。その根拠は土器に付着した炭化物の炭素14年代法である。 弥生時代が何時始まったかについて二つの考え方がある。 この二つは同じ時期ではない。 ・夜臼(ゆうす)式土器は弥生時代の土器か? 水稲耕作が始まった時期とすると、夜臼1・2a式となり、弥生式土器を重視すると夜臼2b式となる。 歴博は当初、夜臼1・2a式を縄文時代としていたが、途中から、弥生時代からとして定義を変えた。つまり土器の定義も古くしている。そこに土器付着炭化物で分析した結果を使えば、弥生時代のはじまりは1000年くらい前になるわけだ。 ・土器付着炭化物の分析の問題 下のグラフから歴博の主張は夜臼2a式で白い丸である。縦軸はBP2800年となり、較正するとBC900~800年となる。 同じ遺跡から出土したデータ数のある分析結果から、土器付着炭化物とそれ以外の炭化物の違いを修正すると、修正率は0.842となる。上記のBP2800年×0.842=約2400年 になり較正曲線で見るとBC400年になる。 歴博は縄文時代のはじまりも、弥生時代のはじまりも、古墳時代のはじまりも、箸墓古墳のはじまりも古く見ている。注意を要することである。
|
2.日本語の起源(前回から続き)
|
■主成分分析法の結果による諸言語の布置
各言語の語頭の第一子音の一致度を調べ、表14のようにまとめる。因子分析法で表14をコンピュータで分析し、縦軸は地図上の南北、横軸は地図の東西に対応するように配置した。グラフにすると、インド・ヨーロッパ諸言語の近さの度合いを平面上にきれいに分類できる。この結果からゲルマン語派は少し離れていることが分かる。また、現代ギリシャ語やアルバニア語はラテン語派とインド・イラニアン語派のどちらにも属さない中間派的言語であることが分かる。
■統計学による言語学 推計学が、昔の統計学と異なるもっとも大きな特徴は、この10円玉のような問題に対して、確率の考え方にもとづき、判断を客観的に行なう論理と基準を提供したことである。 極端な例として、「インチキなしかけはない」という仮説のもとで、10円玉が100万回つづけて表をだす確率は10の下に、零が30万個つく数分の一より小さい。明らかに、「インチキはない」と判断することはありえない。なぜなら、私たちは、日常においても、学問上においても、たえず、より可能性の小さい仮説はすて、より可能性の大きい仮説を、採択して行こうとしているはずである。私たちは、日常生活においても、「十中八九」正しいと思われる仮説は採択している。 ・「有意」ということば ・水かけ論の原因 ・「語彙統計学」こそが、確実な知識をもたらす |
|
■卑弥呼はどの天皇の時代の人か? それでは、『魏志倭人伝』の伝える「卑弥呼」を、『古事記』『日本書紀』の伝える天皇の系譜の上に位置づけると、どうなるであろうか。卑弥呼はどの天皇の時代の人なのであろうか。おもな説としては、つぎの五つがある。 以上のうち、(1)の「卑弥呼=神功皇后説」、(2)の「卑弥呼=倭姫説」、(3)の「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」は、だいたい、「邪馬台国=大和説」となる。(4)の「卑弥呼=天照大御神説」、(5)の「卑弥呼=九州の女酋説」は、「邪馬台国=九州説」となる。 ■天皇継承について 慶応大学の教授であった橋本増吉は、大著『東洋史上よりみたる日本上古史研究』(東洋文庫、1956年刊)のなかで、つぎのようにのべている。 「わが国の古代における皇位継承の状態を観察すると、神武天皇から、仁徳天皇にいたるまでの16代の間は、ほとんど全部父から子へ、子から孫へと垂直的に継承されたことになっている。しかし、このようなことは、私の大いに疑問とするところである。なぜならば、わが国において史実が正確に記載し始められた仁徳以後の歴史、とくに奈良朝以前の時代においては、皇位は、多くのばあい、兄から弟へ、弟からさらにつぎの弟へと、水平的に伝えられているからである。かの仁徳天皇の三皇子が、履中・反正・允恭と順次水平に皇位を伝え、継体天皇の三皇子が、安閑・宣化・欽明と同じく水平に伝え、欽明天皇の三皇子・一皇女の四兄弟妹が、敏達(びたつ)・用明・崇峻・推古と同じく水平に伝えたがごときは、その著しい例である。したがって、この事実を基礎として考えるときは、仁徳天皇以前における継承が、単純に、ほとんど一直線に垂下したものとは、容易に信じがたいのである。 山路愛山は、その力作『日本国史草稿』において、このことに論及し、『直系の親子が縦の線のごとく相継いで世をうけるのは、中国式であって、古(いにしえ)の日本式ではない』。それは、『信ずべき歴史が日本に始った履中天皇以後の皇位継承の例を見ればすぐわかる』『仁徳天皇から天武天皇まで通計二十三例のあいだに、父から子、子から孫と三代のあいだ、直系で縦線に皇位の伝った中国式のものは一つもなく、たいてい同母の兄弟、時としては異母の兄弟のあいだに横線に伝って行く』『もし父子あいつづいて縦に世系の伝って行く中国式が古(いにしえ)皇位継承の例ならば、信ずべき歴史が始ってからの23帝が、ことごとくその様式に従わないのは、真に異常のことと言わなければならない。ゆえに私達は、信ずべき歴史の始まらないまえの諸帝も、やはり歴史後と同じく、多くは同母兄弟をもって皇位を継承したであろうと信ずる』と喝破しているのは傾聴すべきである」(「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫」『考古学雑誌』第14巻、第7号、1924年[大正13年]4月、所収) 即位、退位の時期がはっきりしている用明天皇以後の天皇の一代平均在位年数を算出した。しかし、もし、父から子へという形で皇位の継承がおこなわれたばあいだけをとりだして、一代平均の在位年数を算出すれば、その値は、もっと大きくなるのではないであろうか。そこで、確実な歴史時代にはいってからの、父子継承のばあいの、一代平均在位年数をしらべてみよう。 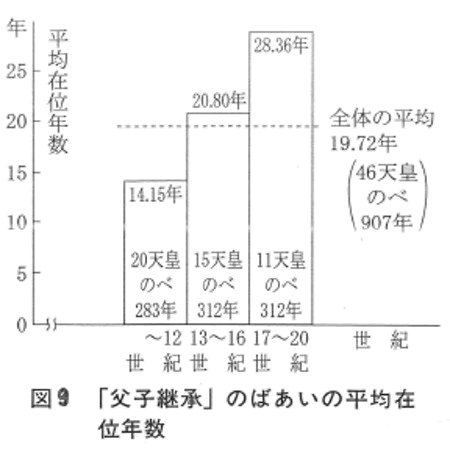 「兄弟継承」の場合、全体での平均在位年数は、10.5年であるが、とくに10世紀以前に即位した8人の天皇をとりあげれば、その平均在位年数は、わずか、6.75年である。 また、表15をみれば、2年とか、3年とか、5年とか、現代ではあまり考えられないほど短い在位年数の天皇も、何人か存在していることに気がつく。 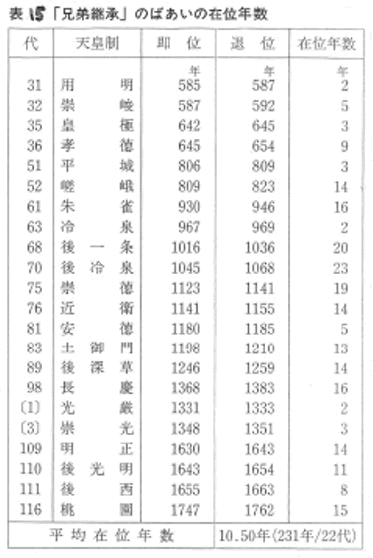
百済王の系譜をとっても、『日本書紀』と『三国史記』では系図が違っている。王の代は一致しているが、親子関係などは違っている場合がある。この結果は王の名は確実に伝えられるが、親子関係などは正確に伝わらないことを示している。 このように、父子継承としても、世代間の年数が違っていること、父子関係情報があてにならないことなどから、笠井新也、白石太一郎の説による年代論で崇神天皇(倭迹迹日百襲姫)の時代が3世紀中頃とすることはない。このように卑弥呼=倭迹迹日百襲姫が成り立たなければ、箸墓古墳=卑弥呼の墓は成り立たない。 |
|
■倭の国々 ・朝鮮について 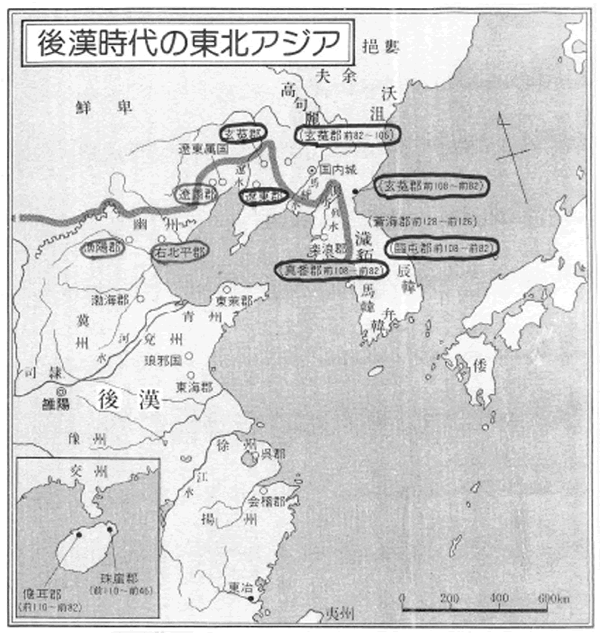 ・どこから出発したか (2)帯方郡の郡治の所在地とし、その位置を、現在の黄海北道沙里院(さりいん)付近とする説 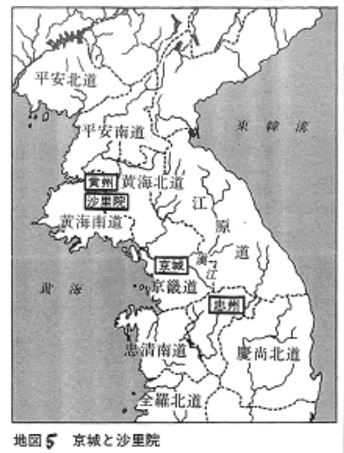 (2)説の「帯方太守張撫夷塼」について、森浩一氏の説がある。 この方墳は一辺約30メートル、高さが約5メートルあって、墳丘内部に塼積の横穴式の墓室がある。塼とは煉瓦のことだが、その塼には「使君帯方太守張撫夷塼」と型押しされていた。これによって墓の主の地位と名が判明した。この古墳の年代は288年ごろとみられ、帯方郡滅亡の少し前に当る。 張撫夷の古墳の年代は帯方郡が濊や韓に滅ぼされる年に近い。すでに述べたように正始8年(247年)には帯方郡の太守弓遵が濊との戦で死んだ。濊は朝鮮半島の北東の日本海(東海)沿岸にあって、濊貊(かいはく)ということもあって扶余や高句麗とも親縁関係にあった。楽浪郡や帯方郡はその鎮圧に長年苦慮してきた。 ■公孫氏と明帝 238年12月8日、明帝は、病の床についた。239年の正月1日に、司馬懿仲達が、遼東から帰還した。明帝は、司馬懿仲達を、寝室にいれ、後事をたくした後、死去した。時に36歳であった。(宋の裴松之[はいしょうし]は、明帝はなくなったとき、34歳のはずであるという)。 このように、遼東の地で自立し燕王と称した公孫氏は滅んだが、公孫氏が遼東付近を支配していたころ、倭は魏に使いを出す時に、公孫氏に阻まれたはずである。公孫氏が魏により滅ぼされてから、使いを出し、魏の記録に残るようになったと考えられる。 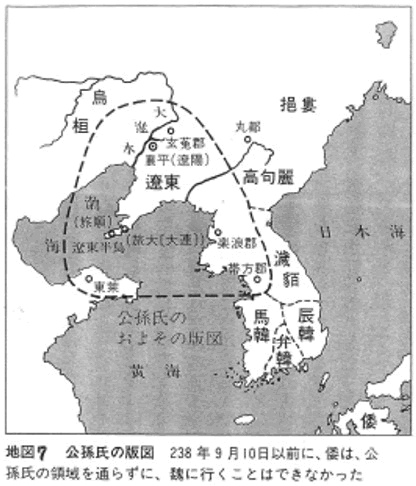 |
5.燕国の影
|
■刺客、荊軻(けいか) 「『史記』刺客列伝には、暗殺を決行しょうとした刺客荊軻の行動がじつにドラマティックに措かれている。燕の太子丹の命を受けた荊軻は、秦王への土産として秦の樊於期(はんおき)将軍の首と、督亢(とくこう)という豊かな地図をもち、秦舞陽(しんぶよう)を連れて出発した。燕の易水[えきすい](地図参照)という川のほとりで見送られるときに、筑(ちく)という楽器に合わせて別離の悲しみを歌った詩はよく知られている。皆白い装束を着て見送った。易水のほとりまで来ると、道祖神を祀り、高漸離(こうぜんり)は筑を撃ち、荊軻はこれに合わせて歌った。見送りの者はすすり泣いた。荊軻はさらに歌った。 「風粛々(しょうしょう)として易水寒し、壮士一たび去って復た還らず。」 「一行は咸陽(かんよう)に到着し、秦王を襲うクライマックスに入っていく。後漢時代の画像石(がぞうせき)は、死者を祀る廟の壁画の石に刻まれたものである。荊軻が秦王を暗殺しょうとする場面が時間を凝縮して一場面に描かれている。いま『史記』刺客列伝の記述に従って画面を見てみよう。秦王から咸陽宮に迎え入れられた荊軻は、樊於期の頭を入れた函を持ち、秦舞陽は地図の箱を捧げて進んだ。いざ秦王の前に出ると秦舞陽は恐れ震え出したので、群臣は怪しんだ。画像石(図11)画面右下に伏せる秦舞陽の姿はその瞬間だ。荊軻は振り返って笑い、『北方の蛮夷のいなかものゆえ、天子にお目にかかったことがないのです』とわびた。秦王が『地図を取らせよ』といったので、荊軻は王に渡した。最後まで開くと、隠してあったヒ首(あいくち)が現れた。刑軻は左手で秦王の袖をつかみ、右手でヒ首を持って刺そうとした。しかし身に届かないうちに、秦王は驚いて立ち上がったので、袖がちぎれた。画像石の中央右、ちぎれた袖が宙に浮いている。秦王は剣を抜こうとしても、とっさのことで剣が堅くて抜けない。荊軻は秦王を追い回し、秦王は柱を回って逃げた。柱の左右に靴を残して逃げる秦王と髪を逆立てる荊軻が対照的に刻まれている。 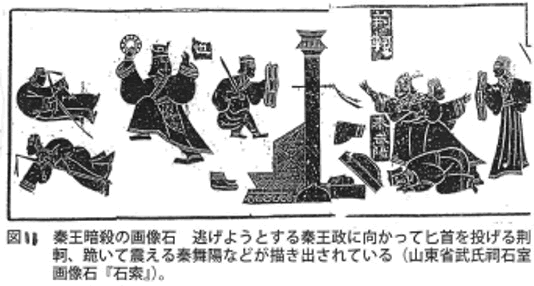
「蓋国(がいこく)は鉅燕(きょえん)の南、倭の北にあり。倭は燕に属す。」 このように、『山海経』はあまりあてになる文献とは言えないが、『漢書』の記載もあり、倭は燕とつながりがあったと考えられる。燕の名は公孫氏にまで使われる。 |
| TOP>活動記録>講演会>第310回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |