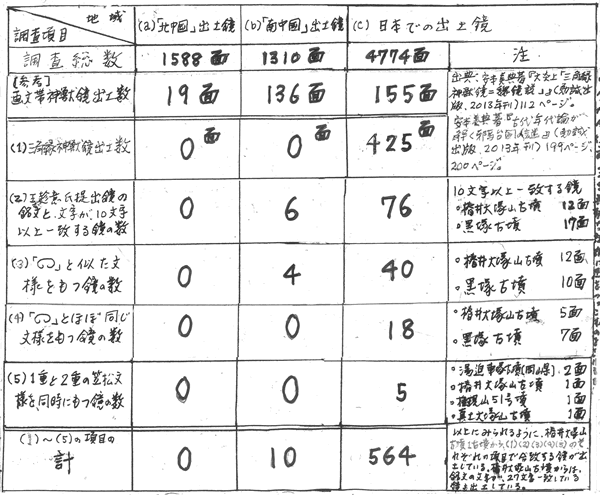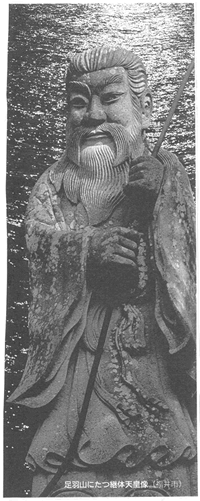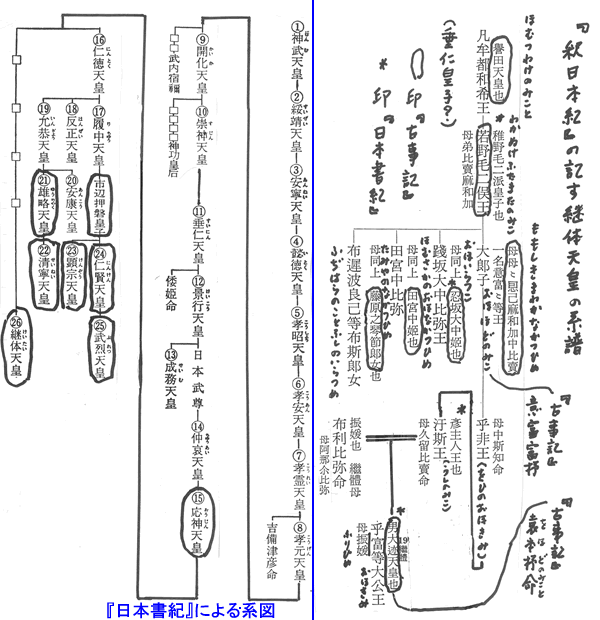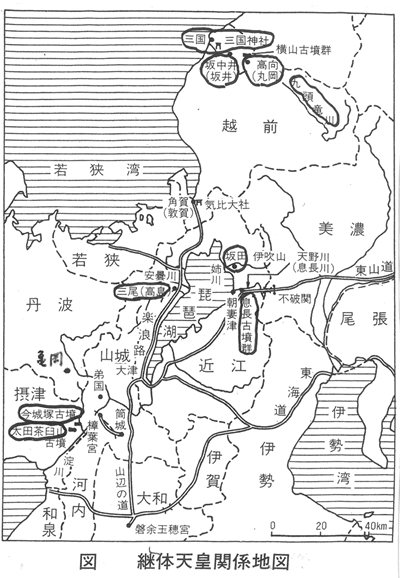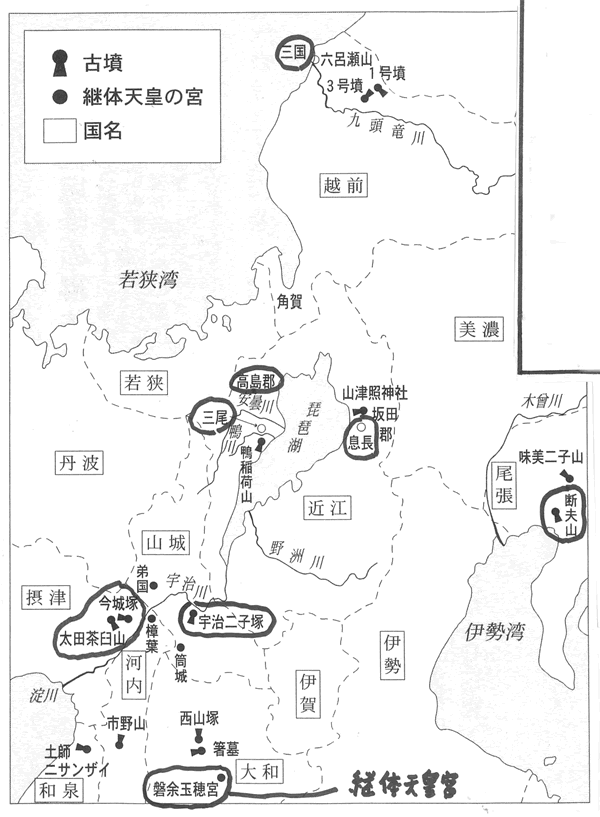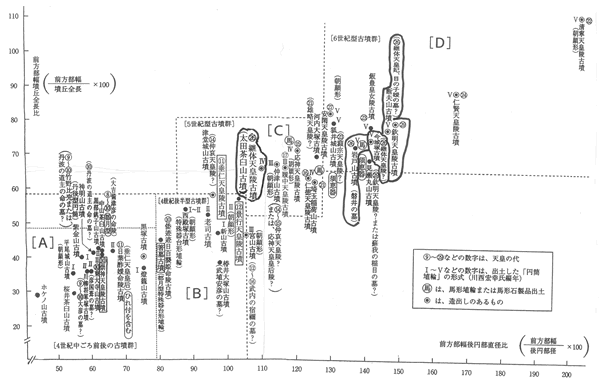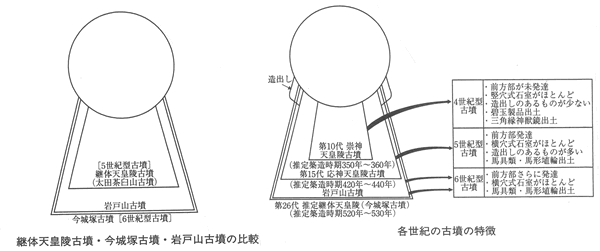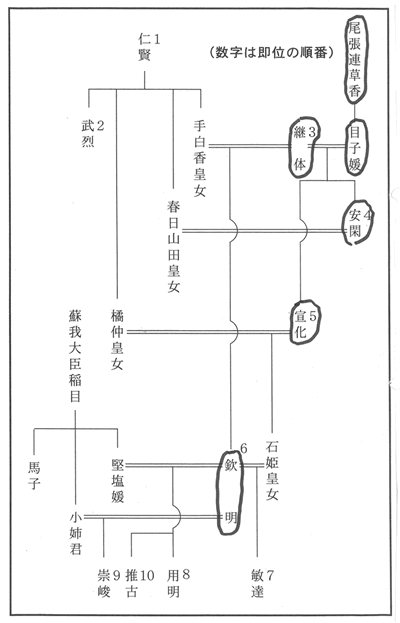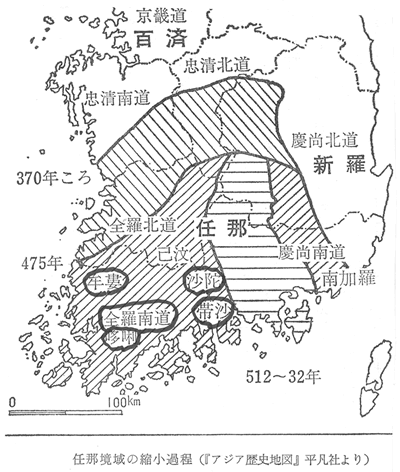| TOP>活動記録>講演会>第346回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第346回 邪馬台国の会(2016.2.28 開催)
| ||||
1.復習と補足「洛陽で新発見の三角縁神獣鏡について」
|
1.1 捏造の土壌 このように、出土が分からないような物で議論することは意味がないことである。 中国の考古学者、王仲殊氏「正始五年作」の銘のある鏡について、(『三角縁神獣鏡の謎』(角川書店、1985年刊) このように、目で真贋を見分けようということは難しいことである。 インターネット上にこの件に関する情報が多くある。その一部を紹介する。 ・鉛同位体比の分析など、科学的な調査も踏まえて、適切な断言が求められるところである。考古遺物なら得体の知れないものを信用してはならないというのが、これまでの大きな経験則でもある。 ・河南省で作られた贋作は、主に北京市の潘家園(はんかえん)骨董市場に運ばれ販売されます。業者は潘家園骨董市場でこの市場で贋作の骨董を仕入れ、北京市内や各地の骨董品店のショーケースに本物としで並べられます。潘家園骨董市場では1日当たり1万点の美術品が売れているそうで、そのほぼ全てが贋作だという定評です。 ■中国広東省深圳市(しんせんし)の油画村(ゆがむら) また、『北海道新聞』2016年2月7日(日)の書評で
本の森書評 斉藤泰嘉 筑波大教授のものがある。 この本がなぜこれほどまでの大著になったかといえばウォング氏が参与観察で得たインタビュー記録や写真などの研究資料を現代哲学(ポスト構造主義)や現代美術(コンセプチュアルアート)の視点から精緻に分析していることがあげられる。 こうした知的論述に加え、ウォング氏の興味深い体験談も随所にちりばめられている。ウォング氏は自分が働いた工房で模写の際、あまり「稿」(原画の写真)を見るなと親方から指導された。「個人的味道」が宿らなくなるというのがその理由である。親方は、徒弟たちに対し、印刷されたゴッホ作品よりも店で売っている完成作品(複製)をよく見るように指導したという。 本書の表紙を飾る写真にはゴッホの複製画(自画像)を広げて見せるゴッホ専門の画家の姿がうつっている。その絵のゴッホの顔がその男性に似ている。創造性とは無縁のはずの複製であっても、それが手描きの模写である限り、複製する者の個性がおのずと絵ににじみ出る。これはゴッホの絵なのか、それを模写した男性の絵なのか。機械による複製とは全く違う複製それは生命が生命を相手に自己を複製する行為に似ている。本書には、原画(親)と複製品(子)、そして生命について考える手がかりが満ちている。 このような現代美術(コンセプチュアルアート)の視点に立つことは、今回の三角縁神獣鏡でも言える。複製品でも前のものをそのまま模写するのではなく、複数のものを持って来て、一つのものを作ることである。
■「レコードチャイナ」から ・北京市の骨董市場・潘家園骨董市場。この市場では骨董品の贋作が数多く販売されている。この市場で仕入れられた安値の贋作骨董品の多くは、骨董品店のショーケースに本物として並べられることになる。 ・北京市で流通している贋作の多くは河南省で製造されたもの。河南省平頂山市宝豊県汝瓷研究所の馬聚魁(マー・ジュークイ)所長によると、同省には贋作作りを主要産業としている村がいくつもある。ある300世帯ほどの小さな村には20以上もの工場があり、加えて無数の小工房まであるのだとか。
・北京大学文化財学院の李彦君(リー・イエンジュン)院長によると、中国骨董品市場の問題点は市場秩序が乱れている点だという。すなわち、最も怪しげに見える露店や個人商店がまだましで、正式な店舗の方がニセモノが多い。いや、それどころか、一番ニセモノが多いのは、正規の企業によるオークションだとか。なんと半数以上がニセモノだという。「真贋についてはオークション企業が責任を負わない」という条項があり、こうした無法がまかり通っていると明かした これによると、河南省が贋作骨董を製作する地域であることが分かる。 今回の王趁意氏の「三角縁神獣鏡」に関連する地域を地図に示す。
1.2 捏造の証明 旧石器捏造事件がおきたとき、人類学者で、国立科学博物館人類研究部長(東京大学大学院理学系生物科学専攻教授併任)の馬場悠男(ばばひさお)氏がのべている。 経験から見ると、国内外を問わず、何ヵ所もの自然堆積層から、同じ調査隊が、連続して前・中期旧石器を発掘することは、確率的にほとんどあり得ない(何兆分の一か?)ことは常識である。 考古学者は、旧石器捏造事件から何も学ばなかったのか。 考古学の分野では「情報考古学」をのぞき、このような科学一般における基本的な「リテラシー(知識、方法、読み書きそろばん的なもの)が、いまだに一般化していないようにみえる。 ■王趁意氏提出鏡には、以下にのべるように、確率的にみて何重もの不自然さがある。 ②王趁意氏提出鏡の銘文が、前回のべたようにたった2冊の本で、すべてまかなえるのは不自然である。しかも、わが国で刊行されている『古鏡総覧(Ⅰ)』1冊で、銘文31文字中の30文字、97パーセントがまかなえる。世界の、どのような2冊をとってきても、このようなことは、不可能である。中国の20冊ほどの代表的な鏡の資料集ではできない。 ③以上のべたことと同様の現象が、くりかえしおきている。 西川氏がとりあげるキサゲにしても、サビにしても、一重と二重の笠松型文様にしても、王趁意氏がその論文のなかで、ウンチクをのべているものばかりである。私の立場からみれば、王趁意氏が、この点に特に留意して、鏡を作るよう指示しましたとのべているようにしか思えない。この鏡が、本物であるという西川氏独自の根拠をのべていない。専門家の目をあざむくために作ったかもしれないものを本物か贋物かをみわけるための議論をするのは、きわめて非生産的な議論で時間とエネルギーのむだである。
|
2.六世紀・継体天皇の謎
|
■5世の孫は本当か 『古事記』にも「品太王 五世の孫袁本杼命」。
『古事記』『日本書紀』には応神天皇から継体天皇までの5代において、途中の人の名前が書かれていない。『日本書紀』の別途あったと言われている系図にはあったかもしれないが失われたため、残っていない。(『日本書紀』から作成された系図は下図参照) 『日本書紀』から作成された系図では分からない、中間の人々について、『釈日本紀』の記す継体天皇の系譜には名前が書かれている。(下図参照)
■出身地は近江説か越前説か
このように、継体天皇の父親が近江で、母親が越前であったのではないか。そのために、『古事記』は近江、『日本書紀』は越前となったのではないか。 ■継体天皇陵はどこか ・宮内庁調査 ・外堤護岸工事事前調査で
また、宇治の二子塚古墳について、京都橘女子大学の門脇禎二氏は、『継体天皇と今城塚古墳』のなかで、つぎのようにのべる。
今城塚古墳が継体天皇陵でよいと言うことは、古墳の築造年代から言えることであり、そのことは円筒埴輪から分かることであるが、別の方法である前方後円墳の前方部の発達度合いからも言える。
今城塚古墳は継体天皇妃の目の子媛の墓と言われている断夫山古墳や欽明天皇陵も同じ時期と考えられる。しかし、宮内庁が継体天皇陵とする太田茶臼山古墳は5世紀となってしまう。 継体天皇陵古墳(太田茶臼山古墳)と今城塚古墳の前方後円墳の前方部の発達の違いを図示すると下記となる。
継体天皇は尾張の目の子媛を妃として、天皇の位につく前に生まれた子が安閑天皇、宣化天皇である。天皇の血が薄い人が天皇の位につくと、天皇の血の濃い人を嫁にもらい、血の濃い子に継いでいく。そこで、仁賢天皇の子である手白香皇女(てしろかひめみこ)を妃として、欽明天皇とする。しかし、継体天皇が亡くなった時、欽明天皇は幼かったので、安閑天皇、宣化天皇となった。
・磐井が大彦の子孫である記述 『日本思想体系1』『古事記』(岩波書店刊)補注 ■百済へ四県割譲 『日本書紀』「継体天皇紀」6年12月の条に四県割譲の記事がある。 ここで、四県は全羅道の殆ど全域に及ぶ地域である。 ■継体天皇の没年は何年か 冬十二(ふゆしわす)の丙申(ひのえさる)の朔日(ついたち)庚子(かのえねのひ)に、藍野陵(あいののみささぎ)に葬(はぶ)りまつる。或本(あるふみ)に云(い)はく、天皇、二十八年[西暦534年]歳次甲寅(きのえとらにやどるとし)に崩(かむあが)りましぬといふ。而(しか)るを此(ここ)に二十五年歳次辛亥(かのとのいのとし)に崩(かむあが)りましぬと云(い)へるは、百済本記(くだらほんき)を取りて文(ふみ)を為(つく)れるなり。其の文に云へらく、太歳辛亥(かのといのとし)の三月(やよい)に、軍(いくさ)進みて安羅(あら)に至りて、乞乇城(こつとくのさし)を營(つく)る。是の月に、高麗(こま)、其の王安(こきしあん)を弑(ころ)す。叉聞く、日本(やまと)天皇及び太子(ひつぎのみこ)・皇子(みこ)、倶(とも)に崩薨(かむさ)りましぬといへり。
亡くなった年について、辛亥(しんがい)の年について25年(西暦531年)としているが、これは百済本記からとると25年になるのである。本当は甲寅(こういん)の年で28年(西暦534年)である。 百済本記に辛亥の年に日本の天皇が亡くなったとしたからである。これは『日本書紀』の編者が百済本記の年代を60年ずらして解釈したのだと思われる。 百済本記は雄略天皇が即位した頃を書いたものである。安康天皇が亡くなり、多くの皇子が殺された。 岩波書店文学大系本頭注に下記がある。 補注は下記である。 ・その第一は、書紀は百済本記により継体天皇は二十五年辛亥(しんがい)の年の崩とするが、次の安閑天皇は甲寅(こういん)[西暦534年]の年即位と明記していて、その間二年間の空位期間がある。しかも安閑紀では継体天皇崩御の直前に皇位を譲ったことになっていて、継体崩御と安閑即位とは同じ年の出来事であり、ここに矛盾がある。又、古事記は継体天皇の崩御を丁未(ていび)[西暦527年]の年のこととしており、一方、書紀も二十八年甲寅(こういん)崩御という一説をも挙げていて、諸説が一定していない。 ・第二に、百済本記の文(四六頁一三行)は、辛亥(しんがい)の年に日本の天皇及び太子皇子がともに死んだという奇怪な記事であって、そこに何か不思議な事件があったように思われる。 ・第三には、有名な仏教公伝の年の年は、書紀では欽明十三年(552年)壬申(じんしん)の年のことにしてあるが、帝説では欽明天皇の戊午(ぼご)年(538年)とし、又、元興寺縁起でも欽明天皇七年戊午(538年)の年のこととする。書紀紀年では欽明朝に戊午の年はなく、しかも書紀では欽明天皇の治世は三十二年間であるが、帝説では四十一年間とあって、食違いがある。 大体以上のような諸点で書紀紀年には大きな問題があるので。これらを合理的に説明しようとして、さまざまな試みが行なわれて来た。その中で平子鐸嶺の説は仏教公伝の年に関する帝説・元興寺縁起の説を生かし、継体紀には七年紀(513年)と二十三年紀(529年)に同じ事が重出しているから錯簡が多いとして書紀紀年を大幅に組替え、継体二十三年に薨じた大臣巨勢男人が、続紀では次の安閑朝にも大臣であったと見えているから、書紀の継体二十三年は実は既に安閑朝に入っていたとし、安閑・宣化の両両を書紀紀年の継体朝の末尾に繰入れて、辛亥の年は継体の崩御でなく、宣化崩御の年(539年)であるとした。 これに反し、喜田貞吉は、欽明天皇の治世は帝説の如く四十一年と見るべく、そうすればその元年は辛亥となり、継体の崩年と同じ年となる。そこで継体天皇の次には実は欽明の即位があったのであるが、これを認めない一派があって、二年を経た甲寅の年に安閑天皇が即位し、続いて宣化天皇が即位した、即ち、安閑・宣化朝と欽明朝の初年は並立したのであって、宣化天皇崩御の後、両朝は合一したのであろうと考えた。 この両朝並立の立場を推しすすめて、内外の情勢からこの期間を内乱の時期として説明しようとしたのが林屋辰三郎で、継体天皇は畿外から大伴氏に擁立されて立ち、反対勢力に妨げられて大和に入るまでに二十年を要する状態であり、半島では朝鮮経営が失敗し、多くの負担を受けて不満を抱いた族長たちの反乱が起こった。その一例が筑紫の磐井の乱であり、継体天皇の崩御に当ってば、辛亥(531年)の変ともいうべき内乱状態があったとした。 そして継体天皇の次には蘇我氏に擁立された欽明天皇が即位したが、一方、大伴氏らはこれに対して二年を経て安閑天皇を擁立し、宣化天皇の崩後、両朝は合一して内乱は収拾されたと推測した。以上の諸説は、継体・欽明朝の紀年の矛盾を合理的に説明しようとした見解であるが、他にも、原勝郎・坂本太郎以下諸種の論がある。
『日本書紀』「神功皇后紀」62年条に似たような話がある。 注:葛城襲津彦(かずらきのそつひこ)は記・紀にみえる伝承上の人物。『古事記』によれば、建内(武内)宿禰(たけうちのすくね)の子とされ、玉手臣(たまてのおみ)、的臣(いくはのおみ)、生江臣(いくえのおみ)、阿芸那臣(あぎなみのおみ)の祖。『日本書紀』には神功(じんぐう)巻から仁徳(にんとく)巻に新羅(しらぎ)、加羅(から)、百済(くだら)など朝鮮に派遣されたことがしるされている。 ここで、『日本書紀』の神功皇后紀六十二年は西暦262年で壬午(じんご)年とされる。年代を新しく考えた場合、百済紀の壬午(じんご)年は382年ではなく442年である。 ■継体とは ヒツギノキミと訓む。ここの「継体」は、第二十六代の継体天皇の意ではなく、皇位を嗣ぐ者の意、「継嗣」である。 |
| TOP>活動記録>講演会>第346回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |
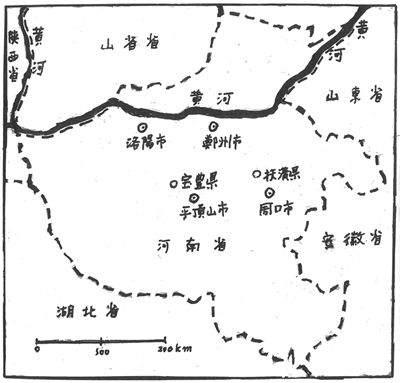 ・もちろん本物の骨董品らしく見せる手法もすでに確立している。磁器の場合には完成後、2~3年土に埋めておき、最後に塩酸と無水アルコールを塗布する。こうすれば磁器に土がしっかりと張り付き、あたかも長年土に埋もれていたように見えるのだという。銅器の場合には分厚い手袋をはめた職人がへりを手でこすり、鉄の棒で叩いてゆがみをつくる。最後に使用した形跡をつくるため、化学薬品を塗って腐蝕層を作り上げる。
・もちろん本物の骨董品らしく見せる手法もすでに確立している。磁器の場合には完成後、2~3年土に埋めておき、最後に塩酸と無水アルコールを塗布する。こうすれば磁器に土がしっかりと張り付き、あたかも長年土に埋もれていたように見えるのだという。銅器の場合には分厚い手袋をはめた職人がへりを手でこすり、鉄の棒で叩いてゆがみをつくる。最後に使用した形跡をつくるため、化学薬品を塗って腐蝕層を作り上げる。