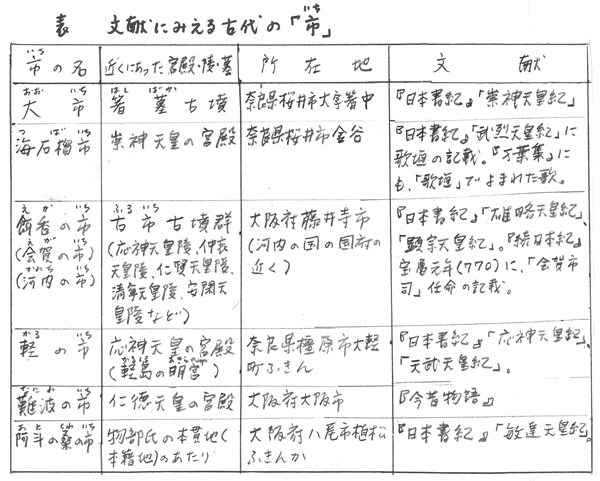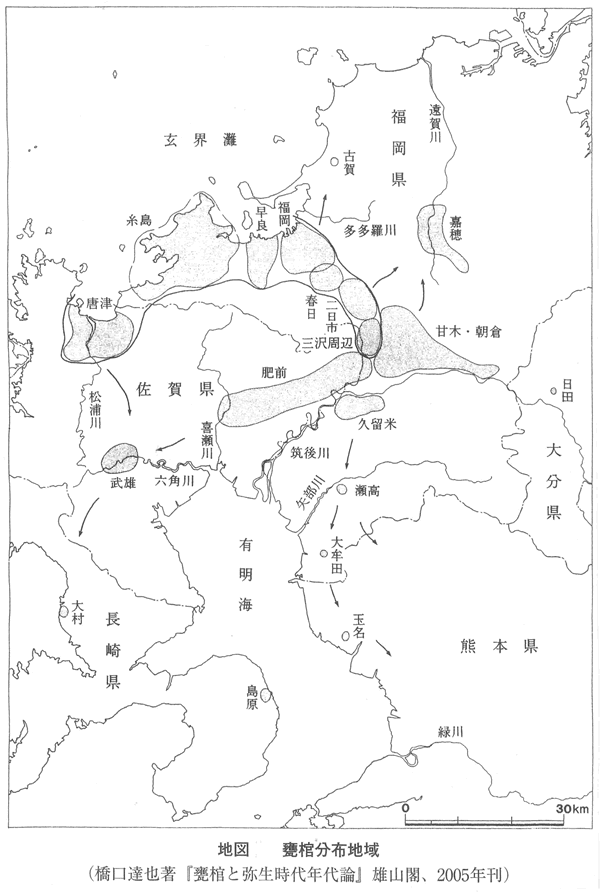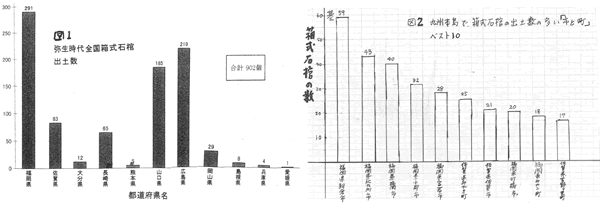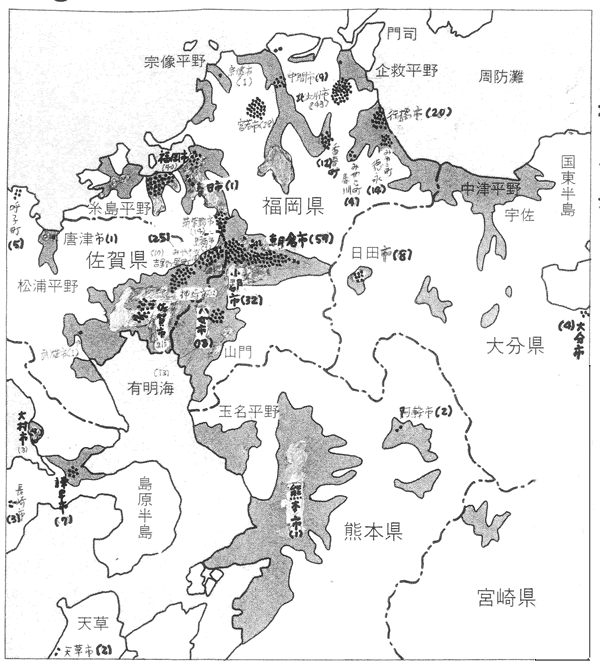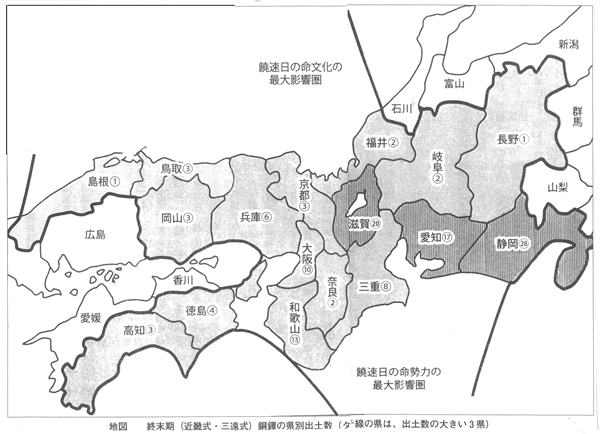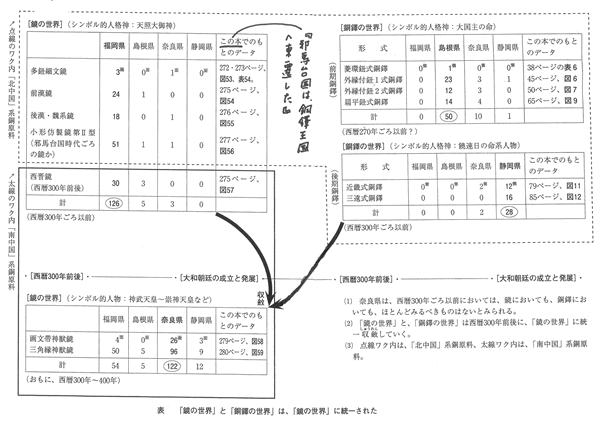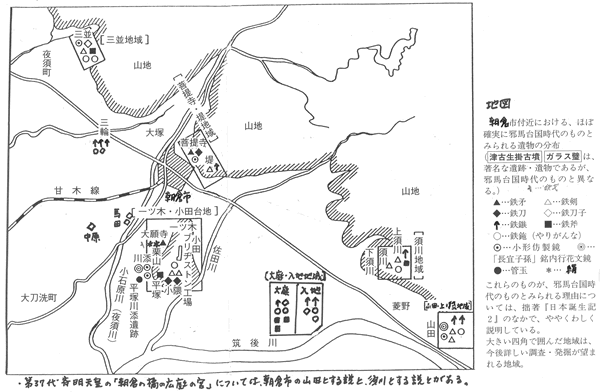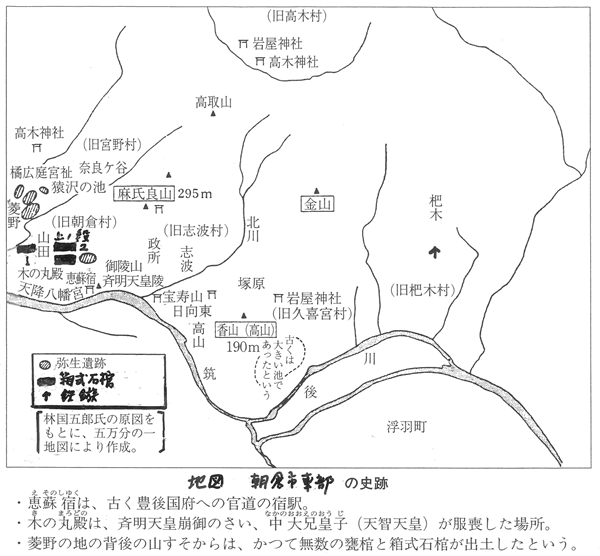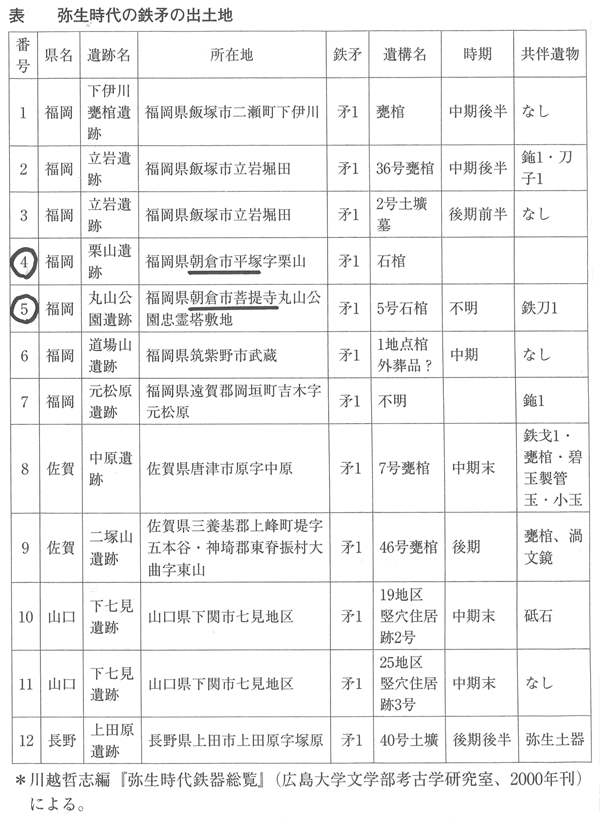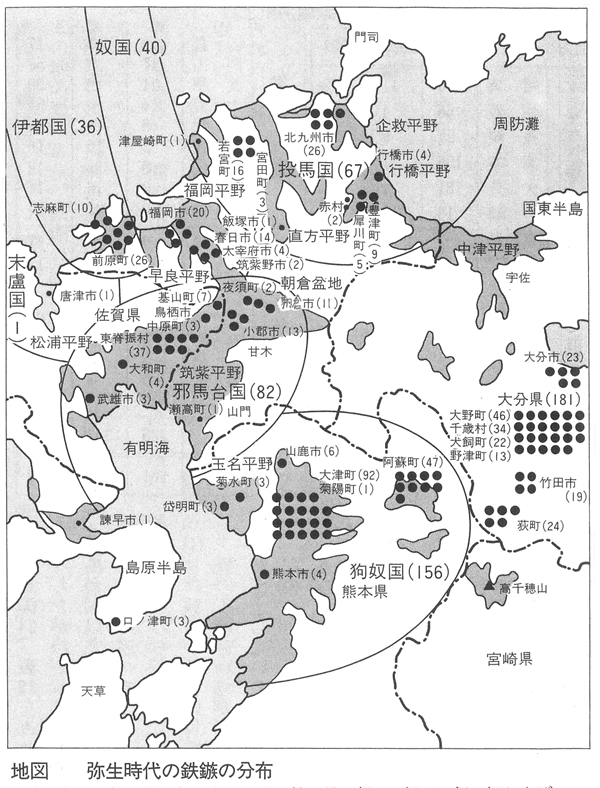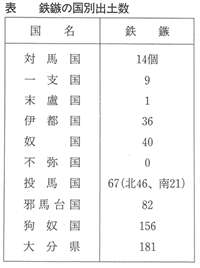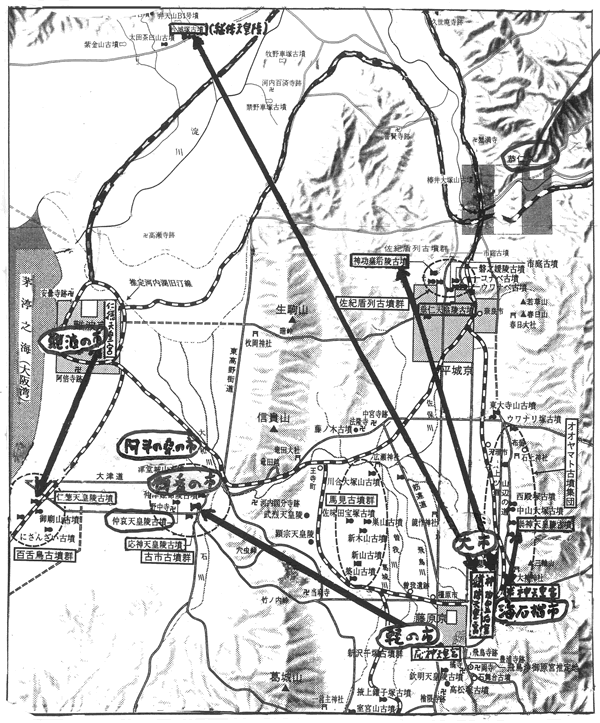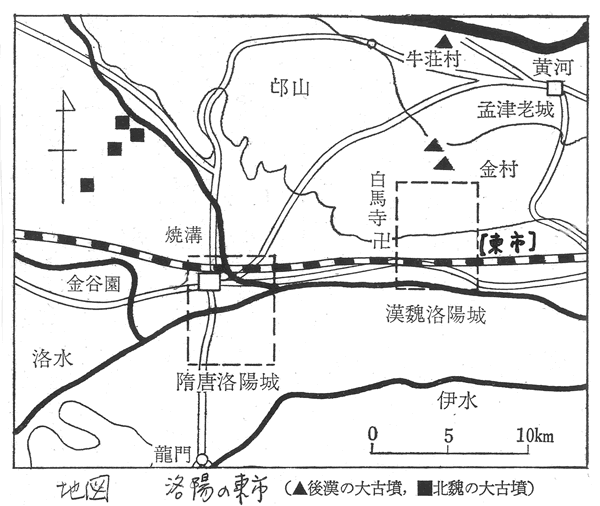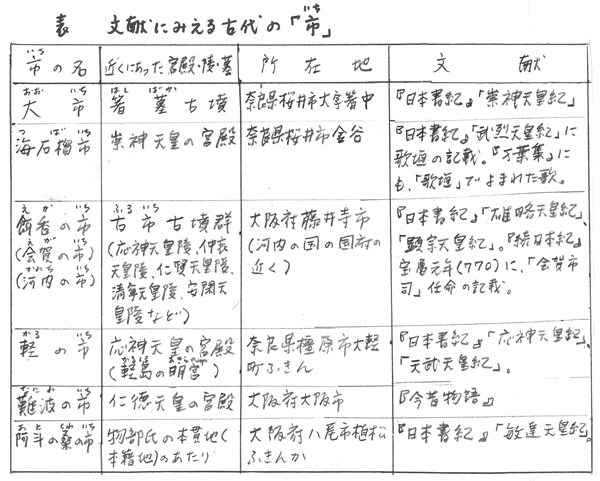■「陵」や「宮殿」と「市(いち)」
箸墓・・・・・・・・・・・・・・・・「大市(おおいち)」(『日本書紀』「崇神天皇紀」)
崇神天皇の宮殿・・・・・・「海石榴市(つばいち)」[桜井市金谷(かなや)]
「歌垣」(『日本書紀』「武烈天皇紀」、『万葉集』にも「歌垣」でよまれた歌)
古市古墳群・・・・・・・・・・「餌香の市(えがのいち)」(『日本書紀』「崇神天皇紀」)
応神天皇の宮殿・・・・・・「軽の市(かるのいち)」
仁徳天皇の宮殿・・・・・・「難波の市(なにわのいち)」
古代の市のあった場所は下記の地図にある。
(下図はクリックすると大きくなります)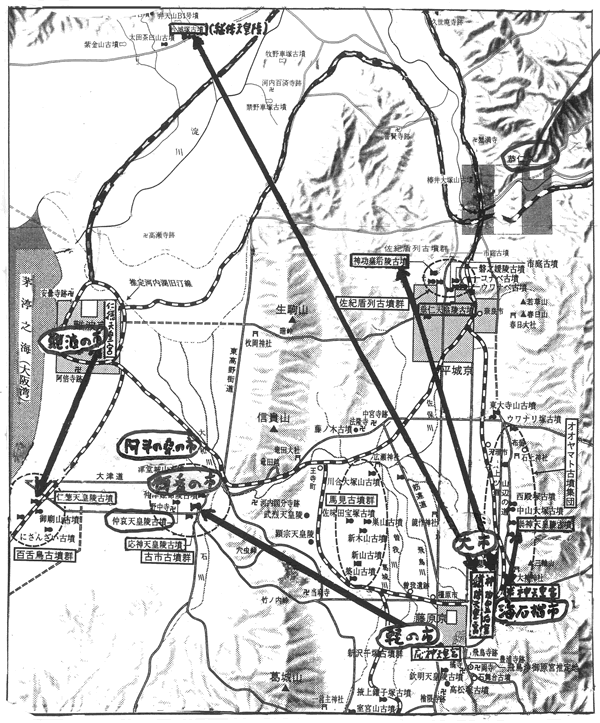
■「市」でなにをおこなうか
①売買、②歌垣、③処刑、④世論調査、⑤雨乞(あまごい)、⑥乞食、⑦説法、⑧接待、⑨宴会、⑩威信を示す
・処刑の例
司馬遷の『史記』「呉王濞列伝(ごおうびれつでん)」
「御史大夫(ぎょしたいふ)の鼂錯(ちょうそ)を(漢の都の)長安の東の市で、礼服を着たまま、腰斬(ようざん)の刑に処した。」
『漢書』の「鼂錯伝(ちょうそでん)」
「鼂錯を腰斬(ようざん)の刑に処し、その父母、妻子、兄弟らも、年齢にかかわりなく、みな棄市(きし)[さらし首]にすべきである。」
『漢書』「劉屈氂伝(りゅうくつりでん)」「雋不疑伝(しゅんふきでん)」・・・天一坊のような事件。太子を詐称した成方逐という男が腰斬(ようざん)の刑になった。
陳寿の『三国志』の「諸夏侯曹伝」
夏侯玄(かこうげん)は度量大きく世を救う志をもった人物であったが、魏の都の洛陽の東の市場での斬刑に臨んでも、顔色一つ変えず、立居ふるまいは泰然自若としていた。時に四十六歳であった。(夏侯玄は魏の国の政治家、司馬氏を打倒しようとした)
『世説新語(せぜつしんご)』(五世紀なかば成立、知識人のエピソード集)
「夏侯玄が捕らえられたとき、鍾毓(しょういく)が廷尉(ていい)[刑罪をつかさどる官]であった。鍾毓の弟の鍾会(魏の国の政治家。蜀の国をほろぼした人)は、それまで夏侯玄と面識がなかった。
鍾会は夏侯玄に、気軽で、なれなれしい態度をとった。
そこで、夏侯玄はいった。
『たとえ刑をうけるものであっても、そのような言葉をうかがうほど、落ちぶれては、おりませぬぞ。
』
夏侯玄は拷問されても、終始一言も発しなかった。
(洛陽の)東の市(中国の洛陽城、長安城、わが国の平城京、長岡京、平安京などには、東の市と、西の市とがあった)で処刑されるさいに顔色ひとつ変えなかった。」
洛陽の東市は下図のように、漢魏洛陽城の東側にあった。 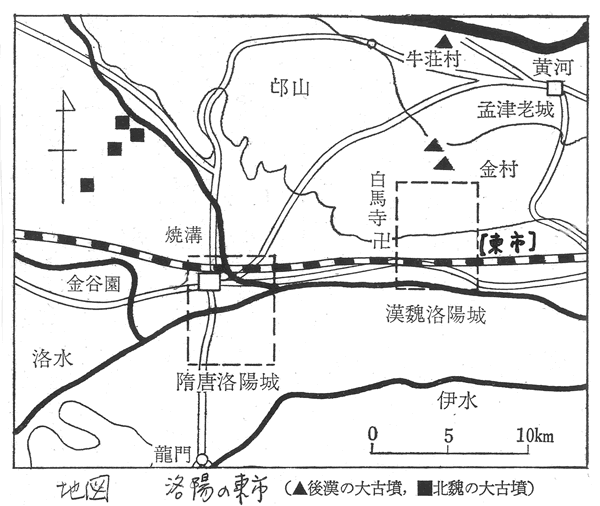
『日本書紀』「雄略天皇紀」十三年三月条
歯田根の命(はたねのみこと)が采女(うねめ)の山辺の小嶋子(やまべのこしまこ)と朝廷の許可なく、仲良くなったので、「餌香の市(えがのいち)」で家財を没収され市場公開された。
『日本書紀』「敏達天皇紀」十四年三月条
物部守屋仏教反対の言から、蘇我の馬子が出家させた尼の善信を「海石榴市(つばいち)」の駅舎(いまや)でむち打ち刑に処した。
・市場について『魏志倭人伝』に下記がある
女王国から北の地には、特に一人の統率者を置いて諸国をとりしまらせている。諸国もこれを恐れはばかっている。その統率者は、つねに伊都国に駐屯していて、中国の刺史(しし)のようなものである。
倭の王が使いを遣わして、魏の都や帯方郡、また、各韓国に行かせるときや、帯方郡の使いが倭国に行くときはみな、港で荷物をあらため、文書・賜り物などにあやまりがないか確かめて女王に差し出す。不足やくい違いは許されない。
・租税と市について、『魏志倭人伝』に下記がある
租賦(そふ)(租税とかみつぎもの)をおさめる。(それらをおさめるための)邸閣(倉庫)がある。国々に市がある(中華書局版『三国志』の句点にしたがえば、「邸閣の国があり、国に市がある」となる)。(たがいの)有無を交易し、大倭(身分の高い倭人)にこれを監(督)させる。
收租賦有邸閣國國有市
交易有無使大倭監之
・接待
①『日本書紀』「推古天皇紀」十六年八月、唐からの客を「海石榴市(つばいち)」の巷(ちまた)で迎えた。
②『日本書紀』「敏達天皇紀」
日羅(?~584)という人を、「阿斗(あと)の桑(くわ)の市」につくった館にとどまらせた。日羅は、日本人系の百済の高級官吏。
・威信を示す
『万葉集』4261番
「大君は 神にしませば 赤駒(あかごま)の腹這(はらば)ふ田居(たい)を都となしつ」
『万葉集』4262番
「大君は 神にしませば 水鳥駒(みずとり)のすだく(あつまる)水沼(みぬき)を都となしつ」
『漢書』「高帝紀」
漢の劉邦(りゅうほう)の時代に、丞相の簫何(しょうか)が、長安に未央宮(びおうきゅう)を造営した。劉邦が長安にはいったときに、未央宮が、あまりに壮麗であるので、簫何に怒っていった。
天下がおののき、戦争に苦労すること数年、その帰趨もわからないのに、こんな度はずれた宮殿をつくるとは、どうしたことか。
蕭何か答えていった。
できるだけ壮麗に造り、威光を示さなければ、天下はしたがわず、平定することはできないのです。
テレビもマスコミもない時代、権力は視覚化される必要があった。人々の話の種となる材料が、必要であったのである。
古代の「市(いち)」は、制度的に、どのようなものであったか。
(1)わが国の『律令(りつりょう)』(「律」は刑法、「令」は行政法など)の「関市令(げんしりょう)」(関所や市についての規定における「市(いち)」に関する条)。
(2)中国の文献『周礼(しゅらい)』の「地官(教育・土地・人事などに関することをつかさどった役人)」の「司市」(市をつかさどる役人)の条。
注:『周礼』は中国春秋時代(紀元前770年~紀元前403年)に成立したとみられる。後世の律令の書。
「関市令(げんしりょう)」の「市(いち)」の規定
「関市令」のなかの「市」についての規定は、次のようになっている。
①市(いち)は、つねに午(うま)の時(正午をはさんだ前後の2時間)に集まること。日の入るまえに、鼓(つづみ)を三度うって解散すること。鼓は、一度ごとに九回うつこと。
②肆(し)[店(みせ)]ごとに、(絹の店、布の店のような)標識をたてて、商品名を記すこと。市(いち)の司(つかさ)(市場を監督する役所)は、商品の時価によって、上中下の三等級をつくること。十日ごとに一簿(いちふ)[実際に売買された価格の記録]をつくること。それは市場にいて、机にむかって書くこと。季節ごとに、それぞれ本庁[左右京職(きょうしき)(みやこの役所)]に報告すること。
③官と私とが売買するとき、(銭以外の)物をもって対価とするばあいに、その物の値段は中等の価格を基準とすること。現物がそこに存在しない盗品などのばあいもまたこのようにすること。
④ものさし(長さをはかる)、ます(量をはかる)、さお秤(ばかり)(重さをはかる)の、いわゆる度(ど)・量(りょう)・衡(こう)は、毎年二月に、大蔵省に行って、精度検査をうけ(合格の題印をしてもらって)、そののちに用いること。
⑤天秤(てんびん)ばかりを用いるにあたっては、みな格(きゃく)[掛(か)けさげておく横木のあるもの]に、かけておくこと。斛(こく)(容量一斛のます)をもちいるにあたっては、[縁(ふち)にそって平らにするための]「ますかき」を使うこと。米粉、麦粉は天秤ばかりではかること。
⑥奴婢(ぬひ)を売るばあいは、居住地の役所にとどけること。奴婢の主人の書いた売るという証文が必要である。そのような保証をとり、正式に役所を通じた文書をつくったうえで、価格をつけること。牛馬のばあいは、もち主からの保証は必要であるが、役所の判署を要しない。私的に証文をつくること。
⑦売るものは、欠陥のあるものを売ったり、品質が名目と異なるものを売ってはならない。横刀(たち)、槍、鞍(くら)、漆器(しっき)の類は、それぞれ製作者の姓名を記録すること。
⑧市で商売をするときは、男と女とは座席を別にすること。
⑨欠陥のあるものや、品質のまがいものを売買したばあいは、官に没収する。寸法が、公定の規格に足りないばあいは、持ち主に返すこと。
⑩官が売り買いをするばあいを除いては、みな市で売買すること。居ながらにして、物主を呼びつけて、時価にそむいた値段をつけてはならない。官私を問わず、たがいに時価をつけること。時価とかけ離れた値段をつけてはならない。
『周礼(しゅらい)』の規定
『周礼』の「地官」の「司市」についての規定は、つぎのようなものである。
①役人の「司市」は、市の治、教、政、刑、量、度、禁令をつかさどる。
②とりあつかうものごとに店[肆(し)]を別にし、とりあつかう商品をたがいに比較できるようにし、値段が騰貴しないようにする。
③政令をもって不相応なぜいたく品を禁じ、ぜいたく品と、そうでないものとの値段差が大きくならないようにする。
④商人をまねき、貨が内にあつまり、布が外に流れるようにし、市の政治がうまく行くようにする。
⑤量度(ますや、ものさし)を定めれば、物の値段が定まり、買う人が来るようになる。
⑥売買にあたっては、証書をつくって、信を結び、訴訟ごとがおきないようにする。
⑦役人が、あざむきごとや、いつわりのぞく。
⑧刑罰をもって、暴を禁じ、盗みを除く。
⑨「泉府」(「泉(せん)」は「銭(せん)」に通じる)という官をもうけ、民の売物が売れないときは、これを買いとり、民が急に求ればこれを貸す。
⑩「大市」は、午後二時ごろの市。すべての人が主となる。「朝市」は、朝の時の市。商人が主となる。「夕市」は夕(ゆうべ)の時の市。男女の商人が主となる。
⑪「市人(市の役人)は、うそいつわりを監察する。鞭(むち)や、ほこをとり、門を守る。市の役人たちは、その店の財貨の名と実(じつ)とがみだれていないようにし、売買、値段が極端にならないようにする。市の役人のものごとを処するところに旗を立てて、市(いち)に指令をする。役人の「市師」という役人は大きな問題、大きな訴訟をとりあつかう。役人の「胥師(しょうし)」「賈師(かし)」は次に位置して処理し、小さい問題、小さい訴訟をとりあつかう。
⑫役人の「質人」は、市の財貨、奴婢、牛馬、兵器、珍異なものの売買価が、極端にならないようにする。
⑬役人の「廛人(てんじん)」は税をとりおさめることなどをつかさどる。市(いち)にならんでいる店の税布、店をもたずに立って売っているものの税、そして、質布、罰布、廛布、などをとりおさめる。質布は、役人の「質人」が、犯罪を犯したものからとりたてたもの、罰布は市令に違反したもののおさめる銭、廛布は財貨や諸物、邸舎にかかる税である。
市の監督者について、
『周礼(しゅらい)』・・・・「司市」
『魏志倭人伝』・・・・・・・・・・「大倭」(に、市を監督させる)
『律令』時代・・・・・・・・・・・・「市司(いちのつかさ)」[市を監督した役所(役人)]
その他「市(いち)」でおこなわれたこと
①世論調査
『続日本紀(しょくにほんぎ)』の聖武天皇の天平十六年(744)の閏四月の四日の条に、つぎのような記事がある。
「都として、恭仁(くに)の京(みやこ)[現在の京都府に属する]と難波の京(みやこ)[現在の大阪府に属する]と、どちらがよいかを、、恭仁(くに)の宮(みや)の市(いち)において、人々の意見をたずねさせた。」
②雨乞(あまごい)
『日本書紀』の皇極天皇元年(642)七月の条に雨乞のために、市場を別のところにうつし、市の門をとじ、人をいれないで、祭りをおこなったことがみえる。『続日本紀』の文武天皇の慶雲(けいうん)二年(705)六月二十八日の条に市の店を出すことをやめさせ、そこでお坊さんたちに雨を乞(こ)わせたことがみえる。
なお、雨乞のために、市場を別のところにうつす話は『後漢書』の『礼儀志』の請雨(しょうう)条や、「郎顗(ろうぎ)伝」(列伝第二十下)にもみえる。[郎顗は後漢の順帝(在位125~144年)ごろの人]
③説法
平安中期の僧、空也(くうや)[903~972]は、民衆に念仏をすすめ、社会事業をおこなった。「市の聖(いちのひじり)」とよばれた。
④乞食
『続日本紀』の淳仁天皇の天平宝字三年(759)五月九日の条に、冬の三カ月のあいだに、市(いち)のあたりで、飢える人が多かった」とあり、同じく淳仁天皇の天平宝字八年(764)三月二十二日の条に「平城京の東西の市の付近に、乞食をする人が多かった」との記事がみえる。
文献にみえる古代の「市(いち)」は下記の表による。