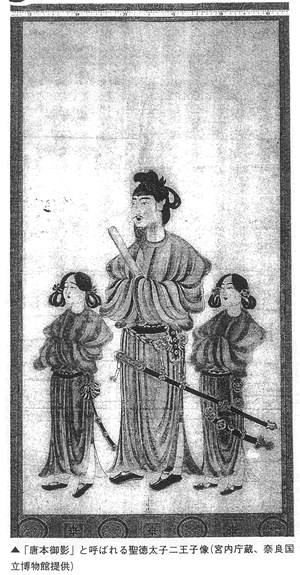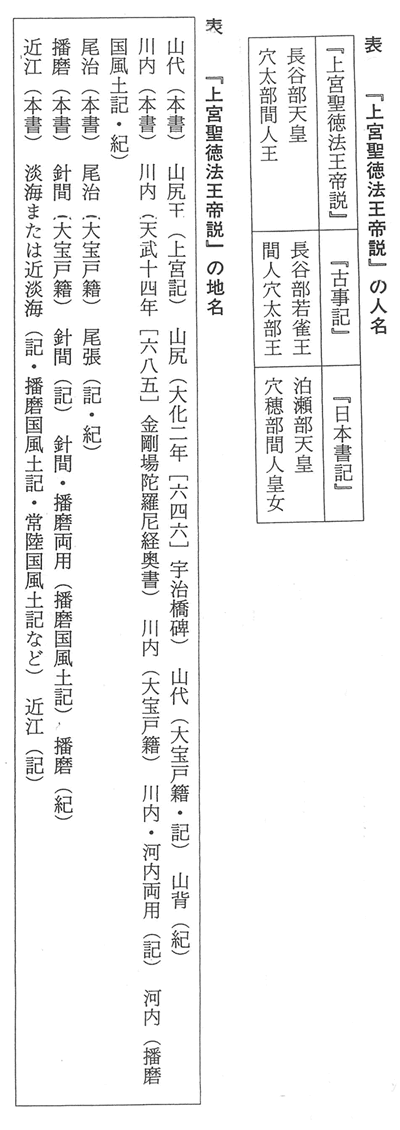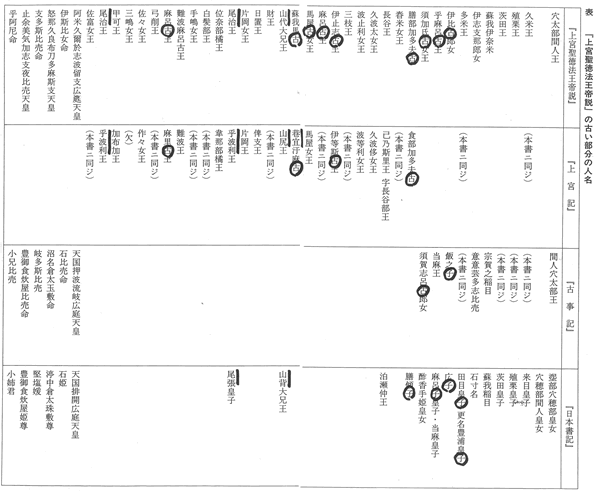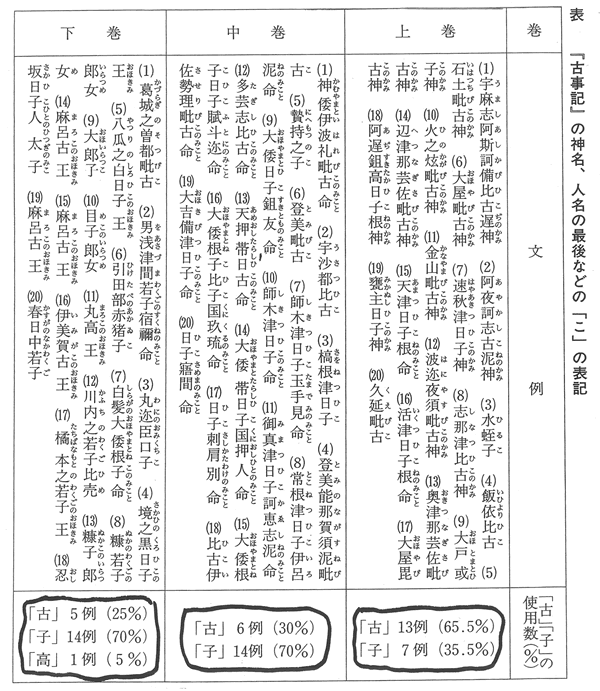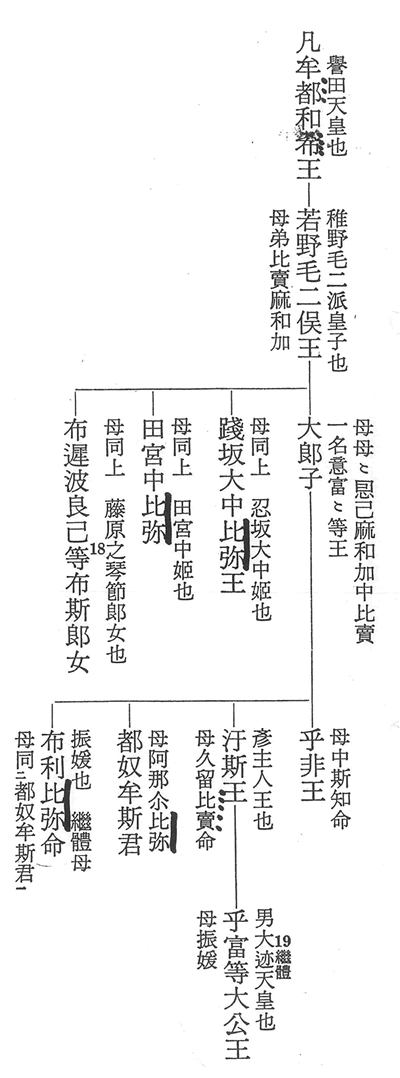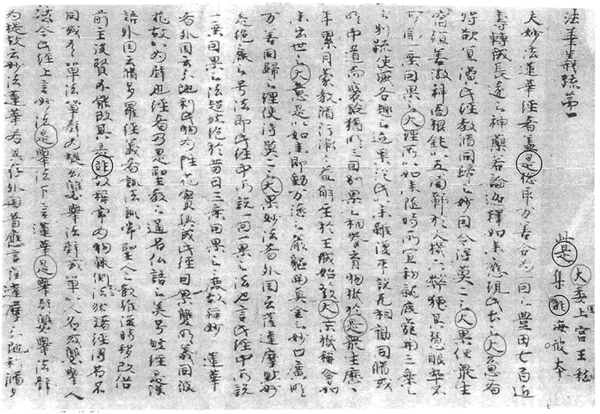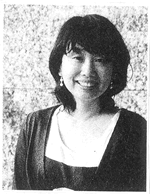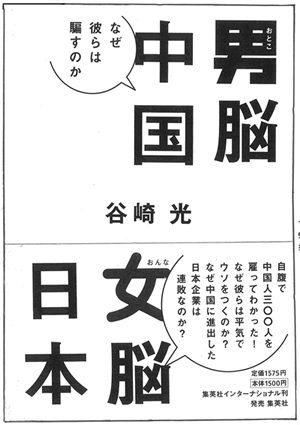■聖徳太子(しょうとくたいし)は人名事典などでは下記のように書かれている。
名は厩戸(うまやど)皇子で、574-622年である。飛鳥時代、用明天皇の皇子。敏達天皇3年に生まれ母は穴穂部間人(あなほべのはしひとの)皇女。推古天皇の皇太子、摂政となり十二階冠位の制定、憲法十七条の発布、遣隋使の派遣などをおこなう。また慧慈(えじ)にまなび、『三経義疏(さんぎょうぎしょ)』をあらわした。豊聡耳命(とよとみみのみこと)、上宮(じょうぐう)王ともいう。推古天皇30年2月22日死去。49歳。墓所は磯長(しながの)墓(大阪府太子町叡福寺)。 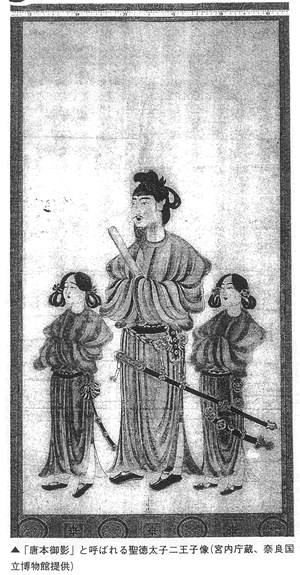
■曽根氏が大山氏の聖徳太子の非実在性について、批評している。
大山誠一氏も曽根正人(そねまさと)氏も東大大学院人文研究科博士を取得している。
曽根正人著『聖徳太子と飛鳥仏教』(吉川弘文館刊)によれば、
聖徳太子非実在説の波紋
・聖徳太子研究の流れ
旧来推古(すいこ)朝仏教を主導していたと見なされていたのは、政権の中枢にあった蘇我馬子(そがのうまこ)、そして没後早くから「聖徳太子」と尊称されて信仰を集めた厩戸(うまやど)皇子であった。なかでも推古朝のみならず飛鳥仏教全体を代表する人物とされてきたのが厩戸皇子である。だが「聖徳太子」という呼称からしてそうなのだが、この人物は没後早くから神話に覆われる。人物像についても史実と神話とが混合した造形がなされ、歴史学においてすら、時代の仏教から掛け離れた理解水準の仏教者という非現実的な人間像が語られてきた。
よしんばそんな高水準の仏教理解者だったとしても、それならば同時代の日本仏教からは遊離していたはずである。ところがさらに奇妙なことに、そうした彼をもって飛鳥仏教を代表させる、といった矛盾した図式がまかり通っていたのである。
そこに近年、大山誠一氏の研究によって一気に正反対のベクトルが形成されるに至った。大山氏は、厩戸皇子=聖徳太子という人物造形のよりどころであった『隋書倭国伝(ずいしょわこくでん)』『日本書紀』『天寿国繍帳銘(てんじゅこくしゅうちょうめい)』、法隆寺諸像の光背銘(こうはいめい)などいわゆる聖徳太子関係史料すべての信憑性(しんぴょうせい)に疑義を呈することにより、「聖徳太子は存在しなかった」と結論した。この刺激的でかつ誤解を招きやすい結論は、発表当時から大きな反響を巻き起こした。
・大山説の概要
大山氏の研究は、本来推古朝の政治状況から聖徳太子関係史料成立期(奈良時代初期)の政治状況などにわたる広い領域を踏まえたものである。
そこから本書で取り上げる仏教者としての厩戸皇子に関わる部分を取り出すと、以下のようになる。
①『隋書倭国伝』に見える「王、多利思比孤(たりしひこ)」「倭王」とは厩戸皇子のことではなく、蘇我馬子のことである。よってそこに見える仏教事績を厩戸皇子に帰することはできない。
②『日本書紀』で厩戸皇子の仏教行業として記されている事績も、他の仏教関係記事同様、ほとんどすべて道慈(どうじ)による捏造(ねつぞう)である。
③法隆寺金堂薬師像・釈迦像光背銘や『天寿国繍帳銘』『三経義疏』(以上いわゆる法隆寺系史料)、あるいは『上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)』『法起寺塔露盤銘(ほっきじとうろばんめい)』といった、『日本書紀』より古い時期の別系統の厩戸皇子関係史料とされてきたものは、いずれも『日本書紀』以後に政治目的から創作されたのであり、記されている内容は史実とは無関係である。
④今日なお学界で流布している聖徳太子像は、『日本書紀』によって創出された原型が、③で挙げた後世の創作物によって肥大化して形成されたものである。
⑤したがって厩戸皇子の仏教事績として認め得るのは、斑鳩寺(いかるがでら)[法隆寺若草伽藍(わかくさがらん)]の造営くらいしかない。
・聖徳太子はいなかった
もともと『日本書紀』記事の多くに人為的操作が加えられていることは、周知の事実である。厩戸皇子の記事にしても、神話的エピソードはもちろん事績の記述すべてが、事実をありのままに記したものと見る研究者は少ない。また法隆寺諸像光背銘・『天寿国繍帳銘』・『法起寺塔露盤銘』にしても成立期や信憑性について意見は分かれており、無批判に依拠し得ないのは学界の共有認識であろう。
ただ大山氏の場合、旧来信憑性に疑問が呈されてきた史料はもちろん、『隋書倭国伝』の「王、多利思比孤」を厩戸皇子とする解釈、比較的信用度の高い史料とされて来た『上宮聖徳法王帝説』、『日本書紀』でも比較的信憑性が高いとされて来た記事までほぼすべてについて、創作であり歴史上の厩戸皇子とは無関係の捏造としたのである。さらにこれを受けて『上宮聖徳法王帝説』、そして『日本書紀』に次いで古い史料で問題視されることの少なかった『元興寺縁起(がんごうじえんぎ)』についても、最近吉田一彦氏から根本的疑義が呈されている(「『元興寺伽藍縁起井流記資財帳』の信憑性」〔大山誠一編『聖徳太子の真実』所収〕)。こうした大山・吉田氏らの論を全面的に肯定するならば、厩戸皇子の仏教に関する史料で使えるものはほぼ皆無ということになる。
かくして以下のような結論が導かれる。厩戸皇子=聖徳太子の事績として記録された事柄はすべて創作だった。人間離れした超人説話が史実でないのはもちろんだが、時代をリードする先進的指導者という造形も含め、すべての聖徳太子像は捏造だった。すなわちいわゆる「聖徳太子」に相当する人物は、そのモデルも含めて歴史上には存在しなかった。
厩戸皇子という王族は存在したが、その実像は「聖徳太子」のモデルたり得るほどの大層なものではなかった、というわけである。
■『上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)』という文献について
『上宮聖徳法王帝説』は、最古の聖徳太子伝である。聖徳太子の誕生、一族のこと、仏教興隆のための事績などを記す。編著者は、未詳である。
『上宮聖徳法王帝説』は、性質の異なるつぎの五つの部分からなる。
①聖徳太子の系譜。聖徳太子の父母兄弟、諸子諸孫、甥姪(おいめい)、祖父母、伯叔(おじ)など。この部分は、大宝年間(701~704年)、慶雲年間(704~708年)以前の成立とみられている。すなわち、『古事記』『日本書紀』以前の成立とみられている(成立年代は、『国史大辞典』〔吉川弘文館刊〕による。以下、成立年代は、『国史大辞典』による)。
②聖徳太子の事績などをのべた部分。政治上の事績・生誕、幼時の逸話。七寺建立。冠位の制定。経典の注釈書の作製のこと。講経を行なったこと。薨去、高句麗の僧・恵慈(えじ)法師の殉死。などの記事を記す。奈良時代の成立とみられている。
③聖徳太子関係の古文の引証とその註釈。法隆寺金堂薬師像銘文。法隆寺金堂釈迦像銘文とその註釈。天寿国繍帳(てんじゅこくしゅうちょう)銘文とその注釈。巨勢三杖(こせのみつえ)の追悼歌など。いわば、聖徳太子の伝記資料を引載した部分。平安時代中期ごろの成立とみられている。
④聖徳太子の事績関係の史実についての記録の再録と追補。物部の守屋討伐のこと。四天王寺建立。戊午(つちのえうま)の年(538年)の仏教伝来と廃仏。仏教興隆。冠位制。「十七条の憲法」。山背(やましろ)の大兄(おおえ)の王(おう)事件。蘇我氏の滅亡など。和銅年間(709~715年)以降、平安時代初期以前の成立とみられている。
⑤聖徳太子に関係する五天皇と聖徳太子の略歴の記録。欽明天皇から推古天皇にいたる五天皇の在位年数・崩年・陵名・聖徳太子の生没年・墓所などについて記した部分。太宝年間(701~704年)・慶雲年間(704~708年)の成立とみられている。
『国史大辞典』の「上宮聖徳法王帝説」の項には、およそ、つぎのように記されている。「はじめ、①の部分のみ、ないし、それに②の部分が加わった原初的な形が、奈良時代に成立し、それに④と⑤旧の部分が加わり(当初、裏書であったとする推定もある)、さらに平安時代中期に③の部分が付加されて今本の形ができ上ったとみる見方が一般的である。
①⑤の部分の皇室系譜は、『帝紀』に類する古い資料に基づくとみられ、貴重である。他の部分にも、記紀と系統を異にする所伝として注目すべき記事が散見し、ことに戊午(つちのえうま)の年の仏教伝来の所伝、太子の薨日に関する『日本書紀』と異なる所伝などは、 著名である。」
「現在、知恩院に蔵せられる平安時代中期ごろの書写とみられる写本(一巻、国宝。古典保存会の複製あり)が現伝本の唯一の祖本である。この写本は、法隆寺に伝来したものである。」
今日、私たちは、奈良時代に成立した代表的な文献として、『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』などを知っている。「上宮聖徳法王帝説」は、奈良時代以前の資料を含むとみられる貴重な資料なのである。
『古事記』『日本書紀』の成立以前に成立した資料を含むのであるが、『古事記』『日本書紀』にくらべれば、あまりにも、断片的である。 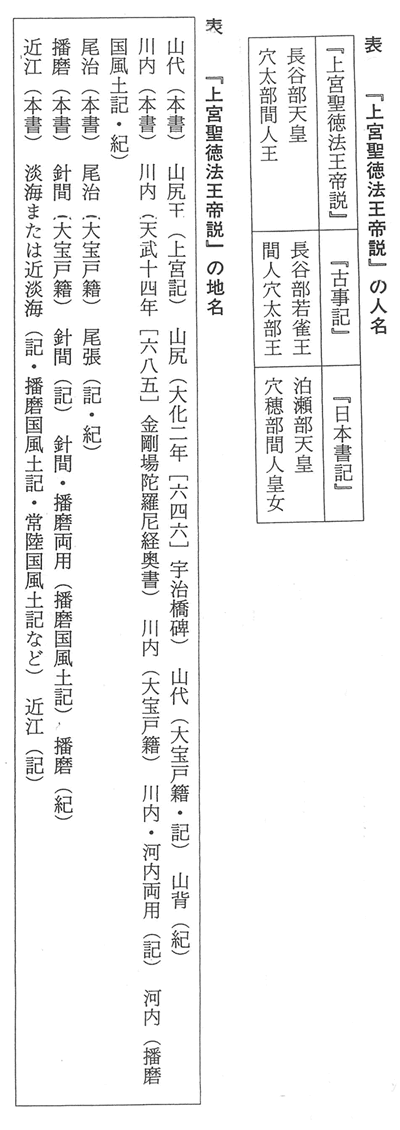
さて、『上宮聖徳法王帝説』については、教科書裁判で著名な家永三郎による有名な研究『上宮聖徳法王帝説の研究』(増訂版。1976年、三省堂刊)がある。
『上宮聖徳法王帝説』の成立事情、年代、編述者については、資料がない。
さきに紹介した『国史大辞典』の①②③④⑤の各部の成立年代の推定は、家永三郎などの研究によっている。
そして、家永三郎は、その年代推定を、おもに、「用字・用語」の研究によって行なっている。
すでに、江戸時代の考証学者、狩谷掖斉(かりやえきさい)は、『上宮聖徳法王帝説』について、つぎのようにのべている。
「その文詞を味わうに、すこぶる『釈日本紀』引用するところの『上宮記(じょうぐうき)』に類す。いまだ『古事記』『日本書紀』を見ざるものの作るところか。」
国学者の伴信友(ばんのぶとも)も、「文体を考えるに、『釈日本紀』に引用されている『上宮記』に似ているところがある。」とのべている。
九州大学の教授などであった国語学者の春日政治(かすがまさじ)は、「法王帝説襍考(ざっこう)」(『国語と国文学』第百六十一号、1937年)において、『上宮聖徳法王帝説』の仮名の用例を比較研究した。『上宮聖徳法王帝説』中の固有名詞が、どのような漢字を用いて表現されているかを検討した。
人名については、表のように、『上宮聖徳法王帝説』と『古事記』とは、ほとんど変わりがなく、『日本書紀』にいたって用字が変わっていることに注意をうながす。
地名については、表のように、山代、川内、尾治などにおいては、古い用字法にしたがっているが、なお「大宝戸籍」ないし『古事記』まで下りうる可能性があり、むしろ、播磨・近江のような比較的新しい用字に、『上宮聖徳法王帝説』の成立が、『古事記』『風土記』あるいは『日本書紀』の時代までも下りうることを感じさせられるものがあると論じた。
ただ、春日政治(かすがまさじ)は、『上宮聖徳法王帝説』の、銘文の引用を除いた地の文を、①②③④⑤などにわけず、一括して取りあつかったために、結論があいまいになった。
①②③④⑤は、成立年代が異なるとみられ、分けて考えなければならない。
家永三郎は、①②③④⑤を分けて、個別に検討した。
さて、家永三郎は『上宮聖徳法王帝説』のうち、とくに古い部分とみられる①⑤の部分について、およそ、つぎのようにのべる。
「①の部分と、記されている内容をほぼ等しくするものに、『上宮記』の註、『古事記』『日本書紀』がある。これらでは、人名の呼称またはその表記に用いた漢字のあて方に多くの相違がある。表示すれば、下の表のとおりである。
(注:特に人の名について、「古」と「子」について比較している)
(下図はクリックすると大きくなります)
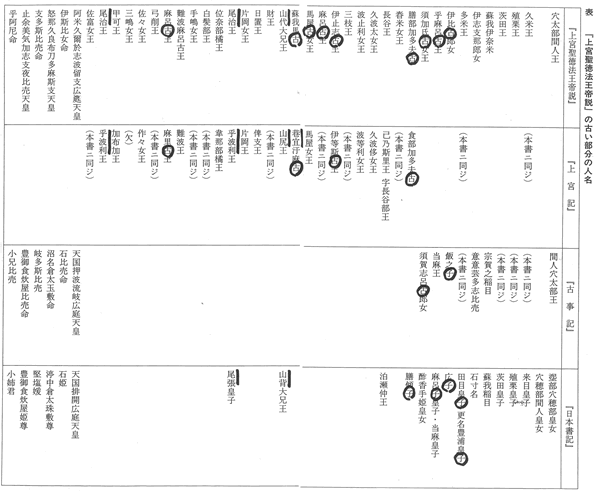
これらのうちには、誤脱または文字改訂などによって生じた相違もあるであろうが、大部分は、同一の発音を異なる漢字によって表現したもので、その表記法の相違は、異伝によるものと解すべきである。
『上宮聖徳法王帝説』のこの部分は、『上宮記』『古事記』『日本書紀』の当該部分とは、直接関係のない資料からでたものと解釈して大過ないようである。」
■漢字の表記
・「こ」を「古」で記す
「オオタタネコ」という人名を、『古事記』は、「意富多多泥古」と記し、『日本書紀』は、「大田田根子」と記す。
人名の最後などの「こ」の音は、『古事記』『日本書紀』ともに、「古」「子」の両様の表記が用いられているが、『古事記』の特に上巻(神話の巻)では、「猨田毘古(さるたひこ)」「海佐知毘古(うみさちひこ)」など、「古」の字を多用する傾向がみとめられる。『日本書紀』では、「ひこ」には、ほとん、ど「彦」の字をあて、その他では、「天種子命(あまのたねこのみこと)」「大日本根子(おほやまとねこ)」「丘稚子王(をかのわくごのみこ)」など、「子」の字を多用する傾向がみとめられる。
「上宮聖徳法王帝説」の①の部分では、人名の最後などの「こ」の音は、「古」の字で写され、「子」の字は、用いられていない。つぎのようなものである。
「比里古(ひろこ)」「伊比古郎女(いひこのいらつめ)」「乎麻呂古王(おまろこのみこ)」「須加氏古女王(すかてこのひめみこ)」「加多夫古臣(かたぶこのおみ)」「伊止志古王(いとしこのみこ)」「麻呂古王(まろこのみこ)」「馬居古女王(まいこのひめみこ)」「蘇我馬古(そがのうまこ)」「刀自古郎女(とじこのいらつめ)」「難波麻呂古王(なにはのまろこのみこ)」
『上宮聖徳法王帝説』の①の部分で、「加多夫古臣(かたふこのおみ)」「蘇我馬古」と記されているものも、『日本書紀』では、「傾子(かたぶこ)」「蘇我馬子」と記されている。
・『古事記』の「古」と「子」
まず、『古事記』をしらべてみる。
『古事記』の上巻、中巻、下巻のそれぞれから、神名、人名の最後などが、「こ」で終っているものを、最初から順に、二〇個ずつ選んでみる。すると、下の表のような表記になっている。
表をみれば、『古事記』のはじめの方の巻ほど、「古」の使用度が大きく、あとの方の巻になるほど、「古」の使用度がへり、「子」の使用度が大きくなっている。
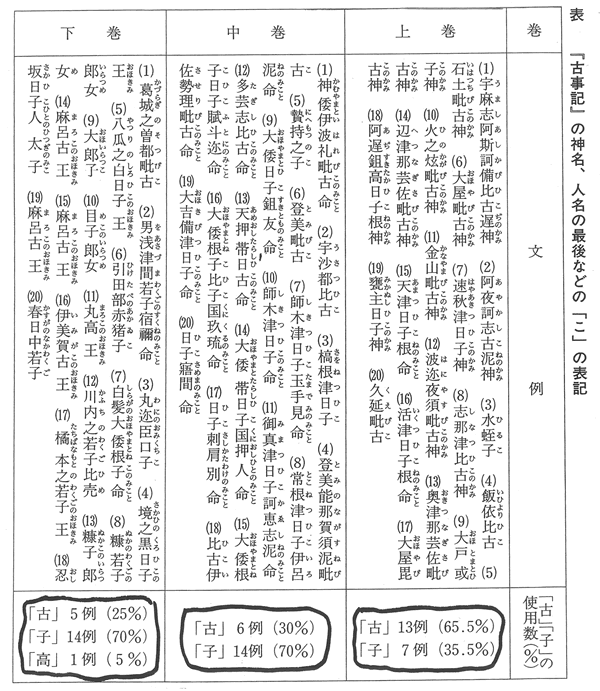
これは、次のいずれかの理由によるものであろう。
①太安万侶(おおのやすまろ)が、参考とした原資料において、古い時代を伝える資料ほど、「古」の使用が多かった。のちの時代になるほど、「子」がよく使用されるようになり、その原資料状況を反映している。
②原資料のほとんどは、「古」で表記されていたが、太安万侶が、書きなれるにしたがって、「古」を「子」にあらためていった。
①の可能性の方が大きいと思われるが、いずれにせよ、古い資料は、「古」を多用していたことを示している。
なお、『古事記』で、「比古」「毗古」「日子」などとあるものは、『日本書紀』では、ほとんどすべて、「彦」に書きあらためている。
・地名「をはり」
地名「をはり」を、『上宮聖徳法王帝説』は、「尾治」と書き、『古事記』『日本書紀』は、「尾張」と書く。
このことは、春日政治(かすがまさじ)が、指摘しているところである。
「尾治」という表記が、『古事記』『日本書紀』成立以前の古い表記であることは、この表記が、「大宝戸籍」にあることや、「藤原宮出土木簡」に、「尾治国春部評春(かすかべのこおり)」「尾治国海部」「尾治国知多郡贄代里(にえしろのさと)」「辛卯年(691)十月尾治国知多評」などとあることから知られる。ちなみに、藤原京は、694~710年まで都であった。
沖森卓也・佐藤信共著『上代木簡資料集成』(おうふう〔桜楓社〕刊)の、「尾治国知多郡贄代里」の木簡の項には、
「国名の尾張を『尾治』と記すのは、古い表記法である。」
とある。
・「すくね」の表記
つぎに、姓(かばね)の「すくね」は『古事記』『日本書紀』では「宿禰」と記す。762年に記された石川年足墓誌も、「宿禰」を用いている。
いっぽう、『古事記』『日本書紀』成立以前の「稲荷山鉄剣銘文」『上宮聖徳法王帝説』「天寿国繍帳銘文」「山ノ上碑」などは「足尼」と記す。
たとえば、「稲荷山鉄剣銘文」に『多加利足尼」とある。『上宮聖徳法王帝説』に、「宗我稲目(そがのいなめ)足尼大臣」、「天寿国繍帳銘文」に、「巷奇(そが)大臣名伊奇米(いなめ)足尼」とある。
稲荷山鉄剣出土地に近い群馬の上野三碑の一つの「山ノ上碑」には、「此新川臣児(にひかはのおみのこ)、斯多々弥足尼(したたみのすくね)孫大児臣(おほこのおみ)」と、ある。この山ノ上碑は、681年に記されたものと見られる。
・「やましろ」の表記
地名の「やましろ(京都府南部)」を「大宝戸籍」『古事記』では「山代」と記す。『日本書紀』では、「山背」と記す。壬申の乱(672年)のころは「山背」である。
その後延暦十三年(794年)の詔では「山城国」となっている。これが一番新しく、
「山代」と表記するほうが古い。
・もう一つの聖徳太子に関連した書物の上宮記(じょうぐうき)でも同じことが言える。
上宮記は古代の史書で、『聖徳太子平氏伝雑勘文』下三に「凡上宮記三巻者、太子御作也」とあり、鎌倉時代後期までは伝存したらしいが、今は逸して、全体の内容などは明らかでない。「太子御作」とするのは仮託であろう。逸文としては『釈日本紀』巻一六に「浮漂」「漂蕩」の訓「クラケナスタ、ヨヘル」が『上宮記』にも存したことがみえ、同書巻十三に男大迹天皇(継体天皇)の出自を示した系譜が「上宮記曰、一伝」として引かれ、『平氏伝雑勘文』下三に聖徳太子・多米王・長谷部王・久米王の子孫の系譜が「上宮記下巻注云」として引用される。ほかに『天寿国曼荼羅繍帳縁起勘点文』に「或書曰」として引かれる欽明天皇・敏達天皇・用明天皇・聖徳太子の系譜も、『平氏伝雑勘文』所引の逸文と一致する部分があるので、本書の逸文と考えてよいであろう。逸文の大部分は皇統譜で、凡牟都和希王(応神天皇、一説に誉津別皇子)、伊久牟尼利比古大王(垂仁天皇)から山背大兄王の子の世代までに及ぶ。「漂蕩」の訓が本書に存したとするのが確かであれば、神代に関する記載もあったことになる。固有名詞の表記の用字に、いわゆる推古朝遺文と共通するものが多いこと、また系譜の様式が、所生の子の名が直ちに次の世代の記述の主格になる古い形であることなどから、記紀以前の古い資料と考えられている。皇統譜に関し記紀や『上宮聖徳法王帝説』にもみえない独自の所伝をもち、特に継体天皇の出自を示した記載は貴重である。
『釈日本紀』に上宮記曰くとして、引用されている記述では「ケ」を「希」など推古朝(聖徳太子の時代)遺文と共通する。
・「比弥」を「ヒメ」と読む
『釈日本紀』に系図で、応神天皇の凡牟都和希望王(ほむたわけのみこ)のように、「タ」を「都」と書く。「比弥」を「ヒメ」と読む。 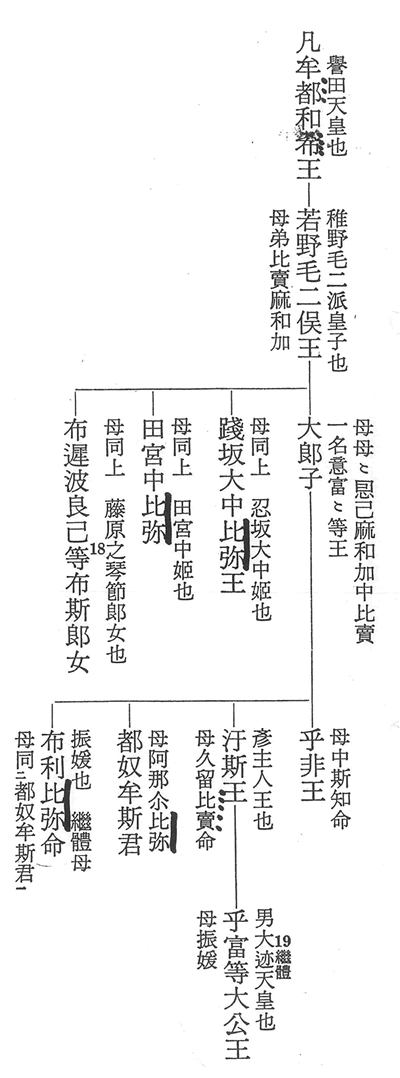
東大の坂本太郎氏の論文でも「比弥」を「ヒメ」と読む、この「比弥」の表記は古い表記である。
「卑弥呼」の音に一致する。「姫子(ひめこ)」は、古典にあらわれるひとつの熟語として、「卑弥呼」と完全に一致する。「卑弥呼」が、「姫子」であるとすれば、「姫」という語に、愛称または尊敬の「子」がついたものであろう。
このことは、坂本太郎が、論文「『魏志』『倭人伝』雑考」(古代史談話会編『邪馬台国』1954年9月刊)のなかで説いている。
「卑弥呼」の「弥」の字は、
(1)等已弥居加斯夜比弥乃弥己等(とよみけかしやひめのみこと)[元興寺塔露盤銘、元興寺縁起]
(2)止与弥挙奇斯岐移比弥(とよみけかしきやひめ)天皇[元興寺丈六光銘、元興寺縁起]
(3)吉多斯比弥乃弥己等(きたしひめのみこと)[法隆寺蔵「天寿国繍帳記」『上宮聖徳法王帝説』]
(4)等已弥居加斯支移比弥乃弥己等(とよみけかしきやひめのみこと)[「天寿国繍帳」]
(5)践坂大中比弥(ほむさかおおなかひめ)王[「上宮記」『釈日本紀』十三述義九]
(6)田宮中比弥(たみやなかひめ)[「上宮記」]
(7)阿那爾比弥(あなにひめ)[「上宮記」]
(8)布利比弥命(ふりひめのみこと)[「上宮記」]
(9)阿波国美馬郡波爾移麻比弥(はにやまひめ)神社(『延喜式』神名帳)
などのように、『古事記』以前の表記法を伝えるとみられるもののなかに、「甲類のメ」をあらわすために用いられている例がある(文例は、坂本太郎の列挙による)。このような事例をみると、「姫」は、むかしは、「ひ(甲)み(甲)」といっていたのではないかと疑われるが、そうではないことは、「上宮記」において、「布利比弥命(ふりひめのみこと)」を「布利比売命(ふりひめのみこと)」とも記していることからわかる。「弥」は、あきらかに、「甲類のメ」に読まれているのである。
ただ、ふしぎなことに、「弥」を「甲類のメ」と読むのは、わが国の古文献においては、「比(甲)弥(甲)[ひめ](姫)」という熟語にかぎられている。さきの(1)の「比弥乃弥己等(ひめのみこと)」のように、「弥己等(みこと)」(命)のばあいは、「弥」を「甲類のミ」に読んでいる。そして、「卑弥呼」の「弥」は、まさに、「卑(甲)=比(甲)」の字のあとに用いられており、「卑(甲)弥(甲)」と読みうるケースである。
『万葉集』の167番の歌で「天照(あまて)らす日女の尊(ひるめのみこと)[天昭日女之命]」という語のすぐあとに、「高照らす日の皇子(ひのみこ)[高照日之皇子」」という語がでてくる。「日女」は、「ひめ」とも読める。「卑弥呼」は「日女皇子(ひめみこ)」のような語をうつしたものであろうか。
市川寛氏の「『御宇』用字考」でも「治天下」と「御宇」について、「治天下」という書き方は古い。「御宇」「馭宇」という書き方は新しいとし、けん責文の事例をあげている。
市川寛氏の論文は『季刊邪馬台国』67号に転載(1999年)されている。
・仮名源流考から推古時代の漢字の読みが参考になる。
大矢透著の本で、本文一冊、証本写真一冊である。明治四十四年(1911)刊。昭和四十五年(1960)覆製刊。推古時代の文献に見られる真仮名の字音の源流を研究して、それが中国の周代の古音の系統であると論定したもの。一般に、仮名の起源を考えようとすれば、それがいかなる漢字から出たものであり、その漢字のいかなる音(漢音か呉音か古音か)をひいているかを研究しなくてはならないが、この大きな問題を解決しようとして、推古期遺文の実際を明らかにしたもの。そこには意(オ)・竒(カ)・宜(ガ)・挙(ケ)・侈(夕)・至(チ)・川(ツ)・止(卜)・移(ヤ)・已(ヨ)などが用いられているが、それが漢・呉両音よりも古い古代音(秦漢音)であり、周代の韻脚に合うと考証している。本書によって推古期の実態が明らかになった。また、片仮名・平仮名の「卜・と」と「ツ・つ」の字源を推論する手掛かりが与えられている。別冊は本研究の根本資料となったものを、拓本・写真で示し、正確さを期しており、独創的な研究で、この分野に一画期をなした。ただし著者の時代はまだ中国の音韻史が十分に判明していなかったので、今日より見れば早急に結論を下しすぎたきらいが多い。中国古音といっても、必ずしも周代に及ぶ必要のないことは、その後の研究で明らかにされている。〔中田祝夫氏より〕
〔参考文献〕『周代古音考同韻徴』大矢透。
・聖徳太子の『法華義疏』の大委国
聖徳太子は、『三経義疏(さんぎょうぎしょ)』をあらわしたと伝えられる。
『法華義疏(ほっけぎしょ)』は四巻、『維摩経義疏(ゆいまぎょうぎしょ)』は三巻、『勝鬘経義疏(しょうまんぎょうぎしょ)』は一巻である。
成立年代は、『上宮聖徳太子伝補闕記』によると、『勝鬘経義疏』が、609年から三年、『維摩経義疏』がそれにつづいて二年、『法華義疏』が二年、合計七年かかって(聖徳太子、36歳~42歳の時期に)完成したという。
『三経義疏』のうちの、『法華義疏』については、聖徳太子の自筆本と伝えられる巻物が存在する。
『法華義疏』は、鳩摩羅什訳の『妙法蓮華経』二十七品本を使用するなど、内容的には、古いものである。『法華義疏』は、西暦614~615年、聖徳太子41~42歳のころの成立とみられる。
『三経義疏』については、聖徳太子の撰述を疑う説がある。
偽撰説には、法隆寺に撰者不明のままに伝えられてきたものに、747年(天平十九)に寺の資財帳提出のさいに、「上宮王私集」という題箋(だいせん)を付したものであるとする説や、中国敦煌出土の『法華経』の註釈と関係づけて疑う説などがある。
しかし、『法華経義疏』をみると、「大委国上宮王私集非海彼本[大委国の上宮王の私集、海彼(かいひ)〔外国〕の本にあらず]」という題箋の筆跡は、本文と同じもののようにみえる。別人が、あとから題箋をふしたもののようにはみえない。
筆跡について、今回は、くわしく触れることができない。
ただ、たとえば、グラビア写真中に○(マル)印をつけて記した題箋中の「是」「非」の字と、本文中の「是」「非」の字との類似性などをみていただきたい。
題箋中の「是」「非」
本文中の「是」「非」
さらに、「委」という文字を、「い(ゐ)」でなく「わ」と読むのは、古い読み方で、いわゆる「推古朝遺文」の読み方である。
このことについては、『季刊邪馬台国』76号所載の「金印銘『漢委奴国王』の読み方という文のなかで詳論した。
たとえば、『日本書紀』をみても、「委」の字を「わ」と読むのは、古い朝鮮系(百済系)資料によるとみられるものにかぎられる。つぎのようなものである。
「賁巴委佐(ほんはわさ)」(安羅の人。「継体天皇紀」)
「委陀(わだ)」(朝鮮の洛東江口の地名。「継体天皇紀」「推古天皇紀」)
「竹斯物部莫奇委沙奇(つくしのもののべのまがわさか)」(百済の人。「欽明天皇紀」)
『日本書記』の「継体天皇紀」に、『百済本紀』という現在は存在しない百済系文献を引用する形で、「委意斯移麻岐弥(やまとのおしやまきみ)」という名がみえる。ここに、「委」の字が用いられている。
これは、朝鮮系資料によっている部分で、本来は、「委意斯移麻岐弥(わおしやまきみ)」と読むべきものとみられる。
そして、以上にあげた例文のなかにみえる「奇(が)」「奇(か)」「意(お)」「移(や)」などは、いずれも、推古朝遺文にみられる古い用字法である(中国の秦・漢時代の音にもとづく)。
『日本書紀』の編纂者は、歌謡を記すばあいなどは、「委」を、「わ」と読まず、「ゐ」と読んでいる。
つぎのように。
「等利委餓羅辞(とりゐがらし)[鳥居枯(とりゐが)らし]」(歌謡中の万葉仮名。「応神天皇紀」)
「委遇比菟区(ゐぐひつく)[堰杙築(ゐぐひつ)く]」(歌謡の中の万葉仮名。「応神天皇紀」)
「爾加委(にかゐ)」[島の名。伊吉連博徳(いきのむらじはかとこ)の書のなかにでてくる。「斉明天皇紀」]
朝鮮系資料によるものと、そうでないものとでは、あきらかに読みが異なっている。
「委」を「ゐ」と読むのは、『日本書紀』編纂時、あるいは、それに近い時期の読みとみられる。
『日本書紀』では、朝鮮系資料によるものとそうでないばあいとで、「委」を「わ」と読むか、「ゐ」と読むかが、整然と読み分けられている。このようなことは、偶然では、とうていおきえないことである。
『日本書紀』の編纂者たちは、「委」の中国古音が、「わ」に近いものであることを知らないはずである。たんに、先行文献での「伝統」にしたがって、「委」を「わ」と読んだとみなければならない。
「委」を「わ」と読むのは、『日本書紀』編纂時に、編纂者が与えた読みではない。
『日本書紀』は、古い伝統を書きとどめているのである。
以上のような考察は、『法華経義疏』が、推古天皇の時代の聖徳太子の撰になるという伝えをサポートするものである。
なお、最近、聖徳太子非実在説が、喧伝されているが、文献学的には、話にならないものと考える(これについては、機会があれば、別にのべたい)。
この『法華義疏』(聖徳太子自筆本とされるもの)において、下図のように、マル印をした「是」「非」などの筆跡特徴をみれば、「此是大委国上宮私集非海彼(かいひ)本[これは、大委国上宮私集で、海外の本ではない]」の題箋(だいせん)の文字と本文の文字とは、共通性がある。同一筆跡とみられる。そして、「委」を「ワ」と読むのは、推古期遺文の読み方である。
(下図はクリックすると大きくなります)
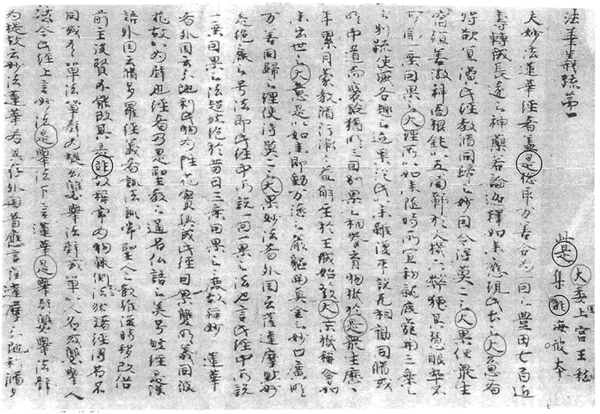
■歴史を伝えるにあたり、事実のことと、誇張されて話と両方が伝えられることになる。十九世紀的文献批判学の方法である。この文献批判学は、文献の記述内容に対して、批判的、懐疑的、否定的な傾向が強い。
それに対し、誇張された表現は神話化する。
・神話化のプロセスは?
系譜学者、太田亮(あきら)の『日本古代史新研究』に、つぎのような話がのっている。
明治維新のまえに、太田亮の郷里(奈良県吉野郡)で、天誅組(てんちゅうぐみ)が旗あげをした。太田亮の毋の話によると、事実をみない村人は、天誅を天中と誤解し、彼等を天と地との間を歩く人として恐れおののいたという。・・・・・・・・・・・・
また、歌手の美輪明宏氏の『紫の履歴書』(水書坊刊)を読むと、長崎での原爆体験が、つぎのように、およそ神話化されたことばで語られている。
「表……そこは地獄だったのです。
荷台の前で、ドサリと横なって死んでいる馬の傍で、馬方らしい人間が、ぴんぴん飛び上がっています。
丸裸で全身が紫とも赤ともつかぬ火ぶくれで獣のような声をあげています。……
阿鼻叫喚(あびきょうかん)の交響楽がシンバルやティンパニーの乱打と共に、何十万の悲鳴の混声合唱(コーラス)を叫び、この世の果てまで届くよう助けを求めて哭(な)いています。凶暴な死が衣をひらめかせながら、眷族(けんぞく)を率いて、空一杯に広がり、地獄の中で大声で笑い躍り、荒れ狂っています。」
このような例は、「事実」が神話化するプロセスを、かなりよく示しているようにみえる。
中国では、はやくから、すぐれた歴史書があらわれ、事実を客観的なことばで記す道がきりひらかれていた。その水準はかなり程度の高いもので、現代の歴史記述の方法に十分つながりうるものであった。
しかし、わが国においては、中国の文化の影響をうけ、その史書などを学ぶ以前においては、神話化したことばで語る以外に、歴史的な事件などを伝える方法を知らなかったといってよい。そのようなことばで語られたものは、現代の歴史記述におけるような意味で、「事実」を客観的につたえるものではない。しかし、しばしば、神話は、事実を核としていることがある。
玄奘三蔵は、実在の人物である。しかし、玄奘三蔵の旅行に材をとった『西遊記』は、数々の化物たちのあらわれる神話化された物語となっている。
釈迦は、実在の人物である。しかし、『法華経』(『妙法蓮華経』)のなかの釈迦は、きわめて幻想的、神話的に語られている。
イエス・キリストものべている。
「木の良否は、実の良否によって知ることができる。」と。
最近の聖徳太子論や、大化の改新論は、新しい資料を提出しているわけではない。『日本書紀』などの文章の観念的な解釈論に、ほとんど終止している。
客観性、実証性の欠けた観念的論争というべきである。
・津田史学は非生産的な水かけ論をもたらしている
行きつくところは、「聖徳太子も実在しなかった。」「いや、聖徳太子は実在したのではないか。」「大化の改新は、偽りだ。」「いや、そうともいえない。」式の、およそ、非生産的な水かけ論に熱中することになる。そこでは、肯定するにしても否定するにしても、科学的・客観的な判断基準が提出されていない。
読者は、どの説を、どこまで信じてよいのか、わからなくなる。
津田左右吉の文献批判学のトレーニングをうけたはずの何人かの日本史学者は、現代人制作の完全な偽書である『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』などを、本物であると主張したりした。『古事記』『日本書紀』を疑って、『東日流外三郡誌』を信ずるのでは、「石が浮かんで木が沈む」ような議論である。
津田左右吉流の文献批判学の発展の結果は、「文献学は、古代史探究にあたって、無用の長物である」ことを証明することになっている。学問としての自己否定をもたらしている。
結局、何が本物で、何がニセモノかという議論は水掛け論になりやすく、非生産的な議論となりやすい。