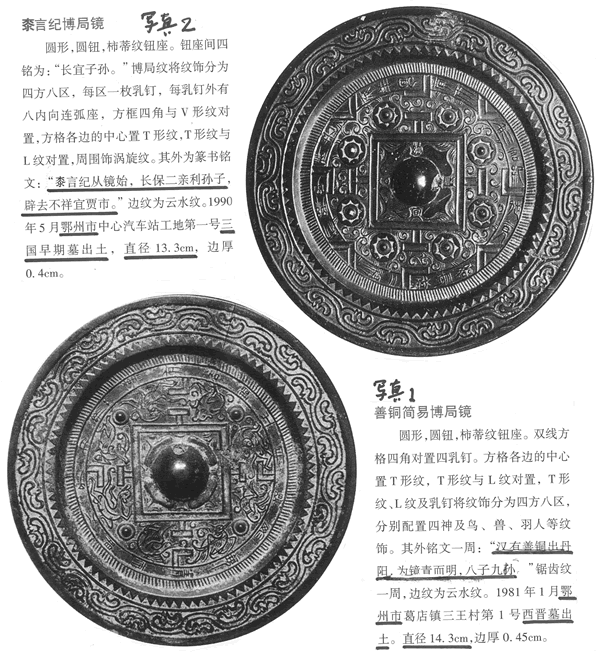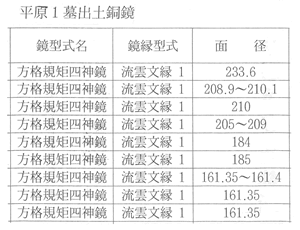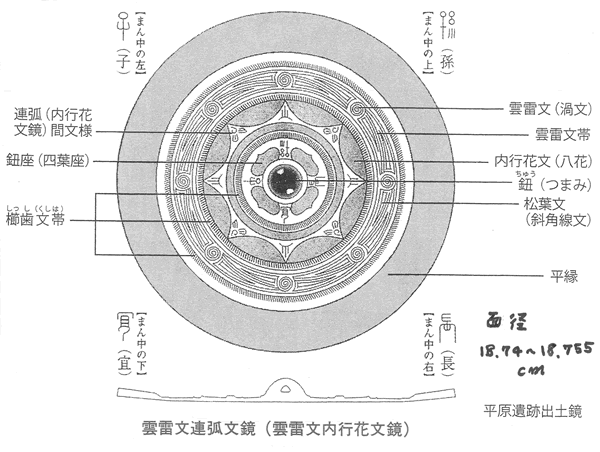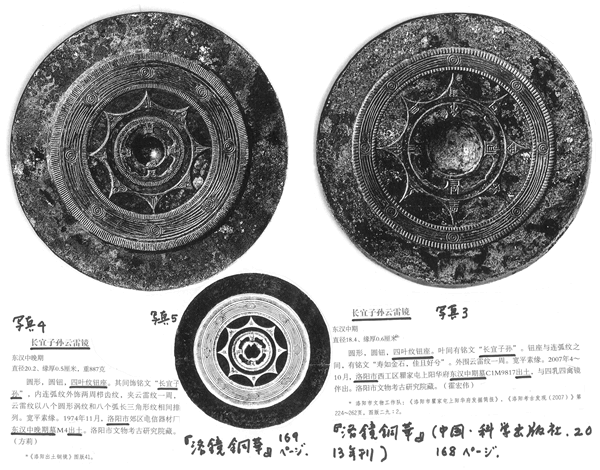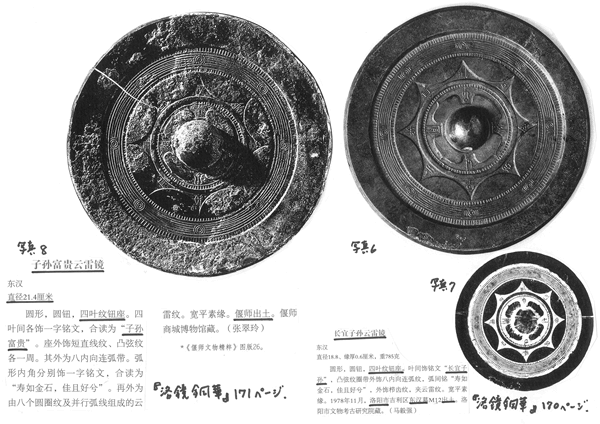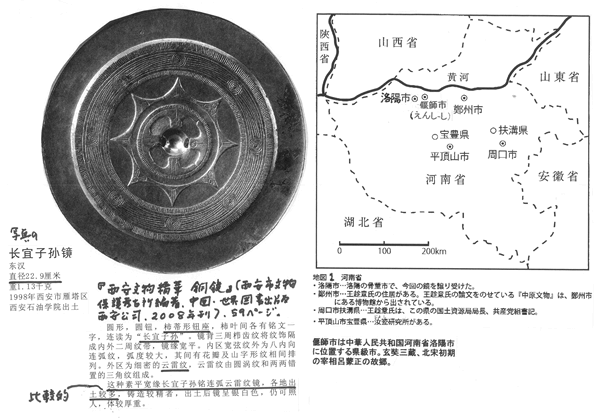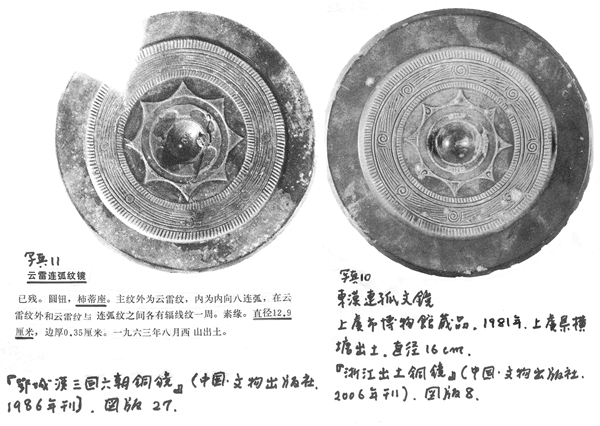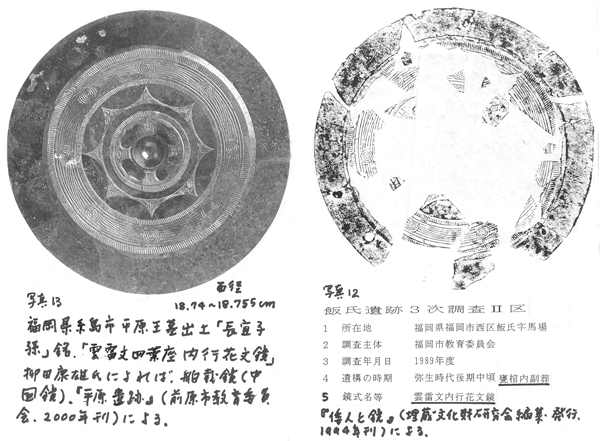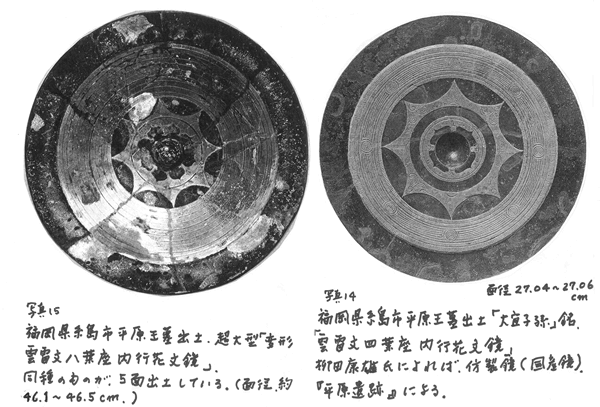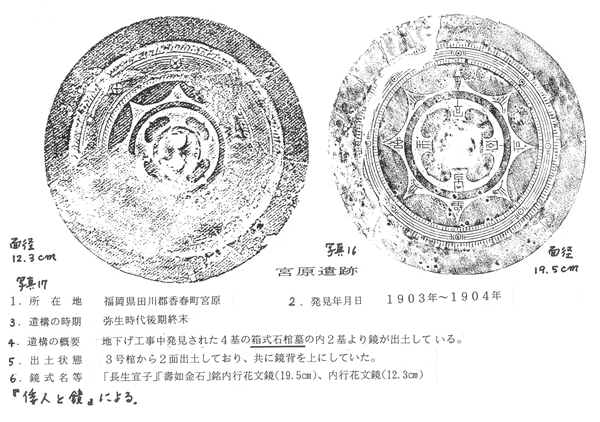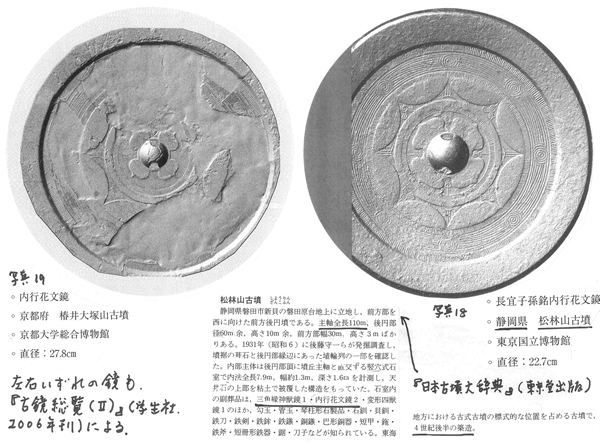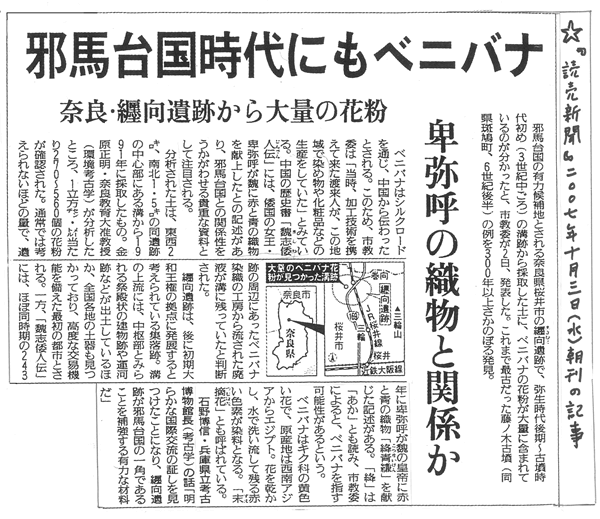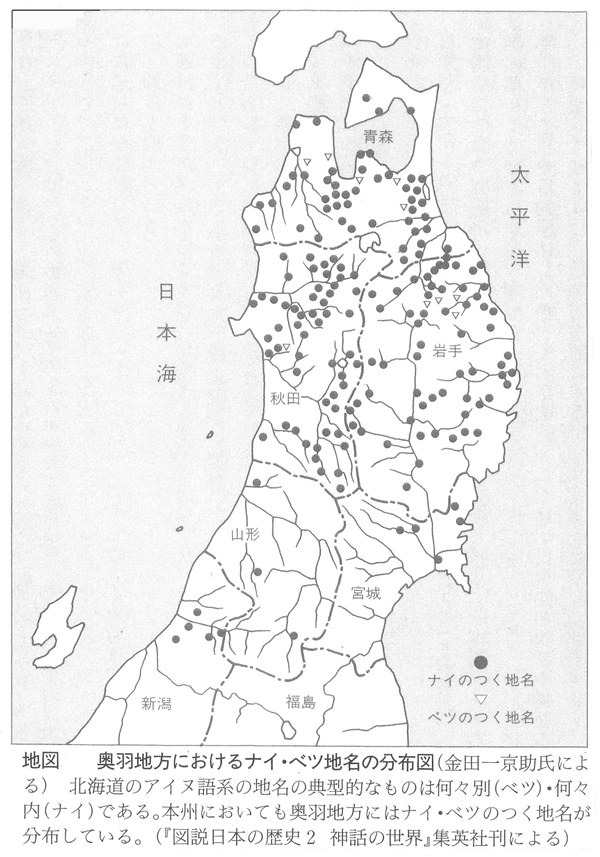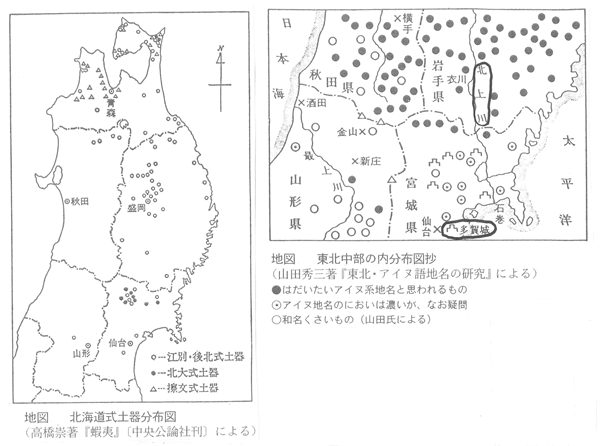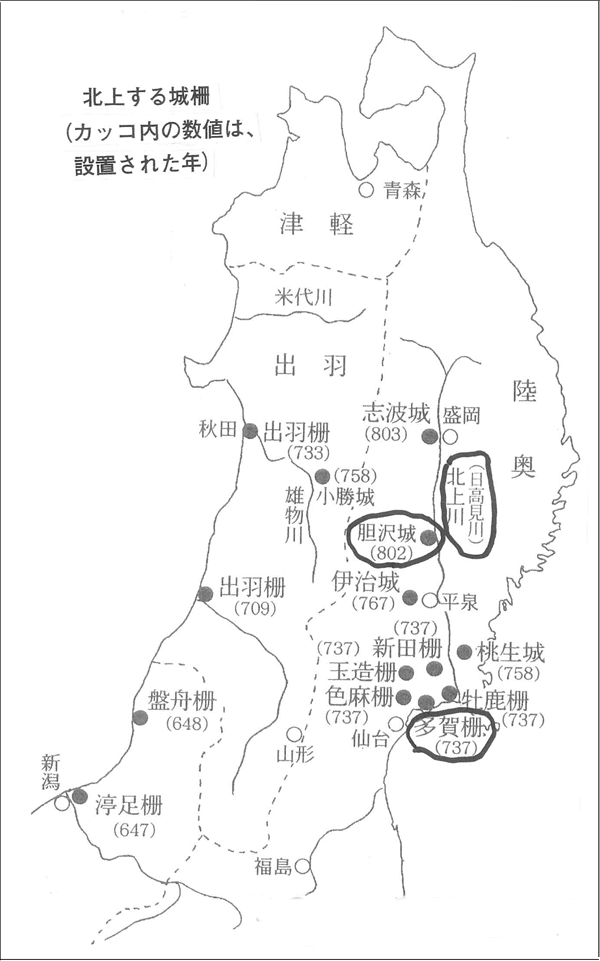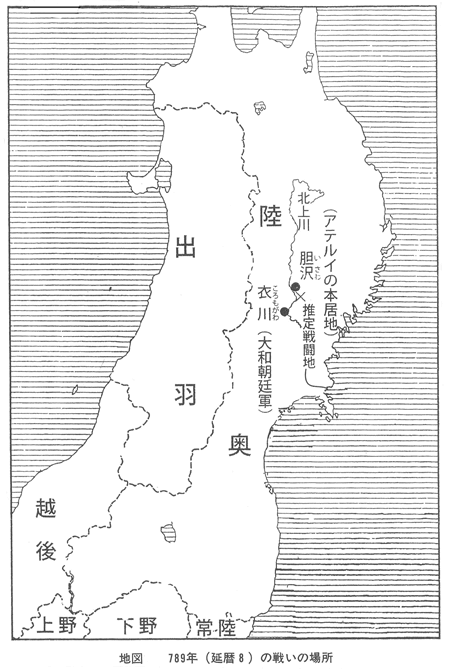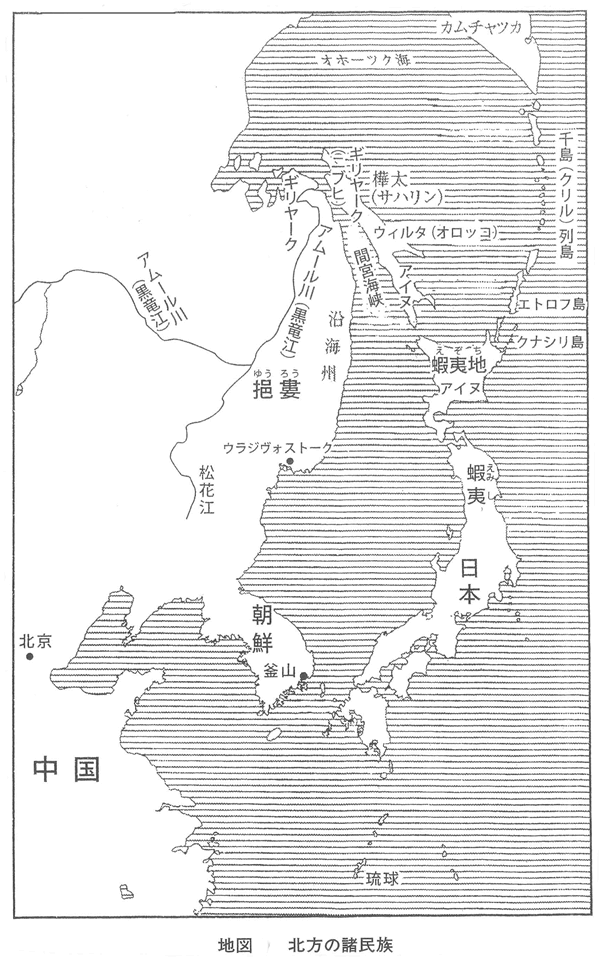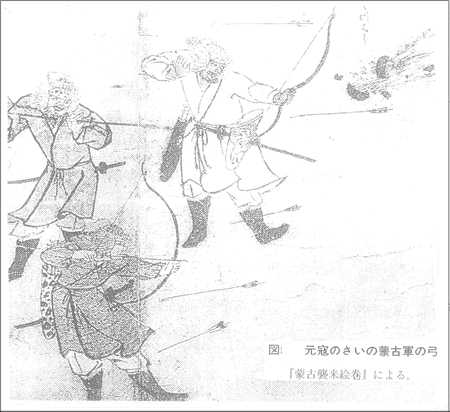『魏志倭人伝』に、倭人は「租賦を収む」と記されている。「租税をとる」というアイデアは、中国からきたものであろう。「租税をとる」ことによって、「国家」は、はじめて、部族国家の域を脱する。強力な「国家」といえるものとなる。「租税」によって、戦争にとくに適した屈強の若者たちを、「兵士」としてやというる。それらの「兵士」は、戦争だけに専念することができる。組織的な訓練をうけることとなる。「租税」によって、最新鋭の武器を購入することができる。最新鋭の武器をもち、組織的な訓練をうけた兵士によって、王朝を守らせることができる。支配地域を拡大させうる。
武力によって、支配地域の人民から、「租税」を収奪することができる。
また、一方、治水や灌漑などの土木工事をより大規模に行なうことができる。外国の新技術も導入し、農業生産力をあげることができる。
「租税」制度をもつ国家は、人々の生活を安定させ、より豊かにする。人口の自然増も大きくなる。支配地域そのものもひろげうる。
「租税」収入をより大きくし、武力を、すなわち、国家権力を、さらに大きくすることができる。
このようにして、国家権力の拡大再生産が可能となる。
アイヌは、最後まで、部族国家の域を脱しなかった。組織的な徴税システムをもたなかった。このような部族国家では、鮭(さけ)が川にのぼってくれば、戦争を放棄して、魚をとらなければならない。兵士は、日ごろは、生産に従事しており、戦争のプロではない。戦争のための組織的な訓練を、十分にうけているわけではない。
徴税システムをもつ「国家」と「部族国家」とが戦ったばあい、長い目でみると、「部族国家」に勝ち目はない。
大和朝廷は、徴税を行なうという、新機軸の国家システムによって、比較的短い期間で、日本列島を席巻していったとみられる。
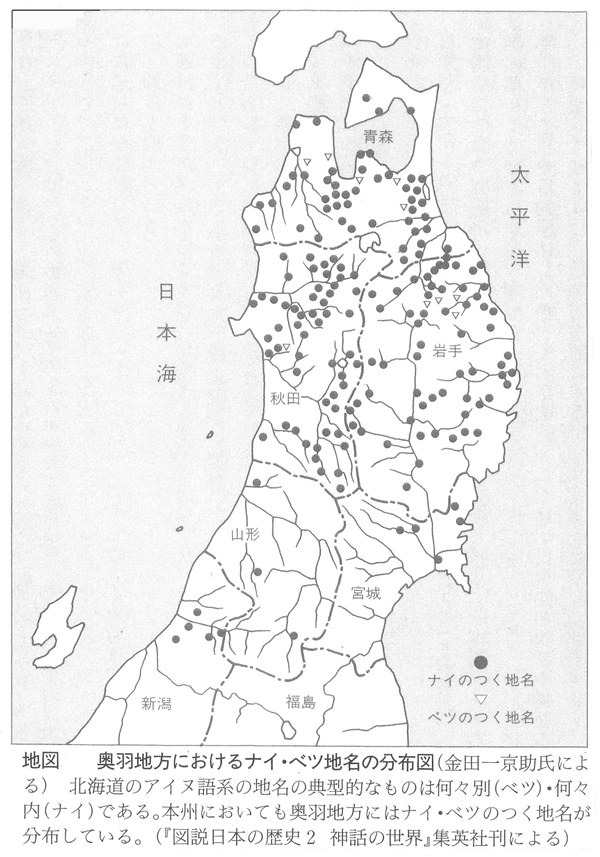
■紀朝臣古佐美(きのあそんこさみ)の征夷
征東副使であった紀朝臣古佐美(733年生まれ、紀麻呂の孫)は、781年に、陸奥守となり、征夷の中心となった。
今回の征夷計画は、786年に東海・東山の軍士を閲し、兵器の点検をはじめ、糧食三万五千斛(こく)、糒二万二千斛などを集積し、東国の歩騎五万二千八百人の集結が命じられた。
節刀をたまわり、副将軍などが法を軽んじ死罪をおかすことがあれば、身を拘禁し、軍監以下は、斬に処せとの詔をうけた。
大和朝廷としては、そうとうの決意で、征夷をこころみたのであった。
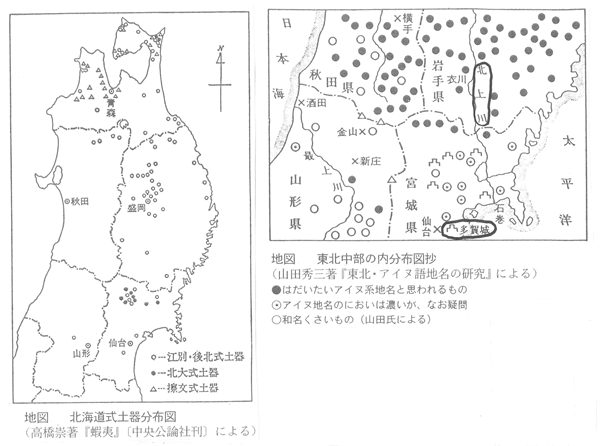
786年3月、諸軍は、陸奥国多賀城に会した。
788年、紀古佐美は、征東将軍となった。
衣川(北上川水系の支流。岩手県平泉町)を渡って、三か所の軍営をおいたが、なかなか進めなかった。朝廷から督促をうけた。
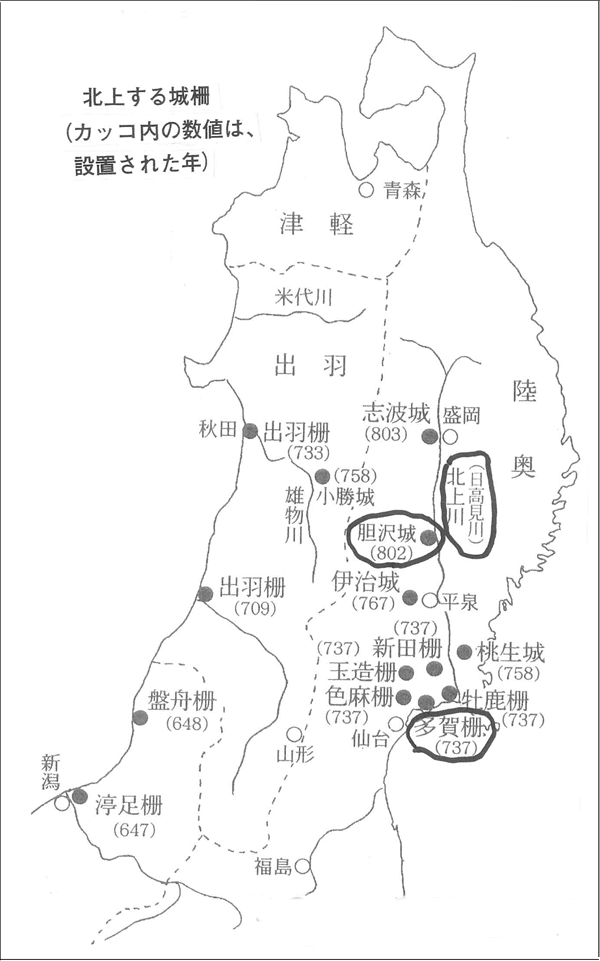
紀古佐美のまえに、大きく立ちふさがったのが、阿弖流為であった。阿弖流為は、陸奥国胆沢(いざわ)[のちの胆沢・江利両郡をあわせた広域地名。胆沢郡は、現在の岩手県胆沢郡と水沢市。江刺郡は、岩手県江刺市と水沢市の一部]地方の蝦夷の族長であった。
789年(延磨八年)、胆沢の蝦夷をひきい、巣伏村(水沢市羽田町付近、あるいは、江刺市愛宕付近にあてる説がある)付近を拠点として、征東将軍紀朝臣古佐美のひきいる軍兵に対抗した。
紀古佐美の軍のうち、四千(中・後軍)の征討軍は、衣川の北の地点にから、北上川東岸にわたり北にむかった。
三百ほどの蝦夷軍が迎え撃った。官軍の勢いがつよく、賊軍は引き退く。征討軍は、「かつ戦い、かつ焼き」つつ、阿弖流為の本拠巣伏村に至った。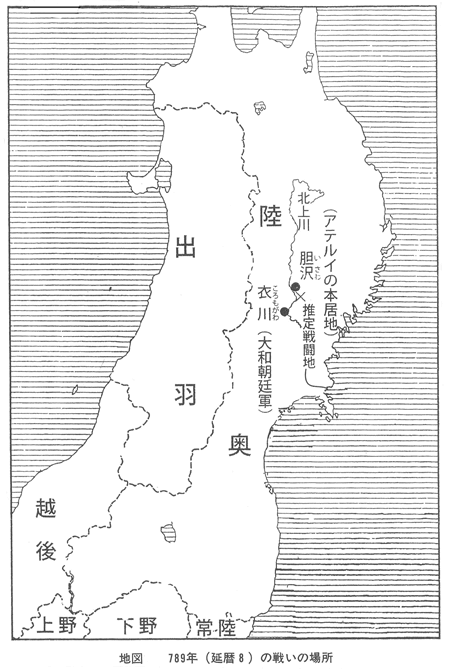
前軍は北上川を東にわたり巣伏村のあたりで、中・後軍と合流することになっていた。前軍の渡河を蝦夷軍がはばんでいるうちに、八百余の蝦夷軍が、中・後軍をおそった。征討軍が後退すると、さらに四百人ばかりの蝦夷軍がたちふさがり、退路をたった。征討軍は、北上川を西に渡って逃げようとする。
戦死するもの二十五人、矢にあたるもの二四五人、河で溺死するもの一〇三六人、はだかで泳いで帰るもの一二五七人という惨敗となった(『続日本紀』)。ゲリラ戦によるあざやかな蝦夷軍の勝利である。
ここで、注目すべきなのは、『続日本紀』が、「矢にあたるもの二四五人」と記している事実である。
『続日本紀』は、蝦夷軍が、毒矢を使ったことを、特に記していない。
もし、『三国志』の「挹婁(ゆうろう)伝」に記されているように、「矢には毒をほどこし、人にあたれば、みな死ぬ」というような情況であれば、さきの文の「矢にあたるもの二四五人」は、みな「戦死者」になったはずである。
つまり、阿弖流為のひきいた蝦夷軍は、毒矢の技術を、もっていないのではないか。
蝦夷軍は、あざやかな勝利をえたが、蝦夷がわの被害も、甚大であった。
蝦夷がわで斬首されたもの百人に近く、官軍は、十四か村、八百戸を焼いた。
789年の征討に惨敗し、政府は、翌年から準備をはじめ、794年には、十万の軍を動員して征夷する。
『日本紀略』の794年10月28日条の、征夷大将軍大伴弟麻呂の奏言によれば、
「四百五十七級を斬首し、百五十人を捕虜とし、八十五匹の馬をえ、巣落七十五処を焼いた。」という。
■征夷大将軍坂上田村麻呂
801年、征夷大将軍坂上田村麻呂が、十か国の四万人の軍をひきい、802年、胆沢城(いざわ)城[城跡は、岩手県水沢市佐倉河]を築きはじめた。田村麻呂は、その「薨伝」によれば、「赤面黄鬚(おうしゃ)[あごひげ]、勇力人に過ぐ。」という人物であった。
阿弖流為は、盤具公母礼(いわくのきみもれ)と五百余人をひきいて、坂上田村麻呂に投降した。
阿弖流為は、その根拠地胆沢地方に、官軍の城が築かれはじめ、さらに奥地まで、征夷軍に上る徹底的な焼土作戦がおしすすめられるなかで、降伏した。
802年7月、坂上田村麻呂は、阿弖流為と母礼をつれて、平安京にはいった。
田村麻呂は、「蝦夷の帰服を説得させたい」と助命を進言した。しかし、公卿らのいれるところとならなかった。阿弖流為らは、802年8月13日、河内国の杜山(もりやま)[大阪府枚方市か]で斬られた。
■俘囚蝦夷の悲劇
『日本紀略』は記している。
「夷(えびす)の大墓公(たものきみ)阿弖利為と、盤具公(いわくのきみ)母礼(もれ)らを斬る。この二虜は、ともに、奥地の賊首である。二虜を斬るとき、将軍らが、申していった。『この度は、願いのままにかえしてやり、その賊類を招かせたい。』しかし、公卿は、論をまげることなく言った。「野性獣心。反覆定めがない。たまたま朝威によって、この梟師をえた。たとえ、申し出によって、奥地に放還しても、いわゆる虎を養って、患(わずらい)をのこす、というものである。すなわち、二虜をとらえ、河内国杜山に斬る。」
『日本後紀』の、811年(弘仁二年)10月13日の条に、つぎのような記事かある。
「蝦夷は、中国(内地)に移配せよ。俘囚は、便宜をはからって、当土(現地)に安置し、つとめて、教喩を加え、騒ぎをおこさせないようにせよ。」
ここで、「蝦夷」といっているのは、本来の蝦夷で、強硬な反抗分子をさすとみられる。「俘囚」は、「熟化した蝦夷」つまり「熟蝦夷(にぎえびす)」で、穏健分子をさすとみられる。
農民化政策で、内地に移配された蝦夷も、「俘囚」「夷俘」などとよばれたが、これらの人たちには、きびしい運命がまっていたとみられる。
『日本後紀』の805年の記事によれば、播磨国に移配された俘囚が、野心を改めないで、しばしば朝憲に違ったという理由で、多褹(たね)島[九州南部の種子島(たねがしま)]に配流されている。
『続日本後紀』の847年の記事には、日向国で、俘囚がほとんど死につくし、生存者の数がすくない、とある。
878年に、秋田城司の苛斂誅求によって、出羽国秋田郡の夷俘が大反乱をおこした「元慶(がんぎょう)の乱」(878~879)などがあった。夷俘は、秋田河(雄物川)以北の独立を要求した。官軍は、軍馬千五百を失なうなど、戦局は、しばしばまったく不利であった。
■アイヌの毒矢について
アイヌは毒矢を用いた。
アイヌの毒矢の作りかたについては、ジョン・バチラー著の『アイヌの伝承と民俗』(安田一郎訳、青土社、1995年刊)に、くわしくのべられている。
そのなかで、ジョン・バチラーは記す。
「猟をするとき、アイヌは矢に毒を塗った。そしてある種の毒は、トリカブトの根から作られた。」
「アイヌが狩猟で用いる矢は貧弱で弱い道具のように見える。しかし、非常に強力である。」1336年(延元元年)1月28日、足利尊氏が、長野県諏訪神社に寄進した『諏訪大明神絵詞』のなかに、北海道のアイヌの毒矢についてふれた文がある。
そこでは、つぎのようにのべられている。
「彼らが用いるところの箭(や)は、魚骨をやじりとして、毒薬をぬる。わずかに皮膚に触れれば、その人は倒れないということはない。」
『文化人類学事典』(弘文堂、1987年刊)では、世界の矢毒の分布を、地理的な分布と、用いられる植物の種類とから、四つにわけている。
その一つに、東北アジアから、アッサム・ヒマラヤにかけてにみられるトリカブト圈をあげる。そしてのべている。
「トリカブト圈において最もよく知られた例はアイヌであるが、彼らはトリカブト(キンポウゲ科)の根を粉にし、マツヤニをつけたやじりにその粉をつけて用いていた。」
毒物学の石川元助氏は、およそ、つぎのようにのべている。
「キンポウゲ科のアコニツム属植物を矢毒につかう伝統は、北海道と沿海州、樺太(サハリン)、アリューシヤン、アラスカ半島に、西南へは、中国大陸を通って、雲南、四川、さらに、ネパール、ブータンにのびる。毒矢文化の起源は、ヒマラヤとみられる。毒矢文化を、アイヌ祖先集団に伝えたのは、挹婁族であろう。」(『毒矢の文化』紀伊図屋書店、1962年刊。『毒薬』毎日新聞社、1965年刊)
『後漢書』や『三国志』の「挹婁(ゆうろう)伝」には、つぎのように記されている。「弓の長さ四尺(約九十六センチ)。」(『後漢書』『三国志』同文)
「矢には毒をほどこし、人にあたればみな死ぬ。」(この文は、『三国志』による。『後漢書』は、「鏃には、みな毒をほどこし、人にあたれば、即死する。」とある。)
挹婁は、「いにしえの粛慎」とされている民族で、ツングース族の一種である。ロシアの沿海州[アムール川(黒竜江)下流域、ウラジヴォストークを中心とする地域]から、中国東北地方(旧満州)東部に住んでいた
(地図参照)。
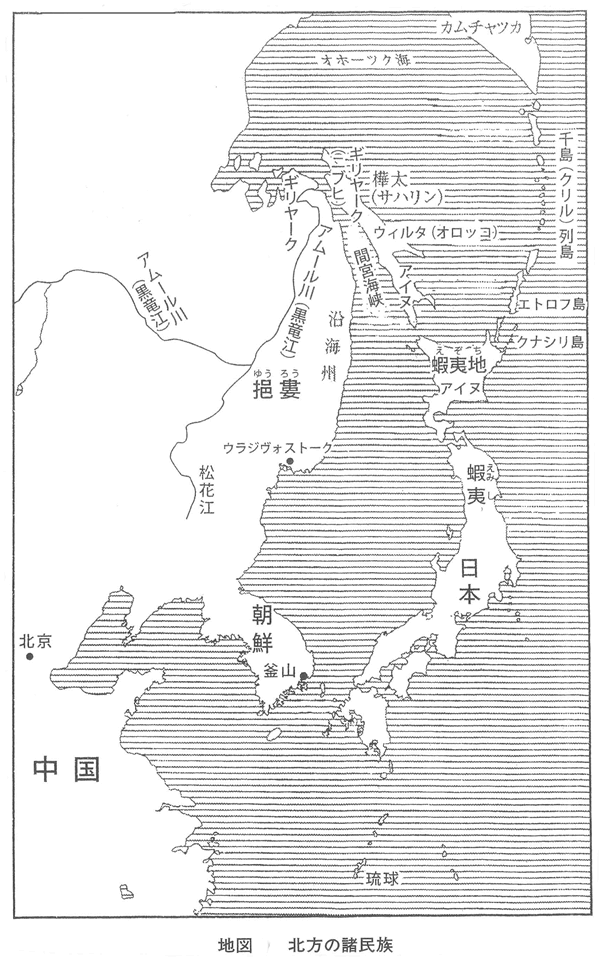
アイヌの弓矢文化が、短弓で毒矢をもつのに対し、倭人の弓矢が、長弓で毒矢を用いないことなど、弓矢については、文化の系統が異なるようにみえる。
弘法大師・空海(774~835)の著書『性霊集(しょうりょうしゅう)』のなかに、つぎの文がある。
「毛人や羽人などの蝦夷(えみし)は、境を接して住んでいる。猛虎や犲(やまいぬ)や狼(おおかみ)のように、ところどころに集っている。年とったカラスのような目をし、猪や鹿の皮ごろもをまとい、たばねた髪のなかに、骨製の毒の箭(や)を插(さ)してつけ、手もとには、つねに刀と矛とをとり、たがやさず、衣を織ることなく、麋(おおしか)や鹿を逐(お)っている。」(毛人羽人接境界、猛虎豺狼処々鳩、老鵶目、猪鹿裘。髻中挿著骨毒箭。手上毎執刀与矛。不田不衣逐麋鹿)(『三教指帰性霊集(さんごうしいきしょうりょうしゅう)』[日本古典文学大系、岩波書店、1965年刊]166ページによる)
この文は、古代の蝦夷が、毒矢を使用していたとする最初の文献である。
これによれば、九世紀の前半には、蝦夷は毒矢を使用していたことになる。アイヌとつながる文化をもっていたことになる。
私には「アテルイ」という名は、なんとなく、大和ことば的ではなく、アイヌ系の名のように思える。
■モンゴルの弓
騎馬によって、欧亜を席巻したことのあるのは、モンゴル族であった。
モンゴル族の弓も、写真にみられるように、短弓系の弓とみてよい。 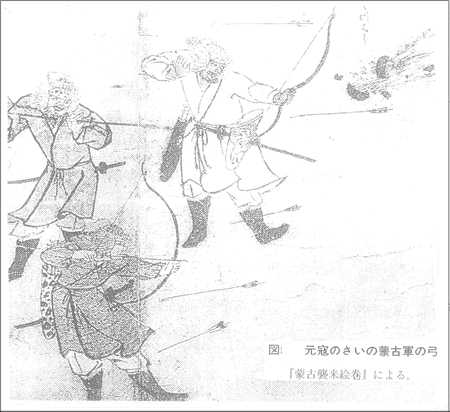
また、図は、元寇の文永の役(1274年)のときの、蒙古軍の弓を描いたものである。
やはり、アーチェリータイプの短弓である。
モンゴル軍も、毒矢を用いた。
鎌倉時代末期の神道書で、岩清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)の霊験記(れいげんき)を書いた『八幡愚童訓(はちまんぐどうくん)』のなかに、つぎのような文章がある。
「(文永十一年[1274])11月21日、蒙古(軍)は、船よりおり、馬に乗り、旗をあげて攻めかかる。日本の大将は、少弐(しょうに)[資能(すけよし)]入道覚恵(かくえ)の孫の、わずかに十二、三歳のもの[少弐資時(すけとき)。十二歳で出陣)で、矢合わせ(開戦を通告する矢をはなつこと)のために、小さい鏑矢(かぶらや)を射たところ、蒙古軍は、一度に、どっとあざ笑った。(中略)蒙古軍の矢は、短いけれども、矢の根に毒を塗っているので、あたったものは毒気を負わないということがない。」(『寺社縁起』[日本思想大系、岩波書店、1975年刊]による)
これは、元寇のときの、文永の役のことをのべているのである。
大阪大学の黒田俊雄氏は、その著『蒙古襲来』(日本の歴史8、中央公論社、1965年刊)のなかで、つぎのように記している。
「蒙古軍は短弓で、矢も短かったが、すばらしくよく飛び、しかも矢じりに毒を塗っていたので、浅い矢傷でもひどく苦痛を与えた。」
矢が短いこと、毒矢であること、強い効力をもつことなど、アイヌの矢と共通している。