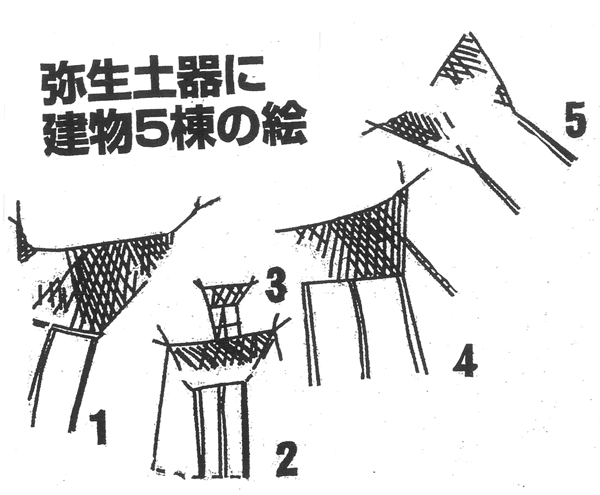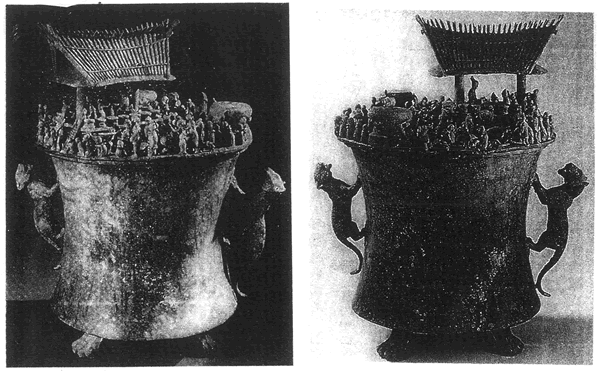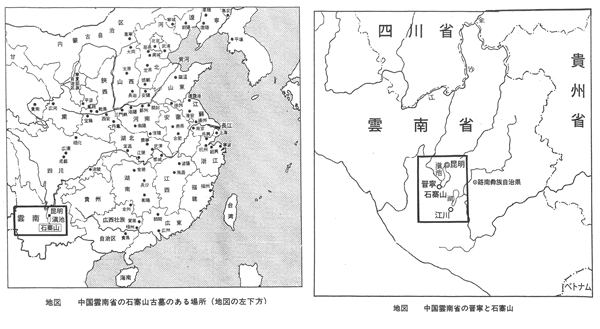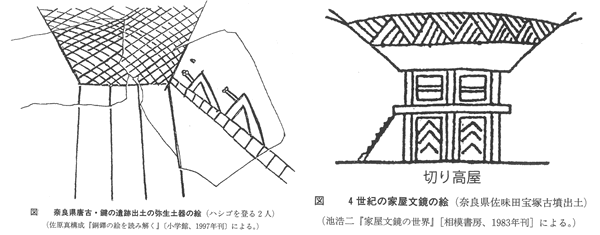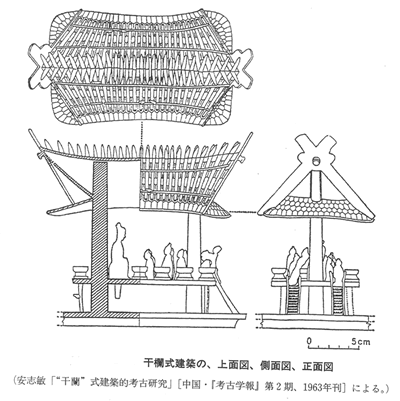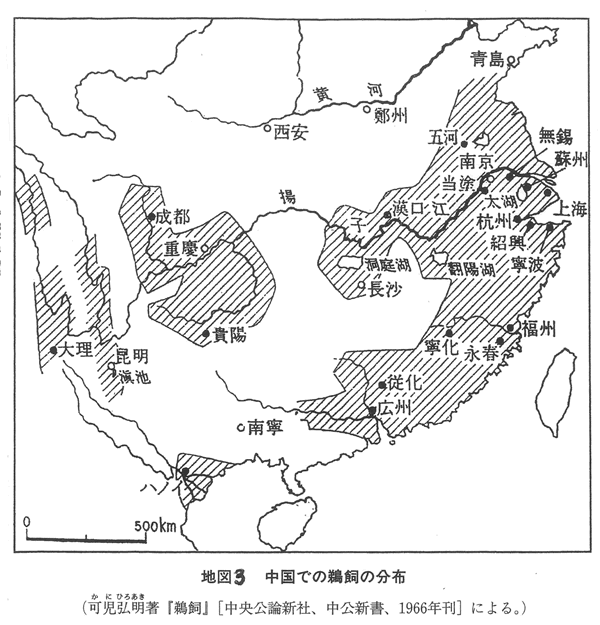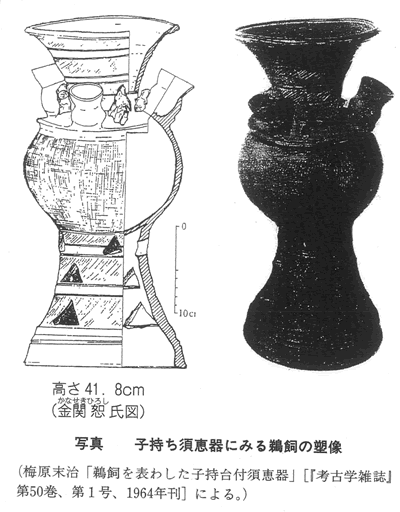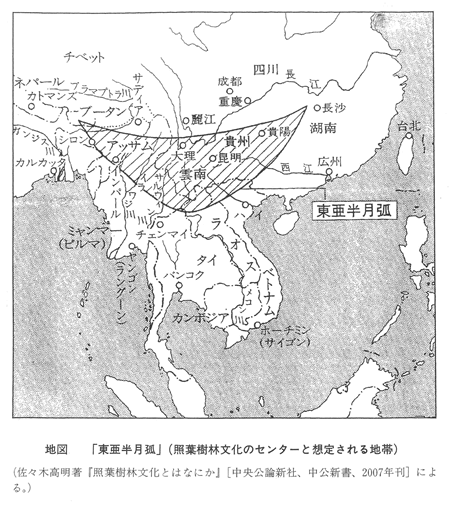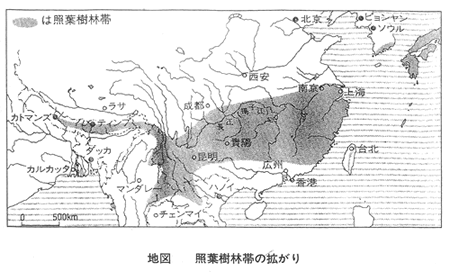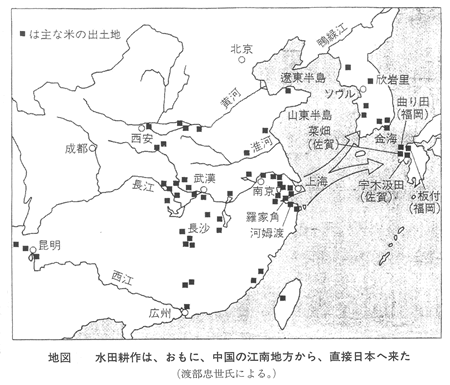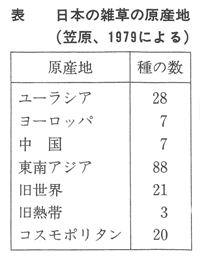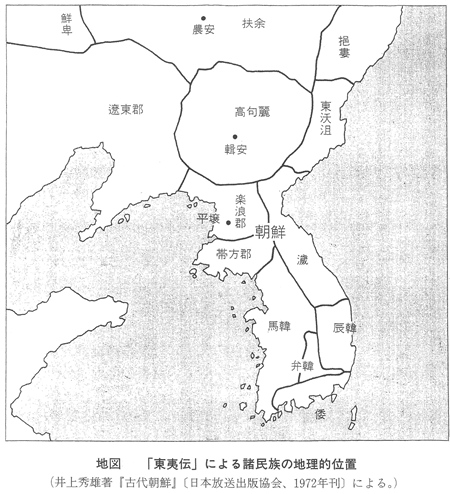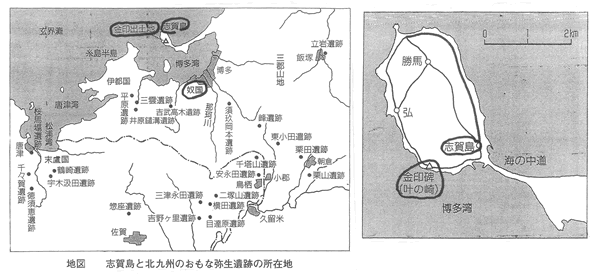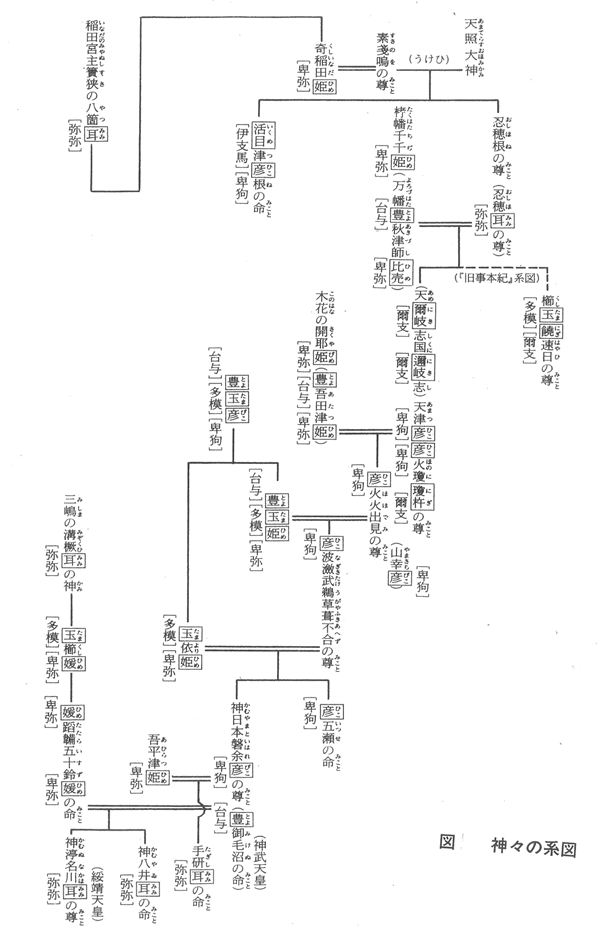「考古学を疑え」の講演部分は省略し、その話の続きの「稲の来た道論争」から始めます。
a.干欄式(かんらんしき)建築
■切妻屋根の高床建物
・『朝日新聞2018年3月24日(土)朝刊』の新聞記事で、「大阪府茨木市にある弥生時代の中河原遺跡で、5棟の切妻屋根の高床建物が描かれた土器片が見つかった。」とある。

これは干欄式(かんらんしき)建築ではないだろうか?
ここで、「干欄式建築」については、『世界考古学事典、上』(平凡社、1979年刊)に、つぎのように説明されている。
・干欄式建築(かんらんしきけんちく)
中国の古典に記載されている高床式建築・新石器時代以後現代にいたるまで、長江流域および江南の諸地域、東南アジア、日本などに広く分布している。(梁書)林邑国伝(りんゆうこくでん)、(北史)蛮獠伝(ばんろうでん)、(唐書)南蛮伝などには、干蘭・干欄・高欄・閣欄、葛欄の用語がみられるが、その建築様式を示すと考えられるいくつかの遺物が知られる。雲南石寨山(せきさいざん)出土の青銅器貯貝器(ちょばいき)[宝物または貨幣とされた子安貝をいれる容器]蓋(ふた)上にみられる建造物は、長方形の高床式建築で、壁はなく、二本の円柱が切妻造(きりづまづく)りの屋根を支え、前端に梯子(はしご)が付く・広東・広西・湖南・四川・貴州省などの後漢墓からは、高床式建築の明器(めいき)[墓の中に埋めるために特製した器物]が出土する。干欄式建築を描いた画象としては、石寨山出土の貯貝器の腰部(胴体の曲った部分)画象や、日本の香川県発見とされる銅鐸の画象、奈良県佐昧田宝塚古墳出土の家屋文鏡の高床式建築の例が知られる。湖北省圻春県毛家嘴(きしゅんけんもうかすい)の西周の遺跡では、二列または三列に配列された柱、木板、木製梯子を有する高床建築の遺構が発見されている。日本においても静岡県登呂遺跡(とろいせき)で高床式建築址と考えられる遺構が発見されている。文献 安志敏(『考古学報』1963-2)。(飯島武次)
このように、「干欄式建築」は建物の屋根の一番上の長さが長く、軒(のき)の長さが短い。
■中国雲南省の干欄式建築
中国雲南省の石塞山遺跡は日本からは遠くへだたっている。しかし同じタイプの建築様式の建物が出土している。
下図は上記の『朝日新聞2018年3月24日(土)朝刊』の新聞記事の写真の拡大。
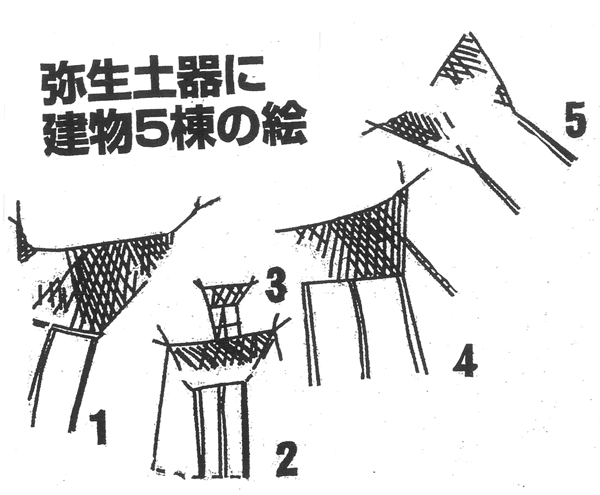
中国・雲南省の干欄式建築の写真
貯貝器(ちょばいき)の蓋(ふた)の上の干欄式建築
下図の左は高さ17.5センチで、雲南省石寨山古墳出土。右は角度を変えて写したもの。
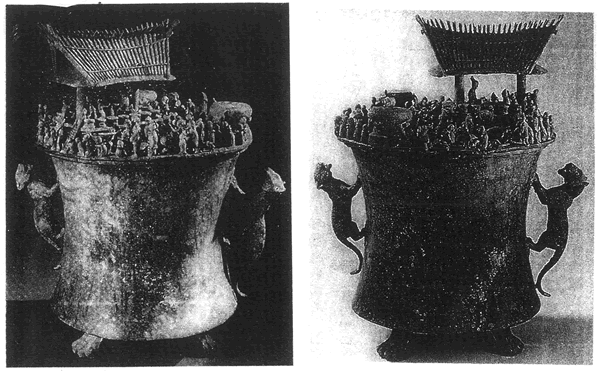
・中国石塞山遺跡と、わが国の弥生時代遺跡との共通点
(1)干欄式建築の建物が、表現されている。
(2)同タイプの前漢鏡「昭明鏡」が出土している。
中国の石塞山遺跡から、前漢時代の「昭明鏡」が出土しており、日本の弥生時代の立岩遺跡の甕棺から、同じように「昭明鏡」が出土している。
(3)ともに、銅剣・銅矛・銅戈が出土している。
日本の弥生時代の遺跡の甕棺から、同じように「細形銅剣・細形銅矛・細形銅戈」が出土している。
(4)ともに、金印蛇鈕の「滇王之印」と「漢委奴国王」の印とが出土している。
(下図はクリックすると大きくなります)
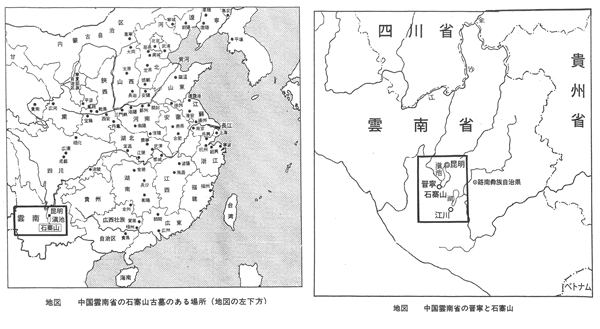
中国の長江(揚子江)の描く線の西の端と、東の延長上とに、かなり共通する文化がみとめられる。
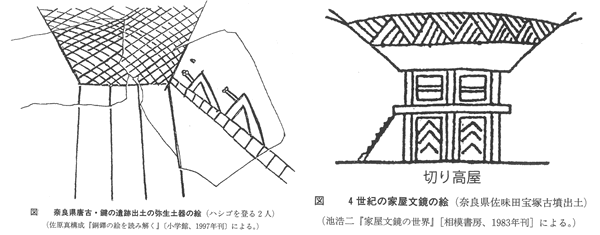
上図の左は奈良県唐古・鍵遺跡出土の弥生土器の絵(ハシゴを登る2人)、上図の右は奈良県左味田宝塚古墳出土の4世紀家屋文鏡の絵。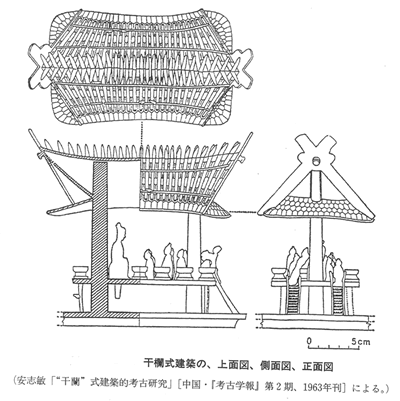
右の図は中国の干欄式建築の上面図、側面図、正面図[安志敏「”干欄”式建築的考古研究」(中国・『考古学報』第2期、1963年刊)による。]
b.鵜飼
■中国での鵜飼の分布
慶應義塾大学名誉教授の可児弘明(かにひろあき)氏の著書、『鵜飼』(中央公論社、中公新書、1966年刊)に、中国での鵜飼の分布図がのっている。
下の地図のようなものである。
この地図をみると、「干欄式建築」の青銅器の出土した雲南省昆明の近くの滇池(てんち)の付近も、鵜飼の分布域のなかにはいっていることがわかる。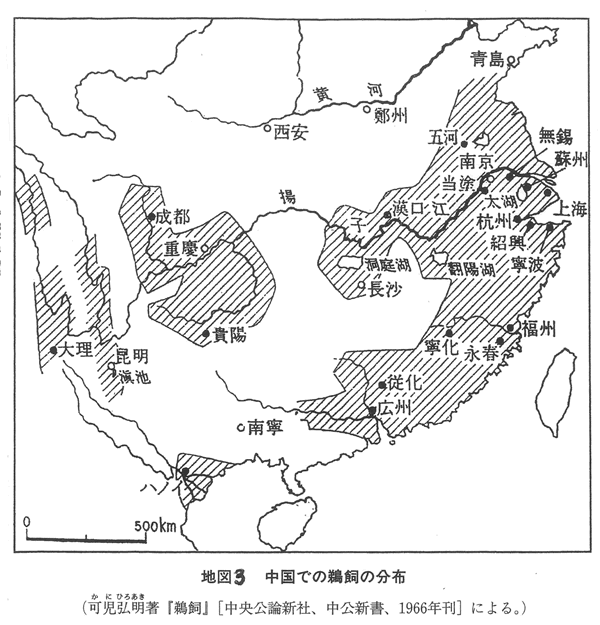
可児弘明氏は、『鵜飼』のなかでのべている。
「鵜飼の歴史的慣行地のひろがりは、原住民国家のうち楚の国と、それに文化的に密接な関係をもつ故地とよく合致している。楚の国は今の湖南、湖北に中心のあった国家であるが、戦国時代(前475~前221)、あるいはそれ以前における楚の文化は四川・雲南方面の土着文化と密接な関係をもち、さらに四川・雲南の土着文化は、広東・広西の土着文化とつながるからである。」
「中国で鵜飼にたずさわるのは、中国人ばかりでなく、中国西部の少数民族、たとえば口口族がある。
このことがわかったのは、1900年、雲南から金沙江(揚子江上流)をこえて四川に入った英人デービスが独立口口族の住む建昌渓谷を踏査し、ウをつれた漁夫の写真を記録してくれたおかげである。」
「華南と日本の稲作地帯にかぎってみると、鵜飼ががんらい、私たちにはまだ未知の、ある稲作民族の文化複合につながる可能性を強く予測することができるのである。」
石寨山ふきんの滇王国の文化のにない手はロロ族であろうといわれている。
かりに、「鵜飼」と「干欄式建物」とが、可児弘明氏のいう「ある稲作民族の文化複合」につながるものであるとしよう。すると、石寨山古墓は、前漢の初期から後漢の初期、つまり、紀元前202年ごろから紀元後100年ごろには、その文化複合が、蜀の地の石寨山ふきんまで、およんでいたことを示していることになる。
■わが国での鵜飼
山口県下関市の土井ヶ浜遺跡(どいがはまいせき)(弥生時代の前期・中期を主体)から、総数243体にのぼる遺存状態良好な弥生人骨が発見された。
そのなかに、鵜を抱いている女性の人骨が出土している(右写真参照)。鉄製品が、副葬されていた。
土井ヶ浜一帯には、現在でも、鵜が群れているということから、この鵜が、たまたま、とらえられたものか、鵜飼のために飼われていたものであるかは、わからない。
鵜は魚食の鳥なので、鵜そのものの肉はくさくて、食用に適さないという。
『古事記』の「神武天皇記」には、奈良県の吉野川の下流で、神武天皇軍が贄持(にえもつ)の子という国つ神と出あうが、この贄持の子は、鵜飼部(うかいべ)の祖先とされている。
また、『古事記』の「神武天皇記」には、神武天皇軍が「鵜飼で漁をする人々よ、助けに来てほしい」という歌もみえる。
『日本書記』では、「雄略天皇紀」の三年の条に、鵜飼の話がでてくる。
盧城部(いほきべ)の連(むらじ)の武彦(たけひこ)が、伊勢神宮に斎宮(いつきのみや)としてつかえていた栲幡(たくはた)の皇女(ひめみこ)と通じ、妊娠させたといいふらすものがいた。武彦の父の枳莒喩(きこゆ)は、わざわいが身におよぶことをおそれて、息子の武彦を鵜飼にさそい、三重県の雲出川(くもずがわ)のほとりで、急に打ち殺したという。
これは、五世紀後半ごろにおきた事件であろう。
また、六世紀ごろの須恵器に、鵜飼の塑像がみられる(下の写真と図を参照)。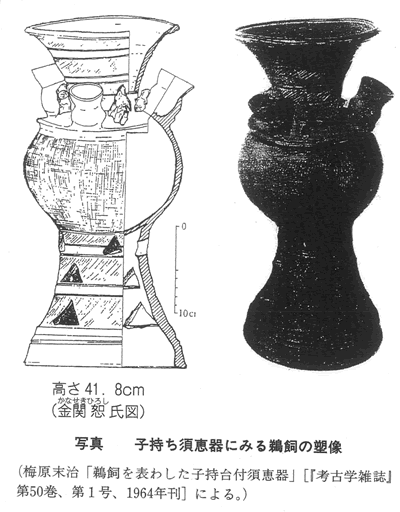
すなわち、岡山県邑久郡(おくぐん)国府の古墳から出土した須恵器の肩の部分に、三つの小さな小壺がはなればなれにつけられ、その小壺と小壺とのあいだの空間に、鵜飼をあらわす塑像がつけられている。
考古学者の梅原末治はのべている。
「今日の鵜狩に当る漁猟を表わしていることは甚だ明白」(『考古学雑誌』第五十巻、第一号、1964年刊)
さらに、『隋書』の「倭国伝」に、わが国の七世紀ごろの鵜飼のことを記した記事がみえる。
すなわち、つぎのような記事である。
「首に小さい輪をかけて、ひもをつけた鵜(う)を水にもぐらせて、魚を捕(と)らえさせる。一日に、百余匹もとる。[小環(しょうかん)をもって、鸕鷄(ろじ)のうじなに挂(か)け、水に入りて魚を捕(と)らえしめ、日に百余頭を得(う)。]」
八世紀成立の『万葉集』では、鵜飼のことが、かなり多く歌われている。
『万葉集』の4011番の歌で、越中の国(現在の富山県)の鵜飼たちのことが歌われている4156番にも、富山県の辟田(さきた)の川で、「鵜飼をする歌」がのっている。
4185番にも、「鮎が躍るころになったら、辟田川(さきたがわ)で、鵜をいっぱい使って川瀬を探って行こう。」という意味の歌がある。
4189番の歌にも、福井県の叔羅川(しくらがわ)の「早瀬で、鵜をもぐらせて」とある。
『万葉集』の、3330番の、「泊瀬川(はつせがわ)[奈良県]の、上の瀬で、鵜を八つもぐらせ、下の瀬で、鵜を八つもぐらせ、上の瀬の鮎を食わしめ、下の瀬の鮎をくわしめ」などの表現も、鵜飼にもとづくものであろう。
このようにみてくると、わが国では、古代から鴉飼がかなり行なわれたことがうかがわれる。
なお、可児弘明氏は、さきの『鵜飼』のなかで、「朝鮮半島に鵜飼がひろまった痕跡はみつからない」と記している。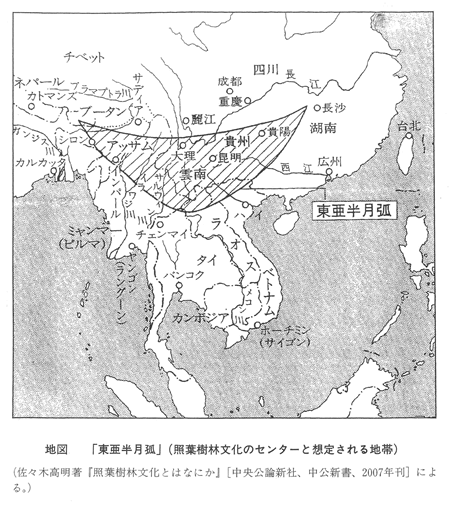
■照葉樹林文化と重なりあう
以上のようにみてくるとき、思いおこされるのは、「照葉樹林文化」という文化概念である。
照葉樹林というのは、カシ、シイ、クスノキ、ツバキ、サザンカなどを代表する常緑広葉樹を主とする樹林である。さきのような照葉樹では、葉が比較的厚く、テラテラとした光沢がある。
照葉樹林文化は、共通の文化的要素によって特徴づけられる。
イモ類、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀類の栽培、稲作、絹の製造などを大きな特徴とする。モチやナットウ、スシを食べ、絹や漆を利用する。麹で酒をつくり、高床の家にすむ。歌垣や鵜飼の習俗がある。
照葉樹林文化は、ヒマラヤ山麓から東南アジア北部山地、南中国、日本西部にかけての東アジアの温暖帯に分布する。
国立民族学博物館の館長などであった佐々木高明(ささきこうめい)は、その著『照葉樹林文化とは何か』(中央公論新社、中公新書、2007年刊)のなかで、「照葉樹林文化のセンターと想定される地帯」として、地図のような「東亜半月孤」を示している。
佐々木高明によれば、この「東亜半月孤」は、「雲南高地を中心に、ブータン・アッサムから中国の湖南省に至る。」という。上の地図をみれば、石寨山の近くの昆明などが、「東亜半月孤」の、ほぼ中心の位置にあることがわかる。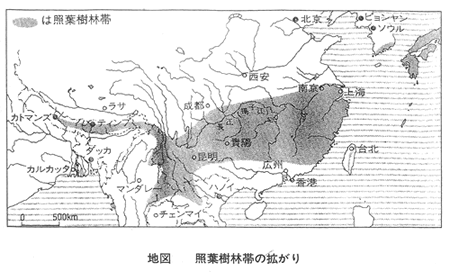
以上のようにみてくるとき、思いおこされるのは、「照葉樹林文化」という文化概念である。
佐々木高明は、また、同じ著書で、「照葉樹林帯の拡がり」として、右図のような地図も示している。
■『魏志倭人伝』の風俗記事が、南方的である
東京大学の民族学者、大林太良(たりょう)の労作『邪馬台国-入墨とポンチョと卑弥呼-』(中公新書)において、『魏志倭人伝』の風俗記事が、南方的であることを、ややくわしくのべている。『魏志倭人伝』には、わが国の、弥生時代後期の風俗習慣が記されている。大林太良は、「倭人の文化は《北方的》要素が少なく、圧倒的に《南方的》要素からなっていた」として、つぎのようにのべる。
「『魏志倭人伝』に描きだされた倭人の文化は圧倒的に南方的であって、中国南部から東南アジアにかけての文化、ことに江南の古文化と密接な親縁関係をもっている。」
「倭人伝に現れた服装が、採集狩猟民的な文化に遡る可能性は少なく、農耕とともに、おそらく弥生時代あるいは縄文後・晩期ごろから、中国の中・南部から入ってきたと考えるのがよいと思われる。」
「倭人の生活様式に関する記事の大部分は、華南から東南アジアに類例をもつものだ。このことは、すでに『魏志』を書いた陳寿自身が注目し、『有無する所、儋耳(たんじ)朱崖と同じ』と述べて、海南島との生物・文化の類似を強調している。」
「東夷伝の諸民族のなかで、倭人だけが著しく江南的・東南アジア的な習俗をもっていると描きだされている。」
大林太良は、「水中の動物からの危害を受けるのを防ぐ」という目的のために入墨をする習俗は、中国南部、ことに、江南の地を中心に、東は倭人から、西はラオスに至る地域に、ほぼ連続的に分布していること、貫頭衣、つまりポンチョ式の服装は、北方ユーラシア東部にはほとんど知られておらず、中国南部から東南アジアにかけての地域に多いこと、横幅衣も、東南アジア的な服装であること、などを指摘する。
■考古学者たちの見解と農学者・イネ学者たちの反論
以上みたように、わが国の弥生稲作文化と、中国の中・南部の長江流域系の文化との関連性は、かなり強いようにみえる。しかし考古学の分野では、このような見解に批判的な見解が根づよい。
奈良県の纒向学研究センター所長の考古学者寺沢薫氏は、その著『王権誕生』(講談社、2000年刊)のなかでのべる。
「日本列島にはイネの原生種は存在しない。
そこで、(中略)水田稲作の日本列島へ伝来ルートを整理すると、次のようになる。
Ⅰ華北から渤海(ぼっかい)湾の北をまわり、朝鮮半島を南下して伝来したとする「北回りルート」。
Ⅱ華中から朝鮮半島を経由して伝来したとする「半島ルート」。次の三つがある。
a.山東半島~遼東半島から朝鮮半島北部を経由するルート。
b.山東半島から朝鮮半島中部西岸を経由するルート。
c.長江下流域から黄海を越え、朝鮮半島南部西岸を経由するルート。
Ⅲ長江下流域から東海を越えての「直接伝来ルート」。
Ⅳ華南地方から南島経由で伝来したとする「海上の道ルート」。
このうちⅠとⅡはおもに考古学者が、ⅢとⅣはおもに農学者や民族(俗)学者が積極的に加担してきた説だ。だが最近の考古学的な成果は無視できないところまできているからだろうか、後者には多元ルートを主張する声が高まっている。しかし稲作の伝来を歴史的にみるとき、水田稲作の最初期の伝来ルートとその後のルート、また水稲以前のコメの伝来ルートは分けて考えなければならない。
縄文晩期後葉、玄界灘沿岸地域に最初に伝来した水田稲作が、おもに朝鮮半島南部から渡来した人々によってもたらされたことは間違いない。つまりⅡのルートだ。こと最初の水稲に関する限り、他のルートは可能性が薄いといってよかろう。
1999年、韓国忠清南道論山(ろんさん)市麻田里(までんり)遺跡と慶南道蔚山(いざん)市無去洞玉峴(むきょどうぎょくけん)遺跡で無文土器時代前期から中期にかけて(前8~前5世紀頃)の小区画の水田が発掘された。まさに列島の縄文晩期後半の水田の直前にあたるものだから、Ⅱのルー卜の決定的な証拠となった。また、菜畑遺跡や曲り田遺跡などで見られる磨製(ませい)石包丁、磨製石鎌、太形蛤刃石斧(はまぐりばせきふ)、扁平片刃石斧(へんぺいかたはせきふ)、抉入(えぐりい)り柱状片刃石斧(ちゅうじょうかたはせきふ)などの、いわゆる大陸系磨製石器といわれるものは、驚くほど朝鮮半島南部の無文土器文化前・中期の磨製石器群と似ている。とくに石包丁は外湾刃半月形(がいわんばはんげつけい)が圧倒し三角形や紡錘(ぼうすい)形もともなうこと、すり切り技法の有溝(ゆうこう)石包丁がめだつことなど、細部の形状や組成においても共通点をもっている。
さらに、朝鮮半島北部に比べて半島南部では石製の鍬や鋤がめだたないことから、北部九州のように木製の鍬や鋤が存在するのではないかと思われてきたが、1995年、栄山江上流の光州市新昌洞(しんしょうどう)遺跡で木製の又鍬(またぐわ)と直柄鍬(ちょくへいぐわ)が出土したことから、ますますⅡのルートは決定的なものとなった。」
「しかも、朝鮮半島出土のコメは日本列島同様、すべて短粒米(多くはジャポニカ種)といわれるコメで、新昌洞遺跡で見つかった炭化米はDNA分析でもジャポニカ種と太鼓判を押された。イネの品種でもⅡのルートは支持される。ちなみに、イネには大別二つの品種群がある。粘り気があり丸みをもった短粒米がジャポニカ、粒が細長く粘り気がなくパサついた長粒米がインディカと呼ばれる亜種である。少し年輩の方なら、内地米と外米と言ったほうがわかりやすいかもしれない。中国では、長江の流域を境に北に短粒米[中国では粳(ジン)という]、南に長粒米[籼(シアン)]が分布し、下流域一帯は両者の混在地帯とされてきた。それはイネの北上と時代が下るにつれて、短粒米を選択する方向に変化していった結果だととらえることができる。
また、朝鮮半島の遺跡からは弥生遺跡同様にコメだけでなく、オオムギ、アワ、ヒエ、モロコシ、マメ類などの畑雑穀がいたるところで出土していることも、朝鮮半島南部こそが弥生農業の直接の故郷だと断定する理由である。
寺沢薫氏はさらに、「直接伝来」説と、「海上の道」説とについてのべる。
「ここで、Ⅲの直接伝来ルートについて少しふれておこう。考古学者のなかには、外湾刃半月形(がいわんばはんげつけい)石包丁や、抉入(ええぐりい)り柱状片刃石斧(ちゅうじょうかたはせきふ)を、長江下流域に起源するものだと考える人もいる。たしかに、長江下流域にもこの型式のものはある。しかし、長江下流域の前一千年紀の湖熟(こじゅく)文化の石包丁には、外湾刃半月形のほかに、内湾刃半月形、舟形、長方形、翼形とじつに多様な形式があり、直接伝来したのであればこうした形式も一緒にもたらされるはずだが、北部九州では発見されていない。
また、湖熟文化の水稲農耕には、収穫具として多数の石鎌や貝製の鎌、耕作のための石犂(いしすき)や除草のための耘田(うんでん)器、そして青銅や鉄製の鎌、鋤(すき)、犂(すき)もすでに存在するけれど、そうした農具も北部九州には見られない。今のところ直接伝来説は、海流による伝来の容易さやイネの生育環境の類縁性、といった推察の域をでるものではない。
Ⅳの南島ルートにいたっては弥生時代にさかのぼる農耕の痕跡じたいがまったくない。もちろんコメもない。海上の道説も、南島に残る稲作文化の古い民俗的基層を、稲作伝来期の南島に求めようとする希望的観測の域をでないのだ。」
寺沢薫氏の本の影響であろうか。考古学者の橋口達也氏も、同趣旨の見解をのべる。
橋口達也氏はその著『甕棺と弥生時代年代論』(雄山閣、2005年刊)のなかで、上のように記す。
しかし、わが国の稲作複合文化が、おもに朝鮮半島から来たとするならば「干欄式建築」や鵜飼などは、どのようなルートをへて、日本に来たことになるのであろうか。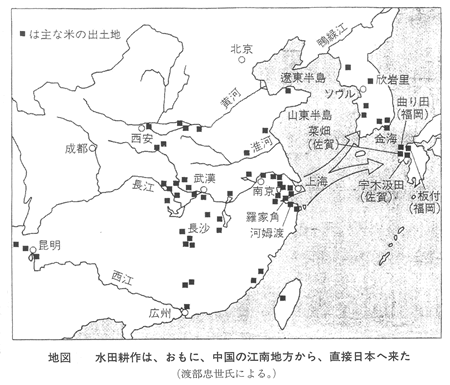
これらのものは、朝鮮半島においては、まずみられない。すくなくともポピュラーとはいえない。
寺沢薫氏は朝鮮半島南部の遺跡からの出土物についてろんじられるが、これは放送大学の渡辺忠世氏が寺沢薫氏以前に主張しておられる「韓国南部と九州北部へほぼ同じ時期に到着したと考えられても誤りはないのではなかろうか」「わが国と韓国と南部にはいずれからいずれに伝えたいというのではないように思われる」という説を、十分に論破しておられるようには思えない。
■稲作は、江南から直接来たとする説
稲作、とくに水田耕作が、もっぱら中国の江南地方から、対馬海流にのって直接日本に来た、とする考えをのべている人は、樋口隆康氏、渡部忠世氏、松尾孝嶺、安藤広太郎などかならずしもすくなくない。
放送大学の渡部忠世教授はつぎのようにのべる。
「稲作が、江南から直接日本、特に九州地方へ渡来したとする説は、多くの農学者も支持するところである。その大きなよりどころとなっている研究に、松尾孝嶺(まつおたかね)の『栽培稲に関する種生態学的研究』の成果がある。アジア各地に栽培される六百六十六品種を供試して、精密に形態、生態、生理的分類を行なったところ、日本の水稲に最も近似する品種は(朝鮮半島のものよりも)華中のジャポユカの一群であることなどが証明されている。
さらに雑草学者の笠原安夫の研究なども興味深い。岡山市津島(つしま)遺跡の水田址で検出された雑草種子八十九種は、東南アジアから華中にかけて分布する雑草が大半で、長江以北には見られないものが多いという。水田の雑草を稲の隨伴物とみる限り、このことも江南地方以南からの渡来を主張するひとつの根拠となりうるだろう。
朝鮮半島を経由したとする考えは、考古学者のなかに支持の多い説といわれている。しかし、陸路を揚子江流域から遼東(りょうとう)半島に至って鴨緑江(おうりょくこう)を渡り、文字どおりに半島を南下したとは、農学者や植物学者にとっては容易に賛同し難い推理であろう。遼東半島付近は北緯四〇度、盛岡よりも北である。
日本に渡来した稲がしだいに東方に移り、やがて北上して津軽地方にまで割合と早くに達したともいわれるが、東北の稲作史を正確に調べれば、陸奥(むつ)や陸中(りくちゅう)に比較的安定した稲作が確立するのは十六世紀も末の頃と考えてよかろう。
稲は長い年数をかけて次第に寒さなどへの適応を重ねた事実を考え合わせると、この経路がわが国に稲を伝えた古い道であったとはにわかに首肯(しゅこう)し難い。
半島を経由したケースとして考えられるのは、淮河(わいが)の周辺から黄海(こうかい)を渡り、今日の韓国南部から九州に達した伝播経路であろう。有名な釜山(ふざん)近郊の金海(きんかい)貝塚から出土した炭化米の存在がそのことを証明しているといえよう。しかし、このような場合に、これを朝鮮半島を経由して日本に達したと解釈する必要はないであろう。韓国南部と九州北部へほぼ同じ時期に到着したと考えても誤りはないのではなかろうか。かつて、安藤広太郎が『わが国の稲作は韓国南部とほぼ同じ時代に双方において始まり、わが国と韓国南部との間にはいずれからいずれに伝えたというのではないように思われる。』という説に、私も同意したい。」(「イネはどこからきたか--雲南と江南を経た道のり」『最新日本文化起源論』学習研究社、1990年刊)
イネ学者池橋宏氏の寺沢薫氏らの説への反論
寺沢薫氏らの説は、大変断言的に決定的であるかのように述べられているが、寺沢薫氏、橋口達也氏らの本の刊行後、イネ学者で、京都大学の教授であった池橋宏氏が『稲作の起源-イネ学から考古学への挑戦-』(講談社、2005年刊)、『稲作渡来民-「日本人」成立の謎に迫る-』(講談社、2008年刊)などの著書で、寺沢薫氏、橋口達也氏などへの、批判的に、反論的意見を述べておられる。
池橋宏氏はくわしい根拠をあげて、結論的に記す。
「新しい資料をもりこんで書かれた寺沢薫(2000)の著書でも、朝鮮半島から出土するコメは日本型であるから、長粒種(秈)があるはずの長江流域からの直接伝来や華南からの伝来は支持されないと述べている。
しかし、そのような論議は今では通用しない。華南の広西の4000年前の遺跡から今日の日本型と同じようなコメが発見されたことは図(ここでは省略)でも示した。江南でインド型の長粒のコメが優占的になったのは、(中略) 時代を下って宋以降(11世紀)のことであり、稲作の起源地では、野生イネは長粒であって、長粒から短粒種の方へ混在しながら数千年かけて変化していたのである。
したがって、江南から短粒の日本型のイネが伝来しても何も不思議ではない。」(『稲作の起源』
「新しい資料をもりこんで書かれた考古学者の寺沢董(てらさわかおる)の本でも、朝鮮半島から出土するコメは日本型であるから、長粒種(秈)があるはずの長江流域からの直接渡来や華南からの渡来は支持されないとしてある。日本への稲作の導入について論じた考古学者の橋口達也(はしぐちたつや)も、コメの粒の形を稲作の伝来ルートの証拠と考えている。すなわち、日本の弥生早期の遺跡では短粒米が栽培されていた。韓国でも欣岩里(ふなむり)や松菊里などの遺跡から短粒米が出土した。これらは日本型のコメであり、したがって日本への稲作は朝鮮半島西・南部を経て、北部九州へ来た。従来主張された江南ルートから来たとすれば、日本型とインド型の両者が混在するはずであるが、実際にはインド型はない。だから仰韶文化期から龍山文化期をへて長江流域から華北へ行って、寒冷地にも適するようになった稲作が日本へ渡来したと述べている。」(『稲作渡来民』)
「先に述べた稲の粒型や陸稲についての誤った見解も関係して、朝鮮半島の農耕が稲作も含めて北から南に伝播したという考え方がある。先にあげた国分直一の陸稲に注目したイネの伝来の考え方もある。また寺沢董の著書では。朝鮮半島の中南部でも、畠作の雑穀・稲作栽培があって、それが日本の水稲伝来以前の農耕のもとになったと考えられている。こうした考え方は、『縄文稲作』を説明するために出てきたものであるが、その証拠は十分とはいえない。」(『稲作渡来民』)
池橋宏氏は、また、笠原安夫の「雑草の歴史」(沼田真編『雑草の科学』[研究者、1979年刊]所収)により、下表のようなデータを紹介したうえで、『稲作の起源』のなかででのべる。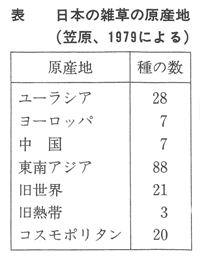
「根栽農耕や水田農耕を通じて、日本が華南からインドシナ半島までと深いつながりをもっていることが、あらためて理解される。」
そして、池橋宏氏は、自説をまとめた部分の文章のなかで、つぎのようにのべている。
「長江中・下流域で長い年月をかけて工夫された漁撈と水田農耕を営む人々が、戦国時代末期から、越の滅亡などの社会的動乱のなかで新たな活路を求めて、東や南に移動したという歴史の背景を説明した。
民俗学者は古くからその見方を支持していたのに対し、考古学者は朝鮮半島からの文物の伝来を重視してきたが、後者は稲作民の移動の背景の説明がかならずしも一貫しない。それには『短粒のコメが長江流域から伝来しないはずである』という誤解も関係したことを指摘した。」
「越で発達した水田稲作が漁撈をともなう効率の高いものであり、それが朝鮮半島南部を経由して九州に伝来して、弥生時代の幕を開け、交通の不便な古代にあっても、それが急速に日本各地に普及した。」
「水田稲作が単なる灌漑農地ではなく、農耕の施設として、高い生産力を示したことが注目される。イネは当初から水田で栽培化され、水田および漁撈は一体として伝来したという本書の見方の方が、『稲作の焼畑起源説』よりも、筋の通った説明を与えられたのではないだろうか。また、古代のイネの栽培で直播き栽培が確認できないということは、イネは水田で苗代と田植えと一体となって起源したとする本書での主張とも両立する。」
池橋氏は、別著『稲作渡来民』(講談社、2008年刊)のなかでものべている。
「一つの鍵は中国の史書に現れる『倭』という集団がどこにいたかという問題である。三世紀ごろまでの『倭』は、朝鮮半島南部と九州北部にいた稲作民を指しているのではないかという可能性は検討に値する。」
■朝鮮半島南部にも、北九州にも、倭人が住んでいた
私は、朝鮮半島南部と北九州とで共通の遺跡・遺物がみられるのは、おもに、北九州から朝鮮半島南部に渡ったものとも考えないし、逆に、おもに、朝鮮半島南部から、北九州に渡ったものとも考えない。
朝鮮半島の南部にも、北九州にも、もともと、日本語の祖先となる言語を用いていた「原倭人」が住んでいたのであり、朝鮮半島と北九州とに、共通の遺跡・遺物を残したのは、おもに、その原倭人たちであったと考える。
そして、私は、この、韓国南部と九州北部の、ほぼ同時期に稲作のもたらされた地域、あるいは稲作をうけいれた地域こそが、倭人発生の地域とみる。
朝鮮半島の南部には、かなりあとの時代まで、倭人が住んでいたとみられる。
『三国志』の『魏志』の「東夷伝」の「韓条」に、つぎのような文がある。
「韓は、帯方(郡)の南にあり。東西は海をもって限りとなし、南は、倭と接す。」「その(弁辰の)瀆慮(とくろ)国は倭と界を接す。」
この文は、韓が、南は、海をへだててではなく、陸つづきで、倭と接していたと、読みとれる文である。
つまり、朝鮮半島南部に倭人が住んでいたことを示しているとみられる。
朝鮮史学者の井上秀雄の手になる『古代朝鮮』(日本放送出版協会刊)にかかげられている地図でも、金海あたりに倭がいたことになっている。
この、韓国南部と九州北部の、ほぼ同時期に稲作のもたらされた地域、あるいは稲作をうけいれた地域こそが、「倭人」のいた地域とみられる。なお、金海貝塚から出土した炭化した米粒は、紀元後一世紀ごろのものとみられている。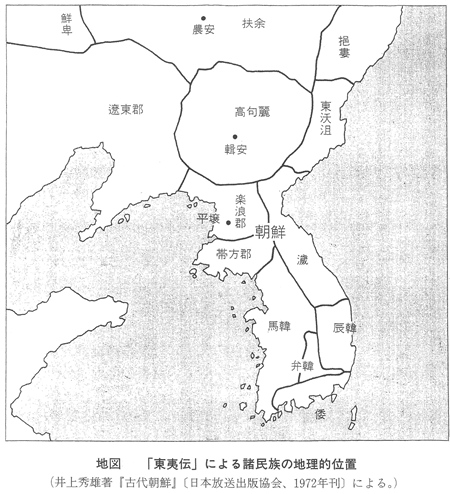
朝鮮半島南部の倭の勢力は、562年の任那の滅亡などの過程をへて、朝鮮半島から消えて行く。
「南船北馬」ということばがある。中国の南では、船が発達していた。
中国の江南の民のなかには、たまたま、朝鮮の南部や、北九州に漂着したものがおり、数千年のあいだには、往復の方法を見いだしたものもいたのであろう。
数千年のあいだには、さまざまなルートで稲がはいってくることがあったであろうが、メインになったのは、江南から直接きたルートであったようである。
外来の民族で、現代の日本民族や日本文化の形成に、もっとも古くもっとも大きな影響をもたらしたのは、北方騎馬民族ではなく、南方就船民族であったようにみえる。考古学関係の方のなかには、稲作や弥生文化の到来は、主として朝鮮半島ルートによるものとし、中国の揚子江流域文化や中国南部、さらには、インドシナ半島(ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、ミャンマーなど)との関連を、ほとんど無視する見解がある。
しかし、わが国の言語や文化において、揚子江流域以南の言語や文化の影響は、あきらかにみとめられる。
それを無視、または、軽視することはできない。
考古学関係の方は、ともかく、考古学至上主義の警告がある。考古学関係の人が書いた本や論文だけを読み、他の分野の研究者の書いた本や論文をあまり読まない。参考にしない傾向がある。「考古学的には、これが正しいのです」式の断定、速断をし、その断定によって説明できないことがらを無視する傾向がある。残念なことである。