■基礎データ
神武天皇から桓武天皇まで、天皇の践祚(せんそ)と即位と退位した年を示した票を下記に示す。
(下図はクリックすると大きくなります)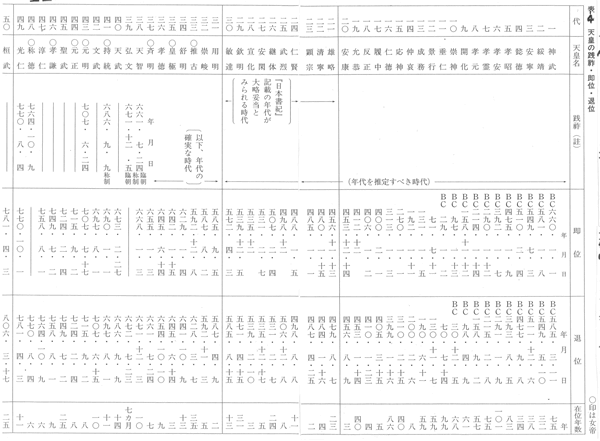
践祚(せんそ)と即位のちがい。
「践祚」は、天皇の世継ぎが、天皇の地位につくことをいう。はじめは、「即位」と同じ意味であった。
平安時代になって、「践祚」と「即位」との意味がわかれた。「践祚」は、神璽(しんじ)をうけて、天皇の地位につくこと、「即位」は、そのことを、天下に公布する儀式をさすこととなった。つまり、「即位」は、即位式または即位礼のことをいうようになった。
今上天皇の即位式は、盛大に行なわれたが、過去には、皇室財政窮乏のため、なかなか即位式の行なえない時代もあった。室町時代の第104代後柏原天皇は、践祚後21年目に即位式をあげ、第105代後奈良天皇は、践祚後10年目に即位式をあげた。即位後の大嘗祭も、後柏原天皇から、江戸時代の霊元天皇まで行なわれなかった。
また、上代においては、まえの天皇が死去したばあい、践祚までに、二~三ヵ月から一年、ときには数年にわたる期間のあることがあった。
即位をとるのか、践祚をとるのか、いろいろな考え方がある。
そして、用明天皇からが、『日本書紀』の年代が確実となると考えられる。
統治する王の在位年数を求めると、下記の表となる。
在位年数が長い王はルイ14世の74年のように70年を超えるが、平均すると10年位になる。
(下図はクリックすると大きくなります)
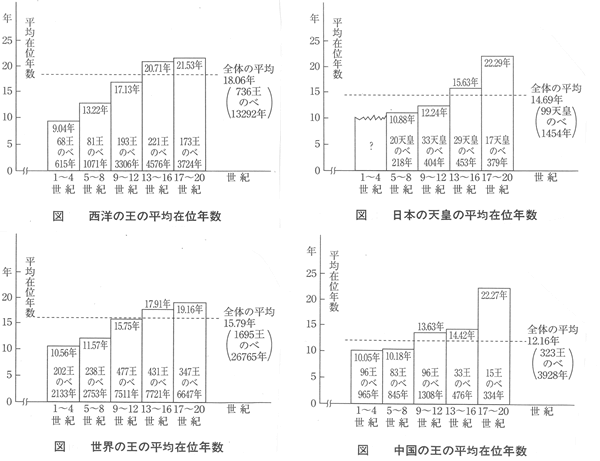
(i)『日本書紀』の年代論
■日本で最初の年代論を論じたのが、『日本書紀』の編纂者
その当時に『古事記』があり、もう一方に中国や朝鮮の歴史書があった。
そこで、日本側の伝承から、古代で外国まで名をとどろかせた女性がいた。それは神功皇后である。また一方で中国の文献から魏志倭人伝の卑弥呼が存在していた。そこで『日本書紀』の編纂者は卑弥呼=神功皇后と考えた。
更に辛酉革命(しんゆうかくめい)説から、紀元前660年に神武天皇が即位したと考えた。
これを、天皇1代の在位年数のグラフにまとめると、下記のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
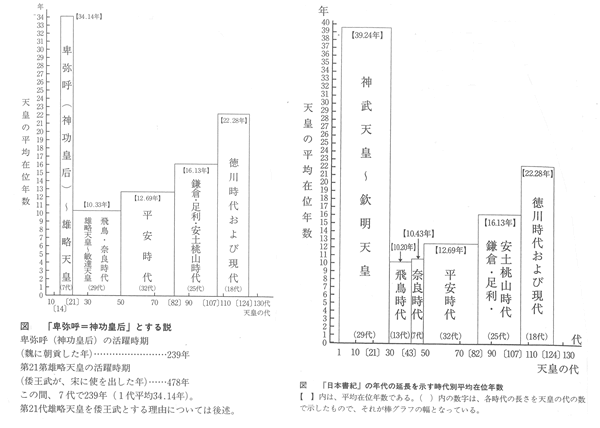
この結果からも分かるように、古代の天皇の在位年数が非常に長くなる。前に示した世界の王の在位年数からもかけ離れている。
(ⅱ)那珂通世の年代論
那珂通世は人名事典では下記となっている。
【那珂通世】(1851-1908)
明治時代の東洋史学者。嘉永4年1月6日生まれ。藤村操の叔父。陸奥盛岡藩士の子。那珂通高[梧楼(ごろう)]の養子となる。千葉師範校長などをつとめ、明治27年高等師範教授。日本で最初に「東洋史」の名称をつかい、日本の紀元問題の研究でも知られる。明治41年3月2日死去。58歳。慶応義塾卒。本姓は藤村。著作に「支那通史」「那珂東洋小史」、訳注書に「成吉思汗実録」など。
■藤貞幹(とうていかん)と那珂通世の600年~660年延長説
『日本書紀』の紀年に、延長のあることを、もっとも早く、はっきりとのべたのは、江戸時代の藤貞幹[藤原貞幹(ふじわらていかん)、1732~1797]である。
藤貞幹は、その著「衝口発(しょこうはつ)」のなかで、つぎのようにのべる。
「(『日本書紀』の神武天皇元年の年代は、)六百年減ぜざれば、三国(中国・朝鮮・日本)の年紀符合せず。」
約600年、年代がくりあげられているというのである。
明治になって、東洋史学者の那珂通世(なかみちよ)[1851~1908]が、上古年代考(『洋々社談』第三十八号、1878年)、「日本上代年代考」[『文』(『文』は、金港堂刊の週刊雑誌)、第一巻、第八、第九号、1888年]、「上世年代考」(『史学雑誌』第八編第八、九、十、十二号、1897年)などを発表し、くわしく根拠をあげ、神武天皇の即位年は、キリスト紀元(西暦元年)とそれほど距(へだた)っていないであろう、と論じた。なお、『日本書紀』は、神武天皇が、西暦紀元前の660年にあたる年に即位したことを記す。そして、西暦元年は、たまたま、辛酉の年である。
つまり、那珂通世は、『日本書紀』の神武紀元は、660年ほど年代の延長があり、660年ほど下にくりさげるべきであると論じたのである。
-----------------
コラムⅠ 世数と代数
古代の天皇の活躍年代(あるいは、即位年代、在位年代など)を推定しようとするばあい、天皇の「代数」を基本的な変数(独立変数)と考える立場と、天皇の「世数」を基本的な変数と考える立場とがある。
たとえば、系図のようなばあい、第二十四代仁賢天皇は、第十六代仁徳天皇から数えて「八代目の天皇である。しかし、世数からいえば、「三世目」の天皇である。「世数」では、親子関係によって、何世目かを数えるわけである。
系図 「世数」と「代数」のちがいを示すための例
(16)仁徳天皇-(17)履中天皇- 市辺押磐皇子-(24)仁賢天皇
l └(23)顕宗天皇
┠(18)反正天皇
l ╓ (20)安康天皇
└(19)允恭天皇 -(21)雄略天皇-(22)清寧天皇
(16)、(17)・・・・・は天皇の代数
-----------------
すでに、慶応大学の教授であった橋本増吉は、大著『東洋史上よりみたる日本上古史研究』(東洋文庫、1956年刊)のなかで、つぎのようにのべている。
「父子直系のばあいの一世平均年数が、ほぼ二十五、六年ないし三十年前後であることは、那珂博士の論じられたとおりであろうけれども、わが上代のおよその紀年を知るために必要なのは、父子直系の一世平均年数ではなく、歴代天皇のご在位年数なのであるから、那珂博士算出の平均一世年数をもって、ただちに上代の諸天皇の御在位平均年数として利用すべきでないことは、明白なところである。」
また、あとで紹介する笠井新也は、つぎのようにのべている。これは、世代数に対する疑問をのべたもので、那珂通世の議論の、基本的前提じたいを否定しているものである。
「わが国の古代における皇位継承の状態を観察すると、神武天皇から仁徳天皇にいたるまでの十六代の間は、ほとんど全部父から子へ、子から孫へと垂直的に継承されたことになっている。
しかし、このようなことは、私の大いに疑問とするところである。なぜならば、わが国において史実が正確に記載し始められた仁徳以後の歴史、とくに奈良朝以前の時代においては、皇位は、多くのばあい、兄から弟へ、弟からつぎの弟へと、水平的に伝えられているからである、かの仁徳天皇の三皇子が、履中(りちゅう)・反正(はんぜい)・允恭(いんぎょう)と順次水平に皇位を伝え、継体天皇の三皇子が、安閑(あんかん)・宣化(せんか)・欽明(きんめい)と同じく水平に伝え、欽明天皇の三皇子・一皇女の四兄弟妹が、敏達(びたつ)・用明・崇峻(すしゅん)・推古と同じく水平に伝えたがごときは、その著しい例である。
したがって、この事実を基礎として考えるときは、仁徳天皇以前における継承が、単純に、ほとんど一直線に垂下したものとは、容易に信じがたいのである。
(下図はクリックすると大きくなります)
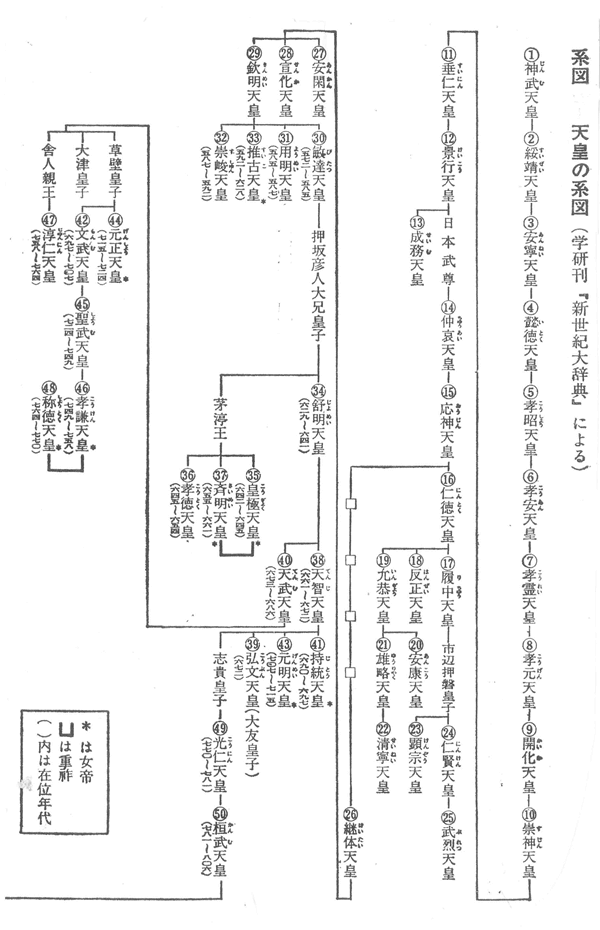
山路愛山(やまじあいざん)は、その力作『日本国史草稿』において、このことに論及し、『直系の親子が縦の線のごとく相次いで世をうけるのは、中国式であって、古(いにしえ)の日本式ではない』。それは、『信ずべき歴史が日本に始った履中天皇以後の皇位継承の例を見ればすぐわかる』『仁徳天皇から天武天皇まで通計二十三例のあいだに、父から子、子から孫と三代のあいだ、直系で縦線に皇位の伝った中国式のものは一つもなく、たいてい同母の兄弟、時としては異母の兄弟のあいだに横線に伝って行く』『もし父子あいつづいて縦に世系の伝って行く中国式が古(いにしえ)の皇位継承の例ならば、信ずべき歴史が始ってからの二十三帝が、ことごとくその様式に従わないのは、誠に異常なことと言わなければならない。ゆえに私達は、信ずべき歴史の始まらないまえの諸帝も、やはり歴史後と同じく、多くは同母兄弟をもって皇位を継承してであろうと信ずる』と喝破(かっぱ)しているのは傾聴すべきである。」[「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫命」『考古学雑誌』第十四巻、第七号、1924年(大正13年)4月、所収]
■年代論における「類ハッブル定律現象」について
京都大学人文科学研究所の教授であった尾崎雄二郎氏は、私の編集していた『季刊邪馬台国』14号(1982年)に、「古代里程記事における類「ハッブル定律現象について」という文章を発表しておられる。
その要点は、つぎのようなものである。
「天文学で、地球から離れているほど、星雲の遠ざかる速度も大きいという『ハッブルの定律』がある。
昔の人にとっては、都から離れるほど、その里程は、感覚的にふえていくものらしい。古代の里程記事においては、類ハッブル現象が見られるのではないか。」
都から遠く離れた場所は、遠いほど、実際の里程以上に、大きく離れているように、認識される。そして、そのように記載されがちであるというのである。
これは、尾崎雄二郎氏が、邪馬台国の里程記事に関連して、中国文献のいろいろな事例などをあげて論じられたものである。
尾崎雄二郎氏はのべる。
「自分の故郷というかホームグラウンドというか、とにかくベースになるものから離れれば離れるほど何らかの比例で主観的な距離はふえていくのではないか。山の高さも、それが高ければ高いだけ、われわれの普通の生活平面から遠ざかるわけですから、その分だけ、実際の差を超える差が加わっていくのではないか、と思うのです。」
ところで、距離についていえるこのような傾向は、また、「年代」についてもいえるようである。
古い時代のことは、客観的な年代よりも、さらに古めに認識されがちのようである。
『日本書紀』の記す古代の年代は、大はばに延長されている。年代が、事実よりも、古めに記載されている傾向がある。このことは、すでに、多くの人が論じているとおりである。
このような傾向は、わが国の史書ばかりではない。『三国史記』などの韓国の史書でも、また、みとめられる。
そのことは、明治時代の東洋史学者の那珂通世(なかみちよ)が、その著『上世年紀考』のなかで、つぎのようにのべているとおりである。
「韓史も上代に遡(さかのぼ)るにしたがい、年暦の延長せりと覚しきところあることは、ほとんど我が古史に異ならず。」
『三国史記』の「新羅本記」は、倭国の女王、卑弥乎(呼)のことを、西暦173年にあたる条のところで記すなどしている。
このような傾向は、現代人の心にも、無意識のうちに強く慟いているようである。
旧石器捏造事件のおりは、五十万年、七十万年と、年代がくりあがっていっても、専門家も、ふしぎと思わなかった。
(ⅲ)辛酉革命(しんゆうかくめい)説
西暦712年に成立した『古事記』は、歴代の天皇について記す。そこでは、第一代の天皇は、「神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)[神武天皇]で、そのつぎは、第二代の天皇である神沼河耳命(かむぬかわみみのみこと)[綏靖(すいぜい)天皇]になっている。そのつぎは、第三代の天皇である師木津日子玉手見命(しきつひこたまでみのみこと)[安寧(あんねい)天皇]になっている。このような歴代の天皇のことなどを、つぎつぎと記している(「コラムⅡ漢風謚号と和風謚号」参照)。
しかし、神倭伊波礼毘古命が、いつごろの人であるかについては、記していない。
これに対し、西暦720年に成立した『日本書紀』は、たとえば、第一代の神日本磐余彦天皇(かむやまといわれびこのすめらみこと)[神武天皇]は、西暦紀元前の660年にあたる年の1月1日に、大和の橿原(かしわら)の宮で、天皇位についたことを記す。
(コラムⅢ参照)。
また、第二代の神渟名川耳天白王(かむぬかわみみのすめらみこと)[綏靖天皇]は、西暦紀元前の581年にあたる年の1月8日に天皇位についたことを記す。
-----------------
コラムⅡ 漢風謚号(かんふうしごう)と和風謚号(わふうしごう)
「神武天皇」「綏靖天皇」「安寧天皇」……などの天皇のよび方を、「漢風謚号」という。中国風のよび方という意味である。天皇の死後におくられた称号である。
これに対し、「神倭伊波社毘古命(かむやまといわれびこのみこと)」(『古事記』の表記法。『日本書記』は、「神日本磐余彦天皇」以下同し)、
「神沼河耳命(かむぬかわみみのみこと)」[神渟名川耳天皇(かむぬなかわみみのすめらみこと)]、「師木津日子玉手見命(しきつひこたまでみのみこと)」[磯城津彦玉手看天皇(しきつひこたまでみのすめらみこと)]などのよび方を、「和風謚号」という。日本風のよび方という意味である。
『古事記』『日本書紀』の成立時には、和風謚号のみが記されていた。漢風謚号は、記されていなかった。
古代の歴代の天皇に、漢風謚号をおくったのは、『釈日本紀(しゃくにほんぎ)(『日本書紀』の最初のまとまった注釈書)の記事などにより、奈良時代に文章博士となった、淡海三船(722~785)であるとみられている。
漢風謚号は、だいたいその天皇の事績にちなんでいるとみられている。
たとえば、「推古天皇」の「推古」つまり「古を考える」は、推古天皇の時代に、歴史書の編纂が行なわれたことによるとみられる。
「継体天皇」の「継体」つまり「体を継ぐ」は、とだえそうになった皇室の体制を継いだことによるとみられる。
-----------------
以下、『日本書紀』は、歴代の天皇について、その即位の年や退位の年(没年)などを記す。
初期の諸天皇について、もともとは、『古事記』のように、どの天皇のつぎがどの天皇で、そのつぎはどの天皇であるかの「順」は伝えるが、即位の「年」などは、伝えられていなかったとみられる。それが、古い所伝であった。
神武天皇が、いつごろの人であったかなどについては、伝えられていなかったとみられる。
中国の史書の体裁にならい、各天皇が、いつごろの人であったかなどを記入していったのは、『日本書紀』の編纂者であったとみられる。
『日本書紀』が、神武天皇の即位の年と定めた西暦紀元前660年は、「干支による紀年法」では、「辛酉(しんゆう)の年」にあたる(「干支による紀年法」については、コラムⅣ参昭)。
-----------------
コラムⅢ 「建国記念の日」の起源
『日本書紀』は、西暦紀元前660年の1月1日に、神武天皇は、大和の橿原の宮で、即位したと記す。
この「1月1日」は、中国からうけいれた「儀鳳暦」という暦にもとづいて記されている。
ところが、この「儀鳳暦」は、中国では、西暦665年から使用されるようになった暦である。紀元前660年には、中国でも、「儀鳳暦」は、使用されていない。神武天皇が、紀元前の660年に即位したという記事などは、『日本書紀』編纂のさいに、編纂時にわが国でも用いられていた「儀鳳暦」によって定めたとみられる(下図参照)。
この「1月1日」を、現代のグレゴリオ暦に換算すると、「2月11日」となる。
1872年(明治5)に、『日本書紀』の記す神武天皇の即位の日を、祝日と定め、「紀元節(きげんせつ)」とした。
第二次大戦後の1966年に、紀元節の日を「建国記念の日」という形で復活させた。
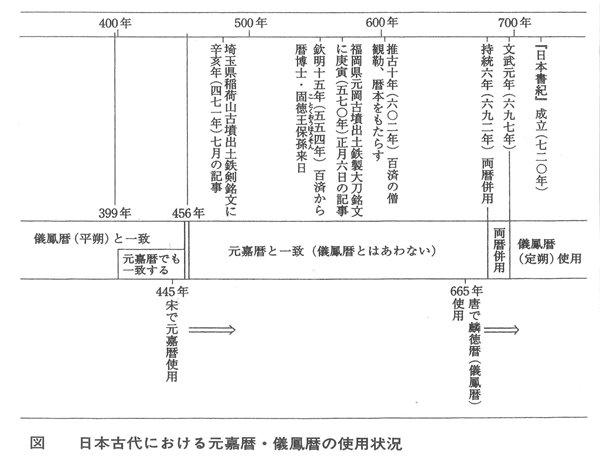
-----------------
神武天皇の即位の年を、「辛酉の年」にしたのは、中国の予言説である讖緯説(しんいせつ)にもとづくものとする東洋史学者、那珂通世などの「辛酉革命説」がある。
「辛酉革命説」によれば、1260年または、1320年ごとの辛酉の年に、大きな革命(大変革)があると考えられる。そこで、推古天皇9年(601)の辛酉の年から1260年、または、天智天皇の即位の辛酉の年(661)から1260年さかのぼった西暦紀元前660年の辛酉の年を、『日本書紀』編纂者たちは、大変革のあった年であるとして、神武天皇の元年に定めたのであるとする。
-----------------
コラムⅣ 干支(かんし)による紀年法
まず十干と十二支についてのべる。
十干とは、次のようなものをさす。
甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
これを、中国の原子論、五行説の五元素(これは、五つの遊星とも対応する)
木、火、土、金、水
に配して、おのおの陽すなわち兄と、陰すなわち弟とにわけた。すなわち、
甲 きのえ 本の兄 乙 きのと 木の弟
丙 ひのえ 火の兄 丁 ひのと 火の弟
戊 つちのえ 土の兄 己 つちのと 土の弟
庚 かのえ 金の兄 辛 かのと 金の弟
壬 みずのえ 水の兄 癸 みずのと 水の弟
と名づけた。
また、十二支とは、
子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
をさす。これは、ふつう
ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い
とよばれている。
(十二支)子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子牛寅……
(十 干)甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲乙丙丁戊……
干支による紀年法では、いま、最初の年を甲子(きのえね)の年とすれば、翌年は、乙丑(きのとうし)の年となる。その翌年は丙寅(かのととら)の年である。
このような組みあわせを一回行なうと、とうぜん、十干のほうは終わってしまっても、十二支のほうは二つあまる。そこで、十干をもう一度はじめからくりかえして組みあわせていく。十二支のほうも終わりまでくれば、またはじめからくりかえす。同じようにしてつづけていくと、十と十二の最小公倍数である六十年目で、いちばんはじめの甲子の年がもどってくる。
なお、干支による紀年法は、中国の戦国時代(紀元前476年~紀元前221年ごろ)にはじまったものらしく、殷の時代にはない。殷代には、年は、何何王の何年というように記されていた。ただ、殷代には、日々に六十干支(表)をふっていく記日の方法はあった。
干支のよみかたは、たとえば、丙午「ひのえうま」という仮の訓でよむよりも、「へいご」と音でよむほうがよいと思われる。しかし、ここでは、いちおう仮の訓でよんでおいた。なお、干支は、方角や時の名前としても用いられる。たとえば、北を子、南を午としたので、現在でも南北の線を子午線とよんでいる。
なお、暦のばあい、「乙」は、ふつう、「いつ」とよむ。たとえば、645年、「乙巳(いっし)の年」に、中大兄の皇子と中臣の鎌足とによって、蘇我の入鹿が誅滅される、大化の改新がはじまる。645年のときの変事を、「乙巳(いっし)の変」という。「乙巳(おつし)の変」とはいわない。
また、「甲子」は、「こうし」とも、「かっし」ともよむ。
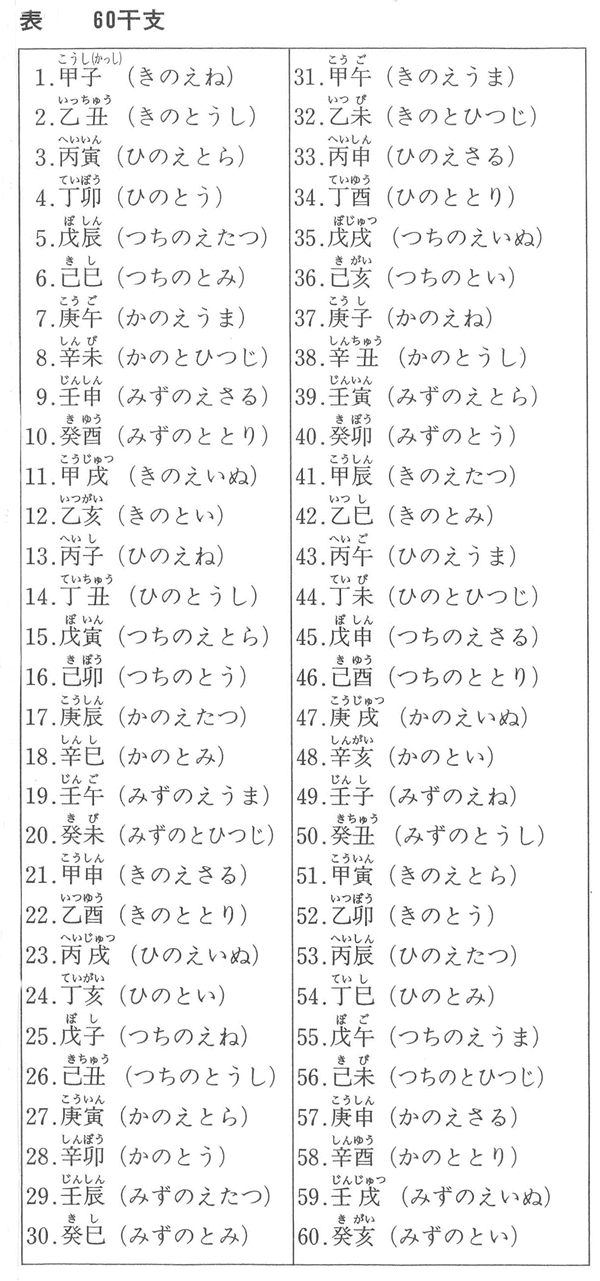
-----------------
(ⅳ)笠井新也(かさいしんや)の年代論
笠井新也は人名事典では下記となっている。
【笠井新也】1884~1956。考古学。徳島県立脇町中学校教諭。
1884年(明治17)6月22日、徳島県美馬郡脇町に生まれる。徳島県立脇町中学校を経て、1906年、国学院大学高等師範部卒業。徳島県立徳島高等女学校教諭。08年、徳島県女子師範学校教諭。11年、長野県立上田中学校教諭。12年(大正元)、大阪府池田師範学校教諭。15年、同退職。東京帝国大学人類学教室聴講生となり、鳥居龍蔵に考古学、人類学を学ぶ。19年、徳島県立脇町中学校教諭。33年(昭和8)、同教頭。39年、同退職。1956年(昭和31)1月10日没、71歳。邪馬台国大和説を唱えたことで知られる。
笠井新也は、那珂通世の年代論をうけつぎ、はじめて「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」「箸墓=卑弥呼の墓説」をうちたて、「邪馬台国=大和説」を、大きく前進させた。
■笠井新也の所説
那珂通世の所説を、大きくはうけいれながら、年代論をあらたに発展させたのは、笠井新也(1884~1956)である。笠井新也は、大正時代から昭和のはじめごろにかけて活躍した。
笠井新也の「邪馬台国畿内説」は、現在でも畿内説にたつ邪馬台国論のうちで、もっともすぐれたものということができよう。
文献的事実と、考古学的事実とを総合した構造性において、論証における手がたさにおいて、部分的にはともかく、総合的にみて、現在でも笠井新也の論考の水準を抜く畿内説の論考は、まず、あらわれていないといっても過言ではない。
そのため、現在でも白石太一郎氏をはじめ、基本的に笠井新也の年代論の立場にたつ考古学者はすくなくない。
笠井新也は、卑弥呼に、『日本書紀』の「崇神天皇紀」に記述のある倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)説をあてはめ、卑弥呼の墓に倭迹迹日百襲姫の墓とされる箸墓をあてはめる。
すなわち、笠井新也は以下のように論ずる。
(1)卑弥呼は、倭迹迹日百襲姫命である
卑弥呼については、九州の女酋とする説、大和朝廷に関係ある婦人とする説があった。卑弥呼の年代は、第十代の崇神天皇の時代である。「崇神天皇紀」に登場する「倭迹迹日百襲姫」は、崇神朝第一の女傑で、神意を奉じて奇跡を行ない、未然を識(し)って反逆を看破するなど、信頼と畏敬をうけるのに十分であった。卑弥呼はヒメミコトの意味で、高貴な婦人に対する尊称である。倭迹迹日百襲姫命は孝元天皇の皇女であり、姫命は卑弥呼の名称によく一致する。卑弥呼は「鬼道につかえ、よく衆をまどわす」とあり、倭迹迹日百襲姫命に似る。(「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫(一)」『考古学雑誌』第十四巻、第七号、1924年4月)
(2)卑弥呼の墓は箸墓古墳である
「崇神天皇紀」に登場する「倭迹迹日百襲姫命」の墓に関する記述は『魏志倭人伝』記載の卑弥呼の墓の記述(箸墓伝説)に酷似する。『日本書紀』のなかで、陵墓については、所在地の記載のみであり、具体的な墓づくりの記述はこれだけである。「されば卑弥呼の冢墓とは、いわゆる百襲姫命の御墓である箸墓を指したもの」である。(「卑弥呼の冢墓と箸墓」『考古学雑誌』第三二巻、第七号、1942年7月」)
笠井新也はその年代論を、その論文「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫命」において、およそつぎのように展開する。
「卑弥呼の擬定はまず年代の決定から出発しなければならない。卑弥呼の『魏志』に現れている年代を、我が国史の年代に引きあてるときは、あたかも崇神天皇の御代にあたることは、私の信じて疑わないところである。わが上古史における年代は、菅政友(かんまさとも)・那珂通世等の『古事記』年紀の研究によって、信憑すべき基礎が置かれ、しかして成務天皇以下歴代の崩御年紀が明確となったことは学界のひとしく認めるところである。しかるに崇神天皇の崩年については、成務天皇崩年の乙卯(きのとう)を標準として、それを一運(めぐ)り中の戊寅(つちのえとら)とすべきかあるいは一運り以前の戊寅とすべきか、これを決定すべき確実な資料を欠いている。

那珂通世はその著『上世年紀考』において、このことに論及し、
『37年(一運り)では、次の仲哀天皇も、在位わずかに7年であるから、四朝を合わせて、ただの42年である。仲哀天皇の四世の祖である崇神天皇の崩年は、四世の孫の崩年から、ただ42年まえであるとは思われないから、三朝の年数は、前の表のように、97年と見るほうが妥当であろう。』
といったのは妥当の見解というべきである。
崇神天皇の没年の258年は、卑弥呼の死んだ正始8年(247)もしくは9年(248)をへだたる10年もしくは11年の後にあたるのである。すなわち卑弥呼の死と崇神天皇の死とは、わずかに十年前後しか相違しないので、卑弥呼の時代はすなわち崇神天皇の時代であることは、もはや疑いを容れないといってよかろう。
要するに、卑弥呼の活動年代は、あたかも崇神天皇の時代にあたっておって、さらにくわしくいえば、彼女の死は、天皇の崩御に少しく先立つものであることは、ほとんど確実というべきである。されば卑弥呼をわが国史中に求めようとすれば、必然崇神天皇の朝に求めなければならないのである。」
すなわち、笠井新也は、大きくは那珂通世の年代論によっているが、より具体的直接的には、『古事記』の記す諸天皇の没年干支によって立論している。それによって卑弥呼の活動年代は、崇神天皇の時代にあたるとしているのである。
『古事記』の「没年干支」について、東京大学の教授であった古代史家の井上光貞は、『神話から歴史へ』(『日本の歴史1』中央公論社、1965年刊)のなかで、つぎのようにのべている。
「この崩年干支(没年干支のこと)は、あまり信用できない。古事記のできたころにはすでに、何らかの記録によってできあかっていたものと考えられるが、その書かれた内容をすべて信用することには賛成しかねるからである。崩年干支によってあまりはっきりした数字をだすことは、しばらくあきらめるほうが無難であろう。」
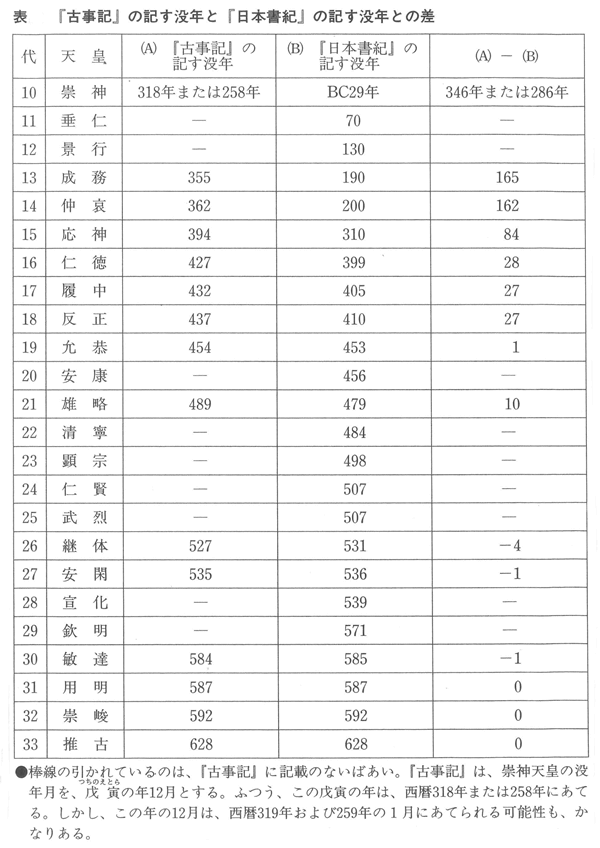
(1)「奈良七代七十年」
奈良時代は第43代元明天皇から、第49代の光仁天皇までの七代、すなわち、元明・元正・聖武・孝謙・淳仁・称徳・光仁の七代で、74年(710~784)。この間、一代平均10.57年。桓武天皇は、はじめ784年に長岡京(京都府向日市のあたりが中心)に都をうつしている。
(2)「君、十帝を経て、年ほとほと(ほとんど)百」
この文は、奈良時代史の基本文献である『続日本紀(しょくにほんぎ)』の、淳仁天皇の天平宝字2年(758)8月25日の条に記されている。これは、第36代の孝徳天皇から、第46代の孝謙天皇までが、十代で、104年ほどであることをのべているのである。
すなわち、天皇一代の平均在位年数が、およそ十年ていどであることは、奈良時代の人たちが大略認識していたことであった。
■箸墓古墳の築造は、四世紀後半ごろ
考古学者の森浩一・大塚初重両氏は崇神天皇陵古墳を、「四世紀の中ごろまたはそれをやや下るもの」としている『シンポジウム 古墳時代の考古学』学生社、1970年刊)。
また、東京大学教授であった考古学者斎藤忠氏も、つぎのようにのべている。
「今日、この古墳の立地、墳丘の形式を考えて、ほぼ四世紀の中頃、あるいはこれよりやや下降することを考えてよい。」
「崇神天皇陵が四世紀中頃またはやや下降するものであり、したがって崇神天皇の実在は四世紀の中頃を中心とした頃と考える・・・・」(以上、斎藤忠「崇神天皇に関する考古学上よりの一試論」『考古学』13巻、1号、1966年刊)
円筒埴輪の編年について画期的な業績を示した筑波大学の考古学者、川西宏幸氏も、崇神天皇陵古墳の築造年代を西暦360~400年とする(下表参照)。
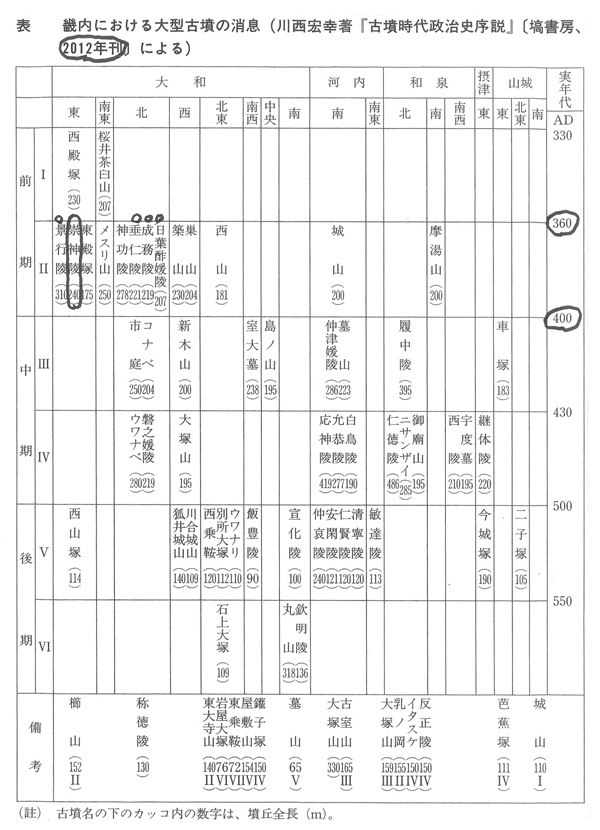
奈良県橿原考古学研究所の考古学者関川尚功(せきかわひさよし)氏も、崇神天皇陵古墳の築造年代を四世紀後半~五世紀初頭とする(『季刊邪馬台国』42号、1990年刊)。
・箸墓古墳の築造年代は、崇神天皇陵古墳の築造年代と関係をもつ。
倭迹迹日百襲姫は、崇神天皇の時代に亡くなって箸墓にほうむられたと『日本書紀』に記されている。したがって、文献上は図に示したような推定にもとづき、箸墓古墳の築造の時期は、360年の前後、四世紀半ばから、それをやや下ったころ、およそ西暦350~370年ごろとなる。
この値は、次の二つの値と整合的である。
(1)炭素14年代測定法による年代
箸墓古墳から出土した桃核の炭素14年代測定値、および奥山誠義氏によるホケノ山古墳出土試料から求められた炭素14年代測定値から推定される箸墓古墳の築造年代(これについては、このシリーズの拙著『卑弥呼の墓・宮殿を捏造するな!』[勉誠出版、2011年刊]にくわしい)。
(2)土器から推定される年代
奈良県立橿原考古学研究所の関川尚功氏によれば、箸墓古墳は布留1式期のものであり、古墳時代前半のもので、四世紀中ごろ前後の築造とみられる、という。私は、関川尚功氏がそうとうに合理的な根拠を示しておられると思う。これについては、関川尚功氏の論文「土器からみたホケノ山古墳と箸墓古墳」(『季刊邪馬台国』102号所載)を参照していただきたい。
■岩石学による検証
石野博信氏は、『三輪山と日本古代史』(学生社、2008年刊)のなかでのべる(傍線は安本)。
「箸墓というのは倭迹迹日百襲姫という女性の墓といって、日本国の最初の天皇、御肇国天皇(はつくにしらすすめらみこと)という初めて国を治めたスメラミコト、天皇と呼ばれる崇神天皇のときに箸墓はつくられたということが『日本書紀』に書いてあります。『日本書紀』は奈良時代につくられた日本の最初の歴史の本ですが、古墳築造のことが書いてある非常に珍しい部分です。
そこに書かれている伝説によると、箸墓は『昼は人つくり、夜は神つくる』と書いてあり、それほど突貫工事だったのだろうと思います。そして、古墳の上に敷き並べた石は逢坂山の石を手越しにして運んだ。これも有名な話ですが、逢坂山の石をリレー式にして運んだ。逢坂山とは二上山です。
二上山と三輪山の間は十四、五キロあります。その間に人がずらっと並んで、一人一メートルだとすると何人になるでしょうか、ずらりと並んでリレー式に逢坂山の石を運んだんだと書かれています。
今、箸中山古墳(箸墓)は宮内庁が、崇神天皇のおばさんの墓だからということで、管理しています。
宮内庁が時々埴輪などの資料を採集して発表している記録によると、箸中山の上に乗っている石は逢坂山、二上山周辺の石であることが十数年前に岩石学的にも証明されました。そうすると、『日本書紀』に書かれた伝説はうそではない。ほんとうのことが奈良時代まで伝わっていて、『日本書紀』に記録されたということがわかります。」
中国文献の記述とあっていない
(1)『魏志倭人伝』と『後漢書』とは、卑弥呼が王になった事情を、つぎのように記している。
「その国は、もと男子をもって王としていた。倭国が乱れ、たがいに攻伐しあって年をへた。そこで、一女子を共立して王とした。名づけて卑弥呼という。」(『魏志倭人伝』)
「倭国は大いに乱れ、たがいに攻伐しあった。歴年、主がいなかった。一女子があった。名を卑弥呼という。ともに立てて王とした。」(『後漢書』「東夷伝」)
『魏志倭人伝』には、卑弥呼の死後に、「更(あらた)めて男王を立てた(更立男王)」とある。「更」には、「かえる」「入れかえる」「あらためかえる[更代(こうたい)]」の意味がある。「それまで、女性であったのをあらためかえて男王を立てた」意味にうけとれる。
これらの文章によれば、もとは男子の王がいたが、卑弥呼が立ったときには男王がいなかったということになる。倭迹迹日百襲姫が卑弥呼であるとすれば、当時は、男王崇神天皇がいたことになり、「歴年、主がいなかった」「あらためて男王を立てた」という『後漢書』「東夷伝」や、『魏志倭人伝』の記事と、はっきり矛盾することとなる。
(2)『魏志倭人伝』は、「親魏倭王卑弥呼」と記すなど、卑弥呼が倭を代表する王であることを明記している。これに対し、『古事記』『日本書紀』のどこにも倭迹迹日百襲姫が帝位についたとは記されていない。
倭迹迹日百襲姫は一人の巫女(みこ)である。当時の天皇は崇神天皇である。卑弥呼は大陸までも名の通った倭の王である。これに対し、倭迹迹日百襲姫は倭王崇神の陰の存在にすぎない。両者では政治的な立場に大きな違いがある。
(3)『魏志倭人伝』は、卑弥呼の死後、争乱があったことを記している。しかし、『日本書紀』では、倭迹迹日百襲姫の没したすぐつぎに、「反(そむ)けりし者は悉(ふつく)に誅(つみ)に伏(ふ)す。畿国(うちつくに)は事無(な)し」という崇神天皇の言葉が現れる。また、「国内(くにのうち)安寧(やすらか)なり」とも、「天下(あめのした)大(おお)きに平(たいらか)なり」とも記されている。倭迹迹日百襲姫が没したために起きたとみられる争乱はない。
(4)『魏志倭人伝』には卑弥呼を、「年すでに長大であるが、夫壻(ふせい)はない」と記している。一方、『日本書紀』には、倭迹迹日百襲姫が大物主神(おおものぬしのかみ)の「妻になった」とも、「夫(せな)に語りて曰(いわ)く」とも記されている。
この点にも関連して、文献史料にも詳しい考古学者の森浩一氏は、つぎのように述べている。
「ヒミコは女王であったのにたいして、モモソ姫はそうではなかったのと、なによりもヒミコと『年すでに長大なるも夫壻なし』であるのに、モモソ姫は大物主神の妻であり、モモソ姫から見て大物主神は夫であった。『夫壻』は『夫婿』に同じ、夫のことである。
よく世間話に、『ヒミコの死と箸墓古墳の年代が近いとすると、箸墓はヒミコの冢でよい』という短絡というよりも杜撰(ずさん)きわまりない発言をする学者もいるけども、その場合は、まず倭人条のうえでのヒミコと崇神紀のモモソ姫とが、同じ人物であったこと、または倭人条の記述と重ねて創られた人物だということを証明しないかぎり、箸墓にはつながらない。ヒミコとモモソ姫との間の共通点についていえば、古代の支配層にいた予知能力者としての女性の共通点としてとらえることができそうだとぼくは考えている。」(『記紀の考古学』朝日新聞社、2000年刊)
卑弥呼はだれか、卑弥呼はどの天皇の時代の人なのか、についてのおもな説としては、つぎの五つがある。
(1)卑弥呼=神功皇后説
『日本書紀』において示されている説である。『神皇正統記』をあらわした南北朝時代の北畠親房(きたばたけちかふさ)や、『異称日本伝』をあらわした江戸元禄時代の国学者、松下見林(まつしたけんりん)も『日本書紀』の記述をうけて、神功皇后を卑弥呼にあてている。明治以後の学者でも、小中村義象(こなかむらよしかた)、森清人など、「卑弥呼=神功皇后説」をとった学者は、かならずしもすくなくない。
(2)卑弥呼=倭姫説
倭姫は、第12代景行天皇のころの人である。
「卑弥呼=倭姫説」は、明治のすえに、京都大学の内藤湖南(虎次郎)がとなえた。現代でも、坂田隆などは、「卑弥呼=倭姫説」をとっている。
(3)卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説
倭迹迹日百襲姫は、第10代崇神天皇のころに活躍したとされている人である。「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」は、大正時代に、笠井新也がはじめてとなえた。
現代でも、歴史学者の肥後和男、和歌森太郎、考古学者の原田大六、その他、『日本誕生の謎』を書いた井上赳夫(たけお)、『倭日の国』を書いた熊本大学の藤芳義男など、「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」をとる研究者はすくなくない。
(4)卑弥呼=天照大御神説
卑弥呼を、第1代神武天皇より五代まえと伝えられる天照大御神にあたるとする説である。
この説は、いずれも東京大学の教授であった白鳥庫吉、和辻哲郎が示唆し、その後、栗山周一が明確な形で主張し、林屋友次郎、飯島忠夫、和田清、市村其三郎、安本美典、鯨清、平山朝治などによってうけつがれている。
この説に立つとき、邪馬台国は、九州にあったことになり、のち西暦300年前後の人と推定される神武天皇の時代に、東遷したことになる。いわゆる「邪馬台国東遷説」を主張することになる。
(5)卑弥呼=九州の女酋説
魏へ使をつかわしたのは、大和朝廷とは関係のない九州の女酋であるとする説である。
この説は、江戸時代に、本居宣長が説き、その後、鶴嶺戊申、星野恒(ひさし)、吉田東伍などによってうけつがれた。
(6)卑弥呼は不明とする説
『古事記』『日本書紀』は、八世紀に成立したものである。卑弥呼は、三世紀に存在した人である。その間に、五百年ちかいへだたりがある。『古事記』『日本書紀』の伝える初期の諸天皇には、実在の疑われる人もあり、『古事記』『日本書紀』によっては、卑弥呼や邪馬台国は、さぐれないとする立場である。津田左右吉が、このような考え方を、体系的にまとめ、現在、この立場に立つ人は多い。
以上のうち、(1)の「卑弥呼=神功皇后説」、(2)の「卑弥呼=倭姫説」、(3)の「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」は、だいたい、「邪馬台国=大和説」となる。(4)の「卑弥呼=天照大御神説」、(5)の「卑弥呼=九州の女酋説」は、「邪馬台国=九州説」となる。
また、(1)、(2)、(3)、(4)は、卑弥呼を、皇室の系譜のうちから求められるとする説であり、(5)、(6)は、皇室の系譜のうちに求められないとする説である。
・東洋史家、白鳥庫吉の説
白鳥庫吉(1865~1942)は、明治期の東京大学を、いやその時代を代表する史家であった。東洋史学の開拓者であり、数々の新研究を発表するとともに、多くの研究者を育成した。
白鳥庫吉は、また、邪馬台国北九州説を説き、畿内大和説を主張する京都大学の内藤湖南と、白熱の論争を戦わせた。邪馬台国の位置をめぐる諸説は、それまでにも出されてはいた。しかし、現代まで長く尾をひく、いわゆる邪馬台国論争は、このときはじめて、激しい沸騰をみせたといってよい。
白鳥庫吉は、「邪馬台国東遷説」を示唆し、のちの和辻哲郎、栗山周一の「邪馬台国東遷説」に、直接つながりうるような内容をもつ論文を、いまからおよそ百年まえに、すでに発表している。
すなわち、白鳥庫吉は、明治43年(1910)に発表した論文「倭女王卑弥呼考」のなかで、『魏志倭人伝』の「卑弥呼」に関する記事内容と、『古事記』『日本書紀』の「天照大御神」に関する記事内容とを比較している。そして、その二つの記事内容について、「その状態の酷似すること、何人も之(これ)を否認する能(あた)わざるべし。」とのべている。この指摘は、のちの「邪馬台国東遷説」の核心部と関係する。
白鳥庫吉は、すでに『古事記』『日本書紀』の神話を伝える天照大御神は、『魏志倭人伝』の記す卑弥呼の反映なのではないか、天照大御神がいたと伝えられる高天の原は、邪馬台国の反映なのではないかとする考えを示している。
文は、文語体であるが、口語体になおして、白鳥庫吉ののべているところを紹介する。
「すべて、神話伝説は、国民の理想をのべたものであって、当時の社会の精神風俗などは、ことごとくそのなかに包含されるものである。したがって、皇祖発祥の地である九州において、上古、卑弥呼をはじめとして、女子で君長であったものが多数いたとすれば、天照大御神が女王として天上に照覧するのも、また、なんの怪しむべきことがあろうか。」
「つらつら神典(『古事記』『日本書紀』)の文を考えると、天照大御神は、素戔鳴の尊の乱暴な振るまいを怒って、天の岩戸に隠れた。このとき、天地は、暗黒となって、万神の声は狭蝿(さばえ)のごとく鳴りさやぎ、万妖がことごとく発した。
ここにおいて、八百万の神たちは、天の安の河原に神集って、大御神を岩戸から引きだし、ついで素戔鳴(すさのお)の尊(みこと)を逐(お)いやったので、天地はふたたび明るくなった。
ひるかって『魏志』の文を考えると、倭女王卑弥呼は狗奴国男王の無体を怒って、長くこれと争ったが、その暴力に堪えず、ついに戦中に死んだ。ここにおいて、国中大乱となり、一時男子を立てて王としたが、国中これに服せず、たがいに争闘して数千人を殺した。しかるに、その後、女王の宗女壱(台)与を奉戴するにおよんで、国中の混乱は一時に治った。
これは地上に起きた歴史上の事実で、かれは、天上に起きた神典上の事跡であるけれども、その状態の酷似すること、何人もこれを否認することはできないであろう。もしも神話が太古の事実を伝えたものとすれば、神典の中に記された天の安の河の物語は、卑弥呼時代におけるような社会状態の反映とみることができようか。」







