■年代の問題を説明する。
天皇1代平均10.99年から、
基準点Ⅰを桓武天皇とし、基準点Ⅱを用明天皇とする。下記の上の図のようになる。
雄略天皇を推定すると478年ごろ活躍したことになる。そして宋書から、倭王武と考えられる。
次に、基準点Ⅰを桓武天皇とし、基準点Ⅱを雄略天皇とする。下記の下の図のようになる。
そうすると、雄略天皇の7代前の神功皇后の活躍年代が402年頃と推定できる。
(下図はクリックすると大きくなります)
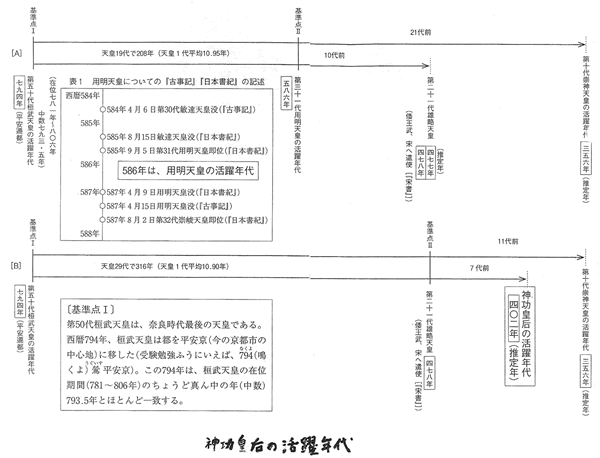
この402年頃に何が起きていたかというと、各種文献では下記のように記されている。
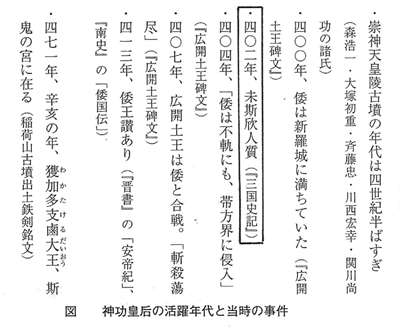
神功皇后の活躍年代は、402年を中心とする前後の年代となる。これは、高句麗の広開土王の活躍年代(在位391~412)と、ほぼ正確に重なる!!(広開土王の在位期間391~412の中数[2つの数字を足して、2で割った値]は、401.5年で、402年と、ほとんど一致する。)
そして、『日本書紀』の「神功皇后紀」の記事は、「新羅の王、波沙寐錦(はさむきん)は、微叱己知波珍干岐(みしこちはとりかんき)[波珍干岐は、新羅の官位]をもって質とした。」となっている。
一方、朝鮮がわの史書は、つぎのように、『三国史記』は未斯欣が倭国の人質になったことが記されている。 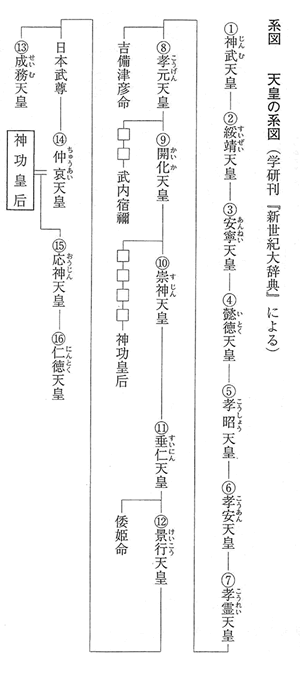
・『三国史記』の「新羅本紀」の記事
「実聖尼師今(じつせいにしこん)[実聖王、在位402年~417年)元(402年)3月に、倭国と通好して、奈勿王(なぶつおう)の子、未斯欣を人質とした。」
・『三国史記』の「列伝」第五の「朴堤上」伝の記事
「実聖王元年壬寅(じんしん)の年(402年)に、倭国と講和を結ぶとき、倭王は奈勿王(なぶつおう)の子、未斯欣を人質にしたいと請うた。(実聖)王は、かつて奈勿王が自分を高句麗へ人質として送ったことをうらんでいたので、そのうらみを、その子ではらそうと思っていた。そこで、倭王の請いを断わらずに、未斯欣を派遣した。」
ところが、『日本書紀』編纂者は、『魏志倭人伝』を読んでいた。そこで、『日本書紀』編纂者は、神功皇后を卑弥呼にあてはめた。そして年代をあわせるために、朝鮮史書『三国史記』の年代干支2めぐり、120年くりあげた。(那珂通世の指摘)
しかし、そのようにくりあげることのできない問題があった。
百済王の直支王の年代である。
直支王の年代を、くりあげることのできない別の史料が存在する。
それは、直支王が、東晋の安帝によって、416年(義熙十二)に、「使持節・都督百済諸軍事・鎮東将軍・百済王」に任命されていることである。
直支王が、東晋の安帝から爵号を、与えられたことは、『宋書』の「夷蛮伝」の「百済国」条に、「義熙12年、以百済王余映(直支王のこと)、為使持節都督百済諸軍事鎮東将軍百済王」とある。この文は、類書(百科全書)の『翰苑』にも、引用されている。同じ記事は、『南史』の「東夷伝」の「百済」条にものっている。さらに、『三国史記』の「百済本紀」の「腆支王」の12年(西暦416)の条に、「東晋の安帝は、使臣を遣わして、(腆支)王を冊命して、『使持節都督百済諸軍事鎮東将軍百済王』にした。」とある。
また、『梁晝』の「諸夷伝」に、「晋、義熙(405~418)中王余映」とある。
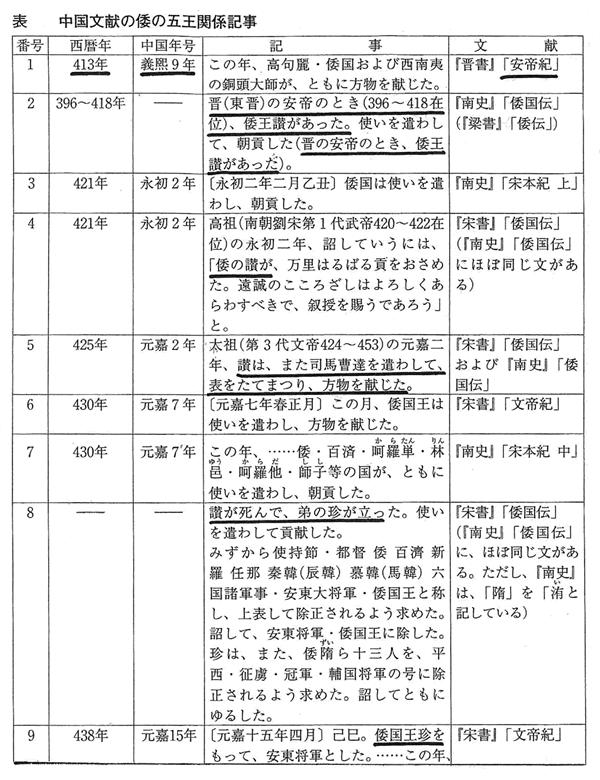
『日本書紀』が、「直支王」と記す百済王の名を、『三国史記』は、「腆支王」と記し、中国の『通典(つてん)』は、「腆」、『翰苑』は「晪」「?」、通行本の『宋書』『梁書』は「映」、朝鮮の『三国遺事』は「眞支王」と記す。
本来は、「腆支王」で、他は、その省略形、あるいは、発音または字体の近似による誤記などであろうとみられる。
この直支王(腆支王)の在位の時期を、『三国史記』は、「405年~420年」と記す。
つまり、直支王の年代について、朝鮮史書『三国史記』の年代は信用できる。『日本書紀』の年代は信用できない。
(下図はクリックすると大きくなります)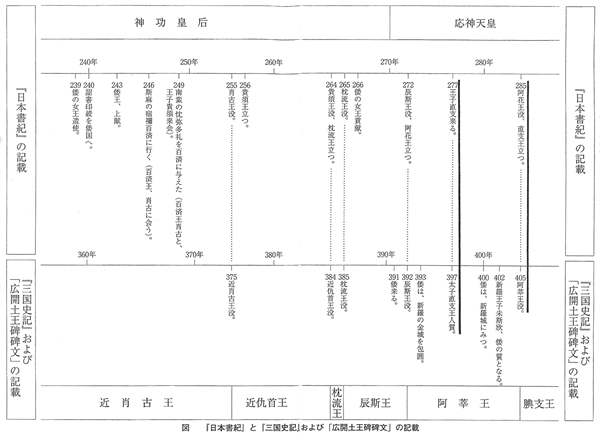
『日本書紀』の「応神天皇紀」によれば、百済の第十六代の王で、直支王のまえの代の阿花王(『三国史記』は、「阿萃王(あしんおう)」と記す。「阿華王(あかおう)」を書き誤ったものか)が、なくなると、阿花王の長子の直支王は、人質として日本に来ていたが、応神天皇は、「お前(直支王)は、国(百済)にかえって、位をつげ。」と命じた、という。
これに対応する記事は、『三国史記』の「百済本紀」の「腆支王」の条にもある。
そこには、つぎのように記されている。
「腆支は倭にあって(阿萃王の)訃報をきき、哭泣しながら帰国を請うと、倭王は、兵士百人をもって護送させた。」
ここで、阿花王がなくなり、直支王が位をついだ年を、『日本書紀』は、西暦285年(応神天皇十六年)のこととし、『三国史記』は、西暦405年(阿萃王の十四年、腆支王の元年)のことと記す。
『日本書紀』の285年と、『三国史記』の405年とでは、ちょうど120年ちがう。
『日本書紀』の年紀は、神功皇后を古く卑弥呼の時代にあてたのにひきずられて、ここでも、120年古くなっているのである。
しかし、応神天皇の時代に、入質になっていた百済王子が、国にかえって位をついだという記事内容自体は、正しいのではないか。日本がわにも、それなりの所伝があったのではないか。
それは、倭の人質となっていた新羅の王子未斯欣[微叱己知波珍干岐(みしこちはとりかんき)]が、神功皇后の時代に、倭の人質になった、という記事と同様である。
これは、「織田信長が本能寺の変で明智光秀に討たれた」この歴史的事件があったことは覚えているが、これが西暦何年かとというと覚えている人は少ないことと同じである。
日本がわの所伝では、本来、年代は、伝わっていなかった。ただ、応神天皇の時代におきた事件、神功皇后の時代におきた事件としてだけ伝わっていたとみられる。真の年代は、『日本書紀』は教えてくれず、朝鮮の史書『三国史記』が教えてくれている。
年代は起きた事件によって考えるべきである。
直支王に関連した記事は、その後も、『日本書紀』の「応神天皇紀」にみえる。
応神天皇の二十五年(西暦294年にあたる年)条に、百済の直支王がなくなった、という記事がある。
『三国史記』の「百済本紀」では、腆支王がなくなったのは、西暦420年にあたる年である。ここでは、『日本書紀』と『三国史記』とで、年代に、126年の違いがある。
[白石太一郎氏の見解]
「白石太一郎氏著『古墳の被葬者を推理する』(中央公論社、2018年刊)で、下記のように直木孝次郎(なおきこうじろう)氏は、井上氏(井上光貞氏)とは異なる考え方を提起しておられる。『日本書紀』の応神紀によると、応神三年[壬辰(じんしん)]条に「阿花を立てて王とす」とあり、同十六年[乙巳(いっし)]条に「是歳(ことし)、百済の阿花王薨(みまか)りぬ」、同二五年[甲寅(こういん)]条に「百済の直支王(ときおう)薨りぬ」とあることから、応神天皇を百済の阿花王辛直支王と同世代と考えられている。『三国史記』によると阿華王(あかおう)の即位は壬辰年(392)、没年は乙巳年(405)、腆支王(ときおう)[直支王]の即位は乙巳年(405)、没年は庚申(こうしん)年(420)であることが知られる。『日本書紀』と『三国史記』のこの部分の二人の百済王の在位に関する記載は、腆支王の没年を除くと完全に一致している(ただし『日本書記』は干支を二巡繰り上げて記載している)。これらのことから直木氏は、応神の在位はまさに四世紀末から五世紀の初めにかけてであろうと想定しておられる[直木、1990年]。
井上、直木両氏の説を比較すると、井上説の肖古王の没年の乙亥年(375)は『日本書紀』では応神の前の神功皇后の時代にあてられていて、神功皇后の時代が古すぎると思う。また『古事記』の崩年干支が古代の天皇の在位時期を考察する上に貴重な資料であることは確かであるが、それも四世紀代にまで遡って信頼性があるものかどうかは疑問である。
それにたいして直木説は、神功紀、応神紀のうち『百済記』など百済系史料によった記載の史実性を認める多くの研究者の考え方とも一致するものであり、説得力があり賛同できる。
このように、筆者は応神の在位は直木氏が考証されたように、四世紀末から五世紀の初め頃とみるのが、もっとも蓋然性の高い想定であろうと考えている。こう考えてよければ、応神の没年は五世紀の第1四半期(400年~425年)のことであり、これは第2節で想定した誉田御廟山古墳の造営年代とほぼ一致する。
ただし、こうした大型前方後円墳については、その造営に要する期間の問題も考慮する必要がある。正確にはわからないが、誉田御廟山古墳クラスの巨大前方後円墳になると、その造営には二〇年程度、あるいはそれ以上の年月を要したものと思われる。
応神の在位については、これまで述べたように四世紀末から五世紀初め頃にかけてと想定できるだけで、それほど厳密な議論ができるほど確かな史料があるわけではない。また誉田御廟山古墳の造営年代も、五世紀の第1四半期といっても、その後半に下る可能か大きいものと思われる。
とはいえ、五世紀初め頃に亡くなった応神の御陵か、五世紀の第1四半期の後半頃に造営されたと考えられるわけで、応神陵である可能性を否定しなければならないほどの大きな矛盾はないであろう。
今一つ大きな課題は、五世紀段階の大王や有力首長の古墳の造営が、どの時点から開始されたのかという問題である。これについては『日本書紀』の仁徳紀にみられるように、大王や有力首長の生前から古墳の造営が開始されていたという、いわゆる寿陵説を採る研究者もおられることは事実である。しかし筆者は、基本的には亡き大王や首長の後継者がその地位についたのちに、前代の大王や首長の古墳の造営を始めるのが原則だったのではないかと考えている。古墳の造営という行為には、新首長による首長権の継承それ自体を表現する意味があったはずである。それは次代の首長の継承が確定してはじめて可能であったと考えられるからである。
残念なからこの問題は、考古学的な方法では実証的に明らかにすることが困難である。しかし逆に、ここに論じつつあるような誉田御廟山古墳=応神陵説が成り立つならば、こうした問題の解明にも大きく寄与することができるのではないかと思う。そのために残された課題はあまりに大きく、今後さらに多角的に検討する必要があることはいうまでもない。
さて考古学の立場からの検討によって、以下のことが明らかになった。
①誉田御廟山古墳は同時期の古墳のなかでの規模の隔絶性から、ヤマト政権の盟主である大王の墓と想定するほかないものである。さらに、
②その造営年代は五世紀の第1四半期でも新しい段階と想定できる。一方、
③応神天皇の在位は、四世紀末から五世紀の早い時期に求められる。
これらを総合すると、誉田八幡宮の存在から、天皇陵の国家的祭祀・管理か始まった律令国家成立期に応神天皇陵として祭祀が行われていたことはまず確実と考えられる誉田擲廟山古墳が、記・紀にみられる応神大王の墳墓である蓋然性を否定するのはきわめて難しいのではないかと思われるのである。」
崇神天皇・神功皇后・仁徳天皇の時代の年代とその時に起きた記事について、中国・朝鮮の文献の記事とあう。そしてその活躍した年代を天皇1代平均年数からみても、用明天皇から神功皇后までの天皇平均1代10.95年であり、用明天皇から応神天皇までの天皇平均1代10.44年であり、用明天皇から仁徳天皇までの天皇平均1代10.13年であり、ほぼ天皇平均1代のほぼ十数年で年数があうことになる。
(下図はクリックすると大きくなります)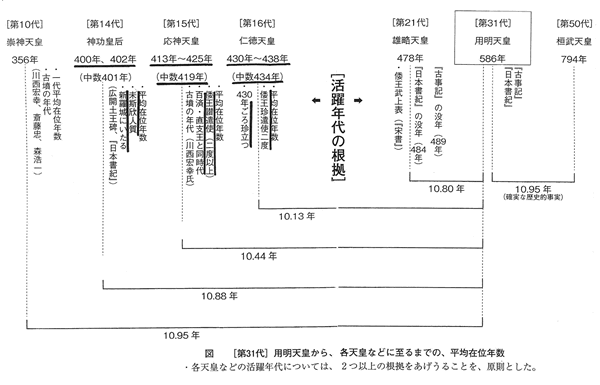
このように、中国の文献、朝鮮の文献、白石太一郎氏の見解から、『日本書紀』の神功皇后・応神天皇の年代が120年古くなっていることが分かる。
■応神天皇の年齢
『三国志』にみえる魏の明帝がなくなったあと、曹芳(斉王、在位231~250)が、皇帝の位をつぐ。そのとき、曹芳は、八歳であったという。
曹芳のあと曹髦(そうぼう)[高貴卿公(こうきこうきょう)、在位254~260]が、皇帝となるが、なくなったとき、二十歳であったという。十四歳で皇帝になったことになる。
曹髦のあと魏の最後の皇帝になった曹奐(そう かん)(陳留王、在位260~265)は、退位して、位を晋の司馬炎にゆずった。曹髦が退位したとき、年は、二十歳であったという。曹髦は、五年間在位しているから、十五歳で即位したことになる。
また、『魏志倭人伝』によれば、卑弥呼の死後、宗女(一族の娘)の壱与(いよ)[台与(とよ)]が、年十三で、王となっている。
西暦400年ごろに生まれたとして、応神天皇(倭王讃)は(413年に東晋の安帝に使いを出したころ、十三歳ていどであったということになろうか。
■魏や後漢の皇帝たちの即位年齢
いま、中国の魏や後漢の皇帝たちの即位年齢などをしらべ、表の形にまとめれば、下の表のようになる。

この表を見ればつぎのようなことがわかる。
(1)合計で、十九人の帝王のうち、十五帝(79パーセント)は、二〇歳未満で即位している。
(2)合計で、十九帝王のうち、十六帝(84ハーセントは、四〇歳未満で、没するか退位している。
(3)十九帝王のうち、四帝王が、廃位または譲位で、十五帝は、在位中になくなっている。
(4)系図と昭らしあわせると西暦156年生まれの後漢の霊帝は、つぎの西暦172年生まれの少帝を十六歳で生んでいることになる。
西暦187年生まれの魏の文帝は。つぎの西暦205年生まれの明帝を、十八歳で生んでいることになる。
このようにみてくると、応神天皇も、おそらくは、二〇歳未満で即位し、四〇歳未満でなくなっている可能性が大きいといえよう。わが国の状況も中国の状況と、それほど大きくは、変わらなかったであろう。
寿命が長く、晩婚化か進んでいる現代の常識で、寿命が短く、早婚の傾向のあった時代を、判断してはいけないと思う。
■神功皇后の「摂政」について
『日本書紀』の「神功皇后紀」は、神功皇后が、「摂政」であったことを記す。
すなわち、神功皇后の摂政元年の条の最後に、辛巳(かのとみ)の年を、神功皇后の「摂政(まつりごとふさねをさめまふ)元年」とする、と記している。辛巳の年は、西暦201年にあたる年である。ここでは、神功皇后を、実際の活躍年代の402年ごろよりも、200年以上古くみつもっているのである。
ここで、「摂政」ということばの意味を考えてみよう。
『国史大辞典8』(吉川弘文館刊)で、『摂政』という語を引くと、つぎのような説明がのっている。
「天皇に代わって万機を摂り行う者、または摂り行うことをいう。」
「摂政の語は中国・朝鮮の文献にみえるが、『史記』などにみえる中国の例は、皇帝は在位するが老齢・幼少などのため統治能力のない場合、皇帝に代わって統治する者をさし、朝鮮の例は『三国史記』などによると、王が幼少のため統治能力を欠く場合、母后である皇太后・太皇太后が王に代わって大政を執ることをいい、わが国の称制に相当するものといえる。摂政をその出自により大別すると、皇族摂政と人臣摂政に分けられる。『日本書紀』によると、仲哀天皇の崩御後、神功皇后が摂政になったとあるのをわが国の摂政の初例とするが、皇后の統治は摂政というよりも称制にもとづいていたと考えられる(中略)。」
ここに、「称制」という語があらわれる。そこで、『国史大辞典7』によって、「称制」という語を引くと、つぎのようにある。
「皇太子あるいは皇后が天皇の崩後に、即位せずに国政を掌ること。」
『日本書紀』の記述や、中国文献などを参考にすると、神功皇后の「摂政」は、『史記』や『三国史記』にみられるように、つぎの意味に理解してよいのではないか。
「皇帝は在位しているが、老齢・幼少などのため統治能力のない場合、皇帝に代わって統治する者」
「王が幼少のため統治能力を欠く場合、母后である皇太后・太皇太后などが王に代わって大政を執ること」
第十四代仲哀天皇のあとの、第十五代の天皇は、応神天皇(=倭王讃)であった。ただ、倭王讃が、413年に、東晋の安帝に使いをつかわしたころ、応神天皇=倭王讃は、なお、幼少であった。そのため、母后の神功皇后が、摂政の位置にあった。ただ、中国との国交のばあいは、母后の神功皇后の名ではなく、「倭王讃=応神天皇」の名で行なった。
425年に、倭王讃が、中国の宋に使いをつかわしたころには、おそらくは、神功皇后摂政の時代ではく、応神天皇の親政の時代であったであろう。
「摂政」というと、わが国の、のちの時代の、推古天皇の時代の聖徳太子の摂政や、鎌倉時代以後や藤原氏の一族が独占した摂政・関白などの職の摂政を、思い出しがちである。これらは成人している天皇を、摂政が補佐する形のものである。しかし、神功皇后の摂政は、『史記』や『三国史記』にみられる摂政の意味に近いとみられる。
■『三国史記』や『晋書』にみえる「摂政」
新羅の第二十四代の王(在位540~576)の真興王は、対外戦争を行ない、領土をいちじるしく拡大させた。新羅の国力を、飛躍的に拡張させた。
真興王は、七歳で即位した。即位直後は、王母が摂政であった。ひとり立ちしたのは、十七歳のころという。
また、高句麗の第六代の大祖大王(在位53~146)は、やはり七歳で即位した。王母が摂政をしたという。
大祖大王も、外征と領土拡張を行なった。『後漢書』の「高句麗伝」に、大祖大王について、「長ずるに及んで勇壮にして、しばしば辺境をおかした。」とあるから、実在の人物である。ただ、『三国史記』に、大祖大王が位をゆずったとき、年齢が百歳で、在位は九十四年とある。日本の古い天皇のばあいと同じく、年代が、なんらかの形で、ひき伸ばされている可能性がある。
中国の例では、「晋書」に、晋の第九代穆帝聃(ぼくていたん)[在位344~361]は、二歳で即位し、皇太后が、「臨朝摂政」したとある。
『晋書』では、第七代の成帝紹(在位325~342)は、五歳で即位、皇太后が、「臨朝称制」したとある。
『日本書紀』の「神功皇后紀」の「摂政」ということばは、これらの事例と、大略同じ意味で用いられているようである。
■402年前後の史実
402年前後の史実をみると、つぎのようになっている。
(1)400年、「倭は新羅城(新羅の王都・金城〔慶州〕)に満ちていた。」(『広開土王碑碑文』)
これに対する日本がわ文献の記事(『日本書紀』)。
「神功皇后の名は、気長足姫の尊(おきながたらしひめのみこと)という。神功皇后は、幼少のころから、聡明で英知であった。容貌も美しかった。仲哀天皇の皇后となり、天皇の没後、神の告げにより、『眼炎(まかがや)く金銀(こがねしろがね)多(さわ)なる国(新羅の国)』を得るべく、諸国に令を発して、船舶と兵士を集め和珥(わに)の津[対馬上県郡鰐浦(かみあがたぐんわにうら)]から出発して、朝鮮の新羅の国を攻めた。軍船は海にみち、旌旗(はた)は日に輝き、山川がことごとく振動した。新羅王は降伏し、船のかじを乾かすことなく春秋の貢献を欠かさないことを誓った。神功皇后は持っていた矛を、新羅の王の門にたてて、後世への印とした。」
(2)402年、「新羅の王子、未斯欣(みしきん)が、倭の人質となった。」(朝鮮の歴史書『三国史記』の「新羅本紀」)。
そして、新羅の王子、微叱己知波珍干岐(みしこちはとりかんき)が、日本の人質になった話は、『日本書紀』の「神功皇后紀」にも記されている。この未斯斤の話と微叱己知波珍干岐の話とは、ふつう、同一の話の異伝とみられている。
(3)404年、「倭は不軌にも(無軌道にも)、帯方界(むかし、帯方郡のあった地域)に侵入した。」(『広開土王碑碑文』)
(4)407年、広開土王は、倭と合戦し、「斬殺蕩尽」した。(『広開土王碑碑文』)
(5)413年、倭王「讃(第十五代の応神天皇のことか)」あり。(『晋書』の「安帝紀」、『南史』の「倭王伝」など)
(6)451年、倭王済(第十九代の允恭天皇か)を、「使持節・都督 倭(わ) 新羅(しらぎ) 任那(みまな) 加羅(から)[任那の一国、または任那と同じ意味に用いられているばあいもある] 秦韓(しんかん) 慕韓(ぼかん) 六国諸軍事・安東将軍」にしている。つまり、倭の軍事支配権が、新羅などにまで及んでいることを、客観的存在である中国の宋がみとめている。(『宋書』「倭国伝」、『南史』「倭国伝」など)
この間の状況について、京都府立大学名誉教授の坂元義種氏は、その著『倭の五王』(教育社、1981年刊)のなかで、つぎのようにのべている。
「好太王碑文によると、倭軍は高句麗によってさんざん敗られたことになっているが、実際はかならずしも『倭寇、潰敗(かいはい)し斬殺すること無数』というわけにはいかなかったようである。倭軍が何度となく出兵して高句麗軍と戦っていることは、高句麗側が決定的な勝利をおさめることができなかった証拠といってよかろう。また、『三国史記』によると、実聖尼師今(こしきん)元年(402)三月、新羅は倭国と好みを通じ、奈勿王(なぶつおう)の王子未斯欣(みしきん)を人質として倭国に送ったという。これは高句麗の庇護(ひご)だけでは迫りくる倭軍の脅威を払いのけることができなかったことを示しており、これもまた朝鮮半島における倭の勢力を物語るものであろう。
百済や新羅の王族が人質として倭国に送られている事実や、たび重なる倭軍と高句麗軍との戦闘を考慮するならば、好太王碑文の『倭、辛卯の年を以て来りて海を渡り、百残(ひゃくざん)[百済のこと]口口(二字欠落か)新羅を破り、以て臣民と為す』という記事がまったくの妄言(ぼうげん)ではないことが理解されるであろう。
倭国王が『使持節、都督倭(わ)・百済(くだら)・新羅(しらぎ)・任那(みまな)・秦韓(しんかん)・慕韓(ぼかん)六国諸軍事、安東大将軍、倭国王』とか。
『使持節、都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事、安東大将軍、開府儀同三司(かいふぎどうさんし)、倭国王』などと自称して、倭国だけでなく朝鮮半島南部の軍事的支配を主張した歴史的背景の一端はここにあるのである。
新羅が王族を人質として倭国に送ったのは、倭との軍事的対決を回避するのが目的であったかもしれないが、他面、見方によっては、新羅が倭と結び、高句麗の軍事的支配から脱却しようとした試みであったとみることもできる。後者の見方を重視するならば、倭国王の自称称号は、倭国王がみずからを強敵高句麗と対決する最高軍司令官-----倭と朝鮮半島南部(以下、韓と略称)諸勢力の最高軍司令官-----に位置づけたものとみることができよう。」
広開土王(374~412。在位は391~412)は、古代の朝鮮半島から中国東北地方にかけて栄えた高句麗第十九代の王である。好太王ともいう。一代の英傑といってよい。
広開土王が十八歳のとき、父の故国(ここく)壌王(じょうおう)が没したので、王位を継いだ。まもなく、百済を攻めて、漢江以北の地を奪った。396年、ふたたび百済を攻め、日本・百済の連合軍を破って、百済の王都に迫った。かくて、朝鮮半島の大部を支配下におさめた。
あとを継いだ、長寿王(ちょうじゅおう)により、広開土王の死後二年に、広開土王の功績を記した石碑が、鴨緑江(おうりょくこう)岸の、通溝(中華人民共和国の吉林省集安県の地)東北方六キロメートルのところに建てられた。広開土王の陵を守護するためのもので、高さ6.3メートルの巨碑である。この碑文は、1884(明治十七)年に、わが国の学界に紹介された。四世紀末から五世紀はじめにかけての同時代史料である。
その碑文は、碑の四面にきざまれ、41字詰44行、約1800字からなる。
■「獲(う)るところの鎧甲(がいこう)一万余領」
「広開土王碑の碑文」によれば「倭人は、新羅の国境に満ち」ていた。
西暦400年に、好太王は軍令を下し、歩騎五万を派遣して、新羅を救った。
高句麗軍が、男居城から新羅の国城にいたると、倭がその中に満ちあふれていた。
高句麗軍がいたると、倭賊は退去した。
しかし、その四年ののちの404年に、「倭は不軌(ふき)[無軌道]にも、帯方界(もとの帯方郡のあった地域)に侵入」した。
帯方界といえば、現在の京城(ソウル)から、その北のあたりをさす。倭は、朝鮮半島の、そうとう奥地にまで侵入しているのである。
「広開土王碑の碑文」は記す。
「好太王の軍は、倭の主力をたち切り、一挙に攻撃すると、倭寇は潰滅し、(高句麗軍が)斬り殺した(倭賊は)無数であった。」
さらに、407年、好太王は、「軍令を下し、歩騎五万を派遣して」、「合戦して、残らず斬り殺し、獲るところの鎧鉀(がいこう)一万余領であった。持ち帰った軍資や器械は、数えることができないほどであった。」
朝鮮に侵入した倭は、正規の高句麗軍五万と、くりかえし戦う力をもつ、万を超える大軍であった。
これらから、神功皇后が戦ったあいては、広開土王であったと考えられる。
■倭軍の侵攻と軍事支配権の範囲
領有権の範囲は、いつの時代でも、当事国と相手国などとで、主張が異なるものである。現代でも、中国との尖閣諸島問題、韓国との竹島問題、ロシアとの北方四島問題など、いくつかの領有権問題がある。
古代においても、同様な問題があった。
『宋書』によれば、西暦430年代(430年から、437年のあいだのころ)、倭王珍か、「みずから、使持節・都督倭百済 新羅 任那 秦韓(辰韓) 慕韓(馬韓)六国諸軍事・ 安東大将軍・倭国王」に除正されるように求めている。
ここで、百済は、むかしの馬韓から起きているが、倭王珍のころ、百済に属していないむかしの馬韓の地を、慕韓と呼んだものとみられる。
倭王珍の主張では、百済、新羅などに、倭国の軍事支配権が及んでいるとの認識であったようにみえる。
中国の宋王朝としては、すでに、430年に百済の毗有王には、「使持節・都督百済諸軍事・鎮東大将軍」の爵号を与えている。そのため、倭国がわの主張を、全面的に認めるわけにはいかなかったようである。
珍のつぎの倭王の済(せい)には、451年に、「使持節・都督 倭 新羅 任那 加羅 秦韓 慕韓 六国諸軍事」と、「百済」だけをのぞいた形で称号を与えている。
新羅や任那などに、倭国の軍事支配権が及んでいたことを、一応、客観的存在である中国が、みとめる形になっている。
倭王珍の、百済にも倭国の軍事支配権が及んでいた、とする主張にも、あるていどの根拠がある。高句麗の広開土王の碑文に、「倭が、辛卯の年(391)に、来りて海を渡り、百残(百済)を破り、口口新羅を臣民とした」と読める文がある。
また、広開土王碑には、「(永楽)十四年(404)甲辰、倭は、不軌(無軌道)にも、帯方界に侵入し」とある。
「帯方界」は、むかし、魏や西晋の時代に存在した帶方郡のあった地域をさす。百済のあった地域の北である。百済の領域を通って、帯方界に侵入しているようにみえる。
軍事支配権のおよぶ範囲について、倭のがわの認識と、中国の宋王朝とで異なるところがあるが、倭のがわの最大侵攻領域と、それが時代がくだるとともに失われて行く状況とを、史料的根拠とともに地図に示せば、下図のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)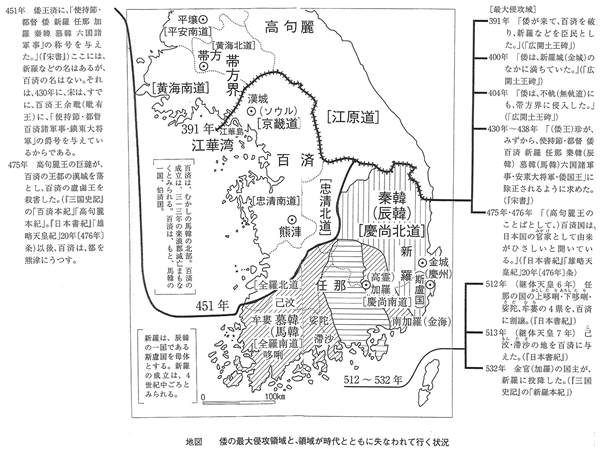
■任那四県の割譲事件
さらに、つぎのような事実もある。(以下、前の地図を参照。)
西暦400年前後の、朝鮮半島への出兵から百年ほど時代がくだり、継体天皇の六年、すなわち、西暦512年のことである。天皇は、穂積の臣押山(ほづみのおみおしやま)を百済(くだら)につかわして、筑紫(つくし)の馬四十匹を、百済に与えた。
穂積の臣押山は、任那のなかの、哆唎(たり)の国守であった。このように、任那へは、日本から国守をつかわしていた。
512年の冬の十二月に、日本で生まれたと伝えられる百済の武寧王(ぶねいおう)は、使いを大和朝廷につかわして、貢(みつぎ)をたてまつった。別に表(ふみ)によって、「任那国の上哆唎(おこしたり)、下哆唎(あろしたり)、娑陀(さだ)、牟婁(むろ)の四県(前の地図参照)を百済に与えてほしい。」とのべた。
これについて、穂積の臣押山が奏上した。
「この四県は、百済に近接し、日本からは遠くへだたっております。四県と百済とは朝夕に通いやすく、鶏や犬も、どちらの国のものか区別がつかないほどです。いまこれらの四県を、百済に与え、同じ国にすれば、これらの地をたもつ策としては、これにまさるものはないでしょう。たとえ百済に与えてその国にあわせても、後世には危いことがあるかもしれません。しかし、このまま切りはなしておいたのでは、とても何年とは、守りきれないでしょう。」
大伴(おおとも)の大連(おおむらじ)の金村(かなむら)は、穂積の臣押山の意見に同意し、天皇に奏上した。
そこで、継体天皇は、物部(もののべ)の大連麁鹿火(おおむらじあらかひ)の使いとして、難波(なにわ)の館(外国使臣のための客舎)につかわし、望みのままに、四県の地を与えるむねの勅を、百済の使いに伝えようとした。
ところが、物部の麁鹿火の妻が、夫にかたくいましめて言った。
「住吉(すみのえ)の大神(おおかみ)は、海のかなたの金銀の国、高麗(こま)[高句麗]・百済・新羅・任那などの国を、応神天皇にお授けになりました。そこで、神功皇后は、大臣の武内の宿禰とはかって、国ごとに官家(みやけ)をおいて、海表(わたのほか)の蕃屛(まがき)[海外の属国]とされました。その後、ながい年月を経て今日に至っています。もし、四県を百済に割譲するならば、もと定めた区域と違うことになります。そうすれば、後世の非難をまぬがれないでしょう。」
物部の麁鹿火がいう。
「お前の言うことは、まことにもっともだ。しかし、勅命に背(そむ)くわけに行かない。」
妻は、さらにきびしく、いさめて言う。
「病気だと申しあげて、勅命を伝えることをおやめなさい。」
麁鹿火は、ついにそのことばに従った。
そこで、朝廷では、使いを別の人にあらためて、百済の使いに勅を宣し、望みのままに、任那の四県を、百済に与えた。
このとき、勾(まがり)の大兄(おおえ)の皇子(みこ)(のちの安閑天皇)は、事情があって、四県割譲の評議に関与していなかった。
あとで、事情を知り、おどろき、あらためようとした。
「応神天皇が、官家を置いた国を、軽々しく、与えてはならない。」
別の使いを難波につかわして、百済の使いに、命令を改め伝えた。
しかし、百済の使いは答えた。
「父君の継体天皇が事情をお考えになり、勅命によって、四県をお与えになったのです。その子である皇子が、勅命にたがい、命令を改めて発するということがありえましょうか。これは、かならず、虚(いつわりごと)でしょう。たとえ、ほんとうのことであるとしても、天皇の勅は重く、皇子の命令は軽いはずです。」
こう答えて、百済に帰ってしまった。
世間では、つぎのような流言があった。
「大伴の大連金村と、哆唎(たり)の国守の穂積の臣押山とは、百済から、賄賂(わいろ)受けとったのだ。」
以上は、いわゆる「任那四県割譲事件」の緊迫したやりとりである。
六世紀はじめの継体天皇の時代に、物部の麁鹿火の妻のことばにあるように、朝鮮半島の官家(みやけ)は、神功皇后と武内の宿禰とがおいたものであると、一般に認識されていたのである。麁鹿火の強い妻。その個性とことばには、臨場感がある。おそらくは、事実そのようにのべたのであろう。そして、それが世間に伝えられたのであろう。
もし、これが麁鹿火の妻のことばでなかったとしても、六世紀はじめの継体天皇の時代に、朝鮮半島の官家は、神功皇后と武内の宿禰とがおいたものという認識があったことを思わせる。
神功皇后は実在しなかったとか、朝鮮半島への出兵は存在せず、推古朝の新羅征討の事実など、後世の七、八世紀の史実をモデルに創作された架空の物語である、などとしたばあいには、歴史のすじみちが、まったく見えてこない。任那四県の割譲の話までも、後世の創作とするのであろうか。つじつまの合わない話だらけになってしまう。
■鉄鋋(てってい)
『古事記』『日本書紀』『延喜式』などは、神功皇后の陵墓の所在地を、つぎのように記す。 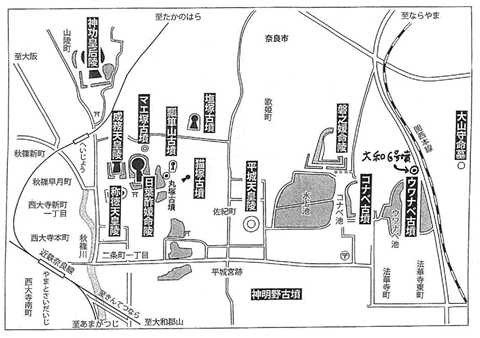
・『古事記』……狭城(さき)の楯列(たてなみ)の陵(みささぎ)
・『日本書紀』……狭城の楯列の陵
・『延喜式』……狭城の楯列池上陵
奈良県奈良市佐紀町から歌姫町・法華寺町にかけての、奈良盆地北部、佐紀丘陵南斜面にかけて、佐紀盾列古墳群(さきたてなみこふんぐん)が存在する。四、五世紀ごろの古墳とみられる。
神功皇后陵、成務天皇陵とよばれる古墳が、ここに存在する。
「佐紀盾列古墳群」は、大きく、東群と西群にわけられる。東群より、西群が古式であるといわれている。
「西群は、四世紀後半から五世紀前半ごろの、東群は五世紀中葉から後半ごろの築造と考えられる」(大塚初重・小林三郎編『古墳辞典』東京堂出版刊)。神功皇后陵古墳は西群に属する。
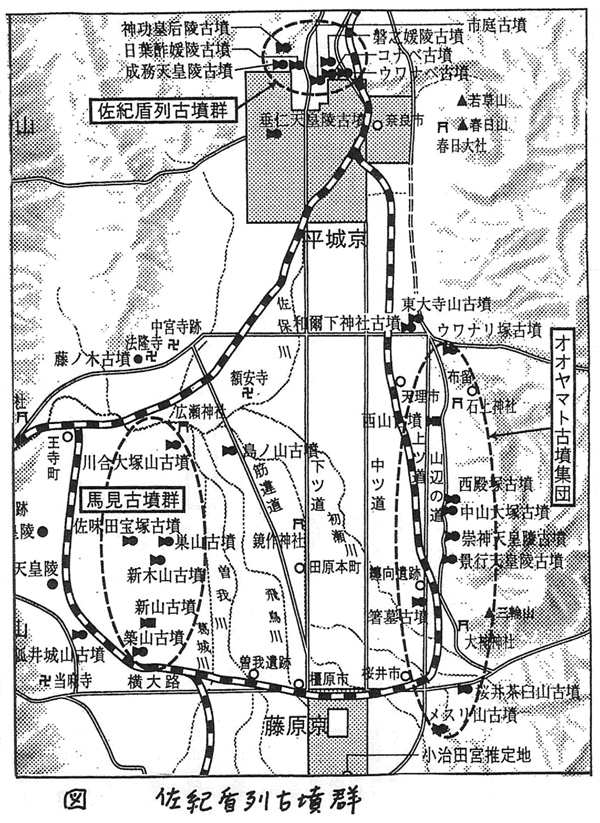
『日本書紀』の「神功皇后紀」四十六年の条に、百済の王が、日本の使臣に、「鉄鋋(ねりかね)40枚」をあたえたとの記事がみえる。
鉄鋋は、鉄材であるが(貨幣ではないかとみる説もある)、その実物とみられるものが、佐紀盾列古墳群から出土している。
すなわち、佐紀盾列古墳群の東群に属する宇和奈辺(うわなべ)古墳の陪塚の一つの、大和六号墳から、多量の鉄鋋が出土した。大型の鉄鋋(重さ200~700グラム)が282枚、小型の鉄梃(重さ20グラム)が590枚、計872枚が、鉄製斧頭102、鉄製鍬(くわ)先または鋤(すき)先179、鉄鎌139、鉄刀子状工具284などとともに出ている。
鉄鋋はまた、新羅の故郷、慶州の金冠塚などからも、多量に出土している。森浩一・石部正志両氏は、この鉄鋋について、つぎのようにのべている(「古墳文化の地域的特色5畿内およびその周辺」『日本の考古学Ⅳ-古墳時代』〈上〉所収、河出書房新社刊)。(傍線を引き、その部分をゴシックにしたのは、安本。)
「五世紀初頭を中心にした約一世紀間に構築された畿内の大古墳のうちで、多数の鉄製武器類を副葬する例は、河内の古市誉田(ふるいちこんだ)古墳群、和泉(いずみ)の百舌鳥古(もず)墳群がとくに顕著である。大和では、河内・和泉ほどではないが、おなじ傾向がこの佐紀古墳群と馬見(うまみ)古墳群にあらわれている。南朝鮮に鉄の産地があったことは『魏志』の東夷伝弁辰の条(「国鉄を出す。韓・濊(わい)・倭みな従ってこれを取る、………」)にうかがうことができるので、大和勢力の南鮮出兵の盛衰が古墳に副葬された鉄素材や鉄製品の増加や減少の傾向に関係があるとすれば、奈良盆地の古墳群のうちでも、この佐紀古墳群は南鮮出兵に関与したか、出兵の影響を直接につよくうける集団の古墳群と想定したい。」
朝鮮半島から出土した鉄鋋を下記に示す。 
森浩一は、また、つぎのようにものべている(「古墳文化に現われた地域社会・畿内」『日本考古学講座』5〈古墳文化〉、河出書房刊)。(文中に、傍線を引き、その部分をゴシックにしたのは、安本。)
「大和六号墳は、単に倍塚の内容究明に役立ったばかりではない。われわれの興味をひくのは、鉄板の形状と鉄の埋蔵量が小古墳としては予想を飛びこえて多いことである。この鉄素材(鉄鋋。写真参照)の形と大きさは、古代の著名な鉄産地であった南鮮新羅の主要な古墳から出土する鉄素材と類似し、五世紀代には大量の鉄が、素材のままで南鮮から輸入されたことがあるという推測が生じる。文献の研究成果からいっても四世紀後半から五世紀にかけては大和朝廷が南鮮侵略に成功していた時期であるから、大量の鉄素材の輸入も充分可能であったわけであり、この現象によって説明困難な大和朝廷の南鮮侵略の目的そのもののうちに鉄素材の獲得があったとも考えられる。
鉄素材に限らず鉄製武器、工具が畿内中心部では四世紀から五世紀中頃にかけて、巨大な古墳には突然変化的に埋蔵量が増大している。
実例は省略するが、このことは大和朝廷を中心とする有力な豪族が南鮮侵略によって多量の鉄を独占する方法を確保したことを示しており、彼らはおびただしい武器や農工具をこしらえ、武力においても生産力においても他地方の豪族達を圧倒し、やがては、この鉄の確保が彼らを支配する原動力となっていったのであろう。」
このように、四世紀後半から五世紀にかけての大和朝廷の南朝鮮侵略を裏づける考古学的資料が、多数存在している。
■倭の五王
筑波大学名誉教授の川西宏幸(かわにしひろゆき)氏の著書『古墳時代政治史序説』(塙書房、2012年刊)によれば、大型古墳の時期の実年代推定値は、下の表のようになっている。
その中で、川西氏は円筒埴輪から応神天皇陵や仁徳天皇陵は430~500年くらいの築造ではないかと考えている。
(下図はクリックすると大きくなります)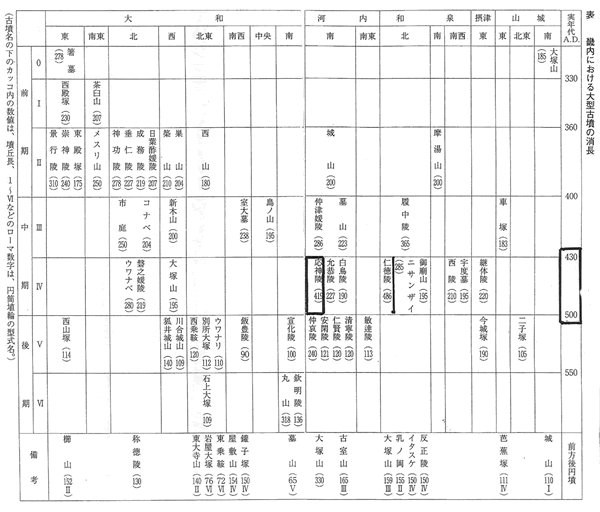
下図は倭の五王関係の資料である。
天皇1代10年説で推定する仁徳~雄略天皇の年代と中国文献と比較すると、讃は応神天皇と仁徳天皇のどちらでも考えられるが、
『日本書紀』に応神天皇の時代に百済の「直支王」の記載がある。この百済の直支王(腆支王)の在位の時期を、『三国史記』は405年~420年と記す。これから倭王讃を応神天皇とする方が妥当と考えられる。
(下図はクリックすると大きくなります)
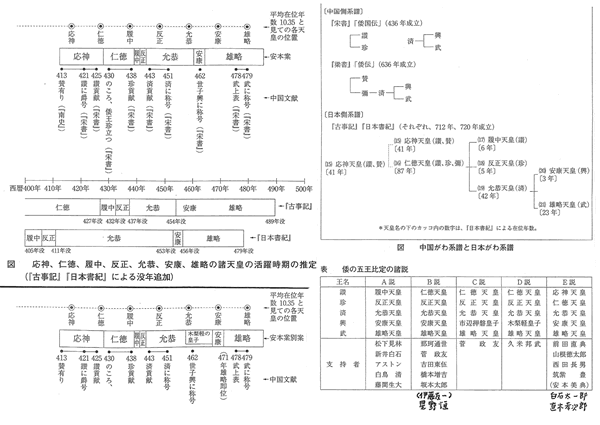
『古事記』と『日本書紀』とで、下の図のように天皇の没年干支に差がある。一般に、『古事記』の方が時代が新しいので、信憑性があるのではないかと考えられている。しかし下記の井上光貞氏の意見がある。
井上光貞氏著『日本の歴史1 神話から歴史へ』(中央公論社、1965年刊)
「ただ、この崩年干支は、あまり信用できない。古事記のできたころにはすでに、何かの記録によってできあがっていたものとは考えられるが、その書かれた内容をすべて信用することには賛成しかねるからである。崩年干支によってあまりはっきりした数字をだすことは、しばらくあきらめるほうが無難であろう。」(『古事記』文註)
このように考えると崇神天皇は古く設定し過ぎであり、応神・仁徳天皇あたりでも、あやしいと考えた方がよい。
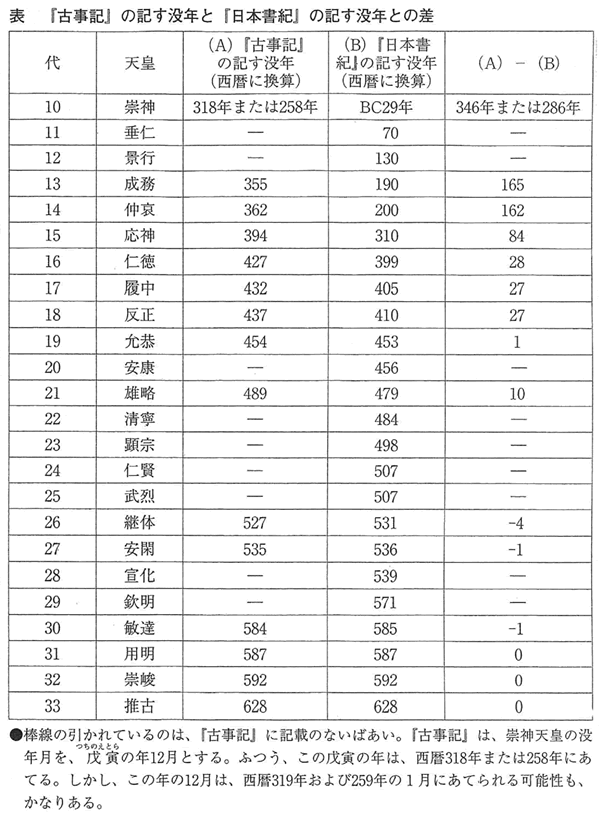
中国文献の記す外国の王の系譜記事は、一般に、かなり粗雑である。たとえば、「宋書」(485年成立)、『梁書』(629年成立)よりも、ずっとのちに成立した『新唐書』(1060年成立)をとりあげてみよう。
中国の文献の記す天皇の系図と、わが国の史書の記す系図とを、かなりなていど対照できるのは、『新唐書』である。
『新唐書』も、『宋書』『梁書』と同じく奏勅撰書であるが、『新唐書』の記す天皇の系譜は、誤りだらけといってよい。
『新唐書』は、「天智死して、子の天武立つ。」と記す。誤りである。天武天皇は、天智天皇の弟である。
『新唐書』は、推古天皇を、「欽明の孫女(まごむすめ)」と記す。誤りである。
推古天皇は、欽明天皇の子である。
『新唐書』は、神功皇后を、開化天皇の「曾孫女(ひまごむすめ)」とする。誤りである。神功皇后は、開化天皇の五世の孫である。
『新唐書』は、文武天皇が死ぬと、「子の阿用立つ。」と記す。まったくの誤りである。文武天皇のつぎに立ったのは、天智天皇の子の元明天皇[名は、阿閉(あべ)]である。『新唐書』は、元明天皇が死ぬと、「子の聖武立つ。」とある。
誤りである。元明天皇のつぎは、「子の元正天皇」である。聖武天皇は、元明天皇の孫である。
朝鮮の歴史書、『三国史記』の「新羅本紀」も、中国文献の誤りをわざわざ記している。「第二十九代武烈王は、第二十五代真智王の孫である。『唐書』に、第二十八第真徳王の弟としているのは誤りである。」武列王は、かなり時代がくだり、654年に即位した人である。(活躍年代の同時代性が重要)
■年代論における「類ハッブル定律現象」について
京都大学人文科学研究所の教授であった尾崎雄二郎氏は、私の編集していた『季刊邪馬台国』14号(1982年)に、「古代里程記事における類ハッブル定律現象について」という文章を発表している。
その要点は、つぎのようなものである。
「天文学で、地球から離れているほど、星雲の遠ざかる速度も大きいという『ハッブルの定律』がある。
昔の人にとっては、都から離れるほど、その里程は、感覚的にふえていくものらしい。古代の里程記事においては、類ハッブル現象が見られるのではないか。」
都から遠く離れた場所は、遠いほど、実際の里程以上に、大きく離れているように、認識される。そして、そのように記載されがちであるというのである。
これは、尾崎雄二郎が、邪馬台国の里程記事に関連して、中国文献のいろいろな事例などをあげて論じられたものである。
尾崎雄二郎はのべる。
「自分の故郷というかホームグラウンドというか、とにかくベースになるものから離れれば離れるほど何らかの比例で主観的な距離はふえていくのではないか。山の高さも、それが高ければ高いだけ、われわれの普通の生活平面から遠ざかるわけですから、その分だけ、実際の差を超える差が加わっていくのではないか、と思うのです。」
ところで、距離についていえるこのような傾向は、また、「年代」についてもいえるようである。
古い時代のことは、客観的な年代よりも、さらに古めに認識されがちのようである。
『日本書紀』の記す古代の年代は、大はばに延長されている。年代が、事実よりも、古めに記載されている傾向がある。このことは、すでに、多くの人が論じているとおりである。
このような傾向は、わが国の史書ばかりではない。『三国史記』などの韓国の史書でも、古い時代の記事では、また、みとめられる。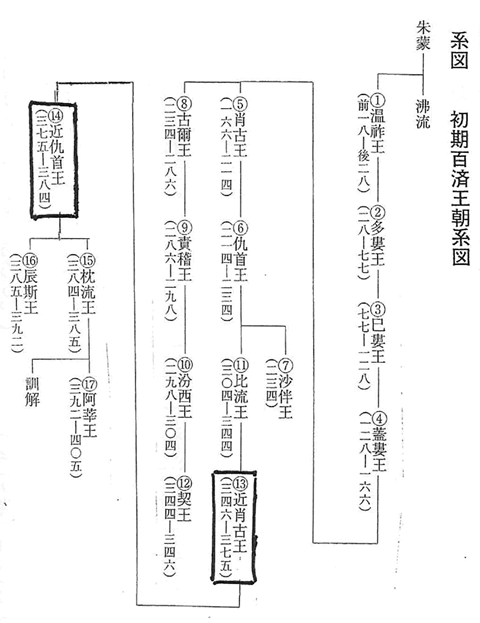
そのことは、明治時代の東洋史学者の那珂通世(なかみちよ)が、その著『上世年紀考』のなかで、つぎのようにのべているとおりである。
「韓史も上代に遡(さかのぼ)るにしたがい、年暦の延長せりと覚(おぼ)しきところあることは、ほとんど我が古史に異ならず。」
『三国史記』の「新羅本紀」は、倭国の女王、卑弥乎(呼)のことを、西暦173年にあたる条のところで記している。「高句麗本紀」では、実在の王である根拠のある大祖大王が、位をゆずったとき、年齢は百歳で、在位は九十四年間であったと記している。
このような傾向は、現代人の心にも、無意識のうちに強く働いているようである。
『日本書紀』では、神武天皇は、西暦紀元前660年に即位したことになっている。
旧石器捏造事件のおりは、五十万年、七十万年と、年代がくりあがっていっても、専門家も、ふしぎと思わなかった。
なにか、古いものが出土したというばあい、マスコミに大きく報じられることがある。しかし、新しいものが出土したばあいは、ほとんど報道されないことが多い。
人間は、無意識の、このような心理的な傾向をもっていることは、年代などの問題をリアルに論ずるためには、強く意識化しておく必要がある。そうでないと、ともすれば、年代は、古いほうへ、古いほうへと流されがちになる。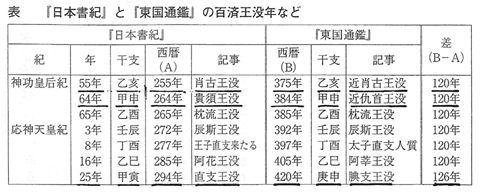
このように、『古事記』『日本書紀』の記述する年代は古すぎると考えられ、史書における兄弟、親子の記述も不正確であることが考えられる。
倭の五王を天皇に比定しする現時点での有力な仮説は、E説の
讃=応神
珍=仁徳
済=允恭
興=安康
武=雄略
ではないだろうか。







