今回は第376回(前々回)の話の続きになり、内容が重複するところがあります。また一部は第376回のサイトに行って参照しています。
■笠井新也説の紹介と批判
現在、箸墓古墳を、卑弥呼の墓とする説が、「邪馬台国畿内説」をとる人々のあいだでかなりさかんである。
箸墓古墳を卑弥呼の墓とする説を、はじめてとなえたのは、大正時代から昭和のはじめにかけて活動した考古学者、笠井新也である。
笠井新也は、基本的には那珂通世の説をうけいれながら、『古事記』の記す「諸天皇の没年干支」にもとづき説をたてた。
すなわち、笠井新也は以下のように論ずる。
(1)卑弥呼は、倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)である
卑弥呼については、九州の女酋とする説、大和朝廷に関係ある婦人とする説があった。卑弥呼の年代は、第十代の崇神天皇の時代である。「崇神天皇紀」に登場する「倭迹迹日百襲姫」は、崇神朝第一の女傑で、神意を奉じて奇跡を行ない、未然を識(し)って反逆を看破するなど、信頼と畏敬をうけるのに十分であった。卑弥呼はヒメミコトの意味で、高貴な婦人に対する尊称である。倭迹迹日百襲姫命は孝元天皇の皇女であり、姫命は卑弥呼の名称によく一致する。卑弥呼は「鬼道につかえ、よく衆をまどわす」とあり、倭迹迹日百襲姫命に似る。(「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫(一)」『考古学雑誌』第14巻、第7号、1924年4月)
(2)卑弥呼の墓は箸墓古墳である
「崇神天皇紀」に登場する「倭迹迹日百襲姫命」の墓に関する記述は『魏志倭人伝』記載の卑弥呼の墓の記述(箸墓伝説)に酷似する。『日本書紀』のなかで、陵墓については、所在地の記載のみであり、具体的な墓づくりの記述はこれだけである。「されば卑弥呼の冢墓とは、いわゆる百襲姫命の御墓である箸墓を指したもの」である。(「卑弥呼の冢墓と箸墓」『考古学雑誌』第32巻、第7号、1942年7月」)
笠井新也氏は、卑弥呼に、『日本書紀』の「祟神天皇紀」に記述の倭迹迹日百襲姫をあてはめ、卑弥呼の墓に倭迹迹日百襲姫の墓とされる箸墓をあてはめる。
そして、笠井新也氏は、卑弥呼を「わが古代史上のスフィンクス」とよび、およそつぎのようにのべる。
「邪馬台国と卑弥呼とは、『魏志倭人伝』中のもっとも重要な二つの名で、しかも、もっとも密接な関係をもつものである。そのいずれか一方さえ解決を得れば、他はおのずから帰着点を見出すべきものである。すなわち、邪馬台国はどこであるかという問題さえ解決すれば、卑弥呼が九州の女酋であるか、あるいは、大和朝廷に関係のある女性であるかの問題は、おのずから解決する。また、卑弥呼が何者であるかという問題さえ解決すれば、邪馬台国が畿内にあるか九州にあるかは、おのずから決するのである。したがって、私は、この二つのうち、解決の容易なものから手をつけて、これを究明し、その他、考えおよぶのが、怜悧な研究法であろうと思う。」(「邪馬台国は大和である」〔『考古学雑誌』第12巻第7号、1922年3月〕)
「思うに、『魏志倭人伝』における邪馬台国と卑弥呼との関係は、たがいに密接不離の関係にあり、これが研究は両々あいまち、あい援(たす)けて、初めて完全な解決に到達するものである。その一方が解決されたかに見えても、他方が解決しない以上、それは真の解決とは言いがたいのである。たとえば錠と鍵との関係のごとく、両者相契合(けいごう)[割符(わりふ)の合うように合うこと]して始めてそれぞれしい錠であり、正しい鍵であることが決定されるのである。」(「卑弥呼の冢墓と箸墓」『考古学雑誌』第32巻、第7号、1942年7月) 卑弥呼はだれか、という問題に正面からとりくんだことによって、笠井新也説は、大きな構造性を獲得した。
笠井新也はその年代論を、その論文「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫命」において、およそつぎのように展開する。
「卑弥呼の擬定はまず年代の決定から出発しなければならない。卑弥呼の『魏志』に現れている年代を、我が国史の年代に引きあてるときは、あたかも崇神天皇の御代にあたることは、私の信じて疑わないところである。わが上古史における年代は、菅政友(かんまさとも)・那珂通世等の『古事記』年紀の研究によって、信憑すべき基礎が置かれ、しかして成務天皇以下歴代の崩御年紀が明確となったことは学界のひとしく認めるところである。しかるに崇神天皇の崩年については、成務天皇崩年の乙卯(きのとう)を標準として、それを一運(めぐ)り中の戊寅(つちのえとら)とすべきかあるいは一運り以前の戊寅とすべきか、これを決定すべき確実な資料を欠いている。
那珂通世はその著『上世年紀考』において、このことに論及し。
『三十七年(一運り)では、次の仲哀天皇も、在位わずかに七年であるから、四朝を合わせて、ただの四十二年である 仲哀天皇の四世の祖である崇神天皇の崩年は、四世の孫の崩年から、ただ四十二年まえであるとは思われないから、三朝の年数は、前の表のように、九十七年と見るほうが妥当であろう。』
といったのは妥当の見解というべきである。
崇神天皇の没年の258年は、卑弥呼の死んだ正始八年(247)もしくは九年(248)をへだたる十年もしくは十一年の後にあたるのである。すなわち卑弥呼の死と崇神天皇の死とは、わずかに十年前後しか相違しないので、卑弥呼の時代はすなわち崇神天皇の時代であることは、もはや疑いを容れないといってよかろう。
要するに、卑弥呼の活動年代は、あたかも崇神天皇の時代にあたっておって、さらにくわしくいえば、彼女の死は、天皇の崩御に少しく先立つものであることは、ほとんど確実というべきである。されば卑弥呼をわが国史中に求めようとすれば、必然崇神天皇の朝に求めなければならないのである。」
すなわち、笠井新也は、大きくは那珂通世の年代論によっているが、より具体的直接的には、『古事記』の記す諸天皇の没年干支によって立論している。それによって卑弥呼の活動年代は、崇神天皇の時代にあたるとしているのである。
そして、卑弥呼に崇神天皇の時代に活動した倭迹迹日百襲姫命をあてはめる。
『古事記』には分注(本文のなかに行をわけて書いた注釈)の形で、第十代崇神天皇以下十五人の天皇について、その没した年が干支で記されている。いわゆる『古事記』分注の「没年干支」である。
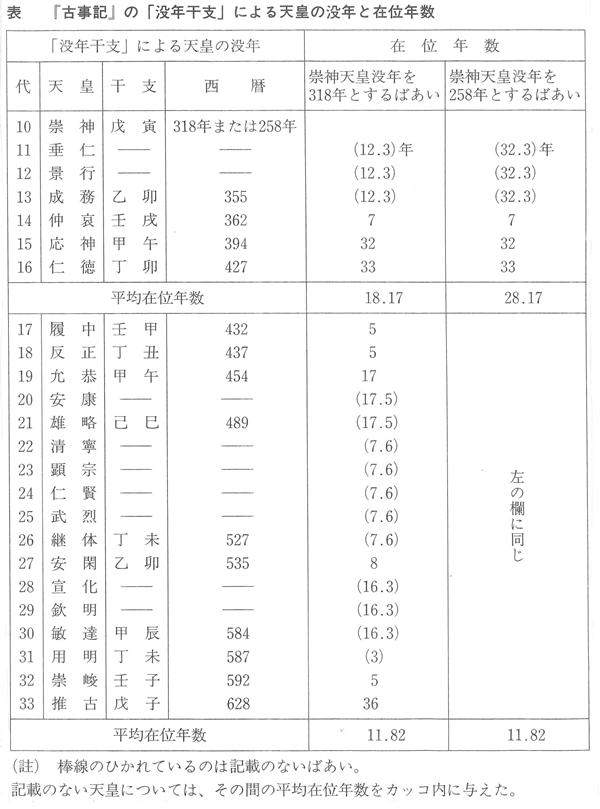
ここで、干支についての基礎を説明する。
干支による紀年法では、いま、最初の年を甲子(きのえね)の年とすれば、翌年は、乙丑(きのとうし)の年となる。その翌年は丙寅(ひのえとら)の年である。(下記コラムⅠ を参照)
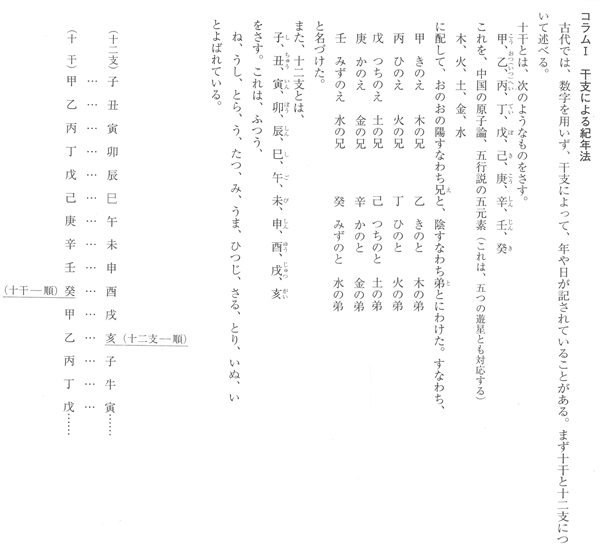
このような組みあわせを一回行なうと、とうぜん、十干のほうは終わってしまっても、十二支のほうは二つあまる。そこで十干をもう一度はじめからくりかえして組みあわせていく。十二支のほうも終わりまでくれば、またはじめからくりかえす。同じようにしてつづけていくと、十と十二の最小公倍数である六十年目で、いちばんはじめの甲子(きのえね)の年がもどってくる。
なお、干支による紀年法は、中国の戦国時代(紀元前476年~紀元前221年ごろ)にはじまったものらしく、殷の時代にはない。殷代には、年は、何何王の何年というように記されていた。ただ、殷代には、日々に六十干支をふっていく記日の方法はあった。
干支のよみかたは、たとえば、丙午「ひのえうま」という仮の訓でよむよりも、「へいご」と音でよむほうがよいと思われる。しかし、ここでは、いちおう仮の訓でよんでおいた。なお、干支は、方角や時の名前としても用いられる。たとえば、北を子、南を午としたので、現在でも南北の線を子午線とよんでいる。
なお、暦のばあい、「乙」は、ふつう、「いつ」とよむ。たとえば、645年、「乙巳(いっし)の年(とし)」に、中大兄(なかのおおえ)の皇子(おうじ)と中臣(なかとみ)の鎌足(かまたり)とによって、蘇我(そが)の入鹿(いるか)が誅滅される、大化の改新がはじまる。645年のときの変事を、「乙巳(いっし)の変(へん)」という。「乙巳(おつし)の変」とはいわない。
また、「甲子」は、「こうし」とも、「かっし」ともよむ。甲子園は、1924年甲子(こうし)の年にできた。 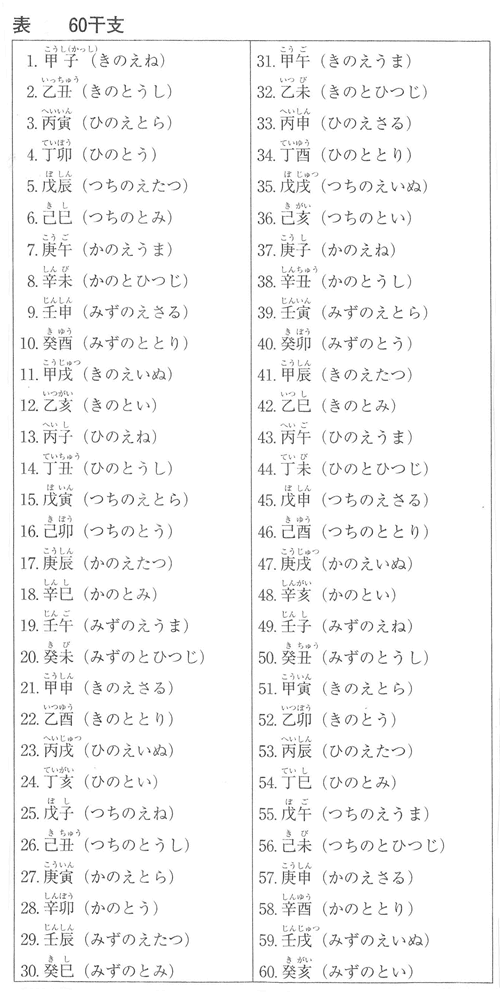
前に述べた『古事記』の「没年干支」について、東京大学の教授であった古代史家の井上光貞は、『神話から歴史へ』(『日本の歴史1』中央公論社、1965年刊)のなかで、つぎのようにのべている。
「この崩年干支(没年干支のこと)は、あまり信用できない。古事記のできたころにはすでに、何らかの記録によってできあがっていたものと考えられるが、その書かれた内容をすべて信用することには賛成しかねるからである。崩年干支によってあまりはっきりした数字をだすことは、しばらくあきらめるほうが無難であろう。」
(a)「奈良七代七十年」
奈良時代は第四十三代元明天皇から、第四十九代の光仁天皇までの七代、すなわち、元明・元正・聖武・孝謙・淳仁・称徳・光仁の七代で、74年(710~784)。この間、一代平均10.57年。
(b)「君、十帝を経(へ)て、年(とし)ほとほと(ほとんど)百」
この文は、奈良時代史の基本文献である『続日本紀』の、淳仁天皇の天平宝字二年(758)8月25日の条に記されている。これは、第三十六代の孝徳天皇から、第四十六代の孝謙天皇までが、十代で、104年ほどであることをのべている。
『古事記』の没年干支から、前の表で示したように、崇神天皇没年を318年とすると、第10代の崇神天皇から第16代仁徳天皇までの平均在位年数は18.17年となる。しかし、崇神天皇没年を258年(笠井新也説)とすると、第10代の崇神天皇から第16代仁徳天皇までの平均在位年数は28.17年となり、他の平均在位年数である11.82や18.17年とかけ離れ、不整合となる。
筑波大学教授の経済学者、平山朝治氏は、最小二乗法といわれる統計的方法により、古代の天皇などの活躍時代についての区間推定(誤差の幅をつけた推定)をしておられる(『季刊邪馬台国』16号、1983年。)
平山朝治氏は、第三十一代用明天皇から、奈良時代の終わりの第四十九代光仁天皇までのデータは、大略直線とみなせるとし、直線をあてはめる。
以下詳細は第376講演記録参照
■箸墓古墳の年代
2008年に、ホケノ山古墳の、正式のくわしい報告書『ホケノ山古墳の研究』(奈良県立橿原考古学研究所編集・発行、2008年)が刊行されている。
そこでは、再利用の可能性のない二本の小枝資料の、炭素14年代測定が行なわれている。そして、四世紀を中心とする新しい年代が得られている。 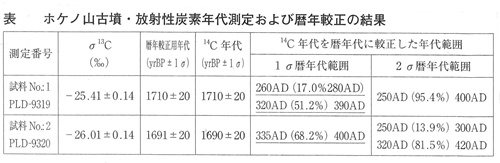
ホケノ山古墳から出土した「およそ12年輪」の二つの小枝について、炭素14年代測定法によって年代を求めた結果、右表、および、下図に示ざれているようなものである。
これらの表、および、図は、原報告書にあるものを、そのままコピーして示したものである。
(下図はクリックすると大きくなります)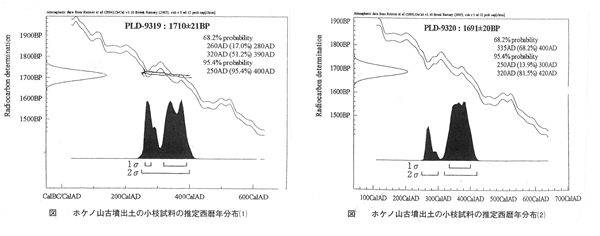
表において、「1σ(しぐま)暦年代範囲」のところに、下線が引いてある。これも、原報告書のままである。
これは、つまり、ホケノ山古墳の推定年代の可能性の大きいのは、三世紀ではなく、四世紀であることを示している。図をみても、その状況は、うかがわれる。
いま、上図、のうえに、方眼紙をあて、ホケノ山古墳出土の二本の小枝が、西暦300年以後のものである確率(黒い山の面積)を求めれば、下図のようになる。
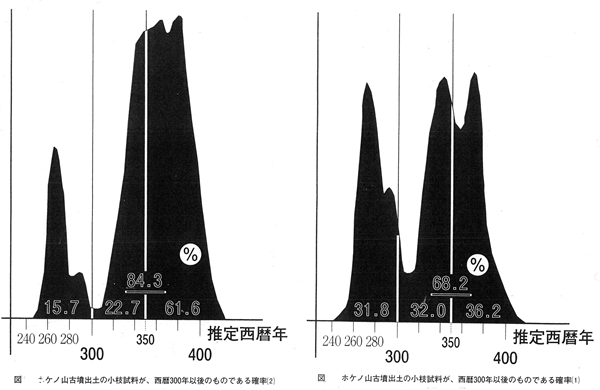
これによれば、これらの小枝試料が、西暦300年以後、つまり、四世紀のものである確率は、それぞれ、68.2パーセント、および、84.3パーセントとなる。
つまり、三世紀のものである確率よりも、四世紀のものである確率のほうが、二倍以上大きい。上の左図では、五倍以上大きくなっている。
(84.3/15.7=5.37)
四世紀の中では、四世紀の前半であるよりも、四世紀の後半である確率のほうが、大きくなっている。
「明日、雨である確率は、70パーセント」というのと同じぐらいの確からしさで、「ホケノ山古墳の築造が四世紀のものである確率は、約70パーセント」といえるデータが存在するのである。
考古学の分野では、考古学者の大塚初重氏がのべておられるような、つぎの基本的な原則がある。
「考古学本来の基本的な常識では、その遺跡から出土した資料の中で、もっとも新しい時代相を示す特徴を以てその遺跡の年代を示すとするのです。」(『古墳と被葬者の謎にせまる』【祥伝社、2012年刊】)
この原則をもってすれば、ホケノ山古墳から出土した資料の中で、もっとも新しい時代相、すなわち年代を示すのは、すでに紹介した二本の、年輪十二年ほどの小枝である。
そして、この二本の小枝については、原報告書の『ホケノ山古墳の研究』に、「小枝については古木効果の影響が低いと考えられるため有効であろうと考えられる」と記されている。
つまり、試料として用いられるのにふさわしいということである。
そして、この二本の小枝の示すところは、上図の示すように、四世紀で、しかも、四世紀の後半の確率が大きいということである。
この事実を、サポートするようなデータは、ほかにも、いくつもあげられる。
箸墓古墳の年代も、そのような例のひとってある。
寺沢薫氏の土器編年によれば、ホケノ山古墳は庄内3式期のもので、庄内3式期のつぎの時期の土器型式は、「布留0(ゼロ)式期古相」である。
纒向古墳群に属する箸墓古墳は、布留0式期古相のものとされている。また、同じく纒向古墳群に属する東田大塚古墳も、布留0式古相のものとされている。
そして、箸墓古墳からは、三個の桃核(桃の種の固い部分)が出土している。東田大塚古墳からは、一個の桃核が出土している。
これらの、合計四個の桃核は、箸墓古墳、および、東田大塚古墳から出土した資料の中で、もっとも新しい時代相を示している。
そして、これらの桃核の炭素14年代測定法による測定値は、ホケノ山古墳出土の小枝試料の年代測定値に近い年代を示している。
いま、ホケノ山古墳出土の二つの小枝試料、箸墓古墳出土の三つの桃核試料、東田大塚古墳出土の一つの桃核試料の合計六つのデータを用い、これらの西暦推定年代の分布を示せば、下の右図のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)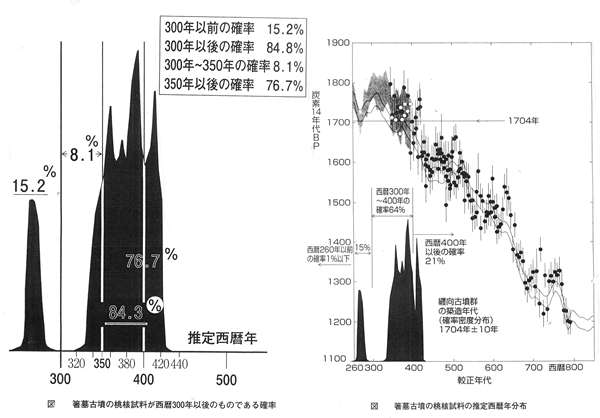
年代分布を描くための計算は、数理考古学者の新井宏氏にしていただいた。
上の右図について、ホケノ山古墳のばあい、(前のホケノ山の小枝の図と)同じような図を描けば、上の左図のようになる。
この図をみればわかるように、これらの三つの古墳の築造の時期が、西暦300年以後である確率は、84.8パーセントとなる。西暦350年以後である確率でさえ、76.7パ-セントとなる。この上の左図は、ホケノ山古墳だけの結果である前のホケノ山の小枝の図と、はなはだ整合的である。
これらは、すべて、四世紀のものである確率が大きい。
なお、箸墓古墳についての年代測定データは、『箸墓古墳周辺の調査』(奈良県橿原考古学研究所、2002年刊)による。
この報告書、『箸墓古墳周辺の調査』のなかで、寺沢薫氏は、箸墓古墳出土の「桃核」について、「明らかに布留0式古相の土器群とPrimaryな状況で共存したと判断された桃核」と記しておられる。あとから、なにかの事情で、まぎれこんだりしたものではない、ということである。
また、桃核試料については、名古屋大学年代測定総合研究センターの中村俊夫教授が、「クルミの殼」について、「クルミの殼はかなり丈夫で汚染しにくいので、年代測定が実施しやすい試料である。」(日本文化財料学学会第26回大会特別講演資料)とのべておられることが、参考になるであろう。
そして、纒向遺跡を発掘し、奈良県立橿原考古学研究所の所員で、纒向遺跡を発掘し、大部の報告書『纒向』を執筆された考古学者の関川尚功(ひさよし)氏は、つぎのようにのべている。
「箸墓古墳とホケノ山古墳とほぼ同時期のもので、布留1式期のものであり、古墳時代前期の前半のもので、四世紀の中ごろ前後の築造とみられる。」(『季刊邪馬台国』102号、2009年刊)
この関川氏の見解は、炭素14年代測定法の測定結果の年代とも、よく合致している。関川尚功氏の見解などを、もっと尊重すべきである。
このような議論については、このシリーズの拙著『邪馬台国は、99.9%福岡県にあった』(勉誠出版、2015年刊)にくわしい。
■2009年白石太一郎氏の見解
最近、国立歴史民俗博物館の研究グループか実施した、箸墓古墳周辺の出土土器の付着物[コゲや煤(すす)]の炭素年代測定の結果が報告されている(春成ほか、2011年)。それによると、箸墓古墳の造営期にあたる布留0式土器の年代は、西暦240~260年代という数値がえられたということである。この年代は、さきに紹介した最近の大型前方後円墳の出現年代に関する多くの考古学研究者の想定と一致しており、こうした考古学的な年代想定が、自然科学的な年代決定法によっても支持されるものであることを示すものとして、筆者はきわめて重要視している。
箸墓(はしはか)は卑弥呼(ひみこ)の墓である---。つい最近(2009年)、こんな説が新聞やテレビのニュースで大々的に報道されるや、大騒動(もはや話題となっているなどというレベルではない)となり、それはいまも続いている。
いったいなぜ、こんな大騒動か起きたのだろうか。
千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館[平川南(みなみ)館長。以下、歴博と略す]の研究グループが、「炭素14年代測定法」という「科学的な方法」を用いて、奈良県桜井市にある箸墓古墳が、ほぼ邪馬台国(やまたいこく)の女王卑弥呼が死んだとされる西暦240~260年ごろに築造されたことが推定できた、と発表した。
ところが、このような「推定」が科学的には成立しえないとするデータや根拠が、他の研究機関や研究者から、同じく炭素14年代測定法を用いて、すでにいくつも報告されている。ただそのような報告は、マスメディアで報じられていないだけである。
いま、「箸墓古墳は卑弥呼の墓である」という仮説を「歴博仮説」と呼ぶことにしよう。すると、歴博仮説は成立しえないという、歴博仮説に対する明確といってよい反証が、いくつも挙げられる。どうも他の機関や研究者が、歴博の研究グループの一連の炭素14年代測定法の研究結果に対して、有力な反証や批判を提出するたびに、この種の騒動が意図的に引き起こされているようにみえる。(注:旧石器捏造事件と似たような構造)
歴博の研究グループは、反証や批判が報告されると、その反証を押し潰すためにマスメディアを巧みに動員しているのではないか? 歴博仮説にとって有利な結果がまたも得られました、と大報道に持ち込むことによって批判や反証を封じようとしているのではないか? こんな疑念が研究者たちの間で広がり、波紋は大きくなりつつある。
マスメディアでの華やかな大宣伝のすぐあと、2009年5月31日、早稲田大学で歴博の研究グループは、「箸墓古墳は卑弥呼の墓である」説を強い確信の言葉とともに述べた(発表者は春成秀爾(ひでじ)氏を中心とするメンバーである)。
ところが、その発表会の司会者で、日本考古学協会理事の北條芳隆東海大学教授が、そのとき、報道関係者に次のような「異例の呼びかけ」を行ったことを、『毎日新聞』が報じている。
「会場の雰囲気でお察しいただきたいが、(歴博の発表が)考古学協会で共通認識になっているのではありません」(『毎日新聞』6月8日付夕刊)
そして、北條教授はその後、自身のヤフーのブログで次のように記している。
「私がなぜ歴博グループによる先日の発表を信用しえないと確信するに至ったのか。その理由を説明することにします」
「問題は非常に深刻であることを日本考古学協会ないし考古学研究会の場を通して発表したいと思います」
「彼らの基本戦略があれだけの批判を受けたにもかかわらず、いっさいの改善がみられないことを意味すると判断せざるをえません」
「歴博発表」は信用できない、これは事情をよく知る学者、研究者たちの間で広がりはじめている共通認識のようにみえる。
それは、歴博研究グループが発表した際の会場の雰囲気や、続出した質問などからもうかがえる。ここで、「続出」という言葉を用いたが、これは私の判断ではなく、『毎日新聞』も「会場からはデータの信頼性に関し、質問が続出した」と報じている(2009年6月1日付)。
(下図はクリックすると大きくなります)

箸墓古墳は、「竪穴式石槨」をもっている?
白石太一郎氏は、その著『古墳の被用者を推察する』(中央公論社、2018年刊)のなかでのべる。
「故(かれ)、大坂山の石を運びて造る。則ち山より墓(みはか)に至るまでに、人民(おおみたから)相踵(あひつ)ぎて、手逓伝(たごし)にして運ぶ。時人(ときのひと)歌(うたよみ)して曰(い)はく、
大坂に 継(つ)ぎ登れる 石群(いしむら)を 手逓伝(たごし)に越さば 越しかてむかも」(『日本書紀』)
「箸墓古墳の北側の大池に転落している多数の川原石に混じって、ごく少量ではあるが扁平(へんぺい)な板石が採集されている。岩石学の奥田尚氏によると、それはこの大坂山、すなわち二上山系の芝山の玄武岩(げんぶがん)にほかならないとされている。畿内の前期古墳の竪穴式石室は、基本的には板石で構築されるから、この箸墓古墳の板石は竪穴式石室の石材である可能性が大きいと思われる。そう考えてよければ、この崇神紀の伝承は、箸墓の埋葬施設である竪穴式石室の石材にかかわる伝承ということになる。
奥田氏の調査・研究によると、箸墓古墳をはじめとするオオヤマト古墳群の前期古墳の竪穴式石室の石材には、この二上山系の板石が広く用いられていることか明らかにされている(奥田、2002年)。すなわち芝山の橄欖石玄武岩(かんらんせきげんぶがん)[箸墓、黒塚、西殿塚、東殿塚(ひがしとのずか)、下池山(しもいけやま)古墳など]、寺山のすぐ南の春日山の輝石安山岩(きせきあんざんがん)A[上ノ山(うえのやま)、天神山(てんじんやま)、黒塚、中山大塚(なかやまおおつか)、東殿塚古墳など]、明神山のすぐ北の亀ノ瀬付近の輝石安山岩B[メスリ山、櫛山(くしやま)古墳]などである。しかがって大坂山の石を運んだというのは、たんに箸墓古墳にとどまらず広くオオヤマ卜古墳群の前期古墳に共通する事実だったのである。」
2012年9月12日(夕刊の大阪本社版の『朝日新聞』夕刊に、箸墓古墳についての記事がのっている。
内容は、朝日新聞が情報公開請求で、宮内庁から入手した資料で明らかになった古墳の構造についてのものである。
その記事のなかで興味をひくのは、下図に示したものである。これは、「宮内庁の公開資料を元に作製」された「箸墓古墳後円部頂の想像図(イメージ)」である。 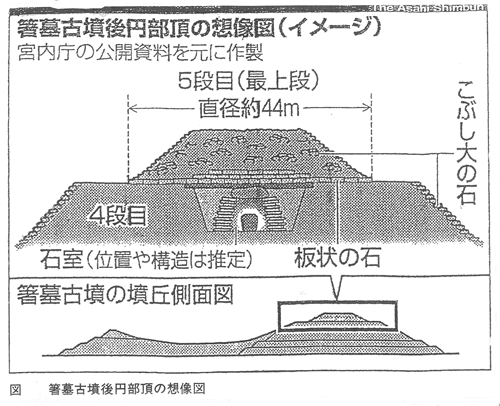
この図のどこが、興味をひくか。
それは、古墳の埋納部が、「竪穴式石室」のなかに、棺が納められている形に描かれている点である。
「竪穴式石室」は、考古学者によっては、「竪穴式石槨」ともよばれる。たとえば、岡山大学の教授であった考古学者の近藤義郎の編集した『前方後円墳集成』(山川出版社刊)では竪穴式石室」のことは、すべて、「竪穴式石槨」と記されている。
『魏志倭人伝』は、倭人の葬制を記し、「棺あって槨なし」とある。
ホケノ山古墳でも、木槨の中に木棺があり、『魏志倭人伝』の記述にあわない。
『三国志』の筆者は、葬制には関心をもっていた。つぎのように各国ごとに、いちいち書き分けている。
『韓伝』……「棺(内棺)ありて槨(外箱)なし。」
『夫余伝』……「厚葬(贅沢な埋葬)にして、槨ありて棺なし。」
『高句麗伝』……「厚く葬り、金銀財幣、送死に尽くす(葬式に使い果たす)。石を積みて封(塚)となし。松柏を列(なら)べ種(う)う。」(この記述は高句麗の積石塚とあう。)
『東沃沮(とうよくそ)伝』……「大木の槨を作る。長さ十余丈。一頭(片方の端)を開きて戸を作る。新(あら)たに死するものは、皆これに埋め、わずかに形を覆(おお)わしむ(土で死体を隠す)。」
『倭人伝』……「棺あって槨なし。土を封じて冢を作る」
このように、倭人の葬制は「韓」とは同じであるが、 「夫余」「高句麗」「東沃沮」と異なっていることを記している。
畿内のばあい、「木槨木棺墓」も「竪穴式石室墓」も、時代のくだる「横穴式石室墓」も、一貫して『魏志倭人伝』の「棺あって槨なし」の記述にあわない。
邪馬台国がかりに畿内にあったとすれば、魏の使いはそれらの葬制を見聞きせずに記したのであろうか。
時代のくだった『隋書倭国伝』は、「死者を斂(おさ)めるに棺槨(かんかく)をもってすること記す。隋の使いが畿内に行ったことは、『日本書紀』に記されている。西暦600年ごろ、日本の墓には棺槨があったのだ。中国人の弁別記述は鋭い。
白石太一郎氏は、「狗奴国=濃尾(のうび)平野[岐阜県と愛知県とにまたがる平野]説」を説く。
いっぽう、考古学者の森浩一氏は「狗奴国=濃尾平野説」について、雑誌『論座』2002年2月号所載の「魂を失う考古学界」という文章のなかで、つぎのようにのべる。
「(新聞は)考古学で判明した事実を報道するというより、面白く書きたてようとの意図が先行してしまっている。ホケノ山古墳は卑弥呼のお父さんの墓だとか、黒塚古墳は難升米(なんしょうまい)の墓だとか、そんなの学問的には何の根拠もありません。最近は狗奴国(くなこく)東海説を絡ませるのがまるで流行のようになっているが狗奴国についての研究史を踏まえないで、一方的な記事を垂れ流している。
一部の考古学者がいっている、東海地方には前方後方墳が多いということからの狗奴国東海説は、考古学の方法からはとうてい無理です。そもそも邪馬台国や狗奴国の所在地は、『魏志』倭人伝という文献上で決定される問題です。狗奴国東海説というのは、まず邪馬台国ヤマト説を前提として、それに『後漢書』の、『女王国より東、海を渡ること千余里、狗奴国に至る。皆倭種なりといえども、女王に属せず』を接合することによって成り立っています。しかしこの文章は、『魏志』倭人伝で『女王の境界の尽きる所なり』に続いて記されている『その南に狗奴国あり、……女王に属せず』という文章と、『女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、皆倭種なり』という文章を、倭人伝から百五十年ほどあとに『後漢書』を撰述した范曄(はんよう)が、頭の中でくっつけて作文したものにすぎないというのが、中国文献を扱っている研究者たちの古くからの通説です。」
朝日新聞社の記者、宮代栄一(みやしろえいいち)氏も、旧石器捏造事件に関連してのべている。
「このようなケ-スは旧石器時代に限らない。邪馬台国畿内説や、狗奴国の所在地論争をめぐって、恣意的な解釈や強引な主張、仮説に仮説を継ぐ議論がいかに平然と行なわれていることか。考古学の学問性は、じつは今や風前のともし火なのである」(以上、「脆弱さを露呈した考古学---捏造発覚から1年に思う」『前期旧石器問題とその背景』[段木一行(だんぎかずゆき)監修、株式会社ミュゼ、2002年刊])
■年代論における「類ハッブル定律現象」について
京都大学人文科学研究所の教授であった尾崎雄二郎氏は、私の編集していた『季刊邪馬台国』14号(1982年)に、「古代里程記事における類「ハッブル定律現象について」という文章を発表しておられる。
その要点は、つぎのようなものである。
「天文学で、地球から離れているほど、星雲の遠ざかる速度も大きいという『ハッブルの定律』がある。
昔の人にとっては、都から離れるほど、その里程は、感覚的にふえていくものらしい。古代の里程記事においては、類ハッブル現象が見られるのではないか。」
都から遠く離れた場所は、遠いほど、実際の里程以上に、大きく離れているように、認識される。そして、そのように記載されがちであるというのである。
これは、尾崎雄二郎氏が、邪馬台国の里程記事に関連して、中国文献のいろいろな事例などをあげて論じられたものである。
尾崎雄二郎氏はのべる。
「自分の故郷というかホームグラウンドというか、とにかくベースになるものから離れれば離れるほど何らかの比例で主観的な距離はふえていくのではないか。山の高さも、それが高ければ高いだけ、われわれの普通の生活平面から遠ざかるわけですから、その分だけ、実際の差を超える差が加わっていくのではないか、と思うのです。」
ところで、距離についていえるこのような傾向は、また、「年代」についてもいえるようである。
古い時代のことは、客観的な年代よりも、さらに古めに認識されがちのようである。
『日本書紀』の記す古代の年代は、大はばに延長されている。年代が、事実よりも、古めに記載されている傾向がある。このことは、すでに、多くの人が論じているとおりである。
このような傾向は、わが国の史書ばかりではない。『三国史記』などの韓国の史書でも、また、みとめられる。
そのことは、明治時代の東洋史学者の那珂通世(なかみちよ)が、その著『上世年紀考』のなかで、つぎのようにのべているとおりである。
「韓史も上代に遡(さかのぼ)るにしたがい、年暦の延長せりと覚しきところあることは、ほとんど我が古史に異ならず。」
『三国史記』の「新羅本記」は、倭国の女王、卑弥乎(呼)のことを、西暦173年にあたる条のところで記すなどしている。
このような傾向は、現代人の心にも、無意識のうちに強く働いているようである。
旧石器捏造事件のおりは、五十万年、七十万年と、年代がくりあがっていっても、専門家も、ふしぎと思わなかった。
なにか、古いものが出土したというばあい、マスコミに大きく報じられることがある。しかし、新しいものが出土したばあいは、ほとんど報道されないことが多い。
人間は、無意識の、このような心理的な傾向をもっていることは、年代などの問題をリアルに論ずるためには、強く意識化しておく必要がある。そうでないと、ともすれば、年代は、古いほうへ、古いほうへと流されがちになる。
考古学者、森浩一氏は、のべておられる。
「最近は、年代が、特に近畿の学者たちの年代が、古いほうへ向って一人歩きしている傾向かある。」(『季刊邪馬台国』53号。梓書院、1994年刊)







