今日は、落語の三題噺になぞらえて、「令和年号」と「邪馬台国」を二題噺として、扱ってみる。「令和年号」は西暦730年頃で、「邪馬台国」は西暦230年頃となる。ざっと500年の差があるが、この年代差を結びつけてみる。
今回の新年号の「令和」(れいわ)について、『朝日新聞』2019年4月2日(火)朝刊は、下記のように記している。
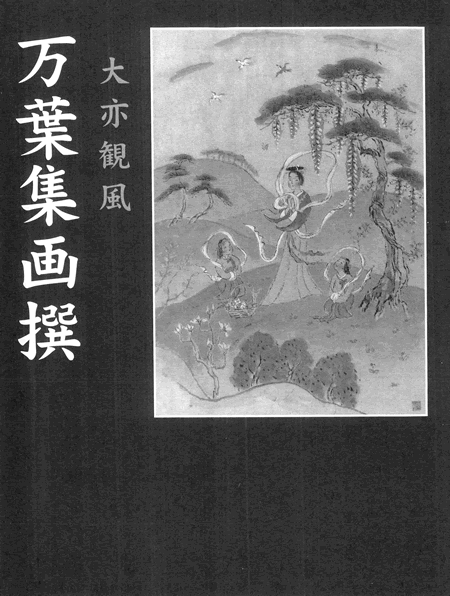
「令和」(れいわ)の典拠
・出典
「万葉集」巻五、梅花の歌三十二首并せて序
・引用文
初春令月、気淑風和、
梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香
・書き下し文:
初春の令月にして、気淑く風和ぎ、
梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす
・現代語訳(中西進著「万葉集」から)
時あたかも新春の好き月、空気は美しく風はやわらかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉のごとく白く咲き、蘭は身を飾った香の如きかおりをただよわせている
この序文について、
明治時代の大亦観風(おおまたかんぷう)が『万葉集撰』で万葉集を題材にして絵を描いている。
注:大亦観風 略歴
明治27年(1894年)9月27日、和歌山市広瀬舟場丁に生まれる。
本名新治郎。日本美術院洋画部出身。更に寺崎広業並びに小室翠雲に師事し日本画を研鑚。従来日本的墨絵主張の下に個人展を東京、大阪にて五回発表す。大東南宗院委員。
短歌は古泉千樫に師事。歌誌「青垣」創刊同人。昭和21年抒情短歌社を興し歌誌「抒情短歌」創刊主宰。随筆、評論の執筆多数。
昭和22年(1947)10月22日53歳で病没。
昭和52年和歌山文化協会より先覚文化功労者顕彰を受く。
作品 永平寺傘松閣天井画「寒椿」、「紀州行脚日記絵巻二巻」(和歌山県立近代美術館蔵)、「良寛の図」(糸魚川歴史民俗資料館蔵)、「万葉集画撰」71点(奈良県立橿原図書館藏)、他。 
そこで、大亦観風は太宰府梅花宴の歌の絵の説明をしている。
第二十九圖 太宰府梅花宴の歌
梅花の歌三十二首並に序
天平二年(730年)正月十三日、帥老の宅に萃(あつま)り、宴會を申(の)べき。時に初春の令月(よきつき)にして、
氣淑(きよ)く風和ぎて、梅は鏡前の粉(よそほ)ひを披(ひら)き、蘭は珮後の香りを薫(かを)しぬ。加以(しかのみならず)、曙の嶺は雲を移し、松は蘿(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾け、夕の岫(くき)は霧を結びて、鳥は縠(うすぎぬ)にし封(ふう)ぜられて林に迷ふ。庭には新蝶舞ひ、空には故雁歸れり。於是(ここに)、天を蓋(きぬがさ)にし、地を座にして、膝を促(ちかづ)けて觴(さかづき)を飛し、言(いふこと)を一室の裏(うち)に忘れて、衿(えり)を煙霞の外に開き、淡然として自ら放ち、快然として自ら足れり。若(けだ)し翰苑に非るよりは、何を以ちて情を攄(の)べむ。詩に、落梅の篇を紀(しる)すと、古今夫何ぞ異ならむ。宜しく、園の梅を賦して、聊か短詠を成すべしてへり。(大伴ノ旅人)。 
旅人卿のこの清遊は、實に太宰府長官としての一代の宴であったに違いない。其の序文を見ると、天平二年正月十三日とあって時期こそ、古来の曲水の宴の三月上巳とは異っているが、如何にも之を髣髴(ほうふつ)せしめる。王義之が、晉の永和九年三月三日に文人を會稽山陰の蘭亭に集め曲水流觴をなした時の、「蘭亭集序」に模したのであらうと思はれるところがある。
「忘言一室裹」は蘭亭記の「悟言一室之内」とか、「快然自足」等はその儘の句である處を見ると、必ずや自ら義之を以て任じたであらう。又梅花宴は、梁の何遜の其れを學んだものであらうと「評釋」にも云っている。
今、筑前、筑紫郡水城村國分の都府樓古址に行って見ると、尚千年を偲ぶ大礎石が草原の中に點在している。古の西海道を總管する政廰として壮大を極めたものであっただらう。
此の清遊は恐らく今、ツキ山と稱される邊りに宴を設けたのではなかったらうか。その東の観世音寺との間に背後の山より突出して来ている小丘が、雑樹鬱蒼として其の古を語るかの様に見える。
圖はその想定で作ったものである。背後の山は大城山の一部である。此山には太宰府防衛の爲、天智天皇四年(665年)に築城された殘壘が、今も尚殘っている。
當時は如何に西海の防備を嚴にしたかが想像されることである。
万葉集では815番の歌の前にこの序文がある。
参考に815番の歌は下記である。
歌:正月(むつき)立ち 春の来(きた)らば かくしこそ 梅を招(を)きつつ 楽しき終(を)へめ (大弐紀卿)
現代語訳:正月になり 春が来たなら こうやって 毎年梅を迎えて 歓(かん)を尽しましょう [大弐紀卿(だいにききょう)]
万葉仮名:武都紀多知 波流能吉多良婆 可久斯許曾 烏梅乎々岐都々 多努之岐乎倍米 (大弐紀卿)
序文は下記である。
漢文:
梅花歌卅二首 并序
天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴会也。
于時、初春令月、気淑風和。
梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。加以、曙嶺移雲、松掛羅而傾盖、夕岫結霧、鳥封縠而迷林。庭舞新蝶、空帰故鴈。
於是、盖天坐地、促膝飛觴。忘言一室之裏、開衿煙霞之外。淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以攄情。請紀落梅之篇、古今夫何異矣。宜賦園梅、聊成短詠。
この漢文は、四六駢儷体(しろくベんれいたい)で書かれている。
これは、
(「駢儷」は語句を対にして並べること)漢文の文体の一つで、主に四字・六字の句を基本として対句(ついく)を用いる華美な文体。漢・魏に起こり、六朝から唐にかけて流行し、韓愈・柳宗元が提唱した古文運動が定着するまでは、文章の主流であった。日本では、奈良・平安時代に盛んに用いられた。駢文。四六文。四六駢儷文ともいう。
読み下し文:
梅花(ばいくわ)の歌三十二首 并(あは)せて序
天平(てんぴやう)二年正月十三日に、帥老(そちらう)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(の)べたり。
時に、初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ。
梅は鏡前(きやうぜん)の粉(ふん)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(ばいご)の香(かう)を薫(かを)らす。加以(しかのみにあらず)、曙(あさけ)の嶺(みね)に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾(かたぶ)け、夕(ゆふへ)の岫(くき)に霧(きり)結び、鳥は縠(うすもの)に封(と)ぢられて林に迷(まと)ふ。庭に新蝶(しんてふ)舞ひ、空には故雁(こがん)帰る。
ここに、天を蓋(きぬがさ)にし、地(つち)を坐(しきゐ)にし、膝(ひざ)を促(ちかづ)け觴(さかづき)を飛ばす。言(こと)を一室の裏(うち)に忘れ、衿(ころものくび)を煙霞(えんか)の外に開く。淡然(たんぜん)に自(みずか)ら放(ゆる)し、快然(くわいぜん)に自(みずか)ら足(た)りぬ。もし翰苑(かんえん)にあらずは、何を以(もち)てか情(こころ)を攄(の)べむ。請(ねが)はくは落梅(らくばい)の篇(へん)を紀(しる)せ、古(いにしえ)と今と夫(そ)れ何か異(こと)ならむ。宜しく、園梅(えんばい)を賦(ふ)して、聊(いささ)かに短詠(たんえい)を成すべし。
現代語訳:
梅花の歌三十二首と序
天平二年正月十三日、大宰帥旅人卿の邸宅に集って、宴会を開く。
折しも、初春の正月の佳(よ)い月で、気は良く風は穏やかである。梅は鏡の前の白粉(おしろい)のように白く咲き、蘭は匂(にお)い袋のように香(かお)っている。そればかりではない、夜明けの峰には雲がさしかかり、松はその雲の羅(ベール)をまとって蓋(きぬがさ)をさしかけたように見え、夕方の山の頂(いただき)には霧がかかって、鳥はその霧の縠(うすぎぬ)に封じ込められて林の中に迷っている。庭には今年生れた蝶が舞っており、空には去年の雁が帰って行く。
そこで、天を屋根にし地を席(むしろ)にし、互いに膝(ひざ)を近づけ酒杯(さかずき)をまわす。一堂の内では言うことばも忘れるほど楽しくなごやがてあり、外の大気に向っては心をくつろがせる。
さっぱりとして各自気楽に振舞い、愉快になって各自満ち足りた思いでいる。
もし文筆によらないでは、どうしてこの心の中を述べ尽すことができようか。諸君よ落梅(らくばい)の詩歌を所望したいが昔も今も風流を愛することには変りがないのだ。ここに庭の梅を題として、まずは短歌を作りたまえ。
この序文について、朝日新聞の記事が参考になる。
『朝日新聞』2019年4月4日(木)寄稿上野誠氏の記事
「世界に開かれた万葉集の時代「令和」文化模索の世へのあこがれ」
新しい年号が『万葉集』から採られた。それは、年号の歴史にとって、新しい第一歩を踏み出したことになる。というのは、中国の皇帝制度から生まれた年号が、日本文化のなかに根付いて、ついには和歌集の漢文序文から採用されることになったからだ。
時は、天平2(730)年正月13日のこと。九州・大宰府の大伴旅人の邸宅で、花見の宴が催された。梅の花見の宴である。
梅は、当時、外来植物で、珍しい植物であった。大宰府は、大陸との交流の玄関にあたる地であり、この地に赴任をした役人たちは、梅の花の白さに、魅了されたのである。旅人宅に集まった客人たちは、次々に歌をうたった。
その歌々を束ねる序文の書き出しには、こうあるのである。
「時に、初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やわら)ぐ。梅は鏡前(きょうぜん)の粉(ふん)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす」
これを原文で示せば、「于時、初春令月、気淑風和。梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香」となる。正月良き時に集えば、天気に恵まれ、風もやわらかで、梅の花は鏡の前にある白粉のように白く、その匂いといったら、まるで匂い袋のようだ、と宴の日を讃(たた)えている部分だ。
良き時に、良き友と宴を共にする。それが、人生の最良の時ではないか、とは、かの王義之(おうぎし)(303?~61?)の蘭亭の序にみえる思想なのだが、大宰府に集まった役人たちは、自分たちを、あこがれの中国文人になぞらえて、漢詩ならぬ和歌を作って、披露しあう宴を催したのである。
天平の時代は、決して良い時代ではなかった。政変と飢饉(ききん)は、人びとの生活を苦しめたし、疫病も蔓延(まんえん)した時代である。ところが、世界の美術史にも特筆すべき、すばらしい仏像を造り、『万葉集』の歌々は、その後の日本の文学の源流となってゆく。
どんな時代にも、人びとは平和な時を求め、新しい芸術と文化を模索していたのである。
「令和」という年号には、そういった平和への思いが込められている、と思う。と同時に、天平文化へのあこがれも内包されているのではなかろうか。万葉学徒のひとりとして、今、私はそんなことを考えている。
『万葉集』とは、いったいどんな歌集なのだろうか。
8世紀の中葉に出来た現存する最古の歌集で、その編纂(へんさん)者のひとりが大伴家持である。大伴家持の父が大伴旅人であり、大伴家持は、父と父の盟友ともいうべき山上憶良(やまのうえのおくら)にあこがれて、歌を作り続けたのである。
『万葉集』に収められている4500首あまりの歌々は、後の時代の範となって、和歌の歴史を作ってゆくことになる。つまり、『万葉集』こそ、和歌始まりの歌集なのである。外来の文字である漢字を使って、自分たちの言葉であるヤマト言葉を、いかに表すか。そこから日本文学の歴史は始まるのである。
『万葉集』の生まれた奈良時代ほど、日本が世界に開かれた時代はなかった。漢字・儒教・仏教・律令という中国文化を受け入れて、それをいかに自分たちのものにするのか。万葉びとは、悪戦苦闘した人びとでもあるのだ。
一方、万葉びとは、常に自分たちの足元を見つめる人びとでもあった。漢文で書けば意味は分かっても、そのニュアンスが伝わらない。和歌は理ではなく、情を伝えるもので、それは、自分たちの言葉で情を伝えるということなのである。
日本人は、歌で恋をすることを学び、人と人との絆を確かめた。『万葉集』は、その始まりの歌集ということができる。
今、新しい時代が始まる。
上野誠(うえの・まこと)1960年、福岡県生まれ。2004年から奈良大教授(万葉文化論)。著書に『万葉文化論』 『万葉集から古代を読みとく』など。オペラの脚本や小説も執筆。
ここで、この序文の作者について、「新編 日本古典文学全集」『万葉集2』(小学館刊)に下記のように書かれている。
この序の作者について諸説があるが、表向きは宴の主催者である大伴旅人、そして実作者は山上憶良と考えられる。この序は、王羲之の「蘭亭序」や王勃・駱賓王などの初唐詩序の構成や語句などに学んだとみられる点が多い。
また、「新日本古典文学大系」(岩波書店1999年刊)『万葉集一』では、下記となる。
序の冒頭の文、「これは羲之が蘭亭記の開端に、永和九年歳在癸丑暮春之初会干会稽山陰之蘭亭脩禊事也。この筆法にならへりとみゆ」[代匠記(初稿本)]と指摘されている。「帥老」は当時六十六歳であった大宰府大判旅人の自称。旅人自身が、序を作り、歌を配列したものであろう。旅人以外の人の作だとすると、旅人の歌の作者名注記が「主人」であって「主人卿」でないことの説明が難しい。序の作者を山上憶良とする説があるが、憶良の歌の作者名「筑前守山大夫」は他称である。
更に、「新日本古典文学大系」(岩波書店)『万葉集二』では下記となる。
この序の作者については、大判旅人説・山上憶良説・某官人説などがある。序の文章構成は、王羲之の蘭亭集序のほかに唐詩の詩序をもまねている。大宰府の帥大伴旅人(当時六十六歳)。萃は集・聚に司じ。
これらから、大伴旅人とするところが、良いのではないか。
■ここで、山上憶良と大伴旅人について、調べてみよう。
人名辞典では下記となっている。
山上憶良(やまのうえのおくら)[660~?]
飛鳥-奈良時代の官吏、歌人。斉明天皇6年生まれ。大宝2年遣唐少録として唐(中国)にわたる。帰国後伯耆守(ほうきのかみ)、東宮侍講をへて筑前守となり、大宰府で大伴旅人らとまじわった。「万葉集」に長歌、短歌、旋頭歌(せどうか)、漢詩文があり、「貧窮問答歌」は有名。天平5年(733)ごろ没したという。編著に「類聚歌林(るいじゅかりん)」。
大伴旅人(おおとものたびと)[665~731]
奈良時代の公卿(くぎょう)、歌人。天智天皇4年生まれ。大伴安麻呂の長男。母は一説に巨勢郎女(こせのいらつめ)。大伴家持(おおとものやかもち)の父。中務(なかつかさ)卿、中納言などをへて、神亀(じんき)4年のころ大宰帥(だざいのそち)として赴任。天平(てんぴょう)2年大納言となり奈良へかえる。翌年従二位。歌人としてもすぐれ、山上憶良と親交があった。大宰帥時代を中心とする歌70首余が「万葉集」にみえる。天平3年7月25日死去。67歳。名は多比等、淡等ともかく。
両者の歌は下記がある。
・山上憶良の歌
和歌:銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も なにせむに 優(まさ)れる宝 子に及(し)かめやも
現代語訳:銀も 金も珠玉も どうして 優(すぐ)れた宝といえよう 子にまさろうか
和歌:憶良(おくら)らは 今は罷(まか)らむ 子泣くらむ それその母も 我(あ)を待つらむそ
現代語訳:憶良めは もうおいとまします 子供が泣いておりましょう あのおその母親も わたしを待っていることでしょうから
・大伴旅人の歌
朝倉郡夜須(やす)での歌
大宰帥大伴卿、大弐丹比県守(だいにたぢひのあがたもり)卿の民部(みんぶ)卿に遷任(せんにん)するに贈る歌一首
原文:為君 醸之待酒 安野尓 独哉将飲 友無二思手
和歌:君がため 醸みし待ち酒 安の野に ひとりや飲まむ 友なしにして
現代語訳:君のために 用意した待酒を 安の野で ひとり寂しく飲むのか 友も居なくて
また、山上憶良渡来人説がある。
山上憶良渡来人論争[『日本古典文学研究史大事典』勉誠社、1997年刊]
山上憶良(やまのうえのおくら)
【研究史】〈伝記〉戦後の伝記研究は、山上氏に関する井村哲夫の考証(「憶良伝一斑-世に出るまで-」『千里山論集』
1・昭38・5、後『憶良と虫麻呂』桜楓社・昭48)を嚆矢に、憶良の教養基盤を作った前半生の解明に向った。殊に土屋文明が示唆し、渡部和雄(「憶良の前半生」『解釈と鑑賞』至文堂・昭44・2)、中西進(「憶良帰化人論」『國學院雑誌』昭44・11、後『山上憶良』河出書房新社・昭48)、比護隆界(「山上臣憶良の出自-律令制度下の国司任官の実状に関連して-」『文芸研究(明治大学)』28・昭47・10)が展開した憶良百済系渡来人説は1970、80年代に一大争点となった。歴史学から青木和夫(「憶良帰化人説批判」『万葉集研究』2・塙書房・昭48、後『日本律令国家論攷』岩波書店・平4)、佐伯有清(「憶良は天智期の渡来人か」『國文學』學燈社・昭55・11)が、古代三韓の文字等より申兌燮(「山上憶良渡来人説考-中西進氏の論をめぐって-」『語文(日本大学)74・平1・6)が批判を加えた。
・山上憶良渡来人説の根拠
(1)「憶良(おくら)」という名が、音読みで、渡来系であることを思わせる。
(2)天武天皇朱鳥元年(686)5月9日にみえる「侍医百済人億仁(おくに)」は、「山上憶良」の父にあてることができる。[『日本古典文学大系』本(岩波書店刊)『日本書紀下』]
「五月(さつき)の庚子(かのえね)の朔戊申(つしのえさるのひ)[9日]に、多紀皇女等(たち)、伊勢(いせ)より至(まうけ)り。是(こ)の日に、侍醫百済人(おもとくすしくだらのひと)億仁(おくに)、病(やまひ)して死(みまか)らむとす。則(すなは)ち勤大壹位(ごんだいいちのくらゐ)を授(さづ)けたまふ。」
[注:侍医百済人億仁は「億」が人偏となっており、山上憶良の「憶」とは違う。]
・山上憶良渡来人説への批判
(1)渡来人ではない人(日本人系の人)の名前でも、音読み名はみられる。[例:「億計(おけ)天皇(仁賢天皇)」、蘇我満智(そがのまち)」など。]
(2)『新撰姓氏録』によれば、山上氏は第5代孝昭天皇の子孫系の人とされている。
(3)山上氏の姓は「臣」であった。山上憶良も「山上臣憶良」と『続日本紀』『万葉集』などにある。渡来人系の人で、「臣」姓の人はすくない。(『続日本紀』に、秦大兄(はだのおおえ)の姓、香登臣(かがとのおみ)など、例がないわけではない。)
■出典を万葉集だけとしてよいのか?
令和について、万葉集の序文は王羲之の「蘭亭序」が元になったのではないかとの説があるが、
「蘭亭序」漢文:
是日也、天朗氣清、惠風和暢、仰觀宇宙之大、府察品類之盛、
所以遊日騁懷、足以極視聽之娛、信可樂也。
「蘭亭序」は「和」はあるが、「令」が無い。
晋の時代の王羲之より古い後漢の時代の張平子(ちょうへいし)の『文選(もんぜん)』(賦篇)下の歸田賦(きでんのふ)に「令」も「和」もある。
(釈漢文大系、明治書院2001年刊から、歸田賦(きでんのふ)について下記に示す。
李善は「張衡仕へて志を得ず、田に帰らんと欲す。因りて此の賦を作る」と注する。「帰田」は官を辞して故郷の田園に帰る意。
「歸田賦」漢文:
於是仲春令月、時和氣清。原隰鬱茂、百草滋榮。
王雎鼓翼、鶬鶊哀鳴。
交頸頡頏、關關嚶嚶。於焉逍遥、聊以娯情。
爾乃龍吟方澤、虎嘯山丘。仰飛纖繳、俯釣長流觸矢而斃、貪餌呑鈎。
落雲間之逸禽、懸淵沈之魦鰡。
書き下し文:
是(ここ)に於(おい)て仲春令月(ちゅうしゅんれいげつ)、時和(ときわ)し気清(ききよ)し。原隰鬱茂(げんしふうつも)し、百草滋榮(ひゃくそうじえい)す。
王雎翼(わうしょうつばさ)を鼓(こ)し、鶬鶊哀(さうかうかな)しみ鳴(な)く。頸(くび)を交(まじ)へて頡頏(けつかう)し、關關嚶嚶(くわんくわんあうあう)たり。焉(ここ)に於(おい)て逍遥(せうえう)し、聊(いささ)か以(もっ)て情(じゃう)を娯(たの)しましむ。爾(しか)して乃(すなは)ち龍(りょう)のごとくに方澤(ほうたく)に吟(ぎん)じ、虎のごとくに山丘(さんりょう)に嘯(うそぶ)く。仰(あふ)ぎて纖繳(せんしゃく)を飛ばし、俯(ふ)して長流(ちゃうりう)に釣(つ)る。矢(や)に觸(ふ)れて斃(たふ)れ、餌(ゑ)を貪(むさぼ)りて鈎(つりばり)を呑む。雲間(うんかん)の逸禽(いつきん)を落(お)とし、淵沈(ゑんちん)の魦鰡(さりう)を懸(か)く。
現代語訳:
さて、仲春の佳い時節ともなれば、気候は穏やか、大気は清々しい。野原や湿原に植物は生し茂り、多くの草が一面に花をつける。ミサゴは羽ばたき、コウライウグイスは悲しげに鳴く。首をすり寄せて昇り降り、さまざまな鳴き声を立てている。そんな中をさまよっては、いささかなりとも我が心を楽しませるのだ。かくして、沢辺では竜の如く吟じ、山野では虎の如く嘯く。空高く射ぐるみを飛ばし、大きな川に釣り糸を垂れる。鳥は矢に当たって落ち、魚は餌を貪って針にかかる。雲間に飛ぶ鳥を射止め、淵の底に潜む魚を釣り上げる。
ここで、
張衡(ちょうこう)[78(建初3)~139(永和4)]
後漢の文学者、科学者。南陽郡西鄂(河南省南召県)出身。字は平子。『西京賦』『東京賦』や『思玄賦』などが有名。
王義之(おうぎし)[303(太安2)頃~361(升平5)頃、321-379]
中国第一の書聖。東晋の書家。『蘭亭序』。
また、『文選』について、清少納言『枕草子』では下記のようにある。
文(ふみ)は 文集(もんじふ)。文選(もんぜん)。新賦(しんぷ)。史記、五帝本紀(ほんぎ)。願文(ぐわんもん)。表(へう)。博士(はかせ)の申文(まうしぶみ)。
現代語訳:漢文の書は 白氏文集(はくしもんじゅう)。文選(もんぜん)。新賦(しんぷ)。史記、特にその中の五帝本紀。願文(がんもん)。表(ひょう)。それに博士(はかせ)の書いた申文(もうしぶみ)。
このように、平安時代では『文選』は漢文の参考書として、一般に使われていたことが分かる。
■文選について
『文選』は、現存する詩文の選集の最古のもの。周から梁にいたる千年間の文章・詩歌などを、細目に分けて編纂した書。30巻、のち60巻。梁の昭明太子(蕭統)が、正統文学の秀れたものを集大成することを意図して、幕下の文人の協力のもとに編。530年ごろ成立の昭明太子の序文によれば、「深い内容を美的に表現したもの(沈思に出でて、翰藻(かんそう)に帰するもの)を採ったという。後世、知識人の必読書とされ、わが国でも、平安時代に盛行。
『文選』には、また、『漢書』の著者として知られる後漢の班固(はんこ)[班孟堅(はんもうけん)、32~92]の「両都の賦(ふ)」(西都長安と東都洛陽をえがく)や、後漢張平氏(ちょうへいし)[張衡(ちょうこう)、72~139]の「二都の賦」[西京(せいけい)の賦、東京(とうけい)の賦ともいう。長安と洛陽をえがく]も収められている。
また、ちょうど邪馬台国が存在したころ、魏の国の明帝は、許昌(きょうしょう)に景福殿という宮殿をつくった。何平叔(かへいしゅく)は、この宮殿をたたえて、「景福殿の賦」をつくった。この「景福殿の賦」も、『文選』に収められている。
蕭繹の「倭国の使の図」をみれば、邪馬台国の使の姿を、ほぼ視覚化することができる。そして、左思の「三都の賦」をはじめとする中国の都をえがいた賦を読めば、邪馬台国の使がおとずれたころの、中国の都の状況を、ほぼ知ることができる。
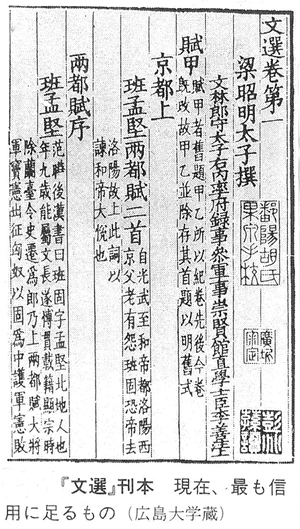
[注:賦(ふ)は漢詩の六義(りくぎ)の一。事物をそのまま述べあらわすこと。「詩-」→六義。漢文の韻文の一。事物を叙述描写し、多くは対句を用い、句末に韻をふむ美文。「赤壁-」]
■拙著『邪馬台国ハンドブック』(講談社、1987年刊)に記したものを紹介
芸術家一族の悲劇
「倭国の使の図」をえがいたといわれる蕭繹(しょうえき)は、南北朝時代の、南朝梁(りょう)の、三代目の王である。
梁の国の歴史を記した『梁書』には、邪馬台国よりものちの時代に、中国に使をつかわした倭の五人の王、讃(さん)、弥(み)[『宋書』は、「珍(ちん)」と記す]、済(せい)、興(こう)、武(ぶ)のことなども記されている。
蕭繹は、たいへんな文化人であった。絵画をよくしたばかりでなく、博学の名も高かった。蕭繹は、江陵(こうりょう)において即位した。当時、蜀(しょく)の地方は、すでに、西魏(せいぎ)の手におち、梁は、揚子江の中流から東を支配するのみとなっていた。
西暦554年、西魏は、桂国(けいこく)[将軍職の量高位]の于謹(うきん)を総司令官として、梁に出兵し、江陵に侵入した。元帝蕭繹は、所蔵した古今の図書十四万巻を焼きすて、嘆いていった。
「文武の道も、今宵かぎりで尽きはてた。」
そして、城から出て降伏した。
ある人から、書物を焼いた理由を問われたとき、答えていった。
「自分は、万巻の書物を読破したにもかかわらず、今日の運命にたちいたった。」
万巻の書物も、国を救うのには、役にたたなかった、というのである。もっとも、蕭繹が好んで読んだのは、老子や荘子の本であったというから、国が滅びたのは、もっともであるかもしれない。当時の中国には、孫子や呉子の兵法書もあったはずであるのに。西魏は、元帝蕭繹を、まもなく殺した。
「倭国の使の図」を残した元帝蕭繹は、文化人でありすぎたために、国を滅ぼしたのであろうか。
蕭繹の兄の昭明太子[蕭統(しょうとう)、501~531]も、すばらしい文化人であった。梁の時代までの、すぐれた文学作品を集めた『文選』を編纂した。
この『文選』も、邪馬台国問題と無関係ではない。
昭明太子は、容姿美しく、挙止優雅、頭脳明晰で、性格また温厚であった。五歳にしてあまねく五経を読み、ことごとく諷誦(ふうしょう)することができたほどの神童であった。
昭明太子の編纂した『文選』は、孔子の書のような経書でもなければ、『老子』『荘子』『孟子』のような思想の書でもなかった。『文選』は、昭明太子の美観、文学観にもとづく、純文学の書である。
昭明太子や元帝蕭繹など、梁王朝の人びとに、色濃くみられるのは、芸術家気質である。
昭明太子は、すぐれた人であったにもかかわらず、皇帝にならなかった。それは、三十一歳の若さで、死没するからである。
三十一歳のとき、昭明太子は、たまたま宮殿のうしろの池に遊び、あや模様を彫刻した美しい船に乗って、蓮の花を摘みにでた。ところが、乗りあわせた宮女たちが、たわむれに船をゆるがした。太子は水中に投げだされ、それがもとで病気となり死没した。太子らしいともいえる死に方である。
さて、『文選』には、晋の詩人、左思(さし)[左太沖(さたいちゅう)、250?~308ごろ]が、十年の歳月を費してつくったといわれる「三都の賦(ふ)」なども、収められている。この左思は、邪馬台国のことを記した『三国志』の編者、陳寿(ちんじゅ)[233~297]と、ほぼ同じころ生きた人である。

左思の「三都の賦」は、三国時代の魏の曹操(そうそう)の都・鄴(ぎょう)、呉の都・建業、蜀の都・成都のありさまを、絢爛(けんらん)たる文体で活写したものである。
左思の「三都の賦」を、当時の人びとは、競って書き写したために、洛陽の紙の価(あたい)が、高くなったという。ここから、ベストセラーを意味する「洛陽の紙価を高める」という言葉がおきた。
右図は倭人をえがいた最古の絵画。梁(りょう)の元帝蕭繹(しょうえき)[508~554、在位552~554]が即位するまえに、みずから描いたものといわれる。541、2年ごろの作と思われるが、現物は1077年の模写。
「職貢図」は、朝貢する諸外国人の容貌を描いて、梁朝の勢威を示す意図があったとみられ、現存する「職貢図」は、十三の国についての記述と、十二の使の画像とを収める。しかし、この「倭国使」の図は、梁朝の「倭国使」の描写ではなく、『魏志倭人伝』の記述にもとづいて描かれている。
■「大宰府の帥(そつ)[長官]と「一大率(いちだいそつ)」
行政区画としての西海道は
以下の十二ヶ国と一島が含まれる。
・筑前国(現在の福岡県西部)
・筑後国(現在の福岡県南部)
・豊前国(現在の福岡県東部、大分県北部)
・豊後国(現在の大分県中央部から南部)
・肥前国(現在の佐賀県、壱岐・対馬を除く長崎県)
・値嘉島(876年に肥前国より分立。数年後に再編入。現在の長崎県平戸島及び江島・平島を除く五島列島)
・肥後国(現在の熊本県)
・日向国(現在の宮崎県、鹿児島県東部のうち志布志市及び大崎町の大部分)
・大隅国(現在の志布志市及び大崎町の大部分を除く鹿児島県東部・奄美)
・多禰国(702年から824年、現在の鹿児島県大隅諸島)
・薩摩国(現在の鹿児島県西部)
・壱岐国(現在の長崎県壱岐)
・対馬国(現在の長崎県対馬)
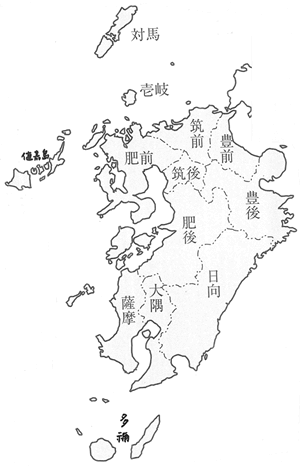 「刺史」はもともと郡国の監察官であった。時代がたつにつれて職務の重要性を増し、地方の行政から軍事、すなわち民治・兵制をもつかさどる官吏となった。したがって「大率」とは、大督率・大将帥を意味する名称である。「大率」が女王国より以北の諸国を巡撫するかたわら、検察(民政・司法)や軍事、そして外交関係の事務をもつかさどっていたとみてよい。(謝銘仁著『邪馬台国 中国人はこう読む』)
「刺史」はもともと郡国の監察官であった。時代がたつにつれて職務の重要性を増し、地方の行政から軍事、すなわち民治・兵制をもつかさどる官吏となった。したがって「大率」とは、大督率・大将帥を意味する名称である。「大率」が女王国より以北の諸国を巡撫するかたわら、検察(民政・司法)や軍事、そして外交関係の事務をもつかさどっていたとみてよい。(謝銘仁著『邪馬台国 中国人はこう読む』)
・一大率
『魏志倭人伝』は、つぎのようなことを記している。
「女王国から北の地には、特に『一大率』を置いて、諸国を検察させている(とりしまらせている)。諸国はこれを恐れはばかっている。その『一大率』はつねに、伊都国にいて政務を行い、中国の刺史(しし)のようなものである。」
「率」という字は、『日本書紀』の「持統天皇紀」に、「筑紫大宰率(つくしのおほみこともちのかみ)」という形で、三回でてくる。のちの大宰府の長官、「大宰帥(だざいのそつ)」のことである。
また、「天智天皇紀」に、「筑紫率(つくしのかみ)」という形で二回でてくる。やはり、「大宰帥」のことである。
「大宰帥」は、数力国を包括する広い範囲を統治する地方行政長官である。
『続日本紀』の文武天皇の、大宝元年(701年)正月の条などには、「右兵衛(うひゅゑ)の率(かみ)[長官]」という形で、「率」がでてくる。読みは、やはり、「かみ」である。(『続日本紀』の「元明天皇紀」には、「五衛(ごゑ)の督率(かみ)」のような表現もでてくる。)
また、『日本書紀』の「孝徳天皇紀」や、「持統天皇紀」では、「筑紫大宰率」のことを、「筑紫大宰帥」とも記している。
「率」と「帥」とは、同じ意味に用いられている。「率」も「帥」も、動詞は、「ひきいる」という意味である。名詞は、「ひきいる人」「リーダー」の意味である。「大宰率」「大宰帥」のばあい、「長官」「最高の統率者」の意味である。
「大」の字は、いろいろな読み方があるが「大納言(おほきものまうすつかさ)」や、「大」と同じ意味の「太」に、「太政大臣(おほきおとど)」などの例があるから、一応、「おほき」と読んでおこう。次項でのべるように、「(身分の)たかき」とも読める。
以上から、「一大率」は、「一(ひと)りの大(おほ)き率(かみ)」と読める。
「刺史」は、中国での地方官である。漢の時代は、地方の監察官、隋・唐の時代は、州の知事のことである。
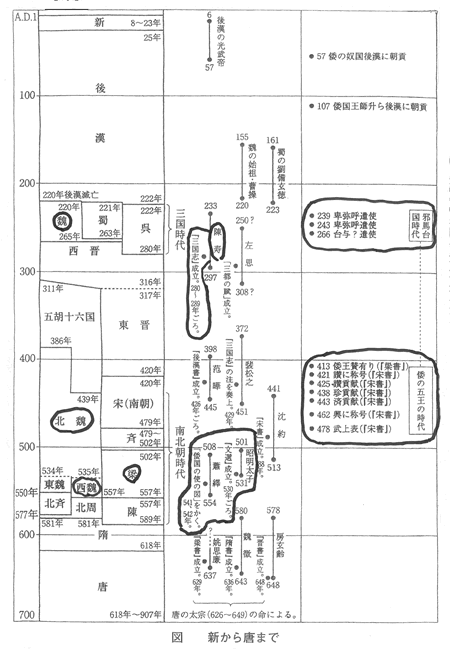 魏晋の時代は、兵権をもつ地方官で「使持節・都督」であるのが、一般的であった。『三国志』の著者陳寿は、「漢代の末以来、刺史は諸郡を総統し、行政を、都の外で行なった。これは、まえの時代に監察だけを行なっていたのと異なっている。」とのべている。
魏晋の時代は、兵権をもつ地方官で「使持節・都督」であるのが、一般的であった。『三国志』の著者陳寿は、「漢代の末以来、刺史は諸郡を総統し、行政を、都の外で行なった。これは、まえの時代に監察だけを行なっていたのと異なっている。」とのべている。
「一大率」は、のちの「大宰帥(だざいのそつ)」にほぼあたるとみてよいだろう。
邪馬台国や、狗奴国については、王名を記している。これに対し、「伊都国」については、「世々王あり。」としながら、王名を記していない。
これは、あるいは、「伊都国」へは、代々女王国から、「王族」を派遣していたことをあらわすか。「王」は、かならずしも、土着の豪族とはかぎらない。
漢でも、皇室の子弟を尊んで、各地の「王」としているし、後世のわが国でも、皇族の「王」を、各地に派遣している。
伊都国の官名「爾支(にき)」と関係あるかとみられる神名「邇邇芸の命(ににぎのみこと)」「邇芸速日の命(にぎはやひのみこと)」などは、「王」と呼んでもよい皇子クラスの神である。
平原王墓なども、そのような「王」の墓であろう。
実際の行政官として、「一大率」がいたのであろう。
・都督
『日本書紀』の景行天皇五十五年の条に、「彦狭嶋王(ひこさしまのみこ)を以(も)て、十五国(とをあまりいつのくに)の都督(かみ)に拝(ま)けたまふ」という文があり、「拝(ま)けたまふ」が、「官職に任命する」の意味で用いられている。
「都督(ととく)」は、「かみ」と読まれている。
また、『日本書紀』の天智天皇の六年十一月の条では、筑紫の太宰府のことを、「筑紫都督府(つくしのおほみこともちのつかさ)」と記している。「都督」を、「おほみこともち」と読んでいる。
「おほみこと」は、「天皇のことば」をさし、「おほみこともち」は、勅命を奉じて任地にくだり、政務を執る官をさす。
『和名抄』の五巻でも、太宰府のことを、「於保美古止毛知乃司(おほみこともちのつかさ)」と記している。
いっぽう、これは『三国志』ではなく、「宋書」であるが、宋の順帝は、倭の五王のひとり、倭王武を、「使持節(しじせつ)・都督(ととく)倭(わ)新羅(しんら)任那(にんな)加羅(から)秦韓(しんかん)慕韓(ぼかん)六国諸軍事(りっこくしょぐんじ)・安東大将軍(あんとんだいしょうぐん)・倭王(わおう)」に任命している。この称号のなかに、「都督」ということばがでてくる。
この「都督」を、「かみ」と解釈すれば、以下六国の「長官」という意味になる。
また、「都督」を、「おほみこともちのつかさ」と解釈すれば、宋の順帝の勅命を奉じて、任地の政務を執る官という意味となる。
藤堂明保の『学研漢和大字典』(学習研究社刊)には、「都督」について、つぎのようにのべられている。
①統率し監督すること。
②官名。三国時代には、地方の軍事をつかさどり、ときには刺史を兼ねた。唐代には節度使にかわって、民政をもつかさどった。
③(国)大宰帥(だざいそつ)[大宰府の長官。823年(弘仁14)以降、多く親王が補任された。]の唐名。
[注:大宰府は
律令制で、筑前国筑紫郡に置かれた役所の名。九州および壱岐・対馬の二島を管轄し、兼ねて外寇を防ぎ、外交のことをつかさどった。 官を帥(そつ)といい、その下に権帥・大弐・少弐・大監・少監・大典・少典などが置かれ、別に祭祀をつかさどる主神(かんづかさ)などがある。福岡県太宰府市にその遺跡があり、正庁であった都府楼の礎石などが残っている。鎮西府。おおみこともちのつかさ。]
■魏都洛陽の状況(『邪馬台国への道』から)
今から、およそ、1700年ほど昔、西暦238年ごろのことである。
中国三国時代の魏の都、洛陽は、見なれない一群の旅人をむかえていた。聞けば、遠い海のかなた、倭(今の日本)の邪馬台国から、万里を越える旅を続けてやって来たとのことであった。
洛陽城の外では、すでに、麦や黍(きび)が黄ばんでいた。秋かぜがその葉をそよがし、とんぼが空に群れ、大きないなごが、道にさえ飛びはねていた。
(「賦」の文章の感じ)
海を越え、山を越え、燃えるように赤い夕陽が、地平の雲にくずれ沈むのを、幾たび見たことであろう。祖国邪馬台は、いま、雲とかすみのかなたにある。そびえる洛陽の城門をくぐり、いまこそ、目ざした大国魏の都大路を踏んでいる---。
このとき、倭の使たちの眼を射たのは、どのような風物であったろうか。
史書は、そのときの洛陽のありさまを、直接には伝えていない。しかし、その情況を、あるていどうかがわせる書物はある。
『漢書』の著者としてしられる後漢の班固[班孟堅(はんもうけん)、西暦32年~92年]は、『両都の賦(ふ)』をあらわし、西都長安と東都洛陽のありさまを活写している。後漢の張平子[張衡(ちょうこう)、72年~139年][『帰田賦』作者]は、『二京の賦』をつくり、そのなかの「東京(とうけう)の賦」で、洛陽をえがいている。
また、晋の左太沖(たいちゅう)[左思、250?~305?]は、傑作『三都の賦』のなかで、蜀の都益州、呉の都建業、魏の都鄴(ぎょう)[魏の都は、はじめ、曹操の時代に鄴にあり、のち西暦220年、文帝曹丕(そうひ)の時代に洛陽にうつった]のありさまをえがいた。『三都の賦』は、洛陽の家々で競って筆写され、文字どおり、洛陽の紙価を高からしめた。
何平叔(かへいしゅく)は、魏の明帝が許昌に宮殿(景福殿)をたてたとき、『景福殿の賦』をつくり、それをたたえている。
魏を建てた曹操も、その子曹丕、曹植も詩人であり、多くの詩を残している。また、『太平御覧(たいへいぎょらん)』195には、晋の陸機(りくき)の『洛陽記』が引かれており、さらに、時代の下るものでは、六世紀にできた楊衒之(ようげんし)の『洛陽伽藍記』がある。
これらの書物や詩や史書などを参考にし、倭の使者たちが見たであろうものをえがいてみよう。
都城洛陽の大きさは、魏のまえの後漢のとき、東西六里(約2.6キロ、南北九里(約4キロ)あまりであったとされ、魏のあとの晋のときも、「東西六里十一歩、南北九里一百歩」(『続漢書』郡国志の劉昭の注に引く皇甫謐(こうふびつ)の「帝王世紀」による)とされている。魏の時代も、ほぼこのていどの大きさであったであろう。洛陽の近くを、黄河の支流である伊水と洛水とが、西から東へとめぐり、穀水が、城内をうるおしていた。城の北に芒(ぼう)山があり、南に嵩山(すうざん)がある。
魏の時代にも、洛陽は、『周礼(しゅらい)』冬官、考工記下、匠人の条の、「[宮闕(きゅうけつ)を中心とし]前(南)に官庁、後(北)に市場がある。左(東)に祖廟、右(西)に神社がある。中央に宮城がある。左右(東西)に民家がある。」[前朝後市、左祖右社、中央宮闕、左右民廛(みんてん)]の原則に、だいたいはしたがっていたと考えられる。そして、長者は城門の近くにすみ、貴人は、宮廷への道に居をかまえていた。
倭人の使者たちは、東側の東陽門からはいったのであろうか(洛陽城には、東側に建春門、東陽門、青明門の三門があり、南側に四門、西側に三門、北側に二門、計十二の門があった)。二層からなる地上百尺(二十数メートル)の城門の楼が、まず、倭の使を圧する。大道は、三つに仕切られていた。中央の御道(ぎょどう)は、公卿(こうけい)高官の専用路である。両側に1メートル(四尺余)ほどの高さの土の墻(かき)が築かれ、その両端の通路が一般人用である。左側の通路から入り、右側の通路から出る定めであった。道の両側は、青槐(えんじゅ)や柳の並木になっていた。大道は、九輛の車が、並んで走りうる幅があった。
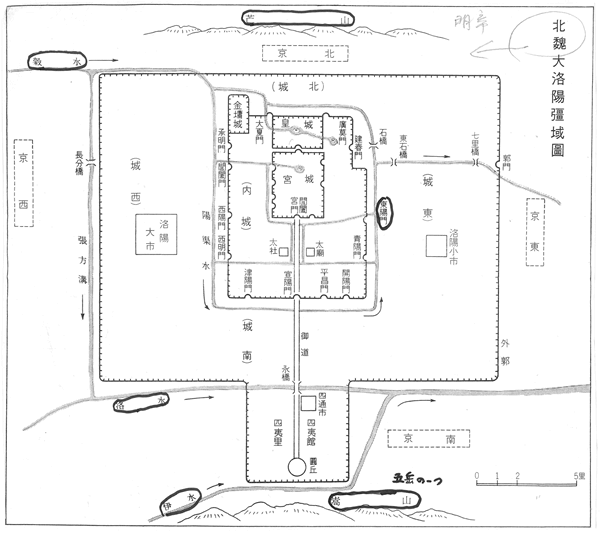
城内にはいった倭の使者たちの耳目を、まず驚かせたのは、鳥の羽の車蓋をつけ、金に飾った横木に倚(よ)った人をのせ(当時、車には立って乗った)、人の背丈ほどの大きさの車輪をとどろかせて走りさる四頭だての馬車であった。竹をそいだような耳をもつ馬は、泡をかみ、さんさんと鈴の音を秋空にあげて疾駆する。また、黄金の面繋(おもがい)でくつわを飾った色よき馬に銀の鞍をおき、むちをあげ、戞戞(かつかつ)とひずめの音も高らかに、貴公子ふうの若者が、通りすぎて行く。当時の倭では、馬車や、乗馬の風習はなたかった。
倭の使者たちにとって、楼閣は、雲にそびえるようにみえた。道をはさんで立つ貴族の屋敷の甍(いらか)の波は、白い壁と朱の柱と飾りのある窓とにはえて、まぶしいほどであった。宮殿は、空に浮かぶようにもみえた。
都大路は、砥石(といし)のようになめらかである。青槐(えんじゅ)が、その上に枝をさしのべ、大路にそった疏水(そすい)が、潺湲(せんかん)たる音をあげている。
柏(かしわ)や松のしげった空地で、高価な剣を身につけ、きらきらと色彩もあざやかな衣服をまとった少年たちが、闘鶏を行なっているのがみえる。
歩いている少女の、なんと美しく軽やかなことであろう。白いたおやかな腕に、金の腕輪をはめ、頭に金の雀のかんざしをさし、細い腰に翠(みどり)の玉をつけ、金銀の刺繍の絹の上衣をつけ、軽やかなもすそをひるがえしている。夜光珠の耳飾りに、細い指をあてながら、長いまつげの、黒く明るいひとみで、驚いたようにこちらを見ている。
あらい織りの、短い着物を着た、貪しげな老人も通りすぎて行く。あかじみた冠と履(くつ)で、あらい布の頭巾をつけ、粗末な麻の服をきた男が、李(すもも)と梨とをつんだ車をおして行く。桃と柰(りんご)とをのせた牛車が通りすぎて行く。
宮殿に近よれば、高い門の屋上の鉄の大鳳(おおとり)は、甍(いらか)をふみ、首(かしら)をあげ、両翼を青空に張り、風にさからって、いまにも飛ぼうとするかのようである。門のほとりに、矛をもち、盾をかけた衛士が立っている。
門をくぐり、宮城内にはいれば、西游園がある。園のなかに、魏の文帝(220年~226年)によって、221年に築かれた楼観(展望台)の凌雲台が、文字どおり、雲を犯してそびえている。これは、高さ二十丈(30メートル弱)といわれ、宮城内随一の高層建築であった。222年につくられた霊芝池には、巨大な石を刻んだ鯨魚がおかれ、その背が、釣り台となっていた。鯨魚は、地下から躍り出たようであった。穀水から引かれた水を、蟾蜍(せんじょ)[大ひきがえる]が含みうけ、それを、九つの竜が、池に吐きだしている。竜のかたわらには、銅を鋳(い)た人像、金を鋳た人像が立っている。『魏略』によれば、池には、博士馬均の作った司南車があり、水転百戯の妙を尽くしたという。池に舟もうかび、緑の水が、宮殿をうつしている。
庭には、赤い芍薬が燃え、大つぶのぶどうが潰(つい)え、ざくろが裂け、風が、甘いにおいを運んでくる。
池を囲む形の宮殿の軒の四隅では、雨だれをうける竜首が、空をにらんでいる。
明帝[曹叡(そうえい)、226年~239年]は、宮殿建築と庭園作りに精をだし、みずから土を握って先頭に立った。
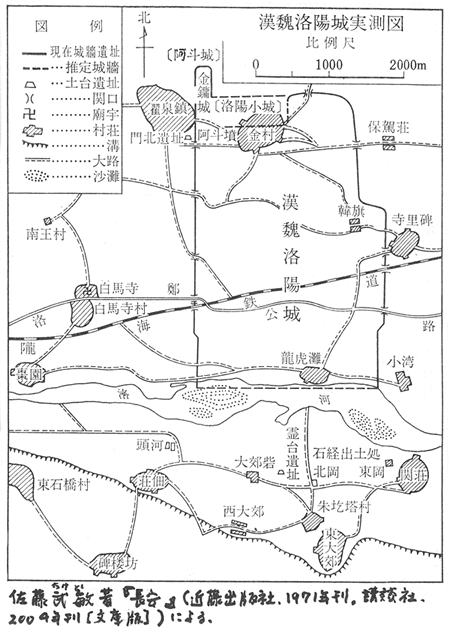 『魏春秋』をあらわした孫盛はいう。
『魏春秋』をあらわした孫盛はいう。
「景初元年、明帝は、いよいよ宮殿をたかくし、観閣を彫刻で飾ろうとし、白石英と紫石英と五色の大石を太行の穀城の山からとった。景陽山を芳林園に起こし(作り)、松竹草木をうえ、禽獣を捕えて、もってその中にみたした。その時には、多くの労役が頻繁におこったので、帝が自身で土を掘り、群臣に率先してはたらいた。そこで、三公以下、力をつくさないものはなかった。」(六世紀のはじめにできた酈道元(れきどうげん)の『水経注』に引用された文による。)
臣下の中には、いさめるものもおり、のちに、北魏の孝文帝(471年~499年)は、「魏の明帝奢侈(しゃし)をもって王朝を失なう」と評している。
後漢末の戦乱で、一度は、洛陽の街が焦土となったこともあり、倭の使がおとずれたころは、宮殿も庭園も、築造後まもないものが多く、もっとも華麗な時代であった。
倭の使は、また、宮城の西にあった金市と名づけられる市場をおとずれることもあったであろう。
市場には、道が縦横に通じている。商家は軒をつらね、売買するものは、織るがごとくである。
西域からきた金の瓶(かめ)、銀の瓮(もたい)、水晶の鉢、瑪瑙(めのう)瑠璃(るり)の碗、赤玉の巵(さかずき)、象牙の器を売る店がある。笙、笛、鼓、箏(こと)、琴(こごと)、瑟(おおごと)、琵琶、筑、箜篌(くご)[ハープ]などの楽器をあつかう店がある。邪馬台国のものよりはるかに大きな桃、梨、なつめ、りんご、柿、栗を売る店がある。そこには、崑崙山から伝えられたという名も知らぬ果物もおかれている。洛水や伊水でとれたすっぽん、えび、鯉、魴(ぼう)が売られている。穀類を売る店がある。塩を売る店がある。獣肉を売る店がある。熊の掌も並べられている。矛(ぼう)、戈(か)、戟(げき)、刀剣、角弓が売られている。縞(しろぎぬ)、羅(あやぎぬ)、紈(ぬりぎぬ)、縠(うすぎぬ)、綵(いろぎぬ)などの布帛(ふはく)が売られている。北方産の良馬も売られている。通行人の足をとめ、卜筮を行なっているものがある。
くつわをあげ、あわを吹く馬、その馬にむちうつ人、走りさる馬車、人と馬と馬車が往きかい、車の轂(こしき)が触れあい、埃(ほこり)は空にまいあがる。その喧噪(けんそう)のさまは、鼎(かなえ)のわくようである。
これらの強烈な印象は、いずれも、祖国邪馬台では、夢にも、想像できないものであった。―
魏の皇帝は、倭の使者たちを、異例ともいえる好遇によってむかえている。
日本は、その後も、中国へは、一流の人物を選んで使としているから、このときの使者たちも、おそらくは、邪馬台を代表するにたる一流の人たちであっただろう。
倭の使たちは、魏の皇帝に、直接まみえたと思われる。
左太沖は、三都をうたい、「魏都の賦」のなかでのべている。
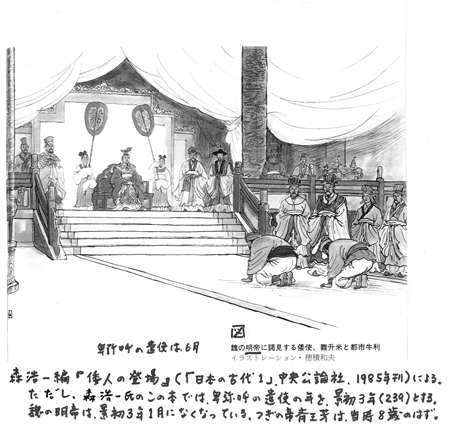 「東鯷(とうてい)の人も、西傾(さいけい)の人も、荊南(けいなん)の人も、朔北(さくほく)の人も、みな魏をしたい、遠く山水をこえ、貢物を負い、訳を重ねて来る。夷人の酋長(かしら)、袵(えり)をたれ、帝闕(ていけつ)を拝す。天子は、文昌殿に置酒し、高く幕を張り、宴を蛮夷に賜(たま)う。宵(よい)には庭燎(かがりび)をたき中華の人、四裔(しえい)の人あい雑(まじわ)る。諸侯の冠は、岌岌(きゅうきゅう)と高く、夷人の弁髪は、累累(るいるい)重なる。清酒は、済河の水のように清く、濁酒は黄河の水のように濁る。和して飲み楽しむ。天帝の音楽を九たび奏し、あるときは、雷のような響きがおこる。金(かね)、石(いし)、糸(いと)、竹(たけ)、匏(ひさご)、土(つち)、革(かわ)、木の八音の楽器が奏せられ、舞人は、盾、斧、雉の羽、旄牛(やく)の尾を手に舞う。四夷の音楽もかなでられ、もって四夷の君を娯(たのし)ませ、八方の人を和睦させる。」
「東鯷(とうてい)の人も、西傾(さいけい)の人も、荊南(けいなん)の人も、朔北(さくほく)の人も、みな魏をしたい、遠く山水をこえ、貢物を負い、訳を重ねて来る。夷人の酋長(かしら)、袵(えり)をたれ、帝闕(ていけつ)を拝す。天子は、文昌殿に置酒し、高く幕を張り、宴を蛮夷に賜(たま)う。宵(よい)には庭燎(かがりび)をたき中華の人、四裔(しえい)の人あい雑(まじわ)る。諸侯の冠は、岌岌(きゅうきゅう)と高く、夷人の弁髪は、累累(るいるい)重なる。清酒は、済河の水のように清く、濁酒は黄河の水のように濁る。和して飲み楽しむ。天帝の音楽を九たび奏し、あるときは、雷のような響きがおこる。金(かね)、石(いし)、糸(いと)、竹(たけ)、匏(ひさご)、土(つち)、革(かわ)、木の八音の楽器が奏せられ、舞人は、盾、斧、雉の羽、旄牛(やく)の尾を手に舞う。四夷の音楽もかなでられ、もって四夷の君を娯(たのし)ませ、八方の人を和睦させる。」
倭の使たちも、また、このようにして迎えられたのであろうか。
倭の使たちは、緑の酒のつがれた黄金の盃をあげながら、魏朝の威容に打たれ、好遇に感謝し、長途の旅の労が、十分にむくわれたことを感じたであろう。
倭の使たちは、たしかに洛陽にあらわれた。そのはなやかな様子を、瞳におさめた。しかし、洛陽の城壁をあとにした倭の使は、どこに帰ったのであろうか。そのうしろ姿は、重なる山々と、風と濤(なみ)と、茫茫(ぼうぼう)千七百年の歳月のかなたに消えている。
邪馬台国の時代から、およそ千年を経た元寇のさいでさえ、蒙古側の使者は、日本をみて、「はるかに対馬島を望み、大洋万里、風濤(ふうとう)天を蹴る。」とのべている。 邪馬台国への道は遠い。しかし、その道を、今、たどってみようと思う。
[佐藤武敏著『長安』(講談社学術文庫、2004年刊)]
「・・・・北魏洛陽城のプランを見てみると、その規模について、『洛陽伽藍記』の巻末のところで東西が20里、南北が15里と記している。これに対し、晋の皇甫謐の『帝王世紀』(『続漢書』那国志劉昭注所引)では東西が6里11歩、南北が9里100歩と言い、晋の『元康地道記』(同じく劉昭注所引)では東西が6里10歩、南北が9里70歩と言い、元『河南志』でも俗に東西が6里、南北が9里とつたえているので、96城と呼ぶと言っている。『洛陽伽藍記』と『帝王世紀』『元康地道記』との記載を比較すると、前者は東西が南北より大きいのに、後者は南北が東西より大きいし、前者は後者より規模が大きいという重要な相違がある。・・・・ ・・・・元『河南志』では、『洛陽伽藍記』の規模が他の記録より大きくなっている理由について、城外をもふくめたためであると説明している。この説にしたがう研究家が多い。」
古代の市については、第347回講演記録参照。




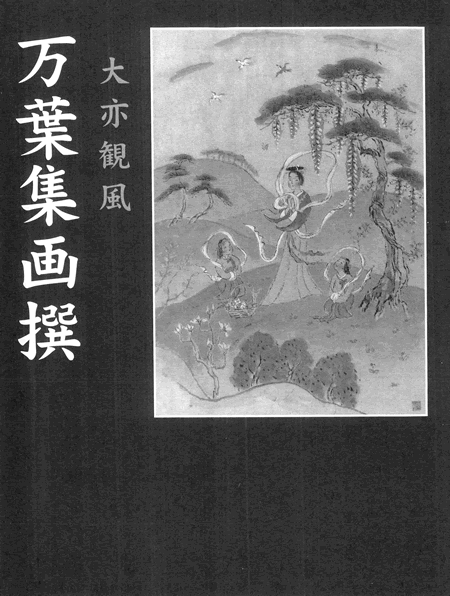


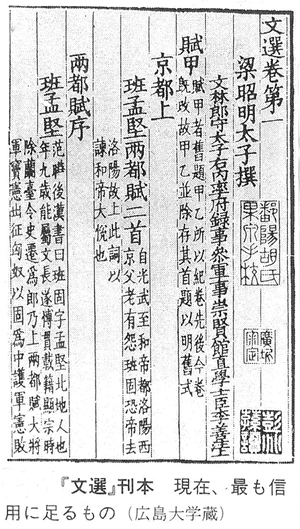

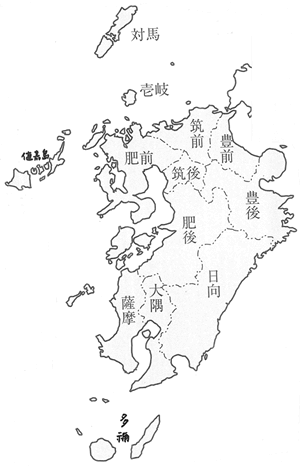 「刺史」はもともと郡国の監察官であった。時代がたつにつれて職務の重要性を増し、地方の行政から軍事、すなわち民治・兵制をもつかさどる官吏となった。したがって「大率」とは、大督率・大将帥を意味する名称である。「大率」が女王国より以北の諸国を巡撫するかたわら、検察(民政・司法)や軍事、そして外交関係の事務をもつかさどっていたとみてよい。(謝銘仁著『邪馬台国 中国人はこう読む』)
「刺史」はもともと郡国の監察官であった。時代がたつにつれて職務の重要性を増し、地方の行政から軍事、すなわち民治・兵制をもつかさどる官吏となった。したがって「大率」とは、大督率・大将帥を意味する名称である。「大率」が女王国より以北の諸国を巡撫するかたわら、検察(民政・司法)や軍事、そして外交関係の事務をもつかさどっていたとみてよい。(謝銘仁著『邪馬台国 中国人はこう読む』)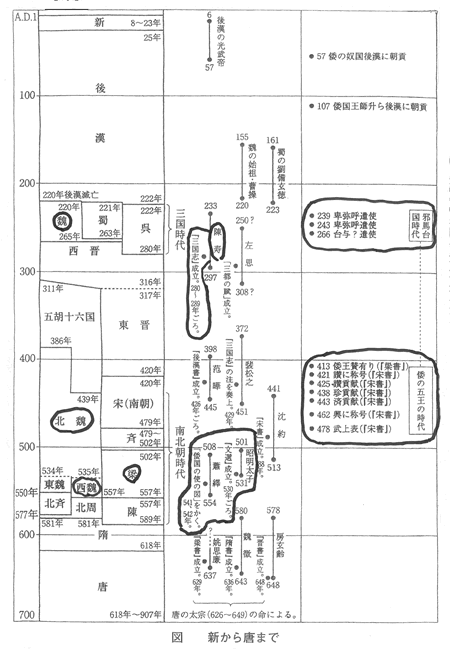 魏晋の時代は、兵権をもつ地方官で「使持節・都督」であるのが、一般的であった。『三国志』の著者陳寿は、「漢代の末以来、刺史は諸郡を総統し、行政を、都の外で行なった。これは、まえの時代に監察だけを行なっていたのと異なっている。」とのべている。
魏晋の時代は、兵権をもつ地方官で「使持節・都督」であるのが、一般的であった。『三国志』の著者陳寿は、「漢代の末以来、刺史は諸郡を総統し、行政を、都の外で行なった。これは、まえの時代に監察だけを行なっていたのと異なっている。」とのべている。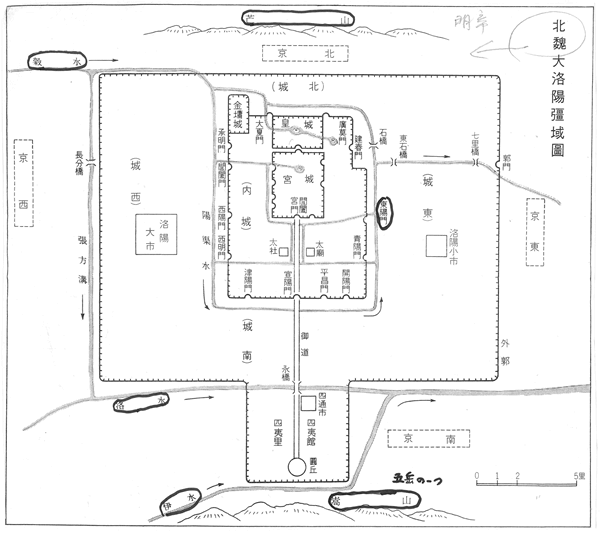
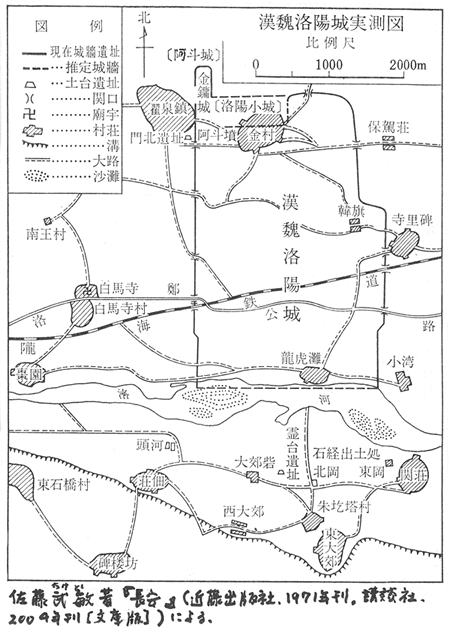 『魏春秋』をあらわした孫盛はいう。
『魏春秋』をあらわした孫盛はいう。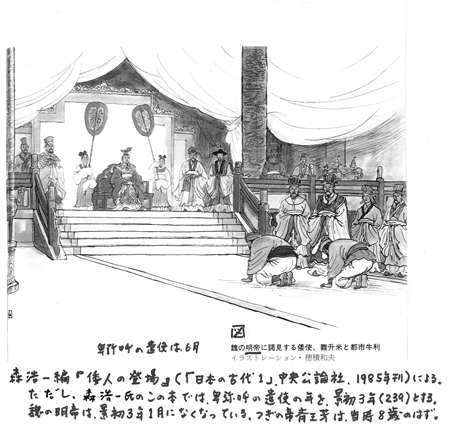 「東鯷(とうてい)の人も、西傾(さいけい)の人も、荊南(けいなん)の人も、朔北(さくほく)の人も、みな魏をしたい、遠く山水をこえ、貢物を負い、訳を重ねて来る。夷人の酋長(かしら)、袵(えり)をたれ、帝闕(ていけつ)を拝す。天子は、文昌殿に置酒し、高く幕を張り、宴を蛮夷に賜(たま)う。宵(よい)には庭燎(かがりび)をたき中華の人、四裔(しえい)の人あい雑(まじわ)る。諸侯の冠は、岌岌(きゅうきゅう)と高く、夷人の弁髪は、累累(るいるい)重なる。清酒は、済河の水のように清く、濁酒は黄河の水のように濁る。和して飲み楽しむ。天帝の音楽を九たび奏し、あるときは、雷のような響きがおこる。金(かね)、石(いし)、糸(いと)、竹(たけ)、匏(ひさご)、土(つち)、革(かわ)、木の八音の楽器が奏せられ、舞人は、盾、斧、雉の羽、旄牛(やく)の尾を手に舞う。四夷の音楽もかなでられ、もって四夷の君を娯(たのし)ませ、八方の人を和睦させる。」
「東鯷(とうてい)の人も、西傾(さいけい)の人も、荊南(けいなん)の人も、朔北(さくほく)の人も、みな魏をしたい、遠く山水をこえ、貢物を負い、訳を重ねて来る。夷人の酋長(かしら)、袵(えり)をたれ、帝闕(ていけつ)を拝す。天子は、文昌殿に置酒し、高く幕を張り、宴を蛮夷に賜(たま)う。宵(よい)には庭燎(かがりび)をたき中華の人、四裔(しえい)の人あい雑(まじわ)る。諸侯の冠は、岌岌(きゅうきゅう)と高く、夷人の弁髪は、累累(るいるい)重なる。清酒は、済河の水のように清く、濁酒は黄河の水のように濁る。和して飲み楽しむ。天帝の音楽を九たび奏し、あるときは、雷のような響きがおこる。金(かね)、石(いし)、糸(いと)、竹(たけ)、匏(ひさご)、土(つち)、革(かわ)、木の八音の楽器が奏せられ、舞人は、盾、斧、雉の羽、旄牛(やく)の尾を手に舞う。四夷の音楽もかなでられ、もって四夷の君を娯(たのし)ませ、八方の人を和睦させる。」