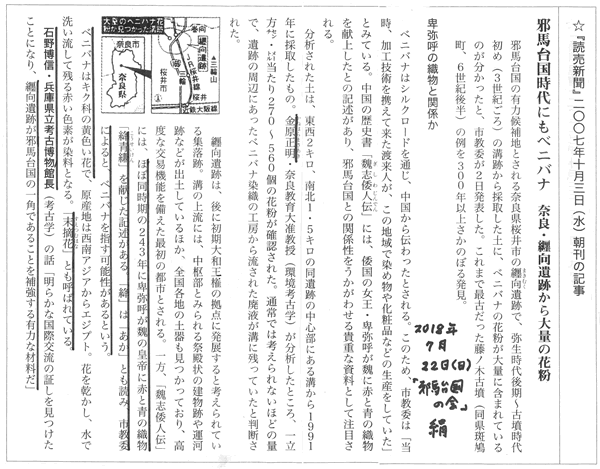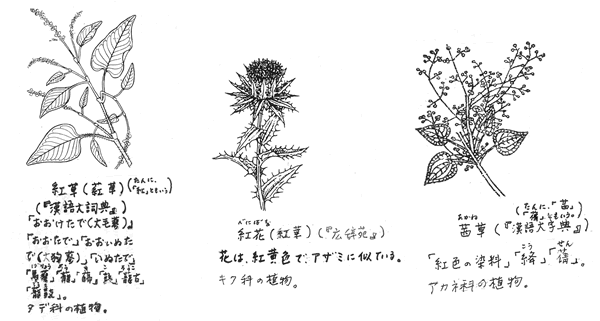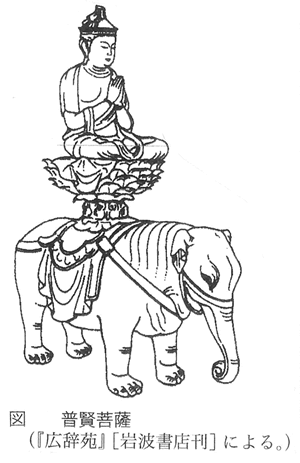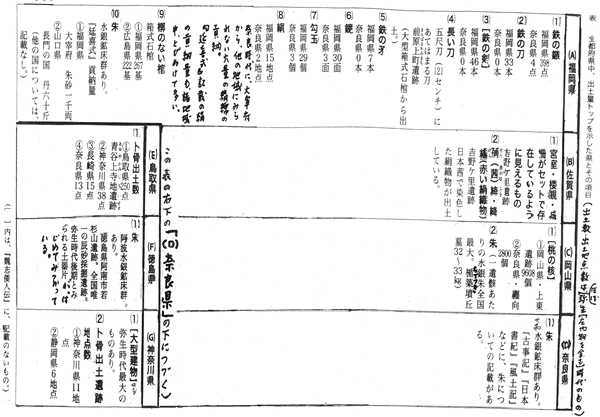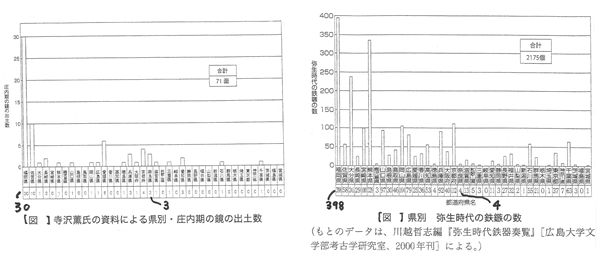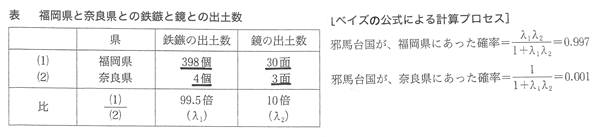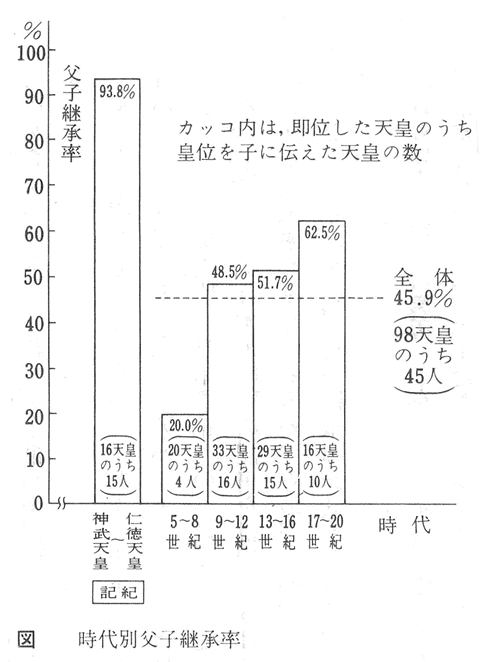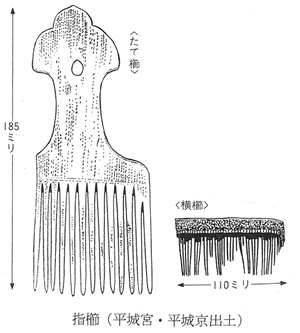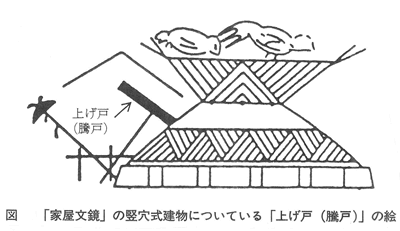| TOP>活動記録>講演会>第380回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
Rev.1 2019.10.29 |
第380回 邪馬台国の会(2019.6.23 開催)
| ||||
1.新刊『誤りと偽りの考古学・纏向』出版記念特別講演会
|
2.年代論の検討
|
■直系相続の問題 笠井新也は、つぎのようにのべている。これは、世代数に対する疑間をのべたものである。 「わが国の古代における皇位継承の状態を観察すると、神武天皇から仁徳天皇にいたるまでの十六代の間は、ほとんど全部父から子へ、子から孫へと垂直的に継承されたことになっている。しかし、このようなことは、私の大いに疑問とするところである。なぜならば、わが国において史実が正確に記載し始められた仁徳以後の歴史、とくに奈良朝以前の時代においては、皇位は、多くのばあい、兄から弟へ、弟からつぎの弟へと、水平的に伝えられているからである。かの仁徳天皇の三皇子が、履中(りちゅう)・反正(はんぜい)・允恭(いんぎょう)と順次水平に皇位を伝え、継体天皇の三皇子が、安閑(あんかん)・宣化(せんか)・欽明(きんめい)と同じく水平に伝え、欽明天皇の三皇子・一皇女の四兄弟妹が、敏達(びたつ)・用明・崇悛(すしゅん)・推古と同じく水平に伝えたがごときは、その著しい例である。 したがって、この事実を基礎として考えるときは、仁徳天皇以前における継承が、単純に、ほとんど一直線に垂下したものとは、容易に信じがたいのである。 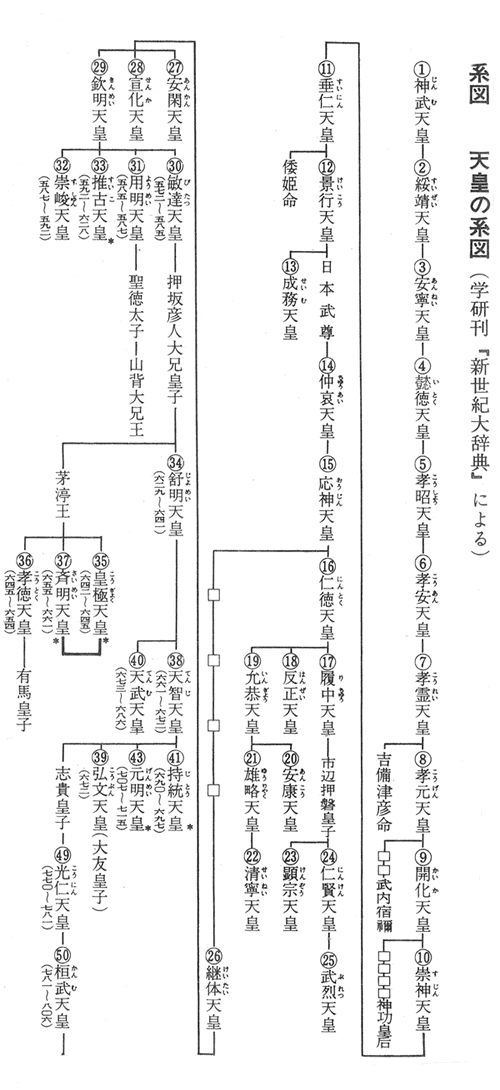
山路愛山(やまじあいざん)は、その力作『日本国史草稿』において、このことに論及し、『直系の親子が縱の線のごとく相次いで世をうけるのは、中国式であって、古(いにしえ)の日本式ではない』。それは、『信ずべき歴史が日本に始った履中天皇以後の皇位継承の例を見ればすぐわかる』『仁徳天皇から天武天皇まで通計二十三例のあいだに、父から子、子から孫と三代のあいだ、直系で縦線に皇位の伝った中国式のものは一つもなく、たいてい同母の兄弟、時としては異母の兄弟のあいだに横線に伝って行く』『もし父子あいつづいて縦に世系の伝って行く中国式が古(いにしえ)の皇位継承の例ならば、信ずべき歴史が始ってからの二十三帝が、ことごとくその様式に従わないのは、誠に異常なことと言わなければならない。ゆえに私達は、信ずべき歴史の始まらないまえの諸帝も、やはり歴史後と同じく、多くは同母兄弟をもって皇位を継承してであろうと信ずる』と喝破(かっぱ)しているのは傾聴すべきである。」(「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫命」『考古学雑誌』第十四巻、第七号、1924年「大正13年」4月、所収) さらに、つぎのような事例もある。 たとえば、為政者である江戸幕府の将軍のばあいでも、五代将軍徳川綱吉が、家康を一代目として五代目であることは、(「五代将軍綱吉」といういい方をよくするので)すぐに答えられる人は多いであろう。しかし、家康から数えて、「何世目」であるかをたずねられれば、答えられない人が多くなるであろう(綱吉は、三代将軍家光の四男で、家康から数えて「三世目」)。
■年代推定の構造上の問題 また、公理(議論の出発点、前提)について、二つの規則をあげている。 さらに、論証について、三つの規則をあげている。 パスカルの方法をまとめれば、自明のものをのぞくすべての「言葉」を「定義」し、また、自明でないすべての「命題」を「証明」しつくすということになるであろう。
■現代の公理主義 現代の公理主義が、パスカルの説いた方法と異なる点は、主として「公理」についての考え方にある。パスカルにおいては、「公理」は「それ自身で完全に明証的なことがら」で、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないと考えられていた。ところが十九世紀のはじめに、「万人に承認される」とはいえない公理をもとにして、完全に無矛盾な非ユークリッド幾何学が建設されるにおよんで、この「公理」についての考え方は大きくゆらいだ。そしてドイツのヒルベルト(1862~1943)により、公理の考え方についての大転換が行なわれた。 一言でいえば、ヒルベルトは、「公理」はなんら自明の真理である必要はなく、たんに明確に定められた「仮定」で十分であるとしたのである。すなわち、いくつかの「仮定(公理)」をおき、そこから、形式的に結論をみちびいて、そこに矛盾を生じなければよいとしたのである。 以上のべてきたことについて、いますこし補足をしておこう。 京都大学人文科学研究所の教授であり、西洋史学者であった会田雄次(あいだゆうじ)は、その著『合理主義』(講談社現代新書)のなかで、つぎのようにのべている。
■公理的方法についての私の立場 私が、「公理」は、あるていど、経験的事実や直感に合致したものが望ましい、と考えるのは、そのような立場の方が説得力があると考えるからであって、そのような立場をとらなければならないという論理上の根拠は存在しない。 十七世紀の末に、アイザックーニュートンは『プリンキピア』(原題『自然哲学数学的原理』)をあらわし、万有引力の法則をはじめて世に知らせた。これにより、天体の力学と地上の力学とは統一的に把握されることとなった。 『プリンキピア』は、ユークリッドの『ストイケイア』(幾何学言論)にならって書かれたものであった。 たとえば、ニュートンはその第1部で、「質量」や「運動量」などを定義したのち、公理をのべている。 【公理Ⅰ】 【公理Ⅱ】 【公理Ⅲ】 ニュートン力学の三法則も、ここで提唱されている。また、力の合成に関する「平行四辺形の公理」も、補足的に示されている。これらの公理から、力学の基本原理、たとえば「万有引力の法則」が演繹されている。 ユークリッドの幾何学とニュートンの力学とは、数学的なものと物理学的なものとして、現代では別々に把握されている。しかし、もともとは同質のものといえる。ともに、はじめに定義を示し、さまざまな定理・命題を導き出すという形をとっている。そして、導き出された定理・命題が、経験的事実と一致する。 私は、ユークリッドの『ストイケイア』やニュートンの『プリンキピア』は、経験科学のあるべき叙述の姿の、ある意味での典型をなしていると思うものである。 以上をまとめるならば、私は、わが国の古代の探求のために、基本的には、公理的方法にしたがう立場をとる。ただしこの公理は、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないとは考えないが、どのようなものであってもよいとはしない。ある程度、経験的な「事実」や直感に合致したものが望ましいとする。 また、用語は、可能なかぎり明確な定義により限定された一義的なものであることが望ましいとする。なお、「公理」の数は、できるだけ少なく、相互に独立のものが望ましいとする。
■私の邪馬台国論の論理構造 【公理I】 【公理Ⅱ】 この二つの公理を設定するとき、つぎのようなことがらが、定理的に導出される。 (2)神武天皇は、西暦280年~290年ごろの人となる。(このころからあとに、大和に古墳がおこり、刀剣、矛、鏃、鉄、鏡、玉などの分布の中心が、九州から大和に移っている。すなわち、記紀に記されている神武天皇の東征によって説明しうると思われる事実が存在する。) (3)崇神天皇は、西暦350~360年前後の人となる。(奈良県天理市大字柳本に存在する崇神天皇の陵を、東大の考古学者、歴史学者である斉藤忠博士は、四世紀の中ごろ、またはそれをやや降るころのものとしておられる。) そしてさらに(1)の「系」として、記紀によれば、天照大御神(卑弥呼)の活躍していた場所が、北九州であると考えられ、また大和朝廷が九州に興ったと考えられる少なからぬ根拠が存在するところから、 以上の議論は、【公理Ⅰ】【公理Ⅱ】をもうけ、そこから、統計学、確率論などの数学の論理をかけて、「定理」、あるいは「系」をみちびきだすという形をしている。 ヒルベルト的な公理設定の自由性をみとめる立場にたてば、【公理Ⅲ】として、「天照大御神=卑弥呼」をたてることも考えられる。そのほうが、全体の説明は簡単になるようにもみえる。 ただ、そのようにすると、【公理Ⅲ】の「天照大御神=卑弥呼」は、あるていど、【公理Ⅰ】と【公理Ⅱ】からみちびかれるので、【公理Ⅰ】【公理Ⅱ】【公理Ⅲ】の三つの公理における相互の独立性がやや失なわれる。 さて、まえにものべたように、「天動説」も一つの仮説であり、「地動説」も一つの仮説である。どちらの説が妥当であるかは、どちらの説のほうが、多くの観測事実にあっているとみられるかによって決定される。 これについては、東京大学の教授であった数学者、小平邦彦(こだいらくにひこ)が『数学のすすめ』(筑摩書房刊)のなかで、おもしろい例をあげている。 もろもろの観測事実をうまく説明できる仮説は、妥当なものとみとめるべきである。
■年代論における「類ハッブル定律現象」について----第378回参照
■父子継承の問題 私は、基本的には、じっさいには父子関係にないものが、『古事記』『日本書紀』には、父子関係と記されていることがあると思うものである。
■父子継承の率は時代をさかのぼるにつれて低くなる 古代の状況をより確実に椎測するためには、時代によって、平均在位年数がどう変わっているか、時代によって父子継承の率がどう変わっているかなどの、全体的な「傾向」あるいは「趨勢(すうせい)」をみることが必要である。 さて、五~八世紀、九~十二世紀、十三~十六世紀、十七~二十世紀の各時代ごとに、父子継承の率を計算すれば、下図のようになる。下図はつぎのようなことを意味する。 たとえば、十七~二十世紀においては、十六人の天皇が即位しており、そのうち、自分の子に皇位をゆずった天皇は十人である。その父子継承率は、62.5パーセント(10/16×100)となる。 図をみると、即位、退位の時期がはっきりしている第三一代用明天皇以後の時代においては、父子継承率は、時代をさかのぼるにつれ、低くなる傾向が、かなりはっきりとみとめられる。 (1)このように高い父子継承率は、時代をさかのぼるにつれ、父子継承率が低くなるという全体的・傾向」とはてきり相反する。 上代になるにしたがい、父子継承率が低くなる原因としては、つぎのようなことが考えられよう。 (2)おもに政治的な原因
■確率的にはきわめておきにくいことがら
■皇子出生率も高すぎる |
3.出雲神話と邪馬台国
|
伊邪那岐の命のおとずれた黄泉(よみ)の国とは? -黄泉の国とは、横穴式石室の内部なのか、喪屋のなかなのか、あるいは、洞窟のなかなのか- ■『古事記』『日本書紀』の記述 『古事記』『日本書紀』には、伊邪那岐の命(いざなぎのみこと)[伊弉諾の尊]が、死んだ妻の伊邪那美の命(いざなみのみこと)[伊弉冉の尊]を追って、黄泉の国を訪れる話がのっている。 まず、『古事記』には、つぎのように記されている。 「ここに、伊邪那岐の命は、その妻の伊邪那美の命にあいたいと思って、黄泉(よみ)の国に追っていった。伊邪那美の命が殿の騰戸(あげど)[縢戸(くみど)(さしど、とざしど、ちぎりど)とするテキストもある]から出てむかえた。 こう言って、その殿のうちにかえり入った。伊邪那岐の命は、大変長いあいだ待った。しかし、待ちかねて、左のみずらに剌していた湯津津間櫛(ゆつつまぐし)[神聖な櫛]の男柱(おばしら)[櫛の両端の太い部分。古代の櫛は、爪形のたて長の櫛で、男柱は長い]をひとつ取り欠いて、一つ火をともして、入って見たところ、蛆(うじ)が寄り集って音をたててうごめき、頭(かしら)には大雷がおり、胸には火雷(ほのいかずち)がおり、腹には黒雷がおり、陰(ほと)には柝雷(さきいかずち)がおり、左の手には若雷(わかいかずち)がおり、右の手には土雷(つちいかずち)がおり、左の足には鳴雷(なりいかずち)がおり、右の足には伏雷(ふしいかずち)がおり、あわせて八種(やくさ)の雷神(いかずちがみ)がいた。」 伊邪那岐の命は、驚きおそれて逃げかえった。 伊邪那岐の命は、黄泉の国と現世とのさかいの黄泉比良坂(よもつひらさか)に、千引(ちびき)の岩(いわ)[千人で引くほどの大きな岩]をおき、伊邪那美の命に、事戸(ことど)[夫婦のなかを絶つことば]を言いわたした、という。 平安時代の初期にできた『旧事本紀』には、 この説話の要点をまとめると、つぎのようになる。 この、黄泉の国訪問の話は、なにを意味するかについてのおもな説は、つぎの三つがある。
■高橋健自、後藤守一らの横穴式石室説 高橋健自は、1914年(大正3)に、「喜田(貞吉)博士の上古の陵墓を読む」(『考古学雑誌』四~七)という論文を発表した。 高橋健自は、およそ、つぎのようにのべる。 横穴式石室が、竪穴式石室よりも新しいことをうけいれたうえで、高橋健自の説を踏襲し、黄泉の国訪問の話は、横穴式石室についての描写であろうとしたのは、後藤守一(しゅいち)である。
■斎藤忠氏の横穴式石室説批判 斎藤忠氏は、まず。高橋健自らの、黄泉の国は、横穴式石室を反映しているとする説の根拠を、つぎの四点に整理する。 つぎに、斎藤忠氏は、この一つ一つの根拠を、あらためて検討し、この説話は、かならずしも、横穴式石室を反映しているとのみはいえないとする。 (A)さきの(1)の腐爛状態を示す遺骸は、喪屋の内部とみることも可能である。 (B)さきの(2)の、「一つ火」を燃やして見たことは、遺骸を安置した内部の、暗い状態を示すものであるが、このような暗い内部は、かならずしも、横穴式石室の内部にかぎらない。喪屋は、小さな簡粗な建物であったろうが、それには、出入口があるとともに密閉されており、しかも、布帛の類でおおわれていたことも考えられる。したがって「一つ火」を燃やして見るような状態にあったものとみなされ、喪屋の内部とすることも、不自然ではない。 (C)さきの(3)の、伊邪那岐の命が追われたという箇所も、伊邪那岐の命は、その途中、櫛や桃の実などを投げ、難をのがれたという内容で、神話を興味深く潤色している。これが、横穴式石室のながい羨道の光景あらわしているという根拠にはならない。 (D)さきの(4)の、千引の岩は、巨大な磐石を思わせる。古代において、この種のものに、呪力が内容されるとし、巨巌崇拝の思想が発達していることは明らかである。千引の岩は、このような思想のもとに、死者の住む汚穢(おわい)の国である黄泉の国と、現国(うつしくに)とを。呪的にさえぎることのできた磐石であって、これが、この坤話のなかに反映されているのである。ことに、遺跡の実際からみると、横穴式石室の入口にせよ閉塞の石材に用いられたとしても、それは、千引の岩というような表現の自然の大磐石ではなく、板石のようなものや、あるいは、石塊を充填させたにすぎない。この千引の岩をもって横穴式石室の閉塞石とする考えは、少し無理なこじつけのようなところがある。むしろ、邪をさける呪性を含む大磐石をもって、黄泉平坂という黄泉の国の境界をへだてたのである。
■斎藤忠氏の喪屋説 (1)横穴式石室よりも、喪屋のほうが、遺骸をのぞきみる機会がしばしばあったとみられる。遺骸を最終的に安置し、入口を閉塞した横穴式石室に、その後近親の人びとが、閉塞石を開いて入るという機会は、かならずしも度重なったものではなかったにちがいない。遺骸を安置した内部は汚れに満ちており、いったんはいった近親者は、外にでて汚れを払うことにも、容易ならないものがあったであろう。したがって、この機会は、追葬などのばあいに多く、供膳の儀式などは、内部でなく、入口の外においてなされたであろう。これにくらべて、喪屋の内部をのぞき見ることは、喪屋が、本来死の確認ということに根本の意味がある以上、頻繁になされたと思われる。この点、「蛆たかれとろろきて」という遺骸に接する機会は、むしろ喪屋に多く、喪屋であってこそ、このような神話の発生に都合がよかったのである。 「死人の葬式の儀は、随意に任されているが、まず、地(土)葬・火葬の二つがある。この島では、近年、神葬式に改めている。以来、地葬すべきは当然であるが、あるところでは、その棺を墓所に送り、モヤととなえる小屋内に備えておき、親子兄弟などが、このモヤに到り、その棺を開いて見ること数回、ついに数日をへ、屍が腐敗しても、臭気をいとわずおもむくときく。これは、人情が厚いのに似ているが、
その臭気をかぐものは、はなはだ健康を害する。また、近所を通行するものも、その臭気に触れれば、病気を伝染し、あるいは、一種の病気を醸(かも)すものである。衛生上はなはだよろしくない。今後このような弊習は、かならず改め、死んだものは、すみやかに埋葬すべきである。云々。諭達する。」 (2)『日本書紀』の一書などは、「殯歛(もがり)のところ」と、明確に記している。これは、喪屋そのものをあらわしている。伊邪那美の命の遺骸のあった場所を、もがりの場とする伝承の一部も、『日本書紀』の編纂のときに、残されていたもののようである。 このような考えが正しいとすれば、この神話が、横穴式石室の発達した五、六世紀以降に成立したとする説も、首肯されにくくなる。喪屋の慣習が古くから行なわれていた以上、もっと古くから、すくなくともその原型は存在していたとみとめるべきである。 なお、『日本書紀』や『旧事本紀』では、「もがり」に、「殯歛」という文字を用いている。 なお、『日本書紀』の、天の稚彦(あめのわかひこ)の死をのべた条に、「喪屋(もや)をつくりて殯(もがり)す」とある。
■私の喪屋説 奈良県北葛城郡河合町の佐味田(さみた)宝塚古墳から出土した有名な「家屋文鏡」に、上のような絵が書かれている。 この絵は、竪穴式の建物の絵である[『古事記』などにあらわれる室屋(むろや)か]。竪穴式の建物では、地表から数十センチ垂直に掘りくぼめて、床面をもうけ、その上に屋根をつくる。 吉野ヶ里遺跡の竪穴式住居などの戸も、このような形で復元されている。
■「騰戸(あげど)」か「縢戸(ちぎりど)」か 森浩一氏の洞窟説(講演資料で省略) まとめ (2)『古事記』『日本書紀』を、成心をもって読むのではなく、すなおに読むかぎり、四世紀や五世紀などよりも、もっとまえのこととして、記されているはずである。
■停喪十日---喪(も)を停(とど)むること十日(とをか) 岩波文庫本のように解釈すると、「仕事にしたがいながら哭泣し」、「他人は就(つ)いて歌舞飲酒す。」ということになってしまう。 養老令(よろうりょう)[「令」は、おもに行政法]の註釈書『令義解(りょうのぎげ)』の「喪葬令(そうそうりょう)」の昌頭に、つぎのようにある。 『日本書紀』をみてみよう。 「皇太子(ひつぎのみこ)[中大兄(なかのおおえ)の皇子、(斉明)天皇の喪(みも)を奉徒(ゐまつ)る。」 『日本書紀』の「孝徳天皇紀」の薄葬令(はくそうれい)のなかに、「庶民(おおみたから)亡(し)なむ時には、地(つち)に収(おさ)め埋(うづ)めよ。一日も停(とど)むること莫(な)かれ。殯(もがりや)営(つく)ること得(え)ざれ。」とのべられている。これは、「停喪(ていそう)[しかばねをととめること)]を一日もするなとのべているのである。 日本語の古語辞典の「喪(も)」の頃に、「しかばね」「なきがら」「ひつぎ」の意味がのっていないのは、不十分といえる。
|
| TOP>活動記録>講演会>第380回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |