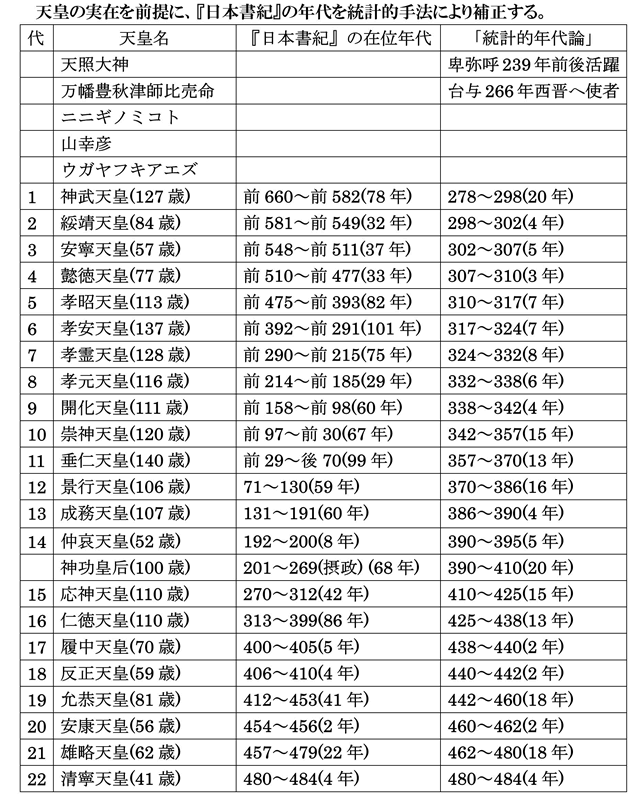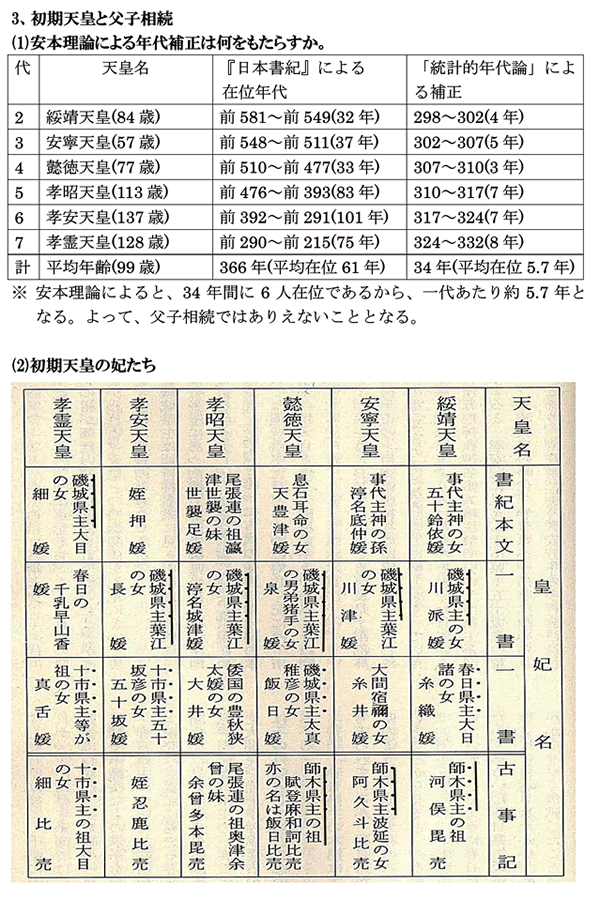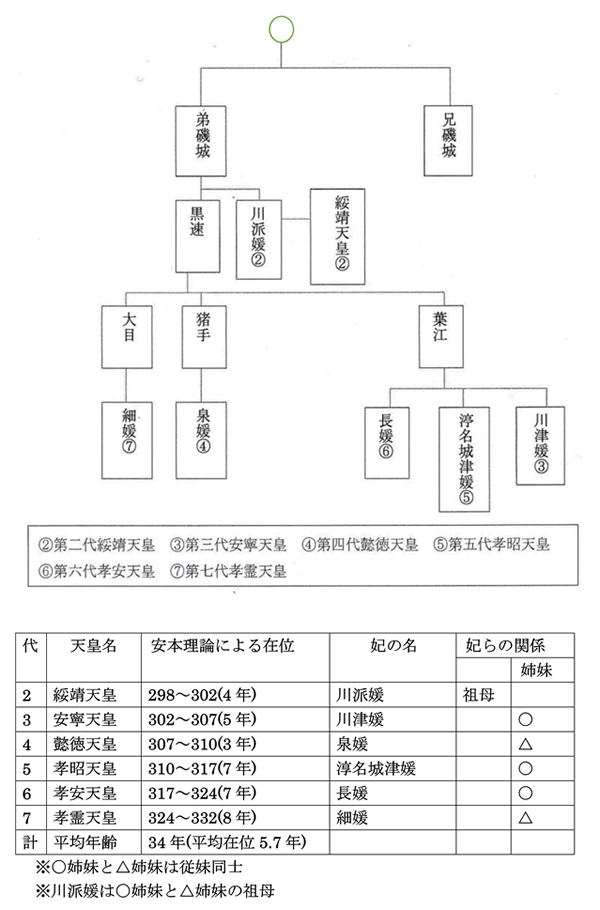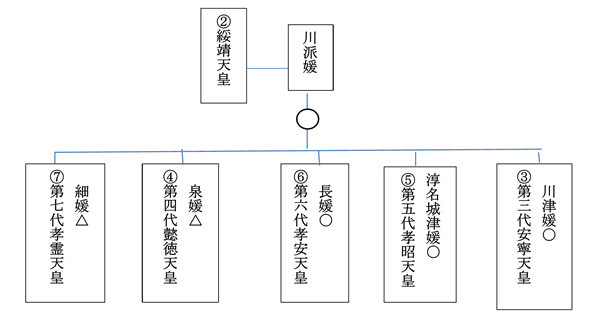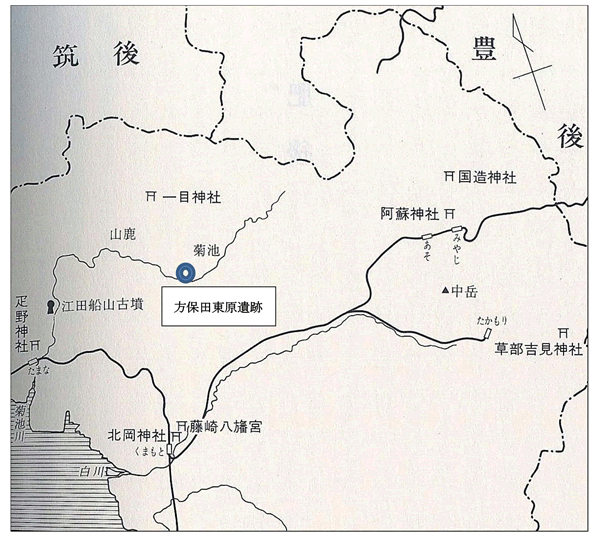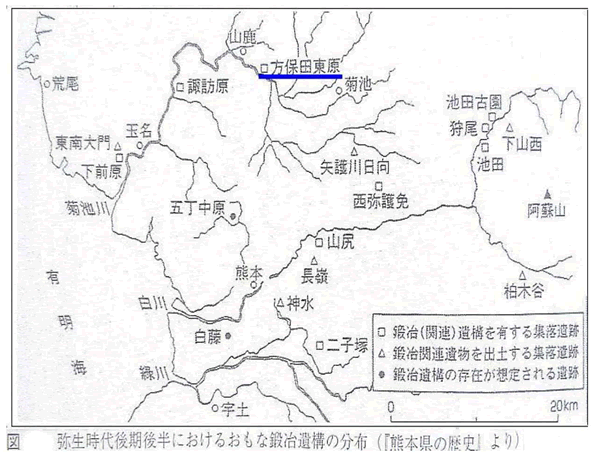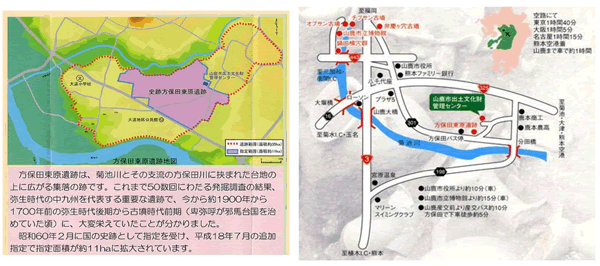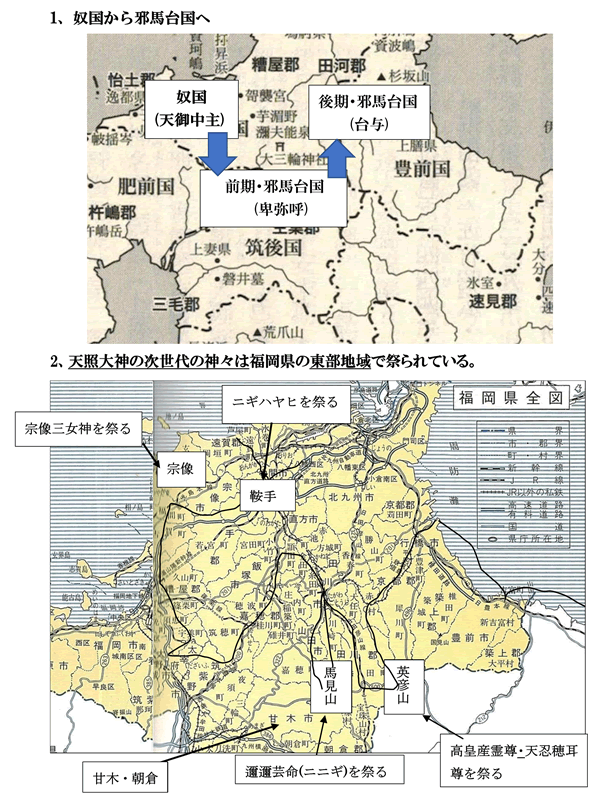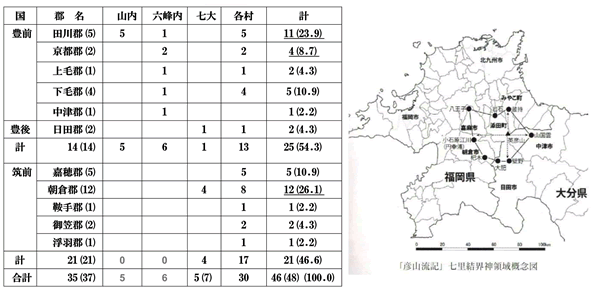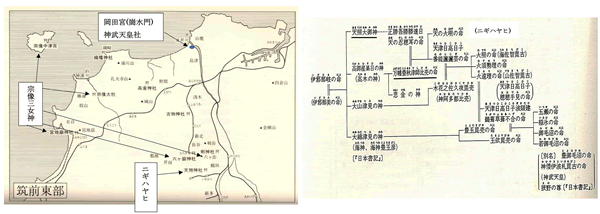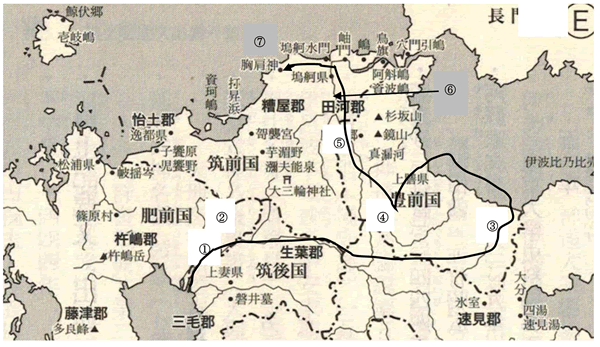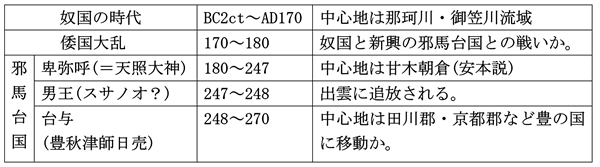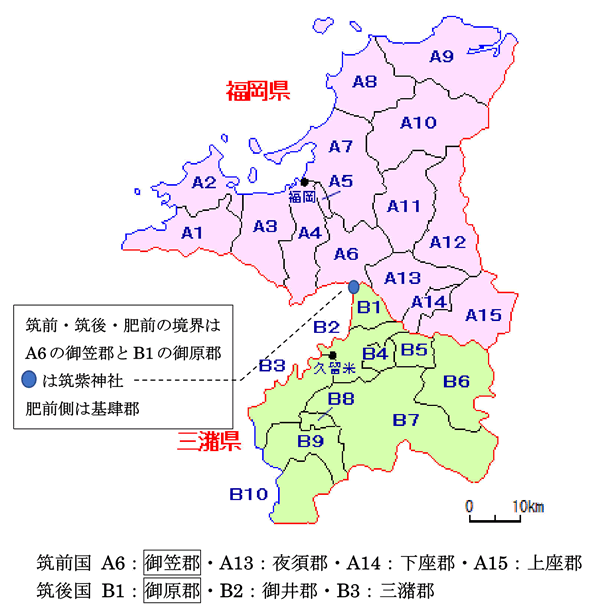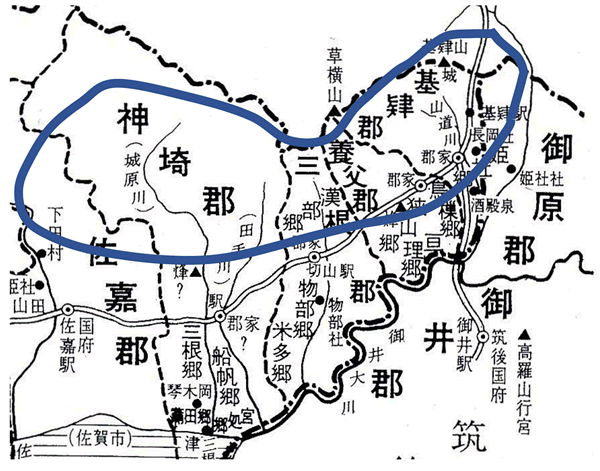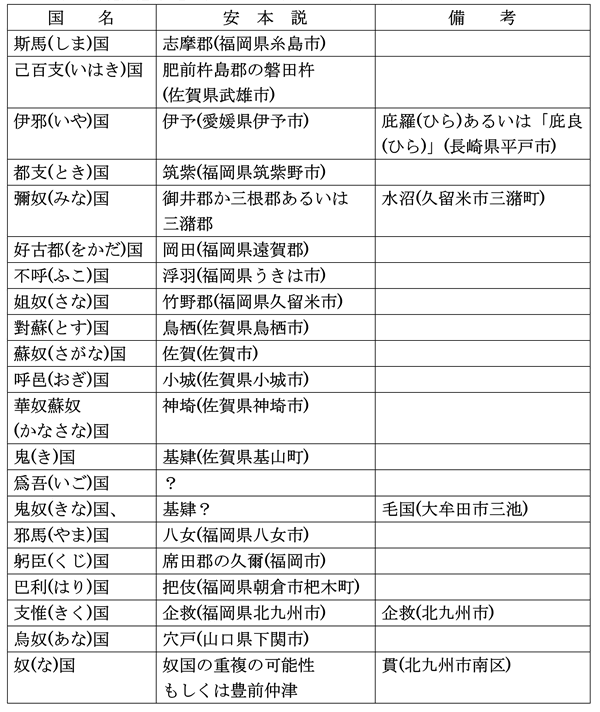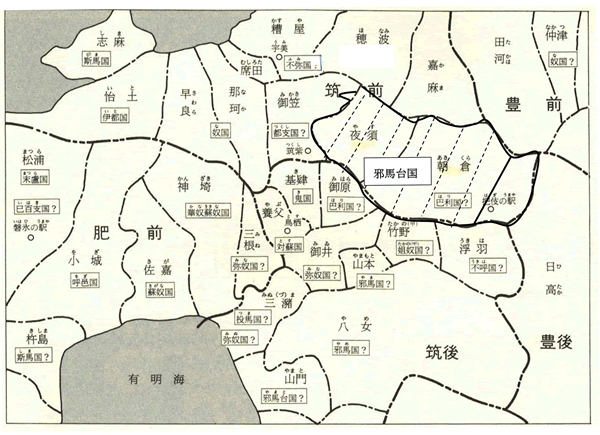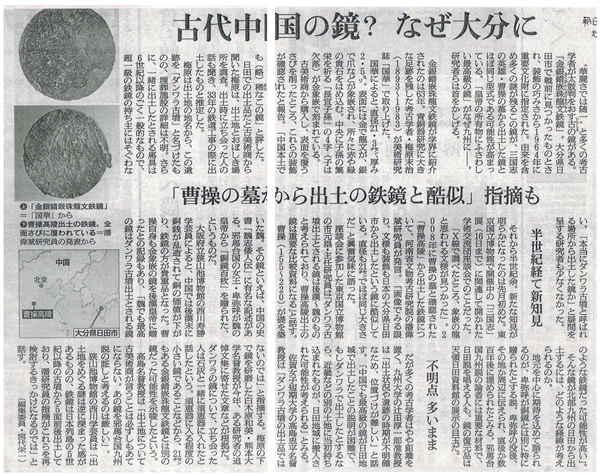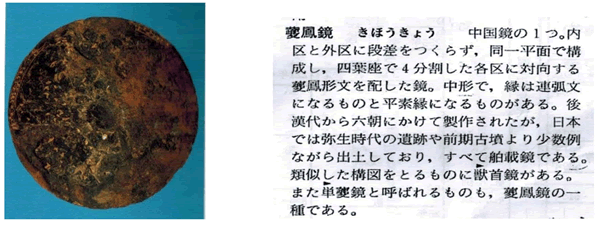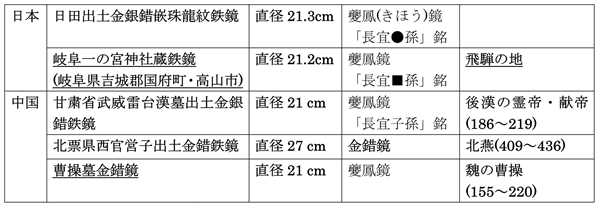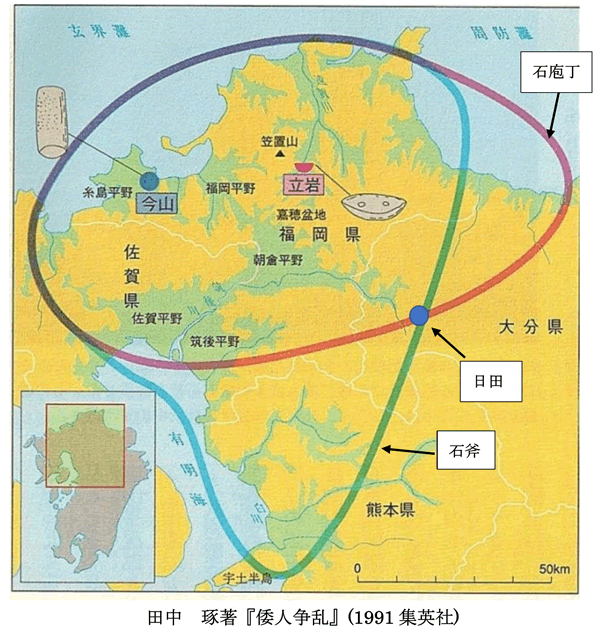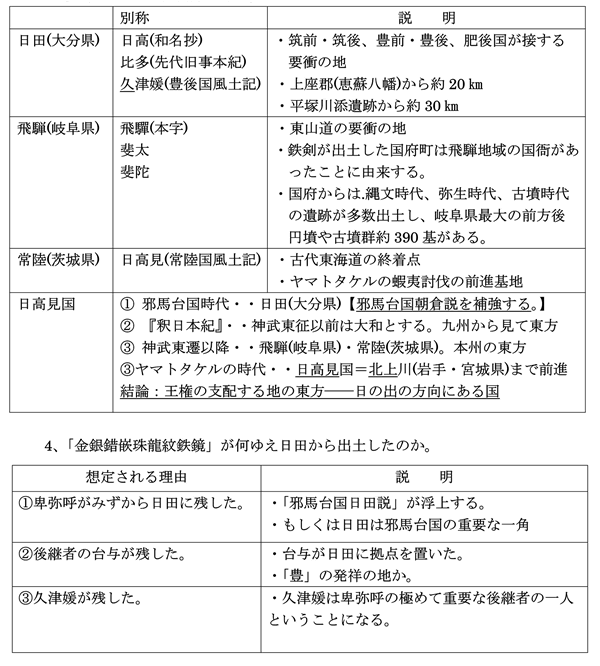【テーマⅠ】里程論について
 1、安本説の根幹-「邪馬台国朝倉説」
1、安本説の根幹-「邪馬台国朝倉説」
(1)水行10日の解釈
帯方郡→狗耶韓国(日数7日 距離7,000里)
狗耶韓国→対馬(日数1日 距離1,000里)
対馬→壱岐(日数1日 距離1,000里)
壱岐→末盧国(日数1日 距離1,000里)
合計:日数10日 合計距離10,000里
・帯方郡から邪馬台国まで12,000里
12,000里(全体)-10,000里(帯方郡~末盧国)=2,000里
『魏志倭人伝』の1里は約90mであるから、末盧国から2,000里×90m=180 kmの範囲内に邪馬台国があることになる。結果として近畿には到底届かない。
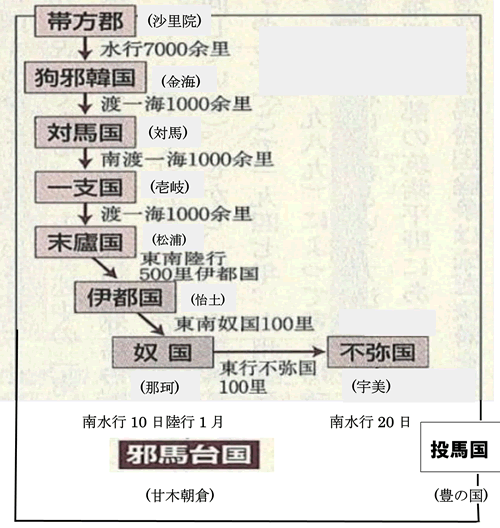 (2)「陸行1月」の解釈
(2)「陸行1月」の解釈
朝鮮半島内の陸行(7,000里)+九州内の陸行(2,000里)=1月と見なす。
1月(30日)を7:2に振り分けると23日と7日になる。
邪馬台国=甘木朝倉として、
帯方郡→狗邪韓国 7,000里、23日
末盧国→邪馬台国 2,000里、7日
計 9,000里、30日
結論:末盧国から歩いて7日程度の距離に邪馬台国がある。
行程:呼子・唐津→①糸島(伊都国)→③那珂川(奴国)→④宇美(不弥国)→⑤太宰府あたり→⑥夜須→⑦甘木朝倉
安本説を前提にすれば、「水行・陸行」の解釈として、帯方郡から水行すれば10日、帯方郡から陸行すれば1月と解釈すればいいということになる。
(3)投馬国まで「水行20日」の解釈
①帯方郡→末廬国=水行10日(前述のとおり)
②末廬国→投馬国=水行10日
計 水行20日
末廬国(呼子)→①唐津→②糸島→③博多→④新宮→⑤宗像→⑥芦屋→⑦洞海湾→⑧門司→⑨苅田→⑩行橋(京都郡)
③投馬国の有力候補地は豊の国
卑弥呼の後継者の「壹与(いちよ)」を「臺与(とよ)」とみる説あり
結論①:「水行10日陸行1月」は帯方郡を起点としなければならない。
結論②:投馬国への「水行20日」も同じく帯方郡を起点としなければならない。
結論③:このような結論は、安本説から必然的に導かれる。
【テーマⅡ】欠史8代ついて
1、戦後の通説的見解
第2代から第9代までの8人の天皇は、後世になって造作されたものとする。
2、安本説
天皇の実在を前提に、『日本書紀』の年代を統計的手法により補正する。
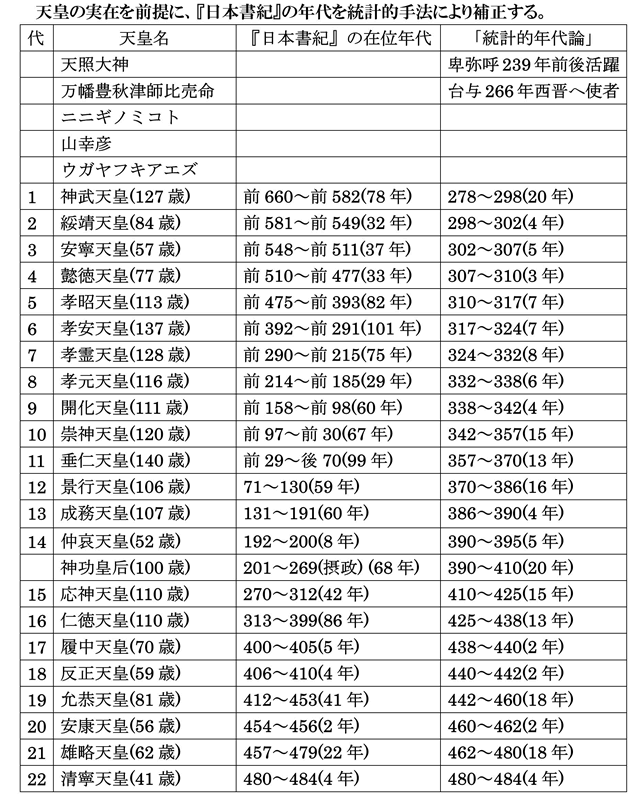
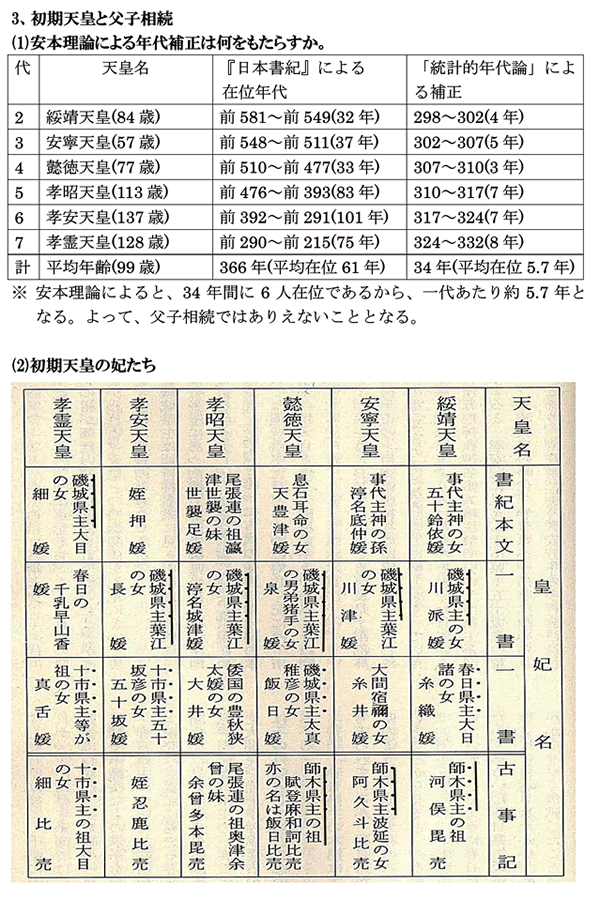
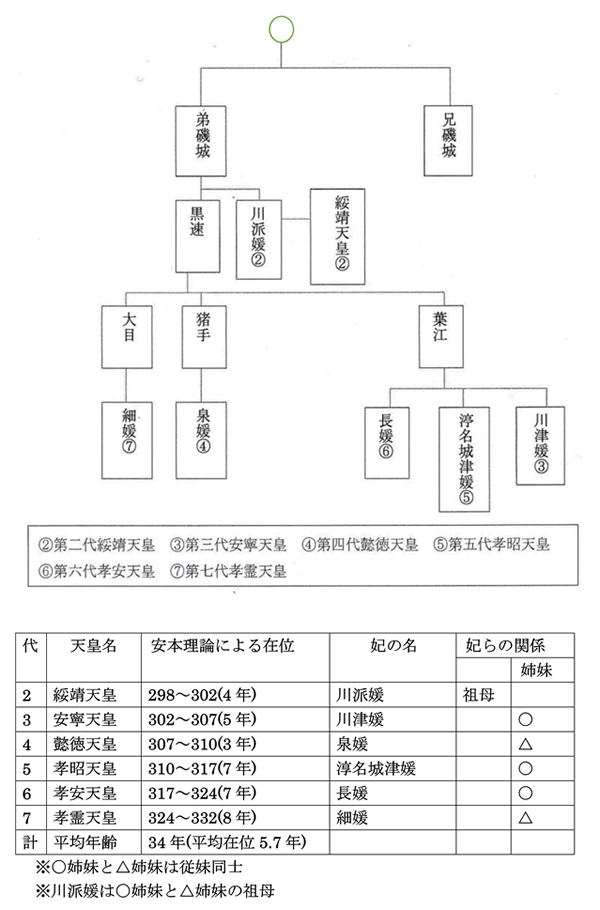
2代~7代の天皇妃は姉妹、従妹からなっていることは、母系社会が考えられる。
(3)初期天皇と母系制社会
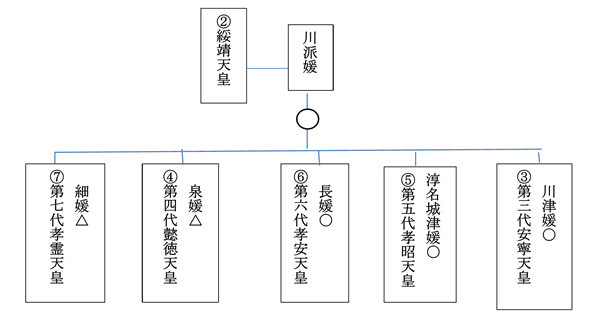
①磯城一族の姉妹と従妹の婿が持ち回りで天皇となっている。
②よって、第3代から第7代までの天皇は父子ではなく、ほぼ同世代の天皇ということになる。
③なお、磯城一族について、『先代旧事本紀』『新撰姓氏録』はニギハヤヒの子孫とする。
④日本の古代史は母系集団を追跡しない限り、その真相は見えない。
⑤このような結論は、安本氏の年代論から必然的に導かれる。
【テーマⅢ】狗奴国の拠点は方保田東原(かとうだ・ひがしばる)遺跡(山鹿市方保田字東原)
1、『魏志倭人伝』の記述
その八年、太守王頎(おうき)官に到る。倭女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の載斯良越等を遣わしで郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史(さいそうえんし)張政等を遣わし、因って詔書・黄幢を齎(もたら)し、難升米に拝仮せしめ、檄を為(つく)りてこれを告喩す。
・・・・・・
その南に狗奴国あり、男子を王となす。その官に狗古智卑狗あり。女王に属せず。
・・・・・・
狗奴国・・女王国の南にある。
女王国と敵対していた。
狗古智卑狗・・菊池彦か。
卑弥弓呼(ひみここ)・・彦御子の誤りか。
(1)安本説の「邪馬台国朝倉説」を前提にすれば、その南方に狗奴国は所在したことになる。
(2)菊池川流域に邪馬台国時代と重なる「方保田東原(かとうだ・ひがしばる)遺跡」という大遺跡があるが、ほとんど知られていない。
これは近畿説を主流とする考古学界において、おそらく意図的に無視ないし軽視された結果である。
(3)邪馬台国九州説にとってきわめて重要な遺跡であり、今後積極的に広報を行う必要がある。
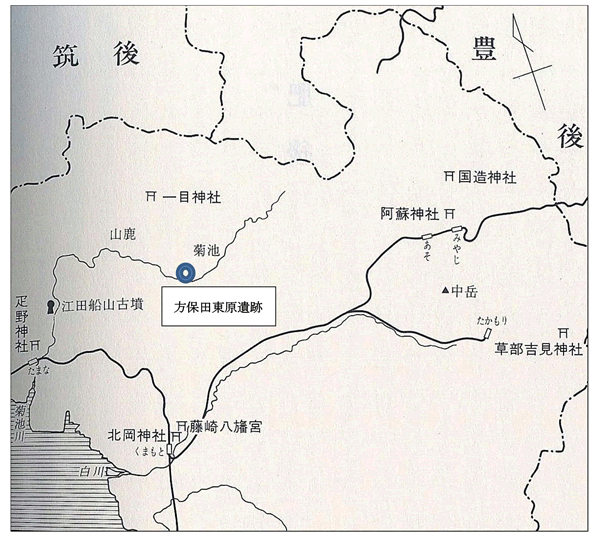
2、鉄の利用
(1)大量の鉄が出土している。
とりわけ戦闘用の「鉄鏃」
(2)鉄器を作った鍛冶場と思われる住居跡の存在
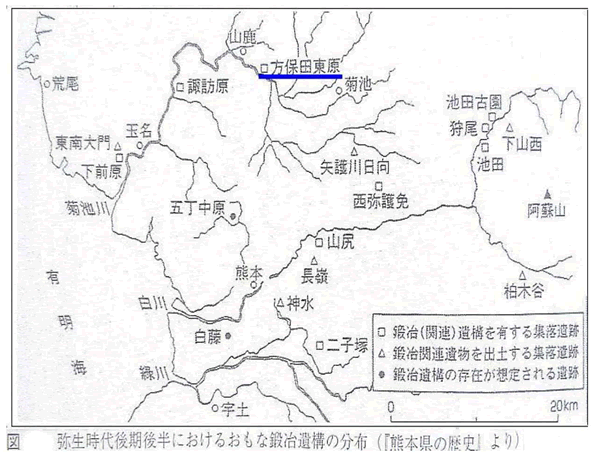
3、方保田東原遺跡の概要
山鹿市出土文化財管理センター(山鹿市方保田東原128)より
・土の中から現れたいにしえの暮らし
国内でも最大級の規模となる幅7.8mの大溝をはじめ、多数の住居跡のほか、土器や鉄器を製作していた可能性がある跡などが見つかっています。当時、大変多くの人々が生活し、進んだ技術を持っていたことが分かります。
今後の発掘調査で、方保田東原遺跡の特長が、さらに明らかとなっていくことでしょう。
・掘り出された古代の貴重な品々
全国唯一となる石包丁形鉄器をはじめ、特殊な祭器とされる巴形銅器や鏡、当時の中国の皇帝も珍重していた朱を精製する道具など、全国でもあまり見られない貴重な品々が見つかっています。
これらのうち、28種139点が熊本県重要文化財に指定されています。
(平成20年6月23日指定考古第13号)
(下図はクリックすると大きくなります)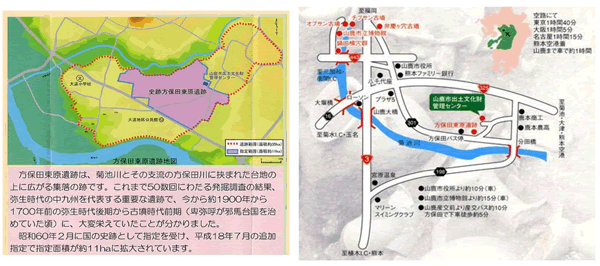
【テーマⅣ】邪馬台国の中心地の移動
1、奴国から邪馬台国へ
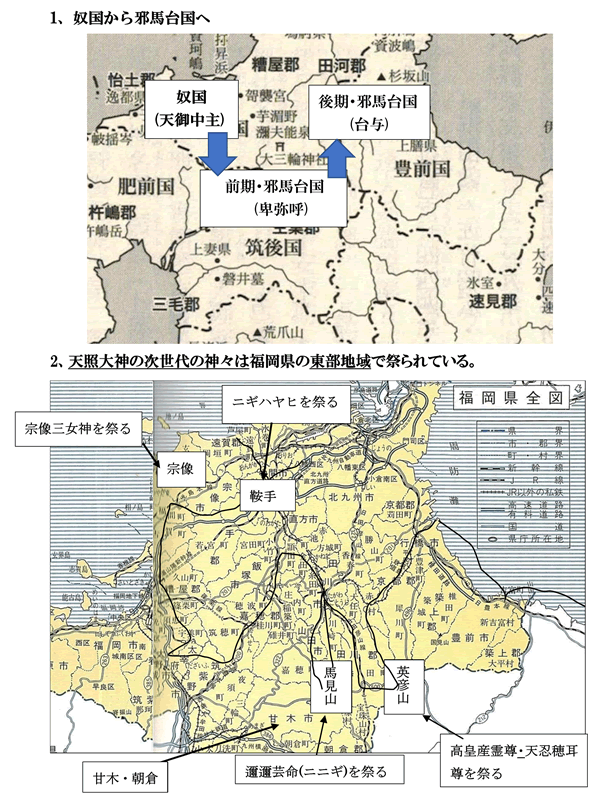
3、高皇産霊尊の拠点的な地域は「英彦(ひこ)山」
(1)豊前の国第一の霊山
①比古山・日子山・彦御山→彦山(819年)→英彦山(1729年)
②祭神に関わる伝承
・北岳・・(もと大国主命・宗像三女神)→天忍穂耳命(主祭神)
・南岳・・ - イザナギ(輔弼神)
・中岳・・ - イザナミ(輔弼神)
中岳の山頂から山腹にかけて英彦山神宮(主祭神:天忍穂耳命)の上津宮・中津宮・下津宮がある。なお、産霊(むすび)神社(英彦山山頂付近)を高皇産霊尊鎮座の故地とする伝承がある。
(2)古代・中世の英彦山の神領---「七里結界」(約30キロ四方)
「大行事社」一明治以降、基本的に「高木神社」と改称
①山内大行事社(四土結界地内大行事社)・・英彦山内に5社
②六峰内大行事社
豊前国内の主要山岳(求菩提山・等覚山・松尾山・蔵持山・檜原山・福智山)に6社
③七大行事社(山麓大行事社)・・七里四方の神域に7社
④各村大行事社・・七里四方の神域内の村々に30社
計48社
(下図はクリックすると大きくなります)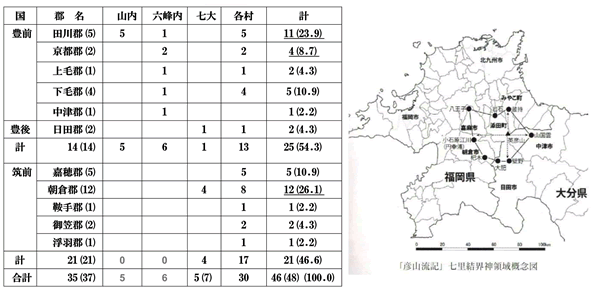
4、ニギハヤヒの拠点的な地域は鞍手郡
(1)ニギハヤヒ
高千穂の天降ったニニギノミコトの兄弟で、神武天皇に先立って近畿に東遷した人物。
(下図はクリックすると大きくなります)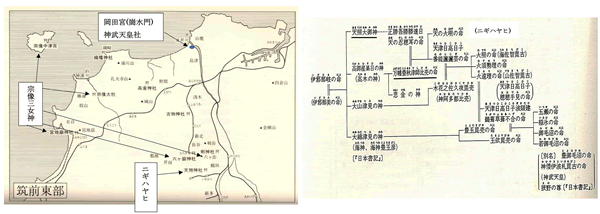
5、宗像三女神の最終的な拠点は宗像
(1)ルーツは筑後川流域か
①『日本書紀』神代紀上・第六段第三の一書
即(すなわ)ち神の生(あ)れませる三(みはしら)の女神(ひめかみ)は以(も)ては、葦原中国(あしはらのなかつくに)の宇佐嶋(うさのしま)に降(あまくだ)り居(ま)さしむ。今、海(うみ)の北(きた)の道の中に在(ま)す。号(なづ)けて道主貴(ちぬしのむち)と曰(まう)す。此(これ)筑紫(つくし)の水沼君(みぬまのきみ)等(ら)が祭(いつきまつ)る神、是(これ)なり。
筑後川下流域の水沼氏は宗像三女神を氏神としていた。
(2)豊前の宇佐へ移動
【宇佐神宮(大分県宇佐市)】・・・周防灘・豊前海
【祭神】
・一之御殿:八幡大神・・誉田別尊(応神天皇)
・二之御殿:比売大神・・宗像三女神(多岐津姫命・市杵島姫命・多紀理命)
・三之御殿:神功皇后・・別名、息長足姫命
※したがって、比売大神を卑弥呼とする説は誤っている。
(3)英彦山に祭られる
北岳の祭神はもと大国主命・宗像三女神であった。
(4)飯塚市を経由
【厳島神社(飯塚市鹿毛馬(かけのうま)】
【祭神】宗像三女神(市杵島姫・田心姫命・湍津姫命)
【由緒】豊前国宇佐島より筑前国宗像郡沖津島に鎮座の時、当村目尾(しゃかのお)山を越し給ふ古実を以て、景行天皇御宇三女神を祭り、参詣に不便なことから延文年中(1356~1361)、筑前国鹿毛午村へ遷す。
(5)鞍手郡を経由
①六ヶ岳(鞍手郡鞍手町)---上宮に天降り
飯塚市鹿毛馬から鞍手郡鞍手町の六ヶ岳(標高338.9m旭岳・天冠・羽衣・高祖・崎戸・出穂の六峰)の崎戸峰に天降りして、そののち宗像に到ったという。
②六嶽神社(鞍手郡鞍手町室木)
【祭神】宗像三女神(田心姫之神・湍津姫之神・市杵島姫之神)
【由緒】「皇女三神霊山六嶽崎門峰ニ御降臨アリ、此地ヲ上宮卜定メ、室木ノ里ニ下宮ヲ建立ス」
③『筑前国続風土記』逸文
「『西海道風土記』にいう。宗像大神が天より降って崎門山にいます時から、青蕤(ずい)玉を奥宮の表に置いて、八尺度(やさかに)の紫玉を中宮の表に置いて、八咫(やた)の鏡を辺宮の表に置いて、この三表が御神体の形となって三宮に納めて、人の目に触れないようにした。これによって身形(みのかた)郡といい、後の人が宗像(むなかた)と言い改めた」(宗像大菩薩縁起)
(6)宗像に赴任
「海北道中」を守護するよう天照大神に命じられる。
『日本書紀』の一書
「(天照大神から)『汝(いまし)三神(みはしらのかみ)、道の中に降りて居(ま)して天孫(あめみま)を助け奉(まつ)りて、天孫の為に祭られよ』との神勅を授けた。
(7)宗像三女神の伝承地
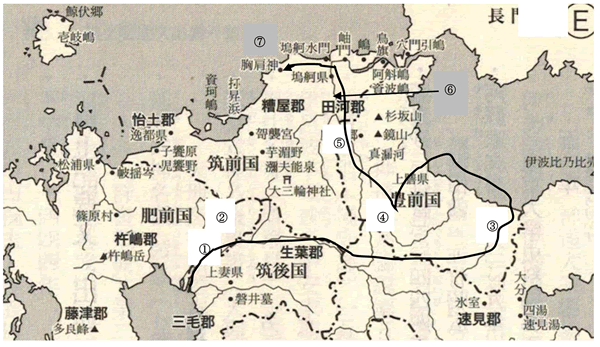
①三潴地方(筑後川下流・久留米市・大川市)
②脊振山(脊振神社の祭神)・・脊振山の氏神
③宇佐(宇佐神宮の祭神)
④英彦山(大国主命・宗像三女神)
⑤飯塚市(飯塚市鹿毛馬)
⑥六ヶ岳(鞍手郡鞍手町)
⑦宗像大社(宗像市)
推測①:宗像三女神は、筑後川流域から豊前→遠賀川流域→宗像へと移動しているようにみえる。
推測②:邪馬台国もまた筑後川流域から豊前方面へと重心を移しているようにみえる。
・奴国から邪馬台国へ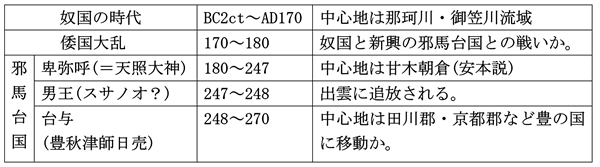
6、筑紫の国と肥の国の境界
(1)「筑紫」の由来---『釈日本紀』
鎌倉時代末期の1274~1301年ごろに書かれた『日本書紀』の注釈書。著者は卜部兼方。『上宮記』、『日本紀私記』、『風土記』など、現在では散逸している書物を参照し、逸文として残している。
『釈日本紀』五の記述
公望(きんもち)が考えるところによると、筑紫の国の風土記にいう、---筑紫の国は、もとは筑前の国と合わせて一つの国であった。昔、この二つの国の間の山にはけわしくて狭い坂があって、往来する人の馬の鞍韉(したくら)[鞍の下に敷く蓆(むしろ)]が摩り尽くされてしまった。それで土地の人は鞍韉(したくら)尽しの坂といった。第三説によると、昔この堺の上に麁猛神(あらぶるかみ)があった。往来の人は半数は助かり、半数は死んだ。その数は大変多かった。それで「人の命尽しの神」といった。その時、筑紫君(つくしのきみ)と肥君(ひのきみ)らが占って、筑紫君らの祖甕依姫(みかよりひめ)を巫祝(ふしゅく)として祭らせた。それから以後は、路を行く人は神に害されなくなった。このことによって筑紫の神という。第四の説によると、その死者を葬るためにこの山の木を伐って棺を造った。このため山の木が尽きようとした。それで筑紫の国という。のち二つの国に分けて前(みちのくち)と後(みちのしり)としたのである。
①「木菟(ミミズク)」説
卜部兼方は、九州島がミミズクの形に似ているからであるとする。
②「鞍鞴(したくら)尽しの坂」説
『魏志倭人伝』→倭国には牛馬はいない。
日本に馬が普及したのは4世紀以降
①「人の命尽しの神」
筑前・筑後・肥前の境界にいた荒ぶる神。「尽し」=殺寸=滅ぼす
④「山の木尽し」説
木棺=邪馬台国時代の墓制(奴国の時代はカメ棺)
(2)「筑紫」の範囲
①最狭義の「筑紫」=御笠郡
脊振山地の北東部・宝満山右岸一帯→「筑紫神社」を中心とした福岡県側
室町~戦国期:「三笠郡筑紫村」(筑紫古文書)
(下図はクリックすると大きくなります)

②狭義の「筑紫」=筑前+筑後
大宝元年(701)西海道の設置により筑前、筑後の2国に分割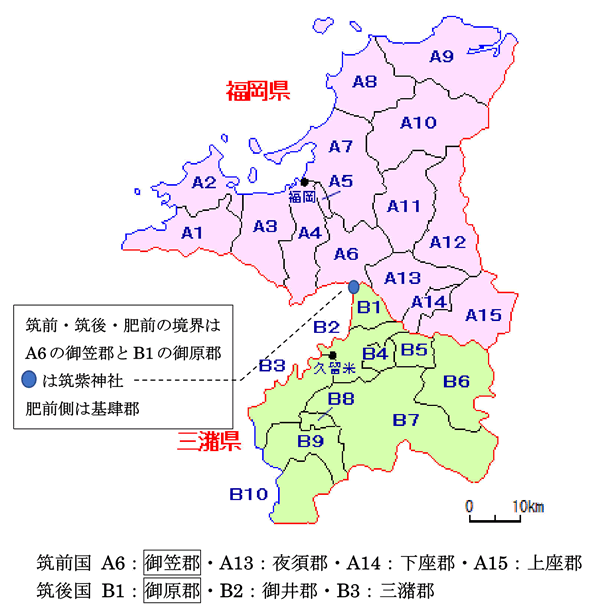
③広義の「筑紫」=九州島
7世紀末~8世紀初頭に、筑前、筑後、豊前、豊後、肥前、肥後、日向、薩摩、大隅の9か国をもって九州=筑紫の島と呼ばれるようになった。
(5)「荒ぶる神」伝承
①『筑後国風土記』逸文---筑前・筑後・肥前の境
「むかし(筑前の国と筑後の国の)境の上に荒ぶる神がいた。往来の大は半数助かり、半数は死んだ。その数は大変多かっか。それで人の命尽くしの神といった」
②『肥前国風土記』基肆郡・姫社(ひめこそ)の郷(鳥栖市)
「この姫社の郷のなかに川があり、山道(やまじ)川(山下川)という。むかしこの川の西に荒ぶる神がいて、道行く大の多くが殺害され、死ぬ者半分、死を免れる者半分であった」
③『肥前国風土記』神埼郡(神埼市)
「むかし、神埼の郡に荒ぶる神があった。往来の大が多数殺害された。景行天皇が巡狩されたとき、この神は和平(やわらぎ)なされた」
④『肥前国風土記』佐嘉郡
「郡の西に川があり、佐嘉川(嘉瀬川)という。この川上に荒ぶる神があった。往来の大を半分は生かし、半分は殺した」
・背振山系の南麓に沿って「荒ぶる神」伝承が残されている。
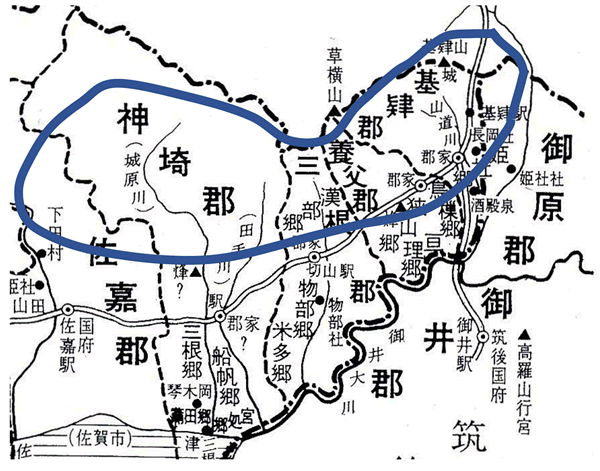
(6)肥前の勢力
①邪馬台国=甘木朝倉の西方の肥前側に「荒ぶる神」の勢力があった。
②これは、肥後の勢力=狗奴国が有明海を迂回して北上した痕跡を思わせる。
③「荒ぶる神」伝承は、邪馬台国と狗奴国間の争乱の記憶なのではないか。
7、「邪馬台国朝倉説」を前提とした邪馬台国の周辺諸国
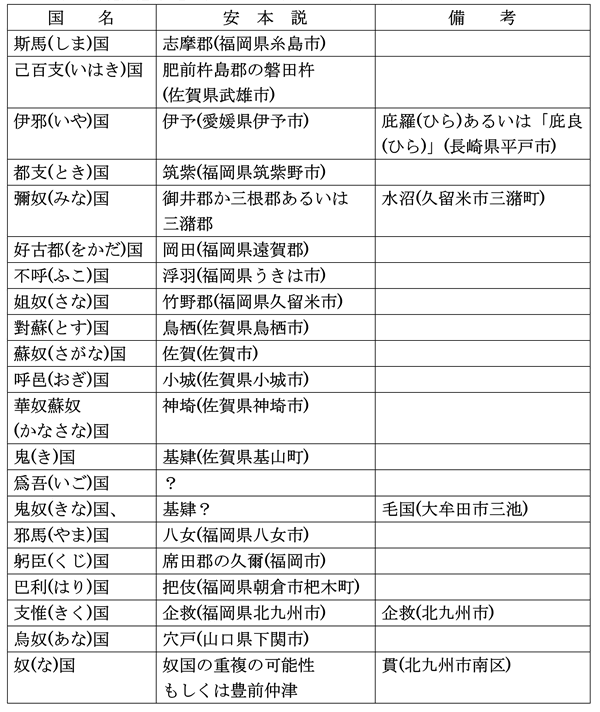
(1)旧朝倉郡のうち、筑前町(夜須・三輪町)、朝倉市の一部(旧甘木市と朝倉町)が見えない。
(2)逆にいえば、この区域に邪馬台国の中心的なエリアがあった可能性が高いことになる。
(3)巴利(はり)国が把伎(朝倉市杷木町)でないとすると、杷木町・小石原村・宝珠山村までの朝倉郡全体が邪馬台国のエリアとなる。
(4)いずれにしても、「邪馬台国朝倉説」とほぼ矛盾なく説明ができる。
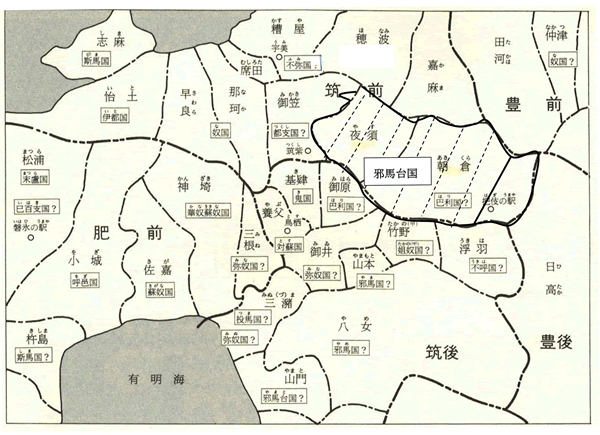
☆追加表題
「金銀錯嵌珠龍紋鉄鏡(きんぎん・さくがん・しゅりゅうもん・てっきょう)」について
令和元年(2019)9月6日の朝日新聞記事に金銀錯嵌珠龍紋鉄鏡がなぜ大分県日田市にあるかとして記事になっている。
(下図はクリックすると大きくなります)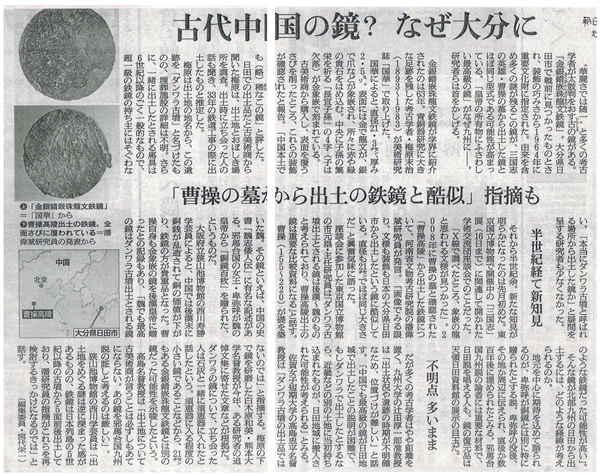
1、発見の経緯
(1)梅原末治氏による偶然の発見
梅原末治氏は偶然にこの鉄鏡を奈良県の古美術店より入手し、熊本大学教授の白木原和美氏の協力を得て鉄サビなどを取り除き研磨したところ、背面の金銀錯文が鏡面の一部に残っていることが確認された。
梅原氏はこの鉄鏡の出土経緯を知るため、1963年(昭和38)九州大学の岡崎敬氏を同行されて、発見者の日田市の渡辺音吉氏に経緯を調査された。この結果、この鉄鏡は1933年国鉄久大本線施設工事にあたり、採土の行われた三芳駅東方約450メートルのダンワラ台地裾に存在した竪穴式石郭を主体としたダンワラ古墳(日田市日高町・東寺1933年消滅)から出土したとされた。
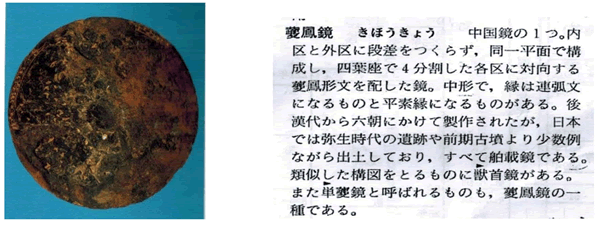
(2)鏡の特徴
鋳鉄製で、径21.3センチ、厚さ2.5ミリの薄い扁平な造りである。
文様は金銀錯の竜文が基調で、各所に玉を嵌装し、破損により全体の3分の1を遺すにすぎないが、旧状はよくうかがえる。四葉座の鈕を中心に葉間に「長宜●孫」の四文字を篆書体で表している。
(3)中国から出土した鉄鏡
・全洪氏の「試論東漢魏晋南北朝時期的鉄鏡」(『考古』1994)
「後漢魏晋南北朝時代の鉄鏡の出土地域は、河南・河北・北京・陝西・遼寧・甘粛・山東・江蘇・湖南・湖北・四川・江西・広東・漸江の県・市の90におよぶ墓と数遺跡から140枚ほど発見された。
時代別には後漢時代の墓から60枚以上発見され、その内訳は北方地域が40枚以上、南方地域が10枚あまりで、黄河と長江流域に集中していた。魏晋時代の墓からは30枚ほど発見され、その内訳は北方地域が20枚以上、南方地域からは10枚ほどであった。その北方地域は洛陽を中心とし、南方地域は寧鎮(南京・鎮江一帯)および太湖付近を中心としていた」
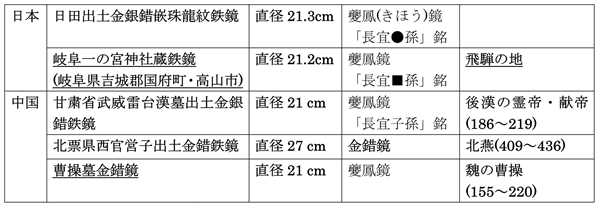
(4)中国文献に出てくる鉄鏡
①『北堂書鈔』(隋の時代の書)
「魏の武帝(曹操)は(1)尺2寸の金錯鉄鏡1枚を、皇后は7寸の銀錯の鉄鏡4枚を持っていた」
②『初学記』(唐の時代の書)
「魏の武帝は(1)尺2寸の金錯の鉄鏡を持っていた」
③『曹操集約注』(魏の曹操の書いたものに注をつけたもの)
「皇帝は(1)尺2寸の金錯鉄鏡1枚を、皇后は銀錯7寸の鉄鏡4枚を、貴人・公主は9寸の鉄鏡を持っていた」
④『太平御覧』(宋の時代の書物)
「魏の武帝(曹操)が皇帝(献帝)に献上した雑物(用物)のなかに(1)尺2寸の金錯 鏡1枚、皇太子の雑物として純銀錯鏡7寸の鉄鏡4枚、貴人・公主用の9寸の鉄鏡40枚があった」
クラス 鏡の種類 直径
皇帝 金錯鉄鏡 1尺2寸(28.9cm)
貴人・公主 銀錯鉄鏡 9寸(21.7cm)[注:貴人・・妃、公主・・皇帝の娘]
皇后・皇太子 鉄鏡 7寸(16.8cm)
[ 注:魏晋時代の1尺=24.1cm]
日田の金銀錯鉄鏡は21.3cmであったので、大きさは貴人・公主並みの9寸であるが、金銀玉石による豪華な象嵌は比類ない一品である。
卑弥呼のために、特別に制作された可能性が高いのではないか。
(5)日田出土の金銀錯嵌珠龍紋鉄鏡は「邪馬台国朝倉説」を補強する
①卑弥呼に特別に授けられた鏡
「魏志倭人伝」は239年、中国皇帝が卑弥呼に「銅鏡百枚」を贈ったと記している。女王卑弥呼のために特別に製作された鏡とみれば、邪馬台国九州説を補強する極めて重要な遺物ということになる。
②日田から出土したことはきわめて重大
日田は筑紫平野の東端に位置している。その西方の朝倉方面に邪馬台国の中心地があった可能性がきわめて高くなる。
2、古代日田の特徴---福岡・佐賀地域との密接な関係
(1)石器の流通範囲(紀元前2世紀ごろ~)
①立岩(飯塚市)の石庖丁の分布
②今山(福岡市西区)の石斧の分布
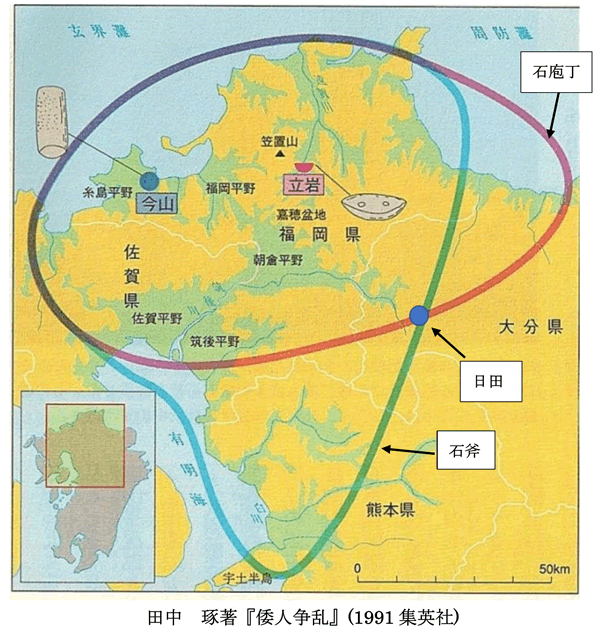
(2)日田はカメ棺文化圏に属する(紀元前2世紀ごろ~)
金印奴国の時代の文化圏の特徴であるカメ棺は、筑後川をさかのぼって日田・玖珠地区に及ぶが水分峠は越えない。
東九州地域から出土する下城式土器は日田・玖珠地区には及ばない。
3、「日田」の意味するところ---その位置は時代によって変遷する。
(1)日(太陽)が昇る方向
それを見る人々は西方にいる。
(2)東へ向かう前進基地
その勢力の中心は西方にある。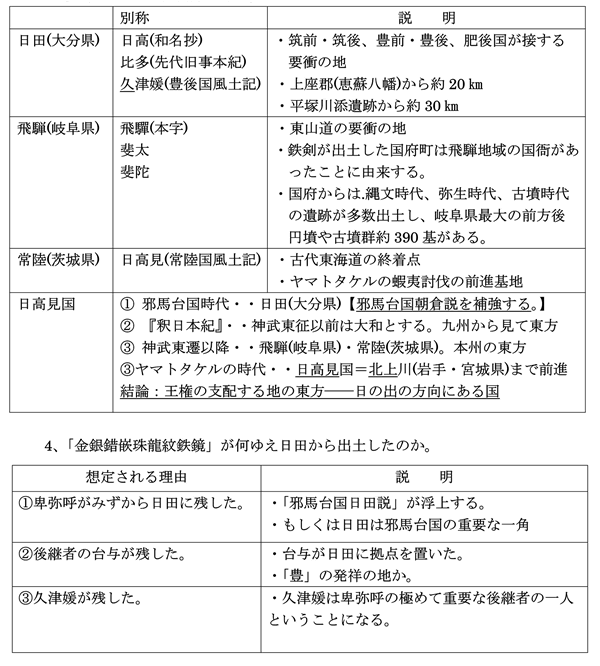





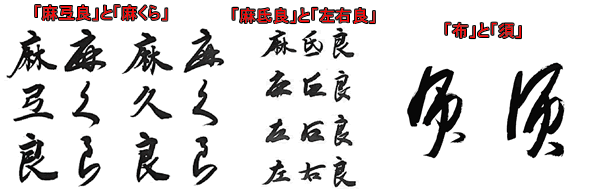
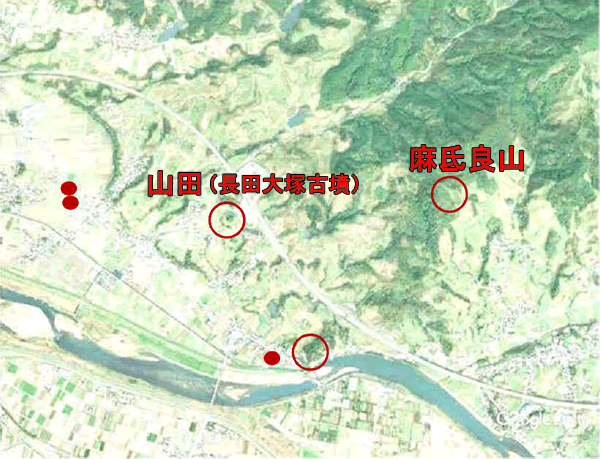
 1、安本説の根幹-「邪馬台国朝倉説」
1、安本説の根幹-「邪馬台国朝倉説」
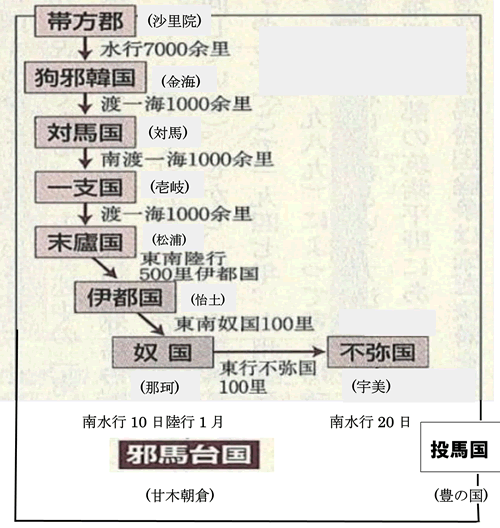 (2)「陸行1月」の解釈
(2)「陸行1月」の解釈