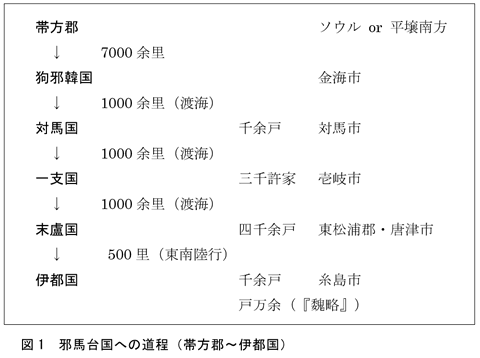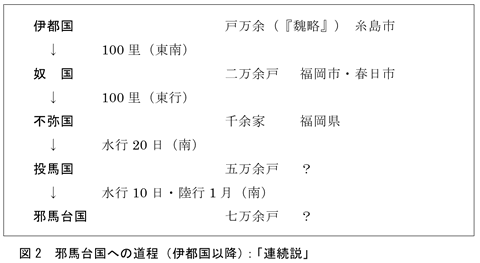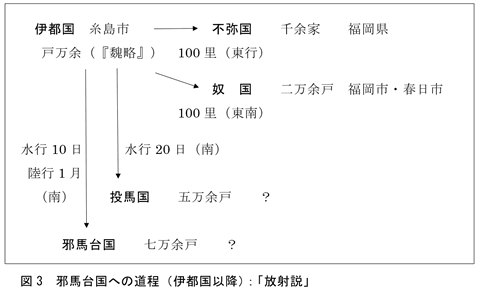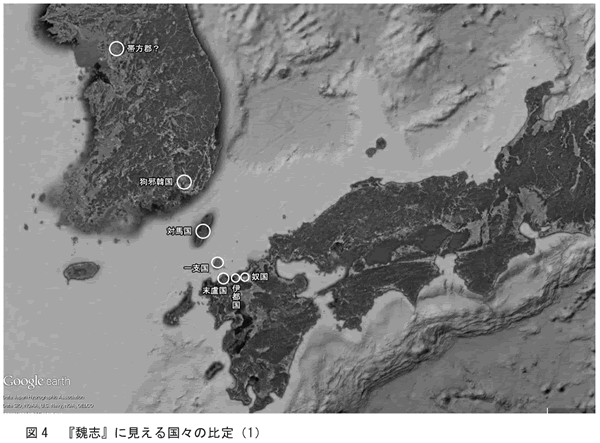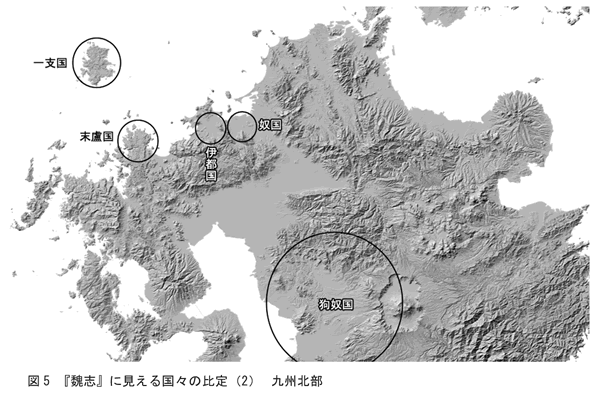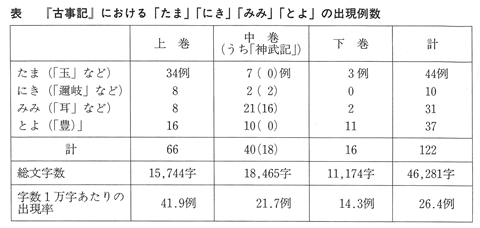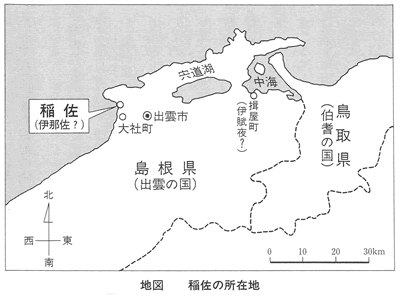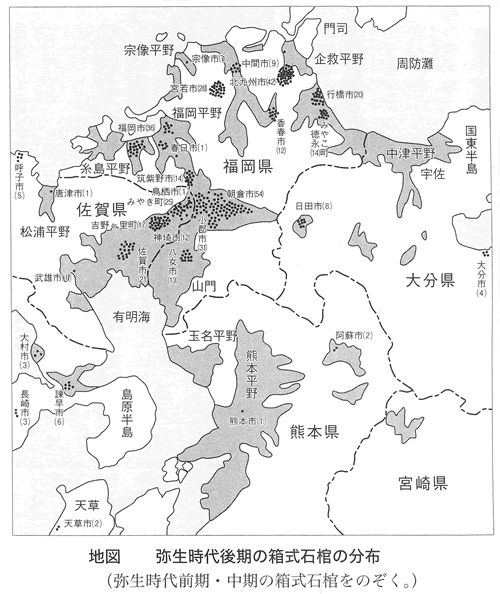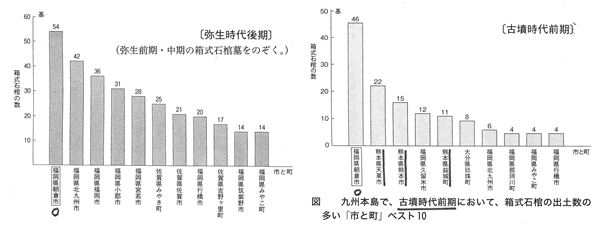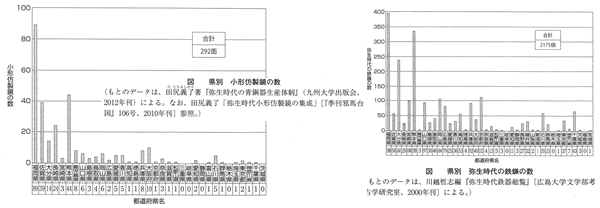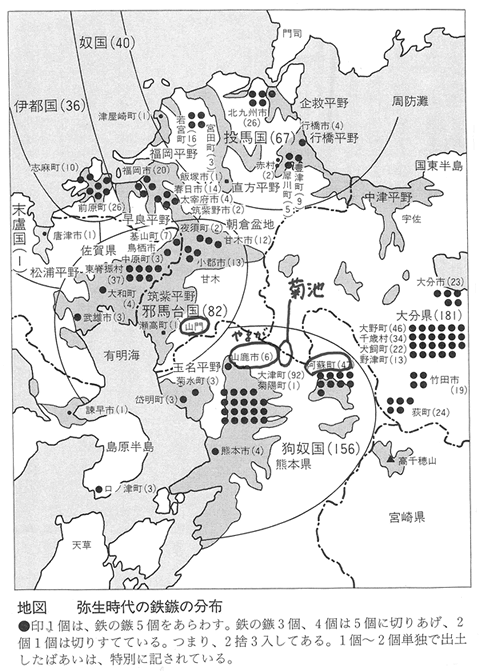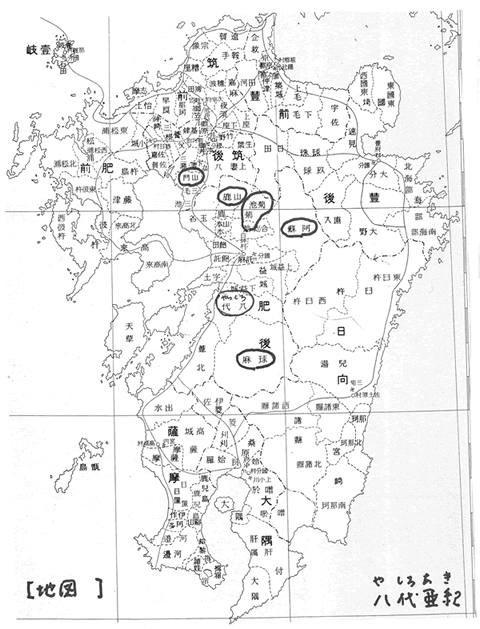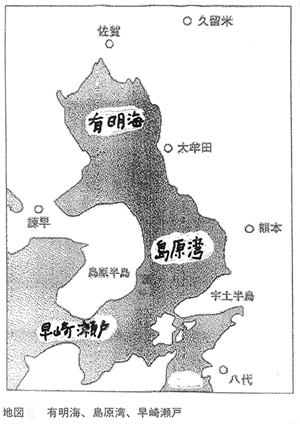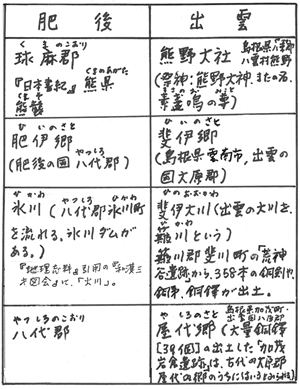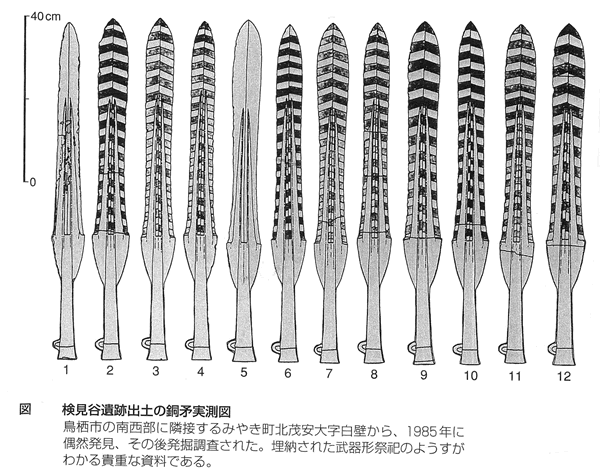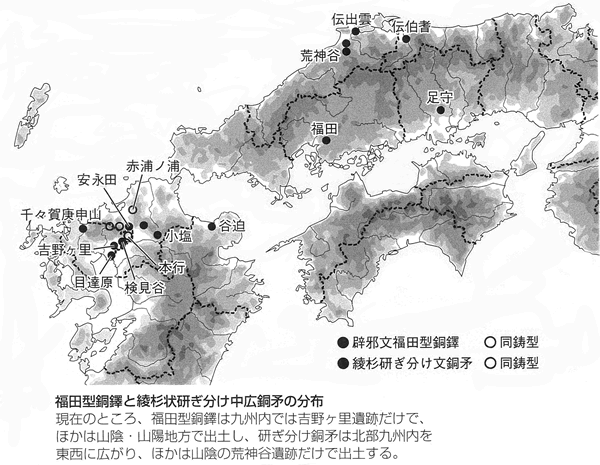2.1 狗奴国について
『魏志倭人伝』に
「倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素(もと)より和せず。」
とある。この「卑弥呼」の読み方にいろいろ議論がある。 
■「卑弥呼」の読み方
「卑弥呼」についての説は、いくつかにわかれる。おもなものを、三つあげてみよう。
(1)日御子(ひみこ)説
新井白石は、『古史通或問(こしつうわくもん)』のなかで、「卑弥呼」を、「日御子(ひみこ)」であるとする。「日御子」 にあたることばとしては、『古事記』に、「多迦比迦流(たかひかる)、比能美古(ひのみこ)」(高光る、日の御子)という使用例が四例、「本牟多能(ほむだの)、比能御子(ひのみこ)」(品陀の、日の御子)という使用例が一例ある。
「日の御子」は、「ひ(甲)(の)み(甲)こ(甲)」であって、「卑弥呼」の音と一致する。ただ、「日(ひ)の御子(みこ)」は、つねに、この形で用いられており、「の」を省略して、「日御呼(ひみこ)」という形で用いられている例がない。また、「日(ひ)の御子(みこ)」は、直接的に、名前の一部として用いられているわけではなく、いわば、形容詞的に用いられている。ただ、「卑弥呼」が、天照大御神、つまり、「日の神」にあたるとすれば、「日(ひ)の御子(みこ)」という形容は、ほぼあてはまる。
(2)姫児(ひめご)説
本居宣長は、「卑弥呼」を、『古事記伝』や『馭戎慨言(ぎょじゅうがいげん)』のなかで、「火之戸幡姫児千千姫(ほのとはたひめごちぢひめ)の命」「万幡姫児玉依姫(よろづはたひめごたまよりひめ)の命」などとある「姫児(ひめこ)」であるとした。ただし、これらは、本居宣長の読み方である。現在の、たとえば、岩波書店刊の日本古典文学大系の『日本書紀』では、「火之戸幡姫(ほのとはたひめ)の児千千姫千姫(こちぢひめ)の命」「万幡姫(よろづはたひめ)の児玉依姫(こたまよりひめ)」のように、「姫(ひめ)の児(こ)」と読まれている。
『肥前国風土記』の松浦郡の条に、「弟日姫子(おとひひめこ)」の名がある。この名は、「弟日姫子(おとひひめこ)」(五回)、「弟日女子(おとひひめこ)」(一回)、「意登比売能古(おとひひめこ)」(一回)の、三通りの書き方で、七回あらわれる。
『旧事本紀』の「天孫本紀」に「市師(いちし)の宿禰(すくね)の祖(おや)穴太(あなほ)の足尼(すくね)の女(むすめ)、比咩古(ひめこ)の命(みこと)」とある「比咩古(ひめこ)も、「姫児」の意味であろう。
『播磨(はりま)国風土記』では、「蚕(かいこ)のことを、「蚕子(ひめこ)」といっている。「蚕(かいこ)」のことを、古語で、たんに、「蚕子(ひめこ)」ともいうが、養蚕や機織(はたおり)には女性がたずさわることが多いので、「蚕子(姫子)といったのであろう。
「姫子」「比咩古」の音は、いずれも、「ひ(甲)め(甲)こ(甲)」であって、「卑弥呼」の音に一致する。「姫子(ひめこ)」は、古典にあらわれるひとつの熟語として、「卑弥呼」と完全に一致する。「卑弥呼」が、「姫子」であるとすれば、「姫」という語に、愛称または尊敬の「子」がついたものであろう。
「卑弥呼」を、「ヒメコ」と読む説は、坂本太郎が、論文「『魏志』『倭人伝』雑考」(古代史談話会編『邪馬台国』 1954年9月刊)のなかで説いている。
「卑弥呼」の「弥」の字は、
①等已弥居加斯夜比弥乃弥己等(とよみけかしやひめのみこと)(元興寺塔露盤銘、元興寺縁起)
②止与弥挙奇斯岐移比弥(とよみけかしきやひめ)天皇(元興寺丈六光銘、元興寺縁起)
③吉多斯比弥乃弥己等(きたしひめのみこと)(法隆寺蔵「天寿国繍帳記」『上宮聖徳法王帝説』)
④等已弥居加斯支移比弥乃弥己等(とよみけかしきやひめのみこと)(「天寿国繍帳」)
⑤践坂大中比弥(ほむさかおおなかつひめ)王「上宮記」『釈日本紀』十三述義九)
⑥田宮中比弥(たみやなかひめ)(「上宮記」)
⑦阿那爾比弥(あなにひめ)(「上宮記」)
⑧布利比弥命(ふりひめのみこと)(「上宮記」)
⑨阿波国美馬郡波爾移麻比弥(はにやまひめ)神社(『延喜式』神名帳)
などのように、『古事記』以前の表記法を伝えるとみられるもののなかに、「甲類のメ」をあらわすために用いられている例がある(文例は、坂本太郎の列挙による)。このような事例をみると、「姫」は、むかしは、「ひ(甲)み(甲)」といっていたのではないかと疑われるが、そうではないことは、「上宮記」において、「布利比弥命(ふりひめのみこと)」を「布利比売命(ふりひめのみこと)」とも記していることからわかる。「弥」は、あきらかに、「甲類のメ」に読まれているのである。
ただ、ふしぎなことに、「弥」を「甲類のメ」と読むのは、わが国の古文献においては、「比弥[ひ(甲)め(甲)](姫)」という熟語にかぎられている。さきの①の「比弥乃弥己等(ひめのみこと)」のように、「弥己等(みこと)」(命)のばあいは、「弥」を「甲類のミ」に読んでいる。そして、「卑弥呼」の「弥」は、まさに、「卑[ひ(甲)]=比[ひ(甲)]」の字のあとに用いられており、「卑弥[ひ(甲)め(甲)]」と読みうるケースである。
『万葉集』の167番の歌で、「天照(あまて)らす日女(ひるめ)の尊(みこと)(天照日女之命)」という語のすぐあとに、「高照(たかて)らす日(ひ)の皇子(みこ)(高照日之皇子)」という語がでてくる。「日女」は、「ひめ」とも読める。「卑弥呼」は「日女皇子(ひめこ)」のような語をうつしたものであろうか。
(3)姫(ひめ)の命(みこと)説
江戸中期の国学者、松下見林は、『異称日本伝』のなかで、「卑弥呼」を、「姫(ひめ)の命(みこと)」の省略形とする。東大教授であった東洋史学者、白鳥庫吉も、論文「倭女王卑弥呼考」のなかで、「姫の命説」をとる。しかし、「み(甲)こ(乙)と(乙)」の「こ(乙)」は、「卑弥呼(ひみこ)」の(甲)」とやや異なる。この説は、おそらくあたらないであろう。
■「卑弥呼」の意味
以上から、「卑弥呼」は、坂本太郎の説くように、「姫子(ひめこ)」の意昧にとるのが、もっとも穏当である。
『日本書紀』では、「女王」は、
「飯豊女王(いいどよのひめみこ)」(「顕宗天皇即位前紀」)
「忍海部女王(おしぬみべのひめみこ)」(「顕宗天皇即位前紀」)
「栗下女王(くるもとのひめみこ)」((舒明天皇即位前紀)」
などのように、「女王(ひめみこ)」(姫御子の意味)と読まれている。
『続日本紀(しょくにほんぎ)』では「女王」は単独で用いられるばあいは、「女王(じょうおう)」と読み「伊福部女王(いほきべのひめみこ)」のように人名として用いられるばあいは「女王(ひめみこ)」と読んでいる(岩波書店刊、新日本古典文学大系『続日本紀』など)。
「卑弥呼」は、「ひめこ」と読み、「姫子」あるいは「姫御子」の意昧とみられる。
『古事記』の「孝霊天皇紀」に、「男王五、女王三」という記事があり、これは、ふつう、「男王五(ひこみこいつはしら)、女王三(ひめみこみはしら)」
のように読まれている。
また、『日本書紀』では、「七(ななはしら)の男(ひこみこ)と六(むはしら)の女(ひめみこ)とを生めり。」(「景行天皇紀」)
のように、「男」の字を、「ひこみこ(彦御子の意味)」と読んでいる例がある。
狗奴(くな)国の男王「卑弥弓呼(ひみここ)」は、「卑弓弥呼」の書き誤りと考えて、「彦御子(ひこみこ)」のこととする説がある。「卑弓弥呼」と記すべきところを、すぐ上に、「卑弥呼」の名があらわれるので、それにひかれて、「卑弥弓呼」と記したのであると考える。
もし、そうであるとすれば、『魏志倭人伝』の、
「倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。」
は、『日本書紀』流に読めば、つぎのようになる。
「倭(やまと)の女王(ひめみこ)、卑弥呼(ひめこ)、狗奴国(くなこく)の男王(ひこみこ)、卑弓弥呼(ひこみこ)と素(もと)より和(あまな)はず。」
すなわち、「卑弥呼(ひめこ)」「卑弓弥呼(ひこみこ)」は、そのまえの、「女王」「男王」という漢語の「大和(やまと)ことば」を、万葉仮名風に表記しただけのこととなる。
のちの時代の話であるが、次のような例がある。
733年(天平5年)に、唐にわたった遣唐副使の中臣名代(なかとみのなしろ)に、唐の玄宗皇帝が授けた勅書が、『文苑英華(ぶんえんえいか)』に収められている。
そこには、「日本国王主明楽美御徳(すめらみこと)[天皇]に勅す。」とある。
この場合、「主明楽美御徳」は、天皇の実名ではない。「天皇」の日本でのよび方を示している。
「卑弥呼」も実名ではなく、たんに「女王」ということばの、日本でのよび方を示している可能性がある。
この可能性は、かなり大きいように思える。
魏の人から、「女王」「男王」のことを、なんと言うかとたずねられて、倭人は、「ひめみこ」「ひこみこ」と答え、それを魏人が漢字の音で、表記したものであろうか。
あるいは、邪馬台国朝廷がわの官人が記したことも考えられる。
『魏志倭人伝』には、「文書、賜遺(しい)の物[賜(たまわり)り物]を伝送して女王(のもと)に詣(いた)らしめ」「倭王使いによりて上表す」などとある。
「上表」という句は、『日本書紀』にしばしば用いられており、そこでは、「上表(ふみたてまつ)る[文たてまつる]」と読まれている。
これらから、邪馬台国の卑弥呼の朝廷には、文字を読み書きできる人のいたことがわかる。
卑弥呼が、上表したとすれば、そこには、署名もあったであろう。署名では、ひめみこ(姫御子)」の「御」は、尊敬語なのでいれず、「ひめこ(姫子)」のように記した可能性もある。
「卑」の字は、「小韻の首字(同音字グループの代表字)」である。「彌(弥)」「呼」も、「小韻の首字」である。「卑弥呼」は、文字としては、ありふれたものばかりが用いられている。「小韻の首字」ばかりを用いたのは、誤読をさけるためであろうか。
なお、「卑弓弥呼(ひこみこ)」の「弓」の字の中国での中古音は、「kIuŋ」である。埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘文では、「大彦(おほひこ)」にあたる人名を、「意富比垝」と記している。この「垝」の字の中古音は、「kɪuĕ」で、「弓」の音に、かなり近い。
また、『日本書紀』の「神功皇后紀」の、四十七年の条に、「千熊長彦(ちくまながひこ)」という名があらわれ、『日本書紀』の編者は、これを、『百済記』にいう「職麻那那加比跪(ちくまなながひこ)」のことかと、疑っている。
さらに、「神功皇后紀」の六十二年の条にも、『百済記』が引用されており、そこに、「沙至比跪(さちひこ)」という名が見える。『日本書紀』は、この「沙至比跪」が、「葛城襲津彦(かつらぎのそつびこ)」をさすとする書き方をしている。「沙至比跪」が「襲津彦」をさすと見てよいことについては、井上光貞が、「帝紀からみた葛城氏」(『日本古代国家の研究』岩波書店刊所収)のなかで、考証しているところである。
「跪」の中古音は、「gɪuĕ」である。やはり、「弓」の音に、かなり近い。
「彦(ひこ)」の「こ」の音については、『魏志倭人伝』の「卑狗」が「狗」(音は、上古音が、「kug」、中古音が「kəu」)の字で書かれている。
以上から、「彦」は、「ひく」「ひきゅ」に近い音で発音されたこともあったようである。(乙類の「こ」の音のばあいは、「ひきょ」に近い。)
いずれにせよ、「卑弓弥呼」は、「彦御子」「男王」を表記しているとみられる。
卑弥呼は、狗奴国男王、卑弥弓呼との争いの中で没するが、天照大御神は、弟の須佐之男(すさのお)の命(みこと)との争いにより、天(あめ)の石屋(いはや)にかくれる。狗奴国は、熊本県、つまり、「肥(ひ)の国」と考えられるが、須佐之男の命が追放された出雲の国には、「肥の河」が流れている。熊本県にも、「火川(ひのかわ)」がある。「狗奴(くま)」と関係のありそうな出雲の「熊野神社」に、須佐之男(すさのお)の命(みこと)はまつられている。あるいは、「須佐之男の命」が、狗奴国男王の「卑弥弓呼」で、出雲に追放されたさい、ふるさとの九州の狗奴(熊)地方の地名をもっていったのであろうか。
■狗奴国の官、「狗古智卑狗」
『魏志倭人伝』は記す。
「其の南には狗奴国(くなこく)[熊襲か球磨か]有り。男子を王と為(な)す。其の官には狗古智卑狗(くこちひこ)[菊池彦か]有り、女王に属せず。」
[その南には狗奴国(くなこく)がある。男を王としている。その官には狗古智卑狗(くこちひこ)がおり、女王には従属していない。]
「狗古智卑狗」は、内藤湖南をはじめ、すでに多くの人の説いているように、肥後の国に「菊池郡」があるので、「菊池彦」とみるのが、もっとも妥当である。
「菊池郡」は『和名抄』に、「久久知」と註がある。『延喜式』も、「くくち」と読んでいる。後世になまって、「きくち」となった(吉田東伍著『大日本地名辞書』)。
「狗古知卑狗」は、「万葉仮名の読み方」で、「くくちひ(甲)こ(甲)」と読め、「菊池彦[くくちひ(甲)こ(甲)]」と、正確に合致する。
百済の肖古王のことを、中国の史書『晋書』は、「余句」と記している。
肖古王の「古(ko)」の音を、「句(音はkɪuまたはkəu)」で写しているとみられる。音が、すこし違っているが、このていどなら通用の範囲とみられる。
藤堂明保編『学研漢和大字典』(学習研究社刊)
【狗】ク呉音、コウ漢音
【句】①ク呉音漢音、②ク呉音、コウ漢音
『古代地名大辞典』(角川書店刊)にのっている「くくち」(「きくち」を含む)の地名は、熊本県の「菊池(くくち)郡」と「菊池城(くくちのき)」の二つだけ。古代において、ありふれた地名とはいえない。ただし吉田東伍著の『大日本地名辞書』(冨山房刊)には、熊本県の「菊池郡」「菊池城」以外に、摂津の国河辺郡(兵庫県)の地名として、「久久知(くくち)」をのせている。熊本県の地名の方が、大地名である。
井上光貞著『日本の歴史1神話から歴史へ』(中央公論社1965年刊)
(井上光貞氏)「この狗奴(くな)国について白鳥氏に、『熊本、球磨(くま)川にその名を残す球磨地方であろう』とした。なぜならウミハラ(海原)がウナバラとなるように、マ行とナ行とは転訛しやすいからである。球磨地方はさらに南方の地方と合して『熊襲(くまそ)』の名で知られているが、この地方は筑後山門(やまと)郡のちょうど南にあたる。だから倭人伝をそのままにうけとって、博多方面から南に邪馬台国があり、その南に狗奴国があると読んでもよく筋が通るのである。」
注:辞書より
①菊池郡(くくちぐん)<熊本県>
肥後国の郡名。肥後国北部。東は阿蘇郡,西は山鹿郡、南は合志(かわし)郡、北は豊後国に接していた。この郡域は現在の菊池市と七城町の範囲で、現在の菊池郡は大部分がかつての合志郡の地域にあたる。熊本平野の北東端、菊池川・白川流域の平坦地から、北は合志台地、東は阿蘇外輪山の西麓に至る。「和名抄」の訓は「久々知」。
②菊池(くくちのき)城<熊本県菊鹿町>
平安期に見える城名。肥後国菊池郡のうち。当地は古く「くくち」と呼ばれていたと推定され、「魏志」倭人伝に見える「狗古智卑狗」と関連させて「狗奴国」を当地に比定する説もある。「続日本紀」文武2年5月25日条に「令大宰府繕治大野・基肄・鞠智三城」と城名として見え、「くくちのき」と訓んだものと推定される。
■「たま」「にき」「みみ」「とよ」について
『古事記』における「たま」「にき」「みみ」「とよ」の出現例数の過半の66回は、『古事記』上巻(神話の巻)にあらわれる。
また、中巻にあらわれる「たま」「にき」「みみ」「とよ」はのべ40回のうち、18回は、最初の、「神武記」にあらわれる。
したがって、「神武記」以前(上巻と「神武記」とを加えたもの)に、「たま」「にき」「みみ」「とよ」は、のべ、84回あらわれることになる。
じつに、「たま」「にき」「みみ」「とよ」の、三分の二以上、69パーセントは、「神武記」以前にあらわれる。
『古事記』の、上巻と中巻と下巻とでは、分量が異なる。このことを考慮しても、結論はかわらない。いな、「たま」「にき」「みみ」「とよ」は、他の巻よりも、上巻に頻出するという傾向は、さらにはっきりとうかびあがってくる。
右下の表には、各巻の総文字数も示しておいた。ここから、文字数一万字あたりの、「たま」「にき」「みみ」「とよ」の、出現率を計算する。 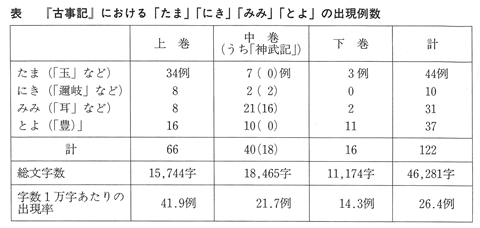
字数一万字あたりの出現率は、上巻で、41.9例、中巻で、21.7例、下巻で、14.3例である。上巻の出現率は、中巻の出現率の約二倍である。
そして、上巻から中巻へ、中巻から下巻へと、時代の下るにつれ、出現率は、減少してゆく。
・島谷良吉(しまやりょうきち)氏の見解
1956年に『魏志倭人伝』の現代語訳を出した島谷良吉(1899~1980。高千穂商科大学教授などであった)氏は、その『国訳魏志倭人伝』の「前がき」の中でのべている。
「陳寿編纂『魏志巻三十』所載の東夷の一たる『倭人』の記述を見ると、まったく記紀神代の巻の謎を解くかのように思える。」
・金子武雄氏の見解
国文学者であった東大の金子武雄氏は、その著『古事記神話の構成』(桜楓杜刊)のなかでのべている。
「古事記神話は一つの体系を持った神話である」
「古事記神話の資材となっている個別神話は、一部分が出雲地方で生育したものであるほか、他の大部分は九州、特に北九州で生育したものであろう。(大国主の命の)国家譲渡の神話は重要な史実に立脚しているものであろう。」
「私の得た結論を先に言うと、国家経営の神話-いわゆる出雲神話-を除いたほかのほとんどすべての神話は筑紫(九州)、特に北九州の地において生育したものであるということになる。」 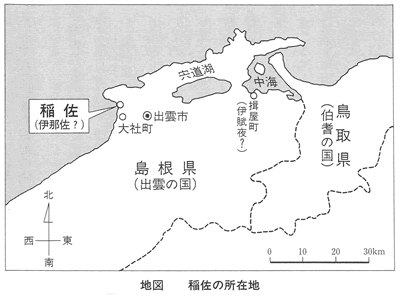
「『天降った』というのは、高天原との関係によって神話化せられたものと考えることができる。この出雲と国譲りの交渉の神話は、おそらくなんらかの史実を基盤としているものと思うのであるが、建御雷神(たけみかずちかみ)が船に乗って出雲の海岸に着いていることが、この神話の基盤になっている史実を反映しているものとすれば、その史実は、当然、近畿と出雲との間の交渉ではなくて、筑紫と出雲との交渉であったとみなければならないであろう。近畿から出雲へは船で行くはずはないからである。こうしてこの国家譲渡の交渉の神話もまた、筑紫で生育したものであることを思わせるのである。」
「古事記の諸神話のうち、国家経営の神話の生育地が出雲であるほかは、日向三代の神話はもとより、天地初発・万物創成・高天原の闘争・国家譲渡の交渉・天孫降臨などの諸神話のほとんど大部分の生育地が筑紫、特に北九州(狭義の筑紫に当たる)であると考えることの根拠を、できるだけ提出してみたつもりである。その論証はもちろん充全ではないが、逆にこれらの神話の生育地が大和あるいは近畿であると主張しようとするならば、その根拠は遥かに薄弱なものでしがないであろう。」
「やや比喩的に言えば、高天原(たかまのはら)はほかならぬ筑紫の上にあったのである。こうして、いわゆる高天原系神話も、いわゆる筑紫系神話と同じく筑紫の地に成育したものと思われる。」
「古事記の神話が史実に立脚しているかどうか、立脚しているとすればどの程度か、ということは、それぞれの神話について吟味してみなければならない。古事記は神話編である上巻をも含めて歴史の書として編纂せられているのだから、編者の姿勢から言っても、こういう吟味は無視せられてよいものではなかろう。特に、歴史的性質の色濃い国家経営の神話、国家譲渡の交渉の神話、それから日向三代の神話についてはなおさらである。
右の三つの神話のうち、日向三代の神話は、すでに先人たちによって説かれているように、九州南部の隼人族や九州北部の海人族の、いわゆる天孫族に対する屈服あるいは服従という史実に立脚しているところの多いものである。残る国家経営の神話と、これと密接な関係のある国家譲渡の交渉の神話ともまた、私にはかなり重大な史実に立脚しているものであろうと思われる。」
「この筑紫の中心勢力が近畿へ移動し、大和中心の大勢力となったのは、いつのころと考えたらよいか。大和朝廷の人々が近畿で生育した個別の神話を持っていなかったとしたら、それは近畿に移動したのが、原初的な神話を生むような時代をすでに過ぎていたためであろうと考えられる。そうすれば、そんなに古い時代のことではなかったであろう。
ところで、考古学の教えるところによれば、墓の中に剣・玉・鏡、および巴形銅器を副葬するのは、筑紫ではすでに弥生時代からのことであったが、近畿ではやっと古墳時代にはいってから始まったという。
その点から言えば、北九州の文化は大体、弥生時代の末ごろに近畿へはいったとも考えられよう。そうして、これらの副葬品の伴なう古墳は、もちろん支配階級のものである。
さらにまた、弥生時代の中期から末期にかけてさかんに用いられたものに、銅鐸・銅剣・銅鉾---これらは実用的な物ではなく、呪物あるいは祭器であるという---があるが、その分布の状態が、三河・遠江・加賀を境界にしてその西方において、かなり明確に二つに分かれているという。すなわち、大体、近畿・山陰・北陸、および四国の東部が銅鐸文化圏であり、九州および瀬戸内海沿岸が銅剣銅鉾文化圏である---私はこれらの銅器はそれぞれ出雲系の神と筑紫系の神とを信奉するしるしであり、同時にまた、それぞれの政治的支配権のしるしでもあったのではないかと思う---。しかもこの二つの文化圏の対立は次の古墳文化の成立と共に消滅しているという。
さらにまた、出雲文化は弥生時代までは相当の進展が見られるけれども、古墳時代にはいると、あまり進展が見られなくなっているという。
考古学の教える以上のような諸事実は、私か古事記の若干の神話の暗示するところを根拠として想定したところと大方合致する。このことは、これらの神話が多分に史実に立脚しているのであろうということを思わせるのである。そうして、筑紫の中心勢が近畿へ移動したとしたら、それは弥生時代の末期ごろではないかと推定せられるのである。」
「このように考えると、古事記上巻に収められている体系神話の中には、近畿で生育した神話は、猿田毘古神(さるたびこのかみ)に関するものなどのほかは、ほとんど、はいっていないということになる。それでは、どうして、大和朝廷の人々が国史の最初の位置に筑紫や出雲に生育したこれらの神話を据え置くことになったのか。
それは、このような位置に据えることのできるほどの神話を大和朝廷の人々は持っていなかったためであろうと思う。それでは、大和朝廷の人々は、近畿の地で生育した神話あるいは伝説を持っていなかったのか。私は古事記の中巻以下に見られる神話や伝説がこの人々の持っていたものであると思う。中巻のはじめには、神倭伊波礼毘古命(かんやまといわれびこのみこと)[神武天皇]の東征のことが語られているが、大和朝廷の人々は、遠い昔、自分らの祖先が筑紫からはるばるとやって来たという伝承を持っていたのである。だから、自分らのこういう伝承の前に、筑紫で生育した神話を据えることには、ほとんど抵抗を感じなかったことであろう。古事記が神倭伊波礼毘古命の日向の高千穂宮からの出発を境として、上巻と中巻とを分けたのも、主としてこういう事情によるものであろうと思われるのである。」
■邪馬台国時代の墓制、箱式石棺の分布
宮崎公立大学の教授であった「邪馬台国=九州説」の考古学者の奥野正男氏は、つぎのようにのべている。(以下、傍線をほどこしたのは安本。)
「いわゆる『倭国の大乱』の終結を二世紀末とする通説にしたがうと、九州北部では、この大乱を転換期として、墓制が甕棺から箱式石棺に移行している。
つまり、この箱式石棺墓(これに土壙墓、石蓋土壙墓などがともなう)を主流とする墓制こそ、邪馬台国がもし畿内にあったとしても、確実にその支配下にあったとみられる九州北部の国々の墓制である。」(『邪馬台国発掘』PHP研究所刊)
「前代の甕棺墓が衰微し、箱式石棺と土壙墓を中心に特定首長の墓が次第に墳丘墓へと移行していく……。」(『邪馬台国の鏡』梓書院、2011年刊)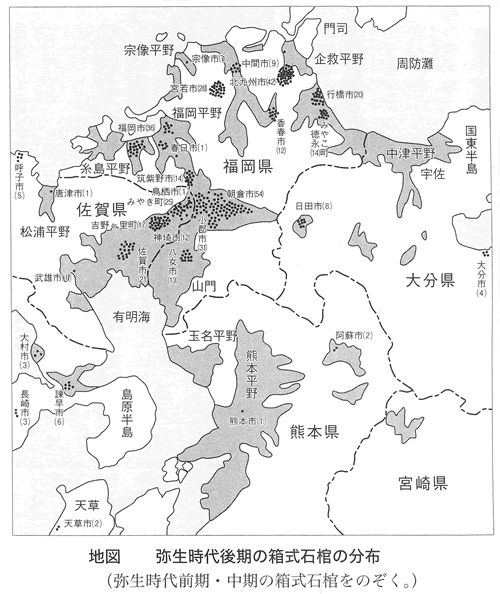
「邪馬台国=畿内説」の考古学者の白石太一郎氏(当時国立歴史民俗博物館。現、大阪府立近つ飛鳥博物館長)ものべている。
「二世紀後半から三世紀、すなわち弥生後期になると、支石墓はみられなくなり、北九州でもしだいに甕棺墓が姿を消し、かわって箱式石棺、土壙墓、石蓋土壙墓、木棺墓が普遍化する。ことに弥生前・中期には箱式石棺がほとんどみられなかった福岡、佐賀県の甕棺の盛行地域にも箱式石棺がみられるようになる。」
「九州地方でも弥生文化が最初に形成された北九州地方を中心にみると、(弥生時代の)前期には、土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が営まれていたのが、前期の後半から中期にかけて大型の甕棺墓が異常に発達し、さらに後期になるとふたたび土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が数多くいとなまれるようになるのである。」(以上、「墓と墓地」学生社刊『三世紀の遺跡と遺物』所収)
このように、邪馬台国の時代の墓制としては、箱式石棺などが考えられる。そして、この箱式石棺を用いるという墓制は、『魏志倭人伝』に記されている「棺あって槨なし」という墓制とも一致するものである。
(下図はクリックすると大きくなります)
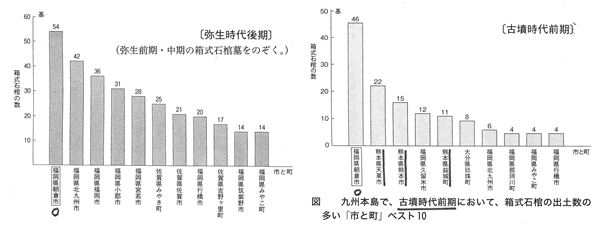
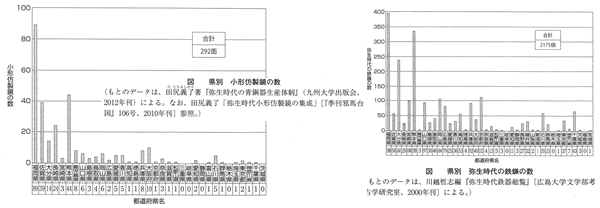
2015年に、茨城大学名誉教授の考古学者、茂木雅博(もぎまさひろ)氏の著書『箱式石棺(付、全国箱式石棺集成表)』(同成社刊)が出版されている。 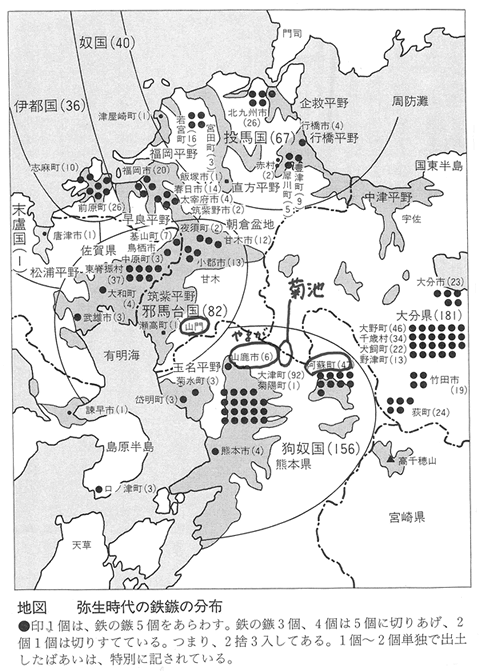
この本の「全国箱式石棺集成表」にもとづき、北九州の地図の上に、弥生時代後期の箱式石棺の分布をプロットすれば、前に示した弥生時代後期の箱式石棺分布の地図のようになる。
箱式石棺の分布は、福岡県の朝倉市を中心とし、小郡(おごうり)市のあたりから、佐賀県の三養基(みやき)郡のみやき町、神埼郡の吉野ヶ里町、神埼市にかけての筑後川の上、中流域に密集地帯がある。
井上光貞氏は、「邪馬台国の領域には、肥後北部の玉名郡、山鹿郡、菊池郡も含まれるであろう」と述べている。
この三つの郡は、ともに、鉄鏃がかなり出土している郡である(右の地図参照)。
井上光貞氏の見解
たとえば、弥生後期についていうと、北九州の甕棺文化を代表する須玖(すく)式土器は、福岡県のみでなく熊本平野に及んでいるが、緑川(みどりかわ)流域一帯より北に限られる。いっぽう球磨川上流の人吉(ひとよし)盆地では、弥生後期の免田(めんだ)式という重弧文(じゅうこもん)土器が発達し、それはおもに南方にひろがり、鹿児島県や宮崎県の山岳地にも及んでいる。そしてこの文化では、弥生後期になってもまだ石器も使っているのである。このような文化圏のありかたも、以上の推測を裏づけるものだが、わたくしは邪馬台国のひろがりを、たんに筑後北部にまで及ぼしたほうが現実的な見方だとおもうのである。 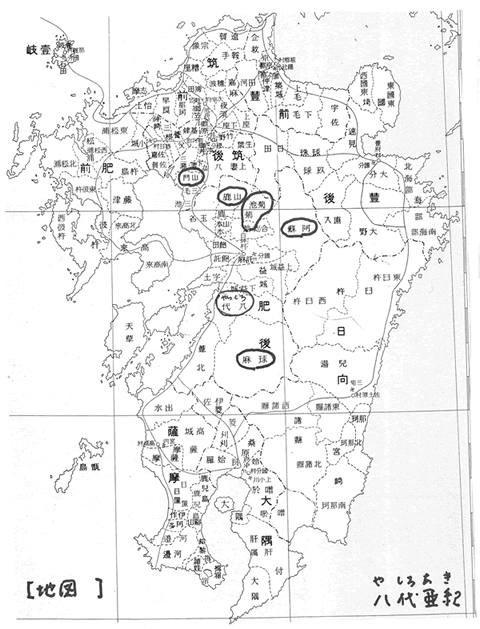
(右図はクリックすると大きくなります)
2.2 狗奴国は有明海から出雲に移ったのか?
・『古事記』から須佐之男命は有明海を治めた
『古事記』上巻に下記の記述がある。
此ノ時、伊耶那伎命(いざなぎのみこと)大(いた)く歓喜(よろこ)ビて詔(の)らさく、「吾(あ)者(は)子(こ)生(う)み生(う)み而(て)、生(う)みノ終於(はてに)三(み)はしらノ貴(たうと)き子(こ)得たり。」トノらす即(すなわ)ち、其(そ)ノ御頸珠之玉(みくびたまのたま)ノ緒(を)、母由良迩(もゆらに)、[此ノ四字 は音(こゑ)を以(もち)ゐる。下(しも)は此に效(なら)ふ。]取り由良迦志而(ゆらかして)、天照大御神(あまてらすおおみかみ)に賜(たま)ひ而詔之(ての)らさく、「汝命者(いましみことは)、高天ノ原矣所知(たかまのはらをし)らせ。」卜、事依(ことよ)さし而賜(てたま)ひき。故(かれ)、其ノ御頸珠(みくびたま)ノ名は、御倉板挙之神(みくらたなのかみ)卜謂(い)ふ。[板挙を訓(よ)みて多那(たな)卜云(い)ふ。] 次に、月読命(つきよみのみこと)に詔(の)らさく、「汝命者(いましみことは)、夜之食国矣所知(よるのをすくにをし)らせ。」卜事依(ことよ)さしき。[食を訓(よ)みて袁須(をす)ト云(い)ふ。]次に、建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)に詔(の)らさく、「汝命者(いましみことは)、海原矣所知(うなはらをし)らせ。」卜事依(ことよ)さしき。
伊耶那伎命は下記のように言ったという。
天照大御神は高天原を治めよ。
須佐之男命は海原を治めよ。
つまり『古事記』に、天照大御神は高天原を治め、海原を有明海から島原湾方面とすると、須佐之男命は熊本県付近を治めていたと考えられ、熊本県に狗奴国があったとすれば須佐之男命は狗奴国を治めていたと考えたらどうだろうか。
九州には、有明海、島原湾がある(地図参照)。筑紫平野の血脈として流れる筑後川は、有明海へとそそいでいる。有明海は、干潮時と満潮時の水位の差が、わが国でもっとも大きいといわれている海である。筑後川の河口での有明海の水位の差は、干潮時と満潮時とで五メートルをこえる。干潮時には、筑後川の濁流ははるかな沖合で海に達する。 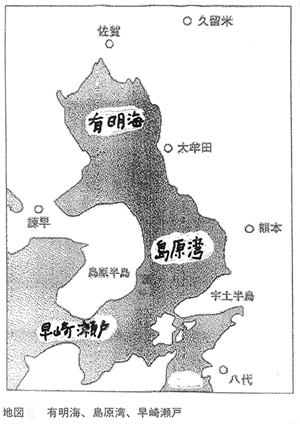
有明海では、このような干潟(ひがた)の幅が、最大六キロメートルに達するところもある。濁流は泥をふくみ、満ち潮は泥をさかさまにはこんで、海岸に堆積する。
筑後川の上流部は多雨地帯で、とくに梅雨(つゆ)と初秋のころに襲ってくる台風にともなう豪雨は、有明海の満潮とあいまって大氾濫をおこす。
有明海、島原湾の入口のところにある早崎瀬戸(はやさきせと)[早崎海岸]については、地名学者の吉田東伍が、その編著の『大日本地名辞書』(冨山房、1972年版)のなかで、「潮流強疾(きょうしつ)[強くてはやい]」「急速を以(もっ)て其名(そのな)高し」と記している。
・狗奴国の位置における『魏志倭人伝』と『後漢書』の記述の違い
『魏志倭人伝』
O此(こ)れ女王の〔治むる〕境界の尽(つ)くる所なり。
其(そ)の南には狗奴国(くなこく)[熊襲か球磨か]有り。男子を王と為す。其の官には狗古智卑狗(くこちひこ)[菊池彦か]有り
O女王国の東、海を渡りて千余里、復(ま)た国有り、皆(みな)、倭(わ)の種なり。
『後漢書』「倭伝」
O女王国自(よ)り東のかた海を度(わた)ること千余里にして、狗奴国(くなこく)に至る。[狗奴国の人は]皆倭種なりと雖(いえど)も、女王に属せず。
『魏志倭人伝』は狗奴国は女王国の南側であったのが、『後漢書』では東側となっている。これについて、森浩一氏は『後漢書』の書き間違いとしているが、
おそらくはその通りだと思うが、次のようにも考えたらどうだろうか。
『魏志倭人伝』の時代に狗奴国は女王国の南にあったが、『後漢書』が書かれたころには狗奴国は女王国の東に移った情報が入っていた。
熊本県の旧行政区である肥後と出雲は、肥伊郷(ひいのさと)と斐伊郷(ひいのさと)のように、地名などに共通性が多い。 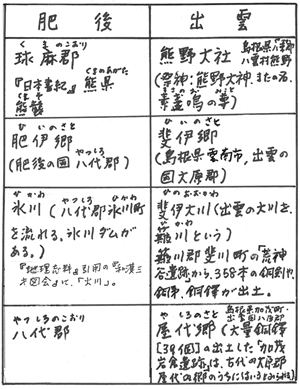
・研ぎ分け文様をもった銅矛の分布からの有明海付近と出雲との共通性
藤瀬禎博(ふじせよしひろ)氏の『九州の銅鐸工房 安永田(やすながた)遺跡』(新泉社、2016年刊)[小澤毅先生も編集委員のひとり]がある。
綾杉状の研ぎ分け文様をもった銅矛
有明海沿岸地域の青銅器にかかわる文化的まとまりをさらにみていこう。
弥生時代の中広形銅矛のうち「綾杉状の研ぎ分け文様」(以下、研ぎ分け文様)をもつ特異な銅矛の存在が知られている。矢羽(やばね)を図案化した矢絣(やがすり)模様で、光のあたり具合で矢羽のかたちに光り、清々しく勇ましい印象を与え、魔をはらう意味もあるので古くからいろいろなものに使われる。
この研ぎ分け文様をもつ中広形銅矛の出土事例をみてみよう。筑紫平野では、佐賀県東部、吉野ヶ里町の目達原(めたばる)(下図参照、以下同)遺跡から出土した銅矛4本のうちの2本(下図参照)が。吉野ヶ里町の東隣り、みやき町の検見谷(けみたに)遺跡出土の12本のうち10本(下図参照)が、そして伝鳥栖市田代(たしろ)とされているもの、また、筑後川中流域の朝倉市の甘木下渕(あまぎしたふち)で3本のうちの1本、朝倉市の東隣り、うきは市の小塩(こじお)に1本、さらに東へ向かい東九州の大分県宇佐市の谷迫(たにさこ)の7本のうち3本の出土例がある。
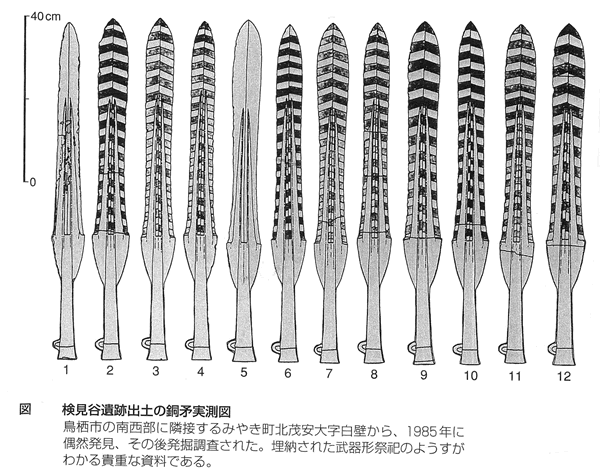
玄界灘側では、唐津平野の唐津市千々賀庚申山(ちちかこうしんやま)の双耳(そうじ)銅矛1本、福岡平野の須玖岡本遺跡D地点1本の出土例がある。また遠く離れた島根県出雲市の荒神谷遺跡では、16本のうち7本が知られている。(上図参照)
以上、現在まで合計24本が研ぎ分け文様をもつ銅矛として知られている。地域ごとにまとめてみると、玄界灘側は2本、有明海側は15本(佐賀平野東部が13本、筑後川中流域が2本)、さらに筑後川を通り抜けた東九州に3本の出土が、研ぎ分け文様をもった銅矛の分布状態となる。
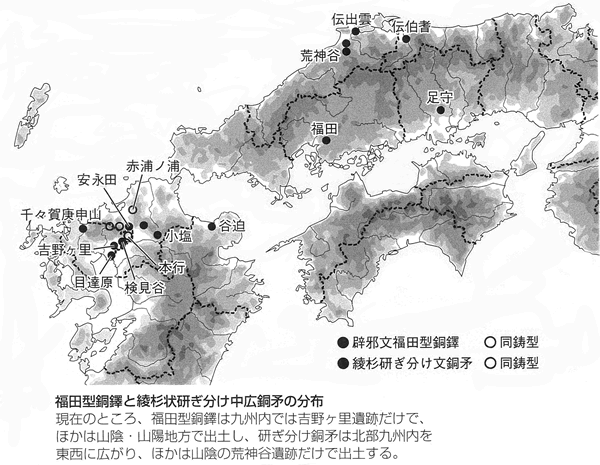
鋳型と製品の分布状態を重ね合わせると、研ぎ分け文様をもった鋼矛は佐賀平野東部から筑後川流域にかけて多く、その中心にある安永田遺跡で製作された可能性が大である。
この状態にさらに、文様を施さない中広形銅矛の分布状態も合わせてみてみると、玄界灘側は15本でこのタイプの銅矛の出土分布は少なく、逆に有明海側は48本と多いといえよう。
注:藤瀬禎博(ふじせよしひろ)
1947年、福岡県飯塚市生まれ。
明治大学文学部史学地理学科考古学専攻卒業。
1977年より鳥栖市教育委員会に所属し、生涯学習課参事(兼市誌編纂係長)等を務め退職。現在、鳥栖郷土研究会会長。
主な著作[安永田遺跡の青銅器鋳型について](松本清張編『銅鐸と女王国の時代』日本放送出版協会)、「環有明海と出雲-青銅器の生産と流通-」(『歴史読本』42-5、新人物往来社)、「環有明海の青銅器文化-青銅器生産はいつはじまったかー」(『地域と文化の考古学』六一書房)、「青銅器文化と技術の革新」『鳥栖市誌』第2巻ほか。
そして、考古学者の森浩一氏はのべている(以下、傍線をほどこしたのは安本。)
「後藤(守一)先生は「三種の神器の考古学的検討」という論文を雑誌『アントロポス』に発表し、翌年には『日本古代史の考古学的検討』(山岡書店)という冊子風の単行本にその論文を収めた。先生の知識の豊かなことや自由な発想に、当時十八歳の僕は驚嘆した。もちろん先生の勇気にも感心した。
僕は考古学だけでは歴史にせまれないことを、この本によってさらに痛感した。神話をも含め『古事記』や『日本書紀』からも信頼できる文献資料を見いだし、考古学資料と総合した時に初めて本当の歴史は描ける。」(『森浩一の考古交友録』朝日新聞社、2013年刊、137ページ)
文献と考古学の結果から、有明海沿岸と出雲方面との共通点から、上記のようにもっともらしくまとめるともっともらしくなる。
皆さんはどう考えますか?