■属人主義
物事の判断に、権威がある人とか、その方面の専門家とかが言ったから正しいとするやり方がある。それをあえて属人主義として、その例について説明する。(注:属人主義は刑法の用語でよく知られている)
・梅原末治氏について
梅原末治氏は、京都帝国大学(現在の京都大学)の教授で、大正から昭和時代にかけての大考古学者であった。
参考:人名辞典から
【梅原末治】(うめはら すえじ)(1893-1983)大正~昭和時代の考古学者。明治26年8月13日生まれ。同志社普通学校在学中から京都帝大考古学教室に出入りし、浜田耕作、内藤湖南らに師事。昭和14年に京都帝大教授。銅鐸(どうたく)、中国青銅器、古墳などの研究によって東洋考古学の基礎を確立した。38年文化功労者。昭和58年2月19日死去。89歳。大阪出身。著作に「鑑鏡の研究」「考古学六十年」など。
梅原末治は、多くの発掘出土品についての、精細な記録を残した人であった。
そしてまた、梅原末治は、伝橿原市出土、大和鳥屋千塚(やまととりやせんづか)[橿原市]出土などのように記して、古代の勾玉として紹介したものの八割以上が、現代技法によって作られたものであるとして、ガラス工芸の専門家の由水常雄(よしみずつねお)氏から、徹底的な批判をあびたことがある(『芸術新潮』1973年1月号、『週刊新潮』1972年1月23日号、由水常雄著『火の贈り物』「せりか書房、1977年刊」)。鉛ガラスでなく、ソーダガラスであること、ビール瓶を溶かして作られた独特の色をしているもののあることなどが指摘されている。
梅原末治は、東洋考古学の基礎を確立した人であった。
梅原末治は、身体虚弱であったため、上級学校に進学せず、京都帝大考古学教室に出入りし、無給の雇(やと)いから出発し、京都帝大の教授となり、八十九歳で没した。
梅原末治の業績と研究方法とについては、医学者で東洋考古学者の穴沢咊光(あなざわわこう)氏(会津若松市の穴沢病院院長)が、「梅原末治論-モノを究めようとした考古学者の偉大と悲惨-」(『考古学京都学派』「角田文衞(つのだぶんえい)編、雄山閣出版、1997年刊所収」)という文章の中で、以下のように述べている(引用文中の一部に傍線を引き、その部分の文字をゴシックにしたのは安本)。
「梅原が殆(ほとん)どフリーハンドに近い天才的画技でさっと書き上げた図面を、同じ遺物について後で厳密な方法で測った図面と比較したところ、殆(ほとん)ど相違がみつからなかったという驚くべき話か伝わっている。」
「梅原の著書の多くは印刷の優秀、図版の鮮明、図面の精密さで知られ、内容的にも重要で貴重な資料が多く、ほとんど豪華美術書にみまがうばかりで、きわめて質の高い出版と評価され、その多くが基本的な資料集や文献として今日なおその価値を保っている。」
「このようにして、梅原に訓練されて考古遺物の優秀な観察、記録の能力を身につけた学生が全国各地に散って、遺物を中心とした事実記載の精細さを誇る日本考古学の大伝統が形成されていったのである。」
「こうして梅原の研究戦略を検討し、彼の学問を評価すると、梅原は『コツコツと遺物自体を徹底的に調べ上げる』ことにかけては万人の及ばぬ努力家で、(整理・観察・事実記載の)天才的な才能を発揮したが、『それを結び合わせて研究を進めて行く』ことはどうも苦手であったようだ。」
「林[中国考古学者で、京大教授などであった林巳奈夫(みなお)]は、梅原という学者は『切手、蝶などと同様な(考古資料の)収集家マニアという色眼鏡で色々と思い起こしてみると説明がつく』と述べた。このきわめて辛辣なコメントの『収集……』という言葉の次に『および記載』という一語を挿入すれば、梅原の学問の本質そのものを最も適確に表現した言葉になるだろう。つまり、厳格経験主義に徹した記述の学者だった梅原にとっては、データ(資料)がすべてであった。彼の学問とはデータをどこからか仕入れてきて表する以外にはタネもシカケもなく、それ以外に特別な方向もなかったのだ。」
「『モノを一つ一つ丹念に観察し、実測し、写真や拓本をとり、その形態や装飾をアタマにたたきこむだけではダメなのであって、青銅器は成分の鉛同位体比を測り、鉄器はX線検査、土器は胎土分析、石器は使用痕の研究、木器は年輪年代の測定、動植物遺存体は専門家の鑑定、遺跡の土は土壌分析と花粉分析を行い、その結果を総合しなければ本当のことはわからない』といった時代になった。資料の激増によって、梅原のやったように自分の頭脳をデータベース化していたのでは追いつかなくなり、碩学(せきがく)の頭脳と資料のファイルに代わってコンピューターが登場し、『考古資料に関する情報ネットワークの開発によって、学会共通のデータベースには夥(おびただ)しい資料が登録され、そこから引き出される情報がただちに研究資料となる』という情報革命の時代が必ず到来するであろう。そういう時代に、考古学の最新課題となるのは、いろいろの情報をいかに総口して過去を復原するかという考古資料の解釈理論であり、『考古学は報告書や図録を出版するだけが能じゃない』といわれるようになるだろう。こういう時代になって、日本考古学が梅原のやったように『資料の語ることがおのずから結論となる』という厳格経験主義に拘泥(こうでい)し続けるならば、国際学界からは『事実を積み上げるばかりで、その説明を試みない』と『峻烈な非難を浴びせられる』であろう。」
一昨年(2019年)、比較的若くしてなくなった考古学者、細谷葵(ほそやあおい)[1967~2019。女性。お茶の水女子大学特任准教授など]は、報告書「理論なき考古学-日本考古学を理解するために-」の中で、日本考古学の「理論の欠如」を指摘して、「(日本の考古学で、)提示されているものは、説明も議論も伴わないバラバラのデータの山積み」と述べている。(この細谷葵の報告書は、最初、イギリスで発表された。現在は、インターネットで、日本文の形で容易に見ることができる。)
このように海外で学んだ学者は日本の考古学会の問題点(一つ一つを丁寧に記録すれば良いとする考え方)を的確に指摘している。
日本の考古学会は属人主義的で、個々の発掘の整理だけで終わっていることが問題である。
・科学の方法について
ここで、科学の歴史について、ふりかえってみよう。
「科学的な研究」においては、次の、「法則の発見」が、重要である。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【法則の発見】
「科学的な研究」においては、正確に観察、測定し、記述するだけではなく、それらの測定値から、法則性・規則性を見出して行くことが重要である。
近代科学の成立をみちびいた「天文学」は、およそ次の(A)(B)(C)の三つの段階をへて発展してきたといえる。
(A)デンマークのティコ・ブラーエが、厖大(ぼうだい)で精密な天文観察記録を残した。
(B)ドイツのケプラーが、ティコ・ブラーエの観察記録にもとづき、惑星は太陽を一つの焦点とする楕円軌道上を動いていることなどを示した。いわゆる「ケプラーの三法則」を示した。
(C)イギリスのニュートンが、万有引力の法則(引力は、二つの物体の質量に比例し、二つの物体間の距離の二乗に反比例する)を仮定すれば、「ケプラーの三法則」をみちびきだせることを示した。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
「天文学」のばあいの(A)の、精密な天文観察記録にあたるのが、「考古学」のばあいの、精密な発掘と、遺跡・遺物についての精密な観察記録にあたるといえよう。考古学の分野では、すでに、厖大な、そのような観察記録が蓄積されている。
ただ、それは、個々の遺跡・遺物についてのものが圧倒的に多い。
「観測値を分析し、それをまとめて法則を引き出すこと。」
そして、これを、意識的に行なうこと。
これは、ケプラーがはじめて確立した「方法」である。これが、近代科学の成立・発展の基本原理となった。
よく、ものを見るのに、多面的に見る必要性が説かれる。
①虫の目で見る(ミクロの視点で見る。細部をよく見る)。
②鳥の目で見る(マクロの視点で見る。大局的に、全体を見る)。
③魚の目で見る(潮の流れを見る。変化の傾向を見る)。
④コウモリの目で見る(コウモリは、逆さまにぶらさがる。ものごとを、逆さの立場から見る。逆の立場から見る)。
梅原末治流の考古学のばあい、いちじるしく詳細なのであるが、①の虫の目で見ている傾向が強い。「肉眼観察主義」である。
鳥の目で、大局的に見る観点、魚の目というか、歴史の流れ、変化の様子を見る観点、コウモリの目で見るというか、勾玉を肉眼で精密に観察するだけではなく、素材が現代のソーダガラスかどうかを調べるなど、別の観点、逆の観点などから見る。そして、それらを総合的にまとめる体系的な方法が必要である。
・科学的探究のためには、道具・方法が必要である
また、科学的探究を行なうためには、次のことも重要で、明確化しておく必要がある。
宇宙を探究するためには、「望遠鏡」が必要である。ドイツの医学者、ロバート・コッホは、当時登場した新しい道具である「顕微鏡」によって、患者の血液を観察し、コレラ菌を発見した。
ガリレイも、コッホも、「望遠鏡」や「顕微鏡」などの新しい道具によって、「直接の肉眼」だけでは見えない、広大な「新世界」を発見した。「肉眼」だけで見える世界が、この世のすべてではない。ごく一部である。
「数式」というものがある。
「数式」は、xとyなどの、「関係」をあらわしている。
「関係」そのものは、抽象的なもので、直接的には目で見えない。「数式」は、その「関係」を可視化する働きをもつ。
「望遠鏡」も「顕微鏡」も、「数式」も、直接肉眼では見えないものを可視化する「道具」であり、「方法」である。
この「道具」「方法」を改良、発展させることこそが、科学を進歩させる。
この世には、「道具」や「方法」を使わず、私たちの直接的な「肉眼観察」だけにたよったのでは、つかむことのできない広大な世界がある。
「すぎ去った過去」「歴史」なども、私たちの肉眼では、もはや、直接的には見ることができない、広大な世界である。
見えない世界を、「道具」「方法」「数式などをふくむことば」を使って、可視化して行くことこそが、「科学」というものである。
私は、これまで数十年にわたって、歴史や言語についての探究を行なって来た。その探究方法は、今風(いまふう)にいえば、データサイエンス的方法によるものであった。
データサイエンスにおいて、探究のための主要な武器は、統計学や確率論である。
統計学や確率論は、科学の広い範囲で用いられるが、データサイエンス以前(あるいは、以外)の科学における統計学などの用いられ方と、データサイエンスにおける統計学などの用いられ方とには、大きな違いがある。
それは主として、統計学などを用いる対象の違いである。
データサイエンス以前(あるいは以外)のばあいには、統計学は、たとえば「人口」であるとか、農業や工場における「生産物の量」であるとか、おもに、具体的に目に見える「物」を数えて、そこで得られた数値を対象としてきた。
いっぽう、データサイエンスにおいては、ある特定の「言葉」の使用頻度であるとか、調査された人々の「意見」の賛成の率であるとか、視聴された率であるとか、ある商品の販売量(販売された回数)のような「出来ごと」の回数であるとか、碁や将棋などにおける「勝率」であるとか、広い意味での「情報の量」を数えるという方向に、統計学の対象が変化してきている。
「情報の量」は、莫大なものとなりつつあるので、ビッグデー夕を分析するための、さまざまな方法が、開発されてきた。
梅原末治は、「考古学の本義は物だ」と述べた。
梅原末治のように、「考古学の対象物は物」ときめてかかれば、「直接肉眼観察主義」が、強い意味をもって、浮かびあがってくるであろう。
そして、梅原末治流考古学では、「正確な観察と記述」それ自体が、目的化するようになる。
しかし、「考古学は、『歴史』を復元するためのもの」と考えれば、肉眼観察主義をこえる「科学的方法」が、強く求められることとなる。
猫は、人間と同じく肉眼を持つ。そして、記憶力も持つが、
百年前のことを知ることはできない。しかし、人間は、千年前のこともあるていど知ることができる。それは、「ことば」によってである。直接的な「肉眼観察」によってではない。
「歴史」とは、いつ、どこで、なにが起きたかを知ることを目的とする。
「時間」という直接目で見ることのできないものを相手にし、「出来ごと」という、これまた直接的に今は見ることのできない「こと」を相手にしているのである。それは、「こと」であって、「物(もの)」ではない。
梅原末治流の「物」と「肉眼観察」を中心とする方法は、「歴史」を知る方法としては、大きな限界がある。
「歴史」を知るためには、梅原末治の方法以外の方法を考えなければならない。
「肉眼」で見えるものを、できるだけ正確に観察し、記述することは、科学的分析をするための、「データ」をととのえるための、基本的な「技術」である。しかし、それだけでは、「技術」でありえても、それ自体は、「科学」ではない。
データを分析するデータサイエンスやビッグデータの世界での、望遠鏡や顕微鏡にあたる道具が「統計学」である。
ビッグデータの世界では、データの量、「情報」の量が多くなりすぎ、個々のデータを、直接の肉眼で追うだけでは、全体の情況をつかみきれなくなっている。
旧石器捏造事件のさい、『ネイチャー』誌は、「捏造された出土物は、批判の欠如をさし示す(Fake finds reveal critical deficiency)」という文章をのせ、「井の中の蛙、大海を知らず」という『荘子』にもとづく日本のことわざの英訳 "A Frog in a well that is unaware of the ocean"を引用して、この事件を痛烈に批判している(Cyranoski,D.,Nature,Vol,408,280ページ,2000年11月号)。
そこには、次のような文章がみえる。
「この(旧石器捏造事件の)話は、藤村新一が捏造作業をつづけるのを許した科学文化についての疑問をひきおこした。」
「日本では、人々を直接批判することは、むずかしい。なぜなら、批判は、個人攻撃とうけとられるからである。」
「直観が、ときおり、事実をこえて評価される。」
■青銅鏡の歴史の「第1次大激変」と「第Ⅱ次大激変」(鏡の分布中心地域の、大激変が存在するという法則)
私はこれまで、日本古代史上のデータについて、成立するいくつかの重要と思われる。「法則」を見出してきた。
そのうち、まず次の「法則」をとりあげる。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
・鏡の分布中心地域の大激変の法則
青銅鏡の歴史において、西暦320~350年ごろに、鏡の分布中心地域が、福岡県など北部九州を中心とする地域から、奈良県など畿内を中心とする地域へと、大変化をするという事実が認められるという「法則」である。以下、略して、「鏡の分布中心地域の大激変が存在するという法則」と呼ぶ。
じつは、わが国の青銅鏡の歴史においては、「鏡の分布中心地域の大激変」が起きるよりも、時期的にまえに、わが国で出土する鏡に用いられている銅原料が、「中国の華北系の銅原料から、中国の華中・華南系(長江流域系)のものに変化するという「大激変」が起きている(鉛の同位体比の分析の結果による)。私は、この大激変を、「第1次大激変」とよび、「鏡の分布中心地域の大激変」を、「第Ⅱ次大激変」と呼んでいる。
「第Ⅰ次大激変」は、西暦280年に、中国で呉の国が滅亡し、長江(揚子江)流域産出の銅が、華北の洛陽などに流れこんだことによって生じた現象とみられる。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
この「第Ⅰ次大激変」については、鉛同位体の説明が必要なので、別の定例会で説明をする予定。
・「第Ⅱ次大激変の法則」
「第Ⅱ次大激変の法則」は、データサイエンス的探究方法の、比較的わかりやすい具体例にもなりうると思う。
なお、私の探究方法の基本的な構造は、次のようになっている。
①確実なデータから出発する。「データそのもの」が、議論の出発点、前提、「公理」といえるものとなる。
②データを、統計的に処理して、「法則」を見出す。この「法則」が、「定理」的なものとなる。
③諸法則(諸定理)を組みあわせて、日本の古代史の「骨格」を作る。
④「文献」「考古学的資料」その他により、「骨格」に「肉づけ」をする。
ユークリッドの幾何学をお手本として、ニュートン力学が成立した。これら近代科学をみちびいた方法をお手本とし、証明の方法や、根拠(エビデンス)のあげ方など、それにならう形で、古代史を考えようというわけである(公理主義)。
近代科学の記述は、物理現象を、数学という「ことば」を用いて記述することからはじまった。他の分野の科学的研究も、それにならうのが、近道である。それにこたえうるような、そして、多くの分野に適用しうるような数学(統計学や確率論)が、すでに用意されているのである。
「位至三公鏡」によって代表される、「いわゆる西晋鏡」以前の鏡は、九州の福岡県を中心に分布する。それよりあとの鏡、「画文帯神獣鏡」「三角縁神獣鏡」などは、奈良県を中心に分布する。
この大激変が起きたのは、大略、西暦320年~350年ごろとみられる。
この「第Ⅱ次大激変」が起きたのは、大和朝廷の成立と発展が関係しているとみられる。このようなことについては、あとで議論する。
以下、時代を追って、わが国の青銅鏡の出土数の地域的分布の情況をみて、「第Ⅱ次大激変」の起きている様子をみてみよう。
まず、以下のワクでかこんだ文章内のグラフをざっと、目で追ってみていただきたい。「大激変」の存在は、一目瞭然であると思う。
・第Ⅱ次大激変の存在を示すグラフ(データ)
(1)前漢の国(紀元前206年~紀元後8年)系の鏡
「草葉文鏡」「星雲鏡」「異体字銘帯鏡」(昭明鏡・日光鏡・清白鏡など)」
(2)後漢の国(西暦23年~222年)、魏の国(西暦220年~265年)系の鏡
「雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡」「四葉鈕座内行花文鏡」「八葉鈕座内行花文鏡」など(「蝙蝠鈕座内行花文鏡」はいれない)
(下図はクリックすると大きくなります)
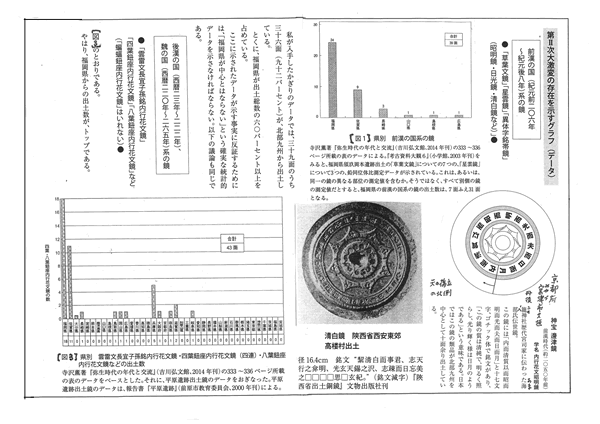
(3)大略、魏の国(西暦220年~265年)のころ、ほぼ邪馬台国の時代に、わが国で作られていたとみられる鏡
a.「小形仿製鏡第Ⅱ型」
この鏡の出土数は、かなり多い。当時、魏の国では、銅原料が不足していた。
鉛同位体比の分析結果をみると、貸泉(銅銭)を大量に溶融すると、「小形彷製鏡第Ⅱ型」の銅のようになるかとみられる。
(4)庄内期の鏡
寺沢薫氏は、庄内期を、ほぼ、邪馬台国時代にあたるとする。
鏡の地域的分布の中心は、福岡県を主とする北九州となる。
とすると、鏡の分布から見たばあい、邪馬台国は、九州にあったことにならないか?
(下図はクリックすると大きくなります)
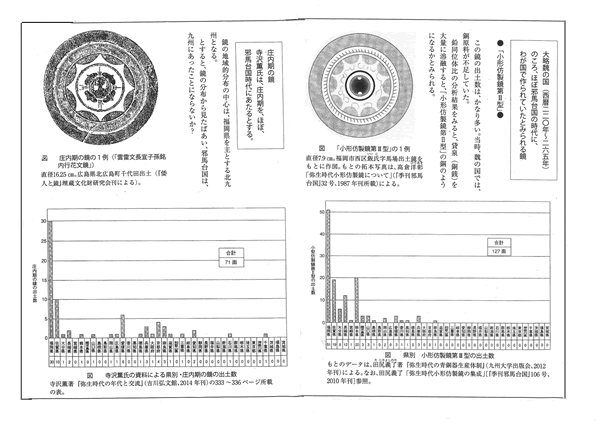
(5)大略、西晋の国(西暦265~316)ごろの鏡
a.「位至三公鏡(いしさんこうきょう)」と「双頭竜鳳文鏡(そうとうりゅうほうもんきよう)」
双頭竜鳳文は西晋時代の鏡であり、一つの体躯の両端に、竜または鳳凰の頭がついている。これを一単位の文様とするとき、二単位(二体躯分)が、左右に描かれている。一単位の二つの頭がともに竜頭のこともあれば、一方が竜頭、一方が鳳頭のこともある。「双頭・竜鳳・文鏡」と区切るべきである。
文様の基本は、S字形または逆S字形で、点対称。双頭竜鳳文鏡では、主文様の外がわに連弧文があるが、位至三公鏡では、連弧文がない。
それに対して、位至三公鏡は鈕をはさんで、上下に「位至」と「三公」の銘文をいれ、内区を二分する。左と右とに、双頭の獣の文様を配する。獣の文様は、ほとんど獣にみえないことがある。小形の鏡で、中国では、後漢末から東晋代にかけて製作された。双頭竜鳳文鏡の系統の鏡である。
『洛鏡銅華』(中国・科学出版社、2013年刊)は、洛陽出土の銅鏡についてまとめている。
『洛陽銅華』は、13面の「位至三公鏡」系の鏡をのせる。
そのうち、13面を、西晋時代の鏡とする。
1面のみを、大略西晋の時代よりもあとの、「北朝(311~619)」の時代のものとする。
また、中国では、本誌前前号(138号)で示したように、「洛陽晋墓」からは、八面の「位至三公鏡」が出土し、そこからは、西暦287年、295年、302年にあたる年の墓誌が出土している。他にも、「285年~289年」ごろの年を記した墓誌とともに出土している「位至三公鏡」が4面ほどある。
そのとおりである。
奈良県からは、弥生時代~庄内期の鏡が、福岡県にくらべ、はるかに、わずかしか出土していない。それにもかかわらず、奈良県の土器編年などをもとに、鏡の年代を考えるのは、非常な無理がある。土器には、年代が直接記されているわけではない。
位至三公鏡」は、鏡の年代を考える上での、重要な手がかりを提供している。
「位至三公鏡」などの西晋時代ころの鏡も、北部九州を中心に分布しているところから見ると、やはり、邪馬台国は、九州にあったようにみえる。
邪馬台国勢力は、卑弥呼の時代のあとも、西晋王朝と国交をもっていたことを、史書は、伝えている。
(下図はクリックすると大きくなります)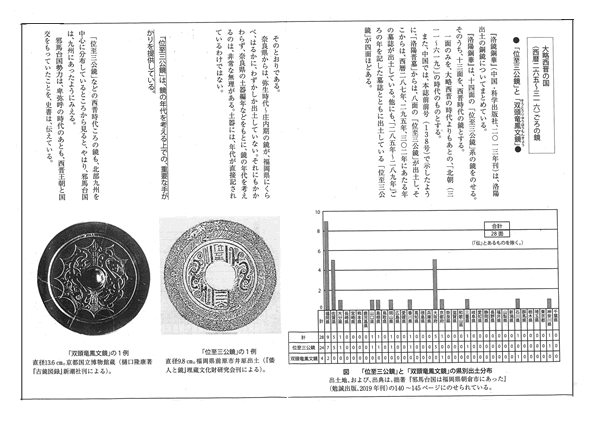
b.「夔鳳鏡(きほうきょう)」と「獣首鏡」
「金銀錯嵌珠竜文鉄鏡」と、ほぼ同種の文様をもつ青銅鏡である。
「夔鳳鏡」と「獣首鏡」とが、おもに北部九州から出土しているのであるから、「金銀錯嵌珠竜文鉄鏡」も、北部九州から出土したとしても、不自然ではないとみられる。
わが国で出土する「夔鳳鏡」と「獣首鏡」は、わが国で出土する「位至三公鏡」や「双頭竜鳳文鏡」と、銅原料が、ほぼ同じであることが知られている(鉛同位体比の測定による)。
また、中国において、「夔鳳鏡」などは、しばしば、「位至三公鏡」が出土するのと、同じ墓から出土している。
「夔鳳鏡」「獣首鏡」も中国で、ほぼ西晋時代を中心とするころに行なわれた鏡とみられる。
c.「蝙蝠鈕座(こうもりちゅうざ)内行花文鏡」
わが国で出土している「蝙蝠鈕座内行花文鏡」は、「位至三公鏡」や「夔鳳鏡」などと、銅原料がほぼ同じであることが知られている(鉛同位体比の測定による)。
また、中国において、「蝙蝠鈕座内行花文鏡」は、「位至三公鏡」が出土するのと、同じ墓からしばしば出土している。
(下図はクリックすると大きくなります)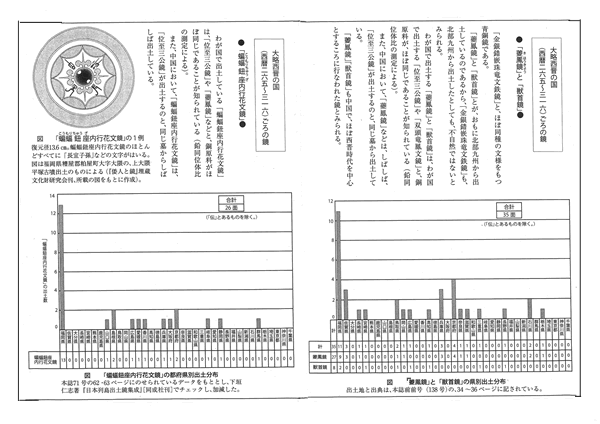
d.「いわゆる西晋鏡」
以上の、大略西晋の国時代ごろの鏡、「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「夔鳳鏡」「獣首鏡」「蝙蝠鈕座内行花文鏡」をまとめて、「いわゆる西晋鏡」と呼ぶことにする。
「いわゆる西晋鏡」について、グラフを作れば、下図の右のグラフようになる。
奈良県から出土の1面の「いわゆる西晋鏡」は、桜井茶臼山古墳出土のもので、図には、「夔鳳鏡」とあるが、正確には、「単夔鏡」である。これを、「夔鳳鏡」の中に入れるべきか否か、やや問題が残る。もし、これを除けば、奈良県出土の「いわゆる西晋鏡」は、確実なものは、一面もないことになる。
(6)『魏志倭人伝』に記載のある事物
鉄の鏃(やじり)
『魏志倭人伝』に、倭人は、「鉄の鏃」を用いるとある。
鏡ではないが、弥生時代の「鉄の鏃」も、福岡県をはじめとする北部九州を中心に分布する(下図の左のグラフ)。
『魏志倭人伝』に記されているもので、考古学的遺物を残しうるもののほとんどは、福岡県をはじめ、北部九州を中心に分布する。
このことは、邪馬台国が、北部九州にあることを、強く指し示している。
(下図はクリックすると大きくなります) 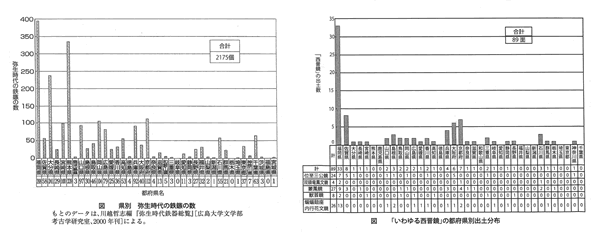
(7)『魏志倭人伝』の記載と関連のある事物
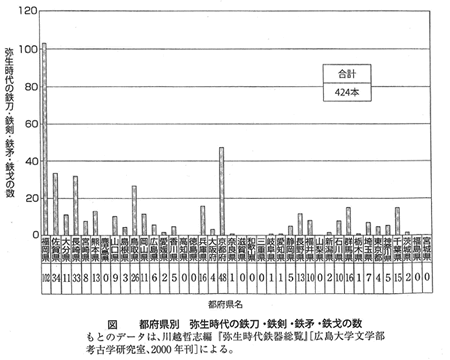
鉄刀・鉄剣・鉄矛・鉄戈
『魏志倭人伝』に、「五尺の刀」二口という記事がある。
また、倭人は、武器に「矛」を用いるとある。
「五尺刀」「矛」は、いずれも鉄製とみられる。
「刀」と「剣」、「矛」と「戈」はかならずしも、
明確には、区別されていないので、「鉄刀」「鉄剣」「鉄矛」「鉄戈」の県別分布を調べれば、右図のようになる。
・大激変の存在
ここまで調べたものは、すべて、福岡県を中心とする北部九州を中心として分布する。
それは、時期的にみれば、次のようなものである。
①中国では、おもに、「前漢(紀元前206~紀元後8年)から、西晋(265~316)のころのものとして出土している遺物である。
②日本では、おもに、弥生時代・庄内期にかけてのころ、出土している遺物である。
③邪馬台国の時代も、この時期のうちに含まれる。このような状況は、邪馬台国が、北部九州にあったことを強く指し示す。
ここで、大激変が起きる。以後、鏡などが、奈良県をはじめとする近畿を中心に分布するようになる。
それは、時期的にみれば、次のようなものである。
①中国では、東晋(317~420)以後の時代にほぼあたる。
②日本では、古墳(前方後円墳)時代、布留式土器以後の時代に、ほぼあたる。
③大和朝廷が成立し、発展した時代にあたる。
以下では、その状況をみてみよう。
(8)中国長江流域系の鏡
わが国出土のものは、四世紀前半あるいは中ごろから登場し、おもに、四世紀の遺跡から出土している。
a.「画文帯神獣鏡」
わが国で、「画文帯神獣鏡」が出現する時期については、あとで議論する。
b.「三角縁神獣鏡」
中国からは一面も出土していない。ただし、文様、鉛同位体比などは、長江流域系のものである。わが国では、「画文帯神獣鏡」よりも、すこし遅れて登場する。おもに四世紀の遺跡から出土している。
(下図はクリックすると大きくなります)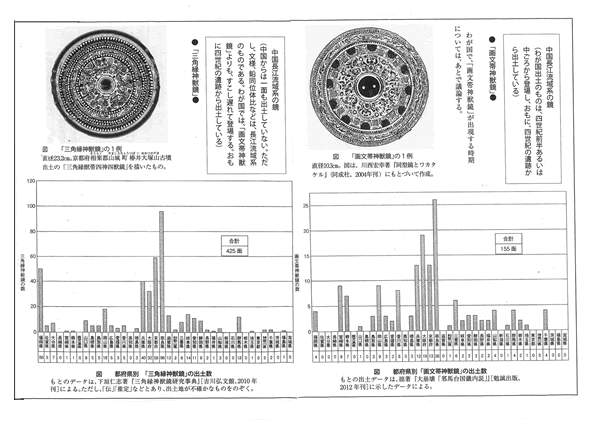
■法則の存在
県別分布は「福岡県」を中心に分布するものと、「奈良県」を中心に分布するものとに、はっきりわかれる。その境をなすのは、「位至三公鏡」などの「西晋鏡」である。
・巨大前方後円墳(全長100メートル以上)の数
下図の右のグラフ参照
・巨大前方後円墳(全長80メートル以上)の数
下図の左のグラフ参照
前方後円墳など、古墳時代に出土する多くの遺物、たとえば、竪穴式石室の数などは、巨大前方後円墳と同じく、奈良県を中心に分布するとみられる。
(下図はクリックすると大きくなります)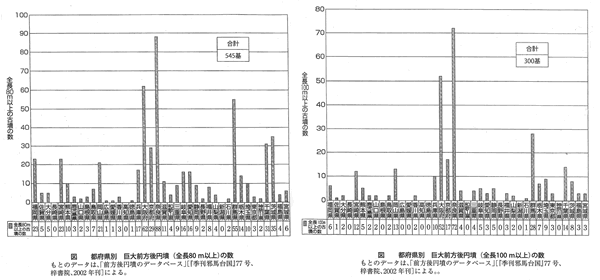
・中国出土の「位至三公鏡」の年代
国立歴史民俗博物館の館長であった考古学者で、なくなった佐原真は述べている。
「弥生時代の歴年代に関する鍵は北九州がにぎっている。北九州地方の中国・朝鮮関連遺物・遺跡によって暦年代をきめるのが常道である。」(「銅鐸と武器形青銅器」『三世紀の考古学』中巻、学生社、1981年刊)
『魏志倭人伝』は魏の時代であり、次は西晋の時代、その次は東晋の時代である。
西晋の時代までは北部九州を中心に鏡が分布して出土し、東晋の時代にあたるころは古墳時代であり、奈良県を中心として鏡がおもに分布して出土する。
位至三公鏡の年代は『洛鏡銅華』(中国・科学出版社。2013年刊。日本語訳『洛鏡銅華』)によって分かる。ほとんどが西晋時代の鏡とされている。
この鏡は日本では北九州を中心に分布している。
ということは、邪馬台国勢力は、まだ北九州に残っていた可能性がある。
この位至三公鏡は鏡の埋納年代推定の鍵となりうる。
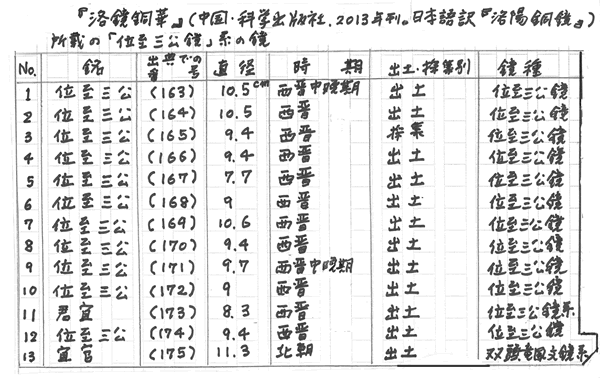
中国の秦・漢時代から南北朝時代までの、洛陽付近での考古学的発掘の、報告書類を集大成したものとして、『洛陽考古集成-秦漢魏晋南北朝巻-』(上・下二巻、中国・北京図書館出版社、2007年刊)が発行されている。
また、洛陽付近から出土した鏡をまとめた図録に、『洛鏡銅華』(上・下二冊、中国・科学出版社、2013年刊)がある。
『洛陽考古集成』『洛鏡銅華』にのせられている「位至三公鏡」のうち、出土地と出土年のはっきりしているものすべてを、表の形にまとめれば、表のようになる。
これらはすべて、魏や西晋の都であった洛陽付近から出土しているものである。
この表をみると、つぎのようなことが読みとれる。
①「位至三公鏡」は、後漢晩期に出現している。

②の全部で二十七面の鏡のうち、後漢時代のものは、一面のみで、魏や西晋期のものが二十六面である。圧倒的に、魏や西晋(265年~316年)の時代のものが多い。No2~9に記すように、「洛陽晋墓」のばあい、二十四面の出土鏡のうち、八面は、「位至三公鏡」である。表の「洛陽晋墓」のばあい、西暦287年(太康八)、295年(元康九)、302年(永寧二)の、三つの墓誌がでていることが注目される。いずれも、西晋時代のもので、西暦300年前後である。
③西晋よりもあとの、南北朝時代のものとしては、双頭竜鳳文鏡系の「宜官」銘翼虎文鏡が一面、北朝(386~581)の鏡として、洛陽市郊区岳家村から出土している。ただし、これは、出土年がしるされていない(この鏡のことは、『洛鏡銅華』および、『洛陽出土銅鏡』に記されている。)
「位至三公鏡」が、主として西晋時代のものであることは、洛陽付近以外から出土した「位至三公鏡」についてもあてはまる。 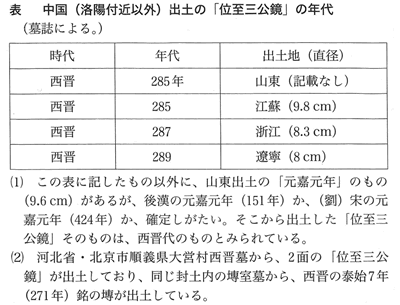
いま、近藤喬一(たかいち)氏の論文「西晋の鏡」(『国立歴史民俗博物館研究報告』55集、2003年刊)にのっている「紀年墓聚成」の表にもとづくとき、年代の確定できる中国出土の「位至三公鏡」は、右表のとおりである。
この表のものに、さきにのべた「洛陽晋墓」出土の八面の「位至三公鏡」を加えれば、年代のほぼ確定できる十二面の「位至三公鏡」のすべてが、西暦285年以後に埋納されたものといえる。すべて、西晋時代のものである。
表に示されている鏡の年代からみて、わが国から出上する「位至三公境」も、そのほとんどは、西暦285年以後ごろ、埋納されたもので、中国と日本との地域差、年代差を考えれば、西暦300年ごろ以後に埋納されたとみるのが穏当である。
そして、その「位至三公鏡」が、わが国においては、北九州を中心に分布している。
なくなった考古学者の森浩一氏は、すでに、警鐘を鳴らしている。
「最近は年代が、特に近畿の学者たちの年代が、古いほうへ向かって一人歩きしている傾向がある。」(『季刊邪馬台国』53号、1994年刊)
・わが国出土の「位至三公鏡」
「位至三公鏡」は、「三角縁神獣鏡」などと異なり、中国からも出土するが。わが国から出土する「位至三公鏡」については、つぎのようなことがいえる。
①中国で、おもに西晋時代に行なわれた「位至三公鏡」は、わが国では、福岡県・佐賀県を中心とする北九州に出現し、多く出土している。奈良県からは、確実な出土例がない(下表参照)。
ただし、下表は、「位至三公鏡」の祖型である「双頭竜鳳文鏡」をふくむ。
②「位至三公鏡」よりも、形式的にまえの時代の鏡(雲雷文「長宜子孫」銘内行花文鏡など。そのなかに、魏代の鏡がふくまれているとみられる)も、北九州を中心に分布する。
③九州出土の「位至三公鏡」は、弥生時代の遺跡から出土しているものがあるが、九州以外の遺跡から出土した「位至三公鏡」は、まず、古墳時代の遺跡から出土している。九州以外の地の「位至三公鏡」は、九州方面からもたらされた伝世鏡か、あるいは、踏みかえし鏡であるにしても、九州よりもややのちの時代に埋納された傾向がみてとれる。
④これらのことから、魏のあとをうけつぐ西晋の西暦300年ごろまで、鏡の出土分布の中心は一貫して北九州にあったといえる。
⑤「位至三公鏡」よりも、形式的にも、出土状況も、あとの時代の「三角縁神獣鏡」などは、畿内、とくに奈良県を中心に分布する。(「位至三公鏡」は、おもに、庄内式土器の時代の遺物として出土し、「三角縁神獣鏡」は、おもに、そのあとの布留式土器の時代の遺物として出土する。)
(下図はクリックすると大きくなります)
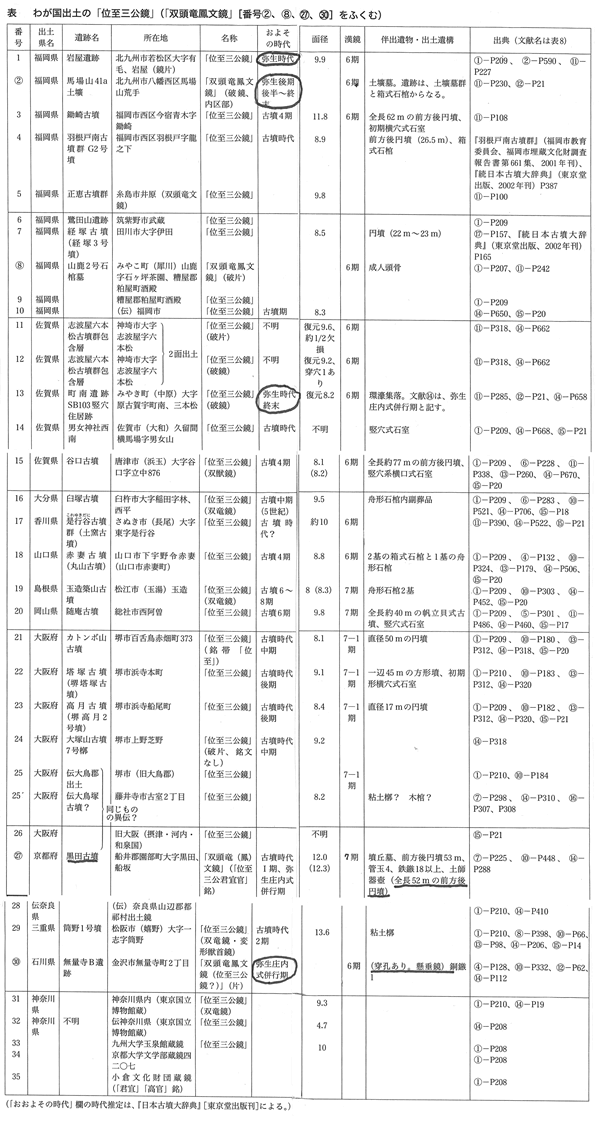
⑥「三角縁神獣鏡」は、確実に三世紀の遺跡から出土例がない。四世紀の遺跡からの出土例がある。
⑦倭国は、西晋王朝と、外交関係があった。『日本書紀』の「神功皇后紀」に引用されているところによれば、西晋の『起居注』(西晋の皇帝の言行などの記録)に、西暦266年に倭の女王が晋に使いをだしたことが記されている(この倭の女王は、卑弥呼のあとをついだ台与であろうといわれている)。『晋書』にも、この年、倭人が来て入貢したことが記されている。
倭の使いが、外交関係のあった西晋の国から鏡をもたらしたとすれば、その鏡のなかには、「位至三公鏡」がふくまれていた可能性が大きい。
「位至三公鏡」などのこのような傾向からみれば、西暦300年近くまで、中国と外交関係をもった倭は、九州に存在していたとみられる。

・西晋の都・洛陽と、北部九州との結びつき
中国では、三国時代に魏・呉・蜀となっていたが、魏の後に晋(しん)となる。
晋は西晋(265~316)と東晋(317~420)に分れる。河内温(かだいうん)[河南]の名族の司馬懿(い)[宣帝]は曹操以来魏に仕え、249年(嘉平元)丞相となり、以後その子 司馬師(景帝)、師の弟 司馬昭(文帝)と権勢を保持した。昭は蜀討滅の功によって晋王となり、封地は全国の3分の1をしめた。晋国の官属には有能の士が集り、さながら王朝内の王朝の観を呈した。やがて昭の子司馬炎(武帝)は魏の禅譲をうけて晋王朝をたて、280年(太康元)呉を併合して天下を統一した。
(下図はクリックすると大きくなります)
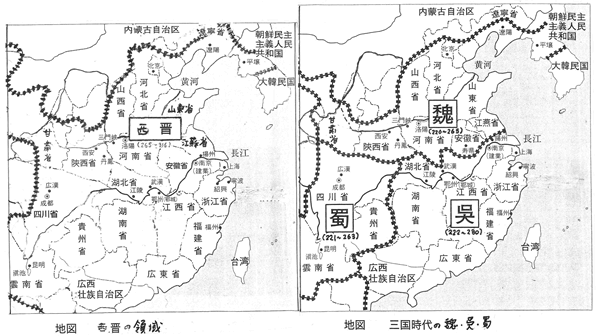
この280年、呉は西晋によって滅ぼされたことにより、呉に産地があった南の銅が西晋全体で使われるようになる。その結果「いわゆる西晋鏡」の銅原料は、長江(揚子江)流域系のものになる。
位至三公鏡は中国では洛陽を中心として出土し、日本では北九州を中心として出土する。
同じように、蝙蝠鈕座内行花文鏡も同じような傾向がある。
これを見ても、邪馬台国が北部九州にあったと考えられる。
(下図はクリックすると大きくなります)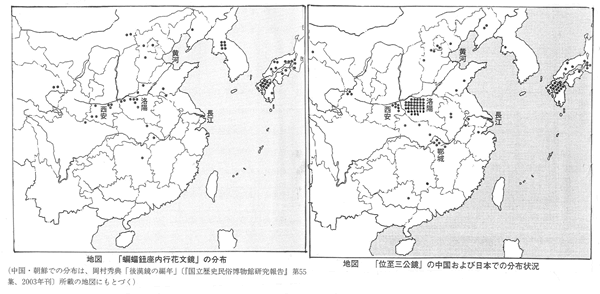
山西にいた南匈奴の族長劉淵は自立して漢を立て、その子劉聡は311年(永嘉5)洛陽を陥れて懐帝をを捕え(永嘉の乱)、ついで長安で即位した愍(びん)帝も316年劉曜とらえられ、ここに晋はいったん滅びた。これより先、帝室の一族・司馬睿(えい)[元帝]は安東将軍として建業(南京)[建康]に鎮していたが、乱を避けて南遷しできた王導など華北の名族や土着の豪族たちの支持をえて即位し、晋を再興した。これが東晋である。
画文帯神獣鏡は東晋時代の鏡で、東晋(317~420)時代の鄂州市付近と、日本の近畿地方(古墳時代)に多く出土する。つまり古墳時代の近畿地方は東晋との結びつきがあったと考えられる。420年は布留式土器の時代であり、邪馬台国時代ではない。
(下図はクリックすると大きくなります)
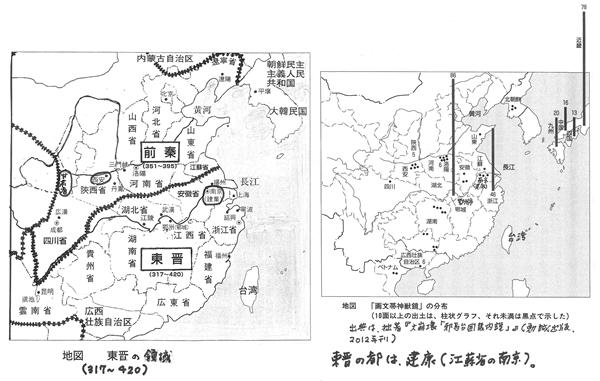
[邪馬台国北部九州存在説・二つの証明法]
①ベイズの統計学による確率計算
福岡県に邪馬台国があった確率は99.8%になる。下のベイズ統計学参照。
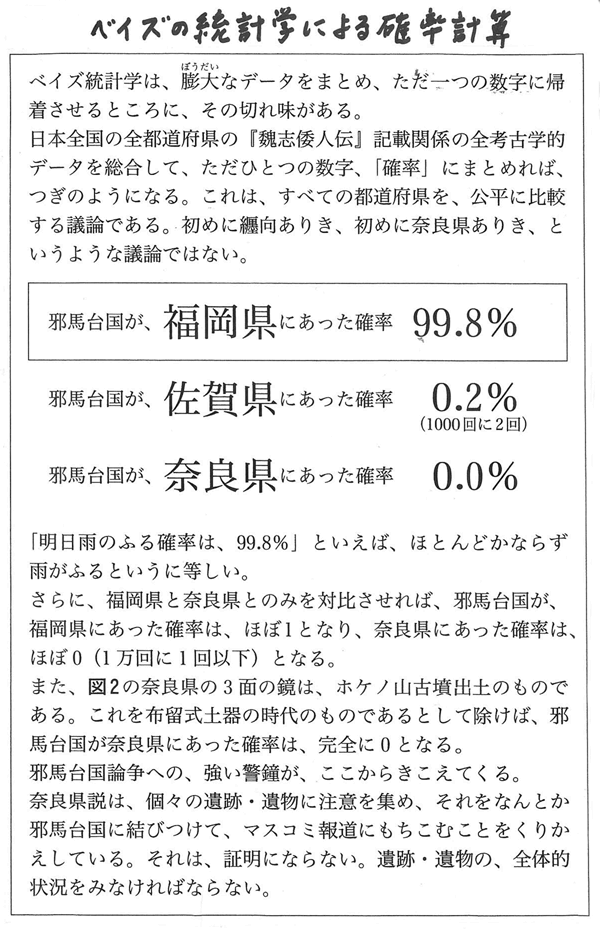
②中国と外交交渉をもった日本の政治勢力は、西晋時代まで北部九州に存在。
今までの説明で証明してきた通りである。
・古墳の年代と三角縁神獣鏡の出土
崇神天皇陵古墳は4世紀型であり、東晋の時代の古墳と考えられる。
画文帯神獣鏡の出土の古墳は4世紀型古墳が多い。
また三角縁神獣鏡と画文帯神獣鏡は同じ古墳から出土し、画文帯神獣鏡の単独より少し後になる。そして4世紀~5世紀型古墳となる。
(下図はクリックすると大きくなります)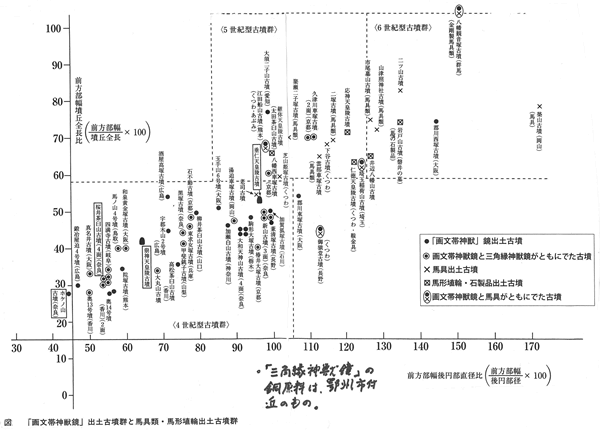
・「鏡の世界」と「銅鐸の世界」は「鏡の世界」に統一された
(下図はクリックすると大きくなります)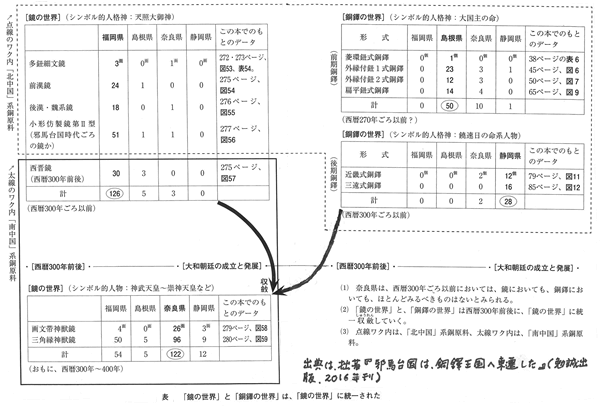
この表から、西晋の時代まで、日本の都は北九州にあったように見える。そして、東晋の時代、日本の都は奈良県にあったように見える。
近畿式銅鐸と三遠式銅鐸と同じ銅原料は広形銅矛と広形銅戈となる。この広形銅矛と広形銅戈(上図では示していない)は北九州に多く出土する青銅器である。
点線で囲まれているものは中国北方系の銅原料である。
西晋鏡はデザイン的には北方系であるが、銅原料は南方系である。これは280年に呉が滅亡して、揚子江流域の銅原料が西晋で流通したことによると考えられる。
東晋の時代となって、画文帯神獣鏡や三角縁神獣鏡はデザインも同原料も南方系となる。
■鏡の世界における「二大激変」の時期と、【連続性】【非連続性】
いままでのことをまとめると下記のようになる。
・280年ごろ
[中国]西暦280年に西晋の国(265~316)が、呉の国(220~280)を滅ぼした。西晋の都は北中国の洛陽。
[日本]庄内式土器の時代。
【連続性】わが国において、「第1次大激変」の前も後も、鏡は、福岡県を中心とする北部九州におもに分布する。
【非連続性(第1次大激変)】わが国において、鏡の銅原料として、北中国系のものが、用いられていたのが、南中国(華中・華南)の、長江(揚子江)流域系のもの、とくに、長江中流域の鄂州市付近の銅原料に変化する。「位至三公鏡」を中心とする「いわゆる西晋鏡」において。「いわゆる西晋鏡」は中国において、洛陽を中心に分布する。
(南中国の銅原料が、北中国に流れ込むようになる)
・320年ごろ~350年ごろ
[中国]西暦320年ごろ~350年の中国は、東晋(317~420)の時代であった。東晋の都は長江下流域の建康(南京)であった。
[日本]古墳時代(布留式土器)の時代がはじまる。
【連続性】鏡の銅原料は「第2次大激変」の前も後も、南中国(華中・華南)の、長江(揚子江)流域系のものが、用いられつづける。
【非連続性(第2次大激変)】わが国において、鏡の分布の中心が、それまで、福岡県を中心とする北部九州にあったものが、奈良県を中心とする近畿地方に、変化する。「画文帯神獣鏡」「三角縁神獣鏡」の分布など。「画文帯神獣鏡」は、中国において、鄂州市付近を中心に分布する。
これらから、西晋時代に邪馬台国が北九州にあったことを証明するものである。
■考古学は統計学によって判断すべき
ベイズ統計学の適用にあたっては、わが国において、ベイズ統計学における第一人者といってよい松原望氏[東京大学名誉教授、聖学院(せいがくいん)大学大学院教授]に、長時間の議論検討、ご指導におつきあいいただいた。
松原望氏は、次のように述べておられる。
統計学者が、『鉄の鏃』の各県別出土データを見ると、もう邪馬台国についての結論は出ています。畿内説を信じる人にとっては、『奈良県からも鉄の鏃が四個出ているじゃないか』と言いたい気持ちはわかります。しかし、そういう考え方は、科学的かつ客観的に データを分析する方法ではありません。私たちは、確率的な考え方で日常生活をしています。たとえば、雨が降る確率が『0.05%未満』なのに、長靴を履き、雨合羽を持って外出する人はいません」
「各県ごとに、弥生時代後期の遺跡から出土する『鏡』『鉄の鏃』『勾玉』『絹』の数を調べて、その出土する割合をかけあわせれば、県ごとに、邪馬台国が存在した可能性の確率を求めることが可能になります。その意味では、邪馬台国問題は、ベイズ統計学向きの問題なのです。」(以上、「邪馬台国を統計学で突き止めた」『文藝春秋』2013年11月号)
データサイエンスの骨格をなす統計学は、イギリスの統計学者、フィッシャー(Fisher.R.A)によって、1920年代に、いわゆる「推計学(推測統計学)」提唱され、大きな変革がもたらされた。それまでの統計学が、観察・記述の学であったものが、確率論にもとづいて、推計の方法を与える学となった。実際の問題を解決する学となった。
以後、統計学は、小標本の理論、ベイズの統計学、多変量解析論、深層学習、ビッグデータ論など、コンピュータの発達普及とともに、急速な進化発展をとげた。
各学問分野は、きそって、これらの方法をとりいれた。しかるに、考古学の分野で発言力をもつ一群の人々は、およそ、この百年間、このような動向にまったくといってよいほど、無関心で、このような方法をとりいれる学問的伝統が作られなかった。







