■『古事記』『日本書紀』の神名・人名と、『魏志倭人伝』の人名・官名
いま、天照大神(あまてらすおおみかみ)以下、神武天皇に至る神々の系図を示せば、下図のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
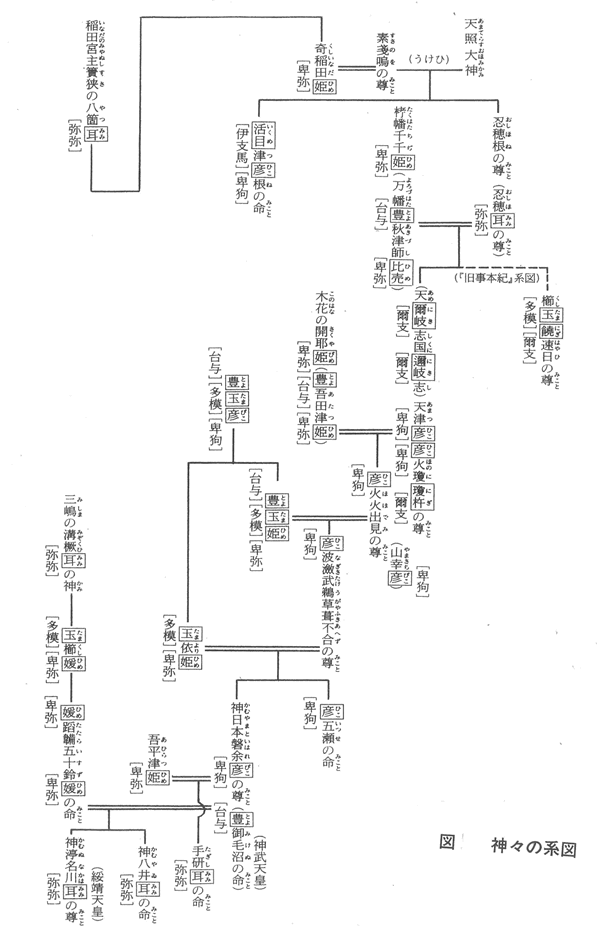
この系図をじっとにらんでみよう。
すると、『魏志倭人伝』にみえる「人名」や「官名」に結びつくように見える「神名」「人名」が、はなはだ多いことに気がつく。
『魏志倭人伝』は、卑弥呼のあとをつぐ宗女(一族の娘)の名を、「台与(とよ)」と記す。
系図をみると、「トヨ」という音のはいる女性の神名に、「万幡豊秋津師比売(よろづはたとよあきづしひめ)」「豊吾田津姫(とよあたつひめ)」「豊玉姫(とよたまひめ)」などがある。
とくに、「万幡豊秋津師比売(よろづはたとよあきづしひめ)」は、高御産巣日(たかみむすび)の神(かみ)の娘で、天孫降臨をする瓊瓊杵(ににぎ)の尊(みこと)[邇邇芸(ににぎ)の命(みこと)]の母である。
天照大御神を「卑弥呼」にあて、万幡豊秋津師比売を「台与」にあてれば、世代的には、あう。
年十三で、卑弥呼のあとをついで女王となった台与(万幡豊秋津師比売)が、のち、成人して忍穂耳(おしほみみ)の尊(みこと)と結婚して、瓊瓊杵(ににぎ)の尊(みこと)を生み、その瓊瓊杵の尊が、皇室の祖先になったと、考えれば、よいわけである。
『魏志倭人伝』に、倭の国の「官名」として、「弥(み)(甲)弥(み)(甲)」が記されている。
系図をみると、「ミ(甲)ミ(甲)」という音をふくむ神名として、「忍穂耳(おしほみみ)の尊(みこと)」「八箇耳(やつみみ)」「溝橛耳(みぞくひみみ)の神(かみ)」「手研耳(たぎしみみ)の命(みこと)」「神八井耳(かむやいみみ)の命(みこと)」「神渟名川耳(かむぬなかはみみ)の尊(みこと)」などがある。
『魏志倭人伝』は、また、倭の国の「官名」として、「爾支(にき)」を記す。
系図をみると、「ニキ」という音をふくむ神名として、「天爾岐志国邇岐志天津日高日子番能邇邇芸(あめにきしくににきしあまつひこひこほのににぎ)の命(みこと)」(『古事記』)、「天津彦彦火(あまつひこひこほ)の瓊瓊杵(ににぎ)の尊(みこと)」(『日本書紀』)、「櫛玉饒速日(くしたまにぎはやひ)の命(みこと)」がある。
さらに、『魏志倭人伝』は、倭の国の「官名」として、「多模」を記す。
「多模」の中国語上古音は、「tar-mag」であるから、「たま」と読める(これについて、くわしくは、藤堂明保編『学研漢和大辞典』、拙著『倭人語の解読』[勉誠出版刊]などを参照)。
系図をみると、「タマ」という音をふくむ神名として、「櫛玉饒速日(くしたまにぎはやひ)の命(みこと)」「豊玉彦(とよたまびこ)」などがある。
「弥弥(みみ)」「爾支(にき)」「多模(たま)」などは、原始的な「姓(かばね)」に近いものかと思われる。
■『古事記』の神話時代の神名・人名が、『魏志倭人伝』の人名・官名と、とくに、よく一致している
『古事記』にみえる「とよ」「みみ」「にき」「たま」を含む神名、人名について全数調査をすると、右下の表のようになる。 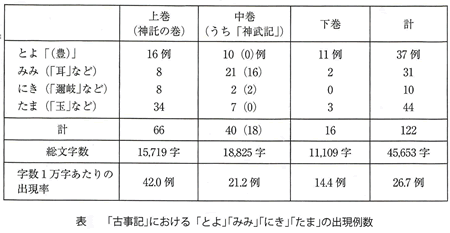
すなわち、「とよ」「みみ」「にき」「たま」を含む神名、人名は、『古事記』全体で、のべ122回あらわれる。
そのうち、過半の66回は、『古事記』上巻(神話の巻)にあらわれる。
また、中巻にあらわれる「とよ」「みみ」「にき」「たま」はのべ40回のうち、18回は、最初の、「神武記」にあらわれる。
したがって、「神武記」以前(上巻と「神武記」とを加えたもの)に、「とよ」「みみ」「にき」「たま」は、のべ、84回あらわれることになる。
じつに、「とよ」「みみ」「にき」「たま」の、三分の二以上、69パーセントは、「神武記」以前にあらわれる。
『古事記』の、上巻と中巻と下巻とでは、分量が異なる。
このことを考慮しても、結論はかわらない。いな、「とよ」「みみ」「にき」「たま」は、他の巻よりも、上巻に頻出するという傾向は、さらにはっきりとうかびあがってくる。
上の表には、各巻の総文字数も示しておいた。ここから、文字数一万字あたりの、「とよ」「みみ」「にき」「たま」の、出現率を計算する。
字数一万字あたりの出現率は、上巻で、42.0例、中巻で、21.2例、下巻で、14.4例である。上巻の出現率は、中巻の出現率の約二倍である。
そして、上巻から中巻へ、中巻から下巻へと、時代が下るにつれ、出現率は、減少してゆく。
以上をまとめれば、次のようになる。
(1)卑弥呼、邪馬台国の時代は、大略、『古事記』『日本書紀』の神話の時代にあたる。
(2)日本神話が語る「高天の原」は、北九州方面と考えられる。
(3)だから、『魏志倭人伝』中にあらわれる人名、官名などは、他の時代よりも、神話時代の神名、人名とより、よく一致することとなるのである。
1956年に『魏志倭人伝』の現代語訳を出した島谷良吉(しまやりょうきち)[1899~1980。高千穂商科大学教授などであった]は、その『国訳魏志倭人伝』の「前がき」の中で述べている。
「陳寿編纂『魏志巻三十』所載の東夷の一たる『倭人』の記述を見ると、まったく記紀神代の巻の謎を解くかのように思える。」
金子武雄氏の「邪馬台国東遷説」
金子武雄氏(1906~1983)は、上代文学の専門家で、東京大学の教授をされた方である。
金子武雄氏は、その著『古事記神話の構成』(桜楓社、1963年刊)のなかで、結論的に、およそ、つぎのようにのべる。
「『古事記』神話の資材となっている個別神話は、国家経営の神話が出雲地方で生育したものであるほかは、日向三代の神話はもとより、高天の原の闘争・国家譲渡の交渉・天孫降臨など、ほとんど大部分の史話が、筑紫(九州)特に北九州の地において生育したものである。」
「『古事記』の伝を虚心に見るならば、この神話を生んだ地は淡路島や近畿ではなく、はるかに西のほうにあったと考えられる。それは、筑紫であろう。」
「国譲りの神話の舞台は高天の原と出雲とであるが、出雲方の人々の立場からではなく、高天の原方の人々の立場で語られていることは明らかである。しかし高天の原方の立場に立つ人々というのは、近畿の人々なのか、それとも筑紫の人々なのか。『古事記』では、武御雷(たけみかづち)の神とこれに添えられた天(あめ)の鳥船(とりふね)の神とが、「出雲(いづも)の国の伊奈佐(いなさ)の小浜(をばま)に降(くだ)り到(いた)りて、十掬剣(とつかつるぎ)を抜きて、逆(さかさま)に浪の穂に刺し立て、その剣の前(さき)に趺(あぐ)み坐(ま)して」、とあり、その上で大国主神と談判したとある。「降(くだ)り到(いた)り」とあるから高天原から降ったという意である。しかし、本来そうだったのか。高天の原から降るというのなら、なぜ、わざわざ岸近くの海に降ったのか。おそらくは海路から出雲に行ったという事実が反映しているのであろう。「天(あめ)の鳥船(とりふね)の神」は船そのものか、あるいは船の操縦者か区別しがたいが、とにかくこの神が添えられたということがそれを思わせる。そして「天降った」というのは、高天の原との関係によって神話化せられたものと考えることができる。この出雲との国譲りの交渉の神話は、おそらくなんらかの史実を基盤としていると思われる。建御雷の神が船に乗って出雲の海岸に着いていることが、この神話の基盤になっている史実を反映しているものとすれば、その史実は、当然、近畿と出雲との間の交渉ではなくて、筑紫と出雲との交渉であったとみなければならない。近畿から出雲へは船で行くはずはないからである。こうしてこの国家譲渡の交渉の神話もまた、筑紫で生育したものであることを思わせる。」 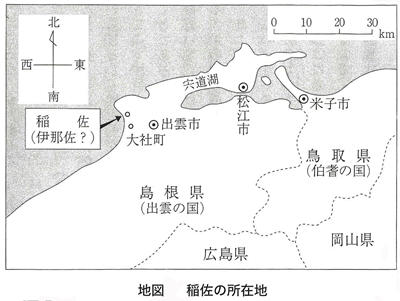
「やや比喩的に言えば、高天の原はほかならぬ筑紫の上にあったのである。……いわゆる高天の原系神話も、いわゆる筑紫系神話と同じく筑紫の地に生育したものと思われる。」
「さらにまた、弥生時代の中期から末期にかけてさかんに用いられたものに、銅鐸・銅剣・銅鉾がある。その分布の状態は、かなり明確に二つに分かれているという。すなわち、大体、近畿・山陰・北陸、および四国の東部が銅鐸文化圏であり、九州および瀬戸内海沿岸が銅剣銅鉾文化圏である。しかもこの二つの文化圏の対立は次の古墳文化の成立とともに消滅している。
考古学の教える以上のような諸事実は、『古事記』の若干の神話の暗示するところを根拠として想定したところと大方合致する。このことは、これらの神話が多分に史実に立脚していることを思わせる。そして、筑紫の中心勢が近畿へ移動したとしたら、それは弥生時代の末期ごろではないかと推定される。これから言えば、『魏志倭人伝』に見える邪馬台国は北九州にあったものということになる。『大和(やまと)』というのも、この『邪馬台』と呼ばれた中心勢力の名であり、近畿へ移動した時にもこの名を負って行き、やがてその地の名ともなり、また、この勢力によって成立した国家の名ともなったのであろう。」
「大和朝廷の人々は、どうして国史の最初の位置に筑紫や出雲に生育した神話を据え置くことになったのか。それは、このような位置に据えることのできるほどの神話を大和朝廷の人々は持っていなかったためであろう。それでは、大和朝廷の人々は、近畿の地で生育した独自の神話あるいは伝説を持っていなかったのか。私は『古事記』の中巻以下に見られる神話や伝説がこの人々の持っていたものであると思う。中巻のはじめには、神倭伊波礼毘古の命の東征のことが語られているが、大和朝廷の人々は、遠い昔、自分らの祖先が筑紫からはるばるとやって来たという伝承を持っていたのである。だから、自分らのこういう伝承の前に、筑紫で生育した神話を据えることには、ほとんど抵抗を感じなかったことであろう。『古事記』が神倭伊波礼毘古の命の日向の高千穂宮からの出発を境として、上巻と中巻とを分けたのも、主としてこういう事情によるものと思われる。」
「そして、上巻と中巻との連結には、『古事記』の編者が苦心したらしい跡が見られる。連結の役割をしているのは、直接には日向三代の神話と神倭伊波礼毘古の命の東征の神話とである。日向三代の神話は、それより前の諸神話にくらべて著しく体裁を異にしており、中巻以下の歴朝体とほとんど同じものになっている。もちろん内容も形式もよく整っていないところもあるがおそらく中巻以下の体裁にならって構成したものであろう。それは邇邇芸(ににぎ)の命を第一代の天皇とみることも可能であるような記述の仕方になっている。邇邇芸(ににぎ)命と木花(このはな)の佐久夜毘売(さくやびめ)との婚姻の条には、『故(かれ)、ここをもちて今に到るまで、天皇命等(すめらみことたち)の御命(みいのち)長くまさざるなり。』というような語句も用いられているのである。」
金子武雄氏の考察は、『古事記』神話を、要素にわけて分析し、その結果を総合するという科学的な方法の上にたっている。
畿内の大和朝廷の役人によって編集された『古事記』の神話の資材のほとんどが、北九州で生育したものであるという。この事実は、神話が、大和朝廷の役人によって「作られた」とする戦後の「作為説」の立場からは、説明できない。『古事記』神話は、古い時代の史実を伝えているとみるべきである。
皇学館大学の学長であった古代史家の、田中卓(たかし)も、記す。「皇室は、もともと北九州に発祥せられた。紀・記神代巻の高天原とはこれを指す。」[田中卓著作集2『日本国家の成立と諸氏族』(1986年、吉川弘文館刊)]
■どこを発掘するべきか 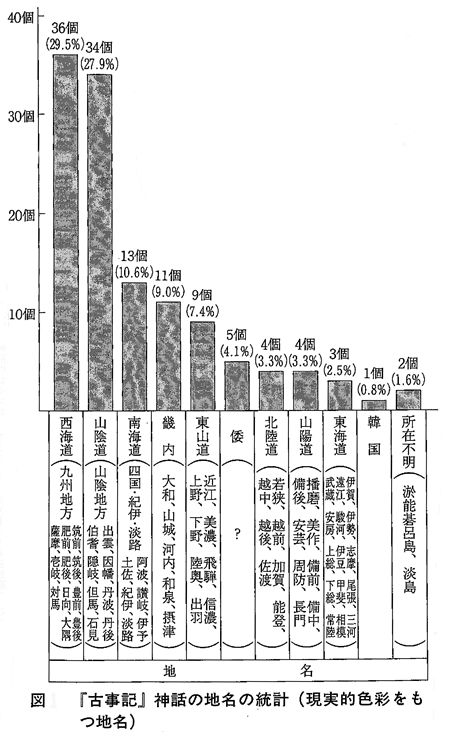
『古事記』神話のなかには、「竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(おど)の阿波岐男(あわぎはら)」など、現実的な色彩をもつ地名が、122個ほどあらわれる。そのうちの70個(57パーセント)ほどは、「九州地方(西海道)」と、「山陰地方(山陰道)」との地名である。
『古事記』神話は、端的にいえば、天照大御神を中心とする「高天の原」勢力と、大国主(おおくにぬし)の神(かみ)を中心とする「出雲」勢力との争いという形で展開する。「出雲の国譲り」の話が、主要なモチーフとなっている。
吉野ヶ里遺跡の発掘で著名な考古学者、高島忠平氏は、「吉野ヶ里史跡指定30年記念シンポジウム」において、つぎのように述べている。
「高島:吉野ヶ里遺跡が、現在発見されている集落の跡、弥生時代の集落としては、最も卑弥呼の都した所に、今のところ近い。
ところが、まだほかの遺跡が、特に九州の場合には、まだまだ発掘がされてない広大な面積を持つ遺跡がある。私は、吉野ヶ里遺跡は全体として300ヘクタールと見ておりますけれども、朝倉市の平塚川添遺跡を含める小田台地というのがありますけれども、それは約400ヘクタール。それから、奴国の中心と言われている比恵・那珂・須久遺跡は一本の道路でつなかっておりますが、この面積は800ヘクタール以上あるのです。
あるいは、三雲遺跡群は、今見るところ100ヘクタールくらいですが、ほかの関連した遺跡を含めると、もっと広大なものになる。そういうことから考えると、吉野ヶ里を掘っただけで、ここが邪馬台国だというふうにはなかなかまいらない。まだ、ほかにもこうした遺跡が、私は筑紫平野にあるのではないかと考えておりますので、もっともっと掘りましょうということであります。」(『季刊邪馬台国』138号、2020年177ページ)
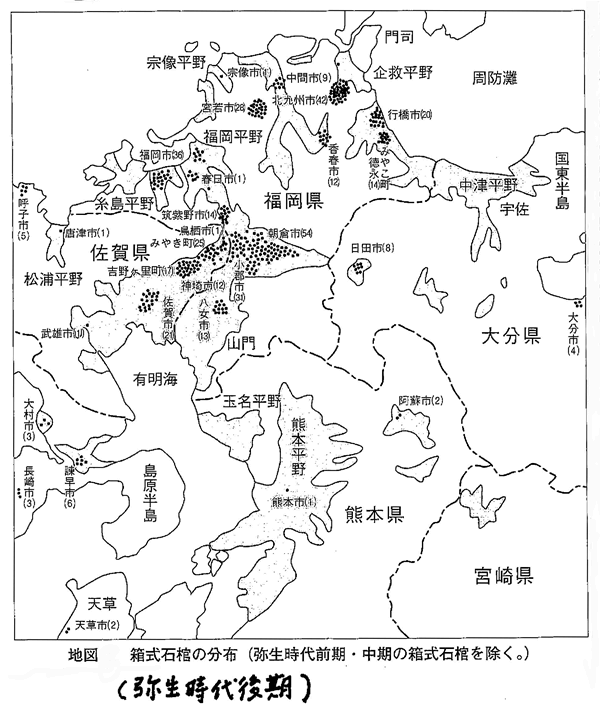
■大和にも、北九州にもある香山(かぐやま)
日本神話にあらわれる地名の「香山(かぐやま)」をとりあげよう。
日本神話に「香山」の名がしばしばあらわれることが、「高天の原=大和説」の、ひとつの根拠となっていた。
さて、古くは、大和の天の香山は、天にある香山がくだってきたものであると考えられていた。
鎌倉時化中期にできた『日本書紀』の注釈書、『釈日本紀』は、『伊予風土記』を引用して、つぎのようにのべている。
「伊予(いよ)の国の風土記に曰(い)はく、伊予(いよ)の郡。郡家(こほりのみやけ)[郡役所]より東北のかたに天山(あめやま)あり。天山(あめやま)と名づくる由(ゆえ)は、倭(やまと)に天香具山(あめのかぐやま)あり。天(あめ)より天降(あも)りし時、二つに分れて、片端(かたはし)は倭(やまと)の国に天降(あまくだ)り、片端(かたはし)は此(こ)の土(くに)に天降(あまくだ)りき。因(よ)りて天山(あめやま)と謂(い)ふ。本(このもと)なり。」
すなわち、「天の香具山は、天から天(あま)くだるときに、二つにわかれて、ひとつは大和に、ひとつは伊予に天降った。大和にくだったものが、大和の天の香具山であり、伊予にくだったものが、天山である。」という意味内容である(久松濳一校註の日本古典全書『風土記下』〔朝日新聞社刊〕には、これに近い内容の逸文が大和の国風土記逸文「香山」、阿波の国風土記逸文「アメノモト山」の条にみえている)。
『万葉集』巻三にも、鴨君足人(かものきみたりひと)の「天降(あも)りつく 天の芳来山(かぐやま)[天からくだりついた天の香具山]……」(二五七)という歌がのせられている。同じく巻三には、「天降(あも)りつく 神の香山……」(二六〇)という歌もみえる。
ここで、「天」を、「高天の原」であると考えてみよう。すると、大和にある天の香山は、「高天の原」すなわち、九州にある香山の東にうつった姿であることになる。そして、九州から大和への政治勢力の移動にともない、地名が移った可能性があらわれてくる。
では、北九州に、天の香山にあたるような山があるであろうか。もしあれば、『古事記』神話に五回あらわれる天の香山は、畿内の香山ではなく、北九州の香山をさしている可能性がでてくる。
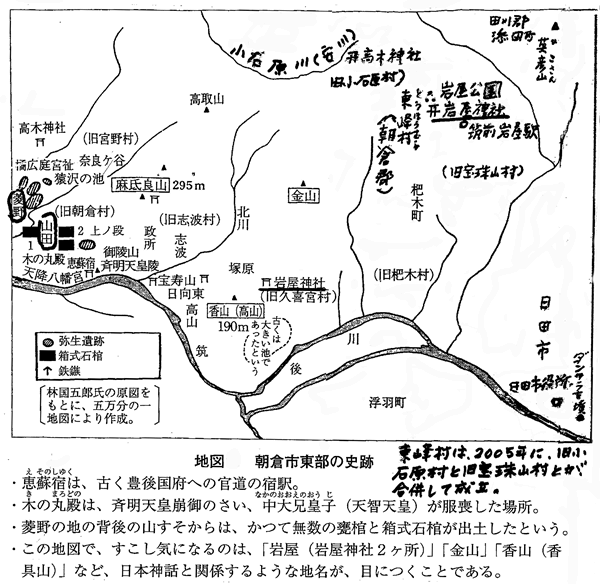
私は、以前、『邪馬台国への道』(筑摩書房、1967年刊)という本のなかで、北九州に「香山」という山は、ないらしい、と書いた。ところが、その後、福岡県朝倉郡旧志波村(現在は、朝倉市のなかで、大分県の日田市よりの地)出身で、当時、福岡県の小郡市(おごうりし)[朝倉市の西]に住む林国五郎氏から、朝倉市ふきんの地名などを、詳細に検討されたお手紙をいただいた。その中で、林国五郎氏はのべられる。
「志波村に香山という山はございます。現在は高山(こうやま)と書いていますが、少年の頃、昔は香山と書いていたのだと、古老からよく耳にいたしました。」
私はこの手紙を読んだとき、あっと思った。『万葉集』では、天の香山のことを、「高山」と記しているからである。
たとえば、かの有名な、「香山(かぐやま)は 畝火雄(うねびを)雄(を)しと 耳梨(みみなし)と 相(あひ)あらそひき 神代より斯(か)くにあるらし……」(巻一、十三)の原文は、「高山波 雲根火雄男志等 耳梨与 相諍競伎 神代従如此余有良之……」で、「高山」と記しているのである。
『古事記』『日本書紀』は、「かぐやま」を、「香具山」とは記さず、「香山」と記している。私は、「高山」の存在を、地図の上で知っていながら、それを「たかやま」と読んでいたため、「香山」との関係に気がつかなかった。「高山」を「こうやま」とよむのは、重箱よみであるから、これは、あて字と考えられる。
藤堂明保編『学研漢和大字典』(学習研究社刊)によれば「高」の上古音は、「kɔg」であった。『万葉集』が、「高」を、「カグ」の音にあてているのは、十分理由がある。
そして、さらに、江戸時代前期の元禄十六(1703)年に成立した貝原益軸(篤信、1630~1714)の『筑前国続風土記(ちくぜんのくにぞくふどき)』にあたってしらべてみると、たしかに、「志波村の香山」と記されている。
香山は、夜須町や甘木市の東南にある。戦国時代に、香山に、秋月氏の出城があった。天正九年(1581)のころ、秋月種実が、大友氏との戦いにおいて、八千余人で「香山」に陣取ったことなどが、『筑前国続風土記』に記されている。香山には、現在、「香山城址」の碑が立っている。
林氏は、高山(香山)の比較的近くに、金山という山もあることを指摘されている[『古事記』神話に、「天の金山(かなやま)の鉄(まがね)を取りて」という記事がある。なお、高山の近くには多多連(たたら)という地名があるのも、おそらくは、製鉄と関係しているのであろう]。
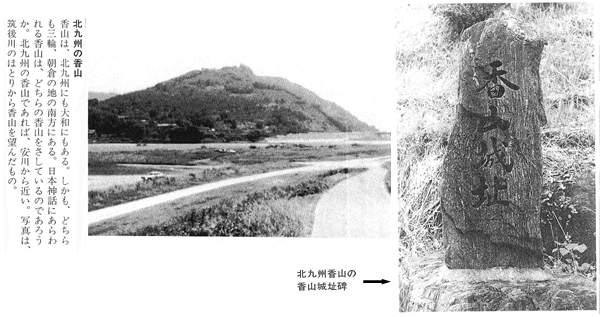
また、『伊予風土記』は、天から山が降(くだ)ったとき、伊予にくだった片端が天山(あめやま)であると記しているが、夜須町の比較的近くには、「天山」という山もある。伊予の天山も、夜須町の近くの天山も、比較的小さな孤立丘である。
『古事記』神話にあらわれる畿内の十一例の地名のうち、六例までは、昔の話ではなく、『古事記』撰録当時存在していた神社について記したものである。そして、神々の行動をいくらかともなっているようにみえる残りの五例は、すべて「天の香山(かぐやま)」という地名である。神々は、天の香山から、鹿や、波波迦(ははか)[朱桜(かにわさくら)]や、常磐木(ときわぎ)や、ひかげのかずらや、ささの葉をとってきている。この「香山」は、九州に存在し、おそらくは祭事などで重要な位置を占めたものであり、大和の香山は、北九州勢力の大和への進出とともに、名前が移されたものであろう。このように考えれば、『古事記』神話には、古くからの伝えと考えられる畿内の地名は一例もないことになってしまう。
さらに、『筑前国続風土記』によれば、北九州の香山(高山)のある旧志波村のふきんは、ふるくは、「遠市(とおち)の里」とよばれていた。いっぽう、畿内の天の香山は、『延喜式』に十市郡にあると記されていることからわかるように、ふるくは、「十市(とをち)郡」(「とをち」の読みは、『延喜式』による)に属していた。ただ『和名抄』の訓(よ)みは、「止保知(とほち)」(東急本)。角川書店刊の『古代地名大辞典』の、奈良県橿原市の「十市県(とおいちのあがた)」の項に、「トオチ・トウイチ・トヲチなどと訓まれ、遠市、藤市とも書かれた」とある。
『和名抄』にみえる「美濃国本巣遠市郷」が、藤原宮出土の木簡では、「三野国本須郡十市・・・」となっている例がある。
北九州の香山と大和の天の香山とは、その相対的位置からいっても、「遠市」「十市」に存在したことなどからも、たがいに対応しているということができよう[宮崎県西臼杵(うすき)郡の天の香山(かぐやま)は、後世の命名と思われる]。
なお、福岡県朝倉郡の「香山」の頂上には、現在、地元の実業家によって、観音様がたてられている。
これらの図をみれば、北九州の香山の所在が、畿内の天の香山の所在と、ほぼ同じく、三輪、朝倉の南方にあることに気がつくであろう。
■地名の拡散
わが国の地名学の樹立に大きな貢献をした鏡味完二(かがみかんじ)は、その著『日本の地名』(1964年、角川書店刊)のなかで、およそつぎのようなことを指摘している。
「九州と近畿とのあいだで、地名の名づけかたが、じつによく一致している。
すなわち、下の表のような、十一組の似た地名をとりだすことができる。そしてこれらの地名は、いずれも、
(1)ヤマトを中心としている。
(2)海のほうへ、怡土(いと)→志摩(しま)[九州]、伊勢(いせ)→志摩(近畿)となっている。
この場合、九州では志摩郡と郡レベルだが、近畿では志摩国と国レベルになっている。
元になっている地名の規模は小さいが、移った地名の方が大きくなる傾向がある。
(3)山のほうへ、耳納(みのう)→日田(ひた)→熊(くま)[九州]、美濃(みの)→飛騨(ひだ)→熊野(くまの)[近畿]となっている。
これらの対の地名は、位置や地形までがだいたい一致している。
これは、たんに民族の親近どいうこと以上に、九州から近畿への、大きな集団の移住があったことを思わせる。」」 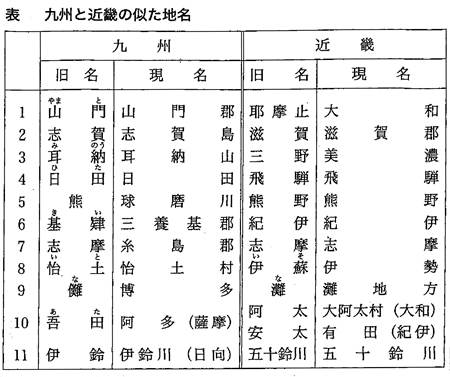
ここで、鏡味完二氏は、九州の「日田(ひた)」と、近畿の「飛騨(ひだ)」(現在の岐阜県の北部で、正確には、近畿地方ではなく、中部地方)とを対応させる。そして、九州の「耳納(みのう)」の地名を、近畿の「美濃(みの)」(岐阜県南部)と対応させる。そして、岐阜県の本巣郡の地に、「遠市郷(とおちごう)」の地名がある。また、「飛騨」には、合掌造りの民家で有名な「高山(たかやま)」の地がある。
この「高山(たかやま)」は、九州の「香具山」をさす「香山」「高山」と関係があるのであろうか。
九州から、地名が、拡散して行っているようにもみえるが、あてはめた漢字によって、地名の呼びかたが変わる例がある。
墨江(すみのえ)→住吉(すみのえ)→住吉(すみよし)
この場合「江」を「吉」という漢字にしたが、その後、この「吉」の漢字により、「え」が「よし」に変わった。
同じように、「香山(こうやま)」が、「高山(こうやま)」に変わり、更に「高山(たかやま)」に変わったとも考えられる。
■北九州の安川と岩屋
北九州のまん中に、今も「安川」が流れている。そして、「安川」の近くに、「香山」という山もある。
また、北九州の「安川」の近くから、大環濠集落遺跡・平塚川添遺跡も出現している。
この地域は、遺跡と人口の密集地域である。ここは、「高天の原」の故地ではないか。
高天の原は、北九州にあると考えられる。では、天照大御神が直接住んでいたのは、北九州のどこであろうか。
それを定めるために、『古事記』上巻に記されている高天の原の環境を整理してみよう。するとつぎのようになる。
(1)高天の原には、「天(あめ)の安(やす)の河(かわ)」が流れている。その河原に、多くの神々が集まって、会議をひらくことができた。すなわち、「天の安の河」は小さな河ではない。
(2)田があり、田には畔(あぜ)があり、溝(みぞ)がひかれていた。天照大御神が、その田の新穀を召しあがる祭殿[大嘗(おおにへ)を聞こしめす殿]もあった。
(3)高天の原には、天の安の河の河上に、「天の岩屋(いわや)」があった。また天の安の河上から、堅(かた)い石[堅石(かたしわ)]や、鉄[天の金山(かなやま)の鉄(まがね)]をとってくることができた。さらに、「天の石位(いわくら)[高天の原なる岩石の御座]」ということばもあらわれる。すなわち、おもに天の安の河の河上には、岩石のある山があった。
(4)天照大御神時代の高天の原の記述には、海はあらわれない。このことは、高天の原が内陸に位置していたことを思わせる。
さて、私たちは、これらの条件をみたす場所を九州に求めることができるであろうか。
ここで注目されるのは、「高天の原」には、「天(あめ)の安(やす)の河」という河があった、とされていることである。『古事記』によれば、天照大御神とその弟の須佐(すさ)の男(お)の命(みこと)とは、天の安の河を中に置いて、うけい(誓約)を行なっている。神々は、天の安の河の河原で、会議をひらいている。天の安の河の河上に天(あめ)の岩屋(いわや)があった。
ヨーロッパの地名研究を行なって、先史時代の民族の分布を明らかにしたドイツのファスマーはのべている。
「古代住民についてなにもわかっていない地方では、地名研究は水名(水に関係する地名)からはじめるのが方法として正しいと思う。経験からみて、居住地名より意味がはるかに単純なので、水名は解釈しやすいからである。その上、水名は変わりにくく、住民が変わっても水名は変わらないことが多い。」
たとえば、アメリカのばあい、ニューヨーク(イギリスにヨークという都市がある)、ニューハンプシャー州(ハンプシャーは、イギリス南部の地名)、ニュージャージー州(イギリス王室属領に、ジャージー島がある)など、イギリスからもって行った地名がある。
いっぽう、ミシシッピ川の「ミシシッピ」は、アメリカインディアンの言語で、「偉大な川」の意味、コネチカット州の「コネチカット」は、アメリカインディアン語で、「長い川」の意味である。ミシガン州の「ミシガン」は、アメリカインディアン語の、「大きな湖」を意味する語のなまったものである。
水に関する地名は、原住民の語を、比較的よく残している。
北海道の地名の稚内(わっかない)・幌内(ほろない)などの「ない」は、アイヌ語で、「川」の意味であるという。北海道の言語がアイヌ語から日本語に変っても、川の名は、もとのまま残っている。
では、九州に「ヤス」とよばれる河、または、河のほとりの地名で「ヤス」とよばれるところがあるであろうか。
地図をひらいてみよう。たしかに、北九州のほぼ中央部に、「夜須」という地名がある(下の地図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)
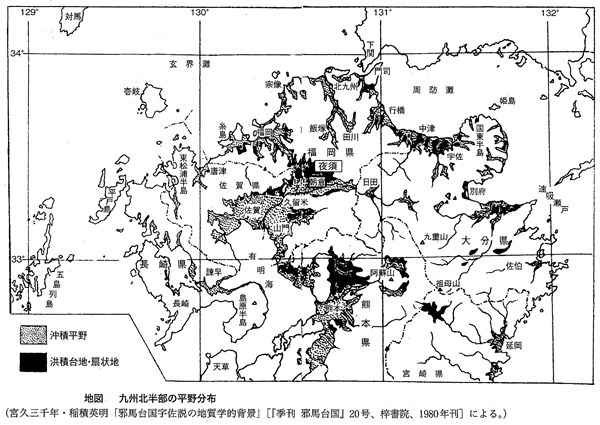
福岡県朝倉郡に夜須町(やすまち)とよばれる町があった[夜須町は、2005年に、三輪町と合併して、筑前町(ちくぜんまち)となった]。現在の、福岡県朝倉市の近くである。
「夜須町」の「夜須」は『日本書紀』の「神功皇后紀」に、「安」と記されている。『万葉集』に「安野(やすのの)」としてでてくる「安」も、「夜須町」の地をさす。また、『延喜式』にも、筑前の国夜須郡としてみえているから、かなり古くからの地名であることはたしかである。夜須町の「夜須」は、古くは一般に「安」と書かれ、おそらくは、元明朝の和銅六年(712)の「郡郷の名(地名)は、今後、好ましい漢字二字で表記せよ。」のいわゆる『風土記』撰進の勅以後、「夜須」と書かれるようになったのであろう。朝倉市を流れる筑後川の支流、小石原川は、夜須川とも呼ばれる。
明治・大正時代の大地名学者、吉田東伍は、その著『大日本地名辞書』(冨山房刊)のなかで、つぎのようにのべている(原文は文語文)。
「小石原 今小石原村という。秋月の東四里(16キロ)、両豊(豊前、豊後)の州界(くにざかい)に接近し、夜須川の渡りである。この川を一名小石原川という。秋月に至り、南方に折れ、甘木(現在の朝倉市の地)を過ぎ、ついに筑後川に入る。長さ九里(36キロ)。」
「続風土記にいう。夜須川(一名小石原川。これは吉田東伍の註)は、夏月蛍が多い。楢原(ならばる)の林中に薬師堂がある。東光院と言う。長谷山には昔千手観音堂があって、和州(大和)の長谷になぞらえたが。天正十五年(1587)、秋月家が本郷(朝倉郡)を去り、日州(日向の国)におもむいたとき、その仏像をも、たずさえていったということである。」
「夫婦石 秋月と弥長(いやなが)村との間の夜須河辺にある。大石二つが、あい対している。夏月このあたりは、蛍が多い。」
「弥永(いやなが)のあたりで、夜須川から水苔(みずごけ)俗名川茸(かわたけ)をとって、食料につくる。寿泉苔(じゅせんごけ)、また秋月苔といって、本郷(朝倉郡)の名産とす。」(以上、下線は安本)
明治初期に、福岡県が編集した『福岡県地理全誌』でも「夜須川」と記されている。
なお、昭和二十九年(1954)に、朝倉郡の二町(甘木・秋月)、八村[安川(やすかわ)・上秋月・立石(たていし)・三奈木(みなぎ)・金川(かながわ)・蜷城(ひなしろ)・福田(ふくだ)・馬田(また)]が合併し、市政をしき、甘木市となるまで、安川村があった。「安川村」の名は、「夜須川」に由来する。2006年に、甘木市は、朝倉町・杷木町と合併し、朝倉市となった。
『明治二十二年(1889)町村合併調書』(『福岡県資料第二輯』)には、つぎのようにある。「安川(小石原)という村名は、人々の希望するところで、合併村の中央を流れ、村内過半その川を引き、用水とする。よって安川村と改称する。」
これでみると、「夜須川」はまた、「安川」とも書かれたことがわかる。
■「八咫の鏡=鉄鏡説」の検討
『古事記』をよく読むと、奇妙な記事がある。
天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、弟の須佐(すさ)の男(お)の命(みこと)の乱暴に怒って、天(あま)の石屋(いわや)にかくれる。
そこで、八百万(やおよろず)の神は、天の安の河の河上の天(あめ)の堅石(かたいし)[鉄を鍛える金敷(かなしき)の石か]を取り、天(あめ)の金山(かなやま)の鉄を取って、鍛人(かぬち)[鍛冶(かじ)職、鍛人(かぬち)は、金打(かなうち)の省略]の天津麻羅(あまつまら)をたずね求め、伊斯許理度売(いしこりどめ)の命(みこと)に命じて、鏡を作らせた。
この話によれば、このときに作られた鏡は、鉄の鏡であったことになる。
それでよいのであろうか。
皇学館大学教授の国文学者・西宮一民(にしみやかずたみ)氏校注の『古事記』(新潮社刊、新潮古典集成)では、
(1)「天(あめ)の堅石(かたしわ)」を、「高天(たかあま)の原(はら)の堅い石。鉄を鍛える金敷(かなしき)の石」とする。
(2)「天(あめ)の金山(かなやま)」を、「高天の原の鉱山。砂鉄を含む山であった」とする。
(3)「鍛人天津麻羅(かぬちあまつまら)」を、「鍛冶職(かじしょく)。『鍛人(かぬち)』は、『金打(かなうち)』の約」とする。
(4)「伊斯許理度売(いしこりどめ)の命(みこと)」を、「鏡作連(かがみつくりのむらじ)らの祖神」とする。
また、青木和夫氏他校注の『古事記』(岩波書店刊、日本思想大系1)では、「伊斯許理度売(いしこりどめ)の命(みこと)」について、「補注」で、つぎのように説明している。
「コリは固まるの意、ドメは老女・石の鋳型に溶かした鉄を流し固まらせて鏡を作る老女をあらわす。」
■「天の金山の鉄」という表現は、あるいは妥当?
さて、ここで、『古事記』に、「天(あめ)の金山(かなやま)の鉄(くろがね)」とあるものが、文献の編纂される時代とともに、つぎのように変化している。
「天(あめ)の金山(かなやま)の鉄(くろがね)」(712年成立の『古事記』)
「天(あま)の香山(かぐやま)の金(かね)」(720年成立の『日本書紀』の一書)
「天(あめ)の香山(かぐやま)の銅(あかがね)」(807年成立の『古語拾遺』)
「天(あま)の金山(かなやま)の銅(あかがね)」(830年ごろ成立かとみられる『先代旧事本紀』)
「天(あま)の香山(かぐやま)の銅(あかがね)」(830年ごろ成立かとみられる『先代旧事本紀』)
『古事記』では、鏡を作った状況を、次のように記している。
「天(あめ)の安(やす)の河原(かわら)の河上の、天(あめ)の堅石(かたしわ)を取り、天(あめ)の金山(かなやま)の鉄をとって、鍛人(かぬち)[金打(かねうち)をする人]天津麻羅(あまつまら)をさがしだし、伊斯許理度売(いしこりどめ)の命(みこと)に命じて鏡をつくらせた。」
この文によるとき、金床(かなどこ)[堅石]の上でトンテンカン、トンテンカンと鉄をきたえて鏡を作ったよかに読みとれる。
日本刀などを見ればわかるように、鉄は、よく磨けば、人の顔などがはっきりとうつる。『古事記』では、「天の金山の鉄」を取って鏡を作ったとあるが、『日本書紀』の編纂者は、「鉄」で鏡を作ったとするのは、穏当でないと考えたのであろう。「鉄」を、一般的な「金(かね)」にあらためている。
さらに、『古語拾遺』の編纂者の斎部(いんべ)の広成(ひろなり)は、鏡は、銅で作るものと考えて、「銅」にあらためたのであろう。
しかし、「天の金山の鉄」という『古事記』の表記が、妥当なのではないかと思われる、つぎのような根拠もあげることができる。
(1)『古事記』の神話は、おぼろげな形であるが、弥生時代のことを伝えているようにみえる。
銅のなかにふくまれる鉛の同位体比の研究によれば、弥生時代から古墳時代にかけての銅は、原材料が、すべて、中国産とみられる。「天の香山」や「天の金山」で、国産の銅がとれたとは思えない。[もっとも、早稲田大学の日本史家・水野祐は、「〔この所伝は、〕銅鉱を採掘して、精錬して銅をつくったのではなく、山地に銅剣や銅鐸のような銅器を埋めておいて、鏡などの必要な銅器を製作しなければならないときに、その銅器を掘りだして、鋳直し、使用した事実を反映しているとみればよい。」(学生社刊『勾玉』)とする。]
(2)卑弥呼が交渉をもった魏の国で、鉄の鏡が作られていたことは、中国の考古学者、徐苹芳氏が、つぎのように述べているとおりである。
「漢代以来、中国の主な銅鉱は、すべて南方の長江流域にあった。三国時代に南北が分裂して、魏の領域内の銅材が不足したことで、銅鏡鋳造業は少なからぬ影響を受けた。こうして魏の銅鏡鋳造業が不振となると、鉄鏡の製造が興ってきた。多くの出土例から見ると、鉄鏡の出現は後漢(ごかん)の後期からであり、後漢末から曹魏の時代にかけて盛んに製造されたが、その地域は北方に限られる。この鉄鏡はすべて菱鳳鏡(きほうきょう)であり、時には金銀で紋様が象嵌され、まことに華麗なものもあった。『太平御覧』が引く『魏武帝〔曹操〕の雑物を上(たてまつ)る疎(そ)[疎は、一条ずつにわけて意見をのべた上奏文]』には、曹操が後漢の献帝に捧げた物品の中に金銀で象嵌された鉄鏡が見える。西晋期にも鉄鏡が引き続き盛んにつくられており、洛陽の西晋墓から出土する鏡のうちで鉄鏡は位至三公鏡と内行花文鏡に次いで第三番目に位置している。北京市の順義、遼寧省の瀋陽、甘粛省の嘉峪関(かよくかん)の魏晋墓からも、すべて副葬された鉄鏡が出土する。魏晋時代の北方の地で、銅材の欠乏によって鉄鏡が盛行することは、注目しておいてよい事実である。」(三国両晋南北朝時代の銅鏡)王仲殊著『三角縁神獣鏡』学生社刊、所収)
この文のなかにみえる「雑物を上(たてまつ)る疎(そ)」(『曹操集訳注』による)に、つぎのようにある。
「皇帝の御物に、一尺二寸(約29センチ)ある金錯(さく)[めっき]鉄鏡一枚、皇后の雑物に純銀錯の七寸(約17センチ)の鉄鏡四枚、皇太子の雑物に純銀錯の七寸の鉄鏡四枚、貴人、公主にいたる九寸(約21.7センチ)の鉄鏡四〇枚(御物有尺二寸金錯鉄鏡一枚、皇后雑物用純銀錯七寸鉄鏡四枚、皇太子雑物純銀錯七寸鉄鏡四枚、貴人至公主九寸鉄鏡四十枚)。」
明治から昭和時代前期の考古学者・高橋健自(たかはしけんじ)が、その著『鏡と剣と玉』(富山房、1911年刊)のなかの、「八咫鏡考」で、「鉄鏡は隋時代以後」にはじめてみえる、としているのは、誤りである。 
(3)そして、事実、魏代に近いころに作られたものかとみられる鉄製の菱鳳鏡(きほうきょう)[直径21.2センチ]が、岐阜県高山市国府(こくふ)の名張一之宮神社古墳(七世紀ごろの築造)から出土している。
また、大分県日田(ひた)市日向町ダンワラ古墳から、金銀錯嵌珠竜文鉄鏡(きんぎんさくがんしゅりゅうもんきょう)(直径21.3センチ)が出土している。(右図参照)
この二つは、直径が、ほとんど一致している。魏の九寸鏡または、それを模したものである可能性がある。九寸鏡は、さきの文にあるように、貴人に与えられるものとすれば、卑弥呼に与えられたものとしてもおかしくはない。大分県日田市出土のものは、中国で出土例をみない紋様のようにみえるので、わが国で作られた可能性もある。そして、日田市の隣の福岡県朝倉市杷木(はき)に、香山や金山、岩屋神社という地名がある。また、これも日田市の隣の福岡県朝倉郡東峰村宝珠山(とうほうむらほうしゅやま)に岩屋神社、岩屋公園などがある。これらは、いずれも、日田市役所から、20キロ以内の地である。







