なぜ、不正と誤りとが、くりかえされるのか
古代史、とくに考古学の分野では、似たような大きな失敗が多すぎる。
個々の目の前のものの細部にとらわれ、全体の構図のおかしさなどに気がつかない。
権威のある人や、空気にしたがうから、みんなでだまされる。というパターンになる。
指摘するのは、外部の人である。(部分で精密、全体で、大きな誤り)
①梅原末治の勾玉(まがたま)事件
②清野謙次の窃盗事件
③永仁の壺事件
④旧石器捏造事件
⑤『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』事件
⑥洛陽の三角縁神獣鏡事件
■梅原末治の勾玉事件
梅原末治は、大正から昭和時代にかけての大考古学者であった。
梅原末治は、多くの発掘出土品の精密な記録を残した人であった。
その梅原末治ですら、梅原末治が伝橿原市出土、大和鳥屋千塚(とりやせんづか)[橿原市]出土などのように記して、古代の勾玉として紹介したものの八割以上が、現代技法によって作られたものであるとして、ガラス工芸の専門家の由水常雄(よしみずつねお)氏から、徹底的な批判をあびたことがある(『芸術新潮』1972年1月号、『週刊新潮』1972年1月23日号、由水常雄著『火の贈り物』[せりか書房、1977年刊])。鉛ガラスでなく、ソーダガラスであること、ビール瓶を溶かして作られた独特の色をしているもののあることなどが指摘されている。 
梅原末治(うめはらすえじ)は、東洋考古学の基礎を確立した人であった。梅原末治は、身体虚弱であったため、上級学校に進学せず、京都帝大考古学教室に出入りし、無給の雇いから出発し、京都帝大の教授となり、八十九歳で没した。
梅原末治の業績と研究方法とについては、医学者で東洋考古学者の穴沢和光(あなざわわこう)氏(会津若松市の穴沢病院院長)が、「梅原末治論-モノを究めようとした考古学者の偉大と悲惨-」(『考古学京都学派』[角田文衞(つのだぶんえい)編、雄山閣出版、1997年刊所収])という文章の中で、以下のように述べている(引用文中の一部に傍線を引いたのは安本)
「梅原が殆(ほとん)どフリーハンドに近い天才的画技でさっと書き上げた図面を、同じ遺物について後で厳密な方法で測った図面と比較したところ、殆(ほとん)ど相違がみつからなかったという驚くべき話が伝わっている。」
「梅原の著書の多くは印刷の優秀、図版の鮮明、図面の精密さで知られ、内容的にも重要で貴重な資料が多く、ほとんど豪華美術書にみまがうばかりで、きわめて質の高い出版と評価され、その多くが基本的な資料集や文献として今日なおその価値を保っている。」
「このようにして、梅原に訓練されて考古遺物の優秀な観察、記録の能力を身につけた学生が全国各地に散って、遺物を中心とした事実記載の精細さを誇る日本考古学の大伝統が形成されていったのである。」
「こうして梅原の研究戦略を検討し、彼の学問を評価すると、梅原は『コツコツと遺物自体を徹底的に調べ上げ』ることにかけては万人の及ばぬ努力家で、(整理・観察・事実記載の)天才的な才能を発揮したが、『それを結び合わせて研究を進めて行く』ことはどうも苦手であったようだ。」
「林[中国考古学者で、京大教授などであった林巳奈夫(みなお)]は、梅原という学者は『切手、蝶などと同様な(考古資料の)収集家マニアという色眼鏡で色々と思い起こしてみると説明がつく』と述べた。このきわめて辛辣なコメントの『収集……』という言葉の次に『および記載』という一語を挿入すれば、梅原の学問の本質そのものを最も適確に表現した言葉になるだろう。つまり、厳格経験主義に徹した記述の学者だった梅原にとっては、データ(資料)がすべてであった。彼の学問とはデータをどこからか仕入れてきて発表する以外にはタネもシカケもなく、それ以外に特別な方法も方向もなかったのだ。」
「『モノを一つ一つ丹念に観察し、実測し、写真や拓本をとり、その形態や装飾をアタマにたたきこむだけではダメなのであって、青銅器は成分の鉛同位体比を測り、鉄器はX線検査、土器は胎土分析、石器は使用痕の研究、木器は年輪年代の測定、動植物遺存体は専門家の鑑定、遺跡の土は土壌分析と花粉分析を行い、その結果を総合しなければ本当のことはわからない』といった時代になった。資料の激増によって、梅原のやったように自分の頭脳をデータベース化していたのでは追いつかなくなり、碩学(せきがく)の頭脳と資料のファイルに代わってコンピューターが登場し、『考古資料に関する情報ネットワークの開発によって、学会共通のデータベースには夥(おびただ)しい資料が登録され、そこから引き出される情報がただちに研究資料となる』という情報革命の時代が必ず到来するであろう。そういう時代に、考古学の最新課題となるのは、いろいろの情報をいかに総合して過去を復原するかという考古資料の解釈理論であり、『考古学は報告書や図録を出版するだけが能じゃない』といわれるようになるだろう。こういう時代になって、日本考古学が梅原のやったように『資料の語ることがおのずから結論となる』という厳格経験主義に拘泥し続けるならば、国際学界からは『事実を積み上げるばかりで、その説明を試みない』と『峻烈な非難を浴びせられる』であろう。」
2019年に、比較的若くしてなくなった考古学者、細谷葵(ほそやあおい)(1967~2019。女性。お茶の水女子大学特任准教授など)は、報告書「理論なき考古学-日本考古学を理解するために」の中で、日本考古学の「理論の欠如」を指摘して、「(日本の考古学で、)提示されているものは、説明も議論も伴わないバラバラのデータの山積み」と述べている。(この細谷葵の報告書は、最初、イギリスで発表された。
現在は、インターネットで、日本文の形で容易に見ることができる。)
--------------------------------------------------------------------------
メモ1
[目録作成主義の問題点]
1960~1970年代にかけて、アメリカの考古学者、ルイス・ビンフォード(Lewis Roberts Binford 1931~2011)は、「新考古学(ニュー・アーケオロジー new archaeology)」をといた。
ビンフォードはいう。
「従来の考古学は、資料を提供するだけで、科学的な学問とはいいがたい。考古学者は、埋蔵品の目録を作成するよりも、埋蔵品をもとに、古代文化を明らかにすることに、力をそそぐべきである。(植木武ら訳『過去を探求する』雄山閣、2021年)
どこから、何が出土したかを、正確・詳細に記述し、目録を作成して行けば、おのずから過去が復元できる、ということにはならない。
---------------------------------------------------------------------------
■京大教授、清野謙次(きよのけんじ)の光と影
梅原末治よりも、八歳年下で、やはり、京都帝国大学の教授であり、大正時代から昭和時代に活躍した清野謙次(1885~1955)の光と影との対比は、梅原末治よりも、さらに強烈である。
清野謙次は、病理学者で、生体染色の研究で、帝国学士院賞をうけている。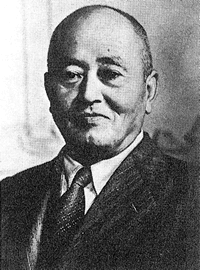
考古学・人類学の分野での業績としては、岩波書店から、上巻・下巻二冊で刊行された『日本考古学・人類学史』(上巻1954年刊、下巻1955年刊)がある。
総ページ数1500ページにあまる。分厚(ぶあつ)い本である。文字通りの大著である。
この本では、たとえば天皇陵については、幕末~明治時代の国学者森善臣(もりよしおみ)の著書『諸陵徴』『諸陵考』などの記事内容が、かなりくわしく紹介されている。
森善臣の著書はみることが、なかなかむずかしい。
また、江戸時代などに出土した鏡や銅鐸などの図も、かなり収められている。
清野謙次は京大文学部考古学の教授も担当した。
清野謙次が起こした「事件」については、穴沢和光氏が、次のように、要領よくまとめている。
「清野は少年時代から考古学や人類学に強い興味を示し、医学研究のかたわら所々の研究施設や社寺に出入りして研究を行った。ところが彼には生来病的な収集癖があり、それが昂じてついにはいろいろなところからモノを勝手に持ち出して自宅に収集するようになった。1937年(昭和12)のある日、清野が研究目的で出入りしていた京都高雄の神護寺(じんごじ)では寺宝の大般若経の巻物が少しずつ紛失していくことに気づき、清野の行動に不審を抱いて、高雄山麓の駅に警官を待機させ、寺から帰る途上の清野を待ち受けて尋問し、彼の鞄の中身を調べたところ、はたして寺から勝手に持ち出した経巻が発見された。これがきっかけとなって、清野宅の家宅捜索が行われ、清野が複数の社寺や大学から遺物や美術品などを無断で持ち出して秘匿していたことが露見し、窃盗罪で逮捕される始末になった。これは京大としては前代未聞の大スキャンダルであり、結局は清野は辛うじて実刑を免れたが、地位も栄誉もすべてを返上して大学を去り、生涯の後半は在野の一研究者として日蔭の生活を送るはめになった。」(角田文衛編『考古学京都学派』259ページ)
梅原末治と清野謙次との事例をみると、いくつかの共通点があることに気がつく。
(1)二人とも、きわめて高い能力をもち、すぐれた研究業績を残していること。
(2)二人とも、強烈な収集癖、収集欲をもっていること。コレクトマニア。
(3)目の前にあるものに、強い関心・興味をもち、心を奪われる。全体的状況が、見えなくなる。
★世界は極端なものによって進化し、平凡なものによって維持される。
参考:人名辞典より
清野謙次(きよのけんじ)[1885~1955]
人類学者、病理学者。岡山市に生まれ、1909年京都帝国大学を卒業。 12年ドイツに渡り、フライブルク大学のアショフ教授に師事した。 21~38年まで京大医学部微生物および病理学教授。生体染色学を創始、ヒスティオサイトhistiocyte(組織班、一種の食細胞)を発見、その命名者でもある。22年生体染色で学士院賞を受けた。19年ころから日本全国にわたる貝塚発掘を行い、集めた人骨は1,500体以上におよび、日本石器時代人種論を確立した。著書に《古代人骨の研究に基づく日本人種論》《日本考古学人類学史》《生体染色の総説総論》その他、医学、人類学、民族学、考古学にわたる約20冊がある。
参考:事件の資料
『科学朝日』1987年6月号「科学をめぐる事件ノート6 京大教授の寺宝窃盗事件」
■永仁の壺事件
1957年に、「永仁の壺事件」が起きている。
「永仁の壺」は、愛知県志段味村(しだみむら)[現、名古屋市守山区]の「出土品」として紹介された。考古学の専門誌の『考古学雑誌』の1943年7月号にも紹介された。
「永仁の壺」は鎌倉時代の「永仁二年」(1294)に作られた古瀬戸の傑作として、重要文化財にもなった。
(下図はクリックすると大きくなります)
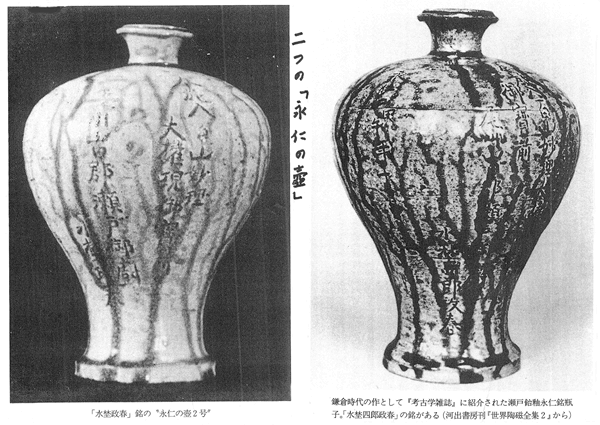
(下図はクリックすると大きくなります)

しかし、これは、結局、重要無形文化財(人間国宝)であった加藤唐九郎(とうくろう)のおこした贋作事件であったことで落着する。
加藤唐九郎は、みずからが編集し、1954年に刊行された『陶器辞典』(志摩晝房刊)の口絵に、鎌倉時代の作品として、自作の「永仁の壺」をカラー写真で紹介し、解説している。あつかましいことである。
「永仁の壺」では、エックス線蛍光分析の結果、釉薬(ゆうやく)[うわぐすり。素焼(すやき)の陶磁器の表面にかける。ガラス質のつやがでる]にふくまれる元素の比率が、鎌倉時代のものと異なっていた。また、位相差顕微鏡による調査では、「永仁の壺」の表面には、数百年まえの作品に見られるはずの経年変化が、みとめられなかった。
この壺の、重要文化財への指定には、陶芸家・美術史家の、小山富士夫(こやまふじお)の強力な推薦があった。小山富士夫は、文部技官で、文化財専門審議会委員であった。当時、陶磁研究の第一人者とされていた。
小山富士夫は、加藤唐九郎の技に心酔する。ひたすら唐九郎を信じこむ。
その結果、検証が、お留守になる。
小山富士夫は、この事件の責任をとって、公職を辞任することとなる。
松井覚進(まついかくしん)著『永仁の壺』(朝日新聞社刊)によれば、小山富士夫が、壺を最近に買った鳥取県米子市の深田雄一郎へ送った手紙のなかに、つぎのようにある。「私だけでなくこの二十年間、唐九郎君に日本の陶界がだまされていたわけですが、佐藤(進三)君などもいゝものと信じ、私もいろいろ手のこんだトリックで、村長(長谷川佳隆)が出土地を案内するし、唐九郎君に窯跡を案内され、いゝものとばかり思っていました。」
このばあいも、専門家であるはずの小山富士夫は、加藤唐九郎にあい、永仁の壺の実物を見ながら、だまされているのである。
じつは、「永仁の壺」なるものは、「水埜(みずの)政春」銘のものと、「水埜(みずの)四郎政春」銘のものと、二つ存在する。ともに、高価で売買されているのである。人の欲しがるものがでてきている。
『論語』に、「徳は孤(こ)ならず、かならず隣(となり)あり。」ということばがある。「徳のある人には、かならず、それによりそう人があらわれる。」という意味である。
それにならっていえば、「捏造品は孤ならず(一つだけではない)、かならず隣(となり)あり(複数存在する)。」といえそうである。
めったに出現しないはずのものが、ある特定の人と関係して、複数出現する。
また、「永仁の壺」1号は、1943年に、志段味(しだみ)村から、道路改修工事のさい出土したとされながら、その前年の1942年に、志段味村の長谷川佳隆が、加藤唐九郎から買い取ったものという。また、1943年には、道路改修工事はなかったという。
松井覚進氏の『永仁の壺』によれば、「永仁の壺を含む一連の”松留窯”つまり唐九郎窯の作品は、1937年から二、三年の間に四窯焼いている。」という。
つまり、出現の年と場所が、はっきりしない。旧石器捏造事件、『東日流外三郡誌』事件、「永仁の壺」事件、STAP(スタップ)細胞事件、そして、あとでのべる「王趁意氏提出鏡」事件には、「構造」上、多くの類似点がみられる。
■旧石器捏造事件
(下図はクリックすると大きくなります)

東京大学名誉教授の医学者、黒木登志夫氏は、その著『研究不正』(中公新書、中央公論新社、2016年)で、12年に発覚した、ある麻酔科医のおこした一連の論文捏造事件について、次のように記す。
「学会とジャーナルは積極的に自浄能力を発揮した。特に、日本麻酔科学会の報告書は、今後のお手本になるだろう。」
そして、旧石器捏造事件については、次のように記す。
「日本考古学協会は、検証委員会を立ち上げたが、ねつ造を指摘した竹岡(俊樹)と角張(かくばり)[淳一(じゅんいち)」は検証委員会に呼ばれなかった。ねつ造発見の10日前に発行された岡村道雄の『縄文の生活誌』は、激しい批判にさらされ回収された。しかし、岡村は、責任をとることなく、奈良文化財研究所を経て2008年退官した。」
「SF(藤村新一)のねつ造を許したのは、学界の長老と官僚の権威であった。その権威のもとに、相互批判もなく、閉鎖的で透明性に欠けたコミュニティが形成された。」
この黒木登志夫氏の文中にでてくる竹岡俊樹氏は、かねてから、旧石器が捏造物であることを、告発していた。『毎日新聞』のスクープ記事が出るまえからである。しかし、考古学界の大勢は、それを無視しつづけていた。
竹岡氏は、事件発覚後、述べている。
「私がさらに情けないと思うのは、発覚の後の対応である。自らの行ってきた学問に対する反省はまったく行われなかった。藤村というアマチュアや、文化庁(岡村)に責任を押し付け、その上、批判する者を排除しつづけた。検証は名誉職が好きな『権威者』たちによるパフォーマンスにすぎず、生産的なことは何もおこなわれなかった。」
「この十数年間待っていたが何も変わらなかった。」(『考古学崩壊』勉誠出版、2014年)
会社の不正を告発した社員を、会社が圧迫しつづけているのと同じような印象をうける。旧石器捏造事件は、現在も、日本考古学の世界のある種の体質がどのようなものであるかについての「情報」を、世間に発信しつづけることになった。
それは、すなわち、次のような「情報(シグナル)」である。
「この考古学の世界では、エスタブリッシュメント(既成の権威、制度、組織)の、『組織の論理』のほうが、『科学や学問の論理』よりも強いのですよ。
まず守られなければならないのは、組織や伝統です。科学や学問的に真実と思われることを優先するのは、この世界の中で、組織人として生きて行く上で、政治的にも経済的にも、不利になることがありますよ。」
旧石器捏造事件のさい、『ネイチャー』誌は、「捏造された出土物は、批判の欠如をさし示す(Fake finds reveal critical deficiency)」という文章をのせ、「井の中の蛙(かわず)大海を知らず」という『荘子』にもとづく日本のことわざの英訳 ”a frog in a well that is unaware of the ocean”を引用して、この事件を痛烈に批判している(Cyranoski,D.,Nature,Vol.408 2000年11月号)。
そこには、次のような文章がみえる。
「この(旧石器捏造事件の)話は、藤村新一が捏造作業をつづけるのを許した科学文化についての疑問をひきおこした。」
「日本では、人々を直接批判することは、むずかしい。なぜなら、批判は、個人攻撃とうけとられるからである。」
「直観が、ときおり、事実をこえて評価される。」
考古学の分野では、エスタブリッシュメントが存在し、そこでは、「組織人としての論理」のほうが、「科学者、学者としての論理」よりも強い。
考古学の世界の組織や文化が、大きな問題をもっていることを示している。
学問や科学の世界では、疑問のある見解に対しては、論理や証拠によって反論すべきである。組織の中で不利益をもたらしますよ、というシグナルを送って、口を封じようとすべきではない。
方法も空気も、前々世紀的なものがあるようである。
これでは、組織は守られても、学問は守られない。科学は守られない。
このような文化になれてしまうと、非合理を非合理と思えなくなってしまう。
徳川家康が言ったという「不自由を、常と思えば不足なし」ということばがあるが「非合理も、常に習えば、慣(な)れてくる」状況になる。正しいように思えてくる。慣れてしまえば、不合理な行動をとっていることも、わからなくなる。
失敗から学ばなければ、同じような事件が、くりかえされることとなる。
そして、それを、国立の大学の先生や、教育委員会などの研究者が行なえば、税金の無駄づかいとなる。
同志社大学の教授であった森浩一(1928~2013)は、述べている。
「ぼくはこれからも本当の学問は町人学者が生みだすだろうとみている。官僚学者からは本当の学問は生まれそうもない。」
「今日の政府がかかえる借金は、国立の研究所などに所属するすごい数の官僚学者の経費も原因となっているだろう。」以上、『季刊邪馬台国』102号、梓書院、2009年)
「僕の理想では、学問研究は民間(町)人にまかせておけばよい。国家が各種の研究所などを作って、税金で雇った大勢の人を集めておくことは無駄である。そういう所に勤めていると、つい権威におぼれ、研究がおろそかになる。」(『森浩一の考古交友録』[朝日新聞出版、2013年])
これは率直にして、かつ、きわめて深刻な意見である。森浩一は、見聞きした経験にもとづく本音を述べている。
文科省の岡村道雄氏は、日本の旧石器の年代は、古くさかのぼりうるはずだという自説を、かねてからもっていた(岡村道雄著『日本旧石器時代史』[雄山閣出版、1990年刊]など参照)。捏造者の藤村新一氏は、その岡村氏の自説にあうような形で、捏造物をだしていった。そのために、検証が甘くなる。岡村氏は、コロッと、だまされてしまう。
岡村道雄氏は、記している。
「1980年4月、座散乱木(ざさらぎ)の切り通しの前に、藤村新一氏や私たちは横一線に並び、地層断面を一生懸命に削った。私の移植ゴテにも石器が当たった『カチッ』という手ごたえがあった。まちがいなく卒業論文以来、長年夢にまで見た『旧人』の石器だ。日本にも四万年前にさかのぼる中期旧石器時代に、確実に人類が生活していたのだ。その瞬間、あまりの感激に、体の中を電気が走り、あたりが暗くなるような眩暈(めまい)を私は覚えた。」(岡村道雄著『縄文の生活誌』[講談社、2000年刊])
捏造物は、ドンピシヤリ、岡村道雄氏の期待のものに合う。そのため、岡村氏の、「体(からだ)の中を電気が走り」ということになるのである。
何十年かにわたる旧石器の研究も、藤村新一氏を、目の前で見ていることも、真贋の弁別のためのなんの役にもたたない。
考古学は、共同で仕事をされることが多いためか、人がらの良い人が多いようにみえる(だます人が悪いので、だまされる自分は悪くない)。そのためか、なにか事件がおきても、「素朴に人をしんじることは、本来よいことである。」「たまたま捏造する人がいるだけだ。」と考える方が多いようである。
しかし、安倍元首相襲撃事件での犯人の母親などの例のように、本来は、だまされて信じた被害者が、いつのまにか、社会に大きな被害を与える加害者になってしまう。
信じやすい、人がらがよいだけではすまないことになってしまう。とくに、公的な立場にある人は責任を生ずる。
オウム真理教のばあいでも、信者には、人がらのよい人、多かったという話を聞く。
ストップ詐欺被害、ストップ詐欺被害者!!
■『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』事件
『東日流外三郡誌』という偽書がある。この偽書のばあいも、「旧石器捏造事件」のばあいと、話は、ほとんど同じである。
古代史研究家の古田武彦は、かねがね、『魏志倭人伝』に記されている女王国の名は、「邪馬台国」ではなく、「邪馬壹國(やまいちこく)」というのが正しい、という自説をもっていた。
現在、『東日流外三郡誌』などの一連の「和田家文書」は、古物商をしていた和田喜八郎(1927年~1999)の捏造した偽書であるみられている。
青森県教育委員会から出された『十三湊(とさみなと)遺跡』(第1分冊、2005年刊)などにも、つぎのように記されている。
「『東日流外三郡誌』については、捏造された偽書であるという評価が既(すで)に定着している。」
1988年の10月に、古田武彦は、和田喜八郎とあう。
古田武彦は、その著書『真実の東北王朝』[駸々堂(しんしんどう)、1990年刊]のなかで記す。
「藤本光幸さんのお宅に、和田喜八郎さんは幾多の文書を運んできて下さった。モーニング姿は、きりりときまっていた。
『磐井王は築紫(ママ)の邪馬壹之系なり』
この一節を見たときの、わたしの驚き。わたしの『九州王朝』のテーマが、ここにすでに語られている。
これは、孝季の『自作文』ではなく、神社所蔵文書などからの『写し』だったようだけれど、知己を見た思いだった。少なくとも、三~六世紀を一貫する間の『九州王朝』論の真髄が、ズバリ語られていたのである。」
話のすじは、こうである。
古文書捏造家の和田喜八郎は、あらかじめ、古田武彦の著書を読んでいるのである。そして、古田武彦の「邪馬壹國」説も知っているのである。
出色の詐欺師は、かなりなていど、勉強家である。それなりの研究をしている。和田喜八郎は、古田武彦とはじめて会ったとき、「邪馬壹」という語のはいっているさる神社所蔵の文書なるものをさしだす。
古田武彦は、それをみて、ここに、自説を支持する、新証拠があらわれたと思う。そして、「『九州王朝』論の真髄が、ズバリ語られていた」と「驚き」、「知己を見た思い」になっているのである、「知己」のはずだよ。和田喜八郎は、古田武彦の本を読んで、神社所蔵文書なるものを作成しているのだもの。和田喜八郎の「ねらい」は、「きりり」ときまる。
古田武彦は、和田喜八郎提供の「虚偽」の文書を信じこんでしまう。
そして、『真実の東北王朝』という本を書く。
一度このような本を書けば、もうあとには、引けない。
岡村道雄氏も、古田武彦も、ともに、感激性の人なのであろう。話が、とてもよく似ている。感激は、伝染しやすいから、そのような人たちの書く本に、引きこまれる人たちも、またでてくる。
古田武彦は、安本から、『東日流外三郡誌』の矛盾をつかれる。
いわく。厖大な『東日流外三郡誌』が、和田喜八郎のところだけから出現するのは、不自然である。
いわく。古文書のはずの『東日流外三郡誌』の筆跡が、古文書の発見者で提出者であるはずの和田喜八郎じしんの筆跡と一致するのは、不自然である。(これらについては、拙著『虚妄の東北王朝-歴史を贋造する人たち-』[毎日新聞社、1994年刊]など参照)。
追いつめられた古田武彦は、驚愕すべき行動にでる。二〇〇万円を払って、みずから、古文書の捏造にのりだすのである。
これは、学生のカンニングなどをとりしまる大学教授のすることであろうか。
(これについては、『季刊邪馬台国』55号[1994年刊]などにくわしい。)
このような話は、ふつうの結婚詐欺などと、構造が、基本的に同じである。
結婚をしたいと思っている女性がいるとする。練達の結婚詐欺師は、女性の結婚をしたいという潜在的願望にたくみによりそう。それにあうように話をもって行く。まったくのつくり話でよいのであるから、自分は、某航空会社のパイロットであるとか医師であるとか、弁護士であるとか、いくらでも、よい条件をそろえることができる。
下記は、古田武彦教授の『古代文偽造スキャンダル」を報じた「アサヒ芸能」』
(下図はクリックすると大きくなります)
『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』は、現代人の、和田喜八郎(1927~1999)という人が製作した厖大な偽書である。
たとえば、インターネットのフリー百科事典の『ウィキペディア(Wikipedia)』で、「和田喜八郎」を引くと、つぎのような、なかなか要領のよい説明かのっている。
《和田喜八郎(1927年~1999年9月14日)は日本の古物商である。『東日流外三郡誌』や『東日流六郡誌』などの和田家文書の自称「発見者」であるが、近年は「制作者」との評価が定着している。
その経歴は、自ら語ることによれば、1927年生まれで1944年陸軍中野学校に入学、その後海軍に転籍したという。(安本注。この経歴には、反証が示されている。)
1949年に、炭焼き窯を造成中に偶然、仏像、仏具、古文書を発見。同年、金光上人に関わる仏像、護摩器、経筒などを発見。
1948年自宅の改装中に天井裏から大量の古文書が落ちてきたという。これが『東日流外三郡誌』を始めとする「和田家文書」であった。その「原本」は、1789年から1822年までの34年間にわたり、陸奥国三春城主の義理の子にあたる秋田孝季と和田喜八郎の先祖である和田吉次の二人が日本全国をめぐって収集し編纂したものであり、これを1870年から1910年の期間に、全巻を和田家の子孫である和田末吉(喜八郎の曾祖父)が写本したとされる。その「写本」は600巻以上にもおよぶ膨大な資料であった。
1975年から1977年にかけて『市浦村史』(資料編上巻東日流外三郡誌)として刊行された。その後、古田武彦(元昭和薬科大学教授)が真書と主張したが、安本美典(元産業能率大学教授)などは偽書であると主張し、大々的な論争となった。
1979年より1983年まで青森県警友会の会員(和田本人は元皇宮護衛官だったと自称したが、宮内庁はこれを否定し、また1969年に和田を無銭飲食の容疑で逮捕したことのある青森県警の元警察官が異議を唱えたことで偽称が発覚し、退会処分となった)。
1999年9月14日、肝心の『東日流外三郡誌』の「原本」の発表を拒んだまま死去。死後、和田家はくまなく調査されたが原本は発見できず、むしろ紙を古紙であるかのように見せかけるために使われる薬剤(尿を長期間保管したもの)が発見され、これにより『東日流外三郡誌』が偽書である事は、ほぼ疑いの無いものとなった(『東日流外三郡誌』をはじめとする「和田家文書」の現存分は現在竹田侑子が管理)。》
青森県教育委員会から出された『十三湊(とさみなと)遺跡』(第1分冊)という報告書がある(2005年3月刊)。青森県埋蔵文化財報告書、第398号として、出されたものである。
この報告書の、「第Ⅱ章 遺跡の環境」「第4節 文献史料から見た十三湊と安藤氏 (2)十三湊関係の文献史料」のところに、つぎのような文章がある。
「『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』については、捏造された偽書であるという評価が既に定着している。」
これらののべるとおりである。『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』は、『東日流外三郡誌』の発見者とされる和田喜八郎が捏造した文書である。
そのことは、和田喜八郎氏じしんの筆跡と、和田喜八郎氏が発見したと称する『東日流外三郡誌』をはじとする一連の古文書とを比較してみただけでも、すぐわかる。
下の写真の右の表ように、「ひらがな」の筆くせが、和田喜八郎の自筆と、発見された「古文書」とで同じである。また、下の写真の左の表のように誤字の傾向も同じである。
(下図はクリックすると大きくなります)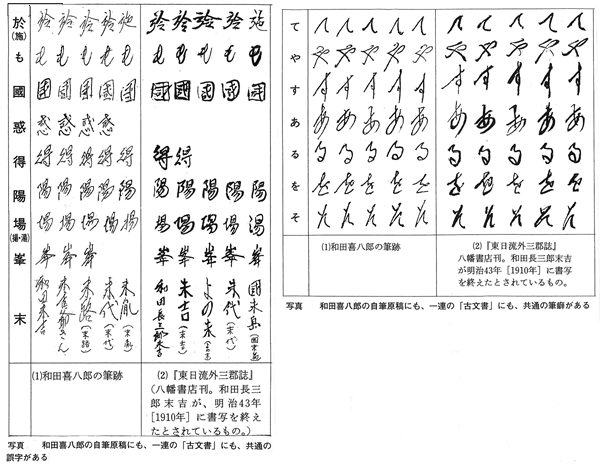
和田喜八郎氏の筆跡には、ひらがなでも漢字でも、最初の横の棒を、やや極端に右あがりに書かれたものが多い、などの特徴をもつ。そのため、ひらがなの「て」の字は、上の写真の右の表にみられるように、手をつきそうなほど、前につんのめっている。
特に重要で決定的なことは、和田喜八郎氏の原稿に見られる「誤字」とまったく同じ特徴的な誤字のセットが、『東日流外三郡誌』その他一連の「古文書」に見られることである。
例をあげる。(上の写真の左の表参照)
(1)和田喜八郎の自筆原稿では、「於」の字を、すべて誤って、[「こ」→「令」としている]、と書いている。『来日流外三郡誌』をはじめとする一連の古文書も、またそうである。
(2)和田喜八郎の原稿では、「於」の字の偏の「方」の字の筆順が、すべて、ふつうと異なっている。ふつう、「亠→フ→方」の筆順で書くものを、すべて、「亠→ノ→方」の筆順で書いている。これは、「方」「施」「族」「旗」「放」などにも、共通していえる。
『東日流外三郡誌』をはじめとする一連の古文書でも、この筆順となっている。
(3)和田喜八郎氏の原稿では、「も」の字の筆順が、ふつうと異なり、すべて、二本横棒を引いて「し」の字を書いている。ふつうは、「し」の字を書いてから、二本横棒である。
『東日流外三郡誌』をはじめとする一連の古文書でも、この筆順となっている。
(4)草書体の場合は、わかりにくいが、楷書体の場合、「国」の旧漢字「國」を誤り、「口」の下になければならない横棒が、「口」の上に引かれている。
「惑」の字の場合も、同じ誤りがみとめられる。
(5)和田喜八郎氏の原稿では、「得」の字をすべて誤って一棒少なく、[「旦」→「日」]と記している。
『来日流外三郡誌』をはじめとする一連の「和田家文書」でも、そうなっている。
(6)和田喜八郎氏の原稿では、「陽」「場」「揚」などを、すべて誤って一棒少なく、[「旦」→「日」]と記している。
『東日流外三郡誌』をはじめとする一連の「和田家文書」でもそうなっており、さらに『東日流外三郡誌』では、「湯」も、誤って[「旦」→「日」]と記している。
(7)和田喜八郎の原稿では、「末」の字を誤って「未」と書いている。「末路」を「未路」と書く。そして、四代前の祖先とされる和田長三郎末吉の名を、「未吉」と書いている。そして、『東日流外三郡誌』でも、「未吉」と書いている。その名の下には、花押も記されている。本人が書いたものなら、文字を間違うはずがない。
以上のほか、「達」「展」などの文字も、一貫して誤っている。「完璧」を、つねに、「完壁」に誤っている。
天井裏から落ちてきたという古文書なるものは、和田喜八郎じしんが書いたものである。このていどの幼稚な偽書にだまされて、いまでも『東日流外三郡誌』は、本物の古文書だといって、がんばっている「学者」がいる。
旧石器捏造事件のばあいでも、歌川広重の『東海道五拾三次』の原画なるものの発見のばあいでも、三角寛のサンカの研究書なるもののばあいでも、『東日流外三郡誌』のばあいでも、一方で、大がかりな捏造をする人がいる。一方で、それを本物だと信じ本物と主張する「大学教授」たちが出現する構図は共通している。
土俗的な教祖がのべたことを信じ、そうとうなインテリたちが、殺人までおかした事件があった。大本営発表を信じ、戦勝にうかれ、ひどい目にあったこともあった。現在も、オレオレ詐欺などの振りこみ詐欺の被害にあう人たちが、あとを絶たない。
振りこみ詐欺のばあい、銀行員などが振りこもうとする間ぎわに注意しても、かまってくれるなと、怒りだす被害者もいるという。
どうして、検証もしないで、そんなに簡単に信じこむのか。
広く情報を集め検討をしないで、一方の情報だけを信じこみ、他の情報を遮断するのか。世のなかには、だまされやすい人が、意外に多いようである。
古代史の世界も、また、例外ではない。
用心、用心
なお、『東日流外三郡誌』が、偽書であることを示す本に、次のようなものがある。
○斉藤光政著『偽書「東日流外三郡誌」事件』(新人物往来社、2006年刊)
○安本美典著『虚妄(まぼろし)の東北王朝』(毎日新聞社、1994年刊)
■洛陽の三角縁神獣鏡事件
マスコミ報道の、「三角縁神獣鏡」
これは、現代中国での捏造鏡だ! 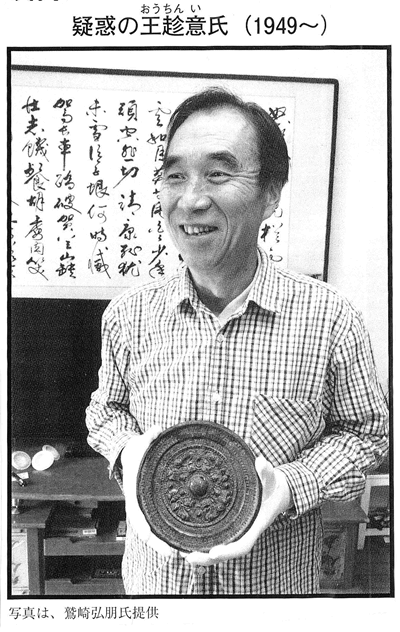
------------------------------------
旧石器捏造事件も、『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』事件も、ピルトダウン人事件(イギリスでおきだ猿と人類との間にいたとされる初期人類化石捏造事件)も、発見者が、すなわち、捏造者であった。中国では、3000面以上の青銅鏡が、発掘により出土している。そのなかに、「三角縁神獣鏡」は、1面もない。しかるに、王趁意氏は、十数面の「三角縁神獣鏡」をとりだしてみせる。王趁意(おうちんい)氏を強く疑うべきである。この鏡で、大さわぎをする日本の行政の考古学研究者やマスコミは、捏造者の商売の宣伝媒体となっている。
------------------------------------
王趁意(おうちんい)なるあやしげな人物が提出した「洛陽発見の三角縁神獣鏡」なるものがある。
これがインチキ物であることは、拙著『邪馬台国全面戦争』(勉誠出版、2017年)の中で詳論した。三角縁神獣鏡は、日本の、おもに3~4世紀の古墳などから出土する直径の平均が22センチほどの大型の銅鏡で、背面に神仙像や竜・虎などの獣形(神獣)が描かれている。「三角縁」は鏡の断面が三角形を指す。古代中国の魏と倭の邪馬台国女王、卑弥呼を結び付ける遺物として、たびたび論議されてきた。ただ、わが国からは、400面以上出土しているのに、中国での出土例はない。もし魏の皇帝が卑弥呼に下賜(かし)した鏡が三角縁神獣鏡なら、中国からも出土しそうなものである。
中国からは、正式な発掘によって、3500面以上の青銅鏡(銅鏡)が出土している(諸報告書類によって、私が確認した面数は、下表にみられるように、3573面)。
(下図はクリックすると大きくなります)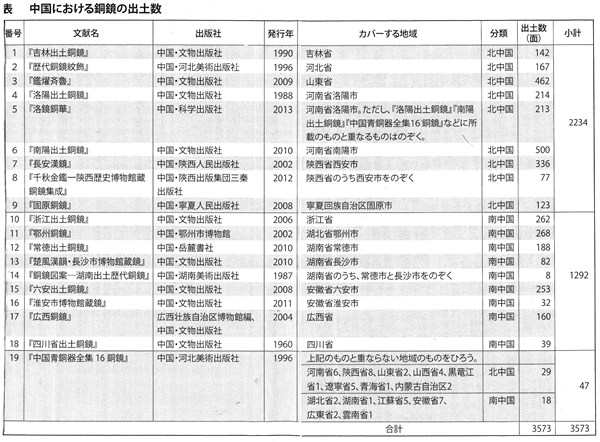
その中には、「三角縁神獣鏡」は、1面も存在しない。しかるに、王趁意氏は、十数面の「三角縁神獣鏡」を、つぎつぎととりだしてみせる。これは、確率論的な基準からいって、インチキ物であると、簡単に判断される。それを、日本の考古学の「専門家」が、「王趁意氏にあい、実物を私が肉眼でみて判断したのであるから、本物の中国出土の三角縁神獣鏡である」などと、マスコミなどで、強く主張する。しかし、その「肉眼でみた判断が正しい」という客観的根拠(エビデンス)が提出されていない。
金石学が専門の鈴木勉氏の書かれた『「漢委奴国王」金印・誕生時空論』(雄山閣、2010年)という本がある。
この本のなかに、次のような文章が記されている。
「今ひとつ、卑近な事例を報告しておきたい。筆者の友人が数年前に北京の骨董市で、二面の人物車馬画像鏡(安本注わが国では、三角縁の『人物車馬画像鏡』系の鏡は、『三角縁神獣鏡』の中にいれられてぃる)を購(あがな)った。最初は日本円で5万円くらいに言われた鏡であったが、2度も3度もその店に出たり入ったりした彼の粘り強い交渉の結果、その現代鏡は約8000円で購人することができた。同行した筆者も、それまで幾面もの出土画像鏡を見ていたので、その人物画像鏡の出来のすばらしさ(出土画像鏡によく似ていること)がよく判った。帰国後、筆者は、その鏡を友人から預かり、当代の著名な古鏡の研究者が集まる研究会に持ち込んだ。失礼がないように言っておくのだが、研究者達の鑑識の力量を試そうとしたのではない。私は本当に彼らの研究者としての力を信頼している。ただ現代中国の鏡造り工人の技術水準を確かめたかったのである。いつの時代も、偽物作りは、その工人と識者の鑑識眼との凌ぎ合いであるからだ。
高名な研究者達にこの鏡を見てもらったが、誰一人として現代鏡だと指摘することはなかった。現代の研究者は、戦前の著名な研究者以上に数多く古文化財を観察調査している。これは間違いないことだ。さらに、彼らは確かな基準資料である出土資料を数多く見ている。であるから、現代の一流の研究者達が戦前の研究者に鑑識眼で劣ることはまずない。それほど、現代の研究者は良いものを沢山見ており、研究環境は戦前とは比べものにならない。しかし、近現代の偽物作りの技術水準は、それを凌ぐ、と認めざるを得ない。筆者は、いかに高い鑑識眼を持つ権威者と言えども、肉眼では偽物作りに立ち向かうことは出来ないのではないかと、考えている。」
つまり、8000円以下の費用で、専門家が見ても本ものと区別がつかないような、すばらし偽造鏡を、つくることができるということである。
マスコミで報道された王趁意氏提出の「三角縁神獣鏡」とは別に、王趁意氏の保証書(箱書き的なもの)のついた「三角縁神獣鏡」を、かなりな価格で買ってきた日本の人もいる。「先生は、これを、どう思われますか」ということで、その保証書のコピーと、鏡の写真とを、私のところへもってこられた方がいる(購入者の方ではないが)。
(下図はクリックすると大きくなります)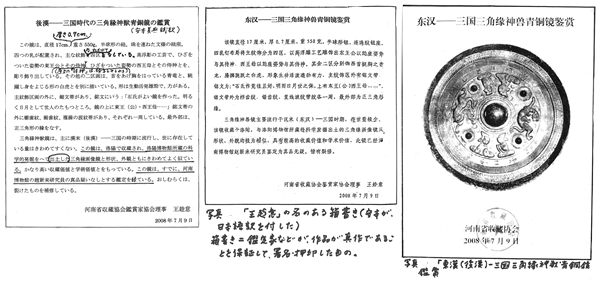
王氏に簡単にだまされる考古学の「専門家たち」(複数であることに注意)は、王氏の商売のお手伝いをしているのである。
これに類した問題があった。そうだ。旧石器捏造事件である。
旧石器捏造事件がおきたとき、人類学者で、国立科学博物館人類研究部長(東京大学大学院理学系生物科学専攻教授併任)の馬場悠男(ばばひさお)氏が、私が「洛陽発見の三角縁神獣鏡」について述べたのと同じようなことを語っている。
「私たち理系のサイエンスをやっている者は、確率統計学などに基づいて『蓋然性が高い』というふうな判断をするわけです。偉い先生がこう言ったから『ああ、そうでございますかすか』ということではないのです。ある事実が、いろいろな証拠に基づいて100%ありそうか、50%か、60%かという判断を必ずします。どうも考古学の方はそういう判断に慣れていらっしゃらないので、たとえば一人の人が同じことを何回かやっても、それでいいのだろうと思ってしまいます。今回も、最初は変だと思ったけれども何度も同じような石器が出てくるので信用してしまったというようなことがありました。
これは私たち理系のサイエンスをやっている者からすると、まったく言語道断だというこことになります。」
「経験から見ると、国内外を問わず、何ヵ所もの自然堆積層から、同じ調査隊が、連続して前期中期旧石器を発掘することは、確率的にほとんどあり得ない(何兆分の1か?)ことは常識である。
だからこそ、私は、東北旧石器文化研究所の発掘に関しては、石器自体に対する疑問や出土状況に対する疑問を別にして、この点だけでも捏造と判断できると確信していたので、以前から、関係者の一部には忠告し、拙著『ホモ・サピエンスはとこから来たか』にも『物証』に重大な疑義があると指摘し、前・中期旧石器発見に関するコメントを求められるたびに、マスコミの多くにもその旨の意見を言ってきた。
しかし、残念ながら、誰もまともに採り上げようとしなかった。とくに、マスコミ関係者の、商売の邪魔をしてもらっては困るという態度には重大な責任がある。」(以上、春成秀爾編『検証・日本の前期旧石器』学生社、2001年)
確率論的にみれば、「洛陽発見の三角縁神獣鏡事件」も、「旧石器捏造事件」も、問題の構造は、同じである。
ふつうの科学の基準では、ある仮説にしたがうとき、計算をすると、一定の確率(ふつうは、100分の5か100分の1以下でしか起きないことが起きたことになるときは、もとの仮説は捨てる(棄却する)「約束」になっている。機械的(メカニカル)に棄却することによって、議論の客観性をたもつという「基準」をもうけている。
それを、「どんなに小さな確率でも、起きえないとはいえない。げんに、志賀島(しかのしま)から、『漢委奴國王(かんのわのこくおう)』金印が出土するというようなことが起きる確率は、1万分の1よりも小さいはずだ。考古学上の大発見などみなそうだ」というような類の議論によって、自説を主張する。
しかし、藤村新一氏のばあいも、王趁意氏のばあいも、特定の人との関連で、何回も、同じようなことが起きている、という「構造」に注目すべきである。
金印のばあいでも、特定の人との関連で、10個ぐらい出土したならば、なにかの手品ではないか、と疑うべきである。
あらかじめ自説をもち、自説は正しいものであって欲しいと強く願うと、その自説にあうものをとりだしてみせる者が出現する。そして、それに容易にひっかかる。「肉眼観察主義」の客観性のない議論をしていると、このようなことになる。鏡の真贋を議論するのなら、せめて、鏡にふくまれる鉛の同位体比ぐらいは、測定した上で主張すべきではないか。
・ネタ本は、たった二冊の本
問題の「王趁意氏提出鏡」制作のネタ本は、わが国で刊行されている『古鏡総覧(I)』(奈良県立橿原考古学研究所編、学生社、2006年刊)と、中国で刊行されている『鄂州銅鏡』(鄂州市博物館、2002年刊)のたった二冊の本であると、みられる。
今回の「王趁意氏提出鏡」の「銘文」31文字のうちの、30文字、97パーセントまでは、『古鏡総覧(I)』にあるものを、見本にすればよい。
下表のとおりである。
(下図はクリックすると大きくなります)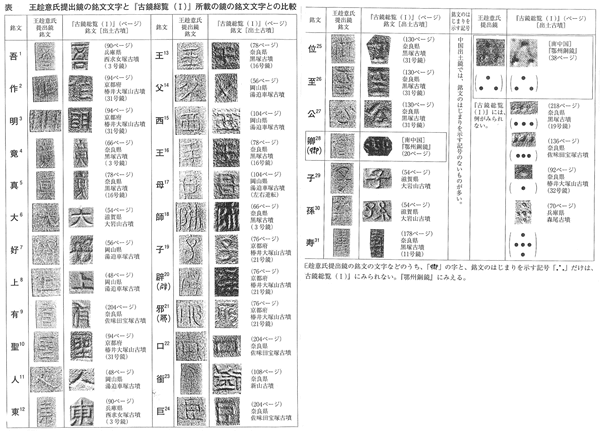
今回、王趁意(おうちんい)氏の提出した「新発見」の鏡の銘文と、『古鏡総覧(I)』にのっているわが国出土の「三角縁神獣鏡」とは、文字の字体が、全体としてきわめてよく似ている。
「新発見」の鏡の銘文の文字の見本を、『古鏡総覧(I)』ほどまとめて面倒をみてくれる本は、世界中のどこにも、ほかに存在していない。
早稲田大学文化財整理室調査員の考古学者、車崎正彦氏は、日本で出土しているすべての三角縁神獣鏡は、中国からもってきた「舶載鏡」であるとする。
「王趁意氏提出鏡」には、つぎのような銘文がある。
吾、明鏡を作るに、真に大いに好(よ)し。
上に聖人東王父・西王母有り。
獅子・辟邪(へきじゃ)、口に鉅(きょ)を銜(ふく)む。
位は公卿(こうけい)に至り、子孫寿(いのちなが)からん。
車崎正彦氏は、「三角縁神獣鏡は国産か舶載か-魏晋鏡説の立場から」(『別冊歴史読本』23、大塚初重編『図説 古墳研究最前線』[新人物往来社、1999年刊、28~35ページ])という文章の末尾でのべる。
「いつか三角縁神獣鏡が中国で出土する日がくることを夢見ながら筆を置く。」
ところで、車崎氏のこの文章を、王趁意氏が、その論文「洛陽の三角縁笠松紋神獣鏡を、はじめて探究する」(「洛陽三角縁笠松紋神獣鏡初探」[『中原文物』2014年第6期])のなかで、引用している。
王趁意氏は、日本で、なにが求められているのか、知っているのである。求める人がいれば、それにこたえるものを、王趁意氏がとりだしてみせる。このような構図になっているのである。
これって、旧石器捏造事件や、『東日流外三郡誌』事件と、同じ「構図」であると、お思いにならないのか?
■「肉眼観察主義」と「属人主義」との問題点
考古学の分野で、ある見解が確かであることを「証明」する方法として、多用されているのが、「肉眼観察主義」と「属人主義」であるようにみえる。
ここで、「肉眼観察主義」は、「百聞は一見にしかず。この眼でよく見たのであるから確かである」というものである。
「属人主義」は、「専門家のA氏あるいは、私じしんの発言であるから確かである」というものである。
そして、これらを確かなものとした上で、議論は、次の段階に進む。
しかし、このような方法は、客観性に欠けている。しばしば、大きな誤りをもたらしている。
京都大学の教授で、考古学の権威であった梅原末治は、「勾玉事件」で、ニセの勾玉をつかまされたときに発言したことばは、「ガラスのいい悪いを決めるのは私です」というものであった。これは、「洛陽発見の三角縁神獣鏡」のばあいに、考古学の「専門家」が、「私が見だのだから確かです」と述べているのと、同じ構図である。
これは、「考古学のモノサシを定めるのは私です」という「属人主義」の主張で、むかしのギリシヤのソフィスト(職業教育家)のプロタゴラスの「万物の尺度は人間である」を、思いおこさせる。
しかし、自信の強さは、「証明」の確からしさと、かならずしも比例しない。
「永仁の壺事件」では、ニセ物の壺を作ったのは、人間国宝とされた人物であった。そして、考古学の「専門家」もだまされた。
「旧石器捏造事件」では、何人もの「専門家」が、肉眼で、しかと見たはずなのに、インチキ物であった。
「神の手」を信じたのでは、「属人主義」が、宗教の段階に近づいたことを示している。
考古学の「専門家」は、しばしば、考古学以外の人の発言を、「専門家以外の人の、余計な口出し」のようにとりあつかい、とかく無視しがちである。
しかし、「勾玉事件」のときに、それがニセ物であることを指摘したのは、ガラスの専門家であった。
「旧石器捏造事件」のさいに、それがはっきりとした「ニセ物」であると「証明」したのは、毎日新聞社の取材班のビデオカメラであった。
いずれも、考古学の「専門家」ではない。
それまでは、考古学の分野での自浄作用は働かず、ニセ物が、ホンモノとしてまかり通っていた。考古学の「専門家」は、なにをしていたのか。
「肉眼観察主義」や「属人主義」がきわまるところ、事件がおきやすい。のっぴきならないところまでつき進むから、大事件になるのである。
それは、「肉眼観察主義」や「属人主義」は、科学の方法として、長い時間をかけて洗練され、客観化されてきたものではなく、主観的判断のはいりやすい、日常生活の経験にもとづく「素朴な経験主義」であるからである。
人間は、あやまちをおかしやすい存在であることをみとめず、みずからをモノサシにするからである。
「属人主義」は、また、データにもとづいて判断せずに、大学の先生や先輩、あるいは、その大学での伝統的見解を優先し、それにもとづいてデータを「読みとる」、または、「解釈する」という姿勢を、生みがちとなる。
他の分野では、何でもなく通る方法や論理が、考古学の分野では、なかなか通らない。
ここに、大きな問題がある。
かすったら邪馬台国、風が吹いたら畿内説。







