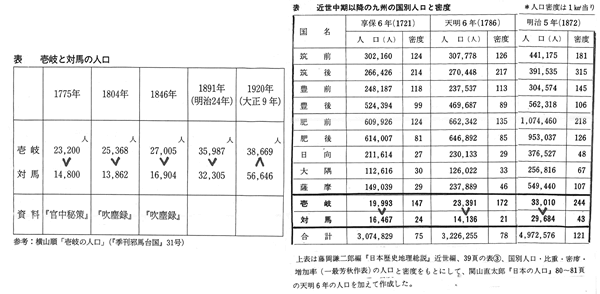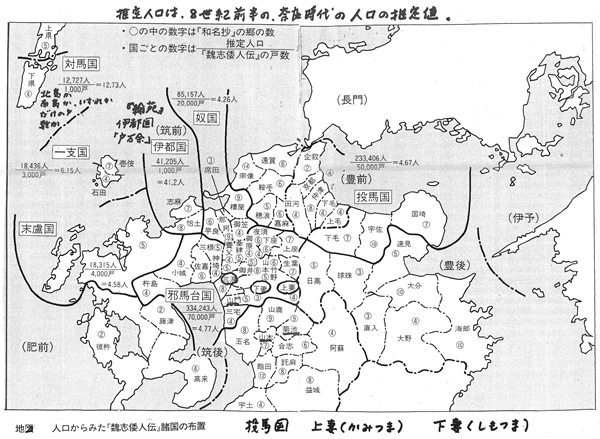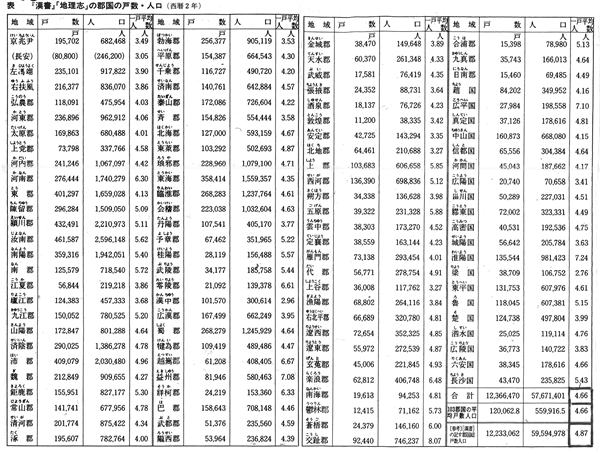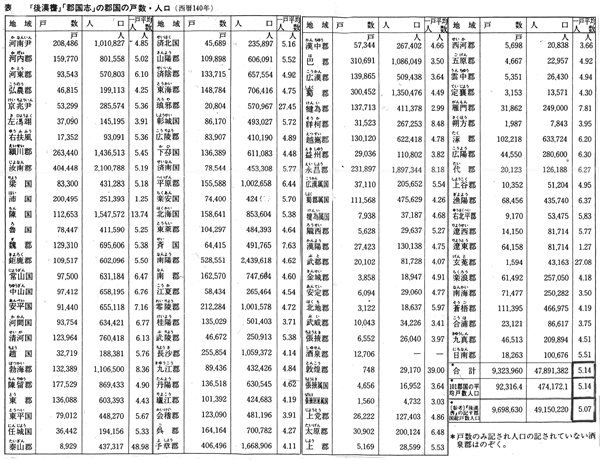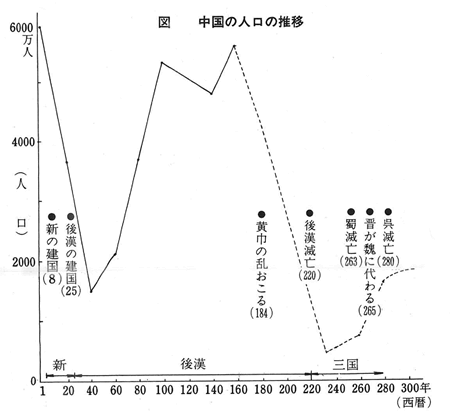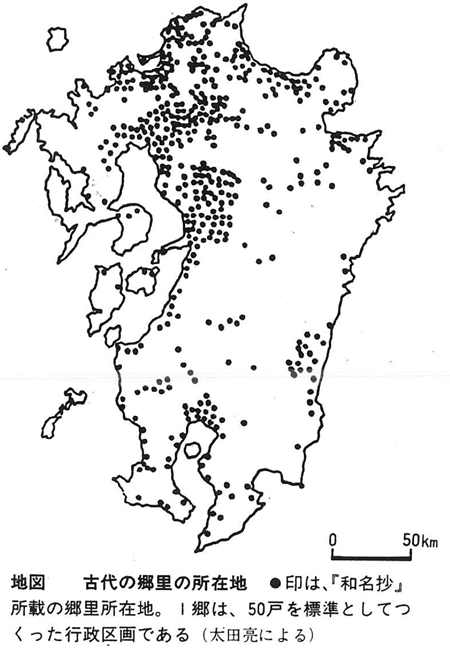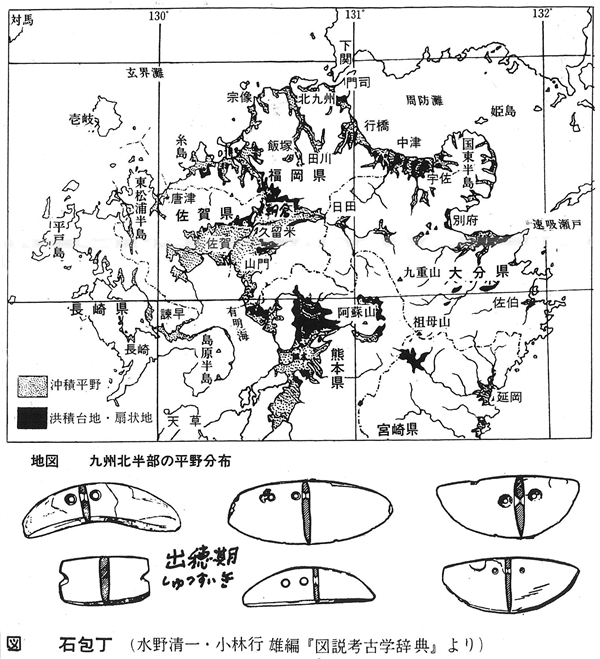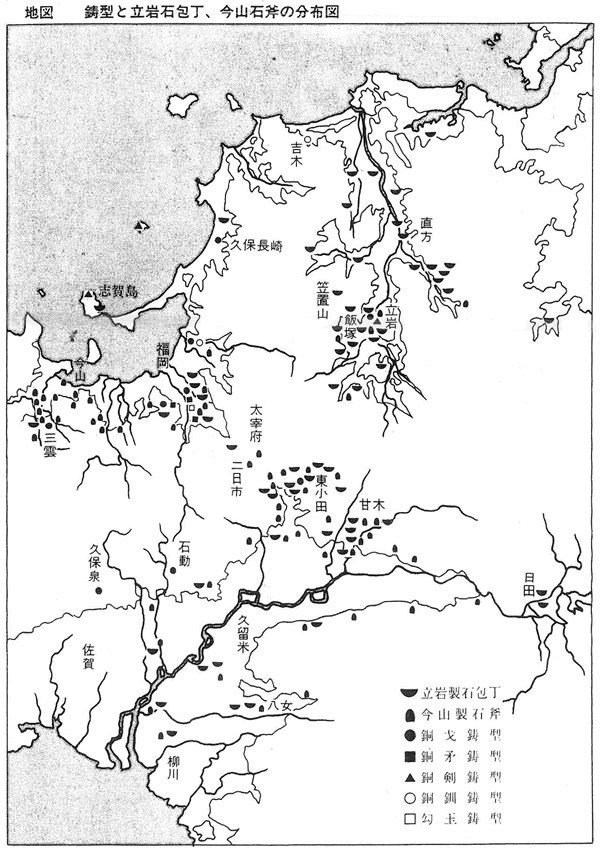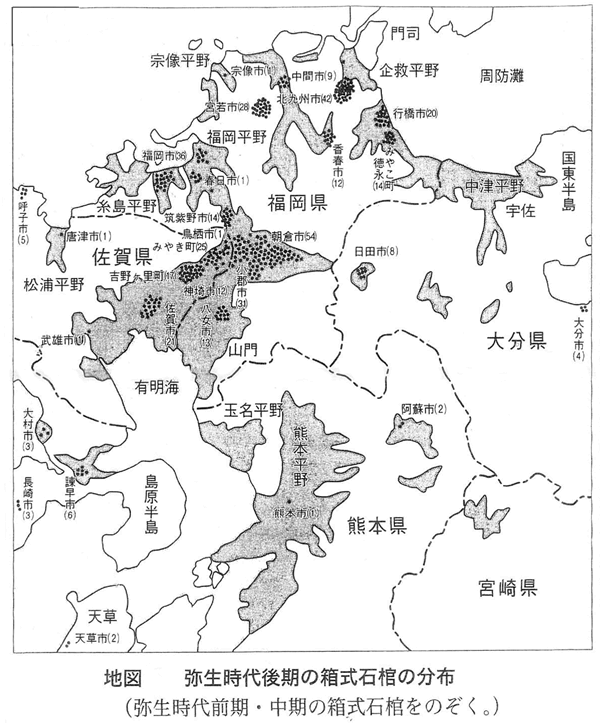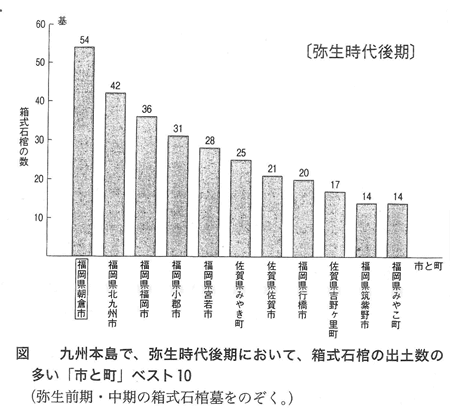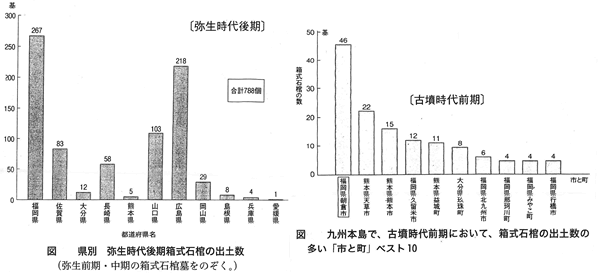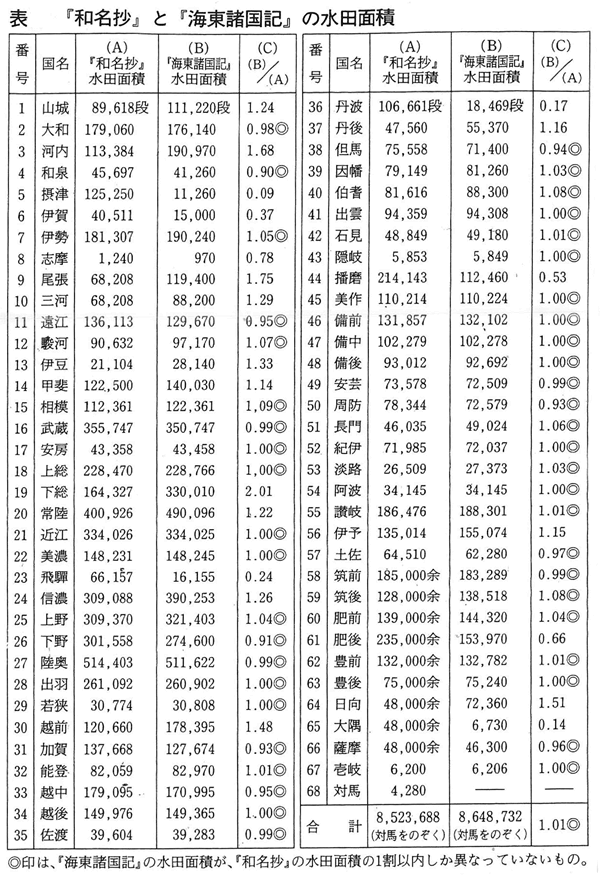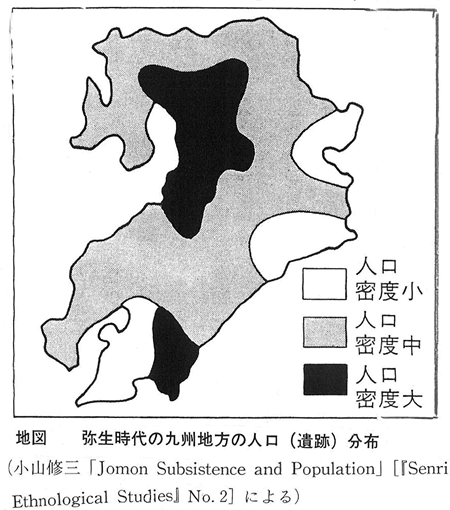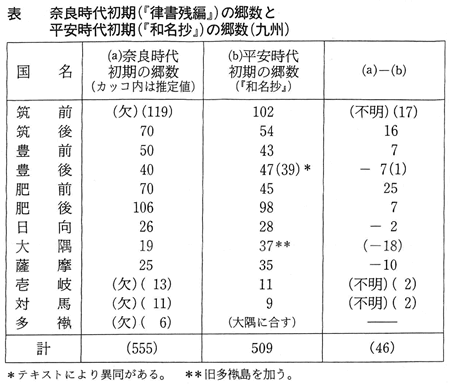藤堂明保監修『倭国伝』(学習研究社、1985年刊)
・倭人(わじん)
倭人は、帯方(たいほう)〔郡(ぐん)〕(黄海北道沙里院付近)の東南、大海の中に在(あ)り、山島に依(よ)りて国邑(こくゆう)を為(つく)る。旧(もと)百余国あり。漢(かん)の時に朝見する者有り。今、使訳の通ずる所三十国なり。
[現代語訳]
倭人(わじん)は、魏(ぎ)の帯方郡(たいほうぐん)から海を隔てた東南の位置に住んでいる。島の中に国ができている。昔は、百以上の国があった。漢(かん)の時、来朝する者がいた。現在、使節が往来しているのは三十国である。
ここの「今」は何時か?三国志が成立した時期を「今」とすると、つじつまが合わないことになる。
・『魏志倭人伝』の倭までの記述
〔帯方(たいほう)〕郡(ぐん)従(よ)り倭(わ)に至るには、海岸に循(したが)いて水行し、 〔諸〕韓国(かんこく)を歴(へ)て乍(たちま)ち南し、乍(たちま)ち東し、其(そ)の北岸狗邪韓国(くやかんこく)に到る〔郡より〕七千余里にして、始めて一つの海を度(わた)り、千余里にして対馬国(つしまこく)に至る。其の大官を卑狗(ひこ)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰う。〔対馬は〕居(お)る所、絶島にして、方四百余里可(ばか)りなり。〔その〕土地は、山険しくして、深き林多く、道路は禽鹿(きんろく)の径(ほそみち)の如(ごと)し。千余戸有り。良田無く、海の物を食(く)らいて自活す。船に乗り、南北に〔ゆきて〕市糴(してき)す。
又(ま)た南して一つの海を渡る。千余里なり。名づけて瀚海(かんかい)と曰(い)う。一大国(いちだいこく)に至る。官を亦(ま)た卑狗(ひこ)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰(い)う。方三百里可(ばか)りなり。竹木の叢林(そうりん)多し。三千許(ばか)りの家有。差(やや)田地有りて、田を耕せども、猶(なお)食(く)らうに足らず。亦(ま)た南北に市糴(してき)す。
[現代語訳]
帯方郡から倭に行くには、海岸沿いに船で行き、韓(かん)の国々を通り、あるときは南に向かい、あるときは東に向かってすすむと、倭の北の対岸に当たる狗邪韓国(くやかんこく)に到着する。
帯方郡から、七千里あまり来たところで一つの海を渡り、千里あまり行くと対馬国に到着する。そこの大官を卑狗(ひこ)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。対馬は離れ小島で、広さは四百余里四方である。土地柄は、山が険しく、深い林が多くて、道は、細くてけもの道のようである。千余戸が住んでいる。よい畑はなく、海産物を食べて生活している。船を使って南北に行き、米などを買ったりしている。
そこから、一つの海を南へ渡ること千里余り、その海を瀚海という。なお壱岐国(いきこく)に到着する。そこの官も卑狗(ひこ)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。広さは三百里四方である。竹や木の繁みが多い。三千軒ほどの人家がある。対馬国(つしまこく)に比べ、いくらか畑があるが、その収穫だけでは生活していけない。それで、この国もまた、南北に行き、米などを買ったりしている。

戸数問題
現在の人口
中国の人口(2021年)14憶
日本の人口(2021年)1.26憶
青木和夫(お茶の水女子大学教授など)著『日本の歴史 3 奈良の都』中央公論社刊1965年刊から
「倭」の諸国の戸数は右の表参照。合計すると15万余戸となる。
三国時代の人口の概要
前漢 5,959万人
後漢 4,915万人
魏 360万人
呉 150万人
蜀 100万人
倭 75万人
・数学と歴史学
還暦を迎えた前東京高商教授、理学士沢田吾一(さわだごいち)氏[わが国古代人口学の建設者(1861~1931)]が、東京帝大の文学部国史学科に再入学したのは、1920年(大正9)の秋であった。すでにひろく使われていた数学教科書の著者として著名な氏が、末っ子のような学生たちと机を並べる気になったのは、日本の古文書の魅力に憑(つ)かれたためらしい。ともかくめでたく卒業して理学士兼文学士となった氏が、まもなく提出した博士論文は、指導教官に握られたまま審査されないうちに古稀(こき)がきて、氏は病没してしまった。奈良時代の人口の推計などを論じたその論文は、横文字の原書を引用して数学理論を縦横に駆使してあったため、他の国史学者たちには審査できなかったからだという。
以来30余年、歴史学者たちは、奈良時代の人口を口にするとき、沢田氏がその博士論文の主旨を、一般の人々のためにやさしく書きなおした著書『奈良朝時代民政経済の数的研究』(初版は1926年)の結論を、そのまま借用している。いわく、
「故に計算上に於て総良口(りょうこう)558万云々(うんぬん)を得たれども、安全なる主張としては500万と600万の間にありと云(い)ふ可(べ)く、従(したがっ)て之(これ)を560万といふも是(こ)れ大体の近似数と見るべきものとす」
・壱岐と対馬の人口
『魏志倭人伝』に記されている戸数が、あるていど実数にもとづいていることは、壱岐と対馬の戸数からうかがえる。 沢田吾一氏は、『奈良朝時代民政経済の数的研究』のなかで、およそつぎのようにのべている。
「九州の西、北、南に島々がちらばり、舟子、漁民が多いので、狭い郷もまた多いであろう。島々、海角においては、その近くの本土にくらべ、郷数の割合に田地面積のすくないことは、『和名抄』により、一郷あたりの田地面積を算出してみれば、あきらかなことである。
また、『三代実録』貞観十八年(876)三月在原行平請事の文中に、壱岐島課丁(かてい)二千余人、水田616町と記されている。これから計算すれば、良民人口一人について、水田0.58段の割りあいにあたる。ここからも、人口が多く、田のすくない土地であることがわかる。また、近代においても、島々や海角の人口が、耕地にくらべ、稠密であることは、あきらかな事実である。」
『魏志倭人伝』にも、対馬国については、「良田なく、海物を食して自活し、船に乗り南北に市糴(してき)す。」、一支(壱岐)国については、「やや田地がある。田を耕すも、なお食するにたらず、また南北に市糴(してき)す。」とある。「市糴」すなわち「米を買っていた」という記事からも、田地にくらべ、人口の多かったことが読みとれる。
面積の小さい壱岐の推定人口のほうが、面積の大きい対馬の推定人口よりも大きい。
さて、『魏志倭人伝』は、一大(支)国の戸数を、「三千許(ばかり)の家」と記し、対馬国の戸数を、「千余戸」と記している。やはり、面積の小さい壱岐の戸数のほうを、面積の大きい対馬よりも大きく記している。これは、実際にあっていると考えられる。『魏志倭人伝』の記述は、なんらかのよりどころがあったと考えるべきである。
対馬歴史民俗史料館の永留久恵氏は、「対馬の人口」(『季刊邪馬台国』31号)という文のなかでのべておられる。
「飛行機の上から眺めると、低くなだらかに起伏する丘陵の天辺まで耕作され、ところどころに叢林がある壱岐の風影と、山岳重畳として自然林多く、谷間や入江の辺にわずかな耕地が見える対馬の景観は対照的で、『魏志倭人伝』の記載が本当であることを教えてくれる。」
『魏志倭人伝』の、つぎのような、対馬国と一支国との書きわけは、実地の見聞にもとづくとみるべきである。
対馬国
「いるところは絶島(離れ島)で、土地は、山けわしく、深林多く、道路は、禽(とり)と鹿(けもの)のこみちのようである。良田はない。海(産)物をたべて自活している。」
一支国
「竹木の叢林(そうりん)が多い。やや田地がある。田をたがやしても、なお食に不足である。」
一方は、「山けわしく、深林多く、良田はない」とされているのに、一方は、「竹木の叢林が多く、やや田地がある」とされている。
『和名抄』の水田面積でも、対馬のほうが、壱岐よりも小さくなっている。
ずっとのちの人口統計でも、下の図左の表(壱岐と対馬の人口)、下の図右の表(近世中期以降の九州の国別人口と密度)にみられるように、明治時代までは、一貫して、壱岐の人口が対馬の人口よりも大きかった。対馬の人口が、壱岐の人口よりも大きくなるのは、大正時代ごろからである。
『魏志倭人伝』による表記
対馬国 方400里ばかり 1000余戸
一支国 方300里ばかり 3000ばかりの家
・壱岐と対馬の人口推定
(下図はクリックすると大きくなります)
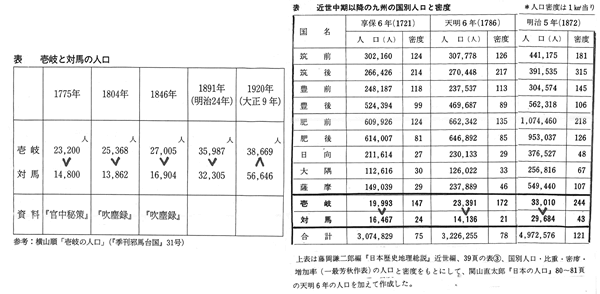
(下図はクリックすると大きくなります)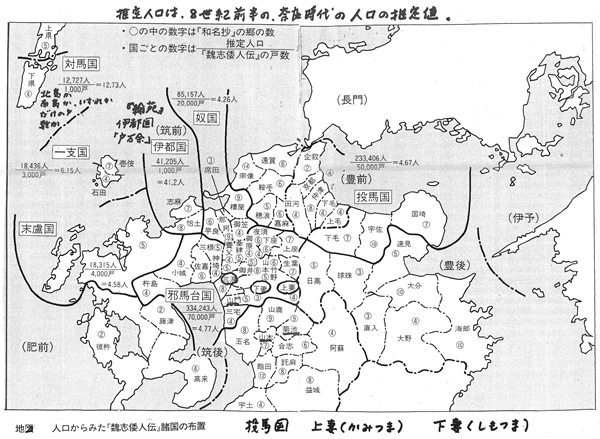
■中国の人口
中国の人口の変化は激しい、千里に鶏鳴(けいめい)なしと表現された時代
魏の国の始祖、曹操(そうそう)[155~220]は、詩人でもあった。
曹操は、「蒿里行(こうりこう)」という詩の中でうたっている(「蒿里」は、人の死後、その霊魂のあつまるところ)。
白骨は野に露(さら)され、
千里に鶏鳴(けいめい)なく、
生民は百に一を遺(のこ)すのみ。
これを念(おも)えば、人腸を断(た)つ。
後漢の中平元年(184)、「蒼天すでに死す。黄天まさに立つべし」のスローガンをかかげ、黄巾(こうきん)の賊が兵をあげた。かくて、二世紀の後半から、中原一帯は、大動乱の中に投げ込まれた。
後漢王朝は衰退し、魏の始祖曹操、呉の始祖孫堅、蜀の始祖劉備玄徳らが、黄巾の賊征定のなかで名をあげていった。
さきの曹操の詩は、大動乱のあとの中原の姿をうたっているのである。
曹操の詩に近い表現は、陳寿の編纂した『三国志』の中にも、いくつも見いだされる。
この当時、天下の戸数、人口は減少し、わずか十分の一までになっている。(『魏書』「二公孫陶四張伝第八」の「張繍(ちょうしゅう)伝」。筑摩書房刊、現代語訳『三国志I』255頁)
現代は荒廃した時代の後を受け、人民は死に絶えている。(『魏書』「諸夏侯曹伝(とうにえんりゅうでん)第九」の「夏侯尚伝」。現代語訳『三国志I』288頁)
現今、千里にわたって人煙なく、見捨てられた人民は困窮しております。(『魏書』「王衛二劉傅伝第二十一」の「衛顗(えいき)伝」現代語訳『三国志Ⅱ』87頁)
後漢の首都洛陽は、焦土となり、周囲百里は、董卓(とうたく)の軍によって焼きはらわれた。
(後漢の)天子のみくるまは、すぐさま西(長安)に向った。董卓配下の兵は、洛陽の城外百里にわたるまで焼きはらった。また、董卓みずから兵をひきつれ、南北の宮殿、宗廟、政府の蔵、民家に火を放ったので、洛陽城中はすっかり灰燼に帰してしまった。さらに、多くの富豪を捕え、罪をかぶせてその財産を没収したため、無実の罪で死んだ者は数知れなかった。[『魏書』「董二袁劉伝(とうにえんりゅうでん)第六」の「董卓伝」の裴松之(はいしょうし)注の文。『後漢書』によるという。現代語訳『三国志Ⅰ』168頁]
このような状況におちいったことは、関中の、長安を中心とする地域も同じであった。
この当時(初平三年、192年ごろ)、三輔(さんぽ)[長安を中心とする地域]の戸数はまだ数十万あったが、李廓?(りかく)らが兵を放って略奪をはたらき、町や村を攻略したため、人民は飢餓に苦しみ、二年の間に互いに食らいあい、ほとんど死にたえてしまった。(『魏書』「董二袁劉伝(とうにえんりゅうでん)第六」の「董卓伝」。現代語訳『三国志I』172頁)
(下図はクリックすると大きくなります)
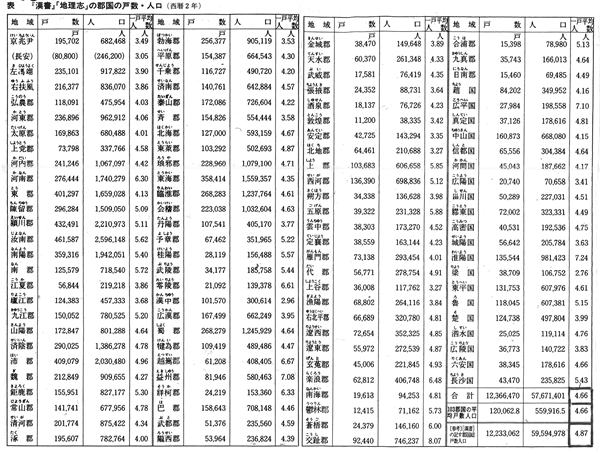
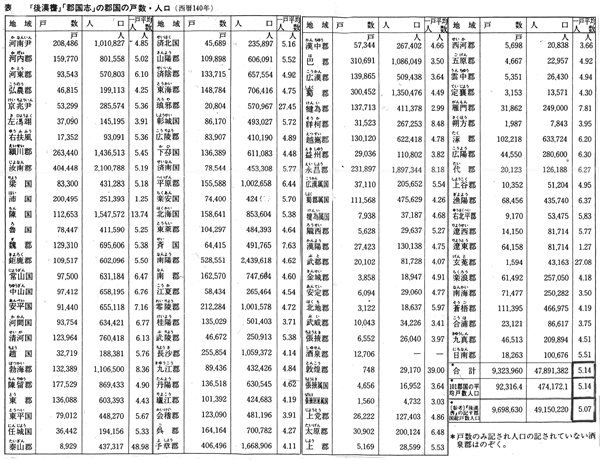
・三国時代の中国の人口
魏の政治家、杜恕(とじょ)[?~252]は、230年ごろ、明帝に意見書を提出している。そこから、当時の華北の人口を推定できる。
杜恕はいう。
今、大魏は十州の地を領有しておりますが、動乱による疲弊のあととて、その戸数・人口を計算すると過去の一州の民にも及びません。しかも二方面(南の呉と西の蜀)の地は僭上して反逆し、北方のえびすはまだ従っておりません。(『魏書』「任蘇杜鄭倉伝第十六」の「杜畿(とき)伝」。現代語訳『三国志Ⅰ』476頁)
「十州」とは、後漢時代の一三州から、呉が支配する揚州と交州、蜀が支配する益州を除いた数である。
後漢時代の中国の総人口は、140年の統計では、49,150,220人となっている。ここから、揚州、交州、益州の人口をさし引くと、残りの10州で、36,355,210人となる。
魏の人口が、その10分の1以下になっていたとすれば、約360万人以下となる。
同じく魏の政治家、陳群(ちんぐん)[?~236]は述べている。
(青竜年間、233~237に)今は動乱の後で、人民の数は極端に少なくなっているのです。漢の文帝・景帝の時代と比較すると、一つの大きな郡にすぎません。加えて国境地帯で は戦闘が起って紜り、将兵は苦労しています。(『魏書』「桓二陳徐衛慮伝第二十二」の「陳群伝」。現代語訳『三国志Ⅱ』109頁)
魏の高官の蔣済(しょうせい)の伝にも述べられている。
景初年間(237~239)、外は征伐にあけくれ、内は宮殿造営に力をついやしたため、やもめの男女が多くなり、穀物も実りが少なかった。蔣済は上奏して述べた。「陛下(明帝)には今し前代の事業を拡大し尊重され、先帝の遺業を輝かせ成就なさるべきでございまして、実際まだ枕を高くして安心して統治できる状態ではありません。今、十二州を領有しているとはいえ、人民の数からいいますれば、漢の時代の一つの大きな郡にすぎません。二賊(蜀・呉)はまだ討滅できず、辺境に兵をとどめたまま、農耕しつつ戦っており、長年にわたってやもめを強いております」。(『魏書』「程郭董劉蔣劉伝第十四」の「蔣済伝」。現代語訳『三国志I』473頁)
ここで、十二州というのは、魏が、雍州(ようしゅう)から、涼州(りょうしゅう)と秦州(しんしゅう)とを分けたからである。
・呉と蜀の人口
東京外国語大学の岡田英弘(おかだひでひろ)氏は、その著『倭国』(1977年、中公新書)の中で、呉と蜀の人口について、次のように述べておられる。
呉の人口は、魏よりずっと少なく、約150万人というところであろう。皇甫謐(こうほひつ)(215~282)の言うところでは、244年に将軍朱照日(しゅしょうじつ)が、呉の領するところの兵戸は13万2千であると魏に報告している。兵戸というのは、軍人の戸籍に登録されている家族のことで、1戸から1人が兵士になるのだから、これはそのまま軍隊の定員と考えてよい。のちに呉が晋に併合されたときの数字では、呉の全人口の九%が兵士となっている。この比率を適用すると、三国時代の初期の呉の人口は、約150万人になるのである。
呉が、三世紀の前半に、約10万の軍をもっていたことは、孫権(182~252、在位229~252)が、つぎのように述べているところからもうかがわれる。
わしは呉の全部の土地、10万の軍勢をそっくりそのままもちながら、人の掣肘(せいちゅう)を受けるわけにはいかない。(『蜀書』「諸葛亮伝第五」。現代語訳『三国志Ⅱ』355頁)
岡田英弘氏は、『倭国』のなかでまた述べられる。
(三世紀前半の)蜀については確かな手がかりはないが、約100万人で、三国の合計は約五百万人らしい。皇甫謐は140年の後漢の南陽郡、汝南郡(じょなんぐん)の戸数統計を引用して、「これを今に方(くら)べるに、三帝が鼎足(ていそく)して、二郡を踰(こ)えない」と言っている。これは500万人弱ということである。黄巾の乱以来、中国の人口は10分の1以下に激減したわけで、これは事実上、中国人種の絶滅である。……
・「思痛記」にみる惨状
いくら戦乱の世の中とはいえ、人口が、10分の1以下に激減するという事実を、信じられない人がいるかもしれない。
しかし、中国では、比較的最近でも、似たような事例がある。
「阿片戦争」は、1840年にはじまり1842年に終わった。それから8年後の1850年に、「太平天国の乱」がおきる。民間宗教的な色彩の強い点て、「黄巾の乱」と「太平天国の乱」とは似ている。
軍隊としての規律がとぼしい太平天国の賊徒が、どのような殺戮を行ったかは、李圭の書いた『思痛記』(松枝茂夫訳、『記録文学集』平凡社刊)にくわしい。
「思痛記」の内容は省略(第367回参照)
中国は、日本にくらべて、山や谷がすくなく、平地が多い。逃げようにも、逃げる場所がないのである。また、わが国では、歴史上、このような無法がまかり通った時代がそれほど多くないので、殺戮によって人口が激減するといった事態が、やや理解しにくくなっている。
二十世紀にはいってからでも、カンボジアにおいて、ポル・ポト軍は、ほしいままの殺戮を行い、人口を激減させている。
ただ人囗の把握は、租税をとりたてることや徴兵と関係している。治安が乱れれば、政府によって把握することのできない、租税を収めない人間や徴兵を逃れようとする人間の数が増加する。治安がよくなれば、政府によって把握することのできる人間の数が増加する。 。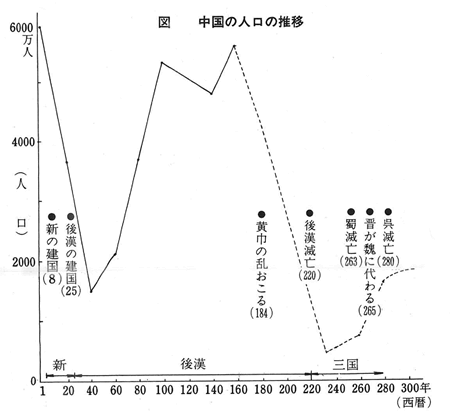
したがって、治安が回復したさいの急激な人口増は、自然増(これも、第二次大戦後のベビー・ブームのように、動乱のあとでは、大きくなると見られる)以外に 逃亡していた民がもどってきたり、把握されなかった民が把握できるようになることからも起きる。
光武帝が定めた緊縮政策のおかげで、中国の人口は順調に回復した。再統一の年からの統計を並べてみよう。
37年 約15,000,000人
57年 21,007,820人
75年 34,125,021人
88年 43,356,367人
105年 53,256,229人
これはほぼ年2%の増加率だが、これからあとの二世紀のはじめには頭打ちとなり、5千万人前後を維持したのである。
他の資料もおぎないながら、西暦2年から、三国時代の終わりである西暦280年までの、中国の人口の推移をまとめれば、右図のようになる。
■人口問題の検討
・『和名抄』の郷の分布
入口についての参考となるデータとしては、『和名抄』の郷の分布がある。
これを最初に示したのは、わが国の氏族制度について、厖大(ぼうだい)なデータを集めた太田亮(おおたあきら)である。
昭和三年、太田亮は、『日本古代史新研究』という本をあらわした。この本のなかで、太田亮は、種々の氏族の地域的分布についての具体的なデータをもとに、「邪馬台国=高天(たかま)の原」説をといた。
(「高天の原」は、『古事記』『日本書紀』の伝える神話の、主要な舞台)。
太田亮は、この本の第四編「天神民族の故国」において、およそ、つぎのように述べる。「中臣(なかとみ)氏も大伴(おおとも)氏も、九州発祥の氏であるらしいが、たとえ、そうでないとしても、大和中心の氏族と離れて。九州に一族がある。中央貴族中、天孫(てんそん)とか皇別と称する皇室より分かれたという氏族をのぞけば、大多数は、大和と九州とを中心として氏族が分布されている。そのいずれの中心が古いかといえば、私は、九州と答えたい。それは、大伴や中臣や物部(もののべ)の発祥地が、九州らしいというばかりではない。また、宇佐とか、壱岐とか、対馬、松浦とかの古い氏が、天神の子孫であると称しているばかりでもない。また、高天の原神話が、九州を中心としているばかりでもない。
-------------------------------------------------------注---------------------------------------------
【皇別】(こうベつ)
新撰姓氏録に見られる氏族の三分類(神別・皇別・諸蕃)の一つ。皇族から出て臣籍に下ったと伝えられ氏族。橘氏、源氏、平氏の類。
【天孫】(てんそん)
天神(あまつかみ)の子孫。天帝の子孫・特に、日本では天照大神の孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)。
【天祖】(てんそ)
天皇の祖先。多くは、天照大神をさし、また、国常立尊(くにとこたちのみこと)から天照大神までをいう場合もある。
【天神】(てんじん)
古代氏族の種別。神別(しんべつ)の一つ。天つ神の後裔とされる氏族の称。中臣・忌部・物部・大伴・久米・弓削・曾禰・佐伯などの諸氏をさす。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
もし、これらの氏が、はじめから大和を中心として栄えたものならば、皇別諸氏のごとく、大和をのみ中心として発展しなければならない。また、近畿の国造(くにのみやつこ)、県主(あがたぬし)というような土地の領主中に一族がなければならない。しかし、事実は、これに反している。よって、ある時代に、これら貴族の中心地が、大和に大移動をしたものであって、それ以前は、九州であったと思うのである。
したがって、天祖の都城は、これを九州に求めなければならない。すなわち、神武天皇の東征を、史実と考えるのである。九州中において、天祖の都城として、もっとも適当なのは、畿内ヤマトと同じ名をもつ肥の国のヤマトの外にないと思う。高天の原神話は、この地を中心としているらしく考えられ、また、畿内のヤマトは、このヤマトの名を移したと思われる。」。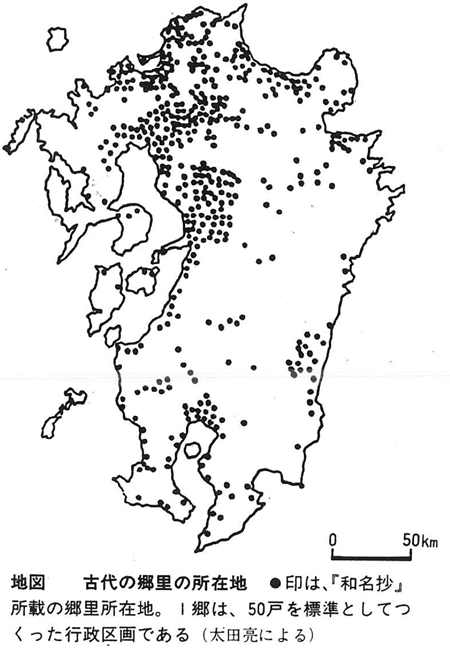
太田亮は、「天祖の都城」を、肥の国のヤマトに求めたうえで、さらに、つぎのように述べる。
「天神族の祖国は、これを九州に求めるのが、一番おだやかだと思う。そして、それは、沃野の打ちつづく、人の住みやすい地でなければならないと考える。その地は、その後も、自然の破壊がなければ、戸数人口の密な場所に違いないのである(右の地図参照)。こう考えてくると、直覚的に、天祖の都は、邪馬台国のような地であったのではないかと思われる。
私は、この広くもない日本列島中の九州と畿内に、ヤマトという二つの大きな国のあったことをあやしむ。わが国は、西から東へと開けていったのである。東の大和なる名称は、肥後のヤマトの名が種族の移住とともに、移ったのであろうと考える。つまり、朝廷が、畿内の今の大和の地にうつったのち、天祖の故国なるヤマトなる名称が、帝都所在地の国名として選ばれたと考えざるをえない。
このような考えから、天神の故国を、邪馬台国と思う。それは、氏族分布からみた想像からいっても、高天の原神話中にふくまれた地理的観念からかえりみても、そうであったという感じを、禁じえない。」
太田亮は、『和名抄』所載の郷里所在地の、九州における分布を示している。
『和名抄』は、十世紀前半の承平(しょうへい)年間(931~938)に撰進された。『和名抄』の郷の分布は、平安時代初期の、九世紀ごろの人口の分布を、反映していると考えられる。
・平野の分布
人口の密集地域を示すデータは、ほかにも存在する。弥生農耕は、多く、平野においていとなまれた。現代でもそうであるが、人口は、おもに、「平野」に集まっていた。
愛媛大学の地質学者、宮久三千年(みやひさみちとし)教授らは、九州北半部の平野の分布を示している(下の地図参照)。上の地図と下の地図とをみくらべるならば、平野の分布が、ほぼ正確に、郷里の所在の密集地と重なりあっていることがわかる。邪馬台国が、もし、北九州にあったとすれば、それは、下の地図に示されている平野のいずれかにあった可能性が大きい。
(下図はクリックすると大きくなります)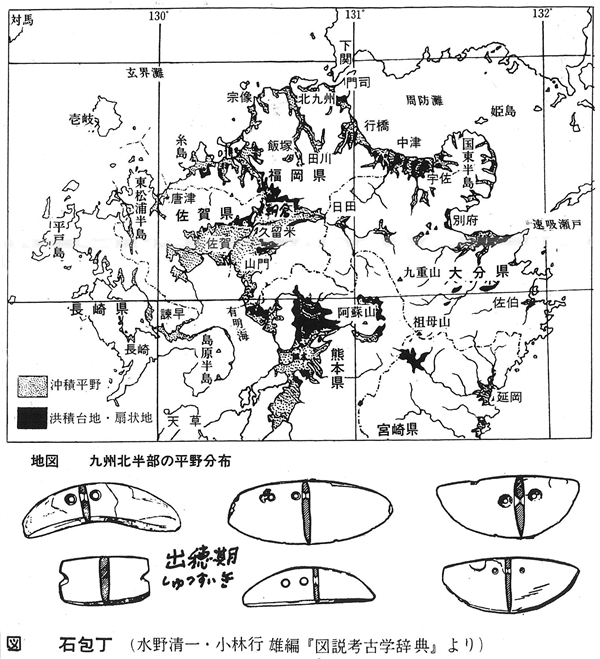
なお、有明海も、博多湾も、大阪湾も、邪馬台国時代においても、現在よりも、ずっと内陸部にくいこんでいたとみられる。現在の平野は、千数百年間の土砂の堆積によって、邪馬台国時代よりもひろがっている。
・石包丁、石斧の分布
弥生文化は、農耕文化であった。したがって、農具の分布は、人口の分布と重なりあっている可能性がある。
弥生式文化にともなう農具の一つに、石包丁がある。稲などの穀物の穂をつむのに用いた。石包丁は、大陸系磨製石器の一種である(上の図参照)。長方形、楕円形、または、半月形をした扁平な石器で、一方の長い辺に刃がついている。一個または二個の孔があり、これにひもをとおして指にかけ、穂をつむのに用いる。明治時代に、調理用のナイフと誤認されたため石包丁とよばれる。
下の地図は、石包丁、石斧などの分布を示す(夕刊フクニチ新聞社刊『奴国(なこく)展』より。なお、この『奴国展』の本は、昭和47年4月28日から5月4日まで、福岡市の岩田屋でひらかれた「奴国展」のさいに作成された資料である)。
(下図はクリックすると大きくなります)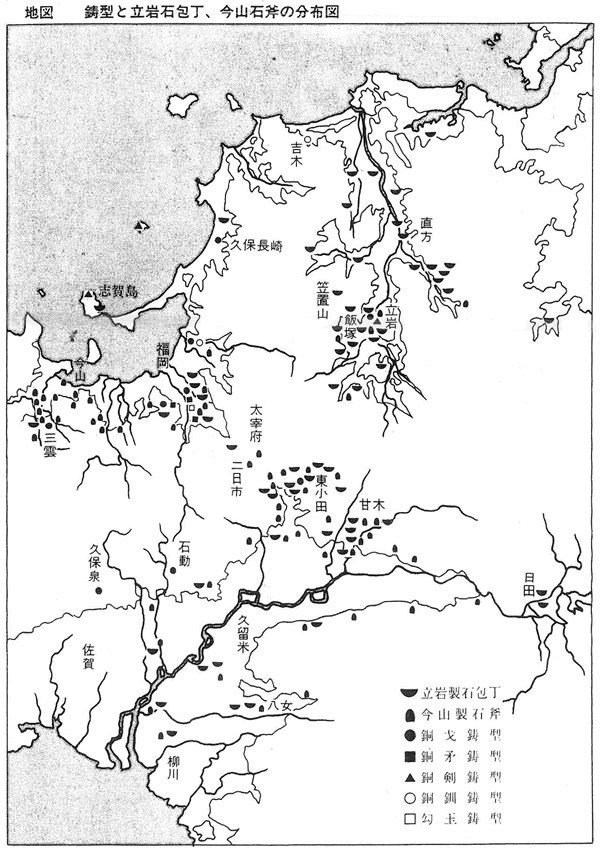
・邪馬台国時代の墓制、箱式石棺の分布
宮崎公立大学の教授であった「邪馬台国=九州説」の考古学者の奥野正男氏は、つぎのようにのべている。(以下、下線をほどこしたのは安本。)
「いわゆる『倭国の大乱』の終結を二世紀末とする通説にしたがうと、九州北部では、この大乱を転換期として、墓制が甕棺から箱式石棺に移行している。
つまり、この箱式石棺墓(これに土壙墓、石蓋土壙墓などがともなう)を主流とする墓制こそ、邪馬台国がもし畿内にあったとしても、確実にその支配下にあったとみられる九州北部の国々の墓制である。」(『邪馬台国発掘』PHP研究所刊)
「前代の甕棺墓が衰微し、箱式石棺と土壙墓を中心に特定首長の墓が次第に墳丘墓へと移行していく……。」(『邪馬台国の鏡』梓書院、2011年刊)
「邪馬台国=畿内説」の考古学者の白石太一郎氏(当時国立歴史民俗博物館。現、大阪府立近つ飛鳥博物館長)ものべている。
「二世紀後半から三世紀、すなわち弥生後期になると、支石墓はみられなくなり、北九州でもしだいに甕棺墓が姿を消し、かわって箱式石棺、土壙墓、石蓋土壙墓、木棺墓が普遍化する。ことに弥生前・中期には箱式石棺がほとんどみられなかった福岡、佐賀県の甕棺の盛行地域にも箱式石棺がみられるようになる。」
「九州地方でも弥生文化が最初に形成された北九州地方を中心にみると、(弥生時代の)前期には、土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が営まれていたのが、前期の後半から中期にかけて大型の甕棺墓が異常に発達し、さらに後期になるとふたたび土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が数多くいとなまれるようになるのである。」(以上、「墓と墓地」学生社刊『三世紀の遺跡と遺物』所収)
このように、邪馬台国の時代の墓制としては、箱式石棺などが考えられる。そして、この箱式石棺を用いるという墓制は、『魏志倭人伝』に記されている「棺あって槨なし」という墓制とも一致するものである。
2015年に、茨城大学名誉教授の考古学者、茂木雅博(もぎまさひろ)氏の著書『箱式石棺(付、全国箱式石棺集成表)』(同成社刊)が出版されている。
この本の「全国箱式石棺集成表」にもとづき、北九州の地図の上に、弥生時代後期の箱式石棺の分布をプロットすれば、下図のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)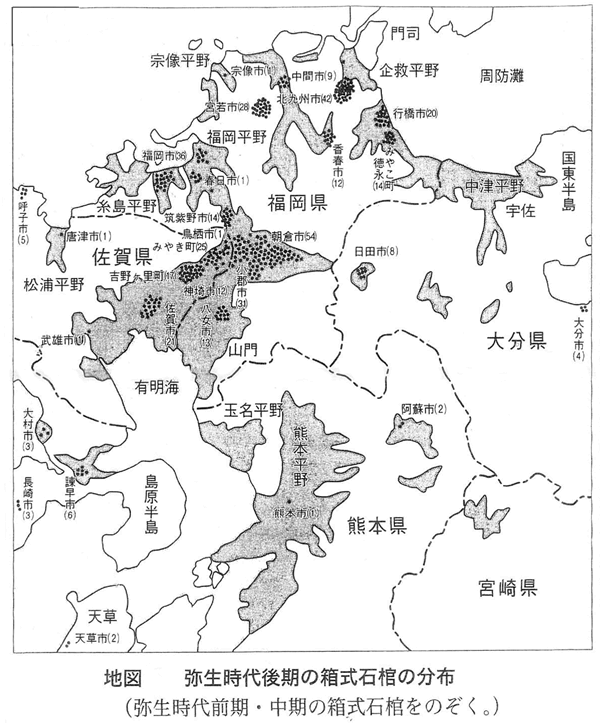
箱式石棺の分布は、福岡県の朝倉市を中心とし、小郡市(おごうりし)のあたりから、佐賀県の三養基郡(みやきぐん)のみやき町、神埼郡の吉野ヶ里町、神埼市にかけての筑後川の上、中流域に密集地帯がある。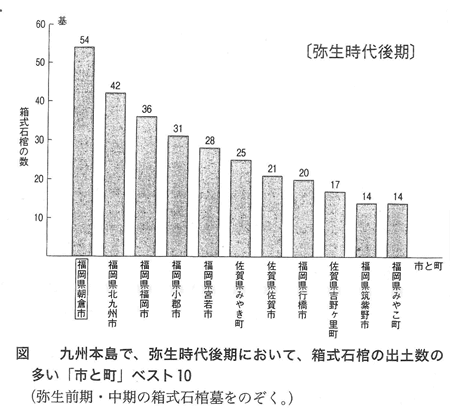
いま、茂木雅博氏の『箱式石棺』により、九州本島において弥生時代後期の箱式石棺の出土数の多い「市と町」との、ベスト10を、グラフに示すと、右図のようになる。
上の地図には、このような数値も、カッコのなかに示されている。
茂木雅博氏の『箱式石棺』により、箱式石棺の、県別の出土状況をみると、下図の左のようになる。
弥生時代後期のばあい、下図の左に示した以外の都道府県からは、箱式石棺は、出土していない。
また、古墳時代前期において、箱式石棺の出土数の多い「市と町」とのベスト10をグラフに示すと下図の右のようになる。
下のグラフを比較すると、つぎのようなことがわかる。
(下図はクリックすると大きくなります)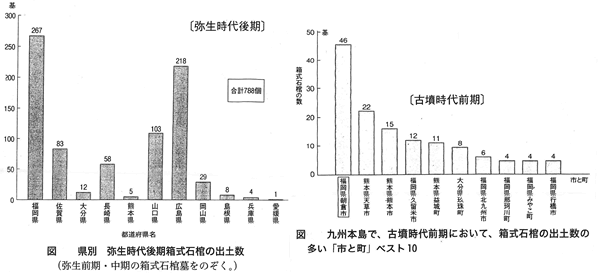
(1)上図右の古墳時代前期になると、熊本県の、天草市や熊本市からの出土数が多くなっている。これは、あるいは、邪馬台国は、福岡県にあり、狗奴国は、熊本県にあり、邪馬台国勢力が、狗奴国勢力を圧倒し、狗奴国地域へ、邪馬台国文化が進出したことを意味するか。(大分県の玖珠町をふくめ、南へ進出。)
(2)古墳時代の前期になると、朝倉市の南の福岡県久留米市からの出土が多くなっている。これも、邪馬台国勢力の南への進出と関係があるか。
・奈良時代の九州の人口
[人口の推定]
(1)郷の数による推定
(2)水田面積による推定
(3)募兵率による推定(十人に一人の徴収)
さて、ここで、しばらく、『魏志倭人伝』に記されている戸数問題をとりあげる。
『魏志倭人伝』に記されている倭人諸国の戸数をまとめれば、最初の方で示した「倭」の諸国の戸数の表のようになる。
この戸数が、実数をあらわしているかどうかは別として、「七万余戸」ほどとされている「邪馬台国」が、人口のそうとうに多い場所であったことはうかがえる。
奈良時代のことを記した歴史書である『続日本紀』によれば恵美押勝(えみのおしかつ)[706~764]が、天平宝字五年(761)に征韓を計画したさい、九州全体で、20,020人の兵士、水手(かこ)をだしている(対馬をふくむ)。
ところで、東国の軍、山陽道、南海道の軍においては、10人の正丁(せいてい)[21歳から60歳までの男子]につき1人という割合で募兵を行なっている。すなわち、東国12国においては、222,800人の正丁に対して、20,620人の兵士、水手(かこ)を募兵している。募兵率は、10.81人に1人である。山陽道、南海道の12国においては、188,100人の正丁に対し、17,420人の兵士、が を募兵している。募兵率は、10.80人に1人である。
以上の、東国12国、山陽道、南海道12国の合計24国では、410,900人の正丁に対して38,040人の兵士、水手を募兵していることになる。募兵率は、10.80人に1人である。
九州でも、この割合で募兵されたとすれば、20,020人の兵士、水手をだすためには、九州に、216,252人の正丁がいたことになる。
一方、わが国の古代の人口の研究において大きな業績を残した沢田吾一氏(1861~1931)が、全国各地の戸籍、計帳から求めたところによれば、良民の人口のなかで、正丁が占める率は、0.1816である(『奈良朝時代民政経済の数的研究』柏書房刊による)。
ここから、九州の奈良時代の良民人口は、1,190,815人と推定される。
沢田吾一氏は、戸籍残簡により、九州地方(西海道)の「奴婢」の人口は、良民人口の約7/100としている。
九州の良民人口を1,190,815人とし、奴婢人口は、良民人口の7/100としたばあい、奴婢などをふくめた九州の総人口は、1,274,172人となる。
八世紀前半の、奈良時代の九州の人口は、このていどと考えるのが、妥当なようである。奈良時代は、班田収授の法が行なわれるなど、一種の国家社会主義が行なわれた時代であった。戸籍調査などが行なわれており、比較的人口などを、推定しやすい時代である。
・奈良時代の人口と邪馬台国時代の人口
以上の九州の人口の推定は、奈良時代のデータにもとづくものである。
この人口の推定値は、邪馬台国時代の人口と、それほど変わりがなかったであろうか。
私は、おそらくは、とくに九州の人口は、それほど大きくは、変わらなかったであろうと思う。
そう思う理由を、以下にのべてみよう。
第一の理由として、古代においては、人口や水田面積の増加の速度は、あまり大きくなかったとみられることがあげられる。
人口や水田面積の増加の速度が、あまり大きくなかったため、数百年を経ても、人口や水田面積は、それほど大きくは変わらなかったようである。
たとえば、『和名抄』という本には、わが国の各国の水田面積が記されている。また、朝鮮でできた『海東諸国記』という本にも、わが国の各国の水田面積が記されている。
『和名抄』は十世紀のはじめ、承平年間(931~938)に成立したものである。一方、『海東諸国記』は、日本へ使者としてきた申叔舟(しんしゅくしゅう)が、1471年にあらわしたもので、わが国の国状などを記したものである。
この二つの書物は、成立の時期に、五百年以上のへだたりがある。
『和名抄』と『海東諸国記』とに記されている水田面積を示せば、下表のとおりである。
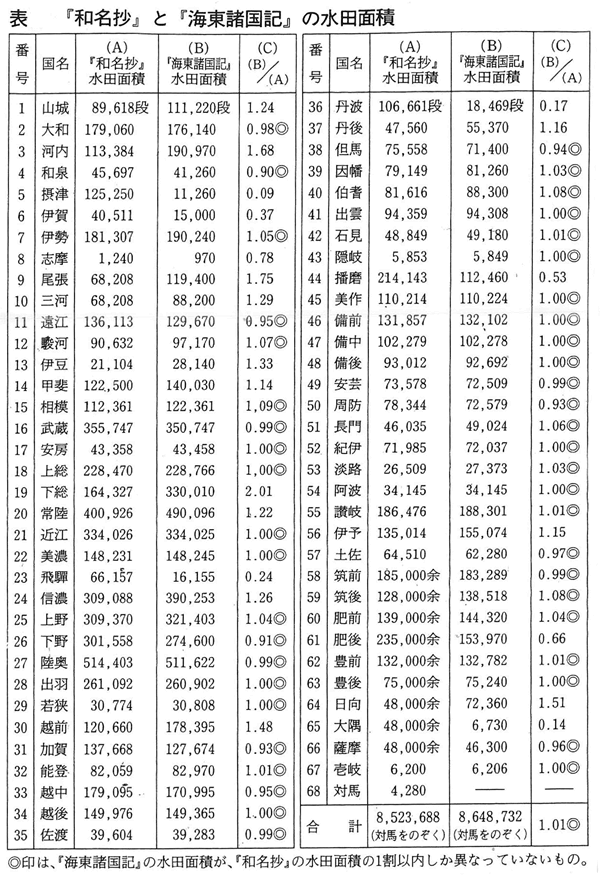
『海東諸国記』の水田面積には、あきらかに、誤記、誤刻と思われるものもふくまれている(たとえば、摂津の国の水田面積は、はじめのほうの数字を、ひとつ書き落としているようである)。
しかし、『和名抄』と『海東諸国記』との水田面積は、全体的には、よく合致している。
上の表(C)欄の数字に「◎印」がつけられているのは、『海東諸国記』の水田面積が『和名抄』の水田面積の1割以内しか異なっていないものである。
67の国のうち、46の国には、「◎印」がつく。すなわち、約7割がたの国においては、水田面積が、1割以内しか異なっていない。
また、合計では、1パーセントほどしかちがわない。
さらに、十世紀にできた『和名抄』に記されている水田面積が、それから二百年さかのぼる奈良時代の水田面積と、それほど大きくは変わらなかったことを示すような証拠もいくつかある。
たとえば、『大日本古文書』には、天平七年(735)の相模(さがみ)の国の26郷ほどの郷の水田面積が記されている。これは、それから200年ほどのちにできた『和名抄』に記されている値と、ほぼ合致している。
沢田吾一氏の『奈良朝時代民政経済の数的研究』には、このような事例がいくつかあげられている。
人口や水田面積の増加の速度が、それほど大きくなかったとすれば、邪馬台国時代と奈良時代(その間の年代差は、約五百年)とでも、とくに、はやくひらけたところでは、人口や水田面積が、それほど大きくは、変わらない可能性がある。
古代においては、新しい田は開墾されたであろうが、河川の氾濫によって田が失われることもあり、その増加の速度は、ゆっくりとしたものであったであろう。
・減少した北九州の人口
奈良時代の人口と、邪馬台国時代の人口とが、あまり大きくはちがわなかったとみられる理由を、いますこしあげておこう。
古代においては、都が別の土地にうつると、もとの都は、急激にさびれていっている。
邪馬台国時代の北九州の人口は、のちの時代にくらべ、相対的に大きかったと考えられる。
そのことをうかがわせる資料が、いくつか存在している。
国立民族学博物館助教授の小山修三氏 は、青森から鹿児島までの各都道府県教育委員会発行の遺跡地図に収められている集落、食糧貯蔵穴、土器大量出土地などの生活跡のデータを、コンピュータにいれ、時代別に分類し、人口の推計をおこなっている。
分析した遺跡数は、縄文期27,996ヵ所、弥生期10,624ヵ所、古墳時代と奈良時代11,803ヵ所である。
そのうちの弥生時代の九州の人口(遺跡)分布図が下の地図である。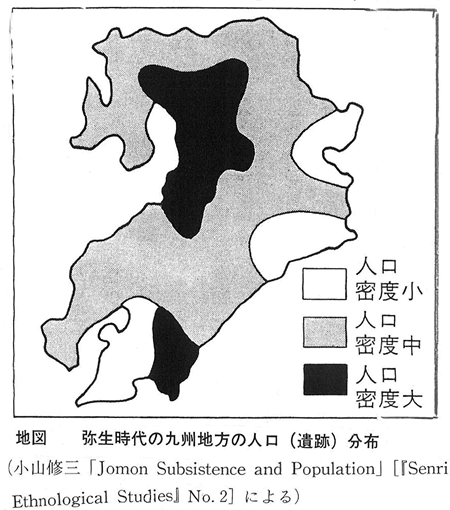
まず、北九州のばあい、奈良時代よりも、平安時代のほうが、各国の郷数がすくなくなる傾向がみとめられる。
古代史家の喜田貞吉(きださだきち)氏は、その著『日向国史』(昭和18年、東洋堂刊)のなかで、『律書残編』と『和名抄』との郷の数を比較し、北九州の郷の数が、奈良時代の初めよりも、平安時代の初期にいって、かえって減少していることを指摘している[古くは、一つの郷が、五十戸で構成されることを基本としていた。『日本書紀』の孝徳天皇の大化元年(645)の条に、五十戸を、「里」とする、とある。715年に、「里」は、「郷」と改称された]。
奈良時代の初期の郷数を、『律書残編』によってしらべる。それを、平安朝初期の『和名抄』の郷数と比較すれば、下の表のようになる(『和名抄』の記す郷の数が、ほぼ9世紀ごろのものであることについては、池辺弥(いけべわたる)氏が、『和名類聚抄郡郷里駅名考証』でのべておられる)。
奈良時代初期と平安時代初期との、両方の郷数のわかる筑後以下の8国においては、奈良時代に406郷であったものが、平安時代初期には、387郷に減っている。
さらに、つぎのような事実もある。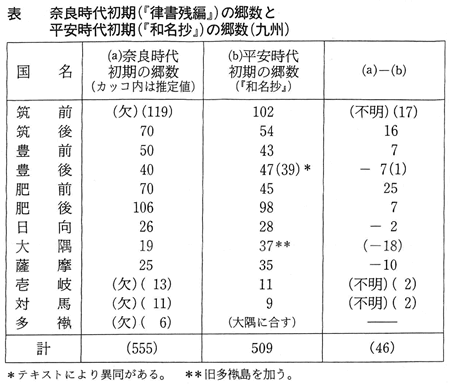
大宝令の規定では、大路の駅馬は、各駅24匹であった。そして、大同2年(807)10月の官符[『類聚三代格(るいじゅさんだいきゃく)』巻十六に記されている]によると、大路である太宰府路の筑前の国の9駅、豊前の国2駅は、はじめ、規定通り、おのおの20匹の駅馬をもったが、
「いま貢上の雑物減少することなかばを過ぎ、逓送(ていそう)の労、旧日よりもすくなく、人馬いたずらに多く、乗用にあまりあり。」
との理由から、各駅5匹減らし、各15匹になったという。
以上のように、のちの時代においても、北九州がさびれる傾向がみとめられるのは、かつては北九州にあった政治の中心が、畿内にうつったなごりではないであろうか。
沢田吾一氏は、奈良時代の壱岐の人口を、約一万人と推定している。一方、『魏志倭人伝』は、壱岐の戸数を、三千ばかりと記している。
もし、邪馬台国時代の壱岐の人口が、一万人よりも、もっとすくなかったとすると、壱岐の一戸あたりの人数が、すくなくなりすぎる。
このような事実も、奈良時代の人口と、邪馬台国時代の人口とが、それほど大きくはちがわなかったことをうかがわせる(もっとも、私は、奈良時代の壱岐の人口は、一万人よりも、もっと多かったと推定しているが)。