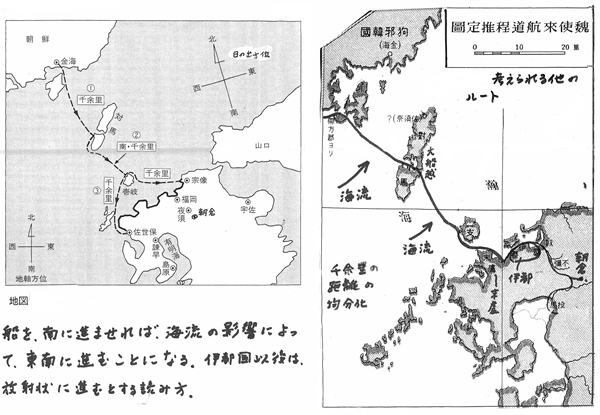■『魏志倭人伝』の里数
〔帯方(たいほう)〕郡(ぐん)従(よ)り倭(わ)に至るには、海岸に循(したが)いて水行し、 〔諸〕韓国(かんこく)を歴(へ)て乍(たちま)ち南し、乍(たちま)ち東し、其(そ)の北岸狗邪韓(くやかんこく)に到る。〔郡より〕七千余里にして、始めて一つの海を度(わた)り、千余里にして対馬国(つしまこく)に至る。其(そ)の大官を卑狗(ひこ)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰う。〔対馬は〕居(お)る所、絶島にして、方四百余里可(ばか)りなり。〔その〕土地は、山険しくして、深き林多く、道路は禽鹿(きんろく)の径(ほそみち)の如(ごと)し。千余戸有り。良田無く、海の物を食(く)らいて自活す。船に乗り、南北に〔ゆきて〕市糴(してき)す。
又(ま)た南して一つの海を渡る。千余里なり。名づけて瀚海(かんかい)と曰(い)う。一大国(いちだいこく)に至る。官を亦(ま)た卑狗(ひこ)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰う。方三百里可(ばか)りなり。竹木の叢林(そうりん)多し。三千許(ばか)りの家有。差(やや)田地有りて、田を耕せども、猶(な)食(く)らうに足らず。亦(ま)た南北に市糴(してき)す。
又(ま)た一つの海を渡り、千余里にして末盧国(まつらこく)に至る。四千余戸有り。山海に浜(ひん)して居(す)む。草木茂り盛(さか)えて、行くに前人〔のかげも〕見えず。魚・鰒(ふく)[あわび]を捕らうることを好み、水は深浅と無く(深さにこだわらず)、皆(みな)、沈没して之(これ)を取る。
東南に陸行すること五百里にして、伊都国(いとこく)に到る。官を爾支(ねぎ)と曰(い)い、副を泄謨觚(えもこ)・柄渠觚(へごこ)と曰(い)う。千余戸有り。
世々(よよ)王有り。皆(みな)、女王国に統属す。〔帯方郡(たいほうぐん)の〕郡使(ぐんし)往来するとき、常に駐(とど)まる所なり。
東南して奴国(なこく)に至る、百里なり。官を兕馬觚(しまこ)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰(い)う。二万余戸有り。
東に行きて不弥国(ふみこく)に至る、百里なり、官を多模(たま)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰(い)う。千余家有り。
南して投馬国(つまこく)に至る。水行すること二十日なり。官を弥弥(みみ)と曰(い)い、副を弥弥那利(みみなり)と曰(い)う、五万余戸可(ばか)り。
南して邪馬壱国(やまとこく)[邪馬台国]に至る。女王の都する所なり。〔投馬国(つまこく)より〕水行すること十日、陸行すること一月なり。官には伊支馬(いきま)有り。次は弥馬升(みまと)と曰(い)い、次は弥馬獲支(みまわけ)と曰(い)い、次は奈佳鞮(なかで)と曰う。七万余戸可(ばか)り。
女王国自(よ)り以北は、其(そ)の戸数・道里、略(ほぼ)載することを得べけれど、其(そ)の余(ほか)の旁国は遠く絶(はな)れて、詳(つまびら)かにすることを得べからず。
〔されども略記すれば〕次に斯馬国(しまこく)有り、次に已百支国(いはきこく)有り、次に伊邪国(いやこく)有り、次に都支国(つきこく)有り、次に弥奴国(みなこく)有り、次に好古都国(こくつこく)有り、次に不呼国(ふここく)有り、次に姐奴国(しゃなこく)有り、次に対蘇国(とさこく)有り、次に蘇奴国(さなこく)有り、次に呼邑国(こおこく)有り、次に華奴蘇奴国(げなさなこく)有り、次に鬼国(きこく)有り、次に為吾国(いがこく)有り、次に鬼奴国(きぬこく)有り、次に邪馬国(やまこく)有り、次に躬臣国(くじこく)有り、次に巴利国(はりこく)有り、次に支惟国(きいこく)有り、次に烏奴国(おなこく)有り、次に奴国(なこく)有り、此(こ)れ女王の〔治むる〕境界の尽(つ)くる所なり。
其(そ)の南には狗奴国(くなこく)有り。男子を王と為す。其の官には狗古智卑狗(くこちひこ)有り、女王に属せず。
[帯方(たいほう)]郡より女王国に至るまで万二千余里なり。
<すこしはなれたあとのほうの記事>
倭(わ)の地〔理〕を参問するに、絶えて、海中、洲島の上に在(あ)り。或(ある)いは絶え、或いは連なり、周旋(しゅうせん)、五千余里可(ばか)りなり。
<現代語訳>
帯方郡から倭に行くには、海岸沿いに船で行き、韓(かん)の国々を通り、あるときは南に向かい、あるときは東に向かってすすむと、倭の北の対岸に当たる狗邪韓国(くやかんこく)に到着する。
帯方郡から、七千里あまり来たところで一つの海を渡り、千里あまり行くと対馬国(つしまこく)に到着する。そこの大官を卑狗(ひこ)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。対馬は離れ小島で、広さは四百余里四方である。土地柄は、山が険しく、深い林が多くて、道は、細くてけもの道のようである。千余戸が住んでいる。よい畑はなく、海産物を食べて生活している。船を使って南北に行き、米などを買ったりしている。
そこから、一つの海を南へ渡ること千里余り、その海を瀚海という。なお壱岐国(いきこく)に到着する。そこの官も卑狗(ひこ)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。広さは三百里四方である。竹や木の繁みが多い。三千軒ほどの人家がある。対馬国(つしまこく)に比べ、いくらか畑があるが、その収穫だけでは生活していけない。それで、この国もまた、南北に行き、米などを買ったりしている。
さらに、一つの海を渡って千里余り行くと、 末盧国(まつら)に到着する。四千戸余りの人家がある。山が海にせまっているので、沿岸すれすれの所に家を造って住んでいる。草や木が繁っており、道を行く前の人が見えないほどである。魚やあわびを獲(と)ることが好きで、海の深い浅いを気にせず、人々はみなもぐって獲っている。
東南に陸路を行くと、五百里で伊都国(いとこく)に到着する。官を爾支(ねぎ)といい、副官を泄謨觚(えもこ)・柄渠觚(へごこ)という。千戸余りの人家がある。代々、王が治めている。以上の国はどれも、女王の国に統治されている。帯方郡の使いが往来するときは、いつも、ここに泊まる。
そこから東南に向かって行くと、奴国(なこく)に到着する。伊都国からの距離は百里である。官を兕馬觚(しまこ)と曰いい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。人家は二万余戸ある。
そこから東に行くと、不弥国(ふみこく)に到着する。距離は百里である。官を多模(たま)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。千余戸の人家がある。
南の方に行くと、投馬国(つまこく)に到着する。船で行って二十日かかる。官を弥弥(みみ)といい、副官を弥弥那利(みみなり)という。五万戸余りの人家がある。
南に行くと邪馬台国(やまたいこく)に到着する。女王の都のあるところである。投馬国から、船で十日かかる。陸を行くと、ひと月かかる。官には、伊支馬(いきま)がある。次の官を弥馬升(みまと)といい、その次の官を弥馬獲支(みまわけ)といい、さらに次の官を奴佳鞮(なかで)という。人家は七万戸余りである。
女王の国から北にある国は、その戸数とか距離のおおよそを書くことができるが、その他の方角の国々は、遠く離れていて、詳しく知ることができない。
しかし、ほぼ記してみると、次に斯馬国(しまこく)があり、次に已百支国(いはきこく)があり、次に伊邪国(いやこく)があり、次に都支国(つきこく)があり、次に弥奴国(みなこく)があり、次に好古都国(こくつこく)があり、次に不呼国(ふここく)があり、次に姐奴国(しゃなこく)があり、次に対蘇国(とさこく)があり、次に蘇奴国(さなこく)があり、次に呼邑国(こおこく)があり、次に華奴蘇奴国(げなさなこく)があり、次に鬼国(きこく)があり、次に為吾国(いがこく)があり、次に鬼奴国(きぬこく)があり、次に邪馬国(やまこく)があり、次に躬臣国(くじこく)があり、次に巴利国(はりこく)があり、次に支惟国(きいこく)があり、次に烏奴国(おなこく)があり、次に奴国(なこく)がある。これで女王の支配する領域が終わるのである。
その南には狗奴国(くなこく)がある。男を王としている。その官には、狗古智卑狗(くこちひこ)がおり、女王には従属していない。
帯方郡(たいほうぐん)から女王国に至る距離は一万二千里余りである。
<すこしはなれたあとのほうの記事>
倭(わ)の地理を聞き合わせてみると、大陸から離れて、海中の島の上にある。倭の国々は、あるものは離れ島であり、あるものは続いていて、五千里ほどである。
この講演会では『魏志倭人伝』を順次読んで行きながら、全部で六つの方法で、「邪馬台国北部九州説」の「証明」を行う。
山にのぼるさい、頂点にいたる道は、いくつもある。
北から登っても、南から登っても、東から登っても、西から登っても、同じ頂点に達しうる。
以下、「小証明」二つ。「中程度の証明」二つ。「大証明」二つ。
■まず、「小証明(1)」・・・・『魏志倭人伝』記載の「里数」による証明。
『魏志倭人伝』は、「(帯方)郡より女王国に至るまで、万二千余里である。」と記している。
朝鮮半島の帯方郡から、女王国までの、総トータルの距離が、「一万二千余里」である、と記されている。
これについて、技術者の、藤井滋氏は、『アジアの古代文化』の、1983年春号(特集「邪馬台国の時代」)にのせられた論文「『魏志』倭人伝の科学」のなかで、およそ、次のようにのべている。
「帯方郡から狗邪韓国までの七千余里、狗邪韓国から末盧国までの三千余里を合計すると、一万余里となる。したがって、末盧国から邪馬台国までは、一万二千余里から一万余里を引いて、二千里ほどとなる。
末盧国から邪馬台国までは、約千五百里から二千五百里の範囲にあることになる。
邪馬台国は、末盧国から一大国(壱岐)までの距離よりは遠く、狗邪韓国よりは近い所にあることになる。これを図示すれば下の地図のようになる。この地図は、帯方郡から邪馬台国までの二万二千余里のもっとも単純、明快な解答である。それゆえ、下の地図の範囲外に、邪馬台国を比定する論者は、その正当な理由を、明示する必要があると思う。」
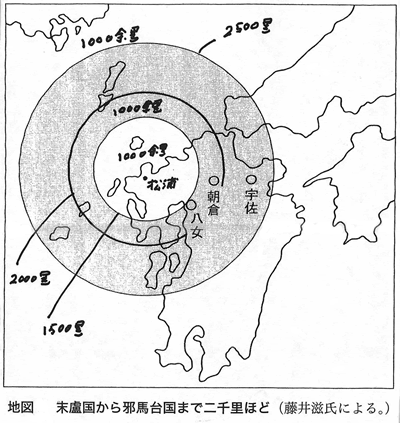
これは、『魏志倭人伝』の記述に即した読み方である。
「『魏志倭人伝』には、「南して投馬国に至る。」とか、「南して邪馬壱(台)国に至る。」とか記されている。「畿内説」のように、この「南」というのは、じつは、「東」のことを指すのである。」といったような、「解釈」や「改変」を加える必要はない。このような読み方は、「勝手読み」である。『魏志倭人伝』に即した読み方ではない。
・方向記事
『魏志倭人伝』 は、「伊都国」と、「女王国」との位置関係を、三度にわたって記す。
すなわち、次の三度である。
(1)『魏志倭人伝』の記す旅程では、伊都国を経て、終わりは、「南、邪馬台国にいたる。女王の都するところ」と記している。
順路の読み方は、「順次式」 「放射式」などがあるが、大略、「邪馬台国」は、「伊都国」の南にあったことになる(下の図参照)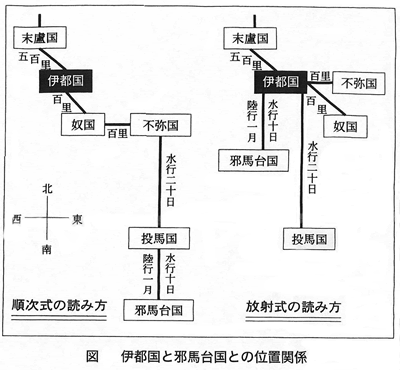
(2)『魏志倭人伝』は、「女王より以北は、その戸数・道里は略載するを得べし」と記す。
戸数・道里を略載されているのは「対馬国」「一支国」「末盧国」「伊都国」「奴国」 不弥国」である。これらは「女王国の以北」にあったのである。
すなわち、「女王国」は「伊都国」の「南」にあったのである。
(3)『魏志倭人伝』は、また記す。「女王国より以北には、とくに一大率をおいて、諸国を検察させている。(一大率は、)つねに伊都国に(おいて)治めている。」
ここでも、「伊都国」は、「女王国」の北だと記されている。つまり、女王国は、「伊都国」の「南」だというのである。『魏志倭人伝』に三度にわたって記されている「伊都国」と「女王国」との位置関係についての方向記事は、三度とも誤りだというのであろうか。『魏志倭人伝』の「南」は、「東」の誤りなどと、そんなに簡単にのべてよいのであろうか。
『魏志倭人伝』は、「里数」も「方向」も、何度も念をおすような書き方をしている。
そのような記事こそ、書きまちがいなどの可能性がよりすくなく、より信頼できる記事とみるべきである。
邪馬台国については、「女王国=邪馬台国」とする説と、「邪馬台国は、女王国の一部で、首都のある場所」とする説がある。いずれのばあいも、邪馬台国は、伊都国の南にあることになる。
「邪馬台国論争」は、『魏志倭人伝』の記事をもとにして起きている。
『魏志倭人伝』に記されている事物の出土状況も、位置情報も無視して議論してよいのであれば、どんな議論でもできてしまう。
『魏志倭人伝』の記述を無視する邪馬台国論争は、空理空論と言うべきである。
水野裕(みずのゆう)[本名、水野正圀(まさくに)]著『評釈魏志倭人伝』(雄山閣、1987年刊)11ページ
「〇周旋可五千里 「周旋」はめぐるの義で、実地についてまわり行くという意味である。倭国の地を一巡すると五千余里であるという。この周旋五千余里はどこからきた数字かというと、前に記した郡より女王の境界の尽きる所までが一万二千余里、郡より狗邪韓国までが七千余里。それで狗邪韓国つまり倭の北限から女王国の南限までは、一万二千余里から七千余里を差引いた五千余里となる。従来この周旋を周囲とか一周する義としたのは誤りであり、山田博士の説のごとく、自己が旋転する義で物の大きさではない。」
参考:山田孝雄(やまだよしお)(1875-1958)明治一昭和時代の国語学者。明治8年8月20日生まれ。論理学をとりいれて山田文法を構築し、「日本文法論」をあらわす。さらに「平安朝文法史」「五十音図の歴史」で独創的な研究をしめした。また「平家物語考」「国学の本義」など、国文学、国史学にも業績をのこした。東北帝大教授、神宮皇学館大学長、国史編修院長などを歴任。昭和32年文化勲章。昭和33年11月20日死去。83歳。富山県出身。富山中学 中退。
山田孝雄氏は「狗奴国考」(『考古学雑誌』第十二巻第一号、大正十一年(1982)七月(佐伯有清編『邪馬台国基本論文集Ⅰ』(創元社、1981年刊にも所収)で下記のように述べている。
「加之周旋の文字は、本来他を纏繞(てんじょう)[まつわりつく]するにあらずして、自己が旋転(せんてん)[めぐり転ずる]するの義なり。今その用例を示さんが為に、佩文韻府中の周旋の字例を悉く掲出して証とすべし。
進退周旋慎斉(礼記)
(中略)
陸廻阜転山高隴長周旋逶迤形似書字(武帝内伝)
(中略)
以上の例にて、自ら旋転して、行動する義にして、物の大さをいふ語にあらざるをさとるべし。さればこゝの周旋もまた武帝内伝の周旋逶迤の字の用法と同じく、紆余屈曲五千余里に連亙(れんこう)[つらなりわたる]すといふべきに似たり。
加之海中州島之上とあるは、益九州一島をさせるにあらずして、多数の州島に跨(またが)りて国をなせるものなるべきを知るべきにあらずや。さて周旋五千余里の周旋の意義明になりたる以上は郡より狗邪韓国に至るまでの七千余里とこの倭地の周旋五千余里と合せて、郡より女王国に至る万二千余里の里数と相一致するに於ては、たとへその里程の単位は疑問なりとすとも、かの筆者の胸中には合理的の推算を下したるものにして、之を顧みずして、誤算なり虚偽なりなどの論を公表するの士は須らく三省を要すべきなり。」
『魏志倭人伝』は里数について、何度も書いてあり、証明になる。
■「小証明」のみでは、不十分
共産中国の建設者、毛沢東(もうたくとう)は、かつてのべた。
「揚子江(ようすこう)は、あるところでは北に流れ、あるところでは南に流れ、あるところでは西にすら流れている。しかし、大きくみると、かならず西から東へ流れている。」
このことばは、歴史の流れについてのべたものであるが、学問的探究についても、よくあてはまる。
ある特定の岸辺に立った観測にもとづく「部分的真実」は、かならずしも、「全体的真実」とは合致しない。
「天動説」と「地動説」。家の中の床が平であることが証明されても、地球の地表が平らであることの証明にならない。
周、春秋、戦国、前漢、後漢、隋などにおいては、六尺が一歩であり、三百歩が標準の一里であった。ただし、一尺の長さや一里の長さは、時代が後代になるにつれ、しだいに長くなる傾向がみとめられる。
たとえば、下の表は、長さの単位の時代別変遷表で、『角川漢和中辞典』(貝塚茂樹、藤野岩友、小野忍編)にのせられているものである。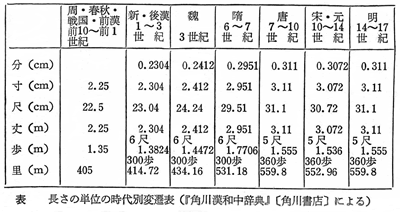
田中卓著『邪馬台国と稲荷山刀銘』(田中卓著作集3、国書刊行会、1981年刊、142ページ)
「これらの数字は決して厳密な意味で正確とはいへない。しかし、およその見当をつけることには役立つであらう。そして、(イ)から(ト)にいたる『倭人伝』の里数を概観すると、それぞれの区間の比率については、それほど大きなアンバランスはみられないから、冨来隆氏も認めてゐるやうに、各国間の距離の比率的な長さとしては、だいたいに妥当するとみてよい。
そこで、仮りの計算であるが、『倭人伝』の一里をそれぞれの区間においてメ-トルに換算すると、(D)の欄に示したやうになる。そこで最短と最長の両方をしめした(ロ)・(ハ)・(ニ)・(ホ)については、まづその平均をだすことにして、それぞれ(ロ)130、(ハ)100、(ニ)45、(ホ)78メートルと仮定すると、(イ)から(ト)までの合計は657メートルとなる。これを区間の数の7で割ると、93.857メートルだから、まづは〈1里=90~100メートル〉と考へておかう。」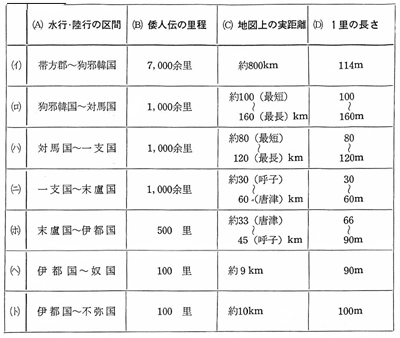
・小澤毅(おざわつよし)(三重大学教授)「『魏志』が語る狗奴国と邪馬台国の所在地」(『季刊邪馬台国』13号、2020年12月、梓書院刊)による
「海の東の「倭種」の国
「女王國東渡海千餘里復有國皆倭種(女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、皆倭種なり)」という『魏志』の記述が、あらためて注目される。これこそは、女王国の東に海を隔てて、別の「倭種」の国々が存在したことを明示するものにほかならず、それらが本州西端部や四国にかかわることは確実とみられる。
この点に関しても、畿内説では合理的な解釈が困難だが、魏と通交をもち、『魏志』に「倭種」の国とは区別して記された倭の領域は、九州の範囲におさまると判断せざるをえない。
『魏志』が記す倭国
したがって、邪馬台国をはじめとする倭の国々の所在も当然、その中で論じられるべき問題であり、ほかの地域、たとえば近畿地方がいかなる状況であったにせよ、本質的には何ら関係がない。」
「末慮国や伊都国、奴国など『魏志』所載の「国」の多くが、令制下の国より小さな、郡に相当する程度の領域とみられる点からも、これらの「国」やその連合体の規模をさほど大きく見積もることはできまい。当時の日本列島は、九州内部でも邪馬台国と狗奴国の間で深刻な抗争がつづいていたように、いまだ政治的統合とはほど遠い段階にあったのである。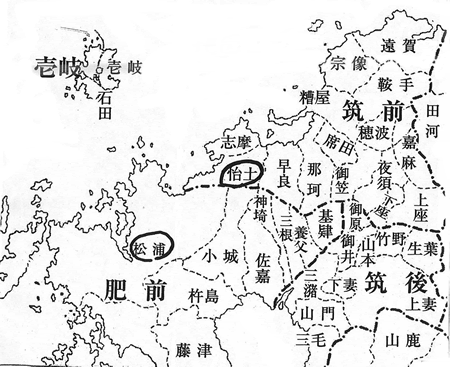
「水行十日、陸行一月」
ところで、『魏志』は、投馬国への道程を水行二十日、の実見に基づく可能性が高いこととあわせて、そうした国内の巡検と情報収集にも一定の日数を要したとみるべきだろう。
もちろん、彼らを迎えての接待や、その準備のために滞留した期間、彼らが次に向かう国や、ときには邪馬台国との間での使者の往来もあったはずである(ただし、『魏志』が記す上記の日数を、そのまま実数としてよいかは疑問があり、この点については後述する)。
参考資料として後代の一例を挙げると、推古十六年(608)、隋使裴世清(はいせいせい)は、小野妹子に従って四月に筑紫に到着し、六月一五日に難波津(なにわづ)の客館に入っている。都である飛鳥へ入ったのは八月三日で、筑紫から難波、難波から飛鳥への移動に、それぞれ一ヵ月半以上を費やしたことになる。そこには、使節を迎えるにあたってのいろいろな準備のほか、朝廷内の争論もあったわけだが、ともあれ、外交使節の来朝と謁見には、それなりの時日が必要であったことをうかがわせる記録といえる。」
「邪馬台国へのそれを水行十日、陸行一月と記しており、九州内に両国を求めた場合、この日数が過大であるとする評価がしばしば見受けられる。
たしかに、『魏志』が、距離をほぼ確定しうる区間に対して別に所要日数を示し、それとの比較から論じられるのであれば、こういった議論は有効かもしれない。ところが、魏使が帯方郡を発したのち、里数をもって記された伊都国ほかの国々まで道程に、どの程度の日数を要したかは、どこにも示されていないのである。したがって、『魏志』から距離と日数の関係を直接うかがうことができない以上、そこに記された日数を単純に過大と評価する論理は成り立たないと考える。
別段、魏使は休みなく行程を急いだとはかぎらないし、また、それが許される状況にあったかどうかも判然としない。むしろ、倭の国々の習俗に関する記事の多くは、魏使の実見に基づく可能性が高いこととあわせて、そうした国内の巡検と情報収集にも一定の日数を要したとみるべきだろう。」
・謝銘仁博士の読み方
邪馬台国へいたる旅程記事のうち、「水行十日、陸行一月」という語句は、論争におけるつまずきの石の一つであった。
これまで、この語句は、次の二つの読み方の、いずれかに読まれてきた。
「水行十日して、しかるのち、さらに陸行一月。(水行十日と、陸行一月とは、andでつながるとみる。)」
「水行十日、または、陸行一月。(水行十日と陸行一月とは、同じ旅程を、二とおりの形で表現したものとみる、水行十日と陸行一月とは、orでつながると考える。)」
台湾の文献学者、謝銘仁博士は、その著『邪馬台国 中国人はこう読む』(立風書房、1982年刊)のなかで、このいずれの読み方も、違っているであろうという。
謝銘仁博士は、これについて、事例を示し、くわしい根拠をあげて、次のようにのべる。「『水行二十日』『水行十日』『陸行一月』は、休日・節日や、いろいろな事情によって、ひまどって遅れたり、鬼神への配慮などから道を急ぐのを控えた日々をひっくるめた総日数に、修辞も加わって記されたものである。決して実際にかかった”所要日数”のことを意味しているのではない。」[注:役人は五日ごとに一日の休暇(遅くとも漢代から)]
「この日程記事は、先に水路を『十日』行ってから、引き続いて、陸路を『一月』行ったという意味ではない。地勢によって、沿海水行したり、山谷を乗り越えたり、川や沼地を渡ったり、陸地を行ったり、水行に陸行、陸行に水行をくり返し、さらに、天候や交渉事のために進めなかった日数や休息・祭日その他の日数を加え、その総計を大ざっぱながらも、整然とした『十日』『一月』で表記したのであろう。」
つまり、魏使の道程には、水行の部分、陸行の部分、さまざまな部分があり、その水行の部分を合計すれば、「水行十日」となり、陸行の部分を合計すれば、「陸行一月」となるという意味であるとする。「水行十日、陸行一月」は、かかった総日数であって、実際に旅行し、進みつづけた日数ではないであろうとする。
謝銘仁博士の見解にしたがえば、「水行十日、陸行一月」のような日数記事によっては、魏使が進んだ実際の距離は、知りがたいことになる。
以上を要するに、「里程記事」のほうは、『魏志倭人伝』に記されている「里程記事」と、現代の地図とを照らしあわせれば、一里が、ほぼどれぐらいの距離を示しているか、およその見当がつく、ということである。
いっぽう、「日数記事」のほうは、一日にどれぐらいの距離をすすんだのか、『魏志倭人伝』によったのでは、知るべきすべがない。
とすれば、「里程記事」にもとづいて、邪馬台国の場所を、たずねるべきである。
・里程問題の検討--地域的短里説
諸家の見解は、魏使が倭国をおとずれた季節を、まず例外なく、夏であったとする。そのおもな理由は、つぎのとおりである。
(1)朝鮮半島から対馬島に渡るばあい、日照時間の長い夏でないと、日のあるうちにつくことができない。3ノットの速力で、約12時間以上かかり、朝五時に出航して、夕方6時すぎにつくことになる。
(2)冬季の航海は、季節風が連吹するので、波が高く、小型船にとって危険である。
(3)『魏志倭人伝』に記されている方位は、夏季の日の出方向を東とする方位に、大略一致している(日の出方向は、6月22日前後の夏至のころ、約30度、北にずれる)。
(4)冬季では、冷たい飛沫や風をあびることになり、漕ぎ手の手がかじかんで、十分な力がだせない。また、難破は、凍死につながる。
現在では、学校教育の結果、温度をはかるのには、ほとんど摂氏が用いられる。しかし、かつては、わが国でも、摂氏と華氏とが、併用された。
そして、暑さを強調したいときだけ、「炎熱百度の猛暑」などと、華氏の100度(摂氏約38度)が、やや熟語的に用いられたりした。
学校教育の普及のため、現在では、いろいろなモノサシが、統一されてきている。そのため、さまざまなモノサシが、平行的に用いられていたころの状況を、実感しにくくなっている。
わが国でも、かつて尺貫法が行なわれていたころ、「尺」の単位には、「曲尺(かねじゃく)」の1尺と、「鯨尺(くじらじゃく)」の1尺とがあった。「曲尺」の1尺は、「鯨尺」の8寸で。あった。「曲尺」は、おもに、大工などによって用いられ、「鯨尺」は、おもに、和裁など布の寸法をはかるのに用いられた。
古い時代に、中国あるいはその周辺において、地域的に、あるいは、特定の時代に、あるいは、特定の測定対象のために、あるいは、特定の職業の人々によって、さまざまなモノサシが行なわれた可能性は、十分にある。
私は、中国の古代に、特定の条件のもとで、「短里」が存在したとするならば、それは、おそらく、60歩をもって一里とするような単位であったであろうと考える。そう考える理由は、つぎの通りである。
(1)前のほうの表「長さの単位の時代別変遷表」にみえるように、古い時代、300歩1里の標準里では、1里の長さは、405メートルであった。したがって、60歩1里の「短里」では、約81メートルほどとなる。
この値は、『周髀算経(しゅうひさんけい)』の一里約77メート、下の表の『魏志』「倭人伝」の実測値と比較したばあいの1里約93メートル弱などに近い。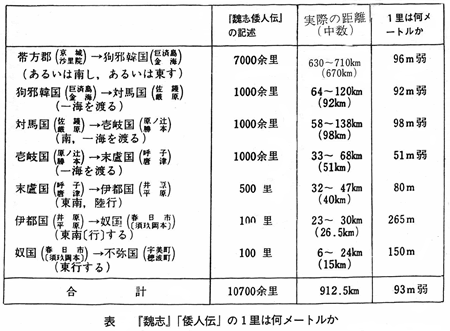
(2)長さの単位が、歩と標準里との間で、ややあきすぎているように思われる。わが国でも、かつて、1町(60間、360尺、約109メートル)という単位の行なわれたことがあっ
た。現在でも、100メートルという単位は、私たちの生活感覚になじみやすい。村落ていどの大きさに、まとまって生活していたばあい、百メートル前後の長さの単位が、必要であるように思われる。
[日本]
1町=109m
1里=36町(上方、西国)(面積の単位との混同)
=3.9Km(地域的長里)
1里=6町(東国)
=654m
下の表から1里が何町か?結構バラバラである。
(3)6尺が1歩、60歩1里とすると、1里は。360尺である。前のほうの表「長さの単位の時代別変遷表」の長さの単位の時代別変遷表にみられるように、唐、宋、元、明代には、360歩が1里であった。中国古代においても、6尺が1歩であり、6進法による単位は、考えつきやすいと思われる。
(4)前のほうの表「長さの単位の時代別変遷表」にみられるように、時代によって、1里は、300歩であったり、360歩であったりする。里と歩との結びつきは、時代によって動くなど、やや不安定である。
なお、白鳥庫吉氏は、その論文「卑弥呼問題の解決」の中で、「倭人伝」の1里が、60歩ていどであることを、「誇張説」の立場から、すでにのべている。すなわち、「倭人伝」の里を、魏のふつうの里とくらべると、「約五倍の誇張がある」とのべている。
また地理学者、藤田元春氏は、その著『上代日支交通史の研究』(刀江書院、昭和十八年刊)の「魏志倭人伝の道里について」の章で、「誇張説」をとらず、「魏略時代に書紀された多くの倭韓の里」は「古周尺の尺度」としている。私の考えは、藤田元春氏の考えに近い。
元禄(げんろく)時代に。オランダの医師として来日したドイツの博物学者ケンペルは、『日本誌』をあらわした。その中の長崎から江戸までの経路をのべたところで、ケンペルは、つぎのように記している。
「日本の里程では、里という長さは一定しない。九州島および伊勢の国では、50町をもって1里とし、その他では、一般に36町をもって1里としている。」
また、戦前の本であるが、陸軍中将であった吉田平太郎氏は、その著『蒙古(もうこ)踏破記』において述べている。
「一寸(ちょっと)支那里につき一言すべし。支那の六、七里が日本の一里に相当する所と、十里が一里に当る所とありて一定せず。」
千数百年まえ、日本よりも広い中国において、時代的、地域的にさまざまなモノサシが用いられた可能性がある。
晋(しん)代の陳寿は、直接日本に行ったわけではない。陳寿が利用しえた資料には、さまざまなものがあったであろう。晋王朝が魏王朝からうけついだ資料(魏から晋へは、禅譲という形で政権がうつっている)、帯方郡の役人がもっていた資料、倭国に使した梯儁(ていしゅん)の報告、魏が滅ぼした公孫氏のもっていたもの(公孫氏は、朝鮮半島北部に支配権をもった)、王沈(おうしん)撰の『魏書』、魚豢(ぎょかん)の『魏略』などの史書、(『魏略』は『三国志』の先行史書ではないとする見解があるが、私はこれに従わない。)(白崎昭一郎著『東アジアの中の邪馬臺国』73ページ以下の考証参照。)・・・・
そして、私は、陳寿が、もとの史書・資料にあった「里数」は、それを尊重し、そのまま『三国志』にのせた可能性が大きいと思うのである。また、陳寿が、どの地方でどのような里制が行なわれていたかを正確に知り、それらを、統一的に換算することは、困難であったであろうと思うのである。現在とちかって、一尺をあらわすモノサシでさえ各地で、すこしずつ異なっていた可能性がある。中国の古尺は、いくつか現存するが、同一時代のものでも、長さがすこし異なっているものが多い。
一般に、ことばや習俗は、中央部からしだいに周辺部におよび、そのことばや習俗が、中央部で滅びたのちにも、周辺部に残ることが多い。これは、柳田国男氏の「周圈論」である。仏教などでも、インドの仏教の生まれた地域では、ヒンズー教にとってかわられ滅びてしまった。
そして、遠くはなれた日本では残っている。
私は、周、春秋、戦国の時代に(ある地域で)、行なわれていた「短里」が、三国時代においても、朝鮮半島南部を中心とする中国周辺で、地域的に行なわれていた可能性が大きいと思うのである。
以下では、そのように思う根拠を、整理してみよう。
明治43(1910)年8月に、藤井甚太郎(1883~1958)は、「邪馬台国の所在に就(つい)て」(『歴史地理』)という論文を発表した。
藤井甚太郎は、今日、おもに、明治維新史の研究によって知られるが、二十歳代においては、邪馬台国関係についてのいくつかの論考を発表している。藤井甚太郎は、のちに、歴史地理学会の会長や、実践女子大学、法政大学の教授となった人である。また、『歴史地理』は、のちに京都大学教授となった喜田貞吉によって創刊された雑誌である。
藤井甚太郎は、「邪馬台国の所在に就(つい)て」の中で、末盧国を、「肥前の国松浦郡呼子付近から、唐津河口におよぶあたり」と推定し、伊都国を、「筑前の国糸島郡の郡村、周船寺村のあたり」とし、奴国を、「筑前の国安徳村のあたり」にあて、不弥国を、「筑前の国糟屋(かすや)郡宇美」にあたるとした。そして、この四つの推定地から、およそ、つぎのように述べる(原文は文語文)。
「その間の里程を考察すると、末盧国・伊都国間で、約15、6里(約59~63キロメートル)、伊都国・奴国間で、約3里(約12キロメートル)、奴国・不弥国間で、約2、3里(約8~12キロメートル)であって、『魏志』の五百里といい、百里というのと、ほぼ比例している。『魏志』の1里は、わが国の1町(109メートル)ばかりと推定できる。」
そして、帯方郡から女王国まで一万二千余里のうち、不弥国までで、一万七百里をついやしているので、残りの千三百余里が、不弥国から邪馬台国までの距離であると考えた。すなわち、邪馬台国は、不弥国から、百四十キロほどのところにあると考えた。
また、東京大学の白鳥庫吉は、昭和23(1948)年に、論文「卑弥呼問題の解読」を発表し、『魏志倭人伝』の里程記事には、誇張がある、としたうえで、つぎのように述べる。
「狗邪韓国(金海)・対馬国間、対馬国・一支国(壱岐)間、一支国・末盧国(松浦郡)間を、おのおの千余里とする割合、帯方郡(漢江下流域)・狗邪韓国(金海)間を七千余里とするのに対して、狗邪韓国・末盧国(松浦郡)間が三千余里となる割合のごときは大体において正鵠(せいこく)を得ている。」
白鳥庫吉も、藤井甚太郎と同じく、一万二千余里から一万七百里をさし引いた残りの千三百余里を、不弥国から邪馬台国までの距離とした。
また、白鳥庫吉は、つぎのようにも述べる。
「魏代の一里は漢代の一里と大差がなく、漢の一里は、ほぼわが国の三町四十八間(414メートル)にあたるとみて大過ないと思われる」
そして、『魏志倭人伝』の里を、魏のふつうの里とくらべると、「約五倍の誇張がある」と述べている。すなわち、白鳥庫吉は、『魏志倭人伝』の一里は、83メートル程度であるとした。
山梨大学、立命館大学などの教授であった地理学者、藤田元春(1879~1958)は、昭和18(1943)年に、『上代日支交通史の研究』という本をあらわしている。その本には、「魏志倭人伝の道里について」という章があり、『魏志倭人伝』の里程が考察されている。
藤田元春は、「誇張説」をとらず、「魏略時代に書記された多くの倭韓の里」は、「古周尺の尺度」としている。藤田元春は、江戸中期の儒家、国学者、松下見林(1637~1703) のあらわした『異称日本伝』の中の、
「日本の薩摩州と浙江(せっこう)は、あい対す。対馬と朝鮮はあい対す。(対)馬島から釜山(ふざん)にいたる約五百里、対馬島から一岐島に至る六百里、一岐から護屋(なごや)島にいたる五百余里。」
とある里数など、後の一里の長さにくらべ、はるかに短いとみられる里の例をいくつかあげ、『魏志倭人伝』の道里も、実地に基づいて記された数であろうとする。
そして、わが国において、地域によって、1里が36町であったり、50町であったり、42町であったり、5町であったり、6町であったり、不定ではあるが、それなりの標準があったことを述べ、『魏志倭人伝』の道里も、それほど不確実なものではないであろうとする。
藤田元春は、およそつぎのように述べる。
「道里というものは、いったん定まると容易にかわらないといえる。したがって、『魏志』の道里なども無暗(むやみ)に記したものではなく、おそらく魏以前のよほど古い時代の言い伝えではなかったかと考える。漢代の一里は、およそ四百メートルである。しかし、日本は遠い国であって、漢代においては中国本土の尺よりも、さらに古い尺を用いていたのではなかったか。漢尺よりも、古い尺は、周尺である。」
そして、いくつかの仮定をおいたうえではあるが、藤田元春は、つぎのように述べる。
「魏略時代に書き記された多くの倭韓の里は、すべて今の日本里の四十倍(すなわち、魏略時代の倭韓の一里は、約百メートル)という 周尺の尺度で、全部明瞭に説明がつく。」
以上をまとめると、実測値と比較するとき、『魏志倭人伝』の一里の長さは、つぎのようになる。
(1)藤井甚太郎……109メートル程度。
(2)白鳥庫吉……83メートル程度。
(3)藤田元春……100メートル程度。
三氏とも、ほぼ近い。
『魏志』の「倭人伝」および「韓伝」の一里が、中国本土内の二地点間の距離を記載するさいの一里にくらべ、きわめて短い理由としてあげられているものをまとめると、つぎの二つとなる。
(A)白鳥庫吉の「誇張説」帯方郡の役人たちは、倭国を、帯方からはるか遠方におこうとした。そのために、誇張が行なわれたとする。
(B)藤田元春の「地域的短里説」倭韓において、1里=100メートル程度の短里が行なわれていたとする。
白鳥庫吉氏は、明治四十三年に発表した論文「倭女王卑弥呼考」のに中で、つぎのように、のべている。
「『魏志』がここ(倭人伝)に示している里数は、ところにより伸縮があるにしても、その全道程を通じて、ことごとく普通の標準里よりも縮小であるので、あるいは、これをもって、魏時代に行なわれた制度であったと考えるものもいるかもしれない。」(原文は、文語文。岩波書店『白鳥庫古全集』第一巻)
このように、白鳥庫吉氏は、「魏志倭人伝」が、あるいは、特別の里制によるのではないかと疑った最初の人であった。
しかし、白鳥氏は、「魏志」の「高句麗伝」「夫余伝」などに記されている里数を、実測値とくらべ、それが、標準里によっていることから、みずから提出した疑問を、みずから否定した。
しかし、私は、やはり、「魏志」の「韓伝」「倭人伝」の里数は、短里である可能性が残されていると思う。
・「誇張」としては、規則的にすぎないか
「韓伝」「倭人伝」にあらわれる里数値は、 ぎのように、14列にのぼる。
(1)韓……方可四千里。
(2)帯方郡→狗邪韓国……七千余里。
(3)狗邪韓国→対馬国……千余里。
(4)対馬国……方可四百余里。
(5)対馬国→一大(支)国……千余里。
(6)一大(支)国……方可三百里。
(7)一大(支)国→末慮国……千余里。
(8)末慮国→伊都国……五百里。
(9)伊都国→奴国……百里。
(10)奴国→不弥国……百里。
(11)帯方郡→女王国……万二千余里。
(12)女王国の東に、千余里を渡海すると、また国がある。みな倭種である。
(13)女王国→侏儒(しゅじゅ)国……四千余里。
(14)倭の地……周施すること五千余里。
このうちに、明確に長里といえるものは一つもなく、逆に、実測と比較して、短里が妥当すると考えられるのは、(1)~(9)までと、(11)の10個である。(10)も短里が妥当すると考えられるが、不弥国の位置を確定しがたい。(12)(14)なども、短里が妥当するとみた方がよいものである。
「韓伝」「倭人伝」の里数の大きすぎることは、山尾幸久氏、白崎昭一郎氏その他多くの人のみとめるところである。これらの里数が大きい理由として、「誇張」「誇大」を考える説がある。
しかし、「誇張」「誇大」とするには、すこし、規則的すぎないであろうか。「誇張」「誇大」であるならば、標準里との倍率が、もっと、デタラメであってもよさそうである。もし、机上で、一定の比率をかけるほど、数値がととのっているのであるならば、わざわざそのような計算をするよりも、もとの数値を、そのまま記しそうなものである。
「誇張」「誇大」説をとるためには、原資料の数値を、だれかが、ほぼ五倍するという操作を、行なったとしなければならない。とすると、原資料に、「余里」などのあるものの処置を、どうしたのであろうか。
私には、そのような、人為的な操作があったと考えるよりも、地域的に行なわれていた短里ではかられた数値が、原資料にあり、それがそのまま「魏志」に記されたと考える方が自然であると思えるのである。
■『周髀算経(しゅうひさんけい)』について
中国の古典においては、『魏志』の「韓伝」「倭人伝」以外にも、あるいは、「短里」によって記されているのではないかと疑われる事例が、いくつかある。
つぎに、そのような事例の、いくつかを示す。
まず、はじめに、『周髀算経』にのっている「里」の例をあげる。
これについては、京大の工学部出身の若い技術者谷本茂氏が、「『周髀算経』之事」と題する論文を、『数理科学』1978年3月号にのせておられる。
以下に、谷本氏の論文の要点を紹介する。
『周髀算経』は、中国最古の天文算術書といわれており、紀元前十二世紀ごろの、周時代に行なわれた天文観測の方法を記載している。漢から、三国時代にかけて整理され、教科書として使用されていた模様である。
『周髀算経』の名が、はじめて現われるのは、『隋書(ずいしょ)』「経籍志」である。
また、現在の『周髀算経』二巻(上・下)版本においては、冒頭に、漢趙君卿(ちようくんけい)注、北周甄鸞(けんらん)重述、唐李淳風(りじゅんぷう)等奉勅注釈とある。
初めて注釈した趙君卿が何時代の人かは、明らかでないが、後漢末から、せいぜい、魏晋にかけての人ではないかといわれている。
『漢書』「芸文志」には、『周髀算経』の名は見えないので、前漢以前には、現存のような形では知られていなかったようである。
後漢の蔡邕(さいよう)の『表志』(『後漢書』「天文志」注の引用)には、「周髀」の語がみられる。また、『周髀算経』中の、暦法上の定数は、ほとんど、後漢四分暦と同じである。また、二十四気の名称順序も、同一である。このようなことから、後漢時代には、『周髀算経』の現存の書の、前身のようなものが存在していたと考えられる。
『周髀算経』の本文を見ると、明らかに、同一時代に同一の人の手によって成立したとは思われない文面が存在する。
熊田忠亮氏の『周髀算経の研究』(東方文化学院京都研究所刊、1933年)によれば、天文学的にみて、西暦紀元前1122年(初周)の前後百年ばかりの間においてのみ観測しうる天象や、春秋時代中期以後、戦国時代初期の間に起源をもつとみられる内容のものがある反面、後世後漢時代の知識も、多分に含まれているという。
『周髀算経』の成立に関して、以上のようなことをまとめると、つぎのようになる。すなわち、この本にみえる概念や方法の起源は、相当に古い。そして、周以来伝承されてきた種々の天文算術知識を集成して、後漢末前後に、最初の注釈者、趙君卿により、現存のような形に整理されたとみて、大過ないと考えられる。
さて、『周髀算経』上巻は、周公(周の武王の弟)と、商高(しょうこう)[当時の賢大夫]の問答からはじまる。ここでは、天文観測の方法の基礎が、「勾股弦(こうこげん)の法」などとして述べられている。「勾股弦の法」とは、「ピタゴラスの定理」のことである。
直角三角形の、直角を挟む短辺を、「勾」という。長辺を、「股」という。斜辺を、「弦」という。
この本の書名の、「周髀」の「髀」は、八尺の棒のことである。周代に、天子が、これを地面に垂直に立てて、「股」とし、その太陽による影を、「勾」として、各種の測量を行なった。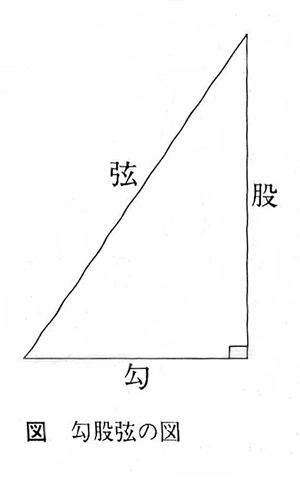
・一寸千里の法
周公と商高の問答に続いて、栄方(えいほう)と陳子(ちんし)の問答がでてくる。栄方と陳子は、周公より時代的に後の人であるが、何時代の人かは不明である。
ここでは、『周髀算経』の天文観測において、測量の公理である「一寸千里の法」が説明される。
「一寸千里の法」とは、つぎのようなものである。
(1)周髀長八尺夏至之晷(き)一尺六寸。[晷(き)は、影のことである。]
周の地において、夏至の日、八尺の長さの棒を垂直にたてると、その影の長さは、一尺六寸である、というのである。
(2)髀者股也正晷者勾也。
垂直に立てた八尺の棒(髀)が、直角をはさむ長辺「股」であり、その影が、直角をはさむ短辺「勾」である、というのである。
(3)正南千里勾一尺五寸。正北千里勾一尺七寸。
もとの地から、南千里の地では、影は、一尺五寸である。北千里の地では、影は、一尺七寸である、というのである。
(4)法日周髀長八尺勾之損益寸千里。
よって、髀の長さ、すなわち「股」八尺に対する「勾」の差一寸は、地上の距離にして、千里にあたる。これが、「一寸千里の法」である。
・『周髀算経』の里単位
『周髀算経』においては、天地のあらゆる里数値は、公理的命題である「一寸千里の法」から導きだされている。
そして、『周髀算経』においては、一貫して、同じ里単位が用いられている。(谷本氏のこの見解には、やや疑問点もある。---安本)
ところが、『周髀算経』の里単位は、通常の漢の里単位とは、異なっている。
「一寸千里の法」をもとに、計算をすると、その1里は、約76メートル~77メートルである。
計算のプロセスは、下の「コラム」のとおりである。
説明のしかたを、若干変えたところもあるが、以上が、谷本氏の論文の要点である。
このように、『周髀算経』の里単位は、『魏志』の「韓伝」「倭人伝」において用いられている「短里」に、ほぼ一致している。
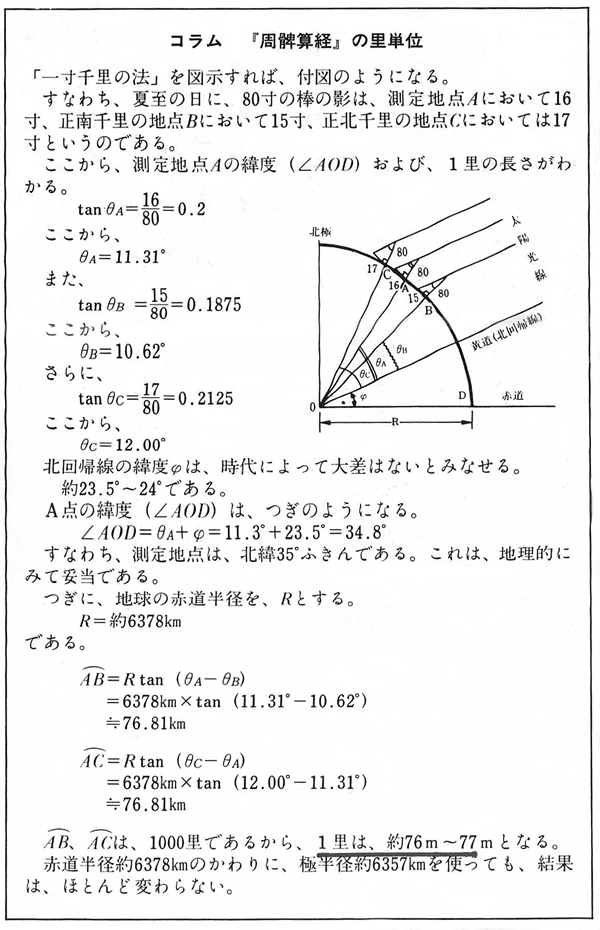
■朝鮮半島から北九州まで
朝鮮半島の巨済島あたりから対馬に渡るばあいには、海流にのることになり、対馬から壱岐へ渡るばあいには、海流を直角に横切ることになり、壱岐から北九州へ渡るばあいには、大略流れのそれほどないところを渡ることになる。
力漕の必要があるのは、朝鮮半島から壱岐までである(とくに壱岐に渡るばあいなど、速力が落ちると、流されて、壱岐につけない)。
壱岐から北九州に渡るばあいは、力漕の必要がなく、それだけ時間をかけて進んだ。そのため、朝鮮半島から対馬までも、対馬から壱岐までも、壱岐から北九州までも、大略同じていどの時間がかかり、それを「里数」に換算したばあい、同じく「千余里」になったかとみられる。
「倭人は、帯方(郡)東南、大海の中にある。」(『魏志倭人伝』)から帯方東南の範囲を見ると下の右の地図となり、奈良県までには及ばない。九州と見る方が無難である。
また、下の左の地図は吉田東吾著『大日本読史地図』である。これによると、邪馬台国は九州のどこかであるとしている。
(下図はクリックすると大きくなります)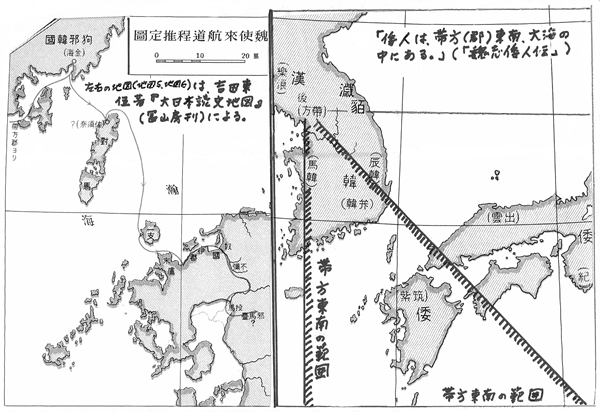
対馬と壱岐の関係を見ると、『魏志倭人伝』は壱岐は対馬の南と書いてある。下の左の地図から、日の出る方向を東とすると合う。また、金海から対馬まで千余里で、対馬から壱岐も千余里、壱岐から末盧までも千余里としている。海の上の距離は線香の燃える時間で測っている。
下の右の地図で、朝鮮半島からは潮の流れを考慮する必要がある。対馬までは海流の流れが速いの漕ぐ勢いが強い。壱岐から九州までは海流がないのでゆっくり漕いでいる可能性がある。
(下図はクリックすると大きくなります)