■狗奴国=肥後熊本説
もっとも根拠が多く可能性の大きい説
テキスト 藤堂明保監修『倭国伝』(学習研究社刊)から
女王国自(よ)り以北は、其(そ)の戸数・道里、略(ほぼ)載することを得べけれど、其(そ)の余(ほか)の旁国は遠く絶(はな)れて、詳(つまびら)かにすることを得べからず。[されども略記すれば]次に斯馬国(しまこく)有り、次に已百支国(いはきこく)有り、次に伊邪国(いやこく)有り、次に都支国(つきこく)有り、次に弥奴国(みなこく)有り、次に好古都国(こくつこく)有り、次に不呼国(ふここく)有り、次に姐奴国(しゃなこく)有り、次に対蘇国(とさこく)有り、次に蘇奴国(さなこく)有り、次に呼邑国(こおこく)有り、次に華奴蘇奴国(げなさなこく)有り、次に鬼国(きこく)有り、次に為吾国(いがこく)有り、次に鬼奴国(きぬこく)有り、次に邪馬国(やまこく)有り、次に躬臣国(くじこく)有り、次に巴利国(はりこく)有り、次に支惟国(きいこく)有り、次に烏奴国(おなこく)有り、次に奴国(なこく)有り、此(こ)れ女王の〔治むる〕境界の尽(つ)くる所なり。
其(そ)の南には狗奴国(くなこく)有り。男子を王と為(な)す。其の官には狗古智卑狗(くこちひこ)有り、女王に属せず。
其(そ)の八年、〔帯方郡(たいほうぐん)の〕太守王頎(たいしゅおうき)、官に到る。倭(わ)の女王卑弥呼(ひめこ)、狗奴国(くなこく)の男王卑弥弓呼(ひめくこ)と素(もと)より和せず。倭(わ)の載斯(そし)・烏越(うお)等(ら)を遣わして郡に詣(いた)り、相(あい)攻撃する状(さま)を説く。塞の曹掾史(そうえんし)張政(ちょうせい)等(ら)を遣わし、因(よ)りて詔書・黄幢(こうどう)を齎(もたら)し、難升米(なとめ)に拝仮せしめ、檄(げき)を為(つく)りて之(これ)に告喩(こくゆ)せしむ。
卑弥呼(ひめこ)以(すで)に死し、大いに冢(つか)を作る、径百余歩なり。
現代語訳
女王の国から北にある国は、その戸数とか距離のおおよそを書くことができるが、その他の方角の国々は、遠く離れていて、詳しく知ることができない。
しかし、ほぼ記してみると、次に斯馬国(しまこく)があり、次に已百支国(いはきこく)があり、次に伊邪国(いやこく)があり、次に都支国(つきこく)があり、次に弥奴国(みなこく)があり、次に好古都国(こくつこく)があり、次に不呼国(ふここく)があり、次に姐那国(しゃなこく)があり、次に対蘇国(とさこく)があり、次に蘇奴国(さなこく)があり、次に呼邑国(こおくこく)があり、次に華奴蘇奴国(げなさなこく)があり、次に鬼国(きこく)があり、次に為吾国(いがこく)があり、次に鬼奴国(きぬこく)があり、次に邪馬国(やまこく)があり、次に躬臣国(くじこく)があり、次に巴利国(はりこく)があり、次に支惟国(きいこく)があり、次に鳥奴国(おなこく)があり、次に奴国(なこく)がある。これで女王の支配する領域が終わるのである。
その南には狗奴国(くなこく)がある。男を王としている。その官には、狗古智卑狗(くこちひこ)がおり、女王には従属していない。
正始八年(247年)、帯方郡の太守、王頎(おうき)が着任した。倭の女王卑弥呼(ひめこ)は、狗奴国の男王卑弥弓呼(ひめくこ)と、以前から仲が悪かったので、倭の載斯(そし)・鳥越(うお)らを帯方郡に遣わし、お互いに攻めあっている様子をのべさせた。帯方郡では、国境守備の属官の張政(ちょうせい)らを遣わし、彼に託して詔書と黄色い垂れ旗を持ってゆかせて、難升米に与え、おふれを書いて卑弥呼を諭した。
使者の張政(ちょうせい)らが到着した時は、卑弥呼(ひめこ)はもう死んでいて、大規模に、直径百余歩の塚を作っていた。
狗奴国は、熊本県など九州南部にあったとする説は、江戸時代の新井白石以来、明治以後の白鳥庫吉、内藤湖南、井上光貞、小林行雄など、歴代の碩学(せきがく)によってとなえられてきた説である。
古代の郡名以上の大地名で『魏志倭人伝』の記述に関連するとみられる「くま」と「くくち」との両方が、そろって存在している地域は、「肥後の国(熊本県)」以外に存在していない。
「狗奴国=肥後熊本説」は、他の諸説にくらべ、文献学的、考古学的根拠を、もっとも多くあげることができ、可能性がもつとも大きい説であると考える。
「女王国」は、「伊都国」の南、「狗奴国」の北にあった。下の地図をみれば、「女王国」のおよその場所は、あきらかであるようにみえる。
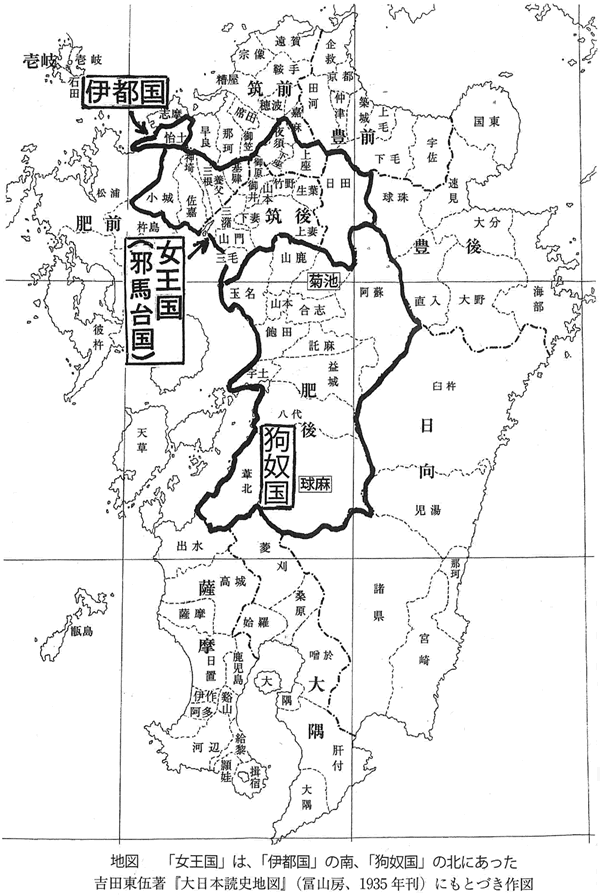
新井白石以来の説
新井白石(1657~1725)は、江戸時代前期~中期の儒者、大学者である。
新井白石は、その著『古史通惑問(こしつうわくもん)』(1716年成立。『新井白石全集』第三所収)の中で述べている。
「其(そ)の(女王国の)南に狗奴国ありと見えしは『日本紀』にみえし熊県(クマアガタ)、後に球磨(クマ)とも球麻ともいいて肥後に隷(れい)せし(属する)郡名」
「また斯(そ)の官に狗古智卑狗ありというは、菊池彦(ククチヒコ)というがごとくにして、即(すなわ)ち今肥後国(ひごのくに)菊池郡をしれる(治める)人に似たれば、……」
その後、明治期になると、白鳥庫吉(1865~1942。東洋史学者。東京帝大教授など)は、論文「倭女王卑弥呼考」[1910(明治四十三)発表。佐伯有清編『邪馬台国基本論文集I』創元社刊所収]の中で、次のように述べる。
「倭国即ち九州全島は南北の二大国に分裂し、北部は出女王国の所領とし、南部は狗奴国の版図として、両々相(あい)対峙して久しく相譲らざる形勢をなししなり。」
そして、白鳥庫吉は、狗奴国を、「熊襲の国」にあてている。
内藤虎次郎(湖南。1866~1934。東洋史学者。京都帝大教授など)も、論文「卑弥呼考に(1910[明治四十三]発表。佐伯有清編『邪馬台国基本論文集I』創元社刊所収)において、「狗古智卑狗」を、「熊襲に属する者なるべし」とし、「卑弥弓呼素」を、「襲国の酋長などをや指しけん」とし、九州南部にあった勢力としている。
考古学者で、邪馬台国畿内説の小林行雄(京都大学教授など)も、「狗古智卑狗をキクチヒコと解釈する説明によれば、その位置は、後の熊本県菊池郡地方をふくむと考えることができる。」と述べている[『女王国の出現』(1967年、文英堂刊)]。
小林行雄は、また、「これは熊本県に拠点をもち、のちの熊襲とも関係ある国であったとおもわれる」とも述べている[「女王国と魏の鏡」(『図説世界文化史大系』日本1、1960年、角川書店刊)]。
私は、新井白石の説でよいと思う。
「狗奴国=肥後熊本説」こそ、他の説にくらべ、文献学的、考古学的根拠を、もっとも多くあげることができる説で、可能性が大きいと考える。
以下では、この説を、私なりに深掘りしてみよう。
■「卑弥呼」を、どう読むか
狗奴国はどこかの問題を考える最初の手がかりとして、『魏志倭人伝』にある次の文章をとりあげよう。
「倭の女王と狗奴国の男王卑弥弓呼とは、素(もと)より和せず(まえまえから不和であった)。」
まず、「卑弥呼」をどう読み、その意味をどう考えるかについて考えよう。これについては、いくつかの説がある。
おもなものを、三つあげる。
(1)日御子(ひみこ)説 新井白石は、『古史通或問(こしつうわくもん)』の中で、「卑弥呼」を、「日御子(ひみこ)」であるとする。「日御子」にあたることばとしては、『古事記』に、「多迦比迦流(たかひかる)、比能美古(ひのみこ)」(高光る、日の御子)という使用例が四例、「本牟多能(ほむだの)、比能御子(ひのみこ)」(品陀の、日の御子)という使用例が一例ある。
「日の御子」は、「ひ(甲)(の)み(甲)こ(甲)」であって、「卑弥呼」の音と一致する(古代においては、「ひ」「み」「こ」などの音には、甲類と乙類の二種類があって区別されていた)。ただ、「日の御子(みこ)」は、つねに、この形で用いられており、「の」を省略して、「日御子」という形で用いられている例がない。また、「日(ひ)の御子(みこ)」は、直接的に、名前の一部として用いられているわけではなく、いわば、形容詞的に用いられている。ただ、「卑弥呼」が、天照大御神、つまり、「日の神」にあたるとすれば、「日(ひ)の御子(みこ)」という形容は、ほぼあてはまる。
(2)姫児(ひめご)説 本居宣長は、「卑弥呼」を、『古事記伝』や『馭戎慨言(ぎょじゅうがいげん)』の中で、「火之戸幡姫児千千姫(ほのとはたひめごちぢひめ)の命(みこと)」「万幡姫児玉依姫(よろづはたひめごたまよりひめ)の命(みこと)」などとある「姫児(ひめこ)」であるとした。ただし、これらは、本居宣長の読み方である。現在の、たとえば、岩波書店刊の日本古典文学大系の『日本書紀』では、「火之戸幡姫の児千千姫(ほのとはたひめのこちぢひめ)の命(みこと)」「万幡姫の児玉依姫(よろずはたひめのこたまよりひめ)」のように、「姫(ひめ)の児(こ)」と読まれている(つまり、母と子の二人の名前としている)。
『肥前国風土記』の松浦(まつら)郡の条に、「弟日姫子(おとひひめこ)」の名がある。この名は、「弟日姫子(おとひひめこ)」(五回)、「弟日女子(おとひひめこ)」 (一回)、「意登比売能古(おとひめのこ)」(一回)の、三通りの書き方で、七回あらわれる。
『旧事本紀』の「天孫本紀」に「市師(いちし)の宿禰(すくね)の祖(おや)、穴太(あなほ)の足尼(すくね)の女(むすめ)、比咩古(ひめこ)の命(みこと)」とある。「比咩古(ひめこ)」も、「姫児」の意味であろう。
『播磨(はりま)国風土記』では、「蚕(かいこ)」のことを、「蚕子(ひめこ)」といっている。「蚕(かいこ)」のことを、古語で、たんに「蚕(こ)」ともいうが、養蚕や機織には、女性がたずさわることが多いので、「蚕子(ひめこ)[姫子]」といったのであろう。
「姫子」「比咩子」の音は、いずれも、「ひ(甲)め(甲)こ(甲)」であって、「卑弥呼」の音に一致する。「姫子(ひめこ)」は、古典にあらわれるひとつの熟語として、「卑弥呼」と完全に一致する。「卑弥呼」が、「姫子」であるとすれば、「姫」という語に、愛称または尊敬の「子」がついたものであろう。
「卑弥呼」を「ヒメコ」と読む説は、東京大学の教授であった古代史家、坂本太郎が、論文「『魏志』『倭人伝』雑考」(古代史談話会編『邪馬台国』1954年9月刊、のち坂本太郎著作集第四巻『風土記と万葉集』「1988年、吉川弘文館刊」に所収)の中で説いている。
「卑弥呼」の「弥」の字は、
①等巳弥居加斯(トヨミケカシ)[支(キ)脱カ]夜比弥乃弥己等(ヤヒメノミコト)[元興寺塔露盤銘(元興寺縁起)](安本注。「トヨミケカシキヤヒメノミコト」は、第33代推古天皇をさす。)
②止与弥挙奇斯岐移比弥(トヨミケカシキヤヒメ)天皇 同丈六光銘(同上)
③吉多斯比弥乃弥己等(キタシヒメノミコト)天寿国繍帳記(上宮聖徳法王帝説)
④等巳弥居加斯支移比弥乃弥己等(トヨミケカシキヤヒメノミコト) 同(「天寿国繍帳」)
⑤践坂大中比弥(ホムサカオオナカツヒメ)王「上宮記」(釈日本紀十三述義九)
⑥田宮中比弥(タミヤナカヒメ) 同
⑦阿那爾比弥(アナニヒメ) 同
⑧布利比弥命(フリヒメノミコト) 同
⑨阿波国美馬郡波爾移麻比弥(ハニヤマヒメ)神社 延喜式神名帳
などのように、『古事記』以前の表記法を伝えるとみられるもののなかに、「甲類のメ」をあらわすために用いられている例がある(文例は、坂本太郎の列挙による)。このような事例をみると、「姫(ひめ)」は、むかしは、「ひ(甲)み(甲)」といっていたのではないかと疑われるが、そうではないことは、「上宮記」において、「布利比弥命(ふりひめのみこと)」を「布利比売命(ふりひめのみこと)」とも記していることからわかる。「弥」は、あきらかに、「甲類のメ」に読まれているのである。
ただ、ふしぎなことに、「弥」を「甲類のメ」と読むのは、わが国の古文献においては、「比[ひ(甲)]弥[め(甲)]{姫}」という熟語にかぎられている。さきの①の「比弥乃弥己等(ヒメノミコト)」の中の、「弥己等(みこと)」(命)のばあいは、「弥」を「甲類のミ」に読んでいる。そして、「卑弥呼」の「弥」は、まさに、「卑[ひ(甲)]=比[ひ(甲)]」の字のあとに用いられており、「卑[ひ(甲)]弥[め(甲)]」と読みうるケースである。
『万葉集』の一六七番の歌で、「天照(あまて)らす日女(ひるめ)の尊(みこと)(天照日女之命)」という語のすぐあとに、「高照(たかて)らす日(ひ)の皇子(みこ)(高照日之皇子)」という語がでてくる。「日女」は、「ひめ」とも読める。「卑弥呼」は「日女皇子(ひめみこ)」のような語をうつしたものであろうか。
(3)姫の命(ひめのみこと)説 江戸中期の国学者、松下見林は、『異称日本伝』のなかで、「卑弥呼」を、「姫(ひめ)の命(みこと)」の省略形とする。東大教授であった東洋史学者、白鳥庫吉も、論文「倭女王卑弥呼考」のなかで、「姫の命説」をとる。 しかし、「み(甲)こ(乙)と(乙)」の「こ(乙)」は「卑弥呼」の「こ(甲)」とやや異なる。この節は、おそらくあたらないであろう。
■「卑弥呼」の意味
以上から、「卑弥呼」は、坂本太郎の説くように、「姫(ひめ)の子(こ)」の意味にとるのが、もっとも穏当である。
『日本書紀』では、「女王」は、
「飯豊女王(いいどよのひめみこ)」(「顕宗天皇即位前紀」)
「忍海部女王(おしぬみべのひめみこ)」(「顕宗天皇即位前紀」)
「栗下女王(くるもとのひめみこ)」(「舒明天皇即位前紀」)
などのように、「女王(ひめみこ)」(姫御子の意味)と読まれている。
『続日本紀(しょくにほんぎ)』では[女王]は単独で用いられるばあいは、「女王(じょうおう)」と読み「伊福部女王(いほきべのひめみこ)」のように人名として用いられるばあいは「女王(ひめみこ)」と読んでいる(岩波書店刊、新日本古典文学大系『続日本紀』など)。
「卑弥呼」は、「ひめこ」と読み、「姫子」あるいは「姫御子」の意味とみられる。
『古事記』の「孝霊天皇記」に、「男王五、女王三」という記事があり、これは、ふつう、「男王五(ひこみこいつはしら)、女王三(ひめみこみはしら)」のように読まれている。
また、『日本書紀』では、「七(ななはしら)の男(ひこみこ)と六(むはしら)の女(ひめみこ)とを生めり。」(「景行天皇紀」)のように、「男」の字を、「ひこみこ(彦御子の意味)」と読んでいる例がある。
狗奴(くな)国の男王「卑弥弓呼(ひみここ)」は、「卑弓弥呼」の書き誤りと考えて、「彦御子(ひこみこ)」のこととする説がある。「卑弓弥呼」と記すべきところを、すぐ上に、「卑弥呼」の名があらわれどので、それにひかれて、「卑弥弓呼」と記したのであると考える。
そうであるとすれば、『魏志倭人伝』の、
「倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。は、『日本書紀』流に読めば、次のようになる。
「倭(やまと)の女王(ひめみこ)、卑弥呼(ひめこ)、狗奴国(くなのくに)の男王(ひこみこ)、卑弓弥呼(ひこみこ)と素(もと)より和(あまな)はず。」
すなわち、「卑弥呼」「卑弓弥呼」は、そのすぐまえの、「女王」「男王」という漢語の「大和ことば」を、万葉仮名風に表記しただけのこととなる。
のちの時代の話であるが、次のような例がある。
733年(天平五)に、唐にわたった遣唐副使の中臣名代(なかとみのなしろ)に、唐の玄宗皇帝が授けた勅書が、『文苑英華(ぶんえんえいか)』(中国で宋の時代の987年に成立。詩文の選集。『文選(もんぜん)』の続編をつくる意図のもとに編集された)に、収められている。
そこには、「日本国王主明楽美御徳(すめらみこと)[天皇]に勅す(このばあいの「すめらみこと」は、第45代聖武天皇をさす)。」とある。これは、『魏志倭人伝』の、「親魏倭王卑弥呼(ひめこ)に制詔す。」と、文の構造が同じである。
この場合、「主明楽美御徳」は、天皇の実名ではない。
「天皇」の日本でのよび方を示している。
「卑弥呼」も、実名ではなく、たんに、「女王」ということばの、日本でのよび方を示している可能性がある。
この可能性は、かなり大きいように思える。
魏の人から、「女王」「男王」のことを、なんと言うかとたずねられて、倭人は、「ひめみこ」「ひこみこ」と答え、それを魏人が漢字の音で、表記したものであろうか。
あるいは、邪馬台国朝廷がわの官人が記したことも考えられる。
『魏志倭人伝』には、「文書、賜遺(しい)の物[賜(たまわり)り物]を伝送して女王(のもと)に詣(いた)らしめ」「倭王使いによりて上表す」などとある。
「上表」という句は、『日本書紀』にしばしば用いられており、そこでは、「上表(ふみたてまつ)る[文たてまつる]」と読まれている。
これらから、邪馬台国の卑弥呼の朝廷には、文字を読み書きできる人のいたことがわかる。
卑弥呼が、上表したとすれば、そこには、署名もあったであろう。署名では、「ひめみこ(姫御子)」の「御」は、尊敬語なのでいれず、「ひめこ(姫子)」のように記したのであろう。
「卑」の字は、韻書(『広韻』などの発音辞典)の「小韻の首字(同音字グループの代表字)」である。「彌(弥)」「呼」も「小韻の首字」である。「卑弥呼」は、文字としては、ありふれたものばかりが用いられている。「小韻の首字」ばかりを用いたのは、誤読をさけるためであろうか。
なお、「卑弓弥呼(ひこみこ)」の「弓」の字の中国での中古音は、「kɪuŋ」である。 埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘文では、「大彦(おほびこ)」にあたる人名を、「意富比垝」と記している。この「垝」の字の中古音は、「kɪuĕ」で、「弓」の音に、かなり近い。
また、『日本書紀』の「神功皇后紀」の、四十七年の条に、「千熊長彦(ちくまながひこ)」という名があらわれ、『日本書紀』の編者は、これを、『百済記』にいう「職麻那那加比跪(ちくまなながひこ)」のことかと、疑っている。
さらに、「神功皇后紀」の六十二年の条にも、『百済紀』が引用されており、そこに、「沙至比跪(さちひこ)」という名が見える。『日本書紀』は、この「沙至比跪」が、「葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)」をさすとする書き方をしている。「沙至比跪」が「襲津彦」をさすと見てよいことについては、古代史家の井上光貞が、「帝紀からみた葛城氏」(『日本古代国家の研究』岩波書店刊所収)のなかで、考証しているところである。
「跪」の中古音は、「gɪuĕ」である。やはり「弓」の音にかなり近い。
「彦(ひこ)」の「こ」の音については、『魏志倭人伝』の「卑狗」では、「狗」(音は、上古音が、「kug」、中古音が「kәu」の字で書かれている。
以上から、「彦」は、「ひく」「ひきゅ」に近い音で発音されたこともあったようである。(乙類の「こ」の音のばあいは、「ひきょ」に近い。)
いずれにせよ、「卑弓弥呼」は、「彦御子(ひこみこ)」「男王(ひこみこ)」を表記しているとみられる。
■狗奴国の官、「狗古智卑狗」
『魏志倭人伝』は、記す。
「其の南には狗奴国(くなこく)有り。男子を王と為(な)す。其の官には狗古智卑狗(くこちひこ)有り、女王に属せず。」[その(女王国の)南には狗奴国(くなこく)がある。男を王としている。その官には、狗古智卑狗(くこちひこ)がおり、女王には従属していない。]
「狗古智卑狗」は、新井白石をはじめ、すでに多くの人の説いているように、肥後の国に「菊池郡」があるので、「菊池彦」とみるのが、もっとも妥当である。
「菊池郡」は『和名抄』に、「久久知」と注がある。『延喜式』も、「くくち」と読んでいる。後世になまって、「きくち」となった(吉田東伍著『大日本地名辞書』)。
「狗古智卑狗」は、「万葉仮名の読み方」で、「くくちひ(甲)こ(甲)」と読め、「菊池彦」と、正確に合致する。
百済の肖古王のことを、中国の史書『晋書』は、「余句」と記している。
肖古王の「古(ko)」の音を、「句(音は、kɪuまたはkәu)」で写しているとみられる。音が、すこし違っているが、このていどなら通用の範囲とみられる。
『古代地名大辞典』(角川書店刊)にのっている「くくち」(「きくち」を含む)の地名は、熊本県の「菊池(くくち)郡」と「菊池城(くくちのき)」の二つだけである。古代において、ありふれた地名とは、いえない。
ただし、吉田東伍著の、『大日本地名辞書』(冨山房刊)には、熊本県の「菊池郡」「菊池城」以外に、摂津の国河辺郡(かわのべぐん)[兵庫県]の地名として、「久久知(くくち)」をのせている。
熊本県の地名の方が、大地名である。
東京大学の教授であった古代史家、井上光貞は、その著『日本の歴史1神話から歴史へ』(中央公論社、1965年刊)の中で、次のように述べる。
「この狗奴(くな)国について白鳥(庫吉)氏は、『熊本、球磨(くま)川にその名を残す球磨地方であろう』とした。なぜならウミハラ(海原)がウナバラとなるように、マ行とナ行とは転訛(てんか)しやすいからである。球磨地方はさらに南方と合して『熊襲(くまそ)』の名で知られているが、この地方は筑後山門(やまと)郡のちょうど南にあたる。だから倭人伝をそのままにうけとって、博多方面から南に邪馬台国があり、その南に狗奴国があると読んでもよく筋が通るのである。」
マ行とナ行との転訛例としては、次のようなものがある。
食物の「ニラ」は古代は、「ミラ」といった。巻貝の「ニナ」も古代には、「ミナ」といった。「かいつぶり」のことは、「ミホドリ」とも、「ニホドリ」ともいう。
「任那」は、「ニンナ」と書いて、「ミマナ」と読む。「壬生」は、「ニンフ」と書いて、「ミブ」と読む。「壬生(みぶ)」の人たちは、皇子・皇女の扶養にあたる。
「狗奴国」について、上代文献中の関連地名をあげれば、下の表のようになる。
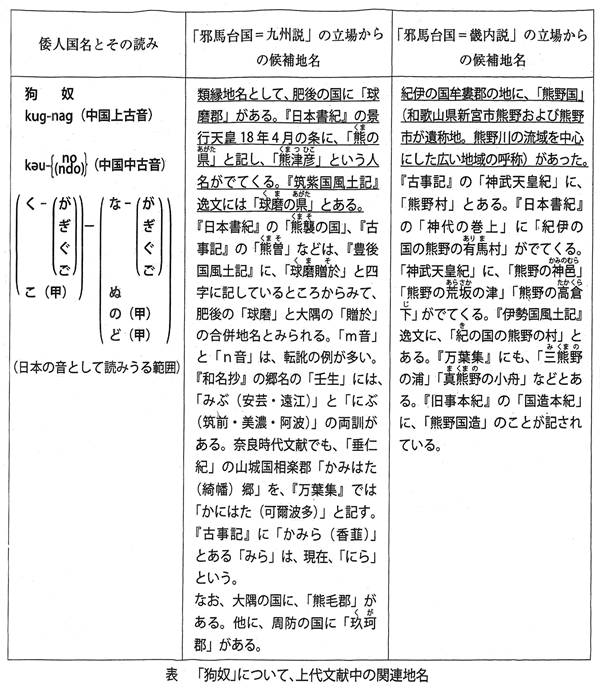
「狗古智卑狗」の関連地名「菊池(くくち)」をあわせて考えるならば、「狗奴国」という地名からは、「邪馬台国=九州説」のほうが有利といえよう。
古代の郡名以上の大地名で、『魏志倭人伝』の記述に関係するとみられる「くま」と「くくち」との両方が、そろって存在している地域は、「肥後の国(熊本県)」以外に存在していない。
■「箱式石棺」の分布が示す事実
『魏志倭人伝』は、次のようなことを記す。
「その八年[正始八(247)]、(帯方郡の)太守王頎(おうき)が、[魏(ぎ)国の]官(庁)に到着した(そして、以下のことを報告した)。
倭の女王、卑弥呼(ひみこ)と狗奴国の男王卑弥弓呼(ひみここ)とは、まえまえから不和であった。倭(国)では、載斯(きし)・鳥越(あお)などを(帯方郡に)つかわした。(使者たちは)(帯方)郡にいたり、たがいに攻撃する状(況)を説明した。
(郡は)塞(さい)の曹掾史(そうえんし)[国境守備の属官]の長政(ちょうせい)らをつかわした。(以前からのいきさつに)よって、(使者たちは)詔書・黄幢(こうどう)をもたらし、難升米に拝仮し、(また)檄(げき)[召集の文書、めしぶみ、転じて諭告する文書、ふれぶみ]をつくって(攻めあうことのないよう)告諭した。」
倭の女王、卑弥呼と、狗奴国の男王とは、たがいに攻撃するなどしたようであるが、結果は、どちらが有利な形でおさまったのであろうか。
それを、あるていどうかがわせるのが、以下に述べるような事実である。
宮崎公立大学の教授であった「邪馬台国=九州説」の考古学者の奥野正男(2020年の6月になくなった)は、次のように述べている。(以下、傍線をほどこしたのは安本。)
「いわゆる『倭国の大乱』の終結を二世紀末とする通説にしたがうと、九州北部では、この大乱を転換期として墓制が甕棺から箱式石棺に移行している。
つまり、この箱式石棺墓(これに土壙墓、石蓋土壙墓などがともなう)を主流とする墓制こそ、邪馬台国がもし、畿内にあったとしても、確実にその支配下にあったとみられる九州北部の国々の墓制である。」(『邪馬台国発掘』PHP研究所刊)
「前代の甕棺墓が衰徴し、箱式石棺と土壙墓を中心に特定首長の墓が次第に墳丘墓へと移行していく……。」(『邪馬台国の鏡』梓書院、2011年刊)
「邪馬台国=畿内説」の考古学者の白石太一郎氏(当時国立歴史民俗博物館。大阪府立近つ飛鳥博物館長など)も述べている。
「二世紀後半から三世紀、すなわち弥生後期になると、支石墓はみられなくなり、北九州でもしだいに甕棺墓が姿を消し、かわって箱式石棺、土墳墓、石蓋土墳墓、木棺墓が普遍化する。ことに弥生前・中期には箱式石棺がほとんどみられなかった福岡、佐賀県の甕棺の盛行地域にも箱式石棺がみられるようになる。」
「九州地方でも弥生文化が最初に形成された北九州地方を中心にみると、(弥生時代の)前期には、土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が営まれていたのが、前期の後半から中期にかけて大型の甕棺墓が異常に発達し、さらに後期になるとふたたび土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が数多くいとなまれるようになるのである。」(以上、「墓と墓地」学生社刊『三世紀の遺跡と遺物』所収)
このように、邪馬台国の時代の墓制としては、箱式石棺などが考えられる。そして、この箱式石棺を用いるという墓制は、『魏志倭人伝』に記されている「棺あって槨なし」という墓制とも一致するものである。
2015年に、茨城大学名誉教授の考古学者、茂木雅弘(もぎまさひろ)氏の著書『箱式石棺(付、全国箱式石棺集成表)』(同成社刊)が出版されている。
この本の「全国箱式石棺集成表」にもとづき、北九州の地図の上に、弥生時代後期の箱式石棺の分布をプロットすれば、下の右の地図(弥生時代後期の箱式石棺の分布)のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)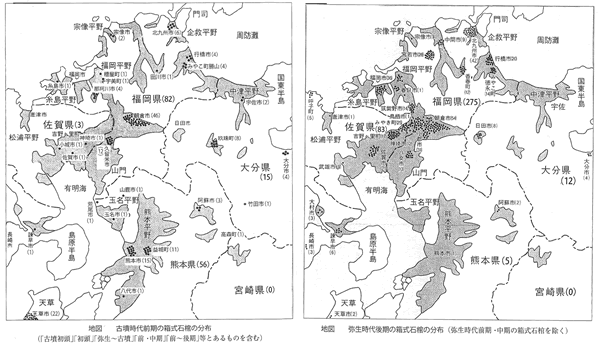
この時代は、弥生時代後期で卑弥呼の時代といえる。
弥生時代後期の箱式石棺の分布は、福岡県の朝倉市を中心とし、小郡市(おごおりし)のあたりから、佐賀県の三養基郡(みやきぐん)のみやき町、神埼郡の吉野ヶ里町、神埼市にかけての筑後川の上、中流域に密集地帯がある。
私は、卑弥呼の宮殿は、福岡県の朝倉市にあったであろうと考えている。
このことについては、すでに拙著『邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!!』(勉誠出版、2019年刊)などにおいて、ややくわしく述べた。
いま、茂木雅弘氏の『箱式石棺』により、九州本島において弥生時代後期の箱式石棺の出土数の多い「市と町」の、ベスト10を、グラフに示すと、下の右のグラフ(九州本島で、弥生時代後期において、箱式石棺の出土数の多い「市と町」ベスト10)のようになる。上の右の地図(弥生時代後期の箱式石棺の分布)には、このような数値も、カッコのなかに示されている。
(下図はクリックすると大きくなります)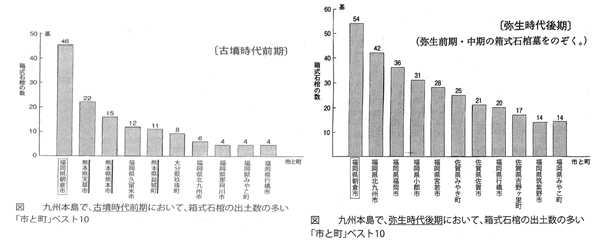
また、古墳時代前期の箱式石棺のデータについて、少し上の右の地図(弥生時代後期の箱式石棺の分布)と同様の地図をつくれば、少し上の左の地図(古墳時代前期の箱式石棺の分布)のようになる。古墳時代前期のデータについて、箱式石棺の出土数の多い「市と町」のベスト10をグラフに示すと上の左のグラフ(九州本島で、古墳時代前期において、箱式石棺の出土数の多い「市と町」ベスト10)のようになる。
これらの地図と図とをよくご覧いただきたい。
次のようなことに気がつく。
(1)古墳時代の前期になると、熊本県からの箱式石棺の出土数が激増している。前述の上の方にある右の地図(弥生時代後期の箱式石棺の分布)では、熊本県からの出土数は5基にすぎなかったのに、その左の地図(古墳時代前期の箱式石棺の分布)では56基になっている。10倍以上に、はねあがっている。
また、上のグラフの右と左とをみると、ベスト10のトップが朝倉市であることは、変わらない。しかし、左では、熊本県の、天草市や熊本市、益城町からの出土数が多くなっている。右ではベスト10のなかに、熊本県の市が一つもはいっていないのに、左では、三つの市がはいっている。これは、邪馬台国は、福岡県にあり、狗奴国は、熊本県にあり、邪馬台国勢力が、狗奴国勢力を圧倒し、狗奴国地域へ、邪馬台国文化が進出したことを意味するようにみえる。[大分県の玖珠町(くすまち)をふくめ、南へ進出。]
(2)古墳時代の前期になると、朝倉市の南の福岡県久留米市からの出土が多くなっている。これも、邪馬台国勢力の南への進出と関係があるか。
北の邪馬台国勢力は、魏の張政らのもたらした詔書、黄幢などの「錦(にしき)の御旗」の威光を背景に、争いを、有利な形でおさめたようにみえる。
■鉄の鏃
『魏志倭人伝』に、倭人は、「鉄の鏃(やじり)」を用いると記されている。 鉄の鏃について、広島大学の川越哲志編の、『弥生時代鉄器総覧』(広島大学文学部考古学研究室、2000年刊)に示されているデータにもとづき、各県別の出土数をみてみよう。すると下のグラフのようになる。
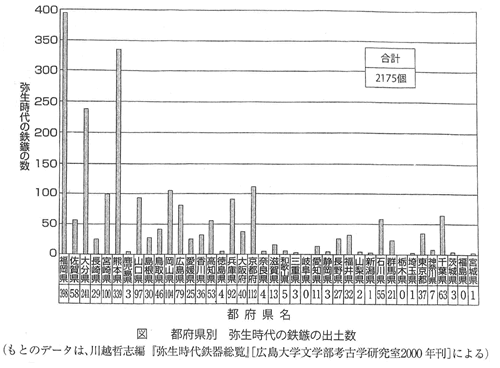
このグラフをよく見てみよう。
鉄鏃の出土数の、もっとも多いのは、福岡県である。第二番目に多いのは、熊本県である。これは、女王国と狗奴国との対立を反映しているようにみえるが、どうであろう。
とくに、熊本県「菊池郡」の大津町(おおづまち)からは、83個の鉄鏃が出土している。これは、奈良県全県からの鉄鏃の出土数4個の20倍をこえる。
少なくとも、女王国と狗奴国との対立を、奈良県とそれ以東との対立の話とする「狗奴国東海説」「狗奴国濃尾平野(岐阜県と愛知県とにまたがる平野)説」などは、鉄の鏃の県別分布状況からみると、あまりにも、根拠が薄弱であるようにみえる。
『魏志倭人伝』の記述と、直接関係していないことをもとに議論している「思考実験」としか思えない。
なくなった考古学者の森浩一(同志社大学文学部教授などであった)は、雑誌『論座』2002年2月号所載の、「魂を失う考古学」という文章の中で、次のように述べている。
「一部の考古学者がいっている、東海地方には前方後方墳が多いということからの狗奴国東海説は、考古学の方法からはとうてい無理です。そもそも邪馬台国や狗奴国の所在地は、『魏志』倭人伝という文献上で決定される問題です。」
「狗奴国東海説」などでは、『魏志倭人伝』に記されている記事と、直接結びつくような遺跡・遺物は、なにも示されてない。
■『魏志倭人伝』と日本神話
「考古栄えて紀・記滅ぶ。」
この言葉は、静岡大学名誉教授の古代史学者、原秀三郎(はらひでさぶろう)氏の作られた標語である。古代史の分野では、かなりポピュラーになっていることばである。
戦後、考古学が盛んになったことは、大変結構なことである。ただ、第二次世界大戦中、『古事記』『日本書紀』が、尊重されたことの反動で、『古事記』『日本書紀』に、目を通そうともしない、触れようともしない考古学者が少なくないのは、残念なことである。
西欧において、ギリシャ、ローマの考古学や、聖書の考古学は、すべての考古学のはじまりであり、母胎であった。
そして、その考古学は、神話・伝承といったものに、みちびかれたものであった。このことを、忘れてはならない。
ドイツのシュリーマンは、ホメロスの詩編にみちびかれて、トロイの遺跡を発掘した。イギリスのエヴァンズは、クノッソスの伝説にもとづいて、ギリシャのクレタ島で発掘を行ない、ミノス文明を明らかにした。
中国の『西遊記』は、荒唐無稽な話であるが、唐の僧の玄奘(げんじょう)三蔵が、インドから仏典をもち帰ったという話は、史実にもとづく。
1956年に『魏志倭人伝』の現代語訳を出した島谷良吉(しまやりょうきち)(1899~1980。高千穂商科大学教授などであった)は、その『国訳魏志倭人伝』の「前がき」の中で述べている。
「陳寿編纂『魏志巻三十』所載の東夷の一たる『倭人』の記述を見ると、まったく記紀神代の巻の謎を解くかのように思える。」
私は、拙著『日本の建国』(勉誠出版、2020年刊)の中で、次のようなことをややくわしく述べた。
(1)邪馬台国時代以後にあたる中国の、魏、西晋、東晋の三王朝の全期間は、ちょうど200年で、その間20人の王が存在している。王の一代の平均在位年数は、ちょうど「10年」である。
(2)「君、十帝を経(へ)て、年(とし)ほとほと(ほとんど)百」。この文は、奈良時代史の基本文献である『続日本紀(しょくにほんぎ)』の、淳仁天皇の天平宝字二年(758)8月25日の条に記されている。これは、第36代の孝徳天皇から、第46代の孝謙天皇までが、十代で、104年ほどであることを述べている。
天皇一代の平均在位年数が、およそ十年ていどであることは、奈良時代の人たちが大略認識していたことであった。「奈良七代七十年」ということばもある。
歴史的に確実な時代にはいってからのちの、最初の300年間ほどの天皇の一代平均在位年数を、実際に求めてみると、10.90年となる。
(3)『古事記』『日本書紀』に記されている天皇は、すべて実在したと仮定して、天皇の一代平均在位年数は、十年ていどとしてさかのぼり、年代を推定すれば、第1代の神武天皇の活躍年代が、280年ごろとなる。
すなわち、大和朝廷のはじまりは、卑弥呼の時代よりもあとである。
(4)『古事記』『日本書紀』では、神武天皇から、五代前の祖先が、天照大御神であるとされている。かりに、同じようにして、天照大御神の活躍年代を推定(数理統計学的な区間推定)すると、大略卑弥呼の時代と重なる。
『古事記』『日本書紀』の記す神話時代の、天照大御神などの活躍の舞台の「高天の原」を、北九州方面と考えた人は多い。
国文学者で、東大教授であった金子武雄は、その著『古事記神話の構成』(桜楓社刊)の中で、『古事記』の内容を、くわしく分析した上で、述べている。
「やや比喩的に言えば、高天原(たかまがのはら)はほかならぬ筑紫の上にあったのである。こうして、いわゆる高天原系神話も、いわゆる筑紫系神話と同じく筑紫の地に成育したものと思われる。」
すでに、明治期の東京大学を代表する史家で、「邪馬台国=北九州説」を説いた白鳥庫吉は、述べている。
「神典(『古事記』『日本書紀』)の中に記された天の安の河(高天の原にあったとされる)の物語は、卑弥呼時代におけるような社会状態の反映をみることができようか。」[1910年に発表された論文「倭女王卑弥呼考」。原文は、文語体。安本が口語体になおし、カッコ( )内の注を付した。]
東京大学の哲学者、和辻哲郎も、その著『日本古代文化』の中で述べている。
「君主の性質については、記紀の伝説は、完全に魏人の記述と一致する。たとえば、天照大御神は、高天の原において、みずから神に祈った。天上の君主が、神を祈る地位にあって、万神を統治するありさまは、あたかも、地上の倭女王が、神につかえる地位にあって人民を統治するありさまのごとくである。また天照大御神の岩戸隠れのさいには天地暗黒となり、万神の声さばえのごとく鳴りさやいだ。倭女王が没した後にも国内は大乱となった。天照大御神が岩戸より出ると、天下はもとの平和に帰った。倭王壱(台)与の出現も、また国内の大乱をしずめた。天の安河原においては八百万神が集合して、大御神の出現のために努力し、大御神を怒らせたスサノオの放逐に力をつくした。倭女王もまた武力をもって衆を服したのではなく、神秘の力を有するゆえに衆におされて王とせられた。この一致は、暗示の多いものである。」「これらの諸伝説の原形がいかなるものであったにしろ、筑紫の生活のほのかなる記憶が、統治者の階級に残っていたとみることは許されねばならぬ。」
皇学館大学の学長であった古代史家の、田中卓(たかし)も、記す。
「皇室は、もともと北九州に発祥せられた。紀・記神代巻の高天原とはこれを指す。」[田中卓著作集2『日本国家の成立と諸氏族』(1986年、吉川弘文館刊)]
■『魏志倭人伝』の人名・官名
千余里にして対馬国(つしまこく)に至る。其(そ)の大官を卑狗(ひこ)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰(い)う。〔対馬(つしま)は〕居(お)る所、絶島にして、方四百余里可(ばか)りなり。〔その〕土地は、山険しくして、深き林多く、道路は禽鹿(きんろく)の径(ほそみち)の如(ごと)し。千余戸有り。
良田無く、海の物を食(く)らいて自活す。船に乗り、南北に〔ゆきて〕市糴(してき)す。
又(ま)た南して一つの海を渡る。千余里なり。名づけて瀚海(かんかい)と曰(い)う。一大国(いちだいこく)に至る。官を亦(ま)た卑狗(ひこ)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰(い)う。方三百里可(ばか)りなり。竹木の叢林(そうりん)多し。三千許(ばか)りの家有り。差(やや)田地有りて、田を耕せども、猶(なお)食(く)らうに足らず。亦(ま)た南北に市糴(してき)す。
東南に陸行すること五百里にして、伊都国(いとこく)に到る。官を爾支(ねぎ)と曰(い)い、副を泄謨觚(えもこ)・柄渠觚(へごこ)と曰(い)う。千余戸有り。
世々王有り。皆、女王国に統属す。〔帯方郡(たいほうぐん)の〕郡使(ぐんし)往来するとき、常に駐(とど)まる所なり。
東南して奴国(なこく)に至る、百里なり。官を兕馬觚と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰(い)う。二万余戸有り。
東に行きて不弥国(ふみこく)に至る、百里なり。官を多模(たま)と曰(い)い、副を卑奴母離(ひなもり)と曰(い)う。千余家有り。
南して投馬国(つまこく)に至る。水行すること二十日なり。官を弥弥(みみ)と曰(い)い、副を弥弥那利(みみなり)と曰(い)う、五万余戸可(ばか)り。
南して邪馬壱国(やまとこく)に至る。女王の都する所なり。〔投馬国(つまこく)より〕水行すること十日、陸行すること一月なり。官には伊支馬(いきま)有り。次は弥馬升(みまと)と曰(い)い、次は弥馬獲支(みまわけ)と曰(い)い、次は奈佳鞮(なかで)と曰(い)う。七万余戸可(ばか)り。
其の南には狗奴国有り。男子を王と為す。其の官には狗古智卑狗(くこちひこ)有り、女王に属せず。
現代語訳
そこから、一つの海を南へ渡ること千里余り、その海を瀚海という。壱岐国(いきこく)に到着する。そこの官も卑狗(ひこ)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。広さは三百里四方である。竹や木の繁みが多い。
三千軒ほどの人家がある。対馬国(つしまこく)に比べ、いくらか畑があるが、その収穫だけでは生活していけない。それで、この国もまた、南北に行き、米などを買ったりしている。
東南に陸路を行くと、五百里で伊都国(いとこく)に到着する。官を爾支(ねぎ)といい、副官を泄謨觚(えもこ)・柄渠觚(へごこ)という。千戸余りの人家がある。代々、王が治めている。以上の国はどれも、女王の国に統治されている。帯方郡(たいほうぐん)の使いが往来するときは、いつも、ここに泊まる。
そこから東南に向かって行くと、奴国(なこく)に到着する。伊都国からの距離は百里である。官を兕馬觚(しまこ)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。人家は二万余戸ある。
そこから東に行くと、不弥国(ふみこく)に到着する。距離は百里である。官を多模(たま)といい、副官を卑奴母離(ひなもり)という。千余戸の人家がある。
南の方に行くと、投馬国(つまこく)に到着する。船で行って二十日かかる。官を弥弥(みみ)といい、副官を弥弥那利(みみなり)という。五万戸余りの人家がある。
南に行くと邪馬台国(やまたいこく)に到着する。女王の都のあるところである。投馬国から、船で十日かかる。陸を行くと、ひと月かかる。官には、伊支馬(いきま)がある。次の官を弥馬升(みまと)といい、その次の官を弥馬獲支(みまわけ)といい、さらに次の官を奈佳鞮(なかで)という。人家は七万戸余りである。
その南には狗奴国(くなこく)がある。男を王としている。
その官には、狗古智卑狗(くこちひこ)がおり、女王には従属していない。
■『古事記』『日本書紀』の神名・人名と、『魏志倭人伝』の人名・官名
いま、天照大神(あまてらすおおみかみ)以下、神武天皇に至る神々の系図を示せば、下の「神々の系図」のようになる。
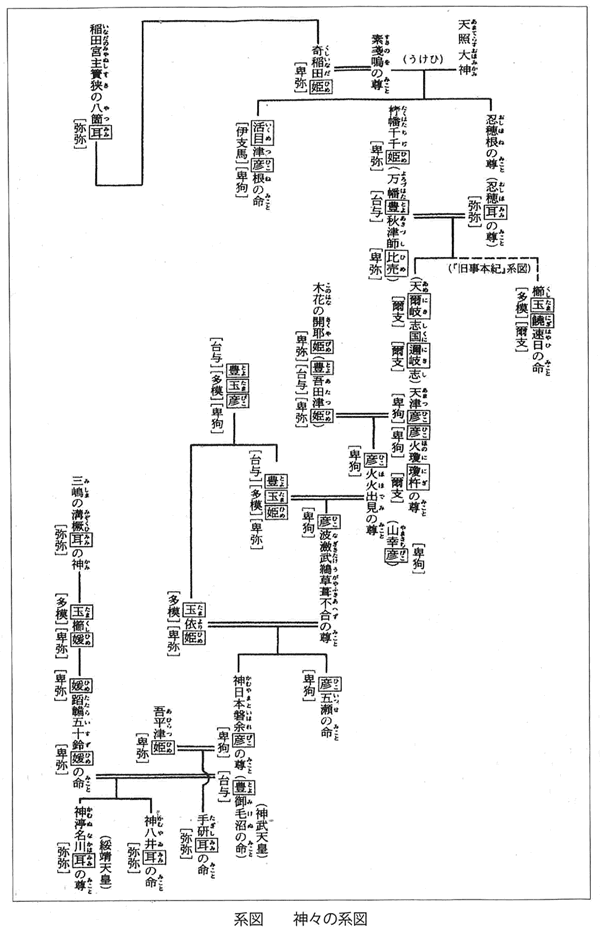
この系図をじっとにらんでみよう。
すると、『魏志倭人伝』にみえる「人名」や「官名」に結びつくように見える「神名」「人名」が、はなはだ多いことに気がつく。
『魏志倭人伝』は、卑弥呼のあとをつぐ宗女(一族の娘)の名を、「台与(とよ)」と記す。
上の系図をみると、「トヨ」という音のはいる女性の神名に、「万幡豊秋津師比売(よろづはたとよあきづしひめ)」「豊吾田津姫(とよあたつひめ)」「豊玉姫(とよたまひめ)」などがある。
とくに、「万幡豊秋津師比売(よろづはたとよあきづしひめ)」は、高御産巣日の神(たかみむすびのかみ)の娘で、天孫降臨をする瓊瓊杵の尊(ににぎのみこと)[邇邇芸の命(ににぎのみこと)]の母である。
天照大御神を「卑弥呼」にあて、万幡豊秋津師比売を[台与]にあてれば、世代的には、あう。
年十三で、卑弥呼のあとをついで女王となった台与(とよ)[万幡豊秋津師比売]が、のち、成人して忍穂耳の尊(おしほみみのみこと)と結婚して、瓊々杵の尊(ににぎのみこと)を生み、その瓊々杵の尊が、皇室の祖先になったと、考えれば、よいわけである。
『魏志倭人伝』に、倭の国の「官名」として、「弥弥[み(甲)み(甲)]」が記されている。
上の系図をみると、「ミ(甲)ミ(甲)」という音をふくむ神名として、「忍穂耳の尊(おしほみみのみこと)」「八箇耳(やつみみ)」「溝橛耳の神(みぞくひみみのかみ)」「手研耳の命(たぎしみみのみこと)」「神八井耳の命(かみやいみみのみこと)」「神渟名川耳の尊(かむぬなかわみみのみこと)」などがある。
『魏志倭人伝』は、また、倭の国の「官名」として、「爾支(にき)」を記す。
上の系図をみると、「ニキ」という音をふくむ神名として、
「天爾岐志国邇岐志天津日高日子番能邇邇芸の命(あめにきしくににきしあまつひこひこほのににぎのみこと)」(『古事記』)、「天津彦彦火の瓊瓊杵の尊(あまつひこひこほのににぎのみこと)」(『日本書紀』)、「櫛玉饒速日の命(くしたまにぎはやひのみこと)」がある。
さらに、『魏志倭人伝』は、倭の国の「官名」として、「多模」を記す。
「多模」の中国語上古音は、「tar-mag」であるから、「たま」と読める(これについて、くわしくは、藤堂明保編『学研漢和大辞典』、拙著『倭人語の解読』[勉誠出版刊]などを参照)。
上の系図をみると、「タマ」という音をふくむ神名として、「櫛玉饒速日の命(くしたまにぎはやひのみこと)」「豊玉彦(とよたまびこ)」などがある。
「弥弥(みみ)」「爾支(にき)」「多模(たま)」などは、原始的な「姓(かばね)」に近いものかと思われる。
■『古事記』の神話時代の神名・人名が、『魏志倭人伝』の人名・官名と、とくに、よく一致している
『古事記』にみえる「とよ」「みみ」「にき」「たま」を含む神名、人名について全数調査をすると、下の表のようになる。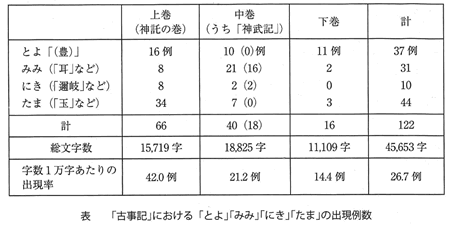
すなわち、「とよ」「みみ」「にき」「たま」を含む神名、人名は、『古事記』全体で、のべ122回あらわれる。
そのうち、過半の66回は、『古事記』上巻(神話の巻)にあらわれる。
また、中巻にあらわれる「とよ」「みみ」「にき」「たま」はのべ40回のうち、18回は、最初の、「神武記」にあらわれる。
したがって、「神武記」以前(上巻と「神武記」とを加えたもの)に、「とよ」「みみ」「にき」「たま」は、のべ、84回あらわれることになる。
じつに、「とよ」「みみ」「にき」「たま」の、三分の二以上、69パーセントは、「神武記」以前にあらわれる。
『古事記』の、上巻と中巻と下巻とでは、分量が異なる。
このことを考慮しても、結論はかわらない。いな、「とよ」「みみ」「にき」「たま」は、他の巻よりも、上巻に頻出するという傾向は、さらにはっきりとうかびあがってくる。
上の表には、各巻の総文字数も示しておいた。ここから、文字数一万字あたりの、「とよ」「みみ」「にき」「たま」の、出現率を計算する。
字数一万字あたりの出現率は、上巻で、42.0例、中卷で、21.2例、下巻で、14.4例である。上巻の出現率は、中巻の出現率の約二倍である。
そして、上巻から中巻へ、中巻から下巻へと、時代が下るにつれ、出現率は、減少してゆく。
以上をまとめれば、次のようになる。
(1)卑弥呼、邪馬台国の時代は、大略、『古事記』『日本書紀』の神話の時代にあたる。
(2)日本神話が語る「高天の原」は、北九州方面と考えられる。
(3)だから、『魏志倭人伝』中にあらわれる人名、官名などは、他の時代よりも、神話時代の神名、人名とより、よく一致することとなるのである。
(4)「高天の原」が、北九州方面であるとすると、邪馬台国も、狗奴国も、九州の範囲の中で考えるべきである。「狗古智(くくち)」にあてはまる地名「菊池」も、諸国の地名中、九州の中で、もっともよくあてはまる地名を見出すことができる。
「狗奴国」問題は、主として、地名学を含む文献学上の問題である。したがって、考古学関係の方も、文献学上の検討をした上で、探究に進むべきである。
文献学的な検討なしで探究に進めば、情報が不足しているために、「狗奴国」を、全国のどこにでも、もって行けることになる。
■おぼろげな「仮説」
「狗奴国」についての、私の考えの主要な点は、以上のとおりである。
ただ、以下に、多少の蛇足を付け加えようと思う。
それは、『古事記』『日本書紀』の神話は、日本古代史を考える上での、仮説を考えるさいの、きわめて豊かなヒントや種を提供しうる宝箱だと、私は考えるからである。
以下は、きわめてたよりなく、おぼろげにゆらめく「仮説」段階の話である。
すでに述べたように、邪馬台国の女王の「卑弥呼(ひめこ)」が「女王(ひめみこ)」という日本語の音を写したものであり、狗奴国男王の「卑弥弓呼」が「卑弓弥呼(ひこみこ)」で、「男王(ひこみこ)」という日本語を写したと、考えてみよう。
とすると、邪馬台国も狗奴国も、ともに、のちの『古事記』『日本書紀』につながるような、共通の言語、日本語の一種を用いており、女王、男王の呼び方も、『古事記』『日本書紀』の記載方法とつながるような、共通の文化をもっていたことをうかがわせる。
卑弥呼は、狗奴国男王、卑弥弓呼との争いの中で没するが、天照大御神は、弟の須佐之男の命(すさのおのみこと)との争いにより、天(あめ)の岩屋(いわや)にかくれる。狗奴国は、熊本県、つまり、「肥の国」と考えられるが、須佐之男の命が追放された出雲の国には、「肥[ひ(乙)]の河」が流れている。熊本県にも、「火[ひ(乙)の川]」がある。「狗奴(くま)」と関係のありそうな出雲の「熊野神社」に須佐之男の命はまつられている。あるいは、「須佐之男の命(すさのおのみこと)」が、狗奴(くま)国男王の「卑弥弓呼」で、出雲に追放されたさい、ふるさとの九州の狗奴(くま)[熊]地方の地名をもっていったのではないか?
『古事記』の上巻(神話)によれば、須佐之男の命は、追放されて、「出雲の国の肥[ひ(乙)]の河のほとり、鳥髪というところに降(お)りていった。」とある。
また、須佐之男の命が、「八俣(やまた)の遠呂智(おろち)」という大蛇を、切り散らしたとき、「肥[ひ(乙)の河(かわ)が、血に変って流れた。」とある。『日本書紀』は、この河を、「簸[ひ(乙)]の川」と記す。ここに、「肥の河」といいう河の名前がでてくる。
ところで、『古事記』には「肥[ひ(乙)]の国」という地名も記されている。この「肥の国」を、『日本書紀』の景行天皇十八年五月条や「肥前風土記」は、「火[ひ(乙)]の国」と記している。
この「肥の国」は、のちに、肥前の国と肥後の国とにわかれた。このうち、肥後の国は、現在の熊本県にあたる。狗奴国があったかとみられる地である。現在、熊本県には、「氷川(ひかわ)」が流れているが、これは、「火(ひ)の川(かわ)」に由来するとされている(吉田東伍著『大日本地名辞書』)。「氷」は、「甲類のヒ」、「火」「簸」「肥」は、「乙類のヒ」で、古代においては、音が異なる。おそらく、甲類、乙類の区別が失われた時代になって、「火(ひ)」に、「氷(ひ)」をあてはめたものであろう。
また、出雲の国の「肥の河」は、現在、「斐伊川(ひいがわ)」という。熊本県の八代郡(やつしろぐん)の氷川町(ひかわまち)を流れる氷川(ひかわ)の流域にも、昔、「肥伊郷(ひいごう)」があった。
これは、次のような事情によるものであろう。
西暦713年(和銅六)第43代元明天皇は、『風土記』撰進を命ずる勅を下す。その勅の中で、元明天皇は、「諸国、郡郷の名は、好ましい漢字二文字で記すように。」という趣旨のことを述べた。
この勅により、それまで「肥(ひ)」「火(ひ)」「簸(ひ)」と、一文字で記されていた地名を、「斐伊(ひい)」「肥伊」などの二文字で記すようになったものであろう。
ちょうど、それまで、「木(き)の国」と記していたものを、「紀伊の国」と記し、「襲(そ)の国」「曽(そ)の県(あがた)」を「贈於郡(そおぐん)」のように記し、参河(みかわ)の国(愛知県東部)の「穂(ほ)の国」を、「宝飫(ほお)郡」と記すことになったように。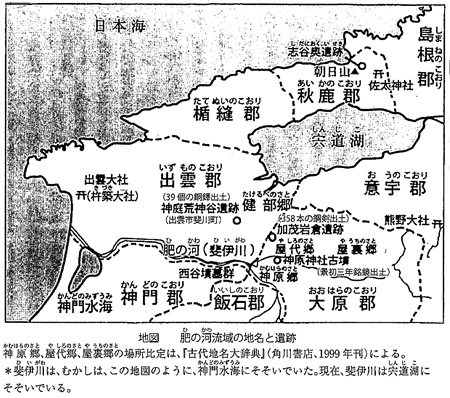
■肥の河(斐伊川)流域の考古学的遺跡
さて、熊本県の氷川(ひかわ)[火の川]の流域に、「八代郡(やつしろぐん)」がある。歌手の「八代亜紀(やしろあき)」さんは、この地の八代市(やつしろし)出身であるが、「八代」を「やつしろ」と読まず、「やしろ」と読ませている。
いっぽう、島根県の斐伊川(肥の河)の流域に、大原郡屋代郷(やしろのさと)があった(右の地図参照)。
「八代(やしろ)」「屋代(やしろ)」は関係する地名なのではないか?
熊本県では、「八代郡」の隣が、「球磨(くま)郡」である。『日本書紀』の景行天皇十八年の条にみえる「熊県(くまのあがた)」や「熊津彦(くまつひこ)」の説話は、この「球磨郡」の地を舞台とする。
いっぽう、島根県の斐伊川(肥の河)の上流の果の地に、「熊野大社」が存在する(上の地図参照)。「熊野大社」の祭神は、素戔嗚の命(すさのおのみこと)と同神とされる熊野大神櫛御気野の命(くしみけのみこと)である。
熊本県と島根県との両方に、「熊」と結びつく地名や神社がある。
ただ、吉田東伍著の『大日本地名辞書』の「索引」をみると、「八代(やしろ)」「八代(やつしろ)」「屋代(やしろ)」「矢代(やしろ)」「社(やしろ)」などは、かなりありふれた地名である。また、和歌山県にも、「熊野本宮(くまのほんぐう)大社」「熊野速玉(くまのはやたま)大社」「熊野那智(くまのなち)大社」などの、「熊(くま)」つく著名な神社がある。
したがって、地名の一致なども、どこまでが、理由のある必然の一致で、どこまでが偶然の一致なのか現在のところではわからない。
ただ、将来の研究のための「仮説」の種、ヒントになるかも知れないと思って、以上のことをここに記した。
そして、島根県の簸川(ひかわ)郡斐川町(ひかわちょう)(当時。現在は、出雲市斐川町)の荒神谷(こうじんだに)遺跡から、1984年に358の銅剣、16本の銅矛、6個の銅鐸が発見されている。荒神谷遺跡のある「簸川(ひかわ)郡」「斐川(ひかわ)町」などの地名は、「肥の河」に由来するとみられる。
「肥(ひ)の川」すなわち「斐伊大川(ひのおおかわ)」(出雲の大川)のことを、「簸川(ひかわ)」とも記す。
荒神谷遺跡からは、「綾杉(あやすぎ)状の研ぎ分け文様」という特殊な文様をもった銅矛が7本出土している。
この「綾杉状の研ぎ分け文様」をもった銅矛は、九州の有明海沿岸地域その他から、かなり出土している。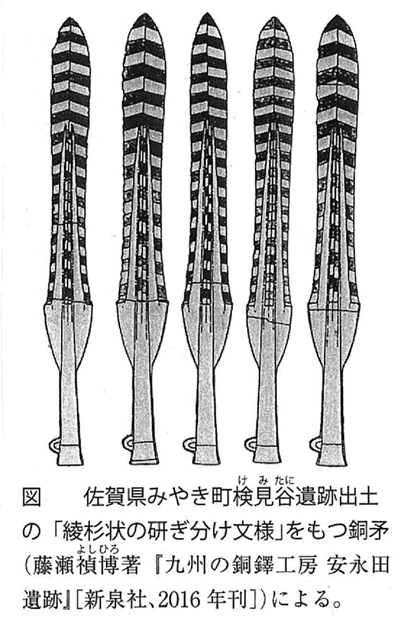
この「綾杉状の研ぎ分け文様」をもった銅矛は、九州の有明海沿岸地域その他から、かなり出土している。
次のようなものである。[藤瀬禎博(ふじせよしひろ)著『九州の銅鐸工房安永田(やすながた)遺跡』(新泉社、2016年刊)に示されたデータによる]
(1)佐賀県みやき町(ちょう)検見谷(けみたに)遺跡 10本
(2)大分県宇佐市谷迫(たにさこ) 3本
(3)佐賀県吉野ヶ里町目達原(めたばる) 2本
(4)佐賀県唐津市千々賀庚申山(ちちかこうしんやま) 1本
(5)福岡県朝倉市甘木下渕(あまぎしたぶち) 1本
(6)福岡県うきは市小塩(こじお) 1本
(7)福岡県須玖岡本遺跡D地点 1本
(8)佐賀県鳥栖(とし)市田代(たしろ)[伝] 1本
九州と出雲とのつながりを思わせる。
また、島根県の大原郡加茂町岩倉の加茂岩倉遺跡から、1996年に、39個の銅鐸が出土している。
この加茂岩倉遺跡の地は、古代の大原郡の「屋代郷(やしろのさと)」のうちにはいるとみられる[少し上の地図(肥の河流域の地名と遺跡)参照]。「屋代(やしろ)」の地名については、すでに検討した。
日本神話が伝えているような、九州勢力の、何度かにわたる出雲方面への進出[伊邪那岐の神(いざなぎのかみ)の話、須佐之男の命(すさのうのみこと)の話、出雲の国譲りのさいの天の菩比の命(あまのほひのみこと)の話など]などの結果により、銅鐸は埋められることになったのであろうか?
■「須佐の男の命(すさのおのみこと)は、海原(うなばら)を治めよ」
『古事記』『日本書紀』は、次のようなことを記す。
伊邪那岐の大神(いざなきのおおかみ)は、「筑紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(おど)の阿波岐原(あわきはら)」で、天照大御神(あまてらすおおみかみ)、須佐の男の命(すさのおのみこと)、月読の命(つきよみのみこと)などの御子(みこ)を得る。
そして、伊邪那岐の大神は、命令をする。
「天照大御神は高天の原(たかまのはら)[北部九州方面か]を治めなさい。」
「須佐の男の命は、海原を治めなさい。」(これは、『古事記』の記載。『日本書紀』では、「滄海之原(あおうなはら)を治めなさい。」となっている。)
もし、「須佐の男の命(すさのおのみこと)」を「卑弥弓呼[ひみここ(ひこみこ)]」と重ね、「狗奴国」を熊本県方面と重ねるならば、「海原(うなはら)」は、八代灘、八代海、島原湾、有明海方面を指すことになるであろう(下の地図参照)。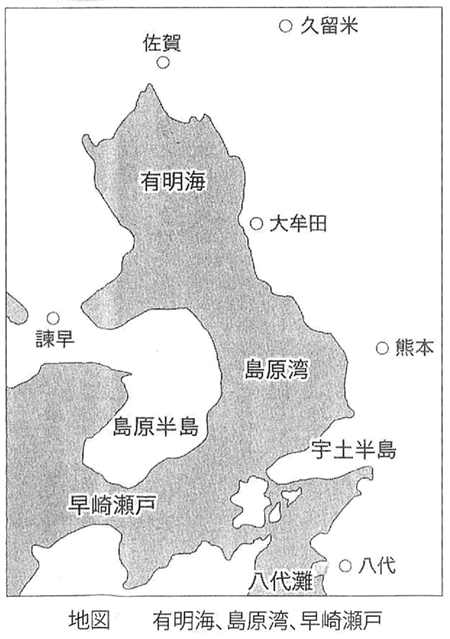
筑紫平野の血脈として流れる筑後川は、有明海へとそそいでいる。有明海は、干潮時と満潮時の水位の差が、わが国でもっとも大きいといわれている海である。筑後川の河口での有明海の水位の差は、干潮時と満潮時とで五メートルをこえる。干潮時には、筑後川の濁流ははるかな沖合で海に達する。
有明海では、このような干潟(ひがた)の幅が、最大六キロメートルに達するところもある。濁流は泥をふくみ、満ち潮は泥をさかさまにはこんで、海岸に堆積する。
筑後川の上流部は多雨地帯で、とくに梅雨(つゆ)と初秋のころに襲ってくる台風にともなう豪雨は、有明海の満潮とあいまって大氾濫をおこす。
有明海、島原湾の入口のところにある早崎瀬戸(はやさきせと)[早崎海岸]については、地名学者の吉田東伍が、その編著の『大日本地名辞書』(冨山房、1972年版)のなかで、「潮流強疾(きょうしつ)[強くてはやい]」「急速を以(もっ)て其名(そのな)高し」と記している。
八代海における大潮時の干潮時と満潮時の水位の差は、四メートルに達するという。球磨川は、大量の土砂を、八代湾に運ぶ。また、流木や灌木などの漂流物を運び、漁業者を悩ませるという。八代海が、外海と接する海域では、急流となり、渦潮(うずしお)も見られる。
貝類や海草が豊富であるが、八代海は、うまく治める必要があったようである。
■『三国志』と『後漢書』とで、「狗奴国」の記載が異なる
蛇足にさらに、蛇足を加えよう。
中国で「魏」の国は、「後漢」の時代のあとに成立している。
ところが、「魏」のことを記した史書の『三国志』は、「後漢」のことを記した史書「後漢書」よりも前に成立している。
つまり、王朝の順番と、史書の成立の順番とが、逆になっている。
『三国志』の成立は、西暦284年ごろとみられる。これに対し、『後漢書』の成立は、426年ごろである。
そのため、時代的にはさきの後漢王朝のことを書いた『後漢書』の著者、范曄(はんよう)は、時代的にはあとの魏王朝のことを書いた『三国志』を参考にして、『後漢書』を書いている。
もちろん、『後漢書』には、後漢の光武帝が、倭の奴国に印綬を与えたことなど、「後漢書」独自の記載も多い。
ところで、『三国志』と『後漢書』とでは、「狗奴国」についての記載内容が異なっている。
次のとおりである。
(1)『三国志』では、
「(女王国の)南に狗奴国(くなこく)あり。」
「女王に属せず。」
「女王国の東、海を渡りて千余里、また国あり。皆(みな)、倭の種なり。」と記す。
(2)いっぽう『後漢書』では、
「女王国より東のかた、海を度(わた)ること千余里にして、拘奴国(くなこく)に至る。皆(みな)倭種なりといえども、女王に属せず。」と記す。
つまり、『三国志』では、女王国の南にあった「狗奴国」が、『後漢書』の「拘奴国」では、女王国の東にあったことになっているのである。(『三国志』の「狗奴国」の「狗」は、「けものへん」、『後漢書』の「拘奴国」は、「てへん」。)
これは、ふつう、『後漢書』の著者の范曄が『三国志』を雑に読み、女王国の南にあったとある狗奴国と、女王国の東にあった倭種の国とを、ごっちゃにしたのであると考えられている。
私もおそらくそうであろうと思う。
私の主観的な、心理的確率では、六、七割方は、范嘩が『三国志』を、読みまちがえたのであろう、と思う。
しかし、二、三割の心理的確率で「まてよ」とも思う。
『三国志』では、「狗奴国」と「女王国の東にある倭種の国」とは、はなれた箇所(かしょ)に記されている。「女王国の東の国」については、わざわざ「海を渡りて」とも書いている。
一方の「狗奴国」は、「南」、一方の「海をわたった倭種の国」は、「東」と、はっきり書いてある。『後漢書』の著者は、そんなに簡単に、話をごっちゃにするであろうか?
次のような考えは、あるいは、なりたつのではないかとも思う。
「狗奴国王」と須佐之男の命(すさのおのみこと)とを重ねることにする。陳寿が、『三国志』を書いたころは、須佐之男の命が出雲へ追放されたという話は、まだ、中国に伝わっていなかった。
陳寿が、『三国志』を書いた284年ごろ以後も、倭国は、中国と外交交渉があった。413年に、倭王賛がいたことは、『梁書』に記されている。421年に、倭王讃に称号を与えたことは、『宋書』に記されている。
そして、『後漢書』の成立は、そのあとの426年ごろなのである。
『後漢書』の著者の范嘩は、狗奴国が出雲方面に移って、そちらに存在しているというような情報を得て、「拘奴国」が、女王国の東にある、と書いたのではないか。
おそらく、以上は、私の思いすごしであろう。
以上のような考えは、おそらく、『古事記』『日本書紀』を、まったく読もうとされない考古学関係の方は、「そんなばかな」と思われるであろう。しかし、文献学関係の方の中には、「もしかして、それもあるかもよ。」と思われる方がおられるのではなかろうか。
千古茫茫(ほうぼう)。夢が、案(あん)[つくえ、または、思案]の上をかけめぐる。「狗奴国」については、確実にいえる事実もある。おぼろげに考えられることがらもある。そのような時代なのである。







