■第2回「安本美典賞」贈呈式
 第2回目となる「安本美典賞」として、
第2回目となる「安本美典賞」として、 安本美典賞選考委員会 代表内野 勝弘会長から新井宏先生へ表彰状と副賞が謹呈されました。
安本美典賞選考委員会 代表内野 勝弘会長から新井宏先生へ表彰状と副賞が謹呈されました。
■新井宏氏の業績(安本先生講演)

2023年に古代史の分野で、著名な方の本が、二冊刊行された。
一冊目は竹岡俊樹『考古学研究法』(雄山閣、2023年刊)である。
この本の下記の記事で新井宏氏の論文を紹介している。
新井宏は、歴博の正式論文「古墳出現期の炭素14年代」『国立歴史民俗博物館研究報告』第163集(春成2011)について、「基礎資料として、肝心な図に土器型式の表示がなく、炭素14年代と土器型式の対比表もない」と批判している[4]。
下図は、新井が報告書の14の「年代較正図」を要約したものである。
(下図はクリックすると大きくなります)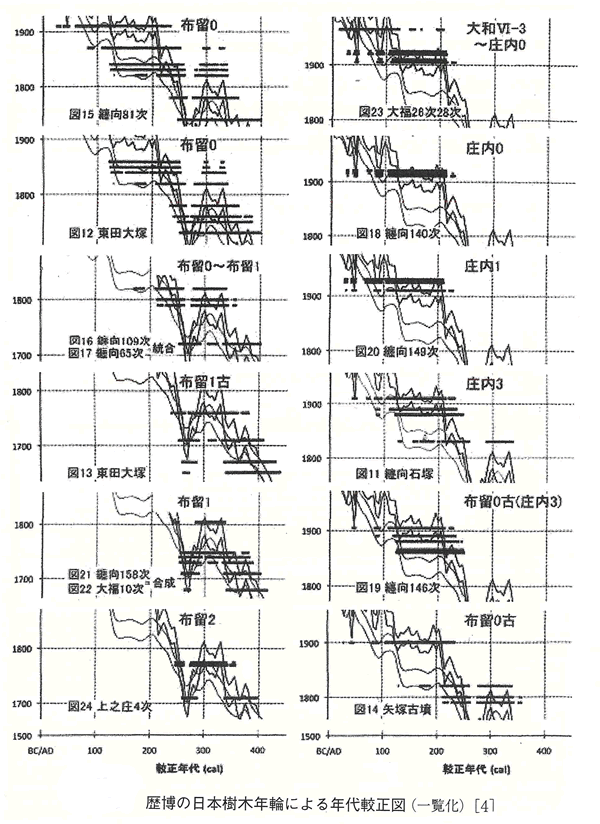
そして、庄内1式、庄内3式、布留0式 布留1式、布留2式の「確からしい推定範囲」を上の図から読み取って下の表を作成する。

各土器型式の時期はオーバーラップしていて、分離しているとは言えない。
しかも、肝心の布留0式期の炭素14年代のデータには西暦120年から340年までの幅がある(歴博年代は240 - 260年)。
さらに、新井は歴博の2011年の正式報告書にはデータの改変がみられると指摘している。
正式論文で庄内3式期として取り扱われた6件のデータの内、5件は原報告書では庄内3式期とはされてはおらず、また、纒向石塚については、原報告書で庄内1式期から布留0古式期という範囲で示されていた3件を、正式論文では庄内3式期と特定し、その上、原報告書で庄内0式期と特定されていたものまでも、庄内3式期と変えている。
さらに、箸墓年代推定の直接的な根拠とされた東田大塚の6件の資料についても、原報告書では布留0式期から布留1式期と記載されていた自然木、竹皮などを布留1古式期と限定している。もしこの資料が布留0式期とされていたなら、「箸墓築造年代が240年から260年」という結論は出せなかったはずである。
また、概報で取り上げられていた唐古・鍵の布留1期のデータは、正式報告では検討対象からはずされ、年代較正図の提示も行われていない。
さらに、今日まで、土器付着炭化物の炭素年代が樹木と同じように得られるということは検証されていない、と新井は述べている。
土器炭化物とその他の試料を用いたときの違いは、第26~28表(注:この表は省略)のようである[5]
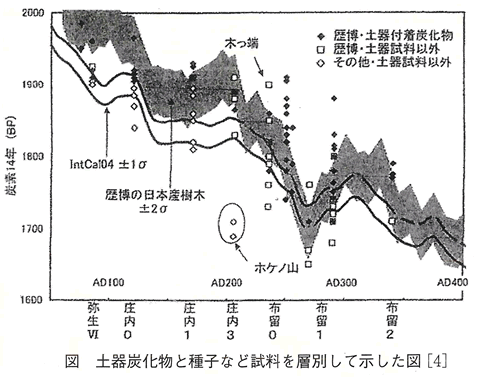
理由はいまだ明らかではないが、やはり土器付着炭化物の炭素14が他の試料と比べて50~100年古く出ていることが分かる。
[参考文献]
[1]新納 泉 2009 箸墓古墳の炭素14年代考『考古学研究』56 - 2
[2]新井 宏 2008 歴博の炭素14年をめぐる論理矛盾『季刊邪馬台国』第100号
[3]河崎貴一 2009/10/22「朝日新聞がミスリード・箸墓古墳 -奈良-「卑弥呼の墓」にダマされるな」『週刊文春』
[4]新井 宏 2011 箸墓年代の歴博正式論文批判一資料の改変・隠蔽と土器炭化物問題の無視-『季刊邪馬台国』第111号
また、この紹介記事の元は『季刊邪馬台国』111号である。
その内容を以下に示す。
大特集『邪馬台国畿内説』の論理の検討
[第一部]国立歴史民俗博物館グループの2011年報告書の検討
箸墓年代の歴博正式論文批判
-資料の改変・隠蔽と土器炭化物問題の無視-
数理考古学者 前韓国国立慶尚大学招聘教授 新井宏
1はじめに
今年になって国立歴史民俗博物館(歴博)は[古墳出現期の炭素14年代]について正式な論文(以下正式論文)を『国立歴史民俗博物館研究報告』第一六三集に発表した(春成2011)。2009年5月の日本考古学協会発表会において「箸墓は240~260年と捉えるのが合理的」と報告した概報(春成2009)と著者もタイトルも同じものである。
この2009年5月の概報については、学会講演以前にマスコミによって大々的に報じられ、邪馬台国論争と絡んで大波紋を呼んだものであるが、学術発表の内容についても批判が相次いだ(安本2009b、新井2009b、関川2009,白石2009、新納2009)。
そもそも、弥生末期から古墳初期の時期は、炭素14年代の較正曲線に「平坦部」や「うねり」があり、原理的に80年以下の精度で求めることなどできないはずなのに、ピンポイントに西暦240~260年と報告したからである。
「歴博のアイディアは、炭素年のデータを時系列的に、庄内1→庄内2→庄内3→布留0→布留1→布留2と配列し、較正曲線の谷部分(西暦270年)の前後に布留0式期と布留1式期を振り分けて配置し、グラフの表示によって箸墓古墳の年代を西暦240~260年と挟み込むものであった。確かに、グラフだけを見ると、誰でも歴博の結論はきわめて整然としているかのように感じられた。
しかし、内容をチェックすると、グラフの横軸、すなわち較正年代は「型式の範囲内であれば、較正曲線に合う形」に任意にプロットしているし、土器形式判定の一部も原報告から変えられているし、不都合なデータはプロットされていないなど、恣意的な取り扱いが多く、学術報告としての要件をまったく満たしていないのである。」
「炭素14年代の測定結果など、ほんの「さしみのツマ」、あるいは「小道具」としてしか使われていないのである。
いわば「始めに結論ありき」の議論である。そういえば、概報の一年前にも歴博は考古学協会総会において、データも不完備の状態で、異なった解析手法を採りながら、結論は「箸墓古墳の布留0式は三世紀中頃と考えるのが合理的である」としていた(藤尾2008)。これにも厳しい批判が相次いだ(簸田2008、新井2008b)」
「以上によって、正式論文の主要部分において、「明快な表示」の意図的な欠如があり、データの土器型式期の「改変」や「隠蔽」があったことを説明した。」
「3土器付着炭化物の炭素年代の問題
土器付着炭化物の炭素年代が古くでていることについては、再三再四警告してきている。それにもかかわらず今回も同じことを書かなければならないのは、筆者にとっても食傷気味であり、しいて言えば苦痛である。しかし、歴博の論文構成上の基本的な問題点を指摘するばかりでは、結論が「明らかに間違っている」ことについて十分説明したことにはならない。やはり、土器炭化物の問題を避けては通れない。」
「歴博のように、考古学を研究する公共機関であるならば、如何にしたら土器付着炭化物から信頼できる炭素年代を得ることができるかの基礎研究こそ優先させるべきである。膨大な費用をかけて、炭素年代を測定しても、結果的に使えないデータばかりであれば、まったく有害無益なのである。」
2023年2月26日(日)の第407回邪馬台国の会の、
・炭素14年代法はどこまで信頼できるのか
で、木本博(きもとひろし)氏『邪馬台国への”道”が分かった』(新潮社年刊)
でも同じような内容の話を紹介した。
また、費用対効果のバランスが悪すぎるでも紹介した。
詳細掲載省略
もう一つの本は寺沢薫『卑弥呼とヤマト王権』(中央公論新書)である。
この本の中で新井宏氏の論文が引用されている。
「公表された鉛同位体比の測定データを詳細に再検討した新井宏氏は、領域Kには領域Eとのオーバーラップが認められることを指摘し、朝鮮系青銅器には雲南(うんなん)省の鉛をふくむ商周青銅器のリサイクル品が数多く存在することが原因ではないかと想定した。さらに肝心の三角縁神獣鏡が属する領域Eには、遼寧省や河北省の鉛鉱山、朝鮮半島の全州(チョンジュン)鉱山、そして日本の岐阜県神岡(かみおか)鉱山の鉛までがふくまれるという[新井、2007年]。」
参考文献
新井宏2007年『理系の視点からみた「考古学」の論争点』大和書房
■三角縁神獣鏡について
大阪府茨木市にある前方後円墳、紫金山(しきんざん)古墳は、「4世紀中ごろから後半ごろの築造」(『日本古墳大辞典』東京堂出版)と考えられている。
ここからは、直径35.7センチの、下の写真のような大鏡が出土している。この鏡は、まわりに、わが国の勾玉がずらりと並べられて刻まれている。だれがみても日本で作られた「倭鏡」である。

この紫金山古墳からは、「三角縁神獣鏡」が10面出土している。
考古学者の森浩一によれば、紫金山古墳出土の三角縁神獣鏡は、鈕の孔が、「全て鋳放(いばな)し(鋳たままで、仕上げをしていないもの)」で、「鈕の孔が全く塞がっているのが」あったという(森浩一「魏鏡と『倭人伝』への認識をぼくが深めていった遍歴」[『季刊邪馬台国』110号、梓書院、2011年])。
つまり、鈕が、鋳造したままで、中には、鋳物の土が詰まったものがあったというのである。また、いっしょにでた大型の鏡も、「鈕の孔が鋳放し」であったという。
森浩一は、そこで述べている。
「中国の皇帝などが周辺の国の人、王などに鏡を与えるときは、必ず紐のところにその王の身分を示す色の組紐を通してあります。だから『倭人伝』のところにも、卑弥呼に与えた印は、『金印紫綬』と書いてあるでしょう。金印も同じように紐をつけます。紫色の組紐。紐は腐ってくるから、よく鏡だけ発掘品に並べてあるけれど、組紐というものとセットで、ある意味では組紐のほうがものずごく重要だったですね。紫綬。だから、もしも本当に三角縁神獣鏡というものが魏の皇帝が大量生産で卑弥呼の使いにやった鏡とすれば、紫綬を通すところの、鈕の孔はきれいに造りあげて、そこには何色かの組紐がつけてあってしかるべきなのです。」
森浩一が述べていることと、ほぼ同じ趣旨のことを奈良県立橿原考古学研究所の所長であった菅谷文則(すがやふみのり)も述べている。
「鏡そのものを見てみますと、三角縁神獣鏡と、いま言われております長宜子孫銘の内行花文鏡でありますとか、それより後の画文帯神獣鏡 --三国時代の画文帯神獣鏡でありますが-- を見ましても、最大の違いはどこにあるかと申しますと、三角縁神獣鏡の鈕の鋳浚(いさらえ)[安本注 鋳型で鋳た製品の仕上げ加工]が非常に不十分であるということであります。紐と申しますのは、円形の鏡の裏、普通われわれ博物館ではそれを表として見ておるわけですが、鏡の裏に穴があるわけであります。そこに紐なり、リボンなりを通して使用に便利なようにしているわけであります。有名な椿井大塚山からでました多数の三角縁神獣鏡のうちの一面は、鈕の穴がつぶれております。そのつぶれておるのは錆(さび)でつぶれたという見方もできるようなつぶれ方なんでありますが、ともかくつぶれております。
それから鋳張(いばり)[安本注 鋳型の合わせ目などに、溶けた金属が流れこみ、そのまま凝固してできたものなど。製品にとって本来必要ではない。仕上げのさいとりのぞくべきもの]ができるわけですが、私が実見しました三角縁神獣鏡のうち七、八割ほどは鋳浚が完全にされていないわけです。だから、ぎざぎざがあるわけです。非常に極端に申しますと、そこにリボン状の房を通しますとほどなく破れてしまいます。その点、画文帯神獣鏡等々はその鋳浚が非常に丁寧にされておりまして、長期間の使用に耐えるように、言い換えれば日常使用に耐えるようにつくられていると考えてよいわけであります。
その点、三角縁神獣鏡は長期間の使用に耐えることを目的にしているのではないと考えてはどうだろうかと、さきの論文で提言しています。だから、これはお墓に入れるために日本で独自にでき上がった鏡の一つのジャンルなんではないだろうかと。その点、中国で長く伝わっております鏡の系譜とは、その鈕の鋳浚という一点だけでもって違うんではないだろうかと。」(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館編『三世紀の九州と近畿』[河出書房新社、1986年])
数理考古学者の新井宏氏(韓国国立慶尚大学校招聘教授など歴任)も述べる。
「三角縁神獣鏡で鈕孔を加工しないまま放置している例の多いことにも通じ、粗製鏡であったことを意味している。これらが共に仿製三角縁神獣鏡と舶載三角縁神獣鏡に共通する製法技法であることにも注目する必要がある。」
「最初から『葬式の花輪』のように使い捨てにする認識があったのではなかろうか。そうであれば、わざわざ中国から輸入する必要性はますます少なくなる。」(新井宏氏の論文「鉛同位体比から見た三角縁神獣鏡」[『古代の鏡と東アジア』学生社、2011年刊所収])
「三角縁神獣鏡」は、わが国で古墳築造時に、その古墳の比較的近くで鋳造されたとみられる根拠が、それぞれ別の人によって、別の根拠によって主張されている。
この問題は、すこし、説明を必要とする。
そこで、次に、項をわけて説明する。
■「三角縁神獣鏡」の、「古墳築造時鋳造説」
「三角縁神獣鏡」は、わが国で古墳築造時に、その古墳の比較的近くで鋳造されたとする見解は、私の知るところ、次の三つである。
(1)鈴木勉氏の見解
(2)新井宏氏の見解
(3)私(安本美典)の見解
まず、(1)の鈴木勉氏の見解は、鏡の鋳造技術面から見た発言である。
奈良県立橿原考古学研究所共同研究員で、工芸文化研究所所長の鈴木勉氏は、その著『三角縁神獣鏡・同笵(型)鏡論の向こうに』(雄山閣、2016年)の中で、次のように述べている。
「三角縁神獣鏡の仕上げ加工痕が、出土古墳によって異なる、つまり、仕上げ加工技術が出土古墳ごとにまとまりを見せる。このことは鏡作りの工人らが出土古墳近くの各地に定住していたか、あるいは移動型の工人集団が各地の政権からの依頼を受けて各地へ赴いて製作にあたったか、を考えることになる。」
「椿井大塚山古墳の『研削』鏡16面は、どれも同じ目の砥石を使って仕上げ加工されたことが分かる。湯迫車塚(ゆばくるまづか)古墳の3面の『研削』鏡には同じ細かい目の砥石が使われたことがわかり、佐味田宝塚古墳の3面の『研削』鏡にも同レベルの細かい目の砥石が使われたことが分かる。」
「仕上げ加工の方法は、同范(型)鏡群よりも、出土古墳によって規定されている。」
「三角縁神獣鏡」は、わが国で古墳築造時に、その古墳の比較的近くで鋳造されたとみられる根拠が、それぞれ別の人によって、別の根拠によって主張されている。
三角縁神獣鏡製作の仕上げのさいの加工の技術が、出土古墳ごとにまとまりを見せる、というのである。
つまり、仕上げ加工の方法は、同范(型)鏡(工場でつくられた製品のように、同じ文様、同じ型式の鏡)でも、出土古墳が異なっていれば違いがあり、同じ古墳から出土した鏡は、異種の鏡でも、同じであるというのである。
また、数理考古学者の新井宏氏は、鏡の原料の銅にふくまれる鉛の同位体比について調べ、鈴木勉氏とまったく違う方法・根拠により、鈴木勉氏とほぼ近い結論を述べておられる(新井宏氏の見解は、『古代の鏡と東アジア』、[学生社、2011年]に収められた論文「鉛同位体比から見た三角縁神獣鏡」に述べられている)。
新井宏氏は述べる。
「鉛同位体比の分析結果が複製鏡の存在をきわめて強く示唆する事例があるので、まずそれらを紹介したい。それは、同一遺跡から出土した鏡の中に、中国での流行時期も流行地域も異なるにもかかわらず、鉛同位体比が(同一の鏡のように)一致している事例が数多くあることである。「他人の空似」とばかりは言えないのである。それらを整理して下表に示す。」
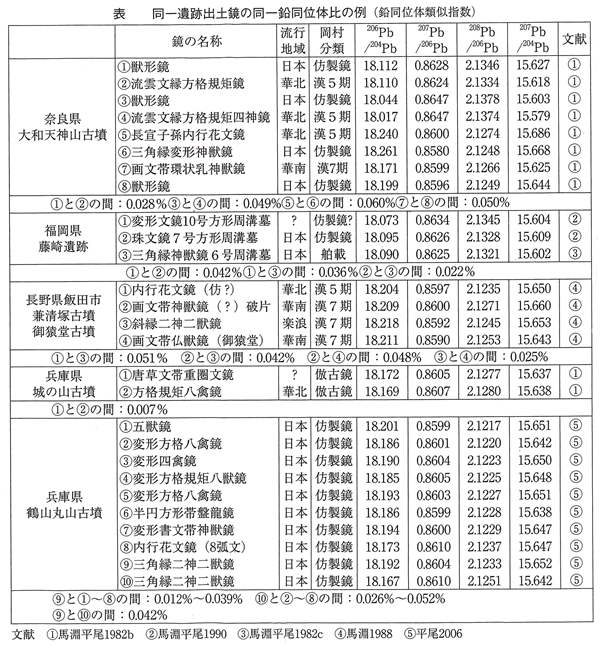
■コピー鏡を作るさいの面径の変化に着目
私も鈴木勉氏や新井宏氏と、ほぼ同じ結論に到っている。ただ、そのような結論を導き出す方法、根拠は両氏とは、また異なる。
私の方法は、鏡のコピー鏡(同笵鏡、同型鏡、踏み返し鏡などといわれるもの)を鋳造するさいに、収縮や、拡大現象がおき、もとの鏡(原鏡、原型など)にくらべ、条件により、コピー鏡の面径が、大きくなったり、小さくなったりすることがあることに着目するものである。
「三角縁神獣鏡」には、コピー鏡が多いが、そして、同一古墳から、コピー鏡が数面出土することがあるが、ある鏡の、同一古墳から出土したコピー鏡では、面径が一致する傾向がみられ、異なる古墳から出土したコピー鏡のあいだでは、古墳ごとに面径が異なる傾向がみられる。このことに着目した議論である。
なお、さきに紹介した『古代の鏡と東アジア』のなかの、菅谷文則氏の論文、「三角縁神獣鏡-国産説の立場から」のなかで、菅谷文則氏が、つぎのようにのべておられることは、やや注目すべきことのように思える。
「洛陽の鏡を調査しましたが、洛陽は、後漢、魏、西晋の首都でした。首都の墓を見ていくと、面白いことに多くの鏡を見たもののなかに、方格規矩鳥文鏡、方格規矩四神鏡などたくさんありましたが、大事なことは、同紋様の鏡は一枚も無い。洛陽の中で同じ鏡、同型にしろ、同范にしろ同じものは無かった。洛陽の鏡というのは、上は大臣から下は役人までの墓を中国では無作為に発掘しており、そこから出土した鏡です。
確実なことは言えませんが、同じ型や同じ范で作られた鏡は、洛陽には無いということです。それはどういうことかと言うと、洛陽の鏡を作る人たちは、同じ型のもの、同じ紋様のものを作って、それを皇帝から土産だと送って朝貢国に贈るという思想はまったく無かった、ということです。つまり、洛陽では、皇帝から鏡をもらうとか、皇帝の工房で同じような似たものを、できるだけ同じ紋様、でぎるだけ同じ文章(銘文)を持つ鏡を、さらに同じ直径のものを作って皇帝から臣下に配るということはなかったようです。
また、町で作っている鏡屋さんも、同じものを作って渡すこともなかった。これは洛陽の調査を数年繰り返した結果、確信を持って言える当たり前のことです。これは状況証拠にしか過ぎませんが、大変なことだと思います。同じ大小、図文のものを大量に作る、という思想は鏡ではなかったということです。」
・新井宏氏著『理系の視点からみた「考古学」の論争点』の「プロローグ」から
藤原正彦氏はベストセラー『国家と品格』の中で、数学者としての観点から、「長い論理は危うい」「短い論理は深みに達しない」と述べている。筆者なりに三角縁神獣鏡に例を採っていえば、「風が吹けば桶屋がもうかる」式の長い論理によって魏鏡であることを説明する議論がある一方で「なぜ三角縁神獣鏡が中国から出土しないか」との問いかけに「特鋳説」で答え、その「特鋳説」の論拠はと問われて「中国から出土しないから」と答えるような短い論理もある。確かに、いずれも危うい。
理系の視点からいえば、これらの論理展開の問題点についても書いてみたい。しかし、不十分とはいえ、既に問題指摘も多くあるので、それは筆者の役割とはいえないだろう。筆者の特徴はあくまでデータに基づく議論、それも数値データに基づく推論にあると自認している。現場操業データや実験データを見て、問題点を発見するのは、技術者、研究者の最も重要な能力であり、その点ではいささか自負しているものがあるからである。
したがって、筆者の主張は、主観的な思考を排し、基礎的な姿値データに基づき展開したものである。







