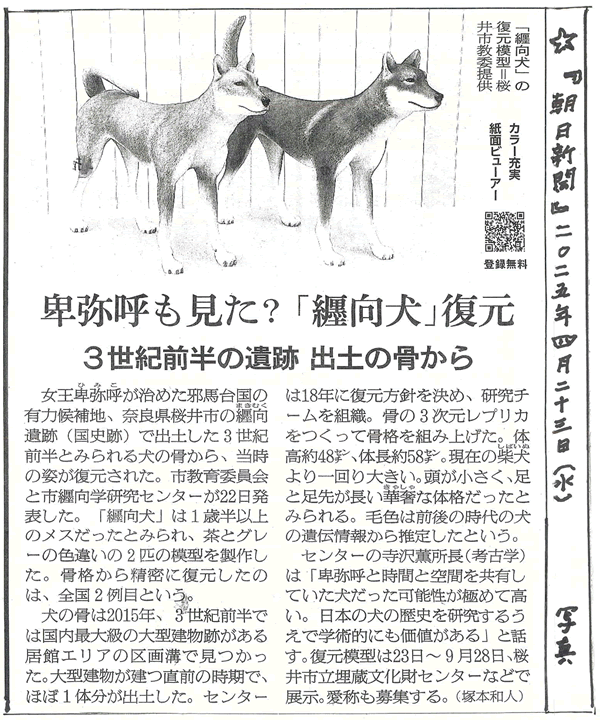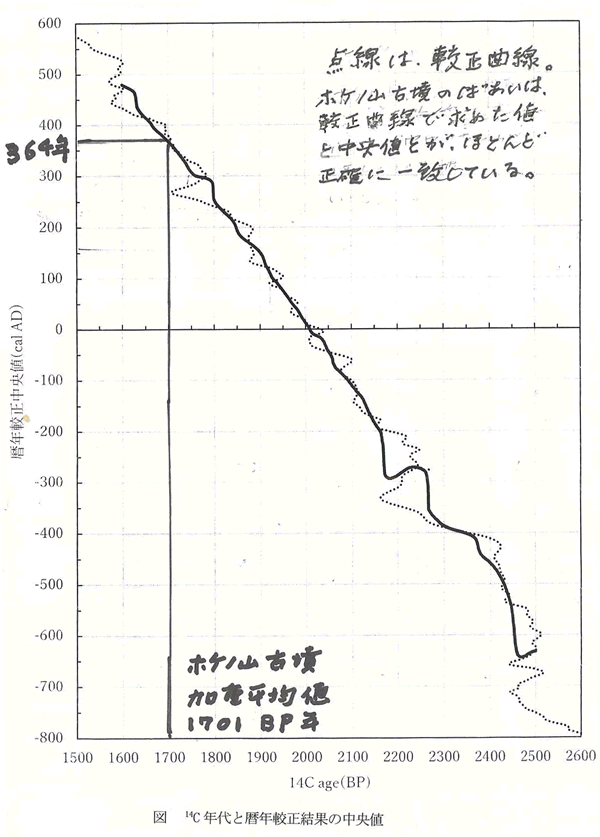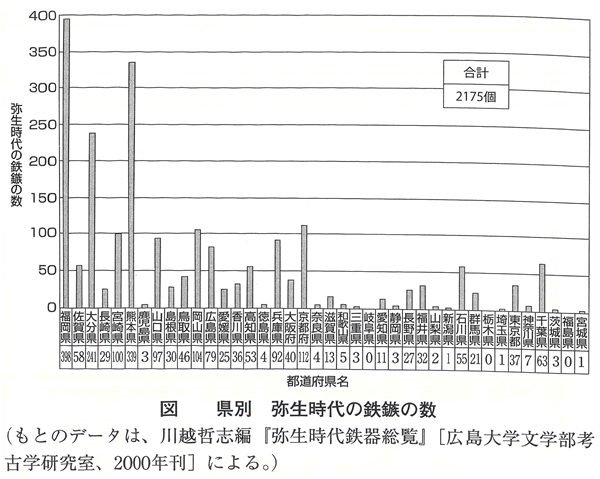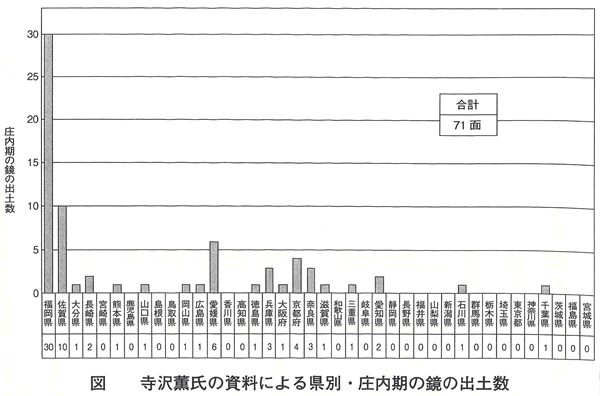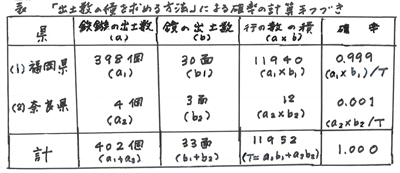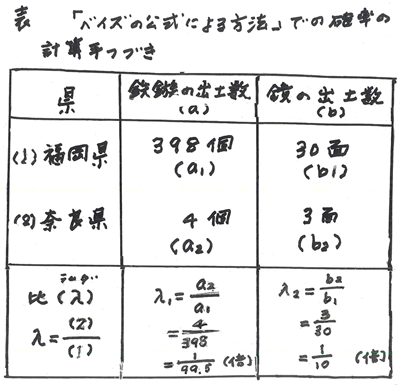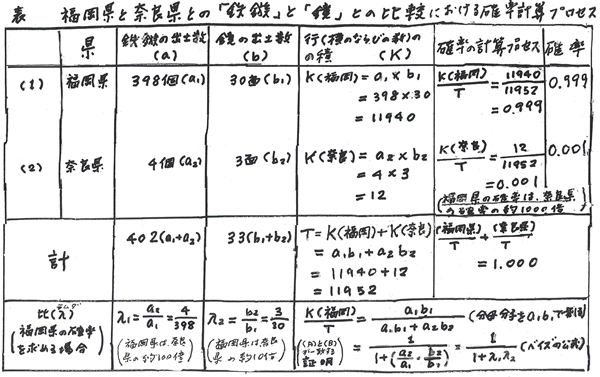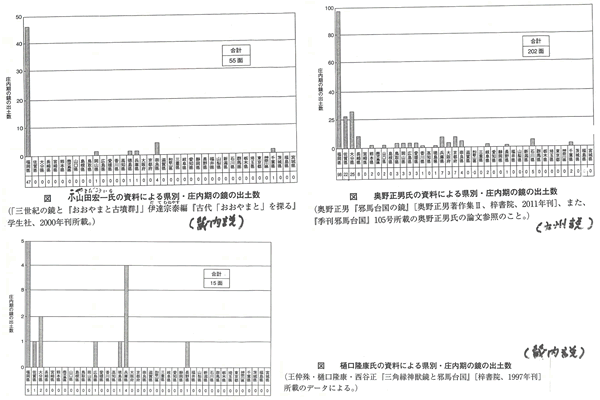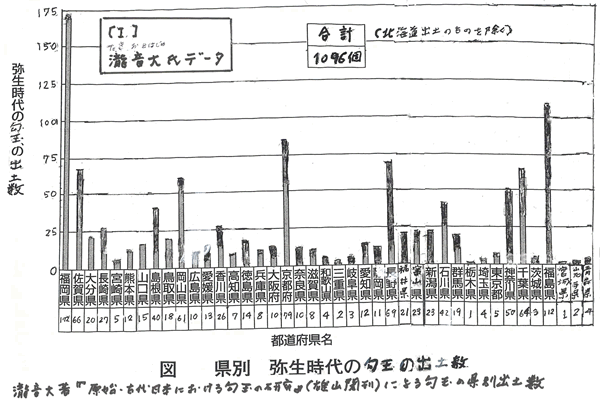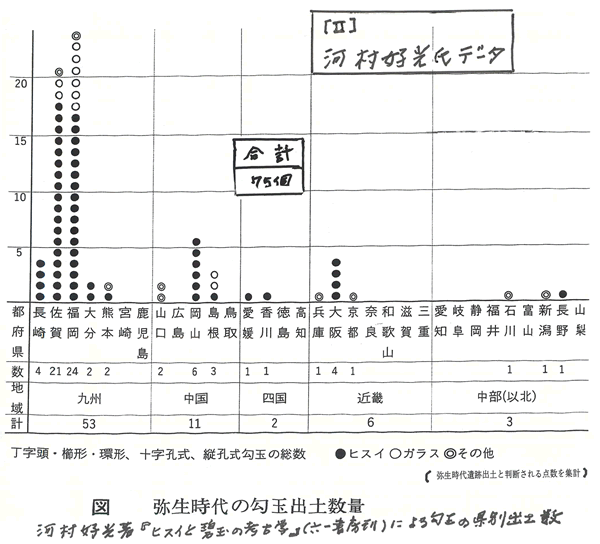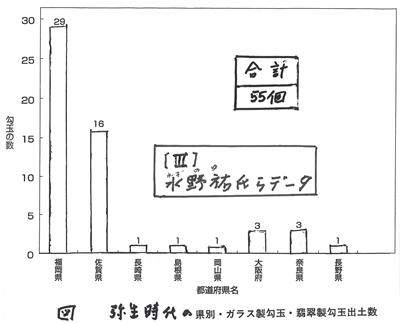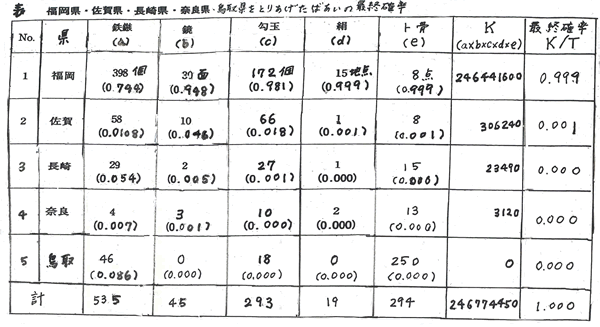■纏向と邪馬台国の問題がしばしば話題になる。
桜井市纏向学研究センター所長の寺澤薫氏は、その著『卑弥呼とヤマト王権』(中央公論新社、2023年刊)の中で述べる。
「纒向の地がこの国の初期の天皇の都宮が置かれた場所として伝承されてきたという歴史的重要性を挙げよう。
『日本書紀』には、第10代崇神天皇の磯城瑞籬宮(しきみずがきのみや)、第11代垂仁(すいにん)天皇の纒向珠城宮(たまきのみや)、第12代景行天皇の纒向日代宮(ひしろのみや)とあり、『古事記』では、御真木入日子印恵命(みまきいりひこいにえのみこと)[崇神天皇]の師木水垣宮(しきみずがきのみや)、伊久米伊理毘古伊佐知命(いくめいりひこいさちのみこと)[垂仁天皇]の師木玉垣宮(たまがきのみや)、大帯日子淤斯呂和気天皇(おおたらしひこおしろわけのすめらみこと)[景行天皇]の纒向日代宮と書く。纒向は師木(磯城)に包括される地域であるから、垂仁の纒向誅城宮が師木玉垣宮であるならば、崇神の磯城瑞籬宮は纒向水垣宮であったとも考えられる。」
この文章はよく考察されていて正しい。
「マキムク」の名は『魏志倭人伝』には現れず、『古事記』『日本書紀』にあらわれるのである。(『尾張国風土記逸文』などにもあらわれる。)
宮内庁の陵墓要覧の「古代天皇陵の陵形」の表(下図参照)から、第8代孝元天皇と第9代開化天皇の陵墓は前方後円墳であるとしているが、多くの考古学者はこの陵墓の比定は違うのではないかとしている。そして第10代崇神天皇の陵墓の比定はあっているのではないかとしている。
(下図はクリックすると大きくなります)
「纏向」という地名は、国内・国外の文献を通覧すれば、卑弥呼や邪馬台国と結びつく地名ではなく、崇神・垂仁・景行などの天皇名と結びつくものであり、時代は4世紀後半ごろと考えられる。
それを、寺沢氏は時代を繰り上げて、卑弥呼・邪馬台国と結びつけるのはかなり無理がある。
それは、桜井市の機関につとめる寺沢氏の、桜井市の名を顕揚したいという意識的・無意識的な願望によってもたらされたもののようにみえる。
そのような顕揚のつみ重ねのうえに、「纏向といえば、卑弥呼・邪馬台国」という条件反射構造が成立しているようにみえる。
・朝日新聞の犬の記事
纏向から犬の骨が出土したからといって、犬が卑弥呼と関係があるわけではない。しかし新聞報道では、纏向は3世紀前半の遺跡であるからとして、報道している。
(下図はクリックすると大きくなります)
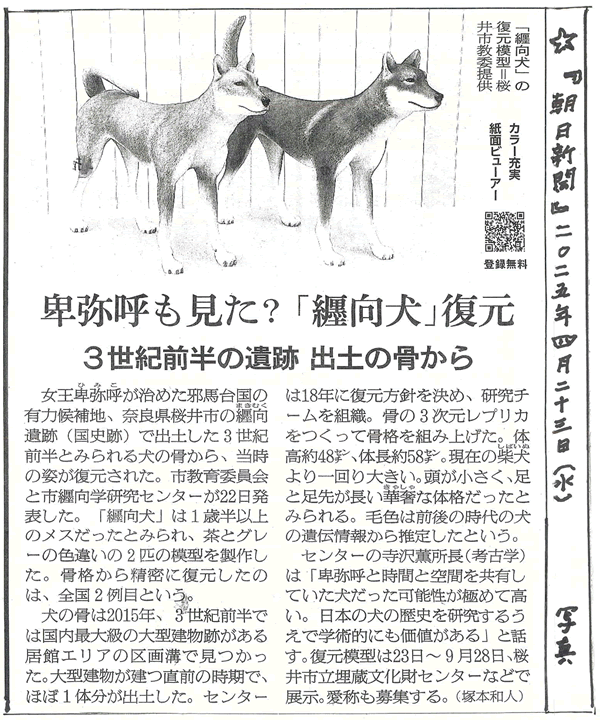
この犬の記事から
(1)「犬」のことは、『魏志倭人伝』に記されていない。
(2)「犬」は、纏向以外の日本列島の広い範囲にいた可能性が大きい。
(3)それを卑弥呼と結び付けて記事にするマスコミにも問題があるが、発表する機関にも問題がある。
読売新聞社の記者であったジャーナリストの矢澤高太郎氏は、次のように述べていている。
「新聞やテレビで大きく報道されることによって社会的な関心が高まり、遺跡の生命が守られたケースは多い。しかし、同時に弊害もまたさまざまな形で発生した。学者にとっては、地味な論文を発表する以前にマスコミで大々的に取り上げられるほうが知名度も高まり、学界内部での地位も保証される傾向が強まった。一部の学者や行政の発掘担当者はそれに気づき、狡知にたけたマスコミ誘導を行ってくるケースが多々見られるようになってきた。その傾向は、[旧石器捏造(ねつぞう)事件の]藤村(新一)氏以外には、考古学の”本場”である奈良県を中心とする関西地方に極端に多い。そして、発表という形をとられると、新聞各社の内部にも何をおいても書かざるを得ないような自縄自縛(じじょうじばく)の状況が、いつの間にか出来上がってしまった。そんなマスコミの泣き所を突く誇大、過大な発表は、関西一帯では日常化してしまっている。藤村(新一)氏は『事実の捏造』だったが、私はそれを『解釈の捏造』と呼びたい。」[「旧石器発掘捏造”共犯者”の責任を問う」(『中央公論』2002年12月号」)]
・纏向遺跡における前方後円墳の出現と変遷 「纏向型」から「定形型」へ
寺沢薫氏は、下図の左にある石塚古墳や矢塚古墳やホケノ山古墳のような古墳が纏向型であって、それが発展して定形になって、勝山古墳や東田大塚古墳になった。それが更に完全な定形の前方後円墳になったとする。
そして、纏向型の石塚古墳や矢塚古墳やホケノ山古墳の時代が卑弥呼の時代であるとしている。

しかし、桜井市の橿原考古学研究所の正式な報告書が出ており、それによると、ホケノ山古墳は西暦364年頃としている。
・寺沢薫氏述べている。
「あとで踏み込んで述べるけれど、多くの文献研究者は「ヤマト王権」という概念のなかに、『記紀(きき)』(『古事記』『日本書紀』)で描かれるような男性大王の系譜のイメージをもっているようだ。ところが最近の考古学の成果によって、纏向型前方後円墳の出現時期が遅くとも三世紀中頃へとさかのぼることか明らかになったために、女王卑弥呼の治世の三世紀前半が「ヤマト王権」の初期と重なりあうことになってしまった。」(本の53ページ)
「纏向遺跡で唯一、埋葬施設の発掘がおこなわれた纏向型のホケノ山古墳は、葺石をもつ三段築成であったし、埋葬施設も北頭位であった(本の写真10)。木槨(もっかく)を囲む石囲いは定形型の石槨(せっかく)の祖型とみることもできるし、副葬品の中国鏡や多数の鉄製品も定形型のもつ画一性と大差ない。
そもそも定形型といえども、竪穴式(たてあなしき)石槨に割竹形木棺(わりがたもっかん)をしつらえ、中国鏡と鉄製品・玉類を多数副葬する前方後円墳が、箸墓古墳の時期にどれほどあるだろうか。」(本の50ページ)
安本注:
①最近の考古学の成果・・・について、あきらかになっていない。
②ホケノ山古墳は『魏志倭人伝』の「棺あって槨なし」の記述とあっていない。
③ホケノ山古墳出土の小枝による炭素14年代による値は、較正曲線で求めた値と中央値がほとんど一致している。
樫原考古学研究所研究成果 第10冊『ホケノ山古墳の研究』によるホケノ山古墳の西暦年数推定値の中央値は「364年」である。その結果を、寺沢氏は、みずからの土器編年を優先して否定される。
『ホケノ山古墳の研究』のデータを基に「パレオ・ラボ」で作成したグラフは下図となる。そして、このグラフでは較正曲線の影響が小さいので、データの信頼性も高いのではないか。
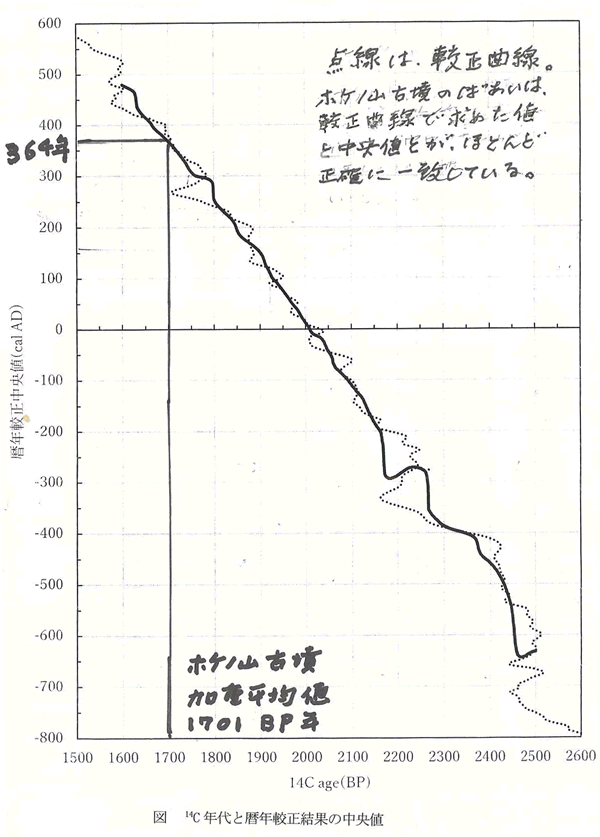
詳細は邪馬台国の会第407回講演(2023年2月26日)での説明を参照
更に、寺澤薫氏は、述べている。
「考古学のタイームスケールは、土器を編年の材料として使うことが一般的だ。(土器を編年の材料として使うことが一般的だとあるが、土器には、西暦年数に換算できる形での年号などは記されていない。)
可塑性(かそせい)のある土器には、製作者の技術や意識、その時々の流行が短期間にストレートに反映されやすいからである。」(『卑弥呼とヤマト王権』21ページ)
「それでは、この(箸墓古墳の)『布留0式』いという時期は実年代上いつ頃と考えたらよいのだろうか。正直なところ、現在考古学の相対年代(土器の様式や型式)を実年代におきかえる作業は至難の技である。ほとんど正確な数値を期待することは現状では不可能といってもいい。」[寺沢薫「箸中山古墳(箸墓)」石野博信編『大和・纒向遺跡』(学生社、2005年刊)所収]
一方で、寺沢氏はこのように、客観的に、「正直のところ、あまり分かりませんよ」と言っている。また、一方で「ホケノ山古墳は卑弥呼の時代にもって行くことは明らかなことである。」と言っている。
要するに、どこまでが客観的な推定で、どこまでが主観的な判断か分からない世界にいるように思われる。
■年代論における「類ハッブル定律現象」について
京都大学人文科学研究所の教授であった尾崎雄二郎氏は『季刊邪馬台国』14号(1982年)に、「古代里程記事における類ハッブル定律現象について」という文章を発表しておられる。
その要点は、つぎのようなものである。
「天文学で、地球から離れているほど、星雲の遠ざかる速度も大きいという『ハッブルの定律』がある。昔の人にとっては、都から離れるほど、その里程は、感覚的にふえていくものらしい。古代の里程記事においては、類ハッブル現象が見られるのではないか。」
都から遠く離れた場所は、遠いほど、実際の里程以上に、大きく離れているように、認識される。そして、そのように記載されがちであるというのである。
これは、尾崎雄二郎氏が、邪馬台国の里程記事に関連して、中国文献のいろいろな事例などをあげて論じられたものである。
尾崎雄二郎氏はのべる。
「自分の故郷というかホームグラウンドというか、とにかくベースになるものから離れれば離れるほど何らかの比例で主観的な距離はふえていくのではないか。山の高さも、それが高ければ高いだけ、われわれの普通の生活平面から遠ざかるわけですから、その分だけ、実際の差を超える差が加わっていくのではないか、と思うのです。」
ところで、距離についていえるこのような傾向は、また、「年代」についてもいえるようである。
古い時代のことは、客観的な年代よりも、さらに古めに認識されがちのようである。
『日本書紀』の記す古代の年代は、大はばに延長されている。年代が、事実よりも、古めに記載されている傾向がある。このことは、すでに、多くの人が論じているとおりである。
このような傾向は、わが国の史書ばかりではない。『三国史記』などの韓国の史書でも、また、みとめられる。
そのことは、明治寺代の東洋史学者の那珂通世(なかみちよ)が、その著『上世年紀考』のなかで、つぎのようにのべているとおりである。
「韓史も上代に遡(さかのぼ)るにしたがい、年暦の延長せりと覚(おぼ)しきところあることは、ほとんど我(わ)が古史に異ならず。」
『三国史記』の「新羅本記」は、倭国の女王、卑弥乎(呼)のことを、西暦173年にあたる条のところで記すなどしている。
このような傾向は、現代人の心にも、無意識のうちに強く働いているようである。
旧石器捏造事件のおりは、五十万年、七十万年と、年代がくりあがっていっても、専門家も、ふしぎと思わなかった。
なにか、古いものが出土したというばあい、マスコミに大きく報じられることがある。しかし、新しいものが出土したばあいは、ほとんど報道されないことが多い。
人間は、無意識の、このような心理的な傾向をもっていることは、年代などの問題をリアルに論ずるためには、強く意識化しておく必要かおる。そうでないと、ともすれば、年代は、古いほうへ、古いほうへと流されがちになる。
国立歴史民俗博物館の館長であった考古学者で、亡くなった佐原真(1932~2002)は述べている。
「弥生時代の暦年代に関する鍵は北九州地方がにぎっている。北九州地方の中国・朝鮮関連遺物・遺跡によって暦年代をきめるのが常道である。」(「銅鐸と武器形青銅祭器」『三世紀の考古学』中巻、学生社、1981)
そのとおりである。
奈良県からは、西暦年数に換算できるような年号を記した土器などは、まったく出土していない。
奈良県からは、弥生時代~庄内期の鏡が、福岡県にくらべ、はるかに、わずかしか出土していない。それにもかかわらず、奈良県の土器編年などをもとに、鏡の年代を考えるのは、非常な無理がある。
遺跡の築造年代や、遺物の「埋納年代」の手がかりを欠いたまま、空想をたくましくすれば、なんでもいえる。
同志社大学の教授であった考古学者の森浩一氏は、記している。
「最近は年代が特に近畿の学者たちの年代が古いほうへ向かって一人歩きをしている傾向がある。」(『季刊邪馬台国』53号、1994年春号)
関川尚功(ひさよし)氏は、ホケノ山古墳からは、布留式土器の指標となる小形丸底土器が出土していることから、ホケノ山古墳も、箸墓古墳も、桜井茶臼山古墳も、布留1式期のものとしておられる。
旧石器捏造事件の告発者、竹岡俊樹氏は、その著『考古学研究法』(雄山閣)の中で、まず、関川尚功氏の、つぎの見解を紹介する。
「ホケノ山古墳をどうしてもみんな古く古くしたがるのですが、いくら古くしようと思っても、ホケノ山古墳には布留1式というくびきが掛かっているわけです。(安本注。ホケノ山古墳からは、布留式土器の指標とされる小形丸底土器が出土している)これ以上は、もう古くはできません。----それを動かそうとしたら、それは考古学ではなくなりますから。そういう考古学の編年の基本原則というのは、やはり、きっちりしておかなければいけないと思います。」
その上で、竹岡俊樹氏は述べる。
「高島(忠平)も布留1式に出現する小形丸底壺が出土していることから、ホケノ山古墳は4世紀後半のものごある、としている。小枝の年代と合致する。」
竹岡俊樹氏は、邪馬台国問題でも、事態を正確にとらえておられるようにみえる。
参考資料
布留式土器(ふるしきどき)
畿内の古墳時代前期の土師器様式。壺・甕など各器種とも丸底で、小形丸底壺(坩)・鉢・小形器台の小形精製土器3種が揃う。
庄内式土器(しょうないしきどき)
弥生後期の畿内第5様式土器と古墳時代前期の布留(ふる)式土器との間をつなぐ型式として、田中琢が提唱した土器型式。古墳時代初頭の土器型式として設定されたが、都出比呂志は定型的前方後円墳出現以前だとして弥生第6様式と改称した。大阪府庄内小学校々庭遺跡を標式とする。
(以上、大塚初重・戸沢充則編『最新日本考古学用語辞典』柏書房刊による。)
ホケノ山古墳からは木槨が出ている。下記の古墳からも木槨が出ている。
・岡山県倉敷市盾築墳丘墓(双方中円形)
「棺を覆う木槨」(2世紀末?)
・島根県出雲市西谷墳丘墓群
方丘部四隅突出 三号墓 「木棺を囲む木槨」
『魏志倭人伝』書いてある「棺あって槨なし」に当てはまるのは、甕棺や箱式石棺の九州地方だけになってしまうのではないか。
寺澤薫氏は、纏向遺跡の年代を、百年ていどは、古くみつもっておられると考えられる。
■ベイズの統計学により計算された「確率」の再現性、堅牢性、安定性について
「ピタゴラスの定理」というのがある。
「ピタゴラスの定理」がなぜ成立するのか、その証明法を知らなくても、「ピタゴラスの定理」を用いることができる。
それと同じことで、「ベイズの公式」というのがある。その公式がなぜ成立するのかを知らなくても、「ベイズの公式」を用いることができる。
「ベイズの公式」を用いることじたいは、いたって簡単である。「鉄鏃」や「青銅鏡」や「勾玉」などの県別出土数から、「邪馬台国が福岡県にあった確率」「奈良県にあった確率」などを求めるのであれば、中学生でも電卓一つと根気があれば、計算できる。
ここでは、そのことを中心にお話しよう。
ごく簡単な例から話を始め、いまのような「仮説」をたてたばあいを考える。
(a)邪馬台国は、福岡県か奈良県かの、どちちかにあったものとする
(b)「鉄鏃」と「鏡」との、出土量の多い県ほどその量に比例して、その県に、邪馬台国が存在した可能性は、大きいものとする。
[寺沢氏は、存在するか否かだけを考え、「どれだけ存在したか」を考えていない。]
「鉄鏃」および「鏡(青銅鏡)」の県別出土数は、下の2つのグラフのとおりである。(拙著『邪馬台国は99.9%福岡県にあった』勉誠出版、2015年刊、参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)
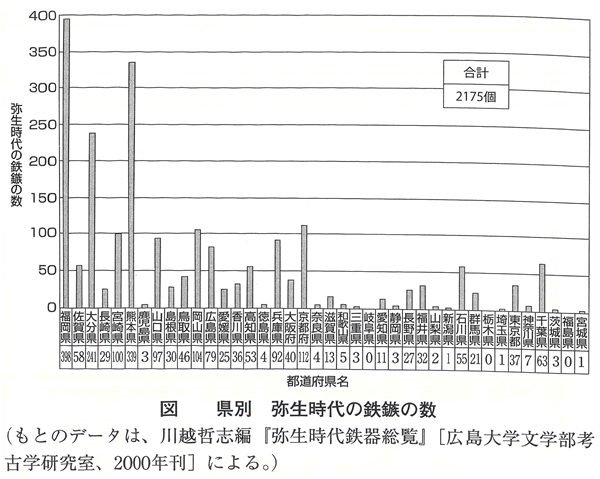
(下図はクリックすると大きくなります)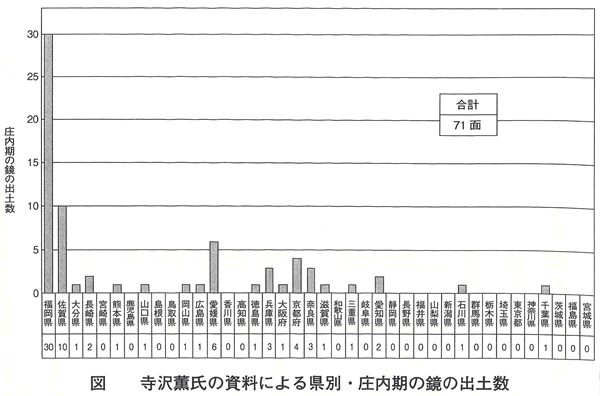
ベイズの統計学による確率計算法を、[A][B]二とおり示す。どちらの方法で計算しても、出てくる答えは変わらない。
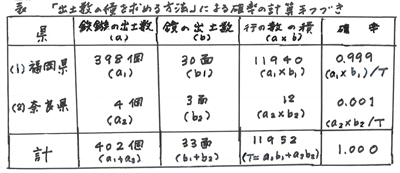
[A][出土数を求める方法]
右表の行の値(横のならびの数、鉄鏃と鏡の出土数の積を求めることによる方法。この方法は、計算のプロセス自体は単純で、機械的に行うことができ、どうすればよいかがわかりやすい。しかし、その計算によって、なぜ「邪馬台国が福岡県にあった確率」「奈良県にあった確率」が算出されることになるのか、その意味を理解することが難しい。
[B][ベイズの公式方法]
この方法は、なぜ「邪馬台国が福岡県にあった確率」などを求めることができるのか、計算の意味が[A]の方法にくらべわかりやすい。ただ、[A]に比べ計算は少し面倒になる。(とくに、行と列をふやしたばあい。)
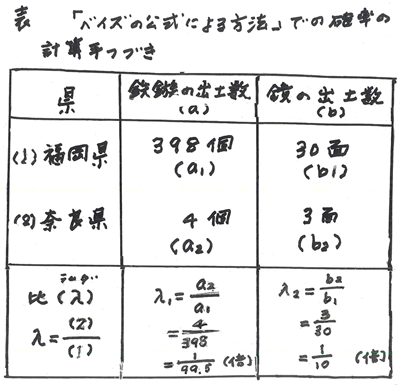
[ベイズの公式による計算プロセス]
λ1×λ2=1/99.5×10=0.001
邪馬台国が福岡県にあった確率=1/(1+λ1×λ2)=0.999
邪馬台国が奈良県にあった確率=λ1×λ2/(1+λ1×λ2)=0.001
[A]の方法と[B]の方法とで、答が一致することの証明
邪馬台国が福岡県にあった確率=1/(1+λ1×λ2)
=1/[1+(a2/a1)×(b2/b1)]=a1×b1/(a1×b1+a2×b2)
=a1×b1/T
データのあり方によって、[A]の方法が楽なばあい、[B]の方法が楽なばあいがある。
また、、[A][B]以外の計算法もある。
これらの「鉄鏃」と「鏡」をベイズの定理で計算すると下記の表のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
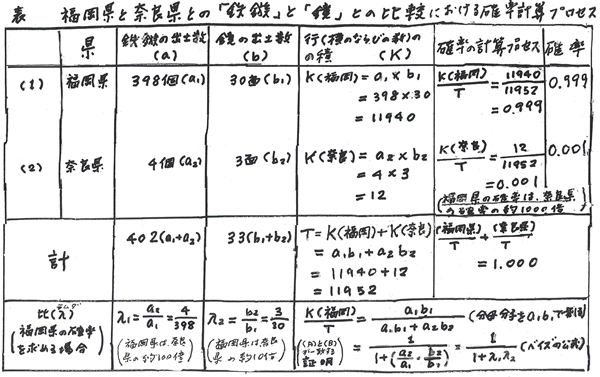
■「統計的再現性」について
小説家で、工学博士でもある森博嗣(もりひろし)氏は、その著『科学的とはどういう意味か』(幻冬舎新書、幻冬舎、2011年刊)という本のなかで、次のように述べている。
「では、科学と非科学の境界はどこにあるのだろう?
実は、ここが科学の一番大事な部分、まさにキモといえるところなのである。
答をごく簡単にいえば、科学とは『誰にでも再現ができるもの』である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが『科学的』という意味だ。
ある現象が観察されたとしよう。最初にそれを観察した人間が、それをみんなに報告する。そして、ほかの人たちにもその現象を観察してもらうのである。その結果、同じ現象をみんなが確かめられたとき、はじめてその現象が科学的に『確からしいもの』だと見なされる。どんなに偉い科学者であっても、一人で主張しているうちは『正しい』わけではない。逆に、名もない素人が見つけたものでも、それを他者が認めれば科学的に注目され、もっと多数が確認すれば、科学的に正しいものとなる。
このように、科学というのは民主主義に類似した仕組みで成り立っている。この成り立ちだけを広義に『科学』と呼んでも良いくらいだ。なにも、数学や物理などのいわゆる理系の対象には限らない。たとえば、人間科学、社会科学といった分野も現にある。
そこでは、人間や社会を対象として、『他者による再現性』を基に、科学的な考察がなされているのである。」
「まず、科学というのは『方法』である。そして、その方法とは、『他者によって再現できる』ことを条件として、組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また、再現の一つの方法として実験がある。」
また、生物学者の池田清彦氏は、その著『科学とオカルト』(講談社学術文庫、講談社、2007年)の中で、次のように述べている。
「十九世紀までは、現在のような制度化された科学はなかった。そればかりか、今日、科学の重要な特徴と考えられている客観性や再現可能性を有した学問それ自体もなかったのである。」
そして、池田氏は、「『再現可能性』という公準」という見出しの節をもうけて、例をあげて、「再現可能性」「同じやり方に従って行なえば、だれがやっても同じ結果がでることこそが、「科学」において重要であることをのべている。(解釈主義との違い)
化学や物理学や医学・薬学など、実験可能な分野における「実験」にあたるものが、天文学における「観測」や、社会科学や人文(じんぶん)科学おける「統計的調査」である。
・鏡と勾玉の県別出土数は福岡県が多い
上の方の「寺沢薫氏の資料による県別・庄内期の鏡の出土数」のグラフで、福岡県は奈良県よりも大きな差で鏡の出土数が多いという結果は、下のグラフのように、奥野正男氏(九州説)、小山田宏一氏、樋口隆康氏(畿内説)の示すグラフも同じ結果を示している。
(下図はクリックすると大きくなります)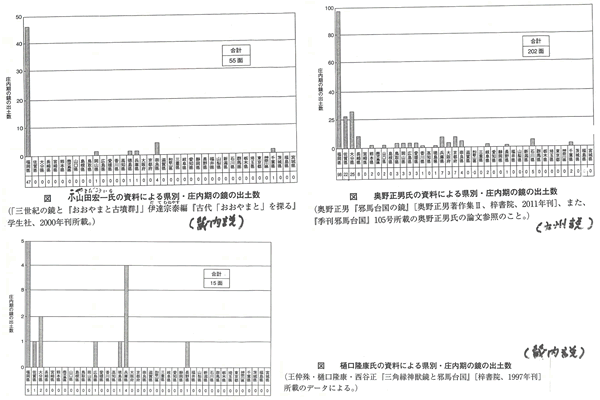
同じように勾玉についての県別出土数も
瀧音大(たきおとはじめ)氏のグラフ(下のグラフ)
(下図はクリックすると大きくなります)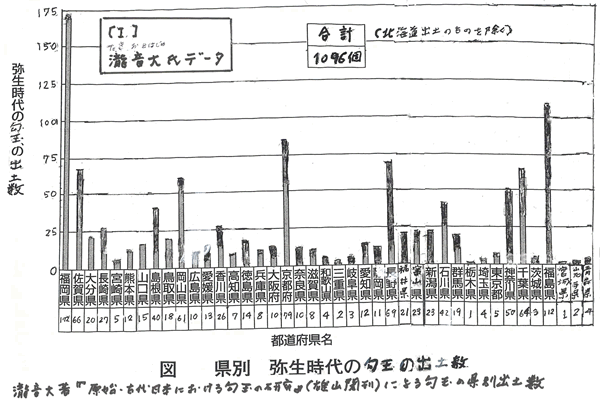
河村好光氏のグラフ(下のグラフ)
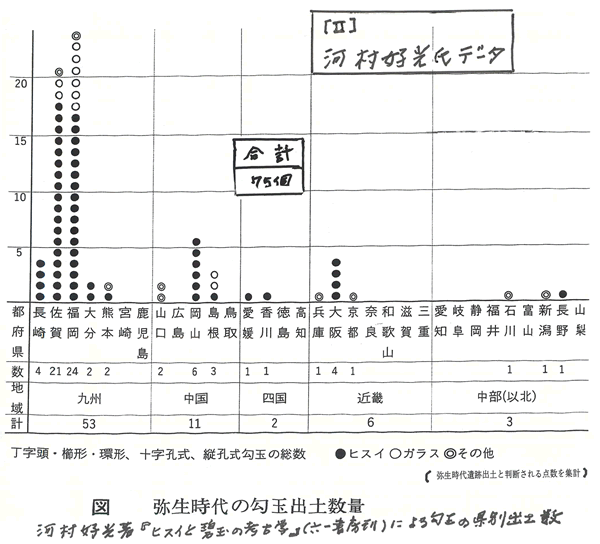
水野祐氏のグラフ(下のグラフ)
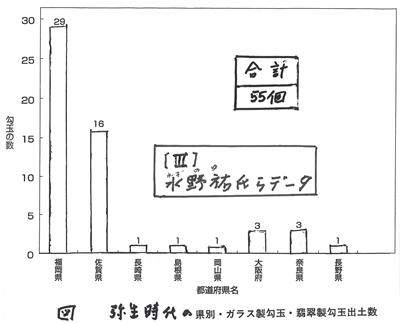
このように、『魏志倭人伝』に記載されている、ものの出土数は福岡県が圧倒的に多い。
[寺沢薫氏の述べる見解(1) -「鉄」について-]
寺沢薫氏はその著『卑弥呼とヤマト王権』(中央公論清社、2023年刊)の211ページで、広島大学の川越哲志(てつし)編の『弥生時代鉄器総覧』(広島大学文学部考古学研究室2000年刊)に示されたデータなどをもとにして、つぎのように述べる。
「(鉄器出土量は)古墳時代の初めまで一貫して北部九州や中部九州の圧倒的な量におよばないことは、一目瞭然だ。とくに機内地方は寥々たるものだ。
その後の集計でも、(弥生時代)後期から古墳時代初めの鉄器出土量の様相は変わらない。」
この資料で示した弥生時代の鉄鏃の県別出土数(18ページの図4)は、寺澤薫氏が指示または支持された川越哲志氏の『弥生時代鉄器総覧』によっている。
[寺沢薫氏の述べる見解(2) -「鏡」について-]
この私(安本)の資料の、19ページの図5は、寺田薫氏の著書『弥生時代政治史研究 弥生時代の年代と交流』(吉川弘文館、2014年刊)に示されたデータによっている。
なお、寺沢薫氏は「三角縁神獣鏡」について、次のように述べている。
「三角縁神獣鏡は画文帯神獣鏡や斜縁神獣鏡をひな型として日本で製作されたとみる方が合理的だと私は考えている。(『卑弥呼とヤマト王権』329ページ)---石野博信氏、国産説
この計算に「佐賀県」「長崎県」「鳥取県」を加え、「勾玉」「絹」「卜骨」を加えても。結果はあまり変わらない。
(下図はクリックすると大きくなります)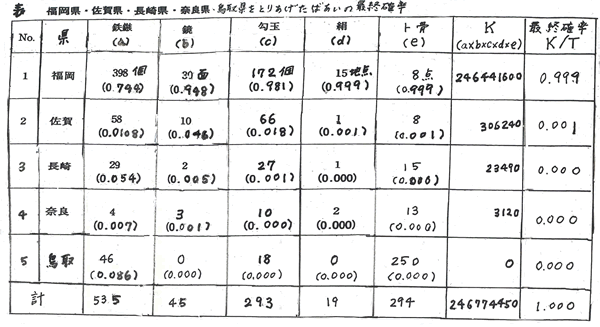
いづれにしても、邪馬台国が福岡県にあった確率は圧倒的に高い
「確率」の概念なしで、科学上の問題を論ずるのは「尺度」なしで「距離」を論じ、「時計」や「暦」なしで、「時間」や「年代」を論じ、「温度計」なしで寒暖や体温を論ずるようなものである。考古学の分野では、「1mmは1mよりも大きい」とするような議論が大手をふって歩いている。遺物を測定するにしても、「確率」を測定しないからである。
寺沢薫氏の提出したデータ、支援するデータ、支示するデータからは、寺沢氏の主張する結論は、みちびきだせない。
フィッシャー流の統計学(現在のふつうの統計学)では、1%(0.01)または5%(0.05)以下の確率でしか成立しない仮説はすてて(棄却して)先にすすむ約束になっている(議論の客観性を保つため)。この立場をとれば、「邪馬台国福岡県説」のみが成立することになる。