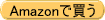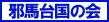 |
TOP > 著書一覧 > | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
| 邪馬台国は、銅鐸王国へ東遷した 大和朝廷の成立前夜 |
||||
| 本書「はじめに」より ●銅鐸出土の状況から構築する古代の新世界● |
日本古代史の問題点 最近の日本古代史の探究、とくに、考古学者による邪馬台国論については、問題点がしばしば指摘されている。傷口(きずぐち)は、しだいに大きく広がりつつあるようにみえる。 問題点の第一は、「正解」は「邪馬台国=畿内説」であるときめてかかり、そこから演繹して、データを理解しようとする姿勢が顕著であることである。 考古学者の北條芳隆(ほうじょうよしたか)氏(現、東海大学教授)はのべる。 「いわゆる邪馬台国がらみでも、(旧石器捏造事件と)同じようなことが起こっている……近畿地方では、古い時期の古墳の発掘も多いが、邪馬台国畿内説が調査の大前提になっているために、遺物の解釈が非常に短絡的になってきている。考古学の学問性は今や、がけっ縁(ぷち)まで追いつめられている。」(『朝日新聞』2001年11月1日) 北條氏は、ここで、「邪馬台国畿内説が調査の大前提」とのべる。それは、炭素14年代測定法や、年輪年代法などによる、本来、自然科学的で、客観的なデータや結果でさえ、「邪馬台国畿内説」を前提とし、その前提にとって、つごうのよい部分だけをひろいだす、あるいは、強調する、ということになりがちとなっている。事実をそのままの形で見ていない。そして、そのような「解釈」をマスコミに流し、マスコミがとりあげれば、それで、証明ができたと思いこむ。このような構造となっている。 『読売新聞』の記者であったジャーナリストの矢沢高太郎氏はのべている。 「新聞やテレビで大きく報道されることによって社会的な関心が高まり、遺跡の生命が守られたケースは多い。しかし、同時に弊害もまたさまざまな形で発生した。学者にとっては、地味な論文を発表する以前にマスコミで大々的に取り上げられるほうが知名度も高まり、学界内部での地位も保証される傾向が強まった。一部の学者や行政の発掘担当者はそれに気づき、狡知にたけたマスコミ誘導を行ってくるケースが多々見られるようになってきた。その傾向は、藤村氏以外には、考古学の”本場”である奈良県を中心とする関西地方に極端に多い。そして、発表という形をとられると、新聞各社の内部にも何をおいても書かざるをえないような自縄自縛(じじょうじばく)の状況が、いつの間にか出来上がってしまった。そんなマスコミの泣き所を突く誇大、過大な発表は、関西一帯では日常化してしまっている。藤村氏は『事実の捏造』だったが、私はそれらを『解釈の捏造』と呼びたい。」(「旧石器発掘捏造”共犯者”の責任を問う」[『中央公論』2002年12月号]) このように、「狡知にたけたマスコミ誘導」、「誇大、過大な発表」は、ほとんど「捏造」の域に達している。 北條芳隆氏、矢沢高太郎氏ともに、「旧石器捏造事件」になぞらえている。「邪馬台国畿内説」は、しだいに第二の「捏造事件」に近づきつつあるようにみえる。 データや事実にもとづき、帰納的に結論をみちびきだすという姿勢が希薄になっている。 「実事求是(じつじきゅうぜ)(事実にもとづき、真理・真実を追求する)」の精神は失なわれ、多数意見を形成することに成功すればよい、という大政翼賛的な姿勢がめだつ。これは、北条芳隆氏ののべるように、考古学の学問性を、がけっ縁(ぷち)に追いつめることになるものである。 問題点の第二は「考古学至上主義」の立場をとり、『古事記』『日本書紀』をはじめとするわが国の古文献を、軽視または無視する傾向が強いことである。 出雲からの銅剣・銅鐸の出土にしても、埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘文の告げるところにしても、大きくみれば、わが国の古典の語るところを裏切っていない。 岡山大学の教授であった考古学者の近藤義郎は、「考古学の資料は、考古学的方法によって、まず徹底的に考えて。他の分野の資料(文献資料など)による考察は、そのあとで。」という趣旨の主張をした。 考古学の分野では、このような立場をとる人は多い。それは、やがて、『古事記』『日本書紀』の伝承をはじめとする他の分野の資料を、ほとんどまったく無視し、「考古学的には、これが正しいのです。」と強く主張する考古学至上主義的傾向を生みだす。 しかし、科学や学問は、できるだけ総合性、統一性をめざすべきである。学問は、その分野だけで孤立してしまうと、容易に科学性を失ない、独断に近づいて行くものである。 ギリシヤ、ローマの考古学や、聖書の考古学は、すべての考古学のはじまりであり、母胎であった。そして、その考古学は、神話、伝承といったものに、みちびかれたものであった。 そのことを忘れてはならないと思う。私たちは、「歌を忘れたカナリア」であってはならない。 歴史学は、「だれが、いつ、どこで、なにをしたか」をたどる学問である。 しかし、考古学だけでは、そもそも、「だれが」の部分がぬけている。考古学は、本来、「なにが、いつ、どこで、どのように出土したか」をテーマとする学問であるからである。 そして、奈良県の考古学のばあい、「いつ」の部分でさえ、かなり不安定である。 奈良県出土の土器に、直接年号などが、書かれているわけではない。 では、わが国の古典は、銅鐸について、なにを語っているのか。 この本では、それを、お話ししようと思う。 この拙著のシリーズは、最初に、勉誠出版の池嶋洋次会長が、たてて下さった。この本で、すでに、十七冊目となった。 だが、日本古代史の全容の骨格を、彫りあげようとする作業は、なお、道なかばである。 今後ともの、読者のご支援をあおぎたい。私のライフワークは、よく完成できるであろうか。 本書の刊行にあたり、ご多忙中にもかかわらず、またまた、直接編集を担当して下さった岡田林太郎社長、そして、お力ぞえいただいた勉誠出版の方々に、深甚の謝意を表したい。 |
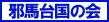 |
TOP > 著書一覧 > | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |