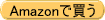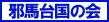 |
TOP > 著書一覧 > | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
| 邪馬台国全面戦争 | ||||
| 本書「はじめに」より 考古学における「研究不正」の構造 |
学問上の研究不正のなかに、「利益相反」にもとづくものがある。「利益相反」というのは、つぎのようなものである。 たとえば、医学研究者は、人の生命の安全をはかる職業上の義務がある。ところが製薬会社が、研究者に多額の研究資金を提供しているばあい、その製薬会社の薬がとくに有効であるかのように臨床研究データがまげられることがある。製薬会社は、まげられた情報により、この薬は、とくにききめがあるという宣伝を行なうわけである。 同一の研究者のなかに、人の生命の安全をはかるという義務と、研究資金を今後も獲得したいという気持と、「利益が相(あ)い反(はん)する形」になるのである。その結果、研究不正がおきる。 有名なものに、ノバルティス社による研究不正事件がある。この事件には五つの大学の研究者が関係した。 これについては黒木登志夫著『研究不正』(中公新書、中央公論社、2016年刊)、河内敏康・八田浩輔共著『偽りの薬』(毎日新聞社、2014年刊)などにくわしい。 これは、ノバルティス社が、自社の降血圧剤ディオバンの売り上げをのばすために行なわれたものであった。ノバルティス社にとって、驚くほど素晴らしいデータが、創出されることになる。その報告が権威のある学会誌にのった。しかしそのデータは操作されていた。 2006年には1100億円あまりであったディオバンの売りあげは、2009年には1400億円となった。 ノバルティス社からは五つの大学へ、合計11億円以上の奨学寄付金が行なわれていた。 2016年に明らかになったロシアにおける国ぐるみの組織的ドーピング事件なども、「利益相反」にもとづく不正といえよう。 国の威信をあげるという利益と、スポーツの競技を、人類共通の祭典として行ない、諸国民の融和をはかるという普遍的な利益とが、「相(あ)い反(はん)する形」となり、不正がおきたのである。 考古学の分野でも、「利益相反」にもとづく不正が、きわめてしばしばあるようにみえる。 各県などの行政担当の考古学研究者は、一方で、学問的科学的に正しい結果を報告しなければならない社会的義務がある。また一方で「地域おこし」の一端をになう義務がある。給与や調査研究費なども、県ごとなどの行政から支給されている。 その立場から、どうしても、地域の振興のほうが、学問的科学的理念よりも、優先されやすいことになる。 『読売新聞』の記者であったジャーナリストの矢沢高太郎(やざわたろう)氏はのべている。 「新聞やテレビで大きく報道されることによって社会的な関心が高まり、遺跡の生命が守られたケースは多い。しかし、同時に弊害もまたさまざまな形で発生した。学者にとっては、地味な論文を発表する以前にマスコミで大々的に取り上げられるほうが知名度も高まり、学界内部での地位も保証される傾向が強まった。一部の学者や行政の発掘担当者はそれに気づき、狡知にたけたマスコミ誘導を行なってくるケースが多々見られるようになってきた。その傾向は、藤村(新一)氏以外には、考古学の。”本場”である奈良県を中心とする関西地方に極端に多い。そして、発表という形をとられると、新聞各社の内部にも何をおいても書かざるをえないような自縄自縛(じじょうじばく)の状況が、いつの問にか出来上がってしまった。そんなマスコミの泣き所を突く誇大、過大な発表は、関西一帯では日常化してしまっている。藤村(新一)氏は『事実の捏造』だったが、私はそれらを『解釈の捏造』と呼びたい。」(旧石器発掘捏造”共犯者”の責任を問う)[『中央公論』2002年12月号]) マスコミは、正確さよりも、センセーショナリズムを重んずる傾向がある。「学界での検討」、よりも、 「マスコミでの発表」を重視するのは、学問や科学の発展にとって、好ましいことではない。 「狡知にたけたマスコミ誘導」、「誇大、過大な発表」は、ほとんど「捏造」に近くなる。 研究者、発掘担当者の多くは、善意の人たちなのである。発掘や個別事実の把握は、正確なのである。しかし、しばしば、無意識のうちに、あるいは、意識的に、地域に有利なように「解釈」がまげられる。 組織集団がある方向にむいているばあい、その内部にいる人たちには、組織集団の文化の特異性に、気づきにくくなる。 思い込みと、あるていどの論証の粗雑さとがあれば、どのような結論でもみちびきだせる。当然見えるべきものが見えず、見えないはずのものが見えるようになる。 さきに紹介した黒木登志夫著『研究不正』では、2012年に、ある麻酔科医のおこした一連の論文捏造事件については、つぎのように記す。 「学会とジャーナルは積極的に自浄能力を発揮した。特に、日本麻酔科学会の報告書は、今後のお手本になるであろう。」 これに対して、旧石器捏造事件については、つぎのように記す。 「日本考古学協会は、検証委員会を立ち上げたが、ねつ造を指摘した竹岡(俊樹)と角張(淳一)は委員会に呼ばれなかった。ねつ造発見の十日前に発行された岡村道雄の『縄文の生活誌』は、激しい批判にさらされ回収された。しかし、岡村は、責任をとることなく、奈良文化財研究所を経て2008年退官した。」 「SF(藤村新一)のねつ造を許したのは、学界の長老と官僚の権威でもあった。その権威のもとに、相互批判もなく、閉鎖的で透明性に欠けたコミュニティが形成された。」 竹岡俊樹氏じたいも、その著『考古学崩壊』(勉誠出版、2014年刊)のなかで、つぎのように記す。 「私たちがさらに情けないと思うのは、発覚の後の対応である。自らの行ってきた学問に対する反省はまったく行われなかった。藤村というアマチュアや、文化庁(岡村)に責任を押し付け、その上、批判する者を排除しつづけた。検証は名誉職が好きな『権威者』たちによるパフォーマンスにすぎず、生産的なことは何も行われなかった。」 「この十数年間待っていたが何も変わらなかった。」 「この学問が存続していくためには、失敗した検証作業にもどって、もう一度やり直すことが必要である。」 考古学の組織じたいが、自浄作用のききにくい構造となっている。容易に不正のおきやすい構造になっている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 続く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
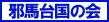 |
TOP > 著書一覧 > | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |