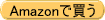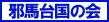 |
TOP > 著書一覧 >卑弥呼の謎 | 一覧 | 次項 | 戻る |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
講談社現代新書 |
| 卑弥呼の謎 | ||||
|
序 - 邪馬台国問題はなぜとけない 1.アンパイアのいない試合 |
昭和四十二年一月に、宮崎康平氏の、『まぼろしの邪馬台国』(講談社刊)が刊行されていら
い、邪馬台国関係の書物が、あいついで刊行されている。昭和四十二年以後に、邪馬台国問題
を直接とりあつかった単行本は、私の知るだけでも、三十冊刊行されている。年平均五冊のわ
りあいである。
しかし、邪馬台国問題は、いまなお、混迷のなかにあるといえる。 それは、なぜであろうか。はじめに、その理由をたずねておくことも、無駄ではないであろ う。 その理由を、私なりに考えてみると、まず、つぎのようなことがあげられる。
では、現代文献学の方法とは、どのような特徴をもつものであろうか。 |
 | 上へ |
|
2.「情報」をとらえる数学 |
かつて、小説家の菊池寛が、つぎのようなことをのべたことがある。
学生時代にならった数学で、社会へ出てから役に立ったのは、『三角形の二辺の和が、他 の一辺よりも大きい』ことを知って、近道をするのに役だったぐらいのものである。 ところで、その幾何学も、もともとは、測量術から発達したものであった。洪水によって失 なわれた境界を復元するためには、幾何学はなくてはならないものであった。幾何学が生まれ たころには、それは、当時の人々の実生活にとって必要なものであった。しかし、現在では、 一般の人々にとって、その実用性はうすれ、幾何学は、論理的思考を養うための道具となって きている。 数学ときいては、顔をしかめる方も多いであろう。しかし、今しばらくきいていただきた い。 時代によって、その社会がとくに必要とする数学は、変わってきている。 かつて、数学は、量的なものはとらえ得ても、質的なものは、とらえ得ないといわれてきた。 しかし、現代の数学は、その版図を、ますます拡大させ、複雑な構造、あるいは、従来質 的な言語でしかとらえられないと考えられていたことがらをとらえる数学へと、変貌をとげつ つある。 そして、現在では、「物質」ではなく、「情報」をとらえる数学が、いちじるしい発達をとげ てきている。これは、社会が、「物質」を基本とする社会から、「情報」を基本とする社会へ と、しだいにうつり変ってきていることと対応している。 かつては、数学からもっとも縁遠いと考えられていた社会科学や人文科学の諸領域において も、現在では、数量的、数学的な研究の方法が発達してきている。 |
 | 上へ |
|
3.同語反復(トートロジー)からの脱出 |
物理学者の湯川秀樹氏は、『現代の科学Ⅱ』(中央公論社刊「世界の名著」第66巻)におさめられ
ている「二十世紀の科学思想」のなかで、のべておられる。
数学が形式論理的な演繹で非常に多くの結論を出せるというのは驚くべきことであって、
数学以外のことばだけを使った論理ではそう先へは進めない。はじめからわかっているこ
と、つまり同語反復以上にはなかなか出られない。
私は思っている。邪馬台国問題は、もともと、文献学的な問題としての色彩がつよいが、す くなくとも文献の面から考えようとするかぎり、現代文献学が開発している数学的方法につい ての基礎的な知識は、どうしても必要である。 これなくして、ふつうのことばの範囲のなかだ けで考えようとする時は、トートロジーの範囲をぬけ出すことは、おそらく不可能であろう と。 |
 | 上へ |
|
4.素朴実証主義的文献批判学と現代文献学 |
現代文献学では、ある文献的事実を信じられるとするか、信じられないとするかの、客観的
基準がはっきりしている。
たとえば、具体的なデータのとりあつかいにおいては、統計学的に 「有意」といえるものは、肯定であれ、否定 であれ、積極的に主張できるとする。そうでないばあいは、「有意とはいえない(情報が不足で ある)」とする。 これをたとえるならば、スポーツにおける写真判定のようなものであろう。 これによって、現代文献学は、その議論における客観的基礎を獲得している。 現代文献学を、それ以前の文献学と比較してみよう。それによって、邪馬台国問題がなぜと けないかの問題が、さらにはっきりとするであろう。 戦後におけるこれまでの文献学の主流的な方法としては、津田左右吉によって代表される文 献批判学があげられる。 この方法の基礎は、十九世紀の末に、フランスのラングロア、セー ニョボスその他によってまとめられた。この方法は、十九世紀末の有力な科学哲学として、オ ーストリアのマッハなどが、一般的な形でといた実証主義哲学とむすびつく。そこで、この方 法を、素朴実証主義的文献批判学とよぶことにしよう。 この文献批判学は、もともと十九世紀の科学である。西欧では、とくに、プラトンの諸著作 についての研究などがきっかけとなり、素朴実証主義的文献批判学の限界が、論理的にも明ら かとなり、明確な方法をもつ現代文献学が発生し、急速な発展をとげつつある。 たとえば、プラトンの諸著作についての問題のばあい、素朴実証主義的文献批判学が、どの ような結果をもたらしたかは、東大の西洋史家村川堅太郎氏と、京大の哲学者田中美知太郎氏 とのつぎのような対談からもうかがわれよう(中央公論社刊「世界の名著」第7巻『プラトンⅡ』の 付録による)。
そのため、第二次大戦後も、極東の一角に、素朴実証主義的文献批判学は生きのこり、繁茂 の地をみいだした。 わが国では、げんざいでも、しばしば、津田史学にしたがっていないとい う理由だけによって、論理的根拠を提示することなく、他説は排撃される。しかも、その排撃 には、手段がえらばれないことがある。 戦後、二十年間に確立した権威を利用し、マスコミな どによって切りすてる。私も、そのような被害をうけたひとりである。 それは、皇国史観にも似て、信念的である。かつて、『数理哲学の歴史』をあらわしたドイ ツのG・マルチンは、素朴実証主義的文献批判学を評して、「自己自身に対して無批判な批判」 とのべたことがあるが、わが国のげんざいの古代史学界の状況は、マルチンが批判した状況に 近い。 しかし、これは、日本古代史学界において、とくにいちじるしい傾向であって、隣接科学の 分野の学者は、素朴実証主義的文献批判学にたいして、より批判的であることも指摘しておき たい。 『英雄伝説を掘る』(新潮社刊「沈黙の世界史3」『ギリシア』)の著者であり、G・W・ツェーラ ムの名著『神・墓・学者』(中央公論社刊)の訳者である西洋古典考古学の村田数之亮氏は、か つて、拙著にたいしてお手紙を下さり、そのなかで、つぎのようにのべておられる。
なぜ、わが国では、伝承がすべて虚構だとしりぞけられるのかと、ギリシアのばあいとく
らべて、その拒否反応というか潔癖というか、そんなものの強さが、私には異常なような気
がしております。
私もこれが今日の史料学の正しいあり方であると思う。曾ての史料学の素朴実証宝義は正 に『樹を見て森を見ない』危険性を包蔵しているのである。 「これが今日の史料学の正しいあり方」は過分であるが、このことばから、林健太郎氏の、素 朴実証主義的文献批判学にたいする見解はうかがわれよう。 |
 | 上へ |
|
5.科学的史学から懐疑主義へ |
現代文献学は、「確実とはいえない文献から、いかにして、正しい情報を獲得するか」の客
観的技術をたずねるのにたいし、素朴実証主義的文献批判学では、「すこしでも疑わしい史料
は用いてはならない。」とする。そして、十パーセントの疑わしさのために、のこりの九十パ
ーセントまでは、確からしいことをも、つぎつぎと捨てさるのである。
その結果、素朴実証主 義的文献批判学は、やがて、真実でないものを捨てさるとともに、多量の真実をも捨てさるも のとなりはじめる。 当初においてこそ、それは史料を無条件に信ずることへの警鐘ともなりえたであろう。科学 的史学の第一歩ともなりえたであろう。 しかし、それが発生したさいの精神よりも、その形骸 だけが固守される場合には、建設をもたらさない否定主義、懐疑主義ともなりがちである。 素朴実証主義的文献批判学の立場の方々は、その方法だけが科学的であり、それ以外の方法 は、科学的でないとされることがある。しかし、科学とは、もっと、生産力と発展性をもつも のではないであろうか。 素朴実証主義的文献批判学は、これまで、西欧や中国において、しばしば、事実によって裏 切られている。 素朴実証主義的文献批判学者が、星体神話にすぎないとした『史記』の「殷本記」にして も、空想の所産で、お伽噺にすぎないとしたホメロスの詩にしても、この方法により作為とさ れたものが、のちに、事実をふくんでいることがあきらかになった例は、きわめて多い。 この方法は、もともと、「疑うこと」を前提にしている。そのため、たとえば、わが国の神 話のばあいでも、『古事記』『日本書紀』の記事に、矛盾や納得できない点があれば、それは、 「作為」であるからこそ、そのような破綻がみられるのではないかと疑い、逆に、話のすじが、 きちんとととのっていれば、それは、「作為」であるからこそ、そのように整然としているの ではないかと疑う。 このような方法が、どのような結論をうみだすことになるか、思考実験と しては、興味があるが、これでは、わが国の神話も、すくわれないのではなかろうか。 |
 | 上へ |
|
6.十九世紀の科学と二十世紀の科学 |
しかも、どのようなばあいには、「作為」とみなすか、客観的な基準が、存在しているわけ
ではない。
非上光貞氏は、その著『日本古代史の諸問題』(思索社刊)のなかで、津田左右吉の 研究を評し、「主観的合理主義につらぬかれている」とのべておられるが、素朴実証主義的文 献批判学は、「主観」を契機として成立している。 そのため、同じくこの立場をとっても、論 者により、その結果は、まちまちとなりがちである。歴史学以外の人が、このような論著を読 めば、歴史学では、主観にしたがって、どのような議論でもしてよいのであろうかと思いがち である。 主観と主観とが議論しても、結末のつきようがない。邪馬台国問題についての混乱の かなりな原因は、このようなところにあるように思われる。 しかも、そればかりではない。十九世紀の諸科学は、みずからが仮説のひとつであることを 承認しないため、理論は、絶対的な真理か、絶対的な誤りかの、信念と信念とのぶつかりあい となる。 二十世紀に、仮説の観念が明確となり、それまでの、独断的、絶対的、信念的な考え 方から、仮説的、相対的、検証的な考え方へと転換した。 |
 | 上へ |
|
7.通説への安住 |
私がこれまでにだしたいくつかの著書を、天皇制、保守主義、神話復活とむすびつけて、そ
ういうレッテルを貼りつけ、「きわめて危険である」とすることによって、私の発言の正当な
意味を、曲げてしまおうとする試みが、すでにいくつかみられている。
私は、これらのものとは、むしろ、反対のがわに立つものである。そのことは、私の「思 想」が、もっとも表面にでているかっての著書『文章心理学入門』(誠信書房刊)などをお読み いただければ、容易にわかるはずである。 「きわめて危険である」という批判は、そのようなレッテルをはって切りすてるにおわり、た とえば、私が、『神武東遷』(中公新書)のなかでのべておいた「固定観念や先入観によってで はなく、結論がうけいれがたいとすれば、論理のすじみちのどこに無理があると考えられるの か、その無理は、本質的なものなのか、修正可能なものなのか、結論がうけいれられるとすれ ば、さらにそこから、どのようなことがみちびきだされる可能性があるか、という立場からお 読みいただければ幸いである。」というようなことばには、答えようとされない。 そこでは、みずからの立場からは、一見どんなに突飛とみえる見解であろうとも、一応は、 そこにどのような矛盾がみられるかを検討してみようという姿勢に欠けている。 いつか、みず からが、その時代の「通説」に安住して、自由な視点から、ものをみることができなくなって いることに気がついていない。しかし、そのような精神構造が、これまで、しばしば、科学の 進歩を阻害してきたのも事実である。 学問を行なうにあたっては、自分の考えと対立するものであっても、そこに地位を与えて、 論じさせることが、まず必要なことである。いずれが正しいかは、次代がきめてくれることで ある。 その時代の常識的見解にしたがわない見解は、しばしば、誤りであるとも、危険な思想 であるとも、考えられがちである。 しかし、マルクスものべている。「科学と常識とが、一致 するならば、あらゆる科学は必要でない。」と。地動説にしても、精神分析学にしても、そし てまた、津田左右吉の学説そのものにしても、その時代においては、危険な思想とも、誤りで あるとも、いわれたものではなかったか。 学問の世界においては、政治の世界と異なり、みず からと対立する見解のなかにも、あるいは、真理を含み、人類の文化を前進させうるものがあ るかもしれないという可能性を、つねにみとめなければならない。 過去の権威、いわゆる「通 説」によって、批判を行なうことはやさしい。しかし、提言は、既存の知識、周知の考え方を 知らないわけでも、無視しているわけでもなく、なおその上で、そこにおさまりきれないもの を感じ、疑問を感じたからこそ提出されているのである。 さきのような批判では、純粋に、学問上の立場から検討しなければならない問題を、政治や その他の問題によって、すりかえている。それはまた、このような批判が、合理性・科学性を 基礎とするものではなく、イデオロギー的なものを判断の基礎としていることを示している。 |
 | 上へ |
|
8.弁証法的唯物論と観念論とのむすびつき |
戦後のわが国においては、弁証法的唯物論の立場にたつ人々が、素朴実証主義的文献批判学
の成果を、そのままとりいれる傾向がみられている。
しかし、もともと、津田左右吉の考えは、唯物史観によるものではなかった。 また、レーニ ンが、『唯物論と経験批判論』(寺沢恒信訳、大月書店刊、国民文庫など)で、マッハなどを、痛烈 に批判していることなどからもうかがえるように、イギリスの経験論などの流れをひき、アメ リカを中心とする論理実証主義、分析哲学につながる素朴実証主義の考え方は、弁証法的唯物 論とは、その基本となる考え方に、あいいれないものがある。 私は、方法を重んじたいと思う性向なので、みずからの思想を表面にだすことを好まないが、 あえてのべるならば、私の素朴 実証主義にたいする批判は、その「観念性」にむけられており、本質的には、唯物論(それはマ ルクス主義と同義ではない)の立場からのものである。 |
 | 上へ |
|
9.否定的精神の開花 |
津田左右吉は、戦前、『神代史の新しい研究』『古事記及び日本書紀の新研究』『神代史の研
究』など、一連の著述をあらわし、『古事記』『日本書紀』などの文献の、史料としての価値に
ついて、くわしい研究を行なった。
津田は、主として、『古事記』『日本書紀』の記述のあいだ のくいちがい、あるいは、相互矛盾をとりあげ、そこから、『古事記』『日本書紀』に記されて いる神話は、天皇がわが国の統一君主となったのち、第二十九代欽明天皇の時代のころ・すな わち、六世紀の中ごろ以後に、大和朝廷の有力者により、皇室が日本を統治するいわれを正当 き..霞きき舞野 化しようとする政治的意図にしたがって、つくりあげられた ものである、と説いた。 端的にいえば、神話は、いわば机上でつくられた虚構であり、事実を記した歴史ではない、 ただ、それをつくった古代人の精神や思想をうかがうものとしては、重要な意味をもつ ものである、というわけである。 津田の見解は、当時、若い研究者たちに、鋭い刺激を与えた。しかし、家永三郎氏が、 日本古典文学大系の、『日本書紀』(岩波書店刊)の「解説」での べているように、戦前の学界では、「いわば異端的な業績として孤立して」いた、といってよ いであろう。 そして、東京大学の黒板勝美が、昭和七年刊の『国史の研究』(岩波書店刊)でのべている津 田左右吉の業績についてのつぎのような意見は、当時の学界における、ほぼ代表的な見解であ ったと思われる。 神話伝説というものが、とくにある時代にある目的をもって作られたようにみるのは、民 族心理学的もしくは比較神話学的の考察を一蹴したような、あまりに独断にすぎるきらいが ある。むしろ長い年月のあいだにだんだんそれらの説話が作られて来たとするほうが妥当で はあるまいか。 左翼思想、自由主義思想弾圧の時代にはいり、津田の研究も迫害される。昭和十五年、津田 の著作は、発売禁止の処分をうけ、ついで津田自身が皇室の尊厳を冒涜した疑いで、起訴さ れ、その学問的活動は、封殺された。しかし、津田の所説は、第二次大戦後の懐疑的風潮のなかで、はなばなしくよみがえる。そ して、わが国の史学界において、圧倒的な勢力をしめることとなる。 戦時中の、神話の全面肯定から、全面否定へと、はげしいうつりかわりであった。 津田左右吉の否定的精神は、すべて否定的、懐疑的となった戦後の土壌のなかで、大きく開 花した。 素朴実証主義的文献批判学の錠で、『古事記』『日本書紀』の神話の文献的価値は、破壊しつ くされた。しかし、その破壊は、絶望と怒りに近いある種の情熱によってささえられてはいて も、科学がもつ冷めたものの見方と、どこかなじまないものをもっていたように思われる。 |
 | 上へ |
|
10.画一主義の弊害 |
戦後の津田史学の盛行は、私には、つぎの二つのような弊害を生みだしたように思われる。
そして、いまや、戦後の日本古 代史学界において、権威をにぎった素朴実証主義的文献批判学の立場にたつ人々は、かつて皇 国史観の立場にたった人々と、ほとんど同じ精神構造にいたりつつある。 現実の多様性に、たえずたちかえろうとすることは、学問が、その野性と柔軟性とをたもつ ためには、ぜひとも必要なことである。つねに与えられたひとつの立場、ひとつの考え方のみ によって現実を解釈しようとするのは、一種の教条主義ともいえる。 それは、しばしば、学問 に硬直性をまねき、学問としての生命力の、枯渇と衰退とをもたらすものである。 私はひろい意味での文献学の、現代化をめざすものである。 私の方法の基礎は、『数理歴史学』(筑摩書房刊)のなかでややくわしくのべた。さらに、現代 文献学の成果や応用については、拙著『邪馬台国への道』(筑摩書房刊)、『神武東遷』(中公新書)、 「人文科学と数学」(筑摩書房刊、数学講座17『数理科学の諸問題』所収)、および『数理科学』(ダイ ヤモンド社刊)誌上に昭和四十七年二月号から十月号まで八回にわたって連載した「日本語の誕 生」などを参照していただければ幸いである。 とくに、私は、『数理歴史学』のなかで、素朴実証主義的文献批判学が、
拙考について、なんらかの見解を表明しようとされ る方々は、まず、そのような指摘のひとつひとつについて、正確に答えてみていただきたい。 |
 | 上へ |
|
11.久保泉氏の批判 |
私たちが、自然科学から学んだ最大のものは、その客観性であろう。
文献学は、もともと、文献を処理するひとつの技術としての色彩がつよい。 素朴実証主義的文献批判学では、文献の批判が、自己の感覚を主要な基準として行なわれ る、学者が、自己の感覚のみにもとづいて、文献を観察し、批判をおこなう素朴実証主義的文 献批判学は、たとえ、主観的に、どれほど厳密であろうとも、それは、その主観性のゆえに、 一定の限界がある。 じゅうぶんな客観化をめざそうとしないがゆえに、それは、ひとつの思想 ではありえても、科学とは、異質のものをふくんでいるからである。 私は、昭和四十五年に刊行された弁護士、久保泉氏の『邪馬台国の所在とゆくえ』(丸ノ内出 版刊)を、その論理性において、きわめてすぐれたものと考えるものである(ただし、この本の酷 評をおこなわれた専門家もいる)。そのなかで、久保氏は、邪馬台国の問題に関してであるが、つ ぎのようにのべておられる。
「わたしは、これらの主張を読んで、歴史学者の想像力のたくましさに、感心したというよ
りはむしろあきれてしまった。
素朴実証主義的文献批判学の立場に立つ人々が、その基礎の客観化をめざさないかぎり、こ のような批判は、永遠にあとをたたないであろう。 |
 | 上へ |
|
12.可能性の計量 |
現代文献学においては、可能性じたいを計量する。可能性の小さい仮説はすて、より可能性
の大きい仮説を、採択して行こうとする。
そして、その可能性の計量の基礎を提供しているの は、確率論であり、推計学(推測統計学)である。その基礎の上にたって、因子分析法などをは じめとする多変量解析論や、コンピュータ技術が適用される。 私たちの日常生活においても、「十中八、九」正しいと思われる仮説は、採択している。 また、いま、あなたが本を読んでいるときに、突然地震がおきて、天井が落ちてくる「可能性」 もないわけではない。しかし、そのような「可能性」は、きわめて小さいので、安心して、本 を読みすすめているのである。 確率の考え方は、いたるところに適用可能である。確率論や推 計学は適切な基準を提供しえたがゆえに、現代社会においては、幾何学などよりも、はるかに 広汎な人々にとって、必要な基礎知識となりつつある。 確率論や推計学を基礎としているので、現代文献学では、その立場から捨てた仮説が、絶対 に誤っているとは主張しない。しかし、どのように可能性の小さいことがら々、も認めるなら ば、議論が、はじめからなりたたないことは、あきらかである。 たとえば、『古事記』『日本書紀』によれば、古代のすくなからぬ天皇の寿命は、百歳をこえ ていたと記されている。それは、崇神天皇や雄略天皇のように、実在がほぼ確かな天皇につい てもそうである。 もちろん、人間が、百歳をこえて生きる可能性も、零ではない。しかし、古代において、そ のようなことが集中して起きた可能性は、きわめて小さいから、『古事記』『日本書紀』のこの ような年齢記事を、多くの学者は、そのままでは、信用しようとはしないのである。 多くの学者は、暗黙のうちに、可能性の小さいものを捨て、可能性の大きいものを採択しようとしてい るのである。 とすれば、計量できるばあいは、可能性じたいを、はっきりと計量し、比較して行くこと が、当然必要である。 そうしなければ、バランスの失した取捨選択の、行なわれる可能性があるからである。 物理学をはじめとして、現代のほとんどすべての科学は、説をたてるための客観的な基準を 定めている。それなくしては、今日の科学の隆盛は、もたらされなかったであろう。 長さを比較するのに、「モノサシ」をあらかじめ定めず、自分の主観、感覚だけで判断するならば、お なじ人の判断でも、ときとばあいによって、異なってくるであろう。 文献学も、また例外ではない。現代文献学は、科学技術のめざましい進展に呼応して、文献 処理の技術を発展させつつある。客観的な基準を設定し、信じられるものと、信じられぬもの とを弁別する技術を、より鋭く磨きつつある。 そのような客観的な基準のひとつである「有意」の概念などは、今日、人文科学の諸分野に おいても、すでに常識化してきている。それは、あることがらが、どのていどおきやすいか を、確率論の助けをかりて測定し、それによって、判断の客観性をうる道をおしえてくれるも のである。(この本の読者のなかにも、あとで説明する「有意」の概念などを、あらためて説明するまで もなくご存じの方も、すくなくないであろう。) このような科学技術の発展に眼をくれることなく、主観的な判断にもとづく議論をくりかえ していても、邪馬台国問題が解決されるみこみは、永久におとずれないであろう。 |
 | 上へ |
|
13.仮説の設定と検証 |
「邪馬台国問題を解決する」とは、なにを意味するのであろうか。
「邪馬台国問題をとく」とは、結局、邪馬台国問題について、もっとも矛盾がすくない、ある いは、「ほとんど矛盾のない」説明体系を構築することにほかならない。そのような説明体系 は、仮説の設定とその検証という過程を通してのみ構築されるものである。 ニュートン力学は、かつて、自然界を、「もっとも矛盾なく」説明しうる体系であった、し かし、それすらも、決定的な真実ではなかった。量子論によって、とってかわられた。 どのように確実にみえる理論体系も、結局は、ひとつの仮説体系にすぎない。そのことは、対象が、 自然科学、社会科学、人文科学のいずれの分野に属するものであるかを問わない。 素朴実証主義的文献批判学がみちびきだした結果も、また、ひとつの仮説である。したがっ て、それにたいする疑問や、その仮説とはあいいれないような事実が指摘されたばあいには、 それらが、その仮説の基礎をゆるがすものであるのか、それとも、その仮説の範囲内で、説明 がつくものであるのかが、検討されなければならない。 反対意見にたいしては、レッテルをは って切りすてようとするがごときは、その立場が、科学というよりも、むしろ、ひとつの思想 といったものに立脚していることを示している。 それはまた、独断とドグマとに、容易におち いりやすい可能性をもつものである。 |
 | 上へ |
|
14.研究の良否 |
以上のようなことから、邪馬台国問題についての研究の良否を判断するめやすとして、すく
なくとも、つぎの三つをあげることができるであろう。
|
 | 上へ |
|
15.「年代」をとりあげる意味 |
この本では、とくに、「年代」の問題をとりあげた。
歴史上のことを考えるさいに、「年代」 が必要であることは、地図に、緯度や経度が必要であるのにも似ている。 しかし、最近の古代史関係の論著のいくつかをみるとき、「年代」の問題が、深くほりさげ て考えられていないため、おちいっていると思われる誤りも、すくなくないように思われる、 また、「年代」を考えることによって、解決すると考えられる問題も、すくなくないようであ る。 この本で、とくに「年代」の問題をとりあげたのは、このような理由による。 |
 | 上へ |
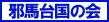 |
TOP > 著書一覧 >卑弥呼の謎 | 一覧 | 次項 | 戻る |