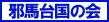 |
TOP > 著書一覧 >高天原の謎 | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
講談社現代新書 |
| 高天原の謎 | ||||

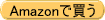 |
いまなお論争に論争をよぶ謎の女王国=邪馬台国。
しかし、日本古代史には、もう一つの長くはなばなしい歴史をもった論争がある。 それが高天原論争である。 いったい、日本神話のふるさと=高天原は実在したのだろうか。 したとしたらどこにあつたのか。 邪馬台国との関係は…。 本書は、この論争の諸説を整理検討し、新しいアプローチで謎を解明した労作。 |
|
序 − 忘れられた論争 1.いま一つの「九州説」と「大和説」 |
戦後のはなばなしい邪馬台国論争のかげで、ほとんど忘れ去られている論争がある。
それは、日本の古代史に関係する論争で、邪馬台国論争とほとんど同じていどの研究の歴史 をもつ。そして、戦前までは、邪馬台国論争と同じていどに、あるいは、それ以上にはなばな しく議論された論争であった。 その論争は、高天の原論争といわれるものである。『古事記』『日本書紀』などの、いわゆる 日本神話で語られている「高天の原」は、じつは、のちに大和朝延の中心となった勢力の祖先 が、遠い昔にいた場所についての記憶を、伝承の形で伝えたものではなかろうか、したがっ て、この地上のどこかの地をさしているのではなかろうか、とする論争である。 ふしぎなことに、この高天の原論争も、邪馬台国論争と同じく、もっとも有力な説として は、「九州説」と「大和説」との二つがあった。すなわち、高天の原は、九州をさし示してい るとする説と、畿内大和をさし示しているとする説との二つがあった。 戦後、日本神話の作為説が説かれ、日本神話は、ずっとのちの、六世紀の中ごろ以後に、大 和朝廷の貴族たちによって、大和朝廷の権威を高めるために、つくりあげられたものであると する説がさかんとなった。 そして、高天の原論争は、正統の史学者たちからは、ほとんど論じ られなくなった。なぜならば、高天の原論争は、日本神話が、なんらかの史的事実を、おぼろ げな形ででも、伝えていることを前提としているからである。もし、日本神話が、ずっとのち の時代につくられたものであるとするならば、高天の原論争がなりたつ余地は、ほとんどなく なってしまうからである。 しかし、私は、これまでにあらわしたいくつかの本のなかで、日本神話を作為とする説が、 真実とそうでないものとを、客観的に弁別する具体的な技術をもつものではないこと、したが って論理的に大きな欠点をもち、それがみちびきだした結論も、多くの矛盾をもっていること を、ややくわしく述べてきた。 また、作為説の基礎となっている素朴実証主義的文献批判学 が、外国では、トロヤの発掘や殷墟の発掘や、そしてまた聖書にもとずく発掘などにより、く りかえしダメージをうけてきたことも指摘した。 さらに、前著『卑弥呼の謎』(講談社現代新書)では、年代論的に検討してみるとき、日本神 話にあらわれる天照大御神が、卑弥呼の反映である可能性が、かなり高いことなどをみてき た。 とすれば、天照大御神が活躍していたと『古事記』『日本書紀』の伝える高天の原こそが、 邪馬台国についての、おぼろげな記憶である可能性が生じてくる。ここで、高天の原論争は、 邪馬台国論争に、重なりあってくるのである。 厚くつもった忘却の土を、とりのぞいてみよう。高天の原についての、長い論争のあとを、 今一度、掘りおこしてみよう。この忘れられた論争のなかに、邪馬台国への道をさし示す道し るべが、朽ちかけて倒れている可能性があるのである。 |
 | 上へ |
|
2.「天」には、都の意味がある
|
『古事記』『日本書紀』は、高天の原が、「天」にあったとしている。ところで、この「天」が
地上の中央、都をさすとする解釈は、すでに、奈良時代からあった。
たとえば、『万葉集』巻十八の、大伴家持が、叔母の大伴坂上郎女におくった歌、 「天ざかる鄙の奴に天人(あまひと)しかく恋すらば生ける験(しるし)あり」(4082) の、「天ざかる」は、「都から遠くはなれた」の意味である(歌の下の数字は、歌番号、テキスト は岩波書店の『日本古典文学大系』の『万葉集』による、以下同じ)。 家持は、みずからを「鄙の奴」といい、それにたいし、坂上郎女を「天人」と呼んでいる。「天人」は、「都の人」の意味でいったものと考えられる。 『万葉集』巻三の、柿本人麿の、「天離る夷の長道(ながぢ)ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ」(255) 巻五の、山上憶良の、「天ざかる鄙に五年住ひつつ都の風俗(てぶり)忘らえにけり」(880) などの、「天ざかる」も「都からはなれた」の意味である。 さらに、万葉歌人は、天皇が一時都をはなれて、地方に行幸したのを、しばしば、「天降(あも)り」 として歌っている(たとえば『万葉集』巻二、199「行宮(かりみや)に天降り座(いま)して」など)。(以上の、「天」に、中央、都の意味があるとする解釈については、京都大学、国語学の、阪倉篤義教授の御教示によると ころが大きい。) 現在でも、都へ行くことを「上る」、地方へ行くことを「下る」という。 『古事記』や『日本書紀』の神話にあらわれる、「葦原の中国」へ「降り到る」とか、邇邇芸 の命が、竺紫(つくし)の日向に「天降」ったとかなどの表現は、かならずしも、天上から地上に降った という意味ではなく、そのときの都から遠ざかって、地方に行ったという意味に解釈されうる 余地があるのである。 |
 | 上へ |
|
3.中国文献にみえる「神代の都=九州説」
|
神代の都が、九州にあったとする記事が、比較的はやく、中国の文献にみえている。
すなわち、北宋の仁宗の代、西暦1057年(わが国の平安時代にあたる)に成立した『新唐 書』の「日本伝」に、つぎのような記事がある。 「その王の姓は阿毎(あめ)氏である。みずから言う。初王は、天の御中主(みなかぬし)と号す。彦瀲(ひこなぎさ)にいたる、 およそ32世、みな尊々もって号となし、筑紫城にいる。彦瀲の子、神武立ち、さらに天皇 をもって号となし、徒(うつ)りて、大和州に治す。次は、綏靖といい、次は、安寧という。」 以下に、第35代皇極天皇までのおくり名を、ほぼ正確に(若干の誤字がある)記している 。 この記事は、日本人から聞いて記したもののようである。 『新唐書』は、神武天皇の父彦瀲(『日本書紀』には、彦波瀲武鵜葺草葺不合尊と記す)以前の王が、 地上の九州にいたと記している。すなわち、これによれば、いわゆる神代の都は、九州にあっ たことになる。 なお、唐の魏徴の撰の『隋書』  国伝(おなじく唐代にできた『北史』でも、邪馬台国を 国伝(おなじく唐代にできた『北史』でも、邪馬台国を 王の都
するところと記している。 王の都
するところと記している。 国は、倭国の誤りと考えられる)に、「開皇20年、 国は、倭国の誤りと考えられる)に、「開皇20年、 王あり。姓は阿
毎(あめ)。字は多利思北(比?)孤、阿輩鶏弥(おほきみ?)と号す。」という記事がある。 王あり。姓は阿
毎(あめ)。字は多利思北(比?)孤、阿輩鶏弥(おほきみ?)と号す。」という記事がある。
ここで、注意されるのは、『新唐書』でも、『隋書』でも(そして、『北史』でも)、中国史書は 「阿毎」を、倭王の「姓」としており、「天上」を意味することばとは、みていないことであ る。 古代では、稲羽の八上比売、登美の那賀須泥毘古、葛城の曾都毘古などのように、出身の地 名を、姓のように用いることがすくなくない。「天」は、もともとは、いわゆる天孫族の住ん でいた地名、または姓、あるいは、「大伴」や「久米」にあたる部族名的なものだったのでは ないであろうか。 たまたまそれが、「天上」を意味する「天」と音が同じであったため、伝承 の過程、あるいは、神話化の過程で、混乱を生じているのではないであろうか。 |
 | 上へ |
|
4.室町時代からあった「高天の原=大和説」
|
いっぽう、高天の原を大和とする説も、すでに室町時代からあった。
太政大臣、摂政、関白となった、室町時代随一の学者、一条兼良(1402〜1481)は、 その著『日本書紀纂疏』のなかで、「高天の原は、天上をさす」としながら、一説として、『日 本書紀』の一書が高天の原にあったと記している天の高市(たけち)を、「大和の国の高市郡これなり。 今、天の高市の神社あり。」とする説を紹介している。 室町前期の神道家、忌部正通は、その著 『神代口訣(くけつ)』(1367)で、天の高市について、「大和の国高市郡これによる。」としている。 |
 | 上へ |
|
5.黒板勝美の『国史の研究』
|
江戸時代以後、「九州説」と「大和説」は、それぞれ発展させられ、さらに、この二つの説
以外の、さまざまな「高天の原=地上説」が登場してくる。では、それらの説は、第二次大戦前のアカデミーの世界では、どのように見られていたであろうか。
昭和七年に、日本古文書学を確立した東京大学の黒板勝美(1874〜1946)の大著『国 史の研究各説』の上巻が、岩波書店から刊行されている。これは、当時の官学アカデミーの中 心に位置した黒板の代表的著作といってよい。 『国史の研究』が刊行された当時、岩波書店は、この本を、「学界の権威として、洛陽の紙価 を高からしめたる名著」とし、「最近まで各方面にわたりて学界に提出されし諸問題」を、「一 一懇切詳密に提示論評し」、「その拠否を説明取捨し以て学界の指針たらしめし「宛然(さながら)最近に於ける国史学界進展の総決算たる観を呈して居る」、そして、「わが国史に就きての中正なる概念を教示する」もので、一般人士はもちろんのこと、「専門研究者も座右に備ふるべき好伴侶たるを失はない」とのべている。 黒板勝美は、『国史大系』などの編集者であり、他説の批判や自説の主張においては、つね にその根拠を、くわしくのべている。岩波書店がのべていることは、当時にあっては、けっし て誇大な宣伝ではなかったのである。その説は、当時、学問的考究の上にたつ、穏健中正な見 解とみられていたのである。 |
 | 上へ |
|
6.国史の出発点は神代
|
黒板は、津田左右吉の日本神話作為説を、「大胆な前提」から出発した研究とし、それを、
「余りに独断に過ぎる嫌がある」と批判する。
そして、黒板は、神話伝説は、むしろ長い年月 の間にだんだん作られて来たとする方が妥当であり、はじめはひとつのけし粒であっても、つ いに金平糖になるようなものであり、しだいに立派な神話となり伝説となるところにやはり歴 史が存在するのではあるまいか、とする。 黒板は、『国史の研究各説』上巻の冒頭で、およそつぎのようにのべて、「国史の出発点を所 謂(いわゆる)神代まで溯らしめ得る」と説く。
「史前時代と有史時代との境目を明瞭に区別しにくいことは、世界の古い国々みなそうであ
る。その太古における物語は、霊異神怪や荒唐無稽の話に富んでいて、神話や伝説などのな
かに歴史がつつまれているといえる。
|
 | 上へ |
|
7.天照大御神は「なかば神話の神、なかば実在の人」
|
ついで、黒板は天照大御神よりもまえの神々は、皇室の祖先として奉斎されていないこと
などから、実在性はみとめがたいが、天照大御神は、「半ば神話の神、半ば実在の御方」と説く。
「天照大御神は、最初から皇祖として仰がれた方であったからこそ、三種の神器の一つであ
る八咫の鏡を霊代(たましろ)として、やがて伊勢に奉斎され、今日まで引きつづき皇室の太廟として、とくに厚く崇祀されているのである。
|
 | 上へ |
|
8.アカデミーの立場からの「地上説」の評価
|
そして、黒板は、高天の原を、「地上の何処かに之を擬すべきである」とし、それを、「九州
の北部」と考える。
「天孫民族が大和や日向に入る以前、すなわち、いまだあい分れていない時の地が、いわゆ
る『高天の原』であるともいえよう。本居宣長が、これを天であると解釈しているのは、
『古事記』のできたころ、わが国民が、そのように考えていたとする意味においては妥当で
あるが、もし、高天の原を、天孫民族の祖国と解すべきであるならば、地上のどこかにこれ
を擬すべきである。
「『古事記』『日本書紀』にみえる神々を研究し、『延喜式』神名帳を調べて、神代における 神々として伝えられる方で、九州北部に鎮座するものの多いのをみれば、その地方が、天孫 民族と深い関係をもつことだけは推測されうるように思う。」 また、神話にあらわれる地名について、つぎのようにのべている。「大和に高天山があり、高天野や天香具山があるにしても、それは神話伝説から附会したも のであるか、あるいは、その反対に、大和の山野の名が、神話伝説に後からとりいれられた ものともみられる。」 |
 | 上へ |
|
9.異端と正統
|
以上、ややくわしく黒板の見解をみてきた。このようにみてくるならば、第二次世界大戦前
においては、「高天の原=地上説」は、けっして、異端の学説ではなかったことがうかがわれ
よう。
むしろ、当時においては、現在盛行している津田左右吉の日本神話作為説のほうが、異 端の学説であったといえる。 異端か正統かは、時代によって変わってくる。 黒板は、史料の検討吟味を通じて発言する歴史学者で、皇国史観に立った思想的立場から自 説を展開しているわけではない。 戦後の作為説は、その立場から皇国史観を批判攻撃し、さらには、皇国史観とは直接関係の ない多くの実証的科学的研究をも、津田左右吉の説と合致しないという理由だけで、捨ててか えりみない傾向をもたらしていえるように思える。 長い研究の歴史をもつ「高天の原=地上説」 が、戦後、ほとんどとりあげられることがないのも、そのゆえである。作為説も、一度は、徹 底しておしすすめられてみる必要はあるにしても、現在では、その潔癖さが、かえって、多く の可能性の芽をつむものとなってはいないであろうか。 このようにみてくるとき、「高天の原=地上説」は、やはり、今一度、ほりおこしてみる価値 がありそうである。 |
 | 上へ |
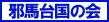 |
TOP > 著書一覧 >高天原の謎 | 一覧 | 次項 | 前項 | 戻る |