| TOP>活動記録>講演会>第249回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第249回 講演会(2006.9.24 開催) | ||||
1.聖徳太子
|
 最近、聖徳太子の実在を廻っていくつかの本が出版され話題になっている。
たとえば、中部大学人文学部教授大山誠一氏の『聖徳太子の誕生』では、「聖徳太子は実在しなかった!」とのべる。
最近、聖徳太子の実在を廻っていくつかの本が出版され話題になっている。
たとえば、中部大学人文学部教授大山誠一氏の『聖徳太子の誕生』では、「聖徳太子は実在しなかった!」とのべる。
これに対して、東北大学大学院教授田中英道氏の『聖徳太子虚構説を排す』では、そんなことはない、聖徳太子は実在したと反論している。 今回は、このような議論について、その内容や根拠について解説する。 ■ 聖徳太子 聖徳太子は574〜622年の飛鳥時代の人であり、用明天皇の皇子で、母は穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇女である。 推古天皇の時代に皇太子、摂政となり、十二階冠位の制定、憲法十七条の発布、遣隋使の派遣などを行った。 また、慧慈(えじ)にまなび、『三経義疏(さんぎょうぎしょ)』をあらわした。 豊聡耳命(とよとみみのみこと)、上宮王(じょうぐうおう)ともいう。 推古天皇30年2月22日死去。 墓所は磯長墓(しながのはか:大阪府太子町叡福寺)。 名は厩戸皇子。 (日本人名大辞典による) 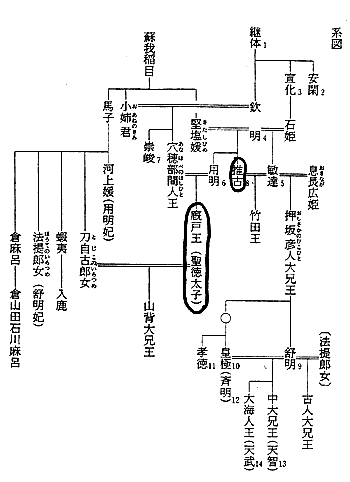 ■ 『三経義疏(さんぎょうぎしょ)』
■ 『三経義疏(さんぎょうぎしょ)』
聖徳太子のあらわした『三経義疏』とは、法華経、維摩経、勝鬘経の解説書であり、『法華義疏(ほっけぎしょ)』四巻、『維摩経義疏(ゆいまぎょうぎしょ)』三巻、『勝鬘経義疏(しょうまんぎょうぎしょ)』一巻からなっている。 『上宮聖徳法太子伝補闕記』によると、それぞれの成立年代は『勝鬘経義疏』が、609年から3年、『維摩経義疏』がそれにつづいて2年、『法華義疏』が2年、合計7年かかって完成したという(聖徳太子36〜42歳)。 鳩摩羅什訳の『妙法蓮華経』二十七品本を使用した『法華義疏』は、内容的には古いものであり、聖徳太子の自筆本と伝えられる巻物が存在する。 『三経義疏』については、聖徳太子の撰述を疑う説がある。法隆寺に撰者不明のままに伝えられてきたものに、747年(天平19年)に寺の資財帳提出のさいに「上宮王私集」という題箋を着けたとする説などである。 |
2.擬古派
|
 聖徳太子の非実在説や、大化の改新が偽りであったなど、古文献を疑う立場の「擬古派」的な主張が、盛んに行われるのはなぜなのだろうか。
聖徳太子の非実在説や、大化の改新が偽りであったなど、古文献を疑う立場の「擬古派」的な主張が、盛んに行われるのはなぜなのだろうか。
「擬古派」的な人はどこの国にも存在し、一流のインテリと自認する人がのめり込む傾向がある。 疑うことが知性の証しというわけである。 しかし、外国と日本とでは事情が少し異なるようである。
それでは、日本の状況はどうであろうか。
擬古派的な考え方は、くりかえし、事実によって粉砕されてきたが、日本では、第二次世界大戦中の『古事記』『日本書紀』をそのまま信ずべしとする教育に対する反動から、擬古的な考えがいまだに強く、結果的に世界の趨勢からいちじるしくたちおくれた議論が、あいかわらず強調される傾向が続いている。 「聖徳太子は実在しなかった」「大化の改新は偽りである」など、擬古派の立場でさまざまな本が出版される背景には、日本のこのような事情があるのである。 |
3.大山誠一氏の『<聖徳太子>の誕生』−聖徳太子は実在しなかった− の問題点
|
大山誠一氏は『<聖徳太子>の誕生』のなかで、「聖徳太子に関する確実な史料は存在しない。現にある『日本書紀』や法隆寺の史料は、厩戸王(聖徳太子)の死後一世紀ものちの奈良時代に作られたものである。それ故<聖徳太子>は架空の人物である。」と述べる。
史料が死後一世紀に作られたものだから、架空の人物だとするのはいささか乱暴な議論である。史料をまとめる時に、さらに古い資料や、生存中の史料すら参照する可能性があるのだから。 このことはさておいても、大山誠一氏が言うように、法隆寺の史料が、聖徳太子の死後一世紀もあとの奈良時代(710〜794)に作られたというのは正しいのだろうか。大山氏が奈良時代以降のものとした『三経義疏』のなかの『法華義疏』と、『上宮聖徳法王帝説』について詳しく見てみよう。 ■ 『法華義疏』 『法華義疏』は聖徳太子の記したものではないとする説がある。具体的には、撰者不明のまま法隆寺に伝えられてきたものに、747年に寺の資財帳提出のさいに「上宮王私集」という題箋を付けたとする説と、これが海外で書かれたものという説である。 また、そのいっぽうでは、『法華義疏』は聖徳太子の真筆であるとも言われている。 
ポイントになるのは右端の題箋の部分である。ここには「此れは是、大委(だいわ:やまと)国の上宮王の私集にして、海彼(かいひ:外国)の本にあらず(此是大委国上宮王私集非海彼本)」と書かれている。
これは、題箋と本文が同一人物によって記されたことを示すもので、撰者不明のまま法隆寺に伝えられてきたものにあとから題箋を付けたとする説は誤りであることを意味する。 また、ここでは、日本のことを「大委国」と記しているが、日本人以外は日本の国号を「大委国」とは書かない。したがって、『法華義疏』が海外で作られたという説も成立しない。 ここで、「委」の文字を「い(ゐ)」ではなく「わ」と読んでいるが、これは「推古朝遺文」に記されているのと同じ読み方で、非常に古いものである。 『日本書紀』では、歌謡を記す場合などは「委」の文字を「い(ゐ)」と読んでいる。「委」を「わ」と読むのは、次のような古い百済系資料によるとみられるものに限られる。
 すねわち、「委」の文字を「わ」と読むのは、『日本書紀』編纂時に、編纂者が与えた読み方ではなく、先行文献の読み方をそのまま記したにすぎない。
すねわち、「委」の文字を「わ」と読むのは、『日本書紀』編纂時に、編纂者が与えた読み方ではなく、先行文献の読み方をそのまま記したにすぎない。
以上のようなことは、『法華義疏』が推古天皇の時代の聖徳太子の撰になるということをサポートするものである。 ■ 『上宮聖徳法王帝説』 『上宮聖徳法王帝説』は、最古の聖徳太子伝である。聖徳太子の誕生、一族のこと、仏教興隆のための事績などを記す。 編著者は未詳である。 大山誠一氏は『上宮聖徳法王帝説』も奈良時代以降のものだと述べる。しかしこれは誤りで、少なくとのその一部は、『古事記』『日本書紀』よりも古いものであることを以下に述べる。 『上宮聖徳法王帝説』は性質の異なる次の五つの部分からなる。
はじめ、「A」の部分ないし、「B」の部分が加わった原初的な形が奈良時代(710〜794年)に成立し、それに
「D」と「E」の部分が加わり、更に平安時代に「C」の部分が付加されて今本の形ができたとされている。
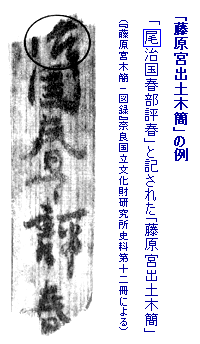 『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』などは、奈良時代に成立した代表的な文献であるが、『上宮聖徳法王帝説』は、奈良時代以前の資料を含むとみられる貴重な資料なのである。
『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』などは、奈良時代に成立した代表的な文献であるが、『上宮聖徳法王帝説』は、奈良時代以前の資料を含むとみられる貴重な資料なのである。
つぎに、用字について分析する。
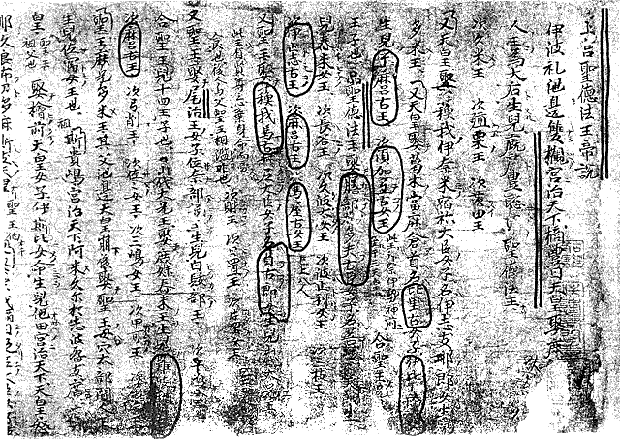
|
4.田中英道氏の『聖徳太子虚構論を排す』の趣旨
|
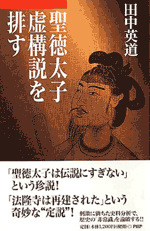 田中英道氏は『聖徳太子虚構説を排す』のなかで、次のような内容を述べて「聖徳太子非実在論」に反論する。
田中英道氏は『聖徳太子虚構説を排す』のなかで、次のような内容を述べて「聖徳太子非実在論」に反論する。
|
| TOP>活動記録>講演会>第249回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |
 戦後の日本では、『古事記』『日本書紀』などの神話は、天皇の権威を高めるための「作り話」で、歴史的事実ではないとする津田左右吉の主張が広く浸透した。
戦後の日本では、『古事記』『日本書紀』などの神話は、天皇の権威を高めるための「作り話」で、歴史的事実ではないとする津田左右吉の主張が広く浸透した。

