| TOP>活動記録>講演会>第275回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第275回 講演会(2008.11.16 開催)
| ||||
1.邪馬台国里程論争
|
■ 距離の尺度
魏の時代は、1里=300歩 =1,800尺 =434.16mである。これを標準里とする。
ちなみに、日本の江戸時代では1里=4kmであった。これは、日本だけの独特な尺度であり、その起源は、長さと面積の単位の混同による誤解のようである。 もともと1里=6町であり、1町=109mであったから、1里=654mほどであった。ところが、町という単位は長さだけでなく面積を表す時も用いられたので、本来、1里=6町とするところを、1里=6町×6町=36町と誤解して、109m×36=3,924m(約4km)とされてしまったのが理由のようである。 『魏志倭人伝』に記された里程に従い、魏の時代の1里=434.16mでたどると、朝鮮半島は台湾近くまで垂れ下がり、邪馬台国は日本列島からはるか離れた海の上になってしまう。 ところが、対馬と壱岐など、地域が特定できるところで、『魏志倭人伝』の里程と実際の距離を比較すると、1里=100mくらいであり、魏の時代の1里の長さの1/4になってしまう。 しかし、同じ『魏志』のなかで中国の国内のことがらを記述する部分では、1里=400mくらいと見て問題はない。この違いをどう説明するかが「邪馬台国里程論争」である。
■ 里程についての諸説
『魏志倭人伝』には、「狗邪韓国→対馬」、「対馬→一大国」、「一大国→末盧国」の距離を、いずれも「千余里」と記している。 しかし、実測では「一大国→末盧国」の距離は、「狗邪韓国→対馬」や「対馬→一大国」の半分ほどしかない。これはなぜだろう。 『唐六典』に次のような文章がある。 およそ行程は、馬は日に70里、歩および驢(ろ)は50里、車は30里。その水程は、重船の流を遡るには、河(黄河)は日に30里、江(揚子江)は40里、余水(その他の河川)は45里。空船にては、河は40里、江は50里、余は60里。重船・空船の流れに順うには、河は日に150里、江は100里、余水は70里。 川の流れの速さを x、舟の速さを y として連立方程式を立てると、その解は次のようになる。ただし、船の速さは重船と空船を平均した。
この表を見ると、川の速さが速いほど、船そのものの速さも速くなっている。流れの速い場合には、それだけ漕ぎ手も頑張るようにみえる。 ところで、朝鮮半島南岸から九州まで渡るあいだの海流の速さはおよそ次の通りである。
壱岐から北九州に渡る場合は、力漕の必要がなく、それだけ時間をかけて進んだ。そのため、朝鮮半島から対馬までも、対馬から壱岐までも、壱岐から北九州までも、大略同じていどの時間がかかり、それを「里数」に換算した場合、同じく「千余里」になったかとみられる。 ■ 魏使の来た季節 魏使が倭国を訪れた季節について、研究者は例外なく夏であったとする。その根拠は以下の通り。
西暦300年ごろの洛陽晋墓からモノサシが発見された。これは、1尺が16cmくらいになっていて、魏の1尺=24.12cmの2/3くらいの長さである。周の時代の小尺と思われる。 『日本書紀』に、日本武尊の身長は1丈と書いてある。奈良時代の1尺は30cmなので、1丈=10尺で3mとなり、ありえない身長である。しかし、洛陽晋墓で出土したような周尺ならば、1丈は160cmとなり、普通の人の身長になる。 この他にも身長については、『古事記』の垂仁天皇紀に景行天皇の身長が1丈2寸、反正天皇紀に反正天皇は9尺2寸と記された例がある。これらの数字も周尺で考えれば説明が付く。 |
2.橘とみかん
|
■ 古文献
わが国の柑橘類の主流をなすものは、次の三つに分けて見るのが、妥当なようである。
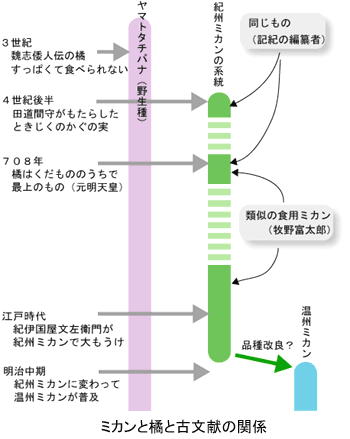
以下のように考えると話のつじつまが合う。 『魏志倭人伝』の時代は、食用ミカンが伝来する前であり、倭人は野生の橘などは酸味が強く食べる習慣がなかった。 田道間守が持ってきた「ときじくのかぐの実」が普及して、記紀が編纂された時代に橘と呼ばれ、おいしい果物として珍重された。 そして、のちの時代には紀州ミカンとなった。 現代の温州ミカンは、在来種の品種改良、あるいは、江戸時代の初期に薩摩国出水郡長島郷で、突然変異で種なしの株が生まれたのが起源とされている。当初は「種なしは家の断絶につながる」と不人気だったが、明治中期以降普及した。 ■ 田道間守(たじまもり)はどこへ行った。 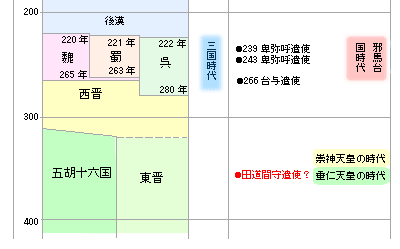
『日本書紀』垂仁天皇紀に、「田道間守は万里(とおく)浪を踏み、弱水(よわのみず)を渡り、絶域(はるかなるくに)に行った。」とされている。 白鳥庫吉は『弱水(じゃくすい)考』のなかで、「弱水」は、黒竜江、大秦国(ローマ帝国)であると述べる。しかし、黒竜江は寒すぎるし、大秦国は遠すぎる。 『後漢書』の大秦国伝には、「弱水」は西王母の居るところに近く、日のいるところと記されているので、漠然と西の方をさしたとも解釈できる。 垂仁天皇の時代は三角縁神獣鏡が盛んに用いられた時代だが、東王父や西王母のモチーフが用いられている三角縁神獣鏡が多数あるのはこれと関係するかも知れない。 記紀によると田道間守は垂仁天皇(第11代)の時代の人。 安本先生の「天皇一代平均在位年数約十年説 」によると、垂仁天皇の活躍した時代は4世紀後半。 中国では、魏の後に建国した晋(西晋)が、北方の異民族の圧力に押されて、南方に進出し建国した東晋の時代。 東晋は柑橘類の集散地として知られる温州を含む。 倭国は中国の王朝に朝貢を行ってきた。後漢には倭国王師匠が、魏には卑弥呼が、西晋には台与が使者を送った。田道間守も垂仁天皇が東晋に送った使者ではなかったのか。 田道間守は、中国南部の東晋の温州あたりに行ったときに、食用ミカンの「ときじくのかぐの実」を手に入れたのであろう。 そして、平縁神獣鏡や三角縁画像鏡などの呉鏡は、温州のある浙江省や隣接の江蘇省を中心に分布しており、三角縁神獣鏡の文様はこの地域からもたらされたデザインがベースになったのではないか。 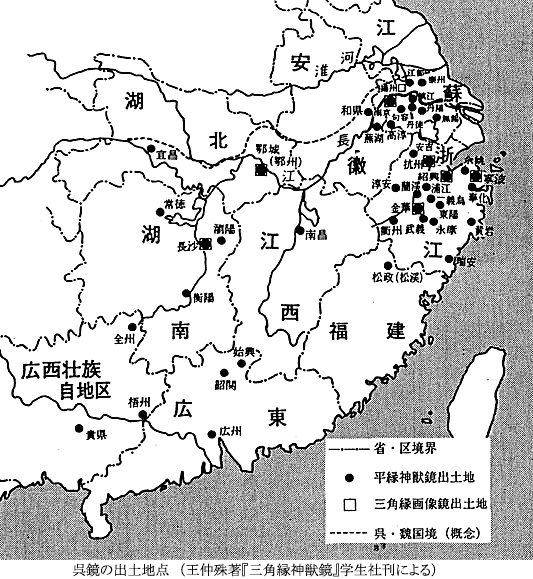
|
| TOP>活動記録>講演会>第275回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |