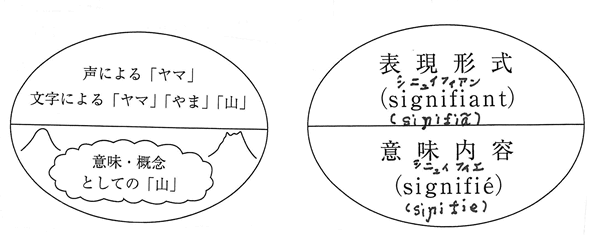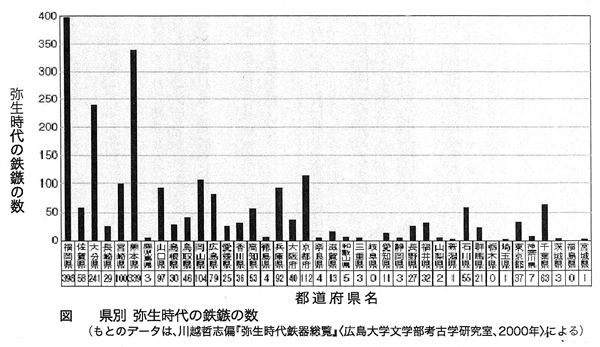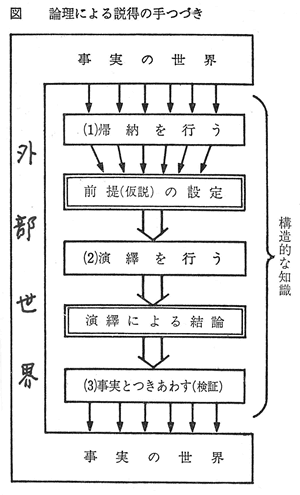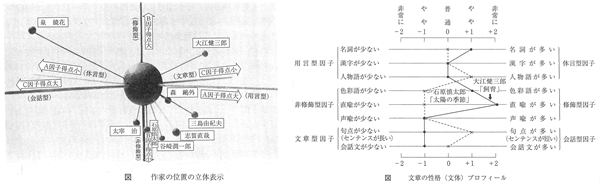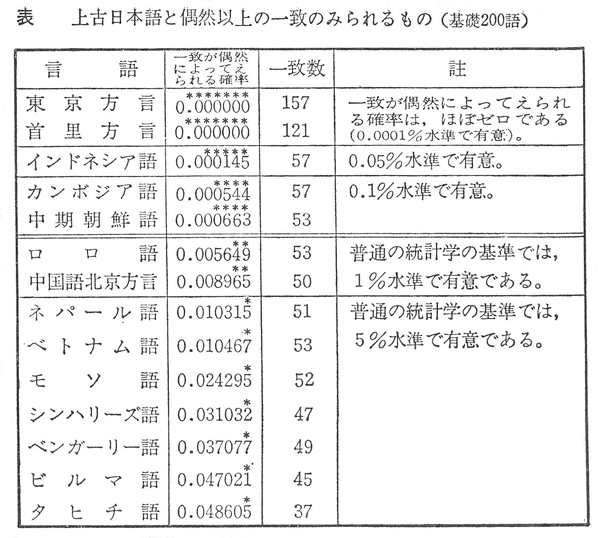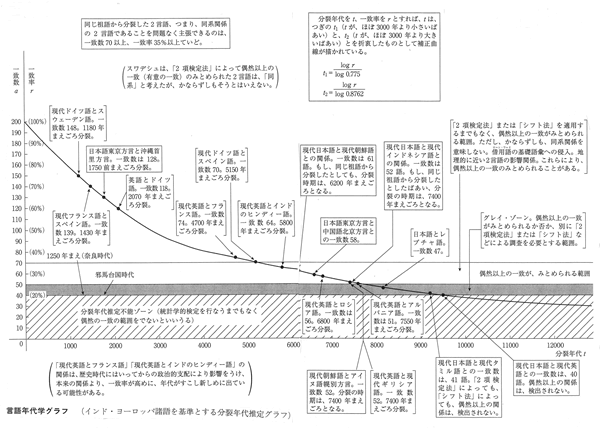■マルクス主義的「唯物論」への疑問
私は、古代史研究において、つぎのような立場に立っている。
私は、「外部世界」は存在するという立場に立つ。この場合、「外部世界」というのは、物質、エネルギー、言語、情報、社会など、私を取り巻く外の世界である。マルクス主義は、「外部世界」のうちの「物質」に力点をおいたが、私は「外部世界」をもう少し広く考えたい。
ここで、言語や、情報や、社会といったものは、物質的なものを基盤にはしているものの、その働きの本貧は、物質に還元できないものをもつ。
簡単な例をあげよう。
ジャンケンでは、手を開いた状態のパーは、手を握った状態のグーに勝つことになっている。これは社会的な、伝統的な「とりきめ」「約束ごと」としてそうなっているのである。
物質的にはまったく同じ、手を握った状態のグーが、手を開いた状態のパーに勝つ「約束」にしてもよいのである。それでもジャンケンは成立する。
人間社会での「約束ごと」は同じ物質的状態に、違う意味を与えることができる。
言語はまさに、その種の約束ごとの体系である。
「犬」という動物を、日本語では「イヌ」という。英語では「dog」という。社会的、伝統的な「約束ごと」としてそうなっている。その「約束ごと」を、私たちは、無意識のうちに、とりいれ、うけついでいる。まったく同じ「犬」を「イヌ」と呼んでも、「dog」といっても、あるいは、「ネコ」といってもよいのである。
社会全体が、「犬」という概念を、「ネコ」と呼ぶことにしているのなら、それはそれで通じるのである。
このような「約束ごと」の体系が、私たちの外部世界では、重要な役割をはたしている。
かつては、食へ物が手にはいるか否かなどの物質的な要因が、私たちにとっての、大きな関心事であった。しかし、現代日本では、最低限の食べ物は保障されるようになってきている。
大臣などが失言などで、窮地におちいることがある。物理的には空気の振動にすぎない言葉の使い方のちょっとした違いが、社会的な「約束ごと」によって、重大な結果をまねく。
人間社会において、このような「約束ごと」は、言語などをはじめとし、体系化され、「構造」をもつ。法律や、文法などは、そのような「約束ごと」の体系を示している。
このような「構造」の研究の必要から、「構造主義」が生まれる。「構造主義」は、はじめ、言語学の分野において、生まれた。
おそらく、私たちの「外部世界」は、「物質」や「エネルギー」などもふくめて、われわれ人間にとって、(あるいは、他の動物たちにとっても、)それなりの「構造」をもっているように認識され、そのため、それらを指示し、把握し、写しとるための「言語」なども、「構造」をもつようになったのであろう。
外部世界を、どのようにすれば、より正確に、そして、より簡潔に把握できるか。
数学なども、そのような必要から生まれた「言語」の一種といえよう。いまや、「数学」は、それじたい、壮大な「構造」や「体系」をもつ。
また、マルクス主義と私とでは、基本的な考え方において、つぎのような点でも異なる。
マルクス主義は「物質」をアプリオリに実在していると考えているように見える。そしてその実在性などは、「実践」によって証明できると考えているように見える。しかし物質の実在はそれほど簡単に証明できるのであろうか。
仮にマルクス主義のように「物質」が実在するものと仮定してみよう。すると、当然字宙も実在することになる(エンゲルスの著書『自然弁証法』「大月書店、1970年刊」、『自然の弁証法』「岩波書店、1957年刊」など参照)。そして、宇宙が存在するとすれば、他の諸々の生物種が絶滅することがあったと同じように、人類もまた絶滅する日がくることになる。人類が一人もいない場合、誰が字宙の存在することを認識し、証明することができるのであろうか。認識し、証明する主体がいないのになぜ字宙が存在するといえるのか。
「実践」によって、「外部世界」の実在を、証明することはできない。
認識し、実践し、証明をする主体が存在しなくなる。その場合でも、字宙や物質が実在するといえるとする。これは、信念的唯物論あるいは観念的唯物論と言わざるをえない。
注:マルクス(Karl Marx)は辞書によると、ドイツの経済学者・哲学者・革命家。1849年以後ロンドンに居住。初めヘーゲル左派に属したが、40年代の中頃、エングルスとともにドイツ観念論、初期社会主義(空想的社会主義)、および古典経済学を批判的に摂取して科学的社会主義の立場を創始、資本主義体制を批判し、終生国際的社会主義運動のために尽した。主著「資本論」。(1813~1883)
注:マルクス主義(Marxism)は辞書によると、マルクス・エングルスによって確立された思想体系。哲学的基礎としての弁証法的唯物論、それを社会に適用して社会をその物質的土台から歴史的に把握する史的唯物論、階級社会の場での階級闘争の理論、資本主義社会の運動法則を解明する経済学説、国家を階級支配の道具と見る国家論、労働者階級の革命運動の戦略・戦術、植民地・従属国の被圧迫民族解放の理論、社会主義・共産主義建設の理論など。
注:上部構造とは辞書によると、(Überbauドイツ語)史的唯物論の概念。土台(下部構造)としての一定社会の経済構造の上に形成される政治的・法的・哲学的・道徳的・美的・宗教的な観念形態(イデオロギー)やそれに対応する制度・組織(例えば国家・政党など)をいう。上部構造は下部構造によって生みだされ、それと不可分に結びついているが、いったん成立すると一定限度において土台へ反作用を及ぼすとされる。
注:下部構造とは辞書によると、(Unterbauドイツ語)マルクスの史的唯物論で、上部構造としての政治・法制・イデオロギーなどに対し、それらの土台をなす社会の経済構造。
注:ソシュール(Ferdinand de Saussure)は辞書によると、スイスの言語学者・ジュネーヴ大学での講義をもとに編集・出版された「一般言語学講義」(1916年刊)は構造主義の理論的出発点をなす。言語研究の関心を従来の歴史的研究から体系性・構造性の研究へと転換させ、今日の科学的言語研究の基礎を築く。(1857~1913)
マルクスの「構造」とソシュールの「構造」では違う。
注:言語記号は、「表現形式」と「意味内容」の結合体である。この図の全体が「記号[signe(シーニュ)]」である。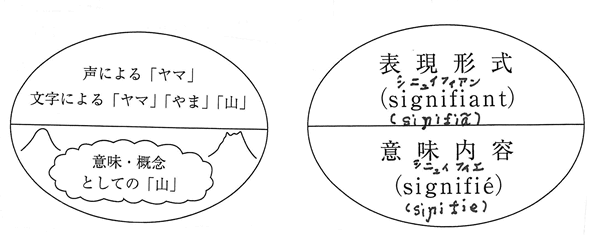
私は以下のように考える。
自然科学の発展とともに、科学方法論自体もしだいに深くたずねられてきた。そして、どのような論理が学問によって望ましい論理であるかということも、明らかになってきている。
そのような論理の基本的な基準は、すでに十七世紀に、フランスのパスカルが、その著『幾何学的精神』のなかでのべている。
パスカルの論理の基準については、埼玉大学の吉田洋一氏、立教大学の赤摂也氏共著の『数学序説』(培風館刊)にきわめて要領よくまとめられている。以下、両氏の著書により、まずパスカルの基準を紹介しよう。パスカルは、定義について三つの規則をあげている。
(1)それよりもはっきりした用語がないくらい明らかなものは、それを定義しようとしないこと。
(2)いくぶんでも、不明もしくはあいまいなところのある用語は、定義しないままにしておかないこと。
(3)用語を定義するにさいしては、完全に知られているか、または、すでに説明されている言葉のみを用いること。
また公理(議論の出発点、前提)について、二つの規則をあげている。
(1)必要な原理は、それがいかに明晰で明証的(論証や検証によらなくても、それじたいが、直接的に明らかで疑えないもの)であっても、けっして承認されるか否かを、吟味しないままに残さないこと。
(2)それ自体で、完全に明証的なことがらのみを公理として要請すること。
さらに、論証について、三つの規則をあげている。
(1)それを証明するために、より明晰なものをさがしても無駄なほど、それだけで明証的なことがらは、これを論証しようとしないこと。
(2)すこしでも不明なところのある命題は、これを、ことごとく証明すること。そして、その証明にあたっては、きわめて明証的な公理、または、すでに承認されていたか、あるいは証明された命題のみを用いること。
(3)定義によって限定された用語のあいまいさによって誤らないために、つねに心の中に定義された名辞の代わりに、定義をおきかえてみること。
パスカルの方法をまとめれば、自明のものを除くすべての「言葉」を「定義」し、また、自明でないすべての「命題」を「証明」しつくすということになるであろう。
・現代の公理主義
パスカルの基準は。ギリシャ人が幾何学を建設するのに用いた方法にほかならない。だからこそ、パスカルは、自分の書物を『幾何学的精神』と名づけたのである。
ところで、このような方法論は、自然科学のめざましい進展とともに、さらに洗練されてきている。
幾何学的精神の現代的な形式としては、「公理主義」がある。ある理論において、他の命題の前提となる基本命題の体系(公理系)を明らかにし、その公理系と、特定の推論規則とから、演繹的に理論をくみたてることを、公理的方法、または公理論という。ユークリッドの幾何学は、不完全ではあるにしても、その適例であると考えられる。またパスカルの方法は、公理主義の原初的な形といえよう。
現代の公理主義が、パスカルの説いた方法と異なる点は、主として「公理」についての考え方にある。パスカルにおいては、「公理」は「それ自身で完全に明証的なことがら」で、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないと考えられていた。ところが十九世紀のはじめに、「万人に承認される」とはいえない公理をもとにして、完全に無矛盾な非ユークリッド幾何学が建設されるにおよんで、この「公理」についての考え方は大きくゆらいだ。そしてドイツのヒルベルトは、「公理」はなんら自明の真理である必要はなく、たんに明確に定められた「仮定」で十分であるとしたのである。すなわち、いくつかの「仮定(公理)』をおき、そこから、「形式的に結論をみちびいて、そこに矛盾を生じなければよいとしたのである。」
ヒルベルトは、数学の基礎として、自分の考えをのべた。しかしその考え方は、やがて自然科学全体に、きわめて広汎な影響をおよぼすこととなった。
ドイツに生まれ、のちアメリカにわたったカルナップ(1891~1970)らは、この方法だけが科学的方法であり、すべての科学は公理論的に構成されるべきであるとして、「公理主義」をとなえた。
正しいと思うことも、ある立場からみて正しいにすぎないことが、すくなくない。
「公理主義」については、東京大学の教授であった数学者、小平邦彦氏が、『数学のすすめ』(筑摩書房刊)のなかで、おもしろい例をあげている。
「基盤の上に碁石を並べて行なうゲームに、五目並べがある。四目並べを考えれば、先手必勝でたちまち勝負がついてしまうので全然つまらない。六目並べにすると、いくら続けても永久に勝負かっかないので、やはりつまらない。すなわち、四目並べも六目並べも、五目並べほど面白くない。」
仮説系は、ゲームの規則に相当する。仮説系の内容が、豊富さをもつということは、ゲームがおもしろいものであることを意味する。ある仮説を設けたならば、非常にたくさんのことが説明できる、というようなことは、結局、新しい、おもしろいゲームを発見するのと同じことである。しかし、そのような新しい、おもしろいゲームを発見するのは容易ではない。仮説系は単なる仮説であって、矛盾を含まないかぎりなんでもよい、とされている。しかし、非常にたくさんのことを説明できるような仮説系を設定することは、きわめてむずかしい。仮説系の選択の自由は、実際上はそれほど多くはない。
私は、古代史の探求において、つぎのように考える。
私の外部世界は実在する。また、過去においても外部世界は実在したと考える。私か死んでも、外部世界は、存在しつづけると考える。しかし、この実在論は「仮説」であると考える立場にたつ。
外部世界が実在すると考えると、そこから、多くの情報を汲み取ることができる。すなわち私の外部世界の実在論は、「仮説的外部世界実在論」である。私の立ち場から言えば、マルクス主義の唯物論は「信念的唯物論」といえようか。そこでは外部世界が実在することを証明しないままで、物質をはじめとする外部世界が実在すると決めてかかっている。
私の場合は外部世界が実在するか実在しないか定めることはできないが、外部世界が実在すると仮定すると色々な物事がうまく説明できると考えられる。だから、外部世界が実在するという「仮説」をうけいれる。すなわち、外部世界実在論の仮説系は、内容が豊富であるといえる。いわば、ゲームであればおもしろいものであるといえる。それは、他の仮説、例えば宗教に基づいてこの世界を説明しようとする仮説よりも、科学などの検証に耐ええて、生産性も豊かであると思う。以上のようにマルクス主義に学ぶところが多いが、私の考え方とは基本において、微妙に異なるのである。
・実証主義哲学について
仮説とか公理とかということをいえば、私の立場は論理実証主義に近いのでないかと思う方もおられるかもしれない。しかし、私の立場は論理実証主義ともまた微妙に異なるのである。
かつてソ連を風靡した唯物論とも、アメリカで盛んであった論理実証主義とも、私の立場はすこし異なる。その両方の立場から学ぶところは多かったのであるが。
実証主義哲学について私の立場をのべてみよう。
まず、戦後の我が国において盛んであった津田左右吉らの実証主義的文献批判学を取りあげよう。
現代のふつうの人は、「実証主義」ということばを、「たとえば、A・B二つの仮説があるばあいに、どちらの仮説が、観測事実や、調査結果や、実験結果によくあうかを、実際に検証して行く方法をとること」のような意味に、解釈しがちである。
しかし、「実証主義的文献批判学」の「実証主義」は、そういう意味ではない。津田左右吉氏らの「実証主義的文献批判学」はドイツなどで盛んであった「十九世紀の実証主義的な文献批判学(原典批判)」と軌を等しくするものであった。「十九世紀の実証主義的な文献批判学」の「実証主義」は、十九世紀に盛んであったオーストリアのマッハなどの説いた「実証主義哲学」の方法にもとづく。
『広辞苑』で、「マッハ」の項を引くと、つぎのように記されている。
「マッハ(Ernst Mach)オーストリアの物理学者・哲学者。近代実証主義哲学の代表者。超音速流の研究を行ない、ニュートン力学に対する批判はアインシュタインに大きな影響を与えた。一方で、実証主義の立場からボルツマンの原子説に反対しつづけた。主著「力学史」。(1838~1916) 【マッハ主義】(Machism)マッハに始まる実証主義的な認識論の立場・傾向。物質や精神を実体とする考えに反対し、直接に経験される感覚要素だけが実在的であるとし、事物はすべて感覚の複合・連関であり、物と心の区別も要素の結びつけ方の相違にすぎないとする。」
『日本国語大辞典』(小学館刊)で、「マッハ主義」を引くと、つぎのようにある。
「マッハ主義〔名〕エルンスト=マッハ(Mach)に始まる実証主義的認識論の立場をいう。物質や精神を実体とする考えに強く反対し、科学の目的は観察された事実を記述することのみにあるとし、仮想的原子などを考えることは全く非科学的であると主張した。」
「科学的」の意味が、マッハと、私たちとでは、違っている。ひいては、十九世紀的実証主義的文献批判学の立場の人々と、私たちとでは、「科学的」の意味が異なっている。
・「過去は、実在したのか?」
要するに、マッハらは、目でみ、手でさわることができるもの、直接経験できるもの、つまり感覚できるものだけを「実在的」であるとするのである。そして、「原子や分子のように、直接目でみることのできないものの存在を考えるのは、形而上学的(内容のないことばのもてあそび)である」として、原子論的な立場の人々と対立した。
そして、原子の考えを抜きにして、科学を進めようとした。
しかし、今日、原子論に、反対する科学者はいない。原子の存在を考えることなしに、さまざまな事実を包括的にとらえ、的確な学問的予想をたてることは、困難であるからである。
十九世紀の文献批判学も、実証主義哲学を背景としている。
実証主義の立場に立つ物理学者が、個々の実験事実や現象だけをみて、その奥にある原子をみなかったように、実証主義の立場にたつ文献学者は、目のまえの個々の文献だけをみて、それだけが実在であると考え、その背後にある史実をみない傾向かある。そこでは、文献そのものの批判研究に焦点がしぼられ、歴史を構築し、認識することは、二次的なものとされる傾向がつよい。
「文献によって史実をさぐるまえに、目のまえの文献そのものの、検討が必要である。」というようなことが、強く主張される。
しかし、個々の実験事実や現象は、原子などが、われわれの五感に認知されうる世界に落とした影であり、個々の文献や遺跡・遺物も、史的事実がまず存在して、それが落とした影であるともいいうる。
マッハのいうような「実証主義哲学」をおしすすめるならば、
「過去は、実在したのか。」
「歴史は、実在したのか。」
という重要な疑問に逢着する。
なぜならば、私たちは、過ぎ去った「過去」や、「歴史」的事実そのものを、直接目でみ、耳できき、手でさわることはできないからである。直接経験し、感覚することは、できないからである。私たちが感覚することができ、「実証」できるのは、目のまえにある遺物や、文献などのみである。
マッハらののべた「実証主義」は、目の前にあって、それを見ることなどによって生ずるような感覚の集まりだけを実在を孝え、確かと考える素朴な実証主義なのである。
その本質は、視覚や、聴覚や、触覚によって確かめられるものだけを信じましょう、実在としましょうという素朴な発想なのである。
この立場によれば、私たちが、いま、目でみ、耳できき、手でさわることができたもの、すなわち、「実在」としたものも、たとえば、一ヵ月のちには、「非実在」であるものに転化することになる。直接目でみたり、耳できいたり、手でさわることは、できなくなるからである。
そのように考えるよりも、「現在」が「実在する」のと同じように「過去」は、かつて「実在した」ものであり、その遺物や遺跡、あるいは、過去についての記録を、私たちが観察しているのだと考えるほうが、はるかに生産的ではないか?
奇妙な「実証主義」にあまりまきこまれては、いけないのではないか?
目のまえにある物質などをとりあつかう物理学の研究などならともかく、「過去」をあつかう歴史学の基本的な哲学として、マッハらのとく「実証主義的哲学」が、ふさわしいものとは、とても思えない。
・文献から歴史を構成する理論をふくまない
一九世紀の諸科学では、まだ、「仮説概念」が明確化されていない。みずからの説が、仮説の一つであることを承知しない。その理論は、絶対的な真理か、絶対的な誤りかの、信念と信念とのぶつかりあいとなる。二十世紀に、仮説の観念が明確となり、それまでの、独断的、絶対的、信念的な考え方から、仮説的、相対的、検証的な考え方へと転換した。実証主義哲学が、確実な事実から出発しようとしたことはよい。
平凡社刊の『世界大百科事典』も、「実証主義」の項目で、つぎのように記す。
「実証主義:経験の背後に、または経験をこえて、何かがあるということを認めようとしない哲学、または思想上の一つの立場をいう。いいかえれば、われわれが経験によって確かめることのできないような原理をあらかじめ想定し、それによって、われわれの経験を説明しようというのではなく、われわれが実際に確かめられること以外はすべて疑っていこうという考え方である。したがって、実証主義の立場から断言できることはわずかではあるが、確実なことばかりである。」
インターネットの『ウィキペディア』で、「エルンスト・マッハ」を検索すれば、つぎのように記されている。
「マッハは、感覚に直接立ち現れないことを先験的に認めて命題に織り込むようなことは認めない、としたわけで、いわば、実証主義の中でも極端なそれの立場をとったということになる。」
「そして当時、ニュートン流の粒子論(原子論)的世界観を応用して理論を構築しつつあり世界を実在論的な見方で見ていたルートヴィッヒ・ボルツマンやマックス・ブランクらと論争を繰り広げた。」
しかし、マッハ流の実証主義では、「過去」が実在したことを、「仮定」することが、できなくなってしまう。
以上、のべてきたように「実証主義哲学」によるばあいは、古代の天皇の実在性などばかりでなく、「過去そのもの」「歴史そのもの」の実在性を否定できる論理を、そのうちにふくんでいるのである。原子や分子の「実在性」を否定することができたのと同じように。
『広辞苑』は、「実証主義」の項で記している。
「実証主義(positibismueフランス語)所与の事実だけから出発し、それらの間の恒常的な関係・法則性を明らかにする厳密な記述を目的とし、一切の超越的・形而上学的思弁を排する立場。これを初めて体系的に説いたコントらは現象の根底にある実在を(不可知としながらも)認めたが、マッハ・ウィトゲンシュタインらの論理実証主義者はこのような実存を認めない。」
かくて、実証主義的文献批判学では、目のまえにあり、経験できる文献の相互比較などが、主要な関心事となる。その文献に書かれている内容から、妥当な歴史を構成、構築するというような作業は、二の次、三の次になってしまうのである。
したがって、文献から歴史を構成、構築するための論理や方法を発展させることもない。過去の事件などについて、「仮説」をたて、それを、諸資料によって検証するという形をとることをしない。「仮説」概念が、明確化されるまえの科学方法論であるからである。
・唯物論とマッハ主義
レーニンは、『唯物論と経験批判論』(寺沢垣信訳、大月書店、国民文庫など)を書き、マッハの実証主義哲学を、「感覚の複合としての物、というマッハの学説は、主観的観念でありバークリー主義のたんなる焼きなおし」ときびしく批判している。
注:バークリー【George Berkeley】イギリスの経験論哲学者。主観的観念論の代表。一切の物心感覚の結合にほかならず、物が存在するとは知覚されることにすぎないと主張。
事物は精神によってはじめて実在する。唯心論、唯神論
しかし、マッハの実証主義哲学は、生きのこる。論理実証主義という形で発展する。『広辞苑』も、「論理実証主義」について、マッハの名にもふれ、つぎのようにのべている。
「【論理実証主義】(logical positivism) 1930年頃にウィーンの学者シュリックらから始まった実証主義哲学。ラッセル・ウィトゲンシュタインの科学基礎論や言語分析を介し英国や北欧諸国(エイヤー・フォン=リクト)に、カルナップの統一科学を介し第二次大戦中にアメリカ(クワイン)に広まり、主要な哲学潮流となる。ヒューム・マッハの流れを汲む実証主義を復活、経験的に検証不可能な命題は無意味であるとして形而上学を排し、哲学の仕事を科学の言語の論理的分析にありとし、記号論理学の研究を発展させた。」
「論理実証主義」が、論証の質を高めたことは高く評価すべきである。
ただ、この立場では、どのような前提から、どのような結果がみちびきだされるかについての、論理記号や数学を使っての推論の整合性のみに、焦点があてられているようにみえる。外部世界の実在性については、不問とされるか、あるいは否定的である。
しかし、外部世界の実在を否定したのでは、歴史の研究はできなくなってしまう。
私は外部世界は、仮説的なものであることを認めながらも、実在したと考える。過去の世界も、かつて実在したものと考える。
たとえば、邪馬台国問題を考えてみよう。女王がおさめたわが国の邪馬台国は実在したと考える。西暦238年ごろに存在していた。すなわち、時間がわかっていて、場所を求める問題である。
ある意味できわめて物理学的な問題である。
残された証拠物件をもとにして、刑事が犯人像を推理するのと同じ種類の構造の問題である。
・邪馬台国はどこにあったかを、確率計算する
昭和時代の経済学者の字野弘蔵(うのこうぞう)氏(1897~1922)は、マルクスの『資本論』について、資本主義社会の内在的論理を解明しようとする科学的体系知的な理論面と、革命をおこし資本主義体制を打破しなくてはならないとする政治的イデオロギー的な面とを区別する。
この字野弘蔵氏の説については、最近刊行された佐藤優氏の『「資本論」の核心』(角川新書、2016年刊)にくわしく、かつ要領よく紹介されている。
邪馬台国問題にも例えば、邪馬台国はどこかということを解明しようとする問題と、えられた結果を人々に認めさせようとするやや政治的な問題とは別けて考えたほうがよいと、私は思う。将棋や碁のようなゲームでも、コンピュータが一流の棋士逹に対抗できる時代である。データを集積し、ビッグデータを分析する方法で処理すれば、邪馬台国問題は全く機械的に解決できる見込みがある。そのようなこころみを、私たちは、行なってみた。
広島大学の教授であった川越哲志(かわごえてつし)氏のまとめた本に、『弥生時代鉄器総覧』(広島大学文学部考古学研究室、2000年刊)がある。
弥生時代の鉄器の出土地名表をまとめたものである。鉄器についての、尨大なデータが整理されている。
『魏志倭人伝』には、倭人は、「鉄鎖」を用いる、などとある。
『弥生時代鉄器総覧』の鉄器出土地名表をみると、福岡県には、49ページさかれている。これに対し、奈良県には1ページしかさかれていない。
「邪馬台国=奈良県存在説」を説く人々には、この愕然とするほどの圧倒的な違いが、目にはいらないのだろうか。
いま、たとえば、弥生時代の鉄族の出土数の県別の出土数をみれば、下図のようになる。
『魏志倭人伝』に記されている事物[鏡・絹・勾玉(まがたま)など]で、遺跡・遺物を残しうるものは、すべて、出土数において、福岡県が、奈良県を圧倒している。
(下図はクリックすると大きくなります)
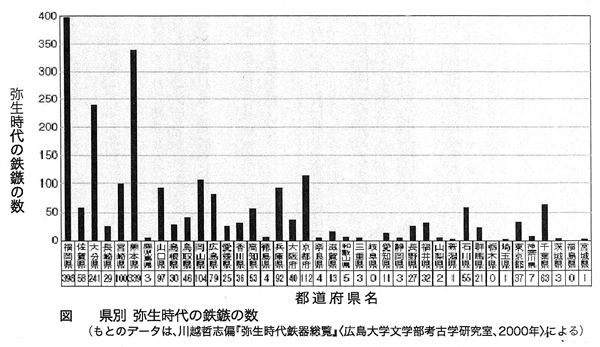
図のような分布を示すいくつかのデータから、邪馬台国が福岡県にあった確率や、奈良県にあった確率を計算によって求めることができる。
県ごとの確率は、つぎのようになる。
邪馬台国が、福岡県にあった確率 99.9%
邪馬台国が、佐賀県にあった確率。0.1%(千回に1回ていど)
邪馬台国が、奈良県にあった確率 0.0%
これについて、くわしくは、拙著『邪馬台国は99.9%福岡県にあった』(勉誠出版、2015年刊)をご参照いただきたい。
この確率計算にあたってご指導、ご協力をいただいた現代を代表する統計学者、松原望(まつばらのぞむ)氏(東京大学名誉教授、聖学院大学教授)はのべている。
「統計学者が『鉄の鏃』の各県別出土数データを見ると、もう邪馬台国についての結論はでています。」
統計学や、作戦計画(オペレーションズーリサーチ「OR」)の分野に、「探索問題」とか、「索敵問題」とかいわれる問題がある。これらは、そのまま、邪馬台国の探索問題につながりうる。
「探索問題」や「索敵問題」というのは、つぎのような問題である。
(1)探索問題
2014年3月8日、マレーシア航空機が行方不明になるという事件があった。この種の事件はこれまでにもたびたび起きている。
1966年1月16日に、アメリカのノースカロライナ州のセイモア空軍基地から四つの水爆を積んだジェット爆撃機が、とび立った。ところが、その爆撃機は給油機と接触し、燃料が爆発し、七名の乗務員が命をおとした。乗務員と、水爆と、飛行機の残骸が、空から降りそそいだ。しかし。幸いにして、核爆発はおきなかった。四つの水爆のうち、三つは、事故後に、二十四時間以内に発見された。ただ、最後の一つの水爆がみつからなかった。
大ざっぱにいえば、このようなばあい、爆弾の沈んでいそうな場所をふくむ地域についての確率地図をつくる。海面または海底の地図の上に、メッシュ(網の目)をかぶせる。小さい正方形のグリッド(格子)に分ける。そして、その一つ一つの正方形(セル、網の目)についての残留物などの情報をデータとしていれる。そして、爆弾がそのセルに存在する確率を計算する。このようにして、爆弾が沈んでいそうな場所を示す確率地図をつくる。
1968年にも、ソ連とアメリカの潜水艦が、乗組員もろとも、行方不明になっている。
(2)索敵問題
基本的には、探索問題と同じである。ただ逃げまわるターゲットや、人間の操縦で動いている目標物の位置をとらえたり、追跡したりする。
私たちは、基本的に、探索問題を解く方法によって、邪馬台国の場所を求めた。
確率の計算には、ベイズの統計学を用いた。
邪馬台国問題は、統計学や確率論の問題としては、ふっうの「探索問題」や「索敵問題」にくらべ、はるかに簡単な問題である。
それは、つぎのような理由による。
(1)「探索問題」では、セル(正方形の網の目)の数は、ふつう一万ヵ所ていどにはなる。
セルの数がふえると、確率計算は、急速に面倒なものとなる。邪馬台国問題のばあい、「どの県に邪馬台国はあったか」という形で、「県」を、セルとして用いれば、対象となるセルの数は、五十たらずである。電卓によってでも、根気よく計算すれば、計算できるてぃどの問題である。
(2)「鉄の鏃」「鏡」など、『魏志倭人伝』に記されている事物などの、各県ごとの出土数などを、データとして入れていく。このばあい、「索敵問題」などと違って、遺跡・遺物などは、動かない。逃げまわらない。
・専門性と市民運動
『読売新聞』の記者であったジャーナリストの矢沢高太郎氏はのべている。
「新聞やテレビで大きく報道されることによって社会的な関心が高まり、遺跡の生命が守られたケースは多い。しかし、同時に弊害もまたさまざまな形で発生した。学者にとっては、地味な論文を発表する以前にマスコミで大々的に取り上げられるほうが知名度も高まり、学界内部での地位も保証される傾向か強まった。
一部の学者で行政の発掘担当者はそれに気づき、狡知にたけたマスコミ誘導を行なってくるケースが多々見られるようになってきた。その傾向は、藤村新一氏以外には、考古学の。”本場”である奈良県を中心とする関西地方に極端に多い。そして、発表という形をとられると、新聞各社の内部にも何をおいても書かざるをえないような自縄自縛(じじょうじばく)の状況が、いつの間にか出来上がってしまった。
そんなマスコミの泣き所を突く誇大、過大な発表は、関西一帯では日常化してしまっている。藤村(新一)氏は『事実の捏造』だったが、私はそれらを『解釈の捏造』と呼びたい。」(旧石器発掘捏造。”共犯者”の責任を問う)[『中央公論』2002年12月号])
行政の発表が、しばしば地域の振興や、発掘費などの予算の獲得などをめざした我田引水的な大本営発表となっている。
なくなられた考古学者の森浩一氏も、考古学は、町人の学問であるべきであることを説き、官による考古学を批判している。
森浩一氏は述べている。
「今日の政府のかかえる借金は、国立の研究所などに所属するすごい数の官僚学者の経費も原因となっているだろう。」
「ぼくはこれからも本当の学問は町人学者が生みだすだろうとみている。官僚学者からは本当の学問は生まれそうもない。」
(以上、季刊『邪馬台国』102号、梓書院、2009年刊)
そして、行政には、目を光らせなければならないマスコミなども、しばしば、行政のお先棒かつぎになっている。
市民は、このような事態に時に声をあげなければいけない。そうでなければ、厖大な租税の浪費となる。しかし、そのような声は、かならずしも大きくはない。
なぜか。それは、ほとんど、すべての学問分野がそうなのであるが、学問や科学がしだいに専門性をおびてきているからであるとみられる。
行政にもの申すためには、専門的な知識を必要とする時代になってきている。たとえば、『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』は、詐欺的な現代人が捏造した文書である明白な根拠がある。それにもかかわらず、これをあくまで捏造の書ではないと言いはる「市民運動家?」がいる。
こうなると、もうイワシの頭も信心からで、宗教活動と異ならない。科学や学問の進展にとって、百害あって一利もない。科学的、客観的根拠をあげての議論よりも罵倒の応酬となる。市民があるていどの専門的な知識を身につけることが必要な時代となってきている。そして、わが国では、そのような必要性に十分にこたえうる水準にある市民はけっしてすくなくないとみられる。
私は月に一回、勉強会を開いている。私は本来、既存のもろもろの考えを検討し、整理し、その上で、自分の「知りたい」を追求したい人間である。勉強会は、私の知りえたことを発表し、それを検討していただき、そこで出た意見を私がとりいれる場である。それは、おもに、探究のための場である。それは、地味ではあっても、私なりの市民運動といえよう。
孔子はのべている。
「学びて思わざれば、すなわち暗く。思いて学ばざれば、すなわちあやうし。」
それにならっていえば、つぎのようになる。
「学びて動かざれば、知識の光は一般にとどかず、すなわち暗し。学ばずして動けば、誤りをおかすことになり、すなわちあやうし。」
・フッサールの現象学
現象学(Phänomenologieドイツ語)は辞書によると、哲学や諸学の確実な基礎をすえるために、一切の先入観を排して意識に直接に明証的に現れている現象を直観し、その本質を記述するフッサールの方法。彼はそれに到達するため日常的見方の土台にある外界の実在性について判断中止を行い、そのあとに残る純粋意識を分析し記述した。
この判断中止はエポケー(epocheギリシャ語)と言う。
宇宙全体からみれば、人間は時間的にも、空間的にも、きわめて小さな存在なのに、その人間の感覚とか意識とか、精神とかに重点をおいて世界をみている。そこから出発して議論をしようとする。
しかし、私はその立場をとらない。
・「認識」についての、「反映論」と「地図論」
私たちは、この世の中のさまざまな事象について、「認識」をするが、この「認識」とは、何であるかについて、おもに二つの立場をあげることができよう。
一つは、「反映論」、一つは、「地図論」である。
「反映論」は、おもに、唯物論の学者たちによってとなえられている。唯物論の学者たちは、私たちの認識、すなわち、感覚とか、概念などは、客観的な存在の反映、あるいは、模写であるとする。
そして、感覚から概念、判断、推理への移行を、反映過程の深化発展であると考える。すなわち、感性から知性への移行を、反映の深化とみなす。とくに、科学的な研究などでは、反映は、実験、調査、分析など、研究対象に対する人間の能動的な働きかけ、実践によってのみ得られるとする。
たえまない実践によって、対象についての反映は、たえず是正されていく。表面的な現象の記述から、対象がどのようなものでできあがっているかという実体的な知識へ、さらに、それらが、相互にどのように働きあって発展し、運動しているかという本質的な知識へと、しだいに内面に向かってすすんでいく。このようにして、対象への接近は、たえまなく進み、より深く、より近似的に、より全体的に、対象の本質にせまっていくことになるとする。
認識についての今一つの考え方である「地図論」は、おもに、コージプスキー(Korzybski,A.1879~1950)など、アメリカの、一般意味論の学者たちによってとなえられている。
一般意味論学者たちは、私たちの認識は、いわば、「地図」のようなものであると説く。「地図」によって、私たちは、A地点からB地点まで行くことができる。それと同じように、「地球は、まるい」という、外界についての認識(一種の地図)にしたがって、行動し、コロンブスは、アメリカを発見した。
はじめ、人びとは、「地球は平らである」と考えていた。これも、一つの素朴な地図である。人間の活動の範囲がせまいばあいは、そのような素朴な地図でも、とくに支障はもたらされなかった。
人間の知的、実際的な活動範囲がひろがるとともに、「地球はまるい」という、より正確な地図、あるいは認識が、しだいに人びとのあいだに浸透していった。
そして、さらに現代では、「地球は、球に近いが、北にややとびだしており、西洋ナシ形をしている」というあらたな地図がえられている。
物理学上の法則も、反映の一種であり、「地図」のような働きをもつ。その地図によって、ある結果を予測することができる。ある結果に行きつくことができる。
たとえば、万有引力の法則という外界についての「認識」(一種の地図)によって、人工衛星を打ちあげるのには、どのていどの初速度を与えればよいかなどを知ることができる。
外界についての「認識」が誤っていることは、誤った地図が与えられたことにたとえることができる。
このように、地図は、ときに誤っていたり、杜撰(ずさん)であったり、ゆがんでいたりすることがある。人間の認識が進むにつれ、地図は、より正確なものとなったといえるであろう。
また、「地図」には、ある一地域のみを拡大し、その地域のみをくわしくえがいたりすることができるが、私たちの「認識」も、あるせまい範囲の問題だけをとりあげて、くわしく示しているばあいがある。
私は、どちらかといえば、「認識」については、「反映論」よりも、「地図論」の方に賛成である。
・手つづき
(1)具体的な多くの事実やデータから、帰納的な方法によって、比較的わずかな、いくつかの前提(仮説、仮定)を導きだす(帰納を行う)。 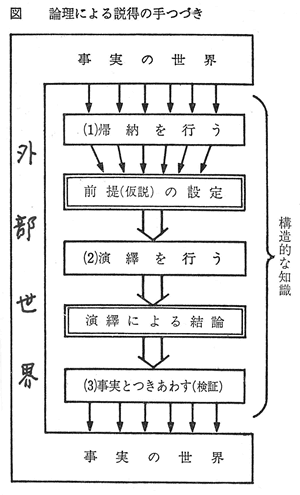
(2)そのいくつかの前提を出発点として、形式的にととのった落ちのない議論を展開し、結論を導きだす(演繹を行う)。
(3)その結論を、具体的な事実やデータといま一度照らしあわせて、矛盾することがないかどうかを調べる(事実とつきあわす)。
(4)矛盾したばあいは、いま一度前提を検討し、前提を修正するか、あるいはほかのもっと適切な前提を選ぶ。新たな前提によって(2)以下の手つづきをくりかえす。
(5)このようにして、矛盾なく対象を説明する体系がえられたならば、他を説得しうるものとして提示することができる。
昔、山下清という絵描きがいた、彼は兵隊の位で言えばという表現をした。これも再現性言語である。
■具体的手法
・分類論
安本美典・本田正久著『文因子分析法』培風館1981年刊などから・・・
作家の位置の立体表示について、
分類論の具体的例として文体の研究を行った時、漢字をどの程度使うか、センテンスの長さがどうであるかなどの因子を因子分析法という統計手法で文体を分析して、幾つかの要因に分け、どの因子が強く働いたかを、現代作家について三次元グラフにしたものである。因子得点を用い、8人の作家の文章を、三次元空間に位置付ける。
たとえば泉鏡花の場合、A因子得点は43.97、 B因子得点は61.77、C因子得点は66.64である。したがって、A因子得点は平均得点50(座標の中心)より小さく、B因子得点、C因子得点は平均得点より大きい。そこで、泉鏡花の位置は図のようになる(左のグラフ)。
文章の性格(文体)プロフィールについて、
どういう要素が強く働いているかを分類して文章の性格を表す。「プロフィール」というのは、本来は、人間の「横顔」のことである。しかし、心理学では、個人の精神のさまざまな側面、たとえば、能力や性格などをテストによって測定した結果を、折れ線グラフなどで表示したものを「プロフィール」という。右のグラフは、それにならっている。
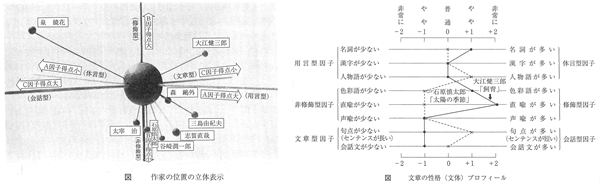
更に、いくつかの因子の組み合わせによって現代作家100人を分類したものが下図である。

・検定論
いかに可能性の低いことでも起こりうるとすると議論ができなくなる。そこで、統計的な一定の基準をおいて、仮説を破棄する必要がある。したがって一定の確率(百分の一、または百分の五)以下の仮説は棄てるとする約束を設けるのである。
このようにして、日本語の起源を求める手法に使う。他の言語と日本語の近さを基礎200語から偶然以上の一致があるか検定する。
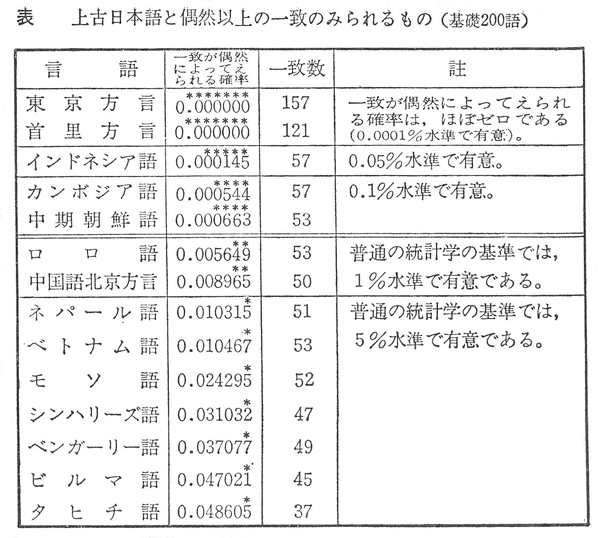
そして、各言語の分裂した言語年代学のグラフができる。
(下図はクリックすると大きくなります)
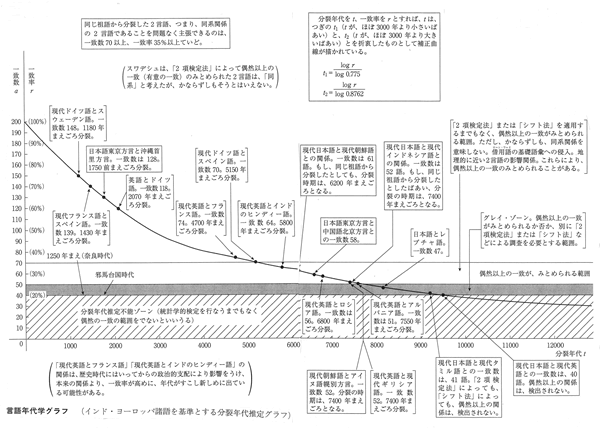
・確率論
既に説明した邪馬台国が福岡県にあった確立などの手法である。
どうも、「トランプ主義」、「フェイク・ニュース」、「事実より説得」、「言ったもの勝ち」、と言ったことがやたらになど横行している。
これらについて、機会があったら説明していきたい。




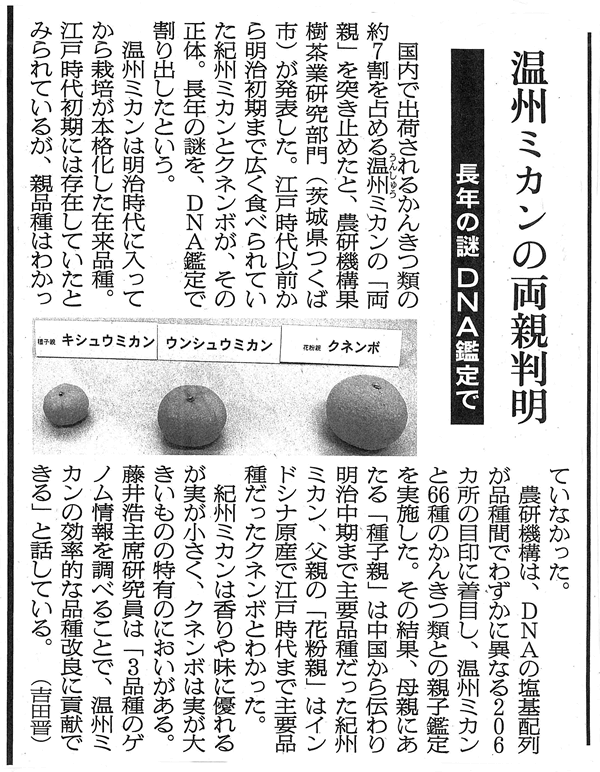
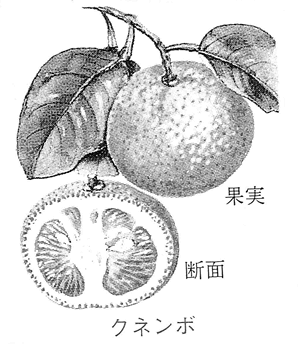 「結論として、薩摩マンダリン(温州ミカン)は紀州ミカンタイプのマンダリン(「南豊蜜橘」の子孫あるいは同類)の種子親とクネンボタイプのマンダリン(「本地広橘」の子孫あるいは同類)の花粉親とのたまたまの交雑に由来しているようにみえる。」とされている。
「結論として、薩摩マンダリン(温州ミカン)は紀州ミカンタイプのマンダリン(「南豊蜜橘」の子孫あるいは同類)の種子親とクネンボタイプのマンダリン(「本地広橘」の子孫あるいは同類)の花粉親とのたまたまの交雑に由来しているようにみえる。」とされている。
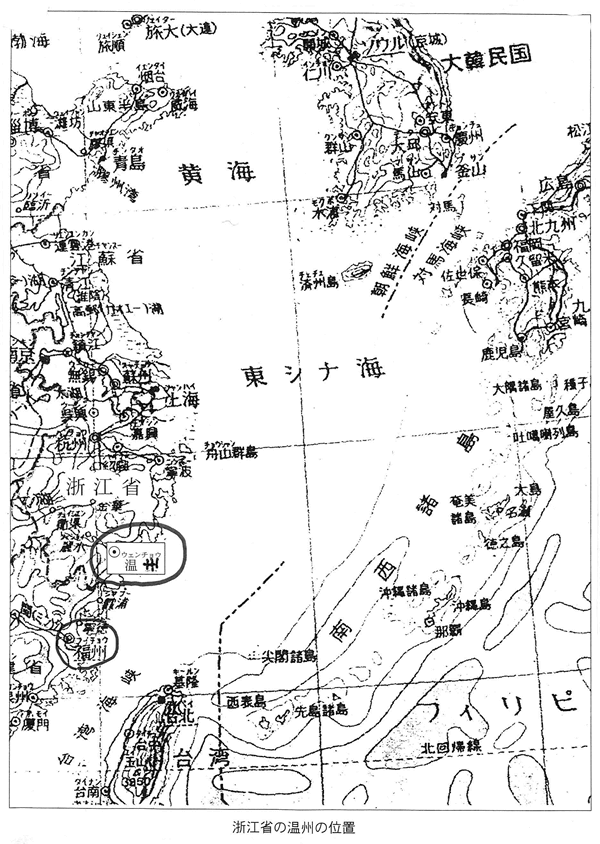
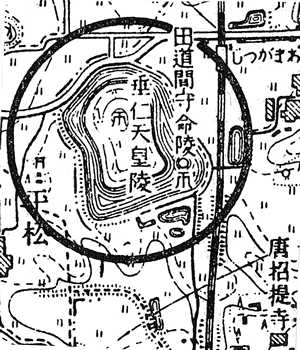 田道間守は、天皇が崩御されたことを聞いて、泣き悲しんで、「ご命令を天皇より承って、遠隔の地に参り、万里の波浪を越えて、遥かに弱水を渡りました。この常世国は、神仙が隠れ住む世界であって、俗人が行ける所ではありません。そういうわけで、往復する間に自然に十年が経過いたしました。思いもよらないことでありました、ただひとり高い波頭を越えて再び本土に戻ることができようとは。しかしながら、聖帝の神霊によって、かろうじて帰って来ることができました。
田道間守は、天皇が崩御されたことを聞いて、泣き悲しんで、「ご命令を天皇より承って、遠隔の地に参り、万里の波浪を越えて、遥かに弱水を渡りました。この常世国は、神仙が隠れ住む世界であって、俗人が行ける所ではありません。そういうわけで、往復する間に自然に十年が経過いたしました。思いもよらないことでありました、ただひとり高い波頭を越えて再び本土に戻ることができようとは。しかしながら、聖帝の神霊によって、かろうじて帰って来ることができました。