■序論
炭素14年代測定法というと、科学的な年代測定法である印象を与える。
しかし、炭素14年代測定法によって得られる年代推定値は、100年単位の広い幅をもっている。
また、同じ遺跡から出土した試料であっても、土器付着炭化物を測定するか、桃の核を測定するかなど、「なにを測定するか」によって、得られる年代推定値が、大きく異なる。
さらに考古学では、炭素14年代測定法によって、古い年代が得られたときには、マスコミ発表を行ない、新しい年代が、得られたときには、マスコミ発表を行なわないということを、くりかえしている。これをくりかえすと、個々に得られた発表事実は、正しくても、全体としては、正しくない判断を社会にもたらす。
「年代は、古きをもって貴(たっと)しとす」という基本的感覚は、旧石器捏造事件という大きな失敗をもたらした重要な原因の一つであった。
「懲りない面々」とならぬようチト、反省の必要があるのではないか。
たとえば、中国において「位至三公鏡」といわれる鏡は、しばしば280年~300年ごろの年代を記した墓誌とともに出土している。この鏡は、わが国でもかなり出土している。このような事実は、炭素14年代測定値よりも、より確かな年代情報をもたらしているようにみえる。
情報の信頼性が大きいか小さいかについての基本的な検討なしで、みずからがあらかじめもっている説を支持するような結果がでたときは、マスコミ発表にもって行くという方法は、基本的にあやうい。科学的な方法の進展のための重要な阻害要因となる。
また厖大な公費を無益に費消することにもなる。
桃や大型建物の話は『魏志倭人伝』にはでてこない。桃や大型建物の話がでてくるのは、『古事記』の出雲関係の神話である。
旧石器捏造事件が、いつ、何度おきてもおかしくない土壌が依然として存在している。ここに、強い警鐘をならさざるをえないゆえんがある。
■ベニバナ論争
(根拠にならないことを、根拠にする)
わかりやすい簡単な一例をあげてみよう。
2007年10月3日(水)のことである。朝刊各紙は、奈良県桜井市教育委員会の、纒向遺跡から出土したベニバナ花粉についての発表を報道した。
つぎに、『読売新聞』にのったものを紹介する。『朝日新聞』『毎日新聞』『日本経済新聞』などの各紙も大略『読売新聞』の記事に近い内容を報道した。
(下図はクリックすると大きくなります)
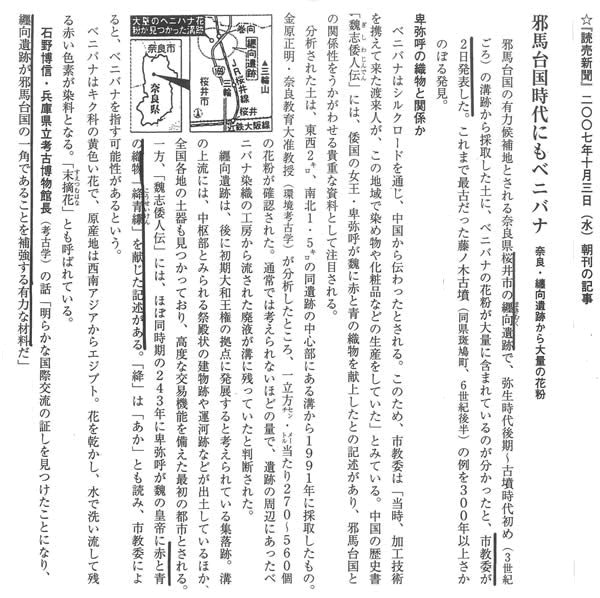
ここで、石野博信・兵庫県立考古博物館長(考古学)の話として「明らかな国際交流の証しを見つけたことになり、纒向遺跡が邪馬台国の一角であることを補強する有力な材料だ」と
掲載している。
このように、簡単に邪馬台国に結び付ける。
今年の春の桃の種からの『毎日新聞』2018年5月15日(火)の記事で石野氏の話が下記である。
「石野博信・兵庫県立考古博物館長の話 今回の分析の結果は、纏向遺跡が4世紀以降だという主張は成り立たないことを示している。邪馬台国の問題では科学的分析による暦年代での議論も必要で、貴重な資料が加わった。」
このときもこのように簡単に邪馬台国に結び付けている。
ベニバナの話として、読者は、この記事の、どこに問題があるか、おわかりであろうか。
この記事のなかの奈良県桜井市の纒向遺跡の溝跡から採取した土に、ベニバナの花粉が、大量に含まれていたことは事実とみられる。
しかし、この記事の、「中国の歴史書『魏志倭人伝』には、倭国の女王・卑弥呼が魏に赤と青の織物を献上したとの記述があり、邪馬台国との関係性をうかがわせる貴重な資料として注目される。」あたりからおかしくなる。
というのは、この記事の、「赤と青の織物」とあるところは、『魏志倭人伝』では、「倭錦(わきん)・絳青縑(こうせいけん)[赤青色の、織りをつめて細かく織った絹の布]・緜衣(めんい)[まわた。絹のわたを用いた衣服]・帛衣(はくい)[白い絹の布]」とあるのである。ここに記されているのは、いずれも、絹製品である。
ところが、三世紀以前の弥生時代において、肝心の絹が出土するのは、もっぱら、北九州であって、奈良県ではないのである。奈良県と『魏志倭人伝』の記事とは、簡単には、結びつかない。
考古学者の森浩一は、その著『古代史の窓』(新潮文庫、1998年刊)のなかでのべている。
「ヤマタイ国奈良説をとなえる人が知らぬ顔をしている問題がある。(中略)
布目氏[布目順郎(ぬのめじゅんろう)、京都工芸繊維大学名誉教授]の名著に『絹の東伝』(小学館、1988年刊)がある。目次をみると、『絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在等を探る』の項目がある。簡単に言えば、弥生時代にかぎると、絹の出土しているのは、福岡、佐賀、長崎の三県に集中し、前方後円墳の時代、つまり四世紀とそれ以降になると奈良や京都にも出土しはじめる事実を東伝と表現された。布目氏の結論はいうまでもなかろう。倭人伝の絹の記事に対応できるのは、北部九州であり、ヤマタイ国もそのなかに求めるべきだということである。この事実は論破しにくいので、つい知らぬ顔になるのだろう。」
『朝日新聞』の記者、柏原精一(かしわばらせいいち)氏は、その著『図説・邪馬台国物産帳』(河出書房新社、1993年刊)のなかで、布目順郎の研究などを紹介したうえで、つぎのようにのべている。
「ここで、弥生時代から古墳時代前期までの絹を出土した遺跡の分布図を見てみよう。邪馬台国があった弥生時代後期までの絹は、すべて九州の遺跡からの出土である。近畿地方をはじめとした本州で絹が認められるのは、古墳時代に入ってからのことだ。
ほぼ同じ時代に日本に入ったとみられる稲作文化が、あっという間に東北地方の最北端まで広がったのとは、あまりの違いである。ヤマグワの分布は別に九州に限らないから、気候的な制約は考えにくい。
布目さんは次のような見解をもっている。
『中国がそうしたように、養蚕は九州の門外不出の技術だった。少なくともカイコが導入されてから数百年間は九州が日本の絹文化を独占していたのではないか』
倭人伝のいうとおりなら、邪馬台国はまさしく絹の国。出土品から見ても、少なくとも当時の九州にはかなり高度化した養蚕文化が存在したことには疑いがない。
『発掘調査の進んでいる本州、とくに近畿地方で今後、質的にも量的にも九州を上回るほどの弥生時代の絹が出土することは考えにくい』
そうした立場に立つなら、『絹からみた邪馬台国の所在地推定』の結論は自明ということになるだろう。」
京都大学の出身者は、伝統的に「邪馬台国=畿内説」をとる人が多いといわれる。
しかし、ここに名のみえる柏原精一氏も、布目順郎も、京都大学の出身者である。
ただ、柏原精一氏も、布目順郎も、理科系の学部の出身者である。
ものごとを、データに即してリアルにみる理科系の方の判断は、京都大学の出身の考古学者とは、また別ということであろうか。
布目順郎は、『絹の東伝』のなかで、「絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在を探る」という見出しのもとに、邪馬台国の時代と、その前後の時代を通じての、絹製品出土地を、くわしく列記したうえでのべる。
「これらを通観すると、弥生後期の絹製品を出した遺跡もしくは古墳は、すべて北九州にある。したがって、弥生後期に比定される邪馬台国の所在地としては、絹を出した遺跡の現時点での分布からみるかぎり、北九州にあった公算が大きいといえるであろう。
わが国へ伝来した絹文化は、はじめの数百年間、北九州の地で醸成された後、古墳時代前期には本州の近畿地方と日本海沿岸地方にも出現するが、それらは北九州地方から伝播したものと考えられる。(中略)
ここで考えられるのは、邪馬台国の東遷のことである。私は、邪馬台国の東遷はあったと思っている。
(後略)」
つまり、桜井市教育委員会の発表にもとづく記事は、「邪馬台国は奈良県にあったはずだ」という前提に立った「解釈記事」なのである。
「ベニバナ→染める→『魏志倭人伝』の赤と青の絹織物記事」という連想ゲームによる記事なのである。
しかし、この連想ゲームは、事実にもとづいていない。
ベニバナの花粉が出土したとしても、ベニバナが、かならず絹製品を染めたことにはならない。奈良県のばあい、絹以外の繊維製品を染めた可能性が大きい。当時の人々も、衣服をきていたのである。その衣服を染めただけの話であるとみられる。
ベニバナは古語では、「くれなゐ」とも、「末摘花(すえつむはな)」ともいわれた。
『万葉集』の861番の歌に、つぎのようなものがある。
「松浦川(まつらがは) 川の瀬速(はや)み くれなゐの 裳(も)の裾(すそ)濡れて 鮎(あゆ)か釣るらむ」
[松浦川の、川の瀬が速いので、くれないの裳[一種の長いスカート]の裾を濡らして、娘たちは鮎を釣っていることだろうか。]
この歌に、「くれないの裳」ということばがみえる。ベニバナで染めた裳とみられる。
娘たちが鮎を釣るのに赤い絹のスカートをつけているとは思えない。これは、「からむし(苧)」か「麻」など繊維を用いた裳であろう。
ベニバナが出土したからといって、それが、『魏志倭人伝』と結びつくということにも、絹と結びつくということにもならない。
次に『万葉集』の1710番の歌がある。
「我妹子(わぎもこ)が、赤裳(あかも)ひづちて 植ゑし田を 刈(か)りて収(をさ)めむ 倉無(くらなし)の浜」
[かわいいあの娘(こ)が 赤裳を濡らして、植えた田を刈りとって収めようにも収まる倉がないという倉無(くらなし)の浜。
田植は一般に女性の作業であった。倉無ノ浜を起す序。豊作で倉に収まらない、という気持でかけた。倉無ノ浜は豊前の海浜の地名なので、豊の国のトヨに豊穣の意を認めて詠んだのであろう。
また、さきの『読売新聞』記事中の、「弥生時代後期~古墳時代初め(3世紀中ごろ)」という記事にも、疑問がある。古墳時代の初めは、4世紀ごろとみる見解もあるからである。
くれなゐの現代名はベニバナ。この植物は原産地のエジプトから中国(当時の呉)を経由して日本に渡来した有用植物であり、万葉人の生活に重要な役割りを果たしたことから29首の歌に詠みこまれている。しかし、くれなゐの花そのものを題材としているのは「外(よそ)のみに見つつ恋せむ紅の末摘花の色に出でずとも」(巻10-1993)など3首だけで、それ以外はすべてくれなゐによって染められた衣や紅に染まる山などを詠み上げた歌ばかりである。
ベニバナ=キク科(辞書より)
エジプトを原産地とする越年生草本で中国の古名「呉(ご)」を経て渡来した藍(あい)ということで呉藍(くれあい)と名づけられ、それが紅(くれない)となり、紅(べに)花と呼ばれるようになった。夏に1メートルほどに伸びた茎の先端にアザミの花によく似た鮮黄色の花が咲き、しだいに赤色に変化する。この花を別名末摘花(すえつむはな)と呼び、染色に用いるほか、便秘、頭痛、血行障害に効く薬となる。種子は食用油、若葉はサラダ菜となる。
この種の例は、あげてゆけばきりがない。この種の連想ゲーム、解釈、確実な事実にもとづくとはいえない大本営発表、フェイク[偽(にせ)の]情報のつみかさねによって、「畿内説」は成立している。
捏造をひきおこす個人、組織、文化は、捏造をくりかえす傾向があるといわれている。
■考古学者 大塚初重氏の感想
大塚初重氏は『朝日新聞』の「語る 人生の贈りもの」欄で、旧石器捏造事件をとりあげてのべておられる。
・2018年、7月4日(水)朝刊
「60年代以降、開発が進み、事業者の負担で何万平方メートルも一気に掘るようになる。そして、成果が出れば、日本最古だ、最大だと、マスコミがはやし立てるわけです。あげくに担当者も「時の人」として祭り上げられる。
ぼくは、あの事件は、成果を求めすぎ、結論を急ぎすぎたゆえに起きたと思っています。学問にはきちんとした方法論とそれにのっとった論証、さらには議論が必要なのに、捏造事件では関係者と周囲がそれをおざなりにした。
学問は一朝一夕にはならない。結論を急いではいけないのです。かまびすしい邪馬台国の所在地論争にも今、同じことを感じています。」
この大塚初重氏の発言ののっている記事は纒向学研究センターが纒向出土の桃の核についてのマスコミ発表を行ってから、二カ月たらずあとの時期の新聞にのっている。微妙で意味深長である。
■桃の話
桃や大型建物の話は邪馬台国や卑弥呼と結びつくものなのか。
桃の話も大型建物の話も、『魏志倭人伝』にはでてこない。桃の話や大型建物の話が出てくるのは『古事記』の神話である。
シュリーマンの話、神話をもとに発掘して、神話を裏づけるものがでてきた。
ギリシャ、ローマについての考古学や聖書の考古学はすべての考古学のはじまりであり母胎であった。
日本のばあい・・・・
「考古栄えて記紀滅ぶ。」となる。
『古事記』桃の実が出る話は下記である。
伊邪那美の命(いざなぎのみこと)、伊邪那岐の命(いざなみのみこと)の国生みで出てくる。
その後、伊邪那美の命が亡くなり、伯耆の国と出雲の国の境にある比婆山に葬られる。
伊邪那岐の命が亡くなった伊邪那美の命に会いたくて、黄泉の国をたずねる。
そこで、伊邪那美の命はすでに私はあの世の食べ物を食べてしまったのでもう帰れませんが、あの世の神様と相談してきますから待っててください。その間に私を見ないでくださいと言って去った。しかし、伊邪那岐の命が待ちきれず、うじがたかった伊邪那美の命の姿を見てしまう。伊邪那美の命は怒って、八種の雷神(いかずちがみ)、千五百の軍を差し向け追いかける。そこで伊邪那岐の命は出雲の国意宇郡伊賦夜坂(いふやさか)まで逃げ、そこで最後に桃の実を投げ、逃げおおせる。そして、感謝の意を込めて桃の実に意富加牟豆美の命(おおかむづみのみこと)の名を授ける。
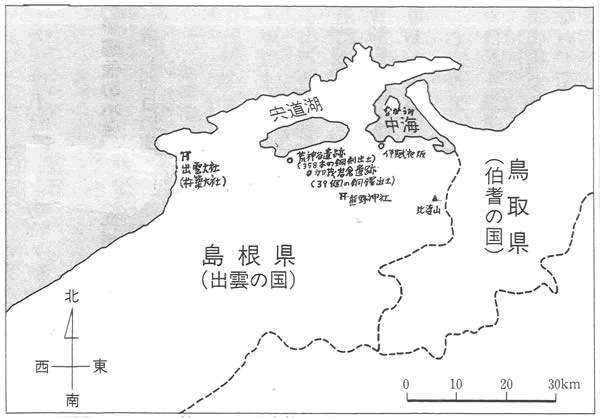
このように、日本神話には桃の実が出てくる。そして桃の実は何らかの意味で邪気を払うように使われている。
また、桃太郎の吉備団子で有名な岡山県では、22遺跡から、13,000個以上の桃の種が出ている。
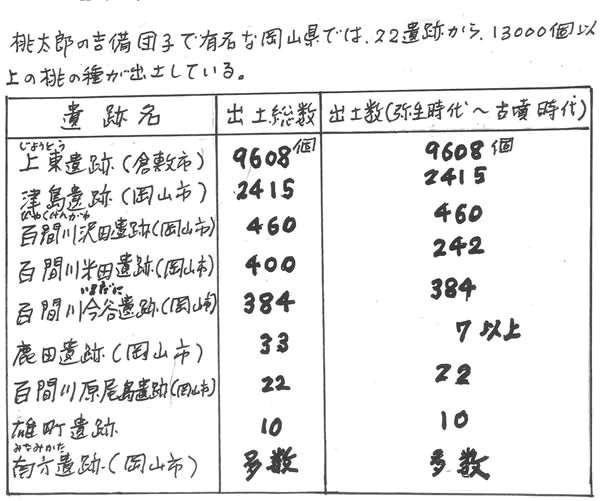
岡山県では、桃の種がたくさん出てくるが、考古学的に桃の種が重要だと思っていないから、出てきても捨てたとの話がある。
しかし、纏向遺跡から桃の種が出てくると、重要視して調べる。
■『古事記』神話のなかの大きな建物
大国主(おおくにぬし)の神(かみ) 国譲り。
2004年4月29日(土)の朝刊各紙は、出雲大社の巨大神殿の跡から、三本の部材を合わせた直径3メートルの柱などが出土したことを報じている。これは11世紀~13世紀(平安時代~鎌倉時代初め)の巨大神殿(本殿)の跡とみられる。
本居宣長の『玉勝間』の十三の巻の、「同社(出雲大社)金輪の造営の図」の条に、つぎのように記されている。
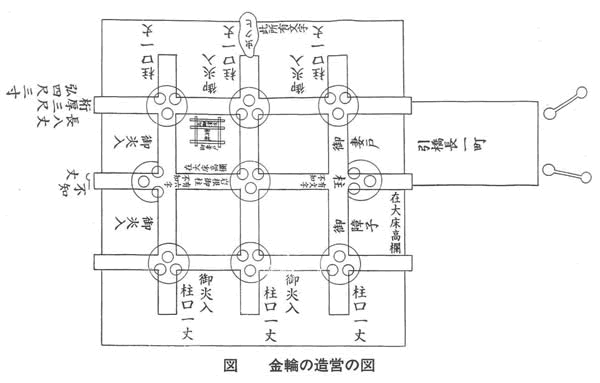
「出雲大社の神殿の高さは、上古には三十二丈あり、中古には十六丈あり、今の世のは八丈である。いにしえの時の図を、『金輪の造営の図』といって、今も千家国造(せんげくにのみやつこ)[出雲国造の一つ。代々出雲大社の宮司]の家で、伝えて持っている。その図は、上に記すとおりである。
この図は、千家国造の家のものを、写し取った。理解しがたいことばかりが多いが、今はただもとのままに記す。
今の世の宮殿も、おおかたの構造は、この図のようであるということである。」(現代語訳は安本。もとのテキス卜は、筑摩晝房刊『本居宣長全集第一巻』による)
この図をみると、「柱口一丈(約三メートル)」とある。2000年に出土した柱と寸法はあっている。
『金輪造営図』の「金輪」とは三本の柱を金輪で束ねたということであろうか。
出雲大社の高さについては、『古代出雲大社の復元』(大林組プロジェクトチーム編著、学生社刊)のなかで、京都大学の教授であった建築史家の福山敏男が、つぎのようにのべている。
「室町時代の本殿の大きさについては資料がほとんどない。ある記録に、景行天皇の時の本殿は高さが三十二丈あり、その後十六丈になり、つぎに八丈になり、今は四丈五尺になってしまったと記す。高さ四丈五尺というのは室町初期のありさまであろう。
平安時代までさかのぼると、本殿が非常に高大であったという記録が見出される。明治四十一年(1908)~四十二年(1909)の『神社協会雑誌』の誌上で、山本信哉博士と伊東忠太博士が出雲大社本殿の高さについて数回にわたって論争されたことがある。その際山本博士によって引用されたのが『口遊(くちずさみ)』の記事である。社伝の三十二丈説は疑わしいものとして両博士とも採用されない。十六丈説は伊東博士は常識的には考えられないとして拒否されるが、山本博士は東大寺七重塔を造る場合には高い足場をかまえるのであるから、十六丈の本殿は造ることができるはずと主張された。
『口遊』というのは、『三宝絵詞(さんぽうえことば)』の作者源為憲(みなもとのためのり)が天禄元年(970)に書いた本で、有名なものを暗記するための言葉を集めてある。そのうち、大屋(たいおく)については『雲太(うんた)、和二(わに)、京三(きょうさん)」(出雲太郎、大和二郎、京三郎の意味)の語を出して、雲太とは出雲国城築(きづき)明神の神殿をいい、和二とは大和国東大寺大仏殿をいい、京三とは京の大極殿をいう』という説明が加えてある。これによるとこの本が書かれた頃には、日本の大建築として、出雲大社の本殿は平安宮の大極殿には勿論のこと、東大寺大仏殿にもまさるものであったと信じられていたことがわかる。高さだけでいえば当時の東大寺の東塔は大仏殿より大きかったはずであるが、殿屋ではないので除外されたのであろう。また面積の点では大仏殿や大極殿の方が大社の本殿より大きかったはずであるが、その点はしばらく考えないで、棟高だけを問題にしたのであろう。当時の大仏殿の棟高については諸説あって一致しないが、一番古い記録に十五丈とあるのを採っておこう。そうすると、『口遊』によると大社の本殿の棟高は十五丈以上ということになる。これは社伝に昔は十六丈であったというのを、裏書きしているようにみえる。
また大社の本殿は、平安時代の中期から鎌倉時代の初期にいたる二百余年の間に七度も倒壊している。
普通の神社ではこのような現象は見られない。これは大社の本殿が特別に不安定な倒れやすい構造をもっていたことを語っており、それは常識では考えられないくらいの長い柱で造られていた結果であろう。
天仁三年(1110)、丹波守藤原家保が大社の造営にあたったとき、大木百本が社辺の海岸に流れつき、この材木で本殿をつくったので、『寄木の造営』とよばれた。この造営の余木で長さ十五丈、直径一丈五尺の大木一本が因幡国に漂着したという。大社の本殿としてはこのように長大な材料が必要であったと信じられていた点に注意すべきである。」
『日本の神々神社と聖地7山陰』(白水社刊には、出雲大社の大きさについて、くわしい説明があり「当社の神殿が古今を通じて『天下無双の大廈(たいか)[大きい建物]であることは動かない。』と記している。
■大和の国の地のかつての支配者
『古事記』は、大国主の神[八千矛(やちほこ)の神]が地方に行くことを「幸行(いでます)[天子がでかけることをいう敬語]と記し、大国主の神の正妻の須勢理毘売(すせりびめ)のことを「后(きさき)」と記している。天皇なみのあつかいがされている。
『古事記』神話にはまた大国主の神が出雲から大和(倭)へ行く話や、大和の三諸山(みもろやま)[三輪山]に、大国主の神の和魂(にきみたま)[おだやかで、柔和なほうの側面の魂・神霊。大物主(おおものぬし)の神という]をまつった話が記されている。それは大神(おおみわ)神社の鎮座起源の話である。日本最古の神社ともいえる。
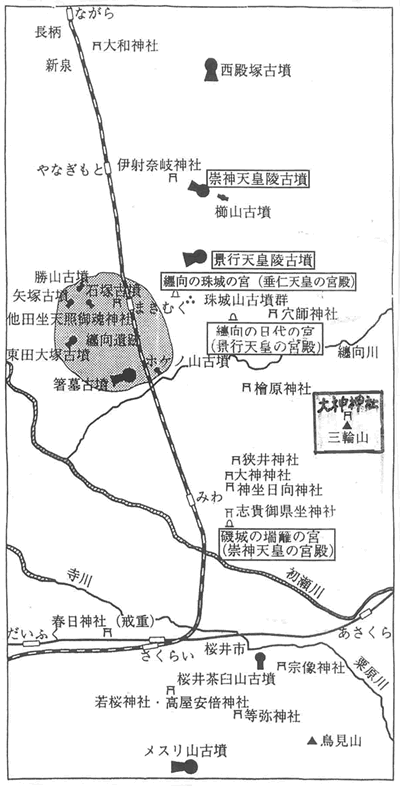
『日本書紀』には、大国主の神の別名を「大物主の神」というとある。
『日本書紀』では、神武天皇は大物主の神の子の事代主(ことしろぬし)の神の娘の媛蹈鞴五十鈴媛の命(ひめたたらいすずひめのみこと)を皇后としたという話をのせている。ここで思い出されるのは、大正~昭和時代の女性研究史の研究家、高群逸枝(たかむれいつえ)が、その著『母系制の研究』(全集第1巻、理論社1966年刊)などのなかで説いた「両系相続(双系相続ともいう)」という概念である。
「両系相続」というのは、つぎのようなものである。
「身分の高い(貴種の)皇子などが、他の土地へ行く。その土地の支配者の娘を妻とし、その間に生まれた子が、やがてその土地の支配者になる。
このように、結婚を通じて、貴種の一族は支配権を広げて行く。」大国主の神なども、多くの地の女性と結ばれることによって、支配権をひろげていったとみられる節がある。
たとえば『新撰姓氏録』の「山城国神別(やましろのくにしんべつ)」をみると、秦忌寸(はたのいみき)という氏族は、邇芸速日の命(にぎはやひのみこと)の子孫であると記されている。
秦忌寸は本来渡来系で、秦(しん)の始皇帝の子孫とされている。邇芸速日の命の子孫では、ありえないように思える。
しかし、それは父系相続のみを考えるから奇異な印象を与えるのである。
秦氏の娘を、邇芸速日の命の子孫がめとり、そのあいだに生まれた子が、その氏族の長となれば、邇芸速日の命の子孫でありながら、渡来系の氏族の長であるということが、おきうるのである。
ふつう、私たちは、ある祖先からはじまって、子孫の数がふえて行く図式を考える。
しかし、父系、母系の両方を考える両系相続では、むしろさかのぼるにつれて、祖先の数がふえて行く図式が考えられる。」
小説家の陳舜臣氏の『中国の歴史』(平凡社刊)に、つぎのような文章がある。
「春秋時代もけっこう戦争は多かったのですが、完全亡国はあんがいすくなかったようです。完全に国をほろぼすと、祭祀をうけない祖神が祟るとおそれられました。だから、周は殷(いん)をほろぼしても、殷の後裔(こうえい)を宋(そう)に封じて、祭祀をつづけさせたのです。春秋時代、虢(かく)という国が晋にほろぼされましたが、これも完全亡国ではなく、小虢と呼ばれる小国が存在を許されています。」
『古事記』『日本書紀』によれば、崇神天皇の時代に、流行病がはやり、大国主の命の子孫の意富多多泥古(おおたたねこ)をさがしだして、祖神を祭らせたという話がみえる。
これは、周が殷をほろぼしても、殷王朝の子孫に、祖神を祭らせたのと同じような考え方によるのであろう。
このようにみてくると、大国主の神は、国譲りをするまで、出雲地方から大和の国にいたる広い地域の支配者的、主権者的存在であったことがうかがえる。
奈良県香芝市二上山博物館編の『邪馬台国時代のツクシとヤマト』(学生社、2006年刊)という本がある。
その本のなかに、寺沢薫氏の「銅鐸の終焉と大型墳丘墓の出現」という文章がおさめられている。その文章のなかで、寺沢薫氏は「破砕銅鐸の一覧表」を示しておられる。
その表のなかから、大阪府と奈良県の部分をとりだすと、下表のようになる。

表をみるとき、つぎのようなことが、注目される。
(1)大阪府和泉氏出土のものは、廃棄時期が庄内式の時期とされる。
(2)大阪府豊中市出土のもののばあい「溝2から庄内甕出土」とされている。
(3)奈良県桜井市纏向遺跡出土のものは「本来は庄内期に所属か」と記されている。庄内期の大阪府や奈良県には銅鐸が存在したことになる。
そして大国主の勢力範囲と、銅鐸の分布圏がかなり重なりあうようにみえる。 今回の大型建物とか桃の種は、庄内式土器の時代である。それは銅鐸の時代となる。これは大国主の時代で、『魏志倭人伝』の邪馬台国より『古事記』などに出ている時代となる。
そして、纏向遺跡からの桃の種の分析からは3世紀前半となる。これは桃の種や大型建物は『古事記』時代であり銅鐸の時代である。
位至三公鏡などの西晋鏡の時代は中国から墓誌が出てきており、3世紀後半である。これは破砕銅鐸の時代である。
箸墓古墳から桃の種が出ている。桃の種から分析すると4世紀になってしまう。箸墓古墳が3世紀とする根拠は土器付着炭化物である。
桃の種の分析から3世紀前半と4世紀の分析結果が出ている。
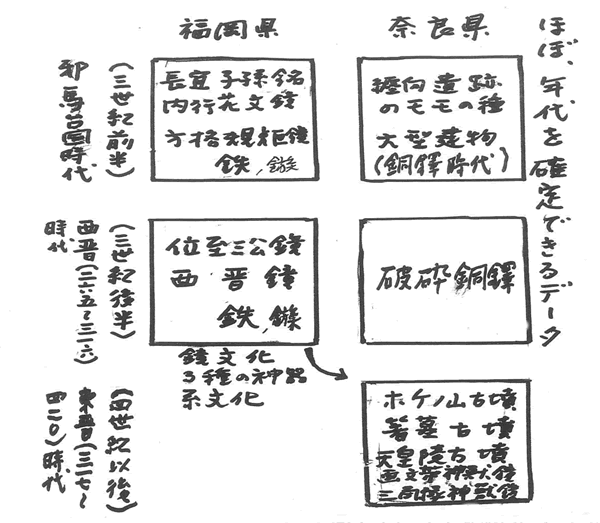
■和辻哲郎の邪馬台国東遷説
ここで思い出されるのは、かつて哲学者の和辻哲郎ののべた「銅剣・銅矛・銅戈文化圏と銅鐸文化圏との対立図式」と「邪馬台国東遷説」とである。
東京大学の古代史家、井上光貞は、和辻哲郎の説を、つぎのように要領よくまとめている。
「もし皇室が大和に興ったとすると、弥生時代の畿内の祭器であった銅鐸は何かの形で大和朝廷の祭祀や文化のなかに残っていてもよさそうなものである。ところが銅鐸は、山麓などで、まるで打ち捨てられたようにして出土する。その反対に、北九州系の鏡・玉・剣は皇室の皇位のシンボルにまでなった。
これは九州の支配者が、銅鐸をもつ畿内の先住民を滅ぼしたことを物語っている。」(井上光貞『日本の歴史1 神話から歴史へ』「中央公論社刊」)
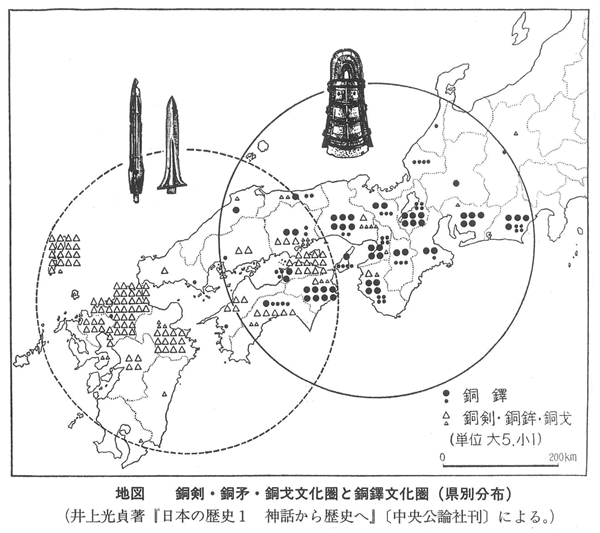
「それでは、この九州の支配勢力とは何をさすのであろうか。和辻氏は、それを邪馬台国であるとした。」
「もっとも自然なのは、邪馬台国東遷なのである。
もちろん邪馬台国東遷説も、可能性のある一つの仮説にすぎないが、『北九州の弥生式文化と大和の古墳文化との連続性』、また『大和の弥生式文化を代表する銅鐸と古墳文化の非連続性』という中山氏や和辻氏の提起した問題は、依然として説得力をもつと考えられる。また、邪馬台国は、その女王壱与(いよ)が266年に晋に遣使した後、歴史の上から姿を消してしまった。いっぽう畿内の銅鐸も、二、三世紀の弥生後期にもっとも盛大となり、しかも突如としてその伝統を絶った。そして三世紀末、おそくとも四世紀はじめごろから古墳文化が畿内に発達して全国をおおっていくのである。邪馬台国東遷説は、この時間的な関係からみても、きわめて有力であるといってよいであろう。
銅剣・銅矛・銅戈の文化圏は、また、鏡の文化圏と重なる。
■全国の大型建物
表をみると、そこに示された21例のうち、関東の都県のものが、14例である。21例のうち2/3を占める。
とくに、神奈川県が9例を占めている。
そのため、奈良県では、きわめてめずらしい大型建物が、神奈川県では、さほどめずらしくないというような現象がおきている。
これは、たまたま、私の手ももとに『弥生の大型建物とその展開』(サンライズ出版、2006年刊)という本があったからである。この本には、「東日本の弥生時代~古墳時代前期のおもな大型住居一覧表」がのっている。これは、東日本の大型建物について、かなりくわしく統一的な基準でまとめた表である。他の地域についても、おなじようにくわしく調査されたならば、状況がかなり変わってくる可能性がある。
(下図はクリックすると大きくなります)

桃の核などでも、桃太郎の吉備団子(きびだんご)でしられる岡山県などでは、これまでにそうとうな桃の種が出土したが、特別に重要な遺物とは思われず捨てられていたというような話もきく。
ベニバナにしても、桃の核にしても、大型建物にしても、我が国の全都道府県での出土状況が、同じ基準で公平にしらべて比較することが行われていない。
たまたま纏向遺跡からでて来たものに『魏志倭人伝』と特別な結びつきがあるような「解釈」強調が行われ、マスコミにとりあげさせて騒ぐというようなことがくりかえされている。
基本文献である『魏志倭人伝』からはなれたところで騒いでいる。
(1)『魏志倭人伝』に記されている事物をとりあげること。そこから出発すること。はじめに纏向遺跡ありきではなく・・・
(2)全国の全都道府県を公平に、同じ基準でしらべ、比較して結論を出すこと。
この二つの基準から、かけはなれたところで議論をしている。科学的な調査がおこなわれているようにみえて、根本において科学的ではない。議論をあらぬ方向にもって行くものである。
さきの(1)(2)の二つの基準に照らし合わせるとき、考古学的な遺物・遺跡データにもとづく邪馬台国問題についての結論は、もう出ていると思う。
ベイズ統計による確率計算の結果にもとづいて話をすすめるか、あるいは、それを検討することから話をすすめたほうがよいと思う。
かりに、纏向出土の桃の核の年代が、三世紀であるとしても、それは、文献上は、むしろ、『魏志倭人伝』の記述や、卑弥呼や、邪馬台国と結びつく根拠はなんら提出されていない。文献上の根拠をもたない連想にもとづく「解釈」なら、どんな「解釈」も可能となる。たとえ、神話であるにしても、文献上の根拠をもつもののほうをとるべきである。
大国主の神の活躍伝承のある場所から大量の銅鐸出土。
■「邸閣(ていかく)」について
『魏志倭人伝』に、つぎのような文章がある。
「収租賦有邸閣国国有市 交易有無使大倭監之」
この文章は、ふつう、わが国では、つぎのように訳されている。
「租賦(そふ)[租税とかみつぎもの]をおさめる。(それらをおさめるための)邸閣(倉庫)がある。国々に市がある。(たがいの)有無を交易し、大倭(身分の高い倭人)に、これを監(督)させる。」
ところが、現代中国人の学者たちの、標準的な読み方で、句読点を記した中華書局版の『三国志』(中華書局標点本『三国志』)では、原文に、つぎのような句読点が付されている。
「収租賦。有邸閣国、国有市、交易有無、使大倭監之。」
ここでは、二つつづく「国」という字のあいだに、「テン(読点)」がはいっている。
「国」と「国」とのあいだに「テン」をいれると、読み方は、つぎのようになる。
「租賦をおさめる。(それらをおさめるための)邸閣(倉庫)国がある。国に市がある。(たがいの)有無を交易し、大倭(身分の高い倭人)に、これを監(督)させている。」このように読むとき、「邸閣国」って、なんだろう。
ここで「邸閣」といえば、「大邸宅」「大型建物」を連想できそうな感じである。
しかし、「邸閣」はそのような意味ではない。
「邸閣」は、「立派な家」という意味よりも、「倉庫」という意味である、と考えられている。」
九州大学の教授であった東洋史学者の日野開三郎(ひのかいざぶろう)は、論文「邸閣-東夷伝用語解のニ-」(『東洋史学』六、1952年)をあらわし、『三国志』にみえる「邸閣」という語の用例についての調査結果を発表した。(この論文は、佐伯有清編『邪馬台国基本論文集Ⅱ』[創元社、1981年刊]にも、おさめられている。)『魏志倭人伝』以外の十一例について、くわしく検討し、つぎのようなことをあきらかにした。
(1)大規模な軍用倉庫である。
(2)糧穀の貯蔵を第一とするが、戦具や絹その他の資財を収めているものがある。
(3)交通・軍事上の要地、政治・経済の中心地などにおかれている。
後漢末以来の戦乱のため、軍事が優先された結果、軍用倉庫の意味として定着したという。
『日本書紀』にも、「邸閣」の用例はある。
すなわち、「継体天皇紀」の八年三月の条に、つぎのような文がある。
「三月(やよい)に、伴跛(はへ)[任那(みまな)の北部の代表的勢力]、城(さし)を子呑(しとん)・帯沙(たさ)に築(つ)きて、満奚(まんけい)に連(つ)け、烽候(とぶひ)、邸閣(や)を置きて、日本(やまと)に備(そな)ふ。」
岩波書店刊の「日本古典文学大系」の『日本書紀 下』のこの個所には、つぎのような頭注がついている。
『魏志、張既伝『置烽候邸閣』による。トブヒは国境に事変があるとき、煙をたてて通信するノロシ。
烽候はノロシをあげる所。邸閣は兵糧を置く倉庫。」
『日本書紀』の用例も、軍用倉庫である。そして、「邸閣(や)」と読ませている。
「邸閣」は、もともと、糧穀を貯蔵する倉庫であったようである。中国で刊行されている収録語彙数世界最大級の漢語辞典、『漢語大詞典』には、「邸閣」について、つぎのように記されている(原文は、中国文)。
「古代の官府が、根食などの物資をたくわえておくために設置した倉庫。」
ところで、わが国の古代において、「屯倉(みやけ)」ということばがあった。「屯倉」は、本来、大和朝廷の直轄領から収穫した稲米の蓄積をする倉庫の意味であった。それが転じて、朝廷の直轄領そのものをさすようになった。
「屯倉(みやけ)」は、「三宅」「官家」「屯家」「屯宅」「三毛(みけ)」などとも書かれる。福岡県の「三宅(みやけ)[三毛(みけ)]郡」をはじめ、茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、奈良県、福岡県、熊本県、宮崎県などの「三宅郷」、神奈川県、島根県の「御宅郷」など、「屯倉」にちなむとみられる地名は、各地にのこる。
「邸閣国」は、あるいは、そのようなものをさすか。
吉野ヶ里遺跡のばあい、外濠の西外側に、大規模な高床式倉庫群と考えられる大きな掘立柱建物跡が、十八棟検出されている。わが国最大級の弥生時代の高床倉庫群といえる。これまで発掘された環濠集落の例では、倉庫は、濠の内側に一~二棟あるのがふつうであった。
今回の纏向遺跡出土の大型建物は祭祀用の建物のイメージがあり、軍用倉庫的なイメージはとぼしいようにみえる。
あるいは市(いち)関係の建物?[肆(し)(店)や庁]
(下図はクリックすると大きくなります)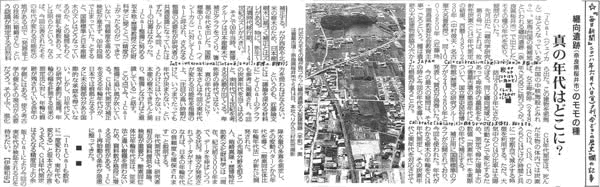
箸墓古墳の築造年代の推定
白石太一郎氏----- 3世紀中葉すぎ
寺沢薫氏--------- 270年~300年
川西宏幸氏------- ~300年
関川尚功氏------- 4世紀中頃前後
土器には、年代が記されていない。畿内説を説く考古学者たちが、考古学的に確実な年代論的根拠を提出しているとは、とても思えない。
マスコミ報道などではしばしば年代が確定しているかのように報じられるが、その根拠をたずねると根拠のよくわからないものがほとんどである。







