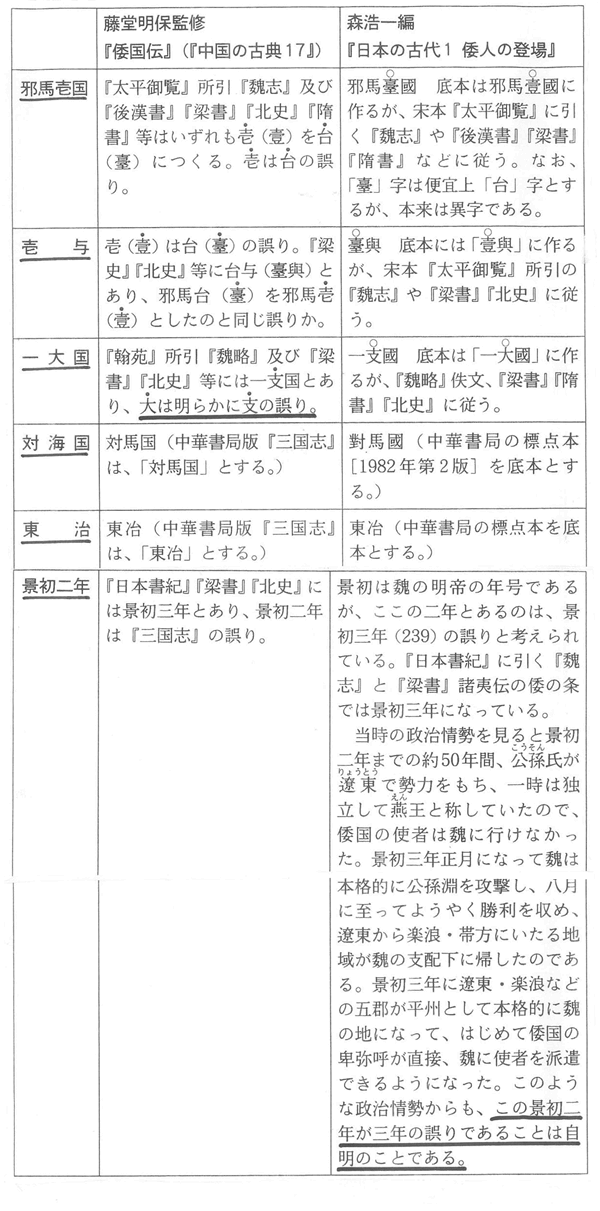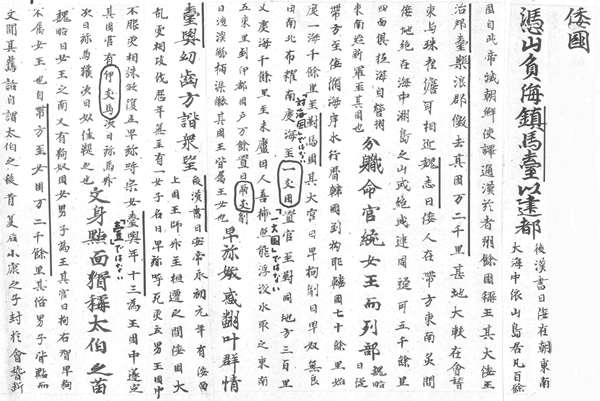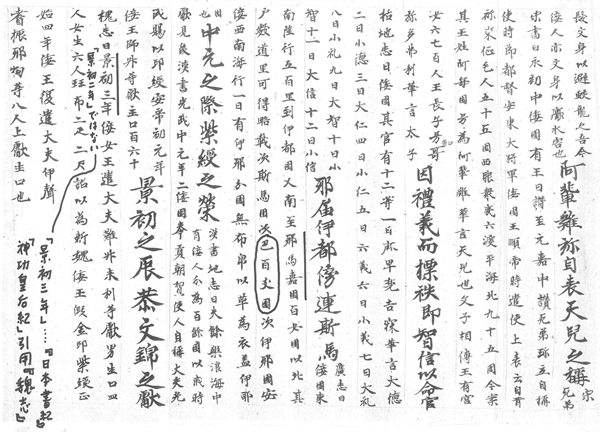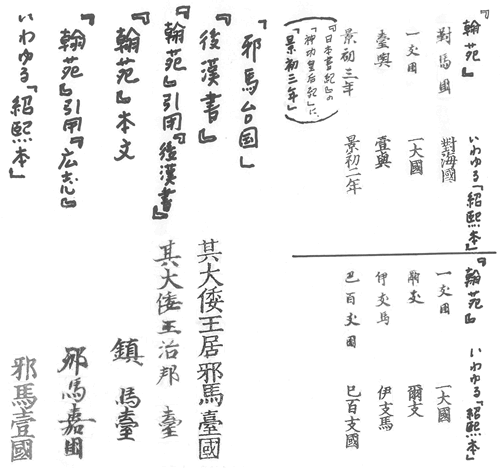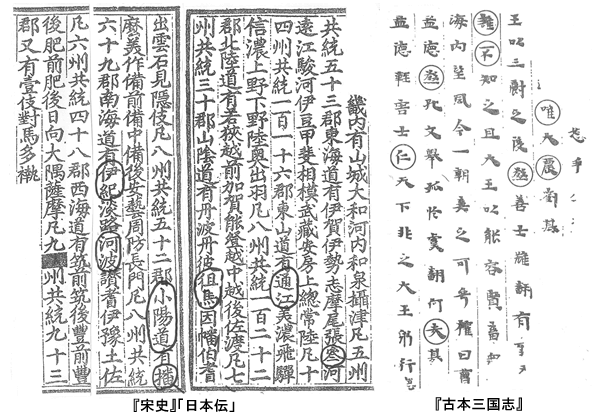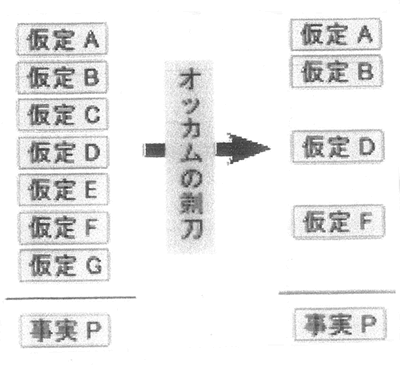■古田武彦氏の『邪馬台〈臺〉国』説
古田武彦説の根拠はいわゆる『紹煕本』とされる12世紀の宋の版本の『三国志』『魏志倭人伝』には「邪馬台〈臺〉国」が「邪馬壹(壱)国」と書かれており、この版本(現行刊本)の記述が正しいとすることから来ている。
中華人民共和国の汪向栄氏は、わが国で翻訳の刊行された『中国人学者の研究 邪馬台国』(風涛社刊、1983年)のなかで述べる。
古田武彦氏の「邪馬一国説(女王国の名は、『邪馬台〈臺〉国』ではなく、『邪馬一〈壹〉国』であるとする説)」は、「魯魚の誤り(似た字の書き誤り、写し誤り)に信をおく、妄説にすぎない」と。
台湾の国立台湾海洋学院大学教授の謝銘仁博士は、その著『邪馬台国 中国人はこう読む』(立風書/房刊、1983年)のなかで、帯方郡から狗邪韓国への七千余里は、水行ののち朝鮮半島内を陸行したものと解する古田説は、「日本流の読み方であって、成立する余地がない」とされる。また、「水行 十日、陸行一月」を、帯方郡から邪馬台国までの所要日数とする古田氏の読み方を、極端な読み方であって、問題にならないことを述べておられる。
謝銘仁博士は、中国で、国文学(中国文学)を専攻された方である。中国には、長い訓詁(注:古いことばの意味を解釈すること)の学の伝統がある。博士は、その著の執筆にさきだち、疑問とする点については、台湾の多くの訓詁学者、歴史学者、中国文学者の門をたたき、徹底的な議論をしておられる。
謝銘仁博士は、また述べる。
「古田武彦氏や山田宗睦氏などは、『使大倭』の三字を一種の官職名と見なしている。奇抜すぎた解釈ではなかろうか。」
「古田武彦氏はその著『邪馬一国への道標』で『一大率』は『一大軍団』であると解釈している。あまりにも文脈を無視し、ロジックに欠けた所論といえよう。」
古田武彦氏の主要な論点の、ほとんどが成立しがたいことについては、台湾の中国人学者、張明澄氏も、「一中国人の見た邪馬台国論争」(『季刊邪馬台国』11号から連載)のなかで、言葉鋭く述べている。
「論理と方法の問題がしっかりしていないため、もう正しさでは勝負は決まらず、悪乗りした方にかならず軍配が上がり、今のところ、その番付けは、
古田武彦先生が横綱
松本清張先生が大関
原田大六先生が関脇
宮崎康平先生は小結
というようになり、プロの学者はすべて十両以下である。もちろん、これはマス・コミ悪乗りの番付けであり、正しさによる番付けとはまったく関係ない。」
張明澄氏の、『誤訳・愚訳-漢文の読めない漢学者たち-』(久保書店刊)のなかに、次のような話がのっている。
ある生半可な日本語の知識をもつ中国人が、日本語の「泥棒」を「セメントで作った柱」と訳した。
中国語で、セメントを「水泥」といい、小さな柱を棒というからである。
このばあい、もし、その中国人が、自信が強く、次のように開きなおったらどうであろう。
「『泥棒』を、『セメントの柱』と理解してどこが悪い。私は、『泥』を、『セメント』と訳すのを、『セメントの論理』と名づける。こんな、子どもでもわかる明々白々の論理が、誤りだというのなら、その根拠を、明確、厳密に示すべきだ。批判者は、論理のイロハをまちかっている。」
日本人は、ただ、失笑するのみであろう。「セメントの論理」がどうであれ、日本語では、「泥棒」は、「セメントの柱」の意味では用いないからである。
古田氏の「論理」は、ほとんどすべて、この「セメントの論理」のたぐいのものである。しかし、古田氏は、自信にあふれて述べる。
「なっとくするのは、たかだか日本人だけ。学問じゃない。」
「従来の日本古代史学、これも『夜郎自大(自分の力量を知らないで、仲間の中で、幅を利かすもののこと。むかし、夜郎という名の夷(えびす)が、漢の強大なことを知らずに、自らの勢力をほこったことから)の歴史学』、世界の心ある人々から、そのように笑われなければ幸いだ。」
「世界の古代史の中の数多くの王朝の歴史を見、その真実の歴史を知ってきた、日本以外の人間たちの健全な常識は、決してこれを認めることがないのであろう。」
だが、じつは、日本の古代史学を、世界の心ある人々からの、笑いものにつくりかえつつあるのは、ほかならぬ、古田武彦氏自身である。古田武彦氏の漢文の読み方が、本場の中国の人々の「笑いもの」になっていることは、さきにみたとおりである。
中国人学者たちの、筆をそろえての批判と、「なっとくするのは、たかだが日本人だけ」という古田氏の強引な「自信」との落差の大きさに唖然とするのは、私だけであろうか。「夜郎自大」など、本来、みずからがこうむるべき批判の矢を、ことごとく相手になげつける。
古田説をみとめる「日本人以外の人」「世界の心ある人々」「健全な常識」をもつ「日本人以外の人間たち」の例を具体的に、この外国人がこのような形でのべている。という形で、示してみてほしい。
古田氏には、日本の現代の学者たちが、「人間の平明な理性」に従っていないのであって、後代の学者、あるいは、外国の学者からみたら、みずからの説の正しさは、「明白きわまりない」という、強い思いこみがある。そこで、次のような表現もでてくる。
「外国の考古学者が聞いたら、やれやれと”舌打ち”したくなるかもしれない。」
しかし、外国から見ても、古田氏の議論のほとんどは、おかしいのである。
古田氏は、『倭人も太平洋を渡った』として、縄文時代に倭人が、アメリカ大陸のエクアドルにわたっていたと主張する。その「影響が疑えない」とする。
これについても、日本の外からみて、意見を述べておられる人がいる。カリフォルニア大学教授の青木晴夫氏は『マヤ文明の謎』(講談社現代新書)の中で、次のように記している。
「言語以外の類似を求めていくつかのつながりを見出す試みがなされた。マヤではないがエクアドルの土器と日本の縄文土器の模様が似ているといった研究がその例である。しかし結論を出す前に、ダニューブ川地方や、アメリカ東海岸のフロリダからも同じような土器が出ているのをどう解釈するか、さらにあまり道具のない時にロープで模様をつけることがそんなに珍しいことなのか、といった基本的なことを考えてみる必要があろう。
今のところ特定のユーラシア文明とのつながりを、決定的に証明する資料はないというべきであろう。」
青木氏は、おだやかな表現をしておられるが、青木氏の「やれやれという”舌打ち”」の音が、きこえてこないであろうか。
私には、アメリカインディアンの言語と文化の研究において、令名の高い青木晴夫氏が、「平明な理性」をもたない方だとは思えない。
なお、この問題については、考古学者の佐原真氏が、『東アジアの古代文化 創刊50号記念特大号』(1987年、早春号。大和書房刊)のなかに、「エクアドルには渡らなかった縄文土器」という一文を書いておられる。
佐原真氏は述べる。
「(縄文土器が太平洋を渡ってエクアドルの土器になったとする説には、)巧妙なからくりがある。」
「一種の詐欺行為ではあるまいか。」
「エクアドル土器の完成品の図をみると、深い器(うつわ)、つまり口の直径をしのぐ深さをもつ深鉢(ふかばち)は僅少、むしろ、口径と深さが同じ程度、あるいは、口径が深さを上回る浅い器の方がずっと多いのだ。これは、縄文土器が、もちろん出水(いずみ)式もふくめて、深鉢を主体とすることと大きく違っている。破片では似ていても、完全な形では違うことになり、土器の本質に係わる決定的な違いというべきである。」
「ひと言でいって学問以前。問題外の外。批判の対象にもなりえない。」
「日本の考古学会がほとんどこれにとりあわなかったのも、皆、こんな馬鹿らしい話にかかわりあうほど暇でないからである。」
「(古田武彦氏の)『倭人も太平洋を渡った』にいたっては、かなりの無理が目立っている。」
いま一つ、例をあげよう。
従来、『魏志倭人伝』の訳注は、東洋史家によって行なわれることが多かった。しかし、最近、中国語学の専門家による訳注が、いくつかみられるようになってきた。中国語学の専門家の訳注は、かなりしっかりした文献学的検討の上で行なわれている。
そこでは、『魏志倭人伝』の現行刊本に、「邪馬壹(壱)国」「壹(壱)与」「一大(支)国」「対馬(海)国」「東治(冶)」「景初二(三)年」と記されているものについて、どのような理解を示されているのであろうか。
いま、次の二つの文献をとりあげてみる。
①藤堂明保監修『倭国伝』(『中国の古典17』、学習研究社、昭和60年10月15日刊)
②森浩一編『日本の古代1 倭人の登場』(杉本憲司、森博達(ひろみち)訳注、中央公論社、昭和60年11月10日刊)
藤堂明保氏(1915~1980)は、東京大学教授、早大教授などを歴任され、『漢字語源辞典』(学燈社)、『学研漢和大字典』(学習研究社)などの著書のある、中国語学の第一人者である。昭和60年2月になくなられた。
また、森浩一氏編の『日本の古代1』の、「『魏志』倭人伝を通読する」の章は、大阪府立大学教授の杉本憲司氏(1931~)と、大阪外国語大学教授の森博達氏(1941~)によって執筆されている。
杉本憲司氏は、中国古代史、考古学専攻の方であるが、森博達氏は、中国語学専攻の方である。とくに、漢字音からみた、上代日本の万葉仮名についての、シャープで、かつ、すぐれた論考を発表されている。
さきの、藤堂明保氏の『倭国伝』と森浩一氏編の『日本の古代1』の二つの本における「邪馬壱国」「壱与」「一大国」「対海国」「東治」「景初二年」等についての記述をまとめると。下表のようになる。 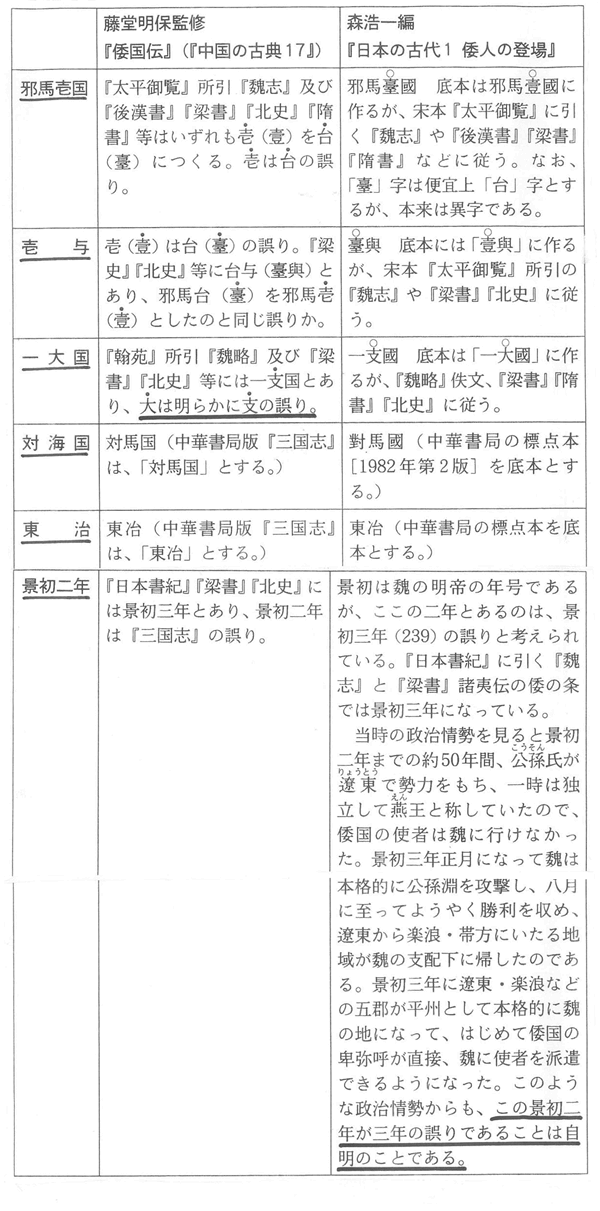
古田武彦氏は、1971年に『「邪馬台国」はなかった』を刊行以来40年間以上、実に熱心に「邪馬台国」ではなく「邪馬壱国」が正しいとする説を主張しつづけてこられた。
また、古田武彦氏は、「壱与」「一大国」「対海国」「東治」「景初二年」などが正しいとする。
藤堂明保氏、杉本憲司氏、森博達氏は、古田武彦氏の主張などは、当然ご存知のはずである。そして、上の表に示したように、「邪馬壱国」「壱与」「一大国」「対海国」「東治」「景初二年」などについての古田武彦氏の説のどれ一つとしてとるべきではないと判断されている。そして諸本の比較により、これらは、「邪馬台国」「台与」「一支国」「対馬国」「東冶」「景初三年」が正しいとされている。
とくに、杉本憲司氏、森博達氏は、『日本の古代1』のなかで、はっきりと、次のようにも、述べておられる。
「こと古典の解読では、先人の読み方に異をはさむに急いで、自分の先入観にまどわされた読み方をすることが多くみられる。」
ここに述べられている「先人の読み方に異をはさむに急で、自分の先入観にまどわされた読み方」をしている人の筆頭が、だれであるかは、多くの人にとって、明らかである。
なお、「対海国」については、『三国志』の「いわゆる紹煕刊本」には、「対海国」とあるが、「いわゆる紹興刊本」には、「対馬国」とある。
古田武彦氏は、「いわゆる紹煕刊本」を、ほんとうに、南宋の紹煕年間(1190~1194)に刊行されたものとうけとられ、これこそ現在求める最良の刊本とされた。そして、「対馬国」ではなく、「対海国」が正しいとされた。
しかし、わが国の中国書誌学の第一人者である、慶応大学の尾崎康教授は、次のように述べられる。
古田武彦氏が、「紹煕本」とされたものは、紹煕年間に刊行されたものではなく、刊行の時期は、南宋中期に下り、「『紹煕本』と称するのは、不見識もはなはだしいものであり、福州建安での「坊刻本」(民間で刊行された本)で、テキストとしては、あまり善い本ではない。」と。そして、「南宋中期建刊本」(注:建安で刊行された本)と呼ぶ方が妥当であるとしておられる。
尾崎康教授は記される。
「(いわゆる『紹煕本』は、)木記や刊記が存在せず、校正者の氏名もみえないから、刊刻の事情を詳らかにしない。ただ、かねてからなぜか『紹煕本』と称されてきたがその根拠はまったくなく、光宗(紹煕1190~1194)(注:1189?~1194)の次の寧宗の嫌名(天子の名前と紛らわしい名前)の『郭廓』字を欠画するから、それ(『紹煕本』と称すること)が誤りであることは明白である。」
「これら建安の坊刻本が営利出版であり、北宋初に統一国家・文治主義の権威にかけて、厳密な校正を施し、写本を初めて刊刻しておこなった官刻本に較(くら)べて、本文が著しく劣ることは、周知の事実である。」
そして、「いわゆる紹興本」は、「倭人伝」を含む刊本としては、現存最古のもので、南宋初期の刊本であることは、ほぼ確実であり、「いわゆる紹興本」は、「いわゆる紹照本」よりも善本なのではないか、とされている。(以上、『季刊邪馬台国』18号~24号)
このような考察を読むと、藤堂明保氏の『倭人伝』や森浩一氏の『日本の古代1』が、古田武彦氏の「いわゆる紹煕本」にもとづく「対海国」説を、一顧だにしておられない理由が明白である。(現代中国人学者たちが判断し、校訂した標準的なテキストである標点本『三国志』〔中華書局版〕では、「対海国」と「東治」については、誤りである明白な根拠をもつものとして、「対馬国」「東冶」として印刷されている。ここでも、海外の学者なら自説をみとめるはずであるとする古田氏の「思いこみ」は、否定されている。)
また、さきの尾崎康教授の述べておられることと、古田武彦氏の、「いわゆる紹煕本」こそ、「現存最良の刊本だったのである。」(『「邪馬台国」はなかった』)などの記述とを読みくらべるならば、古田武彦氏が、いかにあてにならないことを述べておられるかも明らかである。
東京大学の日本史家、井上光貞氏は、『論争邪馬台国』(1980年、平凡社刊)の中で、松本清張氏の問いに答え、次のように述べておられる。
「(邪馬壱国が本当であるというのは)、ぼくは結論的には、古田さんの思い過しであるという結論です。その理由は、古田さんの論拠の根底に原文主義がある、原文通りに読めというんです。ところが問題は、原文とは何ぞやということであります。原文というのは、『魏志』は三世紀に書かれたものですが、そのときの原文、これはないのであります。だから原文原文といっているのは非常に古い版本ということである。しかし古い版本は原文ではないのであります。校訂ということを学者はやるわけであります。おそらく古文をなさる方もいらっしゃるだろうと思いますが、それはいろんな写本やなんかから、元のそれこそ原物はどうであったかということを考えるために、いろんな本を校合して、元を当てていくわけです。これが原文に忠実なのでありまして、たまたまあった版本だの、後の写本に忠実であるということは、原文に忠実ということとは違うんだということですね。
これは非常に基本的なことなのであります。ところが古田さんはそこのところが何かちょっと違っているんじゃないか。これは学問の態度の問題であります。これだけいえばもう私はほとんど何にもいう必要はないのであります。」
「たとえば『三国志』は三世紀の末頃に出来て……これ、末のいつであるかということは問題だけども、まあ三世紀の末だろうと思われる。一方、いちばん古い版本は、……南宋の本で十二世紀なんですね。その間、本としては九世紀の隔(へだ)たりを持ってる。本としてはその間に今日のところ何もないわけです。写本はもとよりのこと、版本もそれだけの距離を持ってるわけです。ところがその間にいくつも逸文というものがある。それを途中で読んだ人の記録というのがあるわけです。
そういう意味からいって、途中で読んだ人の記録を見ると、やはり大きいのは『後漢書』だと思います。『後漢書』も、もちろん原文が残っているわけではないのですけれども、……『後漢書』のあの記事は明らかに『三国志』を見ているわけですけれども、そこにはちゃんと『邪馬台国』『台』と書いている。『後漢書』が出来だのは五世紀でありますが、それが『台』と書いているとすると、『後漢書』の編者のみた『三国志』の『魏志』の『倭人伝』には『台』と書いてあったととるのがすなおな見方です。」
■より古い『三国志』からの写本は、卑弥呼宗女の名を臺與(台与)と記す
十二世紀に成立した現存版本の『三国志』「魏志倭人伝」中に「壹(壱)」とある字が、それ以前のテキストにおいては、「臺(台)」であったことを示す事例をあげる。
現在、福岡県筑紫郡太宰府町、太宰府天満宮に伝来する張楚金撰、雍公叡注の『翰苑』がある(下記文章複写参昭)。
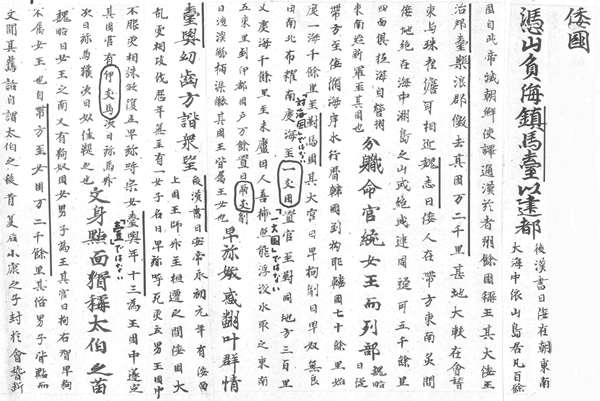
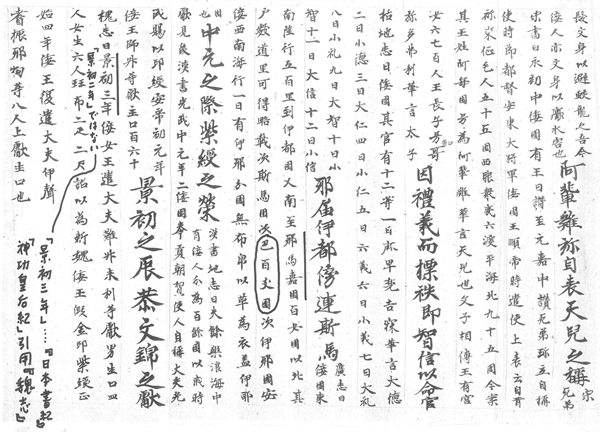
これは平安初期九世紀に書写され、そのまま今日に伝来したものである。張楚金は、唐代の人で、高宗(649~683)につかえた人である。また、雍公叡の註は、唐の太和年間(827~835)以前の成立といわれている。さて、その『翰苑』の中に、つぎのような文章がある。
「後漢書に曰く、安帝の永初元年に、倭面上国王師升(ししょう)至ることあり。桓霊の間、倭国大いに乱る。
更(かわるがわる)に相攻め伐ちて、年を歴るも主無し。一女子有り、名を卑弥呼(ひみこ)と曰う。死して更に男王を立つ。国中服せず。相誅殺す。復た卑弥呼の宗女臺與(台与)、年十三なるを立てて王と為す。国中遂に定まる。其の国の官に、伊支馬(いきめ)有り。次を弥馬升(みめす)と曰い、次を弥馬獲(みめか)と曰い、次を奴佳鞮(ぬかで)と曰う。」(竹内理三校訂・解説『翰苑』〔吉川弘文館刊〕による。傍線は安本。)
この『翰苑』では、正文を大きく記し、注を正文の下に二行にして小さく記している。
ここの引用文は、注の部分であるから、雍公叡の記したものである。
さて、この引用文は、「後漢書に曰く、」で始っている。しかし、傍線の部分は、『後漢書』には、ない。『三国志』の「魏志倭人伝」にある。そのことは、原文を対照してみればすぐわかる。
すなわち、つぎのとおりである。
『翰苑』原文
「更立男王国中不服更相誅殺復立卑弥呼宗女臺與年十三為王国中遂定其国官有伊支馬次曰弥馬升次曰弥馬獲次曰奴佳鞮」
「魏志倭人伝」
「更立男王国中不服更相誅殺……復立卑弥呼宗女壹與年十三為王国中遂定」「官有伊支馬次曰弥馬升次曰弥馬獲支次曰奴佳鞮」
さきの引用文は、はじめ『後漢書』の文を引き、後半においては、「魏志倭人伝」の文を引いている。
そして、『翰苑』の文をよく見られよ。そこでは、現存版本の「魏志倭人伝」には、「壹與(壱与)」とある卑弥呼の宗女の名が、「臺與(台与)」と記されている!
しかも、そればかりではない。雍公叡の記した注ではなく、張楚金の正文の方も、この宗女の名を、「臺與(台与)」と明記しているのである。『後漢書』には、もともと、宗女「臺與(台与)」あるいは「壹與(壱与)」の名は、一切見えない。
したがって、雍公叡の注や、張楚金の正文中の「臺與(台与)」の名が、『後漢書』から来たのではないことは、明らかである。『後漢書』によって、『三国志』の中の字が改定されたという「『後漢書』主義」によっては、説明がつかない。では、どこから来たか。当然、雍公叡が引用しているが如く、七世紀の雍公叡や九世紀の張楚金のそれぞれが目にした『三国志』「魏志倭人伝」から来たのである。
張楚金や雍公叡には、彼らが目にした『三国志』に「壹與(壱与)」とあったものを、とくに「臺與(台与)」と改変しなければならない理由があったとは思えない。
現存する『三国志』の版本の最古のものは、十二世紀のものにすぎない。南宋の紹興(しょうこう)年間(1131から1162まで)に印刷された紹興本がそれである。
太宰府天満宮伝来の『翰苑』の書写の時期は、紹興本、いわゆる紹煕本の刊行の時期より、およそ、三世紀は古い。
そして、『翰苑』引用の『三国志』「魏志倭人伝」は、卑弥呼の宗女の名を、壹與(壱与)ではなく、「臺與(台与)」と記しているのである。
古田氏は、「邪馬壹(壱)国」とともに、卑弥呼の宗女の名も、現存の版本通り、「壹與(壱与)」が正しいとされた。古田氏の主張の、重要な一角が、ここでも、破れている 。
竹内理三校訂解説の『翰苑』(吉川弘文館、1977年刊)[注:竹内理三・・・・東京大学史料編纂所所長。主要編著に『寧楽(なら)遺文』『平安遺文』]
・竹内理三氏の『翰苑』についての「解説」
「「翰苑」は、現在、福岡県筑紫郡太宰府町(現在の太宰府市)、太宰府天満宮に伝来する、天下の孤本である。その書写の年代は、平安初期、即ち九世紀を下らず、縦九寸一分の楮紙に墨界を施して、一紙に二十二行乃至二十三行、一行に十六~十七字詰に墨書する。
尤も、本文が少なく、割註が多く、割註の細字は一行二十二~二十三字詰である。全長五十二尺三寸五分。後に掲げる内藤湖南博士が解題に指摘される如く、終りの方の「両越」の条に、「西域」の記事が継続していて、この間に若干の脱文かある。この連続の間に紙の継目はなく、前段の註文に直ちに引きつづいているので、本巻そのものの紙片の脱落ではなく、本巻のもととなった原本にすでに脱落があったか、或いは本巻書写の者が書写の際に脱落したのか、その何れかであろう。その他の部分については、脱落はみとめられない。従って本書は、九世紀に書写されたそのまま今日に伝来したものである。現在巻子仕立てであるのは、本来の姿を存したものであろう。」
■「対馬国」「一支国」「臺与」「景初三年」
古田氏はのべる。(『邪馬台国はなかった』)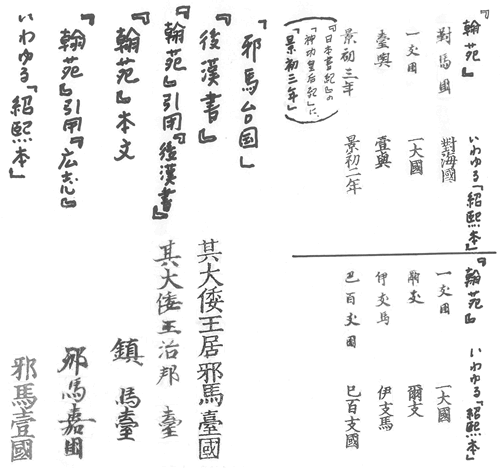
「このように考えてくると、「対馬国」「一支国」という「後代改定」には、史料批判上の根拠がなく、逆に、原文こそ「三世紀に実在した中国側地名」にもとづいて記載された、正確な文面だったことが判明するのである。」
右図の右側ように、『翰苑』と「いわゆる紹煕本」との表記を比較すると、「対馬国と対海国」「一支国と一大国」「臺与と臺与」「景初三年と景初二年」などのように異なっている。
また、右図の左側ように、「邪馬台国」について、『後漢書』は「邪馬臺国」と表記し、『翰苑』も誤植があると言われてるが、引用で「臺」と表記しているものが多くある。それに対し「いわゆる紹煕本」では「邪馬臺国」と表記している。
・『古本三国志』
『古本三国志』は新疆の鄯善出土の古写本で、四世紀西晋代のものと推定される。現行刊本とくらべると、およそ千二百字中五十七ヵ所の異同がある。
○印をつけたのが、『古本三国志』と現行刊本との異同のある個所。[下図の右側の丸印]
このように、『三国志』でも古い写本と現行の刊本と比べても違いが多い。
・『宋史』「日本伝」
1345年完成の『宋史』「日本伝」[下図の左側の丸で囲ったもの]でも地名は「伊紀」→「紀伊」、「徂馬」→「但馬」、「小陽道」→「山陽道」、「通江」→「近江」のように、間違いが多いことが分かる。
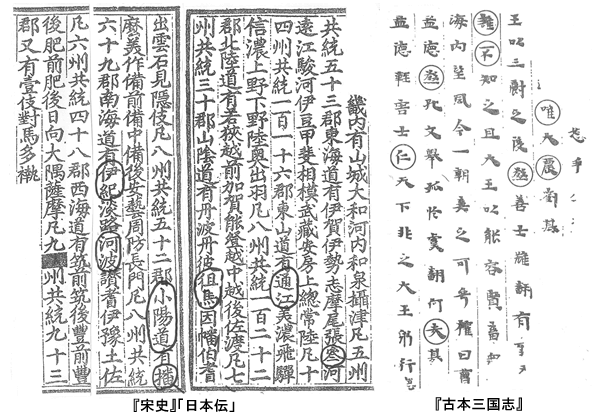
このように『三国志』でも古い写本と現行版本と違い多いことが分かる。また、中国の14世紀の文献でも他国の地名の記述となると間違いが多く、中国の歴史書で示す中国から見たら外国の地名は間違いが多いと考えた方が良い。
古田氏が言う原文は現行版本で、「いわゆる紹煕本」である。「対馬国」「一支国」の表記が「後代改定」としているが、「いわゆる紹煕本」の「対海国」「一大国」の表記の方が「後代改定」である。
■「臺」は、「天子の宮殿及び天子の直属の中央政庁」の意味で使うから「神聖至高の文字」であり、したがって、東夷の女王国の名に用いるはずはない。
古田氏の調査にもれているものが四例ある。その四つの用語例は、いずれも、古田氏の「邪馬壹国」説への、反対根拠となるものである。
その四例のうちの一つに、「築台」がある。この例は、次のような文のなかであらわれる。
「使於緜竹築臺以為京観、用彰戦功」[緜竹において「台」を築き、京観を作り、戦功の記念とした](巻二十八「王・母丘・諸葛・鄧・鍾伝」)[鄧艾(とうがい)伝]
三木太郎氏は、この例について、次のように述べる。
「『台を築きて以て京観と為さしめ』というのは、”武功を示すために(敵の)戦死者の死骸を積んだ上に土を高く封った塚”ということである。ここでの『台』は『京観』のことである。つまり”塚”なのだ。古田氏は『台』一字で天子を指すから、『台』は『神聖至高の文字』だといわれた。
ならばこの例を以て、『台』、一字で”塚”をさすから、『台』は『卑字』である、といえば、どうなるのか。古田氏は表中に、なぜこの用例を漏らされたのか。もし古田氏がこの例に早くきづいておられたなら、古田氏は『台』に、『神聖至高の文字』などという誤った概念を与える無駄な努力をされずにすんだであろうことを思うと、まことに残念に思う。」
また、「臺(台)」の字が、「神聖至高の文字」などではなかったことを示す事例としては、「築台」のほかに、「臺獄」もある。
これについては、白崎昭一郎氏が、『東アジアの中の邪馬臺国』(芙蓉書房、1978年7月刊)の中で、次のように述べておられる。
「第二に、古田氏の看過された『臺獄』の例がある。--------臺獄とは、御史臺に所属する獄のことであるから、天子直属の官庁といえないこともない(しかしそういえば中央政府の官庁は大抵そうなってしまうだろう)だが臺獄の語感は、天子の尊厳性と結びつきそうもない。臺が天子専用の貴字で、臺獄が天子直属の官庁というならば、臺獄なる言葉は当然別の字句を以て変えられたであろう。臺獄という語の存在は、臺がそれ程特別の貴字ではなかったことを語っている。
古田氏は、『「邪馬台国」はなかった』の中で、「三国時代、魏は、劉備や孫権を蜀賊、呉賊と称した。正統の天子たる魏朝に従わないからである。『三国志』もこの立場に立っている」と述べている。つまり、蜀の劉備や呉の孫権は、天子として認められていなかった、という。ところで、『三国志』をしらべてみると、蜀の県名としての、「臺登」がでてくる。「蜀賊」。の地の地名に用いてよい「臺」の字が、なぜ、東夷ではあるにしても、「親魏倭王」の女王国の名には、用いられえないのであろう。古田武彦氏は、『邪馬一国の挑戦』の中でいう。
「わざわざ『天子』を指す神聖な文字を使用するとは、西晋朝の史官であった陳寿としてできることではない。そんなことをしたら、最大の不敬としてとがめられよう。首が飛ぼう。第一そんな危険を冒してまでこの至上神聖の文字をわざわざ使わねばならぬ”義理”がどこにあろう。」
古田武彦氏は、みずからの空想的、思いつき的な説に酔って、ここまで書ける方なのである。しかし、陳寿は、「蜀賊」の地の地名に、「臺」を用いても、「敵の死体を積み重ねて築いた塚」の意味で「臺」を用いても、不敬としてとがめられもしなかったし、首も飛ばなかった。なぜか。
「臺」の字は、至上神聖の文字でもなんでもない、ただのふつうの文字だったからである。
627年に成立した『梁書』においては、「臺に還りて高祖に礼拝す」「臺に送る」などの文章がある。ここでも、「臺」が、「天子の宮殿及び天子の直属の中央政庁」の意味に用いられている。しかるに、『梁書』においては、女王国の名を「祁(き)馬臺国」と記している。「臺」の字を用いている。
古田氏の議論の本質は、「臺」は、「天子の宮殿及び天子の直属の中央政庁」の意味で使うから「神聖至高の文字」であり、したがって、東夷の女王国の名に用いるはずはないというものであった。
したがって、『梁書』で「臺」の字が、「天子の宮殿及び天子の直属の中央政庁」の意味で使われ、しかも、女王国の名にも用いられている例を示せば、古田氏の「神聖至高の文字論」の根拠は崩れてしまう。
私もまた、井上光貞氏、三木太郎氏、山尾幸久氏などの見解に賛同するものである。
私の考えをまとめると、次のようになる。
(1)三世紀『三国志』原本をみた人はだれもいない。三世紀の原本は、存在していないのである。
(2)現存『三国志』の版本は、十二世紀以後のものである。『三国志』の成立から、十二世紀まで、およそ、九百年の歳月が流れている。
(3)十一世紀よりまえの史料で、女王国の名を、「邪馬壹(壱)国」と記すものは、一切ない。
(4)福岡県太宰府市、太宰府天満宮に伝来する『翰苑』の九世紀写本は、卑弥呼の宗女の名を「壹與(壱与)」ではなく、「臺與(台与)」と記し、その都を記すのに、「馬臺(台)」と、「臺(台)」の字を用いている。これは、十二世紀以後の版本と異なっている。
(5)いま、三世紀の女王国名は「邪馬臺(台)国」宗女の名は、「臺与(台与)」であったと仮定してみる。そして、九世紀~十一世紀の間に、誤写、または、誤刻がおきたのだと、考えてみる。現行『三国志』版本に、「邪馬壹(壱)国」「壹與(壱与)」とあるのは、誤写、または、誤刻によって生じたと考えてみる。
(6)このように考えると、『後漢書』『梁書』『北史』『隋書』『通典』『翰苑』などに「臺(台)」の字が用いられている事実を、古田説よりも、はるかに、簡明に説明できる。(古田氏は、『後漢書』などに、「臺」の字があらわれる理由を、つぎのように説明する。すなわち、五世紀になり、南北朝の対立、五胡十六国の出現という時代になって、「臺(台)」の字は、各国の都の名に用いられるようになり、「臺」の字の性質は、変わってきた。したがって、五世紀になって成立した『後漢書』に、「邪馬臺国」が出現してもふしぎはない------。しかし、この古田説では、三世紀に「邪馬壹国」であった女王国の名を、『後漢書』が、とくに、「邪馬臺国」に改変しなければならなかった理由が、十分に説明されていない。三世紀の女王国の名が「邪馬壹国」であるならば、『後漢書』も、それを記すのに、「邪馬壹国」と記すのが、自然ではないか。)
(7)(a)さまざまな現象・事実がある。(b)いま、ある仮説を真とすれば、そのさまざまな現象・事実がうまく説明される。(c)それゆえ、その仮説を真とみる理由がある。以上は、ドイツのヒルベルトの説いた公理論(「公理論」については、拙著『「邪馬壹国」はなかった』参照)以後、アメリカの
C・S・パース、ノーウッド・R・ハンスンなどによって発展させられ、現代の科学方法論の主流となりつつある見解である。
私は、歴史も、このような方法によって、探究されるべきであると考える。仮説は、諸事実を、できるだけ単純に説明できるものであることが望ましい。これは、科学の指導原理のひとつである。同一のことがらを説明するのに、仮説Aによっても説明でき、仮説Bによっても説明できるとする。しかし、仮説Aの方が、単純であるならば、仮説Aの方がすぐれているということができ、仮説Aを採択すべきであるといえる。天体が、きわめて複雑な運動をしていると考えれば、天動説も、なりたちえないわけではない。天動説よりも、地動説がえらばれるのは、説明が、いちじるしく簡易なものとなるからである。逆に、仮説の数をふやし、議論をいくら複雑にしてもよいのであれば、「ナポレオンは女性であった」とすることも、「クレオパトラは男であった」とすることも、自在となる。古田氏の「邪馬壹(壱)国」説は、「誤写・誤刻」説にくらべ、説明の簡明さにおいて、まさるところがあるとは、思えない。
■オッカムの剃刀 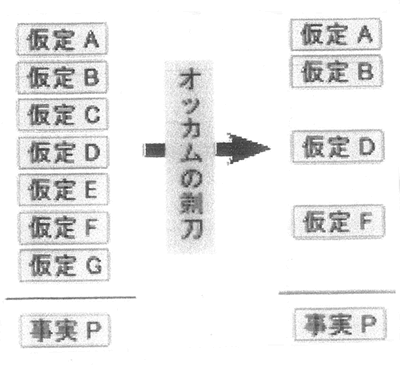
オッカムの剃刀(オッカムのかみそり、英: Occam's razor、Ockham's razor)とは、「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とする指針。
Entities should not be multiplied beyond necessity.
右の図は三浦俊彦氏が描いたオッカムの剃刀の説明図。三浦氏はオッカムの剃刀について「ある事実Pを同様に説明できるのであれば仮説の数[または措定(そてい)される実体の数]は少ないほうが良い」とするものだと説明した。
古田氏の説明はややこしすぎる。このオッカムの剃刀から分かるように、議論を複雑にすれば、どのようにも言えるようになる。
「邪馬台〈臺〉国」、「邪馬壹(壱)国」議論は誤植であったと単純に考えればすむことである。
■古田氏の統計的推論は、まったくの誤りである
古田氏の「邪馬壹(壱)国」論には、つぎの二つの柱があった。
①臺(台)の字は、神聖至高の文字論。
②臺(台)と壹(壱)との統計論。
②の「臺と壹との統計論」をとりあげる。
古田氏は、いわゆる紹煕(しょうき)本『三国志』のすべての「壹」および「臺」の字をぬきだして調査された。
そして、つぎのようなことを示した。
(1)『三国志』全体の中に、「壹」は86個、「臺」は56個、合計142個あらわれる。
(2)86例の「壹」のうち、『魏志倭人紜』中の問題になっている「邪馬壹国」(1個)と卑弥呼のあとをついた女王「壹与」(3個)とを除いた82例において、「臺」の誤記と認識されるものは、一例もない。
(3)56個の「臺」のうち、「壹」の誤記と認識されるものは一例もない。
このような調査の結果にもとづき、古田氏は、魏に使をだした女王国の名が、「邪馬壹国」であったとするのは、「壹と臺は字形が似ているからあやまったのであろう」という、まったく根拠のない憶測にもとづくもので、「邪馬壹国」にこそしたがうべきであるとする。
しかし、このような議論は、現代統計学の立場からは、まったくの誤りといえるものである。「壹」と「臺」とのどちらが、三世紀原本の姿を伝えているかについて、なんらの情報ももたらさない。統計学的には無意味な調査である。
そのことは、誤写や誤刻の性質を考えれば、容易にわかることである。例をあげよう。
古田氏の『失われた九州王朝』の301ページに、「(大業四年)(二月)・・・」と記されている。『隋書』と照らしあわせてみると、この「(二月)」は、「(三月)」の誤りである。古田氏は、そのあとでも、「大業四年の二月」と記している。これからみると、これは、誤植ではなく、古田氏自身の誤記のようである。
「大業四年二月」以外の個所で、古田氏が、「二」と「三」とをとりちがえる「筆癖」をもっていなかったとしても、この「大業四年二月」の「二月」は「三月」の誤りである。
古田氏の本の中の「二」と「三」について統計的調査を行ない、他の個所では、「二」を「三」に誤っているものがなかったとしても、そこから、「大業四年二月」の「二」が「三」に似ているかどうかとか、この「二」が「三」の誤りであるかどうかについて、なんの情報もえられない。
それとまったく同じ意味において、「邪馬壹国」以外の個所で、「壹」と「臺」とがとりちがえられていなかったとしても、それは、「邪馬壹国」の「壹」が「臺」の誤りでないことや、原筆跡が似ていなかったことの証明にはならない。
古田武彦氏の本の、「(大業四年)(二月)」・・・の「(二月)」が「(三月)」の誤りであることがわかるのは、古田武彦氏の本以外に、『隋書』というテキストがあるからである。
『三国志』の「邪馬壹国」や「壹与」が、「邪馬臺(台)国」や「臺(台)与」の誤りとみられるのは、「邪馬壹国」や「壹与」がでてくるのはすべて、十二世紀以後に成立した版本においてのみだからである。十二世紀よりまえの史料で、女王国の名や卑弥呼の宗女の名を、「邪馬壹国」や「壹与」と記すものは、いっさいない。十二世紀よりまえにおいては、女王国や卑弥呼の宗女の名に、「壹」ではなく、「臺」が用いられていたことを示す史料のみが存在する。
現在、福岡県太宰府市、太宰府天満宮に伝来する張楚金撰、雍公叡注の『翰苑』がある。平安初期九世紀に書写され、そのまま今日に伝来したものである。
その『翰苑』では、現在の『三国志』の版本に、「壹与」と記す名を、「臺与」と記している。そして、これは、『翰苑』成立当時存在した『三国志』の『魏志』からの引用であるとみられる。また、『粱書』『北史』なども、『三国志』に「壹」となる人物を、「臺与」と記している。
また、『翰苑』の「倭国伝」に記されている「馬臺」は、「邪馬臺」と関係があるとみるのが自然であり(「邪」の脱字か)、そこでは、「臺」が用いられている。
古田氏の「臺と壹との統計論」が、統計論的にも、実証的にも誤りであることは、拙著『「邪馬壹国」はなかった』(新人物往来社のち徳間文庫刊)の中で、詳論した。
誤記、誤刻のおきる確率(可能性)は、他のテキストと文字の異同があるはあい、急激に大きくなることに留意すべきである。
古田氏は、その著『「邪馬台国」はなかった』の中でいう。
「……誤謬率の統計的検査。両字の分量と分布は統計的処理に十分な、状況であった。そしてその結果は、誤謬率0を示したのである。
これによって、紹煕本以前の空白部の筆跡状況は明白となった。『壹と臺は字形が似ているからあやまったのであろう』……このような『推定』が、全くの根拠なき臆測にすぎぬことが判明したのである。」
「……ある論者は、さらに苦しい反論を試みようとするかもしれぬ。”裴松之が見た『三国志』諸本は、すべて『邪馬臺国』と書いてあったのだ。だから裴松之はこれに注記しないのだ。それが裴松之以後誤写されて『臺』が『壹』にかわったのだ”と。
しかし、その反論の先には、宋紹煕本の全調査の統計的事実がたちふさがっている。そこには、全138個所(邪馬壹国、壹与をのぞく)中『臺→壹』の誤写・誤刻は0であり、両字の原筆跡が似ていなかった、という事実が証明されているのである。」
古田氏のこのような結論は、すべてあやまりである。古田氏は、「統計的処理に十分な状況」といわれるが、現代統計学の教えるところによれば、十分でない。そもそも、古田氏の統計的調査は「両字の原筆跡が似ているかどうか」などを弁別するなんの基準も提供していないのである。
たとえば、赤摂也氏といえば、名著『数学序説』(培風館刊)の著者であり、数々の著書と編著とをもつ、現代日本の数学者の代表者の一人である。『数学序説』では、現在統計学の基礎なども、懇切丁寧に述べられている。
赤摂也氏には、『確率論入門』(ちくま学芸文庫)の著書がある。
赤摂也氏が、『数学セミナー』誌(日本評論社刊)の、1977年10月号に、愛知三郎というペンネームで、「邪馬台国」という随筆を執筆しておられる。その中で、赤摂也氏は述べる。
「『邪馬台国問題』の本で、私が面白いと思ったものはほとんどない。しかし、皮肉な言い方ではあるが、『教訓的』だという意味で面白かったものは少なくない。
古田武彦氏の『「邪馬台国」はなかった』はその一つだ。氏は『邪馬台国』という国はなく、あったのは『邪馬壹国』だったと主張する。
なるほど、『魏志』の古い写本にはたしかに『邪馬壹国』とある。後世の人は、種々の理由から、これを『邪馬臺国』の誤りだとしたのである。
しかし、古田氏は、そんなことはないという。氏は、『魏志』の写本全巻を克明にしらべ、『臺』であるはずのところが『壹』と書き誤られている例は『一つもない』ことをたしかめることができた。
だから、と氏は主張する、『邪馬壹国』は正しいのである、と。
これを読んで、私は古田氏には悪いが思わず苦笑した。
最近でた安本美典氏の『新考・邪馬台国への道』は、『邪馬台国問題』の本で私が本当に面白いと思ったものの一つである。
この本で、氏は古田氏の議論に的確な反論を加えている。古田氏の本には『三』が『二』に誤植されているところが一ヶ所だけある。これは、古田氏も新聞紙上で認めている誤植だ。しかし、それ以外には『三』が『二』に誤植されている例はないのだから、この『三』も『三』でなければならない、といったら、古田氏はどう答えるつもりか、と。
私は、古田氏の本に、過去の倫理教育の欠陥を見る。そういう意味で『教訓的』なのである。」
『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』の話は省略しますので、
以前にまとめた第255回講演を参照してください。