『日本書紀』は記す。
第1代の神武天皇は、南九州の日向(ひゅうが)[宮崎県]の地から出発し、東征して、現在の奈良県の地に入り、西暦紀元前の六六〇年二月十一日(現在の建国記念の日)にあたる日に、畝傍山(うねびやま)の東南の橿原の宮で即位した、と。
『古事記』は東征伝承は記すが、西暦紀元前六六〇年などの年月日は記さない。
たとえば、この西暦紀元前六六〇年という年は、どのようにして定められたのか。
神武東征伝承に関係しては、いくつもの謎がある。
神武天皇の東征経路は下図のように、現在の宮崎市付近の高千穂宮から出発して、北部九州の岡田宮、現在の広島市付近の多祁理宮(たけりのみや)、現在の岡山市付近の高島宮(たかしまのみや)を経て、大阪市付近の浪波(なみはや)で撃退され、紀伊半島を迂回して熊野の方から入って、そこから北上して奈良入って東征を完了させた。
(下図はクリックすると大きくなります)
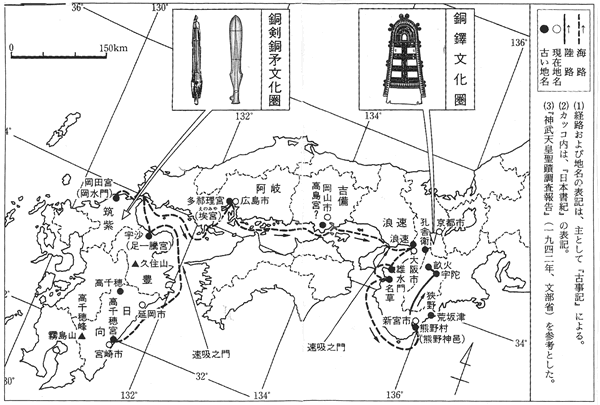
北九州の銅剣・銅矛(どうほこ)は近畿式・三遠式銅鐸(どうたく)と鉛同位体比が同じである。
これは大まかにいえば、銅剣・銅矛の文化圏から、銅鐸文化圏に入っていったと言える。
このことは、神武天皇の前に東遷したという伝承がある饒速日(にぎはやひ)の命がいて、饒速日の命が北部九州の出身で、北九州の銅剣・銅矛の材料を持ち込んで、畿内の銅鐸文化を受け入れ、近畿式銅鐸などを造ったことと思われる。
■第1の謎:使用暦法の逆転現象
最初にとりあげる奇妙な謎は、暦の「逆転現象」の問題である。
これは、『日本書紀』の年月日を記す「暦法」についての問題である。
『日本書紀』では、古い時代の諸天皇のところで、中国の新しい「暦法」[儀鳳暦(ぎほうれき)]が用いられている。そして、それより新しい時代の天皇のところで、中国の古い「暦法」[元嘉暦(げんかれき)]が用いられている。
つまり、儀鳳暦→元嘉暦→儀鳳暦の順で使われている。
この奇妙な「逆転現象」は、なぜ起きたのか。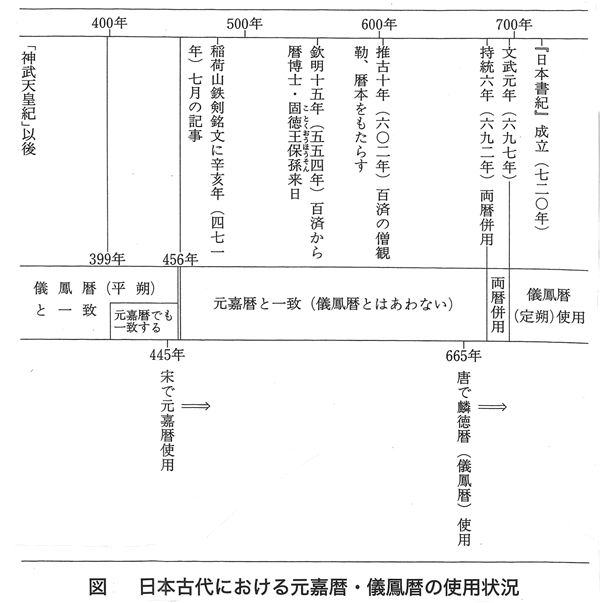
辛酉(しんゆう)革命の説
『日本書紀』の「神武天皇紀」には、神武天皇は、「辛酉(かのとのとり)の年の正月一日」に、大和の橿原(かしはら)の宮で、第一代の天皇に即位したと記されている。ここで用いられている暦は、儀鳳暦で太陰太陽暦なので、これを現行のグレゴリオ暦に換算すれば、「西暦紀元前六六〇年の二月十一日」となる。
この二月十一日が、第二次世界大戦以前は「紀元節」とされた日である。大戦後は、「建国記念の日」となっている。
「辛酉革命説」は、明治の東洋史学者、那珂通世(なかみちよ)が論文「上世年紀考」(1897年)のなかで、整理した形でのべた。
那珂通世は、およそ次のようにいう。
「中国の古代には、「讖緯説(しんいせつ)」というのがあった。陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)[陰と陽、木・火・土・金・水の働きの強さによって、天地の変異、人事の吉凶を説明する説]にもとづき、天変地異や運命を予言する説である。
讖緯家が、「辛酉革命の説」をとなえている。
辛酉(しんゆう)の年、なかでも二十一度目(1260年。60の21倍)の辛酉の年ごとに、大革命[天の命が、革(あらた)まる]があるというのである。
日本の古伝は、『古事記』本文などに記されているような形のもので、元来、起きた事件の「年代」を伝えていなかったとみられる。
『日本書紀』の編纂者たちは、年代を伝えていなかった古伝を、中国の史書にならって、暦年月日などをいれ、形をととのえようとした。そのさい、日本史上の大変革といえる神武天皇の即位を、推古天皇の九年(辛酉の年。601)から逆にさかのぼって、1260年前の
辛酉の年においたのである。」
・第二次世界大戦前においては、今日の「建国記念の日」、二月十一日は、「紀元節」の日と呼ばれていた。
神武天皇即位の日を、『日本書紀』にもとづいて定め、祝日としたものである。
この祝日は、1872年に定められ、第二次世界大戦後に廃止されたが1966年に、「建国記念の日」として復活し、翌年から実施された。
第二次世界大戦前には、小学校などで、この日に式典が行なわれ、「紀元節の歌」が歌われた。
■第2の謎:古代の諸天皇の寿命は、なぜ長い
神武伝承をめぐる第二の謎は、古代の諸天皇の寿命[享年(きょうねん)]が、しばしば、百歳以上になっていて、異常に長いことである。
なぜ、このようなことになっているのであろうか。

一年二歳説
現在の一年を、二年に数える風習は、きわめて古く、中国の殷などにも、あったのかも知れない。殷の国をひらいた湯王(とうおう)は、在位十二年であったが、百歳で崩じたという。
昭和時代の中国文学者、貝塚茂樹(かいづかしげき)編集の『古代殷帝国』(みすず書房刊)には、次のように記されている。
「陳夢家氏は『季』に関しておもしろい仮説を提出した。結論だけいうと、卜辞では、われわれの『今年』や『来年』と同じ使い方で、『今歳』『来歳』ということがある。この『歳』を、陳氏は年のこととせず、半年の『季』をさしていると考えるのだ。一年は、陳氏によれば、禾(か)季(上半年、すなわち後世の春夏)と麦季(下半年)とにわかれる。禾季は禾類[黍(きび)・秬(くろき)等]のできるとき、麦季は麦類(麦・来等)のできるときだ。卜辞の『春』『秋』はそれぞれ禾季と麦季にあたる。そして『今歳』や『来歳』は今季、来季のことで『歳』は半年単位のシーズンをさしているのだと。この説の良否をここでゆっくり検討するひまはないが、たしかに一考を要する新説である。」
「一年二歳説」を、わが国の古代史について、はじめてとなえたのは、デンマーク人で日本にきていたウィリアム・ブラムセン(William Bramsen)である。ブラムセンは、1880年(明治13年)に、「日本年代表(Japanese Chronological Table)」をあらわし、その序説において、次のようにのべている。
(1)神武天皇から仁徳天皇にいたる十七代の天皇の寿命は、いちじるしく長くなっている。この十七代の平均寿命は、一〇九歳である。
(2)履中天皇以後は、にわかに、寿命が短くなり、普通の人の年齢になっている。履中天皇以後十七代の平均寿命は、六十一歳である。
(3)以上のようなことがおきたのは、はじめの十七代においては、後世に普通に用いられたものと異なる暦が用いられていたためでもあろう。すなわち、冬至と夏至の間、または、春分秋分をもって、一年と数えるような暦によったのではなかろうか。
当時日本は、デンマークと修好通商航海条約(日本に不利な不平等条約)を結んでおり、明治初年には、相当数のデンマーク人が、技術指導などのために、日本にきていた。その一人が、ブラムセンであった。
このブラムセンの見解は、イギリス公使館の、ウィリアム・ジョージ・アストン(William George Aston)(1841~1911)の「日本上古史」(『文』第一巻、第十四号、第十五号。1888年〔明治二十一〕十月十三日、二十日)の中でも紹介されている。
この「一年二歳説」をとなえた人・・・民族学者、岡正雄。歴史研究家、大倉粂馬(くめま)。宮崎県総合博物館の沢武人。などの諸氏。
朝鮮半島の古代の王たちの寿命も長くなっている。
那珂通世は、「上世年紀考」のなかで、次のようにのべている。
「韓史も、上代にさかのぼるにしたがい、年暦が延長されていると思われるところのあることは、ほとんどわが国の古史書と異ならない。」
「百済(くだら)の古爾王(こじおう)は、その父、蓋婁王(がいろおう)の没後六十八年に立ち、在位五十三年に及んだので、古爾の年は、少なくとも百二十余歳となる。比流王(ひるおう)は、その父、仇首王の没後七十一年に立ち、在位四十一年に及んだので、比流の寿命も、すくなくとも百十余歳となる。
新羅の上代にも、寿命が九十九歳の脱解尼師今(だつかいにしきん)がいる。また逸聖尼師今(いつせいにしきん)は、儒理尼師今(じゅりにしきん)の長子であって、儒理の没後七十七年に立ち、在位二十一年に及んだので、寿命は百歳を過ぎるであろう。訖解尼師今(きつかいにしきん)は、その父、干老角干の没後五十七年にあたって、『群臣議して曰(い)う。訖解は幼くして老成の徳がある。すなわち、奉じてこれを立てた。』とあるのは、すでに不都合である。さらに、その後在位四十七年となっているのは、また異常の長寿である。
高句麗王、巨連は寿命九十八歳で、長寿王の名をほしいままにした。その上代をみると、太祖大王は在位九十四年、寿命一一九歳、その弟、次大王は、七十六歳で立ち、九十五歳で無道をもって弑(しい)せられ、またその弟、新大王は、七十七歳で立ち、寿命九十一歳、新大王の国相、明臨答夫は、寿命一一三歳とある。また慕本王が弑殺(しさつ)されたとき、群臣は、王の叔父、再思を立てようとしたのを、再思は、年老いているとの理由で、その子、宮(すなわち太祖大王)に譲ったと見えるので、このとき再思は、すくなくともすでに五十をこえた人であるはずなのに、そのすえの子、新大王は、これより三十六年の後に生れている。
また駕洛国(からこく)の始祖首露王の寿命一五八歳のほかに、首露の后、許黄王の寿命一五七歳というのがある。
アストン(イギリスの外交官、日本学者。1841~1911)は、韓史の長寿者は、長寿王のみであるかのように言うが、粗雑な議論である。」
那珂通世が、ここでとりあげている人物のうち、高句麗の第6代の王の太祖大王などは、中国の歴史書の『後漢書』の「高句麗伝」に、「長ずるに及んで勇壮にして、しばしば辺境をおかした。」とあるから、実在の人物である。しかし、『三国史記』の記す太祖大王の記述は、なんらかの理由で、年代がひき伸ばされているようにみえる。
わが国のばあいでも『古事記』は、第21代雄略天皇の享年を、一二四歳とするが雄略天皇は、まず実在の人物と考えられている。
もし、まったくの神話であったり、語りついでいるうちに長くなったり、後世になって作られたりしたものであるならば、二百歳はおろか。三百歳、五百歳などのお年がでてきてもよいはずではないだろうか。じじつ、たとえば『旧約聖書』の「創世記」などでは、アダムは九三〇歳、アダムの子セツは九一二歳、セツの子エノスは九〇五歳まで生きたことになっている。
■第3の謎:神武天皇は、実在したのか
そもそも、第1代の神武天皇をはじめとする初期の諸天皇は、実在したのか。
これについては、長い論争の歴史がある。
実在しないのであれば、神武天皇などの寿命(享年)や、在位年数や、西暦何年ごろの人か、などをたずねるのは、意昧のないことになる。
古文献の読み方についての、三つの立場
第二次大戦後、具体的な史料分析の立場から、日本古代史の実証的研究をおしすすめた東京大学教授の坂本太郎(1901~1987)東京大学史料編纂所長は『季刊邪馬台国』26号(1985年)に寄せた論文「古代の帝紀は後世の造作ではない」のなかで、およそ、次のようにのべている。
「古代の歴代の天皇の都の所在地は、後世の人が頭のなかで考えて定めたとしては、不自然である。古伝を伝えたものとみられる。第五代から見える外戚としての豪族が、尾張の連(おわりのむらじ)、穂積臣(ほずみのおみ)など、天武朝以後、とくに有力になった氏でもないことは、それらが後世的な作為によるものでないことを証する。
天皇の姪(めい)とか庶母(ままはは)とかの近親を妃(みめ)と記して平気なのは、近親との婚姻を不倫とする中国の習俗に無関心であることを示す。これも、古伝に忠実であることを証する。婚姻関係から見て、帝紀の所伝はいろいろ問題はあるにしても、古伝であることは動かしがたく、後世の七世紀あたりの造作だという疑いはまったく斥(しりぞ)けることができる。」
「疑いは学問を進歩させるきっかけにはなるが、いつまでもそれにとりつかれているのは、救いがたい迷いだということも忘れてはなるまい。」
文献によって、古代をたずねようとするばあい、『古事記』『日本書紀』などの文献の記述を、どう考えるかという基本的な姿勢を、まずたずねておかなければならない。
この基本的な姿勢は、大きく、次の三つを、三極の典型とする形でまとめることができるであろう。
(1)古典信奉主義
年代をふくめ、『古事記』『日本書紀』に記されていることは、なるべくそのままうけとろうとする立場。
(2)半実半虚主義
『古事記』『日本書紀』などに記されていることは、実と虚とがあいまじったものと考える立場。
(3)抹殺博士主義
『古事記』『日本書紀』に書かれていることで、すこしでも疑わしい記述は、否定し、史料としてみとめない立場。
私は、(2)の「半実半虚主義」あたりが妥当であると思う。
あることがらを「実」とするのも一つの仮説、「虚」とするのも一つの仮説と考えて、どちらの仮説がより妥当かを、文献やデータにもとづいて検討していくべきであると考える。
文献の個々の記述などについて検討し、実である根拠や、虚である根拠などを、具体的にあげていくべきであると考える。
ただ、第二次世界大戦以前は、(1)の「古典信奉主義」が盛んで、教科書なども(1)の立場から書かれることが多かった。
第二次世界大戦後は、(1)の立場への反動で、(3)の立場が、かなり盛んである。
第二次大戦以前は、(1)の立場を、頭から信ずる人が多く、第二次大戦後は、(3)の立場を、頭から信ずる人が少なくない。
しかし、(1)の立場も、(3)の立場も、ある立場を前提として、その立場から、古典や史料を解釈、理解しようとする傾向が強い。
一つ一つのことがらを、史料にもとづいて具体的に、分析、検討するという姿勢が、がなり欠けている。その意味で、合理性、あるいは科学性に欠けていると思う。
古典信奉主義
[古典信奉主義]は、年代記述をふくめ、『古事記』『日本書紀』などに記されていることは、できるだけそのままうけとろうとする立場である。第二次世界大戦以前の学校教育は、この立場に近い。
わが国の紀元を『日本書紀』に記す神武天皇即位の年(西暦紀元前660年にあたる年)を元年として数える「皇紀」が用いられた。
昭和十五年(西暦1940年、皇紀2600年)には、皇紀2600年をいわう記念行事が行なわれた。
すでにのべたように、二月十一日は、紀元節の日で、国民の祝日であった。
江尸時代の本居宣長の立場は、基本的に、古典信奉主義の立場といえる。
ただ、この立場にたつばあい、たとえば、以下のような問題がおきる。
(1)『古事記』には、古代の十五人の天皇について、没年を記している。そのうち、十二人の天皇については、『日本書紀』の記す没年と異なっている。次のページの表に示すように、そのくいちがいは、天皇の代をさかのぼるにつれ、大きくなる傾向がみとめられる。
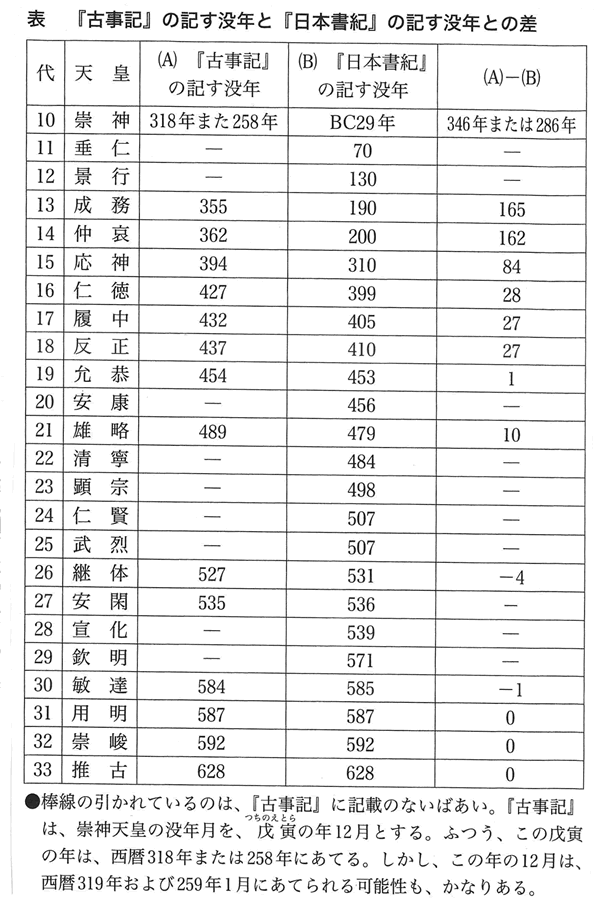
崇神天皇の没年は、『古事記』と『日本書紀』とで、およそ三百年ちがう。このばあい、『古事記』と『日本書紀』とのどちらの記載を信用すべきか。
(2)神話伝承の時代をのぞき、確実な歴史時代にはいってからのちのわが国の諸天皇のうち、もっとも在位期間の長かった天皇は、昭和天皇である。昭和天皇は、1926年に即位し、1989年に死去した。足かけ六十四年間在位した。
いっぽう、『日本書紀』を読むと、第16代仁徳天皇は、八十七年間在位したことになっている。第11代垂仁天皇は九十九年間在位したことになっている。このうち、仁徳天皇などは、中国の宋に使を出した倭の五王の一人の讃か珍にあてられている天皇である。実在の可能性が、かなり高いとみられている天皇である。年代が信用できるかどうかということと、その天皇の実在が信用できるかどうかということとは、問題として、わけて考えなければならない。この仁徳天皇の在位年数などは信用できるのか。
以上あげたような理由などがあるため、古代について合理的に考えようとするばあい、「古典信奉主義」は、そのままの形では、なかなかうけいれがたい。
半実半虚主義
江尸時代に、故実家の伊勢貞丈(いせさだたけ)[1717~1784]はのべている。

「語り違へもあり、聞き違へもあり、忘れて漏(も)れたる事もあり、事を副(そ)へたる事もあるべし。百年五十年以前の事だにも、語り違へ聞き違へて、相違一決せざる事あり。・・・・・・和漢ともに、太古の事は太古の書籍はなし。古(いにし)への語り伝へを後に記したるものなれば、半実半虚なりと思ふべし。」(『安斎随筆』)
1932年に、日本古文書学を確立した東京大学の黒板勝美(くろいたかつみ)[1874~1946]の大著『国史の研究各説』の上巻が、岩波書店から刊行されている。これは、当時の官学アカデミーの中心に位置した黒板の代表的著作といってよい。
『国史の研究』が刊行された当時、岩波書店は、この本を、「学界の権威として、洛陽の紙価を高からしめたる名著」とし、「最近まで各方面にわたりて学界に提出されし諸問題」を「一一懇切詳密に提示論評し」、「その拠否を説明取捨し以て学界の指針たらしめ」「宛然(さながら)最近に於(お)ける国史学界進展の総決算たる観を呈して居る」、そして、「わが国史に就(つ)きての中正なる概念を教示する」もので、一般人士はもちろんのこと、「専門研究者も座右(ざゆう)に備ふるべき好伴侶(はんりょ)たるを失はない」とのべている。
黒板勝美は、『国史大系』などの編集者であり、他の説の批判や自説の主張においては、つねにその根拠を、くわしくのべている。岩波書店がのべていることは、当時にあっては、けっして誇大な宣伝ではなかったのである。その説は、学問的考究の上にたつ、穏健中正な見解とみられていたのである。
黒板は、あとで紹介する津田左右吉の日本神話作為説を「天胆な前提」から出発した研究とし、それを「余りに独断過ぎる嫌(きらい)がある」と批判する。そして、黒板は、神話伝説は、むしろ長い年月の間にだんだん作られてきたとする方が妥当であり、はじめは一つのけし粒であっても、ついに金平糖になるようなものであり、しだいに立派な神話となり伝説となるところにやはり歴史が存在するのではあるまいか、とする。
黒板は、『国史の研究各説』上巻の冒頭で、およそ次のようにのべて、「国史の出発点を所謂(いわゆる)神代まで、遡(さかのぼ)らしめ得る」と説く。
「史前時代と有史時代との境目を明瞭に区別しにくいことは、世界の古い国々みなそうである。その太古における物語は、霊異神怪や荒唐無稽(こうとうむけい)の話に富んでいて、神話や伝説などのなかに歴史がつつまれているといえる。
わが国の神話伝説のなかから、もしわが国のはじまりについての事がらを、おぼろげながらでも知ることができるのであれば、私たちは、国史の出発点を、所謂(いわゆる)神代まで、遡らしめ得るのであり、神代史の研究が、また重要な意義を占めることになるであろう。
もっとも、神武天皇が始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)という尊称をもち、大和に都をひらいた第一代の天皇であるという古伝説にしたがって、あるいは、わが国の歴史の発展を、神武天皇から説明するにとどめようという人があるかも知れない。しかし、わが国のはじまりが、どのようであったかを、いくぶんでも知ることができるとするならば、従来神代といわれている時代に研究を進めることは、また緊要なことといわなければならない。」
ついで、黒板は、天照大御神よりもまえの神々は、皇室の祖先として奉斎(ほうさい)されていないことなどから、実在性はみとめがたいが、天照大御神は、「半ば神話の神、半ば実在の御方」と説く。
「天照大御神は、最初から皇祖として仰がれた方であったからこそ、三種の神器の一つである八咫鏡(やたのかがみ)を霊代(たましろ)として、やがて伊勢に奉斎され、今日まで引きつづき皇室の太廟として、とくに厚く崇祀(すうし)されているのである。
元来史話なるものは、截然(せつぜん)と神話に代るものではなく、その境界は、たがいにいりまじって、両者をはっきりと区別することがむずかしい。これが、天照大御神の半ば神話の神、半ば実在の方として古典に現れる理由である。神話がほどよく史的事象を包んでおり、史的事象がほどよく神格化されている。したがって、須佐の男命(すさのうのみこと)に関する古典の記載なども同様であるが、天照大御神の御代に皇室の基礎が定まり、わが国は天照大御神の徳によってはじまったことは、おぼろげながらみとめられなければならない。」
抹殺博士主義
幕末から明治時代にかけて活躍した歴史学者に、重野安繹(しげのやすつぐ)[1827~1910]という人がいた。帝国大学(のちの東京大学)の教授となり、国史料を設置した人である。
重野安繹は、『太平記』の史料価値を検討し、児島高徳(こじまたかのり)の実在を否認し、「抹殺博士」の異名をとった。
この児島高徳について、現代の『国史大辞典』(吉川弘文館、1985年刊)は、次のように記す。
「高徳(たかのり)の事跡は『太平記』にみえるのみで、他の確実な史料にその名が伝わらないため、高徳を架空の人物とする論が、かつて行われたが、その後、田中義成(たなかよしなり)・八代国治(やしろくにじ)らによって『太平記』の記事の傍証となる史料なども指摘され、また児島氏が今木・大富・和田らの一族とともに備前邑久郡(おおくぐん)地方を中心に繁衍(はんえん)した土豪であることもほぼ確かとされ、今では高徳の実在を疑う人は少ない。」
存在の確証のえられない人物・事績を否定することは、啓蒙期の史学に、よくみられる傾向である。イエス・キリストの実在否定説もあった。親鸞(しんらん)の実在否定もあった。現在でも、聖徳太子の非実在説を説く人がいる。
ドイツのニーブール(1776~1831)は、ローマ史の研究者であった。史料の文献学的批判を行ない、ローマ太古史をおおう神話・伝説の雲をとりのぞこうとした。
文献批判学(テキストクリティーク)は、史料が、史実をさぐる材料として役立つかどうか、もし役立つとすれば、どのていど役立つのか、などを吟味(ぎんみ)する。文献を、本文にしたがって、分析究明し、それを現代の理性にしたがって判断し、さらに、異本、伝説などを参照して、史料の価値をさぐろうとする。
ここで、「批判(クリティーク)」ということばは、内容的には、「考証」ということばと、ほぼ同じであると考えられる。しかし、イメージとしては、より鋭く、近代的であるように思われる。
ニーブールの影響を受けたドイツのランケ(1795~1886)は、文献批判にもとづいて、歴史研究を行なう。これらの人々の研究により、歴史学は、ようやく近代的なものとなった。そして、ドイツのドロイゼン(1808~1884)、ベルンハイム(1850~1942)、フランスのラングロア(1863~1926)、セーニョボス(1854~1942)は十九世紀に、歴史学研究法、あるいは、史料批判の方法を、概論的にまとめた。
十九世紀の後半から、このような文献批判学は、わが国にも、紹介された。
ラングロアおよびセーニョボスは、史料のあつかい方についてのべる。
歴史家は、著書のすべての先験的記事を信用してはならない。それが虚偽でも、過誤でもないと信頼できないからである。
「史料のなかで一致しない記事に出会うまで、懐疑を延ばしてはならない。疑うことから開始しなければならない」(以上、高橋巳寿衛訳『歴史学入門』人文閣、1942年刊より)このような文献批判の方法を、ひとくちでまとめるならば、次のようなテーゼとなるであろう。
「確実に信用できるテキスト以外は、史料として、用いてはならない」
十九世紀文献批判学は、それなりの功績もあった。しかし、やがて、いきすぎを生ずるようになる。十九世紀的文献批判学の、大きな問題点は、その方法が、西欧や中国において、しばしば、失敗を重ねてきたことである。
十九世紀的文献批判学は、文献の記述内容にたいして、批判的、懐疑的、否定的な傾向かつよい。このような傾向のため、十九世紀的文献批判学は、史的事実の把握において、大きな失敗を、くりかえすこととなった。
おもな例を、三つほどあげよう。
(1)十九世紀の文献批判学者たちは、『イリアス』や『オデュッセイア』などを、ホメロスの空想の所産であり、おとぎばなしにすぎないとした。しかし、この結論は、学者としてはアマチュアのドイツのシュリーマンの発掘によって崩壊した(ホメロスの叙事詩は、ゼウス、ポセイドーン、ヘルメス、アポロン、アフロディテなど、オリンポスの神々が登場し、二つにわかれて、ギリシア側とトロヤ側とを助けるなど、十九世紀的な文献批判の方法によるとき、とうてい確実に信用できる文献とはいえない。和辻哲郎は、その著『ホメロス批判』のなかで、「神々のとりあつかい方が、全然神話的である」とのべている)。『イリアス』や『オデュッセイア』の物語は、神話的であるにもかかわらず、シュリーマンの発掘のための重要な手がかりを提供した。
『イリアス』および『オデュッセイア』は西紀前700年~800年ごろのホメロスの手になるとされている。いっぽう、トロヤ戦争により、トロヤが火につつまれて落城したのは、西紀前千二、三百年ごろのことである。
ホメロスの詩のテキストは、紀元前三~四世紀には、なお固定していなかった。今日まで流布本として伝えられているテキトは紀元前215年に生まれたアクサンドリアの文献学者、アリスタルコスが、それまでの多くの研究を集成して、校訂し、定めたものである。
史的な事実があってから、ホメロスまででさえ、およそ、五百年の歳月が流れている。ここで、千年以上あとのテキストが千年以上まえの史実を語っているのである。
ホメロスは、盲目であったと伝えられる。また、ホメロスの詩は、竪琴(たてごと)をたずさえた吟遊詩人たちによって伝えられたともいわれる。史実は、口から口へという形でも、後世に伝わりうるもののようである。
(2)中国においても、かつて、十九世紀的な文献批判がさかんで、学者、政治家として著名な康有為(こうゆうい)[1858~1927]が、『孔子改制考(こうしかいせいこう)』をあらわし、夏(か)・殷(いん)・周(しゅう)の盛世は、孔子が、古(いにしえ)にことよせて説きだした理想の世界にすぎないとのべた。殷王統は、星体神話にすぎないともいわれた。
しかし、甲骨(こうこつ)文字の解読、殷墟の発掘は、『史記』の「殷本記(いんほんき)」に記されていることが、王名にいたるまで、作為でも、創作でもないことをあきらかにした。
司馬遷が『史記』を書いたのは、西暦紀元前100年前後のことである。いっぽう、殷の国が存在したのは、西暦紀元前1600年~紀元前1060年ごろとみられている。司馬遷が「殷本記」を書くまでに、およそ、一千年の歳月が流れている。「殷本記」が、史実を伝えているとは、なかなか信じがたいことである。だが、康有為の知性よりも、『史記』の「殷本記」の記述のほうが、はるかに信頼できるものであった。古人は、私たちが考える以上に誠実だったのである。最近の中国考古学界では、夏王朝の実在説も、さかんに主張されている。現在、殷王統の存在を、否定する学者はいない。
(3)『聖書』のうち、『旧約聖書』編纂の事業は、西紀二世紀の中ごろ、一代の碩学(せきがく)といわれるラビ・アキバによっておこなわれた。ラビ・アキバは、厖大な材料を収集、整理し、今日の『旧約聖書』を確定した。
『聖書』はひとつの伝説集にすぎないとされていた十九世紀に、『旧約聖書』の記述を信じて、メソポタミアのティグリス、ユーフラテスの二つの河の流域で発掘をおこなった人がいた。フランスのエミール・ボッタやレアードである。そして、多くの遺跡や楔形文字のきざまれた粘土板が見いだされた。楔形文字で記された文書の解読や、その後の考古学的あるいは文献学的な研究の結果、『旧約聖書』も多くの史実をふくむことがあきらかにされている。
たとえば、『旧約聖書』は、エジプトに移住したイスラエルの民が、エジプト人によって迫害をうけ、モーセにひきいられて、「出エジプト」を敢行したと記している。このイスラエル人が、出エジプトをおこなった年代は、紀元前1250年ごろと考えて、間違いないようである。
『旧約聖書』のばあいも、史的な事実があってから、テキストが定まるまでのあいだに、長い歳月が、すぎさっているようである。千年をこえる人間のいとなみが、神と人間との物語りのなかに、織りこまれているようである。
以上のべたもののほかにも、神話や伝説がかなりの史実をふくんでいた事例は、きわめて多い。ツェーラム著『神・墓・学者』(村田数之亮訳、中央公論社刊)などは、そのような事例の氾濫であるといえる。
世界的にみたばあい、『古事記』『日本書紀』の神話ていどの質と量とをもつテキストが、史的事実を、まったくふくんでいなかった例は、むしろ、めすらしいといえるようである。
東洋史学者、植村清二の見解
新潟大学などの教授であった植村清二(1901~1987)は、すぐれた東洋史学者であった。また、植村は、直木賞でよく知られている作家、直木三十五の弟でもあった。(「直木」は、本名のなかの「植」の字を分解したもの)。
植村は、その著『神武天皇』(中公文庫、1990年刊)において、『古事記』『日本書紀』のなかの神武天皇についての記述を、くわしく分析したうえで以下のようにのべている(以下、カッコ( )内は、安本がおぎなった)。
「初期の(天皇)の系譜的記事の一切が、机上で制作されたという(抹殺博幸王義的な)説は、古人の構想力をあまりに高く評価し過ぎるものである。」
「帝紀は本来系譜的記載だけであって、これに旧辞の物語がそれぞれ付加されて、記紀の原型ができ上がったのであるから、綏靖天皇から開化天皇までの八代に何の物語も伝えていないのは旧辞にそれが欠けていただけに過ぎないのであって、そのために帝紀の記事を疑う理由とはなり得ないのである。」
「もし更に十数代の世代を増せば、年紀との矛盾はよほど避け易くなったに違いない。然(しか)るに書紀の編者がこれを試みず、智恵もなく八代の天皇の事蹟をブランクのまゝに放置したと共(とも)に、百数十歳の長寿を記して後人を怪しませるに至ったのは、全く彼等が帝紀そのものの所伝を尊重したからに外ならないからであろう。そしてこの点からも帝紀の記事が少なくとも権威あるものと信ぜられたことがわかる。
著者は素朴に崇神天皇以前の天皇は、最初から帝紀に記載されていたことを認め、しかもそれは古い伝承であったと考えるものである。」
七人の東大教授(津田左右吉氏の説に批判的、邪馬台国東遷説支持的) 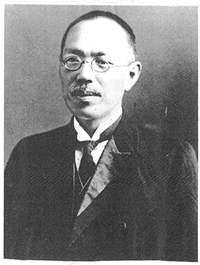
(1)白鳥庫吉氏(しらとりくらきち)(1865~1942)
白鳥庫吉氏は、明治期の東京大学を代表する史家であった。東洋史学の開拓者であり、かずかずの新研究を発表するとともに、多くの研究者を育成した。白鳥庫吉氏は、また、邪馬台国北九州説を説き、畿内大和説を主張する京都大学の内藤湖南氏と、白熱の論争を戦わせた。邪馬台国の位置をめぐる諸説は、それまでにも出されてはいた。しかし、現代まで長く尾をひく、いわゆる邪馬台国論争は、このときはじめて、はげしい沸騰をみせたといってよい。
白鳥庫吉氏は、「邪馬台国東遷説」を示唆し、のちの和辻哲郎氏、の「邪馬台国東遷説」に、直接つながりうるような内容をもつ論文を、いまからおよそ七十年まえに、すでに発表している。
すなわち白鳥氏は、 明治四十三年(1910)に発表した論文「倭女王卑弥呼考」の中で、「魏志倭人伝」の「卑弥呼」に関する記事内容と、『古事記』『日本書紀』の「天照大御神」に関する記事内容とを比較している。そして、その二つの記事内容について、「その状態の酷似すること、何人も之(これ)を否認する能(あた)わざるべし。」と述べている。この指摘は、のちの「邪馬台国東遷説」の核心部と関係する。
(2)和辻哲郎氏(わつじてつろう)(1889~1960)
白鳥庫吉氏の見解は、観察眼の広さと、明晰な思考によって知られる東京大学の哲学者、和辻哲郎氏によってうけつがれ、発展させられた。
和辻哲郎氏は、ニーチェやキェルケゴールの研究から、さらに、日本文化の研究にすすみ、『日本古代文化』、『古寺巡礼』、『風土』などの、数々の名著をあらわした。
和辻氏の「邪馬台国東遷説」は、『日本古代文化』のなかにみえる。『日本古代文化』は、大正九年(1920)に初版が刊行された。そして、大正十四年(1925)と、昭和十四年(1939)とに改稿版が、昭和二十六年(1951)には『新版本古代文化』がだされている。改稿のたびに、内容は、かなり大きく書きあらためられている。
初版の『日本古代文化』は、和辻氏が、若冠二十六歳のときの著作である。和辻氏の「邪馬台国東遷説」は、初版において、もっともくわしい。
和辻氏は、改稿版においては、初版におけるほど明確には、「邪馬台国東遷説」をうちだしていない。 
戦時色が濃くなるにつれ、『古事記』『日本書紀』の記す皇室の祖、天照大御神と、中国の史書『魏志』「倭人伝」の記す東夷の女酋卑弥呼とを結びつけることは、多少とも、はばかるところがあったのであろうか。
初版の『日本古代文化』について、和辻氏は、のちに、つぎのように述べている。
「その後、二十年のあいだに、自分は、幾冊かの著書を書いたが、この書(初版『日本古代文化』)を書きあげた時ほど、うれしかったことは一度もない。」(昭和十四年改稿版『日本古代文化』序文)初版の『日本古代文化』は、和辻氏にとって、記念の一冊であった。
和辻氏は、その「邪馬台国東遷説」を展開するにあたって、まず、『古事記』『日本書紀』の神話と「魏志倭人伝」の記述との一致とを、ややくわしく指摘する。
『古事記』『日本書紀』の伝える天照大御神の事跡は、「魏志倭人伝」の記す卑弥呼の事跡と一致するとし、『古事記』『日本書紀』の神話の伝える高天(たかま)の原時代は、「魏志倭人伝」の伝える邪馬台国時代の記憶ではないかとする。それは、白鳥庫吉氏の論旨にほぼ近い。
「君主の性質については、記紀の伝説は、完全に魏人の記述と一致する。たとえば、天照大御神は、高天の原において、みずから神に祈った。天上の君主が、神を祈る地位にあって、万神を統治するありさまは、あたかも、地上の倭女王が、神につかえる地位にあって人民を統治するありさまのごとくである。また天照大御神の岩戸隠れのさいには天地暗黒となり、万神の声さばえのごとく鳴りさやいだ。倭女王が没した後にも国内は大乱となった。天照大御神が岩戸より出ると、天下はもとの平和に帰った。倭王壱(台)与の出現も、また国内の大乱をしずめた。天の安河原においては八百万神が集合して、大御神の出現のために努力し、大御神を怒らせたスサノオの放逐に力をつくした。倭女王もまた武力をもって衆を服したのではなく、神秘の力を有するゆえに衆におされて王とせられた。この一致は、暗示の多いものである。」
「我々は国民の大きい統一が三世紀以後の機運であることを知っている。また、女王卑弥呼が、倭人の間においても、新しい現象としで起ったという形跡を、魏志の記述から発見する。明らかに国家統一後の所産である神代史が、右のごとき一致を示すとすれば、たとえ伝説化せられていたにもしろ、邪馬台国時代の記憶が、全然国民の心から、消失していたとは思えない。」
和辻氏は、ついで、大和朝廷の国家統一が、どのように行なわれたと考えられるかについて述べる。大和朝廷は、邪馬台国の後継者であり、『古事記』『日本書紀』の伝える神武東征の物語の、「国家を統一する力が九州から来た。」という中核は、否定しがたい伝説にもとづくものであろうとする。
「邪馬台国東遷説」の骨格が、かなり明確な形で提示されている。
和辻氏はいう。
「大和朝廷の国家統一がいかにして行なわれたかは、記紀の古い伝説のうちに、ほのかながらも、痕跡が認められると思う。」
「なんらの伝説もないところに、全然頭のなかから、都合のよい物語をつくりだすというような力は、とてもあったらしく思えない。だから、全体の構想や、一つ一つの物語の連関のつけ方など、後代の創意を認めるとしても、おのおのの物語りには、それぞれ古い民間説話が秘められていると見なければならない。国家統一の事情も、そういう意味で、神代史や上代史から見いだせるであろう。」
「大和朝廷の国家統一については、まず、神武東征の物語が関係をもつ。・・・神代と人代とを結びつける物語が、とくに作者のいちじるしい潤色をうけたのは当然である。しかし、人名や地名や個個の事件などを別として、『国家を統一する力が九州から来た』という物語の中核は、はたして作為であろうか。大八州を生んだイザナギの命の降臨地が大和に近く、また天孫が大八州を治めるために天より降るとすれば、皇室の発祥地を最初より大八州の中央と定める方が、物語の構造としてははるかに自然である。人間のことでない天よりの降臨が、しかも、悠久な古(いにしえ)の出来事が、大和であると九州であるとによって、どれほど神秘的な意味を変えるだろう。ことに、大和に都する皇室のためには、皇祖が、大和に降臨したとする方が、はるかに意味深い。物語りとしても、かえって、その方が、出雲国譲りの事件を活かせることになる。これらの好都合をすべて無視して、天孫を九州に降臨せられたと、国家統一のために神武東征を必要とするのは、作者の作為とは思われない。
統一の力が九州から動いた。このことは、恐らく否定しがたい伝説であったろう。」
「神武東征の物語に、筑紫の勢力がほとんど問題とせられていないのは、筑紫の状況を知るわれわれにとって、力強い暗示である。もし、筑紫以外の九州の勢力が、国家を統一したとすれば、筑紫の勢力との争闘は、なんらかの伝説を残さずにはいまい。しかし、『かつて盛大であった邪馬台(やまと)』の征服を思わせる伝説は、どこにも存しない。邪馬台(やまと)の国は突如として消えた。がそこにはもう全国を統一する大和(やまと)の勢力があらわれている。」
和辻氏は、また、考古学的な事実について、つぎのような点を指摘する。
(a)『古事記』『日本書紀』の神話では鉾と剣とがしばしば語られてぃる。それは筑紫中心の銅鉾銅剣の文化と照応している。
(b)『古事記』『日本書紀』の神話は、銅鐸についての、なんらの記憶も、記していない。これは、『古事記』『日本書紀』の神話が、近畿中心の銅鐸文化圏において発生したものではないことを示している。
(c)大和朝廷および古墳時代の文化は、銅鉾銅剣文化の系統をひく。すなわち、筑紫の銅鉾銅剣文化が、近畿銅鐸文化を征服した。
和辻氏は述べる。
「しかるにわれわれは、銅鐸についての記憶を、伝説のいずこにも発見することができない。銅鐸の用途は、梅原(末治)氏が推測するごとく、祭器であろう。これほどに、顕著な、そうして宗教的意義をもったに相違ない製作品が、古伝説になんらの痕跡を残さないとすれば、古伝説が、銅鐸中心の文化圏内において発生したのではないことはあきらかであろう。」
「ここにおいて、われわれは、われわれの古伝説を生みだした文化圏、すなわち三世紀以後の大和朝廷を中心とする文化圏が、銅鉾銅剣の文化の系統を引くものではないかとの推測に達するのである。すなわち、筑紫地方において急激に発展した勢力---銅鉾銅剣を徴証とすれば、その勢力範囲は朝鮮南部、四国、中国西部を含んでいる---が、・・・東方の大和に移り、そこを中心として関東平野以西全部を統一したのではなかろうかという推測である。」
「古墳からもっとも多量にでる漢鏡(和辻氏は『漢鏡』を、『漢代の鏡』の意味ではなく、『中国の鏡』の意味で用いておられるようである。)勾玉、刀剣の類も、この問題については、暗示するところが多い。
・・・漢人と直接に接触してもっとも多くその影響をうけたのは、筑紫人である。・・・この種の技術の、もっとも古くもっともよく発達していたのは、筑紫の地でなければならない。だから、鏡、玉、剣のごとき物品およびそれを製作する技術は、漢人と直接交通した筑紫人の手を経て、東方に広がったか、もしくは、筑紫人がみずから東方に運んだかでなくてはならぬ。すなわち、古墳時代の文化は、九州起源だということかできるのである。」
「このような考古学的事実を、前述の『東征』という事実に連関せしめてみる。弥生式文化は、筑紫地方を中心として東方へ広がったのであって、これを『東征』と考えて、なんらさしつかえはない。また、武器尊崇は、筑紫地方から起って、東方へ広がったのであって、銅鐸尊崇がそのために消滅したことを、『東征』と考えても、おなじくさしつかえはない。・・・古伝説のなかに、もっとも強力なモチーフとして、東征が語られるのも、ゆえなきことではないであろう。」
(3)黒板勝美(くろいたかつみ)(1874~1946)[右の写真]
「天照大御神の御代に。皇室の基礎が定まり、わが国は天照大御神の徳によってはじまったことは、おぼろげながらみとめられなければならない。」
「(津田左右吉の説について)余りに独断過ぎる嫌(きらい)がある。」
(4)坂本太郎(さかもとたろう)(1901~1987)
「疑いは学問を進歩させるきっかけにはなるが、いつまでもそれにとりつかれているのは、救いがたい迷いだということも忘れてはなるまい。」
(5)金子武雄(かねこたけお)(1906~1983) 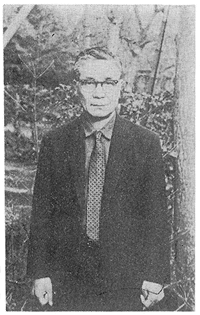
『古事記神話の構成』桜楓社刊、1963年
「国譲りの神話の舞台は高天の原と出雲とであるが、出雲方の人々の立場からではなく、高天の原方の人々の立場で語られていることは明らかである。しかし高天の原方の立場に立つ人々というのは、近畿の人々なのか、それとも筑紫の人々なのか。『古事記』では、建御雷の神(たけみかづちのかみ)とこれに添えられた天の鳥船の神(あめのとりふねのかみ)とが、「出雲(いづも)の国の伊那佐(いなさ)の小浜(をばま)に降(くだ)り到(いた)りて、十掬剣(とつかつるぎ)を抜きて、逆(さかさま)に浪の穂に刺し立て、その剣の前(さき)に趺(あぐ)み坐(ま)して」、とあり、その上で大国主神と談判したとある。
「降(くだ)り到(いた)り」とあるから高天原から降ったという意である。しかし、本来そうだったのか。高天の原から降るというのなら、なぜ、わざわざ岸近くの海に降ったのか。おそらくは海路から出雲に行ったという事実が反映しているのであろう。「天の鳥船の神(あめのとりふねのかみ)」は船そのものか、あるいは船の操縦者か区別しがたいが、とにかくこの神が添えられたということがそれを思わせる。そして「天降った」というのは、高天の原との関係によって神話化せられたものと考えることができる。
この出雲との国譲りの交渉の神話は、おそらくなんらかの史実を基盤としていると思われる。建御雷の神が船に乗って出雲の海岸に着いていることが、この神話の基盤になっている史実を反映しているものとすれば、その史実は、当然、近畿と出雲との間の交渉ではなくて、筑紫と出雲との交渉であったとみなければならない。近畿から出雲へは船で行くはずはないからである。こうしてこの国家譲渡の交渉の神話もまた、筑紫で生育したものであることを思わせる。」
「やや比喩的に言えば、高天の原はほかならぬ筑紫の上にあったのである。・・・いわゆる高天の原系神話も、いわゆる筑紫系神話と同じく筑紫の地に生育したものと思われる。」
(6)和田清(わだせい)(1890~1963) 
1956年に、東京大学教授、和田清博士の『東洋史上より観たる古代の日本』(ハーバード・燕京・同志社東方文化講座委員会刊)が刊行されている。
まず、和田氏は、つぎのような理由から、邪馬台国北九州説をとる。
(a)末盧国、伊都国、奴国、不弥国など、今日でいえば、一郡にもあたらぬ小さな国である。他の三十国近くの国だけが、後の一国にあたるような大国でありうるはずがない。一国が、一郡にもあたらぬ小さな国であるとすれば、三十国は、北九州一帯にすぎない。
(b)当時、日本は、まだ統一していなかったと考えられる。隣の朝鮮半島でも、馬韓は五十余国にわかれ、辰韓は十二国にわかれ、弁韓もまた十二国で、統一していなかった。海をへだてた日本だけが統一していたとは、考えられない。もし、女王国が大和だとすると、大和にいて、壱岐、対馬までしたがえていたとすれば、それは、西日本の統一を意味する、女王国を北九州だとすると、北九州なればこそ、壱岐、対馬を統属していたことになる。しかも、南に、狗奴国、すなわち、熊襲の国が独立してありえたことになる。
(c)「倭人伝」に、「女王国の東、海を渡ること千余里、また国あり、みな倭種である。」とある。女王国が、もし大和であれば、この一句は、まったく意味をなさない。
和田清氏の「邪馬台国東遷説」
和田清氏は、その「邪馬台国東遷論」を、つぎのように展開する。
「端的に申しあげますと、私は、卑弥呼の国が東征して、大和朝廷の基を開いたかと思うのであります。もちろん、卑弥呼は、とうに死んでおりますし、その子孫はありませんが、その勢力をついだものが東征したろうというのであります。」
和田清氏は、「邪馬台国東遷論」をとる理由として、つぎの三つをあげている。
(a)卑弥呼の国は、邪馬台、すなわちヤマトといった。そして、大和朝廷もヤマ卜といった。畿内にはあとにつけた大和国を除いて、ヤマトという固有の地名はない。これは、北九州に、山門という古地名が残っているのと、大きな違いである。邪馬台の勢力をつがなければ、ヤマトを名乗るわけがない。
(b)北九州は、銅剣銅鉾の文化を持っていた。これに対し、畿内は、銅鐸文化をもっていた。しか も、大和朝廷は、銅鐸のことを、まったく知らない。『日本書紀』をみても、『古事記』をみても、天の叢雲(むらくも)の剣や、玉や、鏡のことはよくでているが、さしも盛んであった銅鐸のことは、まったくでてこない。『扶桑略紀』によると、天智天皇の時(天智七年〔668〕に、近江の国、滋賀郡〔今の大津市の北方〕で)、銅鐸(宝鐸)の発見があったが、だれも知るものがない。『続日本紀』によっても、元明天皇の時、(和銅六年〔713〕七月、大和の宇太郡長岡で)銅鐸がでてきたが、だれもわからなかったという。銅鐸は、おそらく祭器で、その部族にとっては、神聖なものであったに相違ない。しかるに、大和朝廷では、当局も、まったくこれを知らない。これは、大和朝廷が、畿内の文化の代表者でなかった証拠である。銅鐸は、多く隠匿したような形ででてくるというが、これは、この文化の代表者が、銅剣文化の保持者の圧迫に対して、これをかくしたものかと思われる。
(c)大和朝廷の伝説には、北九州の勢力を平げた話だけがない。もちろん、歴史時代に、筑紫の磐井の乱を平げた話などがあるが、それは歴史時代のことで、それとこれとは別である。卑弥呼の国は、さしも盛んであったのに、有史以前に、これを平げた話はない。イズモ、クマソすべてを平げた話はくり返してあるのに、北九州を平げた話だけがない。かえって、その代りに、神武東征の話があって、九州から大和を従えたことになっている。
天照大御神は卑弥呼の伝説
和田清氏は、つぎのような理由から、三世紀には、大和朝廷は、成立していなかったと考える。そして、日本の統一を四世紀の上半初期とされる。
「邪馬台国は、三世紀の半ごろに、日本でもっとも有力な国家でありました。もし、当時畿内に、もっと強力な国家があれば、卑弥呼が、いかに邪魔をしても、直接支那に通じないという法はありません。しかも、倭人伝によるかぎり、そういう形跡は、すこしもないのであります。」
和田清氏は、さらに述べられる。
「神武天皇東征の話が、どれだけ歴史事実を伝えたものか解かりませんが、すくなくとも、その話の筋の中には、北九州の勢力が、大和にうち入った記憶だけは、とどめているのではないでしょうか。」
「卑弥呼の時代は、三世紀であって、日本の記録の成ったのは、八世紀であります。その四五百年のあいだには、記録のない未開人の間には、すべてのことが忘れられて、卑弥呼のことも、天照大神の伝説ぐらいになってしまったと考えても、よくはないでしょうか。」
(7)井上光貞(いのうえみつさだ)(1917~1983) 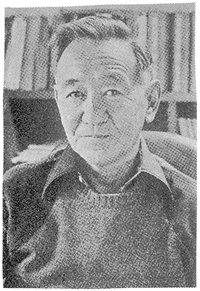
井上氏の「邪馬台国東遷説」は、『日本の歴史1 神話から歴史へ』にくわしい。
「・・・もっと自然なのは、邪馬台国東遷なのである。もちろん邪馬台国東遷説も、可能性のある一つの仮説にすぎないが、『北九州の弥生式文化と大和の古墳文化の連続性』、また『大和の弥生式文化を代表する銅鐸と古墳文化の非連続性』という中山氏や和辻氏の提起した問題は、依然として説得力をもつと考えられる。また、邪馬台国は、その女王壱与(いよ)が266年に晋に適使した後、歴史の上から姿を消してしまった。
いっぽう畿内の銅鐸も、二、三世紀の弥生後期にもっとも盛大となり、しかも突如としてその伝統を絶った。そして三世紀末、おそくとも四世紀はじめごろから古墳文化が畿内に発達して全国をおおっていくのである。邪馬台国東遷説は、この時間的な関係からみても、きわめて有力であるといってよいであろう。」
■第4の謎:神武天皇は、実在したとすれば、いつごろの人か
神武天皇が実在したとすれば、いつごろの人であろうか。
また、初期の諸天皇の活躍年代や没年などは、いつごろと考えられるのであろうか。これについては、1965年以降、数理統計学的手法による推定が、数多く行なわれているようになってきた。
そして、その結果は、おおむね一致している。
(a)「奈良七代七十年」奈良時代は第四十三代元明天皇から、第四十九代の光仁天皇までの七代、すなわち、元明・元正・聖武・孝謙・淳仁・称徳・光仁の七代で、74年(710~784)。この間、一代平均10.57年。桓武天皇は、はじめ784年に長岡京(京都府向日市のあたりが中心)に都をうつしている。
(b)「君、十帝を経(へ)て、年(とし)ほとほと(ほとんど)百」 この文は、奈良時代史の基本文献である『続日本紀(しょくにほんぎ)』の、淳仁天皇の天平宝字二年(758)八月二十五日の条に記されている。これは、第三十六代の孝徳天皇から、第四十六代の孝謙天皇までが、十代で、104年ほどであることをのべているのである。
すなわち、天皇一代の平均在位年数が、およそ10年ていどであることは、奈良時代の人たちが大略認識していたことであった。
詳細は第387回参照
結論:神武天皇は278年前後と考えられる。
■第5の謎:神武天皇は、なぜ、東征したのか
『古事記』『日本書紀』によれば、第1代の神武天皇は、南九州の日向(ひゅうが)[宮崎県]の地から出発し、東に向かい、大和(奈良県)にはいったことになっている。
神武天皇が、日向の地にいたとしても、なぜ、東に向かう必要があったのだろう。また、東征神話が、のちに大和朝廷の役人たちによって、机上で作られたものとすれば、皇室の発祥地を、伊勢(三重県)あたりにでもしたほうが、話はずっと簡明になるはずであるが、・・・。
神武天皇が東に向かったおもな理由として、次の三つをあげることができる。
(1)東に、南九州よりも、生産力の豊かな地のあったこと。
(2)神武天皇に、英雄性のあったこと。
(3)長年月にわたる邪馬台国後継勢力の日本列島植民地化革命運動は、東へ東へという方向性をもっていたこと。この革命運動は、天皇家を貴種と定め、貴種による支配を「正義」とし、租税制度を普及させ、その税収により、軍隊や役人を養い、政治を組織化する構造をもっていたこと。組織的な国家の樹立を、目指しているところがあるため、日本列島内の敵対勢力は、結局は抵抗できなかった。
『魏志倭人伝』に、倭人は、「租賦(そふ)を収(おさ)む」と記されている。米など、収穫物の一部を、官に納める「租税制度」があったのである。「租税をとる」というアイデアは、中国からきたものであろう。「租税をとる」ことによって、「国家」は、はじめて、部族国家の域を脱する。強力な「国家」といえるものとなる。「租税」によって、戦争にとくに適した屈強の若者たちを「兵士」として雇(やと)いうる。それらの「兵士」は、戦争だけに専念することができる。組織的な訓練を受けることとなる。「租税」によって、最新鋭の武器を購入することができる。最新鋭の武器をもち、組織的な訓練をうけた兵士によって、王朝を守らせることができる。支配地域を拡大させうる。
武力によって、支配地域の人民から、「租税」を収奪することができる。
また、一方、「租税」によって、人をやとい、治水や灌漑などの土木工事をより大規模に行なうことができる。外国の新技術も導入し、農業生産力をあげることができる。
「租税」制度をもつ国家は、人々の生活を安定させ、より豊かにする。人口の自然増も大きくなる。支配地域そのものも、ひろげうる。
「租税」収入をより大きくし、武力を、すなわち、国家権力を、さらに大きくすることができる。
このようにして、国家権力の拡大再生産が可能となる。
アイヌは、最後まで、部族国家の域を脱しなかった。組織的な徴税システムをもたなかった。
このような部族国家では、鮭が川にのぼってくれば、戦争を放棄して、魚をとらなければならない。兵士は、日ごろは、生産に従事しており、戦争のプロではない。戦争のための組織的な訓練を、十分にうけているわけではない。
徴税システムをもつ「国家」と「部族国家」とが戦ったばあい、長い目でみると、「部族国家」に勝ち目はない。
大和朝廷は、徴税を行なうという、新機軸の国家システムによって、比較的短い期間で、日本列島を席巻していったとみられる。
『魏志倭人伝』は記している。
「其(そ)の(倭人の)俗、国の大人(たいじん)[身分の高い人]は、皆四、五(人)の婦(よめ)あり。下戸(げこ)[しもじもの家]は、あるいは、二、三(人)の婦あり。」
三世紀の倭人の伝統を引くのであろう。『古事記』『日本書紀』によれば、天皇は、多く妻(みめ)をもっている。そして、天皇家の子弟は、各地に派遣されている。
皇子たちは、中央からの武力をともなって各地におもむき、その地に権威者としてのぞみ、その地で徴税システムをつくり、大和朝廷のさらなる発展に、寄与することとなるのである。
中国の漢および後漢では、王子が、しばしば、各地の王に封じられている。大和朝廷がとった方法も、それに近い。
そして、各地におもむいた皇子たちは、各地で組織された兵をひきいて、中央の政府にも参画し、新たな征服戦にものぞむのである。
徴税システムという新文化をうけいれたのは、九州のほうが、畿内よりも早かったはずである。朝鮮半島や中国に近く、また、南方原産の稲がはいったのも、九州のほうが早かったとみられるからである。
そして、徴税システムを、さきに受けいれたがわのほうが、国を統一して行く権力になりやすかったはずである。
・帝国主義的植民地獲得運動
簡単にいえば、古代の邪馬台国-大和朝廷は、天皇家を中心として、帝国主義的な植民地獲得運動(戦争)を、長期にわたり展開していったのである。 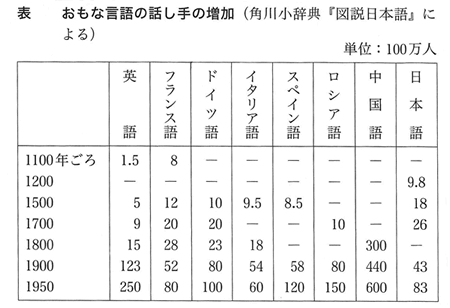
帝国主義といえばふつう、十九世紀末以後の、西欧列強による領土獲得主義、他国または後進の民族を征服して、大国家を建設しようとする運動をさす。
邪馬台国-大和朝廷の起した運動も、かなりそれに近い。とくに、コサックの騎兵を先にたて、地つづきで、広大なシベリアを征服し、植民地化していったロシアの動きに近い。
いま、西欧列強などの、植民地獲得運動の状況を、「言語」という面からみてみよう。
世界には、およそ五千種の言語があるとも、七千種の言語があるともいわれている。そして、日本語は、現在、中国語、英語、ロシア語、ヒンディー語、スペイン語につぎ、世界で、第六番目に使用人口の多い言語である。
表にみられるように、1950年の統計で、英語の使用人口は、約二億五千万人。これに対し、日本語の使用人口は、約八千三百万人。約三分の一である。
しかし、ついその五百年ほどまえの西暦1500年ごろには、英語の使用人口は、約五百万人、日本語の使用人口は、約千八百万人と推定されている(表やグラフ参照。角川小辞典『図説日本語』による)。 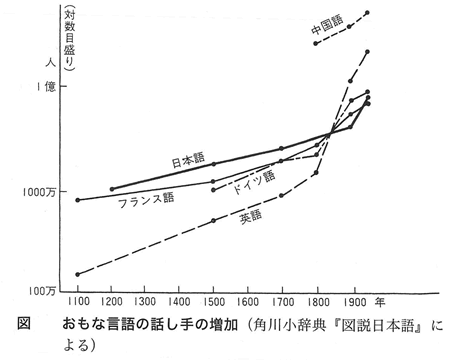
日本語の使用人口は、英語の使用人口の三倍強であった。英語は、五百年ほどのあいだに、使用人口が、およそ五十倍になった。英語の使用人口は、とくに、十九世紀以後に爆発的に多くなった。
ロシア語も、スペイン語も、五百年ほどまえには、日本語よりも使用人口がすくなかった。
五百年ほどのあいだに、ロシア語は、十五倍以上、スペイン語は、十四倍以上に使用人口が膨張した。日本人は決して少数民族ではなく、大河と呼ぶにふさわしい。
英語やロシア語、スペイン語が、ここ五百年ほどのあいだに、急激に膨張したのは、政治的な事情による。植民地獲得運動を、積極的に行なったためといえる。
八世紀の奈良時代の日本の人口は、すでに、六百万~七百万人に達していたと推定されている。これは、数百年のちの、西暦1500年ごろの英語の使用人口よりも多い。
邪馬台国-大和朝廷は、西欧列強よりもずっと早い時期に、わが国内で、植民地獲得運動を展開していたといえる。
第二次世界大戦のあと、わが国の侵略主義は、大いに批判をうけた。反省するべきではあるが、西欧列強や中国は、あまり強くは、他を批判できない過去を持っているといえる。「勝てば官軍」的な勝者の論理を、すなおに受けとりすぎるのも、どんなものであろうか。
邪馬台国の後継勢力による国土統一戦争は、「血統」の正しい支配者を上にいただいているという、「正義はわれにあり」とする理念と、新しい組織的国家をつくろうとする意欲と、徴税システムという新文化と、さらに武力とによって、国土を席巻して行く運動であった。
以上のべたような構造による国家権力の拡大再生産システムは、つねに、あらたな植民地となる土地と人民とを必要とする。
植民地時代に、ロシアは、地つづきでシベリアを植民地にしていった。それと同じように、大和朝廷は、長年月をかけて、日本列島全体を植民地化していった。それは、北海道を、和人化するまで続いたともいえる。
このように、北九州の地に成立した邪馬台国は、その後「血統」と「租税制度」とを基軸として、各地に勢力をひろげていったのである。
そして、わが国古代の、天皇家を中心とする帝国主義的植民地獲得運動は、独特の特色をもつものであった。
それは、武力一辺到の征服主義ではなく、すでに紹介したように、しばしば、「両系相続」の婚姻制度などにより、「言向(ことむ)け和(やわ)す」という方法により、平和裡に、地元勢力を、貴種がわの勢力に組みいれて行くという方法をとる、というものであった。
最後に、古代史を研究する上で重要な問題を考える。
■新(ネオ)・神話史実主義(エウヘメリズム)の提唱
紀元前300年ごろに、シチリア島に生まれたとみられる神話学者、エウヘメロス(Euhēmeros)は、神話は、史実にもとづくとする説をたてた。
すなわち、ギリシア神話の神々は、人間の男女の神話化したものと説いた。神々は、元来、地方の王または征服者、英雄などであったが、これらの人々に対する人々の尊崇、感謝の念が、これらの人々を神にしたとする説(エウヘメリズム euhemerism)である。
エウヘメリズムは、新井白石の、「神は人なり」説に近いといえよう。
第二次大戦後のわが国では、津田左右吉流の立場から、神話と歴史とは峻別すべしということで、エウヘメリズムは、批判の対象とされることが多かった。しかし、エウヘメロスの考えは、シュリーマンの発掘によって、実証された部分があるともいいうる。
ヘレニズム(ギリシア精神)のなかから、もろもろの科学が芽ばえた。
エウヘメリズムは、神話についての合理的説明をこころみたものとして、もう一度みなおされる必要がある。
たとえば、日本神話にでてくる地名の統計をとれば、畿内の地名は、ごくわずかしかでてこない。九州と出雲の地名が圧倒的に多くでてくる。これは、大和朝廷の役人たちが、奈良県の地で、神話を創作したとする説とは、矛盾する。神話が生育したのは、おもに、九州と出雲であることを思わせる。そのような統計調査の結果は、神話に、史実の核があるとする仮説を支持する材料になりうる。このような統計調査は、だれが行なっても、同じ結果がえられるという「再現性」をもつ。
これまでに得られている多くの成果は、エウヘメロスやシュリーマンのような、粗朴な神話理解こそ、実りが豊かであることを示している。津田左右吉流の十九世紀的文献批判学は、あまりにもしばしば事実によって裏切られている。
ギリシア、ローマの考古学や、聖書の考古学は、すべての考古学のはじまりであり、母胎であった。
そして、その考古学は、神話、伝承といったものに、みちびかれたものであった。
ホメロスの詩が、吟遊詩人の口承伝承であったことは、たとえば、矢島文夫氏の、『失われた古代文字99の謎』(産報刊)などにくわしい。そして、『古事記』『日本書紀』の神話には、口承伝承の名ごりと考えて、はじめて理解できる表現形式が、きわめて多いことについては、別の機会に詳論したことがある(『邪馬台国論争批判』)。
シュリーマンの時代にもどってみよう。
ホメロスの『イリアス』は、ゼウスの子アポロンが「遠矢をいて」アカイア人の戦列に、致命的な疾病をあたえることからはじまっている。ゼウスみずから戦いに干渉する。ゼウス、ポセイドーン、ヘルメス、アポロン、アプロディテなど、オリンポスの神々は、ギリシア側とトロヤ側にわかれて助ける。それは、『古事記』『日本書紀』の神話よりも、はるかに神話性の強いものである。
しかも、年代のととのった歴史時代以後のギリシア人は、一小民族にすぎなかった。壮麗な宮殿も、王の権力も、千艘の船も、そこにはみられない。
どうして、ホメロスの詩が、信じられるであろうか。当時の学問的思弁が、『イリアス』は、ホメロスの詩的霊感の産物としたのも、自然な状況ではあった。
が、シュリーマンは、当時の学問的思弁よりも、古人の書いた文献のほうが、いっそう権威もあり、信頼もおけることを示した。
各用語は『ギリシア・ローマ神話辞典』(岩波書店1960年刊)、参考書 村田数之亮著『エーゲ文明の研究』(弘文堂1949年刊)などから下記参照。
シュリーマン[Heinrich Schliemann](1822-1990)は「ミュケナイ文明と トロイア文明との発見者。北ドイツに貧しい牧師の子として生まれる。少年の時トロイア物語の実在を信じてそれの発掘を決心。刻苦して大商人となり巨富をつむと業界を退いて1871年以来その生涯をホメロス世界の発見と実現に努めた。すなわち古えのトロイアを当時の定説に反してヒッサリークの丘に求めて、ここに7層の都市(実は城塞で後に9層と改める)の城壁と財宝とを発見してトロイア文明を実証して世界を驚かした。また、ミュケナイ、ティリュンス、オルコメノスを発掘してミュケナイ文明を発見して設定した。
クレタ島のクノッソスにも着目したが、発掘せずに終わった。彼はエーゲ文明の、少なくともその前半の発見者であり、その数奇な生涯と語学の天才は多くの発掘報告とともに彼の偉大さを示す。
ホメロスの世界は虚構ではなく、実在したことを明らかにした。彼の研究が契機となって、それまで別々の学問とされていた先史学と古典考古学とは、考古学という一つの学問体系に統一される機運が生じた。」とある。
エヴァンズ[Evans Sir Arthur](1851~1941)は「イギリスの考古学者。考古学者ジョンJohn ・エヴァンズ(1823~1908)の子、著述家ジョアンJoan・エヴァンズの兄。オックスフォード大学およびゲッティンゲン大学に学び、オックスフォードのアシュモール博物館の学芸員となった。1900年クレタ島の、クノッソス遺跡を発掘して壮麗なミノス王の宮殿の遺跡を発見、第二次世界大戦が勃発するまで40年近く宮殿の丹念な発掘と復原に専念し、ミノス文明の解明にはかり知れない業績を残した。」とある。
クノッソス[Knossos]は「ギリシア南部のクレタ島の中央部、ヘラクリオン Heraclionの郊外にあるミノス時代の宮殿を中心とした遺跡。1900年イギリス人A.エヴァンズにより発掘が始められた。それによりそれまで知られなかった文明が明らかにされ、エヴァンズはそれにクノッソスの伝説の王ミノスの名をとってミノス文明と名付けた。ミノス文明またはクレタ文明またはミノア文明と呼ばれる。」とある。
ミノス[Minos]は「ギリシア神話によるクレタ王。ゼウスとエウロパの子。パシファエを妃とし2男2女をえた。神が送った美牛をポセイドンに捧げなかったので、ポセイドンは妃に美牛を愛せしめ牛頭人身のミノタウロスを生ませた。彼はこれをラピュリントス(迷宮)に幽閉し、アテナイから毎年、青年男女をえらんで、犠牲とし食わせたので、アテナイの英雄テセウスがミノタウロスを征伐した。ミノスはラビリュントスの作者ダイダロスを追い、シチリアにゆき殺された。
ラビュリントス[Labyrinthos]は「ギリシア神話の迷宮。クレタ王ミノスがその子で怪物のミノタウロスを閉じ込めるためにダイタウロスに建てさせた建物で、入れば出られない。なお伝説によるとテセウスがここに入ってミノタウロスを殺す。発掘されたクノッソス宮殿の複雑な建物はラビュリントスの名にふさわしい。」とある。







