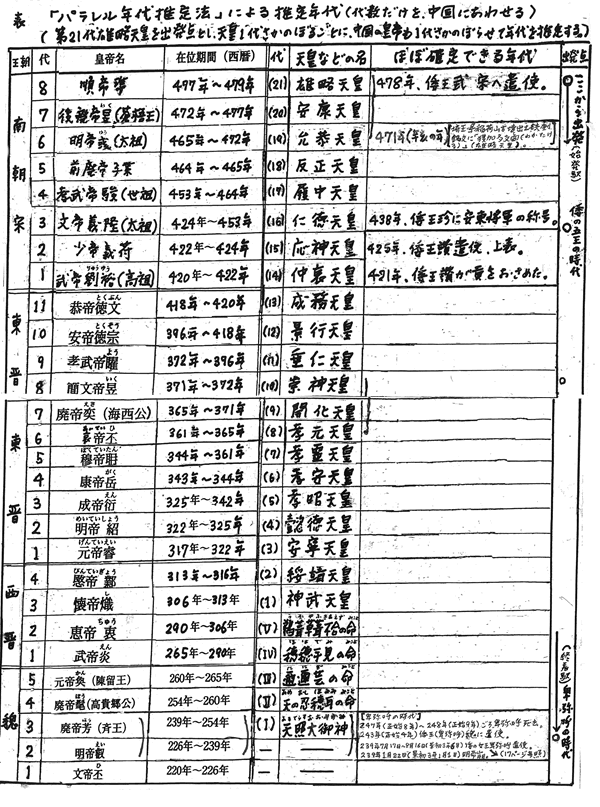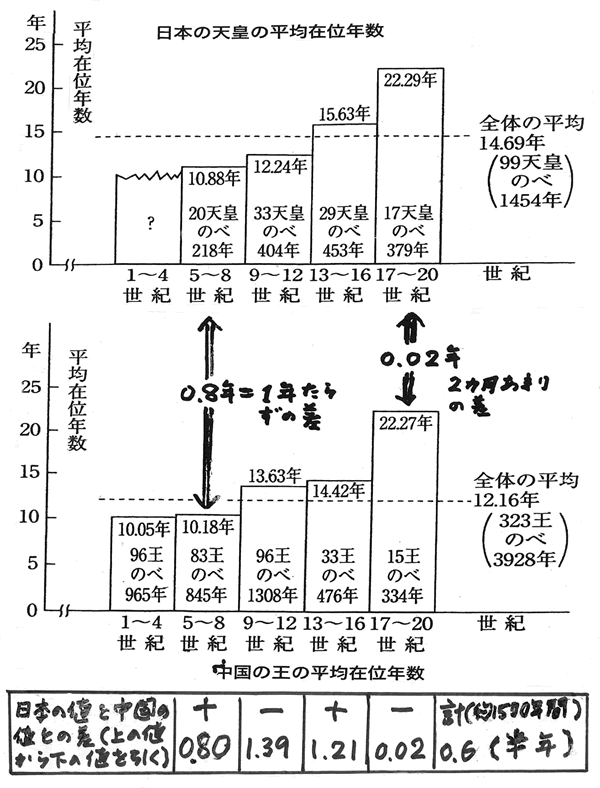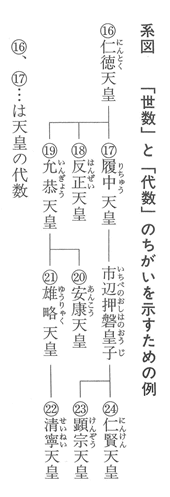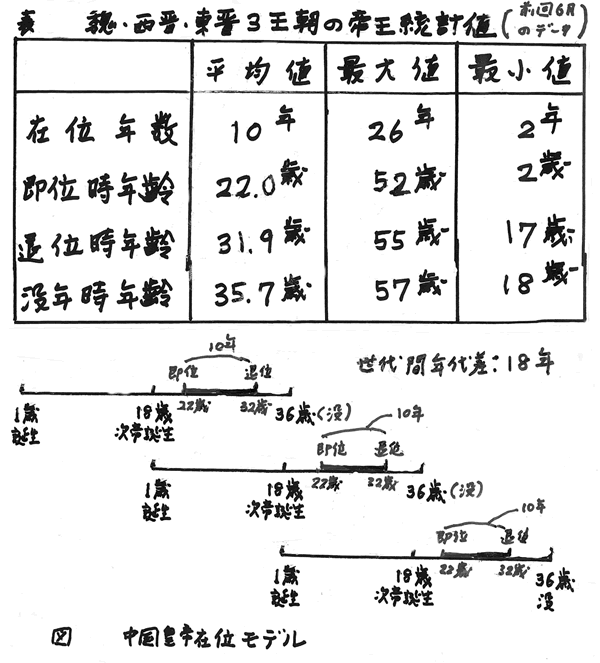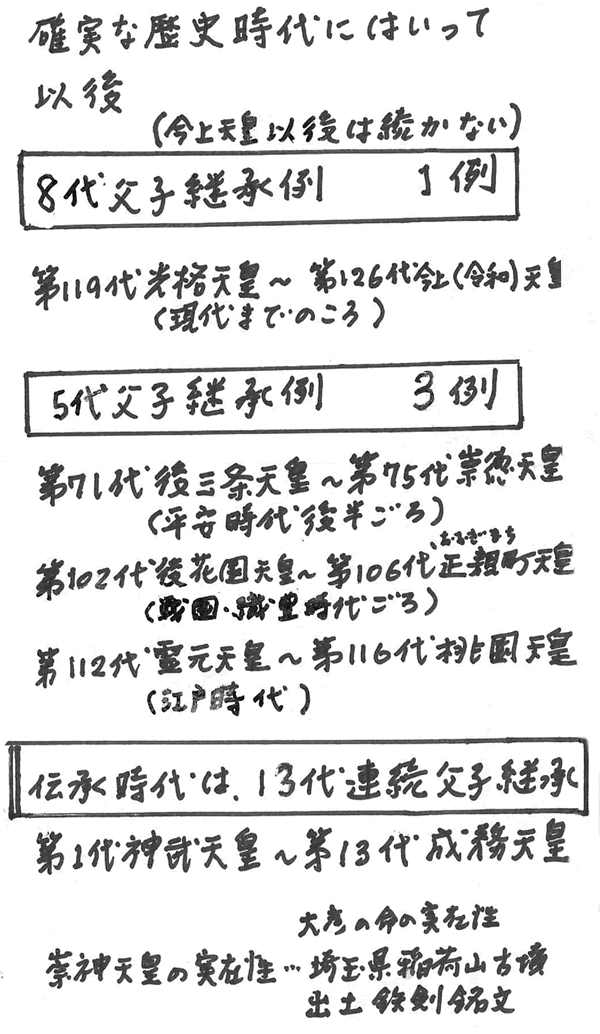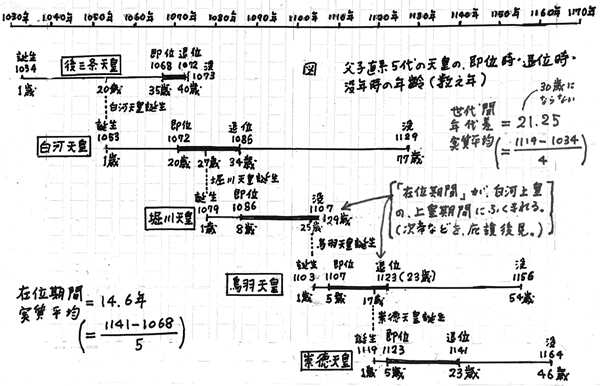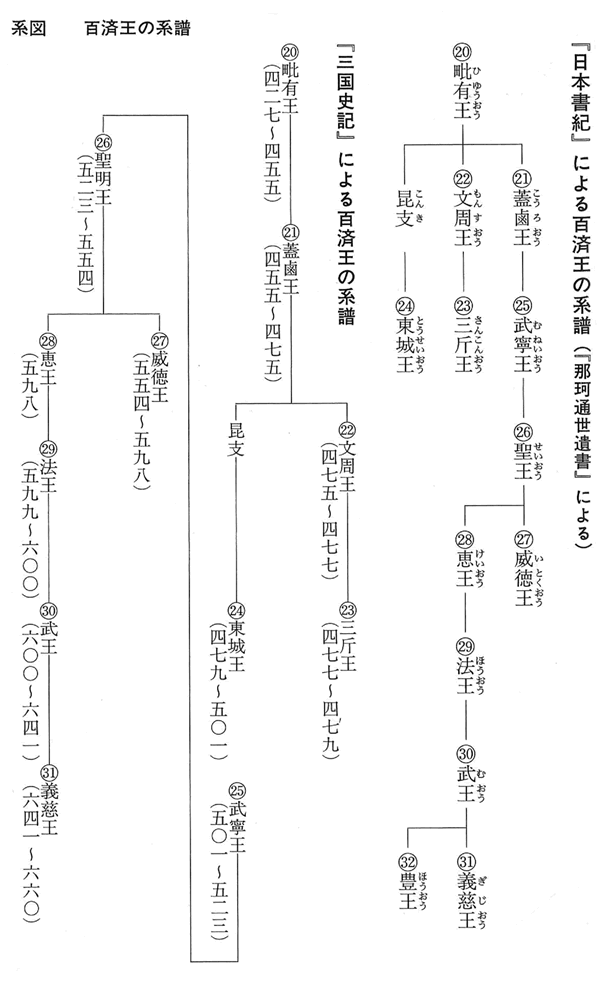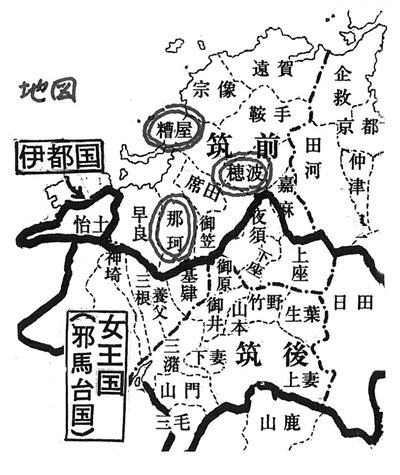| TOP>活動記録>講演会>第401回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
Rev4 2023.4.13 |
第401回 邪馬台国の会(2022.7.24 開催)
| ||||
1.原始二つの太陽があった(卑弥呼と天照大御神)箸墓古墳追考 |
「原始、女性は太陽であった。」 ■パラレル年代推定法-古代への階段(きざはし) (2)倭王の武の「武」の名は、雄略天皇の名である「大長谷若建の命(おおはつせわかたけのみこと)」(『古事記』)、「大泊瀬幼武の天皇(おおはつせのわかたけのすめらみこと)」(『日本書紀』)などの「建(たけ)」「武(たけ)」と関係があるとみられること。 (3)埼玉県稲荷山古墳出土の鉄剣銘文により、471年[辛亥(しんがい)の年]が雄略天皇(獲加多支鹵)時代とみられること。 以上から、わが国の第21代の雄略天皇を、中国の南朝宋の第8代皇帝順帝準と同時代の人であるとみとめる(下のパラレル年代推定法の表を参照)。 そして、雄略天皇から n代さかのぼった天皇は順帝準から n代さかのぼった中国の皇帝と、大略同時代の人と推定することにする。 中国の皇帝については、史書の「帝紀」などに、くわしい記載がある。下のパラレル年代推定法の表の中国がわの、皇帝の在位期間データは、しっかりとしたほぼ確実なデータである。下のパラレル年代推定法の表は、一応それによって、はっきりとはしない日本の古代の天皇のおおまかな活躍年代を推定する方法である。
■日本、中国の天皇・皇帝・王の在位年数
上の図の99天皇ののべ在位期間は、1454年間。
上のパラレル年代推定法の表をみれば、箸墓古墳築造の年代(崇神天皇の時代)を卑弥呼の時代にもって行くのは、とうてい無理である。 津田左右吉説よりも、新井白石の「神は人なり」説、あるいは、「神話史実主義(エウヘメリズム)」をとったほうが、ずっと自然な説明ができる。 紀元前300年ごろに、シチリア島に生まれたとみられる神話学者、エウヘメロス(Euhēmeros)は、神話は、史実にもとづくとする説をたてた。 第二次大戦後のわが国では、津田左右吉流の立場から、神話と歴史とは峻別すべしということで、エウヘメリズムは、批判の対象とされることが多かった。しかし、エウヘメロスの考えは、シュリーマンの発掘によって、実証された部分があるともいいうる。 そもそも、「事実」や「史実」の、神話化や伝説化は、古代においては、容易におきうることである。「史実」と「神話」の峻別は、原理的に不可能である。神話をすてれば、それとともに史実も捨てることになりかねない。
■「世代差による年代間隔」と「在位期間」とは異なる
その前は5代続いた例が、平安時代の第71代後三条天皇からと、戦国織豊時代の第102代後花園天皇からと、江戸時代の第112代霊元天皇からの3例である。(下図参照) それなのに、伝承時代は第1代神武天皇から第13代成務天皇までの13代と続いている。
この例から、平安時代の第71代後三条天皇から崇徳天皇までのつながりを詳細にみると、下記となる。 このように、白河天皇は没するまでに、子供の堀川天皇(8歳で即位)、孫の鳥羽天皇(5歳で即位)の後見役となっている。白河天皇の存命中に3代の天皇が即位していったことになる。 だから、天皇の一世、二世で考えるより、天皇の一代、二代で考える方が良い。
■代数情報は、父子関係情報・兄弟関係情報よりも信頼できる 時代の古いところで、その異なりは大きい。しかも、『日本書紀』と『三国史記』とは、それぞれ文献としての長所をもっている。すなわち、つぎのとおりである。 (1)『日本書紀』の成立は、720年である。『三国史記』の成立は、1145年である。『日本書紀』のほうが、『三国史記』よりも、400年以上はやく成立している。すなわち、古い情報をとどめている可能性が大きい。 (2)『三国史記』は、地元の朝鮮で成立した文献である。外国の史書『日本書紀』の記事よりも、伝聞的要素が少ないはずである。 考古学者の笠井新也は、つぎのようにのべている。 山路愛山(やまじあいざん)は、その力作『日本国史草稿』において、このことに論及し、『直系の親子が縦の線のごとく相次いで世をうけるのは、中国式であって、古(いにしえ)の日本式ではない』。それは、『信ずべき歴史が日本に始った履中天皇以後の皇位継承の例を見ればすぐわかる』『仁徳天皇から天武天皇まで通計二十三例のあいだに、父から子、子から孫と三代のあいだ、直系で縦線に皇位の伝った中国式のものは一つもなく、たいてい同母の兄弟、時としては異母の兄弟のあいだに横線に伝って行く』『もし父子あいつづいて縦に世系の伝って行く中国式が古の皇位継承の例ならば、信ずべき歴史が始ってからの二十三帝が、ことごとくその様式に従わないのは、誠に異常なことと言わなければならない。ゆえに私達は、信ずべき歴史の始まらないまえの諸帝も、やはり歴史後と同じく、多くは同母兄弟をもって皇位を継承してたであろうと信ずる』と喝破(かっぱ)しているのは傾聴すべきである。」(「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫命」『考古学雑誌』第十四巻、第七号、1924年【大正十三年】四月、所収) 慶応大学の教授であった橋本増吉、大著『東洋史上よりみたる日本上古史研究』(東洋文庫、1956年刊)のなかで、つぎのようにのべている。 笠井新也は、邪馬台国問題に関連して、卑弥呼を「わが古代史上のスフィンクス」と呼び、およそつぎのようにのべている。 「思うに、『魏志倭人伝』における邪馬台国と卑弥呼との関係は、たがいに密接不離の関係にあり、これが研究は両々あいまち、あい援(たす)けて、初めて完全な解決に到達するものである。その一方が解決されたかに見えても、それは真の解決とは言いがたいのである。たとえば錠と鍵との関係のごとく、両者相契合(けいごう)[割符(わりふ)のあうようにあうこと]して初めてそれぞれ正しい錠であり、正しい鍵であることが決定されるのである。」(「卑弥呼の冢墓と箸墓」〔『考古学雑誌』第三十二巻第七号、1942年7月〕) 笠井新也の説 「パラレル年代推定法」によれば、魏の国の斉王芳が、卑弥呼、天照大御神の三者の年代が、ほぼ正確に一致する。かつ、卑弥呼と天照大御神とのあいだには、ともに女性であるという一致がみられる。
以上のべてきたように、卑弥呼は神話時代の天照大御神の時代にあたる。崇神天皇の時代に構築された箸墓古墳が卑弥呼の墓であることはありえない。百年以上年代が違っているとみるべきである。
|
2.邪馬台国探究のための方法について |
■邪馬台国探究のための方法について 「夷守」という地名は、『延喜式』にも現在の博多の東方付近の官道沿いに「夷守駅」が記載されていて、平安時代にも都からの遠方を認識・記憶していたようです。また、第12代景行天皇の九州巡行の際に訪れた襲(そ)の国との国境、現在の小林市に「夷守」が置かれていましたが、これは大和の地からは最南端の地の防衛拠点の跡で、肯(うなず)けられる話です。 この記事での指摘は、古代の日本では、「と]という音には甲類の「と」と乙類の「と」の区別があった。「山門(やまと)」と「ヤマト(大和)」とは違うとしている。 また、「ひなもり」は、都から離れた地域で、邪馬台国が福岡県の甘木(あまき)、朝倉、夜須(やす)あたりであれば、対馬国、一大(壱岐)国、奴国、不弥国に夷守があるので、近すぎるとしている。 この指摘は、部分的なところだけを見て指摘している。 『時代別 国語大辞典 上代辺』(三省堂刊)に「ひなもり」が記載されている。 上記、『時代別 国語大辞典 上代辺』から、「ひなもり」は、 大平氏のしてきは、「山門(やまと)」と「ヤマト(大和)」で甲類と乙類の違いを指摘し、「ひなもり」では、『古事記』と『魏志倭人伝』での甲類と乙類の違いを知らないようである。この矛盾をどう考えるか。 古代では甲類と乙類の違いについて、厳密性に疑問があるところもあるので、甲類と乙類だけを問題にすることもできないと考えられる。 「またひなもり」は都から離れている必要があるとしているが、時代によって距離感が違うと考えられる。 「この実地踏査によっていえることは、例えば魏使が佐賀県の呼子港に第一歩を印したとして、陸行一月では、せいぜい佐世保市あたりまでしか行けない、ということを確認できたのが実情である。」 「私は言いたい。『唯(ただ)の一日で良いから、私と同じ体験をしてから意見を述べてくれ。』と。」 「現実に『歩く』という実験を伴わずに思考すれば、どんな人でも、『陸行一日の距離』を大き目に算定するということである。ところで、解り切っていることでありながら、実験を伴って、毎日毎日、連続歩行を続けたうえで、もう一度『陸行一日の距離』を算定すると、これは、想像以上に数字が小さくなってしまうのである。このこと自体、私は多くの協力者や学生と行動をともにして確認しているのである。」 「普通一般の人は、『万歩計』という小計器が普及していることでも解るとおり、よほど努力しても毎日毎日万歩を歩き続けることは困難なのである。普通一般の人が普通に長距離を歩く場合には七十五センチより歩幅は若干狭いといえる。すなわち、一日行程は連日歩行な場合七キロぐらいではなかろうか、ということを『万歩計』使用経験者は納得するのではないであろうか。これとても一般の道路やゴルフ場のように整地されている平地を歩く場合である。」(以上、梓書院刊『季刊邪馬台国』35号所載「実地踏査にもとづく『倭人伝』の里程」、1988年) たしかに、ふつうの人が、ふつうに歩き続ける距離を考えるべきであって、陸軍の行軍で進むような距離を考えるのは、適切でないともいえる。 台湾の学者、謝銘仁氏の見解 「水行十日、または、陸行一月(水行十日、陸行一月とは、同じ旅程を、二とおりの形で表現したとみる。水行十日と陸行一月とは、orでつながると考える)。」 謝銘仁博士は、このいずれの読みかたも、違っているであろうとする。 「この日程記事は、先に水路を『十日』行ってから、引き続いて、陸路を『一月』行ったという意味ではない。地勢によって、沿海水行したり、山谷を乗り越えたり、川や沼地を渡ったり、陸路を行ったり、水行に陸行、陸行に水行をくり返し、さらに天候や何かの事情により進めなかった日数や休息・祭日その他の日数も加算し、卜旬の風習も頭に入れて、大ざっぱながらも、整然とした『十日』『一月』で表記したのであろう。」 つまり、魏使の道程には、水行の部分、陸行の部分、さまざまな部分かあり、その水行の部分を合計すれば、「水行十日」となり、陸行の部分を合計すれば、「陸行一月」となるという意味であるとする。「水行十日、陸行一月」は、かかった総日数であって、実際に旅行し、進みつづけた日数ではないとする。
また、「不弥国」の比定地としてはつぎの二つが有力である。 このように、いろいろな観点から議論すべきである。
|
| TOP>活動記録>講演会>第401回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |
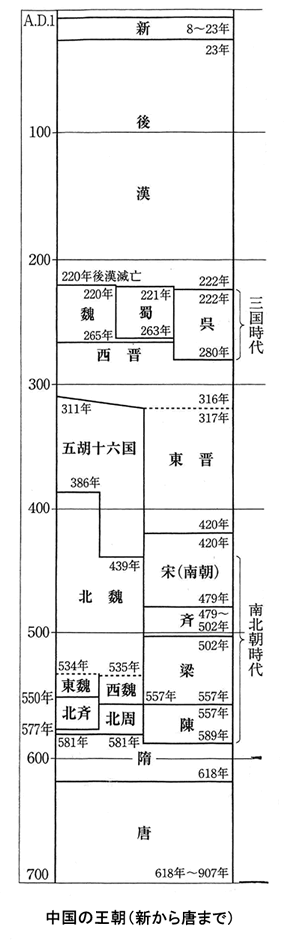 倭の国(日本)は、卑弥呼の時代に、中国の魏の国と国交をもった。そのあと、西晋の国、東晋の国、南朝(江南、南中国)の宋の国など、連続する中国王朝と国交をもった(右の中国王朝の年代参照)。
倭の国(日本)は、卑弥呼の時代に、中国の魏の国と国交をもった。そのあと、西晋の国、東晋の国、南朝(江南、南中国)の宋の国など、連続する中国王朝と国交をもった(右の中国王朝の年代参照)。