| TOP>活動記録>講演会>第230回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第230回 講演会(2005.2.27 開催) | ||||
1.魏志倭人伝のテキスト
|
■ テキストの変遷
現在、私達が見る『三国志』のテキストが成立するまでには、およそ次のような変遷を経ている。
 ■ 紹興本と紹熙本(慶元本)
■ 紹興本と紹熙本(慶元本)
『魏志倭人伝』を含む『三国志』のテキストとしては、紹興本と紹熙本の二つがよく知られている。
『魏志倭人伝』に関する限り、紹興本と慶元本の違いは下表の程度で、差異は少ない。下表のうち、1と7は「紹興本」が正しく、2と5は「慶元本」が正しいとみられる。その他は判断しがたい。
このようにみていくと、ある一つの系統の刊本だけが正しくて、それと一致しない他の 系統の刊本の文字がすべて誤りである、というようなことは主張できない。 いくつかのテキストを照らし合わせて、もっとも妥当とみなされるものをえらぶ以外に方法がない。 ■ 現代のテキスト 現在、『三国志』原本の代表的テキストには次のようなものがある。
『三国志』は晋の史官陳寿によって執筆され、太康年間(280〜289)に成立したと考えられている。『晋書』「陳寿伝」には成立年代が明記されていないが、『華陽国志』によれば、呉が平定された後のこととされる。たしかに『呉志』には280年の呉の滅亡記事がある。しかし、『魏志』の成立はもっと前という説もある。 ■ 『魏志』と『魏略』の関係 『魏志』と『魏略』の記述は大変似ている。この二つの文献の関係については従来から次の三つの説がある。
翰苑や日本書紀などの諸資料での記述は以下の通り。
卑弥呼の朝貢は、景初三年(294年)の方が正しいと思われる。景初二年は、朝鮮半島の公孫氏が、まだ、魏と戦っていた時期であり、公孫氏が滅亡した景初三年に、卑弥呼が魏に使いを出したとするほうが自然である。 |
2.「朱」と神武東征伝承
|
|
■ 神武天皇の進軍経路
熊野から奈良方面に向かう神武天皇の経路を『古事記』は次のように描く。
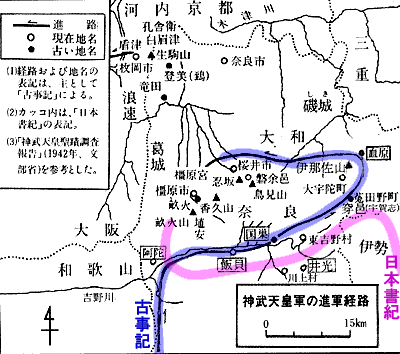 『古事記』と『日本書紀』ではルートが逆になっている。
『古事記』と『日本書紀』ではルートが逆になっている。
ポイントは「いひかひ」を「飯貝(いがい)」にするか「井光(いかり)」にするかで ある。 ■ 「朱」との関係 『古事記』には、このあたりの伝承として、井光(いひか)という地名や、尾の生えた人が現れる。 これらの伝承は、次のように、古代に珍重された「朱(辰砂)」と関係があるとする説がある。 (松田寿男博士、市毛勲氏)
宇陀の穿で、兄宇迦斯(えうかし)弟宇迦斯(おとうかし)を平らげようとしたときに、反抗した兄宇迦斯を斬り散らし、そこを宇陀の血原(ちはら)といった。 血原という地名について、市毛勲氏は『新版 朱の考古学』のなかで次のように記す。 血原とは血のように赤い色の土地という意味で、おそらく、宇陀の地域には辰砂粒が散在していた時期があり、それは血が散った結果と理解され、血原の地名起源伝承を生んだものと考えられる。 ■ 水銀鉱床と丹生神社の分布水銀鉱床は大和、四国、九州に分布する。大和、四国の鉱床近辺に丹生神社が多い。 吉野川沿いに、丹生川上神社の上社、中社、下社があり、宇陀にも丹生神社がある。 |
3.古代八母音について
|

語源的に、「あま(天、ama)」であった語の末尾に、「i」音がつき、「amai」
となり、この「mai」という二重母音が、乙類の「メ」の原形である。
語源的に、「かむ(神、kamu)」であった語の末尾に、「i」音がつき、「kamui」 となり、この「mui」という二重母音が、乙類「ミ」の原形である。 では、なぜ語尾にこのような「i」が付いたのだろうか? ■ 「準後置定冠詞イ」 体言または体言に準ずることばの後に付いて、とくに取り立てて強調するために用いられる「い」がある。このような指示強調の助詞と見られるものは、万葉集に次のような用例がある。
ヨーロッパ諸言語の定冠詞のほとんどすべては、発生的には指示代名詞から転化したものなので、上記の「い」を日本語における「準後置定冠詞イ」と呼ぶと、「準後置定冠詞イ」も、発生的には「指示代名詞イ」から来たと考えられる。 「指示代名詞イ」の用例には次のようなものがある。
「準後置定冠詞イ」が語尾に付いて、乙類の音を持つようになったとみられる名詞には、次のようなものがある。古代人の生活に密接で、特別な重要性をもち、使用頻度の比較的高い単語が多い。
しかし、日本語のまわりの、朝鮮語、中国語、アイヌ語などのすべてが、意味的に近い 「i」という語をもっているから、複合的な要因が働いている可能性もあるとのこと。 |
| TOP>活動記録>講演会>第230回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |

 豫樟
豫樟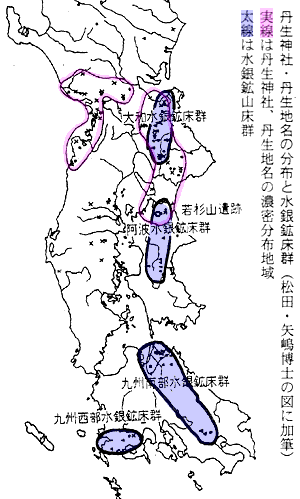 腰に尻当を紐でぶらさげた水銀採鉱者のこと。
腰に尻当を紐でぶらさげた水銀採鉱者のこと。
 (い)が身命(いのち)、亦(また)殆(またあやふ)からずや」(ああ、入鹿・・・お前の生命は、あぶないものだぞ)『日本書紀』
(い)が身命(いのち)、亦(また)殆(またあやふ)からずや」(ああ、入鹿・・・お前の生命は、あぶないものだぞ)『日本書紀』