| TOP>活動記録>講演会>第260回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第260回 講演会(2007.8.26 開催) | ||||
1.日本語の起源
|
|
■ 日本語の起源と形式
以下はだいぶ昔の新聞記事だが、現在も、安本先生の考え方はこの内容とあまり変わっていない。
日本語は、どこからやってきたのだろうか。あるいは、どのようにして成立したのであろうか。
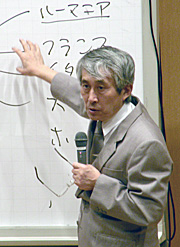
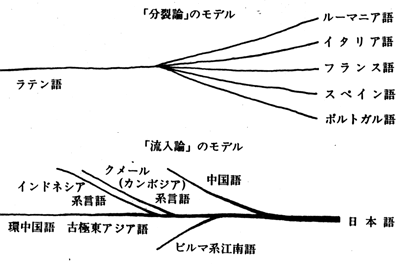
|
2.日本語の起源探求の問題点
|
|
■ 日本語の起源探求の問題点
作家の清水義範氏は、『序文』というパロディー小説のなかで、つぎのような例を多数あげて「英語の起源は日本語」と主張する学者のことを書いている。
しかし、英語をはじめとする印欧語と日本語の間に、なんらかの関係があると真剣に主張する研究者がいる。 琉球大教授だった城間正雄氏などである。 どの言語でも何万という単語を持っている。いっぽう、人間が発音し、聞き分けられる音はせいぜい数十種類である。そのため、世界の任意の言語をえらぶとき、偶然意味と音が一致する単語を二、三百は探し出すことができる。 明治時代以後の日本語の起源探求論は『序文』と同じ方法によっていたと言っても過言ではない。 学者は、みずからとりあげた2言語が、世界の任意の2言語よりも、特に関係が密接であることを「客観的に」証明しなければならない。 ■『万葉集』の謎は英語でもとける 朝鮮語と日本語は4000年前に分かれた。『万葉集』が朝鮮語で解読できることはあり得ない。 しかし、むかしから『万葉集』が朝鮮語で解釈できたとする話が後を絶たず、現在も『人麻呂の暗号』『もう一つの万葉集』など、このような趣旨の本がつぎつぎと刊行されている。 『万葉集』が、他の言語で解釈できるという話の中でとくに有名なものに、いまでも言語学者たちのあいだで語り草になっている『万葉集の謎』事件がある。 もう50年以上まえの、昭和30年(1955)のことである。フロイトの先駆的な紹介者として知られる安田徳太郎医博が、『万葉集の謎』(光文社)をあらわした。 安田徳太郎はいう。 「万葉時代の日本語が、今なお、ヒマラヤの谷底にすむレプチャ人によって語られている。」 そして、『万葉集』の歌のほとんどが、レプチャ語で、解読できるとした。 この本は、読み物としては、たしかに面白いものであった。しかし、この種の本の常として、「日本語とレプチャ語の単語で、発音(形)が似ていれば関係がある。したがって、それは、レプチャ語で解読できる。」という「未証明の前提」のもとに解読が進められていた。 いま、「レプチャ語」を、「英語」におきかえたならば、どうなるだろう。 国語学者の金田一春彦氏は、昭和31年7月号の『文藝春秋』に、「万葉集の謎は英語でも解ける」という軽妙な批判文を発表した。 「安田徳太郎博士のメスの使い方は無茶苦茶だ。あの方法でやれば日本語は地球上の何語とでも結びつく。」とリードのついたこの文章のなかで、金田一氏は、たとえば、つぎのような例をあげる。 「このへんで『万葉集』に入るが、まずこの man y  sh sh という名が、レプチャ語であるさきに英語である。 という名が、レプチャ語であるさきに英語である。
最初の many の部分は言わずと知れた『多くの』の意味、次の  は英語の ode の略で、『頒歌(しょうか)』のこと、sh は英語の ode の略で、『頒歌(しょうか)』のこと、sh は shew で、これは、今の show・・・ファッションショーのショーの古語だ。とコンサイス英和に
も載っている。 は shew で、これは、今の show・・・ファッションショーのショーの古語だ。とコンサイス英和に
も載っている。つまり『たくさんの頒歌の陳列』の意で、巻一あたりに、柿本人麻呂等の宮廷頌歌を集めてあるところから、この名が出たとすることができる。」 「この調子で本文を読めば、『万葉集』20巻は至るところ英語の氾濫だ。……」 このように『万葉集』は、英語ででも解読できてしまうのである。 |
3.明治以前の研究
|
|
■ 『日本書紀』
日本人が「外国語」を意識した時期は古い。 720年に成立した『日本書紀』には「韓語(からさひづり:朝鮮語のこと)」「訳語(をさ:通訳のこと)」という言葉が出てくるし、新羅から「習言者(ことならひひと:日本語を学習する人)」が来たという文も見える。 朝鮮語は、あきらかに外国語として意識されていたのである。 「奈良時代には日本語と朝鮮語は通訳無しでも話が通じた」などの見解が、時おり活字化される。これはたんなる俗説にすぎず、客観的な根拠を欠く。 『日本書紀』の朝鮮関係記事はかなり多くの朝鮮語を記している。「山」を「むれ」、「川」を「なれ」と記している。しかし日本語では「山」を「也万(やま)」、「川」を「箇波(かわ)」と万葉仮名で表しており、朝鮮語と日本語は明らかに異なる形をしていた。 朝鮮語の全体的な姿がかなりはっきりと浮かび上がるのは、1446年に李朝の世宗が表音文字の「ハングル(大いなる文字の意味)を、「訓民正音(くんみんせいおん)」の名で公布してからである。 これは「中期朝鮮語」である。それ以前の古代百済語、古代新羅語には実態を表したものが無い。 ■ 悉曇(しったん)文字の研究 平安時代に「悉曇研究」が盛行した。 「悉曇文字」とは、古代インドで使用されたブラーフミー(Brahmi lipi)文字から、4世紀ごろのグプタ文字を経て、6世紀ごろに発達した文字である。 「悉曇文字」は、仏教東漸の波にのり、真言宗の渡来とともに日本に伝来した。悉曇研究により、日本語の音韻について鋭い考察が行われ、その刺激によって、現在の五十音図が成立したと考えられている。 ■ 日本語化した朝鮮語 近代的な意味での言語比較は新井白石の『東雅』にはじまる。新井白石は『東雅』のなかでつぎのように述べる。
「日本には漢字音が転じたことばだけでなく、朝鮮語の転じたものも少なくない。海をワタと言うことは、わが国の太古のことばに見える。今でも、朝鮮の東南地方の人は海をパタイという。
日本語の「わた」は朝鮮語の「pata(海)」からきているとするのは正しいのであろう。これは、「w」音と「p」音が転化したと考えられるからである。 万葉集には「海」を表すことばとして「わた」と「うみ」が記されている。「わた」は同じ「海」でも「聞けわたつみの声」などの例から、遠いところの「海」を表すようにみえる。 「秦氏」の「はた」は織物から来ているのであろう。 ■ 日本語、朝鮮語、同一論 江戸時代中期の考証学者、藤原貞幹は著書『衝口発』のなかで「わが国の古代の事物、言語みな韓俗なり」と説き、古代日本の文化が、朝鮮・中国から来たことなどを述べる。 藤原貞幹の発想はのちの金沢庄三郎の『日韓両国語同系論』、江上波夫の『騎馬民族征服説』、坂口安吾の天皇の出自は朝鮮であるとする説などとつながるところがある。金沢庄三郎の『日韓両国語同系論』は、戦前の日韓併合の正当化に利用された。 戦後は、韓国の人たちが日本語と朝鮮語が同祖であると述べ、古代の日本の文化はすべて朝鮮半島から来たと主張する材料にしている。 ■ 金田一京助の警告 日本語の起源・系統の問題が、正面から論じられるようになったのは明治以後のことである。 西欧の比較言語学の手法が日本にも紹介され、アイヌ語、朝鮮語、中国語をはじめ、さまざまな言語と結びつけた議論が行われた。 しかし、印欧諸言語の場合の系統論に見られるようなはかばかしい成果が得られたとは言い難い。 今から70年ほど前の1938年にアイヌ語研究で名高い金田一京助は、それまでの日本語の起源論、系統論を要領よくまとめた『国語史系統論』を刊行した。このなかで金田一は、当時の研究についてつぎのような批判を述べている。
「ものを知らないほど、大断定ができる。」
金田一京助の『国語史系統論』を読めば、最近の日本語と朝鮮語とを結びつける論者 などは、かつての日本語と朝鮮語とを結びつける諸説よりも、研究の水準において、 かえって遥かに低いものになっていることを容易に読み取れる。 |
4.世界諸言語の中の日本語
|
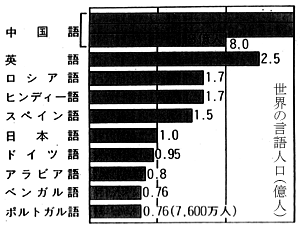 ■ 日本語は少数民族の言葉ではない
■ 日本語は少数民族の言葉ではない
日本語は日本列島以外ではほとんど話されないが、話し手の数は世界で6番目であり、世界の中では大言語と いえる。 日本で織田信長などが活躍していた1500年頃をみてみると、日本語人口は1800万人であり、フランス語は1200万人、ドイツ語は1000万人。英語はわずか500万人でドイツ語、フランス語、イタリア語より少なかった。英語はその後の植民地政策によって話し手の数が激増した。 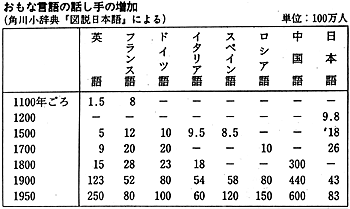 英語は表記と発音とが一致しない。イギリスがフランス系に占領されている時、公用語はフランス語で
英語は下層階級の言葉だった。そのため表記と発音が合わなくなった。
英語は表記と発音とが一致しない。イギリスがフランス系に占領されている時、公用語はフランス語で
英語は下層階級の言葉だった。そのため表記と発音が合わなくなった。
■ 日本語は多くの言語と共通 日本語は英語、中国語などと、主語−述語−目的語の順番が違うので、世界の中ではマイナーなことばと思われがちである。 しかし世界の諸言語をみると、アルタイ諸語(アイヌ語、朝鮮語、ツングース系満州語、 モンゴル語、ウイグル語、トルコ語)、インドイラニアン諸語、ドラヴィダ諸語、 ウラル諸語(フィンランド語、ハンガリー語)、チベット・ビルマ諸語など、日本語の語順と同じ言語のほうが多い。 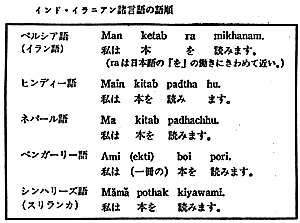
中国を中心にしてその周囲を日本語と同じ語順を持つ言語が取り囲んでいる。もともと、ユーラシア大陸の広い範囲で、日本語と同じ語順の言語が使われていたが、中国の勃興で語順の違う中国語が中国を中心に隆盛となり、周辺部に日本語と同じ語順の言語が残ったと考えられる。 各言語の母音の数を調べると、5個の母音を持つ言語が最も多い。この点でも日本語は特殊な言語ではなく、他の言語と多くの共通点を持つありふれた言語といえる。 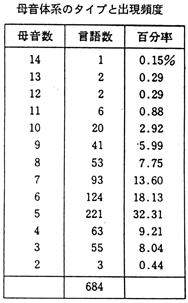
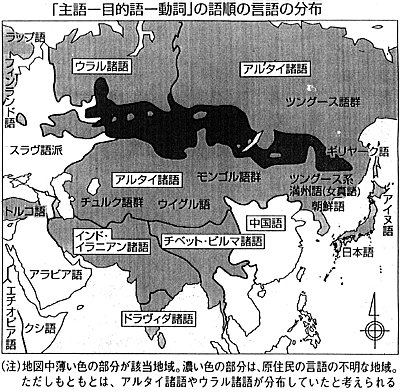
|
5.聖徳太子と物部の守屋
|
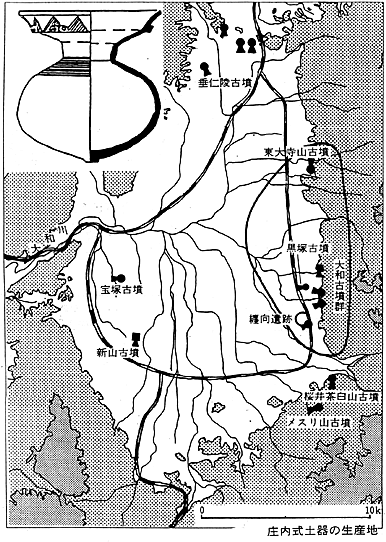 ■物部守屋の墓
■物部守屋の墓
蘇我氏と物部氏とは、仏教伝来以後、その受容の可否をめぐってたびたび争ったことは有名だが、それは小競り合いであった。 しかし585年の敏達天皇の没後、皇位継承問題を契機として対立は最後の段階に入る。 蘇我氏は、諸豪族、諸皇子連合軍によって物部氏を攻撃し、物部氏の本貫の地である河内の国渋川郡渋河の家で、物部守屋を滅ぼしてしまう。 このとき、聖徳太子は四天王に、戦いに勝利した時には四天王のために寺を建てることを誓願し、また、蘇我馬子も諸天と大神王のために寺と塔を建てる約束をした。 物部氏を滅ぼした聖徳太子が建立した寺が四天王寺であり、蘇我馬子が建てたのが法興寺(飛鳥寺)である。 ■庄内式土器 物部守屋が戦死した河内の渋川郡は、物部氏の本貫地である。ここから、庄内式土器が多数出土する。 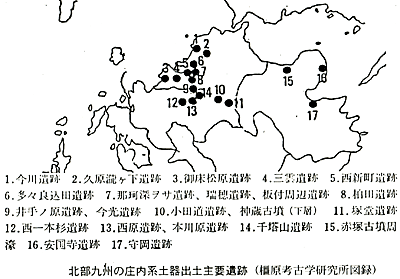 庄内式土器は器壁が薄く、煮沸効率の良い土器である。
庄内式土器は器壁が薄く、煮沸効率の良い土器である。
庄内式土器は北九州では広い地域で使われているが、近畿地方では大阪平野の八尾や東大阪あたりと、奈良盆地の纒向遺跡周辺の限られた範囲で集中的に使われている。 大阪平野の八尾や東大阪一帯は物部氏の本貫地であり、纏向近辺の磯城郡の県主が物部氏であったとされることから、この地域も物部氏に関係する地域である。 奈良と河内の庄内式土器が出土するところは、以下のように共通な地名が多い。 これらの地名の中には、九州にも共通の地名があるものがある。
|
| TOP>活動記録>講演会>第260回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |