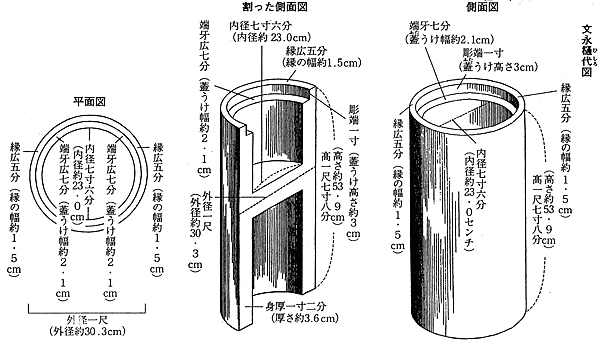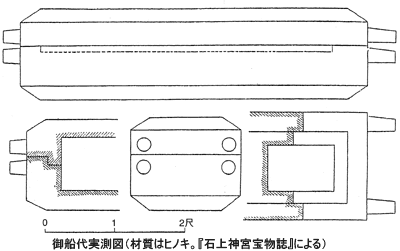| TOP>活動記録>講演会>第282回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第282回 邪馬台国の会(2009.7.26 開催)
| ||||
1.伊勢の皇大神宮(内宮)の創設
|
伊勢神宮は、天照大御神を祀る皇大神宮(内宮)と、豊受大神を祀る豊受大神宮(外宮)の総称である。
豊受大神は、伊耶那岐命の孫、和久産巣日神(わくむすびのかみ)の子とされる。食物をつかさどる神で、豊宇気毘売(とようけびめ)とも呼ばれる。 皇大神宮の創建については、『古事記』『日本書紀』に記されている。 しかし、戦後は、『古事記』『日本書紀』の内容は疑うべしという風潮が盛んになって、これらの古典に記された内容は顧みられなくなっている。 いまも皇大神宮の創建について触れた本がたくさん出版されているが、起源についてははっきりとは判らないという書き方をしているものが多い。また、何を言わんとしているのか判らないものもある。 これは、これらの書物が、『古事記』『日本書紀』に記されたことと別の解釈をしようとしているため、大変複雑な説明になったり、わかりにくい内容になっているためと思われる。 たとえば、皇大神宮は、もともと伊勢の地域にあった地方の神様であって、それがだんだん格上げされて皇室と結びつくようになったというような説明である。 このようなややっこしい解釈をしなくても、大筋においては『古事記』『日本書紀』に書いてあることを認めても良いのではないかと思う。 皇大神宮の創建については、『古事記』『日本書紀』にはつぎのように記されている。
しかし、『古事記』『日本書紀』の記事をほぼそのまま認めても、とくに大きな矛盾が生じるわけではないと考える 逆に、『古事記』『日本書紀』の記事を支持するような根拠もあるていど挙げられる。 ここでは、そのような根拠の一つとして、「御船代(みふなしろ)」の問題を取り上げてみる。 ■ 霊代(たましろ)、樋代(ひしろ)、船代(ふなしろ)
■ 「舟形木棺」「舟形石棺」の年代 「船代」と同じような形状の「舟形木棺」「舟形石棺」は、いわゆる前期古墳から出土する例が多い。たとえば、「舟形木棺」「舟形石棺」の出土例に、次のようなものがある。
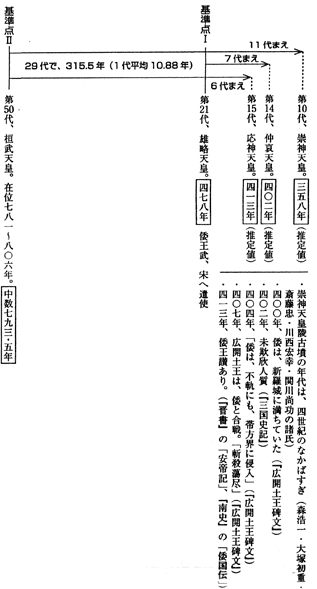
■ 皇大神宮の創建の時代 『古事記』『日本書紀』には、皇大神宮の創建は第11代垂仁天皇の頃と記される。 古代の天皇の一代平均在位年数は、確実な歴史時代に入った、第21代雄略天皇から第50代桓武天皇まで、300年間以上に渡って、約10年である。 天皇の代数をもとに一代約10年で遡らせれば、第11代垂仁天皇や第10代崇神天皇の時代は4世紀後半になる。 これは、森浩一氏、大塚初重氏、川西宏幸氏らの考古学者が、崇神天皇陵の築造年代を、4世紀の半ば過ぎとすることと整合している。 『古事記』『日本書紀』の記す皇大神宮の創建年代は、4世紀半ば過ぎの垂仁天皇の時代である。これは、前述した「舟形木棺」「舟形石棺」の行われる時期と大略あっているように見える。 すくなくとも、「御船代」の形は、5世紀後半や6世紀、7世紀ごろに主流であった棺の形とは、結びつかない。 ■ 八咫の鏡 天照大神の御霊代が八咫の鏡である。天孫降臨の際に、天照大神が邇邇芸命に与えたとされる。 崇神天皇の6年に、それまで宮殿に置かれていた八咫の鏡のレプリカを作り、これを宮殿に残して本物を外部に出し、垂仁天皇の時に伊勢の皇大神宮で祀られるようになる。 奈良県田原本町にある鏡作坐天照御魂(かがみつくりにいますあまてるみたま)神社に、レプリカを作る際に試鋳された鏡が祀られている。 この神社には三座の神々が祀られていて、右座が高天原で八咫の鏡を作った石凝姥(いしこりどめ)、左座はその父である天糠戸(あまのぬかと)神。 中座が、八咫の鏡のレプリカを制作した際に試鋳したものとされている。 そして、この鏡は、三角縁神獣鏡の内区だけのものであることが知られており、鏡を制作する際の原型ではないかと推測されている。 つまり、皇大神宮が創建され、ここで八咫の鏡が祀られるようになったのは、三角縁神獣鏡が制作されていた時代ということになる。 三角縁神獣鏡を出土するのは、4世紀型の古墳が多い。前述のように崇神天応や垂仁天皇は4世紀に活躍した天皇であり、皇大神宮が創建もそのころと考えて矛盾はない。 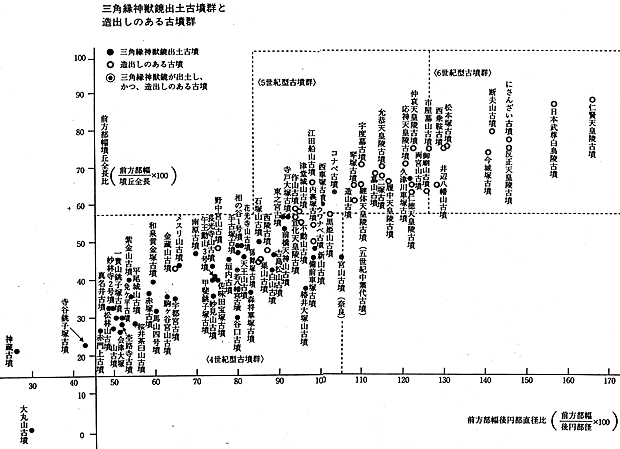
皇大神宮の八咫の鏡の正体については、次のようにいくつかの説がある。
しかし、崇神天皇がレプリカを作ったときに、元の鏡とは異なる三角縁神獣鏡を制作し、以後、宮中で祀るようになったのではないか。 4世紀後半の垂仁天皇の時代に、皇大神宮で祀ることになった八咫の鏡も、樋代の内径の変化から推定すると、のちの時代には小型の鏡に変更されたように見える。 |
2.日本語の起源再論
|
明治大学の言語学者、黒田龍之介は『はじめての言語学』(講談社現代新書)のなかで、次のように述べている。
「日本語の起源については良くわかっていない。でもときどき、そう10年に1回ぐらい『日本語の起源はこれだ!』というセンセーショナルな学説が発生する。 マスコミはすぐに飛びつくが、言語学者たちは黙っている。保守的な業界ゆえに無視しているのではない、あまりひどいので、呆れているのある。 インドのタミル語と日本語の関係を主張した大野晋の「日本語タミル語起源説」もこれと同じである。 信じられないような音韻対応を発明し、言語学を勉強した人はみなビックリしたが、ご本人は自信満々であった。 まじめなインド言語学者が何人か反論していた。でも、こういう真面目な意見は面白くないのか、マスコミはあまり取り上げなかった。」 大野晋の説は、研究の方法に大きな問題がある。2つの言語から似たような単語を集めてくるだけではなんの証明にもならない。 たとえば、「名前」と「name」のように、膨大な数の単語の中で、偶然、意味と音が似たものが見つかることはけっこうあるからである。 このようなやり方では、世界の任意の言語を日本語と結びつけることが出来てしまう。 ■ 言語年代学 言語年代学の基本的なことについては第265回講演会で詳しく述べた。同系の2つの言語の近さの度合いを測定してこれらがいつごろ分離したかを研究する。 言語年代学では基礎語彙をとりあげる。基礎語彙とは、文化的な言葉ではない単語。「手」「鳥」などのように、いかなる未開の民族でも持っている単語のことである。 基礎語彙を活用して、なんらかの方法で2つの言語間の距離を測定する。語頭の音は時間が経っても変化しにくいことに着目し、基礎語彙の語頭の音が一致するかどうかを調べるのは最も単純な方法の一つである。 下図(クリックで拡大)は、このような方法で、抽出した200語の基礎語彙をさまざまな言語で比較した結果である。縦軸は200語の基礎語彙の語頭音の一致率であり、横軸は、言語間の距離に基づいて2つの言語が分離した年代を求めた結果である。 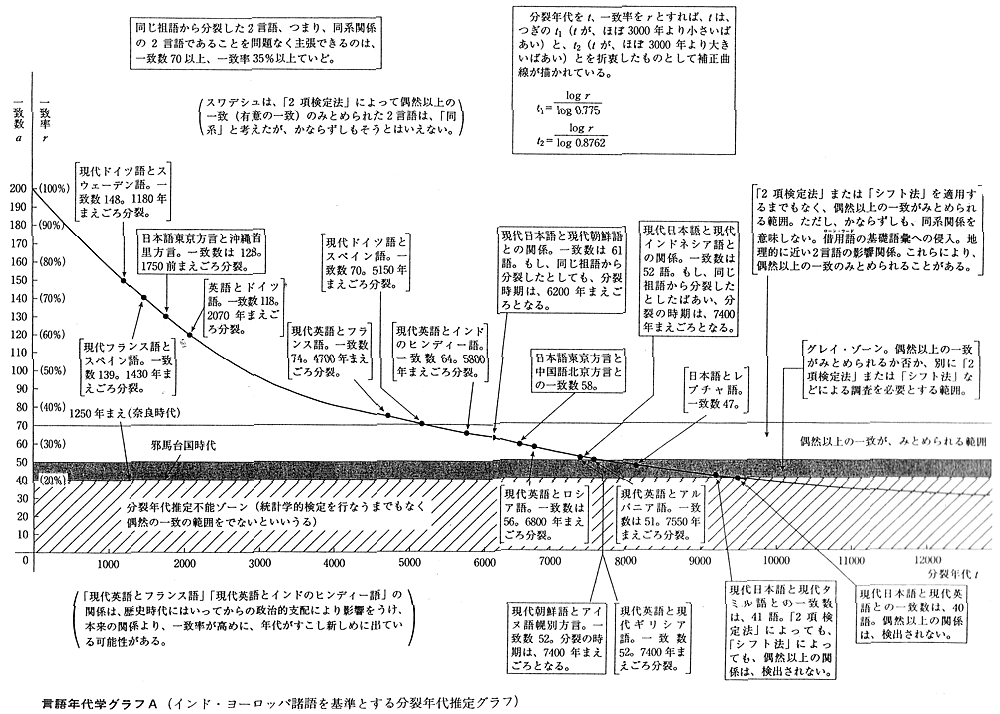
主な言語間の距離、分離した年代を下表に示す。 なお、同じ祖語から分裂した2言語、つまり、同系関係の2言語であることを問題なく主張 できるのは、200語の基礎語彙の場合、一致数70以上、一致率35%程度以上である。
現代日本語と中国語北京方言は、言語的にはまったく別系統であるが、文化的つながりから言語の共通性が生まれた可能性がある。 なお、日本語とタミル語の一致数は41であり、偶然以上の関係は検出されない。これは現代日本語と現代朝鮮語の一致数61よりもはるかに小さい。日本語との関係を見るならば、タミル語の前に朝鮮語を検討しなくてはならない。 ■ 日本語の起源・形成のプロセス 日本語とポリネシア語派、日本語とインドヨーロッパ諸言語との比較や関連についての詳細な分析は、第261回講演会の内容とかなり重複するので、そちらを参照下さい。 安本先生の考える日本語の形成プロセスは、
異なる系統のいくつかの言語が、日本列島に流れこんで、融合し、一つの大きな流れになるという「流入論」によって説明できる。 |
| TOP>活動記録>講演会>第282回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |