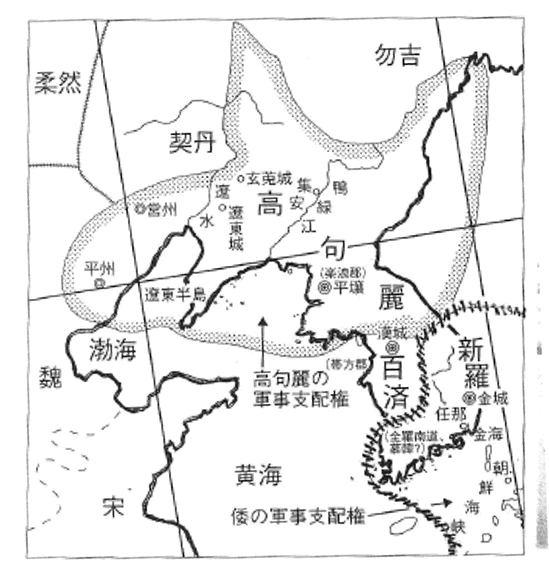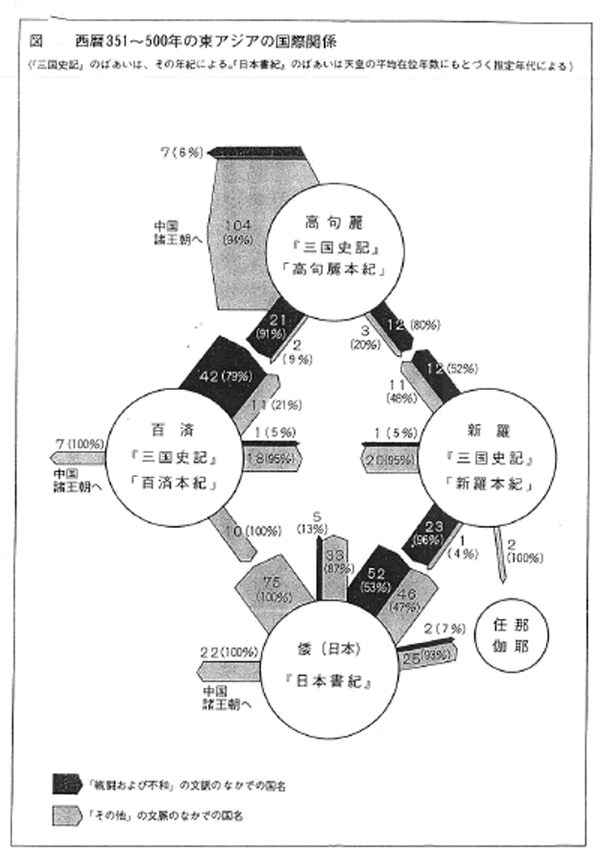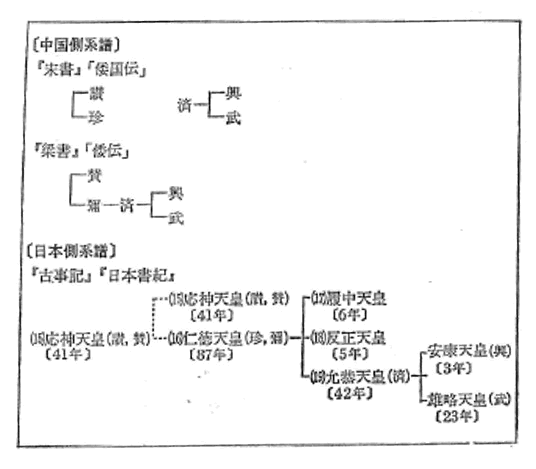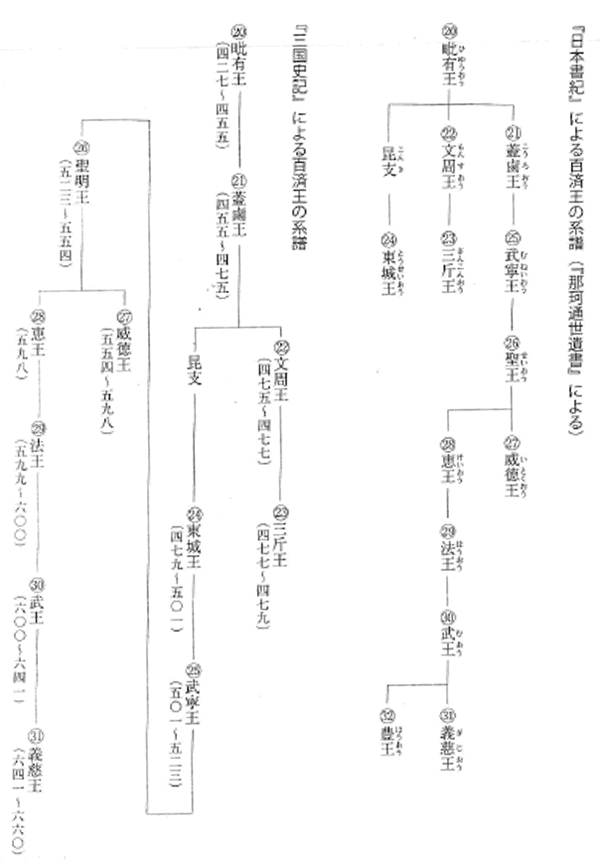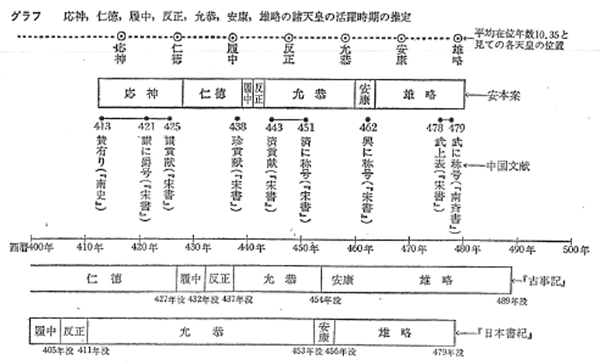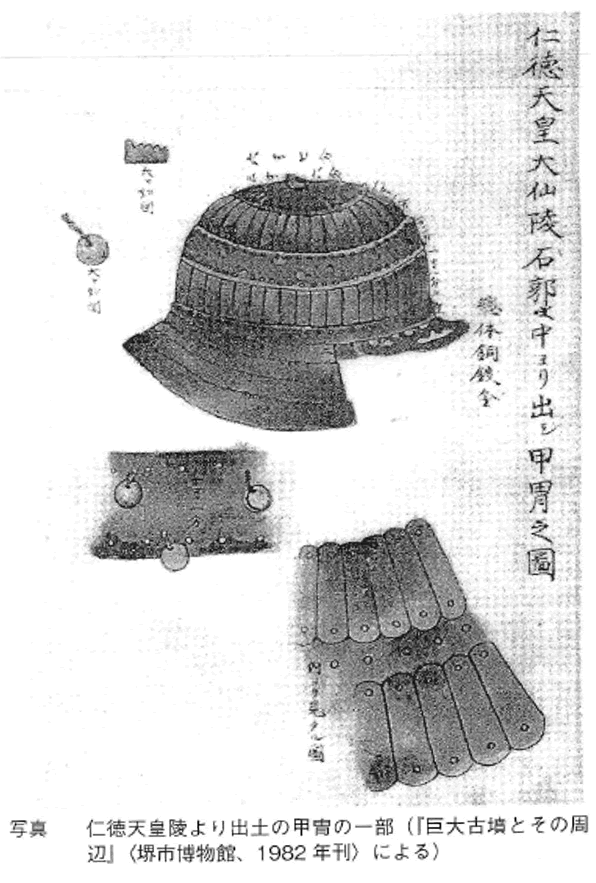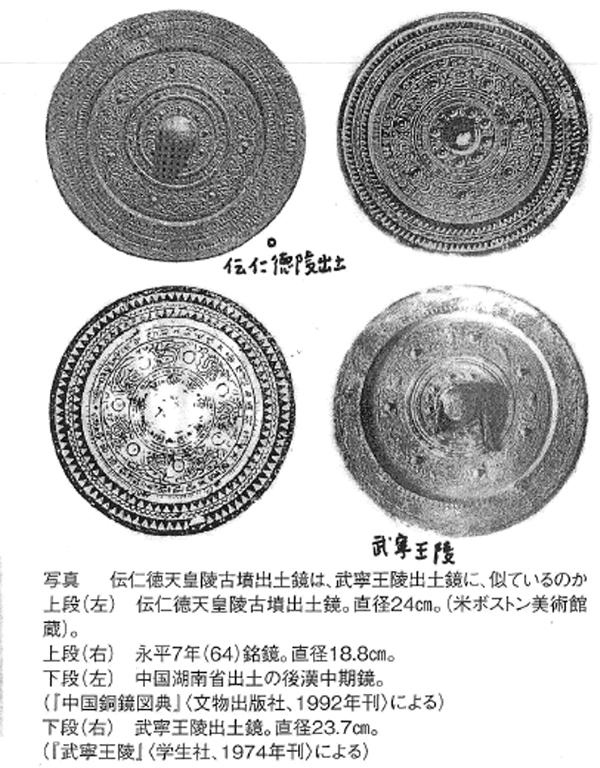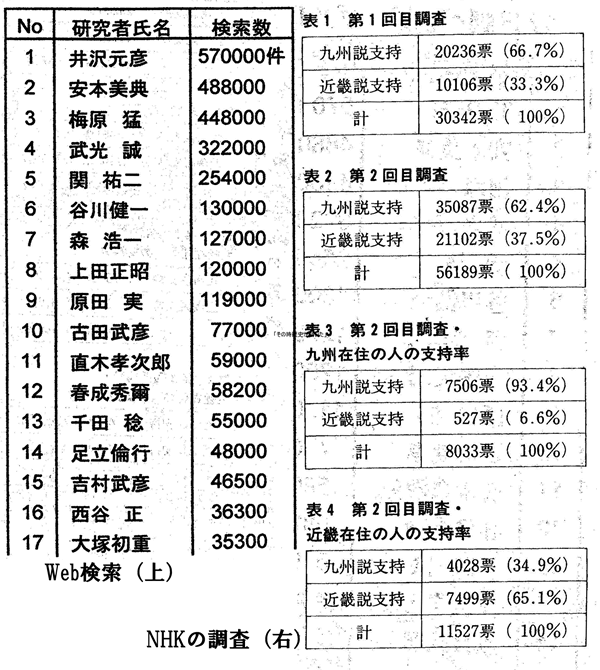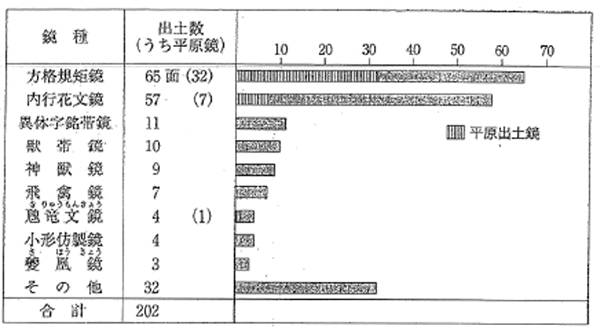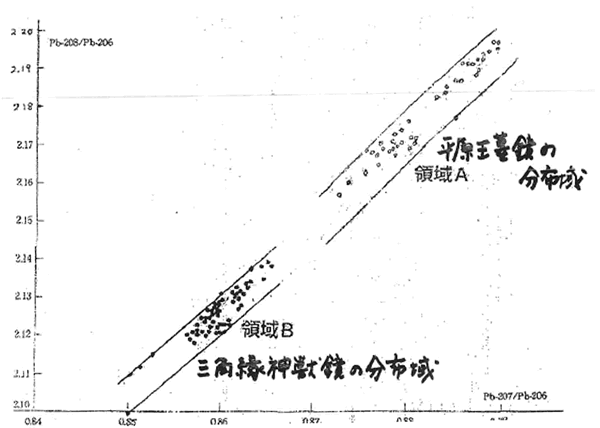| TOP>活動記録>講演会>第301回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第301回 邪馬台国の会 (2011.8.21 開催)
| ||||
1.倭の五王の時代
|
天皇1代約10年説の根拠となる天皇の基準点として、基準点Ⅰとする第21代雄略天皇が478年ごろとなり、第14代仲哀天皇の頃が402年ごろとなる。5世紀の始まりが仲哀天皇となる。仲哀天皇の皇后が神功皇后で、三韓征伐の伝承がある。 神功皇后が、新羅を征討したとする伝承は、『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』など主要な文献が、こぞって記し、また、『続日本紀』『古語拾遺』『新撰姓氏録』など、平安時代以後の諸文献も、昔あった事実であると受けとった書き方をしている。また、とくに九州を中心とする諸社の縁起、各地の地誌、あるいは伝記において、神功皇后と結びつけられたものは、きわめて多い。 また宋は倭王を「使持節・都督倭新羅任那加羅秦韓(辰韓)慕韓(馬韓)六国諸軍事・安東大将軍・倭国王」(『宋書』)としており、日本が新羅を支配下においているように見える。 また、高句麗の広開土王の碑文でも
前回述べた『宋書』の倭国伝でも、順帝に倭王武が東は毛人、西は衆夷、海を渡って海北を平らげたと奏上している。これは景行天皇の時代の日本武尊の活躍、神功皇后の新羅征討とを表したように見える。 国内の文献、海外の文献と内容の表記についてつじつまが合っているように見える。 4~5世紀の東アジアの国際関係をまとめると下記のようになり、
倭の五王の系譜について
また、『日本書紀』による百済王の系譜と『三国史記』による百済王の系譜を比べると王の代は合っているが、親子兄弟関係は合っていないところがある。
天皇の代の長さを記録から調整して、一代約10年説で天皇の代の長さを推定する。『古事記』、『日本書紀』で天皇の没年が違うが、これらを加味して、安本案を作成し、これに中国の文献の表記による譛、珍についてあてはめると、応神天皇が譛、仁徳天皇が珍として考えられる。
|
2.仁徳天皇陵の盗掘
|
天皇陵は古くから盗掘にあっている。今回は仁徳天皇陵についての考察。 仁徳天皇陵は5世紀中葉から後半にかけて築造されたものと見られ、全長486mで、最大の前方後円墳である。
これは税所篤(さいしょあつし)[当時、堺県令(知事)]が県令の権限で盗掘したとの説があるが、税所は台風が来て前方部が崩れて、そこを修復したら、出てきたといっている。 一方、ボストン美術館に仁徳天皇陵から出て来たと伝えられている素環刀の柄頭と鏡がある。
森浩一氏はこの柄頭と鏡は百済の武寧王陵から出土した柄頭と鏡に似ている。武寧王は仁徳天皇より時代が新しいので、この古墳は仁徳天皇よりもっと新しい天皇の古墳ではないかと述べている。 しかし、ボストン美術館の柄頭と鏡は仁徳天皇陵から出て来たとははっきり言えない。 |
3.邪馬台国はどこにあったと『思うか』
|
| TOP>活動記録>講演会>第301回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |