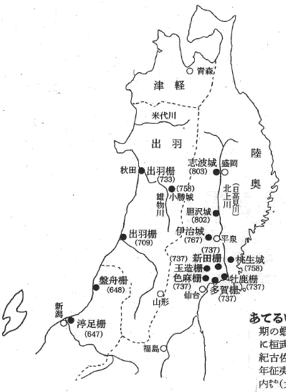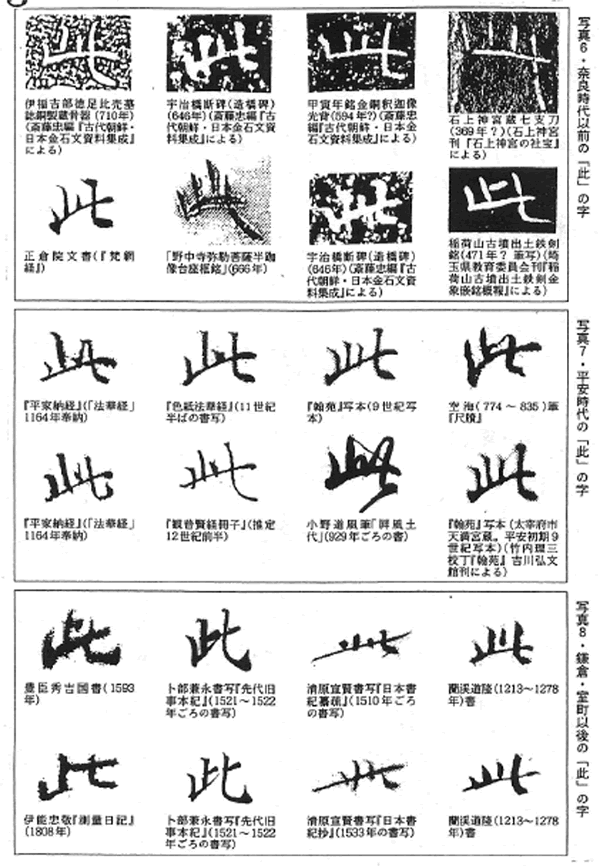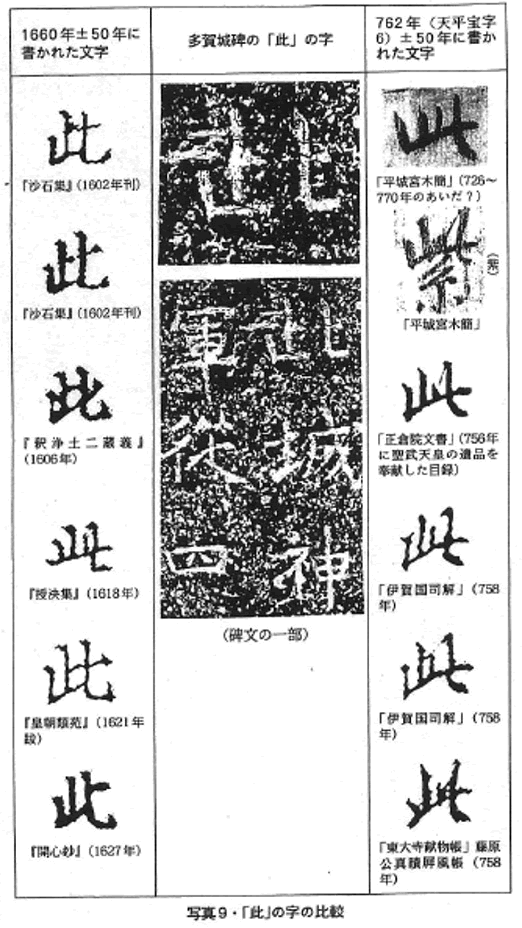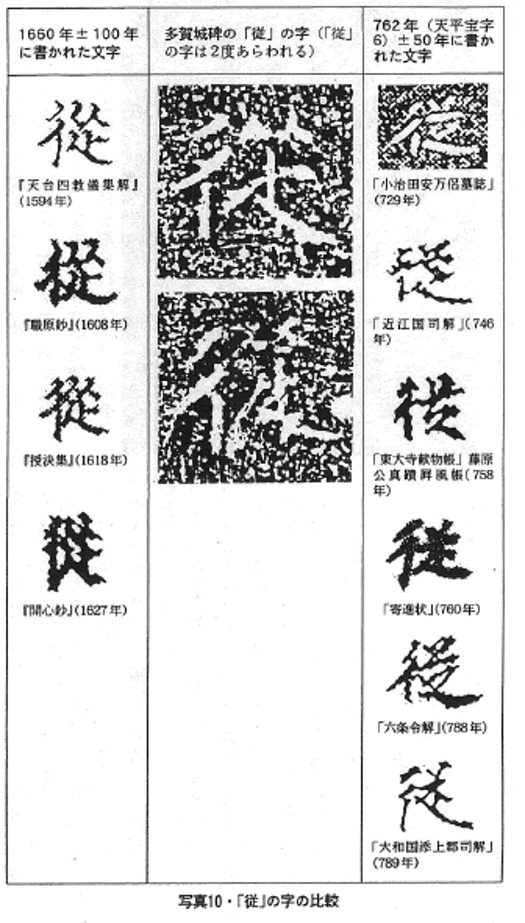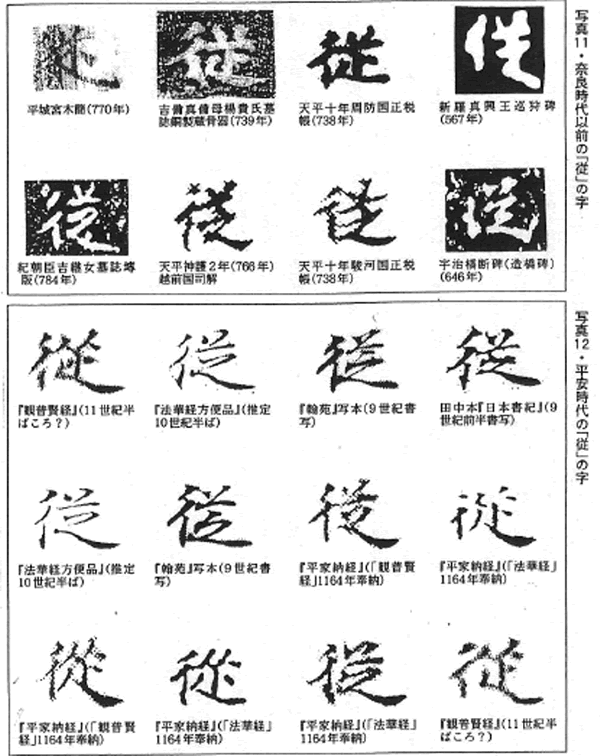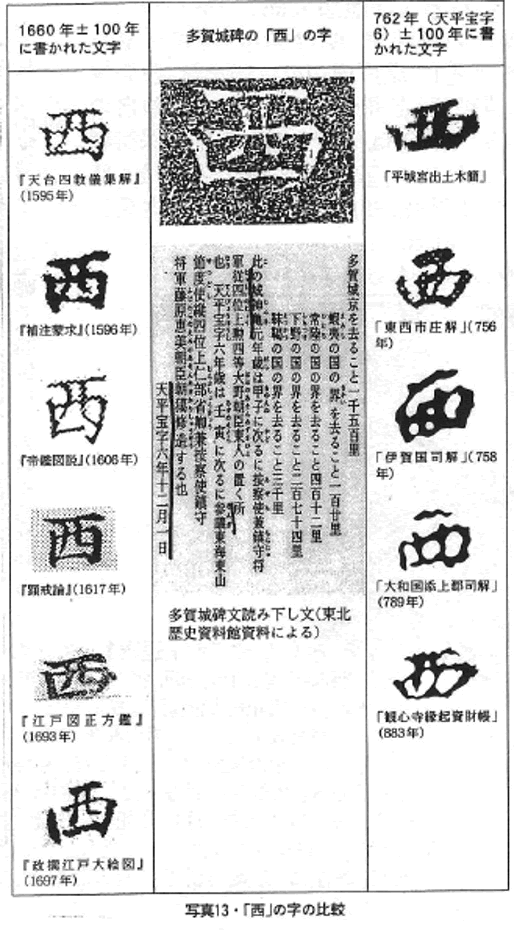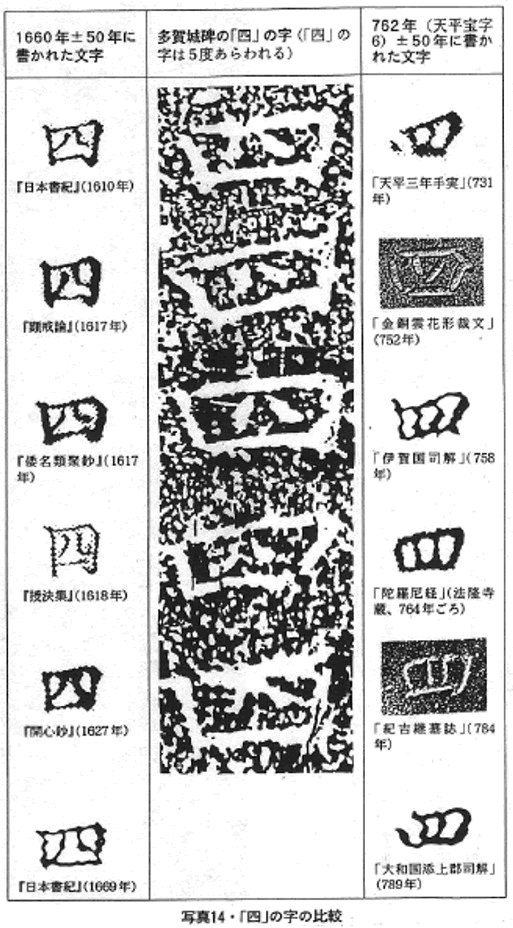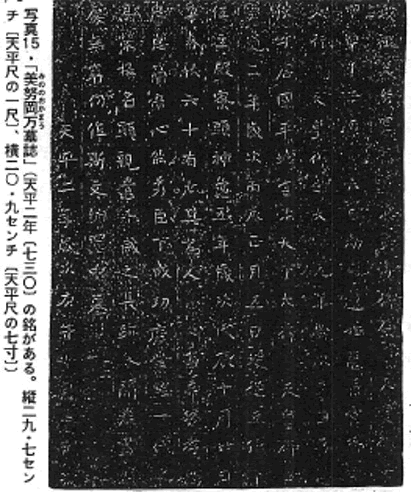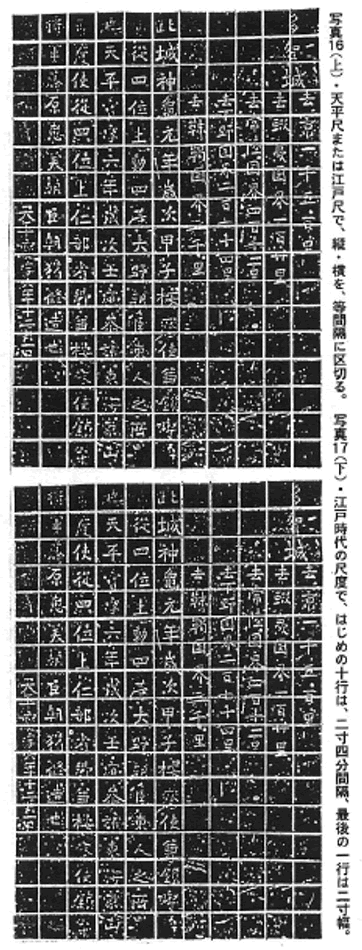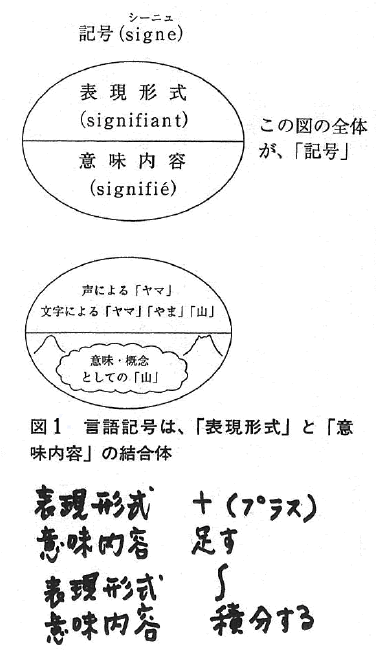邪馬台国論争のもとになる考え方として、基本的なものの考え方について述べる。
■認識論
(1)素朴実在論
「外の世界は自分が見るか見ないかに関係なく存在しているはずだ。それを見たり、聞いたりしているのはその模写である。」とする考え。つまり外界が意識から独立に存在していると見、意識内容はそれの模写と考える立場で、唯物論に近い。
マルクス・エンゲルスは信念的唯物論だが、素朴実在論の考え方は仮説的唯物論となる。
(2)フッサールの現象学
唯物論に対する考えの一つで、「外部世界が存在するかどうか義論することをやめ判断を中止する。(エポケー[判断中止])」とする考え。
哲学や諸学の現実な基礎をすえるために、一切の先入観を排して意識に直接に明証的に現れている現象を直観し、その本質を記述するフッサールの方法。彼はそれに到達するため日常的な見方の土台にある外界の実在性について判断中止を行い、そのあとに残る純粋意識を分析し記述した。
しかし、一切の先入観を排することは可能か?現実は先入観に基づいていることが多い。素朴実在論の方がよいのではないか。
素朴実在論の立場に立った場合、私達は、この世の中のさまざまな事象について、「認識」をする。この外部世界を「認識」するとは、何であるかについて、おもに二つの立場をあげることができよう。
(A)反映論
「外部世界は存在しており、それを脳に写つしているだけで、それを認識しているにすぎない」とするもので、
「反映論」は、おもに、唯物論の学者たちによってとなえられている。唯物論の学者たちは、私たちの認識、すなわち、感覚とか、概念などは、客観的な存在の反映、あるいは、模写であるとする。
そして、感覚から概念、判断、推理への移行を、反映過程の深化発展であると考える。すなわち、感性から知性への移行を、反映の深化とみなす。とくに、科学的な研究などでは、反映は、実験、調査、分析など、研究対象に対する人間の能動的な働きかけ、実践によってのみ得られるとする。
たえまない実践によって、対象についての反映は、たえず是正されていく。表面的な現象の記述から、対象がどのようなものでできあがっているかという実体的な知識へ、さらに、それらが、相互にどのように働きあって発展し、運動しているかという本質的な知識へと、しだいに内面に向かってすすんでいく。このようにして、対象への接近は、たえまなく進み、より深く、より近似的に、より全体的に、対象の本質にせまっていくことになるとする。
(B)地図論
「地図論」は、おもに、コージプスキー(Korzybski,A.1879~1950)など、アメリカの、一般意味論の学者たちによってとなえられている。一般意味論学者たちは、私たちの認識は、いわば、「地図」のようなものであると説く。「地図」によって、私たちは、A地点からB地点まで行くことができる。それと同じように、「地球は、まるい」という、外界についての認識(一種の地図)にしたがって、行動し、コロンブスは、アメリカを発見した。
はじめ、人びとは、「地球は平らである」と考えていた。これも、一つの素朴な地図である。人間の活動の範囲がせまいばあいは、そのような素朴な地図でも、とくに支障はもたらされなかった。
人間の知的、実際的な活動範囲がひろがるとともに、「地球はまるい」という、より正確な地図、あるいは認識が、しだいに人びとのあいだに浸透していった。
そして、さらに現代では、「地球は、球に近いが、北にややとびだしており、西洋ナシ形をしている」というあらたな地図がえられている。
物理学上の法則も、反映の一種であり、「地図」のような働きをもつ。その地図によって、ある結果を予測することができる。ある結果に行きつくことができる。
たとえば、万有引力の法則という外界についての「認識」(一種の地図)によって、人工衛星を打ちあげるのには、どのていどの初速度を与えればよいかなどを知ることができる。外界についての「認識」が誤っていることは、誤った地図が与えられたことにたとえることができる。
このように、地図は、ときに誤っていたり、杜撰であったり、ゆがんでいたりすることがある。人問の認識が進むにつれ、地図は、より正確なものとなったといえるであろう。 また、「地図」には、ある一地域のみを拡大し、その地域のみをくわしくえがいたりすることができるが、私たちの「認識」も、あるせまい範囲の問題だけをとりあげて、くわしく示しているばあいがある。
人間の思考の本質は、地図をつくること、すなわち、マッピング(mapping)にあると考えられる。いわゆる知的能力にすぐれているとは、マッピングの能力にすぐれていること、また、頭の中に、多くの地図が、うまく整理されてはいっていること、といえるかも知れない。それは、与えられたある命題(インプット)から出発するとき、どのような結果(アウトプット)が得られるかということを、それらの地図によって、的確に予知することができることを指すといえよう。学習するとは、既存の地図を頭の中におさめていくことであり、知的な創造をするとは、新たな地図を、つくることを意味する。
二つの方向から掘りすすめられたトンネルが結びあわされたとき、一つのトンネルとなる。それと同じように、インスピレーションとは、頭の中で、掘りすすめられていた思考の回路が、無意識のうちにも、さらに掘りすすめられ、回路が突然つながって、一つの回路となり、全体の様子が簡明にはっきりとつかめる思考の地図ができあがった状態になぞらえることができよう。
たとえば、数学の問題を解くばあいを考えてみよう。数学の問題を解くとは、ある前提から、ある結論をみちびきだすことを意味する。 (安本美典『集中力をたかめる』[福村出版 1987年刊]
■科学とはなにか
できあがった近代科学の姿をみると、少なくとも二本の太い支柱に支えられている。その一本は数学を手段として自然を解釈していこうとする理論的思考、もう一本は真か偽かの決定を実験的事実にゆだねるという行動的態度である。どちらが欠けても近代科学とはいわれない。
日本には他の多くの文化圏と同様に、近代ヨーロッパにおけるような科学は生まれなかった。数学で世界を写しとって理論を整え、実験観察で真偽を決定ずるという鮮明な姿の近代科学は、ヨーロッパ固有の産物であった。
(紫藤貞昭著『科学がわかる本』[日本実業出版社、1980年刊])
では、科学と非科学の境界はどこにあるのだろう?
実は、ここが科学の一番大事な部分、まさにキモといえるところなのである。答をごく簡単にいえば、科学とは『誰にでも再現ができるもの』である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが『科学的』という意味だ。ある現象が観察されたとしよう。最初にそれを観察した人間が、それをみんなに報告する。そして、ほかの人たちにもその現象を観察してもらうのである。その結果、同じ現象をみんなが確かめられたとき、はじめてその現象が科学的に『確からしいもの』だと見なされる。どんなに偉い科学者であっても、一人で主張しているうちは『正しい』わけではない。逆に、名もない素人が見つけたものでも、それを他者が認めれば科学的に注目され、もっと多数が確認すれば、科学的に正しいものとなる。
このように、科学というのは民主主義に類似した仕組みで成り立っている。この成り立ちだけを広義に『科学』と呼んでも良いくらいだ。なにも、数学や物理などのいわゆる理系の対象には限らない。たとえば、人間科学、社会科学といった分野も現にある。
そこでは、人間や社会を対象として、『他者による再現性』を基に、科学的な考察がなされているのである。
まず、科学というのは『方法』である。そして、その方法とは、『他者によって再現できる』ことを条件として、組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また、再現の一つの方法として実験がある。(統計的調査)
現代社会は民主主義を基本として動いている。大衆が方向性を決める。一部の専門家がすべてを決めることはできない。だとすると、大勢の人が非科学的な思考をすれば、それが明らかに間違っていても、社会はその方向へ向かってしまう。
(森博嗣著『科学的とはどういう意味か』[幻冬社2011年刊])
■「数字」や「数学」で表現する意味
次に、「数字」や「数学」で表現する意味について考えよう。
正確な事実や情報を、集約して表現するものに、「数字」がある。
情報伝達型の文章では、「数字」で表現できるものは、できるだけきちんと調べて、「数字」で表現したほうがよい。「過日は」「先日は」よりも、「9月12日には」などのように、「数字」で表現する。「しばしば」「ひじょうに稀である」などの表現よりも、「9月のデータでは、126個中11個(8.7%)」などと表現する。そのほうが、あいまいさがなくなる。そして正確で、きちんとした文章であるという印象を、与えることができる。西洋史学者の会田雄次は、著書「合理主義」(講談社現代新書)で、次のように述べている。「合理主義的なものの考え方をつきつめると、いっさいを量の変化において考え抜こうという精神です。」数量をもとにして考える方法が、すべての科学を満たすとは、もちろん、いえないであろう。しかし、人間の知識のいくつかは、数がそこにある役割をはたすにいたって、はじめて、科学の名に値するようになったことも事実である。
では、数を適用しうる対象と、適用しえない対象とは、何か本質的な違いがあるのであろうか?
人文科学関係の方が、しばしば述べる、数についての誤った意見がある。すなわち、「量的なものは数であらわしうるが、質的なものは数であらわしえない」
「現代科学は、研究対象の量的な面ばかりに注目し、そのため、研究対象の質的な面は無視され、世界はゆがめられて描写されている」などの意見である。
しかし、量的なもの、あるいは質的なものは、対象にはじめからそなわっているものではない。現象それじたいは、数値的なものを何も含んでいない。
温度にしても、速さにしても、明るさにしても、それはもともと質的なものである。それを今日、数字で表現して、量的処理を行って、だれもあやしまない。数量的概念は、対象に数を適用するという、人間の積極的な行為によって、はじめて生じている。
質的なものと、量的なものとの違いは、私たちの概念体系のなかでの違いである。あるいは私たちの言語のなかでの違いである、ということもできよう。
私たちがとり扱おうとしている対象じたいが、質的なものであるのか、それとも量的なものであるのか、ということをたずねるのは、あまり妥当ではない。その研究対象を分析し、記述する言語が、量的な言語であるのか、量以前の質的な言語であるのか、ということをたずねるのであれば、意味がある。
数量による記述、数式による記述が、しばしば、「科学の世界」での言語になる。「数学は科学のことばである」という、ガリレオ・ガリレイの発言は正しい。
数量による記述、数式による記述は、日常言語による記述にくらべ、客観性や合理性において、あるいは推論を行ううえで、すぐれている。
まず、数字を用いることは、次のような長所をもつ
①日常言語を用いると、ていどをあらわすのに、「少し熱い」「やや熱い」「とても熱い」「非常に熱い」「ものすごく熱い」などのように、たくさんの形容詞を用意しなければいけなくなる。しかも、「非常に熱い」と「ものすごく熱い」と、どちらがいっそう熱いのか、形容詞によるていどの序列が、人によって異なる可能性がある。
②「再現性」の検証にすぐれている合う合わないが、はっきりする。「数学」「数式」は、「一義性」(「一意性」。一つの意義[意味]しかもたないという性質)が強い。
③「太揚の温度」のように、日常、経験できない温度の記述は、日常言語では困難になる。数字を用いれば、高い温度も、低い温度も、二つの温度の微妙な差も、測定器具や方 法さえととのえぱ、いくらでもくわしく記述できる。
④測定した数字をグラフにあらわしたり、統計的に処理することなどにより、数式であらわすことができるようになる。数式であらわせば、数字を用いた推理ができる。
物理学者の湯川秀樹は、「現代の科学Ⅱ」(「世界の名著」第66巻 中央公論新社刊)におさめられている[二十世紀の科学思想]のなかで、述べている。 、
「数学が形式論理的な演繹(えんえき)で非常に多くの結論を出せるというのは驚くべきことであって、数学以外のことばだけを使った論理ではそう先へは進めない。はじめからわかっていること、つまり同語反復以上にはなかなか出られない。ところが数学の場合に驚くべき豊富な結論を生み出すことができるのは、その論理のなかに数学的帰納法なるものがふくまれているためでもある。後者は形式論理の単なる繰り返しであるかどうか。ポアンカレ(フランスの数学者)は、ここに一つの大きな飛躍があるとみる。私もたぶんそうだろうと思う。いかにも普通の形式論理と似た形をしているけれども、やはりちがうのではないか」
つまり、数式で表すということは、問題を解くための、演算方法(アルゴリズム)が、定まっていることで、推論を機械的に行いうる。推論に主観がはいらない。
■正確な地図
「一義性」は「事実」と結び付きやすく、「多義性」は「意見」と結び付きやすい。
事実による説得の方法について考えるとき、「事実」と「意見」とを分けて考える必要がある。私たちは、日常の議論などで、事実と意見とをしばしば混同する。
たとえば、「あの娘、美人だね」といったばあい、「美人」という語の意味が一義的に定められていない。そのため、意見の不一致がおきる。一義的に定められていないことばを使うから、「意見」の不一致がおきる。
これに対し、その女性が、二重まぶたであるかどうか、あるいは、身長が150センチ以上であるかどうかといった検証可能な言葉による議論をすれば、意見の不一致は起きにくい。私たちが、客観的な議論をするばあいは、できるだけ、検証可能な議論をする必要がある。
裁判・法律の例は一つ一つの言葉を明確に定める。
多様性を楽しむのはシャレ、落語のオチなどである。
■事実による説得
事実による説得、あるいは、事実とことばとの関係を研究する学問がある。「一般意味論」といわれるものである。この学問の権威で、「思考と行動における言語」(岩波書店刊)などの著書かある、サンフランシスコ州立大学の言語学者、S.Iハヤカワは、日本に来たとき次のように述べた。「事実にもとづいて議論をするばあいには、共産主義者と保守主義者のあいだでも意見の一致をみることができる。ところか、事実にもとづかないでことばだけで議論をすると、たとえ、共産主義者同士、保守主義者同士でも意見の合わないことが生じる」
一般意味論では、意見がくい違ったときには、ことばの段階での話しあいをやめ、具体的事実の検討に移れ、といわれる。ここで事実というのは、観察されたことがらを指す。私たちは、しばしば、「Aさんの考え方は粗雑である」とか、「Bさんの考え方は緻密である」といったいい方をする。これなどは、ことばの段階の議論だといえる。個人の意見の表明である。こういういい方をすると、けっきょくは、意見の対立を深めてしまうことになる。
これに対し、「Aさんの考え方の、この部分はこのように事実に合致していない」とか、「この問題について、新たにこのような事実を指摘している」と述べれば、誤解のはいりこむ余地は少なくなる。
以上述べてきたことについて、いま少し補足しておく。
ポーランドに生まれて、アメリカに帰化し、意味論をとなえて、一般意味論研究所の所長となった論理学者、コージプスキー(1879~1950)は、ことばを専門用語と非専門用語の二種類に分けている。コージプスキーは、専門用語では90度とかH₂Oと書けば、誤解なく議論が進められるが、非専門用語は誤解を招くことばであると、述べている。この90度とかH₂Oにおいては、ことばの意味は一義的である。学問などを進めるさいに用いられることばは、明確な定義によって限定され、可能なかぎり一義的であることがのぞましい。
スイスの言語学者ソシュール(Ferdinand de Saussure 1857~1913)はその著『一般言語学講義(Cours de linguistique generale)』のなかで、つぎのようなことをのべた。
「言語」は、[記号]の体系である。
その「記号」と、つぎの二つのものの結合体である(図1参照)
(1)表現形式 (シニフィアン)(フランス語の、「意味するもの」の意味。「意味する」「表現する」という意味の動詞の、能動態)。能記(小林英夫)、記号表現(丸山圭三郎)などとも訳される。
(2)意味内容 (シニフィエ)(フランス語の「意味されるもの」の意味。「意味する」「表現する」という意味の動詞の受動態)。所記(小林英夫)。記号内容(丸山圭三郎)などとも訳される。
「意味内容」の「山」は、具体的な個々の山をさしているのではない。「表現形式」としての「ヤマ」「やま」「山」などの刺激(耳または目による)によって、日本語を知っている人ならほぼ共通に脳内に思い浮かべるもの(概念・表象)をさす。それは、経験される多くの事物に共通の内容をとりだし(抽象し)、個々の具体的な事物にのみ属する偶然的な性質をすてる(捨象する)ことによって成立している。
言語は、無意識のうちに獲得した社会的拘束の体系のうけいれから出発する。専門用語はなんらかの抽象化により、意味内容を一義化する。
・例
イヌ、オオカミ、キツネ、コヨーテの区別
土器の型式による区別(庄内式3、布留式0など)
自然言語そのままでは、言語は一義的ではない。
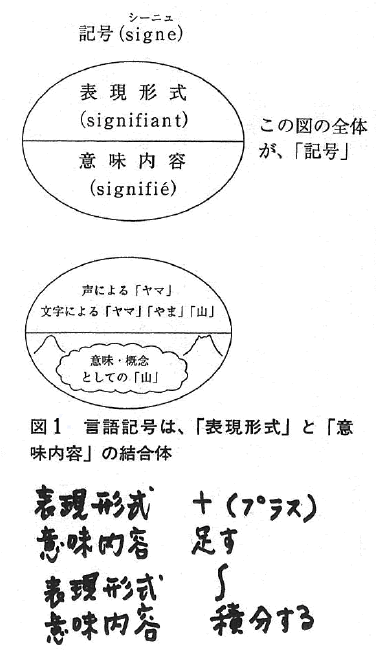
■演繹型と帰納型
科学上の業績などを観察すると、大きくは、二つのタイプに分けることができる。すなわち、一つは、演繹型であり、いま一つは帰納型である。
(1)演繹型
演繹型は、アイザック・ニュートンの『プリンキピア』やユークリッドの「幾何学原論」などのような業績がその典型である。ここでは、まず少数の原理が設定され、「こうだから、こうであり、したがってこうである」と、すきまのない論理によって、全体を貫く秩序が演繹的に導きだされ、体系が樹立される。
演繹型が少数の原理(「公理」とか「仮説」とかいわれるもの)から出発して、そこから導きだされたひじょうに多くの「定理」、あるいは「演繹による結論」によって、いろいろなことがらを説明しようとする。演繹型では、ほぼ確実な少数の事実から出発して、自己完結的な、ほぽ完璧な体系をつくりあげる。それは堅牢で、閉じられた体系といえるかもしれない。ひとたび成功したばあいには容易に破壊されない。ユークリッド幾何学は、非ユークリッド幾何学ができるまでの、およそ2000年の歳月に耐えることができた。またニュートン力学は量子論があらわれるまでの200年間の歳月を耐えた。つまり、数百年、ばあいによっては数千年のあいだ、人びとを説得しつづけることができたわけである。
そのかわり、演繹型の業績によって、壮大な体系が構築されたぱあい、それがゆらぐときは、ちょっとした手なおしではすまないことになる。体系全体の意味が根本から問われることになる。
(2)帰納型
帰納型はチヤールズ・ダーウィンの『種の起源』(1859年刊)などの業績が、その典型である。現実に密着して、客観的な事実を徹底的に収集し、そこから帰納的な方法で、それらの諸事実を説明する一般法則を、仮説として導きだすというやり方である。
帰納型では、ひじょうにたくさんの事実から出発し、観察し、比較し、総合し、原理や法則、あるいは帰納による結論に達しようとする。
私たちの一般社会、あるいは人文科学、社会科学の分野においては、自然科学にくらべて、多くのばあい、対象がいちじるしく個別的な性質をもっている。演繹的な方法による説得よりも帰納的な方法のほうか、適しているばあいも少なくない。ダーウインは事実にもとづく帰納的方法を、科学の基本的な方法とし、その自伝のなかで、科学をおし進める条件として、「事実と観察と収集に対する飽くなき勤勉」をあげている。
邪馬台国時代の鉄鏃、鉄刀、絹、は奈良より九州の方が多く出てくる。だから九州の方が邪馬台国があった可能性が高いというのは、帰納法である。
畿内説は少数の根拠から演繹的手法で強引に畿内説を組み立てる。
■前提の設定
前提(仮説、公理)は観察される諸事実に矛盾しないように、設定する必要があるが、確実に信頼できなくてもよい。その前提から出発することによって、古代の諸事実が、うまく説明できる体系が、つくれればよい。
シュリーマン:「確実に信頼できるとはいえないギリシァ神話から出発」結果的に、ギリシァ神話はおぼろげであっても、宝のありかを示す正しい認識の地図であった。
津田左右吉:「確実に信頼できる文献だけを用いる」
安本美典:「確実に信頼できる文献は存在するのか。信頼できる、できないを定める客観的な基準はなにか、主観的判断を行なっているだけではないか」
安本:「卑弥呼のことが神話化し、伝承化したものが、天照大御神である」、
津田:「安本は確実に信用できるとはいえない前提から出発しているからダメだ」
安本:「この前提から出発することによって、古代のことが全体的にうまく説明できる体系が得られるのならば、前提をみとめるべきである」
■時間により、続きは2011年2月以降の予定。